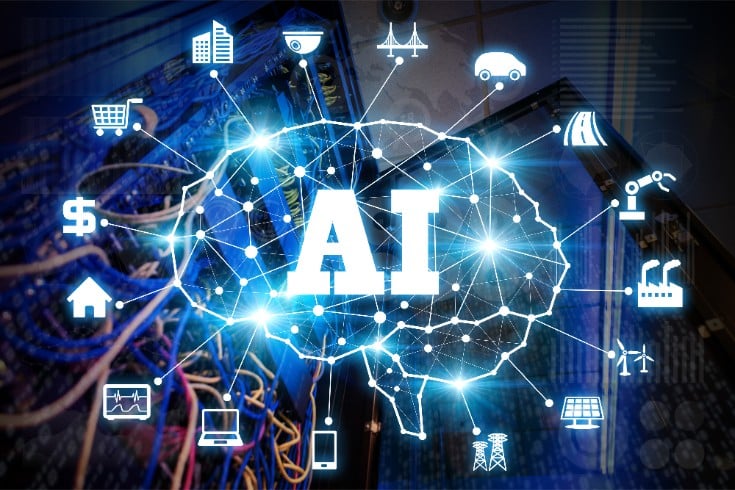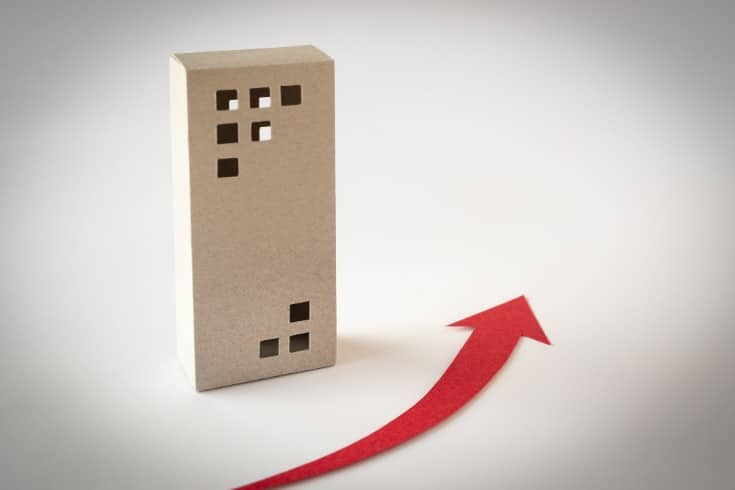株式会社MTGOXの破産に伴う暗号資産預託者の有する請求権・再生債権の法的性質

株式会社MTGOXの経営破綻は、暗号資産の歴史において世界的に最も著名な事件の一つです。この事件は、日本国内だけでなく、世界中の預託者に甚大な影響を及ぼしました。特に法的な観点からは、株式会社MTGOXに暗号資産を預けていた預託者が有する「返還を求める権利」が、日本の法律上どのような性質を持つのかという点が、極めて重要な論点となりました。
この請求権の法的性質は、預託者にとって極めて重要です。もし請求権が「物権的請求権」(特定の資産の返還を求める権利)として認められる場合、預託者は破産手続や再生手続とは無関係に、自己の資産の返還を主張できる可能性があります。日本の倒産法は、このような権利を「取戻権」として保護しています。
これに対し、請求権が単なる「債権」(契約に基づく一般的な請求権)に過ぎないと判断される場合、預託者は他の一般債権者と同列の立場で、手続を通じた平等な配当(弁済)を受けるにとどまります。
株式会社MTGOXの事件が発生した2014年当時、日本には暗号資産の法的地位を直接規定する法律が存在しませんでした。この「法的な空白」の中で、日本の裁判所は、既存の民法や倒産法を解釈・適用することによって、この前例のない問題に答えを出す必要がありました。この記事では、株式会社MTGOXの破産・再生手続において、暗号資産預託者の請求権が日本の法律でどのように解釈され、その法的性質がどのように決定されたのかを解説します。
この記事の目次
株式会社MTGOX破綻の経緯と法的手続上の問題点
2014年、東京を拠点としていた株式会社MTGOXは、ハッキングにより顧客及び同社が保有するビットコインのほぼ全てを喪失し、経営破綻しました。同年4月24日、東京地方裁判所は株式会社MTGOXに対して破産手続開始決定を下しました。
しかし、手続が進む中で、ビットコインの市場価格が劇的に高騰しました。この価格高騰が、破産手続において特異な問題を引き起こしました。日本の破産法では、債権者の権利(破産債権)は、破産手続が開始された時点の評価額で固定されます。株式会社MTGOXの事件では、この評価額は1BTCあたり約451ドルという、高騰後に比べ著しく低い価格でした。
一方で、株式会社MTGOXが保有していた資産(管財人が回収した約20万BTC)の価値は、価格高騰によって負債総額を大幅に上回る事態となりました。もし破産手続がそのまま続行された場合、預託者(債権者)は、2014年時点の低い評価額に基づいた現金配当しか受け取れません。そして、資産価値の高騰によって生じた莫大な差益(残余財産)は、株式会社MTGOXの株主(元代表者を含む)に分配される可能性が生じました。
この事態を回避するため、債権者の一部は2017年に民事再生手続の開始を申し立てました。東京地方裁判所は2018年6月22日にこれを認め、破産手続は中止され、民事再生手続に移行しました。民事再生手続では、再生計画の策定において、ビットコイン現物での弁済(配当)が可能となり、預託者が価格高騰の利益を享受できる道が開かれました。この手続の移行は、預託者の「請求権の法的性質」を巡る議論が、預託者の実質的な利益回復に直結する切実な問題であったことを示しています。
暗号資産預託者が有する請求権の性質に関する法的な対立点

株式会社MTGOXの法的手続において最大の争点となったのは、預託者が有する暗号資産の返還請求権が、法的に「物権的請求権」と解釈されるのか、それとも「債権」と解釈されるのか、という点でした。
もし、この請求権が「物権的請求権」であると認められた場合、預託者は、自己の資産が株式会社MTGOXの総資産とは別個に存在すると主張できます。その場合、預託者は日本の破産法第62条に規定される「取戻権」を行使できます。取戻権とは、倒産手続の枠外で、個別に自己の資産の返還を求めることができる強力な権利です。
これに対して、この請求権が「債権」であると判断された場合、預託者は、株式会社MTGOXに対して契約に基づく返還を要求する権利を持つに過ぎません。その結果、預託者は他の債権者と平等な「一般再生債権者」という地位に置かれます。この地位では、権利の行使は再生手続によって制限され、再生計画に基づいた比例的な配当(弁済)を受けることしかできません。
事件当時の日本における暗号資産の法的地位
株式会社MTGOXの事件が発生した2014年当時、日本には暗号資産の法的地位や取引を直接規律する法律が存在しませんでした。
現在、日本では2019年の改正を経た日本の資金決済法が施行されています。この法律は、「暗号資産」を法的に定義しています(同法第2条14項)。さらに重要な点として、現在の法律は、暗号資産交換業者に対して「利用者資産の分別管理義務」(同法第63条の11)を課しています。また、交換業者が破綻した場合には、利用者が分別管理された資産に対して「優先弁済権」(同法第63条の19の2)を行使できると定めています。
しかし、株式会社MTGOXが破綻した2014年には、これらの預託者保護のための重要な制度は一切整備されていませんでした。この「法的な空白」のため、預託された暗号資産が誰に帰属するのか、倒産時にどのように扱われるのかについて、日本の裁判所は既存の法律、すなわち19世紀に制定された日本の民法の条文を解釈・適用する以外に選択肢がありませんでした。預託者の権利は、契約及び私法上の一般原則に委ねられていたのです。
暗号資産預託者が有する請求権に対する裁判所の判断
裁判所による「所有権」の否定
預託者側は、自らが預けたビットコインの「所有権」を有していると主張しました。そして、その所有権に基づき、日本の破産法第62条が定める「取戻権」の行使を試みました。
しかし、東京地方裁判所は平成27年(2015年)8月5日付の決定において、この主張を明確に否定しました。裁判所の判断の根拠は、日本の民法第85条の解釈にあります。
日本の民法第85条は、この法律における「物」を「有体物」と定義しています。有体物とは、空間の一部を占める有形的な存在、すなわち物理的な実体を持つものを意味します。裁判所は、ビットコインが電磁的記録に過ぎず、有体物ではないため、日本の民法上の「物」には該当しないと判断しました。そして、日本の民法上、「物」でなければ所有権の客体とはなり得ない、と結論付けました。
加えて、同裁判例は、ビットコインの送金(取引)がネットワーク上の不特定多数の第三者(マイナー)の計算・承認作業を必要とする仕組みであることにも言及しました。この仕組みを理由に、利用者は当該ビットコインを「排他的に支配しているとは認められない」とも判示しました。
この司法判断により、預託者が所有権に基づいて暗号資産を取り戻す道は、法的に閉ざされました。
裁判所による「寄託契約」の否定
所有権が否定された場合、次に問題となるのは、預託者と株式会社MTGOXとの間の契約の性質です。預託者側は、この契約が資産の保管を目的とする「寄託契約」に該当すると主張しました。
しかし、この点に関しても、日本の裁判所は預託者にとって不利な判断を下しました。東京地方裁判所 令和2年(2020年)3月2日の判決は、この法律関係を寄託契約とは認めませんでした。
この判断の論理は、所有権の否定と共通しています。日本の民法第657条は、「寄託契約」を、「物」の保管を目的とする契約として定義しています。裁判所は、前述のとおり、暗号資産は日本の民法第85条が定める「物」(有体物)ではないため、法的に寄託契約の目的物となることができないと判断しました。
この判決は、暗号資産そのものに物権的な権利性を認めませんでした。そして、取引所と顧客の間の法律関係は、特定の「物」の保管を前提とする特殊な契約関係ではなく、単なる一般的な「債権関係」(預り金等の返還債務、または債務不履行に基づく損害賠償債務)に過ぎないと位置づけました。
再生手続における請求権の最終的な法的性質
上記の一連の司法判断の結果、株式会社MTGOXの預託者が有する請求権は、再生手続上、担保権や優先権のない「一般再生債権」として取り扱われることが確定しました。
法的には、この請求権は「金銭の支払を目的としない債権」、すなわちビットコイン自体の返還を求める「非金銭債権」として分類されます。日本の破産法第103条第2項第1号イなどの規定に基づき、このような非金銭債権は、破産手続開始時(本件では再生手続)における評価額(日本円)をもって、債権額が算定されることになります。この扱いは、別の裁判例(東京地判平成30年1月31日)によっても確認されています。
株式会社MTGOX事件における裁判所の判断(日本の民法第85条の厳格な適用)は、当時の預託者を法的に保護できませんでした。この司法判断、すなわち裁判所が既存の法律の枠内では暗号資産利用者を保護できないという現実は、立法府(日本の国会)に対する強力なメッセージとなりました。その結果、この事件の教訓として、2019年の日本の資金決済法改正などが進められました。この改正により、暗号資産交換業者に対する「分別管理義務」(同法第63条の11)や利用者の「優先弁済権」(同法第63条の19の2)が新たに導入されたのです。株式会社MTGOX事件における司法の判断が、結果としてその後の日本の立法(利用者保護の強化)を促したという、重要な因果関係が存在します。
暗号資産預託者が有する請求権に関する比較
株式会社MTGOX事件において、預託者の請求権の法的性質は、「物権的請求権」であるか「債権」であるかという点が根本的な対立点でした。
預託者側は、ビットコインを自己の「所有物」または「寄託物」と捉え、物権的請求権に基づく「取戻権」を主張しました。もしこれが認められていれば、彼らは再生手続から独立して、自己の資産を優先的に回収できたはずです。
これに対し、日本の裁判所は、既存の日本の民法第85条(「物」の定義)を厳格に適用しました。ビットコインは「有体物」ではないため、所有権や寄託契約の目的物にはなり得ないと判断しました。
その結果、預託者の請求権は、株式会社MTGOXに対する契約上の一般的な「債権」(再生債権)であると確定しました。これにより、預託者は再生計画の枠内でのみ、他の債権者と平等に配当を受ける地位に置かれることになりました。
暗号資産預託者が有する請求権の損害賠償としての性質

株式会社MTGOXがハッキングによって暗号資産を喪失し、預託者への返還が物理的に不可能になった時点で、その法律関係は「履行不能」となります。このような場合、預託者が有していた「返還請求権」は、株式会社MTGOXの「債務不履行」に基づく「損害賠償請求権」へとその法的性質を変えることになります。
この「損害賠償」という法的性質は、日本の税務上の重要な論点を引き起こします。すなわち、この賠償金(または配当)は非課税となるかという問題です。日本の法律上、例えば交通事故による慰謝料のような、心身への損害に対する賠償金は非課税となる場合があります。
しかし、株式会社MTGOX事件のようなケースは、これに該当しません。返還できなくなった暗号資産に代えて支払われる補償金は、本来所得となるべき資産(またはその売却益)を喪失したことに対する補填です。したがって、日本の税法上、この請求権(損害賠償請求権)に基づいて得られる配当や補償金は、非課税の損害賠償金には該当せず、原則として「雑所得」として課税の対象となります。これは、この再生債権が持つ重要な法的性質の一つです。
まとめ:暗号資産交換業者に関するトラブルは弁護士に相談を
株式会社MTGOXの破綻手続において、暗号資産預託者の請求権は、日本の裁判所によって、特定の資産の返還を求める「物権的請求権」ではなく、契約に基づく一般的な「再生債権」であると判断されました。
この結論は、事件当時の日本法に暗号資産を直接規律する法律がなく、裁判所が日本の民法第85条の「物」(有体物)という定義を厳格に解釈した結果です。これにより、ビットコインは所有権や寄託契約の目的物とは認められませんでした。その結果、預託者は倒産手続の枠外で自己の資産を取り戻す「取戻権」を行使できず、再生手続の債権者として配当を受けることになりました。
現在では、この株式会社MTGOX事件の教訓を経て、日本では資金決済法が改正されました。暗号資産交換業者に対する利用者資産の分別管理義務や優先弁済権が導入されており、株式会社MTGOX事件当時とは預託者の法的地位が大きく異なっている点に注意が必要です。
当事務所による対策のご案内
モノリス法律事務所は、暗号資産、FinTech、そして国際的な倒産・再生手続に関連する複雑な法律問題について、豊富な実績を有しています。そして、当事務所は、日本国内のクライアントはもとより、国際的な案件を扱う多数のクライアントに対してリーガルサービスを提供しています。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務