スイスの多層的な税制とグローバル最低法人税率導入に関する解説

スイス連邦(以下、スイス)の税制は、連邦、26の州(カントン)、そして約2,200に及ぶ地方自治体という、世界的に見ても極めてユニークな三層構造によって成り立っています。この複雑な構造は、各レベルで独自の税率と税法が適用されることを意味し、企業がスイス進出や居住地の選定を行う上での税務計画は、経営戦略において最も重要な決定事項の一つとなります。この多層性によって長年にわたり維持されてきた州間の「タックス・コンペティション(税率競争)」環境は、スイスを国際的なビジネス拠点たらしめてきた主要因です。
しかし、近年、国際的な税務環境が劇的に変化しています。特にOECDが主導するグローバル最低法人税率(Pillar Two)の導入は、この歴史的な競争原理に大きな転換を迫っています。
本稿では、スイス税制の法的根拠となる連邦直接税法(DBG:Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer) や州税調和法(StHG:Steuerharmonisierungsgesetz)に言及しながら、日本の経営者や法務部員がスイスでのビジネス展開を検討する上で不可欠な、最新の税制構造、OECD対応の具体的な動向、そして日本の税法との重要な違いについて、専門的な視点から詳細に解説します。最新の情報に基づき、2024年以降のスイス税制の展望を理解することで、貴社の戦略的な意思決定に資する知見を提供します。
この記事の目次
スイス税制の構造:連邦、州、自治体による三層の課税権
憲法に基づく課税権の分散と州税調和法(StHG)の役割
スイスの税制の基礎は、連邦、州、自治体に課税権が分散されている点にあります。連邦政府は、付加価値税(VAT)と並び、連邦直接税(FDT)を主要な財源としています。連邦直接税は、連邦直接税法(DBG:SR 642.11)に基づき、所得税と法人所得税を徴収します。このDBGは、もともとは戦時税として一時的に導入されましたが、国民投票により2035年まで更新が決定されており、連邦政府の基幹的な収入源としての地位を確立しています。
特筆すべきは、州(カントン)と地方自治体(コミューン)が連邦とは独立した、広範な独自の課税権を持つ点です。この州および自治体の税制の枠組みを定めるのが、州税調和法(StHG:SR 642.14)です。StHGは、州および自治体の税制における課税対象(所得や資産の定義)や基本的な手続きを統一し、州間の二重課税を防ぐための法的基盤を提供しています。
日本の地方税制が国税(所得税や法人税)の課税標準に強く依存し、税率設定の自由度が限定されているのに対し、スイスのStHGは、州が独自の税率(税率乗数)を設定できる自由を残しています。この構造的な差異により、スイスは「連邦レベルでの統一された法的基盤」と「州レベルでの激しい税率競争」という、極めてユニークかつダイナミックな税務環境を成立させています。したがって、スイスの税務上の義務を評価する際、連邦法だけでなく、進出先の州法および自治体条例を詳細に検証することが必須となります。
「タックス・コンペティション(税率競争)」が事業立地に与える影響
州や自治体が独自の税率を設定できるスイスの連邦制は、「タックス・コンペティション(税率競争)」を恒常的に引き起こす要因となっています。これは、どの州に登記上の本社や実質的な経営拠点を置くかという立地選択が、企業の総税務負担を直接的に決定づけることを意味します。税制の競争優位性は、国際的なビジネス拠点としてのスイスの魅力の中心にあります。
法人所得税の実効税率は、連邦税(税引前利益ベースで実効約7.83%)はスイス全土で統一されていますが、州および自治体税率の変動幅が非常に大きいため、連邦・州・自治体の合計実効税率は、国内最低水準の約11.9%から最高水準の約20.5%程度まで、大きく変動します。
例えば、ツーク州(Canton of Zug)は、その合計実効税率が約11.85%と、国内で最も低い水準にあり、国際企業やコモディティ取引企業にとって、非常に魅力的なビジネス拠点であり続けています。このように、税率競争は、単に税率が低い州に企業を誘致するだけでなく、各州政府に対し、税率の引き下げ(例:2024年に税率を大幅に引き下げたアールガウ州)や、インフラ整備、行政サービスの効率化といった形で、立地環境を継続的に改善する強いインセンティブを与えてきました。
法人の税務上の居住地(実質的経営地)を巡る紛争
スイスに進出した多国籍企業が、国内の複数の州に事業体や恒久的施設(PE)を設立する場合、連邦制の原則に基づき、州間の二重課税の禁止が適用されます。この原則に従い、どの州が主要な課税権を持つか(法人の税務上の居住地、すなわち実質的経営地)を巡って、税務当局と紛争が生じることがあります。
スイス連邦最高裁判所の判例は、この実質的経営地の判定基準に関して、重要な実務的影響を及ぼす判断を示しています。一般に、税務当局が納税者に課税を増やすような調整を行う場合、当局側に立証責任があるのが原則です。しかし、複数の州にまたがって事業活動を行う法的実体に関して、連邦最高裁判所は、実質的経営地の場所の立証責任を、当局から納税者に転換する可能性を示しました。
この判例変更は、納税者に対し、実質的経営地に関する適切な文書化の維持を厳格に求めています。裁判所は、判断の基準を「非常に高い蓋然性」から「主に蓋然性がある」(predominantly likely)へと変更しましたが、これは立証のハードルが下がったことを意味するのではなく、納税者が役員会議の議事録や主要な意思決定が行われた場所の証明など、組織運営に関する詳細な記録を継続的に整備する必要性を強く強調しています。日本の読者にとっては、連邦制下で州当局の裁量が大きいスイスにおいて、コンプライアンス維持のための内部体制構築が不可欠であることを示唆しています。
法人所得税の具体的な構造と日本企業進出における留意点
連邦法人税の実効税率と州・自治体税率の決定的な重要性
スイスの法人所得税は、連邦税と州・自治体税の合算で決定されます。連邦レベルでは、法人所得税の税率は利益に対して8.5%ですが、法人所得税自体が税引前利益からの控除対象となるため、税引前利益に対する実効税率は約7.83%となります。この連邦税率が国内で統一された基準となります。
しかし、州および自治体によって適用される税率乗数(タックス・マルチプライヤー)が大きく異なるため、合計の実効税率が大きく変動します。
スイスの税務負担の地域差を理解することは、進出戦略の基本です。
スイス主要州における法人実効税率比較(2024年概算)
| 州(カントン)名 | 連邦・州・自治体合計実効税率 (概算) | 競争上の特徴 |
| ツーク (Zug) | 11.85% | 国内最低水準。国際企業誘致に成功し、OECD対応後もビジネス環境維持を公約 |
| ジュネーブ (Geneva) | 約14%台 | 税制改革を経て競争力を維持。税率引き下げにより競争力強化 |
| バーゼル・シュタット (Basel-Stadt) | 約13%台 | 2019年に税率引き下げを実施 |
| ベルン (Bern), チーノ (Ticino) | 高水準(約18〜20%) | 州税率が高めに設定されている地域 |
| 全州レンジ(下限〜上限) | 11.9% 〜 20.5% | 立地選定の重要性を明確に示す |
このように、所在地によって税負担が8ポイント以上変動する可能性があり、進出地の選定が企業の利益率に決定的な影響を及ぼします。
事業組織形態の選択:支店と子会社の税務上の違い
日本企業がスイス市場に参入する際、支店(Branch Office)として設立するか、子会社(Subsidiary)として設立するかは、税務上の取り扱いを理解した上で慎重に決定する必要があります。
支店は、独立した法人格を持たず、親会社(日本の本社)の直接的な延長と見なされます。この形態の大きな利点は、税務上の優位性です。日本とスイスは強固な租税条約(DTA)を締結しており、支店の利益は、スイスにおける恒久的施設に帰属する利益として課税される場合を除き、二重課税回避のためにスイスでの課税が免除される可能性があります。さらに、スイス法の下で、支店が親会社へ利益を送金する際、通常35%が課される配当の源泉徴収税(WHT)が免除される可能性があります。また、設立に最低資本金が不要である点も、初期コストの面でメリットとなります。
一方、子会社はスイス国内で独立した法人格を持つため、スイスの通常の法人税制(連邦・州・自治体税)の対象となります。子会社が親会社へ配当や利子を支払う際には、スイスの源泉徴収税(WHT)が原則適用されますが、後述する日・スイス租税条約の規定により、この負担は大幅に軽減または免除されます。
税務上の要件に加え、支店は親会社の直接的な統制下にあるのに対し、子会社はより大きな自律性を持つ傾向があり、これらの法的・経営的な要素も組織形態選択の重要な判断材料となります。
移転価格税制の要求水準と文書化の重要性
スイスの税務制度において、関連者間取引の価格設定(移転価格)は、国際的なコンプライアンスの観点から非常に重要です。スイス国内法には、OECDの国別報告書(CbCR)の自動的情報交換に関する連邦法が存在しますが、OECDのTPガイドラインに準拠したマスターファイルやローカルファイルといった移転価格文書を、法人税申告と同時に自動的に税務当局に提出する形式的な義務はありません。
しかし、これは文書化が不要であるということを意味しません。スイスは「自己申告制度(Self-assessment)」を採用しており、税務当局(FTA)による通常の税務調査(Tax Audit)において移転価格が問題視された場合、納税者には、関連者間取引が独立企業間原則(アームズ・レングス・プリンシプル)に準拠していることを証明するための裏付け文書を提出する義務が発生します。
特に、当局は知的財産取引、グループ内融資、低リスク・低利益企業を監査の焦点としているため、納税者が適切な文書を事前に準備・維持できていない場合、立証責任が納税者に転換され、当局の裁量による課税調整を受け入れざるを得なくなるリスクが高まります。したがって、形式的な提出義務がないにもかかわらず、日本の多国籍企業が慣れている基準に基づき、OECDガイドラインに準拠した文書を事前に作成しておくことが、リスク管理上強く推奨されます。
OECDグローバル最低法人税率(Pillar Two)の導入と州の戦略的対応
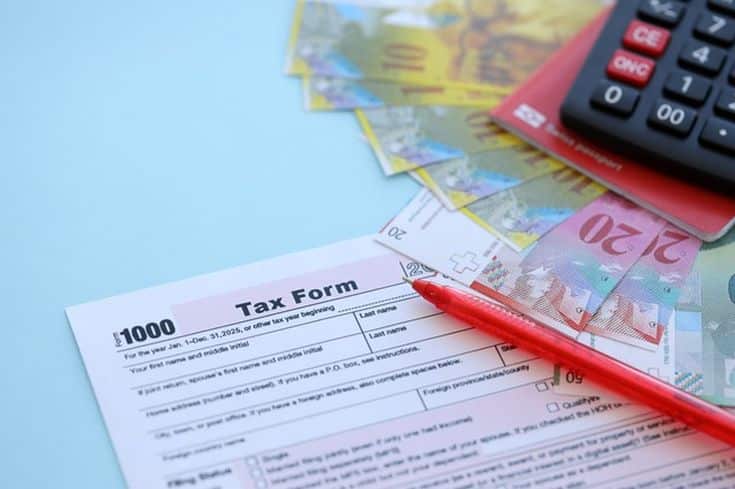
スイスの魅力の中心であった低税率競争環境は、2024年以降、OECD/G20が推進するBEPS 2.0プロジェクトのPillar Two(グローバル最低法人税率15%)の導入によって、根本的な変化に直面しています。
憲法改正による法的基盤の確立と導入スケジュール
スイスは、連結売上高が7億5,000万ユーロ(約1,150億円)以上の多国籍企業グループを対象として、最低実効税率15%の導入を決定しました。この国際的な税制に対応するための法的基盤は、2023年6月18日の国民投票による憲法改正によって確立されています。
スイスは、国際的な税源浸食を防ぎ、税収を国内に留める戦略を採用し、以下の二段階アプローチで導入を進めています。
- 国内補完税(QDMTT)の導入:2024年1月1日以降に開始する会計年度より、国内補完税(Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)が導入されました 16。QDMTTは、スイス国内の事業体が15%を下回る実効税率で課税されている場合に、その差額をスイス国内で徴収するものです。これにより、他国がIIR(所得合算ルール)を適用してスイスの低課税部分を課税するのを防ぐことができます。
- 国際補完税(IIR)の導入:2024年9月、連邦参事会は、所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)を2025年1月1日以降に開始する会計年度から施行することを決定しました 18。これにより、スイスの親会社は、海外の低課税子会社に対してトップアップ税を課す責任を負うことになります。
連邦参事会は、この最低税率を、連邦議会が恒久的な連邦法を制定するまでの間、暫定的に政令(Mindeststeuerverordnung)によって施行する権限を得ています。
税収維持のための州の戦略:追加税収の使途と立地優位性の再構築
Pillar Two導入により、特に低税率で知られていた州(ツーク州など)では、国内補完税(QDMTT)による追加税収が大幅に増加すると見込まれています。この増収分が、スイスの連邦主義の下でどのように分配され、利用されるかは、今後の州間競争の焦点となります。
連邦の決定に基づき、QDMTTによる税収の配分は以下のように定められています。
- 税収の配分:QDMTTによる税収の75%は、課税対象の事業体が属する州に割り当てられます。残りの25%は連邦政府に割り当てられ、スイス全体の立地競争力強化のために使用されます。
この結果、州はもはや税率の低さのみで競争することはできません。州間の競争は、追加税収の戦略的な活用へとシフトしています。税率が15%を下回る場合に適用される補完税により、研究開発(R&D)費用の追加控除やパテントボックスといった従来の税制優遇策は、その効果が相殺されることになります。そのため、ツーク州やジュネーブ州を含む多くの州は、増収分をどのように投資し、税制以外の側面(インフラ、労働力、教育、行政手続きの効率化など)で立地優位性を維持・強化するかという戦略策定に取り組んでいます。
企業グループ内の税務処理の複雑化
スイス国内に複数の州をまたいで事業体が存在し、グループ全体でQDMTTが課される場合、この補完税の負担をどのように州間で配分し、最終的にどの事業体に帰属させるかという複雑な問題が発生します。
最低税率政令に関する連邦参事会の解説では、補完税の徴収を誘発した事業体に対して、グループ内でその税負担を内部で精算(チャージバック)することが求められています。もしこの内部精算が適切に行われない場合、それは実質的に親会社から子会社への「みなし配当」と見なされるリスクがあり、スイスの源泉徴収税(WHT)の対象となる可能性があります。
これは、日本の多国籍企業がスイス国内で複数の拠点を運営する場合、グループ内での資金移動や会計処理を、源泉税コンプライアンスの観点から厳格に管理する必要があることを意味します。内部精算の取り扱いについて、税務および会計のプロセスの見直しが不可欠です。
個人所得税と外国人富裕層向けの特別税制
高い累進性を持つ州レベルの個人所得税構造
スイスの個人所得税も、連邦、州、自治体の三層構造で課税され、居住地によって税率が大きく異なります。
連邦所得税の最高税率は11.5%ですが、州および自治体の所得税は累進性が非常に高く設定されています 26。この州・自治体税率の差異により、連邦・州・自治体税を合計した個人所得税の最大実効税率は、州によって8.05%から33.63%まで広範に及びます。この大きな税率差は、法人税と同様に、個人の居住地選択もまた、重要な税務計画の要素であることを示しています。
日本法との大きな違い:富裕税(純資産税)の存在
スイスの個人税制における日本法との決定的な違いは、富裕税(純資産税/Net Wealth Tax)の存在です。
日本では富裕税(資産課税)は存在しませんが、スイスでは連邦レベルでは課税されないものの、すべての州および自治体レベルで富裕税が課税されます。この税は、原則として全世界の純資産(ただし、外国の不動産や恒久的施設に帰属する資産を除く)に対して課税されます。
富裕税の税率は州によって異なりますが、最大でも約0.10%から0.88%程度の比較的低い比率です。
富裕税の課税は、日本の税制と比較した際の大きな特徴ですが、スイスでは通常、個人資産(非事業用)の売却によって生じたキャピタルゲインは非課税です。この「キャピタルゲイン非課税」と「富裕税課税」の組み合わせは、キャピタルゲインに原則課税される日本の税制と比較し、高資産の個人や投資家にとって、特定の種類の所得に対する税務上の優位性をもたらしています。
外国籍居住者を優遇する「定額課税制度(パウシャルベシュトイヤーリング)」の要件と実務
スイスの個人税制には、外国人富裕層を誘致するためのユニークな制度として「定額課税制度」(Pauschalbesteuerung / Lump-sum taxation)が存在します。この制度は1920年代から存在し、特定の外国籍居住者に対し、全世界の所得や資産を申告する義務を免除し、代わりに、合意された「みなし所得」(主に年間生活費や住居費の一定倍率)に対して課税するものです。日本の税制には、これに相当する制度は存在しません。
資格要件と算定基準
定額課税制度の適用を受けるための主要な要件は以下の通りです。
- スイス国籍を持たないこと(二重国籍者も適用外と見なされる)。
- スイス国内で有償の就労活動を行わないこと。
- 特定の州に居住すること(一部の州では廃止されています。例えばチューリッヒ州では利用できません)。
課税対象となるみなし所得は、納税者の年間生活費を基準に算定されます。連邦レベルでは、最低でも以下のいずれかの高い金額が適用されます。
- 住居の年間家賃(または自己所有の場合の賃貸価値)の7倍。
- スイス源泉の所得に通常税率を適用した場合の税額と同等またはそれ以上であること。
- 連邦レベルで定められた最低課税所得(現在は400,000 CHF)。
この制度の最大の魅力は、全世界の所得や資産の申告義務が免除されることによる「財務上の機密性」と、支払う税額が事前に合意され「予測可能」であることです。しかし、定額課税制度の居住者は、スイスが締結している租税条約の恩典(例:源泉税の減免)を受ける資格に関して制約に直面する可能性があるため、国際的な資産運用戦略に影響を与えるかどうかを慎重に検討する必要があります。
日・スイス租税条約(DTA)の活用とクロスボーダー取引の恩典
スイスと日本は、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための条約(DTA)を締結しており、これは両国間でのビジネスおよび投資活動を円滑にするための最も重要な法的枠組みです。
2023年適用開始の改正プロトコルの要点とBEPS対応
日・スイス租税条約は、2021年7月に署名された改正プロトコルに基づき、2022年11月30日に発効し、ほとんどの規定が2023年1月1日から適用されています。この改正は、OECDが主導するBEPSプロジェクトのミニマルスタンダード(最低基準)を組み込むことを目的としています。
特に、事業利益の課税(条約第7条)に関する規定は、OECDモデル条約(2017年版)に準拠するように修正されました。これにより、スイスにある恒久的施設(PE)に帰属する利益算定において、PEと本社間の内部取引についても独立企業間原則が適用されることが明確化されました。これは、PE間の資金や資産の取引が、あたかも独立した第三者間で行われたかのように評価されることを意味し、国際的な移転価格のコンプライアンス要求が高まっています。
配当および利子にかかる源泉徴収税(WHT)の優遇措置
改正プロトコルにより、配当および利子にかかる源泉徴収税(WHT)の優遇措置が大幅に拡大され、日本企業がスイスに子会社を設立する際の税務効率が劇的に改善されました。
| 取引形態 | 旧条約の取り扱い(主要規定) | 改正条約(2023年適用)の取り扱い | 税務上の影響 |
| 配当 (Dividend) | 50%以上の持分保有(6ヶ月以上)で免税(0%) | 10%以上の議決権または資本を365日以上保有で免税(0%) | 免税要件が大幅に緩和され、親会社からの投資が容易に。 |
| 利子 (Interest) | 原則10%。政府機関、金融機関等に限定して免税 | 居住者間の利子支払いについて完全に免税(0%) | 親会社からスイス子会社への融資スキームにおけるスイス源泉税負担がゼロに。 |
特に利子については、従来の10%の源泉税率が完全に撤廃され、両国居住者間の利子支払いが免除されました。これは、日本の親会社がスイス子会社に資金を供給するためのグループ内融資を行う際、スイス側での源泉税負担がゼロになることを意味し、資金調達スキームにおける税務効率が劇的に向上します。また、ロイヤルティ(使用料)支払いも引き続き源泉地国課税が免除されています。
スイス連邦最高裁判所による国際税務上の居住地判定に関する判例
租税条約の恩典(特に源泉徴収税の減免)を享受するためには、所得を受け取る事業体が、条約上の「受益者」(Beneficial Owner)要件を満たしていることが不可欠です。スイス連邦最高裁判所は、租税条約の適用を巡る事案において、受益者要件について厳格な判断基準を示しています。
連邦最高裁判所は、ルクセンブルク居住の金融機関が、スイスの配当に対する源泉税の還付を請求した事案において、当該金融機関が配当所得の「受益者」ではないとして請求を棄却しています(連邦最高裁判所、2019年12月16日、事件番号 2C_209/2017)。
この判例は、国際的な税務ストラクチャリングを構築する際、単に租税条約締結国に事業体を設立するだけでなく、その事業体が配当や利子の「受益者」として実体(リスク負担、経済的合理性、意思決定機能)を伴っていることが、スイスの税務当局および裁判所から求められていることを明確に示しています。日本の企業がスイスを中間持株会社として利用するなど、国際取引を構築する際には、この受益者要件に関する連邦最高裁判所の厳しい視点を念頭に置いた、実体のある事業運営が必須となります。
まとめ
スイスの税制は、連邦、州、自治体の三層構造に基づき、特に州間における税率競争が、企業の立地選択に決定的な影響を与えてきました。法人税の実効税率は州によって大きく異なりますが、国際的なビジネス拠点としての優位性は維持されてきました。
しかし、2024年1月1日からの国内補完税(QDMTT)導入を皮切りとしたOECDグローバル最低法人税率(Pillar Two)への対応により、スイスは歴史的な転換期を迎えています。今後は、税率の低さだけでなく、州がQDMTTによる追加税収(75%が州に配分)をどのように再投資し、税制以外の側面で競争力(例:R&D優遇、インフラ整備)を強化するかが、企業の進出地選定における新たな焦点となります。
また、個人税制においては、日本の税制には存在しない富裕税(純資産税)が州レベルで課される一方で、キャピタルゲインが非課税となる優位性があります。さらに、外国人富裕層向けの定額課税制度(パウシャルベシュトイヤーリング)は、高い機密性と予測可能性を提供するユニークな制度です。
日・スイス租税条約は、2023年からの改正規定適用により、配当および利子にかかる源泉徴収税が大幅に軽減または免除されることとなり、日本企業がスイス子会社を通じて投資やグループ内融資を行う上での税務上の効率性が劇的に向上しています。
これらのスイス制特有の複雑な税構造、最新の国際課税ルールへの適応、そして日・スイス租税条約の具体的な適用については、高度な専門知識と現地の法規制への深い理解が不可欠です。モノリス法律事務所では、お客様のスイス市場への進出および最適な税務計画の策定をサポートいたします。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務


































