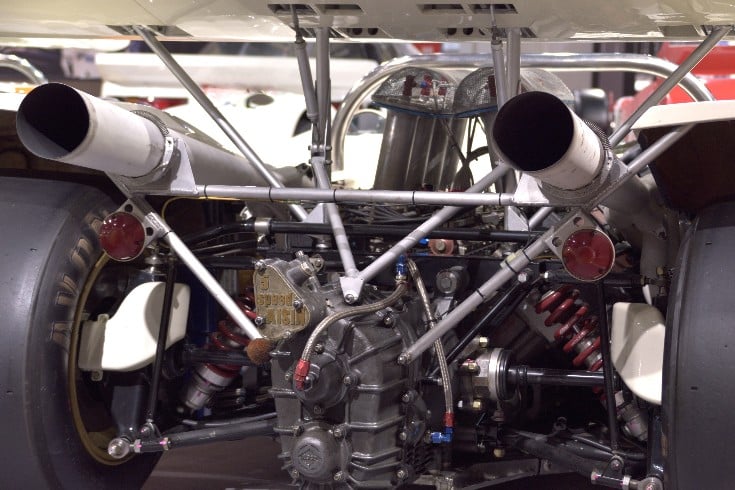т«ЅтЁесЂесЃФсЃ╝сЃФсЂ«сЂ»сЂќсЂЙсЂДРђЋРђЋF1сѓФсЃісЃђGPсђЂУДњућ░жЂИТЅІсЂ«УхцТЌЌУ┐йсЂёУХісЂЌсЂФсѓѕсѓІсЃџсЃісЃФсЃєсѓБсѓњТ│ЋуџёсЂФУђЃт»Ъ

F1сЂ»тИИсЂФт«ЅтЁеТђДсЂеуФХТіђТђДсЂ«сЃљсЃЕсЃ│сѓ╣сЂ«СИГсЂДТѕљсѓіуФІсЂБсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓсЂЌсЂІсЂЌсђЂсЂесЂЇсЂФсЃЅсЃЕсѓцсЃљсЃ╝сЂ«уЏ┤ТёЪсЂФсѓѕсѓІтѕцТќГсЂеУдЈтЅЄсЂ«ТЮАТќЄсЂїТГБжЮбсЂІсѓЅУАЮуфЂсЂЎсѓІсЂЊсЂесЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓсЂЮсѓїсЂї2025т╣┤F1угг10ТѕдсѓФсЃісЃђGPсЂДсђЂсѓфсЃЕсѓ»сЃФсЃ╗сЃгсЃЃсЃЅсЃќсЃФсЃ╗сЃгсЃ╝сѓисЃ│сѓ░сЂ«УДњућ░УБЋТ»ЁжЂИТЅІсЂФуДЉсЂЏсѓЅсѓїсЂЪсЃџсЃісЃФсЃєсѓБсЂДсЂЎсђѓ
F1сЂДсЂ»тцДС║ІТЋЁсЂїуЎ║ућЪсЂЌсЂЪжџЏсѓёсђЂсѓ│сЃ╝сѓ╣СИісЂФтЇ▒жЎ║сЂфжџют«│уЅЕсЂїсЂѓсѓІсЂесЂЇсЂФсђїУхцТЌЌсђЇсЂїТЈљуц║сЂЋсѓїсЂЙсЂЎсђѓсЂЊсЂ«УхцТЌЌсЂїТЈљуц║сЂЋсѓїсЂдсЂёсѓІТюђСИГсЂ»сђЂУ┐йсЂёУХісЂЌсЂїудЂТГбсЂЋсѓїсЂЪсѓісђЂсЃћсЃЃсЃѕсЂФТѕ╗сѓІТјфуй«сЂїТ▒ѓсѓЂсѓЅсѓїсЂЙсЂЎсЂїсђЂУДњућ░жЂИТЅІсЂ»сЃђсЃАсЃ╝сѓИсѓњУ▓асЂБсЂЪсЃъсѓисЃ│сѓњУ┐йсЂёУХісЂЌсЂдсЂЌсЂЙсЂёсЂЙсЂЌсЂЪсђѓсЂЊсѓїсЂФт»ЙсЂЌсђЂFIAсЂ»тј│Та╝сЂфсЃџсЃісЃФсЃєсѓБсѓњуДЉсЂЌсЂЙсЂЌсЂЪсђѓсЂЊсЂ«тѕцТќГсЂ«УЃїтЙїсЂФсЂ»сђЂF1сЂФсЂісЂЉсѓІтј│Та╝сЂфт«ЅтЁеу«АуљєсЂ«уљєт┐хсЂесђЂсЂЮсѓїсѓњТћ»сЂѕсѓІУдЈтЅЄсЂ«жЂЕућесЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
УДњућ░жЂИТЅІсЂ»тЙїсЂ«сѓ│сЃАсЃ│сЃѕсЂДсђїсЃЄсЃќсЃфсЂїжБЏсЂ│С║цсЂєСИГсЂДсђЂтЇ▒жЎ║сѓњжЂ┐сЂЉсѓІсЂЪсѓЂсЂ«тѕцТќГсЂасЂБсЂЪсђЇсЂеСИ╗т╝хсЂЌсђЂт«ЅтЁесЂИсЂ«жЁЇТЁ«сѓњуљєућ▒сЂФсЂѓсЂѕсЂдУ┐йсЂёУХісЂЌсѓњжЂИТіъсЂЌсЂЪухїуи»сѓњУфъсЂБсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓсЂЊсЂ«тѕцТќГсЂ»ТъюсЂЪсЂЌсЂдсЃФсЃ╝сЃФжЂЋтЈЇсЂфсЂ«сЂДсЂЌсѓЄсЂєсЂІ№╝ЪсЂЮсѓїсЂесѓѓТГБтйЊсЂфУЄфти▒жў▓УАЏТјфуй«сЂфсЂ«сЂДсЂЌсѓЄсЂєсЂІ№╝ЪF1сЂФсЂісЂЉсѓІт«ЅтЁесЂеУдЈтЙІсЂФуёдуѓ╣сѓњсЂѓсЂдсЂдсђЂТюгС╗ХсЂ«Т│ЋуџёУЃїТЎ»сЂеУБЂт«џсЂ«тдЦтйЊТђДсѓњтѕєТъљсЂЌсЂдсЂ┐сЂЙсЂЌсѓЄсЂєсђѓ
сЂЊсЂ«УеўС║ІсЂ«уЏ«ТгА
10сѓ░сЃфсЃЃсЃЅжЎЇТа╝сЃџсЃісЃФсЃєсѓБсЂ«УЃїТЎ»

2025т╣┤F1угг10ТѕдсѓФсЃісЃђGPсЂДУДњућ░жЂИТЅІсЂФт»ЙсЂЌсЂдуДЉсЂЏсѓЅсѓїсЂЪсЂ«сЂ»сђЂТ▒║тІЮсЃгсЃ╝сѓ╣сЂДсЂ«10сѓ░сЃфсЃЃсЃЅжЎЇТа╝сђЂсЂЎсЂфсѓЈсЂАсѓ╣сѓ┐сЃ╝сЃѕсЂ«СйЇуй«сѓњ10уЋфТЅІсѓѓСИІсЂњсѓЅсѓїсѓІжЄЇсЂёсЃџсЃісЃФсЃєсѓБсЂДсЂЌсЂЪсђѓСИђУѕгуџёсЂФF1сЂ»сѓ╣сѓ┐сЃ╝сЃѕСйЇуй«сЂїжЄЇУдЂУдќсЂЋсѓїсЂдсЂісѓісђЂТюђтЙїт░ЙсЂІсѓЅсЂ«сѓ╣сѓ┐сЃ╝сЃѕсЂДсЂ»УАетй░тЈ░№╝ѕсЃѕсЃЃсЃЌ3№╝ЅсѓњуІЎсЂєсЂ«сЂ»ТЦхсѓЂсЂдтЏ░жЏБсЂДсЂЎсђѓ
тЋЈжАїсЂесЂфсЂБсЂЪсЂ«сЂ»сђЂсЃЋсЃфсЃ╝Ух░УАї3тЏъуЏ«№╝ѕFP3№╝ЅсЂДсЂ«тЄ║ТЮЦС║ІсЂДсЂЌсЂЪсђѓсЃъсѓ»сЃЕсЃ╝сЃгсЃ│сЂ«сѓфсѓ╣сѓФсЃ╝сЃ╗сЃћсѓбсѓ╣сЃѕсЃфжЂИТЅІсЂїсѓ┐сЃ╝сЃ│14сЂ«тЄ║тЈБсЂДсЃљсЃфсѓбсЂФТјЦУДдсЂЌсђЂтЈ│сЃфсѓбсѓ┐сѓцсЃцсЂ«сЃЉсЃ│сѓ»сЂісѓѕсЂ│сѓхсѓ╣сЃџсЃ│сѓисЃДсЃ│сЂ«ТљЇтѓисЂесЂёсЂєуіХТ│ЂсЂФсЂфсѓісЂЙсЂЌсЂЪсђѓсЂЊсѓїсѓњтЈЌсЂЉсЂдУхцТЌЌсЂїТЈљуц║сЂЋсѓїсђЂсѓ╗сЃЃсѓисЃДсЃ│сЂ»СИђТЎѓСИГТќГсЂЋсѓїсЂЙсЂЌсЂЪсђѓ
сЂЊсЂ«ТЎѓсђЂУДњућ░жЂИТЅІсЂ»сѓ┐сЃ╝сЃ│6С╗ўУ┐ЉсѓњУх░УАїСИГсЂДсЂѓсѓісђЂУхцТЌЌсЂ«ТЈљуц║тЙїсѓѓсѓ╣сЃћсЃ╝сЃЅсѓњуХГТїЂсЂЌсђЂсЃћсѓбсѓ╣сЃѕсЃфжЂИТЅІсЂ«сЃъсѓисЃ│сЂФТјЦУ┐ЉсђѓсЃгсЃ╝сѓ╣тЙїсЂ«сЃЄсЃ╝сѓ┐сЂФсѓѕсѓїсЂ░сђЂсЃћсѓбсѓ╣сЃѕсЃфжЂИТЅІсЂїТЎѓжђЪ86kmсЂДУх░УАїсЂЌсЂдсЂёсЂЪсЂ«сЂФт»ЙсЂЌсђЂУДњућ░жЂИТЅІсЂ»171kmсЂДТјЦУ┐ЉсЂЌсђЂУ┐йсЂёУХісЂЌсѓњУАїсЂёсЂЙсЂЌсЂЪсђѓ
УДњућ░жЂИТЅІсЂ»тЙїсЂ«УЂ┤тЈќсЂДсђЂсђїсЃђсЃАсЃ╝сѓИсѓњУ▓асЂБсЂЪсЃъсѓисЃ│сЂФсѓѕсѓІУх░УАїтдет«│сѓёсЃЄсЃќсЃфсЂФсѓѕсѓІтЇ▒жЎ║сѓњжЂ┐сЂЉсѓІсЂЪсѓЂсЂФУ┐йсЂёУХісЂЌсЂЪсђЇсЂеУфгТўјсЂЌсЂЙсЂЌсЂЪсЂїсђЂсѓ╣сЃЂсЃЦсЃ»сЃ╝сЃЅ№╝ѕуФХТіђсѓњуЏБуЮБсЂЎсѓІсѓ╣сѓ┐сЃЃсЃЋ№╝ЅсЂ»сЂЊсѓїсѓњСИЇжЂЕтѕЄсЂетѕцТќГсЂЌсЂЙсЂЌсЂЪсђѓсЃћсѓбсѓ╣сЃѕсЃфУ╗ісЂ«жђЪт║дсЂеуіХТЁІсЂ»сђЂУ┐йсЂёУХісЂЌсѓњТГБтйЊтїќсЂЎсѓІсЂФУХ│сѓІсѓѓсЂ«сЂДсЂ»сЂфсЂёсЂесЂЋсѓїсЂЙсЂЌсЂЪсђѓ
УДњућ░жЂИТЅІсЂ»сђїтЈ│сЃфсѓбсѓ┐сѓцсЃцсЂїУё▒УљйсЂЌсЂІсЂЉсЂдсЂёсЂЪсЃћсѓбсѓ╣сЃѕсЃфсЂ«сЃъсѓисЃ│сЂІсѓЅтЙїТќ╣сЂФсЃЄсЃќсЃфсЂїжБЏсѓЊсЂДсЂЈсѓІтЇ▒жЎ║ТђДсЂїсЂѓсѓісђЂтЉетЏ▓сЂ«т«ЅтЁесѓњуб║УфЇсЂЌсЂЪСИісЂДТіюсЂёсЂЪсђѓсѓфсѓ╣сѓФсЃ╝сЂїтидтЂ┤сѓњУх░сЂБсЂдсЂёсѓІсЂ«сЂ»УдІсЂдсЂёсЂЙсЂЌсЂЪсЂЌсђЂсЃгсЃЃсЃЅсЃЋсЃЕсЃЃсѓ░сЂДсЂ»У┐йсЂёУХісЂЌсЂїсЂДсЂЇсЂфсЂёсЂЊсЂесѓѓуљєУДБсЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓсЂДсѓѓсЃђсЃАсЃ╝сѓИсѓњУ▓асЂБсЂЪсЃћсѓбсѓ╣сЃѕсЃфсЂ«тЙїсѓЇсЂДсЃћсЃЃсЃѕсѓцсЃ│сЂЎсѓІсЂ«сѓњтЙЁсЂцсЂесЂёсЂєсЂ«сЂ»сђЂтЃЋсЂесЂЌсЂдсЂ»сЃЄсЃќсЃфсЂФтйЊсЂЪсѓІсЂ«сѓњтЙЁсЂцсѓѕсЂєсЂфсѓѓсЂ«сЂДсЂЎсђЇсЂеУ┐░сЂ╣сђЂсђїждгж╣┐сЂњсЂЪсЃџсЃісЃФсЃєсѓБсЂасђЇсЂеСИ╗т╝хсЂЌсЂЙсЂЌсЂЪсђѓсѓцсЃ│сѓ┐сЃ╝сЃЇсЃЃсЃѕСИісЂДсЂ»сЂЊсѓїсЂФУ│ЏтљїсЂЎсѓІТёЈУдІсѓѓУдІсѓЅсѓїсЂЙсЂЌсЂЪсЂїсђЂсѓёсЂ»сѓісЂЊсѓїсЂ»УдЈтЅЄсЂФжќбсЂЎсѓІуљєУДБсЂїСИЇтЇЂтѕєсЂДсЂѓсЂБсЂЪсЂесЂёсЂєТїЄТЉўсѓѓТа╣т╝исЂЈсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
УхцТЌЌсЂ»сђїСЙІтцќсЂфсЂЇухХт»ЙуџёсЃФсЃ╝сЃФсђЇ
сЂЊсЂ«сЃџсЃісЃФсЃєсѓБсЂ«Та╣ТІасЂесЂфсЂБсЂЪсЂ«сЂ»сђЂFIAтЏйжџЏуФХТіђУдЈтЅЄС╗ўтЅЄH№╝ѕAppendix H№╝ЅсЂ«угг2уФасђїсѓцсЃЎсЃ│сЃѕжЂІтќХТЅІжаєсђЇсЂФсЂісЂЉсѓІугг2.5.4.1 bжаЁсЂДсЂЎсђѓтјЪТќЄсЂДсЂ»С╗ЦСИІсЂ«сѓѕсЂєсЂФУдЈт«џсЂЋсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎ№╝џ
b) 1)УхцТЌЌсЂїТЈљуц║сЂЋсѓїсЂЪжџЏсђЂсЂЎсЂ╣сЂдсЂ«У╗іСИАсЂ»сЂЪсЂасЂАсЂФжђЪт║дсѓњУљйсЂесЂЌсђЂсЃћсЃЃсЃѕсЃгсЃ╝сЃ│сЂИсѓєсЂБсЂЈсѓісЂеТѕ╗сѓЅсЂфсЂЉсѓїсЂ░сЂфсѓЅсЂфсЂёсђѓУ┐йсЂёУХісЂЌсЂ»удЂТГбсЂЋсѓїсѓІсђѓ
3№╝ЅУ┐йсЂёУХісЂЌсЂїудЂсЂўсѓЅсѓїсѓІсЂесЂесѓѓсЂФсђЂсЃЅсЃЕсѓцсЃљсЃ╝сЂ»сђЂсЃгсЃ╝сѓ╣У╗іСИАсЂісѓѕсЂ│сѓхсЃ╝сЃЊсѓ╣У╗іСИАсЂїсЃѕсЃЕсЃЃсѓ»СИісЂФтГўтюесЂЎсѓІсЂІсѓѓсЂЌсѓїсЂфсЂёсЂЊсЂесђЂсѓхсЃ╝сѓГсЃЃсЃѕсЂ»С║ІТЋЁсЂ«сЂЪсѓЂсЂ«т«їтЁет░ЂжјќсЂїсЂЋсѓїсѓІсЂЊсЂесЂїсЂѓсѓІсЂЊсЂесђЂтцЕтђЎсЂФсѓѕсѓітйЊУЕ▓сѓхсЃ╝сѓГсЃЃсЃѕсЂДсЃгсЃ╝сѓ╣сѓ╣сЃћсЃ╝сЃЅсЂДсЂ«Ух░УАїсЂїСИЇтЈ»УЃйсЂесЂфсѓІсЂЊсЂесЂїсЂѓсѓІсЂЊсЂесЂФсЂцсЂёсЂдуЋЎТёЈсЂЌсЂдсЂёсЂфсЂЉсѓїсЂ░сЂфсѓЅсЂфсЂёсђѓ
FIAтЏйжџЏуФХТіђУдЈтЅЄС╗ўтЅЄHсѓњтњїУе│
сЂЊсЂ«УдЈт«џсЂ«УХБТЌесЂ»сђЂУхцТЌЌсЂїТЈљуц║сЂЋсѓїсЂЪуъгжќЊсЂФсЂ»сђЂС║ІТЋЁсЂ«уЎ║ућЪтю░уѓ╣сѓёсЂЮсЂ«тй▒жЪ┐сЂїсѓ│сЃ╝сѓ╣тЁеСйЊсЂФтЈісѓЊсЂДсЂёсѓІсЂІсЂЕсЂєсЂІсѓњтЁесЃЅсЃЕсѓцсЃљсЃ╝сЂїтЇ│т║ДсЂФТііТЈАсЂДсЂЇсЂфсЂёсЂЊсЂесѓњтЅЇТЈљсЂесЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
сЂцсЂЙсѓісђЂУхцТЌЌсЂ»сђїуіХТ│ЂТііТЈАсЂїтЏ░жЏБсЂфжЮътИИС║ІТЁІт«БУеђсђЇсЂДсЂѓсѓісђЂсЂЕсЂЊсЂДУ╗іСИАсѓёсЃЄсЃќсЃфсЂїтЂюТГбсЂЌсЂдсЂёсѓІсЂІсђЂсЃъсЃ╝сѓисЃБсЃФ№╝ѕсѓ│сЃ╝сѓ╣сЂ«С┐ѓтЊА№╝ЅсЂїСйюТЦГсЂЌсЂдсЂёсѓІсЂІсђЂсЂЋсѓЅсЂФсЂ»ТЋЉТђЦт»Йт┐юсЂїУАїсѓЈсѓїсЂдсЂёсѓІсЂІсѓѓтѕєсЂІсѓЅсЂфсЂёсђѓсЂЮсЂєсЂЌсЂЪуіХТ│ЂСИІсЂДсЂ«У┐йсЂёУХісЂЌсЂ»сђЂС║ѕТИгСИЇУЃйсЂфС║їТгАуџёС║ІТЋЁсѓёС║║уџёУбФт«│сѓњТІЏсЂЈтЇ▒жЎ║ТђДсЂїсЂѓсѓІсЂЪсѓЂсђЂсЂёсЂІсЂфсѓІСЙІтцќсѓѓтјЪтЅЄсЂесЂЌсЂдУфЇсѓЂсѓЅсѓїсЂфсЂёсђїухХт»ЙуџёсЃФсЃ╝сЃФсђЇсЂесЂЌсЂдУеГт«џсЂЋсѓїсЂдсЂёсѓІсЂ«сЂДсЂЎсђѓ
УДњућ░жЂИТЅІсЂФт»ЙсЂЌсЂдсЂ»сђЂ10сѓ░сЃфсЃЃсЃЅжЎЇТа╝сЂФтіасЂѕсђЂсЃџсЃісЃФсЃєсѓБсЃЮсѓцсЃ│сЃѕ2уѓ╣сЂїтіау«ЌсЂЋсѓїсЂЙсЂЌсЂЪсђѓсЂЊсѓїсЂФсѓѕсѓісђЂуЏ┤У┐Љ12сЂІТюѕжќЊсЂ«у┤»уЕЇсЃџсЃісЃФсЃєсѓБсЃЮсѓцсЃ│сЃѕсЂ»2уѓ╣сЂесЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓ
F1сЂФсЂісЂЉсѓІсЃџсЃісЃФсЃєсѓБсЃЮсѓцсЃ│сЃѕтѕХт║дсЂ»сђЂFIAсЂїсѓ╣сЃЮсЃ╝сЃёсЃъсЃ│сѓисЃЃсЃЌсЂет«ЅтЁеТђДсѓњуЏБУдќсЂЎсѓІТЅІТ«хсЂ«сЂ▓сЂесЂцсЂДсЂѓсѓісђЂ12сЂІТюѕсЂДу┤»уЕЇ12уѓ╣сЂФжЂћсЂЌсЂЪта┤тљѕсЂ»сђЂТгАТѕдсЂИсЂ«тЄ║та┤тЂюТГбсЂесЂёсЂєжЄЇтцДсЂфтѕХУБЂсЂїуДЉсЂЋсѓїсЂЙсЂЎсђѓ
Т│ЋуџёУд│уѓ╣сЂІсѓЅУдІсѓІFIAсЂ«УБЂжЄЈсЂежЎљуЋї

ТюгС╗ХсЂ«сѓѕсЂєсЂфУхцТЌЌСИГсЂ«У┐йсЂёУХісЂЌУАїуѓ║сЂФт»ЙсЂЌсЂдсЂ»сђЂтјЪтЅЄуџёсЂФсђїтЇ│ТЎѓжЂЋтЈЇсђЇсЂесЂЌсЂдтј│Та╝сЂФтЈќсѓіуиасЂЙсѓЅсѓїсѓІсЂ╣сЂЇсЂДсЂЎсЂїсђЂсЂЮсЂ«тѕцТќГсЂФсЂ»С║Іт«ЪУфЇт«џсЂеУДБжЄѕсЂ«СйЎтю░сѓѓсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓСЙІсЂѕсЂ░сђЂУ┐йсЂёУХісЂЋсѓїсЂЪУ╗іСИАсЂ«ТїЎтІЋсђЂжђ▓УАїТќ╣тљЉсђЂсѓ│сЃ╝сѓ╣СИісЂ«СйЇуй«тЈќсѓісђЂт«ЅтЁеТђДсЂ«уеІт║дсЂфсЂЕсЂїУђЃТЁ«сЂЋсѓїсђЂТюђухѓуџёсЂФсЂ»сѓ╣сЃЂсЃЦсЃ»сЃ╝сЃЅсЂ«УБЂжЄЈсЂФтДћсЂГсѓЅсѓїсЂЙсЂЎсђѓ
УДњућ░жЂИТЅІсЂїСИ╗т╝хсЂЌсЂЪсђїт«ЅтЁеуб║С┐ЮсЂ«сЂЪсѓЂсЂ«У┐йсЂёУХісЂЌсђЇсЂїС║Іт«ЪсЂІсЂцтљѕуљєуџёсЂДсЂѓсѓїсЂ░сђЂУГдтЉісѓёУ╗йтЙ«сЂфсЃџсЃісЃФсЃєсѓБсЂФсЂесЂЕсѓЂсѓІжЂИТіъУѓбсѓѓуљєУФќСИісЂ»сЂѓсѓітЙЌсЂЙсЂЌсЂЪсђѓсЂЌсЂІсЂЌсђЂС╗ітЏъсЂ»сЃєсЃгсЃАсЃѕсЃфсЃ╝сЂеТўатЃЈсђЂтљёУ╗іСИАсЂ«уіХТЁІсѓњуиЈтљѕуџёсЂФтІўТАѕсЂЌсђЂсѓ╣сЃЂсЃЦсЃ»сЃ╝сЃЅсЂ»сђїТўјуЎйсЂфжЂЋтЈЇсђЇсЂесЂЌсЂдтЄдуљєсЂЌсЂЙсЂЌсЂЪсђѓ
сЂЙсЂесѓЂ№╝џсЃЅсЃЕсѓцсЃљсЃ╝сЂеУдЈтЅЄсЂ«жќбС┐ѓТђД
F1сЂ»сђЂжЎљуЋїсЂ«СИГсЂДсЂ«тЅхжђаТђДсЂетѕцТќГтіЏсЂїТ▒ѓсѓЂсѓЅсѓїсѓІсѓ╣сЃЮсЃ╝сЃёсЂДсЂѓсѓісђЂсЃФсЃ╝сЃФсЂ«жЂІућесѓѓсЂЙсЂЪу▓Йуи╗сЂфТ│ЋуџётѕцТќГсЂ«жђБуХџсЂДсЂЎсђѓ
УДњућ░жЂИТЅІсЂ«С║ІСЙІсЂ»сђЂсђїУдЈтЅЄсЂ«тГЌжЮбсђЇсЂесђїсЃгсЃ╝сѓ╣СИГсЂ«уЈЙта┤тѕцТќГсђЇсЂесЂ«жќЊсЂФсЂѓсѓІсѓ░сЃгсЃ╝сѓЙсЃ╝сЃ│сЂ«тГўтюесѓњуц║сЂЎтЦйСЙІсЂДсЂЎсђѓС╗ітЙїсђЂУхцТЌЌСИГсЂ«У┐йсЂёУХісЂЌсЂФсЂцсЂёсЂдсѓѕсѓіТўјуб║сЂфжЂІућетЪ║Т║ќсЂїТЈљуц║сЂЋсѓїсѓІтЈ»УЃйТђДсѓѓсЂѓсѓісЂЙсЂЎсЂїсђЂуЈЙТЎѓуѓ╣сЂДсЂ»сђїухХт»ЙудЂТГбсђЇсЂесЂёсЂєтцДтјЪтЅЄсѓњсЃЅсЃЕсѓцсЃљсЃ╝сЂїтєЇУфЇУГўсЂЎсѓІт┐ЁУдЂсЂїсЂѓсѓІсЂДсЂЌсѓЄсЂєсђѓ
ТгАтЏъсЂ»сђЂС╗ітЏъсЂ«УеўС║ІсЂФуХџсЂЈтєЁт«╣сЂесЂЌсЂдсђЂтљїсЂўсЂЈсѓФсЃісЃђGPсЂ«Т▒║тІЮсЂФсЂісЂёсЂдсђЂсѓ╗сЃ╝сЃЋсЃєсѓБсѓФсЃ╝т░јтЁЦСИГсЂ«У┐йсЂёУХісЂЌсЂФсЂцсЂёсЂдтЈќсѓіСИісЂњсЂЙсЂЎсђѓС╗ітЏъсЂетљїТДўсЂ«УАїуѓ║сЂФсѓѓсЂІсЂІсЂІсѓЈсѓЅсЂџсђЂУДњућ░жЂИТЅІсЂ«сѓѕсЂєсЂфсѓ░сЃфсЃЃсЃЅжЎЇТа╝сЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂТѕњтЉісЂФсЂесЂЕсЂЙсЂБсЂЪсЂ«сЂ»сЂфсЂюсЂфсЂ«сЂДсЂЌсѓЄсЂєсЂІсђѓFIAсЂ«сЃџсЃісЃФсЃєсѓБтѕцТќГсЂ«СИђУ▓ФТђДсЂеТ│ЋуџётдЦтйЊТђДсЂФсЂцсЂёсЂдТцюУејсЂЌсЂдсЂёсЂЇсЂЙсЂЎсђѓ
жќбжђБсѓ┐сѓ░№╝џF1сЃфсЃ╝сѓгсЃФсЃ╗сЃЕсЃю
тйЊС║ІтІЎТЅђсЂФсѓѕсѓІт»ЙуГќсЂ«сЂћТАѕтєЁ
сЃбсЃјсЃфсѓ╣Т│ЋтЙІС║ІтІЎТЅђсЂ»сђЂITсђЂуЅ╣сЂФсѓцсЃ│сѓ┐сЃ╝сЃЇсЃЃсЃѕсЂеТ│ЋтЙІсЂ«СИАжЮбсЂФжФўсЂёт░ѓжќђТђДсѓњТюЅсЂЎсѓІТ│ЋтЙІС║ІтІЎТЅђсЂДсЂЎсђѓтйЊС║ІтІЎТЅђсЂДсЂ»сђЂТЮ▒Уе╝сЃЌсЃЕсѓцсЃаСИіта┤С╝ЂТЦГсЂІсѓЅсЃЎсЃ│сЃЂсЃБсЃ╝С╝ЂТЦГсЂЙсЂДсђЂС║║С║ІсЃ╗ті┤тІЎу«АуљєсЂФсЂісЂЉсѓІсѓхсЃЮсЃ╝сЃѕсѓёсђЂсЂЋсЂЙсЂќсЂЙсЂфТАѕС╗ХсЂФт»ЙсЂЎсѓІтЦЉу┤ёТЏИсЂ«СйюТѕљсЃ╗сЃгсЃЊсЃЦсЃ╝уГЅсѓњУАїсЂБсЂдсЂісѓісЂЙсЂЎсђѓУЕ│сЂЌсЂЈсЂ»сђЂСИІУеўУеўС║ІсѓњсЂћтЈѓуЁДсЂЈсЂасЂЋсЂёсђѓ
сЃбсЃјсЃфсѓ╣Т│ЋтЙІС║ІтІЎТЅђсЂ«тЈќТЅ▒тѕєжЄј№╝џITсЃ╗сЃЎсЃ│сЃЂсЃБсЃ╝сЂ«С╝ЂТЦГТ│ЋтІЎ
сѓФсЃєсѓ┤сЃфсЃ╝: ITсЃ╗сЃЎсЃ│сЃЂсЃБсЃ╝сЂ«С╝ЂТЦГТ│ЋтІЎ
сѓ┐сѓ░: Formula1