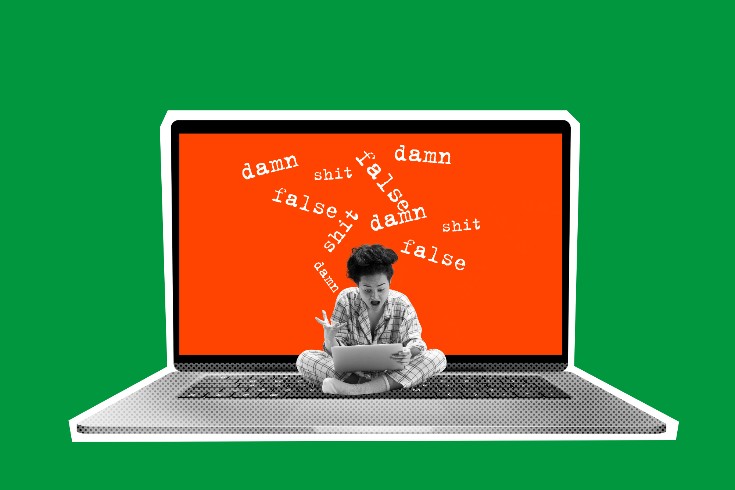DoSж”»ж’ғгҒҜзҠҜзҪӘгҒӢпјҹйӣ»еӯҗиЁҲз®—ж©ҹжҗҚеЈҠзӯүжҘӯеӢҷеҰЁе®ізҪӘгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰејҒиӯ·еЈ«гҒҢи§ЈиӘ¬

йӣ»еӯҗиЁҲз®—ж©ҹжҗҚеЈҠзӯүжҘӯеӢҷеҰЁе®ізҪӘгҒҜгҖҒжҳӯе’Ң62е№ҙ(1987е№ҙ)гҒ«ж–°иЁӯгҒ•гӮҢгҒҹзҠҜзҪӘгҒ§гҒҷгҖӮеҪ“жҷӮгҖҒзӨҫдјҡзөҢжёҲгҒ®й«ҳеәҰжҲҗй•·гӮ„жҠҖиЎ“гҒ®зҷәеұ•гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгӮӘгғ•гӮЈгӮ№гҒ«гӮӮгӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝгғјгҒҢеӨҡгҒҸе°Һе…ҘгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
еҫ“жқҘгҒӘгӮүгҒ°гҖҒдәәгҒ«гӮҲгӮҠиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹдҪңжҘӯгҒҢгӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝгғјгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиЎҢгӮҸгӮҢгҖҒгҒҫгҒҹжҘӯеӢҷзҜ„еӣІгҒ®жӢЎеӨ§гҒ«гӮӮеҜҫеҝңгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝгғјгҒ«еҗ‘гҒ‘гӮүгӮҢгҒҹеҠ е®ігӮ’жүӢж®өгҒЁгҒҷгӮӢжҘӯеӢҷеҰЁе®ігҒҢжғіе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒ«еҜҫеҮҰгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒеҗҢжі•гҒҢж–°иЁӯгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гӮӮгҒЈгҒЁгӮӮеҲ¶е®ҡеҪ“жҷӮгҒҜгҖҒгӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝгғјгҒҜгҒҫгҒ•гҒ«зҷәеұ•йҖ”дёҠгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹгӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲгӮӮжҷ®еҸҠгҒ—гҒҰгҒҠгӮүгҒҡгҖҒгӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲзҠҜзҪӘгӮ’е…·дҪ“зҡ„гҒ«дәҲжё¬гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜеӣ°йӣЈгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҒ“гҒ®жі•еҫӢгҒҜгӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝгғје·ҘеӯҰгӮ„жғ…е ұ科еӯҰгҖҒдёҖиҲ¬зӨҫдјҡгҒ§дҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгӮӢз”ЁиӘһгӮ’з”ЁгҒ„гҒҡгҖҒеҲ‘жі•е…ёгӮүгҒ—гҒ„дҪ“иЈҒгҒ®з”ЁиӘһгҒ§иҰҸе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒи§ЈйҮҲгҒҢж§ҳгҖ…гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒдёҖиҲ¬еёӮж°‘гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜгӮҸгҒӢгӮҠгҒ«гҒҸгҒ„иҰҸе®ҡгҒЁгӮӮгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒжң¬зҪӘгҒҜгҖҒгӮөгӮӨгғҗгғјзҠҜзҪӘгҒ®гҒҶгҒЎгҒ®гӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝзҠҜзҪӘгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢйЎһеһӢгҒ®зҠҜзҪӘгҒ«еҜҫеҝңгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁдёҖиҲ¬гҒ«иӘҚиӯҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ§гҒҜ йӣ»еӯҗиЁҲз®—ж©ҹжҗҚеЈҠзӯүжҘӯеӢҷеҰЁе®ізҪӘгҒ®и©ізҙ°гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеҲҶгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒҸи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡгӮөгӮӨгғҗгғјзҠҜзҪӘгҒ®3еҲҶйЎһгҒЁгҒҜпјҹеҗ„гғ‘гӮҝгғјгғігҒ®иў«е®іеҜҫзӯ–гӮ’ејҒиӯ·еЈ«гҒҢи§ЈиӘ¬
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®зӣ®ж¬Ў
DoSж”»ж’ғгҒЁгҒҜ

DoSж”»ж’ғ(Denial of Service attack)гҒЁгҒҜгҖҒгӮөгӮӨгғҗгғјж”»ж’ғгҒ®дёҖзЁ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒж”»ж’ғзӣ®жЁҷгҒ®гӮҰгӮ§гғ–гӮөгӮӨгғҲгӮ„гӮөгғјгғҗгғјгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰеӨ§йҮҸгҒ®гғҮгғјгӮҝгӮ„дёҚжӯЈгғҮгғјгӮҝгӮ’йҖҒгӮҠгҒӨгҒ‘гҒҹгӮҠгҒ—гҒҰйҒҺеү°гҒӘиІ иҚ·гӮ’гҒӢгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒзӣёжүӢж–№гҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’жӯЈеёёгҒ«зЁјеғҚгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„зҠ¶ж…ӢгҒ«иҝҪгҒ„иҫјгӮҖж”»ж’ғгҒ§гҒҷгҖӮ
DoSж”»ж’ғгҒҜгҖҒдёҚжӯЈгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒ§еҲ©з”ЁжЁ©йҷҗгӮ’гҒӢгҒ„гҒҸгҒҗгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒгӮҰгӮЈгғ«гӮ№гӮ’д»ӢгҒ—гҒҰгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®еҲ¶еҫЎгӮ’еҘӘгҒЈгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгӮөгғјгғҗгғјгҒ«йҒҺеү°гҒӘиІ иҚ·гӮ’гҒӢгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжӯЈиҰҸгҒ®гғҰгғјгӮ¶гҒҢгӮўгӮҜгӮ»гӮ№жЁ©йҷҗгӮ’иЎҢдҪҝгҒҷгӮӢгҒ®гӮ’еҰЁе®ігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮжҳ”гҒӢгӮүгҒӮгӮӢгӮөгӮӨгғҗгғјж”»ж’ғгҒ®жүӢжі•гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒиҝ‘е№ҙгҒ§гӮӮиў«е®ігҒҜе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
DDoSж”»ж’ғгҒЁгҒ®йҒ•гҒ„
DoSж”»ж’ғгҒҜгҖҒ1еҸ°гҒ®гӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝгғјгҒӢгӮүеӨ§йҮҸгҒ®гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гӮ’зҷәз”ҹгҒ•гҒӣгҖҒгӮөгғјгғҗгғјгҒ«иІ иҚ·гӮ’гҒӢгҒ‘гӮӢжүӢжі•гҒ§гҒҷгҖӮдёҖж–№гҖҒDDoSж”»ж’ғгҒҜгҖҒиӨҮж•°гҒ®гӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝгғјгӮ’иёҸгҒҝеҸ°гҒ«гҒ—гҒҰеӨ§иҰҸжЁЎгҒӘж”»ж’ғгӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
DDoSгҒ®ж”»ж’ғиҖ…гҒҜгҖҒгғһгғ«гӮҰгӮ§гӮўгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰд»–иҖ…гҒ®гғ‘гӮҪгӮігғігӮ„IoTж©ҹеҷЁгӮ’ж”Ҝй…ҚгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгӮүгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰгӮөгғјгғҗгғјгҒ«гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гӮ’йӣҶдёӯгҒ•гҒӣгҒҫгҒҷгҖӮDDoSж”»ж’ғгҒҜж”»ж’ғе…ғгҒҢеҲҶж•ЈгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҠ е®іиҖ…гҒ®зү№е®ҡгҒҢеӣ°йӣЈгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒеӨ§йҮҸгҒ®гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒҢйҖҡеёёгҒ®йҖҡдҝЎгҒЁгҒ®еҢәеҲҘгӮ’еӣ°йӣЈгҒ«гҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒж”»ж’ғгғҲгғ©гғ•гӮЈгғғгӮҜгҒ®гҒҝгӮ’йҒ®ж–ӯгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮе®№жҳ“гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гӮөгғјгғҗгғјгҒ«йҒҺеү°гҒӘиІ иҚ·гҒҢгҒӢгҒӢгӮӢгҒҹгӮҒгӮөгғјгғ“гӮ№еҒңжӯўгҒ«иҝҪгҒ„иҫјгҒҫгӮҢгӮӢгӮұгғјгӮ№гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
ж”»ж’ғиҖ…гӮ’зү№е®ҡгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№еҒңжӯўгҒ«гӮҲгӮӢж©ҹдјҡжҗҚеӨұгӮ„еҫ©ж—§гӮігӮ№гғҲгӮ’дәӢжҘӯиҖ…еҒҙгҒҢиІ жӢ…гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒе ҙеҗҲгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜйЎ§е®ўгҒёгҒ®иЈңе„ҹгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮӢгӮұгғјгӮ№гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
DoSж”»ж’ғгҒ®зЁ®йЎһ
DoSж”»ж’ғгҒҜгҖҒгҖҢгғ•гғ©гғғгғүеһӢгҖҚгҒЁгҖҢи„ҶејұжҖ§еһӢгҖҚгҒ®2зЁ®йЎһгҒ«еҲҶгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гғ•гғ©гғғгғүгҒЁгҒҜиӢұиӘһгҒ®вҖҳFloodвҖҷ(=жҙӘж°ҙ)гҒ«з”ұжқҘгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгғ—гғӯгғҲгӮігғ«гӮ’ж”»з•ҘгҒ—гҒҰеӨ§йҮҸгҒ®гғҮгғјгӮҝгӮ’йҖҒгӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒж”»ж’ғеҜҫиұЎгҒҢеҮҰзҗҶгҒ—гҒҚгӮҢгҒӘгҒ„зҠ¶ж…ӢгҒ«иҝҪгҒ„иҫјгӮҖгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
дёҖж–№гҖҒи„ҶејұжҖ§еһӢгҒҜгҖҒгӮөгғјгғҗгғјгӮ„гӮўгғ—гғӘгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҒ®и„ҶејұжҖ§гӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҖҒдёҚжӯЈеҮҰзҗҶгӮ’иЎҢгӮҸгҒӣгҖҒж©ҹиғҪгӮ’еҒңжӯўгҒ•гҒӣгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢдёҚжӯЈгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒЁгҒ®еҢәеҲҘгҒҢжӣ–жҳ§гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒе…ёеһӢзҡ„гҒӘи„ҶејұжҖ§еһӢгҒ®DoSж”»ж’ғгҒ§гҒӮгӮӢLANDж”»ж’ғгҒЁгҒҜгҖҒйҖҒдҝЎе…ғгҒЁе®ӣе…ҲгҒ® IP гӮўгғүгғ¬гӮ№гҒЁгғқгғјгғҲз•ӘеҸ·гҒҢдёҖиҮҙгҒҷгӮӢгғ‘гӮұгғғгғҲгӮ’йҖҒдҝЎгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
е°‘гҒ—еҲҶгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒҸиӘ¬жҳҺгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒж”»ж’ғиҖ…AгҒҢгҖҒж”»ж’ғеҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢгӮөгғјгғҗгғјBгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҢиҮӘеҲҶгҒҜBгҒӘгҒ®гҒ§иҝ”дәӢгҒҢж¬ІгҒ—гҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘іеҶ…е®№гҒ®гғ‘гӮұгғғгғҲгӮ’йҖҒгӮӢгҒЁгҖҒBгҒҜBиҮӘиә«гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҢиҝ”дәӢгҖҚгӮ’иЎҢгҒ„гҖҒгҒқгҒ®иҝ”дәӢгӮ’еҸ—гҒ‘еҸ–гҒЈгҒҹBгҒҢгҒҫгҒҹBиҮӘиә«гҒ«гҖҢиҝ”дәӢгҖҚгӮ’иЎҢгҒ„вҖҰгҒЁгҒ„гҒҶзҸҫиұЎгҒҢз№°гӮҠиҝ”гҒ•гӮҢгҖҒз„Ўйҷҗгғ«гғјгғ—гӮ’зҷәз”ҹгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҜгҖҒгҖҢиҮӘеҲҶиҮӘиә«гҒҢйҖҒдҝЎе…ғгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгғ‘гӮұгғғгғҲгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮиҝ”дәӢгӮ’гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§гҒ®гҖҢи„ҶејұжҖ§гҖҚгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгғ‘гӮ№гғҜгғјгғүиӘҚиЁјгҒӘгҒ©гӮ’жҪңгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒгҖҢдёҚжӯЈгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҖҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҖҢи„ҶејұжҖ§еһӢгҒ®DoSж”»ж’ғгҖҚгҒ«ж•ҙзҗҶгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡдёҚжӯЈгӮўгӮҜгӮ»гӮ№зҰҒжӯўжі•гҒ§зҰҒжӯўгҒ•гӮҢгӮӢиЎҢзӮә
DoSж”»ж’ғгҒ®д»•зө„гҒҝ
DoSж”»ж’ғгҒ®д»•зө„гҒҝгҒҜгҖҒйҖҡеёёTCP/IPгҒ®зҜ„еӣІеҶ…гҒ§жӯЈеҪ“гҒ«иӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’й »з№ҒгҒ«з№°гӮҠиҝ”гҒҷгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒжҠҖиЎ“зҡ„гҒ«гҒҜеҚҳзҙ”гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒдәәж°—гӮўгӮӨгғүгғ«гҒ®е…¬жј”гғҒгӮұгғғгғҲгӮ’дёҖиҲ¬зҷәеЈІгҒ§иіје…ҘгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁиІ©еЈІгғҡгғјгӮёгҒ«гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒеҗҢжҷӮгҒ«еӨҡгҒҸгҒ®дәәгҒҢгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гӮ’гҒ—гҒҹгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒгӮөгӮӨгғҲгҒҢйҮҚгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒгғҖгӮҰгғігҒ—гҒҹгӮҠгҒ—гҒҰз№ӢгҒҢгӮҠгҒ«гҒҸгҒҸгҒӘгӮӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶзҸҫиұЎгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮDoSж”»ж’ғгҒҜгҖҒжӯЈеҪ“гҒӘжЁ©йҷҗгӮ’жӮӘз”ЁгҒ—гҒҰгҖҒж„Ҹеӣізҡ„гҒ«гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҠ¶жіҒгӮ’дҪңгӮҠеҮәгҒҷж”»ж’ғгҒ§гҒҷгҖӮ
DoSж”»ж’ғгҒҜйӣ»еӯҗиЁҲз®—ж©ҹжҗҚеЈҠзӯүжҘӯеӢҷеҰЁе®ізҪӘгҒ«гҒӮгҒҹгӮӢгҒӢ

гҒ§гҒҜгҖҒDoSж”»ж’ғгҒҜзҠҜзҪӘгҒ«гҒӮгҒҹгӮӢгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮе…Ҳиҝ°гҒ—гҒҹйӣ»еӯҗиЁҲз®—ж©ҹжҗҚеЈҠзӯүжҘӯеӢҷеҰЁе®ізҪӘгҒ«еҪ“гҒҹгӮӢгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгӮ’жӨңиЁҺгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
дәәгҒ®жҘӯеӢҷгҒ«дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢйӣ»еӯҗиЁҲз®—ж©ҹиӢҘгҒ—гҒҸгҒҜгҒқгҒ®з”ЁгҒ«дҫӣгҒҷгӮӢйӣ»зЈҒзҡ„иЁҳйҢІгӮ’жҗҚеЈҠгҒ—гҖҒиӢҘгҒ—гҒҸгҒҜдәәгҒ®жҘӯеӢҷгҒ«дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢйӣ»еӯҗиЁҲз®—ж©ҹгҒ«иҷҡеҒҪгҒ®жғ…е ұиӢҘгҒ—гҒҸгҒҜдёҚжӯЈгҒӘжҢҮд»ӨгӮ’дёҺгҒҲгҖҒеҸҲгҒҜгҒқгҒ®д»–гҒ®ж–№жі•гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒйӣ»еӯҗиЁҲз®—ж©ҹгҒ«дҪҝз”Ёзӣ®зҡ„гҒ«жІҝгҒҶгҒ№гҒҚеӢ•дҪңгӮ’гҒ•гҒӣгҒҡгҖҒеҸҲгҒҜдҪҝз”Ёзӣ®зҡ„гҒ«еҸҚгҒҷгӮӢеӢ•дҪңгӮ’гҒ•гҒӣгҒҰгҖҒдәәгҒ®жҘӯеӢҷгӮ’еҰЁе®ігҒ—гҒҹиҖ…гҒҜгҖҒдә”е№ҙд»ҘдёӢгҒ®жҮІеҪ№еҸҲгҒҜзҷҫдёҮеҶҶд»ҘдёӢгҒ®зҪ°йҮ‘гҒ«еҮҰгҒҷгӮӢгҖӮ
еҲ‘法第234жқЎгҒ®2第1й …(йӣ»еӯҗиЁҲз®—ж©ҹжҗҚеЈҠзӯүжҘӯеӢҷеҰЁе®і)
гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒйӣ»еӯҗиЁҲз®—ж©ҹжҗҚеЈҠзӯүжҘӯеӢҷеҰЁе®ізҪӘгҒ®жҲҗз«ӢгҒ«гҒҜгҖҒе®ўиҰізҡ„иҰҒ件гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒ
- йӣ»еӯҗиЁҲз®—ж©ҹгҒ«еҗ‘гҒ‘гӮүгӮҢгҒҹеҠ е®іиЎҢзӮә
- йӣ»еӯҗиЁҲз®—ж©ҹгҒ®еӢ•дҪңйҳ»е®і
- жҘӯеӢҷеҰЁе®і
дёҠиЁҳгҒ® 3гҒӨгӮ’е……и¶ігҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҖҒдё»иҰізҡ„иҰҒ件гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒҷгҒ№гҒҰгҒ«ж•…ж„ҸгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
йӣ»еӯҗиЁҲз®—ж©ҹжҗҚеЈҠзӯүжҘӯеӢҷеҰЁе®ізҪӘгҒ®е®ўиҰізҡ„ж§ӢжҲҗиҰҒ件充足жҖ§гҒЁгҒҜ
дёӢиЁҳгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеҖӢеҲҘгҒ«жӨңиЁҺгҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
йӣ»еӯҗиЁҲз®—ж©ҹгҒ«еҗ‘гҒ‘гӮүгӮҢгҒҹеҠ е®іиЎҢзӮә
еҠ е®іиЎҢзӮә(е®ҹиЎҢиЎҢзӮә)гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒ
- гҖҢйӣ»еӯҗиЁҲз®—ж©ҹгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜгҒқгҒ®з”ЁгҒ«дҫӣгҒҷгӮӢйӣ»зЈҒзҡ„иЁҳйҢІгҒ®жҗҚеЈҠгҖҚ
- гҖҢйӣ»еӯҗиЁҲз®—ж©ҹгҒ«иҷҡеҒҪгҒ®жғ…е ұгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜдёҚжӯЈгҒ®жҢҮд»ӨгӮ’дёҺгҒҲгҖҚ
- гҖҢгҒҫгҒҹгҒҜгҒқгҒ®д»–гҒ®ж–№жі•гҖҚ
гҒ®гҒ„гҒҡгӮҢгҒӢгҒ«еҪ“гҒҹгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҖҢйӣ»еӯҗиЁҲз®—ж©ҹгҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒиЈҒеҲӨдҫӢ(зҰҸеІЎй«ҳеҲӨе№і12.9.21)гҒҢе®ҡзҫ©гӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒиҮӘеӢ•зҡ„гҒ«иЁҲз®—гӮ„гғҮгғјгӮҝгҒ®еҮҰзҗҶгӮ’иЎҢгҒҶйӣ»еӯҗиЈ…зҪ®гҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгӮӘгғ•гӮЈгӮ№гӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝгғјгӮ„гғ‘гғјгӮҪгғҠгғ«гӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝгғјгҖҒеҲ¶еҫЎз”ЁгӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝгғјзӯүгҒҢд»ЈиЎЁгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜдәүгҒ„гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
йӣ»зЈҒзҡ„иЁҳйҢІгҒҜгҖҒеҲ‘жі•7жқЎгҒ®2гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҢйӣ»еӯҗзҡ„ж–№ејҸгҖҒзЈҒж°—зҡ„ж–№ејҸгҒқгҒ®д»–дәәгҒ®зҹҘиҰҡгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜиӘҚиӯҳгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„ж–№ејҸгҒ§дҪңгӮүгӮҢгӮӢиЁҳйҢІгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒйӣ»еӯҗиЁҲз®—ж©ҹгҒ«гӮҲгӮӢжғ…е ұеҮҰзҗҶгҒ®з”ЁгҒ«дҫӣгҒ•гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҖҚгҒЁе®ҡзҫ©гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®е®ҡзҫ©гҒ«з…§гӮүгҒӣгҒ°гҖҒDoSж”»ж’ғгҒ®жЁҷзҡ„гҒЁгҒӘгӮӢгӮөгғјгғҗгғјгӮӮеҪ“然гҖҒйӣ»зЈҒзҡ„иЁҳйҢІгҒ®еҜҫиұЎгҒ§гҒҷгҖӮйӣ»зЈҒзҡ„иЁҳйҢІгҒ®е…·дҪ“дҫӢгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгғ‘гӮҪгӮігғігӮ„гӮ№гғһгғјгғҲгғ•гӮ©гғігҒӘгҒ©гҒ§жүұгӮҸгӮҢгӮӢгғҮгӮёгӮҝгғ«гғҮгғјгӮҝе…ЁиҲ¬гҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒWordгӮ„ExcelгҒ®ж–Үжӣёгғ•гӮЎгӮӨгғ«гӮ„гғҮгӮёгӮҝгғ«гӮ«гғЎгғ©гҒ®еҶҷзңҹгғҮгғјгӮҝгҖҒйҹіжҘҪгғ•гӮЎгӮӨгғ«гҒӘгҒ©гҒҢи©ІеҪ“гҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒҜгғҸгғјгғүгғҮгӮЈгӮ№гӮҜгӮ„SSDгҖҒUSBгғЎгғўгғӘгҖҒSDгӮ«гғјгғүгҒӘгҒ©гҒ®иЁҳжҶ¶еӘ’дҪ“гҒ«дҝқеӯҳгҒ•гӮҢеҝ…иҰҒгҒ«еҝңгҒҳгҒҰиӘӯгҒҝжӣёгҒҚгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒгӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгӮ«гғјгғүгӮ„дәӨйҖҡзі»ICгӮ«гғјгғүгҒ«иЁҳйҢІгҒ•гӮҢгҒҹжғ…е ұгӮӮйӣ»зЈҒзҡ„иЁҳйҢІгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҢжҗҚеЈҠгҖҚгҒЁгҒҜгҖҒзү©зҗҶзҡ„гҒӘз ҙеЈҠгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгғҮгғјгӮҝгҒ®ж¶ҲеҺ»гҒӘгҒ©гҖҒзү©гҒ®еҠ№з”ЁгӮ’е®ігҒҷгӮӢдёҖеҲҮгҒ®иЎҢзӮәгӮ’гҒ„гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҖҢиҷҡеҒҪгҒ®жғ…е ұгҖҚгҒҜеҶ…е®№гҒҢзңҹе®ҹгҒ«еҸҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒ„гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҖҢдёҚжӯЈгҒ®жҢҮд»ӨгҖҚгҒЁгҒҜгҖҒжЁ©йҷҗгҒӘгҒҸеҪ“и©ІгӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝгғјгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҮҰзҗҶеҸҜиғҪгҒӘе‘Ҫд»ӨгӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒ„гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгғ•гғ©гғғгғүеһӢгҒ®DoSж”»ж’ғгӮ’еӨ§йҮҸгҒӢгҒӨйӣҶдёӯзҡ„гҒ«иЎҢгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҖҒж”»ж’ғеҜҫиұЎгҒ®гӮөгғјгғҗгғјгҒҢйҒҺиІ иҚ·гҒ«гҒӘгӮҠгҖҒеҮҰзҗҶгӮ’йҒ©жӯЈгҒ«е®ҹиЎҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„зҠ¶ж…ӢгҒ«гҒ•гҒӣгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж”»ж’ғгҒҜгҖҒгғҮгғјгӮҝгӮ’ж¶ҲеҺ»гҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҒ®гҖҢжҗҚеЈҠгҖҚгҒ«иҮігӮүгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮгҖҒгӮөгғјгғҗгғјиЁӯзҪ®иҖ…гҒ®ж„ҸжҖқгҒ«еҸҚгҒ—гҒҹгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжЁ©йҷҗгҒӘгҒҸе‘Ҫд»ӨгӮ’дёҺгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒЁгҒ„гҒҲгҖҢдёҚжӯЈгҒ®жҢҮд»ӨгҖҚгҒ«гҒӮгҒҹгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
йӣ»еӯҗиЁҲз®—ж©ҹгҒ®еӢ•дҪңйҳ»е®і
гҖҢдҪҝз”Ёзӣ®зҡ„гҒ«жІҝгҒҶгҒ№гҒҚеӢ•дҪңгӮ’гҒ•гҒӣгҒҡгҖҚгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜгҖҢдҪҝз”Ёзӣ®зҡ„гҒ«еҸҚгҒҷгӮӢеӢ•дҪңгӮ’гҒ•гҒӣгӮӢгҖҚгҒ«еҪ“гҒҹгӮӢгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒҢе•ҸйЎҢгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮиӘ°гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒ®дҪҝз”Ёзӣ®зҡ„гӮ’еүҚжҸҗгҒЁгҒҷгӮӢгҒ№гҒҚгҒӘгҒ®гҒӢдәүгҒ„гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжң¬зҪӘгҒ®дҝқиӯ·жі•зӣҠгҒҢжҘӯеӢҷгҒ®е®үе…ЁгҒӢгҒӨеҶҶж»‘гҒӘйҒӮиЎҢгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒиЁӯзҪ®иҖ…гҒ®зӣ®зҡ„гӮ’еүҚжҸҗгҒЁгҒҷгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮӢгҒ№гҒҚгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
DoSж”»ж’ғгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҖҒгӮөгғјгғҗгғјгҒ«йҒҺиІ иҚ·гҒҢгҒӢгҒӢгӮӢгҒЁгҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢеҲ©з”ЁдёҚеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒгӮөгғјгғҗгғјиЁӯзҪ®иҖ…гҒҢзӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҹйҒ©жӯЈгҒӘеҮҰзҗҶеӢ•дҪңгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҢдҪҝз”Ёзӣ®зҡ„гҒ«жІҝгҒҶгҒ№гҒҚеӢ•дҪңгҖҚгҒҢгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒЁгҒ„гҒҲгҖҒеӢ•дҪңйҳ»е®ігҒ«гҒӮгҒҹгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жҘӯеӢҷеҰЁе®і
йӣ»еӯҗиЁҲз®—ж©ҹжҗҚеЈҠзӯүжҘӯеӢҷеҰЁе®ізҪӘгҒҜгҖҒжҘӯеӢҷеҰЁе®ізҪӘ(еҲ‘法第233жқЎпјҢ第234жқЎ)гҒ®еҠ йҮҚйЎһеһӢгҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ®жҘӯеӢҷеҰЁе®ігҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒйҖҡеёёгҒ®жҘӯеӢҷеҰЁе®ізҪӘгҒЁеҗҢж§ҳгҒ«иҖғгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҒгҖҢжҘӯеӢҷгҖҚгҒЁгҒҜгҖҒзӨҫдјҡз”ҹжҙ»дёҠгҒ®ең°дҪҚгҒ«еҹәгҒҘгҒҚеҸҚеҫ©з¶ҷз¶ҡгҒ—гҒҰиЎҢгҒҶдәӢеӢҷгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гҒ„гҒ„гҖҒгҖҢеҰЁе®ігҖҚгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜзҸҫе®ҹгҒ«жҘӯеӢҷгҒҢе®ігҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иҰҒгҒ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
DoSж”»ж’ғгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгӮӢгҒЁгҖҒиЁӯзҪ®иҖ…гҒҢгӮөгғјгғҗгғјгӮ’дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’гӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲдёҠгҒ§жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖҢжҘӯеӢҷгҖҚгҒҢеҰЁе®ігҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҲгҖҒжҘӯеӢҷеҰЁе®ігҒ«гҒӮгҒҹгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
йӣ»еӯҗиЁҲз®—ж©ҹжҗҚеЈҠзӯүжҘӯеӢҷеҰЁе®ізҪӘгҒ®дё»иҰізҡ„иҰҒ件充足жҖ§гҒЁгҒҜ
гҒ“гӮҢгӮүгҒ®иҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒ—гҒҹдёҠгҒ§гҖҒж•…ж„Ҹ(еҲ‘法第38жқЎз¬¬1й …жң¬ж–Ү)гҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮж•…ж„ҸгҒЁгҒҜгҖҒдёҠиЁҳ1гҒӢгӮү3пјҲж§ӢжҲҗиҰҒ件гҒЁгҒ„гҒ„гҒҫгҒҷпјүгҒ«и©ІеҪ“гҒҷгӮӢдәӢе®ҹгӮ’иӘҚиӯҳгғ»иӘҚе®№гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒ„гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҜгҖҒзӣёжүӢгӮ’еҰЁе®ігҒҷгӮӢжӮӘж„ҸгӮ„е®іж„ҸгҒҫгҒ§гҒҜеҝ…иҰҒгҒӘгҒҸгҖҒгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҒӨгӮӮгӮҠгҒҢгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮгҖҒгҖҢгӮӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒҹгӮүгӮөгғјгғҗгғјгҒҢиҗҪгҒЎгҒҰгҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢеҲ©з”ЁдёҚиғҪгҒ«гҒӘгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиӘҚиӯҳгҒҢгҒӮгӮҢгҒ°гҖҒж•…ж„ҸгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҶгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
еІЎеҙҺеёӮз«ӢдёӯеӨ®еӣіжӣёйӨЁгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёеӨ§йҮҸгӮўгӮҜгӮ»гӮ№дәӢ件

дёҠиЁҳгҒ«й–ўйҖЈгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢеІЎеҙҺеёӮз«ӢдёӯеӨ®еӣіжӣёйӨЁгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёеӨ§йҮҸгӮўгӮҜгӮ»гӮ№дәӢ件(йҖҡз§°LibrahackдәӢ件)гҖҚгӮ’зҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
дәӢ件гҒ®зөҢз·Ҝ
ж„ӣзҹҘзңҢеҶ…гҒ®з”·жҖ§пјҲпј“пјҷпјүгҒҢгҖҒиҮӘдҪңгғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ§еӣіжӣёйӨЁгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒӢгӮүж–°зқҖеӣіжӣёгҒ®жғ…е ұгӮ’йӣҶгӮҒгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒгӮөгӮӨгғҗгғјж”»ж’ғгӮ’д»•жҺӣгҒ‘гҒҹгҒЁгҒ—гҒҰйҖ®жҚ•гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒжңқж—Ҙж–°иҒһгҒҢдҫқй јгҒ—гҒҹе°Ӯй–Җ家гҒ®и§ЈжһҗгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒеӣіжӣёйӨЁгӮҪгғ•гғҲгҒ«дёҚе…·еҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒеӨ§йҮҸгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒ«гӮҲгӮӢж”»ж’ғгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«иҰӢгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢеҲҶгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮеҗҢгҒҳгӮҪгғ•гғҲгӮ’дҪҝгҒҶе…ЁеӣҪпј–гӮ«жүҖгҒ®еӣіжӣёйӨЁгҒ§гӮӮеҗҢж§ҳгҒ®йҡңе®ігҒҢиө·гҒҚгҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгӮӮеҲӨжҳҺгҖӮгӮҪгғ•гғҲй–ӢзҷәдјҡзӨҫгҒҜе…ЁеӣҪзҙ„пј“пјҗгҒ®еӣіжӣёйӨЁгҒ§ж”№дҝ®гӮ’е§ӢгӮҒгҒҹгҖӮ
жңқж—Ҙж–°иҒһеҗҚеҸӨеұӢзүҲжңқеҲҠ(2010е№ҙ8жңҲ21ж—Ҙ)
гҖҖгҒ“гҒ®е•ҸйЎҢгҒҜеҗҢзңҢеІЎеҙҺеёӮз«ӢеӣіжӣёйӨЁгҒ§иө·гҒҚгҒҹгҖӮгӮҪгғ•гғҲгҒ«гҒҜгҖҒи”өжӣёгғҮгғјгӮҝгӮ’е‘јгҒіеҮәгҒҷгҒҹгҒігҒ«йӣ»з®—еҮҰзҗҶгҒҢз¶ҷз¶ҡдёӯгҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒйӣ»и©ұгҒ®йҖҡи©ұеҫҢгҒ«еҸ—и©ұеҷЁгӮ’дёҠгҒ’гҒҹгҒҫгҒҫгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӘгӮӢдёҚе…·еҗҲгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮдёҖе®ҡгҒ®жҷӮй–“гҒҢгҒҹгҒӨгҒЁеј·еҲ¶зҡ„гҒ«еҲҮж–ӯгҒ•гӮҢгӮӢгҒҢгҖҒеҗҢеӣіжӣёйӨЁгҒ§гҒҜпј‘пјҗеҲҶй–“гҒ«гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒҢзҙ„пј‘еҚғ件гӮ’и¶…гҒҲгӮӢгҒЁгҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®й–ІиҰ§гҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒеӨ§йҮҸгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«иҰӢгҒҲгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ
гҖҖз”·жҖ§гҒҜгӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮЁгӮўжҠҖиЎ“иҖ…гҒ§гҖҒеІЎеҙҺеёӮз«ӢеӣіжӣёйӨЁгҒӢгӮүе№ҙгҒ«зҙ„пј‘пјҗпјҗеҶҠеҖҹгӮҠгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮеӣіжӣёйӨЁгҒ®гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒҜдҪҝгҒ„еӢқжүӢгҒҢжӮӘгҒҸгҖҒж–°зқҖеӣіжӣёгҒ®жғ…е ұгӮ’жҜҺж—ҘйӣҶгӮҒгӮӢгғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гӮ’дҪңгӮҠгҖҒпј“жңҲгҒӢгӮүдҪҝгҒ„е§ӢгӮҒгҒҹгҖӮ
гҖҖеӣіжӣёйӨЁгҒ«гҒҜеҗҢжңҲд»ҘйҷҚгҖҒгҖҢгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮүгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁеёӮж°‘гҒӢгӮүиӢҰжғ…гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮзӣёи«ҮгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹж„ӣзҹҘзңҢиӯҰгҒҜгҖҒеҮҰзҗҶиғҪеҠӣгӮ’и¶…гҒҲгӮӢиҰҒжұӮгӮ’ж•…ж„ҸгҒ«йҖҒгӮҠгҒӨгҒ‘гҒҹгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҖҒжҘӯеӢҷеҰЁе®іе®№з–‘гҒ§з”·жҖ§гӮ’йҖ®жҚ•гҒ—гҒҹгҖӮеҗҚеҸӨеұӢең°жӨңеІЎеҙҺж”ҜйғЁгҒҜпј–жңҲгҖҒгҖҢжҘӯеӢҷеҰЁе®ігҒ®еј·гҒ„ж„ҸеӣігҒҜиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰиө·иЁҙзҢ¶дәҲеҮҰеҲҶгҒЁгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®дәӢ件гҒ§йҖ®жҚ•гҒ•гӮҢгҒҹз”·жҖ§гҒҜгҖҒеІЎеҙҺеёӮз«ӢдёӯеӨ®еӣіжӣёйӨЁгҒ®еҲ©з”ЁиҖ…гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҗҢйӨЁгӮҰгӮ§гғ–гӮөгӮӨгғҲгҒ®ж–°зқҖеӣіжӣёжғ…е ұгӮ’еҸҺйӣҶгҒҷгӮӢзӣ®зҡ„гҒ§иЎҢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒеӣіжӣёйӨЁгҒ®жҘӯеӢҷгӮ’еҰЁе®ігҒҷгӮӢж„ҸеӣігҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ—гҒҰгӮўгӮҜгӮ»гӮ№й »еәҰгӮӮз§’1еӣһзЁӢеәҰгҒЁдҪҺгҒҸгҖҒйҖҡеёёгҒӘгӮүDoSж”»ж’ғгҒ«гҒҜеҪ“гҒҹгӮүгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒеӣіжӣёйӨЁгҒ®гӮөгғјгғҗгғјгҒ«дёҚе…·еҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒ“гҒ®зЁӢеәҰгҒ§гӮ·гӮ№гғҶгғ йҡңе®ігҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
жӮӘж„ҸгҒҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҲгҒ©гӮӮгҖҒDoSж”»ж’ғгҒ«гҒӮгҒҹгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘе®ҹиЎҢиЎҢзӮәгҒ«гӮҲгӮҠеӣіжӣёйӨЁгҒ®гӮөгғјгғҗгғјгӮ’гғҖгӮҰгғігҒ•гҒӣгҒқгҒ®жҘӯеӢҷгӮ’еҰЁе®ігҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҜиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒе®ўиҰізҡ„иҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒж•…ж„ҸгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒе…ҲгҒ»гҒ©иҝ°гҒ№гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«жӮӘж„ҸгҒҢгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮж•…ж„ҸгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢеҫ—гҒҫгҒҷгҖӮ
зңҢиӯҰгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®з”·жҖ§гҒҢгӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝгҒ«и©ігҒ—гҒ„жҠҖиЎ“иҖ…гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲгӮ’еӨ§йҮҸгҒ«йҖҒгӮҠгҒӨгҒ‘гҒҹгӮүгҖҒеӣіжӣёйӨЁгҒ®гӮөгғјгғҗгҒ«еҪұйҹҝгҒҢеҮәгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гӮ’иӘҚиӯҳгҒ§гҒҚгҒҹгҒ«гӮӮй–ўгӮҸгӮүгҒҡгҖҒгӮҜгӮЁгӮ№гғҲгӮ’еӨ§йҮҸгҒ«йҖҒгӮҠгҒӨгҒ‘гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒж•…ж„ҸгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҖҒзҠҜзҪӘгҒҢжҲҗз«ӢгҒ—гҒҶгӮӢгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҹгӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
дәӢ件гҒ®е•ҸйЎҢзӮ№гӮ„жү№еҲӨ
еІЎеҙҺеёӮз«ӢдёӯеӨ®еӣіжӣёйӨЁгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёеӨ§йҮҸгӮўгӮҜгӮ»гӮ№дәӢ件гҒ§гҒҜгҖҒгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®дёҚеӮҷгҒ«гӮҲгӮӢйҖ®жҚ•дәӢжЎҲгҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҖҒжү№еҲӨгӮ’жӢӣгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
еҗҢйӨЁгҒҜиҮӘеӢ•еҸҺйӣҶгғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ«гӮҲгӮӢгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гӮ’жҘӯеӢҷеҰЁе®ігҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҖҒиӯҰеҜҹгҒ«иў«е®іеұҠгӮ’жҸҗеҮәгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒеҫҢгҒ«гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®иЁӯиЁҲгғҹгӮ№гҒҢеҲӨжҳҺгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮйҒ©еҲҮгҒӘгӮўгӮҜгӮ»гӮ№з®ЎзҗҶгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮҢгҒ°гҖҒйҳІгҒ’гҒҹеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒеҖӢдәәжғ…е ұгҒ®з®ЎзҗҶгҒ«гӮӮе•ҸйЎҢгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮиӯҰеҜҹгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒгӮөгғјгғҗгғјгҒ®еҲ©з”ЁиҖ…гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гғӯгӮ°гӮ„ж°ҸеҗҚгҒӘгҒ©гҒ®гғҮгғјгӮҝгӮ’д»»ж„ҸгҒ§жҸҗдҫӣгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«еҠ гҒҲгҖҒ委託жҘӯиҖ…гҒ®гғҹгӮ№гҒ«гӮҲгӮӢеҖӢдәәжғ…е ұжөҒеҮәгӮӮзҷәз”ҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®иғҢжҷҜгҒ«гҒҜгҖҒгғҮгғјгӮҝз®ЎзҗҶгғқгғӘгӮ·гғјгҒ®дёҚеӮҷгӮ„еӨ–йғЁе§”иЁ—е…ҲгҒ®зӣЈзқЈдёҚи¶ігҒ«гҒӮгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
з”·жҖ§гҒҜгҖҒжҘӯеӢҷеҰЁе®ігҒ®еј·гҒ„ж„ҸеӣігҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒзөҗжһңзҡ„гҒ«иө·иЁҙзҢ¶дәҲеҮҰеҲҶгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒ20ж—Ҙй–“гҒ«гӮӮгӮҸгҒҹгӮӢйҖ®жҚ•гғ»еӢҫз•ҷгҒ§еҸ–иӘҝгҒ№гӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒиә«дҪ“зҡ„жӢҳжқҹгӮ’еј·гҒ„гӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹйҖ®жҚ•жҷӮгҒ«гҒҜе®ҹеҗҚе ұйҒ“гҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
иө·иЁҙзҢ¶дәҲеҮҰеҲҶгҒЁгҒҜгҖҒдёҚиө·иЁҙгҒ®дёӯгҒ§гӮӮгҖҢе«Ңз–‘дёҚеҚҒеҲҶгҖҚгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮҠгҖҒгҖҢзҠҜзҪӘгҒҜгҒӮгҒЈгҒҹгҒҢжӮӘиіӘжҖ§гҒҢдҪҺгҒ„гҖҒгҒЁгҒӢж·ұгҒҸеҸҚзңҒгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹзҗҶз”ұгҒ§д»ҠеӣһгҒҜиө·иЁҙгӮ’иҰӢйҖҒгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶйЎһеһӢгҒ§гҖҒгҒӨгҒҫгӮҠзҠҜзҪӘгҒҜзҠҜгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒиө·иЁҙгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒзӨҫдјҡзҡ„гҒ«еӨ§гҒҚгҒӘдёҚеҲ©зӣҠгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҜе•ҸйЎҢгҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
дәӢ件гҒ®ж•ҷиЁ“гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒз•°еёёгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒ®йҒ©еҲҮгҒӘи§ЈжһҗгӮ„жі•зҡ„еҲӨж–ӯгҒ®ж…ҺйҮҚгҒ•гҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒеҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·гҒ®еҫ№еә•гҒЁе§”иЁ—е…Ҳз®ЎзҗҶгҒ®еј·еҢ–гҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®еҜҫзӯ–гӮ’жҖ гӮӢгҒЁгҖҒиӘӨиӘҚйҖ®жҚ•гӮ„жғ…е ұжјҸгҒҲгҒ„гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹйҮҚеӨ§гҒӘе•ҸйЎҢгӮ’еј•гҒҚиө·гҒ“гҒҷеҚұйҷәжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
иў«е®іеұҠгҒ®жҸҗеҮәгҒҜж…ҺйҮҚгҒ«иЎҢгҒ„гҖҒгҒҫгҒҡгҒҜжҘӯеӢҷеҰЁе®ігҒ«и©ІеҪ“гҒҷгӮӢгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгӮ’жӯЈзўәгҒ«еҲӨж–ӯгҒ—гҒҹгҒҶгҒҲгҒ§гҖҒйҒ©еҲҮгҒӘеҜҫеҮҰгӮ’и¬ӣгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
DoSж”»ж’ғгҒёгҒ®еҜҫзӯ–

DoSж”»ж’ғеҜҫзӯ–гҒ«гҒҜгҖҒдәҲйҳІзӯ–гҒЁзҷәз”ҹжҷӮгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҜҫеҝңгҒ®дёЎж–№гҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮиў«е®ігӮ’жңҖе°ҸйҷҗгҒ«жҠ‘гҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒиӨҮж•°гҒ®гӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈеҜҫзӯ–гӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дәӢеүҚеҜҫзӯ–гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒдёҚиҰҒгҒӘжө·еӨ–гҒӢгӮүгҒ®гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гӮ’йҒ®ж–ӯгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ„гҖҒCDNпјҲContents Delivery NetworkпјүгӮ„WAFпјҲWeb Application FirewallпјүгӮ’е°Һе…ҘгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒж”»ж’ғгҒ®еҪұйҹҝгӮ’и»ҪжёӣгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮи„ҶејұжҖ§еһӢгҒ«гҒҜгҖҒгӮөгғјгғҗгғјгҒёгҒ®гғ‘гғғгғҒйҒ©з”ЁгҖҒдёҚиҰҒгҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ„гғқгғјгғҲгҒ®еҒңжӯўгҖҒи„ҶејұжҖ§жӨңжҹ»гҒӘгҒ©гҒҢжңүеҠ№гҒ§гҒҷгҖӮFloodеһӢгҒ«гҒҜгҖҒдёҚжӯЈгҒӘгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гӮ’жӨңзҹҘгғ»йҳІеҫЎгҒҷгӮӢIPS/IDSгҒ®е®ҹиЈ…гҒҢжӨңиЁҺеҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒеҗҢдёҖIPгӮўгғүгғ¬гӮ№гҒӢгӮүгҒ®гӮўгӮҜгӮ»гӮ№еҲ¶йҷҗгӮ„йҒ©еҲҮгҒӘгӮҝгӮӨгғ гӮўгӮҰгғҲиЁӯе®ҡгӮӮжңүеҠ№гҒ§гҒҷгҖӮйҮҚиҰҒеәҰгҒ«еҹәгҒҘгҒҸгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®еҲҶйӣўгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒдәӢжҘӯз¶ҷз¶ҡгҒ«дёҚеҸҜж¬ гҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’дҝқиӯ·гҒҷгӮӢгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜж§ӢжҲҗгӮӮжӨңиЁҺгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
зӣЈиҰ–гҒЁжә–еӮҷгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒе№іеёёжҷӮгҒӢгӮүгғҲгғ©гғ•гӮЈгғғгӮҜгӮ’зӣЈиҰ–гҒ—гҖҒз•°еёёгӮ’ж—©жңҹгҒ«жӨңзҹҘгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гӮўгғ©гғјгғҲгӮ’иЁӯе®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒиҝ…йҖҹгҒӘеҜҫеҝңгҒҢеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгӮөгӮӨгғҲйҡңе®ізҷәз”ҹжҷӮгҒ«гҒҜгҖҒSNSгҒӘгҒ©гӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҰеҲ©з”ЁиҖ…гҒёзҠ¶жіҒгӮ’йҖҡзҹҘгҒҷгӮӢжүӢж®өгӮ’дәӢеүҚгҒ«зўәдҝқгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠж··д№ұгӮ’йҳІжӯўгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
DoSж”»ж’ғгҒ«гӮҲгӮӢиў«е®ігҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҹйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒиӯҰеҜҹеәҒгҒ®гӮөгӮӨгғҗгғјдәӢжЎҲйҖҡе ұзӘ“еҸЈгҒҫгҒҹгҒҜеҗ„йғҪйҒ“еәңзңҢиӯҰеҜҹжң¬йғЁгҒ®гӮөгӮӨгғҗгғјзҠҜзҪӘзӣёи«ҮзӘ“еҸЈгҒёйҖЈзөЎгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮиӯҰеҜҹеәҒгҒ§гҒҜгӮӘгғігғ©гӮӨгғійҖҡе ұзӘ“еҸЈгӮӮиЁӯзҪ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҸӮиҖғпјҡиӯҰеҜҹеәҒпҪңиӯҰеҜҹеәҒгӮөгӮӨгғҗгғјиӯҰеҜҹеұҖгҖҖеҶ…й–ЈгӮөгӮӨгғҗгғјгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈгӮ»гғігӮҝгғј
еҸӮиҖғпјҡиӯҰеҜҹеәҒпҪңгӮөгӮӨгғҗгғјдәӢжЎҲгҒ«й–ўгҒҷгӮӢзӣёи«ҮзӘ“еҸЈ
йӣ»еӯҗиЁҲз®—ж©ҹжҗҚеЈҠзӯүжҘӯеӢҷеҰЁе®ізҪӘгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜејҒиӯ·еЈ«гҒ«зӣёи«ҮгӮ’
DoSж”»ж’ғгҒҜгҖҒгӮөгғјгғҗгғјгҒ«йҒҺеү°гҒӘиІ иҚ·гӮ’гҒӢгҒ‘гҒҰгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҰЁе®ігҒҷгӮӢгӮөгӮӨгғҗгғјж”»ж’ғгҒ§гҒҷгҖӮ
DoSж”»ж’ғгҒҜгҖҒйӣ»еӯҗиЁҲз®—ж©ҹжҗҚеЈҠзӯүжҘӯеӢҷеҰЁе®ізҪӘгҒ«и©ІеҪ“гҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒе®ўиҰізҡ„гҒҠгӮҲгҒідё»иҰізҡ„иҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒҷгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠзҠҜзҪӘгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
DoSж”»ж’ғгҒҜйҒҝгҒ‘гҒҢгҒҹгҒ„гғӘгӮ№гӮҜгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒж”»ж’ғж–№жі•гҒЁеҜҫзӯ–гӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§иў«е®ігӮ’жңҖе°ҸйҷҗгҒ«жҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮзҠҜдәәгҒ®зү№е®ҡгҒ«гӮҲгӮҠжҗҚе®іиі е„ҹи«ӢжұӮгӮӮеҸҜиғҪгҒӘгҒҹгӮҒгҖҒITе•ҸйЎҢгҒ«и©ігҒ—гҒ„ејҒиӯ·еЈ«гҒ«зӣёи«ҮгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮдёҖгҒӨгҒ®ж–№жі•гҒ§гҒҷгҖӮ
еҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ«гӮҲгӮӢеҜҫзӯ–гҒ®гҒ”жЎҲеҶ…
гғўгғҺгғӘгӮ№жі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒҜгҖҒITгҖҒзү№гҒ«гӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲгҒЁжі•еҫӢгҒ®дёЎйқўгҒ«иұҠеҜҢгҒӘзөҢйЁ“гӮ’жңүгҒҷгӮӢжі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒ§гҒҷгҖӮ
DoSж”»ж’ғгҒӘгҒ©гҒ®гӮөгӮӨгғҗгғјж”»ж’ғгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжҘӯеӢҷгҒҢеҰЁе®ігҒ•гӮҢгҒҹе ҙеҗҲгҖҒжі•зҡ„гҒӘеҜҫеҝңгҒ«еҠ гҒҲгҖҒITжҠҖиЎ“гҒЁжі•еҫӢгҒ®дёЎж–№гҒ«зІҫйҖҡгҒ—гҒҹе°Ӯй–Җ家гҒ«гӮҲгӮӢйҒ©еҲҮгҒӘеҜҫеҝңгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮ
еҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒҜгҖҒжі•еҫӢгҒЁITжҠҖиЎ“гҒ«зІҫйҖҡгҒ—гҒҹејҒиӯ·еЈ«гҒЁITгӮігғігӮөгғ«гӮҝгғігғҲгҒ®гғҒгғјгғ гҒ«гӮҲгӮӢгғҲгғјгӮҝгғ«гӮҪгғӘгғҘгғјгӮ·гғ§гғігӮ’гҒ”жҸҗдҫӣгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮдёӢиЁҳиЁҳдәӢгҒ«гҒҰи©ізҙ°гӮ’иЁҳијүгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғўгғҺгғӘгӮ№жі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒ®еҸ–жүұеҲҶйҮҺпјҡгӮөгӮӨгғҗгғјзҠҜзҪӘгҒ®еҲ‘дәӢе‘ҠиЁҙзӯү
гӮ«гғҶгӮҙгғӘгғј: ITгғ»гғҷгғігғҒгғЈгғјгҒ®дјҒжҘӯжі•еӢҷ
гӮҝгӮ°: DoSдёҚжӯЈгӮўгӮҜгӮ»гӮ№жҗҚе®іиі е„ҹи«ӢжұӮжҘӯеӢҷеҰЁе®ізҪӘ