ギリシャの会社法が定める非公開企業(AE)のコーポレートガバナンス

ギリシャの非公開企業形態であるSociétés Anonymes(以下、AE)に適用されるコーポレートガバナンスの法制、特にその根幹をなす法律4548/2018は、およそ1世紀にわたり適用されてきた旧法を全面的に刷新するもので、ガバナンスの柔軟性、透明性、そして効率性の向上を目指した画期的な改革でした。日本の会社法とは異なる取締役会構造や、強化された少数株主保護の規定など、日本企業が特に注目すべき点を、具体的な法令を根拠に詳述します。
この法律4548/2018は、長らく使用されてきた旧法(法律2190/1920)が現代のビジネス環境と乖離していたため、起業家精神の育成と外国投資の誘致を目的として制定されました。この法改正により、AEの最低資本金が€60,000から€25,000に引き下げられるなど、会社設立が簡素化されました。また、すべてのAEに一段階(monistic)ボードシステムを義務付けている点も特徴的です。これは、取締役会が経営と監督の両方を担うもので、日本の二段階(dualistic)システムとは大きく異なります。さらに、日本の会社法よりも低い持株比率で少数株主が権利を行使できる規定が多数盛り込まれており、少数株主の保護が手厚くなっている点も注目すべきです。これらの変更は、よりビジネスフレンドリーな環境を創出し、透明性を高めるための重要なステップと言えるでしょう。
本記事では、ギリシャのコーポレートガバナンス法制、特にその根幹をなす法律4548/2018に焦点を当てて解説します。
なお、ギリシャの包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。
この記事の目次
ギリシャ企業法制の現代化とコーポレートガバナンス
法律4548/2018の制定背景と目的
ギリシャの会社法制は、1920年代に制定された旧法(法律2190/1920)が長らくその根幹をなしていました。しかし、この古い法制度は現代のビジネス環境や国際的なベストプラクティスから乖離し、過度な官僚主義と非効率性を生み出していました。こうした状況を背景に、法律4548/2018が2019年1月1日に施行されました。この法律の主要な目的は、よりシンプルでビジネスフレンドリーな法的環境を創出し、起業家精神を育み、外国からの投資を呼び込むことにあります。
この法律の制定は、欧州連合(EU)の複数の指令、特にEU指令2017/828(通称SRD II)を国内法に反映させるものであり、取締役の報酬や関連当事者取引など、コーポレートガバナンスに関する規定を大幅に刷新しました。このことは、ギリシャが自国の法制度をEU基準に統一しようとする強い意思から来ていると言えるでしょう。
非公開企業AEへの適用と柔軟性の向上
法律4548/2018は、その適用範囲を上場企業か否かにかかわらず、すべてのAEに統一的に定めています。これにより、非公開企業も現代的なガバナンスの枠組みに従うことが求められます。この法律が導入した柔軟性の例として、以下の点が挙げられます。
- 会社設立の簡素化:定款が法定の最低限の要素のみを含む場合、公証人認証を必要としない私的文書での設立が可能になりました。これは日本の発起設立に似ていますが、より手続き的な柔軟性を提供していると言えます。
- 最低資本金の引き下げ:以前の法律では最低€60,000だったAEの最低資本金が、新法により€25,000に引き下げられました。これは日本の株式会社の最低資本金が1円からとなったこと(会社法改正)に類似しており、起業を促進する共通の意図が見て取れます。
- 無期限存続の許可:以前は一定期間の存続期間を設定する必要がありましたが、新法により無期限の存続が可能となりました。
これらの変更は、単なる手続きの簡素化に留まらず、ギリシャが外国からの直接投資を積極的に誘致し、特に中小規模のビジネスを振興しようとする国家戦略の表れであると捉えられます。法律の目的が「ビジネスフレンドリーな環境の創出」と明記されていることからも、この方向性が明確に読み取れます。日本の企業が子会社を設立する際に、これらの簡素化されたプロセスは大きなメリットとなるでしょう。
取締役会に関するギリシャ法と日本法の相違点

一段階(モノスティック)ボードの原則
ギリシャのAEは、経営の実行と監督を単一の機関である取締役会(Board of Directors, 以下BoD)が担う一段階(monistic)ボードシステムを採用しています。これは、経営を担う取締役会と、その監督を担う監査役会や監査等委員会を明確に分離する日本の二段階(dualistic)システムとは根本的に異なる点です。この一段階ボードは、日常業務を執行する執行取締役(Executive Director)と、独立した視点から監督機能を果たす非執行取締役(Non-Executive Director)で構成されます。
取締役会は最低3名(上場企業でない小規模・超小規模企業では1名も可能)から、最大15名で構成されます。取締役は株主総会で選任され、その2/5までは株主の指名により直接選任される可能性があります。この一段階ボードは、経営判断と監督が同じテーブルで行われるため、情報伝達が迅速で、非執行取締役の業務への直接的な関与度が高まるという利点があります。しかし、同時に経営と監督の役割が曖昧になり、「お手盛り」のリスクを高める可能性もはらんでいます。このため、非執行取締役の独立性の確保が特に重要視されており、特定の要件を満たすことが求められます。日本の親会社から派遣された取締役が子会社の取締役会に加わる場合、この「執行」と「監督」の境界線が曖昧になることへの理解と、独立性に対する意識を常に持つ必要があります。これは日本企業のガバナンス概念と根本的に異なるため、進出前の綿密な教育と理解が不可欠なポイントとなります。
取締役の義務と責任
法律4548/2018は、取締役が会社に対して負う「注意義務、忠実義務、勤勉義務」を明確に定めています。取締役の責任は、「慎重な実務家(prudent businessman)」の基準に基づいて判断されます。これは、日本の会社法における「善管注意義務(善良な管理者の注意義務)」とほぼ同義であり、類似した法的概念として捉えることができます。また、取締役の行為が「ビジネス・ジャッジメント・ルール」に適合する場合、責任を免除されることが明記されています。これは、日本の会社法における「経営判断の原則」に酷似しており、不確実な経営判断による失敗に対して、一定の範囲で取締役を保護する共通の考え方があることがわかります。
取締役は会社に対して損害賠償責任を負いますが、その責任は原則として会社に対して負うものであり、株主や第三者に対して直接負うものではありません。ただし、法律の強制規定や禁止規定に違反した場合は、第三者への賠償請求も可能となります。取締役の責任追及は、株主総会が決定した行動に基づく場合や、善意で十分な情報に基づいて行われた合理的な経営判断に基づく場合には、責任を負わないと推定されます。
ギリシャにおける株主総会の権限と少数株主保護の拡充
最高意思決定機関としての株主総会
ギリシャの会社法において、株主総会は会社の最高意思決定機関です。株主総会は、定款の変更、資本金の増減、取締役の選任・解任、財務諸表の承認、利益の配分といった会社の根幹に関わる事項について、唯一の決定権を有します。法律4548/2018は、遠隔通信手段(テレビ会議など)による株主総会開催を可能にするなど、手続きの柔軟性を高めています。これは、日本の会社法でも同様の動きが見られるため、日本の読者にとっては比較的理解しやすいでしょう。
少数株主権
新法は、各株式に付与される基本的な権利(株主総会への参加権、議決権、配当受領権など)とは別に、少数株主に対し、議決権割合に応じた具体的な権利を付与しています。以下に主要な権利と行使要件を列挙します。
- 情報請求権:総議決権の1/10を保有する株主は、取締役会に対し、会社の業務の進捗や資産に関する情報の提供を請求できます。これは旧法の1/5から引き下げられた要件であり、より多くの株主が経営情報を入手しやすくなりました。
- 株主総会招集請求権:5%以上の議決権を保有する株主は、臨時株主総会の招集を請求できます。
- 議題提案権:5%以上の議決権を保有する株主は、株主総会の議題に追加する権利を有します。
これらの権利の要件は、日本の制度と比較すると、数値上はさほど低くないように見えるかもしれません。しかし、日本の会社法には類似の制度が存在しない、ギリシャ法特有の二つの権利が、少数株主の権限を強化しています。
監査請求権(司法監査)
総議決権の1/5(20%)を保有する株主は、裁判所(Single-Member Court of First Instance)の命令により会社監査を請求する権利を有します。この権利は、経営が公正なルールに沿って行われていないと信じるに足る理由がある場合に発動されるものです。
重要な点として、新法では行政機関による監査請求権が廃止されましたが、少数株主が裁判所を通じて監査を請求する権利は存続しています。これは、従来の「官僚的」な監督から、より「司法的」な監督へと権限が移行したことを示唆しています。この司法監査は、単なる情報提供請求とは異なり、裁判所の強制力と専門家(監査人)の関与を伴うため、経営陣にとって極めて強力な管理監督手段となり、経営の透明性を強制する手段となり得ます。この「司法の力を借りる」という点が、日本法にはない、ギリシャ法の「強さ」の核心です。
株式買取請求権(Put Option)
支配株主が会社の株式の95%以上を保有している場合、5%以下の少数株主は、その持分を支配株主に買い取らせることを請求する権利を有します。これは、日本の会社法には存在しない、少数株主の「出口戦略」を保障する制度です。
この権利の背景には、5%以下の少数株主は、会計帳簿閲覧や総会招集といった一般的な権利を行使する要件を満たせないため、法的な保護が「極めて限定的」であるという認識があります。この「極端なリスク」を相殺するための、少数株主に与えられた強力な「カード」として、この買収請求権が存在します。この権利は、支配株主にとって、予期せぬタイミングで高額な買収価格を迫られるリスクとなり、特に非公開会社では、価格評価をめぐって紛争が生じやすく、円滑な経営を妨げる可能性を秘めています。
ギリシャ企業の内部統制と関連当事者取引の規律
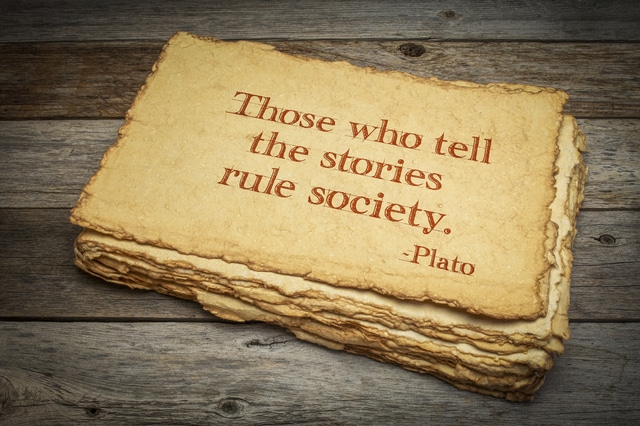
内部統制システムの構築と監督
法律4548/2018は、取締役会に会社の内部統制システム(Internal Control System)の有効性を確保する責任を明確に課しています。上場企業では、監査委員会、報酬委員会、候補者指名委員会の設置が法律により義務化されています。非公開企業にはこれらの義務はありませんが、健全なガバナンスのために同様のベストプラクティスを自主的に導入する余地があります。特に、監査委員会は、財務報告の完全性、内部統制の有効性、リスク管理などを監督する重要な役割を担います。
関連当事者取引(RPT)の承認プロセス
法律4548/2018は、関連当事者取引に関する規制を全面的に見直しました。国際的な金融スキャンダルを教訓に、関連当事者取引における利益相反のリスクが注目され、規制が強化されたものです。法律4548/2018では、取引を類型化するのではなく、統一的な規律を設けることで、より包括的な対応を目指しています。
非公開企業における関連当事者取引は、通常、取締役会および株主の承認が必要です。この承認プロセスは、特に透明性を確保するために重要視されています。日本の会社法における利益相反取引(競業避止義務、利益相反取引の承認)の概念と同様に、ギリシャでも取締役が個人的な利益を追求することなく、会社の利益を最優先に行動することが求められます。重要な相違点は、ギリシャの法制度が関連当事者取引に対してより具体的な承認プロセスや開示を求めている点です。日本企業のギリシャ子会社において、親会社との取引を行う際には、事前にギリシャ法に準拠した詳細な承認手続きを踏む必要があることを理解しておく必要があります。
まとめ
法律4548/2018は、ギリシャのコーポレートガバナンスに、柔軟性、効率性、そして国際的な透明性をもたらす重要な改革でした。この法改正は、約100年間続いた旧法を刷新し、特に会社設立手続きの簡素化や最低資本金の引き下げなど、ビジネス環境の改善を目的としています。
日本の会社法と比較すると、ギリシャのAEに適用される一段階(モノスティック)ボードシステムは、経営と監督の機能が一体となっている点で大きな違いがあります。また、少数株主の権利保護が非常に手厚く、株主総会の招集請求権など、日本法よりも低い持株比率で行使できる権利があることにも注目すべきです。これらの制度は、日本の親会社がギリシャで事業を展開する際に、現地の少数株主との関係を慎重に構築する必要があることを示唆しています。
関連当事者取引については、利益相反を防ぐための透明性の高い承認プロセスが求められます。この点は、親会社と子会社間の取引において、日本企業が特に留意すべき重要なポイントです。
これらの法制度の特性を深く理解することは、ギリシャでのビジネス展開における予期せぬリスクを回避し、円滑な事業運営を実現するために不可欠です。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務


































