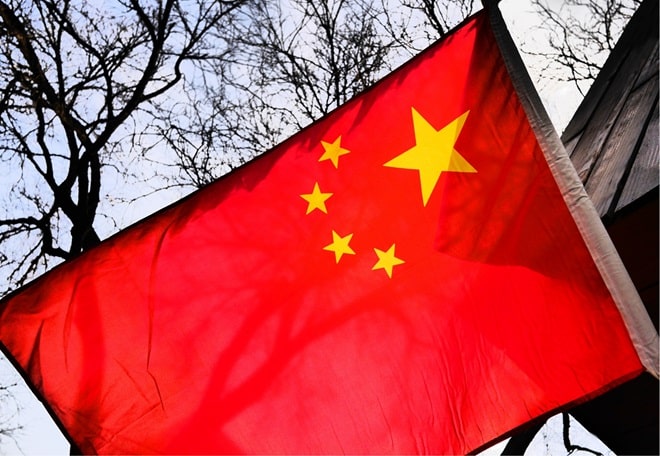ドイツの不動産関連の法制度を弁護士が解説

ドイツの不動産法制は、日本が採用する法体系とは根本的に異なる思想に基づいて構築されています。特に、日本の民法が土地と建物を独立した不動産として扱うのに対し、ドイツ民法(BGB)は「土地と建物の一体性の原則」を基本とし、建物は原則として土地の構成部分とされます。この物権法の基礎的な違いが、担保設定や権利移転の構造に決定的な影響を与えます。
さらに、ドイツの不動産取引は、公的記録の信頼性を極めて重視しており、土地登記簿(Grundbuch)に高い「公信力」(Öffentlicher Glaube)が付与されています。これにより、登記を信頼して取引を行った善意の第三者は強力に保護されます。そして、この高い取引安全性を実現する上で不可欠な存在が、厳格な職務上の義務を負う公証人(Notar)です。
ドイツにおける不動産取引の仕組みは、これらの三つの要素、「一体性の原則」、「登記の公信力」、そして「公証人による公正証書の義務付け」によって支えられており、これにより日本の取引よりも簡潔かつ安全に進められる基盤が形成されています。
本稿では、これらの構造的な違いに焦点を当て、関連する法令(BGB、BNotOなど)に基づいた詳細な解説を提供します。
この記事の目次
ドイツ不動産法の「一体性の原則」
土地・建物の法的不可分性と構成部分(Wesentliche Bestandteile)
ドイツの不動産法(物権法)の根幹をなすのは、土地だけが独立した不動産(物権の対象)であるという原則です。日本の民法においては、土地と建物はそれぞれ独立した不動産として扱われ、別個に所有権が設定され、個別に登記が可能であるため、土地と建物の所有者が異なることも一般的です。
これに対し、ドイツ民法典(BGB)第94条(Wesentliche Bestandteile eines Grundstücks oder Gebäudes – 土地または建物の本質的構成部分)は、土地に固定的に結合された物、特に建物を、土地の本質的構成部分(wesentliche Bestandteile)と定めています。本質的構成部分は、原則として主物(土地)と分離して権利を設定することができません(BGB第93条の規定による)。
この一体性の原則により、建物は土地に付随するものとなり、建物単独で所有権や抵当権を設定することは原則として不可能です。土地の所有権が移転すれば、建物も自動的に土地とともにその所有権が移転することになります。この概念的な違いは、不動産を担保として用いる際に大きな影響を及ぼします。例えば、日本法では、土地だけに抵当権を設定し、建物には設定しないという選択肢が存在しますが、ドイツ法においてはBGB第94条に基づき、土地に設定された抵当権は、例外的な権利が設定されていない限り、自動的に建物全体に効力が及びます。したがって、担保価値の評価やリスク計算は、土地と建物を物理的・法的に切り離せない「一体の財産」として行う必要があり、日本の「土地・建物分離」を前提とした従来の担保戦略は適用できません。
一体原則からの例外としての永代借地権(Erbbaurecht)
一体性の原則が厳格に適用されるドイツ法制において、土地所有権と建物所有権を分離させるための主要な例外として、永代借地権(Erbbaurecht)があります。
永代借地権は、他人の土地の上に建物を所有する権利を目的とした物権であり、土地の所有権とは切り離され、独立した不動産と同様に扱われます。この権利は、永代借地権登記簿(Erbbaugrundbuch)と呼ばれる専用の登記簿に登記され、永代借地権者は建物所有者として、土地所有者とは独立した権利を行使できます。
この制度は、日本の借地権(賃借権や地上権)、特に事業用定期借地権と機能的に類似しています。しかし、その法的性質が大きく異なります。日本法における借地権は土地と建物の独立性を前提とするのに対し、ドイツの永代借地権は、本来一体であるはずの権利を、物権として分離し安定的なものとするために創設されたものであり、その法的安定性や担保能力は極めて高いものとなります。この永代借地権の存在は、ドイツの都市開発や経済活動において、一体性の原則を維持しつつ柔軟な土地利用を可能にする重要な法的ツールとなっています。
公信力を持つドイツの土地登記簿(Grundbuch)
登記の公信力(Öffentlicher Glaube)の定義と善意取得(BGB第892条)
ドイツの不動産取引の確実性と信頼性を飛躍的に向上させているのが、土地登記簿(Grundbuch)が有する「公信力」(Öffentlicher Glaube)の原則です。この原則は、公的な記録の信頼性を優先するという法哲学を反映しています。
公信力は、主に以下の二つの原則から成り立っています。
- 登記簿の推定力(Grundbuchvermutung):登記簿に記載されている権利は存在し、削除された権利は存在しないと推定されます(BGB第891条)。
- 善意取得の保護:登記簿の内容は、法的取引において正確かつ完全であると見なされます。
このうち、BGB第892条が定める善意取得(gutgläubiger Erwerb)の制度は特に重要です。これは、登記簿に所有者として記載されている者(たとえ真実の権利者でなかったとしても)から権利を取得しようとした第三者が、その記載が真実でないことを知らなかった場合、善意の第三者として保護され、有効に権利を取得できるという原則です。
日本の不動産登記制度が「対抗力主義」であり、登記は第三者に権利を主張するための要件に過ぎず、登記簿の記載の公信力は原則として認められていないのに対し、ドイツの公信力制度は、取引の安全性を保証する上で決定的な違いをもたらします。日本においては、登記簿を信頼して取引した善意の第三者であっても、真実の権利者から権利を奪うことは原則としてできません。しかし、ドイツにおいては、公的記録である登記簿の信頼性が法律によって担保されているため、取引の初期段階での法的リスクが大幅に軽減されます。これにより、買主は登記簿の内容に集中して調査(デューデリジェンス)を行うことができ、取引の確実性が高まり、流動性も向上します。
ドイツにおける不動産取引の安全を担保する公証人(Notar)

公正証書作成の義務と予防司法(Präventive Rechtspflege)
ドイツの不動産売買契約は、その成立のために公証人(Notar)による公正証書の作成が法律(BGB第311b条1項、公正証書法(BeurkG)第17条2項)により厳格に義務付けられています。
公証人は、中立的かつ独立した公職者であり、紛争を未然に防ぐための予防司法(präventive Rechtspflege)の役割を担っています。公証人の職務は、単に署名を認証することに留まりません。当事者間の知識や立場の不均衡を是正し、予期せぬリスクを排除することが、公証人制度の核心です。公証人は、売主と買主の双方が契約内容とその法的帰結を完全に理解していることを確認し、その真意を法的に有効な形式で文書化する義務を負います。
当事者の真意確認と指導・説明義務(Belehrungspflicht)
公証人には、当事者の真意を詳細に調査し(Willenserforschung)、取引の法的含意について十分な指導・説明(Belehrungspflicht)を行う義務が課されています。特に法的に未熟な当事者が不利益を被らないよう配慮しなければなりません。
指導義務の中でも特に重要なのが、不動産取引でしばしば問題となる「無防備な先行給付」(ungesicherte Vorleistung)に対する二重の指導義務(Doppelte Belehrungspflicht)です。例えば、買主が所有権移転登記前に代金を支払う場合など、一方の当事者が担保なしで履行を行う構造が生じた場合、公証人は、そのリスク(例:相手方の履行不能)を詳細に説明し、さらに、手付金口座(Notaranderkonto)の利用など、リスクを回避するための代替的な契約構造を提案しなければなりません。
公証人による厳格な指導義務が果たされることにより、ドイツの不動産契約は、日本の私人間契約に比べ、内容の瑕疵や契約無効となるリスクが極めて低くなります。これは、公証人制度が契約の形式的要件だけでなく、実質的な当事者の意思の公平性まで公的に担保する機能を有しているからです。
物権的合意(Auflassung)と引渡予告登記(Vormerkung)
ドイツの不動産所有権の移転は、債権契約(売買契約)とは別に、物権的合意(Auflassung)と登記が必要となるという、ドイツ私法の基本原則である「抽象性・分離原則」(Trennungs- und Abstraktionsprinzip)に基づいています。
物権的合意(Auflassung)とは、土地所有権の移転に関する売主と買主の合意のことであり、公証人の面前でなされなければなりません(BGB第925条)。この合意は、日本の所有権移転の意思表示とは異なり、無条件かつ無期限でなければならないという厳格な要件があります(BGB第925条2項)。日本民法が意思表示だけで所有権が移転する意思主義を採用しているのに対し、ドイツでの取引では、この「契約と物権移転は別個の行為である」という意識が取引のプロセスと完了時期の理解に不可欠です。
さらに、売買契約後、最終的な所有権移転登記が完了するまでの間に、買主の権利を保全するために、引渡予告登記(Auflassungsvormerkung)が登記簿に設定されます(BGB第883条)。この予告登記がなされると、その後になされた売主の処分(二重譲渡や新たな抵当権設定など)は、予告登記によって保護された買主に対して効力を持たないとされています(BGB第883条2項)。これにより、買主は登記完了を待つ間も強力に保護され、取引の確実性が担保されます。
ドイツ公証人の責任(Notarhaftung)と最新判例法理
公証人の損害賠償責任の原則と補充性(BNotO第19条)
公証人は、その厳格な職務の対価として、公的な責任を負います。公証人が故意または過失により職務上の義務(Amtspflicht)を怠り、当事者に損害を与えた場合、公証人は損害賠償責任を負うことになります(連邦公証人法 BNotO第19条1項)。責任の判断基準は、経験豊かで義務感のある、良心的な平均的な公証人の注意義務(Durchschnittsnotar)に照らして判断されます。
公証人の責任において、日本人が最も理解しておくべき特殊な要件は、責任の補充性(Subsidiäre Haftung)です。公証人は、被害者が「他のいかなる方法によっても賠償を得ることができない」場合にのみ、損害賠償義務を負います(BNotO第19条1項)。
「他の賠償を得る方法」には、契約相手方に対する請求のほか、取引に関与した弁護士に対する賠償請求なども含まれます。被害者は、これらの代替手段が法的および経済的に成功の見込みがないこと、例えば、相手方が破産している、または訴訟に勝つ見込みがないことを立証しなければなりません。この補充的責任の構造は、公証人の公的な役割を尊重しつつ、究極的な取引の安全を国家が保証するという考え方に基づいています。
最新判例に見る公証人の指導義務と監督範囲の限界
公証人の義務の具体的な範囲に関わる連邦最高裁判所(BGH)の判例は複数存在し、近年においても、公証人の責任範囲を明確化する判決が出ています。
まず、BGH 2025年5月8日付 判決(Az. III ZR 398/23)では、公証人が、当事者に対してどれほどの範囲で、契約の実行を監視する独立的かつ自己的な監督義務(selbständige Betreuungspflichten)を負うかという点が争われました。事案は、土地開発事業に関わる共同事業体のメンバーが、公証人が作成した契約書に付随する代理権の行使をめぐり、公証人に対する損害賠償を請求したものです。
BGHは、公証人が自己的な監督義務を負うかどうかは、個別の状況に基づいて判断されるとしました。特に、代理権の行使を「公証人の面前でのみ行う」という合意があったとしても、それだけで、公証人が代理権の内部的な制限(当事者間の私的な取り決め)を監視する包括的な監督委託を引き受けたことには直ちにならない、と判断しました。
この判決から言えることは、公証人の業務は主に公的に文書化された内容に基づくものであり、当事者間の内部的な秘密の取り決めまで監視させるためには、契約書においてその監督業務を明確に委託し、公証人に受諾させる必要があるということです。日本の企業がドイツで代理権や信託的な契約構造を用いる際には、公証人に期待する具体的な業務範囲を明確に定義することが極めて重要となります。
次に、BGH 2025年4月24日付 決定(Az. III ZR 18/24)では、不動産取引の実行段階における公証人の重要な職務が再確認されました。BGHは、公証人には、買主の権利を保全するための引渡予告登記(Auflassungsvormerkung)が、後順位で設定され、かつ買主が承継しない負担(Belastungen)より先に抹消されないよう、確実な措置を講じる義務がある、と判断しました。
この判例は、公証人が取引の実行(Vollzug)段階において、買主の物権的保全を確実にするための具体的な職務を怠った場合の責任の厳しさを明確にするものであり、公証人のミスが買主の権利の喪失に直結するリスクがあることを示しています。
まとめ
ドイツと日本とでは、不動産関連の法制度に、構造的な違いがあります。この相違点があるが故に、ドイツにおけるビジネス展開においては、リスクアセスメントとデューデリジェンスの焦点を変更することが必要です。日本の民法は、意思表示だけで所有権が移転する意思主義(Konsensprinzip)を採用しているため、ドイツでの取引には、契約と物権移転が別個の行為であるという「抽象性・分離原則」の意識が不可欠となります。同時に、ドイツ法制は、登記の公信力と公証人の厳格な指導義務により、公的記録と公的介入を通じて取引の確実性を極限まで高めていると言えるでしょう。
| ドイツ(BGB) | 日本(民法) | |
|---|---|---|
| 土地と建物の関係 | 一体性の原則。建物は土地の「本質的構成部分」(BGB § 94)。 | 独立不動産の原則。土地と建物は別個の所有権の対象。 |
| 物権変動の原則 | 抽象性・分離原則。債権契約(原因行為)と物権行為(Auflassung)は別個。 | 意思主義・対抗要件主義。意思表示により所有権移転(原則)。 |
| 例外的に分離される権利 | 永代借地権(Erbbaurecht)として独立した物権を設定。 | 借地権(賃借権、地上権)を設定。建物は独立した物。 |
| ドイツ(Grundbuch) | 日本(不動産登記) | |
|---|---|---|
| 基本原則 | 公信力(Öffentlicher Glaube)。 | 対抗力。 |
| 登記を信頼した善意の第三者の保護 | 積極的に保護され、有効に権利を取得できる(善意取得)。 | 原則として保護されず、真実の権利者に権利を対抗できない。 |
| 取引の担保構造 | 公証人による契約の公正証書化と実行監督。 | 登記のみ、または私的エスクローサービス。 |
ドイツの不動産法制は、「土地と建物の法的不可分性」(BGB第94条)、「土地登記簿の公信力」(BGB第892条)、そして「公証人による公正証書作成の義務と厳格な職務責任」(BNotO第19条)という三つの強固な柱によって成り立っています。
特に、善意取得を可能にする公信力は、公的記録の信頼性を確保することで取引の流動性と安全性を担保し、公証人は、契約内容の法的有効性と当事者の真意の確認という予防司法の役割を担い、取引の実行プロセス全体の安全を確保しています。日本の経営者および法務部員の皆様がドイツでの不動産取引に臨む際には、この構造的な違いを深く理解し、公証人を単なる形式的な手続きの代行者ではなく、取引安全の要として認識することが成功の鍵となります。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務