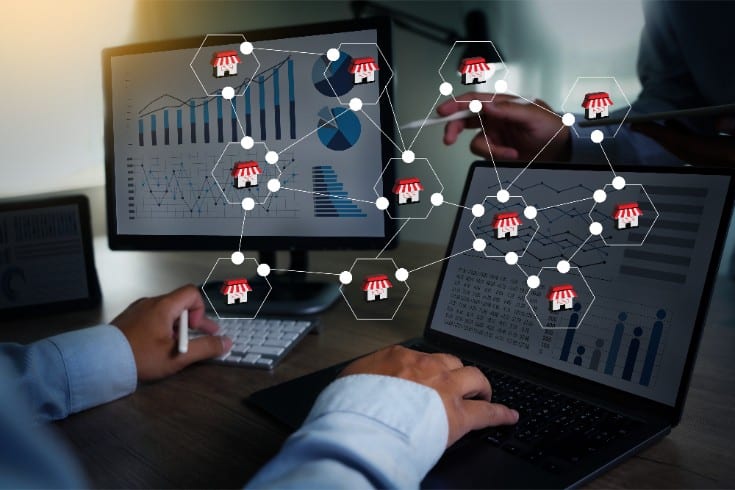еҸ°ж№ҫгҒ®дјҡзӨҫжі•гҒҢе®ҡгӮҒгӮӢдјҡзӨҫгҒ®еҪўж…ӢгҒЁдјҡзӨҫиЁӯз«Ӣ

еҸ°ж№ҫеёӮе ҙгҒҜгҖҒж–ҮеҢ–зҡ„гҒӘиҰӘе’ҢжҖ§гӮ„ең°зҗҶзҡ„иҝ‘жҺҘжҖ§гҒӢгӮүгҖҒж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰдәӢжҘӯеұ•й–ӢгҒ®жңүеҠӣгҒӘйҒёжҠһиӮўгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ®жҲҗеҠҹгҒ«гҒҜзҸҫең°гҒ®жі•еҲ¶еәҰгҖҒзү№гҒ«дјҡзӨҫжі•гҒ«й–ўгҒҷгӮӢж·ұгҒ„зҗҶи§ЈгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮ
жң¬иЁҳдәӢгҒҜгҖҒеҸ°ж№ҫгҒ®дјҡзӨҫгҒ®еҪўж…ӢгҒЁиЁӯз«Ӣгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒЁгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘз•°еҗҢзӮ№гӮ’дёӯеҝғгҒ«и©ізҙ°гҒ«и§ЈиӘ¬гҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒеӨ–еӣҪдјҒжҘӯгҒ®зҸҫең°жі•дәәиЁӯз«ӢгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰжңҖгӮӮдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘгҖҢиӮЎд»Ҫжңүйҷҗе…¬еҸёпјҲж—Ҙжң¬гҒ®ж ӘејҸдјҡзӨҫгҒ«зӣёеҪ“пјүгҖҚгҒ«з„ҰзӮ№гӮ’еҪ“гҒҰгҖҒ2018е№ҙгҒ®дјҡзӨҫжі•ж”№жӯЈгҒҢгӮӮгҒҹгӮүгҒ—гҒҹж©ҹй–ўиЁӯиЁҲгҒ®жҹ”и»ҹжҖ§гҒЁгҒ„гҒҶгҖҒж—Ҙжң¬жі•гҒЁгҒ®жұәе®ҡзҡ„гҒӘйҒ•гҒ„гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰж·ұгҒҸжҺҳгӮҠдёӢгҒ’гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒеҸ°ж№ҫгҒ®еҢ…жӢ¬зҡ„гҒӘжі•еҲ¶еәҰгҒ®жҰӮиҰҒгҒҜдёӢиЁҳиЁҳдәӢгҒ«гҒҰгҒҫгҒЁгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®зӣ®ж¬Ў
еҸ°ж№ҫдјҡзӨҫжі•гҒ®еҹәжң¬пјҡ4гҒӨгҒ®дјҡзӨҫеҪўж…ӢгҒЁгҒқгҒ®йҒёжҠһиӮў
еҸ°ж№ҫгҒ®дјҡзӨҫжі•пјҲе…¬еҸёжі•пјүгҒҜгҖҒдәӢжҘӯйҒӢе–¶гӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒҷгӮӢзӨҫеӣЈжі•дәәгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒдјҡзӨҫгӮ’д»ҘдёӢгҒ®4зЁ®йЎһгҒ«еҲҶйЎһгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®дјҡзӨҫжі•гҒҢе®ҡгӮҒгӮӢгҖҢж ӘејҸдјҡзӨҫгҖҚгҖҢеҗҲеҗҢдјҡзӨҫгҖҚгҖҢеҗҲеҗҚдјҡзӨҫгҖҚгҖҢеҗҲиіҮдјҡзӨҫгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҲҶйЎһгҒЁйЎһдјјгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®еҪўж…ӢгҒҢжҢҒгҒӨжі•зҡ„жҖ§иіӘгҒЁиІ¬д»»зҜ„еӣІгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҢәеҲҘгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
з„Ўйҷҗе…¬еҸёпјҲUnlimited CompanyпјүгҒЁдёЎеҗҲе…¬еҸёпјҲLimited Partnershipпјү
з„Ўйҷҗе…¬еҸёгҒҜдәҢдәәд»ҘдёҠгҒ®ж Әдё»гҒҢзө„з№”гҒ—гҖҒдјҡзӨҫгҒ®еӮөеӢҷгҒ«еҜҫгҒ—йҖЈеёҜгҒ—гҒҰз„ЎйҷҗиІ¬д»»гӮ’иІ гҒҶеҪўж…ӢгҒ§гҒҷгҖӮеҗҢж§ҳгҒ«гҖҒдёЎеҗҲе…¬еҸёгӮӮдёҖдәәд»ҘдёҠгҒ®з„ЎйҷҗиІ¬д»»ж Әдё»гҒЁгҖҒдёҖдәәд»ҘдёҠгҒ®жңүйҷҗиІ¬д»»ж Әдё»гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзө„з№”гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮз„ЎйҷҗиІ¬д»»гҒЁгҒҜгҖҒдјҡзӨҫгҒ®еӮөеӢҷгҒҢеҖӢдәәиіҮз”ЈгҒ«гҒҫгҒ§еҸҠгҒ¶гҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®еҪўж…ӢгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҗҲеҗҚдјҡзӨҫгӮ„еҗҲиіҮдјҡзӨҫгҒ«зӣёеҪ“гҒҷгӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒзҸҫд»ЈгҒ®е®ҹеӢҷгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©жҺЎз”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮеӨ–еӣҪдјҒжҘӯгҒҢзҸҫең°жі•дәәгӮ’иЁӯз«ӢгҒҷгӮӢжңҖеӨ§гҒ®зӣ®зҡ„гҒҜгҖҒжң¬еӣҪгҒ®иҰӘдјҡзӨҫгӮ„жҠ•иіҮ家гҒ®иІ¬д»»гӮ’йҷҗе®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮз„ЎйҷҗиІ¬д»»гӮ’дјҙгҒҶгҒ“гӮҢгӮүгҒ®дјҡзӨҫеҪўж…ӢгҒҜгҖҒгҒқгҒ®зӣ®зҡ„гҒЁж №жң¬зҡ„гҒ«зҹӣзӣҫгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒжі•еҫӢдёҠгҒҜеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒеӨ–еӣҪдјҒжҘӯгҒҢйҒёжҠһгҒҷгӮӢе®ҹз”Ёзҡ„гҒӘйҒёжҠһиӮўгҒЁгҒҜиЁҖгҒҲгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
жңүйҷҗе…¬еҸёпјҲLimited Companyпјү
жңүйҷҗе…¬еҸёгҒҜгҖҒдёҖдәәд»ҘдёҠгҒ®ж Әдё»гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзө„з№”гҒ•гӮҢгӮӢдјҡзӨҫеҪўж…ӢгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒж Әдё»гҒҜгҒқгҒ®еҮәиіҮйЎҚгӮ’йҷҗеәҰгҒЁгҒ—гҒҰдјҡзӨҫгҒ«еҜҫгҒ—иІ¬д»»гӮ’иІ гҒҶгҖҒжңүйҷҗиІ¬д»»гҒ®дјҡзӨҫгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҪўж…ӢгҒҜгҖҒзү№гҒ«дёӯе°ҸдјҒжҘӯгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰеәғгҒҸжҺЎз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзөҢе–¶ж©ҹй–ўгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒ1еҗҚгҒӢгӮү3еҗҚгҒ®и‘ЈдәӢпјҲеҸ–з· еҪ№пјүгӮ’иЁӯзҪ®гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®и‘ЈдәӢгҒҜеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰж Әдё»гҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮж„ҸжҖқжұәе®ҡгҒҜгҖҒи‘ЈдәӢдјҡпјҲеҸ–з· еҪ№дјҡпјүгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒж Әдё»е…Ёе“ЎгҒ®зӣҙжҺҘзҡ„гҒӘжұәиӯ°гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиЎҢгӮҸгӮҢгӮӢзӮ№гҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҗҲеҗҢдјҡзӨҫгҒ«йЎһдјјгҒ—гҒҹзөұжІ»ж§ӢйҖ гҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
иӮЎд»Ҫжңүйҷҗе…¬еҸёпјҲCompany Limited by Sharesпјү
иӮЎд»Ҫжңүйҷҗе…¬еҸёгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®гҖҢж ӘејҸдјҡзӨҫгҖҚгҒ«жңҖгӮӮиҝ‘гҒ„еҪўж…ӢгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®ж ёеҝғзҡ„гҒӘзү№еҫҙгҒҜгҖҒиіҮжң¬гҒҢиӮЎд»ҪпјҲж ӘејҸпјүгҒ«еҲҶеүІгҒ•гӮҢгҖҒж ӘејҸгӮ’зҷәиЎҢгҒ—гҒҰиіҮйҮ‘гӮ’иӘҝйҒ”гҒ§гҒҚгӮӢзӮ№гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮж Әдё»гҒ®иІ¬д»»гҒҜгҖҒдҝқжңүгҒҷгӮӢж ӘејҸгҒ®йҷҗеәҰеҶ…гҒ«йҷҗе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢжңүйҷҗиІ¬д»»гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеӨ§иҰҸжЁЎгҒӘдәӢжҘӯгӮ„е°ҶжқҘзҡ„гҒӘж ӘејҸе…¬й–ӢпјҲдёҠе ҙпјүгӮ’иҰ–йҮҺгҒ«е…ҘгӮҢгҒҹдјҒжҘӯгҒ«йҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҪўж…ӢгҒҜгҖҒдәҢдәәд»ҘдёҠгҒ®ж Әдё»гҖҒгҒҫгҒҹгҒҜж”ҝеәңгӮ„жі•дәәж Әдё»дёҖдәәгҒҢзө„з№”гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§иЁӯз«ӢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮжңҖдҪҺиіҮжң¬йҮ‘гҒҜNT$500,000пјҲзҙ„225дёҮеҶҶпјүгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еӨ–еӣҪдјҒжҘӯгҒҢзҸҫең°жі•дәәгӮ’иЁӯз«ӢгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гҒ“гҒ®еҪўж…ӢгҒҢдё»жөҒгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®иҰӘдјҡзӨҫгҒҢж…ЈгӮҢиҰӘгҒ—гӮ“гҒ зөұжІ»ж§ӢйҖ пјҲи‘ЈдәӢдјҡгӮ„зӣЈеҜҹдәәпјүгӮ’е°Һе…ҘгҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҖҒгӮ¬гғҗгғҠгғігӮ№гҒ®дҪ“еҲ¶гӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶеҲ©зӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒе°ҶжқҘзҡ„гҒ«дәӢжҘӯиҰҸжЁЎгӮ’жӢЎеӨ§гҒ—гҖҒж ӘејҸе…¬й–ӢгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰеӨҡйЎҚгҒ®иіҮйҮ‘гӮ’иӘҝйҒ”гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжҹ”и»ҹгҒӘйҒёжҠһиӮўгҒҢзўәдҝқгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҖҒжҲҰз•Ҙзҡ„гҒӘж„ҸжҖқжұәе®ҡгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰйҮҚиҰҒгҒӘиҰҒзҙ гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҗ„дјҡзӨҫеҪўж…ӢгҒ®зӣёйҒ•зӮ№
д»ҘдёӢгҒ«гҖҒеҸ°ж№ҫгҒ®дё»иҰҒгҒӘдјҡзӨҫеҪўж…ӢгӮ’з°ЎжҪ”гҒ«гҒҫгҒЁгӮҒгҒҫгҒҷгҖӮ
| иӮЎд»Ҫжңүйҷҗе…¬еҸё | жңүйҷҗе…¬еҸё | з„Ўйҷҗе…¬еҸё | дёЎеҗҲе…¬еҸё | |
|---|---|---|---|---|
| дјҡзӨҫеҪўж…ӢпјҲж—Ҙжң¬жі•пјү | ж ӘејҸдјҡзӨҫ | еҗҲеҗҢдјҡзӨҫ | еҗҲеҗҚдјҡзӨҫ | еҗҲиіҮдјҡзӨҫ |
| иІ¬д»»зҜ„еӣІ | жңүйҷҗиІ¬д»» | жңүйҷҗиІ¬д»» | з„ЎйҷҗиІ¬д»» | дёҖйғЁз„ЎйҷҗгҖҒдёҖйғЁжңүйҷҗ |
| иЁӯз«ӢгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘж Әдё»/еҮәиіҮиҖ…ж•° | 2еҗҚд»ҘдёҠпјҲжі•дәәж Әдё»1еҗҚгҒ§гӮӮеҸҜпјү | 1еҗҚд»ҘдёҠ | 2еҗҚд»ҘдёҠ | з„ЎйҷҗиІ¬д»»ж Әдё»1еҗҚд»ҘдёҠгҖҒжңүйҷҗиІ¬д»»ж Әдё»1еҗҚд»ҘдёҠ |
| жңҖдҪҺиіҮжң¬йҮ‘ | NT$500,000 | NT$1пјҲе®ҹеӢҷдёҠгҒҜгӮҲгӮҠеӨҡгҒҸпјү | гҒӘгҒ— | гҒӘгҒ— |
| дё»гҒӘз”ЁйҖ” | еӨ§иҰҸжЁЎдәӢжҘӯгҖҒж ӘејҸе…¬й–Ӣ | дёӯе°ҸдјҒжҘӯ | е°ҸиҰҸжЁЎдәӢжҘӯпјҲе®ҹеӢҷдёҠзЁҖпјү | е°‘ж•°зөҢе–¶иҖ…гҒ«гӮҲгӮӢйҒӢе–¶пјҲе®ҹеӢҷдёҠзЁҖпјү |
еҸ°ж№ҫгҒ®иӮЎд»Ҫжңүйҷҗе…¬еҸёгҒ®ж©ҹй–ўиЁӯиЁҲгҒЁж—Ҙжң¬жі•гҒЁгҒ®жҜ”ијғ
еҸ°ж№ҫгҒ®иӮЎд»Ҫжңүйҷҗе…¬еҸёгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®ж ӘејҸдјҡзӨҫгҒЁйЎһдјјгҒ®еҪўж…ӢгҒ§гҒӮгӮӢдёҖж–№гҖҒ2018е№ҙгҒ®дјҡзӨҫжі•ж”№жӯЈгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒж—Ҙжң¬гҒ«гҒҜгҒӘгҒ„зӢ¬иҮӘгҒ®жҹ”и»ҹгҒӘж©ҹй–ўиЁӯиЁҲгҒҢе°Һе…ҘгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
2018е№ҙдјҡзӨҫжі•ж”№жӯЈгҒ«гӮҲгӮӢж©ҹй–ўиЁӯиЁҲгҒ®жҹ”и»ҹжҖ§
ж”№жӯЈгҒ®жңҖгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘгғқгӮӨгғігғҲгҒҜгҖҒйқһе…¬й–ӢдјҡзӨҫгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒӢгҒӨеҚҳдёҖгҒ®жі•дәәж Әдё»гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзө„з№”гҒ•гӮҢгӮӢиӮЎд»Ҫжңүйҷҗе…¬еҸёгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒи‘ЈдәӢдјҡпјҲеҸ–з· еҪ№дјҡпјүгҒҠгӮҲгҒізӣЈеҜҹдәәпјҲзӣЈжҹ»еҪ№пјүгҒ®иЁӯзҪ®гҒҢдёҚиҰҒгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹзӮ№гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®е ҙеҗҲгҖҒи‘ЈдәӢпјҲеҸ–з· еҪ№пјүгҒҜ1еҗҚгҒҫгҒҹгҒҜ2еҗҚгҒ§и¶ігӮҠгҖҒи‘ЈдәӢдјҡгҒ®жЁ©йҷҗгҒҜеҚҳзӢ¬ж Әдё»гҒ§гҒӮгӮӢиҰӘдјҡзӨҫгҒҢиЎҢдҪҝгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзӣЈеҜҹдәәпјҲж—Ҙжң¬гҒ®зӣЈжҹ»еҪ№пјүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒе®ҡж¬ҫгҒ«е®ҡгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§иЁӯзҪ®гҒ—гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жҹ”и»ҹгҒӘиЁӯиЁҲгҒҜгҖҒзү№гҒ«ж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒ®еӯҗдјҡзӨҫгҒҢдәӢжҘӯйҒӢе–¶гӮ’еҗҲзҗҶеҢ–гҒҷгӮӢдёҠгҒ§еӨ§гҒҚгҒӘгғЎгғӘгғғгғҲгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬жі•гҒЁгҒ®жҜ”ијғ
ж—Ҙжң¬гҒ®дјҡзӨҫжі•гҒ§гҒҜгҖҒйқһе…¬й–ӢдјҡзӨҫпјҲж ӘејҸиӯІжёЎеҲ¶йҷҗдјҡзӨҫпјүгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒеҸ–з· еҪ№дјҡгӮ’иЁӯзҪ®гҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜеҸ–з· еҪ№3еҗҚгҖҒзӣЈжҹ»еҪ№1еҗҚгҒҢеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®е®ҹеӢҷгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒеҸ–з· еҪ№дјҡгӮ’иЁӯзҪ®гҒ—гҒӘгҒ„дјҡзӨҫеҪўж…ӢгӮ’йҒёжҠһгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒеҸ–з· еҪ№1еҗҚгҒ§дјҡзӨҫгӮ’иЁӯз«ӢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҖҒгҒ“гҒ®е ҙеҗҲгҒ«гҒҜзӣЈжҹ»еҪ№гҒ®иЁӯзҪ®зҫ©еӢҷгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ“гҒ®дәӢе®ҹгӮ’иёҸгҒҫгҒҲгӮӢгҒЁгҖҒеҸ°ж№ҫжі•гҒЁж—Ҙжң¬жі•гҒ®зңҹгҒ®йҒ•гҒ„гҒҜгҖҒгҖҢж ӘејҸдјҡзӨҫгҒ«зӣёеҪ“гҒҷгӮӢеҪўж…ӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжһ зө„гҒҝгҒ®дёӯгҒ§гҖҒеҸ–з· еҪ№дјҡгӮ„зӣЈжҹ»еҪ№гӮ’зҪ®гҒӢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮ’жҳҺзӨәзҡ„гҒ«иӘҚгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҒ«гҒӮгӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®еҲ¶еәҰгҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®жҹ”и»ҹжҖ§гҒҜгҖҢеҸ–з· еҪ№дјҡгӮ’иЁӯзҪ®гҒ—гҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶйҒёжҠһиӮўгҒ«д»ҳйҡҸгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҸ°ж№ҫжі•гҒҜгҖҒгӮҲгӮҠж—Ҙжң¬гҒ®иҰӘдјҡзӨҫгҒҢж…ЈгӮҢиҰӘгҒ—гӮ“гҒ гӮ¬гғҗгғҠгғігӮ№гҒ®жһ зө„гҒҝгӮ’з¶ӯжҢҒгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгӮӮгҖҒзө„з№”гӮ’з°Ўзҙ еҢ–гҒ—гҖҒж„ҸжҖқжұәе®ҡгҒ®иҝ…йҖҹеҢ–гӮ’еӣігӮӢгҒ“гҒЁгӮ’еҸҜиғҪгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒзөұжІ»ж§ӢйҖ гҒ«ж…ЈгӮҢиҰӘгҒ—гӮ“гҒ ж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒгӮ¬гғҗгғҠгғігӮ№гҒ®еҗҲзҗҶеҢ–гӮ’еҸҜиғҪгҒ«гҒҷгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘгғЎгғӘгғғгғҲгҒЁгҒӘгӮҠеҫ—гҒҫгҒҷгҖӮ
й–үйҺ–жҖ§иӮЎд»Ҫжңүйҷҗе…¬еҸёпјҲClosely Held Corporationпјү
еҸ°ж№ҫгҒ®дјҡзӨҫжі•гҒҜгҖҒгҒ•гӮүгҒ«е…ҲйҖІзҡ„гҒӘдјҡзӨҫеҪўж…ӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒ2015е№ҙгҒ«й–үйҺ–жҖ§иӮЎд»Ҫжңүйҷҗе…¬еҸёгӮ’е°Һе…ҘгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜж Әдё»ж•°гҒҢ50дәәд»ҘдёӢгҒ®йқһе…¬й–ӢдјҡзӨҫгӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҹгҖҒжҘөгӮҒгҒҰжҹ”и»ҹгҒӘеҲ¶еәҰгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®еҪўж…ӢгҒ®дё»гҒӘзү№еҫҙгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгҒҫгҒҡеҮәиіҮж–№жі•гҒ®еӨҡж§ҳеҢ–гҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮзҸҫйҮ‘гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒжҠҖиЎ“гҖҒеҠҙеӢҷгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜдҝЎз”ЁгҒ«гӮҲгӮӢеҮәиіҮгӮӮиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгӮ№гӮҝгғјгғҲгӮўгғғгғ—дјҒжҘӯгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰиіҮйҮ‘иӘҝйҒ”гҒ®жҹ”и»ҹжҖ§гҒҢеӨ§е№…гҒ«еҗ‘дёҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒж ӘејҸгҒ«йЎҚйқўгӮ’е®ҡгӮҒгҒӘгҒ„з„ЎйЎҚйқўж ӘејҸеҲ¶еәҰгҒ®е°Һе…ҘгӮ„гҖҒиӨҮж•°иӯ°жұәжЁ©д»ҳж ӘејҸгҖҒзү№е®ҡдәӢй …гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжӢ’еҗҰжЁ©пјҲй»„йҮ‘ж Әпјүд»ҳж ӘејҸгҒ®зҷәиЎҢгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеӨ§гҒҚгҒӘзү№еҫҙгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®еҲ¶еәҰгҒҢзӨәе”ҶгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒеүөжҘӯиҖ…гӮ„зү№е®ҡгҒ®ж Әдё»гҒҢгҖҒеҮәиіҮжҜ”зҺҮгӮ’дёӢгҒ’гҒҰгӮӮзөҢе–¶гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢж”Ҝй…ҚжЁ©гӮ’з¶ӯжҢҒгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®е…ҲйҖІзҡ„гҒӘд»•зө„гҒҝгҒҜгҖҒеүөжҘӯиҖ…гҒЁеӨ–йғЁжҠ•иіҮ家гҖҒзү№гҒ«гғҷгғігғҒгғЈгғјгӮӯгғЈгғ”гӮҝгғ«гҒЁгҒ®й–“гҒ®еҲ©е®іиӘҝж•ҙгӮ’е®№жҳ“гҒ«гҒ—гҖҒеҶҶж»‘гҒӘиіҮйҮ‘иӘҝйҒ”гӮ’дҝғйҖІгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®гӮ№гӮҝгғјгғҲгӮўгғғгғ—з•ҢйҡҲгҒ§иҝ‘е№ҙиӯ°и«–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгғҶгғјгғһгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҖҒеҸ°ж№ҫжі•гҒҢдё–з•ҢгҒ®гғҷгғігғҒгғЈгғјжі•еҲ¶гӮ’еј·гҒҸж„ҸиӯҳгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зү©иӘһгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®зөҢе–¶иҖ…гӮ„VCй–ўдҝӮиҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒгҒ“гҒ®еҲ¶еәҰгҒҜеҸ°ж№ҫгҒёгҒ®дәӢжҘӯйҖІеҮәгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢдёҠгҒ§гҒ®ж–°гҒҹгҒӘгӮӨгғігӮ»гғігғҶгӮЈгғ–гҒЁгҒӘгӮҠеҫ—гӮӢгҖҒйҮҚиҰҒгҒӘеҲ¶еәҰзҡ„е„ӘдҪҚжҖ§гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
еӨ–еӣҪдәәгҒ«гӮҲгӮӢеҸ°ж№ҫжі•дәәиЁӯз«ӢжүӢз¶ҡ
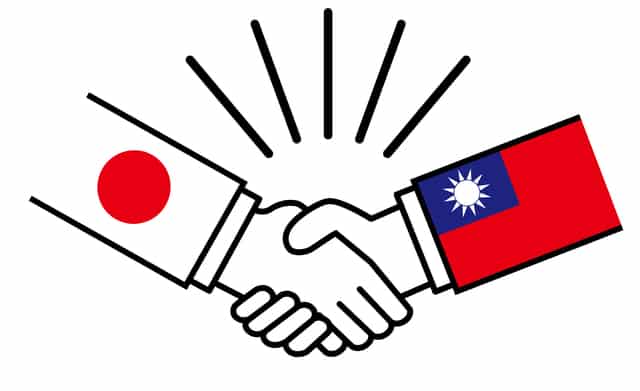
еӨ–еӣҪдјҒжҘӯгҒҢеҸ°ж№ҫгҒ§зҸҫең°жі•дәәгӮ’иЁӯз«ӢгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҖҒеҸ°ж№ҫзөҢжёҲйғЁжҠ•иіҮеҜ©иӯ°дјҡпјҲжҠ•еҜ©дјҡпјүгҒҢжүҖз®ЎгҒҷгӮӢзү№еҲҘгҒӘжүӢз¶ҡгҒҚгҖҒгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҢеӨ–еӣҪдәәжҠ•иіҮиЁұеҸҜз”іи«ӢпјҲFIAпјүгҖҚгҒҢеҝ…й ҲгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҜгҖҒиӨҮж•°гҒ®ж”ҝеәңж©ҹй–ўгӮ’гҒҫгҒҹгҒҺгҖҒж®өйҡҺзҡ„гҒ«йҖІгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
иЁӯз«Ӣгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒ®и©ізҙ°пјҲзҸҫең°жі•дәәпјҡиӮЎд»Ҫжңүйҷҗе…¬еҸёгғ»жңүйҷҗе…¬еҸёгҒ®е ҙеҗҲпјү
- дјҡзӨҫеҗҚз§°гҒЁе–¶жҘӯй …зӣ®гҒ®дәӢеүҚеҜ©жҹ»пјҡжңҖеҲқгҒ«гҖҒеёҢжңӣгҒҷгӮӢдјҡзӨҫеҗҚгҒЁдәӢжҘӯеҶ…е®№гӮ’зөҢжёҲйғЁе•ҶжҘӯзҷәеұ•зҪІгҒ«жҸҗеҮәгҒ—гҖҒдәҲеӮҷеҜ©жҹ»гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҫгҒҷгҖӮиӨҮж•°гҒ®еҖҷиЈңеҗҚгӮ’жә–еӮҷгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжҺЁеҘЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
- еӨ–еӣҪдәәжҠ•иіҮиЁұеҸҜз”іи«ӢпјҲFIAпјүпјҡдәҲеӮҷеҜ©жҹ»е®ҢдәҶеҫҢгҖҒжҠ•еҜ©дјҡгҒ«FIAз”іи«ӢгӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®йҡӣгҖҒиҰӘдјҡзӨҫгҒ®зҷ»иЁҳз°ҝ謄жң¬гҖҒеҸ–з· еҪ№гҒ®иә«еҲҶиЁјжҳҺжӣёгҖҒе®ҡж¬ҫжЎҲгҒӘгҒ©гҖҒеӨҡгҒҸгҒ®жӣёйЎһгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®жӣёйЎһгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®е…¬иЁјдәәиӘҚиЁјгӮ„еҸ°еҢ—й§җж—ҘзөҢжёҲж–ҮеҢ–д»ЈиЎЁеҮҰгҒ§гҒ®иӘҚиЁјжүӢз¶ҡгҒҚгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
- иіҮжң¬йҮ‘гҒ®йҖҒйҮ‘гҒЁжҹ»е®ҡпјҡжҠ•еҜ©дјҡгҒӢгӮүиЁұеҸҜгҒҢдёӢгӮҠгҒҹгӮүгҖҒеҸ°ж№ҫгҒ®йҠҖиЎҢгҒ«жә–еӮҷеҸЈеә§гӮ’й–ӢиЁӯгҒ—гҖҒиіҮжң¬йҮ‘гӮ’йҖҒйҮ‘гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҖҒиіҮжң¬йҮ‘гҒҢе®ҹйҡӣгҒ«жү•гҒ„иҫјгҒҫгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’иЁјжҳҺгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҸ°ж№ҫгҒ®дјҡиЁҲеЈ«гҒ«гӮҲгӮӢжҹ»е®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
- иЁӯз«Ӣзҷ»иЁҳпјҡиіҮжң¬йҮ‘гҒ®жҹ»е®ҡе®ҢдәҶеҫҢгҖҒзөҢжёҲйғЁе•ҶжҘӯзҷәеұ•зҪІгҒ«иЁӯз«Ӣзҷ»иЁҳгӮ’з”іи«ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®зҷ»иЁҳгҒҢе®ҢдәҶгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒдјҡзӨҫгҒ«еӣәжңүгҒ®8жЎҒгҒ®з•ӘеҸ·гҒ§гҒӮгӮӢгҖҢзөұдёҖз·ЁеҸ·гҖҚгҒҢзҷәиЎҢгҒ•гӮҢгҖҒжі•дәәгҒЁгҒ—гҒҰжӯЈејҸгҒ«жҙ»еӢ•гӮ’й–Ӣе§ӢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
- зЁҺеӢҷзҷ»йҢІгҒЁгҒқгҒ®д»–пјҡжңҖеҫҢгҒ«гҖҒжүҖиҪ„гҒ®еӣҪзЁҺеұҖгҒ«гҒҰзЁҺзұҚзҷ»йҢІгӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒзөұдёҖзҷәзҘЁпјҲж—Ҙжң¬гҒ§гҒ„гҒҶй ҳеҸҺжӣёпјүгҒ®зҷәиЎҢгҒҢеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒе–¶жҘӯжҙ»еӢ•гӮ’й–Ӣе§ӢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
д»ҘдёӢгҒ«гҖҒеӨ–еӣҪдәәгҒ«гӮҲгӮӢеҸ°ж№ҫжі•дәәиЁӯз«Ӣгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒ®еҗ„гӮ№гғҶгғғгғ—гҒЁзӣ®е®үгҒЁгҒӘгӮӢжүҖиҰҒжңҹй–“гӮ’гҒҫгҒЁгӮҒгҒҫгҒҷгҖӮ
| гӮ№гғҶгғғгғ— | жүҖз®Ўж©ҹй–ў | зӣ®е®үжүҖиҰҒжңҹй–“ | зӣ®е®үжүҖиҰҒжңҹй–“ |
|---|---|---|---|
| дјҡзӨҫеҗҚгғ»е–¶жҘӯй …зӣ®дәҲеӮҷеҜ©жҹ» | зөҢжёҲйғЁе•ҶжҘӯзҷәеұ•зҪІ | зҙ„3е–¶жҘӯж—Ҙ | еҖҷиЈңеҗҚгҒ®йҮҚиӨҮзўәиӘҚгҖҒдәӢжҘӯеҶ…е®№гҒ®еҜ©жҹ» |
| еӨ–еӣҪдәәжҠ•иіҮиЁұеҸҜз”іи«ӢпјҲFIAпјү | зөҢжёҲйғЁжҠ•иіҮеҜ©иӯ°дјҡ | зҙ„10ж—Ҙй–“ | еҝ…иҰҒжӣёйЎһгҒ®дҪңжҲҗгғ»жҸҗеҮәгҖҒжҠ•иіҮеҜ©жҹ» |
| иіҮжң¬йҮ‘йҖҒйҮ‘з”ЁеҸЈеә§й–ӢиЁӯ | йҠҖиЎҢ | 1ж—ҘгҖң2ж—Ҙй–“ | иіҮжң¬йҮ‘жҢҜиҫјз”ЁгҒ®дёҖжҷӮеҸЈеә§й–ӢиЁӯ |
| иіҮжң¬йҮ‘йҖҒйҮ‘ | йҠҖиЎҢ | 1ж—ҘгҖң2ж—Ҙй–“ | ж—Ҙжң¬гҒӢгӮүеҸ°ж№ҫгҒёгҒ®иіҮжң¬йҮ‘жҢҜиҫј |
| еҮәиіҮйҮ‘жҹ»е®ҡ | дјҡиЁҲеЈ«гҖҒжҠ•иіҮеҜ©иӯ°дјҡ | зҙ„10ж—Ҙй–“ | иіҮжң¬йҮ‘жү•гҒ„иҫјгҒҝгҒ®зӣЈжҹ»гҖҒиЁјжҳҺ |
| дјҡзӨҫиЁӯз«Ӣзҷ»иЁҳ | зөҢжёҲйғЁе•ҶжҘӯзҷәеұ•зҪІ | зҙ„14ж—Ҙй–“ | дјҡзӨҫиЁӯз«Ӣзҷ»иЁҳгҒ®з”іи«ӢгҖҒзөұдёҖз·ЁеҸ·гҒ®еҸ–еҫ— |
| зЁҺеӢҷзҷ»йҢІ | еӣҪзЁҺеұҖ | 1ж—Ҙй–“ | е–¶жҘӯй–Ӣе§ӢгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®зЁҺзұҚзҷ»йҢІ |
гҒқгҒ®д»–гҒ®йҖІеҮәеҪўж…Ӣ
зҸҫең°жі•дәәиЁӯз«Ӣд»ҘеӨ–гҒ«гӮӮгҖҒеҸ°ж№ҫгҒёгҒ®йҖІеҮәеҪўж…ӢгҒЁгҒ—гҒҰж”Ҝеә—гӮ„й§җеңЁе“ЎдәӢеӢҷжүҖгҒЁгҒ„гҒҶйҒёжҠһиӮўгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮж”Ҝеә—гҒҜиҰӘдјҡзӨҫгҒ®е»¶й•·гҒЁгҒ—гҒҰдҪҚзҪ®гҒҘгҒ‘гӮүгӮҢгҖҒзӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹжі•дәәж јгӮ’жҢҒгҒЎгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒж”Ҝеә—гҒ®еӮөеӢҷгҒҜгҒҷгҒ№гҒҰиҰӘдјҡзӨҫгҒҢз„ЎйҷҗиІ¬д»»гӮ’иІ гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒж”Ҝеә—иЁӯз«ӢгҒ®е ҙеҗҲгҖҒжҠ•иіҮеҜ©иӯ°дјҡгҒ®иЁұеҸҜгҒҢдёҚиҰҒгҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдёҖж–№гҖҒй§җеңЁе“ЎдәӢеӢҷжүҖгҒҜгҖҒе–¶жҘӯжҙ»еӢ•гҒҜиЎҢгҒҲгҒҡгҖҒеёӮе ҙиӘҝжҹ»гӮ„йҖЈзөЎжҘӯеӢҷгҒ®гҒҝгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒиЁӯз«ӢжүӢз¶ҡгҒҚгҒҜжңҖгӮӮз°Ўзҙ гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгӮүгҒ®жүӢз¶ҡгҒҚгҒҜгҖҒиЁҖиӘһгҒ®еЈҒгӮ„еҝ…иҰҒжӣёйЎһгҒ®иӘҚиЁјжүӢз¶ҡгҒҚгҒӘгҒ©гҖҒеӨ–еӣҪдјҒжҘӯгҒҢзӢ¬еҠӣгҒ§йҖІгӮҒгӮӢгҒ«гҒҜеӨҡгҒҸгҒ®иӘІйЎҢгӮ’дјҙгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒеҸ°ж№ҫгҒ§гҒ®дјҡзӨҫиЁӯз«ӢгӮ’еҶҶж»‘гҒ«йҖІгӮҒгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒзҸҫең°гҒ®жі•еӢҷгӮ„дјҡиЁҲгҒ«зІҫйҖҡгҒ—гҒҹе°Ӯй–Җ家гҒ®гӮөгғқгғјгғҲгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒ
еҸ°ж№ҫдјҡзӨҫжі•гҒҢжҸҗдҫӣгҒҷгӮӢжҹ”и»ҹгҒӘеҲ¶еәҰгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®дјҒжҘӯгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰдәӢжҘӯеұ•й–ӢгҒ®еӨ§гҒҚгҒӘеҲ©зӮ№гҒЁгҒӘгӮӢдёҖж–№гҖҒгҒқгӮҢгҒ«дјҙгҒҶжі•еӢҷдёҠгҒ®иӨҮйӣ‘гҒ•гӮӮеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒиӨҮж•°гҒ®иЎҢж”ҝж©ҹй–ўгӮ’гҒҫгҒҹгҒҢгӮӢеӨ–еӣҪдәәжҠ•иіҮиЁұеҸҜз”іи«ӢпјҲFIAпјүгҒ®жүӢз¶ҡгҒҚгҒҜгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®жҷӮй–“гҒЁе°Ӯй–ҖзҹҘиӯҳгӮ’иҰҒгҒ—гҖҒиЁӯз«Ӣгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеӨ§гҒҚгҒӘгғӘгӮ№гӮҜгҒЁгҒӘгӮҠеҫ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ«гғҶгӮҙгғӘгғј: ITгғ»гғҷгғігғҒгғЈгғјгҒ®дјҒжҘӯжі•еӢҷ
гӮҝгӮ°: еҸ°ж№ҫжө·еӨ–дәӢжҘӯ