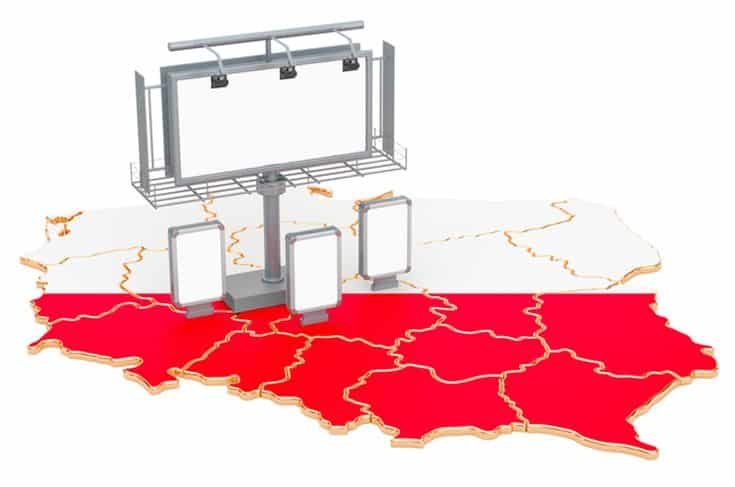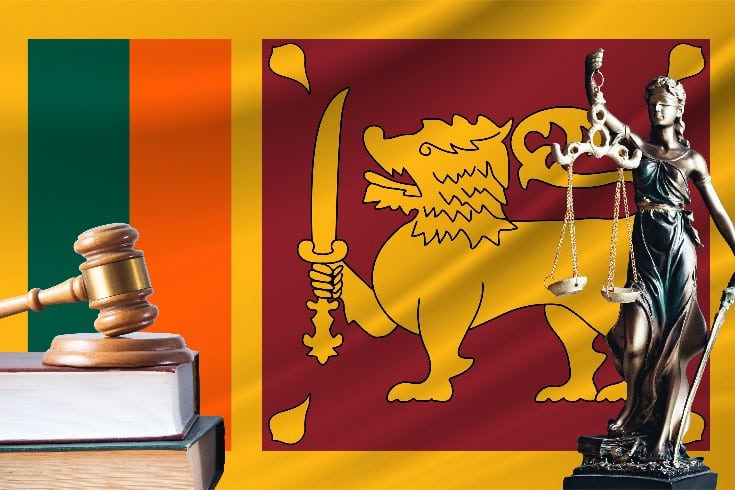гғһгғ«гӮҝе…ұе’ҢеӣҪгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдёҚеӢ•з”Јй–ўйҖЈжі•еҲ¶еәҰгҒ®и§ЈиӘ¬

гғһгғ«гӮҝе…ұе’ҢеӣҪгҒҜгҖҒ欧е·һйҖЈеҗҲпјҲEUпјүгҒ®еҠ зӣҹеӣҪгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиҝ‘е№ҙгҖҒж—Ҙжң¬гӮ’еҗ«гӮҖжө·еӨ–гҒӢгӮүгҖҒжҠ•иіҮгҒҠгӮҲгҒідәӢжҘӯеұ•й–ӢгҒ®жӢ зӮ№гҒЁгҒ—гҒҰжіЁзӣ®гӮ’йӣҶгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгғһгғ«гӮҝгҒ«гҒҜгҖҒеӨ–еӣҪдәәгҒҢдёҚеӢ•з”ЈгӮ’иіје…ҘгҒҷгӮӢйҡӣгҒ®дәӢеүҚгҒ®иЁұеҸҜеҲ¶еәҰгӮ„гҖҒиіғиІёеҖҹеҘ‘зҙ„гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢж”ҝеәңгҒ«гӮҲгӮӢеј·еҲ¶зҡ„гҒӘеёӮе ҙз®ЎзҗҶгҒӘгҒ©гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘгғқгӮӨгғігғҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒгғһгғ«гӮҝе…ұе’ҢеӣҪгҒ®дёҚеӢ•з”Јй–ўйҖЈгҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒзү№гҒ«гҖҒгғһгғ«гӮҝжі•Chapter 246гҖҢImmovable Property (Acquisition by Non-Residents) ActгҖҚгҒ«еҹәгҒҘгҒҸдёҚеӢ•з”ЈеҸ–еҫ—иЁұеҸҜпјҲAIPпјүеҲ¶еәҰгҒЁгҖҒдёҚеӢ•з”ЈжҠ•иіҮгӮ’еҸҜиғҪгҒ«гҒҷгӮӢгҖҢзү№еҲҘжҢҮе®ҡеҢәеҹҹпјҲSDAпјүгҖҚгҖҒиіғиІёеёӮе ҙгӮ’еҢ…жӢ¬зҡ„гҒ«иҰҸеҲ¶гҒҷгӮӢгҖҢз§Ғзҡ„еұ…дҪҸиіғиІёеҖҹжі•пјҲPRLAпјүгҖҚгҒ«з„ҰзӮ№гӮ’еҪ“гҒҰгҖҒгҒқгҒ®и©ізҙ°гӮ’и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒгғһгғ«гӮҝе…ұе’ҢеӣҪгҒ®еҢ…жӢ¬зҡ„гҒӘжі•еҲ¶еәҰгҒ®жҰӮиҰҒгҒҜдёӢиЁҳиЁҳдәӢгҒ«гҒҰгҒҫгҒЁгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®зӣ®ж¬Ў
гғһгғ«гӮҝгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдёҚеӢ•з”Јиіје…ҘгҒ®жі•зҡ„жһ зө„гҒҝ
гғһгғ«гӮҝе…ұе’ҢеӣҪгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдёҚеӢ•з”Јиіје…ҘгҒ®жі•еҲ¶еәҰгӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢдёҠгҒ§жңҖгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘзӮ№гҒҜгҖҒеӨ–еӣҪдәәгҒ«гӮҲгӮӢдёҚеӢ•з”ЈеҸ–еҫ—гӮ’еҺіж јгҒ«иҰҸеҲ¶гҒҷгӮӢгҖҢдёҚеӢ•з”ЈеҸ–еҫ—иЁұеҸҜпјҲAIPпјүеҲ¶еәҰгҖҚгҒЁгҖҒгҒқгҒ®дҫӢеӨ–гҒЁгҒ—гҒҰжҠ•иіҮ家еҗ‘гҒ‘гҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹгҖҢзү№еҲҘжҢҮе®ҡеҢәеҹҹпјҲSDAпјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒдәҢгҒӨгҒ®еҲ¶еәҰгҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
AIPиЁұеҸҜеҲ¶еәҰпјҲAcquisition of Immovable Property PermitпјүгҒ®жҰӮиҰҒ
гғһгғ«гӮҝе…ұе’ҢеӣҪгҒ®дёҚеӢ•з”ЈеҸ–еҫ—жі•пјҲImmovable Property (Acquisition by Non-Residents) ActгҖҒChapter 246 of the Laws of MaltaпјүгҒҜгҖҒйқһEUгғ»EEAеңҸгҒ®еӣҪж°‘гҒҢгғһгғ«гӮҝеӣҪеҶ…гҒ®дёҚеӢ•з”ЈгӮ’еҸ–еҫ—гҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гҖҒеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰж”ҝеәңгҒӢгӮүAIPиЁұеҸҜгӮ’еҫ—гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®гҒ»гҒӢгҖҒдёҖйғЁгҒ®EUеёӮж°‘пјҲдҫӢгҒҲгҒ°гғһгғ«гӮҝгҒ§гҒ®еұ…дҪҸжӯҙгҒҢ5е№ҙжңӘжәҖгҒ§гҖҒгӮ»гӮ«гғігғүгғҸгӮҰгӮ№гӮ’еҸ–еҫ—гҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒӘгҒ©пјүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒдёҖе®ҡгҒ®е ҙеҗҲгҒ«гҒҜAIPиЁұеҸҜгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮйҷҗгӮүгӮҢгҒҹеӣҪеңҹгҒЁдҪҸе®…иіҮжәҗгӮ’жҢҒгҒӨгғһгғ«гӮҝгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒжө·еӨ–гҒӢгӮүгҒ®жҠ•ж©ҹзҡ„гҒӘдёҚеӢ•з”Јиіје…ҘгӮ’жҠ‘еҲ¶гҒ—гҖҒеӣҪеҶ…гҒ®дҪҸе®…еёӮе ҙгҒ®е®үе®ҡгӮ’зўәдҝқгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶж„ҸеӣігҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеӨ–еӣҪдәәгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮдёҚеӢ•з”ЈеҸ–еј•гҒҜеҹәжң¬зҡ„гҒ«иҮӘз”ұгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиіје…ҘеҫҢгҒ®дәӢеҫҢе ұе‘ҠгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгғһгғ«гӮҝгҒ§гҒҜгҖҒзү№е®ҡгҒ®жқЎд»¶гӮ’жәҖгҒҹгҒҷе ҙеҗҲгӮ’йҷӨгҒҚгҖҒдёҚеӢ•з”Јиіје…ҘгҒЁгҒ„гҒҶиЎҢзӮәгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒеҺҹеүҮзҡ„гҒ«дәӢеүҚгҒ«ж”ҝеәңгҒ®иӘҚеҸҜгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
AIPиЁұеҸҜгҒ®еҸ–еҫ—гҒ«гҒҜгҖҒгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘжқЎд»¶гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҡгҖҒеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒAIPиЁұеҸҜгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰеҸ–еҫ—гҒ§гҒҚгӮӢзү©д»¶гҒҜгғһгғ«гӮҝеӣҪеҶ…гҒ§1件гҒ«йҷҗе®ҡгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҲ¶йҷҗгҒҜгҖҒжҠ•ж©ҹзӣ®зҡ„гҒ§гҒ®иӨҮж•°зү©д»¶дҝқжңүгӮ’йҳІгҒҗгҒҹгӮҒгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒиіје…ҘгҒ—гҒҹдёҚеӢ•з”ЈгҒҜдё»гҒ«иҮӘе·ұеұ…дҪҸз”ЁгҒЁгҒ—гҒҰеҲ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеүҚжҸҗгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиіғиІёзӣ®зҡ„гҒ§гҒ®еҲ©з”ЁгҒҜиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒдәӢжҘӯзӣ®зҡ„гҒ§дёҚеӢ•з”ЈжҠ•иіҮгӮ’жӨңиЁҺгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢж—Ҙжң¬гҒ®дјҒжҘӯгӮ„жҠ•иіҮ家гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒзү№гҒ«жіЁж„ҸгҒҷгҒ№гҒҚжҘөгӮҒгҒҰйҮҚиҰҒгҒӘеҲ¶йҷҗдәӢй …гҒ§гҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒеҸ–еҫ—гҒҷгӮӢзү©д»¶гҒ«гҒҜжңҖдҪҺдҫЎйЎҚгҒҢиЁӯе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒ2025е№ҙжҷӮзӮ№гҒ§гҖҒгӮўгғ‘гғјгғҲгғЎгғігғҲгӮ„гғЎгӮҫгғҚгғғгғҲгҒ®е ҙеҗҲгҒҜвӮ¬174,274гҖҒгғҙгӮЈгғ©гӮ„гӮҝгӮҰгғігғҸгӮҰгӮ№гҒӘгҒ©гҒ®е ҙеҗҲгҒҜвӮ¬300,619д»ҘдёҠгҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒӘгҒҠгҖҒжңҖдҪҺдҫЎж јгҒҜжҜҺе№ҙж”№е®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒжңҖж–°гҒ®жғ…е ұгҒҜгғһгғ«гӮҝзЁҺеӢҷеҪ“еұҖгӮөгӮӨгғҲгӮ’гҒ”зўәиӘҚгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮз”іи«ӢжүӢз¶ҡгҒҚгҒ«гҒҜгҖҒеЈІгӮҠжүӢгҒЁгҒ®й–“гҒ§з· зөҗгҒ—гҒҹд»®еҘ‘зҙ„пјҲPromise of SaleгҒҫгҒҹгҒҜKonvenjuпјүгҒ®еҶҷгҒ—гӮ„гғ‘гӮ№гғқгғјгғҲгҒ®еҶҷгҒ—гҖҒгҒқгҒ—гҒҰвӮ¬233гҒ®иҝ”йҮ‘дёҚеҸҜгҒ®з”іи«Ӣж–ҷгҒӘгҒ©гҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒеҜ©жҹ»гҒ«гҒҜйҖҡеёё35ж—ҘгҒӢгӮү40ж—ҘгӮ’иҰҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
жҠ•иіҮ家еҗ‘гҒ‘зү№еҲҘжҢҮе®ҡеҢәеҹҹпјҲSpecial Designated Areas: SDAпјүеҲ¶еәҰ
AIPиЁұеҸҜеҲ¶еәҰгҒ®еҺіж јгҒӘеҲ¶йҷҗгҒҢгҒӮгӮӢдёҖж–№гҒ§гҖҒгғһгғ«гӮҝж”ҝеәңгҒҜгҖҒзү№е®ҡгҒ®зӣ®зҡ„гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«еӨ–еӣҪдәәжҠ•иіҮ家гӮ’з©ҚжҘөзҡ„гҒ«иӘҳиҮҙгҒҷгӮӢж”ҝзӯ–гӮӮеҗҢжҷӮгҒ«еұ•й–ӢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢгҖҒж”ҝеәңгҒҢжҢҮе®ҡгҒҷгӮӢгҖҢзү№еҲҘжҢҮе®ҡеҢәеҹҹпјҲSDAпјүгҖҚгҒ§гҒ®дёҚеӢ•з”Јиіје…ҘеҲ¶еәҰгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®еҢәеҹҹгҒҜгҖҒAIPиЁұеҸҜеҲ¶еәҰгҒ®йҒ©з”ЁеҜҫиұЎеӨ–гҒЁгҒӘгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘдҫӢеӨ–гҒЁгҒ—гҒҰж©ҹиғҪгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
SDAеҲ¶еәҰгҒ®жңҖеӨ§гҒ®еҲ©зӮ№гҒҜгҖҒеӣҪзұҚгӮ„гғһгғ«гӮҝгҒ§гҒ®еұ…дҪҸжӯҙгҒ«й–ўгӮҸгӮүгҒҡгҖҒAIPиЁұеҸҜгҒӘгҒҸдёҚеӢ•з”ЈгӮ’иіје…ҘгҒ§гҒҚгӮӢзӮ№гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒAIPиЁұеҸҜгҒ§гҒҜзҰҒгҒҳгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹзү©д»¶ж•°гҒ®еҲ¶йҷҗгҒҢгҒӘгҒҸгҖҒиӨҮ数件гҒ®дёҚеӢ•з”ЈгӮ’жүҖжңүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеӨ§иҰҸжЁЎгҒӘгғқгғјгғҲгғ•гӮ©гғӘгӮӘгӮ’ж§ӢзҜүгҒҷгӮӢдёҚеӢ•з”ЈжҠ•иіҮгҒҢеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒиіје…ҘгҒ—гҒҹдёҚеӢ•з”ЈгӮ’иҮӘз”ұгҒ«иіғиІёгҒ«еҮәгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜиіғиІёдәӢжҘӯгҒ®еұ•й–ӢгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢжҠ•иіҮ家гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒSDAеҲ¶еәҰгҒҢзү№гҒ«йӯ…еҠӣзҡ„гҒ§гҒӮгӮӢзҗҶз”ұгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®ең°еҹҹгҒ§гҒҜиіғиІёеҸҺе…Ҙе…ЁиҲ¬гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒ15пј…гҒ®жңҖзөӮжәҗжіүзЁҺгӮ’йҒёжҠһгҒ§гҒҚгӮӢеҲ¶еәҰгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒSDAзү©д»¶гӮӮгҒқгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢе ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгӮүгҒ®SDAгҒҜгҖҒTignГ© PointгӮ„PortomasoгҖҒFort CambridgeгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҖҒгғһгғӘгғјгғҠгӮ„гӮ№гғ‘гҖҒгӮ·гғ§гғғгғ”гғігӮ°гғўгғјгғ«гҖҒгғ¬гӮ№гғҲгғ©гғігҒӘгҒ©гӮ’дҪөиЁӯгҒ—гҒҹиӨҮеҗҲзҡ„гҒӘй«ҳзҙҡй–ӢзҷәеҢәеҹҹгҒЁгҒ—гҒҰзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
AIPиЁұеҸҜеҲ¶еәҰгҒЁSDAеҲ¶еәҰ
AIPиЁұеҸҜеҲ¶еәҰгҒЁSDAеҲ¶еәҰгҒЁгҒ„гҒҶ2гҒӨгҒ®еҲ¶еәҰгӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҹгғһгғ«гӮҝгҒ®дёҚеӢ•з”Јжі•еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒиҮӘе·ұеұ…дҪҸгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒҷгӮӢеҖӢдәәжҠ•иіҮ家гҒ«гҒҜеҺіж јгҒӘиҰҸеҲ¶гӮ’иӘІгҒҷдёҖж–№гҒ§гҖҒеӨ§иҰҸжЁЎгҒӘй–ӢзҷәгӮ„иіғиІёдәӢжҘӯгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒҷгӮӢгғ—гғӯгҒ®жҠ•иіҮ家гҒ«гҒҜгҖҒSDAгҒЁгҒ„гҒҶзү№еҲҘгҒӘеҲ¶еәҰгӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒйҷҗгӮүгӮҢгҒҹеӣҪеңҹгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдҪҸе®…еёӮе ҙгҒ®е®үе®ҡгҒЁгҖҒжө·еӨ–гҒӢгӮүгҒ®еӨ§иҰҸжЁЎжҠ•иіҮгҒ®дёЎз«ӢгӮ’еӣігӮҚгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢзөҢжёҲж”ҝзӯ–гҒ®иЎЁгӮҢгҒ гҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гғһгғ«гӮҝгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдёҚеӢ•з”Јиіје…Ҙгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒ®и©ізҙ°гҒЁй–ўйҖЈиІ»з”Ё

гғһгғ«гӮҝгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдёҚеӢ•з”Јиіје…Ҙгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®е•Ҷж…Јзҝ’гӮ„жі•еҲ¶еәҰгҒЁгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮӢзү№еҫҙгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒе…¬иЁјдәәпјҲNotaryпјүгҒҢжһңгҒҹгҒҷеҪ№еүІгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҸёжі•жӣёеЈ«гҒ®гҒқгӮҢгҒЁгҒҜз•°гҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҸ–еј•гҒ®е®үе…ЁжҖ§гӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢдёҠгҒ§дёӯеҝғзҡ„гҒӘеҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
е…¬иЁјдәәпјҲNotaryпјүгҒ®дёӯеҝғзҡ„еҪ№еүІ
гғһгғ«гӮҝгҒ®дёҚеӢ•з”ЈеҸ–еј•гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒе…¬иЁјдәәгҒҜеҚҳгҒӘгӮӢжӣёйЎһдҪңжҲҗгӮ„зҷ»иЁҳд»ЈиЎҢиҖ…гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒе…¬еӢҷе“ЎгҒЁгҒ—гҒҰеҸ–еј•гҒ®е…¬жӯЈжҖ§гҒЁе®үе…ЁжҖ§гӮ’дҝқиЁјгҒҷгӮӢдёӯеҝғзҡ„еҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҪ№еүІгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҸёжі•жӣёеЈ«гҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮҠгҖҒжі•зҡ„жңүеҠ№жҖ§гҒ®жӨңиЁјгӮ„гғҮгғҘгғјгғҮгғӘгӮёгӮ§гғігӮ№гҒ®еӨ§йғЁеҲҶгӮ’е…¬зҡ„гҒ«жӢ…гҒҶзӮ№гҒ«еӨ§гҒҚгҒӘйҒ•гҒ„гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒе…¬иЁјдәәгҒҜгҖҒзү©д»¶гҒ®жүҖжңүжЁ©гҒ®зўәиӘҚгҖҒжӢ…дҝқжЁ©пјҲжҠөеҪ“жЁ©зӯүпјүгҒ®жңүз„ЎгҖҒеҝ…иҰҒгҒӘе»әзҜүиЁұеҸҜгҒ®еҸ–еҫ—зҠ¶жіҒгҒӘгҒ©гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒе…¬зҡ„гҒӘзҷ»иЁҳз°ҝпјҲLand RegistryпјүзӯүгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰи©ізҙ°гҒӘиӘҝжҹ»пјҲsearchesпјүгӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҜгҖҒеҸ–еј•еүҚгҒ«жі•зҡ„гғӘгӮ№гӮҜгӮ’жҙ—гҒ„еҮәгҒ—гҖҒиІ·гҒ„жүӢгӮ’дҝқиӯ·гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«дёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮ
еЈІиІ·еҘ‘зҙ„гҒ®дәҢж®өйҡҺгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒЁиІ»з”ЁдҪ“зі»
гғһгғ«гӮҝгҒ®дёҚеӢ•з”Јиіје…ҘгҒҜгҖҒдәҢж®өйҡҺгҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒ§йҖІгҒҝгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҡгҖҒиІ·гҒ„жүӢгҒЁеЈІгӮҠжүӢгҒҜд»®еҘ‘зҙ„пјҲPromise of SaleгҖҒйҖҡз§°KonvenjuпјүгӮ’з· зөҗгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҘ‘зҙ„гҒҜгҖҒе°ҶжқҘгҒ®еЈІиІ·гӮ’зҙ„жқҹгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®еҸ–еј•гҒ§дёҖиҲ¬зҡ„гҒ«иҰӢгӮүгӮҢгӮӢж°ҙжә–гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®ж®өйҡҺгҒ§иІ·гҒ„жүӢгҒҜеЈІиІ·дҫЎж јгҒ®10%гҒ«зӣёеҪ“гҒҷгӮӢжүӢд»ҳйҮ‘гӮ’еЈІгӮҠжүӢгҒ«ж”Ҝжү•гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒе…¬иЁјдәәгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰеҚ°зҙҷзЁҺпјҲStamp Dutyпјүз·ҸйЎҚгҒ®1%гӮ’ж”ҝеәңгҒ«зҙҚд»ҳгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҖҒе…¬иЁјдәәгҒҢзү©д»¶гҒ«й–ўгҒҷгӮӢжі•зҡ„иӘҝжҹ»гӮ’е®ҢдәҶгҒ•гҒӣгҖҒе•ҸйЎҢгҒҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҹдёҠгҒ§гҖҒжңҖзөӮеҘ‘зҙ„пјҲFinal Deed of SaleпјүгӮ’з· зөҗгҒ—гҖҒдёҚеӢ•з”ЈгҒ®жүҖжңүжЁ©гҒҢиІ·гҒ„жүӢгҒ«з§»и»ўгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жңҖзөӮеҘ‘зҙ„гҒ®з· зөҗжҷӮгҒ«гҖҒж®ӢгӮҠгҒ®д»ЈйҮ‘гҒЁеҚ°зҙҷзЁҺпјҲж®ӢгӮҠгҒ®4%пјүгҒҢж”Ҝжү•гӮҸгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғһгғ«гӮҝгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдёҚеӢ•з”Јиіје…ҘжҷӮгҒ®иІ»з”ЁгҒҜгҖҒеҺҹеүҮзҡ„гҒ«гҒҜгҖҒеҚ°зҙҷзЁҺпјҲеҺҹеүҮ5%пјүгӮ„е…¬иЁјдәәиІ»з”ЁпјҲзү©д»¶дҫЎж јгҒ®1%гҒӢгӮү2.5%пјүгҒ гҒ‘гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжғіе®ҡеӨ–гҒ®иІ»з”ЁгҒҢзҷәз”ҹгҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒзү©д»¶гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒеңҹең°гҒ®еҲ©з”ЁжЁ©гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢе№ҙй–“иІ»з”ЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖҢең°д»ЈпјҲGround RentпјүгҖҚгҒҢиЁӯе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬жі•гҒ«гҒҜгҒӘгҒ„зӢ¬зү№гҒ®жҰӮеҝөгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒзү©д»¶гҒ®жүҖжңүеҪўж…ӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜе°ҶжқҘгҒ«гӮҸгҒҹгӮӢиІЎж”ҝзҡ„иІ жӢ…гҒЁгҒӘгӮҠеҫ—гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒиіје…ҘеүҚгҒ«гҒқгҒ®жңүз„ЎгӮ’е…¬иЁјдәәгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰзўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒйҠҖиЎҢиһҚиіҮгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒ®жүӢж•°ж–ҷгҖҒе»әзү©гҒ®ж§ӢйҖ зҡ„гҒӘе•ҸйЎҢгҒҢгҒӘгҒ„гҒӢгӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®е»әзҜү家гҒ«гӮҲгӮӢе ұе‘ҠжӣёиІ»з”ЁпјҲвӮ¬300гҒӢгӮүвӮ¬800пјүгҖҒгҒқгҒ—гҒҰAIPиЁұеҸҜгҒ®з”іи«Ӣж–ҷпјҲвӮ¬233пјүгҒӘгҒ©гӮӮйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
гғһгғ«гӮҝгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдёҚеӢ•з”ЈгҒ®иіғиІёеҖҹжі•еҲ¶еәҰ
гғһгғ«гӮҝгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдёҚеӢ•з”ЈгҒ®иіғиІёеҖҹжі•гҒҜгҖҒ2020е№ҙ1жңҲ1ж—ҘгҒ«ж–ҪиЎҢгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢз§Ғзҡ„еұ…дҪҸиіғиІёеҖҹжі•пјҲPrivate Residential Leases ActгҖҒPRLAпјүгҖҚгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҢ…жӢ¬зҡ„гҒ«иҰҸеҲ¶гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жі•еҫӢгҒҜгҖҒгғһгғ«гӮҝгҒ®иіғиІёеёӮе ҙгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢйҒҺеҺ»гҒ®дёҚе®үе®ҡжҖ§гӮ„д№ұз”ЁгҒ«еҜҫеҮҰгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒж”ҝеәңгҒҢеёӮе ҙгҒ«з©ҚжҘөзҡ„гҒ«д»Ӣе…ҘгҒҷгӮӢе§ҝеӢўгӮ’еҸҚжҳ гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®еҖҹең°еҖҹ家法гҒҢеҘ‘зҙ„гҒ®з¶ҷз¶ҡжҖ§гӮ„иіғеҖҹдәәгҒ®жЁ©еҲ©дҝқиӯ·гӮ’йҮҚиҰ–гҒ—гҒӨгҒӨгӮӮгҖҒеҘ‘зҙ„еҶ…е®№гҒ®еӨҡгҒҸгӮ’еҪ“дәӢиҖ…й–“гҒ®еҗҲж„ҸгҒ«е§”гҒӯгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒPRLAгҒҜеҘ‘зҙ„гҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ«гҒҫгҒ§иёҸгҒҝиҫјгҒҝгҖҒеҘ‘зҙ„гҒ®еј·еҲ¶зҷ»йҢІгӮ’зҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеёӮе ҙе…ЁдҪ“гӮ’е…¬зҡ„гҒ«зӣЈиҰ–гғ»з®ЎзҗҶгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
PRLAгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘжі•зҡ„иҰҒ件
PRLAгҒҜгҖҒиіғиІёеҖҹеҘ‘зҙ„гҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҖҒж—Ҙжң¬дәәгҒҢзү№гҒ«з•ҷж„ҸгҒҷгҒ№гҒҚгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘиҰҒ件гӮ’е®ҡгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжңҖгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘзӣёйҒ•зӮ№гҒҜгҖҒеҘ‘зҙ„гҒ®еј·еҲ¶зҷ»йҢІзҫ©еӢҷгҒ§гҒҷгҖӮе…ЁгҒҰгҒ®з§Ғзҡ„еұ…дҪҸиіғиІёеҖҹеҘ‘зҙ„гҖҒгҒҠгӮҲгҒігҒқгҒ®жӣҙж–°гҒҜгҖҒгғҸгӮҰгӮёгғігӮ°гӮӘгғјгӮҪгғӘгғҶгӮЈпјҲHousing AuthorityпјүгҒёгҒ®зҷ»йҢІгҒҢзҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®зҷ»йҢІгҒҜиіғиІёдәәгҒ®зҫ©еӢҷгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҘ‘зҙ„й–Ӣе§ӢеҫҢ30ж—Ҙд»ҘеҶ…гҒ«гӮӘгғігғ©гӮӨгғігҒ§жүӢз¶ҡгҒҚгӮ’е®ҢдәҶгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮдёҮдёҖгҖҒеҘ‘зҙ„гҒҢзҷ»йҢІгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҖҒеҪ“и©ІеҘ‘зҙ„гҒҜгҖҢз„ЎеҠ№пјҲnull and voidпјүгҖҚгҒЁгҒҝгҒӘгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒжҘөгӮҒгҒҰеҺіж јгҒӘжі•зҡ„еҠ№жһңгӮ’дјҙгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҪ“дәӢиҖ…й–“гҒ®еҗҲж„ҸгҒ®гҒҝгҒ§жҲҗз«ӢгҒҷгӮӢж—Ҙжң¬гҒ®иіғиІёеҖҹеҘ‘зҙ„гҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮҠгҖҒгғһгғ«гӮҝгҒ§гҒҜгҖҒеҘ‘зҙ„гҒ®жі•зҡ„еҠ№еҠӣгҒ«е…¬зҡ„ж©ҹй–ўгҒ®й–ўдёҺгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒPRLAгҒҜиіғиІёжңҹй–“гҒЁи§Јзҙ„гғ«гғјгғ«гҒ«й–ўгҒ—гҒҰгӮӮи©ізҙ°гҒӘиҰҸе®ҡгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮй•·жңҹиіғиІёеҖҹеҘ‘зҙ„пјҲLong private residential leaseпјүгҒ®е ҙеҗҲгҖҒжңҖдҪҺиіғиІёжңҹй–“гҒҢ1е№ҙд»ҘдёҠгҒЁе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮиіғиІёдәәгҒҢеҘ‘зҙ„жңҹй–“жәҖдәҶжҷӮгҒ«еҘ‘зҙ„гӮ’зөӮдәҶгҒ•гҒӣгӮӢе ҙеҗҲгҖҒе°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮ3гғ¶жңҲеүҚгҒҫгҒ§гҒ«жӣёйқўгҒ«гӮҲгӮӢйҖҡзҹҘгӮ’иЎҢгҒҶеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдёҖж–№гҖҒиіғеҖҹдәәгҒ«гӮҲгӮӢдёӯйҖ”и§Јзҙ„гҒ«гҒҜгҖҒеҘ‘зҙ„жңҹй–“гҒ«еҝңгҒҳгҒҹдёҖе®ҡгҒ®жңҹй–“пјҲдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒ1е№ҙеҘ‘зҙ„гҒ®е ҙеҗҲгҒҜ6гғ¶жңҲеҫҢпјүгӮ’зөҢйҒҺгҒ—гҒҹеҫҢгҒ«гҖҒ1гғ¶жңҲеүҚгҒ®йҖҡзҹҘгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®и©ізҙ°гҒӘи§Јзҙ„гғ«гғјгғ«гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®дёҖиҲ¬зҡ„гҒӘи§Јзҙ„дәҲе‘Ҡжңҹй–“пјҲйҖҡеёёгҒҜ1гғ¶жңҲгҒӢгӮү3гғ¶жңҲпјүгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮҠгҖҒеҘ‘зҙ„жңҹй–“гҒ®е°ҠйҮҚгӮ’еј·гҒҸжұӮгӮҒгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒиіғж–ҷгҒ®еў—йЎҚгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгӮӮиҰҸеҲ¶гҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮPRLAгҒҜгҖҒе№ҙй–“иіғж–ҷгҒ®еў—йЎҚгӮ’еүҚе№ҙеәҰгҒ®иіғж–ҷгҒ®5%гӮ’дёҠйҷҗгҒЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иҰҸе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®ж°‘жі•гӮ„еҖҹең°еҖҹ家法гҒҢзөҢжёҲжғ…еӢўгҒ®еӨүеҢ–гҒ«еҝңгҒҳгҒҹгҖҢиіғж–ҷеў—жёӣйЎҚи«ӢжұӮжЁ©гҖҚгӮ’иӘҚгӮҒгӮӢгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒӘдёҠйҷҗгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„зӮ№гҒЁгҒҜз•°гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
иіғиІёеҘ‘зҙ„гҒ®е®ҹйҡӣ

гғһгғ«гӮҝгҒ®иіғиІёеёӮе ҙгҒ§гҒҜгҖҒгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ®зү©д»¶гҒҢ家具д»ҳгҒҚгҒ§жҸҗдҫӣгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒҷгҖӮиіғиІёеҖҹеҘ‘зҙ„з· зөҗжҷӮгҒ«гҒҜгҖҒйҖҡеёёгҖҒ1гғ¶жңҲеҲҶгҒ®иіғж–ҷгҒ«зӣёеҪ“гҒҷгӮӢгғҮгғқгӮёгғғгғҲпјҲж•·йҮ‘пјүгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜзү©д»¶гҒ®жҗҚеӮ·гӮ„жңӘжү•гҒ„йҮ‘гҒ«е……еҪ“гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒй•·жңҹиіғиІёеҘ‘зҙ„гҒ§гҒҜгҖҒж°ҙйҒ“гғ»йӣ»ж°—д»ЈгҒҜиіғж–ҷгҒ«еҗ«гҒҫгӮҢгҒҡгҖҒиіғеҖҹдәәгҒҢиІ жӢ…гҒҷгӮӢгҒ®гҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒҷгҖӮдёҚеӢ•з”Јд»Ід»ӢжҘӯиҖ…гӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒ®д»Ід»ӢжүӢж•°ж–ҷгҒҜгҖҒйҖҡеёёгҖҒ家主гҒЁиіғеҖҹдәәгҒ®еҸҢж–№гҒҢгҒқгӮҢгҒһгӮҢ1гғ¶жңҲеҲҶгҒ®иіғж–ҷгҒ®еҚҠйЎҚгӮ’иІ жӢ…гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҸӮиҖғпјҡдёҚеӢ•з”Јиіје…ҘгҒЁгғ“гӮ¶еҸ–еҫ—
гҒӘгҒҠгҖҒж—Ҙжң¬дәәгҒӘгҒ©жө·еӨ–гҒ®дәәй–“гҒҢгғһгғ«гӮҝеӣҪеҶ…гҒ«дёҚеӢ•з”ЈгӮ’жүҖжңүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®еӨ§гҒҚгҒӘзҗҶз”ұгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒдёҚеӢ•з”ЈгҒёгҒ®жҠ•иіҮгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰж°ёдҪҸжЁ©гӮ„еёӮж°‘жЁ©гӮ’зҚІеҫ—гҒ§гҒҚгӮӢгҖҢеұ…дҪҸжЁ©гғ»еёӮж°‘жЁ©гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҖҚгҒ®еӯҳеңЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮж°ёдҪҸжЁ©гӮ’еҸ–еҫ—гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гҖҢгғһгғ«гӮҝж°ёдҪҸгғ—гғӯгӮ°гғ©гғ пјҲMalta Permanent Residence Programme, MPRPпјүгҖҚгҒЁгҖҒеёӮж°‘жЁ©гӮ’еҸ–еҫ—гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гҖҢгғһгғ«гӮҝеёӮж°‘жЁ©еҸ–еҫ—гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ пјҲMalta Exceptional Investor Naturalisation, MEINпјүгҖҚгҒ§гҖҒе…ұгҒ«дёҚеӢ•з”ЈгҒЁй–ўйҖЈжҖ§гӮ’жңүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгӮүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®иЁҳдәӢгҒ§и©ігҒ—гҒҸи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒ
гғһгғ«гӮҝе…ұе’ҢеӣҪгҒ®дёҚеӢ•з”Јй–ўйҖЈжі•еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒдәӢжҘӯеұ•й–ӢгӮ„жҠ•иіҮгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢж—Ҙжң¬гҒ®дјҒжҘӯгӮ„жҠ•иіҮ家гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒж—Ҙжң¬гҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢзӢ¬иҮӘгҒ®иҰҸеҲ¶гӮ„ж…ЈиЎҢгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒдёҚеӢ•з”ЈеҸ–еҫ—гҒ«йҡӣгҒ—гҒҰгҒ®гҖҢAIPиЁұеҸҜгҖҚгҒЁгҖҢSDAгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶдәҢгҒӨгҒ®еҲ¶еәҰгҖҒгҒқгҒ—гҒҰиіғиІёеҖҹеҘ‘зҙ„гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢеј·еҲ¶зҷ»йҢІзҫ©еӢҷгҖҚгҒҜгҖҒдәӢжҘӯгӮ„жҠ•иіҮеҲӨж–ӯгӮ’иЎҢгҒҶдёҠгҒ§жңҖгӮӮж·ұгҒҸзҗҶи§ЈгҒҷгҒ№гҒҚгғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒҷгҖӮ
гғһгғ«гӮҝгҒ®дёҚеӢ•з”Јжі•еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®гҒқгӮҢгҒЁгҒҜж №жң¬зҡ„гҒ«з•°гҒӘгӮӢжҖқжғігҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ•гӮүгҒ«жңҖж–°гҒ®жі•ж”№жӯЈгҒҢй »з№ҒгҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒеӢ•зҡ„гҒӘеҒҙйқўгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒӘеҸ–еј•гӮ„еҘ‘зҙ„гҒ«йҡӣгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒзҸҫең°гҒ®жі•еҲ¶еәҰгӮ’зҶҹзҹҘгҒ—гҒҹе°Ӯй–Җ家гҒ«гӮҲгӮӢжі•еӢҷгғҮгғҘгғјгғҮгғӘгӮёгӮ§гғігӮ№гӮ„гӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№гҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ гҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
й–ўйҖЈеҸ–жүұеҲҶйҮҺпјҡеӣҪйҡӣжі•еӢҷгғ»гғһгғ«гӮҝе…ұе’ҢеӣҪ
гӮ«гғҶгӮҙгғӘгғј: ITгғ»гғҷгғігғҒгғЈгғјгҒ®дјҒжҘӯжі•еӢҷ
гӮҝгӮ°: гғһгғ«гӮҝе…ұе’ҢеӣҪжө·еӨ–дәӢжҘӯ