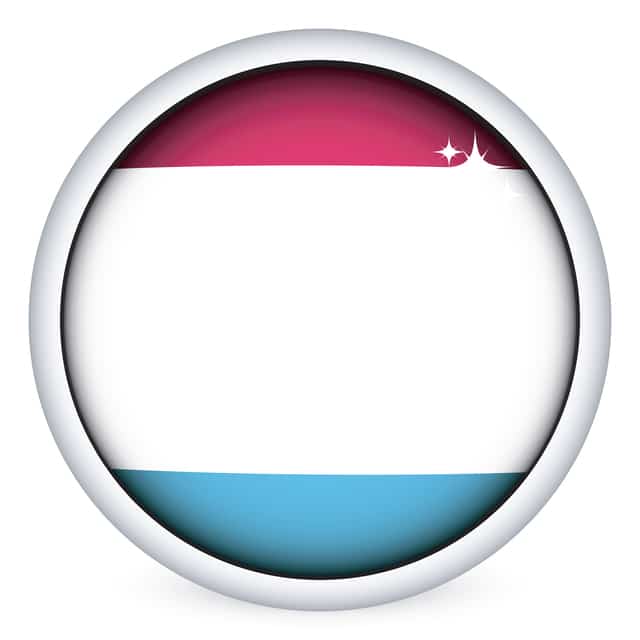ŃéżŃā│ŃāēÕģ▒ÕÆīÕøĮŃü«õ╝ÜńżŠĶ©Łń½ŗŃüŖŃéłŃü│µ│Ģõ║║ķüŗÕ¢ČŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗÕīģµŗ¼ńÜäĶ¦ŻĶ¬¼

µŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīŃé░ŃāŁŃā╝ŃāÉŃā½Ńü¬µłÉķĢʵł”ńĢźŃéƵÅÅŃüÅõĖŖŃü¦ŃĆüŃéżŃā│ŃāēÕģ▒ÕÆīÕøĮ’╝łõ╗źõĖŗŃĆüŃéżŃā│Ńāē’╝ēŃü»ŃĆüŃüØŃü«ÕĘ©Õż¦Ńü¬õ║║ÕÅŻÕĖéÕĀ┤Ńü©ķ½śŃüäńĄīµĖłµłÉķĢĘńÄćŃü½ŃéłŃéŖŃĆüõĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¬ķĆ▓Õć║ÕģłŃü©ŃüŚŃü”Ńü«Õ£░õĮŹŃéÆńó║ń½ŗŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüŃéżŃā│ŃāēŃü½ŃüŖŃüæŃéŗŃāōŃéĖŃāŹŃé╣Õ▒Ģķ¢ŗŃĆüŃü©ŃéŖŃéÅŃüæńÅŠÕ£░µ│Ģõ║║Ńü«Ķ©Łń½ŗŃü©ķüŗÕ¢ČŃü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü©Ńü»µĀ╣µ£¼ńÜäŃü½ńĢ░Ńü¬Ńéŗµ│ĢõĮōń│╗’╝łŃé│ŃāóŃā│Ńā╗ŃāŁŃā╝’╝ēŃéäŃĆüĶżćķøæŃüŗŃüżÕÄ│µĀ╝Ńü¬Ńé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣Ķ”üõ╗ČŃü½ŃéłŃéŖŃĆüõ║łµ£¤ŃüøŃü¼µ│ĢńÜäŃā¬Ńé╣Ńé»ŃéÆõ╝┤ŃüåŃü«ŃüīÕ«¤µāģŃü¦ŃüÖŃĆé
Ķ┐æÕ╣┤ŃĆüŃéżŃā│Ńāēµö┐Õ║£Ńü»ŃĆīEase of Doing Business’╝łŃāōŃéĖŃāŹŃé╣Ńü«ŃüŚŃéäŃüÖŃüĢ’╝ēŃĆŹŃéÆÕøĮÕ«Čµł”ńĢźŃü©ŃüŚŃü”µÄ▓ŃüÆŃĆüõ╝ÜńżŠĶ©Łń½ŗŃāŚŃāŁŃé╗Ńé╣Ńü«ŃāćŃéĖŃé┐Ńā½Õī¢ŃéÆµĆźķƤŃü½µÄ©ķĆ▓ŃüŚŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéńē╣Ńü½ŃĆüńĄ▒ÕÉłŃé”Ńé¦Ńā¢ŃāĢŃé®Ńā╝ŃāĀŃĆīSPICe+’╝łŃé╣ŃāæŃéżŃé╣Ńā╗ŃāŚŃā®Ńé╣’╝ēŃĆŹŃü«Õ░ÄÕģźŃü½ŃéłŃéŖŃĆüÕĢåÕÅĘõ║łń┤äŃüŗŃéēµ│Ģõ║║ńÖ╗Ķ©śŃĆüń┤Źń©ÄńĢ¬ÕÅĘŃü«ÕÅ¢ÕŠŚŃü½Ķć│ŃéŗõĖĆķĆŻŃü«µēŗńČÜŃüŹŃü»ŃĆüÕĮóÕ╝ÅõĖŖŃĆüÕŖćńÜäŃü½ń░Īń┤ĀÕī¢ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüŃüōŃü«ŃĆīµēŗńČÜŃüŹŃü«ń░Īń┤ĀÕī¢ŃĆŹŃéÆŃĆīµ│ĢńÜäĶ”üõ╗ČŃü«ńĘ®ÕÆīŃĆŹŃü©µĘĘÕÉīŃüŚŃü”Ńü»Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃéĆŃüŚŃéŹŃĆüŃāćŃéĖŃé┐Ńā½Õī¢Ńü½ŃéłŃüŻŃü”ĶĪīµö┐Õü┤Ńü«ńøŻĶ”¢ĶāĮÕŖøŃüīÕÉæõĖŖŃüŚŃü¤ŃüōŃü©Ńü¦ŃĆüÕ▒ģõĮÅÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«Ķ©ŁńĮ«ńŠ®ÕŗÖŃéäÕż¢ÕøĮńé║µø┐ń«ĪńÉåµ│Ģ’╝łFEMA’╝ēŃü½Õ¤║ŃüźŃüÅÕĀ▒ÕæŖńŠ®ÕŗÖŃĆüõ║ŗµźŁķ¢ŗÕ¦ŗÕ▒Ŗ’╝łCommencement of Business’╝ēŃü«µÅÉÕć║Ńü©ŃüäŃüŻŃü¤Õ«¤õĮōńÜäŃü¬Ńé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣ķüĢÕÅŹŃüīŃĆüŃéłŃéŖÕÄ│µĀ╝Ńü½µæśńÖ║ŃüĢŃéīŃéŗÕéŠÕÉæŃü½ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
µ£¼Ķ©śõ║ŗŃü¦Ńü»ŃĆüŃéżŃā│ŃāēŃüĖŃü«ķĆ▓Õć║ŃéƵż£Ķ©ÄŃüÖŃéŗµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü«ńĄīÕ¢ČĶĆģŃüŖŃéłŃü│µ│ĢÕŗÖµŗģÕĮōĶĆģŃéÆÕ»ŠĶ▒ĪŃü½ŃĆüµ£ĆŃééõĖĆĶł¼ńÜäŃü¬ķĆ▓Õć║ÕĮóµģŗŃü¦ŃüéŃéŗŃĆīķØ×Õģ¼ķ¢ŗõ╝ÜńżŠ’╝łPrivate Limited Company’╝ēŃĆŹŃü«Ķ©Łń½ŗŃāŚŃāŁŃé╗Ńé╣ŃéÆŃĆüµ£Ćµ¢░Ńü«µ│Ģõ╗żŃüŖŃéłŃü│ÕłżõŠŗŃü½Õ¤║ŃüźŃüŹĶ®│Ķ¬¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéÕŹśŃü¬ŃéŗµēŗńČÜŃüŹŃü«Ķ¦ŻĶ¬¼Ńü½Ńü©Ńü®ŃüŠŃéēŃüÜŃĆüµŚźµ£¼µ│ĢŃü©Ńü«µ»öĶ╝āµ│ĢńÜäĶ”¢ńé╣ŃéÆńö©ŃüäŃü¬ŃüīŃéēŃĆüÕ«¤ÕŗÖõĖŖŃü«ĶÉĮŃü©ŃüŚń®┤Ńü©Ńü¬ŃéŗŃāØŃéżŃā│ŃāłŃéäŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«µ│ĢńÜäĶ▓¼õ╗╗Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗµ£Ćµ¢░Ńü«ÕÅĖµ│ĢÕłżµ¢ŁŃéÆńČ▓ńŠģńÜäŃü½Õłåµ×ÉŃüŚŃĆüŃéżŃā│ŃāēŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕ╝ĘÕø║Ńü¬µ│ĢńÜäÕ¤║ńøżµ¦ŗń»ēŃü«Ńü¤ŃéüŃü«µīćķćØŃéƵÅÉõŠøŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
Ńü¬ŃüŖŃĆüŃéżŃā│ŃāēŃü«Õīģµŗ¼ńÜäŃü¬µ│ĢÕłČÕ║”Ńü«µ”éĶ”üŃü»õĖŗĶ©śĶ©śõ║ŗŃü½Ńü”ŃüŠŃü©ŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«Ķ©śõ║ŗŃü«ńø«µ¼Ī
ŃéżŃā│Ńāēµ│ĢÕłČÕ║”Ńü«Õ¤║ńżÄŃü©µŚźµ£¼µ│ĢŃü©Ńü«µ¦ŗķĆĀńÜäÕĘ«ńĢ░
ŃéżŃā│ŃāēŃü«õ╝ÜńżŠµ│ĢÕłČŃéÆńÉåĶ¦ŻŃüÖŃéŗõĖŖŃü¦ŃĆüŃüŠŃüÜĶ¬ŹĶŁśŃüÖŃü╣ŃüŹŃü»ŃĆüŃüØŃü«µ│ĢõĮōń│╗ŃüīµŚźµ£¼Ńü«ŃüØŃéīŃü©Ńü»µĀ╣µ£¼ńÜäŃü½ńĢ░Ńü¬ŃéŗŃü©ŃüäŃüåńé╣Ńü¦ŃüÖŃĆ鵌źµ£¼Ńü«µ│ĢõĮōń│╗ŃüīŃāēŃéżŃāäµ│ĢŃü«ÕĮ▒ķ¤┐ŃéÆÕ╝ĘŃüÅÕÅŚŃüæŃü¤Õż¦ķÖĖµ│Ģ’╝łCivil Law’╝ēń│╗Ńü½Õ▒×ŃüŚŃĆüÕłČիܵ│Ģ’╝łµØĪµ¢ć’╝ēŃü«Ķ¦ŻķćłŃéÆõĖ╗Ķ╗ĖŃü©ŃüÖŃéŗŃü«Ńü½Õ»ŠŃüŚŃĆüŃéżŃā│ŃāēŃü»Ķŗ▒ÕøĮµ│ĢŃéÆÕ¤║ńżÄŃü©ŃüÖŃéŗŃé│ŃāóŃā│Ńā╗ŃāŁŃā╝’╝łCommon Law’╝ēń│╗Ńü½Õ▒×ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
Ńé│ŃāóŃā│Ńā╗ŃāŁŃā╝õĮōń│╗Ńü½ŃüŖŃüäŃü”Ńü»ŃĆüÕøĮõ╝ÜŃüīÕ«ÜŃéüŃü¤ÕłČիܵ│Ģ’╝łAct’╝ēŃü©ÕÉīńŁēŃĆüŃüéŃéŗŃüäŃü»ŃüØŃéīõ╗źõĖŖŃü½ŃĆüĶŻüÕłżµēĆŃü«Õłżµ▒║’╝łCase Law’╝ēŃüīµ│ĢńÜäµŗśµØ¤ÕŖøŃéƵīüŃüżµ│Ģµ║ÉŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃü¤ŃüīŃüŻŃü”ŃĆüõ╝ÜńżŠĶ©Łń½ŗŃéäķüŗÕ¢ČŃü«Õ«¤ÕŗÖŃü½ŃüŖŃüäŃü”Ńü»ŃĆü2013Õ╣┤õ╝ÜńżŠµ│Ģ’╝łThe Companies Act’╝ēŃü«µØĪµ¢ćŃéÆńó║Ķ¬ŹŃüÖŃéŗŃüĀŃüæŃü¦Ńü»õĖŹÕŹüÕłåŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüŃĆīķĪ×õ╝╝Ńü«õ║ŗµĪłŃü½ŃüŖŃüäŃü”ĶŻüÕłżµēĆŃüīŃü®Ńü«ŃéłŃüåŃü¬Õłżµ¢ŁŃéÆõĖŗŃüŚŃü¤ŃüŗŃĆŹŃü©ŃüäŃüåÕģłõŠŗ’╝łPrecedent’╝ēŃü«Ķ¬┐µ¤╗ŃüīõĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¦ŃüÖŃĆéµØĪµ¢ćõĖŖŃü»µø¢µś¦Ńü¬Ķ”ÅÕ«ÜŃü¦ŃüéŃüŻŃü”ŃééŃĆüĶŻüÕłżµēĆŃü«Ķ¦ŻķćłŃü½ŃéłŃüŻŃü”ķØ×ÕĖĖŃü½ÕÄ│µĀ╝Ńü¬ķüŗńö©ŃüīŃü¬ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃé▒Ńā╝Ńé╣ŃüīÕżÜŃĆģŃüéŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüµŚźµ£¼ńÜäŃü¬ŃĆīµØĪµ¢ćŃü½µøĖŃüäŃü”ŃüäŃü¬ŃüäŃüŗŃéēÕĢÅķĪīŃü¬ŃüäŃĆŹŃü©ŃüäŃüåńÖ║µā│Ńü»ŃĆüŃéżŃā│ŃāēŃü¦Ńü»ķćŹÕż¦Ńü¬Ńā¬Ńé╣Ńé»Ķ”üÕøĀŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ńÅŠÕ£©Ńü«ŃéżŃā│ŃāēŃü«õ╝ÜńżŠµ│ĢÕłČŃü«µĀ╣Õ╣╣ŃéƵłÉŃüÖŃü«Ńü»ŃĆüŃĆī2013Õ╣┤õ╝ÜńżŠµ│Ģ’╝łThe Companies Act’╝ēŃĆŹŃü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüÕŹŖõĖ¢ń┤Ćõ╗źõĖŖŃü½ŃéÅŃü¤ŃéŖķüŗńö©ŃüĢŃéīŃü”ŃüŹŃü¤1956Õ╣┤õ╝ÜńżŠµ│ĢŃéÆÕģ©ķØóńÜäŃü½µö╣µŁŻŃüŚŃü¤ŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃéŖŃĆüńÅŠõ╗ŻńÜäŃü¬Ńé│Ńā╝ŃāØŃā¼Ńā╝ŃāłŃā╗Ńé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣Ńü«Õ╝ĘÕī¢ŃĆüÕ░æµĢ░µĀ¬õĖ╗Ńü«õ┐ØĶŁĘŃĆüõ╝üµźŁŃü«ńżŠõ╝ÜńÜäĶ▓¼õ╗╗’╝łCSR’╝ēŃü«ńŠ®ÕŗÖÕī¢Ńü¬Ńü®ŃüīńøøŃéŖĶŠ╝ŃüŠŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéńē╣Ńü½µŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīńĢÖµäÅŃüÖŃü╣ŃüŹŃü»ŃĆü2013Õ╣┤õ╝ÜńżŠµ│ĢŃüīÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«Ķ▓¼õ╗╗’╝łLiability of Directors’╝ēŃéÆÕż¦Õ╣ģŃü½Õ╝ĘÕī¢ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗńé╣Ńü¦ŃüÖŃĆéŃĆīõĖŹÕ▒źĶĪīĶ▓¼õ╗╗ĶĆģ’╝łOfficer in Default’╝ēŃĆŹŃü«µ”éÕ┐ĄŃüīµśÄńó║Õī¢ŃüĢŃéīŃĆüŃé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣ķüĢÕÅŹŃüīńÖ║ńö¤ŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕ«¤Ķ│¬ńÜäŃü½ńĄīÕ¢ČŃü½ķ¢óõĖÄŃüŚŃü”ŃüäŃéŗÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü»ŃĆüŃüØŃéīŃüīķØ×ÕĖĖÕŗżŃü¦ŃüéŃüŻŃü¤Ńü©ŃüŚŃü”ŃééŃĆüÕłæõ║ŗĶ▓¼õ╗╗ŃéÆÕɽŃéĆķćŹŃüäĶ▓¼õ╗╗ŃéÆĶ▓ĀŃüåÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃéżŃā│ŃāēŃüĖŃü«ķĆ▓Õć║ÕĮóµģŗŃü«ķüĖµŖ×Ńü©ķØ×Õģ¼ķ¢ŗõ╝ÜńżŠŃü«ńē╣µĆ¦
µŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīŃéżŃā│ŃāēŃü½µŗĀńé╣ŃéÆĶ©ŁŃüæŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüķ¦ÉÕ£©ÕōĪõ║ŗÕŗÖµēĆ’╝łLiaison Office’╝ēŃĆüµö»Õ║Ś’╝łBranch Office’╝ēŃĆüŃāŚŃāŁŃéĖŃé¦Ńé»ŃāłŃé¬ŃāĢŃéŻŃé╣’╝łProject Office’╝ēŃĆüµ£ēķÖÉĶ▓¼õ╗╗õ║ŗµźŁńĄäÕÉł’╝łLLP’╝ēŃĆüŃüØŃüŚŃü”ńÅŠÕ£░µ│Ģõ║║’╝łCompany’╝ēŃü©ŃüäŃüŻŃü¤ķüĖµŖ×ĶéóŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃü«õĖŁŃü¦ŃééŃĆüÕ£¦ÕĆÆńÜäÕżÜµĢ░Ńü«µŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīķüĖµŖ×ŃüÖŃéŗŃü«ŃüīŃĆīķØ×Õģ¼ķ¢ŗõ╝ÜńżŠ’╝łPrivate Limited Company’╝ēŃĆŹŃü¦ŃüÖŃĆé
ķØ×Õģ¼ķ¢ŗõ╝ÜńżŠŃü©Õģ¼ķ¢ŗõ╝ÜńżŠŃü«µ»öĶ╝ā
ŃĆīÕģ¼ķ¢ŗõ╝ÜńżŠ’╝łPublic Limited Company’╝ēŃĆŹŃü©ŃüäŃüåÕÉŹń¦░ŃüŗŃéēŃĆüõĖŖÕĀ┤õ╝üµźŁŃü«ŃéłŃüåŃü¬ŃéżŃāĪŃā╝ŃéĖŃéƵīüŃü¤ŃéīŃüīŃüĪŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃéżŃā│ŃāēŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕģ¼ķ¢ŗõ╝ÜńżŠŃü»ŃĆüÕ┐ģŃüÜŃüŚŃééõĖŖÕĀ┤õ╝üµźŁŃéƵäÅÕæ│ŃüŚŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüŃé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣Ķ”üõ╗ČŃü»ķØ×Õģ¼ķ¢ŗõ╝ÜńżŠŃü½µ»öŃü╣Ńü”ĶæŚŃüŚŃüÅÕÄ│µĀ╝Ńü¦ŃüÖŃĆ鵌źµ£¼õ╝üµźŁŃüī100%ÕŁÉõ╝ÜńżŠ’╝łŃüŠŃü¤Ńü»ŃüØŃéīŃü½Ķ┐æŃüäÕĮóµģŗ’╝ēŃü©ŃüŚŃü”ńÅŠÕ£░µ│Ģõ║║ŃéÆĶ©Łń½ŗŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüµäŵĆص▒║Õ«ÜŃü«Ķ┐ģķƤµĆ¦Ńü©Ńé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣Ńé│Ńé╣ŃāłŃü«Ķ”│ńé╣ŃüŗŃéēŃĆüŃüéŃüłŃü”Õģ¼ķ¢ŗõ╝ÜńżŠŃéÆķüĖµŖ×ŃüÖŃéŗŃāĪŃā¬ŃāāŃāłŃü»ŃĆüÕ░åµØźńÜäŃü¬ńÅŠÕ£░Ńü¦Ńü«Õż¦Ķ”ŵ©ĪĶ│ćķćæĶ¬┐ķüöŃéäõĖŖÕĀ┤ŃéÆÕģĘõĮōńÜäŃü½Ķ”¢ķćÄŃü½ÕģźŃéīŃü”ŃüäŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃéÆķÖżŃüŹŃĆüķÖÉÕ«ÜńÜäŃü¦ŃüÖŃĆé
õ╗źõĖŗŃü«ĶĪ©Ńü»ŃĆüķØ×Õģ¼ķ¢ŗõ╝ÜńżŠŃü©Õģ¼ķ¢ŗõ╝ÜńżŠŃü«õĖ╗Ńü¬Ķ”üõ╗ČŃéƵ»öĶ╝āŃüŚŃü¤ŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆé
| ķĀģńø« | ķØ×Õģ¼ķ¢ŗõ╝ÜńżŠ (Private Limited Company) | Õģ¼ķ¢ŗõ╝ÜńżŠ (Public Limited Company) |
| µ£ĆõĮĵĀ¬õĖ╗µĢ░ | 2ÕÉŹ’╝łµ£ĆÕż¦200ÕÉŹ’╝ē | 7ÕÉŹ’╝łõĖŖķÖÉŃü¬ŃüŚ’╝ē |
| µ£ĆõĮÄÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣µĢ░ | 2ÕÉŹ | 3ÕÉŹ |
| µĀ¬Õ╝ÅĶŁ▓µĖĪ | իܵ¼Š’╝łAOA’╝ēŃü½ŃéłŃéŖĶŁ▓µĖĪŃüīÕłČķÖÉŃüĢŃéīŃéŗ | Ķć¬ńö▒Ńü½ĶŁ▓µĖĪÕÅ»ĶāĮ |
| Ķ│ćķćæĶ¬┐ķüö | Õģ¼Õŗ¤’╝łIPOńŁē’╝ēŃü»ń”üµŁó | Õģ¼Õŗ¤ŃüīÕÅ»ĶāĮ |
| Ńé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣ | µ»öĶ╝āńÜäńĘ®ŃéäŃüŗ | ķØ×ÕĖĖŃü½ÕÄ│µĀ╝’╝łńŗ¼ń½ŗÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«ķüĖõ╗╗ńŠ®ÕŗÖńŁē’╝ē |
µö»Õ║ŚÕĮóµģŗŃü«Ńā¬Ńé╣Ńé»Ńü©ńÅŠÕ£░µ│Ģõ║║Ńü«Õä¬õĮŹµĆ¦
µŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü«õĖŁŃü½Ńü»ŃĆüÕĮōÕłØŃü»µö»Õ║ŚÕĮóµģŗŃü¦Ńü«ķĆ▓Õć║ŃéƵż£Ķ©ÄŃüÖŃéŗŃé▒Ńā╝Ńé╣ŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüŃéżŃā│ŃāēŃü½ŃüŖŃüäŃü”Ńü»ŃĆüµö»Õ║ŚŃü»Õż¢ÕøĮĶ”¬õ╝ÜńżŠŃü©ÕÉīõĖĆŃü«µ│Ģõ║║µĀ╝Ńü©Ńü┐Ńü¬ŃüĢŃéīŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüµö»Õ║ŚŃüīµŖ▒ŃüłŃü¤µ│ĢńÜäĶ▓¼õ╗╗’╝łÕźæń┤äõĖŹÕ▒źĶĪīŃĆüõĖŹµ│ĢĶĪīńé║Ķ▓¼õ╗╗ŃĆüń©ÄÕŗÖĶ©┤Ķ©¤ńŁē’╝ēŃüīŃĆüńø┤µÄźµŚźµ£¼Ńü«Ķ”¬õ╝ÜńżŠŃü½ÕÅŖŃüČŃü©ŃüäŃüåķćŹÕż¦Ńü¬Ńā¬Ńé╣Ńé»ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéÕźæń┤äńżŠõ╝ÜŃü¦ŃüéŃéŖĶ©┤Ķ©¤Ńā¬Ńé╣Ńé»Ńüīķ½śŃüäŃéżŃā│ŃāēŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüÕłźµ│Ģõ║║µĀ╝Ńü¦ŃüéŃéŗńÅŠÕ£░µ│Ģõ║║’╝łSubsidiary’╝ēŃéÆĶ©Łń½ŗŃüŚŃĆüĶ”¬õ╝ÜńżŠŃüĖŃü«Ńā¬Ńé╣Ńé»ķü«µ¢Ł’╝łLimited LiabilityŃü½ŃéłŃéŗõ┐ØĶŁĘ’╝ēŃéÆÕø│ŃéŗŃüōŃü©Ńü»ŃĆüµ│ĢÕŗÖµł”ńĢźõĖŖŃü«Õ«Üń¤│Ńü©Ķ©ĆŃüłŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüĶŻĮķĆĀµźŁŃü¬Ńü®ÕżÜŃüÅŃü«µźŁń©«Ńü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüµö»Õ║ŚÕĮóµģŗŃü¦Ńü»µ┤╗ÕŗĢń»äÕø▓ŃüīÕłČķÖÉŃüĢŃéīŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃüīŃüéŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüõ║ŗµźŁŃü«µŗĪÕ╝ĄµĆ¦Ńü©ŃüäŃüåĶ”│ńé╣ŃüŗŃéēŃééńÅŠÕ£░µ│Ģõ║║ŃüīµÄ©Õź©ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ŃāćŃéĖŃé┐Ńā½Õī¢ŃüĢŃéīŃü¤ŃéżŃā│Ńāēõ╝ÜńżŠĶ©Łń½ŗµēŗńČÜŃüŹ’╝ÜSPICe+Ńü«ķüŗńö©Õ«¤ÕŗÖ

ŃéżŃā│ŃāēŃü½ŃüŖŃüæŃéŗõ╝ÜńżŠĶ©Łń½ŗµēŗńČÜŃüŹŃü»ŃĆüõ╗źÕēŹŃü»ĶżćµĢ░Ńü«µøĖķĪ×ŃéÆńē®ńÉåńÜäŃü½µÅÉÕć║ŃüŚŃĆüÕÉäń£üÕ║üŃü«µē┐Ķ¬ŹŃéÆķĀåµ¼ĪÕÅ¢ÕŠŚŃüŚŃü”ŃüäŃüÅńģ®ķøæŃü¬ŃééŃü«Ńü¦ŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüńÅŠÕ£©Ńü»ŃĆīSPICe+’╝łSimplified Proforma for Incorporating Company Electronically Plus’╝ÜForm INC-32’╝ēŃĆŹŃü©Õæ╝Ńü░ŃéīŃéŗńĄ▒ÕÉłŃé”Ńé¦Ńā¢ŃāĢŃé®Ńā╝ŃāĀŃü½õĖĆÕģāÕī¢ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖŃĆüõ╝ÜńżŠĶ©Łń½ŗńÖ╗Ķ©śŃĆüDIN’╝łÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ĶŁśÕłźńĢ¬ÕÅĘ’╝ēŃĆüPAN’╝łń┤Źń©ÄĶĆģńĢ¬ÕÅĘ’╝ēŃĆüTAN’╝łµ║ɵ│ēÕŠ┤ÕÅÄńĢ¬ÕÅĘ’╝ēŃü¬Ńü®Ńü«ÕÅ¢ÕŠŚŃüīÕŹśõĖĆŃü«ŃāŚŃāŁŃé╗Ńé╣Ńü¦Õ«īńĄÉŃüÖŃéŗŃéłŃüåŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
SPICe+ŃéÆńö©ŃüäŃü¤Ķ©Łń½ŗŃāŚŃāŁŃé╗Ńé╣Ńü»ŃĆüÕż¦ŃüŹŃüÅŃĆīPart A’╝łÕĢåÕÅĘõ║łń┤ä’╝ēŃĆŹŃü©ŃĆīPart B’╝łĶ©Łń½ŗńö│Ķ½ŗŃüŖŃéłŃü│ÕÉäń©«ńÖ╗ķī▓’╝ēŃĆŹŃü«2µ«ĄķÜÄŃü½ÕłåŃüŗŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
Ķ©Łń½ŗŃāŚŃāŁŃé╗Ńé╣Ńü«Õģ©õĮōÕāÅ
| µ«ĄķÜÄ | µēŗńČÜŃüŹÕåģÕ«╣ | µ│ĢńÜäńĢÖµäÅńé╣ |
| õ║ŗÕēŹµ║¢ÕéÖ | ŃāćŃéĖŃé┐Ńā½ńĮ▓ÕÉŹĶ©╝µśÄµøĖ (DSC) Ńü«ÕÅ¢ÕŠŚ ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ÕĆÖĶŻ£ĶĆģŃü«DSCŃéÆÕÅ¢ÕŠŚŃüÖŃéŗŃĆé | 2021Õ╣┤õ╗źķÖŹŃĆüµ£Ćķ½śŃā¼ŃāÖŃā½Ńü«ŃĆīClass 3 DSCŃĆŹŃüīÕ┐ģķĀłŃĆ鵌źµ£¼Õ£©õĮÅĶĆģŃü«ÕĀ┤ÕÉłŃĆüµ£¼õ║║ńó║Ķ¬ŹµøĖķĪ×Ńü«Õģ¼Ķ©╝Ńā╗ŃéóŃāØŃé╣ŃāåŃéŻŃā╝Ńā”Ķ¬ŹĶ©╝ŃüīÕ┐ģĶ”üŃĆé |
| Part A | ÕĢåÕÅĘõ║łń┤ä (Name Reservation) õ╝ÜńżŠńÖ╗Ķ©śÕ▒Ć (ROC) ŃüĖÕĢåÕÅĘŃü«µē┐Ķ¬Źńö│Ķ½ŗŃéÆĶĪīŃüåŃĆé | ķĪ×õ╝╝ÕĢåÕÅĘŃü«Õ»®µ¤╗Ńü»ķØ×ÕĖĖŃü½ÕÄ│µĀ╝ŃĆ鵌óÕŁśŃü«õ╝ÜńżŠÕÉŹŃéäÕĢ嵩ÖŃü©ńÖ║ķ¤│Ńüīõ╝╝Ńü”ŃüäŃéŗŃüĀŃüæŃü¦ŃééµŗÆńĄČŃüĢŃéīŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŗŃĆé |
| Part B | ńĄ▒ÕÉłńö│Ķ½ŗ Ķ©Łń½ŗńÖ╗Ķ©śŃĆüDINŃĆüPANŃĆüTANŃĆüEPFO/ESICŃĆüķŖĆĶĪīÕÅŻÕ║¦ķ¢ŗĶ©ŁńŁēŃéÆõĖƵŗ¼ńö│Ķ½ŗŃĆé | Ķ”¬õ╝ÜńżŠŃüŗŃéēŃü«ÕĢåÕÅĘõĮ┐ńö©Ķ©▒Ķ½ŠµøĖ (NOC) ŃéäŃĆüիܵ¼Š (MOA/AOA) Ńü«µÅÉÕć║ŃüīÕ┐ģĶ”üŃĆéÕż¢ÕøĮµĀ¬õĖ╗Ńü«ÕĀ┤ÕÉłŃü»ŃéóŃāØŃé╣ŃāåŃéŻŃā╝Ńā”Ķ¬ŹĶ©╝ŃüĢŃéīŃü¤µøĖķĪ×ŃüīÕ┐ģķĀłŃĆé |
| Ķ©Łń½ŗÕŠī | Ķ©Łń½ŗĶ©╝µśÄµøĖ (COI) ÕÅ¢ÕŠŚ Õ»®µ¤╗Õ«īõ║åÕŠīŃĆüŃāćŃéĖŃé┐Ńā½ÕĮóÕ╝ÅŃü¦ńÖ║ĶĪīŃüĢŃéīŃéŗŃĆé | COIńÖ║ĶĪīµŚźŃüīµ│Ģõ║║Ńü«µłÉń½ŗµŚźŃü©Ńü¬ŃéŗŃĆéŃüōŃéīŃéÆŃééŃüŻŃü”µ│Ģõ║║µĀ╝ŃéÆÕÅ¢ÕŠŚŃüÖŃéŗŃĆé |
իܵ¼ŠõĮ£µłÉŃü½ŃüŖŃüæŃéŗµł”ńĢźńÜäĶ”¢ńé╣
ŃéżŃā│ŃāēŃü«õ╝ÜńżŠµ│ĢŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüիܵ¼ŠŃü»ŃĆīÕ¤║µ£¼Õ«Üµ¼Š’╝łMemorandum of Association’╝ÜMOA’╝ēŃĆŹŃü©ŃĆīķÖäÕ▒×իܵ¼Š’╝łArticles of Association’╝ÜAOA’╝ēŃĆŹŃü«õ║īŃüżŃü«µ¢ćµøĖŃü½ÕłåŃüŗŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃéēŃü»õ╝ÜńżŠŃü«µå▓µ│ĢŃü©ŃééĶ©ĆŃüåŃü╣ŃüŹµ£ĆķćŹĶ”üµ¢ćµøĖŃü¦ŃüÖŃĆé
ńē╣Ńü½MOAŃü«ŃĆīńø«ńÜäµØĪķĀģ’╝łObject Clause’╝ēŃĆŹŃü»ŃĆüõ╝ÜńżŠŃü«µ┤╗ÕŗĢń»äÕø▓ŃéƵ│ĢńÜäŃü½ńö╗Õ«ÜŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃé│ŃāóŃā│Ńā╗ŃāŁŃā╝Ńü½Ńü»ŃĆīŃé”Ńā½ŃāłŃā®Ńā╗ŃāōŃā¼Ńé╣Ńü«µ│ĢńÉå’╝łDoctrine of Ultra Vires’╝ēŃĆŹŃü©ŃüäŃüåµ”éÕ┐ĄŃüīŃüéŃéŖŃĆüõ╝ÜńżŠŃü»MOAŃü½Ķ©śĶ╝ēŃüĢŃéīŃü¤ńø«ńÜäõ╗źÕż¢Ńü«ĶĪīńé║ŃéÆĶĪīŃüåµ│ĢńÜäĶāĮÕŖøŃéƵīüŃü¤Ńü¬ŃüäŃü©Ķ¦ŻŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃééŃüŚõ╝ÜńżŠŃüīMOAŃü«ń»äÕø▓Õż¢Ńü«Õźæń┤äŃéÆńĘĀńĄÉŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüØŃü«Õźæń┤äŃü»ńäĪÕŖ╣’╝łVoid’╝ēŃü©Ńü¬ŃéŖŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü»µ©®ķÖÉÕż¢ĶĪīńé║Ńü©ŃüŚŃü”Ńü«Ķ▓¼õ╗╗ŃéÆÕĢÅŃéÅŃéīŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃü¤ŃüīŃüŻŃü”ŃĆüńÅŠÕ£©õ║łÕ«ÜŃüŚŃü”ŃüäŃéŗõ║ŗµźŁŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüÕ░åµØźńÜäŃü½ĶĪīŃüåÕÅ»ĶāĮµĆ¦Ńü«ŃüéŃéŗõ║ŗµźŁŃééÕɽŃéüŃü”ŃĆüńø«ńÜäµØĪķĀģŃéÆÕīģµŗ¼ńÜäŃüŗŃüżÕģĘõĮōńÜäŃü½ŃāēŃā®ŃāĢŃāåŃéŻŃā│Ńé░ŃüÖŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü¤ŃĆüAOAŃü»õ╝ÜńżŠŃü«Õåģķā©Ķ”ÅÕēćŃéÆÕ«ÜŃéüŃüŠŃüÖŃĆéÕÉłÕ╝üõ║ŗµźŁ’╝łJV’╝ēŃü¬Ńü®Ńü¦µĀ¬õĖ╗ķ¢ōÕźæń┤ä’╝łSHA’╝ēŃéÆńĘĀńĄÉŃüŚŃü”ŃüäŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüØŃü«ÕåģÕ«╣’╝łµŗÆÕÉ”µ©®ŃĆüµĀ¬Õ╝ÅĶŁ▓µĖĪÕłČķÖÉńŁē’╝ēŃéÆAOAŃü½µśÄĶ©śŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīµźĄŃéüŃü”ķćŹĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆéŃéżŃā│ŃāēŃü«ÕłżõŠŗŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüµĀ¬õĖ╗ķ¢ōÕźæń┤äŃü«ÕåģÕ«╣Ńü»AOAŃü½ÕÅŹµśĀŃüĢŃéīŃü”ÕłØŃéüŃü”õ╝ÜńżŠŃéƵŗśµØ¤ŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüåÕĤÕēćŃüīńó║ń½ŗŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃü¤ŃéüŃü¦ŃüÖŃĆé
µŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīńø┤ķØóŃüÖŃéŗŃéżŃā│ŃāēÕø║µ£ēŃü«Ńé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣Ķ¬▓ķĪī
ŃāćŃéĖŃé┐Ńā½Õī¢Ńü½ŃéłŃéŖĶ©Łń½ŗµēŗńČÜŃüŹĶć¬õĮōŃü»Ķ┐ģķƤÕī¢ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü½Ńü©ŃüŻŃü”Õ«¤Ķ│¬ńÜäŃü¬ŃāÅŃā╝ŃāēŃā½Ńü©Ńü¬Ńéŗµ│ĢńÜäĶ”üõ╗ČŃüīŃüäŃüÅŃüżŃüŗÕŁśÕ£©ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃüōŃü¦Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼µ│ĢŃü©Ńü«ķüĢŃüäŃüīķÜøń½ŗŃüżõĖ╗Ķ”üŃü¬Ķ½¢ńé╣ŃéÆĶ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
Õ▒ģõĮÅÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣’╝łResident Director’╝ēŃü«ńó║õ┐ØŃü©µ│ĢńÜäĶ”üõ╗Č
2013Õ╣┤õ╝ÜńżŠµ│Ģń¼¼149µØĪń¼¼3ķĀģŃü»ŃĆüŃĆīŃüÖŃü╣Ńü”Ńü«õ╝ÜńżŠŃü»ŃĆüÕēŹµÜ”Õ╣┤Ńü½ŃüŖŃüäŃü”ÕÉłĶ©ł182µŚźõ╗źõĖŖŃéżŃā│ŃāēŃü½µ╗×Õ£©ŃüŚŃü¤ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ŃéÆŃĆüÕ░æŃü¬ŃüÅŃü©Ńéé1ÕÉŹńĮ«ŃüŗŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéēŃü¬ŃüäŃĆŹŃü©Ķ”ÅÕ«ÜŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
µŚźµ£¼Ńü¦Ńü»ŃĆü2015Õ╣┤Ńü«µ│ĢÕŗÖń£üķĆÜķüöŃüŖŃéłŃü│ŃüØŃü«ÕŠīŃü«ķüŗńö©Õżēµø┤Ńü½ŃéłŃéŖŃĆüõ╗ŻĶĪ©ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«Õģ©ÕōĪŃüīµŚźµ£¼ķØ×Õ▒ģõĮÅĶĆģŃü¦ŃüéŃüŻŃü”Ńé鵌źµ£¼µ│Ģõ║║Ńü«Ķ©Łń½ŗŃüīÕÅ»ĶāĮŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖŃĆüÕż¢Ķ│ćń│╗õ╝üµźŁŃü»µŚźµ£¼Ńü½Õ▒ģõĮÅŃüÖŃéŗõ╗ŻĶĪ©ĶĆģŃéÆńĮ«ŃüÅŃüōŃü©Ńü¬ŃüÅķĆ▓Õć║Ńü¦ŃüŹŃéŗŃéłŃüåŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüŃéżŃā│ŃāēŃü¦Ńü»ķĆåŃü½ŃĆüÕ┐ģŃüÜ1ÕÉŹŃü»ŃĆīÕ▒ģõĮÅĶĆģŃĆŹŃéÆÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü©ŃüŚŃü”ķüĖõ╗╗ŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüŃé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣ķüĢÕÅŹŃéäń©ÄÕŗÖõĖŖŃü«ÕĢÅķĪīŃüīńÖ║ńö¤ŃüŚŃü¤ķÜøŃü½ŃĆüŃéżŃā│ŃāēŃü«ń«ĪĶĮ䵩®ÕåģŃü¦Ķ▓¼õ╗╗ŃéÆĶ┐ĮÕÅŖŃü¦ŃüŹŃéŗõ║║ńē®ŃéÆńó║õ┐ØŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüåµö┐ńŁ¢ńÜäµäÅÕø│ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
µ¢░Ķ©Łõ╝ÜńżŠŃü«ÕĀ┤ÕÉłŃĆüĶ©Łń½ŗµŚźŃüŗŃéēŃüØŃü«õ╝ÜĶ©łÕ╣┤Õ║”µ£½ŃüŠŃü¦Ńü«µ£¤ķ¢ōŃü½ŃüŖŃüæŃéŗµ╗×Õ£©µŚźµĢ░Ńü¦µ»öõŠŗĶ©łń«Ś’╝łPro-rata’╝ēŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆ鵌źµ£¼ŃüŗŃéēķ¦ÉÕ£©ÕōĪŃéƵ┤ŠķüŻŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüĶ©Łń½ŗńø┤ÕŠīŃü»ŃüØŃü«ķ¦ÉÕ£©ÕōĪŃüīŃüŠŃüĀµ╗×Õ£©µŚźµĢ░Ńü«Ķ”üõ╗ČŃéƵ║ĆŃü¤ŃüŚŃü”ŃüäŃü¬ŃüäŃüōŃü©ŃüīõĖĆĶł¼ńÜäŃü¦ŃüÖŃĆéŃüØŃü«Ńü¤ŃéüŃĆüĶ©Łń½ŗÕĮōÕłØŃü»ńÅŠÕ£░Ńü«Ńé│Ńā│ŃéĄŃā½Ńé┐Ńā│ŃāłŃéäõ┐ĪķĀ╝Ńü¦ŃüŹŃéŗŃéżŃā│Ńāēõ║║ÕŠōµźŁÕōĪŃéÆõĖƵÖéńÜäŃü½ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü©ŃüŚŃü”ķüĖõ╗╗ŃüŚŃĆüķ¦ÉÕ£©ÕōĪŃüīĶ”üõ╗ČŃéƵ║ĆŃü¤ŃüŚŃü¤µÖéńé╣Ńü¦õ║żõ╗ŻŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüåµēŗµ│ĢŃüīµÄĪŃéēŃéīŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
õ║ŗµźŁķ¢ŗÕ¦ŗÕ▒Ŗ’╝łCommencement of Business’╝ēŃü©Ķ│ćµ£¼ķćæµ│©ÕģźŃü«Ńé┐ŃéżŃā¤Ńā│Ńé░
Ķ©Łń½ŗĶ©╝µśÄµøĖ’╝łCOI’╝ēŃéÆÕÅ¢ÕŠŚŃüŚŃü”ŃééŃĆüµ│ĢńÜäŃü½õ║ŗµźŁŃéÆķ¢ŗÕ¦ŗŃü¦ŃüŹŃéŗŃéÅŃüæŃü¦Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆé2019Õ╣┤Ńü«õ╝ÜńżŠµ│Ģµö╣µŁŻŃü½ŃéłŃéŖÕŠ®µ┤╗ŃüŚŃü¤ń¼¼10AµØĪŃü½Õ¤║ŃüźŃüŹŃĆüĶ©Łń½ŗŃüŗŃéē180µŚźõ╗źÕåģŃü½ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«ŃāŚŃāŁŃé╗Ńé╣ŃéÆńĄīŃü”ŃĆīõ║ŗµźŁķ¢ŗÕ¦ŗÕ▒Ŗ’╝łForm INC-20A’╝ēŃĆŹŃéÆROCŃü½µÅÉÕć║ŃüÖŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
- ķŖĆĶĪīÕÅŻÕ║¦Ńü«ķ¢ŗĶ©Ł’╝ÜCOIÕÅ¢ÕŠŚÕŠīŃĆüķƤŃéäŃüŗŃü½µ│Ģõ║║ÕÅŻÕ║¦ŃéÆķ¢ŗĶ©ŁŃüÖŃéŗŃĆé
- Ķ│ćµ£¼ķćæŃü«ķĆüķćæ’╝ÜÕÉäµĀ¬õĖ╗’╝łńÖ║ĶĄĘõ║║’╝ēŃü»ŃĆüÕ╝ĢÕÅŚµĀ¬Õ╝ÅŃü«Õģ©ķĪŹŃéÆõ╝ÜńżŠŃü«ķŖĆĶĪīÕÅŻÕ║¦Ńü½ķĆüķćæŃüÖŃéŗŃĆé
- INC-20AŃü«µÅÉÕć║’╝ÜÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ŃüīŃĆüµĀ¬õĖ╗ŃüŗŃéēŃü«µēĢĶŠ╝ŃüīÕ«īõ║åŃüŚŃü¤ŃüōŃü©ŃéÆÕ«ŻĶ©ĆŃüŚŃĆüķŖĆĶĪīŃü«ÕģźķćæĶ©╝µśÄńŁēŃéƵĘ╗õ╗śŃüŚŃü”µÅÉÕć║ŃüÖŃéŗŃĆé
µŚźµ£¼Ńü¦Ńü«õ╝ÜńżŠĶ©Łń½ŗ’╝łńÖ║ĶĄĘĶ©Łń½ŗ’╝ēŃü¦Ńü»ŃĆüĶ©Łń½ŗńÖ╗Ķ©śńö│Ķ½ŗµÖéŃü½Ķ│ćµ£¼ķćæŃü«µēĢĶŠ╝Ķ©╝µśÄµøĖŃéƵĘ╗õ╗śŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüńÖ╗Ķ©śÕ«īõ║åµÖéńé╣Ńü¦Ķ│ćµ£¼ķćæŃü«µēĢĶŠ╝Ńü»Õ«īõ║åŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéÕ»Šńģ¦ńÜäŃü½ŃĆüŃéżŃā│ŃāēŃü¦Ńü»ŃĆīĶ©Łń½ŗńÖ╗Ķ©ś’╝łCOIńÖ║ĶĪī’╝ēŌåÆ ķŖĆĶĪīÕÅŻÕ║¦ķ¢ŗĶ©Ł ŌåÆ Ķ│ćµ£¼ķćæķĆüķćæ ŌåÆ õ║ŗµźŁķ¢ŗÕ¦ŗÕ▒ŖŃĆŹŃü©ŃüäŃüåķĀåÕ║ÅŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃééŃüŚ180µŚźõ╗źÕåģŃü½INC-20AŃéƵÅÉÕć║ŃüŚŃü¬ŃüŗŃüŻŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüROCŃü»ŃĆīõ╝ÜńżŠŃüīõ║ŗµźŁŃéÆĶĪīŃüŻŃü”ŃüäŃü¬ŃüäŃĆŹŃü©Ńü┐Ńü¬ŃüŚŃĆüõ╝ÜńżŠµ│Ģń¼¼248µØĪŃü½Õ¤║ŃüźŃüŹõ╝ÜńżŠŃü«ńÖ╗Ķ©śŃéÆĶüʵ©®Ńü¦µŖ╣µČł’╝łStrike Off’╝ēŃüÖŃéŗµ©®ķÖÉŃéƵīüŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéĶ┐æµÖéŃü« Sita Ram Singhal v. Registrar of Companies (NCLAT, 2023) Ńü¬Ńü®Ńü«ÕłżõŠŗŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüõ║ŗµźŁÕ«¤µģŗŃüīŃü¬ŃüäŃĆüŃüéŃéŗŃüäŃü»Ńé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣ŃéƵĆĀŃüŻŃü”ŃüäŃéŗõ╝ÜńżŠŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗĶŻüÕłżµēĆŃü«Õ¦┐ÕŗóŃü»ÕÄ│µĀ╝Ńü¦ŃüéŃéŗŃüōŃü©Ńüīńż║ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
Õż¢ÕøĮńé║µø┐ń«ĪńÉåµ│Ģ’╝łFEMA’╝ēŃü½Õ¤║ŃüźŃüÅÕĀ▒ÕæŖńŠ®ÕŗÖ
ŃéżŃā│ŃāēŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕż¢ÕøĮõ╝üµźŁŃü½ŃéłŃéŗµŖĢĶ│ćŃü»ŃĆüŃéżŃā│Ńāēµ║¢ÕéÖķŖĆĶĪī’╝łRBI’╝ēŃüīµēĆń«ĪŃüÖŃéŗÕż¢ÕøĮńé║µø┐ń«ĪńÉåµ│Ģ’╝łForeign Exchange Management Act, 1999’╝ÜFEMA’╝ēŃüŖŃéłŃü│ķ¢óķĆŻĶ”ÅÕēćŃü½ŃéłŃüŻŃü”ÕÄ│µĀ╝Ńü½Ķ”ÅÕłČŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéõ╝ÜńżŠµ│ĢõĖŖŃü«µēŗńČÜŃüŹŃü©Ńü»ÕłźŃü½ŃĆüRBIŃüĖŃü«ÕĀ▒ÕæŖńŠ®ÕŗÖŃüīÕŁśÕ£©ŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüåõ║īķ揵¦ŗķĆĀŃüīŃĆüŃé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣ŃéÆĶżćķøæŃü½ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
µŚźµ£¼Ķ”¬õ╝ÜńżŠŃüŗŃéēŃéżŃā│ŃāēÕŁÉõ╝ÜńżŠŃüĖĶ│ćµ£¼ķćæŃéÆķĆüķćæŃüŚŃĆüµĀ¬Õ╝ÅŃéÆÕē▓ŃéŖÕĮōŃü”Ńü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüØŃü«Õē▓ÕĮōµŚźŃüŗŃéē30µŚźõ╗źÕåģŃü½ŃĆüRBIŃü«ŃāØŃā╝Ńé┐Ńā½ŃéĄŃéżŃāł’╝łFIRMS’╝ēŃéÆķĆÜŃüśŃü”ŃĆīForm FC-GPRŃĆŹŃéƵÅÉÕć║ŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéµÅÉÕć║ķüģÕ╗ČŃü»FEMAķüĢÕÅŹŃü©Ńü┐Ńü¬ŃüĢŃéīŃĆüRBIŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”ķüĢÕÅŹŃéÆĶ¬ŹŃéüŃĆüÕÆīĶ¦Żķćæ’╝łCompounding Fee’╝ēŃéƵö»µēĢŃüåŃĆīŃé│Ńā│ŃāæŃé”Ńā│ŃāćŃéŻŃā│Ńé░’╝łCompounding’╝ēŃĆŹµēŗńČÜŃüŹŃüīÕ┐ģĶ”üŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéRBI compounds FEMA case against Genpact India Ńü«ŃéłŃüåŃü¬õ║ŗõŠŗŃüŗŃéēŃééÕłåŃüŗŃéŗŃéłŃüåŃü½ŃĆüÕż¦µēŗÕżÜÕøĮń▒Źõ╝üµźŁŃü¦ŃüéŃüŻŃü”ŃééµēŗńČÜŃüŹŃü«ķüģÕ╗ČŃü½ŃéłŃéŖŃāÜŃāŖŃā½ŃāåŃéŻŃéÆĶ¬▓ŃüĢŃéīŃéŗŃé▒Ńā╝Ńé╣ŃüīµĢŻĶ”ŗŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ŃéżŃā│ŃāēŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«µ│ĢńÜäĶ▓¼õ╗╗Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗµ£Ćµ¢░Ńü«ÕÅĖµ│ĢÕłżµ¢Ł
ŃéżŃā│ŃāēŃü½ŃüŖŃüäŃü”ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ŃéÆÕŗÖŃéüŃéŗŃüōŃü©Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼õ╗źõĖŖŃü½ķćŹÕż¦Ńü¬µ│ĢńÜäĶ▓¼õ╗╗ŃéÆõ╝┤ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéńē╣Ńü½ŃĆīŃü┐Ńü¬ŃüŚĶ▓¼õ╗╗’╝łVicarious Liability’╝ēŃĆŹŃü«ķü®ńö©ń»äÕø▓Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüµ£Ćµ¢░Ńü«µ£Ćķ½śĶŻüÕłżµ▒║ŃéÆĶĖÅŃüŠŃüłŃü¤ńÉåĶ¦ŻŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆé
õ╝ÜńżŠµ│Ģń¼¼2µØĪń¼¼60ķĀģŃü»ŃĆüŃĆīõĖŹÕ▒źĶĪīĶ▓¼õ╗╗ĶĆģ’╝łOfficer in Default’╝ēŃĆŹŃéÆÕ«ÜńŠ®ŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüõ╝ÜńżŠŃüīµ│Ģõ╗żķüĢÕÅŹŃéÆńŖ»ŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüķ¢óõĖÄŃüŚŃü¤ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüÕģ©ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ŃüīĶ▓¼õ╗╗ŃéÆÕĢÅŃéÅŃéīŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü¦ŃüéŃéŗŃü©ŃüäŃüåÕ£░õĮŹŃü«Ńü┐ŃéÆŃééŃüŻŃü”Ķć¬ÕŗĢńÜäŃü½Õłæõ║ŗĶ▓¼õ╗╗ŃéÆĶ▓ĀŃéÅŃüøŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃéŗŃüŗŃü©ŃüäŃüåńé╣Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüÕÅĖµ│ĢÕłżµ¢ŁŃüīµÅ║ŃéīÕŗĢŃüäŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüōŃü«ńé╣Ńü½ķ¢óŃüŚŃĆü2025Õ╣┤Ńü«µ£Ćķ½śĶŻüÕłżµ▒║ Sanjay Dutt v. State of Haryana (Supreme Court of India, 2025) Ńü»µźĄŃéüŃü”ķćŹĶ”üŃü¬µīćķćØŃéÆńż║ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéµ£¼Õłżµ▒║Ńü½ŃüŖŃüäŃü”µ£Ćķ½śĶŻüÕłżµēĆŃü»ŃĆüńē╣Õłźµ│Ģ’╝łńÆ░Õóāµ│Ģķ¢óķĆŻ’╝ēķüĢÕÅŹŃü«õ║ŗµĪłŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«ŃĆīŃü┐Ńü¬ŃüŚĶ▓¼õ╗╗ŃĆŹŃéÆĶ¬ŹŃéüŃéŗŃü¤ŃéüŃü½Ńü»ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«ŃüäŃüÜŃéīŃüŗŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüéŃéŗŃü©Õłżńż║ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
- ÕĮōĶ®▓ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ŃüīńŖ»ńĮ¬ĶĪīńé║Ńü½ń®ŹµźĄńÜäŃü½ķ¢óõĖÄŃüŚŃü¤ŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»Õģ▒Ķ¼ĆŃüŚŃü¤Ńü©ŃüäŃüåÕģĘõĮōńÜäŃü¬Ķ©╝µŗĀŃüīŃüéŃéŗŃüōŃü©ŃĆé
- ÕĮōĶ®▓ńē╣Õłźµ│ĢŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«Ķ▓¼õ╗╗ŃéƵśÄńż║ńÜäŃü½Ķ”ÅÕ«ÜŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃüōŃü©ŃĆé
ŃüōŃü«Õłżµ▒║Ńü»ŃĆüÕŹśŃü½ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü¦ŃüéŃéŗŃü©ŃüäŃüåńÉåńö▒ŃüĀŃüæŃü¦Õłæõ║ŗĶ©┤Ķ┐ĮŃüĢŃéīŃéŗŃā¬Ńé╣Ńé»Ńü½Õ»ŠŃüŚŃĆüõĖĆÕ«ÜŃü«µŁ»µŁóŃéüŃéÆŃüŗŃüæŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüķĆåŃü½Ķ©ĆŃüłŃü░ŃĆüµźŁÕŗÖÕ¤ĘĶĪīµ©®ķÖÉŃéƵīüŃüżÕĖĖÕŗżÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣’╝łManaging DirectorńŁē’╝ēŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüŃĆīµźŁÕŗÖŃéƵÄīµÅĪŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃĆŹŃü©Ńü┐Ńü¬ŃüĢŃéīŃĆüÕÄ│ŃüŚŃüäĶ▓¼õ╗╗Ķ┐ĮÕÅŖŃüīŃü¬ŃüĢŃéīŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīõŠØńäČŃü©ŃüŚŃü”ķ½śŃüäŃüōŃü©ŃéÆńż║ÕöåŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü©Ńéü
ŃéżŃā│ŃāēŃü½ŃüŖŃüæŃéŗõ╝ÜńżŠĶ©Łń½ŗŃü»ŃĆüSPICe+ŃāĢŃé®Ńā╝ŃāĀŃü«Õ░ÄÕģźŃü½ŃéłŃéŖŃĆüµēŗńČÜŃüŹŃü«ÕģźŃéŖÕÅŻŃüōŃüØŃāćŃéĖŃé┐Ńā½Õī¢ŃüĢŃéīŃĆüĶ┐ģķƤŃüŗŃüżķĆŵśÄµĆ¦Ńüīķ½śŃüäŃééŃü«Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüŃüØŃü«ĶāīÕŠīŃü½Ńü»ŃĆüŃé│ŃāóŃā│Ńā╗ŃāŁŃā╝Ńü½Õ¤║ŃüźŃüÅÕÄ│µĀ╝Ńü¬Õ«Üµ¼ŠĶ¦ŻķćłŃĆüÕ▒ģõĮÅÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«ńó║õ┐ØŃĆüFEMAŃü½ŃéłŃéŗÕż¢Ķ│ćĶ”ÅÕłČŃĆüŃüØŃüŚŃü”õ║ŗµźŁķ¢ŗÕ¦ŗÕ▒ŖŃü«µÅÉÕć║µ£¤ķÖÉŃü©ŃüäŃüŻŃü¤ŃĆüµŚźµ£¼µ│ĢŃü©Ńü»ńĢ░Ńü¬Ńéŗµ│ĢńÜäµ”éÕ┐ĄŃü©ÕÄ│µĀ╝Ńü¬Ńé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣Ńü«ÕŻüŃüīÕ╣ŠķćŹŃü½ŃééÕŁśÕ£©ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃéīŃéēŃü»ÕŹśŃü¬Ńéŗõ║ŗÕŗÖµēŗńČÜŃüŹŃü«ÕĢÅķĪīŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüķüĢÕÅŹŃüÖŃéīŃü░ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ÕĆŗõ║║Ńü«Õłæõ║ŗĶ▓¼õ╗╗ŃéäŃĆüµ£Ćµé¬Ńü«ÕĀ┤ÕÉłŃü»õ╝ÜńżŠŃü«µŖ╣µČł’╝łStrike Off’╝ēŃü½ŃüżŃü¬ŃüīŃéŗķćŹÕż¦Ńü¬ńĄīÕ¢ČŃā¬Ńé╣Ńé»Ńü¦ŃüÖŃĆéńē╣Ńü½ŃĆüÕ▒ģõĮÅÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«ķüĖõ╗╗ŃéäŃĆüÕÉłÕ╝üõ║ŗµźŁŃü½ŃüŖŃüæŃéŗµĀ¬õĖ╗ķ¢ōÕźæń┤äŃü«Õ«Üµ¼ŠŃüĖŃü«ÕÅŹµśĀŃü©ŃüäŃüŻŃü¤Ķ½¢ńé╣Ńü»ŃĆüŃāōŃéĖŃāŹŃé╣µł”ńĢźŃü©µ│ĢÕŗÖŃüīÕ»åµÄźŃü½õ║żķī»ŃüÖŃéŗķĀśÕ¤¤Ńü¦ŃüéŃéŖŃĆüÕłØµ£¤µ«ĄķÜÄŃü¦Ńü«ķü®ÕłćŃü¬Ķ©ŁĶ©łŃüīÕ░åµØźŃü«ń┤øõ║ēõ║łķś▓Ńü«ķŹĄŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
Ńé½ŃāåŃé┤Ńā¬Ńā╝: ITŃā╗ŃāÖŃā│ŃāüŃāŻŃā╝Ńü«õ╝üµźŁµ│ĢÕŗÖ
Ńé┐Ńé░: ŃéżŃā│ŃāēÕģ▒ÕÆīÕøĮµĄĘÕż¢õ║ŗµźŁ