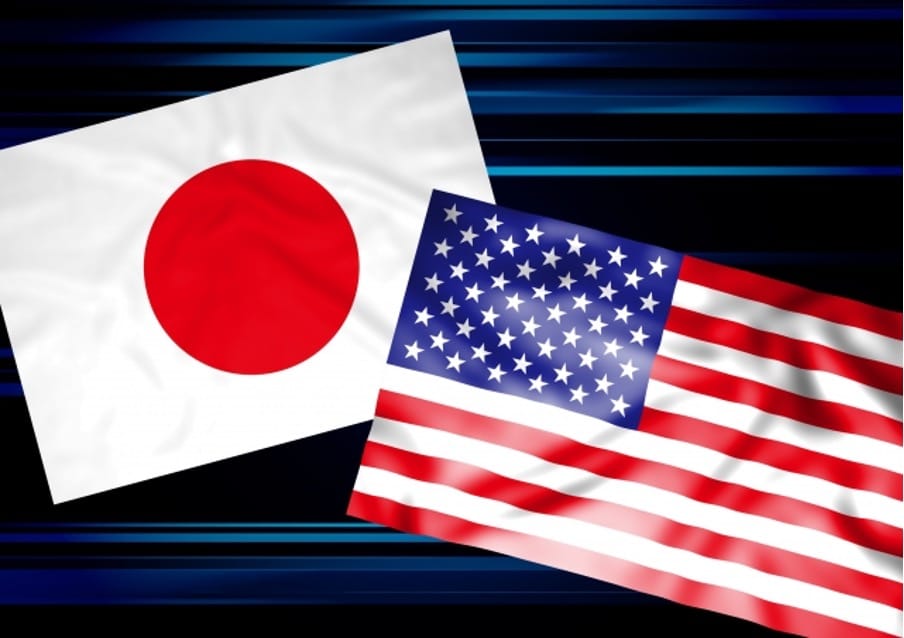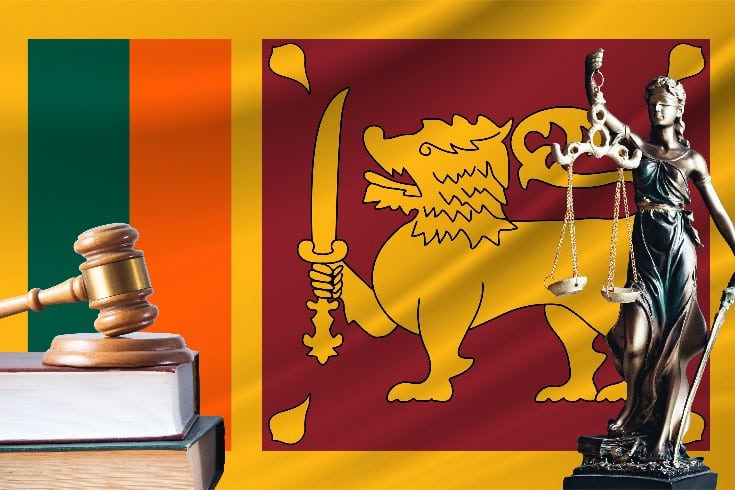مƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯ه¤§ه…¬ه›½مپ«مپٹمپ‘م‚‹é‡‘èچو©ںé–¢مپ®مƒ©م‚¤م‚»مƒ³م‚¹مپ¨ç›£ç£مپ«é–¢مپ™م‚‹و³•هˆ¶ه؛¦

ه›½éڑ›é‡‘èچم‚»مƒ³م‚؟مƒ¼مپ¨مپ—مپ¦ن¸–ç•Œçڑ„مپ«ç¢؛ه›؛مپںم‚‹هœ°ن½چم‚’築مپ„مپ¦مپ„م‚‹مƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯ه¤§ه…¬ه›½مپ¯م€په¤ڑو§کمپھوٹ•è³‡مƒ•م‚،مƒ³مƒ‰م‚„金èچم‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپŒé›†ç©چمپ™م‚‹و¬§ه·مپ®çژ„é–¢هڈ£مپ¨مپ—مپ¦م€په¤ڑمپڈمپ®و—¥وœ¬ن¼پو¥مپ‹م‚‰و³¨ç›®م‚’集م‚پمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپمپ®ه …ه›؛مپھهœ°ن½چم‚’و”¯مپˆمپ¦مپ„م‚‹مپ®مپ¯م€پهچکمپ«هœ°çگ†çڑ„مپھه„ھن½چو€§م‚„ç¨ژهˆ¶ن¸ٹمپ®é…هٹ›مپ مپ‘مپ§مپ¯مپ‚م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚金èچم‚»م‚¯م‚؟مƒ¼مپ®هپ¥ه…¨و€§مپ¨ه®‰ه®ڑو€§م‚’ç¢؛ن؟مپ™م‚‹مپںم‚پمپ«م€په¼·ه›؛مپ‹مپ¤é€ڈوکژو€§مپ®é«کمپ„و³•هˆ¶ه؛¦مپŒو•´ه‚™مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ¨مپŒم€پمƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯مپ®وœ€ه¤§مپ®ç‰¹ه¾´مپ¨è¨€مپˆم‚‹مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚
وœ¬è¨کن؛‹مپ¯م€پمپمپ®ن¸و ¸م‚’مپھمپ™م€Œé‡‘èچم‚»م‚¯م‚؟مƒ¼مپ®ه°‚é–€ه®¶م€چ(Professional of the Financial Sector: PSF)مپ®مƒ©م‚¤م‚»مƒ³م‚¹مپ¨ç›£ç£مپ«é–¢م‚ڈم‚‹و³•هˆ¶ه؛¦مپ«مپ¤مپ„مپ¦م€پو—¥وœ¬مپ®و³•هˆ¶ه؛¦مپ¨مپ®éپ•مپ„مپ«م‚‚触م‚ŒمپھمپŒم‚‰è©³ç´°مپ«è§£èھ¬مپ—مپ¾مپ™م€‚
مپھمپٹم€پمƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯مپ®هŒ…و‹¬çڑ„مپھو³•هˆ¶ه؛¦مپ®و¦‚è¦پمپ¯ن¸‹è¨کè¨کن؛‹مپ«مپ¦مپ¾مپ¨م‚پمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
مپ“مپ®è¨کن؛‹مپ®ç›®و¬،
مƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯مپ®PSFمƒ©م‚¤م‚»مƒ³م‚¹هˆ¶ه؛¦مپ®و¦‚è¦پمپ¨ç›£ç£و©ںé–¢CSSF
مƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯é‡‘èچم‚»م‚¯م‚؟مƒ¼و³•مپ®ن½چç½®مپ¥مپ‘مپ¨PSFمƒ©م‚¤م‚»مƒ³م‚¹
مƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯مپ«مپٹمپ„مپ¦م€پ金èچم‚µمƒ¼مƒ“م‚¹م‚’و£è¦ڈمپ®ن؛‹و¥مپ¨مپ—مپ¦وڈگن¾›مپ—م‚ˆمپ†مپ¨مپ™م‚‹ن¼پو¥مپ¯م€پ1993ه¹´4وœˆ5و—¥ن»کمپ®é‡‘èچم‚»م‚¯م‚؟مƒ¼و³•ï¼ˆLaw of 5 April 1993 on the financial sector)مپ«هں؛مپ¥مپچم€پمƒ©م‚¤م‚»مƒ³م‚¹م‚’هڈ–ه¾—مپ™م‚‹ه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ“مپ®و³•ه¾‹مپ¯م€پ金èچم‚»م‚¯م‚؟مƒ¼مپ¸مپ®هڈ‚ه…¥م€پمپمپ®هپ¥ه…¨مپھ監ç£م€پمپمپ—مپ¦ه†چç·¨م‚„解و•£مپ«è‡³م‚‹مپ¾مپ§مپ®هŒ…و‹¬çڑ„مپھو 組مپ؟م‚’ه®ڑم‚پمپ¦مپ„م‚‹م€پمƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯مپ®é‡‘èچو´»ه‹•م‚’è¦ڈه¾‹مپ™م‚‹هں؛وœ¬و³•مپ§مپ™م€‚
مپ“مپ®و³•ه¾‹مپ®ن¸‹مپ§مƒ©م‚¤م‚»مƒ³م‚¹م‚’هڈ—مپ‘مپںن؛‹و¥ن½“مپ¯م€پم€Œé‡‘èچم‚»م‚¯م‚؟مƒ¼مپ®ه°‚é–€ه®¶م€چ(Professional of the Financial Sector: PSF)مپ¨مپ„مپ†ç·ڈ称(generic label)مپ§ه‘¼مپ°م‚Œمپ¾مپ™م€‚مپ“مپ®م€ŒPSFم€چمپ¨مپ„مپ†ه‘¼ç§°مپ¯م€پو—¥وœ¬مپ®é‡‘èچه•†ه“پهڈ–ه¼•و¥مپ«مپٹمپ‘م‚‹م€Œç¬¬ن¸€ç¨®م€چم€Œç¬¬ن؛Œç¨®م€چمپ¨مپ„مپ£مپںوکژç¢؛مپھو¥و…‹هˆ†é،مپ¨مپ¯ç•°مپھم‚ٹم€پوٹ•è³‡ن¼ڑ社م€په°‚é–€çڑ„م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹وڈگن¾›è€…م€پمپمپ—مپ¦ITم‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مƒ—مƒمƒگم‚¤مƒ€مƒ¼مپ®م‚ˆمپ†مپھم‚µمƒمƒ¼مƒˆو¥ه‹™مپ¾مپ§م€پو§کم€…مپھو´»ه‹•م‚’ه¹…ه؛ƒمپڈهŒ…هگ«مپ™م‚‹مƒ©مƒ™مƒ«مپ§مپ™م€‚
監ç£و©ںé–¢CSSFمپ®ه½¹ه‰²مپ¨و¨©é™گ
مƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯مپ®é‡‘èچم‚»م‚¯م‚؟مƒ¼مپ®ç›£ç£م‚’و‹…مپ†ن¸»è¦پمپھه…¬çڑ„و©ںé–¢مپ¯م€پ金èچم‚»م‚¯م‚؟مƒ¼ç›£ç£ه§”ه“،ن¼ڑ(Commission de Surveillance du Secteur Financier: CSSF)مپ§مپ™م€‚CSSFمپ¯م€پPSFم‚’هگ«م‚€é‡‘èچم‚»م‚¯م‚؟مƒ¼ه…¨ن½“مپ®ه®‰ه…¨مپ¨هپ¥ه…¨و€§م‚’ç¢؛ن؟مپ™م‚‹مپ“مپ¨م‚’ه”¯ن¸€مپ®ه…¬ه…±مپ®هˆ©ç›ٹمپ¨مپ™م‚‹ن½؟ه‘½م‚’ه¸¯مپ³مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپمپ®ه½¹ه‰²مپ¯ه¤ڑه²گمپ«م‚ڈمپںم‚ٹم€پèھچهڈ¯م‚’هڈ—مپ‘مپںن؛‹و¥ن½“مپŒéپ©ç”¨مپ•م‚Œم‚‹è¦ڈهˆ¶م€پ特مپ«é‡‘èچو¶ˆè²»è€…مپ®ن؟è·م‚„مƒمƒچمƒ¼مƒمƒ³مƒ€مƒھمƒ³م‚°مƒ»مƒ†مƒè³‡é‡‘ن¾›ن¸ژéک²و¢ï¼ˆAML/CFT)مپ®è¦ڈهˆ¶م‚’éپµه®ˆمپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ‹م‚’監視مپ—مپ¾مپ™م€‚
CSSFمپ¯م€پمپمپ®ç›£ç£ن»»ه‹™م‚’éپ‚è،Œمپ™م‚‹مپںم‚پمپ«م€پéه¸¸مپ«ه¼·هٹ›مپھو¨©é™گم‚’وœ‰مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ«مپ¯م€پمپ„مپ‹مپھم‚‹و–‡و›¸مپ¸مپ®م‚¢م‚¯م‚»م‚¹و¨©م‚„م‚³مƒ”مƒ¼مپ®è¦پو±‚م€پçڈ¾ه ´مپ§مپ®èھ؟وں»و¨©é™گم€پ電話م‚„é›»هگé€ڑن؟،è¨ک録مپ®è¦پو±‚م€پو³•ن»¤éپ•هڈچè،Œç‚؛مپ®هپœو¢ه‘½ن»¤مپھمپ©مپŒهگ«مپ¾م‚Œمپ¾مپ™م€‚مپ•م‚‰مپ«م€پCSSFمپ¯م€په¤ڑé،چمپ®è،Œو”؟ه‡¦هˆ†م‚’èھ²مپ™و¨©é™گم‚‚وŒپمپ،م€پمپمپ®ن¸ٹé™گمپ¯ه¯¾è±،ن¼پو¥مپ®ه¹´é–“ç´”ه£²ن¸ٹé«کمپ®10%مپ«éپ”مپ™م‚‹ه ´هگˆم‚„م€پوœ€ه¤§500ن¸‡مƒ¦مƒ¼مƒمپ«م‚‚هڈٹمپ³مپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œم‚‰مپ®è،Œو”؟ه‡¦هˆ†مپ¯م€پمپمپ®ه†…ه®¹مپ®é‡چه¤§و€§مپ«ه؟œمپکمپ¦ه…¬è،¨مپ•م‚Œم‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ‚م‚ٹم€پو¥ç•Œه…¨ن½“مپ¸مپ®ه¼·مپ„è¦ه‘ٹمپ¨مپ—مپ¦و©ں能مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
مƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯مپ«مپٹمپ‘م‚‹مƒ©م‚¤م‚»مƒ³م‚¹هڈ–ه¾—مپ®è¦پن»¶مپ¨و—¥وœ¬و³•مپ¨مپ®و±؛ه®ڑçڑ„مپھ相éپ•ç‚¹
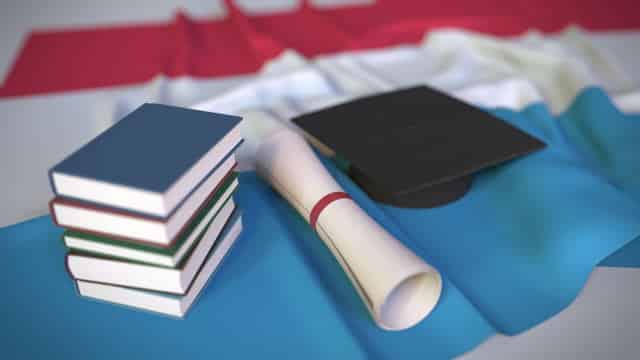
مƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯مپ§PSFمƒ©م‚¤م‚»مƒ³م‚¹م‚’هڈ–ه¾—مپ™م‚‹مپںم‚پمپ«مپ¯م€پè²،ه‹™çœپمپ¸مپ®ç”³è«‹مپŒه؟…è¦پمپ§مپ‚م‚ٹم€پCSSFمپ®هٹ©è¨€م‚’経مپ¦و‰؟èھچمپŒن¸ژمپˆم‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚مپ“مپ®ç”³è«‹و‰‹ç¶ڑمپچمپ¯م€پن؛‹و¥ه†…ه®¹م‚„組織ن½“هˆ¶م€پ経ه–¶é™£م€پن¸»è¦پو ھن¸»مپ®éپ©و ¼و€§مپھمپ©م€په¤ڑه²گمپ«م‚ڈمپںم‚‹هژ³و ¼مپھè¦پن»¶م‚’م‚¯مƒھم‚¢مپ™م‚‹ه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
ه®ںن½“è¦پن»¶ï¼ˆSubstance)مپ¨ç‰©çگ†çڑ„هں؛盤مپ®ç¢؛ç«‹
PSFمƒ©م‚¤م‚»مƒ³م‚¹هڈ–ه¾—مپ®é‡چè¦پمپھè¦پن»¶مپ®ن¸€مپ¤مپ«م€پمƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯مپ«مپٹمپ‘م‚‹م€Œه®ںن½“è¦پن»¶م€چ(Substance)م‚’و؛€مپںمپ™مپ“مپ¨مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ¯م€پهچکمپ«و›¸é¢ن¸ٹمپ®ç™»è¨کç°؟م‚’ç½®مپڈمپ مپ‘مپ§مپ¯ن¸چهچپهˆ†مپ§مپ‚م‚ٹم€پمƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯مپ«م€Œن¸ه¤®ç®،çگ†هœ°م€چمپ¨م€Œç™»è¨کن¸ٹمپ®ن؛‹ه‹™و‰€م€چم‚’è¨مپ‘م‚‹مپ“مپ¨م‚’و„ڈه‘³مپ—مپ¾مپ™م€‚
مپ“مپ“مپ§مپ®م€Œن¸ه¤®ç®،çگ†هœ°م€چمپ¨مپ¯م€پن¼ڑ社مپŒه®ںéڑ›مپ«çµŒه–¶مƒ»ç®،çگ†مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹ه ´و‰€م‚’وŒ‡مپ—م€پوˆ¦ç•¥çڑ„مپھو„ڈو€و±؛ه®ڑمپŒمپھمپ•م‚Œم‚‹ه ´و‰€م‚„م€پهڈ–ç· ه½¹ن¼ڑمƒ»و ھن¸»ç·ڈن¼ڑمپŒé–‹ه‚¬مپ•م‚Œم‚‹ه ´و‰€مپھمپ©مپŒè€ƒو…®مپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚مپ¾مپںم€پPSFمپ¯م€پ独è‡ھمپ®هں·è،Œو‹…ه½“者م€پéپ‹ç”¨م‚·م‚¹مƒ†مƒ م€پهڈ–ه¼•é–¢é€£و–‡و›¸م€پمپمپ—مپ¦çµŒçگ†م‚„ITم€په†…部統هˆ¶مپھمپ©مپ®م‚µمƒمƒ¼مƒˆو©ں能م‚’ه‚™مپˆمپںéپ©هˆ‡مپھم‚¤مƒ³مƒ•مƒ©م‚’ç™»è¨کن¸ٹمپ®ن؛‹ه‹™و‰€مپ«ç½®مپڈه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ¯م€پن؛‹و¥مپŒمƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯مپ‹م‚‰ه®ںéڑ›مپ«éپ‹ه–¶مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ¨م‚’ç¤؛مپ™م€پéه¸¸مپ«ه®ںè³ھçڑ„مپھè¦پو±‚مپ¨è¨€مپˆمپ¾مپ™م€‚
申請مƒ•م‚،م‚¤مƒ«مپ«مپ¯م€پن؛‹و¥è¨ˆç”»م€پITè¨ه®ڑمپ®è©³ç´°مپھèھ¬وکژم€پAMLو‰‹ç¶ڑمپچمپ®èچ‰و،ˆم€پمپٹم‚ˆمپ³ن¼ڑ社è¨ç«‹é–¢é€£و–‡و›¸مپ®و؛–ه‚™مپŒهگ«مپ¾م‚Œمپ¾مپ™م€‚ITè¨ه®ڑمپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯م€پIT組織ه›³م€پم‚¹م‚؟مƒƒمƒ•و•°م€پITوˆ¦ç•¥ï¼ˆه†…製مپ‹م‚¢م‚¦مƒˆم‚½مƒ¼م‚·مƒ³م‚°مپ‹ï¼‰م€پم‚¢م‚¦مƒˆم‚½مƒ¼م‚·مƒ³م‚°ه…ˆمپ«é–¢مپ™م‚‹وƒ…ه ±ï¼ˆو‰€هœ¨هœ°م‚„監ç£ه½“ه±€مپ®ç›£ç£ن¸‹مپ«مپ‚م‚‹مپ‹مپھمپ©ï¼‰م€پم‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ®ه†—é•·و€§م‚„مƒچمƒƒمƒˆمƒ¯مƒ¼م‚¯é€ڑن؟،مƒ—مƒمƒˆم‚³مƒ«م€پمƒھمƒ¢مƒ¼مƒˆم‚¢م‚¯م‚»م‚¹مپ®وœ‰ç„،مپ¨مپمپ®ç›®çڑ„مپھمپ©م‚’詳細مپ«è¨کè؟°مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒو±‚م‚پم‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚
PSFمپ®م‚«مƒ†م‚´مƒھمƒ¼مپ«ه؟œمپکمپ¦م€پوœ€ن½ژ資وœ¬é‡‘م‚‚هژ³و ¼مپ«ه®ڑم‚پم‚‰م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚ن¾‹مپˆمپ°م€پم‚¯مƒ©م‚¤م‚¢مƒ³مƒˆمپ®è³‡é‡‘م‚„証هˆ¸م‚’ن؟وœ‰مپ—مپھمپ„وٹ•è³‡ن¼ڑ社مپ¯75,000مƒ¦مƒ¼مƒم€پن؟وœ‰مپ™م‚‹ه ´هگˆمپ¯150,000مƒ¦مƒ¼مƒمپŒه؟…è¦پمپ¨مپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚ه°‚é–€çڑ„PSF(Specialised PFS)مپ¯50,000مƒ¦مƒ¼مƒمپ‹م‚‰وœ€ه¤§730,000مƒ¦مƒ¼مƒم€پم‚µمƒمƒ¼مƒˆPSF(Support PFS)مپ¯50,000مƒ¦مƒ¼مƒمپ‹م‚‰125,000مƒ¦مƒ¼مƒمپ®ç¯„ه›²مپ§è³‡وœ¬è¦پن»¶مپŒè¨ه®ڑمپ•م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œم‚‰مپ®è³‡وœ¬مپ¯م€پن؛‹و¥ن½“è‡ھè؛«مپ®هˆ©ç›ٹمپ®مپںم‚پمپ«وٹ•è³‡مپ•م‚Œم€په¸¸مپ«هˆ©ç”¨هڈ¯èƒ½مپ§مپھمپ‘م‚Œمپ°مپھم‚‰مپڑم€پو ھن¸»مپ®وٹ•è³‡ç›®çڑ„م‚„و ھن¸»مپ¸مپ®è²¸ن»کمپ«ç”¨مپ„م‚‹مپ“مپ¨مپ¯هژںه‰‡مپ¨مپ—مپ¦èھچم‚پم‚‰م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ›م‚“م€‚
経ه–¶é™£مپ¨و ھن¸»مپ®éپ©و ¼و€§ï¼ˆFit & Proper)
مƒ©م‚¤م‚»مƒ³م‚¹هڈ–ه¾—مپ«مپ‚مپںمپ£مپ¦مپ¯م€پ申請م‚’ن¸»ه°ژمپ™م‚‹è²¬ن»»è€…مپ مپ‘مپ§مپھمپڈم€پ経ه–¶é™£م‚„ن¸»è¦پو ھن¸»مپ®éپ©و ¼و€§مپŒهژ³مپ—مپڈه¯©وں»مپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚ن¸»è¦پو ھن¸»مپ®éپ©و ¼و€§مپ¯م€پè©•هˆ¤م€پ経験م€پè²،ه‹™مپ®هپ¥ه…¨و€§م€پمپمپ—مپ¦مƒمƒچمƒ¼مƒمƒ³مƒ€مƒھمƒ³م‚°مƒھم‚¹م‚¯مپ®è¦³ç‚¹مپ‹م‚‰è©•ن¾،مپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚特مپ«è°و±؛و¨©مپ®10%ن»¥ن¸ٹم‚’ن؟وœ‰مپ™م‚‹ن¸»è¦پو ھن¸»مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯م€پçٹ¯ç½ھ経و´è¨¼وکژو›¸م‚„ç›´è؟‘3ه¹´é–“مپ®ç›£وں»و¸ˆمپ؟و±؛ç®—و›¸م€پمپ•م‚‰مپ«مپ¯ه®£èھ“و›¸مپھمپ©مپ®وڈگه‡؛مپŒو±‚م‚پم‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚
و—¥م€…مپ®çµŒه–¶م‚’و‹…مپ†çµŒه–¶é™£مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯م€پمپ•م‚‰مپ«è©³ç´°مپھè¦پن»¶مپŒèھ²مپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚
経ه–¶è€…مپ®ن؛؛و•°è¦پن»¶مپ¨ه±…ن½ڈè¦پن»¶ï¼ڑن؛Œهگچن½“هˆ¶مپ®هژںه‰‡
مƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯مپ®é‡‘èچم‚»م‚¯م‚؟مƒ¼و³•مپ§مپ¯م€پو—¥م€…مپ®çµŒه–¶م‚’م€Œè©•هˆ¤مپ¨çµŒé¨“م€چم‚’وœ‰مپ—م€پم€Œمپ»مپ¼هگŒç‰مپ®و¨©é™گم‚’وŒپمپ¤ه°‘مپھمپڈمپ¨م‚‚2هگچمپ®è‡ھ然ن؛؛م€چمپ«ه§”مپم‚‹م€پمپ„م‚ڈم‚†م‚‹م€Œن؛Œهگچن½“هˆ¶مپ®çµŒه–¶è€…(two-man management principle)م€چمپŒهژںه‰‡مپ¨مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ“مپ®ن½“هˆ¶مپ¯م€پ経ه–¶é™£ه†…部مپ«مپٹمپ‘م‚‹ç›¸ن؛’監視مپ¨ه…±هگŒو„ڈو€و±؛ه®ڑم‚’هڈ¯èƒ½مپ«مپ™م‚‹مپ“مپ¨م‚’ç›®çڑ„مپ¨مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
مپ¾مپںم€پمپ“م‚Œم‚‰2هگچمپ®çµŒه–¶è€…مپ¯م€پمƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯مپ¾مپںمپ¯م‚°مƒ©مƒ³مƒ»مƒ¬م‚¸م‚ھمƒ³ï¼ˆه›½ه¢ƒمپ«وژ¥مپ™م‚‹è؟‘éڑ£هœ°هںں)مپ«ه±…ن½ڈمپ—مپ¦مپ„م‚‹ه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ¯م€پ監ç£و©ںé–¢مپ§مپ‚م‚‹CSSFمپŒم€پç·ٹو€¥و™‚مپ«مپ„مپ¤مپ§م‚‚経ه–¶è€…مپ«é€£çµ،مپŒهڈ–م‚Œم‚‹ن½“هˆ¶م‚’ç¢؛ن؟مپ™م‚‹مپںم‚پمپ§مپ™م€‚مپںمپ مپ—م€پمپ“مپ®ه±…ن½ڈè¦پن»¶مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯م€پمƒ©م‚¤م‚»مƒ³م‚¹ç™؛è،Œه¾Œمپ®وœ€هˆمپ®6مƒ¶وœˆé–“مپ¯م€پن¸€و–¹مپ®çµŒه–¶è€…مپ«مپ¤مپ„مپ¦ه…چ除مپŒèھچم‚پم‚‰م‚Œم‚‹ه ´هگˆمپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
éپ©و ¼و€§مپ®ه¯©وں»ه®ںه‹™مپ¨و‹’絶ن؛‹ن¾‹
CSSFمپ¯م€پ経ه–¶é™£م‚„ن¸»è¦پو ھن¸»مپ®éپ©و ¼و€§م‚’ه¯©وں»مپ™م‚‹مپ«مپ‚مپںم‚ٹم€پçٹ¯ç½ھ経و´è¨¼وکژو›¸مپ®وڈگه‡؛م‚’義ه‹™ن»کمپ‘مپ¦مپ„م‚‹مپ»مپ‹م€پéپژهژ»مپ®هˆ‘ن؛‹م€پو°‘ن؛‹م€پمپ¾مپںمپ¯è،Œو”؟訴è¨ںمپ®وœ‰ç„،مپ«مپ¤مپ„مپ¦م‚‚詳細مپھه ±ه‘ٹم‚’و±‚م‚پمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ¾مپںم€پ申請者م‚„مپمپ®é–¢é€£ن¼پو¥مپ¨م€پ申請ه¯¾è±،مپ¨مپھم‚‹é‡‘èچو©ںé–¢م‚„مپمپ®ç«¶هگˆم€پé،§ه®¢مپ¨مپ®é–“مپ«ه®ںè³ھçڑ„مپھهˆ©ه®³é–¢ن؟‚مپŒمپھمپ„مپ‹مپ©مپ†مپ‹م‚‚ç¢؛èھچمپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚
مƒ©م‚¤م‚»مƒ³م‚¹ç”³è«‹مƒ—مƒم‚»م‚¹مپ¯éه¸¸مپ«هژ³و ¼مپ§مپ‚م‚ٹم€پCSSFمپ¯ç”³è«‹و›¸é،مپ®م€Œه®ںن½“مپ¨ه†…ه®¹م€چمپ®ن¸،و–¹مپ«هں؛مپ¥مپ„مپ¦è©•ن¾،م‚’è،Œمپ„مپ¾مپ™م€‚申請و›¸é،مپŒن¸چه®Œه…¨مپ§مپ‚مپ£مپںم‚ٹم€پè¦پن»¶م‚’و؛€مپںمپ—مپ¦مپ„مپھمپ„مپ¨هˆ¤و–مپ•م‚Œمپںه ´هگˆم€پمƒ©م‚¤م‚»مƒ³م‚¹مپ¯و‹’هگ¦مپ•م‚Œم‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚ه®ںéڑ›مپ«م€پéپژهژ»مپ«مپ¯م€پCSSFمپŒç‰¹ه®ڑمپ®ن¼پو¥ï¼ˆARM Asset Backed Securities S.A.مپھمپ©ï¼‰مپ¸مپ®مƒ©م‚¤م‚»مƒ³م‚¹ن»کن¸ژم‚’و‹’هگ¦مپ—مپںن؛‹ن¾‹م‚‚ه…¬è،¨مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
申請مƒ—مƒم‚»م‚¹مپ«مپ¯و™‚é–“çڑ„هˆ¶ç´„م‚‚هکهœ¨مپ—مپ¾مپ™م€‚ه®Œه…¨مپھ申請و›¸é،مپŒCSSFمپ«هڈ—çگ†مپ•م‚Œمپ¦مپ‹م‚‰م€پ6مƒ¶وœˆن»¥ه†…مپ«و±؛ه®ڑمپŒé€ڑçں¥مپ•م‚Œم‚‹مپ“مپ¨مپŒو±‚م‚پم‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚مپ¾مپںم€پCSSFمپ¯ç”³è«‹مƒ•م‚،م‚¤مƒ«مپŒن¸چه®Œه…¨مپ§مپ‚م‚‹ه ´هگˆم€پè؟½هٹ مپ®وƒ…ه ±وڈگن¾›م‚’و±‚م‚پمپ¾مپ™مپŒم€پمپ“مپ®وœںé–“م‚’هگ«م‚پم€پ申請مپ®هڈ—é کمپ‹م‚‰وœ€é•·مپ§12مƒ¶وœˆن»¥ه†…مپ«و±؛ه®ڑمپŒمپھمپ•م‚Œمپھمپ‘م‚Œمپ°مپھم‚‰مپڑم€پمپ“مپ®وœںé–“ه†…مپ«و±؛ه®ڑمپŒé€ڑçں¥مپ•م‚Œمپھمپ„ه ´هگˆم€پ申請مپ¯و‹’هگ¦مپ•م‚Œمپںمپ¨مپ؟مپھمپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚مپ“مپ®مپںم‚پم€پ申請者مپ¯م€پو£ه¼ڈمپھ申請مپ®ه‰چمپ«CSSFمپ¨مپ®ن؛ˆه‚™çڑ„مپھهچ”è°م‚’وژ¨ه¥¨مپ•م‚Œمپ¦مپٹم‚ٹم€پمپ“م‚Œمپ«م‚ˆم‚ٹه††و»‘مپھمƒ—مƒم‚»م‚¹é€²è،Œم‚’ه›³م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچمپ¾مپ™م€‚
و—¥وœ¬و³•مپ¨مپ®و¯”較
و—¥وœ¬مپ®é‡‘èچه•†ه“پهڈ–ه¼•و¥è€…م‚’ن¾‹مپ«وŒ™مپ’م‚‹مپ¨م€پن»£è،¨è€…مپ¯هژںه‰‡مپ¨مپ—مپ¦و—¥وœ¬مپ«ه±…ن½ڈمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒو±‚م‚پم‚‰م‚Œمپ¾مپ™مپŒم€په®ںه‹™ن¸ٹمپ¯م€پن¸€éƒ¨مپ®و¥ه‹™ه½¢و…‹مپ«مپٹمپ„مپ¦وµ·ه¤–ه±…ن½ڈمپ®éه¸¸ه‹¤ه½¹ه“،م‚’é…چç½®مپ™م‚‹م‚±مƒ¼م‚¹م‚‚èھچم‚پم‚‰م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
ن¸€و–¹م€پمƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯مپ®هˆ¶ه؛¦مپ¯م€پو—¥م€…مپ®çµŒه–¶م‚’و‹…مپ†ن¸»è¦پمپھو„ڈو€و±؛ه®ڑ者مپŒم€پ物çگ†çڑ„مپ«ç›£ç£ه½“ه±€مپ®ç®،轄ن¸‹مپ«هکهœ¨مپ—م€پè؟…é€ںمپھ監ç£مپ«ه؟œمپکم‚‰م‚Œم‚‹ن½“هˆ¶م‚’هژ³و ¼مپ«و±‚م‚پمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ¯م€پهچکمپھم‚‹و›¸é¢ن¸ٹمپ®è¦پن»¶مپ§مپ¯مپھمپڈم€پ経ه–¶مپ®ç›£ç£و©ں能مپ®ه®ںهٹ¹و€§م‚’ç¢؛ن؟مپ™م‚‹مپںم‚پمپ®é‡چè¦پمپھهژںه‰‡مپ§مپ‚م‚ٹم€پو—¥وœ¬مپ®é‡‘èچو©ںé–¢مپŒمƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯مپ¸é€²ه‡؛مپ™م‚‹éڑ›مپ«م€پم‚¬مƒگمƒٹمƒ³م‚¹ن½“هˆ¶م‚’و§‹ç¯‰مپ™م‚‹ن¸ٹمپ§وœ€م‚‚و·±مپڈ考و…®مپ™مپ¹مپچ相éپ•ç‚¹مپ¨è¨€مپˆمپ¾مپ™م€‚
| مƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯ï¼ˆPSF) | و—¥وœ¬ï¼ˆé‡‘èچه•†ه“پهڈ–ه¼•و¥è€…) | |
|---|---|---|
| 監ç£و©ںé–¢ | CSSFم€پECB(ن؟،用و©ںé–¢مپ®ه ´هگˆï¼‰ | 金èچه؛پ |
| ن¸»è¦پو ¹و‹ و³• | 1993ه¹´é‡‘èچم‚»م‚¯م‚؟مƒ¼و³• | 金èچه•†ه“پهڈ–ه¼•و³•م€پéٹ€è،Œو³•مپھمپ© |
| مƒ©م‚¤م‚»مƒ³م‚¹مپ®ç·ڈ称 | PSF(金èچم‚»م‚¯م‚؟مƒ¼مپ®ه°‚é–€ه®¶ï¼‰ | 金èچه•†ه“پهڈ–ه¼•و¥è€…ç‰ |
| 経ه–¶é™£مپ®ن؛؛و•°è¦پن»¶ | و—¥م€…مپ®çµŒه–¶م‚’و‹…مپ†مپ®مپ¯م€پمپ»مپ¼هگŒç‰مپ®و¨©é™گم‚’وŒپمپ¤ م€Œه°‘مپھمپڈمپ¨م‚‚2هگچم€چمپ®è‡ھ然ن؛؛ | هژںه‰‡مپ¨مپ—مپ¦ن»£è،¨è€…م‚’هگ«م‚€è¤‡و•°هگچ |
| 経ه–¶é™£مپ®ه±…ن½ڈè¦پن»¶ | 2هگچمپ¨م‚‚مƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯مپ¾مپںمپ¯ م‚°مƒ©مƒ³مƒ»مƒ¬م‚¸م‚ھمƒ³ه±…ن½ڈمپŒهژںه‰‡ (1هگچمپ®مپ؟6مƒ¶وœˆé–“مپ®ه…چ除هڈ¯ï¼‰ | ن»£è،¨è€…مپ¯و—¥وœ¬ه±…ن½ڈمپŒهژںه‰‡ |
| ن¸»è¦پو ھن¸»مپ®ه¯©وں»هں؛و؛– | è°و±؛و¨©مپ®10%ن»¥ن¸ٹم‚’ن؟وœ‰مپ™م‚‹و ھن¸»م‚’ م€Œè©•هˆ¤م€پ経験م€پè²،ه‹™مپ®هپ¥ه…¨و€§م€چç‰مپ§ه¯©وں» | è°و±؛و¨©مپ®20%ن»¥ن¸ٹم‚’ن؟وœ‰مپ™م‚‹و ھن¸»مپ¯ 金èچه؛پé•·ه®کمپ®èھچهڈ¯مپŒه؟…è¦پ |
| 監ç£ه®ںه‹™مپ®ç‰¹ه¾´ | AML/CFTéپ•هڈچن؛‹ن¾‹م‚’ ه…·ن½“çڑ„مپھه†…ه®¹مپ¨مپ¨م‚‚مپ«è©³ç´°مپ«ه…¬è،¨ | ه‡¦هˆ†ه†…ه®¹مپ¯و¯”較çڑ„وٹ½è±،çڑ„مپھه‚¾هگ‘مپŒمپ‚م‚‹ |
هژ³و ¼هŒ–مپ™م‚‹مƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯مپ®AML/CFTè¦ڈهˆ¶مپ¨ç›£ç£ه®ںه‹™مپ®و·±هŒ–

مƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯مپ®é‡‘èچم‚»م‚¯م‚؟مƒ¼مپ¯م€پمƒمƒچمƒ¼مƒمƒ³مƒ€مƒھمƒ³م‚°مپٹم‚ˆمپ³مƒ†مƒè³‡é‡‘ن¾›ن¸ژه¯¾ç–(AML/CFT)مپ®و 組مپ؟م‚’継ç¶ڑçڑ„مپ«ه¼·هŒ–مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚CSSFمپ¯م€پمپ“مپ®هˆ†é‡ژمپ®ç›£ç£م‚’و‹…مپ†ن¸»è¦پو©ںé–¢مپ¨مپ—مپ¦م€پéپ•هڈچمپŒèھچم‚پم‚‰م‚Œمپںن¼پو¥مپ«ه¯¾مپ—مپ¦م€پمپمپ®è¦ڈو¨،مپ®ه¤§ه°ڈم‚’ه•ڈم‚ڈمپڑه¤ڑé،چمپ®è،Œو”؟ه‡¦هˆ†م‚’èھ²مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
CSSFمپŒه…¬é–‹مپ™م‚‹è،Œو”؟ه‡¦هˆ†و–‡و›¸مپ¯م€پهچکمپھم‚‹ç½°ه‰‡مپ®ه‘ٹçں¥مپ«ç•™مپ¾م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚مپم‚Œمپ¯م€پ金èچو©ںé–¢مپŒç‰¹مپ«و³¨و„ڈمپ™مپ¹مپچم‚³مƒ³مƒ—مƒ©م‚¤م‚¢مƒ³م‚¹ن¸ٹمپ®ه¤±و•—م‚’ه…·ن½“çڑ„مپ«ç¤؛مپ™م€په®ںه‹™ن¸ٹمپ®م‚¬م‚¤مƒ‰مƒ©م‚¤مƒ³مپ¨مپ—مپ¦مپ®ه½¹ه‰²م‚‚وœمپںمپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ¨هˆ†وگمپ§مپچمپ¾مپ™م€‚
ن¾‹مپˆمپ°م€پCSSFمپŒ2024ه¹´مپ«Sogexia S.A.مپ«ه¯¾مپ—مپ¦èھ²مپ—مپںè،Œو”؟ه‡¦هˆ†مپ¯م€پé،§ه®¢مƒ‡مƒ¥مƒ¼مƒ‡مƒھم‚¸م‚§مƒ³م‚¹مپ«مپٹمپ‘م‚‹è³‡é‡‘و؛گوƒ…ه ±مپ®ن¸چ足م‚„م€په®ںè³ھçڑ„و”¯é…چ者مپ®ç¢؛èھچن¸چه‚™م‚’مپمپ®çگ†ç”±مپ¨مپ—مپ¦وŒ™مپ’مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ¾مپںم€پINTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES S.A.مپ¸مپ®ه‡¦هˆ†مپ§مپ¯م€پم‚ھمƒ•م‚·مƒ§م‚¢و³•ن؛؛مپ‹م‚‰مپ®è³‡é‡‘مپ®ه‡؛و‰€مپŒن¸چوکژçمپ§مپ‚م‚‹مپ«م‚‚مپ‹مپ‹م‚ڈم‚‰مپڑم€پمپمپ®ç¢؛èھچم‚’و€ مپ£مپںمپ“مپ¨مپŒوکژç¢؛مپ«وŒ‡و‘کمپ•م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œم‚‰مپ®ن؛‹ن¾‹مپ¯م€پCSSFمپŒوٹ½è±،çڑ„مپھم€Œو³•ن»¤éپµه®ˆم€چمپ مپ‘مپ§مپھمپڈم€په…·ن½“çڑ„مپھو¥ه‹™مƒ—مƒم‚»م‚¹مپ«مپٹمپ„مپ¦م€پ資金و؛گمپ®ç¢؛èھچم‚„هڈ–ه¼•مƒ¢مƒ‹م‚؟مƒھمƒ³م‚°م‚’ه¾¹ه؛•çڑ„مپ«è،Œمپ†مپ“مپ¨م‚’و±‚م‚پمپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ¨م‚’ç¤؛مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
مپ¾مپںم€پJ.P. Morgan SEمپ®مƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯و”¯ه؛—مپŒهڈ—مپ‘مپںوˆ’ه‘ٹه‡¦هˆ†مپ§مپ¯م€پهˆ¶è£پمƒھم‚¹مƒˆï¼ˆEU Regulation No 269/2014)مپ¸مپ®ç¶™ç¶ڑçڑ„مپھم‚¹م‚¯مƒھمƒ¼مƒ‹مƒ³م‚°م‚’و€ مپ£مپںمپ“مپ¨م‚„م€په†…部統هˆ¶م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ®é‡چه¤§مپھو¬ 陥مپŒم€پéپ•هڈچمپ®ن¸»مپںم‚‹çگ†ç”±مپ¨مپ—مپ¦وŒ™مپ’م‚‰م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ•م‚‰مپ«م€پç–‘م‚ڈمپ—مپ„و´»ه‹•م‚„هڈ–ه¼•م‚’金èچوƒ…ه ±مƒ¦مƒ‹مƒƒمƒˆï¼ˆFIU)مپ¸ه ±ه‘ٹمپ™مپ¹مپچ義ه‹™مپŒمپ‚مپ£مپںمپ«م‚‚مپ‹مپ‹م‚ڈم‚‰مپڑم€پمپمپ®ه ±ه‘ٹمپŒéپ…ه»¶مپ—مپںمپ“مپ¨مپŒم€پ複و•°مپ®ه‡¦هˆ†ن؛‹ن¾‹مپ§ه…±é€ڑمپ—مپ¦وŒ‡و‘کمپ•م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
| Sogexia S.A. | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch | INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES S.A. | |
|---|---|---|---|
| ه‡¦هˆ†و—¥ | 2024ه¹´2وœˆ22و—¥ | 2024ه¹´10وœˆ14و—¥ | 2024ه¹´11وœˆ28و—¥ |
| ه‡¦هˆ†ه†…ه®¹ | è،Œو”؟ه‡¦هˆ†ï¼ˆç½°é‡‘68,000مƒ¦مƒ¼مƒï¼‰ | è،Œو”؟ه‡¦هˆ†ï¼ˆوˆ’ه‘ٹ) | è،Œو”؟ه‡¦هˆ†ï¼ˆç½°é‡‘27,000مƒ¦مƒ¼مƒï¼‰ |
| ن¸»مپھéپ•هڈچمپ®و¦‚è¦پ | مƒ»é،§ه®¢مƒ‡مƒ¥مƒ¼مƒ‡مƒھم‚¸م‚§مƒ³م‚¹مپ®ن¸چه‚™ï¼ˆè³‡é‡‘و؛گç¢؛èھچمپ®ن¸چ足) مƒ»ه®ںè³ھçڑ„و”¯é…چ者مپ®ç¢؛èھچن¸چه‚™ مƒ»éهٹ¹çژ‡مپھهڈ–ه¼•مƒ¢مƒ‹م‚؟مƒھمƒ³م‚° مƒ»ç–‘م‚ڈمپ—مپ„هڈ–ه¼•مپ®FIUمپ¸مپ®ه ±ه‘ٹو€ و…¢ | مƒ»هˆ¶è£پمƒھم‚¹مƒˆمپ¸مپ®ç¶™ç¶ڑçڑ„مپھم‚¹م‚¯مƒھمƒ¼مƒ‹مƒ³م‚°ن¸چ足 مƒ»هˆ¶è£پوژھç½®مپ®ه®ںو–½مپٹم‚ˆمپ³ه ±ه‘ٹمپ®éپ…ه»¶ مƒ»ه†…部統هˆ¶م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ®é‡چه¤§مپھو¬ 陥 | مƒ»é،§ه®¢مƒ‡مƒ¥مƒ¼مƒ‡مƒھم‚¸م‚§مƒ³م‚¹مپ®ن¸چه‚™ï¼ˆè³‡é‡‘و؛گمپ¨è³‡ç”£مپ®ه‡؛و‰€ç¢؛èھچن¸چ足) مƒ»ç–‘م‚ڈمپ—مپ„هڈ–ه¼•مپ®FIUمپ¸مپ®ه ±ه‘ٹéپ…ه»¶ مƒ»çµ‚çµگمپ—مپںهڈ–ه¼•é–¢ن؟‚مپ®FIUمپ¸مپ®ه ±ه‘ٹéپ…ه»¶ |
| 関連و³•è¦ڈ | AML/CFTو³• CSSF Regulation 12-02 | 2020ه¹´12وœˆ19و—¥و³• AML/CFTو³• | AML/CFTو³• |
مپ“م‚Œم‚‰مپ®ن؛‹ن¾‹مپ‹م‚‰è¨€مپˆم‚‹مپ“مپ¨مپ¯م€پمƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯مپ®ç›£ç£ه½“ه±€مپŒم€په½¢ه¼ڈçڑ„مپھAML/CFTمƒمƒھم‚·مƒ¼مپ®هکهœ¨مپ مپ‘مپ§مپھمپڈم€پمپم‚ŒمپŒو—¥م€…مپ®و¥ه‹™مپ«مپ©مپ®م‚ˆمپ†مپ«çµ„مپ؟è¾¼مپ¾م‚Œم€پو©ں能مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ‹م‚’هژ³مپ—مپڈ監視مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨مپ§مپ™م€‚و—¥وœ¬مپ®é‡‘èچه؛پمپ®ه‡¦هˆ†ه…¬è،¨مپŒو¯”較çڑ„وٹ½è±،çڑ„مپ§مپ‚م‚‹ه‚¾هگ‘مپ¨و¯”較مپ™م‚‹مپ¨م€پمƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯مپ®CSSFمپŒه…·ن½“çڑ„مپھéپ•هڈچه†…ه®¹مپ¾مپ§è©³ç´°مپ«ه…¬è،¨مپ™م‚‹ç›£ç£ه®ںه‹™مپ¯م€پم‚ˆم‚ٹن؛ˆéک²çڑ„مپھو©ں能م‚’وœ‰مپ—مپ¦مپٹم‚ٹم€پو¥ç•Œه…¨ن½“مپ¸مپ®ه¼·مپ„è¦éگکمپ¨مپ—مپ¦ن½œç”¨مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ—مپںمپŒمپ£مپ¦م€پمƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯مپ§مپ®ن؛‹و¥ه±•é–‹م‚’計画مپ™م‚‹éڑ›مپ«مپ¯م€پهچکمپ«و³•ن»¤م‚’éپµه®ˆمپ™م‚‹مپ مپ‘مپ§مپھمپڈم€پمپمپ®èƒŒه¾Œمپ«مپ‚م‚‹ç›£ç£ه®ںه‹™مپ®هژ³و ¼مپ•مپ¨ه…·ن½“çڑ„مپھè¦پو±‚ن؛‹é …م‚’و·±مپڈçگ†è§£مپ—م€پ詳細مپھه†…部ç®،çگ†ن½“هˆ¶م‚’و§‹ç¯‰مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒç«¶ن؛‰ه„ھن½چو€§مپ«مپ¤مپھمپŒم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
مƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯DORA(Digital Operational Resilience Act)مپ®ه°ژه…¥مپ¨ITمƒھم‚¹م‚¯ç®،çگ†مپ®ه¤‰é©
مƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯م‚’هگ«م‚€EUهںںه†…مپ§مپ®é‡‘èچم‚µمƒ¼مƒ“م‚¹وڈگن¾›م‚’و¤œè¨ژمپ™م‚‹ن¸ٹمپ§م€پ2025ه¹´1وœˆ17و—¥م‚ˆم‚ٹéپ©ç”¨مپŒé–‹ه§‹مپ•م‚Œم‚‹DORA(Digital Operational Resilience Act)مپ¯م€پITمƒھم‚¹م‚¯ç®،çگ†مپ«ه¤§مپچمپھه¤‰é©م‚’م‚‚مپںم‚‰مپ™é‡چè¦پمپھè¦ڈه‰‡مپ§مپ™م€‚DORAمپ¯م€پEUوŒ‡ن»¤ï¼ˆDirective)مپ¨ç•°مپھم‚ٹم€پهگ„هٹ ç›ںه›½مپ®ه›½ه†…و³•مپ¸مپ®è»¢وڈ›م‚’è¦پمپ›مپڑم€پ金èچو©ںé–¢مپ«ç›´وژ¥éپ©ç”¨مپ•م‚Œم‚‹م€Œè¦ڈه‰‡ï¼ˆRegulation)م€چمپ§مپ‚م‚‹ç‚¹مپŒç‰¹ç†مپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ¯م€پEUه…¨ن½“مپ§ن¸€è²«مپ—مپںمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«مƒ»م‚ھمƒڑمƒ¬مƒ¼م‚·مƒ§مƒٹمƒ«مƒ»مƒ¬م‚¸مƒھم‚¨مƒ³م‚¹مپ®و 組مپ؟م‚’ه°ژه…¥مپ—م€پICT関連م‚¤مƒ³م‚·مƒ‡مƒ³مƒˆمپŒé‡‘èچم‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ®ه®‰ه®ڑو€§مپ«ن¸ژمپˆم‚‹مƒھم‚¹م‚¯م‚’軽و¸›مپ™م‚‹مپ“مپ¨م‚’ç›®çڑ„مپ¨مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
DORAمپ¯م€پن»¥ن¸‹مپ«ç¤؛مپ™5مپ¤مپ®ن¸»è¦پمپھوں±مپ«هں؛مپ¥مپچم€پ金èچو©ںé–¢مپ«ن¸€é€£مپ®ç¾©ه‹™م‚’èھ²مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
- ICTمƒھم‚¹م‚¯ç®،çگ†مپ®و 組مپ؟مپ®ه®ں装ï¼ڑه¼·ه›؛مپھه†…部م‚¬مƒگمƒٹمƒ³م‚¹مپ¨ICTمƒ“م‚¸مƒچم‚¹ç¶™ç¶ڑو€§و–¹é‡مپ®ç–ه®ڑم‚’هگ«م‚€م€‚
- ن¸»è¦پمپھICT関連م‚¤مƒ³م‚·مƒ‡مƒ³مƒˆمپ®ه ±ه‘ٹï¼ڑه›½ه®¶مپ®ç®،轄ه½“ه±€ï¼ˆمƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯مپ§مپ¯CSSF)مپ¸مپ®ه ±ه‘ٹم€‚
- مƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«مƒ»م‚ھمƒڑمƒ¬مƒ¼م‚·مƒ§مƒٹمƒ«مƒ»مƒ¬م‚¸مƒھم‚¨مƒ³م‚¹è©¦é¨“مپ®ه®ںو–½ï¼ڑن¸€éƒ¨مپ®و©ںé–¢مپ«مپ¯م€پè„…ه¨پن¸»ه°ژه‹مƒڑمƒچمƒˆمƒ¬مƒ¼م‚·مƒ§مƒ³مƒ†م‚¹مƒˆï¼ˆTLPT)م‚’هگ«م‚€é«که؛¦مپھمƒ†م‚¹مƒˆمپŒو±‚م‚پم‚‰م‚Œم‚‹م€‚
- ICTم‚µمƒ¼مƒ‰مƒ‘مƒ¼مƒ†م‚£مƒھم‚¹م‚¯مپ®ç®،çگ†ï¼ڑم‚¢م‚¦مƒˆم‚½مƒ¼م‚·مƒ³م‚°ه…ˆم‚’هگ«م‚€مƒھم‚¹م‚¯è©•ن¾،مپ¨م€پو–°مپںمپھه¥‘ç´„è¦پن»¶مپ®éپ©ç”¨م€‚
- وƒ…ه ±مƒ»م‚¤مƒ³مƒ†مƒھم‚¸م‚§مƒ³م‚¹مپ®è‡ھç™؛çڑ„مپھه…±وœ‰ن½“هˆ¶ï¼ڑم‚µم‚¤مƒگمƒ¼è„…ه¨پم‚„脆ه¼±و€§مپ«é–¢مپ™م‚‹وƒ…ه ±مپ®ه…±وœ‰م‚’ه¥¨هٹ±م€‚
特مپ«م€پمƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯مپ§ن؛‹و¥م‚’è،Œمپ†é‡‘èچو©ںé–¢مپ«مپ¨مپ£مپ¦é‡چè¦پمپھمپ®مپ¯م€پم‚¤مƒ³م‚·مƒ‡مƒ³مƒˆه ±ه‘ٹمپ«é–¢مپ™م‚‹ه®ںه‹™è¦پن»¶مپ®ه¤‰و›´مپ§مپ™م€‚DORAمپ®éپ©ç”¨مپ«ن¼´مپ„م€پICT関連مپ®و—¢هکمپ®CSSFé€ڑéپ”(Circulars CSSF 20/750م€پ22/806مپھمپ©ï¼‰مپ¨DORAمپ®è¦ڈه®ڑمپŒé‡چ複مپ™م‚‹éƒ¨هˆ†مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯م€پDORAمپ®è¦ڈه®ڑمپŒه„ھه…ˆمپ•م‚Œم‚‹مپ“مپ¨مپ«مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
ه ±ه‘ٹ義ه‹™م‚’وœمپںمپ™مپںم‚پمپ«مپ¯م€پ金èچو©ںé–¢مپ¯و³•ه‹™ه®ںن½“èکهˆ¥هگ(Legal Entity Identifier: LEI)م‚³مƒ¼مƒ‰م‚’ن؟وŒپمپ—م€پم€ŒIT incident notifierم€چمپ¨مپ„مپ†ç‰¹ه®ڑمپ®ه½¹ه‰²م‚’ن»»ه‘½مپ—م€پCSSFمپ«é€ڑçں¥مپ™م‚‹ه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚2025ه¹´1وœˆ17و—¥ن»¥é™چم€پCSSFمپ¯eDeskمƒمƒ¼م‚؟مƒ«ن¸ٹمپ«DORAه°‚用مپ®و–°مپ—مپ„ه ±ه‘ٹو‰‹ç¶ڑمپچم‚’é–‹è¨مپ—م€پمپ“م‚Œمپ«م‚ˆم‚ٹم€پمپ“م‚Œمپ¾مپ§مپ®è¤‡و•°مپ®ه ±ه‘ٹمƒپمƒ£مƒچمƒ«مپŒن¸€مپ¤مپ«é›†ç´„مپ•م‚Œم‚‹مپ“مپ¨مپ«مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ¯م€پ金èچو©ںé–¢مپŒITم‚¤مƒ³م‚·مƒ‡مƒ³مƒˆه ±ه‘ٹم‚’م€پم‚ˆم‚ٹé«که؛¦مپ§çµ±ن¸€مپ•م‚Œمپںهں؛و؛–مپ§è،Œمپ†مپ“مپ¨مپŒو±‚م‚پم‚‰م‚Œم‚‹مپ“مپ¨م‚’و„ڈه‘³مپ—مپ¾مپ™م€‚
و—¥وœ¬مپ®é‡‘èچه؛پم‚‚ITمƒ»م‚·م‚¹مƒ†مƒ مƒھم‚¹م‚¯ç®،çگ†م‚’é‡چ視مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™مپŒم€پDORAمپ¯م€پم‚¤مƒ³م‚·مƒ‡مƒ³مƒˆه ±ه‘ٹمپ®مƒ•م‚©مƒ¼مƒمƒƒمƒˆم‚„م€پمپمپ®مپںم‚پمپ®ه…·ن½“çڑ„مپھه½¹ه‰²م‚’EUه…¨ن½“مپ«م‚ڈمپںمپ£مپ¦çµ±ن¸€çڑ„مپ«è¦پو±‚مپ—مپ¦مپ„م‚‹ç‚¹مپ§م€پمپمپ®هژ³و ¼و€§مپ¨ه…±é€ڑو€§مپ¯éڑ›ç«‹مپ£مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
مپ¾مپ¨م‚پ
مƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯ه¤§ه…¬ه›½مپ«مپٹمپ‘م‚‹é‡‘èچم‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپ®مƒ©م‚¤م‚»مƒ³م‚¹مپ¨ç›£ç£هˆ¶ه؛¦مپ¯م€پهچکمپ«مƒ“م‚¸مƒچم‚¹م‚’èھک致مپ™م‚‹مپںم‚پمپ®ه½¢ه¼ڈçڑ„مپھو 組مپ؟مپ§مپ¯مپ‚م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚مپم‚Œمپ¯م€پ金èچم‚»م‚¯م‚؟مƒ¼مپ®é•·وœںçڑ„مپھهپ¥ه…¨و€§مپ¨ه®‰ه®ڑو€§م‚’ç¢؛ن؟مپ™م‚‹مپںم‚پمپ«م€په …牢مپ‹مپ¤ه®ںè³ھçڑ„مپھè¦پن»¶م‚’èھ²مپ™م€پو¥µم‚پمپ¦وˆگç†ںمپ—مپںو³•هˆ¶ه؛¦مپ§مپ™م€‚特مپ«م€پو—¥وœ¬مپ®ن¼پو¥مپŒن؛‹و¥ه±•é–‹م‚’و¤œè¨ژمپ™م‚‹ن¸ٹمپ§ç•™و„ڈمپ™مپ¹مپچ点مپ¯ه¤ڑه²گمپ«م‚ڈمپںم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
経ه–¶é™£مپ«èھ²مپ•م‚Œم‚‹هژ³و ¼مپھن؛Œهگچن½“هˆ¶مپ¨ه±…ن½ڈè¦پن»¶مپ¯م€پو—¥وœ¬مپ§مپ®و…£è،Œمپ¨مپ¯ç•°مپھم‚‹م€پ物çگ†çڑ„مپھ監ç£مپ®ه®ںهٹ¹و€§م‚’é‡چ視مپ—مپںمƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯ç‰¹وœ‰مپ®è¦پن»¶مپ§مپ™م€‚مپ¾مپںم€پCSSFمپŒه…¬é–‹مپ™م‚‹è،Œو”؟ه‡¦هˆ†ن؛‹ن¾‹مپ¯م€پهچکمپھم‚‹ç½°ه‰‡مپ®ه‘ٹçں¥مپ§مپ¯مپھمپڈم€په…·ن½“çڑ„مپھéپ•هڈچه†…ه®¹مپ¨ه¯¾ه؟œç–م‚’و¥ç•Œه…¨ن½“مپ«ç¤؛مپ™ه®ںè·µçڑ„مپھم‚¬م‚¤مƒ‰مƒ–مƒƒم‚¯مپ¨مپ—مپ¦و©ں能مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ•م‚‰مپ«م€پDORAمپ®م‚ˆمپ†مپھEUه…±é€ڑمپ®è¦ڈه‰‡مپ®éپ©ç”¨مپ¯م€پITمƒھم‚¹م‚¯ç®،çگ†م‚„م‚¤مƒ³م‚·مƒ‡مƒ³مƒˆه ±ه‘ٹم‚’م€پمƒ«م‚¯م‚»مƒ³مƒ–مƒ«م‚¯مپ®مƒمƒ¼م‚«مƒ«مپھو 組مپ؟م‚’超مپˆمپ¦م€پم‚ˆم‚ٹé«که؛¦مپھم‚°مƒمƒ¼مƒگمƒ«م‚¹م‚؟مƒ³مƒ€مƒ¼مƒ‰مپ¸مپ¨ه¼•مپچن¸ٹمپ’مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
مپ“مپ†مپ—مپں複雑مپ§ه¤ڑه²گمپ«م‚ڈمپںم‚‹و³•هˆ¶ه؛¦مپ«éپ©هˆ‡مپ«ه¯¾ه؟œمپ—م€په††و»‘مپ«مƒ©م‚¤م‚»مƒ³م‚¹م‚’هڈ–ه¾—مپ™م‚‹مپںم‚پمپ«مپ¯م€پçڈ¾هœ°مپ®è¦ڈهˆ¶ه½“ه±€مپ®éپ‹ç”¨ه®ںو…‹مپ¨م€پو—¥وœ¬ن¼پو¥مپ®ه•†ç؟’و…£م‚’و·±مپڈçگ†è§£مپ—مپںه°‚é–€çڑ„مپھم‚¢مƒ‰مƒگم‚¤م‚¹مپŒن¸چهڈ¯و¬ مپ§مپ™م€‚
م‚«مƒ†م‚´مƒھمƒ¼: ITمƒ»مƒ™مƒ³مƒپمƒ£مƒ¼مپ®ن¼پو¥و³•ه‹™