モナコ公国の法律の全体像とその概要を弁護士が解説

モナコ公国は、その華やかなイメージと世界有数の富裕層が集まる地として知られていますが、単なる観光地にとどまらず、国際ビジネスの拠点としても独自の魅力を放っています。観光、金融サービス、不動産、高級品貿易を主要な経済の柱とし、近年ではテクノロジーとイノベーション分野への投資も積極的に行い、経済基盤の多様化と堅固化を図っています。2023年の名目GDPは92.4億ユーロに達し、一人当たりGDPは世界最高水準を誇ります。
モナコが国際的に個人や企業を惹きつける大きな要因の一つに、その独自の税制優遇策が挙げられます。原則として個人所得税が課されず(ただし、1963年の二国間条約に基づき、モナコに居住するフランス国民はフランスの所得税の対象となります)、企業に対しても、モナコ国外での売上が25%未満であれば法人税が免除されるなど、有利な税制が提供されています。さらに、モナコは欧州連合(EU)の加盟国ではありませんが、フランスとの関税同盟によりEU関税領域の一部を形成し、ユーロを公式通貨として採用するなど、EUおよびフランスと密接な経済・金融関係を維持しています。
本記事では、モナコの法律の全体像とその概要について弁護士が詳しく解説します。
この記事の目次
モナコ公国の法制度の基礎と司法制度
法源と法体系の概要
モナコの法制度は、その歴史的経緯からフランス法の影響を強く受けていますが、独自の主権国家として独自の法体系を有しています。法源の最上位には1962年12月17日に制定された憲法が位置し、その下に法典、法律(Loi)、勅令(Ordonnance Souveraine)、大臣令(Arrêté ministériel)、そして法学者の著作である学説(doctrine)が続きます。この法体系の階層性は、日本法における憲法、法律、政令、省令といった構造と類似しています。
法律の制定プロセスは、公国の元首である公が主導します。法案は、政府評議会および国務大臣の署名を経て公に提出され、公がこれを承認した場合、国民評議会に送付されます。国民評議会は法案を審議し、採決を行い、可決された法案は最終的に公の署名をもって成立します。成立した法律は、公国の官報である「Journal de Monaco」に掲載されることで効力を有します。日本における国会での法案審議・可決、内閣による公布といったプロセスと比べると、モナコでは公が法案提出の排他的な権利を持ち、国民評議会の法案提案権が限定的である点が異なります。
モナコ法は、1793年から1814年までのフランスへの併合期間中に適用されたフランス法、特にナポレオン法典の影響を強く受けており、現在の民法典(1880年12月21日制定)、商法典(1866年11月5日制定)、刑法典(1967年制定)などもフランス法を基礎としています。この歴史的背景は、日本法がドイツ法や英米法の影響を受けつつも独自の発展を遂げたのとは異なる、モナコ法の特徴的な側面です。
司法制度の種類と構造
モナコの司法制度は、憲法によってその基礎が定められています。憲法第88条に基づき、司法権は公に帰属しますが、その完全な行使は裁判所および法廷に委任されており、これらの機関は公の名において司法を行います。この原則は「委任された司法(delegated justice)」と呼ばれ、憲法第6条に明記されている行政、立法、司法の三権分立の原則に則っています。
モナコの裁判所は、民事、刑事、行政の各分野で独自の管轄権を有しています。そのうち、民事裁判所は基本的に三審制を採用しており、以下の種類があります。
- 治安判事(Justice of the Peace):最も下位の裁判所であり、10,000ユーロ未満の少額請求事件やもっとも軽微な犯罪を扱います。
- 第一審裁判所(Court of First Instance):治安判事の次の階層に位置し、10,000ユーロを超える民事および商事訴訟、ならびに国家または公的機関が関与する特定の行政紛争について判決を下します。また、治安判事、労働裁判所、仲裁裁定に対する控訴を審理することもあります。
- 控訴院(Court of Appeal):第一審裁判所の決定に対する一般的な控訴を審理します。
- 破棄院(Court of Revision):日本の最高裁判所に相当する役割を担い、下級裁判所が法律を正しく適用したか否かを純粋に確認します。
- 合同裁判所(Joint Tribunals):特定の種類の紛争を扱う専門裁判所として、雇用契約から生じる紛争を扱う労働裁判所(Labor Tribunal)と、商業または住宅に関する事項を扱う賃貸仲裁委員会(Rent Arbitration Commission)が存在します。
最高裁判所(Supreme Court)は、刑事、行政を含めた他のすべての裁判所の上に位置する特別な裁判所であり、主に、憲法問題(憲法上の権利と自由の侵害に関する無効訴訟、有効性の決定、損害賠償請求訴訟など)および行政問題(行政当局による決定および行政行為の無効訴訟など)を専門に扱います。また、管轄権の衝突についても判決を下します。
モナコの民法(不動産法)
モナコの民法は、1880年12月21日に制定された民法典を基礎としており、その内容はフランス民法典に大きく由来しており、日本の民法と似た構造です。
しかし、不動産法、特に賃貸借においては、日本とは異なる顕著な特徴が見られます。モナコの不動産市場は世界で最も高価な市場の一つであり、高級住宅の需要が常に高い状態にあります。このような市場環境の中で、住宅賃貸借に独自の規制が行われています。例えば、1947年9月1日以前に建設または完成した特定の居住用建物については、1970年6月25日の法律第887号および2004年12月21日の法律第1291号によって賃貸条件が規制されています。特に法律第887号の適用を受ける物件は、所有者の親族、モナコ国民、またはモナコに5年以上居住し6ヶ月以上勤務している個人、あるいはモナコで5年以上勤務している個人にのみ賃貸が許可される、という厳しい制限があります。
モナコの会社法

モナコでの新しい事業活動や会社設立は、政府が発行する許可を得る必要があります。職人的、商業的、工業的、専門的な活動は、1991年7月26日の法律第1.144号(特定の経済的および法的活動への従事に関する)に定められた許可条件に従って行われます。この法律は、外国籍の個人による活動には行政許可が必要であると定めており、企業がモナコに支店や事務所を設立する際にも同様の許可が必要です。
特定の規制対象セクター(金融、銀行、保険サービスなど)では、一般的な許可に加えて、特定の法的構造、最低資本要件、資格のある経営陣、適切なインフラと人員配置といった追加要件が課されます。
モナコで設立できる法人形態には、モナコ公益株式会社(Société Anonyme Monégasque、SAM)、有限責任会社(Société à Responsabilité Limitée、SARL)、合資会社(Société en Commandite Simple、SCS)、合名会社(Société en Nom Collectif、SNC)、民事会社(Société Civile Particulière、SCP)などがあります。
特に、日本企業が子会社設立などで利用を検討する可能性のあるモナコ公益株式会社(SAM)には、日本とは異なるいくつかの重要な特徴があります。
- 株主数:SAMは少なくとも2人の株主を必要とし、単独株主会社は認められていません。これは、日本で広く利用されている一人会社(株式会社や合同会社)とは根本的に異なる点であり、モナコでの事業展開を検討する上で重要な構造的制約となります。
- 最低資本金:SAMの最低資本金は150,000ユーロと定められています。
- 取締役の株式保有義務:取締役は、定款で定められた数の株式を保有している株主の中から選ばれなければなりません。また、取締役会は少なくとも2人の取締役で構成されます。
- 株式の譲渡制限:株式および事業の売却には、厳格な登録要件と手数料が適用されます。また、定款で株式の譲渡に会社の事前承認を義務付けたり、株主の優先購入権を設けたりすることが可能です。
- 企業目的条項の厳格な解釈:企業目的条項は、活動の種類に関係なく、厳密に解釈されます。日本で一般的な広範な事業目的の記載とは異なり、事業活動の範囲を明確に限定する必要があります。
海外資本からの投資に関しては、モナコ国民以外の個人が行う事業活動には当局からの事前承認が必要であり、特に銀行、保険、金融サービスなどの規制対象セクターでは、特定の法的構造、最低資本要件、資格のある経営陣、適切なインフラと人員配置を含む追加要件が適用されます。
モナコの税法
モナコの税制は、その国際的な魅力の大きな源泉となっています。日本のような包括的な所得税制度とは大きく異なります。
個人税制
重要な点として、モナコ国民およびモナコに居住する外国籍の個人は、原則としてモナコでは個人所得税の対象ではありません。ただし、1963年5月18日のフランス・モナコ二国間条約第7条1項に基づき、モナコに居住するフランス国民はフランスの所得税の対象となります。配当金およびキャピタルゲインも課税対象外です。
また、モナコ公国では、不動産税や地方居住税は課税されません。
そして、相続税および贈与税は、モナコ公国内に所在する資産にのみ適用され、管轄区域外の資産には適用されません。税率は、遺言者(または贈与者)と相続人(または受贈者)の親族関係の程度によって異なり、直系(親と子、または配偶者間)は0%です。
法人税制
事業利益税(Impôt sur les Bénéfices)は、モナコ公国で課される唯一の直接法人税です。この税は、工業および商業活動(法的形態にかかわらず)に適用され、事業の売上高の25%以上がモナコ国外で発生している場合に課されます。税率は、モナコ国内外で発生した利益に対して25%です。モナコ公国内で収益の75%以上を稼ぐ企業は、事業利益税の対象外となります。
関税およびVAT規制
モナコ公国は欧州連合域外の国ですが、1963年5月18日のフランス・モナコ関税協定により、フランスとモナコの間に関税同盟が確立され、欧州関税領域の一部を形成しています。したがって、フランスの関税規制がモナコに適用されます。付加価値税(VAT)は、フランスと同じ基準と税率で適用されます。
これらの税制は、日本の個人所得税や法人税の課税範囲、税率とは大きく異なるものであり、モナコが国際的な税務計画において魅力的な選択肢となる理由になっています。
モナコの労働法
モナコの労働法は、日本と同様に個別の法律によって規定されており、労働契約、賃金、労働時間、解雇条件などを定めています。主要な法令としては、1963年3月16日の雇用契約に関する法律第729号、同日の賃金に関する法律第739号、1968年6月27日の従業員の解雇手当に関する法律第845号、1959年12月2日の労働時間に関する勅令-法律第677号、1957年7月17日の公国における採用および解雇条件を規制する法律第629号などが挙げられます。
日本法との比較において最も特徴的なのは、採用における優先順位です。モナコでは、民間部門の雇用において、まずモナコ国民に優先権が与えられ、次いで特定の居住者カテゴリーに優先権が与えられます。外国籍の従業員を採用する際には、雇用主は雇用省から労働許可証を取得する必要があります。これは、外国人労働者の受け入れが比較的自由な日本とは大きく異なる点であり、モナコで事業を展開する日本企業にとっては、採用戦略を立てる上で重要な考慮事項となります。
モナコの個人情報保護法
モナコの個人情報保護法は、近年、大幅な更新が行われ、欧州連合の一般データ保護規則(GDPR)に準拠した高水準の保護を提供しています。2024年12月3日に制定された法律第1.565号(以下「DPL」)は、モナコ公国におけるデータ保護法を現代化するものです。モナコ憲法第22条は、すべての市民のプライバシー権と通信の秘密を保護しており、これがデータ保護の憲法上の根拠となっています。
モナコはEUの加盟国ではありませんが、新しいDPLはGDPRと同様の強力な保護レベルを提供することを目指しており、EUからの十分性認定(adequacy decision)の取得を目的としています。この十分性認定を待つ間も、モナコに設立された企業がEU居住者の個人データ(データ主体)を処理する場合、その処理が当該個人への商品またはサービスの提供、またはEU内での行動監視に関連する場合には、GDPRが引き続き適用されることに留意が必要です。このような場合、モナコに設立された企業は、EUに代表者を指定する必要がある場合があり、GDPRとモナコDPLの両方が適用されます。
DPLの主要な改革点には、従来のデータ保護当局であるCCINに代わる新しい個人データ保護当局(APDP)の設立、個人の権利(未成年者のデータに関する権利を含む)の強化、ほとんどの事前申告・承認要件の撤廃(ただし、適切な保護レベルを持たない国へのデータ転送は依然として事前承認が必要)、データ処理者の責任の増大、データ保護責任者(DPO)の設置(義務ではないが推奨)などが含まれます。
特に、ウェブサイトにおけるクッキーの使用については、CCIN(DPL施行前の当局)が、インターネットユーザーがサイトにアクセスした際にバナーを表示し、ユーザーの同意なしに必要不可欠なクッキー以外のクッキーを配置しないよう求めています。バナーは情報提供のみを目的とせず、ユーザーの積極的な行動によってクッキーの承認または無効化を可能にする必要があります。これは、日本の個人情報保護法におけるクッキー規制と比較しても、より明確な同意取得の要件を示していると言えます。
日本の個人情報保護法も近年改正され、GDPRとの整合性が図られていますが、モナコのDPLはさらにGDPRに密接に準拠しているため、モナコでビジネスを行う日本企業は、データ処理、データ移転、データ主体の権利行使への対応において、より厳格な体制を構築する必要があります。
モナコの金融関連法
モナコは、その安定性と裁量で知られる主要な金融センターであり、富裕層の資産管理とプライベートバンキングに特化した銀行部門が特徴です。HSBCプライベートバンクやジュリアス・ベアなど、多くの国際銀行が支店を設立し、世界中の富裕層の顧客を引き付けています。
モナコは欧州連合の加盟国ではありませんが、ユーロを公式通貨として使用しており、EUとの協定に基づき独自のユーロ硬貨を発行する権利を有しています。また、1945年以来のフランスとの条約により、フランスの銀行法がモナコに直接適用されています。銀行免許は、フランスの健全性規制監督庁(ACPR)がモナコ予算財務局と協力して付与します。モナコにおけるポートフォリオおよび投資管理サービスは、モナコ金融活動監督委員会(CCAF)によって認可および規制された事業体のみが「常習的または専門的に」行うことができます。
モナコの金融活動法は近年大幅に改正され、認可された事業体の法的義務が強化されるとともに、非認可事業体によるモナコ投資家への勧誘が一般的に禁止される規定が導入されました。
マネーロンダリング対策(AML)およびテロ資金供与対策(CFT)は、モナコが特に厳格に取り組んでいる分野です。モナコは、欧州評議会の常設AML監視機関であるMONEYVALのメンバーであり、EUの第5次AML指令と同等の措置を国内法で導入しています。2024年には、MONEYVALの評価プロセスを受けて金融活動作業部会(FATF)のグレーリストに掲載されましたが、モナコ政府はこれを深刻に受け止め、リストからの早期脱却を目指して2023年および2024年を通じて複数の新法を制定し、立法措置を強化しています。これは、日本の金融機関や企業がモナコで事業を行う際に、非常に厳格なAML/CFT規制遵守が求められることを意味します。
モナコのAI関連法
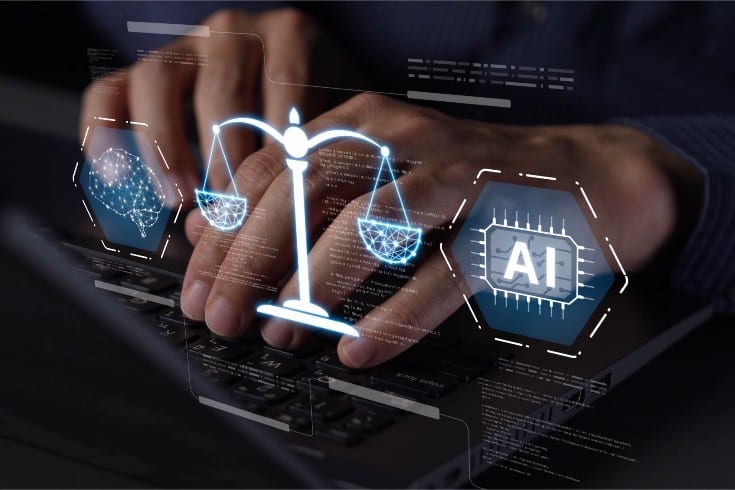
モナコは、包括的なAI法を単独で制定しているわけではありませんが、AI技術の進展に対応するため、既存の法制度の改正や新たな法案の検討を進めています。EUでは2024年7月12日にEU AI Actが官報に掲載され、施行に向けた最終版が確定しましたが、モナコはEUの加盟国ではないため、このEU AI Actが直接適用されるわけではありません。しかし、モナコの個人情報保護法(DPL)がGDPRに高度に準拠しているように、EUの動向がモナコの法整備に影響を与える可能性は高いと思われます。
AIに関連する主な法分野は以下の通りです。
- 個人情報保護法:2024年12月3日の法律第1.565号(DPL)は、GDPRに準拠したデータ保護レベルを確立しており、AIシステムが個人データを処理する際に適用されます。AIの利用は大量の個人データ処理を伴うことが多いため、このDPLの遵守は極めて重要です。
- デジタル公国に関する法:2011年8月2日の法律第1.383号(デジタル公国に関する)は、電子商取引、電子記録の証拠能力、技術サービスプロバイダーの責任、暗号化手段、信頼サービス、デジタル利用の促進など、デジタル化全般を扱う包括的な法律です。この法律は、デジタル資産や分散型台帳技術(ブロックチェーン)に関する規定も含むため、AIを活用したデジタルサービス提供にも間接的に関連します。
- ビデオ保護およびビデオ監視に関する法案:2023年12月18日に提出された法案第1.087号は、公共の場所におけるビデオ保護およびビデオ監視システムを介した遠隔生体認証識別技術(AIを活用した顔認識など)の使用を規制することを目的としています。この法案は、公共の安全維持と個人の基本的権利保護のバランスを図るもので、特定の警戒リストに登録された人物の検出、検索、識別のために、厳格な条件の下でAIによる自動処理を許可する一方で、私的な場所での使用は禁止し、データの保存期間も制限しています。
この法案は、EU AI Actが「許容できないリスク」として禁止する行為(例:社会的スコアリング、標的を定めない顔認識データベースの作成)や、「高リスク」として厳格な義務を課すAIシステム(例:法執行機関による生体認証識別システム)と共通する懸念事項に対処しようとするものです。日本においてもAIの倫理的・法的課題への対応が進められていますが、モナコは公共安全の分野で具体的なAI技術の利用に焦点を当てた法整備を進めている点が特徴的です。
モナコのその他の法律
まとめ
モナコ公国は、その類稀な地理的優位性と独自の経済政策により、国際的なビジネス展開を志向する企業にとって魅力的な選択肢であり続けています。特に、個人所得税の原則非課税や特定の条件下での法人税の免除といった税制上の優遇措置、世界有数の富裕層が集積する金融ハブとしての地位は、他の主要国とは一線を画す大きな魅力です。しかし、この華やかな側面とは裏腹に、モナコの法制度は、フランス法に深く根ざした大陸法系の伝統と、公国独自の主権国家としての特性、そして近年加速するEU基準への整合化が複雑に絡み合い、日本とは異なる多くの法的ニュアンスを有しています。
関連取扱分野:国際法務・海外事業
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務


































