スリランカ民主社会主義共和国の民法・契約法
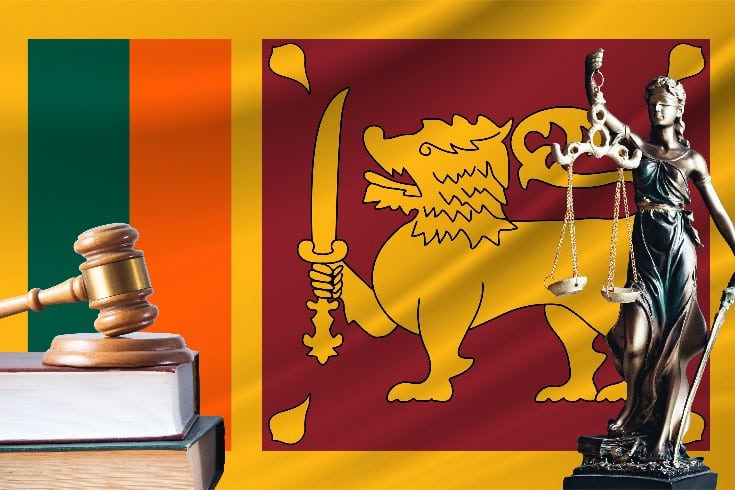
スリランカの法制度は、オランダ東インド会社(V.O.C.)が統治下の沿岸部に導入したローマ・オランダ法をその一般法(コモンロー)の基礎としています。その後、イギリス統治時代には、商取引や特定の法律分野でイギリス法が導入され、既存のローマ・オランダ法と並存する形で適用されるようになりました。さらに、スリランカは多様な民族で構成されており、シンハラ仏教徒に適用されるカンディアン法、タミル系ヒンドゥー教徒に適用されるテサワラマイ法、そしてイスラム教徒に適用されるイスラム法といった固有の個人法(パーソナル・ロー)が、特定の事項(婚姻・離婚、夫婦財産、相続など)に関しては一般法に優先して適用されます。これらの法律に加えて、現代の商取引や電子契約を規定する制定法も整備されています。
日本では、契約関係は民法を中心とする統一的なルールで整理できる場面が多いのに対し、スリランカでは「取引がどの領域に属するか」によって、参照すべきルールが一般法なのか、あるいは個人法が関与するのかが問題となる可能性があります。したがって、契約締結に先立っては、取引内容だけでなく、当事者が個人法の適用対象に当たるか、そして当該取引が個人法が関与する類型(身分・家族・相続・夫婦財産等)に該当しないかを含めて、前提事情を確認することが重要となります。
本記事では、スリランカの民法と契約法について詳しく解説します。
なお、スリランカの包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。
この記事の目次
「約因」(Consideration)の概念
スリランカの契約法を理解する上で、日本法との根本的な違いの一つは、「約因」(Consideration)の概念です。日本の民法においては、契約は当事者間の「意思の合致」のみで成立します。例えば、無償で物品を贈与する約束も、当事者双方が合意すれば贈与契約として法的に有効となります。一方で、スリランカはローマ・オランダ法を基層に英国法の影響も受ける混合法体系であり、単なる合意だけで常に当然に法的拘束力が認められるとは限りません。無償の約束がどこまで拘束力を持つかは、契約の類型や方式、当事者の意思表示の状況、原因(cause)の有無などを踏まえて評価されます。
約因の定義と基本原則
約因とは、契約が法的に有効であるために、各当事者が相手方に対して提供する「対価」を指します。これは、金銭、物品、サービス、約束、または不作為といった、何らかの交換の要素を意味します。この概念は「quid pro quo」(何かの見返りに何かを与える)というラテン語の原則に基づくと説明されることがあります。例えば、不動産の売買契約においては、売主が不動産を譲渡する約束と、買主が代金を支払う約束が、互いの約因となります。
この原則は、“A bare promise is not binding”(裸の約束は拘束力を持たない)という格言に集約されます。つまり、一方的な約束や、何の対価も伴わない合意は、たとえ当事者間で口頭や書面で合意がなされたとしても、原則として裁判所でその履行を強制することはできないのです。この点が、スリランカでビジネスを行う日本企業が、特に無償の取引や一方的な協定を締結する際に、その法的有効性を慎重に確認しなければならない最大の理由です。
「Causa」という概念
スリランカの契約法は、イギリスのコモンローに由来する「約因」の概念に加え、ローマ・オランダ法に由来する「causa」というより広範な概念の影響も受けています。約因が客観的な「交換」の要素を重視するのに対し、causaは約束の根拠、理由、または目的を意味し、その動機や道徳的義務までも包含する場合があります。
スリランカの判例法においては、道徳的義務がcausaを構成するのに十分であるとされた例があります。これは、道徳的義務を約因として認めないイギリスのコモンローとは異なる、スリランカ法独自の解釈を示すものです。
つまり、極めて単純化して言えば、「契約成立に約因が必要なので、無償譲渡は拘束力を持たないことが原則」だが「道義的責任もcausaたり得るので、例外的に無償譲渡が拘束力を持つこともある」というような構造です。
契約の形式と電子取引法の特例

日本の法律実務では、口頭での合意も法的有効性を持つのが原則ですが、スリランカの法律も同様の原則を採用しています。しかし、全ての契約が同じ形式で有効となるわけではなく、特定の取引には厳格な書面要件が適用されます。
口頭合意と不動産取引
スリランカ法において、一般的な商業契約は口頭での合意によっても成立し、法的強制力を持つことが可能で、この点は日本の法律と共通しています。
特に重要な例外として、不動産に関する取引が挙げられます。Prevention of Frauds Ordinance (不正防止条例)は、不動産の売買、譲渡、抵当権の設定、またはこれらを目的とする約束について、厳格な形式要件を定めています。具体的には、契約書が書面で作成され、公証人および二人の証人の面前で、すべての署名者が署名または指印を行うことが義務付けられています。この形式要件を満たさない不動産契約は、法的に無効と判断されます。
電子取引法(Electronic Transactions Act)
スリランカでは、現代の商取引における電子化の進展に対応するため、Electronic Transactions Act No. 19 of 2006が制定されています。この法律は、電子記録や電子署名に法的効力を与え、物理的な書面や署名と同等に扱うことを定めています。これにより、多くの商取引において、電子メールや電子署名を活用した契約締結が可能となり、日本の電子署名法と同様に、ペーパーレス化と取引の迅速化に貢献しています。
しかし、この法律には重要な例外が存在します。電子取引法第23条は、遺言や委任状、不動産の売買・譲渡、信託など、特定の種類の取引について、同法の適用を明示的に除外しています。これは、不動産取引における詐欺を防ぎ、確実な記録を残すという不正防止条例の法的精神が、デジタル時代の法制度においても維持されていることを示唆しています。日本の法務担当者が、スリランカでの事業で土地や建物の賃借・購入を計画する際には、一般的な商取引とは異なり、依然として物理的な書面と公証人による厳格な手続きが必要であることを認識しておく必要があります。
契約違反時の救済手段と時効

契約違反時の救済手段の概要
スリランカ法における契約違反の主な救済手段は、損害賠償と特定履行(Specific Performance)です。損害賠償は、契約違反がなければ被害者が得られていたであろう状態に、可能な限り回復させることを目的とします。その範囲は、通常発生する直接的な損失(general damages)と、当事者が事前に予見できた特別な状況下での損失(special damages)に分けられます。一方、特定履行は、裁判所が契約上の義務を文字通り履行するよう命じることで、金銭的補償では不十分な場合に適用される手段です。
特定履行の性質
日本法では、債務不履行時の主要な救済手段の一つとして特定履行が広く認められています。しかし、スリランカの法律では、特定履行は「例外的」な救済手段と見なされる傾向があります。裁判所は特定履行を命じるかどうかに大きな裁量権を持ち、損害賠償が適切な救済手段であると判断した場合、特定履行の請求を認めない場合があります。
この判例法理があるため、事前に損害賠償額を定める約定損害賠償条項(liquidated damages)を契約書に盛り込むことが非常に有効です。万一の紛争時にも救済手段が不確実になるリスクを低減し、予測可能性を高めることができます。
時効制度
スリランカの時効制度は、Prescription Ordinance No. 22 of 1971(時効条例)によって規定されています。この条例に基づき、書面による契約上の請求権に関する一般的な時効期間は、請求権が発生した日から6年間と定められています(書面によらない契約の場合は、請求権が発生した日から3年間)。
日本の時効制度と比較すると、その起算点に違いがあることがわかります。日本の民法では、債権の時効は原則として「権利を行使することができることを知った時から5年間」または「権利を行使することができる時から10年間」と規定されており、主観的な要素が含まれています。これに対し、スリランカの時効は客観的な事実、つまり「請求権が発生した日」からカウントが始まります。
まとめ
スリランカの契約法と日本法の違いとして、「約因」の概念、不動産取引における厳格な形式要件、特定履行の限定的な性質、そして時効の起算点を中心に解説しました。これらの違いは、単なる法制度上の相違点ではなく、事業計画、契約書ドラフト、そして債権管理といった実務上のプロセスに直接影響を及ぼす重要なリスク要因となります。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務


































