スリランカ民主社会主義共和国の法体系と裁判制度
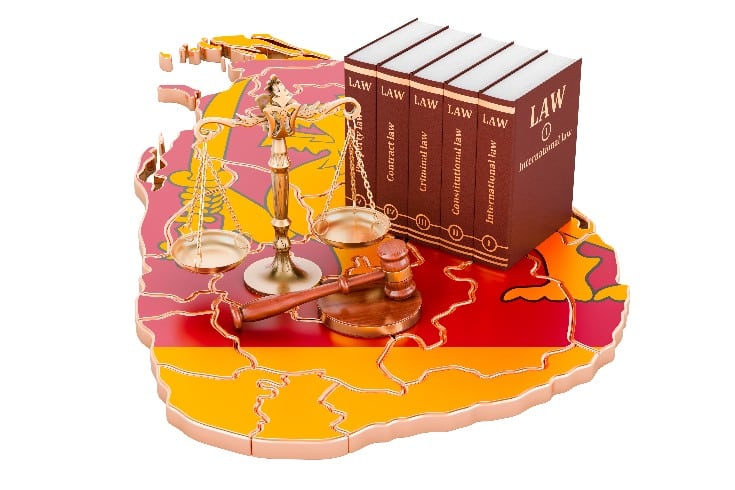
スリランカの法体系には、日本とは根本的に異なる点があります。日本が「六法」に代表される単一かつ統一された成文法主義を基盤とするのに対し、スリランカの法制度は、多様な歴史的背景から生まれた複数の法源が複雑に混在する「モザイク」のような構造を呈しているという点です。具体的には、旧宗主国であるオランダ統治時代に導入されたローマ・オランダ法を基礎としつつ、その後の英国植民地時代に持ち込まれた英国コモンロー、さらには民族や宗教、地域に固有の慣習法が多層的に絡み合っています。
この多層的な法体系から、特定の分野や当事者によっては適用される法律が異なるという法的複雑性が生じます。例えば、契約や商取引の基礎となる民法はローマ・オランダ法に由来する一方、刑事法は英国コモンローを基盤としており、さらに結婚や相続といった家族法分野では、コミュニティごとに異なる独自の慣習法が適用されます。
スリランカの法制度が持つこの特有の構造を解説し、特にビジネスとの関係で注意すべき法的ポイントについて掘り下げていきます。
なお、スリランカの包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。
この記事の目次
スリランカの国家体制と法の源泉
スリランカの法の源泉
スリランカは1978年憲法に基づく民主社会主義共和国であり、大統領が国家元首および政府の長を務めています。立法権は一院制の議会に与えられており、これは英国議会モデルに倣ったものです。この国家体制の下、スリランカの法制度は、日本の法典中心主義とは一線を画す、独特の混合法体系として機能しています。
スリランカの法の源泉は、大きく分けて三つあります。第一に、民法の「残余法」(Residuary Law)としての役割を担うローマ・オランダ法です。17世紀から18世紀にかけて沿岸部を支配したオランダによって導入されたものですが、詳細は後述します。第二に、18世紀末から同国全土を植民地化した英国が持ち込んだコモンローです。刑事法や会社法、知的財産法など、多くの分野がこの英国コモンローを基礎としています。第三に、特定のコミュニティにのみ適用される慣習法です。これらの法源が、憲法を最高法規として階層的に統合されています。
日本の法体系が単一の民法典を持つことで、すべての民事事案がその法典に基づき解決されるのに対し、スリランカでは、まず当事者に特定の慣習法が適用されるかを確認し、次に適用可能な特別法がないかを探し、これらの法律が適用されない場合に初めてローマ・オランダ法が適用されるという、多段階的な適用プロセスが存在します。したがって、契約書や合弁事業の法的枠組みを構築する際に、当事者の人種や出身地といった要素まで考慮に入れる必要があります。
歴史的変遷
スリランカの現在の法体系は、約400年にわたる外国支配の歴史的帰結です。16世紀に到来したポルトガル、続いて17世紀から18世紀にかけて沿岸部を支配したオランダは、それぞれ自国の法源を導入し、特にオランダは裁判制度を整備してローマ・オランダ法を適用しました。
この法体系の複雑さを決定づけたのは、1796年にオランダを放逐して支配権を確立したイギリスの統治政策でした。通常、征服地では旧宗主国の法律が廃止されることが多いのに対し、イギリスは既存の法律を継続させるという原則を採用しました。これは、新たな統治者であるイギリスの、旧宗主国の法体系を完全に抹消するのではなく、英米法を並行して導入することで、支配の正当性を確保し、社会の円滑な移行を図るという支配政策の帰結でした。この政策により、ローマ・オランダ法は廃止されることなく、英米法と共存する形でスリランカの法体系に組み込まれました。
スリランカの裁判所は、植民地時代に導入された法源を静的に適用するだけでなく、時代の変化に合わせて法を発展させてきました。言い方を変えれば、単なる外国法の継受に留まらず、スリランカ独自の法体系を形成してきました。裁判官は、ローマ・オランダ法や英米法の基本原則を、スリランカ社会の現実と結びつけて解釈し、新たな判例を形成することで、法律を動的なシステムとして機能させているのです。
「残余法」(Residuary Law)
「残余法」とは、特定の事案に適用されるべき特別な法律(制定法や慣習法など)が存在しない場合に、そのギャップを埋めるために適用される一般的な法律を指します。スリランカの文脈においては、ローマ・オランダ法が「残余法」としての役割を担っています。これは、特定のコミュニティを対象とする個人法や、議会が制定した特別法が適用されないすべての事柄において、ローマ・オランダ法が適用されることを意味します。この概念は、日本の民法が原則としてすべての民事事案に適用されるのと対照的です。
スリランカ法の多層構造と「個人法」

スリランカの法体系の最も特異な点の一つは、特定の民族や宗教に属する個人にのみ適用される「個人法」の存在です。
「個人法」とは、特定の民族的または宗教的コミュニティに属する人々に適用される慣習法を指します。これらの法律は、全ての国民に一律に適用されるのではなく、その人の出自や宗教によって適用対象が限定される点に特徴があります。例えば、カンダヤン法は仏教徒であり、かつてのカンダヤン王国の領域出身のスリランカ人に適用され、結婚や相続などを規定します。また、テサワラマイ法は北部州に所在する不動産、およびジャフナ出身のタミル人に適用されます。このように、個人の属性に基づいて適用される法律が異なるため、外国企業が現地で事業を展開する際には、取引相手の法的ステータスを慎重に確認することが不可欠となります。
例えば、北部州で主に適用されるテサワラマイ法は、その適用が「領土的」かつ「個人的」な性格を併せ持つことで知られています。これは、北部州に所在する全ての不動産に適用される「領土的」な側面がある一方で、ジャフナ出身のタミル人に「個人的」に適用される側面も持つことを意味します。このため、北部州以外、たとえばコロンボにある不動産であっても、その所有者がジャフナ出身のタミル人である場合、テサワラマイ法の規定が適用される可能性があります。
そして、テサワラマイ法の下では、例えば、女性が自身の名義で不動産を所有していても、結婚後は夫がその財産の管理権を持つため、夫の書面による同意がなければ、単独で不動産を売却したり抵当権を設定したりすることができない、という規律があります。このような文化的・歴史的背景を持つ法律があるため、例えば不動産取引のデューデリジェンスといった場面では、取引相手の民族的背景や家族構成まで踏み込んだ調査が不可欠となります。もし怠れば取引が無効となるリスクを孕んでいるからです。
以下に、スリランカの主要な個人法の概要をまとめます。
| 適用対象 | 適用分野の例 | |
|---|---|---|
| カンダヤン法 | 仏教徒で、かつてのカンダヤン王国領域(中央、北中央、ウバ、サバラガムワ、北西部の一部)出身のスリランカ人 | 結婚、離婚、相続、財産譲渡、養子縁組 |
| テサワラマイ法 | 北部州に所在する不動産、およびジャフナ出身のタミル人 | 結婚、相続、不動産(特に先買権)、財産権 |
| ムスリム法 | スリランカのイスラム教徒 | 結婚、離婚、後見、扶養 |
スリランカ司法制度の構造と裁判所の役割
スリランカの司法制度は、行政および立法から独立した存在であり、この独立性は憲法によって保障されています。この点において、日本の「三権分立」の原則と類似していると言えます。裁判官の任命プロセスには、大統領、議会、市民社会の代表から成る独立した機関「憲法評議会」が関与しており、最高裁判所および控訴裁判所の裁判官は、この評議会の承認を得て大統領が任命します。これにより、裁判官の任命に政治的な恣意性が入り込むことを防ぎ、司法の公正性が確保される仕組みとなっています。また、下級裁判所の司法官の任命、異動、懲戒は、最高裁判所長官を含む3名で構成される独立機関「司法サービス委員会(JSC)」に権限が与えられています。
スリランカの裁判所は、最高裁判所を頂点とする階層構造を持っています。
| 裁判所階層 | 裁判所名 | 主な管轄権 |
|---|---|---|
| 頂点 | 最高裁判所 | 最終上訴管轄権、憲法事項に関する管轄権、基本的人権の原管轄権 |
| 上訴審 | 控訴裁判所 | 控訴管轄権、令状管轄権 |
| 原審(上級) | 州高等裁判所 | 重大な刑事事件の原管轄権 |
| 原審(下級) | 地方裁判所 | 民事事件の原管轄権 |
| 原審(軽微) | 治安判事裁判所 | 軽微な刑事事件の原管轄権 |
基本的人権侵害に関する「原管轄権」

スリランカ最高裁判所が持つ「基本的人権侵害に関する原管轄権」とは、他の下級裁判所を経ることなく、直接、最高裁判所に人権侵害の訴えを提起できる権限を指します。日本の司法制度では、人権侵害の訴えは原則としてまず地方裁判所に提起され、その後、高等裁判所、最高裁判所へと上訴していくことになりますが、スリランカでは直接最高裁判所に訴えることができる点で大きく異なります。
具体的には、憲法で保障された基本的人権(例:言論の自由、平等の権利など)が、行政機関や政府の行動によって侵害されたり、そのおそれが生じたりした場合、市民は最高裁判所に直接訴訟を提起できます。この制度は、政府による不当な権力行使から市民を迅速に保護するための強力なセーフガードとして機能します。しかし、最高裁判所は全ての侵害事例について介入するわけではなく、不当な差別や意図的な不平等な扱いが本質的なものである場合に限られます。例えば、政治的な見解を理由に雇用が不当に打ち切られたケースや、正当な理由なく長期にわたって懲戒処分が遅延され、被処分者の権利が侵害されたケースなどが、この管轄権に基づき審理されています。
一方で、最高裁判所は企業(法人)の基本的人権侵害の訴えは受理しないという判例を示しています。これは、法人が憲法上の基本的人権の主体ではないという考え方によるもので、たとえ株主である個人がその会社の事業を通じて言論の自由を主張しようとしても、会社そのものが直接の被害者である場合、最高裁判所はこれを人権侵害の訴えとして受理しません。
「法案制定前審査」(Pre-enactment Review)
スリランカ最高裁判所が持つもう一つの重要な権限が、「法案制定前審査」(Pre-enactment Review)です。これは、議会で法案が成立し法律となる前に、その法案が憲法に合致しているかどうかを審査する権限を指します。日本の司法制度では、法律の合憲性は、具体的な事件の審理過程で事後的に判断される「付随的違憲審査制」が採用されていますが、スリランカでは法案段階で事前に審査が可能です。
この審査プロセスは、大統領または一般市民からの申し立てによって開始されます。法案が議会の議事日程に掲載されてから1週間以内に、最高裁判所に書面で請願書を提出しなければなりません。請願が提出されると、最高裁判所は3週間以内にその法案の合憲性を判断し、大統領と議会にその決定を伝えます。
この制度の具体例としては、コロンボ・ポート・シティ経済委員会法案に対する最高裁の判断が挙げられます。この法案は、外国からの投資誘致を目的とした特別経済区を設立するものでしたが、請願者らはその一部条項が憲法に違反していると主張しました。これに対し、最高裁判所は、複数の条項が憲法に違反しており、これらを修正しない限り、法案の成立には特別多数決と国民投票が必要であるとの判断を下しました。この判断を受けて、政府は法案を修正し、最終的に通常の手続きで成立させることができました。
まとめ
スリランカでの事業展開は、戦略的な優位性と政府のオープンな投資政策により、多くの可能性を秘めています。しかし、その成功の鍵は、同国の法体系が持つ固有の複雑性を深く理解することにあります。日本の成文法主義とは異なり、スリランカではコモンロー、ローマ・オランダ法、そして独自の慣習法が複雑に絡み合った混合法体系が機能しています。この多層性は、特に不動産や家族法といった分野で、人や場所によって適用される法律が異なるという、予期せぬ法的課題をもたらす可能性があります。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務


































