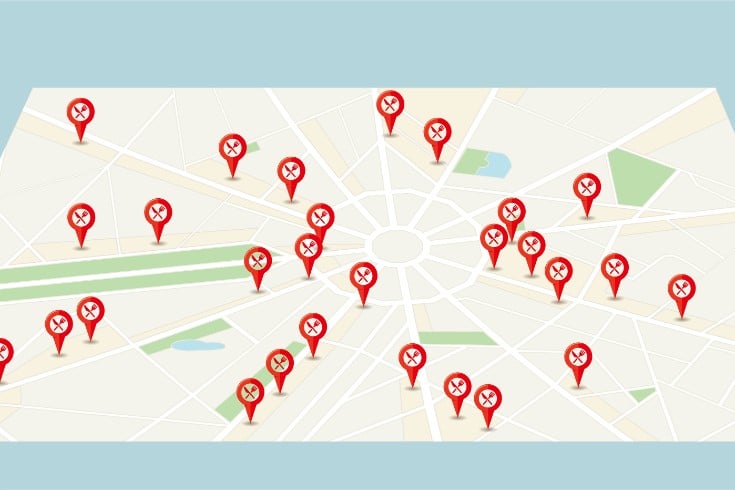職務著作とは?争いになった裁判例・判例を解説

職務著作に関する判例は、著作権の帰属を巡るトラブルを防ぐうえでの重要な指針となります。従業員や業務委託先が作成した著作物であっても、必ずしも企業に著作権が帰属するとは限りません。
職務著作として認められるためには、著作権法上の4つの成立要件をすべて満たす必要があり、契約や実務対応が法的に有効かどうかが争点となるケースもあります。
本記事では、各要件が争点となった実際の裁判例を紹介しながら、企業が著作権を適切に確保するための注意点を解説します。
この記事の目次
職務著作の成立要件
当サイトの別記事で解説しましたが、著作権法では、一定の要件を満たすときには、創作者を雇用している法人に著作権が帰属し、かつ当該法人が著作者になると定めています。これを、職務著作(または法人著作)といいます。
職務著作が成立するのは、以下の要件を満たす場合となります(著作権法第15条1項)。
- 著作物の創作が、法人等の発意に基づくものであること
- 法人等の業務に従事する者が職務上作成するもの
- その法人等の著作名義で公表するもの
- 契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと
要件を満たしているかどうかの判断によって、裁判では職務著作を認めない場合も多いのですが、それぞれの要件がどのように判断されているのかを、実際の裁判例で見てみましょう。
関連記事:職務著作とは?4個の要件と法人が著作権を得る方法を解説
「法人等の発意に基づく」ものと認められなかった事例
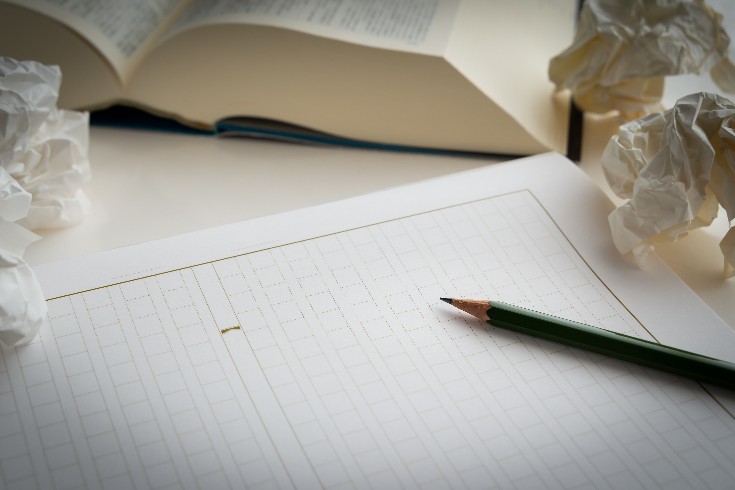
従業員が会社の業務時間や設備を利用して創作活動を行ったとしても、必ずしも職務著作が認められるわけではありません。「法人等の発意に基づく」要件が、実態に即して厳格に判断された裁判例を紹介します。
経緯
本件は、医療機関向けの経営コンサルティング会社Xが、元従業員Yの出版した書籍について同社の著作物を複製したものであり著作権を侵害していると主張した事案です。XはYに対し、書籍の出版の差止めと損害賠償を求めて訴訟を提起しました。
最大の争点は、Yが執筆した書籍のもとになった著作物がXの「職務著作」に該当するかどうかという点であり、特に「法人等の発意に基づく著作物」といえるかどうかが判断の中心となりました。
原審の判断
東京地方裁判所は、Xの請求を棄却する判決を言い渡しました。問題となった著作物について、職務著作の要件を満たさないと判断されたためです。
Xは、Yの執筆活動が業務時間内に行われたこと、会社の会議室や貸与されたパソコンが使われたことなどを主張しました。しかし、裁判所はこれらの状況証拠だけでは法人等の発意に基づく著作物とはいえず、Yが個人的に受けた執筆依頼であるという認定を覆すには不十分であると指摘しています。
結果として、Xの著作権侵害の訴えは認められませんでした。
控訴審の判断
控訴審である知的財産高等裁判所も原審の判断を支持し、Xの控訴を棄却しました。主な理由は、職務著作の成立に不可欠な要件である「法人等の発意」が認められないと判断された点にあります。
裁判所は以下の事実を総合的に評価し、会社の発意を否定しました。
- 出版社からの執筆依頼は、Xを介さずY個人に直接行われた。
- Xと出版社との間で、執筆に関する契約書や覚書は一切作成されていなかった。
- Yが退職する際、執筆作業に関する引き継ぎはまったく行われなかった。
- 出版された書籍はY個人の著作名義であり、原稿料もY個人に支払われた。
これらの客観的事実から、執筆は会社の業務として企画・遂行されたものではなく、あくまでもY個人による活動であったと裁判所は結論づけています。
著者が法人の社員であるからといって、その著作物の著作権が法人に帰属するとは限りません。「法人等の発意に基づく」を検討するに際しても、この裁判例のように、様々な事情が総合的に考慮されます。
「法人等の業務に従事する者」と認められなかった事例

続いて、フリーランスのクリエイターが「法人等の業務に従事する者」に該当するかどうかについて、第一審と控訴審で見解が分かれた裁判例を取り上げます。雇用契約が存在しない場合に職務著作が認められるかどうかという点で、重要な示唆を与える事例です。
経緯
本件は、フリーランスの写真家Xが、撮影業務を依頼した会社Yに対して著作権侵害を理由に損害賠償を求めた事案です。
Yは、Xが撮影したオートバイレースの写真を、イベント主催者のWebサイトやポスターで使用することを認めていました。
これに対しXは、Yによる写真の使用が自身の承諾を得ていない無断使用であると主張し、著作権(複製権・譲渡権)および著作者人格権の侵害にあたると訴えたのです。一方でYは、Xが事前に写真の無償利用を許諾していたと反論しました。
裁判では、XがYの「業務に従事する者」に該当するか、撮影した写真が「職務著作」にあたるかどうかに加え、Xが写真の無償利用を事前に許諾していたかどうかが主要な争点となりました。
原審の判断
原審である水戸地方裁判所龍ケ崎支部は、職務著作の成立を認めたうえで写真家Xの請求を棄却しました。裁判所は、Xが会社の「業務に従事する者」に該当し、当該写真は会社の著作物にあたると判断したためです。
その根拠として、Yが撮影場所やアングルについて具体的な指示を出していた点が挙げられました。また、Xへの報酬が撮影枚数に応じた出来高払いではなく、拘束時間に基づく定額制であったことも雇用に近い指揮命令関係を示す証左と判断しました。
これらの事実からXの創作活動における裁量は限定されており、写真は会社業務として制作されたものと結論づけられました。
控訴審の判断
控訴審である知的財産高等裁判所は、原審の判断を覆し職務著作の成立を否定しました。写真家Xを会社の指揮監督下にあった「業務に従事する者」と認めることはできない、と結論づけたのです。
裁判所は、Xが個人で写真事務所を経営するプロのカメラマンである点に注目しました。また、Xが自身の撮影であることを示すクレジットの表示を求め、会社側がそれに応じた事実もXが独立した立場で業務にあたっていた証拠と見ています。
ただし、Xは事前に写真の無償利用を許諾していたと認定されたため、著作権侵害は成立せず、請求自体は棄却される結果となりました。
プロの写真家として行動している人を、法人の指揮監督の下において労務を提供するという実体にあったのだと裁判所に認めてもらうことは難しいので、あらかじめ契約書を取り交わし、著作権の帰属を明確にしておくべきだったといえます。
「職務上作成するもの」と認められなかった事例

従業員が会社の企画で著作物を制作した場合でも、その業務内容によっては「職務上作成したもの」とは認められない場合があります。弁理士が所属事務所の企画で執筆した原稿について、職務著作の成立が否定された判例を見ていきましょう。
経緯
弁理士である原告は、勤務先の特許事務所が企画した書籍の執筆者募集に応じ、「著作権の登録」に関する原稿を執筆しました。執筆は勤務時間外で行われ、事務所からの指揮監督も受けていません。
その後、原告が特許事務所を退職する際、原稿の著作権譲渡に関する覚書を同事務所と取り交わしました。原稿は書籍として出版されましたが、原告の氏名は掲載されておらず、原告は著作者人格権の侵害を理由に損害賠償を請求しています。
裁判では、この原稿が事務所の職務著作物に該当するか否かが主要な争点となりました。
裁判所の判断
裁判所は、本件原稿が原告の日常業務に含まれず、勤務時間外に執筆された点などを踏まえ「職務上作成された著作物」には該当しないと判断しました。
理由として、原稿の執筆が特許事務所の本来的な業務には含まれず日常の業務とも関係がなかったこと、執筆が勤務時間外に行われ事務所の指揮命令も受けていなかった点を挙げています。
加えて、原告と事務所が交わした覚書に「職務に関連して作成」とあえて記載されていたことも、かえって職務著作ではないことを示す事情として重視されました。
これらの事実を総合的に考慮し、裁判所は本件原稿について職務著作の成立を否定。その結果、原告の氏名表示権の侵害が認められ、特許事務所に対して損害賠償の支払いが命じられました。
著者が法人の社員であるからといって、その著作物の著作権が法人に帰属するとは限りません。「職務上作成するもの」を検討するに際しても、やはり、様々な事情が総合的に考慮されます。
「法人等の著作名義で公表するもの」と認められなかった事例
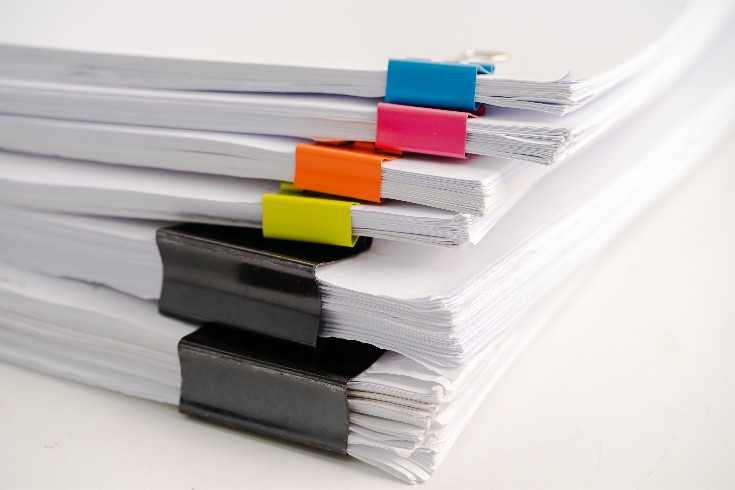
会社名が著作物に記載されている場合でも、「法人等の著作名義」とは判断されず職務著作が成立しない場合もあります。その判断基準が示された裁判例を紹介します。
経緯
本件は、社団法人Y2工業会が主催する「計装士技術維持講習」で使用された資料(以下「12年度資料」)に関して提起された著作権侵害訴訟です。この資料は、Y1会社に所属していた従業員Xが、平成12年度に作成したものでした。
後にXが他部署へ異動したことに伴い、講習の担当を引き継いだBが、Xが作成した12年度資料の電子データをもとに13年度および14年度用の新たな講習資料を作成。その際、資料の内容には一部変更が加えられており、それを受けてXは自身の著作権が侵害されたと主張し、訴訟を起こしました。
これに対してY1およびY2は、該当する資料は著作権法第15条第1項に規定されている「職務著作」に当たり、著作者はX本人ではなくY1であると反論。争点となったのは、職務著作の成立要件の一つである「法人等の名義の下で公表されたもの」すなわち「公表名義要件」を満たしていたかどうかという点でした。
原審の判断
東京地方裁判所は、12年度資料が職務著作には該当しないと判断。特に、公表名義要件を満たすかどうかについては、資料の体裁や名義の表示方法を重視しました。
判決では、資料集全体の表紙にはY2工業会の名があったものの、12年度資料そのものには「Y1株式会社東京支店計装システム部部長 X」と記載されていました。この表記は講師の所属と肩書であって、著作名義としての法人表示ではないとされました。
形式的に法人名があっても、それが実質的に著作名義であると理解できなければ職務著作としての公表にはあたらないと判断されたのです。
控訴審の判断
控訴審も原審の判断を支持し、職務著作の成立を否定しました。控訴審は、表紙に記された「Y1株式会社」という記載は、あくまで講師の所属を示すにとどまり著作名義とは解されないと明言しています。
さらに公表名義要件の判断基準として、表示の形式だけでなく、受け手がその表示を著作名義として認識するかどうかという実質面を重視する必要があるとしました。
すなわち、単に法人名が記されているだけでは足りず、それが著作権者としての名義であると受け取られることが必要であると述べています。
「著作物の創作が、法人等の発意に基づくもの」であり、「法人等の業務に従事する者が職務上作成するもの」であったとしても、その著作物の著作権が法人に帰属するとは限りません。職務著作は、冒頭にあげた4つの要件を全て満たしたときにだけ、認められます。
参考:東京地方裁判所平成18年2月27日判決
契約書・就業規則の重要性
職務著作に関するトラブルを防ぐには、契約書や就業規則において著作権の帰属先を明確に定めることが重要です。
職務著作の成立には法律で定められた4つの要件があるため、就業規則に「会社に帰属する」と記載するだけでは、著作権が自動的に企業に移転することにはなりません。
企業は、従業員と著作権譲渡の契約を結ぶことで権利を取得できます。ただし、著作者人格権は譲渡できませんが、その行使を行わない旨の合意を交わすことは可能です。
また、派遣社員や外部委託者と契約を結ぶ際には、著作権の取り扱いについて契約書で明示しておく必要があります。
著作権をめぐる紛争を防ぐには、ルールの整備が不可欠です。判断に迷う場合には、弁護士などの専門家に相談して対応方針を検討することをおすすめします。
まとめ:著作権の帰属は契約や実態を踏まえ慎重に判断を
法人等の経済的な負担において作成された著作物を当該法人等が利用するに当たっては、著作物の権利関係を集中し、明確にしなければ、その円滑な利用に支障を来す場合が多いと考えられるので、職務著作の規定が採用されたわけですが、あらかじめ権利関係を明確にしておくことが必要です。
職務著作を主張できるのか否か、あるいは職務著作を主張されているのだが認めざるを得ないのか否か、判断が難しい問題です。経験豊かな弁護士にご相談ください。
当事務所による対策のご案内
モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に豊富な経験を有する法律事務所です。近年、著作権をめぐる知的財産権は注目を集めており、リーガルチェックの必要性はますます増加しています。当事務所では知的財産に関するソリューション提供を行っております。下記記事にて詳細を記載しております。
モノリス法律事務所の取扱分野:各種企業のIT・知財法務
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務