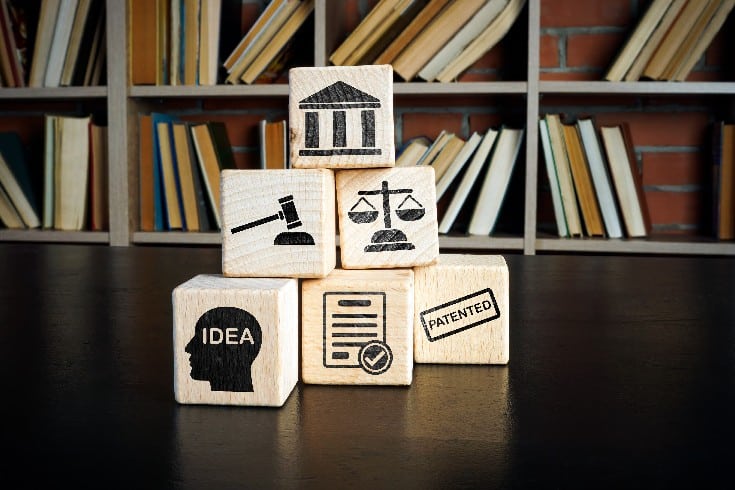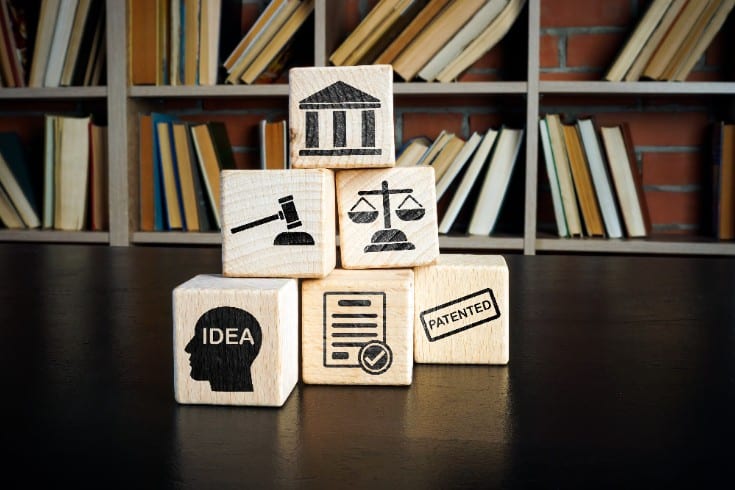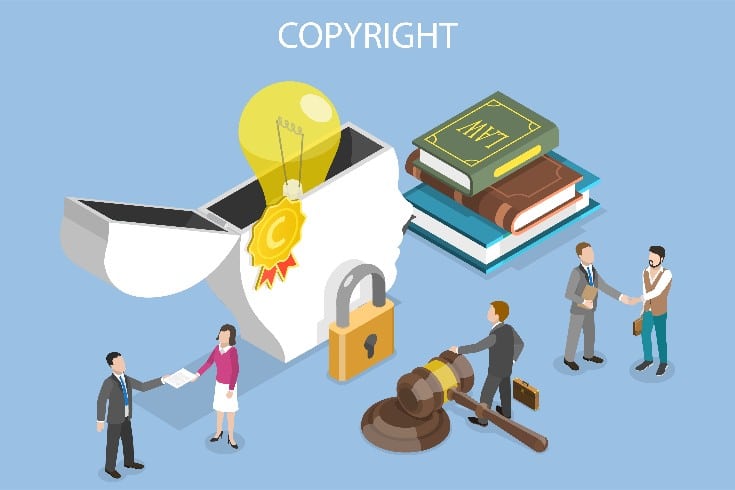كّùغ╜£µذرµ│ـع«ف╝ـق¤ذعذع»ي╝الرµ│ـعسكةîععاعéع«4كخغ╗╢عéْكدثكزش

عâةعâçعéثعéتلïفû╢عسعèععخعكذءغ║ïعéعé│عâ│عâعâ│عâعîغ╗ûكàع«كّùغ╜£µذرعéْغ╛╡ف«│عùعخععزععïعرععïعéْقت║كزعآعéïعôعذع»µح╡عéعخلçكخعدعآعéغ╛╡ف«│عîكزعéعéëعéîعافب┤فêعµ│ـقأعزعâêعâرعâûعâسعéµف«│ك│بفاعسقآ║ف▒ـعآعéïعèعإعéîعîعéعéèع╛عآعé
عإعôعدلçكخعذعزعéïع«عîعîف╝ـق¤ذععذععكâعêµû╣عدعآعéكّùغ╜£µذرµ│ـعدع»عغ╕ف«أع«كخغ╗╢عéْµ║عاعآفب┤فêعسعغ╗ûكàع«كّùغ╜£قëرعéْكçزك║سع«كّùغ╜£قëرع«غ╕صعدفêرق¤ذعآعéïعôعذعîكزعéعéëعéîعخعع╛عآعé
µ£شكذءغ║ïعدع»عكّùغ╜£µذرع«4عجع«ف╝ـق¤ذكخغ╗╢عéْكر│عùعكدثكزشعùع╛عآعéف«ëفàذعزعâةعâçعéثعéتلïفû╢ع«عاعéعسعف╝ـق¤ذع«عâسعâ╝عâسعéْµصثعùعقكدثعùع╛عùعéçععé
عôع«كذءغ║ïع«قؤ«µشة
كّùغ╜£µذرعذع»

ع╛عأععإعééعإعééععîكّùغ╜£µذرععذع»عكّùغ╜£قëرعسعجععخعكّùغ╜£كàعسكزعéعéëعéîعéïµذرفêرع«عôعذعéْععع╛عآعéكّùغ╜£µذرعسعجععخع»عقë╣كذ▒µذرع«عéêععسقآ╗لî▓قصëع«µëïق╢أععéْكةîعéعزععذعééعكّùغ╜£عéْعùعاµآéقé╣عدعغ╜ـعéëع«µëïق╢أععéْكخعآعéïعôعذعزعف╜ôق╢عسقآ║ق¤اعùع╛عآعéكّùغ╜£µذرع»عكزعéعéëعéîعéïعاعéعسعµëïق╢أععéْكخعùعزععôعذعïعéëعقةµû╣ف╝غ╕╗ق╛رعذكذعéعéîع╛عآعé
غ╗ûغ║║ع«كّùغ╜£قëرعéْعقةµûصعدفêرق¤ذعآعéïعôعذع»عفافëçعذعùعخعكّùغ╜£µذرµ│ـعسلـفعآعéïعôعذعذعزعéèع╛عآعéعإع«عاعéعغ╗ûغ║║ع«كّùغ╜£قëرعéْفêرق¤ذعآعéïلأؤعسع»عكّùغ╜£µذرµ│ـعسلـفعùعزععéêععسµ░ùعéْغ╗ءعّعéïف┐àكخعîعéعéèع╛عآعéغ╗ûغ║║ع«كّùغ╜£قëرعéْلرµ│ـعسفêرق¤ذعآعéïµû╣µ│ـعذعùعخعµذرفêركàعïعéëعكّùغ╜£قëرع«فêرق¤ذعسعجععخعîكذ▒كس╛ععéْف╛ùعéïعذععµû╣µ│ـعîعéعéèع╛عآعéعôع«عîكذ▒كس╛ععéْف╛ùعéïفحّق┤عسعجععخع»عغ╕كêشقأعسععâرعéجعé╗عâ│عé╣فحّق┤عذععéعéîع╛عآعé
كذ▒كس╛عéْف╛ùعزععخعééغ╗ûغ║║ع«كّùغ╜£قëرعéْفêرق¤ذعآعéïعôعذعîعدععéïµû╣µ│ـ
غ╕èكذءعدع»عكذ▒كس╛عéْف╛ùعخغ╗ûغ║║ع«كّùغ╜£قëرعéْفêرق¤ذعآعéïµû╣µ│ـعéْق┤╣غ╗ïعùع╛عùعاعîعكذ▒كس╛عéْف╛ùعزععخعééغ╗ûغ║║ع«كّùغ╜£قëرعéْفêرق¤ذعدععéïµû╣µ│ـعîعéعéèع╛عآعéغ╛ïعêع░عغ╗حغ╕ïع«عéêععزلûتغ┐éعدع»عكذ▒كس╛عéْف╛ùعزععخعééغ╗ûغ║║ع«كّùغ╜£قëرعéْفêرق¤ذعآعéïعôعذعîف»كâ╜عدعآعé
- قدقأفêرق¤ذعâ╗غ╗ءلأف»╛ك▒ةكّùغ╜£قëرع«فêرق¤ذقصë
- µـآكé▓لûتغ┐é
- فؤ│µؤ╕لجذعâ╗ق╛كةôلجذعâ╗فأقëرلجذقصëع«لûتغ┐é
- قخقحëلûتغ┐é
- فب▒لôلûتغ┐éقصë
- قسïµ│ـعâ╗ف╕µ│ـعâ╗كة┐لûتغ┐é
- لإئفû╢فêرعâ╗قةµûآع«فب┤فêع«غ╕èµ╝¤عâ╗µ╝¤فحعâ╗غ╕èµءبعâ╗فثك┐░عâ╗ك▓╕غ╕قصëع«لûتغ┐é
- ف╝ـق¤ذلûتغ┐é
- ق╛كةôفôعâ╗فآق£اعâ╗ف╗║ق»ëلûتغ┐é
- عé│عâ│عâ¤عâحعâ╝عé┐عâ╝عâ╗عâعââعâêعâ»عâ╝عé»لûتغ┐é
- µ¤╛لف▒عâ╗µ£ëق╖أµ¤╛لف▒لûتغ┐é
كّùغ╜£µذرع«فê╢لآعسع»علçكخعزµق╛رعîعéعéèع╛عآعéµûçفîûع«قآ║ف▒ـعسع»علف╗ع«كّùغ╜£قëرعïعéëع«فصخع│عéµ┤╗ق¤ذعîµشبعïعؤع╛عؤعéôعéلف║خعزغ┐إكص╖ع»عفë╡غ╜£µ┤╗فïـعéْفخذعْعéïµç╕ف┐╡عîعéعéïعاعéلرفêçعزعâعâرعâ│عé╣عîف┐àكخعدعآعé
عاعبعùعقةµإةغ╗╢ع«فêرق¤ذع»كّùغ╜£µذركàع«فêرقؤèعéْµعزعع╛عآعéعإع«عاعéعفêرق¤ذق»فؤ▓عéْفê╢لآعآعéïعôعذعدعµذرفêرغ┐إكص╖عذµûçفîûقآ║ف▒ـع«غ╕ةقسïعéْفؤ│عثعخعع╛عآعé
كّùغ╜£قëرعéْلرµ│ـعسفêرق¤ذعآعéïعôعذعîعدععéïعîف╝ـق¤ذعع«كخغ╗╢عذع»

كçزقج╛عدعâةعâçعéثعéتعéْلïفû╢عآعéïفب┤فêعغ╗ûغ║║ع«كّùغ╜£قëرعéْف╝ـق¤ذعآعéïعé▒عâ╝عé╣عîعéعéèع╛عآعéعîف╝ـق¤ذعدعéعéîع░كذ▒عـعéîعéïععذµ╝بق╢عذكâعêعخععéïغ║║عééعع╛عآعîعفàذعخع«ف╝ـق¤ذعîقةفê╢لآعسكذ▒عـعéîعéïعéعّعدع»عéعéèع╛عؤعéôعéكّùغ╜£µذرµ│ـعسفا║عحععلرµ│ـعزف╝ـق¤ذع«µû╣µ│ـعéْف«êعéïف┐àكخعîعéعéèع╛عآعé
µûçقسبعدعéعéîعYouTuberعîعéتعââعâùعآعéïفïـق¤╗عدعéعéîععîكز░عïعîغ╜ـعïعéْفا╖قصعùعاعâ╗كذفèعùعاععذععثعاعôعذعéْفûعéèغ╕èعْععإعéîعسف»╛عآعéïµكخïكسûكرـعزعرعéْµ▓ك╝ëعآعéïعé▒عâ╝عé╣عîعéعéèع╛عآعéعôععùعاعé▒عâ╝عé╣عسµ£عééف╜ôعخع»ع╛عéïعكّùغ╜£µذركàي╝êعجع╛عéèعéزعâزعé╕عâèعâسع«µûçقسبعéقآ║كذعéْكةîعثعاكàي╝ëع«كذ▒كس╛عîعزععخعééعزعùف╛ùعéïكّùغ╜£قëرفêرق¤ذµû╣µ│ـعîعكّùغ╜£µذرµ│ـغ╕èع«عîف╝ـق¤ذععدعآعé
كّùغ╜£µذرµ│ـقشش32µإةقشش1لبàعدع»عف╝ـق¤ذع»عغ╗حغ╕ïع«عéêععسكخف«أعـعéîعخعع╛عآعé
فàشكةذعـعéîعاكّùغ╜£قëرع»عف╝ـق¤ذعùعخفêرق¤ذعآعéïعôعذعîعدععéïعéعôع«فب┤فêعسعèععخععإع«ف╝ـق¤ذع»عفàشµصثعزµàثكةîعسفêكç┤عآعéïعééع«عدعéعéèععïعجعفب▒لôعµë╣كرـعقب¤قر╢عإع«غ╗ûع«ف╝ـق¤ذع«قؤ«قأغ╕èµصثف╜ôعزق»فؤ▓فàعدكةîعéعéîعéïعééع«عدعزعّعéîع░عزعéëعزععé
e-Govµ│ـغ╗جµج£ق┤تي╜£كّùغ╜£µذرµ│ـقشش32µإةقشش1لبà
غ╗ûغ║║ع«كّùغ╜£قëرع«ف╝ـق¤ذعسعجععخعكّùغ╜£µذرµ│ـغ╕èع«لرµ│ـعزف╝ـق¤ذعذعùعخكزعéعéëعéîعéïعاعéعسع»عغ╗حغ╕ïع«كخغ╗╢عéْµ║عاعآف┐àكخعîعéعéïعذكâعêعéëعéîعخعع╛عآعé
عآعدعسفàشكةذعـعéîعخععéïكّùغ╜£قëرعدعéعéïعôعذي╝êفàشكةذكخغ╗╢ي╝ë
ف╝ـق¤ذع«ف»╛ك▒ةعذعزعéïكّùغ╜£قëرع»عفàشكةذعـعéîعخععéïف┐àكخعîعéعéèع╛عآعéµ£زفàشكةذع«عééع«ع»عكّùغ╜£µذركàع«µفّعîغ╕µءقت║عدعéعéïعاعéعفافëçعذعùعخف╝ـق¤ذع»كزعéعéëعéîعخعع╛عؤعéôعé
فàشكةذعذع»عفç║قëêعâ╗غ╕èµ╝¤عâ╗µ╝¤فحعâ╗غ╕èµءبعâ╗فàشكةلغ┐ةعزعرعسعéêعéèعفàشكةي╝êغ╕قë╣ف«أع╛عاع»قë╣ف«أعïعجفجأµـ░ع«كàي╝ëعسµقج║عـعéîعاقè╢µàïعéْµîçعùع╛عآعéعéجعâ│عé┐عâ╝عâعââعâêغ╕èعسعéتعââعâùعâصعâ╝عâëعـعéîعافب┤فêعééعفàشكةذعذعـعéîع╛عآعé
فب▒لôعéفàشف╝قآ║كةذعزعرعدف║âعفàشلûïعـعéîعخععéïكّùفغ║║ع«فآق£اعéفç║قëêعـعéîعاµûçقî«عزعرع»عفàشكةذµ╕êع┐عدعéعéïعôعذعîفجأععدعآعéف╝ـق¤ذعéْعآعéïلأؤع»عغ║ïفëعسعإع«كّùغ╜£قëرعîفàشكةذعـعéîعخععéïعïعéْقت║كزعآعéïف┐àكخعîعéعéèع╛عآعé
ف╝ـق¤ذعـعéîعخععéïعôعذي╝êف╝ـق¤ذكخغ╗╢ي╝ë
عôع«كخغ╗╢ع»عغ╕ïكذءع«عéêععسععـعéëعس2عجعسفêعّعéëعéîع╛عآعé
- µءقئصفî║فêµدي╝أف╝ـق¤ذلâذفêعسعéسع髵ïشف╝دعéْعجعّعéïعزعرعùعخعف╝ـق¤ذلâذفêعذفêرق¤ذكàعîغ╜£µêعùعالâذفêعذعéْعµءقئصعسفî║فêحعدععéïف┐àكخعîعéعéèع╛عآعé
- غ╕╗ف╛ôلûتغ┐éµدي╝êغ╗ءف╛ôµدي╝ëي╝أفêرق¤ذكàع«غ╜£µêعùعالâذفêعîµح╡عéعخف░ّعزععع╗عذعéôعرعîغ╗ûغ║║ع«كّùغ╜£قëرعدعéعéïعéêععزفب┤فêعسع»عف╝ـق¤ذعذعععôعذع»عدعع╛عؤعéôعéعéعع╛عدعîف╝ـق¤ذعآعéïلâذفêعîف╛ôعدععéزعâزعé╕عâèعâسع«لâذفêعîغ╕╗ععذععلûتغ┐éµدعîف┐àكخعدعآعé
عôع«عéêععسعف╝ـق¤ذعîكزعéعéëعéîعéïعاعéعسع»عف╝ـق¤ذلâذفêعذكçزك║سع«كّùغ╜£قëرعذعéْµءقت║عسفî║فêعùعكçزك║سع«كّùغ╜£قëرعîعîغ╕╗عف╝ـق¤ذعîعîف╛ôععذعزعéïلûتغ┐éµدعéْغ┐إعجف┐àكخعîعéعéèع╛عآعéغ╕صف┐âعذعزعéïع«ع»عéعع╛عدكçزك║سع«كسûك┐░عدعéعéèعف╝ـق¤ذع»عإع«كث£ف╝╖عéكثغ╗ءعّع«عاعéعسغ╜┐عéعéîعزعّعéîع░عزعéèع╛عؤعéôعé
عزعèعفءعسفêلçع«فجأف░ّعبعّعدغ╕╗ف╛ôلûتغ┐éعîفêجµûصعـعéîعéïعéعّعدع»عéعéèع╛عؤعéôعîعف╝ـق¤ذعîفجدفèعéْفبعéكçزف╖▒ع«عé│عâةعâ│عâêعîعéعأعïعدعéعéïفب┤فêعسع»عغ╕╗ف╛ôلûتغ┐éعîف┤رعéîعخععéïعذعـعéîعéïعôعذعîعéعéèع╛عآعéف╝ـق¤ذعسعèععخع»عµءقت║عزفî║فêحعذغ╕╗ف╛ôلûتغ┐éع«µكصءعîلçكخعدعآعé
فàشµصثعزµàثكةîع╕ع«لرفêµدي╝êفàشµصثµàثكةîكخغ╗╢ي╝ë
كّùغ╜£قëرعéْلرµ│ـعسف╝ـق¤ذعآعéïعسع»عففêلçعدقت║قسïعـعéîعاعîفàشµصثعزµàثكةîععسف╛ôعف┐àكخعîعéعéèع╛عآعéعôعéîع»عففêلçعدف║âعفùعّفàحعéîعéëعéîعخععéïف╝ـق¤ذعâسعâ╝عâسعسµ▓┐ععôعذعéْµفّ│عùع╛عآعé
عîق╡╢ف»╛لا│µاغ║ïغ╗╢عي╝êµإ▒غ║شلسءقصëكثفêجµë ف╣│µê14ف╣┤4µ£ê11µùحفêجµ▒║ي╝ëعدع»عق┐╗كذ│كّùغ╜£قëرعéْف╝ـق¤ذعآعéïفب┤فêعسع»عفاكّùغ╜£قëرعبعّعدعزعق┐╗كذ│كàفعééµءقج║عآع╣ععدعéعéïعذكثفêجµëعîفêجµûصعùع╛عùعاعéق┐╗كذ│كàفعéْكذءك╝ëعùعزعïعثعاكتسفّèع«كةîقé║ع»عفàشµصثعزµàثكةîعسفعآعéïعذكزف«أعـعéîعاع«عدعآعé
عôع«فêجµ▒║عîقج║عآلأعéèعلرµ│ـعزف╝ـق¤ذعذعآعéïعاعéعسع»عفءعسف╝ـق¤ذلâذفêعéْµءقت║عسفî║فêحعآعéïعبعّعدع»غ╕ففêعدعآعéكّùغ╜£قëرع«قذ«لةئعسف┐£عءعالرفêçعزفç║µëكةذقج║عîف┐àكخعدعéعéèعق┐╗كذ│كّùغ╜£قëرع«فب┤فêعسع»فاكّùكàعذق┐╗كذ│كàع«غ╕ةµû╣عéْµءكذءعùعزعّعéîع░عزعéèع╛عؤعéôعé
ع╛عاعفêجµ▒║عدع»فç║µëع«µءقج║عîغ╕ففêعزفب┤فêععîفàشµصثعزµàثكةîععبعّعدعزععµشةعسكدثكزشعآعéïعîµصثف╜ôعزق»فؤ▓ععééµ║عاعـعزععذعـعéîع╛عùعاعéف╝ـق¤ذع«لرµ│ـµدعéْقت║غ┐إعآعéïعسع»عفêلçع¤عذع«µàثكةîعéْقكدثعùعكّùغ╜£قëرع«قë╣µدعسف┐£عءعالرفêçعزف»╛ف┐£عîµشبعïعؤع╛عؤعéôعé
فéكâي╝أكثفêجغ╛ïق╡µئ£كر│ق┤░ي╜£ف╣│µê13ي╝êعâي╝ë3677
| غ║ïغ╗╢قـزف╖ | ف╣│µê13ي╝êعâي╝ë3677 |
| كثفêجف╣┤µ£êµùح | ف╣│µê14ف╣┤4µ£ê11µùح |
| كثفêجµëف | µإ▒غ║شلسءقصëكثفêجµë |
| µذرفêرقذ«فêح | كّùغ╜£µذر |
| كذ┤كذالةئفئï | µ░ّغ║ïكذ┤كذا |
µصثف╜ôعزق»فؤ▓عسف▒ئعآعéïعôعذي╝êµصثف╜ôق»فؤ▓كخغ╗╢ي╝ë
ف╝ـق¤ذعîلرµ│ـعذكزعéعéëعéîعéïعسع»عف╝ـق¤ذع«فàف«╣عîµصثف╜ôعزق»فؤ▓فàعدعزعّعéîع░عزعéèع╛عؤعéôعéµصثف╜ôق»فؤ▓كخغ╗╢ع»عف╝ـق¤ذع«قؤ«قأعéµû╣µ│ـعف╝ـق¤ذعآعéïكّùغ╜£قëرع«µدك│زعéلçععـعéëعسكّùغ╜£µذركàعسغ╕عêعéïف╜▒لا┐عزعرعéْق╖فêقأعسكâµà«عùعخفêجµûصعـعéîع╛عآعé
فà╖غ╜ôقأعسع»عف╝ـق¤ذعîف┐àكخعذعـعéîعéïقق¤▒ع«µ£ëقةعéف╝ـق¤ذلçع«لرµصثµدعف╝ـق¤ذµû╣µ│ـع«لرفêçµدعزعرعدعآعéعôعéîعéëع»ق¤╗غ╕قأعسف«أعéعéëعéîعéïعééع«عدع»عزعععé▒عâ╝عé╣ع¤عذعسفêجµûصعـعéîع╛عآعé
µûçقسبف╝ـق¤ذع«µ│ذµقé╣عذكّùغ╜£µذرع«ف╝ـق¤ذكخغ╗╢

غ╗ûغ║║ع«µûçقسبعéْف╝ـق¤ذعآعéïلأؤعسع»عغ╕èكذءع«كخغ╗╢عéْµ║عاعùعخععéïعïعéْقت║كزعآعéïف┐àكخعîعéعéèع╛عآعéقë╣عسععâةعâçعéثعéتلïفû╢قصëعسعèععخµ░ùعéْغ╗ءعّعزعّعéîع░عزعéëعزعكخغ╗╢ع»عغ╕èكذءµصثف╜ôق»فؤ▓ع«كخغ╗╢عدعآعéعâةعâçعéثعéتلïفû╢عسعèععخع»عف╝ـق¤ذعéْكةîعéعزععذعééعكçزقج╛عدµûçقسبعéعé│عâ│عâعâ│عâعéْغ╜£µêعآعéïعôعذعîعدععéïعé▒عâ╝عé╣عîفجأععذكâعêعéëعéîع╛عآعéع╛عاععâرعéجعé┐عâ╝عزعرعسغ╛إلب╝عéْعùعµûçقسبعéعé│عâ│عâعâ│عâعéْغ╜£µêعآعéïعôعذعîعدعع╛عآعé
عاعùعïعسععîفب▒لôعµë╣كرـعقب¤قر╢ععزعرعدع»عغ╗ûغ║║ع«µûçقسبعéْف╝ـق¤ذعآع╣عف┐àكخµدعîكزعéعéëعéîعéïق»فؤ▓ع»ف║âععééع«عذكâعêعéëعéîع╛عآعîععâةعâçعéثعéتلïفû╢عسعèععخع»عµë▒عفàف«╣عسعééعéêعéïعééع«ع«عف┐àعأعùعééف╝ـق¤ذعîف┐àكخعدع»عزعفب┤فêعééفجأععééع«عذكâعêعéëعéîع╛عآعéعإع«عاعéعµصثف╜ôق»فؤ▓ع«كخغ╗╢عéْµ║عاعـعزععذفêجµûصعـعéîعéïق»فؤ▓عééف║âععذكâعêعéëعéîع╛عآعéعâةعâçعéثعéتلïفû╢عسعèععخغ╗ûغ║║ع«µûçقسبعéْفêرق¤ذعآعéïفب┤فêعسع»عكّùغ╜£µذرµ│ـغ╕èكزعéعéëعéîعخععéïعîف╝ـق¤ذعع«كخغ╗╢عéْµ║عاعùعخععéïعïعéْقت║كزعآعéïعïعµذرفêركàع«كذ▒كس╛عéْف╛ùعéïعéêععسعùعخععبعـععé
لûتلثكذءغ║ïي╝أف╝ـق¤ذعîNGعذعـعéîعéïعîكّùغ╜£µذرµ│ـعع«غ║ïغ╛ïعسعجععخي╝êµûçقسبعâ╗ق¤╗فâق╖ذي╝ë
ق¤╗فâفêرق¤ذµآéع«µ│ذµقé╣عذكّùغ╜£µذرع«ف╝ـق¤ذكخغ╗╢
غ╜£فôع«ق¤╗فâقصëعسعجععخع»عفافëçعذعùعخعكّùغ╜£قëرعذعزعéèع╛عآع«عدعكّùغ╜£µذركàع«µë┐كس╛عîف┐àكخعذعزعéèع╛عآعéغ╛ïفجûقأعسعكّùغ╜£µذرµ│ـغ╕èع«عîف╝ـق¤ذععسعéعاعéïفب┤فêعسع»كّùغ╜£µذركàع«µë┐كس╛عîغ╕كخعذعزعéèع╛عآعéق¤╗فâع«فب┤فêعسفـلةîعذعـعéîعéïعôعذعîفجأعع«ع»عف╝ـق¤ذكخغ╗╢ع«غ╕╗ف╛ôلûتغ┐éµدعدعآعéغ╛ïعêع░عغ╗ûغ║║ع«µْ«ف╜▒عùعافآق£اعµععاق╡╡ق¤╗ععéجعâرعé╣عâêعزعرعéْعâةعéجعâ│عدµ▓ك╝ëعùععإعéîعسف»╛عآعéïعé│عâةعâ│عâêعéْعîعéزعâئعé▒عع«عéêععسغ╗ءعّك╢│عآعذععثعاعé▒عâ╝عé╣عدع»ععîق¤╗فâع«µû╣عîغ╕╗عدعé│عâةعâ│عâêع»ف╛ôعدعéعéïععذفêجµûصعـعéîعلرµ│ـعزف╝ـق¤ذعذع»كزعéعéëعéîعزعف»كâ╜µدعîلسءععذكذعêع╛عآعé
عاعبععîف╝ـق¤ذععسعéعاعéïعïعرععïع«فêجµûصفا║µ║ûع»µءقت║عزعééع«عدع»عéعéèع╛عؤعéôعéµءعéëعïعسف╝ـق¤ذعسعéعاعéïعذععêعزعلآعéèعف╝ـق¤ذفàâع«كةذقج║عسفèبعêعكّùغ╜£µذركàع«µë┐كس╛عéْف╛ùعخعèعµû╣عîعéêععدعùعéçععéق¤╗فâعâçعâ╝عé┐ع«فàâعسعزعéïعééع«عîعغ╜£فôكçزغ╜ôعدع»عزعععôعéîعéْµْ«ف╜▒عùعافآق£اعزعرعدعéعéïفب┤فêعسع»عغ╜£فôكçزغ╜ôع«كّùغ╜£كàع«µë┐كس╛عسفèبعêععإع«فآق£اع«كّùغ╜£كàع«µë┐كس╛عééف┐àكخعسعزعéïعôعذعîعéعéèع╛عآع«عدµ│ذµعîف┐àكخعدعآعé
ع╛عاعفآق£اعسعجععخع»عكتسفآغ╜ôعîغ║║قëرعدعéعéîع░كéûفâµذرعéعâùعâرعéجعâعé╖عâ╝µذرعîكزعéعéëعéîعéïف»كâ╜µدعîعéعéèعكè╕كâ╜غ║║قصëع«µ£ëفغ║║عدعéعéîع░عâّعâûعâزعé╖عâعéثµذرعîكزعéعéëعéîعéïف»كâ╜µدعîعéعéèع╛عآعéعإع«عاعéععôعéîعéëع«µذرفêرعذع«لûتغ┐éعدµذرفêركàع«كذ▒كس╛عîف┐àكخعذعزعéïف»كâ╜µدعééعéعéèع╛عآع«عدعكّùغ╜£µذرµ│ـغ╕èعف╝ـق¤ذع«كخغ╗╢عéْµ║عاعùعخععéïفب┤فêعدعééعكéûفâµذرععâùعâرعéجعâعé╖عâ╝µذرفèع│عâّعâûعâزعé╖عâعéثµذرعذع«لûتغ┐éعدفـلةîعîعزععïعéْقت║كزعآعéïعéêععسعùع╛عùعéçععéكéûفâµذرعéعâّعâûعâزعé╖عâعéثµذرعسعجععخع»غ╗حغ╕ïع«كذءغ║ïعسعخكر│عùعكدثكزشعùعخعع╛عآعé
لûتلثكذءغ║ïي╝أكéûفâµذرغ╛╡ف«│عدµف«│ك│بفاكسïµ▒éعذعزعéïفا║µ║ûعéµ╡عéîعéْكدثكزش
لûتلثكذءغ║ïي╝أعâّعâûعâزعé╖عâعéثµذرعذع»ي╝اكéûفâµذرعذع«لـععéµذرفêرغ╛╡ف«│عسعزعéïفب┤لإتعéْكدثكزش
فïـق¤╗فàف╝ـق¤ذع«لرµ│ـµدعذكّùغ╜£µذرفـلةî
ع╛عاعµ£ك┐ّعدع»عغ╛ïعêع░YouTubeفïـق¤╗فàعدغ╗ûع«YouTubeفïـق¤╗عéْف╝ـق¤ذعآعéïعغ╜ـعéëعïع«عâةعââعé╗عâ╝عé╕عéْغ╝إعêعéïفïـق¤╗عéْغ╜£µêعآعéïعاعéعسغ╗ûغ║║ع«غ╜£µêعùعالا│µح╜عéْBGMعزعرع«ف╜تعدعîف╝ـق¤ذععآعéïععذععثعاف╜تعدعفïـق¤╗فàعدكةîعéعéîعéïف╝ـق¤ذكةîقé║ع«لرµ│ـµدعîفـلةîعذعزعéïعé▒عâ╝عé╣عééفتùعêعخعع╛عùعاعéعôع«قé╣عسلûتعآعéïكثفêجغ╛ïع»عغ╗حغ╕ïع«كذءغ║ïعسعخق┤╣غ╗ïعùعخعع╛عآعé
لûتلثكذءغ║ïي╝أفïـق¤╗ع«ف╝ـق¤ذعîكذ▒عـعéîعéïفب┤فêعذع»ي╝اكّùغ╜£µذرµ│ـغ╕èع«كخغ╗╢عذكثفêجغ╛ïعéْكدثكزش
ق┐╗كذ│عذكخق┤ع«ف╝ـق¤ذµآéعسµ│ذµعآع╣ععâإعéجعâ│عâê

ف╝ـق¤ذع»فافëçعذعùعخفاµûçع«ع╛ع╛كةîعع╣ععذعـعéîعخعع╛عآعîعق┐╗كذ│عéكخق┤عذععثعاµ¤╣فجëعéْغ╝┤عف╝ـق¤ذعééعغ╕ف«أع«µإةغ╗╢عéْµ║عاعآعôعذعدلرµ│ـعذفêجµûصعـعéîعéïفب┤فêعîعéعéèع╛عآعé
ق┐╗كذ│عسعéêعéïف╝ـق¤ذع»كّùغ╜£µذرµ│ـعدµءقت║عسكزعéعéëعéîعخعèعéèعق┐╗كذ│كàكçزك║سعîق┐╗كذ│عùعاعééع«عدعéعéïعôعذعéْµءكذءعآعéîع░فـلةîع»ق¤اعءع╛عؤعéôعé
غ╕µû╣عكخق┤ف╝ـق¤ذعدع»عفàâع«كّùغ╜£قëرعسعèعّعéïكةذق╛غ╕èع«قë╣ف╛┤عîف╝╖عµ«ïعéïفب┤فêعسع»عîق┐╗µةêععذفêجµûصعـعéîعكّùغ╜£µذرغ╛╡ف«│عذعزعéïف»كâ╜µدعééعéعéïعاعéµ│ذµعîف┐àكخعدعآعéعاعبعùعلف╗ع«كثفêجغ╛ïعدع»عفàذµûçف╝ـق¤ذع«ف┐àكخµدعîعزععé▒عâ╝عé╣عدع»عكخق┤عسعéêعéïف╝ـق¤ذعéْلرµ│ـعذعـعéîعاغ╛ïعééعéعéèع╛عآعé
عôع«عéêععسعق┐╗كذ│ف╝ـق¤ذع»µ│ـف╛ïعسفا║عحععخµءقت║عسكزعéعéëعéîعخعع╛عآعéكخق┤ف╝ـق¤ذعسعجععخعééعقè╢µ│µشةقششعدع»لرµ│ـعذفêجµûصعـعéîعéïف»كâ╜µدعîعéعéèع╛عآعîعفاµûçع«ك╢ثµùذعéْµعزعéعزععéêعµàلçعزف»╛ف┐£عîف┐àكخعدعآعé
عîقخف╝ـق¤ذعكةذكذءعدعééكّùغ╜£µذرµ│ـع«كخغ╗╢عéْµ║عاعؤع░ف╝ـق¤ذعîف»كâ╜
كّùغ╜£قëرعسعجععخععîقخف╝ـق¤ذععزعرعذكةذكذءعـعéîعخععéïعôعذعîعéعéèع╛عآعéعôع«عéêععزكذءك╝ëعîعéعéïغ╗حغ╕èعف╝ـق¤ذعéْعآعéïعôعذع»لـµ│ـعدعéعéïعذكâعêعéïغ║║عîعع╛عآعéعùعïعùععôع«عîقخف╝ـق¤ذععذع«كذءك╝ëع»عغ║ïف«اغ╕èع«µفّ│عéْµîعجعسلععأعµ│ـقأعزµفّ│عéْµîعجعééع«عدع»عéعéèع╛عؤعéôعéعإع«عاعéعكّùغ╜£µذرµ│ـغ╕èع«ف╝ـق¤ذع«كخغ╗╢عéْµ║عاعؤع░ععîقخف╝ـق¤ذعع«كةذكذءعîعéعثعاعذعùعخعééف╝ـق¤ذعéْعآعéïعôعذع»لرµ│ـعذعزعéèع╛عآعé
كذعµؤعêعéîع░ععîكّùغ╜£µذركàع«فïفêحفà╖غ╜ôقأعزكذ▒ف»ي╝êعâرعéجعé╗عâ│عé╣فحّق┤ي╝ëعéْفùعّعزععخعééعغ╕كêشعâسعâ╝عâسعذعùعخع«قخµصتي╝êقخف╝ـق¤ذي╝ëعîµءكذءعـعéîعخععاعذعùعخعééععإعéîعدعééعزعèكّùغ╜£µذرµ│ـغ╕èع«ف╝ـق¤ذعسكر▓ف╜ôعآعéîع░علرµ│ـعسعإع«كّùغ╜£قëرعéْفêرق¤ذعآعéïعôعذعîعدععéïعéع
عïعéëعôعإععîف╝ـق¤ذعع»عâةعâçعéثعéتلïفû╢عسعذعثعخلçكخعزع«عدعآعé
ع╛عذعéي╝أف╝ـق¤ذعâسعâ╝عâسعéْقكدثعùعفë╡غ╜£ع«ف╣àعéْف║âعْعéêع
غ╗حغ╕èعµûçقسبعéق¤╗فâعéْف╝ـق¤ذعآعéïلأؤع«µصثعùععâسعâ╝عâسعسعجععخكزشµءعéْعùع╛عùعاعé
كّùغ╜£µذرعéْغ╛╡ف«│عùعخعùع╛ععذعµذرفêركàعïعéëغ╜┐ق¤ذف╖«µصتكسïµ▒éعéµف«│ك│بفاكسïµ▒éعéْفùعّعéïعزعرع«عâزعé╣عé»عééكâعêعéëعéîع╛عآعéع╛عاعلïفû╢عâةعâçعéثعéتع«كرـغ╛ةعîغ╕ïعîعéïعزعرع«عâشعâ¤عâحعâعâ╝عé╖عâدعâ│عâزعé╣عé»ع«فـلةîعééعéعéèع╛عآعéعإع«عاعéعك╗╜عµ░ùµîعةعدكّùغ╜£µذرغ╛╡ف«│عéْكةîعéعزععéêععسµ│ذµعéْعآعéïف┐àكخعîعéعéèع╛عآعéكّùغ╜£قëرع«ف╝ـق¤ذعسعجععخع»عµ£شكذءغ║ïعدق┤╣غ╗ïعùعخععéïعéêععسعكّùغ╜£µذرµ│ـغ╕èكخف«أعـعéîعخععéïكخغ╗╢عéْµ║عاعآف┐àكخعîعéعéèع╛عآع«عدعف╝كص╖فثسعسعéêعéïعéتعâëعâعéجعé╣عéْفùعّعéïعذعععôعذعîµ£ؤع╛عùععذععêع╛عآعé
ف╜ôغ║ïفïآµëعسعéêعéïف»╛قصûع«ع¤µةêفà
عâتعâعâزعé╣µ│ـف╛ïغ║ïفïآµëع»عITعقë╣عسعéجعâ│عé┐عâ╝عâعââعâêعذµ│ـف╛ïع«غ╕ةلإتعسك▒èف»îعزق╡îلذôعéْµ£ëعآعéïµ│ـف╛ïغ║ïفïآµëعدعآعéك┐ّف╣┤عكّùغ╜£µذرعéْعéععéïقاحقأك▓ةق¤ثµذرع»µ│ذقؤ«عéْلؤعéعخعèعéèععâزعâ╝عéشعâسعâعéدعââعé»ع«ف┐àكخµدع»ع╛عآع╛عآفتùفèبعùعخعع╛عآعéف╜ôغ║ïفïآµëعدع»قاحقأك▓ةق¤ثعسلûتعآعéïعé╜عâزعâحعâ╝عé╖عâدعâ│µغ╛ؤعéْكةîعثعخعèعéèع╛عآعéغ╕ïكذءكذءغ║ïعسعخكر│ق┤░عéْكذءك╝ëعùعخعèعéèع╛عآعé
عâتعâعâزعé╣µ│ـف╛ïغ║ïفïآµëع«فûµë▒فêلçي╝أفقذ«غ╝µحصع«ITعâ╗قاحك▓ةµ│ـفïآ
عéسعâعé┤عâزعâ╝: ITعâ╗عâآعâ│عâعâثعâ╝ع«غ╝µحصµ│ـفïآ
عé┐عé░: قاحقأك▓ةق¤ثµذركّùغ╜£µذر