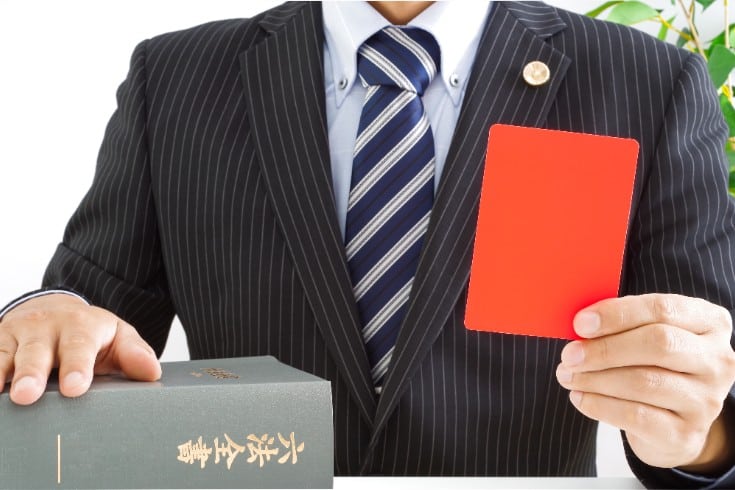дәәжқҗй–Ӣзҷәж”ҜжҸҙеҠ©жҲҗйҮ‘гҒ®дёҚжӯЈеҸ—зөҰгҒ§жҮІеҪ№3е№ҙеҹ·иЎҢзҢ¶дәҲ4е№ҙгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹеІЎеұұең°еҲӨд»Өе’Ң4е№ҙ2жңҲ14ж—ҘеҲӨжұә

ж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“з—ҮгҒ®жӢЎеӨ§жңҹгҒ«ж”ҜзөҰиҰҒ件гҒҢз·©е’ҢгҒ•гӮҢгҒҹйӣҮз”ЁиӘҝж•ҙеҠ©жҲҗйҮ‘пјҲйӣҮиӘҝйҮ‘пјүгӮ„гҖҒиҝ‘е№ҙжіЁзӣ®гӮ’йӣҶгӮҒгӮӢгғӘгӮ№гӮӯгғӘгғігӮ°пјҲдәәжқҗй–Ӣзҷәж”ҜжҸҙеҠ©жҲҗйҮ‘пјүгҒӘгҒ©гҖҒеӣҪгҒ®е…¬зҡ„ж”ҜжҸҙеҲ¶еәҰгҒҜеӨҡгҒҸгҒ®дәӢжҘӯдё»гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰзөҢе–¶з¶ӯжҢҒгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘжүӢж®өгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®иЈҸеҒҙгҒ§гҖҒгҖҢе®ҹиіӘз„Ўж–ҷгҖҚгӮ„гҖҢгӮӯгғғгӮҜгғҗгғғгӮҜгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹз”ҳиЁҖгӮ’еј„гҒҷгӮӢжӮӘиіӘгҒӘгӮігғігӮөгғ«гӮҝгғігғҲгҒ«гӮҲгӮӢдёҚжӯЈеҸ—зөҰгҒ®еӢ§иӘҳгҒҢжЁӘиЎҢгҒ—гҖҒж„ҸеӣігҒӣгҒҡе…¬йҮ‘гӮ’дёҚжӯЈгҒ«еҸ—зөҰгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹдјҒжҘӯгӮ„дәӢжҘӯдё»гҒҢгҖҒеҲ‘дәӢе‘ҠзҷәгҒ®дёҚе®үгӮ’жҠұгҒҲгҒӘгҒҢгӮүж—ҘгҖ…гӮ’йҒҺгҒ”гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢзҸҫзҠ¶гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
иЈңеҠ©йҮ‘гӮ„еҠ©жҲҗйҮ‘гҒ®дёҚжӯЈеҸ—зөҰгҒҜгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢиЎҢж”ҝдёҠгҒ®гғҡгғҠгғ«гғҶгӮЈпјҲиҝ”йӮ„е‘Ҫд»ӨгӮ„еҠ з®—йҮ‘пјүгҒ§гҒҷгӮҖе•ҸйЎҢгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮжӮӘиіӘжҖ§гҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҹе ҙеҗҲгҖҒгҒқгӮҢгҒҜеҲ‘жі•дёҠгҒ®и©җж¬әзҪӘгҒ«гҒӮгҒҹгӮҠгҖҒжӢҳзҰҒеҲ‘гӮ’е•ҸгӮҸгӮҢгӮӢйҮҚеӨ§гҒӘеҲ‘дәӢзҠҜзҪӘгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹдёҚжӯЈеҸ—зөҰгҒ§е®ҹйҡӣгҒ«жңүзҪӘеҲӨжұәгҒҢдёӢгҒ•гӮҢгҒҹдҫӢгҒҜгҖҒиӨҮж•°еӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еІЎеұұең°еҲӨд»Өе’Ң4е№ҙ2жңҲ14ж—ҘеҲӨжұәгҒ®дәӢ件гҒ§гҒҜгҖҒеҠ©жҲҗйҮ‘гҒ®еӯҳеңЁгҒҷгӮүзҹҘгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹдјҒжҘӯгҒ®д»ЈиЎЁеҸ–з· еҪ№гӮүгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒе°Ӯй–Җ家гҒ§гҒӮгӮӢзӨҫдјҡдҝқйҷәеҠҙеӢҷеЈ«гҒҢдёҚжӯЈеҸ—зөҰгӮ’з©ҚжҘөзҡ„гҒ«еӢ§гӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒиЁ“з·ҙжңӘе®ҹж–ҪгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡиҷҡеҒҪгҒ®ж—ҘиӘҢдҪңжҲҗгӮ’жҢҮеҚ—гҒ—гҖҒгҒ•гӮүгҒ«гӮігғӯгғҠзҰҚгҒ®дј‘жҘӯе®ҹж…ӢгҒҢгҒӘгҒ„гҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡзҙ„520дёҮеҶҶгӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒ—гҒҰи«ӢжұӮгҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒдәәжқҗй–Ӣзҷәж”ҜжҸҙеҠ©жҲҗйҮ‘гҒҠгӮҲгҒійӣҮз”ЁиӘҝж•ҙеҠ©жҲҗйҮ‘гҒ®дёҚжӯЈеҸ—зөҰпјҲж—ўйҒӮгғ»жңӘйҒӮеҗҲиЁҲзҙ„1,100дёҮеҶҶпјүгӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®иЎҢзӮәгҒҜи©җж¬әзҪӘгҒ«е•ҸгӮҸгӮҢгҖҒжҮІеҪ№3е№ҙгғ»еҹ·иЎҢзҢ¶дәҲ4е№ҙгҒ®еҲӨжұәгҒҢдёӢгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
жң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®еҲӨжұәгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҢдёҚжӯЈеҸ—зөҰгҒ®дҪ•гӮ’гҖҢжӮӘиіӘгҖҚгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҹгҒ®гҒӢгҖҒгҒқгҒ—гҒҰиў«е‘ҠдәәгӮүгҒҜгҒ„гҒӢгҒ«гҒ—гҒҰе®ҹеҲ‘еҲӨжұәгӮ’еӣһйҒҝгҒ—еҹ·иЎҢзҢ¶дәҲгӮ’еҫ—гҒҹгҒ®гҒӢгӮ’и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®зӣ®ж¬Ў
зӨҫдјҡдҝқйҷәеҠҙеӢҷеЈ«гҒЁдјҒжҘӯеҪ№е“ЎгҒ«гӮҲгӮӢи©җж¬әдәӢ件гҒ®жҰӮиҰҒ

дәӢжЎҲгҒ®еҪ“дәӢиҖ…гҒЁзөҢз·Ҝ
жң¬д»¶гҒҜгҖҒеҠ©жҲҗйҮ‘з”іи«ӢгҒ®е°Ӯй–Җ家гҒ§гҒӮгӮӢзӨҫдјҡдҝқйҷәеҠҙеӢҷеЈ«пјҲд»ҘдёӢгҖҒжң¬д»¶гҒ®зӨҫеҠҙеЈ«пјүгҒЁгҖҒгҒқгҒ®йЎ§е•Ҹе…ҲгҒ§гҒӮгӮӢжңүйҷҗдјҡзӨҫaгҒ®зөҢе–¶йҷЈгҒҢе…ұи¬ҖгҒ—гҒҰгҖҒеҗҲиЁҲзҙ„592дёҮеҶҶгҒ®еҠ©жҲҗйҮ‘гӮ’дёҚжӯЈеҸ—зөҰгҒ—гҖҒгҒ•гӮүгҒ«зҙ„520дёҮеҶҶгҒ®дёҚжӯЈеҸ—зөҰгӮ’и©ҰгҒҝгҒҹпјҲжңӘйҒӮпјүдәӢжЎҲгҒ§гҒҷгҖӮ
иЈҒеҲӨгҒ§еҲ‘дәӢиІ¬д»»гӮ’е•ҸгӮҸгӮҢгҒҹдё»иҰҒгҒӘеҪ“дәӢиҖ…гҒҜд»ҘдёӢгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
- жң¬д»¶гҒ®зӨҫеҠҙеЈ«пјҲиў«е‘ҠдәәпјүпјҡгӮҜгғ©гӮӨгӮўгғігғҲдјҒжҘӯгҒ®еҠҙеғҚгҒ«й–ўгҒҷгӮӢз”іи«ӢжӣёзӯүгҒ®дҪңжҲҗгҒҠгӮҲгҒіжҸҗеҮәгҒ®д»ЈиЎҢжҘӯеӢҷгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹе°Ӯй–Җ家гҖӮгҒ“гҒ®дәәзү©гҒҢиЈҒеҲӨгҒ§гҖҢиў«е‘ҠдәәгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰиө·иЁҙгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹ
- дјҒжҘӯгҒ®д»ЈиЎЁеҸ–з· еҪ№пјҡеҪ“и©ІдјҒжҘӯгҒ®д»ЈиЎЁеҸ–з· еҪ№гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҗҢзӨҫгҒ®жҘӯеӢҷе…ЁиҲ¬гӮ’зөұжӢ¬гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹдәәзү©
- дјҒжҘӯгҒ®еҸ–з· еҪ№гҒЁеҠҙеғҚиҖ…пјҡдәәжқҗй–Ӣзҷәж”ҜжҸҙеҠ©жҲҗйҮ‘гҒ®дёҚжӯЈеҸ—зөҰгҒ«й–ўдёҺгҒ—гҒҹгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®еҸ–з· еҪ№гҒҠгӮҲгҒіеҪ“жҷӮгҒ®еҠҙеғҚиҖ…
иЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒжң¬д»¶гҒ®зӨҫеҠҙеЈ«гҒЁдјҒжҘӯгҒ®д»ЈиЎЁеҸ–з· еҪ№гӮүгҒҢгҖҢеҪ№еүІеҲҶжӢ…гҒ®дёҠгҖҒеҚ”еҠӣгҒ—гҒҰиЎҢгҒЈгҒҹгҖҚе…ұеҗҢжӯЈзҠҜгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиӘҚе®ҡгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гҖҢеҚ”еҠӣгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒҢжҘөгӮҒгҒҰйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҠ©жҲҗйҮ‘з”іи«ӢгҒ®е°Ӯй–Җ家гҒҢиҷҡеҒҪгҒ®з”іи«ӢжӣёйЎһгӮ’дҪңжҲҗгҒ—гҖҒдәӢжҘӯдё»гҒҢгҒқгӮҢгӮ’жүҝиӘҚгғ»жҸҗеҮәгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒе…ұи¬ҖгҒ—гҒҹе…Ёе“ЎгҒҢи©җж¬әзҪӘгҒ®еҲ‘дәӢиІ¬д»»гӮ’иІ гҒҶж №жӢ гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
дёҚжӯЈгҒ®гӮҝгғјгӮІгғғгғҲгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹдәҢгҒӨгҒ®еҠ©жҲҗйҮ‘еҲ¶еәҰ
жң¬д»¶гҒ§дёҚжӯЈеҸ—зөҰгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒжҖ§иіӘгҒ®з•°гҒӘгӮӢдәҢгҒӨгҒ®еҠ©жҲҗйҮ‘еҲ¶еәҰгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
- дәәжқҗй–Ӣзҷәж”ҜжҸҙеҠ©жҲҗйҮ‘пјҲиҒ·жҘӯиЁ“з·ҙгҒ®еҠ©жҲҗпјүпјҡдјҒжҘӯгҒҢеҠҙеғҚиҖ…гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰиҒ·еӢҷгҒ«й–ўйҖЈгҒ—гҒҹе°Ӯй–Җзҡ„гҒӘзҹҘиӯҳгӮ„жҠҖиғҪгҒ®зҝ’еҫ—гӮ’гҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®иҒ·жҘӯиЁ“з·ҙгӮ’иЁҲз”»гҒ«жІҝгҒЈгҒҰе®ҹж–ҪгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒ«гҖҒиЁ“з·ҙзөҢиІ»зӯүгӮ’еҠ©жҲҗгҒҷгӮӢеҲ¶еәҰгҒ§гҒҷгҖӮжң¬д»¶гҒ®зӨҫеҠҙеЈ«гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®еҲ¶еәҰгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰдёҚжӯЈгҒ«зҸҫйҮ‘гӮ’гҒ гҒҫгҒ—еҸ–гӮҚгҒҶгҒЁдјҒеӣігҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
- йӣҮз”ЁиӘҝж•ҙеҠ©жҲҗйҮ‘пјҲдј‘жҘӯжүӢеҪ“гҒ®еҠ©жҲҗпјүпјҡж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“з—ҮгҒ®еҪұйҹҝгҒ«дјҙгҒҶдәӢжҘӯжҙ»еӢ•гҒ®зё®е°ҸгӮ’зҗҶз”ұгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҫ“жҘӯе“ЎгӮ’дј‘жҘӯгҒ•гҒӣгҒҹе ҙеҗҲгҒ«ж”Ҝжү•гҒЈгҒҹдј‘жҘӯжүӢеҪ“гҒ®дёҖйғЁгӮ’еҠ©жҲҗгҒҷгӮӢеҲ¶еәҰгҒ§гҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒжң¬д»¶гҒ®з”іи«Ӣжңҹй–“пјҲд»Өе’Ң2е№ҙ6жңҲгҖңд»Өе’Ң3е№ҙ5жңҲпјүгҒҜгҖҒгӮігғӯгғҠзҰҚгҒ«еҜҫеҝңгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒж”ҜзөҰиҰҒ件гҒҢз·©е’ҢгҒ•гӮҢгҖҒеҜ©жҹ»йҒҺзЁӢгҒҢз°Ўзҙ еҢ–гҒ•гӮҢгҒҹзү№дҫӢжҺӘзҪ®гҒ®жңҹй–“гҒ«гҒӮгҒҹгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®з°Ўзҙ еҢ–гҒҢжӮӘз”ЁгҒ•гӮҢгӮӢзөҗжһңгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®еҲӨжұәгҒҢдәӢжҘӯдё»гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰзү№гҒ«йҮҚиҰҒгҒӘж•ҷиЁ“гӮ’жҢҒгҒӨгҒ®гҒҜгҖҒдёҖгҒӨгҒҜе°Ӯй–Җ家гҒҢдё»е°ҺгҒ—гҒҹиЁҲз”»жҖ§гҒ®й«ҳгҒ„иЁ“з·ҙеҠ©жҲҗйҮ‘гҒ®дёҚжӯЈгҖҒгӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒҜгӮігғӯгғҠзү№дҫӢгҒ®йҡҷгӮ’зӘҒгҒ„гҒҹз·ҠжҖҘжҖ§гҒ®й«ҳгҒ„йӣҮз”Ёз¶ӯжҢҒеҠ©жҲҗйҮ‘гҒ®дёҚжӯЈгҒҢиӨҮеҗҲгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҒ§гҒҷгҖӮиӨҮж•°гҒ®еҠ©жҲҗйҮ‘еҲ¶еәҰгҒ«жүӢгӮ’еҮәгҒ—гҖҒгҒӢгҒӨй•·жңҹй–“гҒ«гӮҸгҒҹгӮҠеӨҡж•°еӣһз”іи«ӢгӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒҷиЎҢзӮәгҒҜгҖҒеҚҳзҷәгҒ®гғҹгӮ№гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒ§гҖҢиЁҲз”»зҡ„гҒӢгҒӨиҒ·жҘӯзҡ„гҒӘзҠҜиЎҢгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰиӘҚе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢгғӘгӮ№гӮҜгҒҢй«ҳгҒ„гҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
еҠ©жҲҗйҮ‘иҷҡеҒҪз”іи«ӢгҒ®е…·дҪ“зҡ„гҒӘжүӢеҸЈгҒЁйҮ‘йЎҚ
иЈҒеҲӨжүҖгҒҢиӘҚе®ҡгҒ—гҒҹгҖҢзҪӘгҒЁгҒӘгӮӢгҒ№гҒҚдәӢе®ҹгҖҚгҒҜгҖҒиҷҡеҒҪгҒ®з”іи«ӢжӣёйЎһгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰеҠҙеғҚеұҖгӮ’ж¬әгҒ„гҒҹиЎҢзӮәгҖҒгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎи©җж¬әиЎҢзӮәгҒ®и©ізҙ°гӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
дәәжқҗй–Ӣзҷәж”ҜжҸҙеҠ©жҲҗйҮ‘гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢиЁ“з·ҙжңӘе®ҹж–ҪгҖҚгҒ®еҒҪиЈ…пјҲж—ўйҒӮпјү
жң¬д»¶гҒ®зӨҫеҠҙеЈ«гҒҜгҖҒдјҒжҘӯгҒ®д»ЈиЎЁеҸ–з· еҪ№гҒҠгӮҲгҒіеҸ–з· еҪ№гӮүгҒЁе…ұи¬ҖгҒ—гҖҒгҒҫгҒҡдәәжқҗй–Ӣзҷәж”ҜжҸҙеҠ©жҲҗйҮ‘гҒ®дёҚжӯЈеҸ—зөҰгҒ«зқҖжүӢгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
еҲӨжұәж–ҮгҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒгҖҢиў«е‘Ҡдәә,еүҚиЁҳAпјҲд»ЈиЎЁеҸ–з· еҪ№пјүеҸҠгҒіеүҚиЁҳBпјҲеҸ–з· еҪ№пјүгҒҢеүҚиЁҳCпјҲеҠҙеғҚиҖ…пјүгҒ«жңүжңҹе®ҹзҝ’еһӢиЁ“з·ҙгӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҹдәӢе®ҹгҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ«гҖҚгҖҒиЁ“з·ҙгӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҹж—ЁгӮ’иЁҳијүгҒ—гҒҹеҶ…е®№иҷҡеҒҪгҒ®ж·»д»ҳжӣёйЎһгӮ’жҸҗеҮәгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®ж·»д»ҳжӣёйЎһгҒ«гҒҜгҖҒжң¬д»¶гҒ®зӨҫеҠҙеЈ«пјҲиў«е‘ҠдәәпјүгҒҢдҪңжҲҗгӮ’жҢҮеҚ—гҒ—гҒҹиҷҡеҒҪгҒ®иЁ“з·ҙж—ҘиӘҢгҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
иЁ“з·ҙгҒ®е®ҹж–ҪгҒҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°ж”ҜзөҰгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„е…¬йҮ‘гӮ’гҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜиЁ“з·ҙгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒиҷҡеҒҪгҒ®жӣёйЎһгӮ’дҪңжҲҗгҒ—гҒҰеҠҙеғҚеұҖгҒ®еҜ©жҹ»гӮ’ж¬әгҒҚгҖҒзөҗжһңгҒЁгҒ—гҒҰ62дёҮ4520еҶҶгӮ’гҒ гҒҫгҒ—еҸ–гӮҠгҖҒеҸ—зөҰгҒ«иҮігӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
йӣҮз”ЁиӘҝж•ҙеҠ©жҲҗйҮ‘гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢжһ¶з©әдј‘жҘӯгҖҚгҒ®з”іи«ӢпјҲж—ўйҒӮйғЁеҲҶпјү
ж¬ЎгҒ«гҖҒжң¬д»¶гҒ®зӨҫеҠҙеЈ«гҒЁдјҒжҘӯгҒ®д»ЈиЎЁеҸ–з· еҪ№гҒҜгҖҒгӮігғӯгғҠзҰҚгҒ§зү№дҫӢжҺӘзҪ®гҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹйӣҮз”ЁиӘҝж•ҙеҠ©жҲҗйҮ‘гӮ’жӮӘз”ЁгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
зӨҫеҠҙеЈ«гҒЁдјҒжҘӯгҒ®д»ЈиЎЁеҸ–з· еҪ№гҒҜгҖҒзңҹе®ҹгҒҜгҖҢжңүйҷҗдјҡзӨҫaгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҗҢзӨҫеҫ“жҘӯе“ЎC, E, FеҸҠгҒіGгӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҰдј‘жҘӯгӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҹдәӢе®ҹгҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеҗҢдәәгӮүгҒ«дј‘жҘӯжүӢеҪ“гӮ’ж”Ҝжү•гҒЈгҒҹдәӢе®ҹгҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ«гҖҚгҖҒдј‘жҘӯгӮ’е®ҹж–ҪгҒ—дј‘жҘӯжүӢеҪ“гӮ’ж”Ҝжү•гҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ«иЈ…гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒеҶ…е®№иҷҡеҒҪгҒ®дј‘жҘӯе®ҹзёҫдёҖиҰ§иЎЁеҸҠгҒіиіғйҮ‘еҸ°еёізӯүгҒ®ж·»д»ҳжӣёйЎһгӮ’йӣҮз”ЁиӘҝж•ҙеҠ©жҲҗйҮ‘ж”ҜзөҰз”іи«ӢжӣёгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒд»Өе’Ң2е№ҙ6жңҲ3ж—Ҙй ғгҒӢгӮүеҗҢе№ҙ11жңҲ10ж—Ҙй ғгҒҫгҒ§гҒ®й–“гҖҒ6еӣһгҒ«гӮҸгҒҹгӮҠеҠҙеғҚеұҖгҒ«жҸҗеҮәгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒеҗҲиЁҲ529дёҮ9931еҶҶгҒ®дәӨд»ҳжұәе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒгҒ гҒҫгҒ—еҸ–гӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
жңӘйҒӮгҒ«зөӮгӮҸгҒЈгҒҹи©җж¬әиЎҢзӮә
ж—ўйҒӮеҲҶгҒ«з¶ҡгҒҚгҖҒзӨҫеҠҙеЈ«гҒЁдјҒжҘӯгҒ®д»ЈиЎЁеҸ–з· еҪ№гҒҜгҖҒд»Өе’Ң2е№ҙ12жңҲ7ж—Ҙй ғгҒӢгӮүд»Өе’Ң3е№ҙ5жңҲ26ж—Ҙй ғгҒҫгҒ§гҒ®й–“гӮӮгҖҒеҗҢж§ҳгҒ®жүӢеҸЈгҒ§гҒ•гӮүгҒ«6еӣһгҒ«гӮҸгҒҹгӮҠз”іи«ӢгӮ’и©ҰгҒҝгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жңӘйҒӮеҲҶгҒ§и«ӢжұӮгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹйҮ‘йЎҚгҒҜгҖҒеҗҲиЁҲгҒ§520дёҮ515еҶҶгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®жңӘйҒӮеҲҶгҒ®з”іи«ӢгҒҜгҖҒеҠҙеғҚеұҖйғЁиҒ·е“ЎгӮүгҒ«гҖҢдёҚжӯЈз”іи«ӢгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иҰӢз ҙгӮүгӮҢгҒҹгҒҹгӮҒгҖҚгҖҒж”Ҝжү•гҒ„гҒҢз•ҷдҝқгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
дәӢжҘӯдё»гҒҢгҒ“гҒ“гҒ§иӘҚиӯҳгҒҷгҒ№гҒҚгҒҜгҖҒдёҚжӯЈгҒҢзҷәиҰҡгҒ—гҖҒеҜ©жҹ»дёӯгҒ«ж”Ҝжү•гҒ„гҒҢз•ҷдҝқгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒеҲ‘зҪ°гҒ®еҜҫиұЎгҒӢгӮүйҖғгӮҢгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ§гҒҷгҖӮи©җж¬әзҪӘгҒҜгҖҒе…¬йҮ‘гӮ’дәӨд»ҳгҒ•гӮҢгҒҹгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢпјҲж—ўйҒӮпјүгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒж¬әзҪ”иЎҢзӮәпјҲиҷҡеҒҪжӣёйЎһгҒ®жҸҗеҮәпјүгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹжҷӮзӮ№гҒ§жңӘйҒӮзҪӘгҒЁгҒ—гҒҰжҲҗз«ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮжң¬д»¶гҒ§гҒҜгҖҒеҸ—зөҰгҒ«иҮігӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹзҙ„520дёҮеҶҶгҒ®и«ӢжұӮгӮӮгҖҒи©җж¬әжңӘйҒӮзҪӘгҒЁгҒ—гҒҰиө·иЁҙгҒ•гӮҢгҖҒжңүзҪӘеҲӨжұәгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж—©жңҹгҒ®иҮӘдё»з”іе‘ҠгҒЁеҸ–гӮҠдёӢгҒ’гҒҢгҖҒеҲ‘дәӢиІ¬д»»гӮ’е•ҸгӮҸгӮҢгӮӢгғӘгӮ№гӮҜгӮ’и»ҪжёӣгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«дёҚеҸҜж¬ гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
| дәәжқҗй–Ӣзҷәж”ҜжҸҙеҠ©жҲҗйҮ‘ | йӣҮз”ЁиӘҝж•ҙеҠ©жҲҗйҮ‘ | |
|---|---|---|
| дёҚжӯЈгҒ®жүӢеҸЈгҒ®жҰӮиҰҒ | иЁ“з·ҙжңӘе®ҹж–ҪгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡиҷҡеҒҪгҒ®иЁ“з·ҙж—ҘиӘҢзӯүгӮ’дҪңжҲҗгҖӮ | дј‘жҘӯгғ»дј‘жҘӯжүӢеҪ“жңӘжү•гҒ„гҒ®жһ¶з©әз”іи«ӢгҖӮиҷҡеҒҪгҒ®иіғйҮ‘еҸ°еёізӯүгӮ’дҪңжҲҗгҖӮ |
| ж—ўйҒӮеҸ—зөҰйЎҚпјҲзҙ„пјү | 62дёҮеҶҶ | 530дёҮеҶҶ |
| жңӘйҒӮи«ӢжұӮйЎҚпјҲзҙ„пјү | – | 520дёҮеҶҶ |
| и«ӢжұӮеӣһж•° | 1еӣһ | ж—ўйҒӮ6еӣһгҖҒжңӘйҒӮ6еӣһ |
еҠ©жҲҗйҮ‘дёҚжӯЈеҸ—зөҰгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢе°Ӯй–Җ家гҒ®дё»е°ҺгҖҚгҒЁгҖҢеҲ¶еәҰи¶Јж—ЁгҒ®жӮӘз”ЁгҖҚ
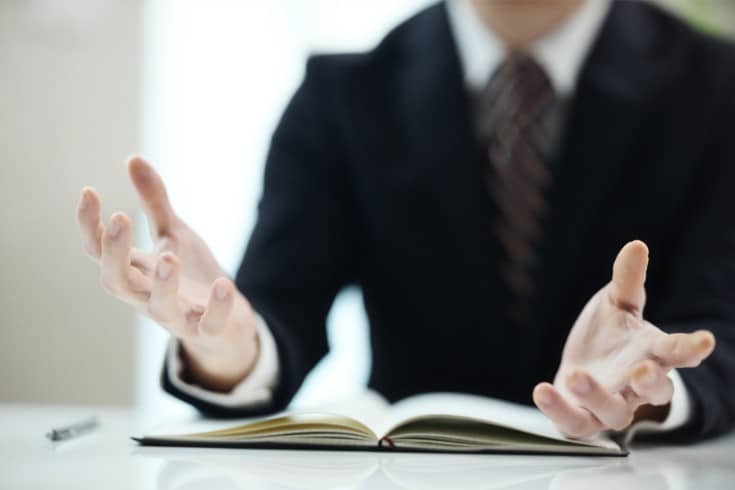
жң¬еҲӨжұәгҒ®гҖҢйҮҸеҲ‘гҒ®зҗҶз”ұгҖҚгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҢдёҚжӯЈеҸ—зөҰгӮ’жҘөгӮҒгҒҰжӮӘиіӘгҒӘиЎҢзӮәгҒЁгҒ—гҒҰи©•дҫЎгҒ—гҖҒйҮҚгҒ„еҲ‘дәӢиІ¬д»»гӮ’иІ гӮҸгҒӣгҒҹеҲӨж–ӯеҹәжә–гҒҜгҖҒдёҚжӯЈгҒ®е®ҹиЎҢжҖ§гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгҒқгҒ®иғҢеҫҢгҒ«гҒӮгӮӢгҖҢеӢ•ж©ҹгҖҚгҒЁгҖҢй–ўдёҺиҖ…гҒ®е°Ӯй–ҖжҖ§гҖҚгҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
иЁҲз”»зҡ„гғ»иҒ·жҘӯзҡ„зҠҜиЎҢгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®и©•дҫЎ
иЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒжң¬д»¶зҠҜиЎҢе…ЁдҪ“гӮ’гҖҢдјҡзӨҫеҒҙй–ўдҝӮиҖ…гҒЁзӨҫеҠҙеЈ«гҒҢеҪ№еүІеҲҶжӢ…гҒ®дёҠгҖҒеҚ”еҠӣгҒ—гҒҰиЎҢгҒЈгҒҹиЁҲз”»зҡ„гҒӢгҒӨиҒ·жҘӯзҡ„гҒӘзҠҜиЎҢгҖҚгҒЁж–ӯгҒҳгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮзү№гҒ«гҖҒйӣҮз”ЁиӘҝж•ҙеҠ©жҲҗйҮ‘гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒж—ўйҒӮеҲҶгҒЁжңӘйҒӮеҲҶеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰеҗҲиЁҲ12еӣһгҒ«гӮӮгӮҸгҒҹгӮҠи«ӢжұӮгӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒқгҒ®еҸҚеҫ©жҖ§гғ»еёёзҝ’жҖ§гҒҢгҖҢж…Ӣж§ҳжӮӘиіӘгҒ§гҒӮгӮӢгҖҚгҒЁеҺігҒ—гҒҸжҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
дёҚжӯЈеҸ—зөҰйЎҚгҒҜж—ўйҒӮеҲҶгҒ§еҗҲиЁҲзҙ„592дёҮеҶҶгҖҒжңӘйҒӮи«ӢжұӮеҲҶгӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҒЁзҙ„1,100дёҮеҶҶгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®йҮ‘йЎҚгҒҜгҖҢгҒҠгӮҲгҒқзңӢйҒҺгҒ§гҒҚгҒҡгҖҒжң¬д»¶зөҗжһңгҒҜйҮҚгҒ„гҖҚгҒЁи©•дҫЎгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
зӨҫдјҡдҝқйҷәеҠҙеӢҷеЈ«гҒ«гӮҲгӮӢз©ҚжҘөзҡ„гҒӘзҠҜиЎҢдё»е°Һ
еҠ©жҲҗйҮ‘з”іи«ӢгҒ®е°Ӯй–Җ家гҒ§гҒӮгӮӢжң¬д»¶гҒ®зӨҫеҠҙеЈ«гҒ®иІ¬д»»гҒҜгҖҒжңҖгӮӮйҮҚгҒҸиҝҪеҸҠгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒеҠ©жҲҗйҮ‘гҒ®зЁ®йЎһгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒдёҚжӯЈгҒ«жүӢгӮ’жҹ“гӮҒгӮӢгҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒҢз•°гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’и©ізҙ°гҒ«иӘҚе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
дәәжқҗй–Ӣзҷәж”ҜжҸҙеҠ©жҲҗйҮ‘гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒжң¬д»¶гҒ®зӨҫеҠҙеЈ«гҒҢгҖҒеҠ©жҲҗйҮ‘гҒ®еӯҳеңЁгӮӮзҹҘгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹдјҒжҘӯгҒ®д»ЈиЎЁеҸ–з· еҪ№гӮүгҒ«дёҚжӯЈеҸ—зөҰгӮ’еӢ§гӮҒгҖҒзҠҜиЎҢгӮ’гҖҢз©ҚжҘөзҡ„гҒ«зҠҜиЎҢгӮ’дё»е°ҺгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖҚгҒЁиӘҚе®ҡгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
е…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒжң¬д»¶гҒ®зӨҫдјҡдҝқйҷәеҠҙеӢҷеЈ«пјҲиў«е‘ҠдәәпјүгҒҢгҖҢиў«е‘ҠдәәгҒҢдҪңгӮӢиЁ“з·ҙиЁҲз”»гҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҒ«иЁ“з·ҙгӮ’гҒ—гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«йҒ©еҪ“гҒ«ж—ҘиӘҢгӮ’жӣёгҒ‘гҒ°гӮҲгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶи¶Јж—ЁгҒ®и©ұгӮ’гҒ—гҒҰдёҚжӯЈеҸ—зөҰгӮ’еӢ§гӮҒгҖҒж—ҘиӘҢгҒ®еҶ…е®№гӮӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«жҢҮеҚ—гҒҷгӮӢгҖҚгҒӘгҒ©гҖҒе°Ӯй–Җзҡ„зҹҘиӯҳгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰзҠҜиЎҢгӮ’е…Ҳе°ҺгҒ—гҒҹгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
зөҢе–¶жӮӘеҢ–гӮ’иғҢжҷҜгҒЁгҒ—гҒҹдјҒжҘӯеҒҙгҒӢгӮүгҒ®дҫқй ј
дёҖж–№гҖҒйӣҮз”ЁиӘҝж•ҙеҠ©жҲҗйҮ‘гҒ®дёҚжӯЈгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒзөҢз·ҜгҒҢз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдјҒжҘӯгҒ®д»ЈиЎЁеҸ–з· еҪ№гӮүгҒҜгҖҒж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“з—ҮгҒ®еҪұйҹҝгҒ§зөҢе–¶гҒҢжӮӘеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ«гҖҒеҗҢжҘӯиҖ…гҒҢеҸ—зөҰгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиҒһгҒҚеҸҠгҒігҖҒеҪ“еҲқгҒҜжӯЈиҰҸгҒ®еҸ—зөҰгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзӣёи«ҮгӮ’гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҖҒгҖҢиҒ·дәәгҒҢдј‘жҘӯжҢҮзӨәгҒ«еҫ“гӮҸгҒҡгҒ«еҮәеӢӨгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҒ“гҒ®гҒҫгҒҫз”іи«ӢгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒӘгҒ„гҒӢгҖҚгҒЁгҖҒдјҒжҘӯгҒ®д»ЈиЎЁеҸ–з· еҪ№еҒҙгҒӢгӮүдҫқй јгҒ•гӮҢгҒҰжң¬д»¶гҒ®зӨҫеҠҙеЈ«гҒҢеҝңгҒҳгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®зӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜзӨҫеҠҙеЈ«еҒҙгҒҜгҖҢеҸ—еӢ•зҡ„гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖҚгҒЁдё»ејөгҒ—гҖҒиЈҒеҲӨжүҖгӮӮгҖҢе ұй…¬ж¬ІгҒ—гҒ•гҒӢгӮүз©ҚжҘөзҡ„гҒ«жҢҮеҚ—гҒ—гҒҹзҠҜиЎҢгҒЁгҒҜиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁдёҖйғЁиӘҚгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®еӢ•ж©ҹгӮ„гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒҢдҪ•гҒ§гҒӮгӮҢгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҢдёӢгҒ—гҒҹзөҗи«–гҒҜеӨүгӮҸгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮжң¬д»¶гҒ®зӨҫеҠҙеЈ«гҒҢгҖҢе°Ӯй–Җзҡ„зҹҘиӯҳгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰгҖҒиҷҡеҒҪгҒ®еҠҙеӢҷй–ўдҝӮжӣёйЎһгӮ„з”іи«ӢжӣёйЎһгӮ’ж•ҙгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдёҚеҸҜж¬ гҒӘеҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«еӨүгӮҸгӮҠгҒҜгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒе°Ӯй–Җ家гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®й–ўдёҺгҒ®йҮҚеӨ§жҖ§гӮ’иӘҚе®ҡгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®еҸ—еӢ•жҖ§гҒ®дё»ејөгӮ’йҖҖгҒ‘гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®зӮ№гҒҜгҖҒзҸҫеңЁдёҚе®үгӮ’жҠұгҒҲгӮӢдәӢжҘӯдё»гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰйқһеёёгҒ«йҮҚиҰҒгҒӘж•ҷиЁ“гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгӮӮгҒ—гҖҒжӮӘиіӘгҒӘгӮігғігӮөгғ«гӮҝгғігғҲгӮ„зӨҫдјҡдҝқйҷәеҠҙеӢҷеЈ«гҒ«йЁҷгҒ•гӮҢгҒҰдёҚжӯЈгҒ«еҠ жӢ…гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒ§гӮӮгҖҒгҖҢе°Ӯй–Җ家гҒ«иЁҖгӮҸгӮҢгӮӢгҒҢгҒҫгҒҫгҒ«гӮ„гҒЈгҒҹгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶдё»ејөгҒҜгҖҒиҮӘзӨҫгҒ®еҠҙеӢҷжғ…е ұпјҲеӢӨеӢҷз°ҝгӮ„иіғйҮ‘еҸ°еёіпјүгӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒиҷҡеҒҪгҒ®еҶ…е®№гӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҹгӮҠгҒ—гҒҹдәӢжҘӯдё»еҒҙгҒ®й–ўдёҺгӮ’иҰҶгҒҷгҒ“гҒЁгҒ«гҒҜгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮиЈҒеҲӨжүҖгҒӢгӮүиҰӢгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгӮҢгҒҜгҖҢеҪ№еүІеҲҶжӢ…гҖҚгӮ’гҒ—гҒҹе…ұзҠҜиҖ…гҖҒгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎе…ұеҗҢжӯЈзҠҜгҒЁгҒ—гҒҰжүұгӮҸгӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гӮігғӯгғҠзү№дҫӢгӮ’жӮӘз”ЁгҒ—гҒҹжӮӘиіӘжҖ§
йӣҮз”ЁиӘҝж•ҙеҠ©жҲҗйҮ‘гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ®и©•дҫЎгӮӮеҺіж јгҒ§гҒҷгҖӮж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“з—ҮгҒ®еҪұйҹҝгҒ«гӮҲгӮӢзү№дҫӢжҺӘзҪ®гҒҜгҖҒеҫ“жҘӯе“ЎгҒ®йӣҮз”ЁгҒ®з¶ӯжҢҒгӮ’еӣігӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒжң¬д»¶гҒ§гҒҜгҖҢеҫ“жҘӯе“ЎгӮ’дј‘жҘӯгҒ•гҒӣгҒҹдәӢе®ҹгӮӮгҖҒдј‘жҘӯжүӢеҪ“гӮ’ж”Ҝжү•гҒЈгҒҹдәӢе®ҹгӮӮгҒӘгҒ„гҒ®гҒ«гҖҚгҖҒиҷҡеҒҪгҒ®з”іи«ӢгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
иЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®иЎҢзӮәгӮ’гҖҢеҲ¶еәҰи¶Јж—ЁгҒ«еҸҚгҒ—гҖҒеҚҳгҒ«дјҡзӨҫгҒ®йҒӢи»ўиіҮйҮ‘гҒ®и¶ігҒ—гҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’дјҒеӣігҒ—гҒҰгҖҒеҲ¶еәҰгӮ’жӮӘз”ЁгҒ—гҒҹзҠҜиЎҢгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжӮӘиіӘгҒ§гҒӮгӮӢгҖҚгҒЁж–ӯгҒҳгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮжң¬жқҘгҖҒе…¬йҮ‘гҒ§иі„гӮҸгӮҢгӮӢгҒ№гҒҚеҠ©жҲҗйҮ‘гӮ’з§ҒзӣҠгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«жӮӘз”ЁгҒ—гҖҒе…¬йҮ‘гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢдҝЎй јгӮ’жҗҚгҒӘгҒЈгҒҹиЎҢзӮәгҒҜгҖҒгҖҢеҗҢзЁ®зҠҜиЎҢгӮ’йҳІжӯўгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶдёҖиҲ¬дәҲйҳІгҒ®иҰӢең°гӮӮз„ЎиҰ–гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҺізҪ°еҢ–гҒ®еҝ…иҰҒжҖ§гҒҢзӨәгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
зөҗи«–гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒзӨҫдјҡдҝқйҷәеҠҙеӢҷеЈ«гҒЁгҒ„гҒҶгҖҢзӨҫдјҡзҡ„гҒ«иІ¬д»»гҒӮгӮӢз«Ӣе ҙгҒ«гҒӮгӮҠгҒӘгҒҢгӮүгҖҒеҠ©жҲҗйҮ‘гҒ®еҲ¶еәҰгӮ’и»ҪгӮ“гҒҳгҒҰгҖҚзҠҜиЎҢгҒ«еҸҠгҒігҖҒгҖҢиҒ·жҘӯзҡ„еҖ«зҗҶиҰігҒ«д№ҸгҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгҖҚгҒЁи©•дҫЎгҒ•гӮҢгҒҹжң¬д»¶гҒ®зӨҫеҠҙеЈ«гҒҜгҖҒгҖҢзӨҫеҠҙеЈ«гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢдҝЎй јгӮ’гӮӮжҗҚгҒӘгҒЈгҒҹжң¬д»¶зҠҜжғ…гҒҜжӮӘгҒҸгҖҒжң¬д»¶гҒ®зӨҫдјҡдҝқйҷәеҠҙеӢҷеЈ«гҒ®еҲ‘дәӢиІ¬д»»гҒҜйҮҚгҒ„гҖҚгҒЁзөҗи«–д»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
жҮІеҪ№3е№ҙгғ»еҹ·иЎҢзҢ¶дәҲ4е№ҙгҒ®еҲӨжұәгҒЁжі•зҡ„ж №жӢ
еҹ·иЎҢзҢ¶дәҲпјҲ4е№ҙй–“пјүгҒҢд»ҳгҒ•гӮҢгҒҹзҗҶз”ұ
иЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒдёҠиЁҳгҒ®жӮӘиіӘжҖ§гӮ’йҮҚгҒҸгҒҝгҒҰгҖҒи©җж¬әзҪӘпјҲеҲ‘法第246жқЎз¬¬1й …пјүгҒҠгӮҲгҒіи©җж¬әжңӘйҒӮзҪӘпјҲеҲ‘法第250жқЎпјүгӮ’йҒ©з”ЁгҒ—гҖҒдё»ж–ҮгҒЁгҒ—гҒҰгҖҢиў«е‘ҠдәәгӮ’жҮІеҪ№3е№ҙгҒ«еҮҰгҒҷгӮӢгҖҚгҒЁгҒ—гҒҹеҫҢгҖҒгҖҢгҒ“гҒ®иЈҒеҲӨгҒҢзўәе®ҡгҒ—гҒҹж—ҘгҒӢгӮү4е№ҙй–“гҒқгҒ®еҲ‘гҒ®еҹ·иЎҢгӮ’зҢ¶дәҲгҒҷгӮӢгҖҚгҒЁд»ҳгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®еҹ·иЎҢзҢ¶дәҲгӮ’зҚІеҫ—гҒҷгӮӢдёҠгҒ§гҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҢжңҖгӮӮйҮҚиҰ–гҒ—гҖҒйҮҸеҲ‘еҲӨж–ӯгҒ®жұәе®ҡзҡ„гҒӘеҲҶеІҗзӮ№гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒиў«е®іеӣһеҫ©гҒ®зҠ¶жіҒгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
иЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒйҮҸеҲ‘гҒ®зҗҶз”ұгҒ®жңҖеҫҢгҒ«гҖҒд»ҘдёӢгҒ®дәӢе®ҹгҒ«и§ҰгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жң¬д»¶гҒ®иІЎз”Јзҡ„жҗҚе®ігҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒAпјҲд»ЈиЎЁеҸ–з· еҪ№пјүгҒҢbеҠҙеғҚеұҖгҒ«жң¬д»¶иў«е®ійҮ‘еҸҠгҒіе»¶ж»һйҮ‘гҒ®е…ЁйЎҚгӮ’иҝ”йӮ„гҒ—гҖҒиў«е‘ҠдәәпјҲзӨҫеҠҙеЈ«пјүгӮӮе ұй…¬еүІеҗҲгҒ«зӣёеҪ“гҒҷгӮӢ2еүІгӮ’иІ жӢ…гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҚ”еҠӣгҒ—гҒҰиў«е®ійЎҚе…ЁйғЁгҒ®еӣһеҫ©гҒҢеӣігӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢ
еІЎеұұең°еҲӨд»Өе’Ң4е№ҙ2жңҲ14ж—ҘеҲӨжұә
гҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиў«е®іејҒе„ҹзҠ¶жіҒгҒ«з…§гӮүгҒҷгҒЁгҖҒжң¬д»¶гҒҜгҖҒеҲ‘гҒ®еҹ·иЎҢзҢ¶дәҲгӮӮгҒӮгӮҠеҫ—гӮӢдәӢжЎҲгҒЁгҒ„гҒҶгҒ№гҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖҚгҒЁи©•дҫЎгҒ—гҖҒиў«е®ігҒ®е…ЁйЎҚиҝ”йӮ„пјҲ延ж»һйҮ‘гӮ’еҗ«гӮҖпјүгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®йҮҚзҪӘгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰе®ҹеҲ‘гӮ’еӣһйҒҝгҒҷгӮӢжңҖеӨ§гҒ®иҰҒеӣ гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®д»–гҒ®й…ҢгӮҖгҒ№гҒҚдёҖиҲ¬жғ…зҠ¶
иў«е®іеӣһеҫ©гҒ«еҠ гҒҲгҒҰгҖҒд»ҘдёӢгҒ®жғ…зҠ¶гӮӮгҖҒеҹ·иЎҢзҢ¶дәҲгӮ’д»ҳгҒҷгҒҹгӮҒгҒ®гҖҢй…ҢгӮҖгҒ№гҒҚдәӢжғ…гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰиҖғж…®гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
- жң¬д»¶гҒ®зӨҫеҠҙеЈ«гҒҢдәӢе®ҹгӮ’иӘҚгӮҒгҒҰеҸҚзңҒгҒ®ж…ӢеәҰгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁ
- зӨҫдјҡзҡ„гҒӘиІ¬д»»гӮ’еҸ–гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒзӨҫдјҡдҝқйҷәеҠҙеӢҷеЈ«зҷ»йҢІгӮ’жҠ№ж¶ҲгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁпјҲзӨҫеҠҙеЈ«гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰдёҚжӯЈгҒҢе…¬гҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®зҷ»йҢІжҠ№ж¶ҲгҒЁгҒ„гҒҶжңҖгӮӮйҮҚгҒ„иЎҢж”ҝеҮҰеҲҶгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҫгҒҷпјү
- жң¬д»¶гҒ®зӨҫеҠҙеЈ«гҒ®еҰ»гҒҢеҮәе»·гҒ—гҖҒд»ҠеҫҢгҒ®зӣЈзқЈгҒЁжӣҙз”ҹгҒёгҒ®еҚ”еҠӣгӮ’зҙ„жқҹгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁ
- еҸӢдәәгҒ§гҒӮгӮӢзЁҺзҗҶеЈ«гӮ„йЎ§е•Ҹе…ҲгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹдјҡзӨҫзөҢе–¶иҖ…гҒ®еҸӢдәәгҒҢеҮәе»·гҒ—гҖҒжӣҙз”ҹгӮ’ж”ҜжҸҙгҒҷгӮӢж—ЁгӮ’зҙ„жқҹгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁ
- жң¬д»¶гҒ®зӨҫеҠҙеЈ«гҒ«жҮІеҪ№еүҚ科гҒҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁ
иЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨж–ӯж§ӢйҖ гӮ’иҰӢгӮӢгҒЁгҖҒгҖҢжӮӘиіӘжҖ§гҖҚпјҲиЁҲз”»жҖ§гҖҒе°Ӯй–Җ家гҒ®й–ўдёҺгҖҒеҲ¶еәҰжӮӘз”ЁпјүгҒӢгӮүе°ҺгҒӢгӮҢгӮӢйҮҚгҒ„еҲ‘дәӢиІ¬д»»пјҲжҮІеҪ№3е№ҙзӣёеҪ“пјүгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгҖҢиў«е®ігҒ®еӣһеҫ©зҠ¶жіҒгҖҚгҒҢгҖҒгҒқгҒ®еҲ‘гҒ®еҹ·иЎҢгӮ’зҢ¶дәҲгҒҷгӮӢжұәе®ҡзҡ„гҒӘиҰҒзҙ гҒЁгҒ—гҒҰеғҚгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдәӢжҘӯдё»гҒҢд»ҠгҖҒжңҖгӮӮжіЁеҠӣгҒҷгҒ№гҒҚгҒҜгҖҒеҸҚзңҒгҒ®ж…ӢеәҰгӮ’зӨәгҒҷгҒ“гҒЁд»ҘдёҠгҒ«гҖҒгҒ„гҒӢгҒ«иҝ…йҖҹгҒӢгҒӨе®Ңе…ЁгҒ«иў«е®ійҮ‘йЎҚпјҲ延ж»һйҮ‘еҗ«гӮҖпјүгҒ®е…ЁйЎҚгӮ’еҠҙеғҚеұҖгҒ«иҝ”йӮ„гҒҷгӮӢгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶиў«е®іеӣһеҫ©жҲҰз•ҘгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
| еҲ‘дәӢиІ¬д»»гҒҢйҮҚгҒҸгҒӘгӮӢзҗҶз”ұ | й…ҢгӮҖгҒ№гҒҚдәӢжғ… | |
|---|---|---|
| иЎҢзӮәж…Ӣж§ҳ | иЁҲз”»зҡ„гҒӢгҒӨиҒ·жҘӯзҡ„зҠҜиЎҢпјҲеҪ№еүІеҲҶжӢ…пјү | – |
| й–ўдёҺиҖ… | е°Ӯй–Җ家пјҲзӨҫеҠҙеЈ«пјүгҒ«гӮҲгӮӢз©ҚжҘөзҡ„гҒӘдё»е°Һ | зӨҫеҠҙеЈ«зҷ»йҢІгҒ®жҠ№ж¶Ҳ |
| еӢ•ж©ҹ | гӮігғӯгғҠзү№дҫӢгӮ’жӮӘз”ЁгҒ—гҖҒдјҡзӨҫгҒ®йҒӢи»ўиіҮйҮ‘гҒ«е……еҪ“ | – |
| зөҗжһң | ж—ўйҒӮйЎҚзҙ„592дёҮеҶҶгҖҒжңӘйҒӮи«ӢжұӮйЎҚзҙ„520дёҮеҶҶгҒЁеӨҡйЎҚ | иў«е®ійҮ‘еҸҠгҒіе»¶ж»һйҮ‘гҒ®е…ЁйЎҚгӮ’иҝ”йӮ„гҒ—гҒҹ |
| дёҖиҲ¬жғ…зҠ¶ | еҲ¶еәҰгӮ’и»ҪгӮ“гҒҳгҒҹиҒ·жҘӯзҡ„еҖ«зҗҶиҰігҒ®ж¬ еҰӮ | еҸҚзңҒгҒ®ж…ӢеәҰгҖҒ家ж—Ҹгғ»еҸӢдәәгҒ®жӣҙз”ҹж”ҜжҸҙгҒ®зҙ„жқҹгҖҒеүҚ科гҒӘгҒ— |
еҠ©жҲҗйҮ‘дёҚжӯЈеҸ—зөҰгҒ®иҮӘе·ұз”іе‘ҠгҒЁејҒиӯ·еЈ«гҒ®еҪ№еүІ

иў«е®іеӣһеҫ©гҒ®з·ҠжҖҘжҖ§
гҒ“гҒ®еІЎеұұең°иЈҒгҒ®еҲӨжұәгҒҜгҖҒеҠ©жҲҗйҮ‘гҒ®дёҚжӯЈеҸ—зөҰгҒҢеҲ‘дәӢдәӢ件гҒЁгҒ—гҒҰз«Ӣ件гҒ•гӮҢгҖҒжҮІеҪ№еҲ‘гҒЁгҒ„гҒҶйҮҚгҒ„еҲӨжұәгҒҢдёӢгҒ•гӮҢгӮӢзҸҫе®ҹгӮ’зӨәгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒдёҚжӯЈгҒ«й–ўдёҺгҒ—гҒҹиҖ…гҒҢеҚ”еҠӣгҒ—гҖҒиҮӘдё»зҡ„гҒӘиў«е®іеӣһеҫ©гӮ’е®ҢдәҶгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒе®ҹеҲ‘гӮ’еӣһйҒҝгҒ—гҖҒеҹ·иЎҢзҢ¶дәҲгӮ’зҚІеҫ—гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«йҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
дёҚе®үгӮ’жҠұгҒҲгӮӢдәӢжҘӯдё»гҒҢд»ҠгҖҒжңҖгӮӮиӯҰжҲ’гҒҷгҒ№гҒҚгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒдёҚжӯЈгӮ’жҢҮеҚ—гҒ—гҒҹе°Ӯй–Җ家пјҲгӮігғігӮөгғ«гӮҝгғігғҲгӮ„зӨҫеҠҙеЈ«пјүгҒҢгҖҒиҮӘиә«гҒ®е°Ӯй–ҖиіҮж јгҒ®еҸ–ж¶ҲгҒ—еҮҰеҲҶпјҲзӨҫеҠҙеЈ«зҷ»йҢІгҒ®жҠ№ж¶ҲгҒӘгҒ©пјүгӮ’жҒҗгӮҢгҒҰгҖҒиІҙзӨҫгҒ«еҜҫгҒ—гҖҢй»ҷгҒЈгҒҰгҒҠгҒ‘гҒ°еӨ§дёҲеӨ«гҖҚгҖҢиҮӘе·ұз”іе‘ҠгҒҜгҒҷгӮӢгҒ№гҒҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁиӘ¬еҫ—гҒ—гҒҰгҒҸгӮӢгӮұгғјгӮ№гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒиІҙзӨҫгӮ’е®ҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгӮігғігӮөгғ«гӮҝгғігғҲгӮ„зӨҫеҠҙеЈ«иҮӘиә«гҒ®дҝқиә«гҒҢзӣ®зҡ„гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиІҙзӨҫгҒ®жі•зҡ„гғӘгӮ№гӮҜгӮ’жҘөйҷҗгҒҫгҒ§й«ҳгӮҒгӮӢеҚұйҷәгҒӘгӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№гҒ гҒЁиЁҖгӮҸгҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
еҠҙеғҚеұҖгӮ„иӯҰеҜҹгҒ«гӮҲгӮӢиӘҝжҹ»гҒҢжң¬ж јзҡ„гҒ«й–Ӣе§ӢгҒ•гӮҢгҖҒеҲ‘дәӢе‘ҠзҷәгҒ«иҮігҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҖҒдәӢж…ӢгҒҜжҘөгӮҒгҒҰж·ұеҲ»еҢ–гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮжңҖжӮӘгҒ®дәӢж…ӢпјҲд»ЈиЎЁиҖ…еҖӢдәәгҒ®е®ҹеҲ‘еҲӨжұәгҖҒдјҒжҘӯгҒ®еӯҳз¶ҡеҚұж©ҹпјүгӮ’йҒҝгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒжҷӮй–“гҒҢжңҖеӨ§гҒ®ж•өгҒ§гҒҷгҖӮ
еҲ‘дәӢе‘ҠзҷәгӮ’еӣһйҒҝгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гҖҢиҮӘдё»з”іе‘ҠгҖҚ
еӨҡгҒҸгҒ®дәӢжҘӯдё»гҒҜгҖҒгҖҢе®ҹиіӘз„Ўж–ҷгҖҚгҖҢгӮӯгғғгӮҜгғҗгғғгӮҜгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжӮӘиіӘгҒӘж”ҜжҸҙдәӢжҘӯиҖ…гҒ®еӢ§иӘҳгҒ«д№—гӮҠгҖҒиӨҮйӣ‘гҒӘеҲ¶еәҰгҒ®зҗҶи§ЈдёҚи¶ігҒӢгӮүж„ҸеӣігҒӣгҒҡзҠҜзҪӘиЎҢзӮәгҒ«еҠ жӢ…гҒ•гҒӣгӮүгӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖҢиў«е®іиҖ…гҖҚгҒ®еҒҙйқўгӮӮжҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒиҷҡеҒҪз”іи«ӢгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶдәӢе®ҹгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®еҲӨжұәгҒ®йҖҡгӮҠи©җж¬әзҪӘгҒЁгҒ—гҒҰж–ӯзҪӘгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®еҚұж©ҹгӮ’и„ұгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«жңҖгӮӮеҠ№жһңзҡ„гҒӘжҲҰз•ҘгҒҢгҖҒзӨҫеҠҙеЈ«гҒ®дҝқиә«гҒ«гӮҲгӮӢй»ҷз§ҳгҒ®еӢ§гӮҒгӮ’ж–ӯгҒЎеҲҮгӮҠгҖҒгҖҢиҮӘдё»з”іе‘ҠгҖҚгӮ’йҖҹгӮ„гҒӢгҒ«е®ҹиЎҢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮиҮӘдё»з”іе‘ҠгҒ«гҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғЎгғӘгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
- еҲ‘дәӢе‘ҠзҷәгҒ®еӣһйҒҝгҒҫгҒҹгҒҜи»ҪжёӣпјҡиӘҝжҹ»еүҚгҒ«иҮӘгӮүдёҚжӯЈгҒ®дәӢе®ҹгӮ’иӘҚгӮҒгҖҒиў«е®ігҒ®е…ЁйЎҚгӮ’иҝ”йӮ„гҒҷгӮӢж„ҸжҖқгҒЁиЎҢеӢ•гӮ’зӨәгҒҷгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҪ“еұҖгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒдёҚжӯЈгӮ’йҡ и”ҪгҒҷгӮӢж„ҸеӣігҒҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮ’иЁјжҳҺгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеҲ‘дәӢе‘ҠзҷәгӮ’еӣһйҒҝгҒ§гҒҚгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҖҒгҒҫгҒҹгҒҜе‘ҠзҷәгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮжғ…зҠ¶йқўгҒ§жңүеҲ©гҒ«еғҚгҒҸеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒҫгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
- 延ж»һйҮ‘гӮ„йҒ•зҙ„йҮ‘гҒ®и»ҪжёӣдәӨжёүпјҡејҒиӯ·еЈ«гҒҢд»Ід»ӢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒиҝ”йӮ„иЁҲз”»гӮ„延ж»һйҮ‘гғ»йҒ•зҙ„йҮ‘гҒ®еҸ–гӮҠжүұгҒ„гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒеҪ“еұҖгҒЁе»әиЁӯзҡ„гҒӘдәӨжёүгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒйҮ‘йҠӯзҡ„гҒӘиІ жӢ…гӮ’иЁҲз”»зҡ„гҒ«еҮҰзҗҶгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
- дјҒжҘӯгҒ®зӨҫдјҡзҡ„дҝЎй јз¶ӯжҢҒпјҡиӘ е®ҹгҒӢгҒӨиҝ…йҖҹгҒӘиҮӘдё»з”іе‘ҠгҒЁиў«е®іеӣһеҫ©гҒ®е§ҝеӢўгҒҜгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ®иЎҢж”ҝеҮҰеҲҶпјҲжҢҮеҗҚеҒңжӯўгӮ„е…¬иЎЁгҒӘгҒ©пјүгҒ®еҲӨж–ӯгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰжңүеҲ©гҒ«иҖғж…®гҒ•гӮҢгҖҒдјҒжҘӯгҒ®зӨҫдјҡзҡ„дҝЎз”ЁгҒёгҒ®гғҖгғЎгғјгӮёгӮ’жңҖе°ҸйҷҗгҒ«жҠ‘гҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«з№ӢгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒпјҡеҠ©жҲҗйҮ‘дёҚжӯЈеҸ—зөҰгҒҜиҝ…йҖҹгҒӘиҮӘдё»з”іе‘ҠгҒЁиў«е®іеӣһеҫ©гҒҢйҮҚиҰҒ
еІЎеұұең°иЈҒгҒ®еҲӨжұәгҒҜгҖҒеҠ©жҲҗйҮ‘дёҚжӯЈеҸ—зөҰгҒҢгҖҒе°Ӯй–Җ家гҒ®й–ўдёҺгӮ„еӨҡж•°еӣһгҒ®з”іи«ӢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгҖҢиЁҲз”»зҡ„гҒӢгҒӨиҒ·жҘӯзҡ„гҒӘи©җж¬әзҪӘгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰеҺігҒ—гҒҸж–ӯзҪӘгҒ•гӮҢгӮӢзҸҫе®ҹгӮ’зӘҒгҒҚгҒӨгҒ‘гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮж—ўйҒӮгғ»жңӘйҒӮеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰзҙ„1,100дёҮеҶҶгҒ«еҸҠгҒ¶дёҚжӯЈи«ӢжұӮгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒжҮІеҪ№3е№ҙгҒЁгҒ„гҒҶйҮҚгҒ„еҲӨжұәгҒҢдёӢгҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒ®дәӢжЎҲгҒҜгҖҒдёҚе®үгӮ’жҠұгҒҲгӮӢдәӢжҘӯдё»гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰжұәгҒ—гҒҰд»–дәәдәӢгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®еҲӨжұәгҒҜеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒиў«е®ійҮ‘гҒЁе»¶ж»һйҮ‘гҒ®е…ЁйЎҚиҝ”йӮ„гҒҢгҖҒе®ҹеҲ‘гӮ’еӣһйҒҝгҒ—еҹ·иЎҢзҢ¶дәҲгӮ’зҚІеҫ—гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«йҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮзӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдёҚжӯЈеҸ—зөҰгҒҜгҖҢзҹҘгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖҚгҒ§гҒҜжёҲгҒҫгҒ•гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒеҚұж©ҹгӮ’еӣһйҒҝгҒ—гҖҒдјҡзӨҫгҒЁд»ЈиЎЁиҖ…еҖӢдәәгҒ®жңӘжқҘгӮ’е®ҲгӮӢйҒ“гҒҜж®ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
е®ҹеҲ‘еҲӨжұәгӮ„дјҒжҘӯгҒ®еӯҳз¶ҡеҚұж©ҹгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжңҖжӮӘгҒ®дәӢж…ӢгӮ’йҒҝгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒе°Ӯй–Җ家гҒ®дҝқиә«гҒ«гӮҲгӮӢгҖҢй»ҷз§ҳгҖҚгҒ®еӢ§гӮҒгӮ’ж–ӯгҒЎеҲҮгӮҠгҖҒдёҖеҲ»гӮӮж—©гҒҸејҒиӯ·еЈ«гҒ«гҒ”зӣёи«ҮгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҖҒиҮӘдё»з”іе‘ҠгҒҠгӮҲгҒіиў«е®іеӣһеҫ©гҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҹжҲҰз•Ҙзҡ„еҜҫеҝңгӮ’й–Ӣе§ӢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
еҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒҜгҖҒеҠ©жҲҗйҮ‘гҒ®дёҚжӯЈеҸ—зөҰе•ҸйЎҢгҒ«й–ўгҒҷгӮӢе®ҹзёҫгҒЁе°Ӯй–ҖзҹҘиӯҳгӮ’жҢҒгҒЎгҖҒдәӢжҘӯдё»гҒҢзӣҙйқўгҒҷгӮӢжі•зҡ„гғ»зөҢе–¶зҡ„гғӘгӮ№гӮҜгӮ’жңҖе°ҸйҷҗгҒ«жҠ‘гҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®жңҖе–„гҒ®жҲҰз•ҘгӮ’з«ӢжЎҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
еҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ«гӮҲгӮӢеҜҫзӯ–гҒ®гҒ”жЎҲеҶ…
гғўгғҺгғӘгӮ№жі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒҜгҖҒITгҖҒзү№гҒ«гӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲгҒЁжі•еҫӢгҒ®дёЎйқўгҒ«й«ҳгҒ„е°Ӯй–ҖжҖ§гӮ’жңүгҒҷгӮӢжі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒ§гҒҷгҖӮеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§гҒҜгҖҒжқұиЁјгғ—гғ©гӮӨгғ дёҠе ҙдјҒжҘӯгҒӢгӮүгғҷгғігғҒгғЈгғјдјҒжҘӯгҒҫгҒ§гҖҒгғ“гӮёгғҚгӮ№гғўгғҮгғ«гӮ„дәӢжҘӯеҶ…е®№гӮ’ж·ұгҒҸзҗҶи§ЈгҒ—гҒҹдёҠгҒ§жҪңеңЁзҡ„гҒӘжі•зҡ„гғӘгӮ№гӮҜгӮ’жҙ—гҒ„еҮәгҒ—гҖҒгғӘгғјгӮ¬гғ«гӮөгғқгғјгғҲгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдёӢиЁҳиЁҳдәӢгҒ«гҒҰи©ізҙ°гӮ’иЁҳијүгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ«гғҶгӮҙгғӘгғј: ITгғ»гғҷгғігғҒгғЈгғјгҒ®дјҒжҘӯжі•еӢҷ