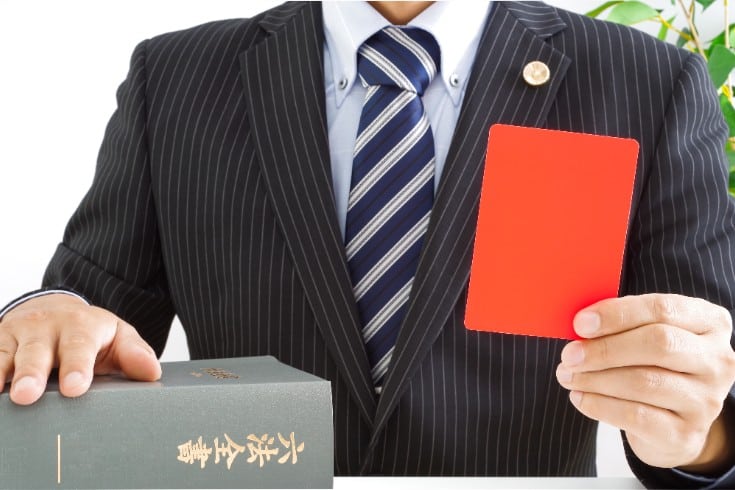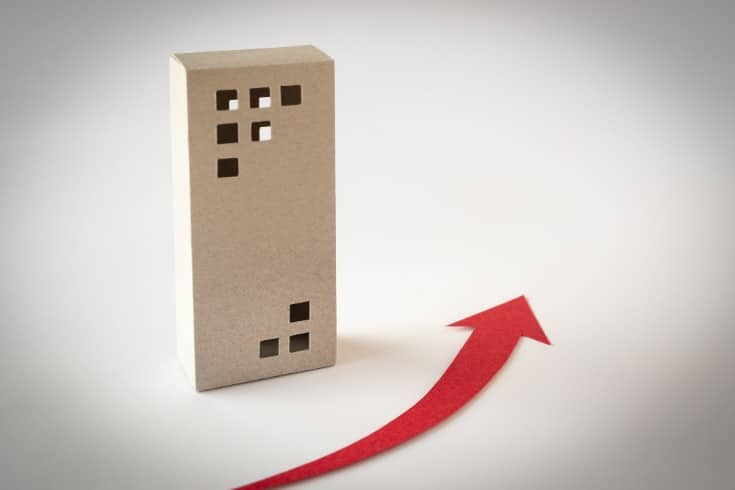補助金不正受給は「後で適切に使った」では許されない旨を示した広島地判昭和44年12月16日判決

国や地方自治体から提供される補助金や助成金の交付申請において、内容を偽ったり、虚偽の実績を報告したりする不正受給行為は、単なる行政上のルール違反や資金の返還問題にとどまらず、悪質な場合、刑法上の詐欺罪(10年以下の拘禁刑)や補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(適正化法)違反として、刑事責任を問われる重大な犯罪行為となります。
近年でも、特に悪質な研修会社やコンサルタント等に「唆される」ことで不正受給に手を染めてしまう会社は後を絶ちません。こうした不正受給を行ってしまった場合、以下のような疑問が出るかもしれません。
- 不正に受給した資金を後で正当に使った場合、罪を免れることができるのか?
- 不正が発覚した場合、資金を全額返還すれば、刑事責任を問われることは100%ないのか?
こうした論点に関して、明確かつ厳しい法的判断を下した裁判が存在します。広島地判昭和44年12月16日判決を、不正受給に関わる刑事責任についての重要な裁判例として、解説します。
この記事の目次
本件事件で補助金の不正受給が行われた背景
被告人(町の代表者)の属性と動機
本件の被告人は、昭和31年(1956年)から継続して広島県安芸郡下蒲刈島村(後に町制施行により下蒲刈町)の代表者(町長)を務めていた人物です。
不正行為に手を染めた動機は、当時の町の極めて厳しい財政状況であったことにあります。下蒲刈町は人口約5,000人余りであり、財源も乏しく、「広島県下でも最も貧しい市町村の一つ」であったとされています。町の代表者は、簡易水道布設事業を推進するにあたり、これに必要な費用に対する地元負担分の軽減を図るため、国庫補助対象事業費の申請額を水増しするという、内容虚偽の補助申請を行うことを企てました。
不正の対象となった国庫補助金と事業
不正の対象となったのは、昭和39年度(1964年度)の三之瀬地区簡易水道布設事業です。下蒲刈町は離島振興法に基づく対策実施地域に指定されており、関連政令に基づき、国庫補助基本額に対して10分の4の割合の国庫補助金が交付されることになっていました。
補助金や助成金は、多くの場合、「実際に支出した金額のうちの、一定割合」を国や地方自治体が支給するという建付になっており、この構造は、現代的な補助金・助成金と変わりがありません。
共謀者(担当職員)の関与と計画性
この不正計画は、町の代表者単独で実行されたものではありませんでした。代表者は、申請事務を担当していた同町の住民係長と共謀のうえ、内容虚偽の国庫補助申請書を作成・行使しました。
これは、不正受給の多くが、企業内部の複数の役員や担当者、あるいは外部のコンサルタントや業者を巻き込んだ組織的な共謀によって実行される現代の事案に通じる構造です。組織的な不正行為は、個人の単なるミスとは異なり、刑事責任を問われる際の悪質性や計画性が高いと評価され、量刑判断において不利な要素となります。
補助金「水増し申請」の手口

町の代表者らは、地元負担分の軽減を図るため、工事費と用地費の二つの項目で意図的な水増しを行いました。
工事費の水増し
町の代表者は、工事請負契約を締結するに先立ち、入札に参加した業者に対し、実際の見積額より1,000,000円を上積みした金額で入札するよう発言したことが認められました。
つまり、「実際よりも過大な金額を基本額にする(水増しを行う)」と、「その分、補助金の金額も増える」という構造で、これもまた、現代的な補助金・助成金の不正受給と変わりがありません。
なお、弁護側は、この発言について「後日設計変更があっても増額は認められないから、そこのところを考えて入札するよう注意したにすぎない」と主張しました。しかし、裁判所は、契約締結の数日後に町の住民係長が代表者の命令により1,000,000円の架空の領収書を業者より徴収した事実を認定しました。この事実を総合し、裁判所は、代表者の真意は、設計変更の注意喚起ではなく、当初から上積みさせた金額で請負契約を結び、これをもとにして補助金の水増し申請をする積りであったと結論づけました。たとえ、実際の請負価格が、国が定める補助金交付の上限(算定基準)を下回っていたとしても、実際の価格が算定基準を下回る場合は、低い方の実際価格を補助基本額とするのが原則です。したがって、実際の実支出額を超えて架空の費用を計上する行為は、補助金制度の趣旨から逸脱した不正行為と認定されました。
用地費・補償費の水増しと寄附の偽装
用地買収費については、工事費よりもさらに大きな水増しが行われました。
裁判所は、実際の買上価格が補助申請書に記載された金額よりはるかに少ないにも関わらず、その差額を土地所有者が町に寄附したという弁護側の主張を否定しました。認定された事実は、各土地所有者が、実際の買上価格と申請額の差額を町に寄附することの認識を持っていなかったという点です。町の代表者は、担当職員に対し、土地所有者の認識がないにも関わらず、その差額について「あたかも寄附されたような形式を書面上整えさせたにすぎない」と判断されました。
この手口は、現代の助成金不正事案で問題となる、サービス提供業者と申請事業主の間で資金を環流させたり、リベートを支払ったりして「実質的な費用負担がない状態」を作り出すスキームに近しいと見ることができます。領収書、寄附書など、形式的な書面の整合性があっても、実態として費用負担の虚偽があった場合、それは不正受給の根拠となります。
不正受給額の確定と虚偽公文書の行使
町の代表者らは、工事費等および用地費等を水増しすることにより、国庫補助基本額を水増し前の18,961,200円から、虚偽の22,150,000円へと水増ししました。その結果、本来正当に申請すべき補助申請額7,584,480円に対し、虚偽の申請額8,860,000円を算出し、その差額金1,275,520円を偽りの手段により交付を受けたと認定されました。
不正受給額の対照表
| 正当な補助基本額 | 虚偽の補助基本額(申請額) | 水増し金額 | |
|---|---|---|---|
| 工事費および諸経費 | 18,323,000円 | 19,323,000円 | 1,000,000円 |
| 用地費および補償費 | 369,200円 | 2,558,000円 | 2,188,800円 |
| 事務費 | 269,000円 | 269,000円 | 0円 |
| 合計(国庫補助基本額) | 18,961,200円 | 22,150,000円 | 3,188,800円 |
虚偽の補助申請書は、町の代表者名義で作成され、広島県庁の衛生部公衆衛生課室において、不正の計画を知らない同課の水道係員に対し、真実なもののように装い提出・行使されました。
裁判所は、この県庁係員が「情を知らない」状態で申請書を受け付けたという点を明記しています。これは、虚偽の申請書が、行政の審査過程における「人を欺く行為」(詐欺の構成要件)として機能したことを示すものです。
補助金不正受給が詐欺罪となる既遂時期と法的論点
「事後的な適正使用」という反論
弁護側は、この事案において、不正受給が認定されたとしても、刑事責任は成立しないという重要な反論を展開しました。
その主張は、「仮に本件国庫補助申請において水増しがあったとしても、不正に受給したとされる補助金1,275,520円は、その後、もともと補助対象事業である本件簡易水道工事のためにすべて支出されたのであるから、国において財政上の損失を生ずることがなく、従って適正化法第29条第1項に当らない」という趣旨でした。
この主張は、不正行為に手を染めた事業主が「結果的に会社のためになった」「資金は本来の目的に使われた」と自己正当化を図る際によく用いる論理と同質でしょう。
裁判所による否定
裁判所は、弁護側のこの主張を明確に退けました。これは、補助金不正受給の法的リスクを考える上で、最も重要な結論です。
裁判所は、補助金行政の適正な運用を保護するために適正化法が存在するという前提に立ち、以下のように判断を下しました。
補助金行政の適正な運用をはかるために補助金の交付申請、交付決定、その使途等につき詳細かつ厳格な諸規定をおく同法が、いわゆる水増申請によつて余分に受給された補助金が、たまたま事後的に補助対象たりうる事業のために支出されたからといつて、既になされた水増申請が遡って不正でなくなることを容認する趣旨であるとは到底解されない
広島地判昭和44年12月16日判決
この判決は、犯罪の成立を判断する上で、不正な申請が行われた時点の行為の性質が決定的に重要であり、事後的な行為でその不正性が解消されることはない、という姿勢を示しています。
なぜ「不正受給の既遂時期」が重要なのか
本判決は、詐欺罪や適正化法違反による不正受給罪の既遂時期は、補助金の交付を受けた時点であると判断しました。
裁判所がこの結論に至った詳細な法的な論理は、補助金適正化法の保護法益が、単に国の「最終的な財政の健全性」にあるのではなく、「補助金行政の適正な運用」と「交付プロセスの信頼性」にあることによります。
裁判所は、不正行為が国の財政的利益を侵害した時期について、以下のように述べています。
いわゆる水増申請によつて余分の補助金を受給する行為は、その不正受給分につき右の申請およびそれに対する国の審査、交付決定等手続過程上のチェックをすべて潜脱して補助金をいわば先取りするものであり、しかも改めて申請した場合に必ず交付を受けられるとは限らないから、たとえ事後的に補助対象事業のために支出されたとしても、補助金の交付を受けた時点において既に国の財政的利益を侵害したものといわなければならない。
広島地判昭和44年12月16日判決
この判断は、虚偽の申請によって行政の手続き上のチェック(審査や配分調整)を「潜脱」し、補助金を本来の適正な手続きなしに「先取り」した行為自体が、行政の適正性を侵害した結果、国の財政的利益を侵害したと捉えています。したがって、資金が交付された時点、すなわち不正受給が成功した時点で犯罪は「既遂」となります。
この法理の重要性は、事業主が不正発覚後に全額返還したとしても、それは既に成立した刑事責任を消滅させる行為ではないという点にあります。返還行為は、あくまでも「量刑において配慮されうる」(刑の重さを判断する際に考慮される)にとどまり、罪そのものを否定する理由にはならないのです。
補助金不正受給に関する刑事罰とペナルティ
本件の判決と量刑

町の代表者の行為は、単一の犯罪ではなく、複数の罪状が成立する複合的な犯罪として扱われました。
- 有印虚偽公文書作成罪(刑法第156条、第155条第1項)
- 有印虚偽公文書行使罪(刑法第158条第1項、第156条)
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反(適正化法第29条第1項)
裁判所は、これらの行為の間には「順次手段結果の関係」(例:虚偽の公文書を作成し、それを行使することが、不正受給の手段となった)があると認定しました。このような手段と結果の関係にある複数の犯罪については、刑法第54条第1項後段により、最も重い刑罰である罪の刑で処断されます。
本件では、法定刑の上限がより重い有印虚偽公文書行使罪(当時の法定刑は拘禁刑3月以上10年以下)の刑で処断されました。これは、不正受給という経済犯罪が、虚偽の申請書を提出したという公文書に関する罪によって、量刑リスクが劇的に増幅される現実を示しています。
| 罪状 | 根拠法条 | 法定刑の上限 | 本件判決 |
|---|---|---|---|
| 有印虚偽公文書作成 | 刑法第156条、第155条第1項 | 10年以下の拘禁刑 | (他の罪と手段結果の関係) |
| 有印虚偽公文書行使 | 刑法第158条第1項、第156条 | 10年以下の拘禁刑 | 拘禁刑1年6月(執行猶予3年) |
| 補助金等適正化法違反 | 適正化法第29条第1項 | 拘禁刑5年以下または罰金100万円以下 | (他の罪と手段結果の関係) |
| 処断刑 | 刑法第54条第1項後段 | 最も重い罪の刑 | 有印虚偽公文書行使罪 |
裁判の結果、町の代表者は、拘禁刑1年6月、情状により執行猶予3年となりました。執行猶予の判断には、不正受給した資金が事後的に事業のために使われたという点が量刑上の情状として考慮されたものと推察されます。
刑事責任と行政責任の複合リスク
なお、現代において、IT導入補助金やリスキリング助成金などの補助金・助成金について、事業主が不正受給で有罪となった場合は、刑事罰(拘禁刑、罰金)に加えて、行政処分と金銭的ペナルティが複合的に課されます。
- 補助金全額の返還命令:不正受給額のみならず、その事業全体で交付された補助金全額について、返還が命じられるケースが多いです。
- 加算金の支払い:不正受給額に対し、行政庁の定める加算金(通常20%から40%程度)が追加で課されます。
- 指名停止措置:補助金・助成金の受給停止、または一定期間、国や自治体との取引における指名停止措置(ブラックリスト掲載)を受け、企業の経営活動に打撃を与えます。
- 企業名・代表者名の公表:行政機関(労働局、経産局など)により、企業名や代表者名が公表され、社会的信用が失われます。
本判決が示す補助金不正受給対応の教訓
広島地判の教訓が示す最も重要なポイントは、補助金不正受給は、虚偽の申請書を行政機関に提出し、補助金の交付を受けた時点で既に既遂の犯罪として成立しており、後から不正に受給した資金を返還する意思や、結果的に本来の目的で利用したという事実をもって、罪責が否定されることはないという点です。
不正に関与してしまったという認識を持っている事業者は、この厳格な法理を理解することが重要です。不正行為を速やかに認め、自首や調査への最大限の協力、そして不正受給額の計算と返還計画の策定を行うことは、刑事責任との関係では、「罪を消す」行為ではありません。それらは、将来的な刑事処分(起訴・不起訴)や量刑判断を見据えて、執行猶予の獲得や罰金刑での収束を目指すため、「情状」として扱われるための前提条件となります。
まとめ:補助金不正受給に関する相談は弁護士へ
補助金不正事案は、行政機関による調査と、警察・検察による刑事捜査が並行して進むことが一般的であり、両方の手続きに適切に対応する必要があります。特に、虚偽申請に至った経緯(例えば、外部の悪質なコンサルタントの指南があったかどうか)、共犯者(従業員や業者)との関係の整理、そして不正受給額の確定と行政への自主的な返還準備といった対応は、法的知識なくして適切に進めることはできません。早期に専門の弁護士に相談し、組織体制の見直しや再発防止策の徹底といった情状を有利にするための具体的な防御戦略を立てることが不可欠です。
補助金や助成金の不正受給問題は、企業の存続、経営者の社会的信用、そして人生そのものを脅かす重大な法的リスクです。不正に関与した可能性を認識した時点で、一刻も早く弁護士に相談することが、被害を最小限に抑えるために重要であると言えるでしょう。
当事務所による対策のご案内
モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。当事務所では、東証プライム上場企業からベンチャー企業まで、ビジネスモデルや事業内容を深く理解した上で潜在的な法的リスクを洗い出し、リーガルサポートを行っております。下記記事にて詳細を記載しております。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務