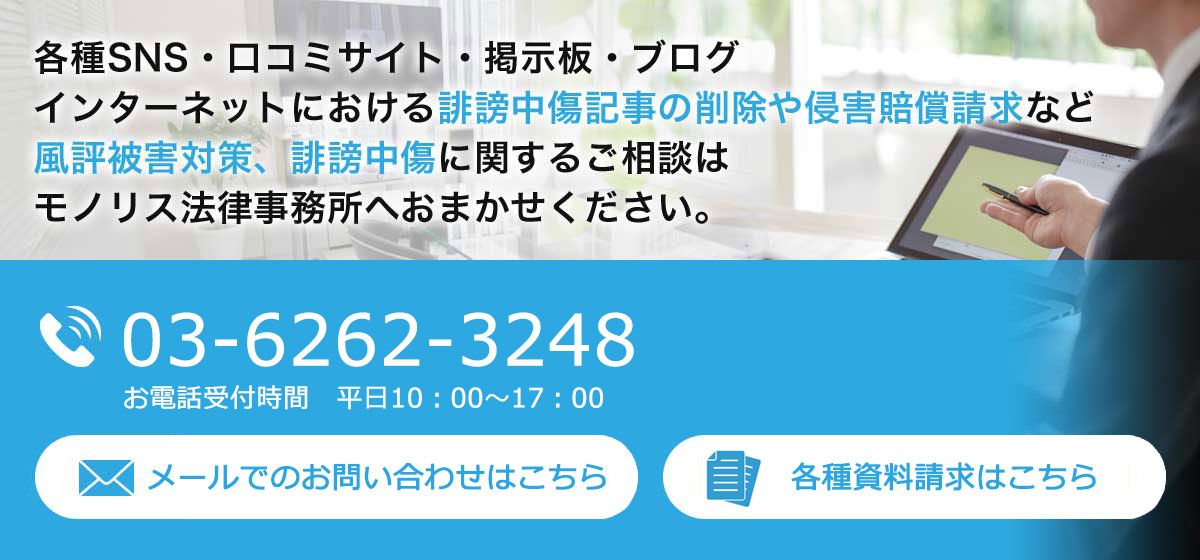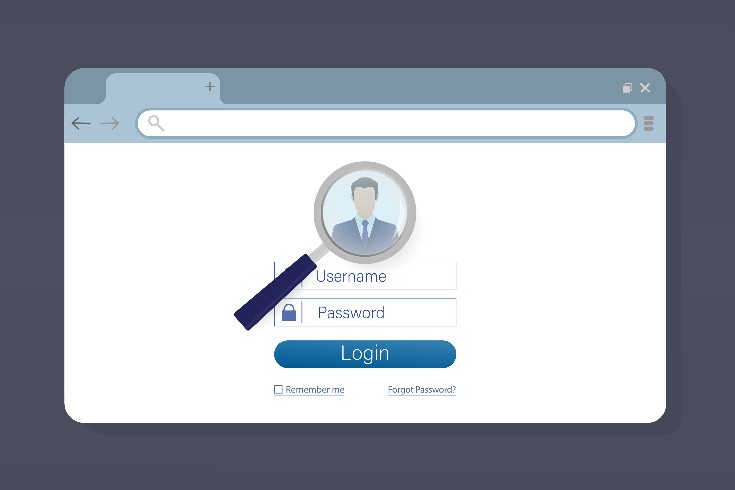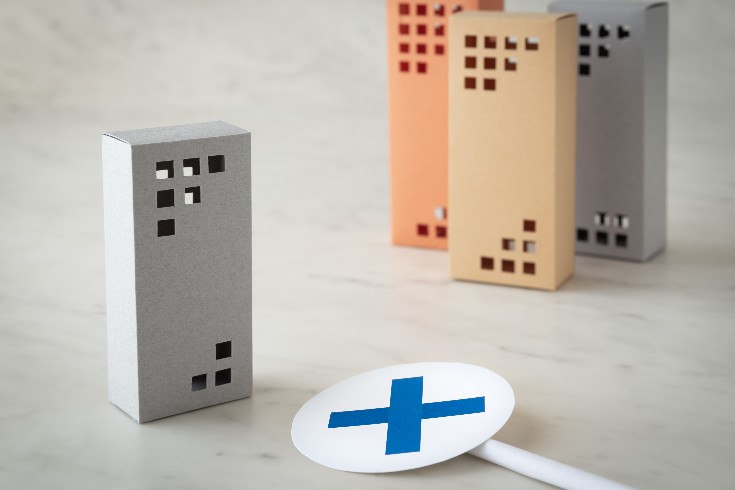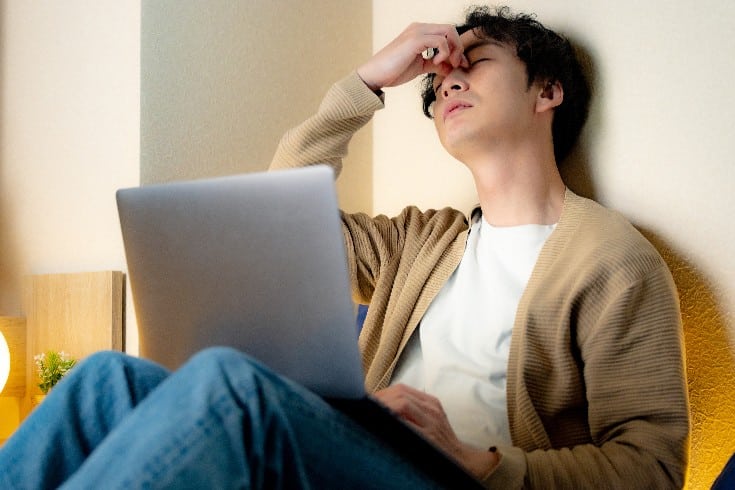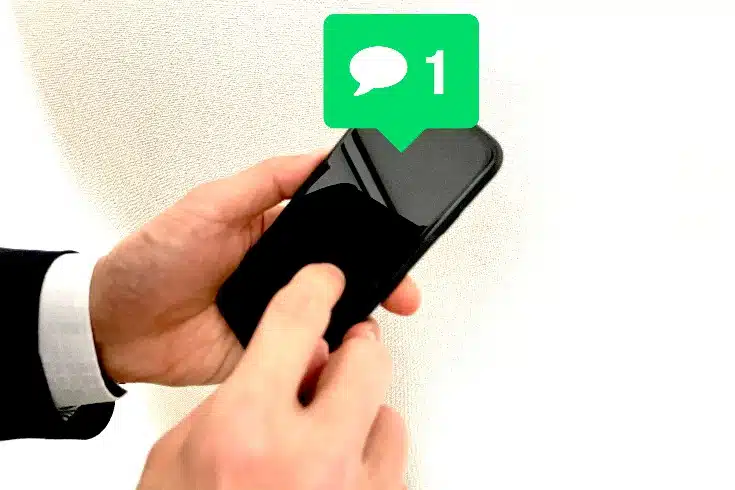ÒâìÒââÒâêÒü½ÒüèÒüæÒéïÞ¬╣Þ¼ùõ©¡ÕéÀÒü«Õ«Üþ¥®´╝ÜÞäàÞ┐½þ¢¬Òü«µêÉþ½ïÞªüõ╗ÂÒéäÚûóÚÇúÒüÖÒéïþè»þ¢¬ÒééÞºúÞ¬¼

ÞäàÞ┐½Òü¿ÒüäÒüåÒü¿õ¢ôµá╝Òü«ÒüäÒüäþöÀÒüîµÇûÒüäÚíöÒüºÒüÖÒüöÒéÇÒéñÒâíÒâ╝Òé©ÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒüîÒÇüÒéñÒâ│Òé┐Òâ╝ÒâìÒââÒâêõ©èÒüºÒü»õ©¡Õ¡ªþöƒÒüïÒéëÚ½ÿÚ¢óÞÇàÒü¥ÒüºÒÇüÞ¬░ÒüºÒééÞäàÞ┐½Òü«ÕèáÕ«│ÞÇàÒü½Òü¬ÒéèÕ¥ùÒü¥ÒüÖÒÇé
µ│òÕïÖþ£üÒü«þÁ▒Þ¿êÒüºÒü»Õ╣│µêÉ29Õ╣┤Òü«ÞäàÞ┐½ÒüºÒü«ÚÇ«µìòÞÇàÒü»2800õ║║ÒÇüÒüØÒü«ÒüåÒüíÒéÁÒéñÒâÉÒâ╝þ®║ÚûôÒüºÒü«ÞäàÞ┐½Òü»310õ╗ÂÒüºÒüùÒüƒÒÇéÒâìÒââÒâêõ©èÒüºÒü»þø©µëïÒü¿þø┤µÄÑÕÉæÒüìÕÉêÒéÅÒü¬ÒüäÒüƒÒéüÕ«ëµÿôÒü½Úüĵ┐ÇÒü¬Þí¿þÅ¥ÒéÆõ¢┐ÒüúÒüªÒüùÒü¥ÒüäÒÇüÒüØÒéîÒüîÞäàÞ┐½þ¢¬Òü½þÖ║Õ▒òÒüÖÒéïÕá┤ÕÉêÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
µ£¼Þ¿ÿõ║ïÒüºÒü»ÒÇüÒâìÒââÒâêõ©èÒü«µèòþ¿┐ÒüºÞäàÞ┐½þ¢¬ÒüîµêÉþ½ïÒüÖÒéïÒé▒Òâ╝Òé╣ÒéäÕ»¥Õ┐£µû╣µ│òÒü½ÒüñÒüäÒüªÞºúÞ¬¼ÒüùÒü¥ÒüÖÒÇé
ÒüôÒü«Þ¿ÿõ║ïÒü«þø«µ¼í
Þ¬╣Þ¼ùõ©¡ÕéÀÒü«õ©ÇÞê¼þÜäÒü¬µäÅÕæ│
Þ¬╣Þ¼ùõ©¡ÕéÀÒü¿Òü»ÒÇüµá╣µïáÒü«Òü¬Òüäµé¬ÕÅúÒéÆÞ¿ÇÒüäÒüÁÒéëÒüùÒüªõ╗ûõ║║ÒéÆÕéÀÒüñÒüæÒéïÞíîþé║ÒüºÒüÖÒÇéÞ¬╣Þ¼ùõ©¡ÕéÀÒü»µ│òÕ¥ïõ©èÒü«þö¿Þ¬×ÒüºÒü»Òü¬ÒüÅÒÇüõ©ÇÞê¼þÜäÒü½õ¢┐þö¿ÒüòÒéîÒéïÞ¿ÇÞæëÒüºÒüÖÒÇéÒÇîÞ¬╣Þ¼ùÒÇìÒü¿ÒÇîõ©¡ÕéÀÒÇìÒü¿ÒüäÒüåõ║îÒüñÒü«Þªüþ┤áÒüïÒéëµêÉÒéèþ½ïÒüúÒüªÒüèÒéèÒÇüÒÇîÞ¬╣Þ¼ùÒÇìÒü»õ╗ûõ║║ÒéƵé¬ÒüÅÞ¿ÇÒüåÒüôÒü¿Òéäµé¬ÕÅúÒéƵîçÒüùÒÇüÒÇîõ©¡ÕéÀÒÇìÒü»µá╣µïáÒü«Òü¬ÒüäÕÿÿÒéäÒüºÒüƒÒéëÒéüÒéÆÞ┐░Òü╣ÒéïÒüôÒü¿ÒéƵäÅÕæ│ÒüùÒü¥ÒüÖÒÇé
Þ¬╣Þ¼ùõ©¡ÕéÀÒü½ÕɽÒü¥ÒéîÒéïÒü«Òü»ÒÇüµé¬ÕÅúÒÇüÕ½îÒüîÒéëÒüøÒÇüÒü¬ÒéèÒüÖÒü¥ÒüùÒÇüµ│òÕ¥ïõ©èÒü«õ©ìµ│òÞíîþé║´╝굿®Õê®õ¥ÁÕ«│´╝ëÒÇüþè»þ¢¬Þíîþé║Òü¬Òü®ÒÇüÕ╣àÕ║âÒüäÞíîþé║ÒüºÒüÖÒÇéõ©ÇÞê¼þÜäÒü½Òü»ÒÇüõ║║Òéäõ╝üµÑ¡Òü½Õ»¥ÒüùÒüªõ©ìÕ┐½Òü¬µÇØÒüäÒéäµüɵÇûÕ┐âÒéÆÒééÒüƒÒéëÒüÖÞíîþé║Òü»ÒüÖÒü╣ÒüªÞ¬╣Þ¼ùõ©¡ÕéÀÒü¿ÒüùÒüªµìëÒüêÒéëÒéîÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇé
ÒüôÒéîÒü»ÒÇîµë╣ÕêñÒÇìÒü¿Òü»µÿÄþó║Òü½þò░Òü¬ÒéèÒü¥ÒüÖÒÇéµë╣ÕêñÒü»þë®õ║ïÒü½µñ£Þ¿ÄÒéÆÕèáÒüêÒüªÕêñÕ«ÜÒâ╗Þ®òõ¥íÒüÖÒéïÒüôÒü¿ÒéäÒÇüõ║║Òü«Þ¿ÇÕïòÒâ╗õ╗òõ║ïÒü¬Òü®Òü«Þ¬ñÒéèÒéäµ¼áþé╣ÒéƵîçµæÿÒüùÒÇüµ¡úÒüÖÒü╣ÒüìÒüºÒüéÒéïÒü¿ÒüùÒüªÞ½ûÒüÿÒéïÒüôÒü¿ÒüºÒüÖÒÇéµë╣ÕêñÒüîÕ╗║Þ¿¡þÜäÒü¬þø«þÜäÒéƵîüÒüúÒüªÞíîÒéÅÒéîÒéïÒü«Òü½Õ»¥ÒüùÒÇüÞ¬╣Þ¼ùõ©¡ÕéÀÒü»Õ░éÒéëþø©µëïÒéƵö╗µÆâÒüùÕéÀÒüñÒüæÒéïÒüôÒü¿ÒéÆþø«þÜäÒü¿ÒüùÒüªÒüäÒéïþé╣ÒüîÕñºÒüìÒü¬ÚüòÒüäÒüºÒüÖÒÇé
Þ¬╣Þ¼ùõ©¡ÕéÀÒü»ÒÇüþë╣Òü½SNSÒéäµÄ▓þñ║µØ┐Òü¬Òü®Òü«ÒéñÒâ│Òé┐Òâ╝ÒâìÒââÒâêõ©èÒüºµÀ▒Õê╗Òü¬ÕòÅÚíîÒüºÒüÖÒÇéþø©µëïÒü«þñ¥õ╝ÜþÜäÞ®òõ¥íÒéÆõ¢Äõ©ïÒüòÒüøÒüƒÒéèÒÇüþ▓¥þÑ×þÜäÒü¬ÞïªþùøÒéÆõ©ÄÒüêÒüƒÒéèÒüÖÒéïÕá┤ÕÉêÒü½Òü»ÒÇüÕÉìެ뵻ǵÉìþ¢¬Òéäõ¥«Þ¥▒þ¢¬Òü¬Òü®Òü«þè»þ¢¬Òü¿ÒüùÒüªÕçªþ¢░ÒüòÒéîÒéïÕÅ»Þ⢵ǺÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
ÞäàÞ┐½þ¢¬Òü«µêÉþ½ïÞªüõ╗ÂÒü¿Òü»
1ÒÇÇþöƒÕæ¢ÒÇüÞ║½õ¢ôÒÇüÞç¬þö▒ÒÇüÕÉìÞ¬ëÕÅêÒü»Þ▓íþöúÒü½Õ»¥ÒüùÕ«│ÒéÆÕèáÒüêÒéïµù¿ÒéÆÕæèþƒÑÒüùÒüªõ║║ÒéÆÞäàÞ┐½ÒüùÒüƒÞÇàÒü»ÒÇü2Õ╣┤õ╗Ñõ©ïÒü«µç▓Õ¢╣ÕÅêÒü»30õ©çÕååõ╗Ñõ©ïÒü«þ¢░ÚçæÒü½ÕçªÒüÖÒéïÒÇé
Õêæµ│òþ¼¼222µØí (ÞäàÞ┐½)
2ÒÇÇÞª¬µùÅÒü«þöƒÕæ¢ÒÇüÞ║½õ¢ôÒÇüÞç¬þö▒ÒÇüÕÉìÞ¬ëÕÅêÒü»Þ▓íþöúÒü½Õ»¥ÒüùÕ«│ÒéÆÕèáÒüêÒéïµù¿ÒéÆÕæèþƒÑÒüùÒüªõ║║ÒéÆÞäàÞ┐½ÒüùÒüƒÞÇàÒééÒÇüÕëìÚáàÒü¿ÕÉÿÒü¿ÒüÖÒéïÒÇé
õ©èÒü½Þ®▓Õ¢ôÒüÖÒéïÒéêÒüåÒü¬µèòþ¿┐ÒéÆÒüÖÒéïÒü¿ÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬Òü»ÚØ×Þª¬Õæèþ¢¬Òü¬Òü«ÒüºÒÇüÞó½Õ«│ÞÇàÒüîÕêæõ║ïÕæèÞ¿┤ÒéÆÒüùÒü¬ÒüÅÒüªÒééÒÇüÕçªþ¢░ÒüòÒéîÒüªÒüùÒü¥ÒüåÕÅ»Þ⢵ǺÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
õ╗ÑÚÖìÒüºÒü»ÒÇüµØíµûçÒü½Õç║ÒüªÒüÅÒéïµûçÞ¿ÇÒéÆÒü¿ÒéèÒüéÒüÆÒüñÒüñÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬Òü«µêÉþ½ïÞªüõ╗ÂÒéÆÞºúÞ¬¼ÒüùÒü¥ÒüÖÒÇé
Õ«│µé¬Òü«ÕæèþƒÑ
ÒÇîÕ«│ÒéÆÕèáÒüêÒéïµù¿ÒéÆÕæèþƒÑÒÇìÒÇüÒüñÒü¥ÒéèÒÇîÕ«│µé¬Òü«ÕæèþƒÑÒÇìÒéÆÒüùÒü¬ÒüæÒéîÒü░ÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬Òü»µêÉþ½ïÒüùÒü¥ÒüøÒéôÒÇé
ÒÇîÕ«│µé¬ÒÇìÒü½Þ®▓Õ¢ôÒüÖÒéïÒüïÒü®ÒüåÒüïÒü»ÒÇüÕ«óÞª│þÜäÒü½Õêñµû¡ÒüòÒéîÒéïÒü«ÒüºÒÇüÞó½Õ«│ÞÇàÒüîÒÇîÞäàÞ┐½ÒÇìÒü¿µäƒÒüÿÒüªÒééÒÇüÒÇîÞäàÞ┐½ÒÇìÒü½Òü¬ÒéëÒü¬ÒüäÒüôÒü¿ÒüîÒüéÒéèÒÇüÒüØÒü«Õêñµû¡Òü»ÒÇüþèµ│üÒü½ÒéêÒüúÒüªþò░Òü¬ÒéïÒü¿ÒüòÒéîÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇéÒüØÒü«õ¥ïÒü¿ÒüùÒüªÒÇüÞïÑÒüÅÒüªÒüƒÒüÅÒü¥ÒüùÒüäõ¢ôµá╝Òü«þöÀµÇºÒüîÒÇîÒé▒Òé¼ÒéÆÒüòÒüøÒéïÒü×ÒÇìÒü¿Þ¿ÇÒüúÒüƒÕá┤ÕÉêÒü¿ÒÇüÕ░ÅÒüòÒü¬Õ¡ÉÒü®ÒééÒüîÒÇîÒé▒Òé¼ÒéÆÒüòÒüøÒéïÒü×ÒÇìÒü¿Þ¿ÇÒüúÒüƒÕá┤ÕÉêÒü¿ÒüºÒü»ÒÇüÕ«óÞª│þÜäÒü½ÞªïÒüªÒééÒÇüÞó½Õ«│ÞÇàÒüîµäƒÒüÿÒéïµüɵÇûµäƒÒüîþò░Òü¬ÒéïÒü¿ÒüäÒüåÕá┤ÕÉêÒüîÒÇüõ╗ÑÕëìÒüïÒéëÒüéÒüÆÒéëÒéîÒüªÒüìÒü¥ÒüùÒüƒÒÇé
ÕëìÞÇàÒü«Õá┤ÕÉêÒü½Òü»ÒÇîÕ«│µé¬Òü«ÕæèþƒÑÒÇìÒü½Òü¬ÒéèÒÇüÕ¥îÞÇàÒü«Õá┤ÕÉêÒü½Òü»ÒÇîÕ«│µé¬Òü«ÕæèþƒÑÒÇìÒü½Òü¬ÒéëÒü¬ÒüäÒü¿ÒüòÒéîÒüªÒüìÒüƒÒü«ÒüºÒüÖÒüîÒÇüÒâìÒââÒâêõ©èÒüºÒü»ÒÇüÒüôÒü«õ¥ïÒü»ÚÇÜþö¿ÒüùÒü¥ÒüøÒéôÒÇéÕçµÜ┤Òü¬þöÀÒü«µèòþ¿┐Òü¬Òü«ÒüïÒÇüÕ¡ÉÒü®ÒééÒü«µèòþ¿┐Òü¬Òü«ÒüïÒÇüÕî║ÕêÑÒüîÒüñÒüìÒü¥ÒüøÒéôÒÇé
Õ«ƒÚÜøÒÇüÒéÁÒéñÒâÉÒâ╝þ®║ÚûôÒü½ÒüèÒüæÒéïÞäàÞ┐½Òü«µæÿþÖ║ÞÇàÒü«õ©¡Òü½Òü»õ©¡Õ¡ªþöƒÒéäÚ½ÿÚ¢óÞÇàÒééÕɽÒü¥ÒéîÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇé
ÞäàÞ┐½Òü«µû╣µ│ò

ÞäàÞ┐½þ¢¬ÒüîµêÉþ½ïÒüÖÒéïÒüƒÒéüÒü½Òü»ÒÇîÕ«│µé¬Òü«ÕæèþƒÑÒÇìÒüîÕ┐àÞªüÒüºÒüÖÒüîÒÇüÒÇîÕæèþƒÑÒÇìÒü¿ÒüäÒüåÕá┤ÕÉêÒÇüÒü®Òü«ÒéêÒüåÒü¬µû╣µ│òÒüîÕɽÒü¥ÒéîÒéïÒü«ÒüºÒüùÒéçÒüåÒüïÒÇé
µ│òÕ¥ïõ©èÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬Òü«Õ«│µé¬Òü«ÕæèþƒÑµû╣µ│òÒü½ÒüñÒüäÒüªÒÇüþë╣Òü½ÕêÂÚÖÉÒü»ÒééÒüåÒüæÒéëÒéîÒüªÒüäÒü¥ÒüøÒéôÒÇéÒü¥ÒüÜÒÇüþø┤µÄÑÞ¿ÇÞæëÒüºÕæèÒüÆÒüƒÕá┤ÕÉêÒü½Òü»ÒÇüÒÇîÕæèþƒÑÒÇìÒüºÒüÖÒÇéµ¼íÒü½ÒÇüµëïþ┤Ö(ÞäàÞ┐½þèÂ)ÒéÆÚÇüõ╗ÿÒüùÒüƒÕá┤ÕÉêÒü½ÒééÒÇü´¢óÕæèþƒÑ´¢úÒü¿Òü¬ÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
ÒüáÒüïÒéëÒÇüþø©µëïÒü½þø┤µÄÑLINEÒéäÒâíÒâ╝Òâ½ÒüºÒÇîþºÿÕ»åÒéÆÒü░ÒéëÒüÖÒü×ÒÇìÒÇîÒüƒÒüáÒüºµ©êÒéÇÒü¿µÇØÒüåÒü¬ÒéêÒÇìÒü¬Òü®Òü«ÞäàÞ┐½Òü«ÒâíÒââÒé╗Òâ╝Òé©ÒéÆÚÇüÒüúÒüƒÕá┤ÕÉêÒü½Òü»ÒÇü´¢óÕæèþƒÑ´¢úÒüºÒüéÒéèÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬Òü¿Òü¬ÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
ÒâìÒââÒâêõ©èÒü«µèòþ¿┐ÒüºÒééÒÇüþø©µëïÒéÆþòŵÇûÒüòÒüøÒéïÒü½ÞÂ│ÒéèÒéïÒééÒü«Òü¬ÒéëÕ¢ôþäÂÒÇîÕ«│µé¬Òü«ÕæèþƒÑÒÇìÒüºÒüÖÒÇéõ¥ïÒüêÒü░ÒÇüþø©µëïÒü«SNSÒéäÞç¬ÕêåÒü«ÒâûÒâ¡Òé░Òü½µèòþ¿┐ÒüùÒüƒÕá┤ÕÉêÒÇüÒÇî2ÒüíÒéâÒéôÒü¡ÒéïÒÇìÒü¬Òü®Òü«ÒâìÒââÒâêµÄ▓þñ║µØ┐Òü½µèòþ¿┐ÒüùÒüƒÕá┤ÕÉêÒüºÒééÒÇüÒüØÒéîÒüîÒÇîÕ«│µé¬Òü«ÕæèþƒÑÒÇìÒüºÒüéÒéîÒü░ÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬ÒüîµêÉþ½ïÒüÖÒéïÕÅ»Þ⢵ǺÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé ÒâìÒââÒâêÒüºÒü»ÒÇüþ░íÕìÿÒü½ÞäàÞ┐½þ¢¬ÒüîµêÉþ½ïÒüùÒüªÒüùÒü¥ÒüåÒü«ÒüºÒÇüµèòþ¿┐Òü½Òü»ÒüÅÒéîÒüÉÒéîÒééµ│¿µäÅÒéƵëòÒéÅÒü¬ÒüæÒéîÒü░Òü¬ÒéèÒü¥ÒüøÒéôÒÇé
ÞäàÞ┐½Òü«Õ»¥Þ▒íÒü½ÒüñÒüäÒüª
ÞäàÞ┐½þ¢¬ÒüºÒü»ÒÇüÕêæµ│òþ¼¼222µØíÒü½ÒéêÒéèÒÇüÞäàÞ┐½Òü«Õ»¥Þ▒íÒüîÚÖÉÕ«ÜÒüòÒéîÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇé
- þöƒÕ梴╝ÜþöƒÕæ¢Òü½Õ»¥ÒüÖÒéïÕ«│µé¬Òü«ÕæèþƒÑÒü¿Òü»ÒÇüÒüäÒéÅÒéåÒéﵫ║Õ«│õ║êÕæèÒüºÒüéÒéèÒÇüÒÇ║ÒüÖÒÇìÒü¿ÒüäÒüåÒüôÒü¿ÒüºÒüÖÒÇéÒüáÒüïÒéëÒÇüÒÇ║ÒüÖÒü×ÒÇìÒü¿Þ¿ÇÒüúÒüƒÒéèÒÇîÕæ¢Òü»Òü¬ÒüäÒééÒü«Òü¿µÇØÒüêÒÇìÒü¿ÒüäÒüåµø©ÒüìÞ¥╝Òü┐ÒéÆÒüùÒüƒÒéèÒüÖÒéïÒü¿ÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬ÒüîµêÉþ½ïÒüÖÒéïÕÅ»Þ⢵ǺÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
- Þ║½õ¢ô´╝ÜÞ║½õ¢ôÒü½Õ»¥ÒüÖÒéïÕ«│µé¬Òü¿Òü»ÒÇüµÜ┤ÞíîÒéÆÒüÖÒéïµù¿Òü«ÕåàÕ«╣ÒüºÒüéÒéèÒÇüþø©µëïÒéÆÕéÀÒüñÒüæÒéïÒüôÒü¿ÒüºÒüÖÒÇéõ¥ïÒüêÒü░ÒÇüÒÇ┤ÒéïÒü×ÒÇìÒü¿Þ¿ÇÒüúÒüƒÒéèÒÇîÒüƒÒüáÒüºµ©êÒéÇÒü¿µÇØÒüåÒü¬ÒéêÒÇìÒü¿ÒüäÒüåµø©ÒüìÞ¥╝Òü┐ÒéÆÒüùÒüƒÒéèÒüÖÒéïÒü¿ÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬ÒüîµêÉþ½ïÒüÖÒéïÕÅ»Þ⢵ǺÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
- Þç¬þö▒´╝ÜÞç¬þö▒Òü½Õ»¥ÒüÖÒéïÕ«│µé¬Òü¿Òü»ÒÇüþø©µëïÒü«Þ║½õ¢ôÒéƵ؃þ©øÒüÖÒéïÒüôÒü¿ÒüºÒüÖÒÇéõ¥ïÒüêÒü░ÒÇüÒÇîþøúþªüÒüÖÒéïÒü×ÒÇìÒü¿ÕæèÒüÆÒüƒÒéèÒÇîÞ¬ÿµïÉÒüÖÒéïÒü×ÒÇìÒü¿ÒüäÒüåµø©ÒüìÞ¥╝Òü┐ÒéÆÒüùÒüƒÒéèÒüÖÒéïÒü¿ÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬ÒüîµêÉþ½ïÒüÖÒéïÕÅ»Þ⢵ǺÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
- ÕÉìÞ¬ë´╝ÜÕÉìÞ¬ëÒü½Õ»¥ÒüÖÒéïÕ«│µé¬Òü¿Òü»ÒÇüþø©µëïÒü«õ©ìÕÉìÞ¬ëÒü¬õ║ïÕ«ƒÒéÆÕà¼ÚûïÒüÖÒéïµù¿Òü«µø©ÒüìÞ¥╝Òü┐ÒüºÒÇüõ¥ïÒüêÒü░ÒÇüÒÇîõ©ìÕǽÒü«õ║ïÕ«ƒÒéÆÒü░ÒéëÒüÖÒü×ÒÇìÒÇîõ©ìµ¡úÒüùÒüªÒüäÒéïÒüôÒü¿ÒéÆÕà¼Òü½ÒüÖÒéïÒü×ÒÇìÒü¿ÒüäÒüåµø©ÒüìÞ¥╝Òü┐ÒéÆÒüùÒüƒÒéèÒüÖÒéïÒü¿ÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬ÒüîµêÉþ½ïÒüÖÒéïÕÅ»Þ⢵ǺÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇéÒüôÒü«Õá┤ÕÉêÒÇüÕà¼Òü½ÒüùÒéêÒüåÒü¿ÒüùÒüªÒüäÒéïõ║ïÕ«ƒÒüîþ£ƒÕ«ƒÒüºÒüéÒüúÒüªÒééÞäàÞ┐½Òü½Òü¬ÒéïÕÅ»Þ⢵ǺÒüîÒüéÒéïÒü«ÒüºÒÇüµ│¿µäÅÒüîÕ┐àÞªüÒüºÒüÖÒÇé
- Þ▓íþöú´╝Üþø©µëïÒü«Þ▓íþöúÒü½Õ»¥ÒüÖÒéïõ¥ÁÕ«│ÒéÆÒü╗Òü«ÒéüÒüïÒüÖÒüôÒü¿ÒüºÒüÖÒÇéõ¥ïÒüêÒü░ÒÇüÒÇîÒüèÕëìÒü«ÚçæÒéÆÕà¿Úâ¿ÕѬÒüúÒüªÒéäÒéïÒÇìÒÇîÕ«ÂÒéÆþçâÒéäÒüùÒüªÒéäÒéïÒÇìÒü¿ÒüäÒüåµø©ÒüìÞ¥╝Òü┐ÒéÆÒüùÒüƒÒéèÒüÖÒéïÒü¿ÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬ÒüîµêÉþ½ïÒüÖÒéïÕÅ»Þ⢵ǺÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
õ©èÞ¿ÿÒü«5Òüñõ╗ÑÕñûÒü«ÒééÒü«Òü½Õ»¥ÒüÖÒéïÞäàÒüùÒéÆÒüùÒüªÒééÒÇüÕƒ║µ£¼þÜäÒü½Òü»ÞäàÞ┐½þ¢¬Òü½Òü¬ÒéèÒü¥ÒüøÒéôÒÇé
õ¥ÁÕ«│ÒéÆÕÅùÒüæÒéïÞÇà(õ¥ÁÕ«│Õ»¥Þ▒í)
ÞäàÞ┐½þ¢¬ÒüºÒü»ÒÇüÕêæµ│òþ¼¼222µØíÒü½ÒéêÒéèÒÇüÞäàÞ┐½Òü«õ¥ÁÕ«│Õ»¥Þ▒íÒééÚÖÉÕ«ÜÒüòÒéîÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇé
ÞäàÞ┐½þ¢¬ÒüîµêÉþ½ïÒüÖÒéïÒü«Òü»ÒÇüþ¼¼222µØíþ¼¼´╝æÚáàÒéêÒéèÒÇîÒÇîõ║║ÒÇìÒüñÒü¥ÒéèÒÇîµ£¼õ║║ÒÇìÒÇüÕÉîµØíþ¼¼´╝ÆÚáàÒéêÒéèÒÇîÞª¬µùÅÒÇìÒü½Õ«│ÒéÆÕèáÒüêÒéïµù¿ÒéÆÕæèþƒÑÒüùÒüƒÕá┤ÕÉêÒü«Òü┐ÒüºÒüÖÒÇé
õ¥ïÒüêÒü░ÒÇüÒÇîÒüèÕëìÒü«Õª╗ÒéƵ«║ÒüÖÒü×ÒÇì ÒÇîÕ¡ÉÒü®ÒééÒéÆÞ¬ÿµïÉÒüÖÒéïÒü×ÒÇìÒü¬Òü®Òü¿µø©ÒüìÞ¥╝ÒéÇÒü¿ÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬ÒüîµêÉþ½ïÒüÖÒéïÕÅ»Þ⢵ǺÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇéÒüùÒüïÒüùÒÇüÕÅïõ║║ÒéäþƒÑõ║║Òü¬Òü®Òü½Õ»¥ÒüÖÒéïÕ«│µé¬Òü«ÕæèþƒÑÒüºÒü»ÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬Òü»µêÉþ½ïÒüùÒü¬ÒüäÒü«ÒüºÒÇüÒÇîÒüèÕëìÒü«µüïõ║║ÒéƵ«║ÒüÖÒü×ÒÇìÒü¿µø©ÒüìÞ¥╝ÒéôÒüºÒééÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬Òü½Òü»Þ®▓Õ¢ôÒüùÒü¬ÒüäÒüôÒü¿Òü½Òü¬ÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
ÒüƒÒüáÒüùÒÇüÒâÜÒââÒâêÒü»ÒÇîÞ▓íþöúÒÇìÒü¿Òü¬ÒéèÒü¥ÒüÖÒüïÒéëÒÇüÒÇîÒüèÕëìÒü«ÒâìÒé│ÒéÆÒü▓Òü®Òüäþø«Òü½ÕÉêÒéÅÒüøÒéïÒü×ÒÇìÒü¬Òü®Òü¿µø©ÒüìÞ¥╝ÒéÇÒü¿ÒÇüÒÇîµ£¼õ║║Òü«Þ▓íþöúÒÇìÒü½Õ»¥ÒüÖÒéïÕ«│µé¬Òü«ÕæèþƒÑÒü¿Òü¬ÒéèÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬ÒüîµêÉþ½ïÒüÖÒéïÕÅ»Þ⢵ǺÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
µ│òõ║║Òü½Õ»¥ÒüÖÒéïÞäàÞ┐½Òü»µêÉþ½ïÒüÖÒéïÒüï´╝ƒ
ÞäàÞ┐½þ¢¬Òü»ÒÇüÕƒ║µ£¼þÜäÒü½µ£¼õ║║Òü¥ÒüƒÒü»Þª¬µùÅÒü½Õ»¥ÒüÖÒéïÕ«│µé¬ÕæèþƒÑÒüîÒü¬ÒüäÒü¿µêÉþ½ïÒüùÒü¬ÒüäÒü«ÒüºÒÇüµ│òõ║║Òü»Õ»¥Þ▒íÕñûÒü¿Òü¬ÒéïÒü«ÒüîÕăÕëçÒüºÒüÖÒÇé
ÒüƒÒüáÒÇüÕêñõ¥ïÒéêÒéèÒÇüµ│òõ║║Òü©Òü«Õ«│µé¬Òü«ÕæèþƒÑÒüºÒüéÒüúÒüªÒééÒÇüÒüØÒéîÒüîÒüØÒü«Õ«│µé¬Òü«ÕæèþƒÑÒéÆÕÅùÒüæÒüƒÕÇïõ║║(µ│òõ║║Òü«õ╗úÞí¿ÞÇàÒéäõ╗úþÉåõ║║Òü¬Òü®)Òü«þöƒÕæ¢ÒéäÞ║½õ¢ôÒÇüÞç¬þö▒ÒÇüÕÉìÞ¬ëÒÇüÞ▓íþöúÒü½Õ»¥ÒüÖÒéïÕ«│µé¬Òü«ÕæèþƒÑÒü½Òü¬ÒéïÒü¬ÒéëÒÇüÒüØÒü«ÕÇïõ║║Òü½Õ»¥ÒüÖÒéïÞäàÞ┐½þ¢¬ÒüîµêÉþ½ïÒüÖÒéïÒü¿ÒüòÒéîÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇé
õ¥ïÒüêÒü░ÒÇüõ╝Üþñ¥Òü«õ╗úÞí¿ÞÇàÒü¬Òü®Òü½Õ»¥ÒüùÒÇüÒÇîÒüèÕëìÒü«õ╝Üþñ¥ÒéÆÒüñÒüÂÒüÖÒü×ÒÇìÒü¬Òü®Òü«µø©ÒüìÞ¥╝Òü┐ÒéÆÒüÖÒéïÒü¿ÒÇüõ╗úÞí¿ÞÇàÒü»ÒÇüÞç¬ÕêåÕÇïõ║║Òü½Õ»¥ÒüùÒüªÞäàÞ┐½ÒéÆÕÅùÒüæÒüƒÒü«Òü¿ÕÉîÒüÿÒéêÒüåÒü½þòŵÇûÒüùÒüªÒüùÒü¥ÒüåÒüôÒü¿ÒüîÕìüÕêåÒü½ÞÇâÒüêÒéëÒéîÒü¥ÒüÖÒÇéÒüôÒü«ÒéêÒüåÒü¬Òé▒Òâ╝Òé╣ÒüºÒü»ÒÇüõ╝Üþñ¥Òü½Õ»¥ÒüÖÒéïÕ«│µé¬Òü«ÕæèþƒÑÒéÆÒÇüÒüØÒü«ÕæèþƒÑÒéÆÕÅùÒüæÒüƒÕÇïõ║║Òü«þöƒÕæ¢ÒéäÞ║½õ¢ôÒÇüÞç¬þö▒ÒÇüÕÉìÞ¬ëÒÇüÞ▓íþöúÒü½Õ»¥ÒüÖÒéïÕ«│µé¬Òü«ÕæèþƒÑÒü¿Òü¿ÒéëÒüêÒüªÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬ÒüîµêÉþ½ïÒüÖÒéïÕÅ»Þ⢵ǺÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
ÞäàÞ┐½þ¢¬Òü»þø©µëïÒüîÒÇîþòŵÇûÒÇìÒüÖÒéïÕ┐àÞªüÒü»Òü¬Òüä
ÞäàÞ┐½þ¢¬Òü»ÒÇîþø©µëïÒéÆþòŵÇû´╝êÒüäÒüÁ´╝ܵüÉÒéîÒüèÒü«Òü«ÒüÅÒüôÒü¿´╝ëÒüòÒüøÒéïÒéêÒüåÒü¬Õ«│µé¬Òü«ÕæèþƒÑÒÇìÒü½ÒéêÒüúÒüªµêÉþ½ïÒüÖÒéïþè»þ¢¬ÒüºÒüÖÒüîÒÇüÕ«ƒÚÜøÒü½þø©µëïÒüîÒÇîþòŵÇûÒÇìÒüÖÒéïÕ┐àÞªüÒü»ÒüéÒéèÒü¥ÒüøÒéôÒÇé
ÞäàÞ┐½þ¢¬Òü½Òü»µ£¬Úüéþ¢¬ÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüøÒéôÒÇéÒÇîÞäàÞ┐½ÒüùÒüƒÒÇìµÖéþé╣ÒüºÒÇîµùóÚüéÒÇìÒü¿Òü¬ÒüúÒüªÒüùÒü¥ÒüåÒüïÒéëÒüºÒüÖÒÇéÒüáÒüïÒéëÒÇüþø©µëïÒüîÕ«ƒÚÜøÒü½ÒüèÒü│ÒüêÒüƒÒüïÒü®ÒüåÒüïÒü»Úûóõ┐éÒü¬ÒüäÒüôÒü¿Òü½Òü¬ÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
ÞäàÞ┐½þ¢¬Òü«ÒéêÒüåÒü½ÒÇüÕòÅÚíîÒü«Þíîþé║ÒéÆÞíîÒüåÒü¿Õ¢ôþäÂÒü½µêÉþ½ïÒüùÒüªÒüùÒü¥ÒüåÒé┐ÒéñÒâùÒü«þè»þ¢¬ÒéÆÒÇüÒÇîµè¢Þ▒íþÜäÕì▒ÚÖ║þè»ÒÇìÒü¿Þ¿ÇÒüäÒü¥ÒüÖÒÇéÒüØÒü«Þíîþé║Þç¬õ¢ôÒüîÕì▒ÚÖ║Òü¬Òü«ÒüºÒÇüÞíîþé║ÒüîÞíîÒéÅÒéîÒüƒµÖéþé╣ÒüºÕì▒ÚÖ║ÒüîþÖ║þöƒÒüùÒÇüþ¢¬ÒüîµêÉþ½ïÒüÖÒéïÒü¿ÒüäÒüåÞÇâÒüêµû╣ÒüºÒüéÒéèÒÇüÕêæµ│òþ¼¼108µØíÒü«þÅ¥õ¢ÅÕ╗║ÚÇáþë®þ¡ëµö¥þü½þ¢¬ÒüîÒüØÒü«õ╗úÞí¿õ¥ïÒü¿ÒüòÒéîÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇé
ÒüØÒüôÒüºÒÇüþø©µëïÒü½Õ»¥ÒüùÒüªÞäàÞ┐½ÒâíÒâ╝Òâ½ÒéÆÚÇüÒüúÒüƒÒéèÒÇüþø©µëïÒü«SNSÒü½Õ«│µé¬Òü«ÕæèþƒÑÒéƵø©ÒüìÞ¥╝ÒéôÒüáÒü¿ÒüìÒÇüþø©µëïÒüîõ╗«Òü½ÒÇîµÇûÒüäÒÇìÒü¿µÇØÒéÅÒü¬ÒüÅÒüªÒééÒÇüÒüØÒéîÒüîÕ«óÞª│þÜäÒü½õ║║ÒéÆþòŵÇûÒüòÒüøÒéïÒéêÒüåÒü¬ÕåàÕ«╣ÒüºÒüéÒéîÒü░ÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬ÒüîµêÉþ½ïÒüùÒüªÒüùÒü¥ÒüäÒü¥ÒüÖÒÇé
Þ¬╣Þ¼ùõ©¡ÕéÀÒü½ÒéêÒéïÞäàÞ┐½þ¢¬Òü«þ¢░Õëç
ÕæèÞ¿┤Òü¿Òü»ÒÇüÞó½Õ«│ÞÇàÒüîµì£µƒ╗µ®ƒÚûóÒü½þè»þ¢¬Òü«õ║ïÕ«ƒÒéÆþö│ÕæèÒüùÒüªÞ¿┤Þ┐¢ÒéƵ▒éÒéüÒéïµëïþÂÜÒüìÒüºÒüÖÒÇéÕæèÞ¿┤Òü»ÕÅúÚá¡ÒüºÒééÕÅ»Þâ¢ÒüºÒüÖÒüîÒÇüÚÇÜÕ©©Òü»µø©ÚØóÒüºÞíîÒéÅÒéîÒü¥ÒüÖÒÇéÞ¬╣Þ¼ùõ©¡ÕéÀÒü½ÚûóÚÇúÒüÖÒéïÕÉìެ뵻ǵÉìþ¢¬Òéäõ¥«Þ¥▒þ¢¬Òü»ÒÇîÞª¬Õæèþ¢¬ÒÇìÒüºÒüéÒéèÒÇüÞó½Õ«│ÞÇàÒüïÒéëÒü«ÕæèÞ¿┤ÒüîÕ┐àÞªüÒüºÒüÖÒÇéõ©Çµû╣ÒüºÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬Òü»ÚØ×Þª¬Õæèþ¢¬ÒüºÒüéÒéèÒÇüÕæèÞ¿┤ÒüîÒü¬ÒüÅÒüªÒééÞ¡ªÕ»ƒÒüîþè»þ¢¬Þíîþé║ÒéÆÞ¬ìþƒÑÒüÖÒéîÒü░µì£µƒ╗ÒéÆÚûïÕºïÒüÖÒéïÒüôÒü¿ÒüîÕÅ»Þâ¢ÒüºÒüÖÒÇé
ÕæèÞ¿┤ÒüîÕÅùþÉåÒüòÒéîÒéïÒü¿Þ¡ªÕ»ƒÒüîµì£µƒ╗ÒéÆÞíîÒüäÒÇüÕ┐àÞªüÒü½Õ┐£ÒüÿÒüªÕèáÕ«│ÞÇàÒéÆÚÇ«µìòÒüùÒüƒÕ¥îÒÇüµñ£Õ»ƒÒü½ÚÇüÞç┤ÒüòÒéîÒüªÞÁÀÞ¿┤Òüïõ©ìÞÁÀÞ¿┤ÒüïÒüîµ▒║Õ«ÜÒüòÒéîÒü¥ÒüÖÒÇéÞÁÀÞ¿┤ÒüòÒéîÒéïÒü¿ÞúüÕêñÒüîÚûïÒüïÒéîÒÇüµ£ëþ¢¬Òü«Õá┤ÕÉêÒü»Õêæþ¢░ÒéÆÕÅùÒüæÕëìþºæÒüîÒüñÒüÅÒüôÒü¿Òü½Òü¬ÒéèÒü¥ÒüÖÒÇéÞ¬╣Þ¼ùõ©¡ÕéÀÒü»ÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬Òü«Òü╗ÒüïÒü½ÒééÕÉìެ뵻ǵÉìþ¢¬Òéäõ¥«Þ¥▒þ¢¬Òü¬Òü®Òü½Þ®▓Õ¢ôÒüÖÒéïÕÅ»Þ⢵ǺÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒüîÒÇüÒü®Òü«þ¢¬Òü½Þ®▓Õ¢ôÒüÖÒéïÒüïÒü«Õêñµû¡Òü»ÚøúÒüùÒüäÒüƒÒéüÒÇüÕ░éÚûÇÕ«ÂÒü«Õè®Þ¿ÇÒüîÚçìÞªüÒüºÒüÖÒÇé
ÚûóÚÇúÞ¿ÿõ║ï´╝Üõ¥«Þ¥▒þ¢¬Òü¿Òü»´╝ƒÕàÀõ¢ôþÜäÒü¬Þ¿ÇÞæëÒü«õ¥ïÒéäÕÉìެ뵻ǵÉìþ¢¬Òü¿Òü«ÚüòÒüäÒéÆÞºúÞ¬¼
ÞäàÞ┐½þ¢¬Òü»ÒÇü2Õ╣┤õ╗Ñõ©ïÒü«µç▓Õ¢╣Òü¥ÒüƒÒü»30õ©çÕååõ╗Ñõ©ïÒü«þ¢░ÚçæÒüîþºæÒüøÒéëÒéîÒü¥ÒüÖÒÇé
Òü¬ÒüèÒÇüõ╗ñÕÆî7Õ╣┤´╝ê2025Õ╣┤´╝ë6µ£ê1µùѵû¢ÞíîÒü«Õêæµ│òµö╣µ¡úÒüºÒü»ÒÇüþÅ¥Õ£¿Òü«ÒÇîµç▓Õ¢╣ÒÇìÒü¿ÒÇîþªüÚî«ÒÇìÒéÆþÁ▒ÕÉêÒüùÒüƒÒÇîµïÿþªüÕêæÒÇìÒüîÕ░ÄÕàÑÒüòÒéîÒéïõ║êÕ«ÜÒüºÒüÖÒÇéµû¢ÞíîÕ¥îÒü»ÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬Òü½Òü»ÒÇü2Õ╣┤õ╗Ñõ©ïÒü«µïÿþªüÕêæÒü¥ÒüƒÒü»30õ©çÕååõ╗Ñõ©ïÒü«þ¢░ÚçæÒüîþºæÒüøÒéëÒéîÒéïÒüôÒü¿Òü½Òü¬ÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
ÞäàÞ┐½þ¢¬Òü¿ÒüØÒü«õ╗ûÒü«þè»þ¢¬Òü«Úûóõ┐é
SNSÒéäÒéñÒâ│Òé┐Òâ╝ÒâìÒââÒâêõ©èÒüºÒü«Þ¬╣Þ¼ùõ©¡ÕéÀÒü½ÒéêÒéïÞäàÞ┐½Þíîþé║Òü»ÒÇüÕìÿÒü¬ÒéïÞäàÞ┐½þ¢¬Òü½Òü¿Òü®Òü¥ÒéëÒüÜÒÇüÕ╝ÀÞªüþ¢¬ÒéäÕ¿üÕèøµÑ¡ÕïÖÕª¿Õ«│þ¢¬Òü¬Òü®ÒÇüÒéêÒéèÚçìÒüäþ¢¬Òü½þÖ║Õ▒òÒüÖÒéïÕá┤ÕÉêÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇéÒü¥ÒüƒÒÇüÕÉìެ뵻ǵÉìþ¢¬Òü¿Òü«Úûóõ┐éÒééÞÇâµà«ÒüîÕ┐àÞªüÒüºÒüÖÒÇé
õ╗Ñõ©ïÒüºÒü»ÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬Òü¿ÚûóÚÇúÒüÖÒéïÕÉäþè»þ¢¬Òü«ÚüòÒüäÒéäþë╣Õ¥┤ÒÇüþ¢░ÕëçÒü«ÚüòÒüäÒü½ÒüñÒüäÒüªÞ®│ÒüùÒüÅÞºúÞ¬¼ÒüùÒüªÒüäÒüìÒü¥ÒüÖÒÇé
ÞäàÞ┐½þ¢¬Òü¿Õ╝ÀÞªüþ¢¬
ÞäàÞ┐½þ¢¬Òü¿Õ╝ÀÞªüþ¢¬Òü»ÒÇüµÀÀÕÉîÒüòÒéîÒéïÒüôÒü¿ÒüîÕñÜÒüäÒü«ÒüºÒÇüÒüØÒü«ÚüòÒüäÒéÆþó║Þ¬ìÒüùÒüªÒüèÒüìÒü¥ÒüùÒéçÒüåÒÇé
´╝æÒÇÇþöƒÕæ¢ÒÇüÞ║½õ¢ôÒÇüÞç¬þö▒ÒÇüÕÉìÞ¬ëÞïÑÒüùÒüÅÒü»Þ▓íþöúÒü½Õ»¥ÒüùÕ«│ÒéÆÕèáÒüêÒéïµù¿ÒéÆÕæèþƒÑÒüùÒüªÞäàÞ┐½ÒüùÒÇüÕÅêÒü»µÜ┤ÞíîÒéÆþö¿ÒüäÒüªÒÇüõ║║Òü½þ¥®ÕïÖÒü«Òü¬ÒüäÒüôÒü¿ÒéÆÞíîÒéÅÒüøÒÇüÕÅêÒü»µ¿®Õê®Òü«Þíîõ¢┐ÒéÆÕª¿Õ«│ÒüùÒüƒÞÇàÒü»ÒÇü3Õ╣┤õ╗Ñõ©ïÒü«µç▓Õ¢╣Òü½ÕçªÒüÖÒéïÒÇé
Õêæµ│òþ¼¼223µØí ´╝êÕ╝ÀÞªü´╝ë
2 ÒÇÇÞª¬µùÅÒü«þöƒÕæ¢ÒÇüÞ║½õ¢ôÒÇüÞç¬þö▒ÒÇüÕÉìÞ¬ëÕÅêÒü»Þ▓íþöúÒü½Õ»¥ÒüùÕ«│ÒéÆÕèáÒüêÒéïµù¿ÒéÆÕæèþƒÑÒüùÒüªÞäàÞ┐½ÒüùÒÇüõ║║Òü½þ¥®ÕïÖÒü«Òü¬ÒüäÒüôÒü¿ÒéÆÞíîÒéÅÒüøÒÇüÕÅêÒü»µ¿®Õê®Òü«Þíîõ¢┐ÒéÆÕª¿Õ«│ÒüùÒüƒÞÇàÒééÒÇüÕëìÚáàÒü¿ÕÉÿÒü¿ÒüÖÒéïÒÇé
3ÒÇÇ Õëì2ÚáàÒü«þ¢¬Òü«µ£¬ÚüéÒü»ÒÇüþ¢░ÒüÖÒéïÒÇé
Õ╝ÀÞªüþ¢¬Òü¿Òü»ÒÇüþø©µëïÒü½Õ»¥ÒüùÒüªÞäàÞ┐½Þíîþé║ÒéÆÒüùÒüƒÒéèµÜ┤ÞíîÒéÆÕèáÒüêÒüƒÒéèÒüÖÒéïÒüôÒü¿Òü½ÒéêÒéèÒÇüÒÇîþ¥®ÕïÖÒü«Òü¬ÒüäÒüôÒü¿ÒÇìÒéÆÞíîÒéÅÒüøÒüƒÒéèÒÇüÒÇ®Õê®Òü«Þíîõ¢┐ÒéÆÕª¿Õ«│ÒüùÒüƒÒÇìÒü¿ÒüìÒü½µêÉþ½ïÒüÖÒéïþè»þ¢¬ÒüºÒüÖÒÇé
ÞäàÞ┐½þ¢¬Òü¿Òü«ÕñºÒüìÒü¬ÚüòÒüäÒü»ÒÇîþ¥®ÕïÖÒü«Òü¬ÒüäÒüôÒü¿ÒéÆÒüòÒüøÒéïÒÇìÒÇ®Õê®ÒéÆÞíîõ¢┐ÒüòÒüøÒü¬ÒüäÒÇìÒü¿ÒüäÒüåþÁɵףÒéÆÒü¿ÒééÒü¬Òüåþé╣ÒüºÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬Òü«Õá┤ÕÉêÒü½Òü»ÒÇüÒüôÒüåÒüùÒüƒþÁɵףÒüîþÖ║þöƒÒüÖÒéïÒüôÒü¿Òü»Òü¬ÒüÅÒÇüÕìÿÒü½ÞäàÒüÖÒüáÒüæÒüºÒÇüõ¢òÒüïÒéÆÒüòÒüøÒéêÒüåÒü¿ÒüÖÒéïÒüôÒü¿ÒééÒüéÒéèÒü¥ÒüøÒéôÒÇé
ÒüôÒéîÒü½Õ»¥ÒüùÒÇüÕ╝ÀÞªüþ¢¬Òü«Õá┤ÕÉêÒÇüõ©èÞ¿ÿÒü«ÒéêÒüåÒü¬þø«þÜäÒéƵîüÒüíÒÇüþø©µëïÒü½þ¥®ÕïÖÒü«Òü¬ÒüäÒüôÒü¿ÒéÆÒüòÒüøÒüƒÒé赿®Õê®Þíîõ¢┐ÒéÆÕª¿Õ«│ÒüùÒüƒÒéèÒüÖÒéïÒüôÒü¿ÒüîÕ┐àÞªüÒüºÒüÖÒÇéÒüùÒüƒÒüîÒüúÒüªÒÇüÕ╝ÀÞªüþ¢¬Òü½Òü»µ£¬Úüéþ¢¬ÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
ÞäàÞ┐½þ¢¬Òü¿Õ╝ÀÞªüµ£¬Úüéþ¢¬
ÒüØÒüôÒüºÒÇüÒéäÒéäÒüôÒüùÒüÅÒü¬ÒéïÒü«ÒüîÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬Òü¿Õ╝ÀÞªüµ£¬Úüéþ¢¬Òü«ÚüòÒüäÒüºÒüÖÒÇéÒÇîÞäàÞ┐½ÒüùÒüƒÒüîÒÇüþø©µëïÒüîþ¥®ÕïÖÒü«Òü¬ÒüäÒüôÒü¿ÒéÆÒüùÒü¬ÒüïÒüúÒüƒÒÇìÒü¿ÒüäÒüåþé╣ÒüºÒü»ÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬ÒééÕ╝ÀÞªüµ£¬Úüéþ¢¬ÒééÕÉîÒüÿÒüáÒüïÒéëÒüºÒüÖÒÇé
Õ╝ÀÞªüµ£¬Úüéþ¢¬Òü«Õá┤ÕÉêÒÇüÞäàÞ┐½Þíîþé║Òü»ÒÇüþø©µëïÒü½þ¥®ÕïÖÒü«Òü¬ÒüäÒüôÒü¿ÒéÆÒüòÒüøÒéïÒüôÒü¿Òü½ÕÉæÒüæÒéëÒéîÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇéõ¥ïÒüêÒü░ÒÇîÕ£ƒõ©ïÕ║ºÒüùÒü¬ÒüäÒü¿µ«║ÒüÖÒü×ÒÇìÒü¬Òü®Òü¿Þ¿ÇÒüúÒüƒÕá┤ÕÉêÒüºÒÇüÒÇîÕ£ƒõ©ïÕ║ºÒéÆÒüùÒéìÒÇìÒü¿ÒüäÒüåÒâíÒââÒé╗Òâ╝Òé©ÒüîÞ¥╝ÒéüÒéëÒéîÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇéÒüØÒüôÒüºÒÇüþø©µëïÒüîÕ£ƒõ©ïÕ║ºÒéÆÒüùÒü¬ÒüïÒüúÒüƒÒéëÒÇüÕ╝ÀÞªüµ£¬Úüéþ¢¬Òü½Òü¬ÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
ÒüôÒéîÒü½Õ»¥ÒüùÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬Òü»ÒÇüÕìÿþ┤öÒü½´¢óµ«║ÒüÖÒü×´¢úÒü¿Þ¿ÇÒüúÒüƒÒüáÒüæÒü«Òé▒Òâ╝Òé╣ÒüºÒüéÒéèÒÇüõ¢òÒüïÒéÆÒüòÒüøÒüƒÒé赿®Õê®Þíîõ¢┐ÒéÆÕª¿Õ«│ÒüùÒéêÒüåÒü¿ÒüùÒüƒÒéèÒüÖÒéïµäÅÕø│Òü»ÒüéÒéèÒü¥ÒüøÒéôÒÇéÒüôÒüôÒüîÒÇüÕ╝ÀÞªüµ£¬Úüéþ¢¬Òü¿ÞäàÞ┐½þ¢¬Òü«ÚüòÒüäÒüºÒüÖÒÇé
ÒâìÒââÒâêõ©èÒü«µèòþ¿┐Òü½ÒéêÒéèÒÇüþø©µëïÒü½Õ»¥ÒüùÒÇîÒÇçÒÇçÒéÆÒüùÒü¬ÒüäÒü¿µ«║ÒüÖÒÇìÒÇîÒÇçÒÇçÒéÆÒüùÒüƒÒéëµö¥þü½ÒüÖÒéïÒÇìÒü¬Òü®Òü¿ÒÇüõ¢òÒüïÒéÆÕ╝ÀÞªüÒüùÒüƒÒé赿®Õê®Þíîõ¢┐ÒéÆÕª¿Õ«│ÒüùÒéêÒüåÒü¿ÒüùÒüƒÒéèÒüÖÒéïÒü¿ÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬ÒüºÒü»Òü¬ÒüÅÕ╝ÀÞªüþ¢¬ÒéäÕ╝ÀÞªüµ£¬Úüéþ¢¬ÒüîµêÉþ½ïÒüùÒü¥ÒüÖÒÇé Õ╝ÀÞªüþ¢¬Òü«Õêæþ¢░Òü»ÒÇüµ£¬Úüéþ¢¬ÒüºÒéé3Õ╣┤õ╗Ñõ©ïÒü«µç▓Õ¢╣ÕêæÒü¿Òü¬ÒüúÒüªÒüèÒéèÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬ÒéêÒéèÚçìÒüäÒü«ÒüºÒÇüµ│¿µäÅÒüøÒü¡Òü░Òü¬ÒéèÒü¥ÒüøÒéôÒÇé
ÞäàÞ┐½þ¢¬Òü¿ÕÉìެ뵻ǵÉìþ¢¬

ÒâìÒââÒâêõ©èÒü«Þ¬╣Þ¼ùõ©¡ÕéÀÒü¿Þ¿ÇÒüêÒü░ÒÇüÕÉìެ뵻ǵÉìþ¢¬ÒéƵÇØÒüäµÁ«ÒüïÒü╣Òéïõ║║ÒüîÕñÜÒüäÒüºÒüùÒéçÒüåÒÇéÒüôÒüôÒüºÒü»ÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬Òü¿ÕÉìެ뵻ǵÉìþ¢¬Òü«Úûóõ┐éÒéÆÞºúÞ¬¼ÒüùÒü¥ÒüÖÒÇé
ÞäàÞ┐½þ¢¬Òü»ÒÇüþø©µëïµ£¼õ║║ÒéäÒüØÒü«Þª¬µùÅÒü«ÒÇîÕÉìÞ¬ëÒéƵ»ÇµÉìÒüÖÒéïÒü×ÒÇìÒü¿ÒüùÒüªÞäàÒüùÒüƒÕá┤ÕÉêÒü½ÒééµêÉþ½ïÒüùÒü¥ÒüÖÒÇéÒüØÒüôÒüºÒÇüÒüØÒü«ÒéêÒüåÒü¬µèòþ¿┐ÒéÆÒüùÒüƒÒü¿ÒüìÒü«ÕÉìެ뵻ǵÉìþ¢¬Òü¿Òü«Úûóõ┐éÒüîÕòÅÚíîÒü½Òü¬ÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
ÞäàÞ┐½þ¢¬Òü»ÒÇüÒÇîÕÉìÞ¬ëÒéƵ»ÇµÉìÒüÖÒéïÒü×ÒÇìÒü¿ÒüùÒüªÞäàÒüÖÞíîþé║ÒüºÒüÖÒÇéÒüôÒéîÒü½Õ»¥ÒüùÒÇüÕÉìެ뵻ǵÉìþ¢¬Òü»ÒÇüÒÇîÕ«ƒÚÜøÒü½ÕÉìÞ¬ëÒéƵ»ÇµÉìÒüùÒüƒÒü¿ÒüìÒÇìÒü½µêÉþ½ïÒüÖÒéïþè»þ¢¬ÒüºÒüÖÒÇéÒüØÒüôÒüºÒÇüµÖéÚûôþÜäÒü½Òü»ÞäàÞ┐½þ¢¬Òü«µû╣ÒüîÕàêÒü½Òü¬ÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
þø©µëïÒü½Õ»¥ÒüùÒÇîÕÉìÞ¬ëÒéƵ»ÇµÉìÒüÖÒéïÒü×ÒÇìÒü¿Þ¿ÇÒüúÒüªÞäàÒüùÒüƒµÖéþé╣ÒüºÞäàÞ┐½þ¢¬ÒüîµêÉþ½ïÒüùÒÇüÒüØÒü«Õ¥îÒü½ÒÇüÕ«ƒÚÜøÒü½ÕÉìÞ¬ëÒéƵ»ÇµÉìÒüÖÒéïÞíîþé║ÒéÆÒüùÒüƒÒéëÒÇüÒüØÒü«µÖéþé╣ÒüºÕÉìެ뵻ǵÉìþ¢¬ÒüîµêÉþ½ïÒüÖÒéïÒüôÒü¿Òü½Òü¬ÒéèÒü¥ÒüÖÒÇéÒüôÒü«Õá┤ÕÉêÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬Òü¿ÕÉìެ뵻ǵÉìþ¢¬Òü»ÒÇîõ¢ÁÕÉêþ¢¬ÒÇìÒü«Úûóõ┐éÒü½Òü¬ÒéïÒü«ÒüºÒÇüÕêæþ¢░ÒüîÕèáÚçìÒüòÒéîÒü¥ÒüÖÒÇé
ÕàÀõ¢ôþÜäÒü½Òü»ÒÇüµç▓Õ¢╣ÕêæÒüîÒéêÒéèÚòÀµ£ƒÒüºÒüéÒéïÕÉìެ뵻ǵÉìþ¢¬Òü«3Õ╣┤ÒéÆÕƒ║µ║ûÒü¿ÒüùÒÇüÒüØÒü«1.5ÕÇìÒü¿Òü¬ÒéïÒü«ÒüºÒÇü4.5Õ╣┤õ╗Ñõ©ïÒü¿Òü¬ÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
ÕÉìެ뵻ǵÉìÒü¿Òü»õ¢òÒüïÒéÆþƒÑÒéèÒüƒÒüäµû╣Òü»õ╗Ñõ©ïÒü«Þ¿ÿõ║ïÒéÆÕÅéÞÇâÒü½ÒüùÒüªÒüÅÒüáÒüòÒüäÒÇé
ÕÅéÞÇâ´╝ÜÕÉìެ뵻ǵÉìÒüºÞ¿┤ÒüêÒéïµØíõ╗ÂÒü¿Òü»´╝ƒÞ¬ìÒéüÒéëÒéîÒéïÞªüõ╗ÂÒü¿µà░޼صûÖÒü«þø©Õá┤ÒéÆÞºúÞ¬¼
ÞäàÞ┐½þ¢¬Òü¿Õ¿üÕèøµÑ¡ÕïÖÕª¿Õ«│þ¢¬
ÞäàÞ┐½þ¢¬Òü¿Õ¿üÕèøµÑ¡ÕïÖÕª¿Õ«│þ¢¬Òü¿Òü«Úûóõ┐éÒü½ÒüñÒüäÒüªÒééÒÇüÞºúÞ¬¼ÒüùÒüªÒüèÒüìÒü¥ÒüùÒéçÒüåÒÇé
Õ¿üÕèøµÑ¡ÕïÖÕª¿Õ«│þ¢¬Òü»ÒÇüÒÇîÕ¿üÕèøÒÇìÒéäÒÇîÕ¿üÕïóÒÇìÒéÆþñ║ÒüùÒüª Õ»¥Þ▒íÞÇàÒü«µÑ¡ÕïÖÒéÆÕª¿Õ«│ÒüùÒüƒÕá┤ÕÉêÒü½µêÉþ½ïÒüÖÒéïþè»þ¢¬ÒüºÒüÖÒÇéõ¥ïÒüêÒü░ÒÇü´╝ÆÒüíÒéâÒéôÒü¡Òéïþ¡ëÒü«µÄ▓þñ║µØ┐Òü½ÒÇîÒÇçÒÇçÒü«Òé│Òâ│ÒéÁÒâ╝Òâêõ╝ÜÕá┤Òü½þêåÕ╝¥ÒéÆõ╗òµÄøÒüæÒéïÒÇìÒü¬Òü®Òü¿µèòþ¿┐ÒüÖÒéïÒü¿ÒÇüÕ¿üÕèøµÑ¡ÕïÖÕª¿Õ«│þ¢¬ÒüîµêÉþ½ïÒüÖÒéïÕÅ»Þ⢵ǺÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇéÒüØÒüùÒüªÒüôÒü«Õá┤ÕÉêÒÇüÕ»¥Þ▒íÞÇàÒü½Õ»¥ÒüÖÒéïÞäàÞ┐½þ¢¬ÒééÕÉîµÖéÒü½µêÉþ½ïÒüùÒü¥ÒüÖÒÇé
ÞäàÞ┐½þ¢¬Òü¿Õ¿üÕèøµÑ¡ÕïÖÕª¿Õ«│þ¢¬ÒüîµêÉþ½ïÒüÖÒéïÒü¿ÒüìÒü½Òü»ÒÇüÚÇÜÕ©©Òü»ÒÇü1ÒüñÒü«µèòþ¿┐Òü½ÒéêÒüúÒüª2ÒüñÒü«þ¢¬ÒüîµêÉþ½ïÒüùÒü¥ÒüÖÒÇéÒüôÒüåÒüùÒüƒÕá┤ÕÉêÒÇü2ÒüñÒü«þ¢¬Òü»ÒÇîÞª│Õ┐ÁþÜäþ½ÂÕÉêÒÇìÒü«Úûóõ┐éÒü¿Òü¬ÒéèÒÇüÚçìÒüäµû╣Òü«þ¢¬Òü«Õêæþ¢░Òü½ÒéêÒüúÒüªÞúüÒüïÒéîÒéïÒüôÒü¿Òü½Òü¬ÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
Õ¿üÕèøµÑ¡ÕïÖÕª¿Õ«│þ¢¬Òü«Õêæþ¢░Òü»ÒÇü3Õ╣┤õ╗Ñõ©ïÒü«µç▓Õ¢╣Òü¥ÒüƒÒü»50õ©çÕååõ╗Ñõ©ïÒü«þ¢░ÚçæÕêæÒüºÒüéÒéèÒÇüÞäàÞ┐½þ¢¬Òü«Õêæþ¢░ÒéêÒéèÚçìÒüäÒü«ÒüºÒÇüÞäàÞ┐½Þíîþé║Òü½ÒéêÒüúÒüªþø©µëïÒü«µÑ¡ÕïÖÒéÆÕª¿Õ«│ÒüùÒüƒÕá┤ÕÉêÒü½Òü»ÒÇüÕ¿üÕèøµÑ¡ÕïÖÕª¿Õ«│Òü«þ¢¬Òü½ÒéêÒüúÒüªÞúüÒüïÒéîÒéïÒüôÒü¿Òü½Òü¬ÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
ÞäàÞ┐½Þíîþé║ÒüºÞ║½Òü«Õì▒ÚÖ║ÒéƵäƒÒüÿÒüƒÕá┤ÕÉêÒü«Õ»¥Õ窵│ò
ÒéñÒâ│Òé┐Òâ╝ÒâìÒââÒâêõ©èÒüºÞäàÞ┐½Þó½Õ«│Òü½Úü¡ÒüúÒüƒÕá┤ÕÉêÒÇüÚü®ÕêçÒü¬Õ»¥Õ┐£ÒéÆÕÅûÒéïÒüôÒü¿ÒüîÚçìÞªüÒüºÒüÖÒÇéÕàÀõ¢ôþÜäÒü¬Õ»¥Õ┐£Òü»ÒÇüÞ¡ªÕ»ƒÒü©Òü«þø©Þ½çÒü¬Òü®Òü«Õêæõ║ïþÜäÕ»¥Õ┐£Òü¿ÒÇüµèòþ¿┐Òü«ÕëèÚÖñÞ½ïµ▒éÒü¬Òü®Òü«µ░æõ║ïþÜäÕ»¥Õ┐£Òü½ÕñºÕêÑÒüòÒéîÒü¥ÒüÖÒÇéÒüØÒéîÒü×ÒéîÒü«Õ»¥Õ┐£Òü½ÒüñÒüäÒüªÒÇüÕàÀõ¢ôþÜäÒü¬µëïÚáåÒü¿µ│¿µäÅþé╣ÒéÆÞ¬¼µÿÄÒüùÒü¥ÒüÖÒÇé
Õêæõ║ï´╝êÞ¡ªÕ»ƒÒü©Òü«Õ»¥Õ┐£´╝ë
Òü¥ÒüÜÒÇüÞ║½Òü«Õ«ëÕà¿þó║õ┐ØÒü¿Þ¡ªÕ»ƒÒü©Òü«þø©Þ½çÒüîµ£ÇÕä¬Õàêõ║ïÚáàÒüºÒüÖÒÇéþöƒÕæ¢Òâ╗Þ║½õ¢ôÒü©Òü«Õì▒Õ«│ÒéÆÕæèþƒÑÒüòÒéîÒéïÒü¬Òü®µÀ▒Õê╗Òü¬ÞäàÞ┐½ÒéÆÕÅùÒüæÒüƒÕá┤ÕÉêÒü½Òü»ÒÇüþø┤ÒüíÒü½Þ¡ªÕ»ƒÒü½þø©Þ½çÒüÖÒéïÒüôÒü¿ÒéÆÒüèÕïºÒéüÒüùÒü¥ÒüÖÒÇé
ÒüØÒü«ÚÜøÒÇüÞäàÞ┐½ÒüîÞíîÒéÅÒéîÒüªÒüäÒéïÒâÜÒâ╝Òé©Òü«þö╗ÚØóÒé¡ÒâúÒâùÒâüÒâúÒü¿ÒâùÒâ¬Òâ│ÒâêÒéóÒéªÒâêÒü½ÒéêÒéïÞ¿╝µïáõ┐ØÕà¿ÒéÆÞíîÒüäÒÇüµèòþ¿┐Òü«URLÒÇüµùѵÖéÒÇüµèòþ¿┐ÞÇàµâàÕá▒´╝êÞí¿þñ║ÒüòÒéîÒüªÒüäÒéïÕá┤ÕÉê´╝ëÒéÆÞ¿ÿÚî▓ÒüùÒüªÒüèÒüïÒü¬ÒüæÒéîÒü░Òü¬ÒéèÒü¥ÒüøÒéôÒÇéÞ¡ªÕ»ƒÒü½Òü»ÞäàÞ┐½ÒéÆÕÅùÒüæÒüƒþÁîþÀ»Òéäþèµ│üÒéÆÕàÀõ¢ôþÜäÒü½Þ¬¼µÿÄÒüùÒü¥ÒüùÒéçÒüåÒÇéÞ¡ªÕ»ƒÒüîÕïòÒüŵíêõ╗ÂÒüºÒüéÒéîÒü░µì£µƒ╗ÒüîÚûïÕºïÒüòÒéîÒÇüµèòþ¿┐ÞÇàÒü«þë╣Õ«ÜÒééÞ¡ªÕ»ƒÒüîÞíîÒüåÒüôÒü¿Òü½Òü¬ÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
Þ¡ªÕ»ƒÒüîÕïòÒüïÒü¬ÒüäÕá┤ÕÉêÒüºÒééÒÇüÕêæõ║ïÕæèÞ¿┤Òü»ÕÅ»Þâ¢ÒüºÒüÖÒÇéÒüùÒüïÒüùÒÇüÒüØÒü«Õá┤ÕÉêÒü»µèòþ¿┐ÞÇàþë╣Õ«ÜÒü«ÒüƒÒéüÒü«þÖ║õ┐íÞÇàµâàÕá▒Úûïþñ║Þ½ïµ▒éÒéÆÞç¬ÒéëÞíîÒéÅÒü¬ÒüæÒéîÒü░Òü¬ÒéèÒü¥ÒüøÒéôÒÇé
þÖ║õ┐íÞÇàµâàÕá▒Úûïþñ║Þ½ïµ▒éÒü½ÒüñÒüäÒüªÒü»ÒÇüõ╗Ñõ©ïÒü«Þ¿ÿõ║ïÒéÆÕÅéÞÇâÒü½ÒüùÒüªÒüÅÒüáÒüòÒüäÒÇé
ÚûóÚÇúÞ¿ÿõ║ï´╝ÜþÖ║õ┐íÞÇàµâàÕá▒Úûïþñ║Þ½ïµ▒éÒü¿Òü»´╝ƒµö╣µ¡úÒü½õ╝┤Òüåµû░ÒüƒÒü¬µëïþÂÜÒüìÒü«ÕëÁÞ¿¡Òü¿ÒüØÒü«µÁüÒéîÒéÆÕ╝üÞ¡ÀÕú½ÒüîÞºúÞ¬¼
µ░æõ║ï´╝êÕëèÚÖñÒÇüÚûïþñ║Þ½ïµ▒éÒÇüµÉìÕ«│Þ│áÕäƒÞ½ïµ▒é´╝ë
µ░æõ║ïþÜäÕ»¥Õ┐£Òü¿ÒüùÒüªÒü»ÒÇüµèòþ¿┐Òü«ÕëèÚÖñÞ½ïµ▒éÒü¿µÉìÕ«│Þ│áÕäƒÞ½ïµ▒éÒüîÕÅ»Þâ¢ÒüºÒüÖÒÇéÕëèÚÖñÞ½ïµ▒éÒü½ÒüñÒüäÒüªÒü»ÒÇüÒü¥ÒüÜÒéÁÒéñÒâêþ«íþÉåÞÇàÒü©Òü«ÕëèÚÖñþö│Þ½ïÒéÆÞíîÒüäÒÇüÒüØÒéîÒüºÒééÕëèÚÖñÒüòÒéîÒü¬ÒüäÕá┤ÕÉêÒü»ÞúüÕêñµëÇÒü©Òü«õ╗«ÕçªÕêåþö│Þ½ïÒéƵñ£Þ¿ÄÒüùÒü¥ÒüùÒéçÒüåÒÇé
µÉìÕ«│Þ│áÕäƒÞ½ïµ▒éÒéÆÞíîÒüåÕá┤ÕÉêÒü»ÒÇüþÖ║õ┐íÞÇàµâàÕá▒Úûïþñ║Þ½ïµ▒éÒü½ÒéêÒéèµèòþ¿┐ÞÇàÒéÆþë╣Õ«ÜÒüùÒÇüÒüØÒü«Õ¥îµÉìÕ«│Þ│áÕäƒÞ½ïµ▒éÞ¿┤Þ¿ƒÒéƵÅÉÞÁÀÒüùÒü¥ÒüÖÒÇé
ÒüôÒéîÒéëÒü«µ│òþÜäÕ»¥Õ┐£Òü»Õ░éÚûÇþÜäÒü¬þƒÑÞ¡ÿÒéÆÞªüÒüÖÒéïµëïþÂÜÒüìÒü«ÒüƒÒéüÒÇüþÁîÚ¿ôÞ▒èÕ»îÒü¬Õ╝üÞ¡ÀÕú½Òü©Òü«þø©Þ½çÒüîÒüèÒüÖÒüÖÒéüÒüºÒüÖÒÇéµÀ▒Õê╗Òü¬ÞäàÞ┐½Þó½Õ«│Òü«Õá┤ÕÉêÒü½Òü»ÒÇüÒü¥ÒüÜÒü»Þ¡ªÕ»ƒÒü½þø©Þ½çÒüùÒÇüÕ╝üÞ¡ÀÕú½Òü¿Òééþø©Þ½çÒüùÒü¬ÒüîÒéëÒÇüÕêæõ║ïÒâ╗µ░æõ║ïõ©íÚØóÒüïÒéëÒü«Úü®ÕêçÒü¬Õ»¥Õ┐£ÒéƵñ£Þ¿ÄÒüÖÒéïÒüôÒü¿ÒüîÚçìÞªüÒüºÒüÖÒÇé
ÚûóÚÇúÞ¿ÿõ║ï´╝ÜÚüĵ┐ÇÒü¬ÒâìÒââÒâêµèòþ¿┐Òü»ÞäàÞ┐½Òü½Òü¬ÒéïÒüôÒü¿ÒééÒÇÇÒÇ║ÒüÖÒÇìÒéäÒÇ╗Òü¡ÒÇìÒü»ÞäàÞ┐½Òü½Õ¢ôÒüƒÒéïÒü«Òüï
Òü¥Òü¿Òéü´╝ÜÞäàÞ┐½Òü»Õ╝üÞ¡ÀÕú½Òü½þø©Þ½çÒüùÒüªÕêæõ║ïÒâ╗µ░æõ║ïõ©íÚØóÒüºÒü«Õ»¥Õ┐£ÒéƵñ£Þ¿Ä
ÒéñÒâ│Òé┐Òâ╝ÒâìÒââÒâêõ©èÒü«Þ¬╣Þ¼ùõ©¡ÕéÀÒü½ÒéêÒéïÞäàÞ┐½Òü»ÒÇüÕî┐ÕÉìµÇºÒéÆÕê®þö¿ÒüùÒüƒµÀ▒Õê╗Òü¬ÕòÅÚíîÒüºÒüÖÒÇéÒâìÒââÒâêõ©èÒüºÒü«ÞäàÞ┐½Òü»µèòþ¿┐ÞÇàÒü«Õ▒׵ǺÒü½Úûóõ┐éÒü¬ÒüÅÒÇüÕ«óÞª│þÜäÒü½õ║║ÒéÆþòŵÇûÒüòÒüøÒéïÕåàÕ«╣ÒüºÒüéÒéîÒü░ÞäàÞ┐½þ¢¬ÒüîµêÉþ½ïÒüùÒÇüÒüòÒéëÒü½Õ╝ÀÞªüþ¢¬ÒéäÕÉìެ뵻ǵÉìþ¢¬Òü¬Òü®Òü«ÒéêÒéèÚçìÒüäÕêæþ¢░Òü«Õ»¥Þ▒íÒü½Òü¬ÒéèÒüêÒü¥ÒüÖÒÇé
Þó½Õ«│Òü½Úü¡ÒüúÒüƒÕá┤ÕÉêÒü»ÒÇüÚü®ÕêçÒü¬µû╣µ│òÒüºÞ¿╝µïáõ┐ØÕà¿ÒéÆÞíîÒüäÒÇüÞ¡ªÕ»ƒÒü©Òü«þø©Þ½çÒéäµèòþ¿┐ÕëèÚÖñÞ½ïµ▒éÒü¬Òü®ÒÇüÕêæõ║ïÒâ╗µ░æõ║ïõ©íÚØóÒüïÒéëÕ»¥Õ┐£ÒüùÒü¬ÒüæÒéîÒü░Òü¬ÒéèÒü¥ÒüøÒéôÒÇéµÀ▒Õê╗Òü¬Þó½Õ«│Òü«Õá┤ÕÉêÒü»ÒÇüÒüÖÒüÉÒü½Þ¡ªÕ»ƒÒü½þø©Þ½çÒüùÒÇüÕ╝üÞ¡ÀÕú½Òü½þø©Þ½çÒüùÒü¬ÒüîÒéëÞ┐àÚǃÒü½Úü®ÕêçÒü¬µ│òþÜäÕ»¥Õ┐£ÒéÆÕÅûÒéïÒüôÒü¿ÒüîÚçìÞªüÒüºÒüÖÒÇé
Þ¬╣Þ¼ùõ©¡ÕéÀÒü½ÒüñÒüäÒüªÒü»õ╗Ñõ©ïÒü«Þ¿ÿõ║ïÒééÕÅéÞÇâÒü½ÒüùÒüªÒüÅÒüáÒüòÒüäÒÇé
ÚûóÚÇúÞ¿ÿõ║ï´╝ÜÒâìÒââÒâêÒü«Þ¬╣Þ¼ùõ©¡ÕéÀÒüºÞó½Õ«│Õ▒èÒéÆÕç║ÒüùÒüªÒééÞ¡ªÕ»ƒÒü»ÕïòÒüïÒü¬Òüä´╝ƒÕ»¥Õ窵│òÒéÆÞºúÞ¬¼
Õ¢ôõ║ïÕïÖµëÇÒü½ÒéêÒéïÕ»¥þ¡ûÒü«ÒüöµíêÕåà
ÒâóÒâÄÒâ¬Òé╣µ│òÕ¥ïõ║ïÕïÖµëÇÒü»ÒÇüITÒÇüþë╣Òü½ÒéñÒâ│Òé┐Òâ╝ÒâìÒââÒâêÒü¿µ│òÕ¥ïÒü«õ©íÚØóÒüºÞ▒èÕ»îÒü¬þÁîÚ¿ôÒéƵ£ëÒüÖÒéïµ│òÕ¥ïõ║ïÕïÖµëÇÒüºÒüÖÒÇéÞ┐æÕ╣┤ÒÇüÒâìÒââÒâêõ©èÒü½µïíµòúÒüòÒéîÒüƒÚó¿Þ®òÞó½Õ«│ÒéäÞ¬╣Þ¼ùõ©¡ÕéÀÒü½ÚûóÒüÖÒéïµâàÕá▒Òü»ÒÇîÒâçÒé©Òé┐Òâ½Òé┐ÒâêÒéÑÒâ╝ÒÇìÒü¿ÒüùÒüªµÀ▒Õê╗Òü¬Þó½Õ«│ÒéÆÒééÒüƒÒéëÒüùÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇéÕ¢ôõ║ïÕïÖµëÇÒüºÒü»ÒÇîÒâçÒé©Òé┐Òâ½Òé┐ÒâêÒéÑÒâ╝ÒÇìÕ»¥þ¡ûÒéÆÞíîÒüåÒé¢Òâ¬ÒâÑÒâ╝ÒéÀÒâºÒâ│µÅÉõ¥øÒéÆÞíîÒüúÒüªÒüèÒéèÒü¥ÒüÖÒÇéõ©ïÞ¿ÿÞ¿ÿõ║ïÒü½ÒüªÞ®│þ┤░ÒéÆÞ¿ÿÞ╝ëÒüùÒüªÒüèÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
ÒâóÒâÄÒâ¬Òé╣µ│òÕ¥ïõ║ïÕïÖµëÇÒü«ÕÅûµë▒ÕêåÚçÄ´╝ÜÒâçÒé©Òé┐Òâ½Òé┐ÒâêÒéÑÒâ╝