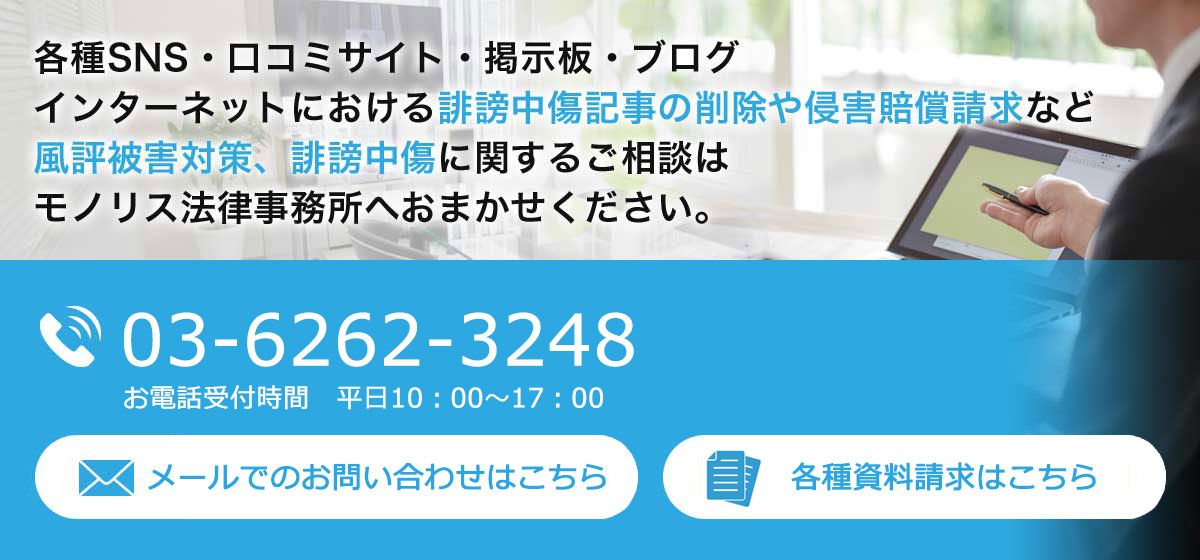スラップ訴訟はどのような場合に違法となるのか?実際の判例をもとに解説

自分を批判してくる相手の言論を封じ込めることを目的として訴訟が用いられることを「スラップ訴訟」と呼びます。このような訴訟は一見正当なものに見えますが、相手に多大な負担を強いる不当なもので違法となることがあるため注意が必要です。
一方で、憲法では裁判を受ける権利が定められていることから、訴訟提起が違法行為になるかどうかの線引きは非常に難しい判断といえます。
ここでは、裁判所がスラップ訴訟であると実質的に認めた裁判例を紹介しつつ、スラップ訴訟につき、解説します。
この記事の目次
スラップ訴訟とは
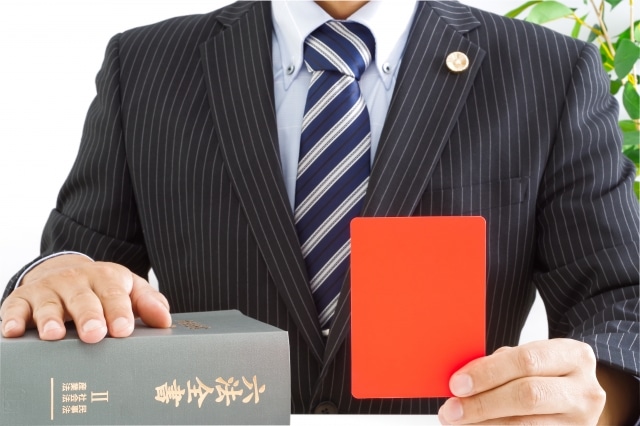
スラップ訴訟とは、米国で生まれた概念で、「Strategic Lawsuit Against Public Participation」の頭文字「SLAPP(スラップ)」をとって名付けられました。
直訳すると「市民参加を妨害するための戦略的民事訴訟」となりますが、一般的には、「自由な言論を封じる脅し目的の訴訟」とされています。
米国では複数の州がスラップ訴訟を防ぐ法律を制定しています。
訴えを提起した原告が正当性を立証できなければ訴訟が打ち切られるほか、州政府が被告を支援する制度もあり多様な支援策が見られます。
一方、日本では状況が異なります。
憲法で裁判を受ける権利が保障されているため、裁判所は起こされた訴訟を進めるのが原則です。
また、正当な訴えとスラップ訴訟を区別するのは難しいという側面もあります。
スラップ訴訟の問題点

スラップ訴訟の問題点は「威圧効果」や「消耗効果」、「見せしめ効果」の3つが挙げられます。
威圧効果とは、スラップ訴訟で法外な損害賠償を請求することで、スラップ訴訟を提起された者を精神的に追い詰め、これ以上の言動や運動を抑止させることです。
事例として、問題を告発され、マスコミに取り上げられた企業が営業妨害や名誉毀損を理由に3,000万円の損害賠償を請求する訴訟を提起して告発側を威圧することで、これ以上の活動を抑止する一連の流れは、威圧効果によるものといえます。
消耗効果とは、スラップ訴訟を提起することで、被告とされた者の時間と費用を消費させ、肉体と精神の疲労により消耗させることです。被告は仮に請求を退けたとしても、弁護士費用などの多大な不利益を被ります。
数千万円の損害賠償請求を提起され、仮に裁判で勝利し損害賠償請求が棄却された場合でも、着手金や報酬金を含む弁護士費用が発生するため、消耗効果が働きます。
見せしめ効果とは、スラップ訴訟を提起し、それが報道されて被告を見せしめとすることで、他の者が自分に類が及ぶことを恐れ、関わることを避けるように仕向けることです。
企業の問題点の告発者が、スラップ訴訟で数千万の損害賠償請求をされた際、企業に対し同様の意見を持つ者も自分に類が及ぶことを懸念し、関わり合いを避けることがあります。これは、スラップ訴訟の見せしめ効果を意図しており、告発者とその周囲の言動抑制に働きます。
訴えの提起が違法な行為となる場合

「スラップ訴訟」という言葉がまだ知られていない1980年代に、「違法な訴え」についての判例がありました。
ここでは訴訟の詳細は省きますが、訴訟提起に先立ち、事実の確認をすることが、通常人の採るべき常識に即した措置であるか否かについて、最高裁判所は「紛争の終局的解決を裁判所に求めうることは、法治国家の根幹にかかわる重要な事柄であるから、裁判を受ける権利は最大限尊重されなければならない」とし、「提訴者が敗訴の確定判決を受けたことのみによつて、直ちに当該訴えの提起をもつて違法ということはできないというべき」と明示しました(最高裁判所 昭和63年1月26日判決)。
裁判を受ける権利は尊重されなくてはならない大切な権利です。
しかし、訴えを提起された者にとっては、応訴を強いられ、弁護士費用を支払わなければならないなど、経済的、精神的負担を余儀なくされるのは事実です。
よく調べもせずに裁判を提起されるのは迷惑な話ですが、これにつき最高裁判所は、訴えの提起が違法な行為となる場合を判示しました。
訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である。
最高裁判所 昭和63年1月26日判決
実質的にスラップ訴訟とされた事案

大手化粧品会社の会長が政治家に資金を貸し付けたことをブログで批判した弁護士が化粧品会社と会長から、名誉毀損の裁判を起こされました。その後、この弁護士が原告となり名誉毀損の裁判は「スラップ訴訟」であるとし、精神的苦痛による損害賠償を求めた事例があります。
訴訟の発端
2014年3月27日発売の雑誌「週刊新潮」に、ある化粧品会社会長の独占手記が掲載されました。
手記の内容は下記のとおりです。
会長は、健康食品市場の停滞の主要な原因が厚労省による監視の強化にあると指摘し、規制緩和を求めるA議員らを支援していました。2010年7月と2012年3月の2度にわたってA議員から選挙資金の融資依頼があり、会長は合計8億円を貸し付けました。その後、会長はA議員と決別しましたが、A議員への貸付の意義についてもう一度彼自身に、そして世に問いたいという内容の手記でした。
この弁護士は、同年3月31日、4月2日及び同月8日にブログ記事を掲載し、化粧品会社会長を批判しました。
そのブログ記事には、この政治家への融資は、規制緩和により自社の利益を追求するために政治を歪めようとしたものであると記されていました。また、A議員が自身の意に沿った行動をしないことから化粧品会社会長が本件手記を雑誌に掲載してA議員を切り捨てたということを指摘するものでした。
会長及び化粧品会社は、これらのブログ記事により名誉が毀損されたとして、弁護士に対して合計6,000万円の損害賠償等を求め、同年4月16日に訴訟を提起しました。結果的には、地裁、高裁ともに化粧品会社会長らの請求を棄却、最高裁も上告不受理の決定をし、2016年10月に判決が確定しました。
2017年5月、今度はこの弁護士が原告となって化粧品会社会長らに対し、前件訴訟がいわゆるスラップ訴訟であり、不当提訴であると主張して、600万円の損害賠償を請求する訴訟を提起しました。
以下、弁護士を原告(控訴審では被控訴人)、化粧品会社会長らを被告(控訴審では控訴人)として説明していきます。
原告側の主張
原告となった弁護士が、化粧品会社会長らが提起した訴訟をスラップ訴訟だと主張したのは、以下を根拠にしています。
1.会長らが問題にしたブログ記事は、いずれも原告である弁護士の意見を表明した論評であるが、意見表明による名誉毀損については、いわゆる公正な論評の法理により、違法性を欠くものとされることは確立した判例であること。
2.弁護士による論評は、いずれも、規制の厳しい健康食品を製造・販売する大企業の代表者が政治家に対して不明朗で多額な貸付をしたことについての違法性や、政治資金規正法の厳格化の必要性といった、いわゆる「政治とカネ」の問題に関係し、民主主義の根幹に関わる事項であり、公共性が高く、公益目的であることは明らかであったこと。
3.論評の前提となった事実は、会長が週刊誌の手記で告白した事実が主であることは一般の読者にとって容易に認識し得たし、それ以外の事実も公刊された新聞紙に掲載された記事や会社において過去にあった事実、または公知の事実であったから、真実であることは検討するまでもなかったこと。
4.ブログの掲載から被告らが訴訟提起をするまでに、極めて短い期間しか経過しておらず、その間に勝訴の見込みについて十分な検討をした形跡が見当たらないこと。
5.会長らは、本件訴訟を提起した際に、これとほぼ同時期に、被告らに対する批判的言論をした者を相手に、9件の名誉毀損訴訟を提起していたこと。
以上の理由から、会長らは名誉毀損が認められないのを十分に認識していたのに、言論封殺のために裁判を提起したと主張しました。
関連記事:名誉毀損の成立と公益性
地裁の判断:「違法な訴え」と認定
1審である東京地方裁判所は、上述の最高裁判所昭和63年1月26日判例を引用しつつ被告らによる訴訟提起の違法性の有無を検討しました。
裁判所によれば、被告らが提起した訴訟において権利侵害を主張した弁護士のブログ記事について「その前提とする事実の重要な部分が真実であると認められ、公共の利害に関するものであり、その目的が専ら公益を図ることにあって、その前提事実と意見ないし論評との間には論理的関連性も認められ、しかも、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものということはできないから、違法性を欠くと認定判断された」と評価しました。そのうえで、
請求が認容される見込みがないことを通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したものとして、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものということができ、原告に対する違法行為と認められる。
以上の検討を総合すると、被告らによる前件訴訟の提起等は、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものというべきであり、違法な訴え提起であったと認められる。
東京地方裁判所令和元年10月4日判決
として、慰謝料100万円、弁護士費用10万円、合計110万円の支払いを被告らに命じました。「スラップ訴訟」という言葉は判決文中では見られませんが、最高裁判所昭和63年1月26日判例の「違法な訴え」に当たるとする判断です。会長ら被告はこれを不服として、控訴しました。
控訴審の判断:「違法行為」であると認定
控訴審において化粧品会社会長ら控訴人は、名誉毀損訴訟において事実の摘示か意見ないし論評かにより違法性阻却事由が異なることなどについて知っている通常人など存在せず、通常人が容易に認識し得るという第1審の判断は健全な社会常識に明らかに反すると主張しました。
ですが、裁判所は、ブログ記事は、その記載内容から本件手記ないし新聞記事に記載されている事実を前提としている点に着目しました。さらに、一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すれば、被控訴人である弁護士が考える政治と金銭との健全な関係の観点から、会長らの内心を推察しつつ批判を加えようとするものと読めるとしました。よって、弁護士の意見ないし論評に当たるものであると通常人も、そして、会長らも容易に認識することができるものであるとしました。
また、会長らは憲法上の裁判を受ける権利(憲法第32条)についてもこのように言及しました。「被控訴人(弁護士)のブログ記事の各記述は、強い口調で控訴人(会長)らを断定的に罵倒して社会的評価を低下させるものであり、およそ名誉毀損になる余地などないと容易に認識することなどあり得ず、裁判所に救済を求めることが不法行為を構成することとなれば、裁判を受ける権利(憲法第32条)を不当に侵害するものとなる」。
そして、いわゆる「政治とカネ」の問題に関して、企業ないしその経営者による政治家に対する多額の資金提供について、企業に対する利益誘導の原因となりうるものとして厳しく批判する意見が広く存在することに照らしても、公正な意見・論評と認められることからすれば、名誉毀損に当たらないことは会長らとしても十分認識することができたというべきであるとしました。
さらに、以下の点も、被控訴人である弁護士に対する違法行為として挙げました。
- 請求額が、6,000万円という通常人にとっては意見の表明を萎縮させかねない高額なものである点
- 言論という方法で対抗せず、直ちに訴訟による高額の損害賠償請求という手段で臨んでいる点
- ほかにも近接した時期に9件の損害賠償請求訴訟を提起し判決に至ったものはいずれも本件貸付に関する名誉毀損部分に関しては、会長らの損害賠償請求が認められずに確定している点
以上の点から、
| 前件訴訟の提起等は、控訴人らが自己に対する批判の言論の萎縮の効果等を意図して行ったものと推認するのが合理的であり、不法行為と捉えたとしても、控訴人らの裁判を受ける権利を不当に侵害することにはならないと解すべきである。したがって、控訴人ら(会長ら)の前件訴訟の提起等は、請求が認容される見込みがないことを通常人であれば容易に知り得たといえるのに、あえて訴えを提起するなどしたものとして、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものということがで、被控訴人(弁護士)に対する違法行為と認められる。 東京高等裁判所令和2年3月18日判決、カッコ内は筆者が補足 |
として、被控訴人(弁護士)の損害は、前件訴訟の弁護士費用のうち50万円及び慰謝料100万円の合計150万円と、その請求のために本件訴訟を提起せざるを得なかった弁護士費用として、その1割に相当する15万円を認め、合計165万円の支払いを会長らに命じました。
上記の判決では、「スラップ訴訟」という言葉は使用していませんが、「自己に対する批判の言論の萎縮の効果等を意図して行ったもの」、つまりスラップ訴訟を、「請求が認容される見込みがないことを通常人であれば容易に知り得たといえるのに、あえて訴えを提起」した場合とされる「違法な訴え」に含めたものと言えるでしょう。
なお、被控訴人(弁護士)は、控訴人(会長)らは837万円(前件訴訟の請求額を基準とした各審級ごとの着手金と印紙代の合計)及び原判決認容額110万円の出捐を覚悟すれば、前件訴訟と同様のスラップ訴訟の提起を繰り返すことが可能となり、予防的効果が期待できないと主張したのですが、裁判所は損害賠償の金額については、填補賠償を基準とすべきであり、予防的効果を期待して懲罰的な損害賠償を認めることは相当でないとしています。
関連記事:名誉毀損の慰謝料が加害行為の悪質性で高額になるケースとは
スラップ訴訟と同じ目的で使われる他の法的措置

スラップ訴訟以外にも、嫌がらせなどの目的で「刑事告訴」と「懲戒請求」が行われる場合があります。この2つの手続きは、スラップ訴訟同様に相手の精神面や体力面の消耗、威圧などを目的として用いられることがあります。
営業妨害や名誉毀損などの刑事告訴は、発言や運動などを抑制する手段となり得ます。また、裁判では弁護士費用等が発生するため、精神と肉体面などの消耗が強いられます。
懲戒請求は、弁護士について、所属弁護士会に懲戒処分を請求する手続きを指します。懲戒請求に対応するためには、弁護士は時間や労力を費やさなければなりません。不当な懲戒請求は、弁護士の本来の業務を妨害する行為となります。また、懲戒請求は、弁護士の信用や名誉を傷つける可能性があります。
まとめ:スラップ訴訟の相談は弁護士に
訴訟は、誰でも起こすことはできますが、「自己に対する批判の言論の萎縮の効果などを意図して」起こされた訴訟は、違法となる可能性があります。
上記の判例は「スラップ訴訟」という言葉こそ用いられていません。
しかし、訴訟を提起することが違法行為になる場合があるという裁判所の判断が示されています。
訴訟が違法行為になるかどうかは個別具体的な判断になるため、訴訟がいわゆる「スラップ訴訟」であるかどうかの判断は弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所による対策のご案内
モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に豊富な経験を有する法律事務所です。当事務所では幅広い分野でのソリューション提供を行っております。下記記事にて詳細を記載しております。
モノリス法律事務所の取扱分野:風評被害対策