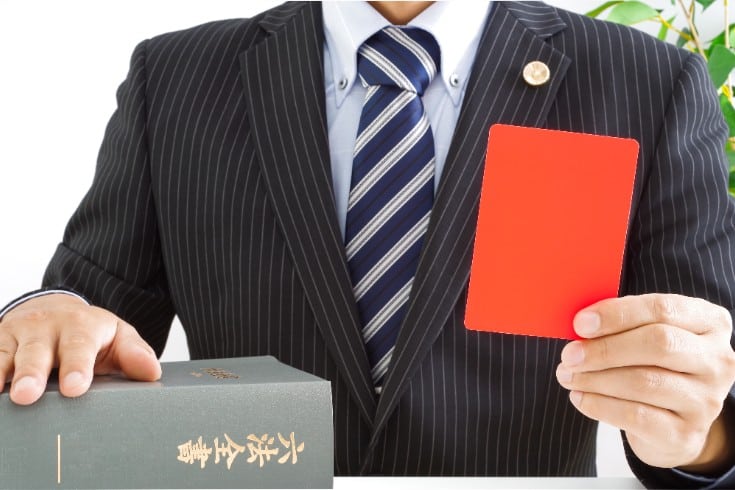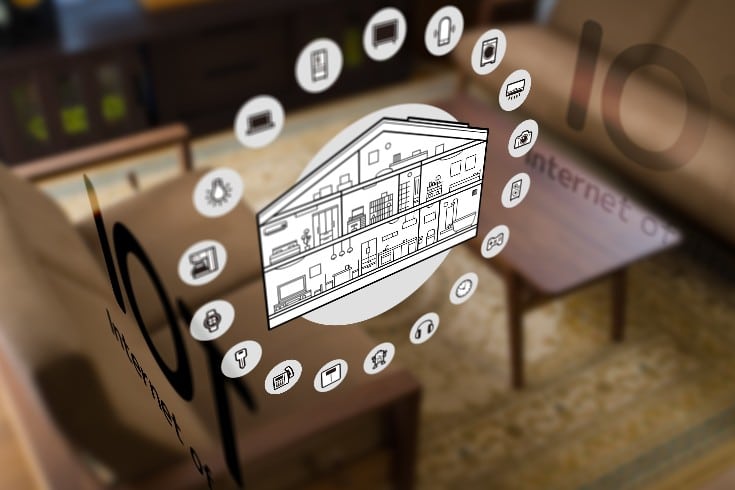カスハラ防止対策が義務化 東京都の条例や企業に必要な対策を解説

顧客の悪質なクレームによって従業員の就業環境が害される「カスタマーハラスメント」が問題視されています。令和7年(2025年)3月11日にはカスハラ対策を強化する法案が提出され、企業のカスハラ対策は義務化される流れにあります。企業はカスハラに対してより適切な措置を講じることが求められるようになるでしょう。
しかし、条例や法律で義務化の流れがあるカスハラ防止対策について対応に不安がある企業も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、全国で初めてカスハラ禁止を定めた東京都の条例の内容とともに、法律改正を見据えて企業がとるべき対策を解説します。カスハラ対策を進める情報として、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次
企業が対策するべきカスハラとは?
カスハラとは、「カスタマーハラスメント」の略語であり、従業員の就業環境を害するハラスメントの一種です。カスタマーハラスメントの定義は、法律上に明確な定義はありません。しかし、企業へのヒアリング調査等の情報から、企業の現場におけるカスハラとは以下のようなものであると、厚生労働省は示しています。
顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの
厚生労働省|カスタマーハラスメント対策マニュアル
顧客や取引先からのクレームすべてが、カスハラにあてはまるわけではありません。クレームには、商品やサービスの改善を求める正当なクレームもあることに注意が必要です。
しかし、過剰な要求を行ったり、商品やサービスに不当な言いがかりをつける悪質なクレームも存在します。このような悪質クレームはカスハラとして認定し、従業員を守る対応が求められます。カスハラの具体例については、以下の記事で詳しく紹介しているため、ぜひご参照ください。
関連記事:カスタマーハラスメントにはどのような事例がある?裁判例から対策ポイントを解説
カスハラ対策が義務化される

法律により、企業がカスハラ対策を講じることが義務化される流れが生まれています。厚生労働省のマニュアルなどによって、カスハラ対策の枠組みは整備されつつあります。しかし、企業がより実効性のある対策を実施できるように、政府が法改正に向けて動いていることに注意が必要です。
カスハラ対策の強化等を内容とする法案が、令和7年(2025年)3月11日に国会に提出されました。この法案が成立すれば、企業はカスハラ防止対策の実施が義務付けられるようになります。企業はこの法改正の成立を想定し、必要な対策を進めていかなければなりません。
東京都がカスハラ防止条例を施行
カスハラの防止対策が法律によってどのように規制されるのかを見据えるため、ここでは東京都のカスハラ防止条例について解説します。
全国初のカスハラ防止条例
東京都議会では、「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が全国で初めて可決・成立しました。この条例は、令和7年(2025年)4月1日から施行されています。カスハラに対する罰則規定は設けられていないものの、カスハラの違法性が条例に明記されたことで、カスハラ被害の緩和が期待されています。
これまでも、悪質なクレーム行為を違法と訴えられる法律は、民法や刑法などにありました。しかし、東京都カスハラ防止条例は、カスハラそのものに焦点を当てた初めての規制であることが重要です。
カスハラの禁止
東京都カスハラ防止条例では、カスハラの一律禁止が明記されました。これは、カスハラは、従業員の就業環境を害し、事業者の事業継続に影響を及ぼすものであり、社会全体で防止を図るべきという基本理念に基づきます。
カスハラは違法行為であることは明記されたものの、カスハラをした者に対する罰則は定められていません。まずは、都民に対してカスハラの違法性を意識づけることを目的とした規定といえるでしょう。
ただし、顧客の権利を不当に侵害しないように注意が必要です。顧客の正当な要求やクレームを、カスハラとして不当に対応を拒否してはいけません。顧客と従業員は、対等な立場で相互に尊重する念を持つことが重要です。
都・顧客・従業員・事業者の責務
東京都カスハラ防止条例において、都は次のような責務を果たすべきであると定められています。
- カスハラ防止に関する情報の提供
- カスハラの啓発および教育
- カスハラの相談および助言
- 施策実施における特別区および市町村との連携
- 施策を推進するための財政上の措置
顧客の立場には、以下のような努力義務が示されました。
- カスハラ問題に対する関心と理解を深めること
- 就業者に対する言動に必要な注意を払うこと
- 都のカスハラ防止施策に協力すること
また、従業員の立場では、次のようなことに努めなければなりません。
- カスハラ問題に対する関心と理解を深めること
- カスハラ防止に資する行動をとること
- 事業者(雇用企業)が実施するカスハラ防止の取組に協力すること
事業者には、以下のような努力義務が定められています。
- カスハラ防止に主体的かつ積極的に取り組むこと
- 都のカスハラ防止施策に協力すること
- カスハラを受けた従業員の安全を確保すること
- カスハラを行った顧客に対して必要で適切な措置を講ずること
- 自社従業員が顧客としてカスハラを行わないように必要な措置を講ずること
カスハラは、社会全体で防止に努めなければならないことが読み取れます。
都が定めるカスハラ防止指針
東京都カスハラ防止条例において、都は、カスハラの防止に関する指針(ガイドライン)を定める旨が示されています。条例には罰則が設けられないものの、指針によってカスハラ防止の実効性を高める狙いがあるといえるでしょう。
参考:東京都|カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)
指針への記載を想定している内容は、次のようなものです。
- カスハラの内容に関する事項
- 顧客、就業者、事業者の責務に関する事項
- 都の施策
- 事業者の取組
そして都は、指針に基づいて、以下のようなカスハラ防止施策を実施することとされています。
- 都の事業等に関する情報提供
- カスハラ防止に関する理解を深める啓発および教育
- 労働問題や消費生活問題に関する相談および助言
- 中小企業等に対する専門家による相談および助言
事業者に求められる措置
事業者は、都の指針に基づいて以下のような措置を講じなければなりません。
- クレームに適切に対応するための体制の整備
- カスハラを受けた者を配慮する取組
- カスハラ防止のためのマニュアル作成や研修の実施
- 取引先で自社従業員がカスハラをしないための配慮
従業員は、事業者が作成したマニュアルを遵守するように努める必要があります。
東京都カスハラ防止条例について、さらに詳しく調べたい方は以下の資料をご参照ください。
産業労働局|東京都カスタマーハラスメント防止条例の基本的な考え方
カスハラ対策を怠った場合のリスク
カスハラ防止策を実施することの重要性を理解するため、ここではカスハラ対策を怠った場合のリスクを解説します。
従業員への悪影響
カスハラ対策を怠った場合、従業員の就業環境に多大な悪影響が及びます。従業員が顧客の悪質なクレームに振り回されている状況では、業務のパフォーマンス低下を招くおそれがあるでしょう。精神的負担が大きな事例の場合、睡眠不良や精神疾患などの健康不良を起こすかもしれません。
企業は、従業員の就業環境を守る安全配慮義務を負っています。従業員が快適に働ける環境を整えるためには、カスハラ対策を講じることが欠かせません。
企業への悪影響
カスハラ対策を講じなければ、企業自体にも大きな悪影響が及びます。悪質なクレームに振り回されていては、返品や返金、慰謝料請求などによって金銭的損失が発生する可能性があるでしょう。
また、クレーム対応には一定の人員や時間を割かなければならないため、全体の業務に少なからず支障をきたします。
さらに、クレームを放置して悪評が広まれば、企業のブランドイメージを低下させる事態も招きかねません。
カスハラのトラブルが企業に全体に悪影響を与える前に適切な対応をするためには、事前に対策を講じることが重要です。
他の顧客への悪影響
カスハラを放置してしまえば、他の顧客にも悪影響が及ぶ可能性があります。悪質なクレーム客がいる場合、他の来店客の利用環境を悪化させてしまうことになるでしょう。クレーム対応に従業員の人員が割かれることで、サービスが行き届かなくなる可能性もあります。嫌な思いをした顧客の口コミが広がれば、企業のブランドイメージが低下する事態にもなりかねません。
顧客に対するサービスをより高めるためにも、カスハラ対策は必要です。
企業がとるべきカスハラへの対策

ここでは、カスハラの発生に備えて企業がとるべき対策について解説します。
基本方針を明確に定めて従業員へ周知する
カスハラ対策の構築を進める際は、まず基本方針を明確に定め、その内容を従業員に周知しましょう。基本方針を明確に示すことができれば、従業員を守ろうとする企業の姿勢が、従業員に伝わります。企業の姿勢が明確に伝われば、カスハラに関する訴えや意見交換がしやすくなるでしょう。
反対に、企業が従業員を守ってくれるという安心感がなければ、カスハラを訴える土壌が生まれないかもしれません。
まずは、基本方針を定めて、企業の姿勢を従業員に示すことが重要です。
相談体制を整備する
カスハラに関する問題を、従業員が気軽に相談できる環境を整備しましょう。現場の従業員がカスハラに遭った際、まず相談するべきは上司や現場監督者です。実際にトラブルが起きた場合、誰に相談するべきかをあらかじめ定めておきましょう。そして、相談を受けた者がどのように対応するのかを記載したマニュアルを作成することも重要です。
関係部署や外部関係機関(弁護士など)との連携体制を構築することも、迅速な問題解決につながるでしょう。
クレーム発生時の対応手順を決める
カスハラに対して適切な対応を進めるためには、対応手順を事前に決めておく必要があります。具体的に起こりうるトラブルを想定しながら、以下のような事項を検討しましょう。
- クレームへの対応人数
- 謝罪のタイミング
- 情報共有の流れ
- 電話録音の有無
- 顧客の要望を聞き取るポイント
具体的な対応手順は、業務内容や業務形態によって異なります。起こりうるカスハラの内容や対応の仕方は、自社のサービスや人員状況を踏まえた上で検討しましょう。
従業員に研修を行う
カスハラ対策の実効性を高めるためには、従業員に対する研修が必要です。定期的な研修を行い、従業員のカスハラに対する理解を深めましょう。研修は、正社員だけではなく、顧客対応を行う従業員は可能な限り全員受講することが望ましいです。
相談体制や対応手順について詳しく認知してもらうことで、組織として迅速かつ適切な対応を実現できるでしょう。
また、顧客対応をする現場の従業員だけでなく、相談を受ける上司や現場監督者に対する教育も欠かせません。
カスハラ発生時の対応方法

ここでは、カスハラが発生してしまったときの対応方法について解説します。
事実関係の正確な確認を進める
カスハラが発生したら、まずは事実関係の正確な確認を進めましょう。顧客の要求が、正当な主張か悪質なクレームかを判断するためです。事実認定は、客観性が重要です。当事者以外の人たちや、録画映像などを含めて広く情報を集めましょう。
顧客のクレームがカスハラであると判断したならば、企業は次のような対応をしなければなりません。
- クレーマーに帰ってもらう
- クレーマーを出入り禁止にする
事実確認が曖昧なまま、軽率な判断をしないように注意が必要です。
カスハラを受けた従業員に配慮措置を講じる
カスハラの被害を受けた従業員がいる場合、配慮措置を講じる必要があります。従業員が暴力や暴言、セクハラなどの行為を受けているならば、速やかに身の安全を確保しなければなりません。場合によっては、弁護士や警察に連絡することが望ましいでしょう。
また、精神的負担を受けている場合もあるため、アフターケアやストレスチェックは欠かせません。
メンタルヘルス不調の兆候がある場合は、専門家や医療機関に相談するように促しましょう。
再発防止の対策に取り組む
カスハラが発生した場合、同じような問題が再発しないように、対策を検討することが重要です。トラブルの内容を事例として共有し、マニュアルや研修の見直しに活かしましょう。
接客方法を見直すことによって、従業員の顧客対応に対する理解が深まり、効果的な予防につながる可能性があります。
カスハラ対策を考える際に注意して取り組むべきこと

カスハラ対策を考える際の注意点について解説します。
カスハラ発生時の状況を迅速に把握する
カスハラ対策を検討する際は、カスハラ発生時の状況を迅速に把握できるように仕組みづくりをしましょう。従業員の相談を受けてから動くだけでなく、能動的に情報を取得できれば、カスハラの予兆を事前に捉えることにつながるかもしれません。
たとえば、以下のような体制があげられます。
- 通話内容を文字化するシステムでリアルタイムチェックする
- 事故報告書を書く前にメールや電話で早期対応を進める
- 上長への電話相談を徹底させる
カスハラが発生したら、すぐに情報が共有されることが重要です。
情報の記録と管理を欠かさない
カスハラ対応に関する情報の記録と管理を欠かさないようにしましょう。クレームの内容や対応の経緯・結果は、報告書や日報で正確に記録します。正しい情報が、関係部署に共有・報告されることが重要です。再発防止策の検討に活用しやすくなります。
取組内容の見直しを行う
カスハラ防止対策の効果を高めていくためには、必要に応じて取組内容を見直すようにしましょう。社会状況の変動や顧客のニーズ、サービス形態の変化などでクレームの質も変わります。
事例の分析と対応方法の検討は、定期的に更新していくことが重要です。
まとめ:企業のカスハラ対策は弁護士に相談を
カスハラ防止の対策を企業がとることは、法律で義務化される流れがあります。先んじて東京都では、カスハラを一律禁止する全国初のカスハラ防止条例が施行されました。
カスハラ対策が義務化されることを想定しながら、従業員の就業環境を守るために、企業はカスハラへの適切な対処を検討する必要があります。カスハラ対策について自社の判断だけでは不安がある場合、弁護士に相談することをおすすめいたします。
弁護士にあらかじめ相談しておくことで、カスハラトラブルが発生した際も対応をサポートしてもらうことが可能です。
当事務所による対策のご案内
モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。当事務所では、東証上場企業からベンチャー企業まで、さまざまなリーガルサポートの提供や、契約書の作成・レビュー等を行っております。詳細については、下記記事をご参照ください。
モノリス法律事務所の取扱分野:IT・ベンチャーの企業法務
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務