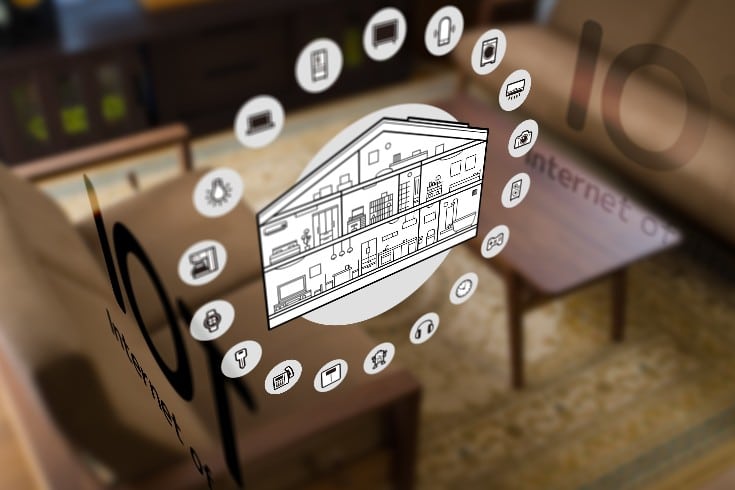õ╗żÕÆī7Õ╣┤µłÉń½ŗŃü«ŃĆīĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ص│ĢŃĆŹŃü©Ńü»’╝¤ĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØŃā╗µēƵ£ēµ©®ńĢÖõ┐ØŃĆüABLŃü©Ńü«ķüĢŃüäŃéÆĶ¦ŻĶ¬¼

ńĄīµĖłµ┤╗ÕŗĢŃüīÕżÜµ¦śÕī¢Ńā╗ĶżćķøæÕī¢ŃüÖŃéŗŃü¬ŃüŗŃĆüµ®¤µó░ŃéäÕ£©Õ║½ŃĆüÕŻ▓µÄøķćæŃü©ŃüäŃüŻŃü¤ŃĆīÕŗĢńöŻŃā╗Õ饵©®ŃĆŹŃéƵŗģõ┐ØŃü½ŃüÖŃéŗÕÅ¢Õ╝ĢŃüīÕóŚŃüłŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
õŠŗŃüłŃü░ŃĆüõ╝üµźŁŃüīµīüŃüżµ®¤µó░Ķ©ŁÕéÖŃéäÕ£©Õ║½Ńü¬Ńü®ŃéƵŗģõ┐ØŃü©ŃüŚŃü”’╝łµ│ĢÕĮóÕ╝ÅõĖŖŃü»ĶŁ▓µĖĪŃüŚŃü”’╝ēĶ׏Ķ│ćŃéÆÕÅŚŃüæŃéŗŃĆīĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØŃĆŹŃéäŃĆüĶć¬ÕŗĢĶ╗ŖŃāŁŃā╝Ńā│Ńü«ŃéłŃüåŃü½õ╗ŻķćæŃüīÕ«īµĖłŃüĢŃéīŃéŗŃüŠŃü¦ÕŻ▓ŃéŖõĖ╗ŃüīµēƵ£ēµ©®ŃéƵīüŃüĪńČÜŃüæŃéŗŃĆīµēƵ£ēµ©®ńĢÖõ┐ØŃĆŹŃü©ŃüäŃüŻŃü¤ÕÅ¢Õ╝ĢŃü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃéēŃü»ÕŠōµØźŃüŗŃéēÕ║āŃüÅõĮ┐ŃéÅŃéīŃü”ŃüäŃéŗõĖƵ¢╣Ńü¦ŃĆüÕÅ¢Õ╝ĢŃā½Ńā╝Ńā½ŃüīµśÄµ¢ćÕī¢ŃüĢŃéīŃü”ŃüŖŃéēŃüÜŃāłŃā®Ńā¢Ńā½Ńü½Ńü¬ŃéŗµćĖÕ┐ĄŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüōŃüåŃüŚŃü¤ĶāīµÖ»ŃüŗŃéēŃĆüõ╗żÕÆī7Õ╣┤5µ£łŃü½µ¢░Ńü¤Ńü½ŃĆīĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ص│ĢŃĆŹ’╝łĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØÕźæń┤äÕÅŖŃü│µēƵ£ēµ©®ńĢÖõ┐ØÕźæń┤äŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗµ│ĢÕŠŗ’╝ēŃüīµłÉń½ŗŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ص│ĢŃü»ŃĆüŃĆīÕģ¼ÕĖāŃüŗŃéē2Õ╣┤6Ńāȵ£łõ╗źÕåģŃĆŹŃü½µ¢ĮĶĪīŃüĢŃéīŃéŗŃü©Õ«ÜŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüķüģŃüÅŃü©Ńééõ╗żÕÆī9Õ╣┤’╝ł2027Õ╣┤’╝ēŃü«12µ£łŃüŠŃü¦Ńü½Ńü»µ¢ĮĶĪīŃüĢŃéīŃéŗŃüōŃü©Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
µ£¼Ķ©śõ║ŗŃü¦Ńü»ŃĆüŃüōŃü«ĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ص│ĢŃü©ŃĆüŃĆīĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØŃĆŹŃĆīµēƵ£ēµ©®ńĢÖõ┐ØŃĆŹŃü«Õ¤║µ£¼ńÜäŃü¬õ╗ĢńĄäŃü┐ŃĆüŃüØŃüŚŃü”ÕŠōµØźŃü«ABL’╝łÕŗĢńöŻŃā╗Õ饵©®µŗģõ┐ØĶ׏Ķ│ć’╝ēŃü©Ńü«ķüĢŃüäŃéÆÕłåŃüŗŃéŖŃéäŃüÖŃüÅĶ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«Ķ©śõ║ŗŃü«ńø«µ¼Ī
µ│ĢÕŠŗµĪłµłÉń½ŗŃü«ĶāīµÖ»Ńü©µ”éĶ”ü

ŃüōŃéīŃüŠŃü¦µŚźµ£¼Ńü¦Ńü»ŃĆüĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØŃéäµēƵ£ēµ©®ńĢÖõ┐ØŃü»µśÄµ¢ćŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗµ│ĢĶ”ÅŃüīÕŁśÕ£©ŃüŚŃü¬ŃüäŃüŠŃüŠŃĆüÕ«¤ÕŗÖµģŻĶĪīŃü©ÕłżõŠŗŃü½ŃéłŃüŻŃü”ķüŗńö©ŃüĢŃéīŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéńē╣Ńü½ĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüÕĮóÕ╝ÅńÜäŃü½Ńü»µēƵ£ēµ©®Ńü«ń¦╗Ķ╗óŃéÆõ╝┤ŃüåÕźæń┤äŃü¦ŃüéŃéŖŃü¬ŃüīŃéēŃĆüÕ«¤Ķ│¬ńÜäŃü½Ńü»µŗģõ┐ØŃü«µĆ¦Ķ│¬ŃéƵīüŃüżŃü©ŃüäŃüåõ║īķØóµĆ¦ŃüīŃĆüÕł®ńö©Ńü«ŃāÅŃā╝ŃāēŃā½Ńü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃüōŃü¦Ńü»ŃĆüĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØŃéäµēƵ£ēµ©®ńĢÖõ┐ØŃü©Ńü»õĮĢŃüŗŃü½ŃüżŃüäŃü”Ķ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØŃü©Ńü»
ĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØŃü©Ńü»ŃĆüÕ饵©®ĶĆģŃüīŃĆüÕéĄÕŗÖĶĆģŃüŠŃü¤Ńü»ń¼¼õĖēĶĆģŃüŗŃéēńø«ńÜäńē®Ńü«ŃĆīÕĮóÕ╝ÅńÜäŃü¬µēƵ£ēµ©®ŃĆŹŃéÆĶŁ▓ŃéŖÕÅŚŃüæŃéŗŃüōŃü©Ńü¦ŃĆüµŗģõ┐ØńÜäŃü¬ÕŖ╣ÕŖøŃéƵīüŃü¤ŃüøŃéŗÕźæń┤äÕĮóµģŗŃü¦ŃüÖŃĆéÕ«¤ÕŗÖõĖŖŃü¦Ńü»õĖ╗Ńü½ÕŗĢńöŻŃéäÕ饵©®ŃéÆńø«ńÜäńē®Ńü©ŃüŚŃĆüĶ┐öµĖłŃüīÕ«īõ║åŃüÖŃéīŃü░µēƵ£ēµ©®Ńü»ÕåŹŃü│ÕéĄÕŗÖĶĆģŃü½µł╗ŃüĢŃéīŃéŗÕĮóŃü¦ķüŗńö©ŃüĢŃéīŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØŃü»ŃĆüĶ│¬µ©®Ńü©ńĢ░Ńü¬ŃéŖŃĆüÕŹĀµ£ēŃü«ń¦╗Ķ╗óŃüīõĖŹĶ”üŃü¦ŃüéŃéŗńé╣Ńüīńē╣ÕŠ┤Ńü¦ŃüÖŃĆéĶ│¬µ©®Ńü«ÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕ饵©®ĶĆģŃüīńø«ńÜäńē®ŃéÆÕŹĀµ£ēŃüÖŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØŃü¦Ńü»ÕéĄÕŗÖĶĆģŃüīńø«ńÜäńē®ŃéÆÕ╝ĢŃüŹńČÜŃüŹõĮ┐ńö©Ńā╗Õć”ÕłåŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīÕÅ»ĶāĮŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«Ńü¤ŃéüŃĆüõ║ŗµźŁńö©Ķ│ćńöŻŃéƵŗģõ┐ØŃü©ŃüŚŃü¬ŃüīŃéēŃééŃĆüõ║ŗµźŁµ┤╗ÕŗĢŃéÆńČÖńČÜŃü¦ŃüŹŃéŗŃü©ŃüäŃüåÕż¦ŃüŹŃü¬Õł®ńé╣ŃüīŃüéŃéŖŃĆüńē╣Ńü½õĖŁÕ░Åõ╝üµźŁŃü«Ķ│ćķćæĶ¬┐ķüöµēŗµ«ĄŃü©ŃüŚŃü”ķćŹĶ”üĶ”¢ŃüĢŃéīŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõĖƵ¢╣Ńü¦ŃĆüµēƵ£ēµ©®ŃéÆÕĮóÕ╝ÅńÜäŃü½ń¦╗Ķ╗óŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃü嵦ŗķĆĀŃüŗŃéēŃĆüµēƵ£ēµ©®Ńü«µēĆÕ£©ŃĆüń¼¼õĖēĶĆģÕ»ŠµŖŚĶ”üõ╗ČŃĆüÕä¬ÕģłķĀåõĮŹńŁēŃü½ŃüŖŃüäŃü”µ│ĢÕŠŗńÜäŃü½õĖŹµśÄńó║Ńü¬ķā©ÕłåŃüīÕżÜŃüÅŃĆüń┤øõ║ēŃü«ÕĤÕøĀŃü½ŃééŃü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
µēƵ£ēµ©®ńĢÖõ┐ØŃü©Ńü»
µēƵ£ēµ©®ńĢÖõ┐ØŃü©Ńü»ŃĆüÕŻ▓Ķ▓ĘÕźæń┤äŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüÕŻ▓õĖ╗ŃüīĶ▓ĘõĖ╗Ńü½ÕĢåÕōüŃéÆÕ╝ĢŃüŹµĖĪŃüŚŃü¤ÕŠīŃééŃĆüõ╗ŻķćæŃüīÕģ©ķĪŹµö»µēĢŃéÅŃéīŃéŗŃüŠŃü¦ŃĆīµēƵ£ēµ©®ŃĆŹŃéÆÕŻ▓ŃéŖõĖ╗Ńü½Ńü©Ńü®ŃéüŃü”ŃüŖŃüÅ’╝łńĢÖõ┐ØŃüÖŃéŗ’╝ēÕźæń┤äÕĮóµģŗŃü¦ŃüÖŃĆéÕ«¤ÕŗÖŃü¦Ńü»õĖ╗Ńü½ÕŗĢńöŻÕŻ▓Ķ▓ĘŃü½Õł®ńö©ŃüĢŃéīŃĆüńē╣Ńü½Õē▓Ķ│”Ķ▓®ÕŻ▓Ńü¬Ńü®Ńü¦Õ║āŃüÅńö©ŃüäŃéēŃéīŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüōŃü«Õźæń┤äŃü¦Ńü»ŃĆüĶ▓ĘõĖ╗ŃüīÕĢåÕōüŃéÆÕŹĀµ£ēŃüŚõĮ┐ńö©ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃéŗõĖƵ¢╣Ńü¦ŃĆüÕ«īÕģ©Ńü¬µēƵ£ēµ©®Ńü»ÕŻ▓õĖ╗Ńü½ńĢÖŃüŠŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüõ╗Żķćæµ£¬µēĢŃüäµÖéŃü½Ńü»ÕĢåÕōüŃéÆÕ╝ĢŃüŹõĖŖŃüÆŃéŗŃüōŃü©ŃüīÕÅ»ĶāĮŃü¦ŃüÖŃĆéĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØŃü©ńĢ░Ńü¬ŃéŖŃĆüµēƵ£ēµ©®Ńü«ńĢÖõ┐ØŃéÆķĆÜŃüśŃü”µŗģõ┐ØńÜäÕŖ╣ÕŖøŃéƵīüŃü¤ŃüøŃéŗńé╣Ńüīńē╣ÕŠ┤Ńü¦ŃüÖŃĆé
µēƵ£ēµ©®ńĢÖõ┐ØŃü»ŃĆüĶ▓ĘõĖ╗Ńü½Ńü©ŃüŻŃü”Ńü»õ╗ŻķćæŃéÆÕłåÕē▓Ńü¦µö»µēĢŃüłŃéŗµ¤öĶ╗¤µĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃĆüÕŻ▓õĖ╗Ńü½Ńü©ŃüŻŃü”Ńü»Õø×ÕÅÄõĖŹĶāĮŃā¬Ńé╣Ńé»ŃéÆĶ╗ĮµĖøŃüÖŃéŗµēŗµ«ĄŃü©ŃüŚŃü”µ®¤ĶāĮŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃü¤ŃüĀŃüŚŃĆüń¼¼õĖēĶĆģŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗÕ»ŠµŖŚĶ”üõ╗ČŃü«ÕģĘÕéÖŃéäŃĆüÕĆÆńöŻµÖéŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕÅ¢µē▒ŃüäŃü¬Ńü®ŃĆüµ│ĢńÜäŃü¬µĢ┤ÕéÖŃüīµ▒éŃéüŃéēŃéīŃéŗńé╣ŃééÕżÜŃüÅŃĆüÕ«¤ÕŗÖõĖŖŃü«µ│©µäÅŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆé
ĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ص│ĢŃü«3ŃüżŃü«ŃāØŃéżŃā│Ńāł

µ£¼µ│ĢŃü¦Ńü»ŃĆüŃüōŃéīŃüŠŃü¦Ńü«ÕłżõŠŗńÉåĶ½¢ŃéƵĢ┤ńÉåŃā╗µśÄµ¢ćÕī¢ŃüÖŃéŗÕĮóŃü¦ŃĆüĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØÕźæń┤äŃüŖŃéłŃü│µēƵ£ēµ©®ńĢÖõ┐ØÕźæń┤äŃü«µ│ĢńÜäµĆ¦Ķ│¬ŃéäÕŖ╣ÕŖøŃéÆÕ«ÜńŠ®ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéńē╣Ńü½ķćŹĶ”üŃü¬µö╣µŁŻŃāØŃéżŃā│ŃāłŃü»õ╗źõĖŗŃü«3ńé╣Ńü¦ŃüÖ
┬ĀÕ»ŠµŖŚĶ”üõ╗ČÕÅŖŃü│õ╗¢Ńü«µŗģõ┐ص©®Ńü©Ńü«Õä¬ÕŖŻ
Õźæń┤äŃü»ŃĆüÕĮōõ║ŗĶĆģŃü«ķ¢ōŃü¦Ńü«Ńü┐ÕŖ╣ÕŖøŃéƵ£ēŃüÖŃéŗŃü«ŃüīÕĤÕēćŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕźæń┤äŃü«ÕŖ╣ÕŖøŃéÆŃĆüń¼¼õĖēĶĆģŃü½ÕÅŖŃü╝ŃüÖŃü¤ŃéüŃü½Ńü»ŃĆüÕłźķĆöÕ»ŠµŖŚĶ”üõ╗ČŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆé
ÕŠōµØźŃü»ŃĆüĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ص©®Ńü«Õ»ŠµŖŚĶ”üõ╗ČŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüÕŗĢńöŻŃü¦ŃüéŃéīŃü░Õ╝ĢµĖĪŃüŚ’╝łµ░æµ│Ģń¼¼178µØĪ’╝ēŃĆüÕ饵©®Ńü¦ŃüéŃéīŃü░ÕéĄÕŗÖĶĆģŃüĖŃü«ķĆÜń¤źŃüŠŃü¤Ńü»µē┐Ķ½Š’╝łµ░æµ│Ģń¼¼467µØĪń¼¼1ķĀģ’╝ēŃü©ŃüĢŃéīŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕŖĀŃüłŃü”ŃĆüńÖ╗Ķ©śÕłČÕ║”ŃéƵ┤╗ńö©ŃüÖŃéīŃü░ŃĆüÕ╝ĢµĖĪŃüŚŃüīŃüéŃüŻŃü¤ŃééŃü«Ńü©Ńü┐Ńü¬ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖ’╝łÕŗĢńöŻŃā╗Õ饵©®ĶŁ▓µĖĪńē╣õŠŗµ│Ģń¼¼3µØĪŃĆüń¼¼4µØĪ’╝ēŃĆéŃüØŃüŚŃü”ŃĆüõ╗¢Ńü«µŗģõ┐ص©®Ńü©Ńü«ķ¢óõ┐éŃü¦Ńü»ŃĆüÕ»ŠµŖŚĶ”üõ╗ČŃéÆÕéÖŃüłŃü¤µÖéńé╣Ńü«ÕģłÕŠīŃü¦ŃĆüµŗģõ┐ص©®Ńü«ķĀåÕ║ÅŃüīµ▒║Õ«ÜŃüĢŃéīŃéŗŃüōŃü©Ńü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤’╝łÕÉīµ│Ģń¼¼32µØĪŃĆüń¼¼49µØĪŃĆüń¼¼55µØĪ’╝ēŃĆé
ŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüÕŹĀµ£ēµö╣Õ«ÜŃü½ŃéłŃéŗÕ╝ĢµĖĪŃüŚ’╝łµ░æµ│Ģń¼¼183µØĪ’╝ēŃü»Õż¢ÕĮóńÜäŃü½Ńü»ŃéÅŃüŗŃéŖŃü½ŃüÅŃüä’╝łÕģ¼ńż║µĆ¦Ńüīõ╣ÅŃüŚŃüä’╝ēŃü¤ŃéüŃĆüĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ص│ĢŃü¦Ńü»ÕŹĀµ£ēµö╣Õ«ÜŃü½ŃéłŃéŗÕ»ŠµŖŚĶ”üõ╗ČŃü»õ╗¢Ńü«µŗģõ┐ص©®Ńü½ÕŖŻÕŠīŃüÖŃéŗ’╝łĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ص│Ģń¼¼36µØĪń¼¼1ķĀģ’╝ēŃüōŃü©ŃüīÕ«ÜŃéüŃéēŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüÕÉīŃüśÕÅ¢Õ╝ĢŃéäķ¢óõ┐éŃüŗŃéēńö¤ŃüśŃü¤ķ¢óķĆŻµĆ¦Ńü«ŃüéŃéŗÕéĄÕŗÖ’╝łńēĮķĆŻµĆ¦Ńü«ŃüéŃéŗÕéĄÕŗÖ’╝ēŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»õ╗¢Ńü«ÕéĄÕŗÖŃéłŃéŖõŠŗÕż¢ńÜäŃü½Õä¬ÕģłŃüĢŃéīŃéŗŃüōŃü©Ńü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤’╝łÕÉīµ│Ģń¼¼31µØĪŃĆüń¼¼37µØĪ’╝ēŃĆé
ĶżćµĢ░ķĀåõĮŹŃü«Ķ©ŁÕ«ÜŃüīµśÄµ¢ćõĖŖÕÅ»ĶāĮŃü©Ńü¬ŃüŻŃü¤ŃüōŃü©
ÕŠōµØźŃü»ŃĆüĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØŃü½ŃüŖŃüæŃéŗĶżćµĢ░ķĀåõĮŹŃü«Ķ©ŁÕ«ÜŃü»ŃĆüÕłżõŠŗõĖŖŃü»Ķ¬ŹŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüäŃü¤ŃééŃü«Ńü«’╝łµ£ĆÕłżÕ╣│µłÉ18Õ╣┤7µ£ł20µŚź’╝ēŃĆüµśÄµ¢ćŃü«µ│ĢńÜäµĀ╣µŗĀŃüīŃü¬ŃüÅńÖ╗Ķ©śÕłČÕ║”Ńééµ£¬µĢ┤ÕéÖŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéŃüØŃü«Ńü¤ŃéüŃĆüĶżćµĢ░Ńü«ĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ص©®ŃüīĶ©ŁÕ«ÜŃüĢŃéīŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕä¬ÕģłķĀåõĮŹŃü«Õłżµ¢ŁŃüīÕø░ķøŻŃü¦ŃĆüń┤øõ║ēŃü«ÕĤÕøĀŃü©Ńü¬ŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«Ńü¤ŃéüŃĆüõ┐ĪĶ©ŚŃéäń¦üńÜäÕźæń┤äŃü¦Õ»ŠÕ┐£ŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü©Ńü¬ŃéŖŃĆüµ│ĢńÜäÕ«ēÕ«ÜµĆ¦Ńü½µ¼ĀŃüæŃéŗŃü«ŃüīÕ«¤µāģŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆé
õĖŖĶ©śŃü«ŃéłŃüåŃü¬õ║ŗµāģŃüŗŃéēŃĆüŃüōŃéīŃüŠŃü¦Ńü»ŃĆüÕ«¤ÕŗÖõĖŖŃĆüĶżćµĢ░ķĀåõĮŹŃü«ĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ص©®Ńü«Ķ©ŁÕ«ÜŃü»ŃĆüķü┐ŃüæŃéēŃéīŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ص│ĢŃü½ŃéłŃéŖŃĆüŌĆŗŌĆŗŃĆīĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØĶ▓ĪńöŻŃü»ŃĆüķćŹŃüŁŃü”ĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØÕźæń┤äŃü«ńø«ńÜäŃü©ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃéŗŃĆŹŃü©ŃüĢŃéīŃĆüĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃééĶżćµĢ░ķĀåõĮŹŃü«Ķ©ŁÕ«ÜŃüīÕÅ»ĶāĮŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤’╝łń¼¼7µØĪ’╝ēŃĆé
ŃüōŃü«ńĄÉµ×£ŃĆüĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ص©®ĶĆģŃüīÕä¬ÕģłķĀåõĮŹŃü½Õ┐£ŃüśŃü”Õ╝üµĖłŃéÆÕÅŚŃüæŃéŗõ╗ĢńĄäŃü┐ŃüīµĢ┤ÕéÖŃüĢŃéīŃĆüĶ׏Ķ│ćŃü«µ¤öĶ╗¤µĆ¦Ńü©õ║łĶ”ŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīÕÉæõĖŖŃüŚŃĆüõ╝üµźŁŃü«Ķ│ćķćæĶ¬┐ķüöŃü½ŃééÕźĮÕĮ▒ķ¤┐Ńüīµ£¤ÕŠģŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
┬ĀĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØŃü«Õć”ÕłåŃā╗Õ«¤ĶĪīŃü«Ńā½Ńā╝Ńā½ŃéƵśÄµ¢ćÕī¢
ÕéĄÕŗÖõĖŹÕ▒źĶĪīµÖéŃü«µŗģõ┐ص©®Õ«¤ĶĪīµ¢╣µ│ĢŃĆüŃüÖŃü¬ŃéÅŃüĪÕ»ŠĶ▒Īńē®Ńü«µÅøõŠĪÕć”ÕłåµēŗńČÜ’╝łń½ČÕŻ▓ŃĆüõ╗╗µäÅÕŻ▓ÕŹ┤ńŁē’╝ēŃü½ķ¢óŃüŚŃü”ŃééŃĆüõĖĆÕ«ÜŃü«µēŗńČÜŃüŹŃéÆńĄīŃéŗŃüōŃü©Ńüīµ▒éŃéüŃéēŃéīŃéŗµŚ©ŃüīĶ”ÅÕ«ÜŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖ’╝łń¼¼5µØĪ’╝ēŃĆé
ń¼¼60µØĪõ╗źõĖŗŃü«Ķ”ÅÕ«ÜŃü½ŃéłŃéŖŃĆüŃüōŃéīŃüŠŃü¦Ńā¢Ńā®ŃāāŃé»Ńā£ŃāāŃé»Ńé╣Õī¢ŃüŚŃü”ŃüäŃü¤ĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØŃü«Õ«¤ÕŗÖķüŗńö©ŃüīķĆŵśÄÕī¢ŃüĢŃéīŃĆüµŗģõ┐ØÕÅ¢Õ╝ĢŃü«Õ«ēÕģ©µĆ¦Ńüīķ½śŃüŠŃéŗŃüōŃü©Ńüīµ£¤ÕŠģŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØŃü©ABLŃü«ķ¢óõ┐éµĆ¦Ńā╗Ķ│ćķćæĶ¬┐ķüöŃü½ŃüŖŃüæŃéŗµäÅńŠ®
ĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØŃéäµēƵ£ēµ©®ńĢÖõ┐ØŃüīµśÄµ¢ćÕī¢ŃüĢŃéīŃü¤ŃüōŃü©Ńü¦ŃĆüµ│ĢńÜäŃü¬õĮŹńĮ«ŃüźŃüæŃüīµśÄńó║Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖŃĆüŃüōŃéīŃéēŃü«µŗģõ┐ØŃéÆÕł®ńö©ŃüÖŃéŗÕÅ¢Õ╝ĢŃü«ķĆŵśÄµĆ¦Ńéäõ┐ĪķĀ╝µĆ¦ŃüīÕÉæõĖŖŃüŚŃĆüõ╝üµźŁŃü½Ńü©ŃüŻŃü”Ńü»ŃéłŃéŖÕ«ēÕ«ÜŃüŚŃü¤ÕĮóŃü¦Ķ│ćķćæĶ¬┐ķüöŃü½µ┤╗ńö©Ńü¦ŃüŹŃéŗŃéłŃüåŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ńē╣Ńü½ŃĆüõĖŁÕ░Åõ╝üµźŁŃéäŃé╣Ńé┐Ńā╝ŃāłŃéóŃāāŃāŚŃü½Ńü©ŃüŻŃü”Ńü»ŃĆüĶć¬ńżŠŃü«ÕŗĢńöŻŃéäÕŻ▓µÄøÕ饵©®Ńü¬Ńü®ŃéƵŗģõ┐ØŃü©ŃüŚŃü”Ķ׏Ķ│ćŃéÆÕÅŚŃüæŃéäŃüÖŃüÅŃü¬ŃéŗŃü©ŃüäŃüåńé╣Ńü¦ŃĆüÕż¦ŃüŹŃü¬µäÅÕæ│ŃéƵīüŃüżµö╣µŁŻŃü©Ķ©ĆŃüłŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüµ£¼µö╣µŁŻŃü½ŃéłŃüŻŃü”ŃĆüÕĮ▒ķ¤┐ŃéÆÕÅŚŃüæŃéŗŃĆüŃéóŃé╗ŃāāŃāłŃā╗ŃāÖŃā╝Ńé╣ŃāłŃā╗Ńā¼Ńā│ŃāćŃéŻŃā│Ńé░’╝łAsset-Based LendingŃĆüõ╗źõĖŗŃĆīABLŃĆŹ’╝ēŃü½ŃüżŃüäŃü”Ķ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüŚŃéćŃüåŃĆé
ABLŃüĖŃü«µ┤╗ńö©

ĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØÕłČÕ║”Ńü«µśÄµ¢ćÕī¢Ńü»ŃĆüŃéóŃé╗ŃāāŃāłŃā╗ŃāÖŃā╝Ńé╣ŃāłŃā╗Ńā¼Ńā│ŃāćŃéŻŃā│Ńé░’╝łAsset-Based LendingŃĆüõ╗źõĖŗŃĆīABLŃĆŹ’╝ēŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüķØ×ÕĖĖŃü½ķćŹĶ”üŃü¬µ│ĢńÜäŃéżŃā│ŃāĢŃā®ŃéƵÅÉõŠøŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ABLŃü©Ńü»
ABLŃü«Ńé╣ŃéŁŃā╝ŃāĀŃü»ŃĆüõ╝üµźŁŃüīõ┐ص£ēŃüÖŃéŗÕŗĢńöŻŃéäÕ饵©®Ńü¬Ńü®Ńü«Ķ│ćńöŻŃéƵŗģõ┐ØŃü½ŃüŚŃü”ŃĆüķćæĶ׏µ®¤ķ¢óŃüŗŃéēĶ׏Ķ│ćŃéÆÕÅŚŃüæŃéŗõ╗ĢńĄäŃü┐Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģĘõĮōńÜäŃü½Ńü»ŃĆüŃüŠŃüÜõ╝üµźŁŃüīÕŻ▓µÄøÕ饵©®ŃĆüÕ£©Õ║½ŃĆüµ®¤µó░Ķ©ŁÕéÖŃĆüõĖŹÕŗĢńöŻŃü¬Ńü®ŃéƵŗģõ┐ØŃü©ŃüŚŃü”µÅÉńż║ŃüŚŃĆüķćæĶ׏µ®¤ķ¢óŃü»ŃüØŃéīŃéēĶ│ćńöŻŃü«õŠĪÕĆżŃéƵ¤╗Õ«ÜŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéµŗģõ┐ØĶ│ćńöŻŃü«Ķ®ĢõŠĪŃü½Õ¤║ŃüźŃüäŃü”Ķ׏Ķ│ćµ×ĀŃüīĶ©ŁÕ«ÜŃüĢŃéīŃĆüõ╝üµźŁŃü»ŃüØŃü«ń»äÕø▓ÕåģŃü¦Ķ│ćķćæŃéÆĶ¬┐ķüöŃü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆé
µŗģõ┐ØŃü«Õ»ŠĶ▒ĪŃü©Ńü¬ŃéŗĶ│ćńöŻŃü»ŃĆüÕżēÕŗĢŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīÕżÜŃüäŃü¤ŃéüŃĆüķćæĶ׏µ®¤ķ¢óŃü»Õ«Üµ£¤ńÜäŃü½ŃāóŃāŗŃé┐Ńā¬Ńā│Ńé░ŃéÆĶĪīŃüäŃĆüĶ׏Ķ│ćµ×ĀŃü«Ķ”ŗńø┤ŃüŚŃéÆĶĪīŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüÕŻ▓µÄøÕ饵©®ŃéƵŗģõ┐ØŃü©ŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»ŃĆüÕ饵©®Ńü«ĶŁ▓µĖĪńÖ╗Ķ©śŃéäķĆÜń¤źŃü¬Ńü®Ńü«µēŗńČÜŃüŹŃüīĶĪīŃéÅŃéīŃĆüńó║Õ«¤Ńü½Õø×ÕÅÄŃü¦ŃüŹŃéŗõĮōÕłČŃüīµĢ┤ŃüłŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ABLŃü»ŃĆüõ╝üµźŁŃü«õ┐Īńö©ÕŖøŃü½õŠØÕŁśŃüŚŃü¬ŃüäĶ│ćķćæĶ¬┐ķüöµēŗµ«ĄŃü©ŃüŚŃü”ŃĆüõĖŁÕ░Åõ╝üµźŁŃé䵳ÉķĢĘõ╝üµźŁŃü½Ńééµ£ēÕŖ╣Ńü¦ŃĆüĶ│ćńöŻŃü«µ┤╗ńö©Õ║”ŃéÆķ½śŃéüŃéŗŃé╣ŃéŁŃā╝ŃāĀŃü©ŃüŚŃü”Õł®ńö©ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØŃééABLŃééŃĆīĶ│ćńöŻŃéƵŗģõ┐ØŃĆŹŃü½ŃüÖŃéŗńé╣ŃéäŃĆīÕŗĢńöŻŃéäÕ饵©®ŃĆŹŃüīÕ»ŠĶ▒ĪŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗńé╣Ńü¦õ╝╝Ńü”ŃüäŃéŗŃéłŃüåŃü½µĆØŃüłŃüŠŃüÖŃĆé
ABLŃü©ĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐Ø
ŃüōŃéīŃüŠŃü¦ŃĆüµŚźµ£¼Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗABLŃü«µÖ«ÕÅŖŃüīķĆ▓ŃüŠŃü¬ŃüŗŃüŻŃü¤õĖĆÕøĀŃü©ŃüŚŃü”ŃĆüŃĆīĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØŃĆŹŃü«µ│ĢńÜäõĮŹńĮ«ŃüźŃüæŃü«õĖŹµśÄńó║ŃüĢŃüīµīÖŃüÆŃéēŃéīŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéķćæĶ׏µ®¤ķ¢óŃü½Ńü©ŃüŻŃü”Ńééµŗģõ┐ØõŠĪÕĆżŃü«Ķ®ĢõŠĪŃé䵩®Õł®Õ«¤ĶĪīŃü«Ńā¬Ńé╣Ńé»ŃüīĶ¬ŁŃü┐Ńü½ŃüÅŃüÅŃĆüĶ׏Ķ│ćŃü«ķÜ£Õ«│Ńü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ص│ĢŃü«µłÉń½ŗŃü½ŃéłŃéŖŃĆüĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØŃü«µ│ĢńÜ䵦ŗķĆĀŃéäÕ»ŠµŖŚĶ”üõ╗ČŃüīµśÄńó║Ńü½Ńü¬ŃüŻŃü¤ŃüōŃü©Ńü¦ŃĆüABLŃü«µ│ĢńÜäÕ«ēÕ«ÜµĆ¦Ńüīķ½śŃüŠŃéŖŃĆüķćæĶ׏µ®¤ķ¢óŃü½ŃéłŃéŗµ┤╗ńö©ŃüīķĆ▓ŃéĆŃü©õ║łµā│ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØŃā╗ABLµ┤╗ńö©Ńü«õ╗ŖÕŠīŃü«Õ▒Ģµ£ø
ĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ص│ĢŃü«µłÉń½ŗŃü½ŃéłŃéŖŃĆüŃüōŃéīŃüŠŃü¦µśÄµ¢ćŃü«Ķ”ÅÕ«ÜŃüīŃü¬ŃüäŃü¤ŃéüŃü½ĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØŃü«Õł®ńö©Ńüīķü┐ŃüæŃéēŃéīŃü”ŃüäŃü¤ÕĀ┤ķØóŃü¦ŃééŃĆüµ│ĢÕŠŗõĖŖŃü«µĀ╣µŗĀŃü½Õ¤║ŃüźŃüäŃü¤Õźæń┤äĶ©ŁĶ©łŃé䵩®Õł®ĶĪīõĮ┐ŃüīÕÅ»ĶāĮŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéµŗģõ┐Øõ╗śŃüŹÕÅ¢Õ╝ĢŃü«ķĆŵśÄµĆ¦Ńü©õ║łµĖ¼ÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīµĀ╝µ«ĄŃü½ķ½śŃüŠŃéŖŃĆüÕźæń┤äµøĖķØóŃü«µĢ┤ÕéÖŃéäńÖ╗Ķ©śÕ«¤ÕŗÖŃü½ŃééĶ”ŗńø┤ŃüŚŃüīĶ┐½ŃéēŃéīŃéŗŃüōŃü©Ńü½Ńü¬ŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆé
ŃüŠŃü¤ŃĆüńÖ╗Ķ©śŃü½ŃéłŃéŗÕä¬ÕģłķĀåõĮŹŃü«Õģ¼ńż║ŃéäŃĆüµŗģõ┐ص©®Õ«¤ĶĪīŃü½ŃüŖŃüæŃéŗµēŗńČÜńÜäÕ«ēÕģ©µĆ¦Ńüīńó║õ┐ØŃüĢŃéīŃü¤ŃüōŃü©Ńü¦ŃĆüµŗģõ┐ØŃü«õŠĪÕĆżŃéƵŁŻķØóŃüŗŃéēĶ®ĢõŠĪŃüŚŃü¤Ķ׏Ķ│ćŃüīŃéłŃéŖÕ«¤ńÅŠŃüŚŃéäŃüÖŃüÅŃü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüĶ▓ĪÕŗÖÕ¤║ńøżŃüīĶäåÕ╝▒Ńü¬õĖŁÕ░Åõ╝üµźŁŃü½Ńü©ŃüŻŃü”ŃĆüĶ│ćńöŻŃéƵ┤╗ŃüŗŃüŚŃü¤Ķ│ćķćæĶ¬┐ķüöŃü«ķüōŃéÆÕ║āŃüÆŃéŗŃüōŃü©Ńü½ń╣ŗŃüīŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
õĖƵ¢╣Ńü¦ŃĆüµ¢░Ńü¤Ńü¬ÕłČÕ║”Õ░ÄÕģźŃü½ŃéłŃüŻŃü”ŃĆüõ╝üµźŁÕĆÆńöŻµÖéŃü«µŗģõ┐ØÕć”ńÉåŃü½ŃééÕżēÕī¢Ńüīńö¤ŃüśŃüŠŃüÖŃĆéŃü¤Ńü©ŃüłŃü░ŃĆüõ╝üµźŁŃü«Õ£©Õ║½ŃéäÕŻ▓µÄøķćæŃü¬Ńü®Ńü«ŃéłŃüåŃü½µŚźŃĆģÕåģÕ«╣ŃüīÕģźŃéīµø┐ŃéÅŃéŗŃĆīķøåÕÉłµŗģõ┐ØŃĆŹŃü½ķ¢óŃüŚŃü”Ńü»ŃĆüõĖĆÕ«ÜŃü«µÖéńé╣Ńü¦µŗģõ┐ØÕŖ╣ÕŖøŃüīÕø║Õ«ÜÕī¢ŃüĢŃéīŃĆüŃüØŃéīõ╗źķÖŹŃü½ÕŖĀÕģźŃüŚŃü¤Ķ│ćńöŻŃü½µŗģõ┐ص©®ŃüīÕÅŖŃü░Ńü¬ŃüäŃü©ŃüäŃüåŃā½Ńā╝Ńā½ŃüīĶ©ŁŃüæŃéēŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüĢŃéēŃü½ŃĆüÕĆÆńöŻµēŗńČÜŃü«ķ¢ŗÕ¦ŗÕŠīŃü½ŃĆüķüÄÕÄ╗Ńü½ĶĪīŃéÅŃéīŃü¤µŗģõ┐ص©®Õ«¤ĶĪīŃü«ÕŖ╣µ×£ŃéÆĶŻüÕłżµēĆŃü«ÕæĮõ╗żŃü½ŃéłŃéŖÕÅ¢ŃéŖµČłŃüøŃéŗÕłČÕ║”ŃééÕ░ÄÕģźŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖŃĆüµŗģõ┐ص©®ĶĆģŃü©ÕĆÆńöŻµēŗńČÜŃü«Õł®Õ«│ķ¢óõ┐éĶĆģŃü©Ńü«Ķ¬┐µĢ┤Ńüīµ│ĢńÜäŃü½µĢ┤ńÉåŃüĢŃéīŃéŗÕÅŹķØóŃĆüÕ«¤ÕŗÖõĖŖŃü«Õłżµ¢ŁŃü½Ńü»ŃüōŃéīŃüŠŃü¦õ╗źõĖŖŃü«µģÄķćŹŃüĢŃüīµ▒éŃéüŃéēŃéīŃéŗŃüōŃü©Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü©Ńéü’╝ÜĶ│ćńöŻŃéƵŗģõ┐ØŃü½ŃüŚŃü¤Ķ│ćķćæĶ¬┐ķüöŃü»Õ░éķ¢ĆÕ«ČŃü½ńøĖĶ½ćŃéÆ
ĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ص│ĢŃü«µłÉń½ŗŃü»ŃĆüÕŹśŃü¬Ńéŗµŗģõ┐ØÕłČÕ║”Ńü«µĢ┤ÕéÖŃü½Ńü©Ńü®ŃüŠŃéēŃüÜŃĆüµŚźµ£¼Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗĶ│ćķćæÕŠ¬ńÆ░Ńü«ÕŖ╣ńÄćÕī¢Ńü©ŃĆüõĖŁÕ░Åõ╝üµźŁŃéÆÕɽŃéĆÕ╣ģÕ║āŃüäõ║ŗµźŁĶĆģŃü«ŃāĢŃéĪŃéżŃāŖŃā│Ńé╣µēŗµ«ĄŃü«µŗĪÕģģŃü½ńø┤ńĄÉŃüÖŃéŗÕż¦ŃüŹŃü¬µäÅńŠ®ŃéƵ£ēŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéÕłżõŠŗŃāÖŃā╝Ńé╣Ńü«Õ«¤ÕŗÖŃéƵ│ĢÕłČÕī¢ŃüŚŃü¤ŃüōŃü©Ńü½ŃéłŃéŖŃĆüµ│ĢńÜäÕ«ēÕ«ÜµĆ¦Ńā╗õ║łµĖ¼ÕÅ»ĶāĮµĆ¦Ńüīķ½śŃüŠŃéŖŃĆüõ╗ŖÕŠīŃü«ńĄīµĖłµ┤╗ÕŗĢŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃééŃüØŃü«µ×£Ńü¤ŃüÖÕĮ╣Õē▓Ńü»ŃüŠŃüÖŃüŠŃüÖķćŹĶ”üŃü½Ńü¬ŃéŗŃü©ĶĆāŃüłŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ص│ĢŃéÆĶ│ćķćæĶ¬┐ķüöńŁēŃü½µ┤╗ŃüŗŃüÖŃü½ŃüéŃü¤ŃüŻŃü”Ńü»ŃĆüŃüōŃéīŃüŠŃü¦Ńü«ÕłżõŠŗµ│ĢńÉåńŁēŃü«µĄüŃéīŃéÆĶĖÅŃüŠŃüłŃü¤µ£¼µ│ĢŃü«Ķ¦ŻķćłŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆéĶŁ▓µĖĪµŗģõ┐ØŃéäµēƵ£ēµ©®ńĢÖõ┐ØŃü«Õł®ńö©Ńü½ŃüéŃü¤ŃüŻŃü”Ńü»ŃĆüÕ░éķ¢ĆńÜäŃü¬ń¤źĶ”ŗŃéƵ£ēŃüÖŃéŗÕ╝üĶŁĘÕŻ½ŃüĖŃü«ńøĖĶ½ćŃéÆŃüŖÕŗ¦ŃéüŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ÕĮōõ║ŗÕŗÖµēĆŃü½ŃéłŃéŗÕ»ŠńŁ¢Ńü«ŃüöµĪłÕåģ
ŃāóŃāÄŃā¬Ńé╣µ│ĢÕŠŗõ║ŗÕŗÖµēĆŃü»ŃĆüITŃĆüńē╣Ńü½ŃéżŃā│Ńé┐Ńā╝ŃāŹŃāāŃāłŃü©µ│ĢÕŠŗŃü«õĖĪķØóŃü½ķ½śŃüäÕ░éķ¢ĆµĆ¦ŃéƵ£ēŃüÖŃéŗµ│ĢÕŠŗõ║ŗÕŗÖµēĆŃü¦ŃüÖŃĆéÕĮōõ║ŗÕŗÖµēĆŃü¦Ńü»ŃĆüµØ▒Ķ©╝õĖŖÕĀ┤õ╝üµźŁŃüŗŃéēŃāÖŃā│ŃāüŃāŻŃā╝õ╝üµźŁŃüŠŃü¦ŃĆüŃüĢŃüŠŃü¢ŃüŠŃü¬Ńā¬Ńā╝Ńé¼Ńā½ŃéĄŃāØŃā╝ŃāłŃü«µÅÉõŠøŃéäŃĆüÕźæń┤äµøĖŃü«õĮ£µłÉŃā╗Ńā¼ŃāōŃāźŃā╝ńŁēŃéÆĶĪīŃüŻŃü”ŃüŖŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéĶ®│ń┤░Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüõĖŗĶ©śĶ©śõ║ŗŃéÆŃüöÕÅéńģ¦ŃüÅŃüĀŃüĢŃüäŃĆé
Ńé½ŃāåŃé┤Ńā¬Ńā╝: ITŃā╗ŃāÖŃā│ŃāüŃāŻŃā╝Ńü«õ╝üµźŁµ│ĢÕŗÖ