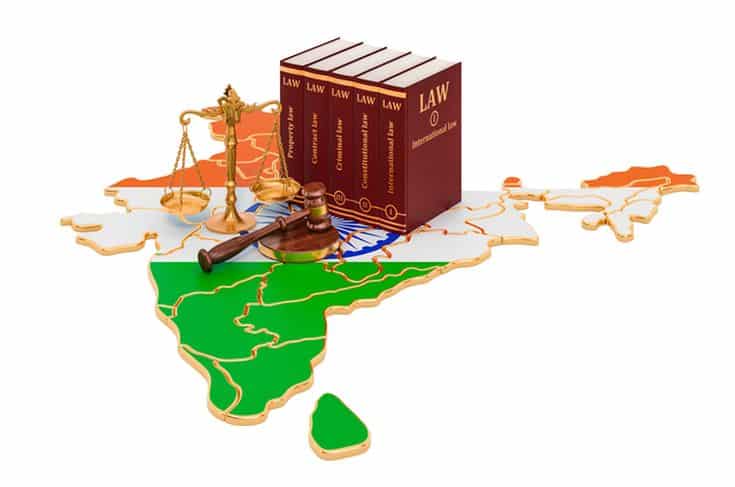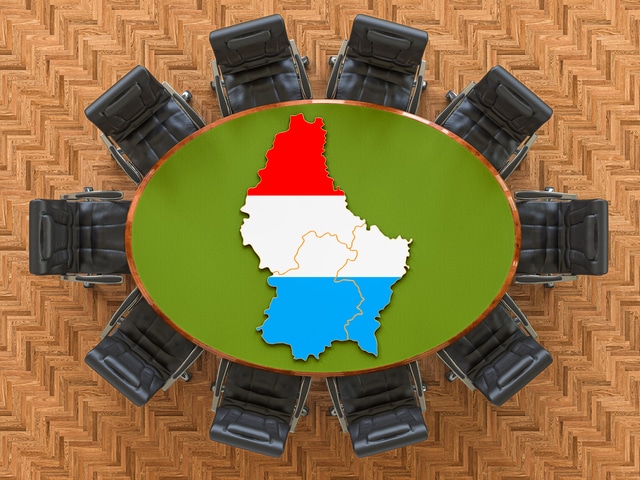гғһгғ«гӮҝгҒ®гғ“гӮ¶еҸ–еҫ—гҒЁгӮ·гғігӮ°гғ«гғ‘гғјгғҹгғғгғҲеҲ¶еәҰ

ең°дёӯжө·гҒ®дёӯеҝғгҒ«дҪҚзҪ®гҒ—гҖҒжё©жҡ–гҒӘж°—еҖҷгҒЁжӯҙеҸІзҡ„гҒӘиЎ—дёҰгҒҝгҒ§зҹҘгӮүгӮҢгӮӢгғһгғ«гӮҝпјҲжӯЈејҸеҗҚз§°гҖҒгғһгғ«гӮҝе…ұе’ҢеӣҪпјүгҒҜгҖҒиҝ‘е№ҙгҖҒ欧е·һгҒ§гҒ®дәӢжҘӯеұ•й–ӢгӮ„ж–°гҒҹгҒӘз”ҹжҙ»гҒ®е ҙгӮ’жұӮгӮҒгӮӢж—Ҙжң¬дәәгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒйӯ…еҠӣзҡ„гҒӘйҒёжҠһиӮўгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®еӣҪгҒ®гғ“гӮ¶гғ»еңЁз•ҷеҲ¶еәҰгҒҜгҖҒEUеҠ зӣҹеӣҪгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еӣҪйҡӣзҡ„гҒӘжһ зө„гҒҝгҒЁзӢ¬иҮӘгҒ®еӣҪеҶ…жі•гҒҢиӨҮйӣ‘гҒ«зөЎгҒҝеҗҲгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢзӮ№гҒҢеӨҡгҖ…еӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒзҹӯжңҹж»һеңЁгҒҜгӮ·гӮ§гғігӮІгғіеҚ”е®ҡгҒ«гӮҲгӮҠгғ“гӮ¶е…ҚйҷӨгҒ®жҒ©жҒөгӮ’дә«еҸ—гҒ§гҒҚгӮӢдёҖж–№гҒ§гҖҒе°ұеҠҙгӮ„з•ҷеӯҰгҖҒ家ж—Ҹж»һеңЁгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹдёӯй•·жңҹгҒ®ж»һеңЁгӮ’зӣ®жҢҮгҒҷйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒгҒқгҒ®еҲ¶еәҰгҒ®е…ЁдҪ“еғҸгҒЁи©ізҙ°гҒӘиҰҒ件гӮ’жӯЈзўәгҒ«зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮ
жң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒгғһгғ«гӮҝгҒ®гғ“гӮ¶еҲ¶еәҰгӮ’гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҮәе…ҘеӣҪз®ЎзҗҶжі•гҒЁгҒ®жҜ”ијғгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰе°Ӯй–Җзҡ„гҒ«и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮеҚҳгҒӘгӮӢжүӢз¶ҡгҒҚгҒ®иӘ¬жҳҺгҒ«з•ҷгҒҫгӮүгҒҡгҖҒеҗ„гғ“гӮ¶гҒ®жі•зҡ„ж №жӢ гӮ„гҖҒ欧е·һгҒ®еҲӨдҫӢгҒӢгӮүжө®гҒӢгҒідёҠгҒҢгӮӢеҲ¶еәҰзҡ„иӘІйЎҢгҒ«гӮӮи§ҰгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғһгғ«гӮҝгҒёгҒ®з§»дҪҸгғ»ж»һеңЁгӮ’жӨңиЁҺгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢзҡҶж§ҳгҒ«гҖҒгӮҲгӮҠж·ұгҒҸгҖҒе®ҹз”Ёзҡ„гҒӘжҙһеҜҹгӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒгғһгғ«гӮҝгҒ®еҢ…жӢ¬зҡ„гҒӘжі•еҲ¶еәҰгҒ®жҰӮиҰҒгҒҜдёӢиЁҳиЁҳдәӢгҒ«гҒҰгҒҫгҒЁгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®зӣ®ж¬Ў
гғһгғ«гӮҝгҒ®гғ“гӮ¶еҲ¶еәҰгҒЁй–ўйҖЈж”ҝеәңж©ҹй–ў
гғһгғ«гӮҝгҒ®еӨ–еӣҪдәәгҒ«гӮҲгӮӢж»һеңЁиЁұеҸҜеҲ¶еәҰгҒҜгҖҒгҒқгҒ®зӣ®зҡ„гҒЁжңҹй–“гҒ«еҝңгҒҳгҒҰгҖҒиӨҮж•°гҒ®жі•д»ӨгҒЁиЎҢж”ҝж©ҹй–ўгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰйҒӢз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҮәе…ҘеӣҪз®ЎзҗҶеҸҠгҒійӣЈж°‘иӘҚе®ҡжі•гҒҢдёҖе…ғзҡ„гҒ«еҮәе…ҘеӣҪеңЁз•ҷз®ЎзҗҶеәҒгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжүҖз®ЎгҒ•гӮҢгӮӢгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒҜж №жң¬зҡ„гҒ«з•°гҒӘгӮӢзү№еҫҙгҒ§гҒҷгҖӮ
гғһгғ«гӮҝгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢж»һеңЁиЁұеҸҜгҒ®зЁ®йЎһ
гғһгғ«гӮҝгҒ®гғ“гӮ¶еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒж»һеңЁжңҹй–“гҒЁзӣ®зҡ„гҒ«еҝңгҒҳгҒҰдё»гҒ«3гҒӨгҒ®йЎһеһӢгҒ«еҲҶйЎһгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҡгҖҒгӮ·гӮ§гғігӮІгғіеҚ”е®ҡгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒиҰіе…үгӮ„зҹӯжңҹе•Ҷз”ЁгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҖҒ90ж—Ҙд»ҘеҶ…гҒ®зҹӯжңҹж»һеңЁгӮ’иЁұеҸҜгҒҷгӮӢзҹӯжңҹж»һеңЁгғ“гӮ¶пјҲCгғ“гӮ¶пјүгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬еӣҪзұҚиҖ…гҒҜгҒ“гҒ®гғ“гӮ¶гҒ®е…ҚйҷӨеҜҫиұЎгҒ§гҒҷгҖӮж¬ЎгҒ«гҖҒ90ж—ҘгӮ’и¶…гҒҲгӮӢй•·жңҹж»һеңЁгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒҷгӮӢгғҠгӮ·гғ§гғҠгғ«гғ“гӮ¶пјҲDгғ“гӮ¶пјүгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜе°ұеҠҙгҖҒз•ҷеӯҰгҖҒ家ж—Ҹж»һеңЁгҒӘгҒ©гҖҒзү№е®ҡгҒ®зӣ®зҡ„гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«д»ҳдёҺгҒ•гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®гғ“гӮ¶гҒҜгҖҒгғһгғ«гӮҝгҒ®жі•еҫӢгҒ§гҒӮгӮӢImmigration Act (Cap. 217)гҒҠгӮҲгҒігҒқгҒ®д»ҳеұһжі•иҰҸпјҲSubsidiary LegislationпјүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰи©ізҙ°гҒ«е®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжңҖеҫҢгҒ«гҖҒ移дҪҸгӮ„ж°ёдҪҸгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒҷгӮӢй•·жңҹгҒ®еұ…дҪҸиЁұеҸҜиЁјгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒҜеҗ„гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ®иҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒҷгҒ“гҒЁгҒ§еҸ–еҫ—гҒҢеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮВ
гғ“гӮ¶з”іи«ӢгӮ’з®ЎиҪ„гҒҷгӮӢдё»иҰҒж©ҹй–ў
гғһгғ«гӮҝгҒ®гғ“гӮ¶гғ»еңЁз•ҷз®ЎзҗҶгҒҜгҖҒеҚҳдёҖгҒ®зңҒеәҒгҒҢз®ЎиҪ„гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒиӨҮж•°гҒ®ж”ҝеәңж©ҹй–ўгҒҢйҖЈжҗәгҒ—гҒҰиЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжңҖгӮӮдёӯеҝғзҡ„гҒӘеҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒҶгҒ®гҒҢгҖҢIdentitГ гҖҚгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж”ҝеәңж©ҹй–ўгҒҜгҖҒгғ“гӮ¶гҒ®зҷәиЎҢгӮ’жӢ…гҒҶгҖҢCentral Visa Unit (CVU)гҖҚгҒЁгҖҒеұ…дҪҸиЁұеҸҜиЁјгҒ®зҷәиЎҢгӮ’жӢ…гҒҶгҖҢExpatriates UnitгҖҚгӮ’еӮҳдёӢгҒ«зҪ®гҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒеёӮж°‘жЁ©й–ўйҖЈгҒ®жүӢз¶ҡгҒҚгҒҜгҖҢCommunity Malta AgencyгҖҚгҒҢзӢ¬з«ӢгҒ—гҒҰз®ЎиҪ„гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иЎҢж”ҝж©ҹж§ӢгҒ®еҲҶжҺҢдҪ“еҲ¶гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҮәе…ҘеӣҪеңЁз•ҷз®ЎзҗҶеәҒгҒҢгҖҒе…ҘеӣҪгҒӢгӮүеңЁз•ҷз®ЎзҗҶгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒҜеё°еҢ–з”іи«ӢгҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§гҖҒеҹәжң¬зҡ„гҒ«дёҖе…ғзҡ„гҒ«жүҖз®ЎгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁеӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«ж…ЈгӮҢгҒҹж—Ҙжң¬дәәгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒжүӢз¶ҡгҒҚгҒ®иӨҮйӣ‘жҖ§гӮ„зӘ“еҸЈгҒ®еӨҡгҒ•гҒ«жҲёжғ‘гҒҶеҺҹеӣ гҒЁгҒӘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒй•·жңҹгғ“гӮ¶гҒ§е…ҘеӣҪгҒ—гҒҹеҫҢгҒ«гҖҒж»һеңЁиЁұеҸҜиЁјгҒ®з”іи«ӢгҒҜеҲҘгҒ®ж©ҹй–ўгҒ§гҒӮгӮӢExpatriates UnitгҒ«з§»иЎҢгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒз”іи«ӢиҖ…гҒҜеёёгҒ«гҒ©гҒ®ж®өйҡҺгҒ§гҒ©гҒ®ж©ҹй–ўгҒ«йҖЈзөЎгҒҷгҒ№гҒҚгҒӢгӮ’жҠҠжҸЎгҒ—гҒҰгҒҠгҒӢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҲҶжҺҢдҪ“еҲ¶гҒҜгҖҒе®ҹеӢҷдёҠгҖҒеҗ„ж©ҹй–ўй–“гҒ®йҖЈжҗәгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжӣёйЎһгҒ®гҒҹгӮүгҒ„еӣһгҒ—гӮ„жүӢз¶ҡгҒҚгҒ®йҒ…延гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹе•ҸйЎҢгҒҢз”ҹгҒҳгӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮӢеӮҫеҗ‘гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгғһгғ«гӮҝгҒёгҒ®з§»дҪҸгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒе°Ӯй–Җ家гҒ«гӮҲгӮӢгӮөгғқгғјгғҲгҒ®йҮҚиҰҒжҖ§гҒҢй«ҳгҒҫгӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮВ
гғһгғ«гӮҝгҒ®е°ұеҠҙгғ»е°Ӯй–ҖиҒ·еҗ‘гҒ‘гғ“гӮ¶гҒЁгӮ·гғігӮ°гғ«гғ‘гғјгғҹгғғгғҲеҲ¶еәҰ

гғһгғ«гӮҝгҒ§гҒ®е°ұеҠҙгӮ’еёҢжңӣгҒҷгӮӢйқһEU/EEA/гӮ№гӮӨгӮ№еӣҪж°‘гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒжңҖгӮӮдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘйҒёжҠһиӮўгҒҜгҖҢгӮ·гғігӮ°гғ«гғ‘гғјгғҹгғғгғҲгҖҚеҲ¶еәҰгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еңЁз•ҷиіҮж јеҲ¶еәҰгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢзӢ¬иҮӘгҒ®иҰҒ件гӮ’еҗ«гӮ“гҒ§гҒҠгӮҠгҖҒзү№гҒ«ж—Ҙжң¬гҒ®дјҒжҘӯгҒҢжө·еӨ–йҖІеҮәгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒгҒқгҒ®йҒ•гҒ„гӮ’жӯЈзўәгҒ«зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҢгӮ·гғігӮ°гғ«гғ‘гғјгғҹгғғгғҲгҖҚеҲ¶еәҰгҒ®и§ЈиӘ¬
гғһгғ«гӮҝгҒ®е°ұеҠҙгғ»ж»һеңЁеҲ¶еәҰгҒ®ж №е№№гӮ’гҒӘгҒҷгҒ®гҒҢгҖҢгӮ·гғігӮ°гғ«гғ‘гғјгғҹгғғгғҲгҖҚгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒе°ұеҠҙиЁұеҸҜпјҲEmployment LicenceпјүгҒЁж»һеңЁиЁұеҸҜпјҲResidence PermitпјүгӮ’дёҖжң¬еҢ–гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒImmigration Status (Single Permit) Regulations (S.L. 217.17)гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҲ¶еәҰгҒ®жңҖеӨ§гҒ®зү№еҫҙгҒҜгҖҒгғһгғ«гӮҝгҒ®йӣҮз”Ёдё»гҒҢгӮӘгғігғ©гӮӨгғігғқгғјгӮҝгғ«гӮ’йҖҡгҒҳгҒҰз”іи«ӢгӮ’иЎҢгҒҶзӮ№гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮз”іи«ӢиҖ…гҒҜгҖҒйӣҮз”Ёдё»гҒҢжҸҗеҮәгҒ—гҒҹжғ…е ұгҒ®зўәиӘҚгҒЁгҖҒгғҗгӮӨгӮӘгғЎгғҲгғӘгӮҜгӮ№пјҲз”ҹдҪ“иӘҚиЁјпјүгғҮгғјгӮҝгҒ®зҷ»йҢІгҖҒгҒҠгӮҲгҒій–ўйҖЈиІ»з”ЁпјҲеҲқеӣһ600гғҰгғјгғӯпјүгҒ®ж”Ҝжү•гҒ„гӮ’жӢ…еҪ“гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гӮ·гғігӮ°гғ«гғ‘гғјгғҹгғғгғҲеҲ¶еәҰгҒҜгҖҒз”іи«ӢгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢйӣҮз”Ёдё»гҒ®еҪ№еүІгҒҢгӮҲгӮҠйҮҚгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ§гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еңЁз•ҷиіҮж јеҲ¶еәҰгҒЁеӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгғһгғ«гӮҝгҒ§гҒҜгҖҒгӮ·гғігӮ°гғ«гғ‘гғјгғҹгғғгғҲгҒ®з”іи«ӢгҒ«йҡӣгҒ—гҖҒйӣҮз”Ёдё»гҒҢгҒқгҒ®иҒ·еӢҷгҒ«гҖҢгғһгғ«гӮҝдәәгӮ„EUеёӮж°‘гҒ§гҒҜйҒ©еҲҮгҒӘдәәжқҗгҒҢгҒ„гҒӘгҒ„гҖҚгҒ“гҒЁгӮ’иЁјжҳҺгҒҷгӮӢгҖҢеҠҙеғҚеёӮе ҙгғҶгӮ№гғҲгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢзҫ©еӢҷгҒҢиӘІгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒйӣҮз”Ёдё»гҒҢйҒ©еҲҮгҒӘзҸҫең°гғЎгғҮгӮЈгӮўгҒ«жңҖдҪҺ3йҖұй–“гҖҒжұӮдәәеәғе‘ҠгӮ’жҺІијүгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’иЁјжҳҺгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮдёҖж–№гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҲ¶еәҰгҒ§гҒҜгҖҒејҒиӯ·еЈ«гӮ„иЎҢж”ҝжӣёеЈ«гҒҢд»ЈзҗҶгҒ§з”іи«ӢгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮҠ гҖҒйӣҮз”Ёдё»гҒҢгҖҢд»ЈжӣҝеҠҙеғҚеҠӣгҒ®дёҚеңЁгҖҚгӮ’иЁјжҳҺгҒҷгӮӢиҰҒ件гҒҜдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ“гҒ®йҒ•гҒ„гҒҜгҖҒе°ұеҠҙгғ“гӮ¶еҸ–еҫ—гҒ®йӣЈжҳ“еәҰгӮ’ж №жң¬зҡ„гҒ«е·ҰеҸігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гғһгғ«гӮҝгҒ§гҒҜгҖҒз”іи«ӢиҖ…гҒ®иіҮж јгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒзҸҫең°гҒ®еҠҙеғҚеёӮе ҙеӢ•еҗ‘гҒ«дҫқеӯҳгҒҷгӮӢж§ӢеӣігҒҢгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®дјҒжҘӯгҒҢгғһгғ«гӮҝгҒ«гӮӯгғјгғ‘гғјгӮҪгғігӮ’жҙҫйҒЈгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гҖҒдәҲжңҹгҒӣгҒ¬жҷӮй–“зҡ„гӮігӮ№гғҲгӮ„жүӢз¶ҡгҒҚгҒ®еӣ°йӣЈгҒ•гӮ’з”ҹгҒҳгҒ•гҒӣгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәе”ҶгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮВ
й«ҳеәҰе°Ӯй–ҖиҒ·еҗ‘гҒ‘гҒ®зү№еҲҘеҲ¶еәҰ
гғһгғ«гӮҝгҒҜй«ҳеәҰгҒӘгӮ№гӮӯгғ«гӮ’жҢҒгҒӨеӨ–еӣҪдәәгҒ®еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгӮ’з©ҚжҘөзҡ„гҒ«жҺЁйҖІгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒиҝ…йҖҹгҒӘеҜ©жҹ»гғ—гғӯгӮ»гӮ№гӮ’жҢҒгҒӨзү№еҲҘгҒӘгғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®дёҖгҒӨгҒҢгҖҢKey Employee Initiative (KEI)гҖҚгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒй«ҳеәҰжҠҖиЎ“иҒ·гҒҫгҒҹгҒҜз®ЎзҗҶиҒ·еҗ‘гҒ‘гҒ«иЁӯиЁҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒе№ҙй–“зөҰдёҺгҒҢвӮ¬30,000д»ҘдёҠгҒ§гҖҒй–ўйҖЈгҒҷгӮӢиіҮж јгӮ„иҒ·еӢҷзөҢйЁ“гҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢиҰҒ件гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҲ¶еәҰгҒ®жңҖеӨ§гҒ®зү№еҫҙгҒҜгҖҒеҜ©жҹ»жңҹй–“гҒҢгӮҸгҒҡгҒӢ5ж—ҘгҒЁйқһеёёгҒ«иҝ…йҖҹгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮВ
гҒҫгҒҹгҖҒгҖҢEU Blue CardгҖҚгҒҜгҖҒEUе…ЁдҪ“гҒ§зөұдёҖгҒ•гӮҢгҒҹеҲ¶еәҰгҒ§гҖҒй«ҳеәҰгҒӘиіҮж јгӮ’жҢҒгҒӨе°Ӯй–Җ家гҒҢеҜҫиұЎгҒ§гҒҷгҖӮгғһгғ«гӮҝгҒ§гҒ®е№іеқҮе№ҙй–“з·ҸиіғйҮ‘гҒ®1.5еҖҚд»ҘдёҠгҒ®еҸҺе…ҘгҒҢиҰҒ件гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®гҖҢй«ҳеәҰе°Ӯй–ҖиҒ·гҖҚгғ“гӮ¶гҒЁе…ұйҖҡгҒ®зӣ®зҡ„гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиҰҒ件гҒ«гҒҜйҒ•гҒ„гҒҢиҰӢгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®еҲ¶еәҰгҒҜеӯҰжӯҙгҖҒиҒ·жӯҙгҖҒе№ҙеҸҺгҒӘгҒ©гӮ’гғқгӮӨгғігғҲеҲ¶гҒ§и©•дҫЎгҒҷгӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ— гҖҒгғһгғ«гӮҝгҒҜгӮҲгӮҠгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘе№ҙеҸҺгӮ„иҒ·еӢҷеҶ…е®№гҒ«з„ҰзӮ№гӮ’еҪ“гҒҰгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒӘгҒҠгҖҒгғһгғ«гӮҝгҒ®йӣҮз”Ёй–ўйҖЈжі•иҰҸгҒ®ж №е№№гӮ’гҒӘгҒҷEmployment and Training Services Act (Cap. 343)гҒҜгҖҒ2018е№ҙж–ҪиЎҢгҒ®Act XXXIX of 2018гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе»ғжӯўгҒ•гӮҢгҖҒCap. 594гҒ«з§»иЎҢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жі•ж”№жӯЈгҒҜгҖҒгғһгғ«гӮҝж”ҝеәңгҒҢеҠҙеғҚеёӮе ҙгҒ®иҰҸеҲ¶гӮ’жҷӮд»ЈгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰиҰӢзӣҙгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәе”ҶгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮВ
гғһгғ«гӮҝгҒ®з•ҷеӯҰгғ»е®¶ж—Ҹж»һеңЁгғ“гӮ¶гҒЁгҒқгҒ®д»–гҒ®гғ“гӮ¶
е°ұеҠҙзӣ®зҡ„д»ҘеӨ–гҒ®ж»һеңЁгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒгғһгғ«гӮҝгҒ®гғ“гӮ¶еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®гҒқгӮҢгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢзӢ¬иҮӘгҒ®иҰҒ件гӮ’е®ҡгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒз”іи«ӢиҖ…гҒҢеҚҒеҲҶгҒӘиІЎж”ҝиғҪеҠӣгӮ’жңүгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иЁјжҳҺгҒҷгӮӢиҰҒ件гҒ«гҒҜгҖҒжіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
з•ҷеӯҰгғ“гӮ¶гҒ®иҰҒ件гҒЁжіЁж„ҸзӮ№
90ж—ҘгӮ’и¶…гҒҲгӮӢз•ҷеӯҰгҒ«гҒҜгҖҒгғҠгӮ·гғ§гғҠгғ«гғ“гӮ¶пјҲDгғ“гӮ¶пјүгҒ®з”іи«ӢгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮз”іи«ӢиҖ…гҒҜгҖҒгғһгғ«гӮҝгҒ®ж•ҷиӮІж©ҹй–ўгҒӢгӮүгҒ®е…ҘеӯҰиЁұеҸҜжӣёгҖҒжҺҲжҘӯж–ҷгҒ®ж”Ҝжү•гҒ„иЁјжҳҺгҒ«еҠ гҒҲгҖҒжңҖгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘгҒ®гҒҢгҖҢеҚҒеҲҶгҒӘиІЎж”ҝиЁјжҳҺгҖҚгҒ§гҒҷгҖӮгғһгғ«гӮҝгҒ®е…¬ејҸгҒӘиҰҒ件гҒ§гҒҜгҖҒж»һеңЁжңҹй–“дёӯгҖҒжҜҺжңҲвӮ¬950зӣёеҪ“гҒ®жңҖдҪҺж®Ӣй«ҳгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҖҒйҒҺеҺ»3гғ¶жңҲй–“гҒ®йҠҖиЎҢеҸ–еј•жҳҺзҙ°жӣёгҒ§иЁјжҳҺгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҚҳгҒӘгӮӢж®Ӣй«ҳиЁјжҳҺжӣёгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜдёҚеҚҒеҲҶгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиіҮйҮ‘гҒ®еҮәжүҖгӮ’жҳҺзўәгҒ«зӨәгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®зӮ№гҒҜгҖҒиіҮйҮ‘иЁјжҳҺгҒ®ж–№жі•гҒҢжҜ”ијғзҡ„жҹ”и»ҹгҒӘж—Ҙжң¬гҒ®еҹәжә–гҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰеҺіж јгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮВ
家ж—ҸеҶҚзөұеҗҲпјҲFamily Reunificationпјүгғ“гӮ¶гҒ®иҰҒ件
гғһгғ«гӮҝгҒ®е®¶ж—ҸеҶҚзөұеҗҲгғ“гӮ¶гҒҜгҖҒй•·жңҹж»һеңЁиЁұеҸҜгӮ’жҢҒгҒӨеӨ–еӣҪдәәгҒ®е®¶ж—ҸгӮ’е‘јгҒіеҜ„гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҖҒImmigration Act (Cap. 217)гҒ®д»ҳеұһжі•иҰҸгҒ§гҒӮгӮӢSubsidiary Legislation 217.06гҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдё»гҒӘиҰҒ件гҒҜгҖҒгӮ№гғқгғігӮөгғјгҒҢд»ҘдёӢгҒ®жқЎд»¶гӮ’жәҖгҒҹгҒҷгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
- еұ…дҪҸжңҹй–“пјҡеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгғһгғ«гӮҝгҒ«2е№ҙд»ҘдёҠеҗҲжі•зҡ„гҒ«еұ…дҪҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒеҖӢеҲҘгҒ®зҠ¶жіҒгҒ«еҝңгҒҳгҒҰ2е№ҙжңӘжәҖгҒ§гӮӮжӨңиЁҺгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
- иІЎж”ҝиғҪеҠӣпјҡ家ж—Ҹе…Ёе“ЎгӮ’жү¶йӨҠгҒ§гҒҚгӮӢе®үе®ҡгҒ—гҒҹеҸҺе…ҘгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒгғһгғ«гӮҝгҒ®е№іеқҮиіғйҮ‘гҒ«гҖҒ家ж—Ҹ1дәәгҒӮгҒҹгӮҠ20пј…гӮ’еҠ гҒҲгҒҹйҮ‘йЎҚд»ҘдёҠгҒ®еҸҺе…ҘгҒҫгҒҹгҒҜиіҮз”ЈгӮ’иЁјжҳҺгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
- дҪҸеұ…пјҡ家ж—Ҹе…Ёе“ЎгҒҢдҪҸгӮҖгҒ®гҒ«йҒ©еҲҮгҒӘеәғгҒ•гҒЁе®үе…Ёеҹәжә–гӮ’жәҖгҒҹгҒҷдҪҸеұ…гӮ’зўәдҝқгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҖӮ
- й–ўдҝӮиЁјжҳҺпјҡзөҗе©ҡиЁјжҳҺжӣёгӮ„еҮәз”ҹиЁјжҳҺжӣёгҒӘгҒ©гҖҒ家ж—Ҹй–ўдҝӮгӮ’иЁјжҳҺгҒҷгӮӢе…¬зҡ„гҒӘжӣёйЎһгӮ’жҸҗеҮәгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҖӮ
гҒ“гҒ®еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®гҖҢ家ж—Ҹж»һеңЁгҖҚгҒ®еңЁз•ҷиіҮж јгҒЁйқһеёёгҒ«дјјгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒжү¶йӨҠиҖ…гҒ§гҒӮгӮӢеӨ–еӣҪдәәгҒҢжү¶йӨҠиғҪеҠӣгӮ’иЁјжҳҺгҒ—гҖҒ家ж—Ҹй–ўдҝӮгӮ’иЁјжҳҺгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢзӮ№гӮӮе…ұйҖҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгғһгғ«гӮҝгҒ®еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒЁеҗҢж§ҳгҖҒ家ж—ҸгҒ®е®үе®ҡгҒ—гҒҹз”ҹжҙ»з’°еўғгӮ’йҮҚиҰ–гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
| гғһгғ«гӮҝ | ж—Ҙжң¬ | |
|---|---|---|
| гғ“гӮ¶еҲ¶еәҰгҒ®еҗҚз§° | гӮ·гғігӮ°гғ«гғ‘гғјгғҹгғғгғҲ (Single Permit) | еңЁз•ҷиіҮж јпјҲжҠҖиЎ“гғ»дәәж–ҮзҹҘиӯҳгғ»еӣҪйҡӣжҘӯеӢҷгҒӘгҒ©пјү |
| е°ұеҠҙгғ»ж»һеңЁиЁұеҸҜгҒ®зөұеҗҲ | зөұеҗҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢпјҲе°ұеҠҙиЁұеҸҜгҒЁж»һеңЁиЁұеҸҜгҒҢдёҖдҪ“пјү | еҲҘеҖӢгҒ®жҰӮеҝөпјҲеңЁз•ҷиіҮж јгҒЁе°ұеҠҙиіҮж јиЁјжҳҺжӣёпјү |
| йӣҮз”Ёдё»гҒ®еҪ№еүІ | йӣҮз”Ёдё»гҒҢз”іи«ӢгӮ’дё»е°ҺгҒ—гҖҒең°е…ғгғ»EUгҒӢгӮүгҒ®д»ЈжӣҝдәәжқҗгҒҢгҒ„гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮ’иЁјжҳҺгҒҷгӮӢзҫ©еӢҷгҒӮгӮҠ | з”іи«Ӣдәәгғ»д»ЈзҗҶдәәгғ»йӣҮз”Ёдё»гҒҢз”іи«ӢеҸҜиғҪгҒ§гҖҒд»ЈжӣҝдәәжқҗгҒ®дёҚеңЁиЁјжҳҺгҒҜеҺҹеүҮдёҚиҰҒ |
| жңҖдҪҺзөҰдёҺиҰҒ件 | зү№е®ҡгҒ®й«ҳеәҰе°Ӯй–ҖиҒ·еҗ‘гҒ‘гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ«гҒ®гҒҝйҒ©з”ЁпјҲKEIгҒҜвӮ¬30,000д»ҘдёҠпјү | зү№е®ҡгҒ®й«ҳеәҰе°Ӯй–ҖиҒ·гғ“гӮ¶гҒ«гҒ®гҒҝйҒ©з”ЁпјҲгғқгӮӨгғігғҲеҲ¶пјү |
| 家ж—Ҹж»һеңЁгҒ®еҗҚз§° | 家ж—ҸеҶҚзөұеҗҲ (Family Reunification) | 家ж—Ҹж»һеңЁ |
| жү¶йӨҠиғҪеҠӣиЁјжҳҺ | гӮ№гғқгғігӮөгғјгҒ®еҸҺе…ҘгҒҢгғһгғ«гӮҝгҒ®е№іеқҮиіғйҮ‘пјӢ家ж—Ҹ1дәәгҒӮгҒҹгӮҠ20%гҒ®еҸҺе…Ҙгғ»иіҮз”ЈгӮ’иЁјжҳҺ | жү¶йӨҠиҖ…гҒҢжү¶йӨҠиғҪеҠӣгӮ’иЁјжҳҺгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁпјҲе…·дҪ“зҡ„гҒӘйҮ‘йЎҚеҹәжә–гҒҜиҒ·зЁ®гғ»е®¶ж—Ҹж§ӢжҲҗгҒ«гӮҲгӮӢпјү |
| еұ…дҪҸжңҹй–“гҒ®иҰҒ件 | гӮ№гғқгғігӮөгғјгҒҜеҺҹеүҮ2е№ҙд»ҘдёҠеҗҲжі•зҡ„гҒ«еұ…дҪҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁ | жү¶йӨҠиҖ…гҒ®еңЁз•ҷжңҹй–“гҒҢжңүеҠ№гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁ |
гҒқгҒ®д»–гҒ®ж»һеңЁеҲ¶еәҰ
гғһгғ«гӮҝгҒЁж—Ҙжң¬гҒ®й–“гҒ§гҒҜгҖҒ2025е№ҙ1жңҲгӮҲгӮҠгғҜгғјгӮӯгғігӮ°гғӣгғӘгғҮгғјеҚ”е®ҡгҒҢзҷәеҠ№гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒ18жӯігҒӢгӮү30жӯігҒ®ж—Ҙжң¬дәәгҒҢгҖҒгғһгғ«гӮҝгҒ§жңҖй•·1е№ҙй–“гҖҒдј‘жҡҮгӮ’йҒҺгҒ”гҒ—гҖҒгҒқгҒ®иІ»з”ЁгӮ’иЈңгҒҶгҒҹгӮҒгҒ®е°ұеҠҙгӮӮеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒгғһгғ«гӮҝгҒ®ж–ҮеҢ–гӮ„з”ҹжҙ»гӮ’дҪ“йЁ“гҒҷгӮӢдёҠгҒ§гҖҒйқһеёёгҒ«дҫЎеҖӨгҒ®гҒӮгӮӢйҒёжҠһиӮўгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ®д»–гҖҒгғӘгғўгғјгғҲгғҜгғјгӮ«гғјеҗ‘гҒ‘гҒ®гҖҢгғҮгӮёгӮҝгғ«гғҺгғһгғүгғ“гӮ¶гҖҚгҒӘгҒ©гҖҒзҸҫд»ЈгҒ®еғҚгҒҚж–№гҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹж–°гҒ—гҒ„еҲ¶еәҰгӮӮе°Һе…ҘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гғһгғ«гӮҝгҒ®гғ“гӮ¶еҲ¶еәҰгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжі•зҡ„иӘІйЎҢгҒЁдёҚжңҚз”із«Ӣ
гғһгғ«гӮҝгҒ®гғ“гӮ¶еҲ¶еәҰгҒ«гҒҜгҖҒеӣҪйҡӣзҡ„гҒӘжі•иҰҸзҜ„гҒ«з…§гӮүгҒ—гҒҰйҮҚиҰҒгҒӘиӘІйЎҢгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒ欧е·һгҒ®й«ҳзӯүиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨдҫӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®иӘІйЎҢгҒҜгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢжүӢз¶ҡгҒҚгҒ®йҒөе®ҲгҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгӮүгҒӘгҒ„гҖҒгӮҲгӮҠж·ұгҒ„жі•зҡ„гғӘгӮ№гӮҜгӮ’з”іи«ӢиҖ…гҒ«зӨәе”ҶгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
Immigration Appeals Board (IAB)гҒ«гӮҲгӮӢдёҚжңҚз”із«ӢеҲ¶еәҰ
гғһгғ«гӮҝгҒ®гғ“гӮ¶гӮ„ж»һеңЁиЁұеҸҜгҒ®з”іи«ӢгҒҢеҚҙдёӢгҒ•гӮҢгҒҹе ҙеҗҲгҖҒз”іи«ӢиҖ…гҒҜImmigration Appeals Board (IAB)гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰдёҚжңҚгӮ’з”ігҒ—з«ӢгҒҰгӮӢжЁ©еҲ©гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮз”іи«ӢжӢ’еҗҰйҖҡзҹҘгҒӢгӮүгҖҒгғ“гӮ¶з”іи«ӢгҒ®е ҙеҗҲгҒҜ15ж—Ҙд»ҘеҶ…гҖҒгӮ·гғігӮ°гғ«гғ‘гғјгғҹгғғгғҲз”іи«ӢгҒ®е ҙеҗҲгҒҜ3е–¶жҘӯж—Ҙд»ҘеҶ…гҒЁгҒ„гҒҶйқһеёёгҒ«зҹӯгҒ„жңҹйҷҗеҶ…гҒ«з”ігҒ—з«ӢгҒҰгӮ’иЎҢгҒҶеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®дёҚжңҚз”із«ӢеҲ¶еәҰгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®е…Ҙз®Ўжі•гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдёҚжңҚз”із«ӢеҲ¶еәҰгҒ«зӣёеҪ“гҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгғһгғ«гӮҝгҒ®IABгҒҜгҖҒгҒқгҒ®е®ҹж…ӢгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰйҮҚеӨ§гҒӘиӘІйЎҢгӮ’жҠұгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒ欧е·һдәәжЁ©иЈҒеҲӨжүҖпјҲECHRпјүгҒ®еҲӨдҫӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮВ
еҲӨдҫӢгҒӢгӮүиҰӢгӮӢеҲ¶еәҰзҡ„иӘІйЎҢгҒЁж—Ҙжң¬жі•гҒЁгҒ®з•°еҗҢ
欧е·һдәәжЁ©иЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒJ.B. v. MaltaеҲӨжұәпјҲ2025е№ҙ1жңҲ7ж—ҘпјүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгғһгғ«гӮҝгҒ®IABгҒҢгҖҒеӨ§иҮЈгҒ«гӮҲгӮӢеәғзҜ„гҒӘиЈҒйҮҸгҒ§е§”е“ЎгҒҢд»»е‘ҪгҒ•гӮҢгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒгҒқгҒ®зӢ¬з«ӢжҖ§гҒҢж§ӢйҖ зҡ„гҒ«ж¬ еҰӮгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁжҢҮж‘ҳгҒ—гҖҒеҸёжі•ж©ҹй–ўгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®жҖ§ж јгӮ’жҢҒгҒҹгҒӘгҒ„гҒЁж–ӯгҒҳгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒIABгҒҢIdentitГ гҒӢгӮүиҮӘеҫӢгҒ—гҒҹж©ҹй–ўгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒҷгӮӢгғһгғ«гӮҝж”ҝеәңгҒ®дё»ејөгҒЁзңҹгҒЈеҗ‘гҒӢгӮүеҜҫз«ӢгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒгғһгғ«гӮҝгҒ®з§»ж°‘еҲ¶еәҰгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢжі•гҒ®ж”Ҝй…ҚгҖҚгҒ®и„ҶејұжҖ§гӮ’зӨәгҒҷгӮӮгҒ®гҒ гҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®иЎҢж”ҝдёҚжңҚеҜ©жҹ»жі•гҒ«еҹәгҒҘгҒҸеҜ©жҹ»и«ӢжұӮгҒҜгҖҒзӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹ第дёүиҖ…ж©ҹй–ўгҒ§гҒӮгӮӢеҜ©жҹ»дјҡгҒ«гӮҲгӮӢеҜ©зҗҶгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒе…¬жӯЈгҒӘеҲӨж–ӯгҒҢжңҹеҫ…гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгғһгғ«гӮҝгҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒҜгҖҒгғ“гӮ¶жӢ’еҗҰгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢдёҚжңҚз”із«ӢжүӢз¶ҡгҒҚгҒҢгҖҒе®ҹиіӘзҡ„гҒ«жңүеҠ№гҒӘж•‘жёҲжүӢж®өгҒЁгҒ—гҒҰж©ҹиғҪгҒ—гҒӘгҒ„еҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮВ
гҒ•гӮүгҒ«гҖҒSuso Musa v. MaltaеҲӨжұәпјҲ2012е№ҙ7жңҲ23ж—ҘпјүгҒ§гҒҜгҖҒдёҚжі•е…ҘеӣҪиҖ…гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиҮӘеӢ•зҡ„гҒӘеҸҺе®№жҺӘзҪ®гҒҢгҖҒеҖӢеҲҘе…·дҪ“зҡ„гҒӘзҠ¶жіҒгӮ’иҖғж…®гҒӣгҒҡгҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®е•ҸйЎҢзӮ№гҒҢжҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮECHRгҒҜгҖҒеҖӢдәәгҒ®зҠ¶жіҒгҒ«еҝңгҒҳгҒҹгҖҢгӮҲгӮҠеј·еҲ¶еҠӣгҒ®дҪҺгҒ„жҺӘзҪ®гҖҚгҒ®жӨңиЁҺгӮ’жұӮгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгӮүгҒ®еҲӨдҫӢгҒҢзӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгғһгғ«гӮҝгҒ§гҒҜ移民гғ»гғ“гӮ¶й–ўйҖЈгҒ®иЎҢж”ҝжүӢз¶ҡгҒҚгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒиЎҢж”ҝиЈҒйҮҸгӮ„жүӢз¶ҡгҒҚгҒ®е…¬жӯЈжҖ§гҒҢеӣҪйҡӣзҡ„гҒӘжі•зҡ„еҹәжә–гҒ«з…§гӮүгҒ—гҒҰеҺігҒ—гҒҸе•ҸгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гғһгғ«гӮҝж°ёдҪҸжЁ©гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ пјҲMPRPпјүгҒЁеёӮж°‘жЁ©гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ пјҲMEINпјү

гғһгғ«гӮҝж”ҝеәңгҒҜгҖҒзөҢжёҲзҡ„иІўзҢ®гӮ’дё»гҒӘиҰҒ件гҒЁгҒҷгӮӢзү№еҲҘгҒӘж»һеңЁгғ»еёӮж°‘жЁ©гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒҜжң¬иЁҳдәӢгҒ®дё»иҰҒгғҶгғјгғһгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒгҒқгҒ®жҰӮиҰҒгҒЁжі•зҡ„иғҢжҷҜгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰз°ЎжҪ”гҒ«и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гғһгғ«гӮҝж°ёдҪҸжЁ©гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ пјҲMPRPпјү
Malta Permanent Residence Programme (MPRP)гҒҜгҖҒйқһEU/EEA/гӮ№гӮӨгӮ№еӣҪж°‘гҒҢгғһгғ«гӮҝгҒ®ж°ёдҪҸжЁ©гӮ’еҸ–еҫ—гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҲ¶еәҰгҒ§гҒҷгҖӮдё»гҒӘиҰҒ件гҒҜгҖҒдёҖе®ҡйЎҚгҒ®ж”ҝеәңгҒёгҒ®иІўзҢ®йҮ‘гҖҒж…Ҳе–„еӣЈдҪ“гҒёгҒ®еҜ„д»ҳгҖҒгҒқгҒ—гҒҰдёҚеӢ•з”ЈгҒёгҒ®жҠ•иіҮгҒ§гҒҷгҖӮгҒӘгҒҠгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®жҠ•иіҮиҰҒ件гҒ®йҮ‘йЎҚгҒҜгҖҒжҷӮжңҹгӮ„жғ…е ұжәҗгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеӨүеӢ•гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒз”іи«ӢгҒ«йҡӣгҒ—гҒҰгҒҜжңҖж–°гҒ®жі•д»ӨгӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еӨүеӢ•жҖ§гҒҜгҖҒе°Ӯй–Җ家гҒ«гӮҲгӮӢжӯЈзўәгҒӘжғ…е ұеҸҺйӣҶгҒ®еҝ…иҰҒжҖ§гӮ’еј·гҒҸзӨәе”ҶгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гғһгғ«гӮҝеёӮж°‘жЁ©гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ пјҲMEINпјүгҒЁж¬§е·һеҸёжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨдҫӢ
гғһгғ«гӮҝж”ҝеәңгҒҢжҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹMalta Citizenship by Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment (MEIN)гҒҜгҖҒзӣҙжҺҘжҠ•иіҮгҒ«гӮҲгӮӢеёӮж°‘жЁ©д»ҳдёҺеҲ¶еәҰгҒЁгҒ—гҒҰзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒйҮҚеӨ§гҒӘжі•зҡ„и»ўжҸӣзӮ№гӮ’иҝҺгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ欧е·һеҸёжі•иЈҒеҲӨжүҖпјҲECJпјүгҒҜгҖҒEuropean Commission v Republic of Malta (Case C-181/23) еҲӨжұәпјҲ2025е№ҙ4жңҲ29ж—ҘпјүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒҢEUжі•гҒ«йҒ•еҸҚгҒҷгӮӢгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮECJгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒҢеӣҪзұҚгӮ’гҖҢгҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҹж”Ҝжү•гҒ„гҒҫгҒҹгҒҜжҠ•иіҮгҒЁеј•гҒҚжҸӣгҒҲгҒ«е®ҹиіӘзҡ„гҒ«д»ҳдёҺгҒҷгӮӢгҖҚгҖҢеҸ–еј•зҡ„гҒӘжүӢз¶ҡгҒҚгҖҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеёӮж°‘жЁ©гҒҢжңүгҒҷгӮӢгҖҢзү№еҲҘгҒӘйҖЈеёҜй–ўдҝӮгҖҚгҒ®жҰӮеҝөгҒЁзӣёе®№гӮҢгҒӘгҒ„гҒЁзөҗи«–д»ҳгҒ‘гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮВ
гҒ“гҒ®еҲӨжұәгҒҜгҖҒеҚҳгҒ«гғһгғ«гӮҝгҒ®гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ®еҗҲжі•жҖ§гӮ’е•ҸгҒҶгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒEUе…ЁдҪ“гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢеёӮж°‘жЁ©гҒ®еЈІиІ·гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж…ЈиЎҢгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ«жҳҺзўәгҒӘеўғз•Ңз·ҡгӮ’еј•гҒҸгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮECJгҒҜгҖҒеӣҪзұҚгҒ®д»ҳдёҺгҒҜеҠ зӣҹеӣҪгҒ®дё»жЁ©зҡ„жЁ©йҷҗгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ—гҒӨгҒӨгӮӮгҖҒгҒқгҒ®жЁ©йҷҗгҒҜEUжі•гҒ®жһ еҶ…гҒ§иӘ е®ҹгҒ«иЎҢдҪҝгҒ•гӮҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶеҺҹеүҮгӮ’ж”№гӮҒгҒҰзӨәгҒ—гҒҹгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒ
гғһгғ«гӮҝгҒ®гғ“гӮ¶еҸ–еҫ—гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢзӢ¬иҮӘгҒ®жһ зө„гҒҝгҒ®дёӯгҒ§йҒӢз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒқгҒ®жүӢз¶ҡгҒҚгҒҜиӨҮйӣ‘гҒӢгҒӨеӨҡеІҗгҒ«гӮҸгҒҹгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе°ұеҠҙгҖҒз•ҷеӯҰгҖҒ家ж—Ҹж»һеңЁгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘгғ“гӮ¶гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒйӣҮз”Ёдё»гҒ®еҪ№еүІгҖҒиІЎж”ҝиЁјжҳҺгҒ®еҺіж јжҖ§гҖҒгҒқгҒ—гҒҰжі•йҒӢз”ЁгҒ®е®ҹж…ӢгҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§гҖҒж—Ҙжң¬гҒЁгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘйҒ•гҒ„гҒҢж•°еӨҡгҒҸеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
зү№гҒ«гҖҒ欧е·һгҒ®й«ҳзӯүиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨдҫӢгҒҢзӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒдёҚжңҚз”із«ӢгҒҰеҲ¶еәҰгҒ®ж§ӢйҖ зҡ„иӘІйЎҢгӮ„гҖҒеёӮж°‘жЁ©гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ®еҗҲжі•жҖ§гҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒёгҒ®з–‘зҫ©гҒҜгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢжүӢз¶ҡгҒҚгҒ®йҒөе®ҲгҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгӮүгҒӘгҒ„гҖҒгӮҲгӮҠж·ұгҒ„жі•зҡ„гғӘгӮ№гӮҜгӮ’еҶ…еҢ…гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәе”ҶгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиӨҮйӣ‘гҒӘжі•еҲ¶еәҰгҒ®з¶ІгҒ®зӣ®гӮ’жӯЈзўәгҒ«иӘӯгҒҝи§ЈгҒҚгҖҒйҒ©еҲҮгҒӘз”іи«ӢжҲҰз•ҘгӮ’з«ӢгҒҰгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒе°Ӯй–Җзҡ„гҒӘзҹҘиҰӢгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮ
гӮ«гғҶгӮҙгғӘгғј: ITгғ»гғҷгғігғҒгғЈгғјгҒ®дјҒжҘӯжі•еӢҷ
гӮҝгӮ°: гғһгғ«гӮҝе…ұе’ҢеӣҪжө·еӨ–дәӢжҘӯ