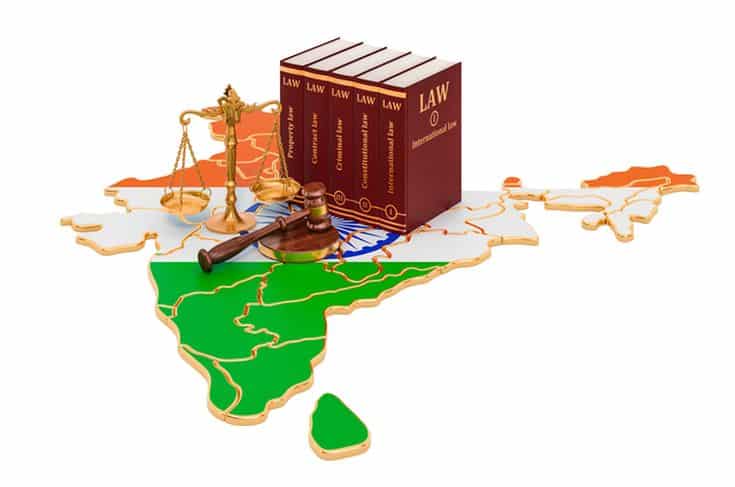гӮӘгғ©гғігғҖзҺӢеӣҪгҒ®M&Aй–ўйҖЈжі•еҲ¶гӮ’ејҒиӯ·еЈ«гҒҢи§ЈиӘ¬

гӮӘгғ©гғігғҖпјҲжӯЈејҸеҗҚз§°гҖҒгӮӘгғ©гғігғҖзҺӢеӣҪпјүгҒҜгҖҒ欧е·һйҖЈеҗҲпјҲEUпјүгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢйҮҚиҰҒгҒӘзөҢжёҲзҡ„гғ»жі•зҡ„жӢ зӮ№гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгӮ°гғӯгғјгғҗгғ«дјҒжҘӯгҒӢгӮүй«ҳгҒ„й–ўеҝғгӮ’йӣҶгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®жҲҰз•Ҙзҡ„гҒӘең°зҗҶзҡ„дҪҚзҪ®гҖҒе®үе®ҡгҒ—гҒҹжі•еҲ¶еәҰгҖҒгҒҠгӮҲгҒізҶҹз·ҙгҒ—гҒҹеӨҡиЁҖиӘһеҠҙеғҚеҠӣгҒҜгҖҒеӣҪйҡӣзҡ„гҒӘM&AеҸ–еј•гҒ®гғҸгғ–гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®ең°дҪҚгӮ’зўәз«ӢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®жҠ•иіҮ家гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгӮӘгғ©гғігғҖгҒҜ欧е·һеёӮе ҙгҒёгҒ®гӮІгғјгғҲгӮҰгӮ§гӮӨгҒЁгҒ—гҒҰйӯ…еҠӣзҡ„гҒӘйҖІеҮәе…ҲгҒ§гҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®йӣ»еҠӣдјҡзӨҫгҒ§гҒӮгӮӢдёӯйғЁйӣ»еҠӣгҒҢгҖҒ欧е·һгҒ§з·ҸеҗҲгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјдәӢжҘӯгӮ’еұ•й–ӢгҒҷгӮӢгӮӘгғ©гғігғҖдјҒжҘӯEnecoгӮ’иІ·еҸҺгҒ—гҒҹдәӢдҫӢгҒҜгҖҒгӮӘгғ©гғігғҖгҒ®M&AеёӮе ҙгҒҢжҸҗдҫӣгҒҷгӮӢжҠҖиЎ“еҠӣгӮ„гғҺгӮҰгғҸгӮҰгҒ®еҗёеҸҺж©ҹдјҡгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӘгғ©гғігғҖгҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒд»–гҒ®EUеҠ зӣҹеӣҪгҒЁеҗҢж§ҳгҒ«гҖҒгӮӘгғ©гғігғҖеӣҪеҶ…жі•гҒЁEUжі•гҒ®дәҢйҮҚж§ӢйҖ гӮ’жҢҒгҒӨгҒЁгҒ„гҒҶзү№еҫҙгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еӨҡеұӨзҡ„гҒӘжі•зҡ„жһ зө„гҒҝгҒҜгҖҒM&AеҸ–еј•гҒ«иӨҮйӣ‘жҖ§гӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒҷдёҖж–№гҒ§гҖҒEUжҢҮд»ӨгҒ«еҹәгҒҘгҒҸжҒ©жҒөгӮӮдә«еҸ—гҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеҲ©зӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгӮӘгғ©гғігғҖгҒҜдё–з•Ңжңүж•°гҒ®еәғзҜ„гҒӘз§ҹзЁҺжқЎзҙ„гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮ’ж§ӢзҜүгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒ100гӮ«еӣҪд»ҘдёҠгҒЁгҒ®й–“гҒ§дәҢйҮҚиӘІзЁҺгҒ®еӣһйҒҝгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҹжқЎзҙ„гӮ’з· зөҗгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®зӮ№гҒҜгҖҒеӣҪйҡӣзҡ„гҒӘдәӢжҘӯеҶҚз·ЁгӮ„жҢҒж ӘдјҡзӨҫиЁӯз«ӢгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒеӨ§гҒҚгҒӘзЁҺеӢҷдёҠгҒ®еҲ©зӮ№гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жң¬иЁҳдәӢгҒҜгҖҒгӮӘгғ©гғігғҖгҒ®M&Aй–ўйҖЈжі•еҲ¶гӮ’еҢ…жӢ¬зҡ„гҒ«и§ЈиӘ¬гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮиЎЁйқўзҡ„гҒӘжі•д»Өжғ…е ұгҒ®жҸҗдҫӣгҒ«з•ҷгҒҫгӮүгҒҡгҖҒдјҡзӨҫжі•гҖҒеҠҙеғҚжі•гҖҒ競дәүжі•гҖҒзҹҘзҡ„иІЎз”ЈжЁ©жі•гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹй–ўйҖЈеҲҶйҮҺгӮ’з¶Ізҫ…гҒҷгӮӢгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒжңҖж–°гҒ®жі•ж”№жӯЈгҖҒйҮҚиҰҒгҒӘжңҖй«ҳиЈҒеҲӨдҫӢгҖҒгҒқгҒ—гҒҰж—Ҙжң¬гҒ®жҠ•иіҮ家гҒҢзү№гҒ«з•ҷж„ҸгҒҷгҒ№гҒҚе®ҹеӢҷдёҠгҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒ«з„ҰзӮ№гӮ’еҪ“гҒҰгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еӨҡи§’зҡ„гҒӘеҲҶжһҗгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒгӮӘгғ©гғігғҖгҒ®иӨҮйӣ‘гҒӘжі•зҡ„з’°еўғгӮ’д№—гӮҠи¶ҠгҒҲгҖҒM&AгӮ’жҲҗеҠҹиЈҸгҒ«йҒӮиЎҢгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®е®ҹи·өзҡ„гҒӘжҢҮйҮқгӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒгӮӘгғ©гғігғҖгҒ®еҢ…жӢ¬зҡ„гҒӘжі•еҲ¶еәҰгҒ®жҰӮиҰҒгҒҜдёӢиЁҳиЁҳдәӢгҒ«гҒҰгҒҫгҒЁгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®зӣ®ж¬Ў
гӮӘгғ©гғігғҖгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢM&AеҸ–еј•гҒ®жі•зҡ„жҖ§иіӘгҒЁгғ—гғӯгӮ»гӮ№
ж ӘејҸиӯІжёЎпјҲShare DealпјүгҒЁдәӢжҘӯиӯІжёЎпјҲAsset Dealпјү
гӮӘгғ©гғігғҖгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢM&AеҸ–еј•гҒҜгҖҒдё»гҒ«ж ӘејҸиӯІжёЎгҒЁдәӢжҘӯиӯІжёЎгҒ®2гҒӨгҒ®еҪўж…ӢгҒ§е®ҹиЎҢгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®еҸ–еј•жүӢжі•гҒҜгҖҒжі•зҡ„жүӢз¶ҡгҒҚгҖҒгғӘгӮ№гӮҜгҒ®жүҝз¶ҷгҖҒгҒҠгӮҲгҒій–ўдҝӮиҖ…гҒ®еҪ№еүІгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰж №жң¬зҡ„гҒӘйҒ•гҒ„гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жҠ•иіҮ家гҒҜгҒ“гӮҢгӮүгҒ®е·®з•°гӮ’ж·ұгҒҸзҗҶи§ЈгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
ж ӘејҸиӯІжёЎгҒҜгҖҒдјҡзӨҫгҒ®е…Ёж ӘејҸгӮ’иӯІжёЎгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдјҡзӨҫгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ®жүҖжңүжЁ©гӮ’移転гҒҷгӮӢеҸ–еј•гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҸ–еј•гҒ®жңҖеӨ§гҒ®еҲ©зӮ№гҒҜгҖҒдјҡзӨҫгҒҢдҝқжңүгҒҷгӮӢгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®иіҮз”ЈгҖҒиІ еӮөгҖҒеҘ‘зҙ„гҖҒгҒҠгӮҲгҒізҹҘзҡ„иІЎз”ЈжЁ©пјҲIPпјүгҒҢгҖҒеҖӢеҲҘгҒ®з§»и»ўжүӢз¶ҡгҒҚгӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒӣгҒҡгҖҒиҮӘеӢ•зҡ„гҒ«иІ·гҒ„жүӢгҒ«еј•гҒҚз¶ҷгҒҢгӮҢгӮӢзӮ№гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒгӮӘгғ©гғігғҖгҒ®йқһе…¬й–ӢжңүйҷҗдјҡзӨҫпјҲBVпјүгӮ„е…¬й–ӢжңүйҷҗдјҡзӨҫпјҲNVпјүгҒ®ж ӘејҸгӮ’иӯІжёЎгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҖҒе…¬иЁјдәәпјҲcivil-law notaryпјүгҒ«гӮҲгӮӢгҖҢе…¬иЁјиӯІжёЎиЁјжӣёгҖҚпјҲnotarial transfer deedпјүгҒ®дҪңжҲҗгҒҢжі•зҡ„гҒ«зҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
дёҖж–№гҖҒдәӢжҘӯиӯІжёЎгҒҜгҖҒдјҡзӨҫгҒ®зү№е®ҡдәӢжҘӯгӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢеҖӢгҖ…гҒ®иіҮз”ЈгҒҠгӮҲгҒіиІ еӮөгӮ’гҖҒеҖӢеҲҘгҒ«иӯІжёЎгҒҷгӮӢеҸ–еј•гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жүӢжі•гҒ§гҒҜгҖҒ移転гҒҷгӮӢиіҮз”Јгғ»иІ еӮөгӮ’гҒҷгҒ№гҒҰзү№е®ҡгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ«еҝңгҒҳгҒҹ移転жүӢз¶ҡгҒҚгӮ’еҖӢеҲҘгҒ«е®ҢдәҶгҒ•гҒӣгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒдёҚеӢ•з”ЈгӮ„IPгҒ®з§»и»ўгҒ«гҒҜеҲҘйҖ”гҒ®зҷ»иЁҳгӮ„зҷ»йҢІжүӢз¶ҡгҒҚгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮдәӢжҘӯиӯІжёЎгҒ§гҒҜгҖҒ移転гҒҷгӮӢиіҮз”Јгғ»иІ еӮөгӮ’еҺіеҜҶгҒ«йҒёеҲҘгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶжҹ”и»ҹжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢдёҖж–№гҒ§гҖҒжүӢз¶ҡгҒҚгҒҢз…©йӣ‘гҒ«гҒӘгӮҠгҒҢгҒЎгҒ§гҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒеҫ“жҘӯе“ЎгҒ®з§»и»ўгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒеҠҙеғҚжі•дёҠгҒ®зү№еҲҘгҒӘиҰҸе®ҡгҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғҮгғҘгғјгғ»гғҮгғӘгӮёгӮ§гғігӮ№пјҲDue DiligenceпјүгҒ®зҜ„еӣІгҒЁйҮҚиҰҒжҖ§
гғҮгғҘгғјгғ»гғҮгғӘгӮёгӮ§гғігӮ№гҒҜгҖҒM&AеҸ–еј•гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҜҫиұЎдәӢжҘӯгҒ®дҫЎеҖӨгҒЁгғӘгӮ№гӮҜгӮ’и©•дҫЎгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®дёҚеҸҜж¬ гҒӘгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒиІ·гҒ„жүӢгҒҜеҜҫиұЎдјҡзӨҫгҒ®иЁҳйҢІгӮ„иІЎеӢҷгғҮгғјгӮҝгӮ’зІҫжҹ»гҒ—гҖҒжҸҗзӨәгҒ•гӮҢгҒҹжғ…е ұгҒҢжӯЈзўәгҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгҖҒгҒқгҒ—гҒҰжҪңеңЁзҡ„гҒӘгғӘгӮ№гӮҜгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒӘгҒ„гҒӢгӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮеЈІгӮҠжүӢгҒ«гҒҜгҖҒгғҮгғҘгғјгғ»гғҮгғӘгӮёгӮ§гғігӮ№дёӯгҒ«жӯЈзўәгҒӘжғ…е ұгӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢзҫ©еӢҷгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғҮгғҘгғјгғ»гғҮгғӘгӮёгӮ§гғігӮ№гҒҜгҖҒеҚҳгҒ«иІЎеӢҷгғ»жі•еӢҷгҒ®еҒҙйқўгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒйқһеёёгҒ«еәғзҜ„гҒӘеҲҶйҮҺгӮ’з¶Ізҫ…гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒйӣҮз”Ёгғ»е№ҙйҮ‘й–ўйҖЈгҒ®ж–ҮжӣёгҖҒзҹҘзҡ„иІЎз”ЈжЁ©гҖҒиҰҸеҲ¶жі•гҖҒз’°еўғй–ўйҖЈзҫ©еӢҷгҖҒдҝӮдәүдёӯгҒ®иЁҙиЁҹгҒӘгҒ©гҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮж ӘејҸиӯІжёЎгҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®й …зӣ®гҒ«еҠ гҒҲгҖҒдјҡзӨҫгҒ®иЁҳйҢІгҖҒиӯ°дәӢйҢІгҖҒж Әдё»еҗҚз°ҝгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹдјҡзӨҫзө„з№”гҒ«й–ўгҒҷгӮӢдәӢй …гҒҢзү№гҒ«йҮҚиҰҒиҰ–гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
е…¬й–ӢдјҡзӨҫгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢM&AгҖҒзү№гҒ«ж•өеҜҫзҡ„иІ·еҸҺгҒ®е ҙеҗҲгҖҒгғҮгғҘгғјгғ»гғҮгғӘгӮёгӮ§гғігӮ№гҒ§еҲ©з”ЁеҸҜиғҪгҒӘжғ…е ұгҒҢйҷҗе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзү№еҫҙгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®е ҙеҗҲгҖҒиІ·гҒ„жүӢгҒҜйҖҡеёёгҖҒе…¬й–ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢжғ…е ұпјҲе№ҙж¬ЎгҒҠгӮҲгҒідёӯй–“иІЎеӢҷе ұе‘ҠжӣёгҒӘгҒ©пјүгҒ®гҒҝгҒ«дҫқеӯҳгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӘгғ©гғігғҖгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢM&AжҲҰз•ҘгӮ’зӯ–е®ҡгҒҷгӮӢйҡӣгҖҒеҸ–еј•жүӢжі•гҒ®йҒёжҠһгҒҜгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢжүӢз¶ҡгҒҚгҒ®е®№жҳ“гҒ•гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгғҮгғҘгғјгғ»гғҮгғӘгӮёгӮ§гғігӮ№гҒ®зҜ„еӣІгҒЁгҖҒеҸ–еј•еҫҢгҒ®гғӘгӮ№гӮҜжүҝз¶ҷгҒ«еӨ§гҒҚгҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮж ӘејҸиӯІжёЎгҒ§гҒҜгҖҒдјҡзӨҫгҒЁгҒ„гҒҶгҖҢз®ұгҖҚгҒ®жүҖжңүжЁ©гҒҢ移転гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҫ“жҘӯе“ЎеҘ‘зҙ„гӮ„зҹҘзҡ„иІЎз”ЈжЁ©гҒҜиҮӘеӢ•зҡ„гҒ«иІ·гҒ„жүӢгҒ«еј•гҒҚз¶ҷгҒҢгӮҢгҖҒйӣҮз”Ёй–ўйҖЈгҒ®з¶ҷз¶ҡзҡ„гҒӘиІ¬д»»гҒҜеҜҫиұЎдјҡзӨҫгҒҢиІ гҒ„з¶ҡгҒ‘гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒдәӢжҘӯиӯІжёЎгҒ§гҒҜгҖҒеҖӢгҖ…гҒ®иіҮз”Јгғ»иІ еӮөгҒ®з§»и»ўжүӢз¶ҡгҒҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒзү№гҒ«гҖҢдәӢжҘӯгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еҗҢдёҖжҖ§гӮ’з¶ӯжҢҒгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒеҠҙеғҚжі•дёҠгҒ®гҖҢдәӢжҘӯиӯІжёЎгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҫ“жҘӯе“Ўдҝқиӯ·иҰҸе®ҡпјҲTUPEпјүгҖҚгҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҖҒеҫ“жҘӯе“ЎгҒҢжі•еҫӢгҒ®дҪңз”ЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиҮӘеӢ•зҡ„гҒ«иІ·гҒ„жүӢгҒ«з§»и»ўгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®зөҗжһңгҖҒдәӢжҘӯиӯІжёЎгҒ®е ҙеҗҲгҖҒиІ·гҒ„жүӢгҒҜ移転еүҚгҒ«з”ҹгҒҳгҒҹйӣҮз”ЁеҘ‘зҙ„дёҠгҒ®зҫ©еӢҷгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒеЈІгӮҠжүӢгҒЁйҖЈеёҜгҒ—гҒҰиІ¬д»»гӮ’иІ гҒҶеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгҒ“гҒ®гғӘгӮ№гӮҜгҒҜж ӘејҸиӯІжёЎгӮҲгӮҠгӮӮйЎ•еңЁеҢ–гҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒеҸ–еј•жүӢжі•гҒ®йҒёжҠһгҒҜгҖҒеҠҙеғҚй–ўйҖЈгғӘгӮ№гӮҜгҒ®иіӘгҒЁйҮҸгӮ’ж №жң¬гҒӢгӮүеӨүгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҹдёҠгҒ§гҖҒж…ҺйҮҚгҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгӮӢгҒ№гҒҚгҒ§гҒҷгҖӮВ
дё»иҰҒгҒӘM&AеҘ‘зҙ„ж–Үжӣё
гӮӘгғ©гғігғҖгҒ§гҒ®M&AеҸ–еј•гҒ§гҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдё»иҰҒгҒӘеҘ‘зҙ„ж–ҮжӣёгҒҢз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҫгҒҷпјҡ
- з§ҳеҜҶдҝқжҢҒеҘ‘зҙ„жӣёпјҲNon-disclosure agreementпјүпјҡгғҮгғҘгғјгғ»гғҮгғӘгӮёгӮ§гғігӮ№гҒ§е…ұжңүгҒ•гӮҢгӮӢж©ҹеҜҶжғ…е ұгҒ®дҝқиӯ·гӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
- еҹәжң¬еҗҲж„ҸжӣёпјҲLetter of intent/Term sheetпјүпјҡдәӨжёүжүӢз¶ҡгҒҚгҒ«й–ўгҒҷгӮӢж„Ҹеҗ‘гӮ’ж–ҮжӣёеҢ–гҒ—гҖҒзӢ¬еҚ дәӨжёүжЁ©гӮ„ж©ҹеҜҶдҝқжҢҒгҒӘгҒ©гҒ®жқЎд»¶гӮ’е®ҡгӮҒгҒҫгҒҷгҖӮ
- ж ӘејҸ/дәӢжҘӯеЈІиІ·еҘ‘зҙ„жӣёпјҲSale and purchase agreementпјүпјҡеҸ–еј•гҒ®жңҖзөӮзҡ„гҒӘжқЎд»¶гҖҒиЎЁжҳҺдҝқиЁјпјҲwarranties and indemnitiesпјүгҖҒиІ·еҸҺеҫҢгҒ®иӘҝж•ҙжқЎй …гҒӘгҒ©гӮ’и©ізҙ°гҒ«иҰҸе®ҡгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
- е…¬иЁјиӯІжёЎиЁјжӣёпјҲNotarial deedsпјүпјҡж ӘејҸиӯІжёЎгҒ®е ҙеҗҲгҒ«жі•зҡ„гҒ«еҝ…й ҲгҒЁгҒӘгӮӢж–ҮжӣёгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӘгғ©гғігғҖM&Aй–ўйҖЈжі•иҰҸгҒ®и§ЈиӘ¬
дјҡзӨҫжі•пјҲDutch Civil Code – DCCпјү
гӮӘгғ©гғігғҖгҒ®дјҡзӨҫжі•гҒҜгҖҒгӮӘгғ©гғігғҖж°‘жі•е…ёпјҲDCCпјүгҒ®з¬¬2е·»гҒ«иҰҸе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒM&AеҸ–еј•гҒ®жі•зҡ„жһ зө„гҒҝгҒ®ж ёеҝғгӮ’гҒӘгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жі•еҫӢгҒҜгҖҒж ӘејҸгҖҒдәӢжҘӯгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜиіҮз”ЈгҒ®иіје…ҘгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжі•зҡ„жһ зө„гҒҝгӮ’е®ҡгӮҒгҖҒзү№гҒ«йқһе…¬й–ӢпјҲprivateпјүеҸ–еј•гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҪ“дәӢиҖ…гҒҢиҮӘз”ұгҒ«еҸ–еј•жқЎд»¶гӮ’еҗҲж„ҸгҒ§гҒҚгӮӢгҖҢеҘ‘зҙ„иҮӘз”ұгҒ®еҺҹеүҮгҖҚгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
йҮҚиҰҒгҒӘеҸ–еј•гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢж Әдё»гҒҠгӮҲгҒіеҸ–з· еҪ№дјҡгҒ®еҪ№еүІгҒҜгҖҒDCCгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰи©ізҙ°гҒ«иҰҸе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮDCC第2е·»гҒҜгҖҒзү№е®ҡгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘеҸ–еј•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰж Әдё»з·ҸдјҡгҒ®жүҝиӘҚгӮ’иҰҒжұӮгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒе…¬й–ӢдјҡзӨҫгҒ®е ҙеҗҲгҖҒгҒқгҒ®гӮігғјгғқгғ¬гғјгғҲгӮ¬гғҗгғҠгғігӮ№гӮігғјгғүгҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҖҒгҖҢcomply or explainгҖҚпјҲйҒөе®ҲгҒҷгӮӢгҒӢгҖҒиӘ¬жҳҺгҒҷгӮӢгҒӢпјүгҒЁгҒ„гҒҶеҺҹеүҮгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒжңҖе–„гҒ®ж…ЈиЎҢгӮ’е®ҡгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӘгғ©гғігғҖгҒ®дјҡзӨҫжі•гҒ«гҒҜгҖҒгӮ°гғ«гғјгғ—дјҒжҘӯгҒ«зү№жңүгҒ®жі•зҡ„еҲ¶еәҰгҒЁгҒ—гҒҰгҖҢ403-DeclarationгҖҚгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒDCC第2е·»403жқЎгҒ«еҹәгҒҘгҒҸгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒгӮӘгғ©гғігғҖгҒ®еӯҗдјҡзӨҫгҒҢиҰӘдјҡзӨҫгҒӢгӮүгҒ®еӮөеӢҷеұҘиЎҢдҝқиЁјпјҲDeclaration of Joint and Several LiabilityпјүгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒиҰӘдјҡзӨҫгҒ®йҖЈзөҗжұәз®—жӣёгҒ«еӯҗдјҡзӨҫгҒ®иІЎеӢҷжғ…е ұгҒҢеҗ«гӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жқЎд»¶гҒ«гҖҒеӯҗдјҡзӨҫгҒҢеҖӢеҲҘгҒ®е№ҙж¬Ўжұәз®—е ұе‘ҠжӣёгҒ®дҪңжҲҗгғ»е…¬й–Ӣзҫ©еӢҷгӮ’е…ҚйҷӨгҒ•гӮҢгӮӢеҲ¶еәҰгҒ§гҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®еҲ¶еәҰгҒҜжі•зҡ„гғӘгӮ№гӮҜгӮ’дјҙгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮиҰӘдјҡзӨҫгҒҜгҖҒ403-DeclarationгӮ’жҸҗеҮәгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеӯҗдјҡзӨҫгҒ®гҖҢжі•еҫӢиЎҢзӮәгҒӢгӮүз”ҹгҒҳгӮӢеӮөеӢҷгҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰйҖЈеёҜиІ¬д»»гӮ’иІ гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®дҝқиЁјгҒҢж’ӨеӣһгҒ•гӮҢгҒҹеҫҢгӮӮгҖҒж’ӨеӣһеүҚгҒ«зҷәз”ҹгҒ—гҒҹеӮөеӢҷгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢгҖҢж®ӢеӯҳиІ¬д»»гҖҚгҒҜеӯҳз¶ҡгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨдҫӢгҒҜгҖҒ403-DeclarationгҒ«еҹәгҒҘгҒҸиҰӘдјҡзӨҫгҒёгҒ®и«ӢжұӮгҒҢгҖҒд»–гҒ®еӮөжЁ©иҖ…гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰжі•еҫӢдёҠгҒ®е„Әе…ҲжЁ©гӮ’жҢҒгҒҹгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮ’жҳҺзўәгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҲӨдҫӢгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®еҲ¶еәҰгҒҢжҢҒгҒӨдҝқиӯ·гҒ®йҷҗз•ҢгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеӮөжЁ©иҖ…гҒ®з«Ӣе ҙгҒӢгӮүгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒиҰӘдјҡзӨҫгҒ®йҖЈеёҜдҝқиЁјгҒҜд»–гҒ®еӮөжЁ©иҖ…гҒЁе№ізӯүгҒ«жүұгӮҸгӮҢгӮӢгҒ«йҒҺгҒҺгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶдәӢе®ҹгӮ’иӘҚиӯҳгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҠҙеғҚжі•
гӮӘгғ©гғігғҖгҒ®еҠҙеғҚжі•гҒҜгҖҒдәӢжҘӯиӯІжёЎгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҫ“жҘӯе“Ўдҝқиӯ·гҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҖҒEUгҒ®гҖҢдәӢжҘӯиӯІжёЎгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҫ“жҘӯе“Ўдҝқиӯ·жҢҮд»ӨпјҲAcquired Rights DirectiveпјүгҖҚгӮ’гӮӘгғ©гғігғҖ民法典第7編第662жқЎгҒӢгӮү第666жқЎгҒ«е®ҹиЈ…гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®иҰҸе®ҡгҒҜгҖҒгҖҢдәӢжҘӯгҒ®зөҢжёҲзҡ„е®ҹдҪ“гҖҚгҒҢеҗҢдёҖжҖ§гӮ’з¶ӯжҢҒгҒ—гҒҹгҒҫгҒҫ移転гҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒ«йҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®жі•еҫӢгҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢе ҙеҗҲгҖҒеҫ“жҘӯе“ЎгҒ®жЁ©еҲ©гҒЁзҫ©еӢҷгҒҜжі•еҫӢгҒ®дҪңз”ЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиҮӘеӢ•зҡ„гҒ«иІ·гҒ„жүӢгҒёгҒЁз§»и»ўгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒйӣҮз”ЁеҘ‘зҙ„гҒ®жқЎд»¶гҖҒиіғйҮ‘гҖҒгҒҠгӮҲгҒігҒқгҒ®д»–гҒ®жЁ©еҲ©пјҲгҒҹгҒ гҒ—гҖҒе№ҙйҮ‘еҲ¶еәҰгҒ«гҒҜдҫӢеӨ–гҒҢгҒӮгӮӢпјүгҒҢгҖҒM&AеҫҢгӮӮз¶ӯжҢҒгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
дәӢжҘӯиӯІжёЎгҒҢгҖҒзөҢе–¶йҷЈгҒ«гӮҲгӮӢеҫ“жҘӯе“ЎгҒёгҒ®жғ…е ұжҸҗдҫӣгғ»еҚ”иӯ°зҫ©еӢҷгӮ’зҷәз”ҹгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘзӮ№гҒ§гҒҷгҖӮдјҒжҘӯгҒҢ50дәәд»ҘдёҠгҒ®еҫ“жҘӯе“ЎгӮ’жҠұгҒҲгӮӢе ҙеҗҲгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜеҠҙеғҚеҚ”зҙ„гҒ«иҰҸе®ҡгҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҖҒзӨҫдјҡзөҢжёҲи©•иӯ°дјҡпјҲSERпјүгҒҠгӮҲгҒіеҠҙеғҚзө„еҗҲгҒ«M&AгӮ’йҖҡзҹҘгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒзөҢе–¶йҷЈгҒҜеҫ“жҘӯе“Ўд»ЈиЎЁж©ҹй–ўпјҲгғҜгғјгӮҜгӮ№гғ»гӮ«гӮҰгғігӮ·гғ«пјүгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒM&AгҒ®ж„ҸеӣігҖҒзҗҶз”ұгҖҒеҫ“жҘӯе“ЎгҒёгҒ®жі•зҡ„гғ»зөҢжёҲзҡ„гғ»зӨҫдјҡзҡ„еҪұйҹҝгҖҒгҒҠгӮҲгҒіи¬ӣгҒҳгӮүгӮҢгӮӢжҺӘзҪ®гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒдәӢеүҚгҒ«еҚ”иӯ°гғ»жғ…е ұжҸҗдҫӣгҒҷгӮӢзҫ©еӢҷгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
M&AеҸ–еј•гӮ’зҗҶз”ұгҒЁгҒҷгӮӢеҫ“жҘӯе“ЎгҒ®и§ЈйӣҮгҒҜжі•еҫӢгҒ§зҰҒжӯўгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒдәӢжҘӯгҒ®еҶҚз·ЁпјҲж•ҙзҗҶи§ЈйӣҮгҒӘгҒ©пјүгҒҢгҖҢзөҢжёҲзҡ„гҖҒжҠҖиЎ“зҡ„гҖҒгҒҫгҒҹгҒҜзө„з№”зҡ„зҗҶз”ұгҖҚгҒ«еҹәгҒҘгҒҸе ҙеҗҲгҒҜиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒе®ҹеӢҷдёҠгҒҜгҖҒM&AеҫҢгҒ®еҶҚз·ЁгҒҜгҖҒ移転гҒЁгҒҜз„Ўй–ўдҝӮгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒҷгҒҹгӮҒгҖҒйҖҡеёё6гҒӢжңҲгҒӢгӮү12гҒӢжңҲеҫҢгҒ«е®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
競дәүжі•гғ»еӣҪ家е®үе…ЁдҝқйҡңеҜ©жҹ»
гӮӘгғ©гғігғҖгҒ§гҒ®M&AеҸ–еј•гҒҜгҖҒгӮӘгғ©гғігғҖж¶ҲиІ»иҖ…гғ»еёӮе ҙеәҒпјҲACMпјүгҒ«гӮҲгӮӢ競дәүжі•еҜ©жҹ»гҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҜ©жҹ»гҒ®еҝ…иҰҒжҖ§гҒҜгҖҒй–ўдҝӮдјҒжҘӯгҒ®еЈІдёҠй«ҳгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰжұәе®ҡгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒй–ўдҝӮдјҒжҘӯгҒ®е…Ёдё–з•ҢгҒ§гҒ®йҖЈзөҗеЈІдёҠй«ҳгҒҢ1е„„5,000дёҮгғҰгғјгғӯи¶…гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒӢгҒӨгҖҒгҒқгҒ®гҒҶгҒЎе°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮ2зӨҫгҒҢгӮӘгғ©гғігғҖеӣҪеҶ…гҒ§гҒқгӮҢгҒһгӮҢ3,000дёҮгғҰгғјгғӯи¶…гҒ®еЈІдёҠгӮ’йҒ”жҲҗгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҖҒеұҠеҮәгҒҢзҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮеҜ©жҹ»гҒҜйҖҡеёёгҖҒгғ•гӮ§гғјгӮә1пјҲ4йҖұй–“пјүгҒЁгғ•гӮ§гғјгӮә2пјҲ13йҖұй–“пјүгҒ®2ж®өйҡҺгҒ§иЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
EUгҒ®й–ҫеҖӨгӮ’жәҖгҒҹгҒҷеҸ–еј•гҒҜгҖҒEU競дәүжі•гҒ®дёӢгҒ§еҜ©жҹ»гҒ•гӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгӮӘгғ©гғігғҖеӣҪеҶ…гҒ§гҒ®еұҠеҮәгҒҜдёҚиҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒEU競дәүжі•гҒ«гҒҜгҖҢDutch ClauseгҖҚпјҲECMR第22жқЎпјүгҒЁгҒ„гҒҶиҰҸе®ҡгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒеӣҪеҶ…гҒ«з«¶дәүжі•гӮ’жҢҒгҒҹгҒӘгҒ„еҠ зӣҹеӣҪгҒҢгҖҒEUгҒ®й–ҫеҖӨгӮ’дёӢеӣһгӮӢM&AеҸ–еј•гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒеҹҹеҶ…иІҝжҳ“гҒ«еҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҖҒ競дәүгӮ’и‘—гҒ—гҒҸйҳ»е®ігҒҷгӮӢгҒҠгҒқгӮҢгҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҖҒEU委員дјҡгҒ«еҜ©жҹ»гӮ’иҰҒи«ӢгҒ§гҒҚгӮӢгғЎгӮ«гғӢгӮәгғ гҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
иҝ‘е№ҙгҒ®гӮӘгғ©гғігғҖгҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒ競дәүжі•дёҠгҒ®й–ҫеҖӨгӮ’жәҖгҒҹгҒ•гҒӘгҒ„M&AеҸ–еј•гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒеӣҪ家е®үе…ЁдҝқйҡңгҒЁеӣҪеҶ…еёӮе ҙ競дәүгҒ®иҰізӮ№гҒӢгӮүзӣЈиҰ–гӮ’еј·еҢ–гҒҷгӮӢеӮҫеҗ‘гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒеӨ–еӣҪжҠ•иіҮгӮ’жӯ“иҝҺгҒ—гҒӨгҒӨгӮӮгҖҒиҮӘеӣҪгҒ®йҮҚиҰҒеҲ©зӣҠгӮ’е®ҲгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒгӮҲгӮҠйҳІиЎӣзҡ„гҒӘж”ҝзӯ–гҒёгҒ®и»ўжҸӣгӮ’зӨәе”ҶгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ®иұЎеҫҙгҒҢгҖҒ2023е№ҙ6жңҲ1ж—ҘгҒ«ж–ҪиЎҢгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢеӣҪ家е®үе…ЁдҝқйҡңеҜ©жҹ»жі•пјҲVifo ActпјүгҖҚгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жі•еҫӢгҒҜгҖҒ競дәүжі•дёҠгҒ®й–ҫеҖӨгҒЁгҒҜз„Ўй–ўдҝӮгҒ«гҖҒеӨ–еӣҪгҒҠгӮҲгҒіеӣҪеҶ…гҒ®жҠ•иіҮгҒҢгҖҢеӣҪ家е®үе…ЁдҝқйҡңгҒ«гғӘгӮ№гӮҜгӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒҷеҸҜиғҪжҖ§гҖҚгӮ’еҜ©жҹ»гҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮеҜ©жҹ»гҒ®еҜҫиұЎгҒҜгҖҒйҳІиЎӣй–ўйҖЈгҖҒйҮҚиҰҒгӮӨгғігғ•гғ©пјҲгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгҖҒйҖҡдҝЎгҖҒз©әжёҜгҒӘгҒ©пјүгҖҒгҒҠгӮҲгҒізү№е®ҡгҒ®гҖҢгӮ»гғігӮ·гғҶгӮЈгғ–жҠҖиЎ“гҖҚеҲҶйҮҺпјҲAIгҖҒйҮҸеӯҗжҠҖиЎ“гҖҒеҚҠе°ҺдҪ“гҖҒгғҗгӮӨгӮӘгғҶгӮҜгғҺгғӯгӮёгғјгҒӘгҒ©пјүгҒ®дјҒжҘӯгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ•гӮүгҒ«гҖҒ2025е№ҙ9жңҲ1ж—Ҙд»ҘйҷҚгҖҒACMгҒҜзӢ¬еҚ зҰҒжӯўжі•з¬¬24жқЎгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒй–ҫеҖӨд»ҘдёӢгҒ®еҸ–еј•гӮ’еҜ©жҹ»гҒҷгӮӢжЁ©йҷҗгӮ’еј·еҢ–гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®ж”№жӯЈгҒҜгҖҒгӮӘгғ©гғігғҖеӣҪеҶ…еёӮе ҙгҒ®гҒҝгҒ«еҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢеҸ–еј•гӮӮеҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒACMгҒ®зӣЈиҰ–зҜ„еӣІгӮ’еәғгҒ’гӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҜгҖҒM&AгҒ®иЁҲз”»еҲқжңҹж®өйҡҺгҒ§гҖҒ競дәүжі•дёҠгҒ®й–ҫеҖӨгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒеҜҫиұЎдәӢжҘӯгҒҢVifo ActгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢгҒӢеҗҰгҒӢгҖҒгҒҫгҒҹе°ҶжқҘзҡ„гҒ«ACMгҒ®еҜ©жҹ»гӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒӢеҗҰгҒӢгӮ’гҖҒдәӢеүҚгҒ«еҫ№еә•зҡ„гҒ«зўәиӘҚгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒе°ҸиҰҸжЁЎгҒӘгғҶгғғгӮҜдјҒжҘӯгӮ„гӮ№гӮҝгғјгғҲгӮўгғғгғ—дјҒжҘӯгҒёгҒ®жҠ•иіҮгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒ競дәүжі•дёҠгҒ®еұҠеҮәгҒҢдёҚиҰҒгҒЁеҲӨж–ӯгҒ•гӮҢгҒҰгӮӮгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®ж–°гҒ—гҒ„еҜ©жҹ»еҲ¶еәҰгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҸ–еј•гҒ®дәҲжё¬еҸҜиғҪжҖ§гҒҢдҪҺдёӢгҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒжіЁж„ҸгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
зҹҘзҡ„иІЎз”ЈжЁ©жі•
гӮӘгғ©гғігғҖгҒ®зҹҘзҡ„иІЎз”ЈжЁ©жі•гҒҜгҖҒзү№иЁұжЁ©гҖҒе•ҶжЁҷжЁ©гҖҒи‘—дҪңжЁ©гҒӘгҒ©гҒ®еӣҪеҶ…жі•гҒЁгҖҒEUзөұдёҖзү№иЁұеҲ¶еәҰгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹEUжі•гҒҢе…ұеӯҳгҒҷгӮӢдәҢйҮҚж§ӢйҖ гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮM&AеҸ–еј•гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒзҹҘзҡ„иІЎз”ЈжЁ©пјҲIPпјүгҒ®з§»и»ўгҒҜйҮҚиҰҒгҒӘиҰҒзҙ гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®жүӢз¶ҡгҒҚгҒҜзҹҘзҡ„財産権移転еҘ‘зҙ„пјҲIntellectual Property Transfer AgreementпјүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиҰҸе®ҡгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҘ‘зҙ„гҒҜгҖҒгӮӘгғ©гғігғҖж°‘жі•е…ёгҒҠгӮҲгҒіеҗ„зҹҘзҡ„иІЎз”ЈжЁ©жі•гҒ«жә–жӢ гҒ—гҒҰдҪңжҲҗгҒ•гӮҢгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғҮгғҘгғјгғ»гғҮгғӘгӮёгӮ§гғігӮ№гҒ§гҒҜгҖҒеҜҫиұЎдјҒжҘӯгҒҢдҝқжңүгҒҷгӮӢIPгҒ®жңүеҠ№жҖ§гҖҒ第дёүиҖ…гҒ®жЁ©еҲ©дҫөе®ігҒ®жңүз„ЎгҖҒж—ўеӯҳгҒ®гғ©гӮӨгӮ»гғігӮ№еҘ‘зҙ„гҒӘгҒ©гӮ’з¶ҝеҜҶгҒ«иӘҝжҹ»гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒи‘—дҪңжЁ©гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгӮӘгғ©гғігғҖгҒ®и‘—дҪңжЁ©жі•пјҲAuteurswetпјүгҒҢгҖҒи‘—дҪңиҖ…дәәж јжЁ©пјҲmoral rightsпјүгҒҢе®Ңе…ЁгҒ«з§»и»ўгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„жЁ©еҲ©гҒЁиҰҸе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҒ«жіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒЁгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘзӣёйҒ•зӮ№гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒM&AеҫҢгҒ®дәӢжҘӯйҒӢе–¶гҖҒдҫӢгҒҲгҒ°и‘—дҪңзү©гӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹиЈҪе“Ғй–ӢзҷәгӮ„гғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒи‘—дҪңиҖ…гҒ®еҗҢж„ҸгҒҢеј•гҒҚз¶ҡгҒҚеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒеҪұйҹҝгӮ’еҸҠгҒјгҒҷеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮВ
гӮӘгғ©гғігғҖM&Aй–ўйҖЈжі•еҲ¶гҒ®жңҖж–°еӢ•еҗ‘гҒЁйҮҚиҰҒеҲӨдҫӢ

еҸёжі•еҲӨж–ӯгҒ®жҪ®жөҒ
гӮӘгғ©гғігғҖгҒ®жңҖй«ҳиЈҒгҒҜгҖҒM&AгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮҝгғғгӮҜгӮ№гғ»гғ—гғ©гғігғӢгғігӮ°гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒеҪўејҸзҡ„гҒӘжі•зҡ„иҰҒ件гҒ®е……и¶ігҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгҖҢзөҢжёҲзҡ„е®ҹдҪ“гҖҚгҒЁгҖҢдәӢжҘӯдёҠгҒ®еҗҲзҗҶжҖ§гҖҚгӮ’еҺіж јгҒ«и©•дҫЎгҒҷгӮӢеӮҫеҗ‘гӮ’еј·гӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒйҒҺеҺ»гҒ®з§ҹзЁҺеӣһйҒҝзҡ„гҒӘгӮ№гӮӯгғјгғ гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҸёжі•гҒ®ж–ӯеӣәгҒҹгӮӢе§ҝеӢўгҒ®иЎЁгӮҢгҒ§гҒҷгҖӮ
M&AиһҚиіҮгҒ®еҲ©еӯҗжҺ§йҷӨгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжұәгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®жҪ®жөҒгӮ’иұЎеҫҙгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҲӨдҫӢгҒ§гҒҜгҖҒеҸҚгғҷгғјгӮ№гӮЁгғӯгғјгӮёгғ§гғіиҰҸе®ҡпјҲCITA第10aжқЎпјүгҒ®еҪўејҸзҡ„гҒӘиҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒ—гҖҒдәӢжҘӯдёҠгҒ®еҗҲзҗҶжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒЁиҰӢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҹеҸ–еј•гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒжңҖй«ҳиЈҒгҒҜгҖҢfraus legisгҖҚпјҲжі•гҒ®жҝ«з”ЁпјүгҒ®еҺҹеүҮгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒеҲ©еӯҗжҺ§йҷӨгҒҢжӢ’еҗҰгҒ•гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
еҗҢж§ҳгҒ«гҖҒй…ҚеҪ“жәҗжіүзЁҺгҒ®е…ҚйҷӨгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжұәгӮӮгҖҒгҒ“гҒ®еӮҫеҗ‘гӮ’иЈҸд»ҳгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҲӨжұәгҒ§гҒҜгҖҒй…ҚеҪ“жәҗжіүзЁҺгҒ®е…ҚйҷӨгӮ’иӘҚгӮҒгӮӢгҖҢжҝ«з”ЁйҳІжӯўиҰҸе®ҡгҖҚгҒ®йҒ©з”ЁеҲӨж–ӯгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҖҢзөҢжёҲзҡ„е®ҹдҪ“гҒЁй–ўйҖЈжҖ§гҒ®гҒӘгҒ„дәәе·Ҙзҡ„гҒӘд»•зө„гҒҝгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгӮ’еҺіж јгҒ«еҜ©жҹ»гҒҷгӮӢж–№йҮқгҒҢзӨәгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮжңҖй«ҳиЈҒгҒҜгҖҒеҪ“еҲқгҒҜдәӢжҘӯдёҠгҒ®еҗҲзҗҶжҖ§гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒзҠ¶жіҒеӨүеҢ–гҒ«гӮҲгӮҠгҒқгҒ®д»•зө„гҒҝгҒҢгҖҢдәәе·Ҙзҡ„гҖҚгҒЁиҰӢгҒӘгҒ•гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еҲӨдҫӢгҒҜгҖҒжҝ«з”ЁгғҶгӮ№гғҲгҒҢеҸ–еј•е®ҹиЎҢжҷӮгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ®зҠ¶жіҒеӨүеҢ–гӮ’иҖғж…®гҒҷгӮӢгҖҢз¶ҷз¶ҡзҡ„гҒӘгғҶгӮ№гғҲгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒе®ҡжңҹзҡ„гҒӘиҰӢзӣҙгҒ—гҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгӮүгҒ®еҲӨдҫӢгҒҜгҖҒгӮҝгғғгӮҜгӮ№гғ»гғ—гғ©гғігғӢгғігӮ°гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҚҳгҒ«жі•д»ӨгҒ®жқЎж–ҮгӮ’еҪўејҸзҡ„гҒ«йҒөе®ҲгҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒеҸ–еј•гҒ®иғҢеҫҢгҒ«гҒӮгӮӢгҖҢе•ҶжҘӯзҡ„гғ»зөҢжёҲзҡ„еҗҲзҗҶжҖ§гҖҚгӮ’еёёгҒ«иЁҳйҢІгҒ—гҖҒиӘ¬жҳҺгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәе”ҶгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
M&Aй–ўйҖЈиІ»з”ЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒжҲҗеҠҹгғ»еӨұж•—гҒ«й–ўгӮҸгӮүгҒҡгҖҒй–ўйҖЈиІ»з”ЁпјҲеҶ…йғЁгӮігӮ№гғҲгғ»еӨ–йғЁгӮігӮ№гғҲпјүгҒ®зЁҺеӢҷдёҠгҒ®еҸ–гӮҠжүұгҒ„гҒ«й–ўгҒҷгӮӢжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжұәгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҲӨжұәгҒҜгҖҒM&Aгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҢжҲҗеҠҹгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒй–ўйҖЈиІ»з”ЁгҒҜжҗҚйҮ‘дёҚз®—е…ҘгҒЁгҒӘгӮӢгҒҢгҖҒдәӨжёүгҒҢдёҚиӘҝгҒ«зөӮгӮҸгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҖҒзү№е®ҡгҒ®жқЎд»¶гҒ§иІ»з”ЁгҒҢжҗҚйҮ‘з®—е…ҘеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶи©ізҙ°гҒӘжҢҮйҮқгӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
Broadcom/VMwareиІ·еҸҺгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҲӨжұә
2024е№ҙгҖҒBroadcomгҒ«гӮҲгӮӢVMwareиІ·еҸҺеҫҢгҖҒгӮӘгғ©гғігғҖгҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҒҢдёӢгҒ—гҒҹеҲӨжұәгҒҜгҖҒM&AеҫҢгҒ®е•ҶжҘӯзҡ„жұәе®ҡгҒҢе…¬е…ұгҒ®еҲ©зӣҠгҒ«дёҺгҒҲгӮӢеҪұйҹҝгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгӮӘгғ©гғігғҖгҒ®еҸёжі•гҒҢеј·гҒ„е§ҝеӢўгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒҷз”»жңҹзҡ„гҒӘдәӢдҫӢгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
дәӢжЎҲгҒ®жҰӮиҰҒгҒҜгҖҒBroadcomгҒҢиІ·еҸҺеҫҢгҖҒгӮӘгғ©гғігғҖж”ҝеәңж©ҹй–ўгҒҢеҲ©з”ЁгҒҷгӮӢVMwareиЈҪе“ҒгҒ®гғ©гӮӨгӮ»гғігӮ№дҪ“зі»гӮ’гҖҒеҫ“жқҘгҒ®ж°ёз¶ҡгғ©гӮӨгӮ»гғігӮ№гҒӢгӮүгӮөгғ–гӮ№гӮҜгғӘгғ—гӮ·гғ§гғіеһӢгҒёеӨүжӣҙгҒ—гҖҒгӮөгғқгғјгғҲгӮ’дёӯж–ӯгҒҷгӮӢж–№йҮқгӮ’жү“гҒЎеҮәгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«з«ҜгӮ’зҷәгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒйҒ“и·ҜгҖҒж©ӢжўҒгҖҒж°ҙй–ҖгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹйҮҚиҰҒгӮӨгғігғ•гғ©гӮ’жүҖз®ЎгҒҷгӮӢж”ҝеәңж©ҹй–ўгҒҜгҖҒгӮ·гӮ№гғҶгғ 移иЎҢгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®зҢ¶дәҲжңҹй–“гҒЁгҒ—гҒҰ2е№ҙй–“гҒ®з¶ҷз¶ҡгӮөгғқгғјгғҲгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁдё»ејөгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
иЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒж”ҝеәңж©ҹй–ўгҒ®дё»ејөгӮ’иӘҚгӮҒгҖҒBroadcomгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒе№ҙйЎҚ176дёҮ5еҚғгғҰгғјгғӯгҒ®жңүе„ҹгӮөгғқгғјгғҲгӮ’2е№ҙй–“жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’е‘ҪгҒҳгӮӢеҲӨжұәгӮ’дёӢгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒгҖҢж°ёз¶ҡгғ©гӮӨгӮ»гғігӮ№еҘ‘зҙ„гҒ«еҹәгҒҘгҒҸгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®жңҹеҫ…гҒҜжӯЈеҪ“гҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҖҒгҒҠгӮҲгҒігҖҢBroadcomгҒҢе®ҹиіӘзҡ„гҒ«зӢ¬еҚ зҡ„гҒӘз«Ӣе ҙгӮ’жҝ«з”ЁгҒ—гҒҹгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гӮ’йҮҚиҰ–гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®еҲӨжұәгҒҜгҖҒгӮӘгғ©гғігғҖгҒ®еҸёжі•гҒҢгҖҒM&AеҫҢгҒ®е•ҶжҘӯзҡ„жұәе®ҡгҒҢе…¬е…ұгҒ®еҲ©зӣҠгҖҒзү№гҒ«йҮҚиҰҒгӮӨгғігғ•гғ©гҒ®е®үе®ҡжҖ§гӮ„гӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈгҒ«еҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢе ҙеҗҲгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’еҲ¶зҙ„гҒ—гҒҶгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеј·гҒ„е§ҝеӢўгӮ’зӨәгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒVifo ActгҒ«д»ЈиЎЁгҒ•гӮҢгӮӢеӣҪ家е®үе…ЁдҝқйҡңеҜ©жҹ»гҒ®жһ зө„гҒҝгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ®еҸёжі•еҲӨж–ӯгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮиЈҸд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҲӨдҫӢгҒҜгҖҒзү№гҒ«ITгҖҒйҖҡдҝЎгҖҒгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҲҶйҮҺгҒ®дјҒжҘӯгӮ’иІ·еҸҺгҒҷгӮӢйҡӣгҖҒиІ·еҸҺеҫҢгҒ®дәӢжҘӯзөұеҗҲиЁҲз”»гӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№жҸҗдҫӣж–№йҮқгҒҢгҖҒеҚҳзҙ”гҒӘе•ҶжҘӯзҡ„еҗҲзҗҶжҖ§гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒж”ҝеәңгӮ„еҸёжі•гҒҢйҮҚиҰ–гҒҷгӮӢе…¬е…ұзҡ„еҲ©зӣҠгҒЁеҗҲиҮҙгҒҷгӮӢгҒӢгӮ’ж…ҺйҮҚгҒ«жӨңиЁҺгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶйҮҚиҰҒгҒӘж•ҷиЁ“гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒ
жң¬и§ЈиӘ¬иЁҳдәӢгҒҜгҖҒгӮӘгғ©гғігғҖM&Aжі•еҲ¶гҒҢгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢжҲҗж–Үжі•е…ёгҒ®дҪ“зі»гҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгӮүгҒҡгҖҒеӢ•зҡ„гҒӘеҸёжі•еҲӨж–ӯгҒЁеӨүеҢ–гҒҷгӮӢеӣҪйҡӣжғ…еӢўпјҲзү№гҒ«еӣҪ家е®үе…ЁдҝқйҡңгҒ®йҮҚиҰ–пјүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҪўдҪңгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮзү№гҒ«гҖҒиҝ‘е№ҙгҒ®жңҖй«ҳиЈҒеҲӨдҫӢгҒҢгҖҒгӮҝгғғгӮҜгӮ№гғ»гғ—гғ©гғігғӢгғігӮ°гӮ„е•ҶжҘӯзҡ„жұәе®ҡгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҢзөҢжёҲзҡ„е®ҹдҪ“гҖҚгҒЁгҖҢе…¬е…ұзҡ„еҲ©зӣҠгҖҚгӮ’еҺіж јгҒ«и©•дҫЎгҒҷгӮӢеӮҫеҗ‘гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҢгӮӘгғ©гғігғҖгҒ§M&AгӮ’йҒӮиЎҢгҒҷгӮӢдёҠгҒ§гҖҒеҫ“жқҘгҒ®жі•еӢҷгғҮгғҘгғјгғ»гғҮгғӘгӮёгӮ§гғігӮ№гӮ’и¶…гҒҲгӮӢгҖҒгӮҲгӮҠж·ұгҒ„жҲҰз•Ҙзҡ„жҖқиҖғгӮ’жұӮгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәе”ҶгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ«гғҶгӮҙгғӘгғј: ITгғ»гғҷгғігғҒгғЈгғјгҒ®дјҒжҘӯжі•еӢҷ
гӮҝгӮ°: гӮӘгғ©гғігғҖзҺӢеӣҪжө·еӨ–дәӢжҘӯ