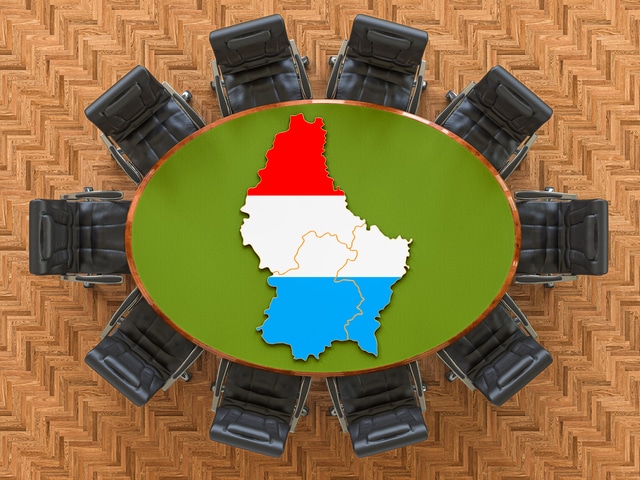ŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣õ╝ÜńżŠµ│Ģ2006Õ╣┤’╝łCompanies Act 2006’╝ēŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«µ│ĢńÜäńŠ®ÕŗÖ

ŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣Ńü¦Ńü«õ║ŗµźŁÕ▒Ģķ¢ŗŃü»ŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü½Ńü©ŃüŻŃü”ķŁģÕŖøńÜäŃü¬µ®¤õ╝ÜŃéÆń¦śŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüµłÉÕŖ¤Ńü«ķŹĄŃü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«µ│ĢńÜäµ×ĀńĄäŃü┐Ńü©Ńü»ńĢ░Ńü¬ŃéŗŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣Ńü«õ╝ÜńżŠµ│ĢŃĆüńē╣Ńü½ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«µ│ĢńÜäńŠ®ÕŗÖŃéƵĘ▒ŃüÅńÉåĶ¦ŻŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü½ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆ鵌źµ£¼õ╝üµźŁŃüīńø┤ķØóŃüÖŃéŗŃü¦ŃüéŃéŹŃüåŃĆüµ│ĢÕō▓ÕŁ”ŃĆüÕ«¤ÕŗÖµģŻĶĪīŃĆüŃüØŃüŚŃü”Ķ▓¼õ╗╗Ńü«ń»äÕø▓Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗµ▒║Õ«ÜńÜäŃü¬ńøĖķüĢńé╣ŃéÆńÉåĶ¦ŻŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü»ŃĆüŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣õ║ŗµźŁŃü½ŃüŖŃüæŃéŗµ│ĢńÜäŃā¬Ńé╣Ńé»ń«ĪńÉåŃü©Õ╝ĘÕø║Ńü¬Ńé│Ńā╝ŃāØŃā¼Ńā╝ŃāłŃā╗Ńé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣µ¦ŗń»ēŃéÆŃéĄŃāØŃā╝ŃāłŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
µ£¼Ķ©śõ║ŗŃü¦Ńü»ŃĆüŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣õ╝ÜńżŠµ│Ģ2006Õ╣┤Ńü½µłÉµ¢ćÕī¢ŃüĢŃéīŃü¤7ŃüżŃü«ńŠ®ÕŗÖŃéÆŃĆüŃüØŃü«µŁ┤ÕÅ▓ńÜäĶāīµÖ»ŃĆüŃé│ŃāóŃā│Ńā╗ŃāŁŃā╝Ńü©Ńü«ĶżćķøæŃü¬ķ¢óõ┐éµĆ¦ŃĆüŃüØŃüŚŃü”µ£Ćµ¢░Ńü«ÕłżõŠŗŃüīńż║ŃüÖńÅŠõ╗ŻńÜäŃü¬Ķ¬▓ķĪīŃéÆõ║żŃüłŃü”Ķ®│ń┤░Ńü½Ķ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
Ńü¬ŃüŖŃĆüŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣Ńü«Õīģµŗ¼ńÜäŃü¬µ│ĢÕłČÕ║”Ńü«µ”éĶ”üŃü»õĖŗĶ©śĶ©śõ║ŗŃü½Ńü”ŃüŠŃü©ŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«Ķ©śõ║ŗŃü«ńø«µ¼Ī
ŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣Ńé│ŃāóŃā│Ńā╗ŃāŁŃā╝Ńü«ķøåÕż¦µłÉŃü©ŃüŚŃü”Ńü«õ╝ÜńżŠµ│Ģ2006Õ╣┤
Ńé│ŃāóŃā│Ńā╗ŃāŁŃā╝ŃüŗŃéēµłÉµ¢ćµ│ĢŃüĖ
ŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«µ│ĢńÜäńŠ®ÕŗÖŃü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«ŃéłŃüåŃü¬Õż¦ķÖĖµ│Ģń│╗Ńü«µłÉµ¢ćµ│ĢÕģĖŃü½õĖĆÕģāńÜäŃü½Ķ”ÅÕ«ÜŃüĢŃéīŃü”ŃüŹŃü¤ŃéÅŃüæŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüķĢĘŃü䵣┤ÕÅ▓Ńü«õĖŁŃü¦Ńé│ŃāóŃā│Ńā╗ŃāŁŃā╝’╝łÕłżõŠŗµ│Ģ’╝ēŃü«ń®ŹŃü┐ķćŹŃüŁŃéÆķĆÜŃüśŃü”ńÖ║Õ▒ĢŃüŚŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéńē╣Ńü½ŃĆüÕÅŚĶ©ŚĶĆģ’╝łfiduciary’╝ēŃü©ŃüŚŃü”Ńü«ńŠ®ÕŗÖŃü»ŃĆüõ┐ĪĶ©Śµ│ĢŃü«µ│ĢńÉåŃéÆÕ¤║ńżÄŃü©ŃüŚŃü”ÕĮóµłÉŃüĢŃéīŃĆüŃĆīõ╝ÜńżŠŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗÕ┐ĀÕ«¤ńŠ®ÕŗÖŃĆŹŃéäŃĆīÕł®ńøŖńøĖÕÅŹÕø×ķü┐ńŠ®ÕŗÖŃĆŹŃü©ŃüäŃüŻŃü¤ÕĤÕēćŃüīńó║ń½ŗŃüĢŃéīŃü”ŃüŹŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüÖŃĆéõ╝ÜńżŠµ│Ģ2006Õ╣┤’╝łCompanies Act 2006’╝ēŃü»ŃĆüŃüōŃüåŃüŚŃü¤õ╝ØńĄ▒ńÜäŃü¬ÕłżõŠŗµ│ĢõĖŖŃü«ńŠ®ÕŗÖŃéƵłÉµ¢ćÕī¢ŃüŚŃĆüÕŹśõĖĆŃü«µ│ĢõĮōń│╗Ńü½ńĄ▒ÕÉłŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéƵäÅÕø│ŃüŚŃü”ÕłČÕ«ÜŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
µŚźµ£¼Ńü«õ╝ÜńżŠµ│ĢŃü©Ńü«µ»öĶ╝ā
õ╝ÜńżŠµ│Ģ2006Õ╣┤Ńü«µłÉµ¢ćÕī¢Ńü»ŃĆüµ│ĢńÜäńó║Õ«¤µĆ¦ŃéÆķ½śŃéüŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ŃüīķüĄÕ«łŃüÖŃü╣ŃüŹńŠ®ÕŗÖŃéÆŃéłŃéŖµśÄńó║Ńü½ŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüåķćŹĶ”üŃü¬µäÅńŠ®ŃéƵīüŃüĪŃüŠŃüÖŃĆ鵌źµ£¼µ│ĢŃü¦Ńü»ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«õĖ╗Ķ”üŃü¬ńŠ®ÕŗÖŃü©ŃüŚŃü”ŃĆīÕ¢äĶē»Ńü¬ń«ĪńÉåĶĆģŃü«µ│©µäÅńŠ®ÕŗÖŃĆŹ’╝łÕ¢äń«Īµ│©µäÅńŠ®ÕŗÖŃĆüõ╝ÜńżŠµ│Ģń¼¼330µØĪ’╝ēŃü©ŃĆīÕ┐ĀÕ«¤ńŠ®ÕŗÖŃĆŹ’╝łõ╝ÜńżŠµ│Ģń¼¼355µØĪ’╝ēŃüīÕ«ÜŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüŃüōŃéīŃéēŃü»Õīģµŗ¼ńÜäŃüŗŃüżµŖĮĶ▒ĪńÜäŃü¬µ”éÕ┐ĄŃü©ŃüŚŃü”Ķ¦ŻķćłŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü½Õ»ŠŃüŚŃĆüŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣õ╝ÜńżŠµ│ĢŃü»ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«ńŠ®ÕŗÖŃéÆń¼¼171µØĪŃüŗŃéēń¼¼177µØĪŃüŠŃü¦Ńü«7ŃüżŃü«ÕģĘõĮōńÜäŃü¬µØĪµ¢ćŃü©ŃüŚŃü”µśÄĶ©śŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«ŃéóŃāŚŃāŁŃā╝ŃāüŃü«ķüĢŃüäŃü»ŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü½Ńü©ŃüŻŃü”ŃĆüŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗµ│ĢńÜäŃā¬Ńé╣Ńé»Ńü«ńē╣Õ«ÜŃü©ń«ĪńÉåŃéÆŃéłŃéŖÕ«╣µśōŃü½ŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüåÕ«¤ÕŗÖńÜäŃü¬Õł®ńé╣ŃéÆŃééŃü¤ŃéēŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«µłÉµ¢ćÕī¢Ńü»ŃĆüŃé│ŃāóŃā│Ńā╗ŃāŁŃā╝Ńü«ÕĤÕēćŃéÆÕŹśń┤öŃü½µØĪµ¢ćÕī¢ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńø«ńÜäŃü©ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüńē╣Ńü½ń¼¼172µØĪŃü½õ╗ŻĶĪ©ŃüĢŃéīŃéŗŃéłŃüåŃü½ŃĆüŃüØŃü«Ķ¦ŻķćłŃü©ķü®ńö©Ńü½ŃüŖŃüäŃü”Ńü»ŃĆüŃé│ŃāóŃā│Ńā╗ŃāŁŃā╝Ńü«õ╝ØńĄ▒ŃüīÕ╝ĢŃüŹńČÜŃüŹķćŹĶ”üŃü¬ÕĮ╣Õē▓ŃéƵףŃü¤ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«Ńü¤ŃéüŃĆüń¼¼172µØĪŃü«ŃĆīÕĢōńÖ║ŃüĢŃéīŃü¤µĀ¬õĖ╗õŠĪÕĆżŃĆŹŃü«µ”éÕ┐ĄŃüīŃĆüÕłżõŠŗµ│ĢŃü½ŃéłŃüŻŃü”õŠØńäČŃü©ŃüŚŃü”µĀ¬õĖ╗õĖŁÕ┐āõĖ╗ńŠ®ńÜäŃü½Ķ¦ŻķćłŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃü©ŃüäŃüåµē╣ÕłżŃééÕŁśÕ£©ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüµłÉµ¢ćµ│ĢŃüīÕłżõŠŗµ│ĢŃü«õ╝ØńĄ▒ńÜäĶ¦ŻķćłŃü½Õ╝ĢŃüŹŃüÜŃéēŃéīŃéŗŃü©ŃüäŃüåŃĆüŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣µ│Ģńē╣µ£ēŃü«ńÅŠĶ▒ĪŃéÆńż║ÕöåŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃü¤ŃüīŃüŻŃü”ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«ńĄīÕ¢ČĶĆģŃüīŃĆüµØĪµ¢ćŃü«µ¢ćÕŁŚķØóŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüŃüØŃü«ĶāīÕŠīŃü½ŃüéŃéŗŃé│ŃāóŃā│Ńā╗ŃāŁŃā╝Ńü«ÕĤÕēćŃü©µ£Ćµ¢░Ńü«ÕłżõŠŗµ│ĢŃéÆńÉåĶ¦ŻŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░ŃĆüń£¤Ńü«µ│ĢńÜäŃā¬Ńé╣Ńé»ŃéƵŖŖµÅĪŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü»Õø░ķøŻŃü¦ŃüÖŃĆéõŠŗŃüłŃü░ŃĆüń¼¼172µØĪŃü¦ÕłŚµīÖŃüĢŃéīŃü¤Ńé╣ŃāåŃā╝Ńé»ŃāøŃā½ŃāĆŃā╝ŃüĖŃü«ķģŹµģ«Ńü»ŃĆüµØĪµ¢ćõĖŖŃü»ńŠ®ÕŗÖńÜäŃü¦ŃüéŃéŗŃééŃü«Ńü«ŃĆüĶŻüÕłżµēĆŃüīŃüØŃéīŃéÆŃü®Ńü«ŃéłŃüåŃü½Ķ®ĢõŠĪŃüÖŃéŗŃüŗŃü»ŃĆüÕĆŗÕłźŃü«õ║ŗµĪłŃü©ĶŻüÕłżµēĆŃü«ĶŻüķćÅŃü½Õż¦ŃüŹŃüÅõŠØÕŁśŃüÖŃéŗŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆé
ŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣Ńü«ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü½Õ»ŠŃüÖŃéŗ7ŃüżŃü«õĖ╗Ķ”üŃü¬µ│ĢńÜäńŠ®ÕŗÖŃü©ÕłżõŠŗ

µ©®ķÖÉÕåģĶĪīÕŗĢńŠ®ÕŗÖ’╝łCompanies Act 2006 Section 171’╝ē
ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü»ŃĆüõ╝ÜńżŠŃü«µå▓ń½Ā’╝łConstitution’╝ēŃĆüõĖ╗Ńü½Õ«Üµ¼Š’╝łArticles of Association’╝ēŃü½ÕŠōŃüŻŃü”ĶĪīÕŗĢŃüŚŃĆüõĖÄŃüłŃéēŃéīŃü¤µ©®ķÖÉŃéƵŁŻÕĮōŃü¬ńø«ńÜäŃü«Ńü¤ŃéüŃü½Ńü«Ńü┐ĶĪīõĮ┐ŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆé
õŠŗŃüłŃü░ŃĆüÕóŚĶ│ćŃü«µ©®ķÖÉŃéÆŃĆüµĀ¬õĖ╗ńĘÅõ╝ÜŃü¦ńē╣Õ«ÜŃü«µĀ¬õĖ╗Ńü«ĶŁ░µ▒║µ©®ŃéÆÕĖīĶ¢äÕī¢ŃüĢŃüøŃéŗńø«ńÜäŃü¦ĶĪīõĮ┐ŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃü¤Ńü©Ńüłõ╝ÜńżŠŃü«Ńü¤ŃéüŃü½Ńü¬ŃéŗŃü©ĶĆāŃüłŃü”ŃééŃĆüŃüōŃü«ńŠ®ÕŗÖŃü½ķüĢÕÅŹŃüÖŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ńŠ®ÕŗÖŃü»ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńüīµ©®ķÖÉŃéÆķĆĖĶä▒ŃüŚŃü¤ŃéŖŃĆüõĖŹķü®ÕłćŃü¬ńø«ńÜäŃü¦Õł®ńö©ŃüŚŃü¤ŃéŖŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆķś▓ŃüÄŃĆüõ╝ÜńżŠŃü«µ│ĢńÜäµ×ĀńĄäŃü┐ŃéÆńČŁµīüŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńø«ńÜäŃü©ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
õ╝ÜńżŠŃü«µłÉÕŖ¤õ┐āķĆ▓ńŠ®ÕŗÖ’╝łCompanies Act 2006 Section 172’╝ē
ŃüōŃéīŃü»ŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣õ╝ÜńżŠµ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ńŠ®ÕŗÖŃü«µĀĖÕ┐āŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüŃüØŃü«ŃāŗŃāźŃéóŃā│Ńé╣ŃéÆńÉåĶ¦ŻŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńüīµ£ĆŃééķćŹĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆéÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü»ŃĆüĶ¬ĀÕ«¤ŃüŗŃüżÕ¢äµäÅŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüõ╝ÜńżŠÕģ©õĮōŃü«µĀ¬õĖ╗Ńü«Õł®ńøŖŃü«Ńü¤ŃéüŃü½õ╝ÜńżŠŃü«µłÉÕŖ¤ŃéƵ£ĆŃééõ┐āķĆ▓ŃüÖŃéŗµ¢╣µ│ĢŃü¦ĶĪīÕŗĢŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃüōŃü«ńŠ®ÕŗÖŃü»ŃĆīÕĢōńÖ║ŃüĢŃéīŃü¤µĀ¬õĖ╗õŠĪÕĆż’╝łenlightened shareholder value’╝ēŃĆŹŃü©ŃüäŃüåµ”éÕ┐ĄŃéƵłÉµ¢ćÕī¢ŃüŚŃü¤ŃééŃü«Ńü¦ŃĆüÕŹśŃü¬ŃéŗµĀ¬õĖ╗Õł®ńøŖµ£ĆÕż¦Õī¢Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüķĢʵ£¤ńÜäŃü¬Ķ”¢ńé╣ŃüŗŃéēõ╝ÜńżŠŃü«µłÉÕŖ¤ŃéÆĶ┐Įµ▒éŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéƵ▒éŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ńē╣ńŁåŃüÖŃü╣ŃüŹŃü»ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ŃüīŃüōŃü«ńŠ®ÕŗÖŃéƵףŃü¤ŃüÖŃü½ŃüéŃü¤ŃéŖŃĆüõ╗źõĖŗŃü«ķØ×ńČ▓ńŠģńÜäŃü¬Ķ”üń┤ĀŃéÆŃĆīĶĆāµģ«Ńü½ÕģźŃéīŃéŗ’╝łhave regard to’╝ēŃĆŹŃüōŃü©Ńüīµ▒éŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüäŃéŗńé╣Ńü¦ŃüÖŃĆé
- ķĢʵ£¤ńÜäŃü¬µäŵĆص▒║Õ«ÜŃü«ÕĖ░ńĄÉ’╝łthe likely consequences of any decision in the long term’╝ē
- ÕŠōµźŁÕōĪŃü«Õł®ńøŖ’╝łthe interests of the company’s employees’╝ē
- ŃéĄŃāŚŃā®ŃéżŃāżŃā╝ŃĆüķĪ¦Õ«óńŁēŃü©Ńü«õ║ŗµźŁķ¢óõ┐éŃéÆĶé▓ŃéĆÕ┐ģĶ”üµĆ¦’╝łthe need to foster the company’s business relationships with suppliers, customers and others’╝ē
- õ╝ÜńżŠŃü«õ║ŗµźŁŃüīŃé│Ńā¤ŃāźŃāŗŃāåŃéŻŃü©ńÆ░ÕóāŃü½õĖÄŃüłŃéŗÕĮ▒ķ¤┐’╝łthe impact of the company’s operations on the community and the environment’╝ē
- ķ½śŃüäµ░┤µ║¢Ńü«õ║ŗµźŁµģŻĶĪīŃéÆńČŁµīüŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü«ķćŹĶ”üµĆ¦’╝łthe desirability of the company maintaining a reputation for high standards of business conduct’╝ē
- µĀ¬õĖ╗ķ¢ōŃü«Õģ¼Õ╣│µĆ¦’╝łthe need to act fairly as between members of the company’╝ē
µŚźµ£¼Ńü«ńĄīÕ¢ČĶĆģŃü½Ńü©ŃüŻŃü”ŃĆüŃüōŃéīŃü»µŚźµ£¼Ńü«Õ┐ĀÕ«¤ńŠ®ÕŗÖ’╝łõ╝ÜńżŠµ│Ģń¼¼355µØĪ’╝ēŃüīÕĤÕēćŃü©ŃüŚŃü”õ╝ÜńżŠŃü«Õł®ńøŖŃéƵ£ĆÕä¬ÕģłŃü½µ▒éŃéüŃéŗŃü«Ńü©ńĢ░Ńü¬ŃéŖŃĆüµäŵĆص▒║Õ«ÜŃāŚŃāŁŃé╗Ńé╣Ńü½ÕżÜµ¦śŃü¬Ńé╣ŃāåŃā╝Ńé»ŃāøŃā½ŃāĆŃā╝Ńü«Õł®ńøŖŃéÆńĄäŃü┐ĶŠ╝ŃéĆŃüōŃü©ŃéƵśÄńó║Ńü½µ▒éŃéüŃü”ŃüäŃéŗńé╣Ńü¦ŃĆüµ▒║Õ«ÜńÜäŃü¬ńøĖķüĢńé╣Ńü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«ńŠ®ÕŗÖŃü«Ķ¦ŻķćłŃü»ŃĆüńÅŠõ╗ŻńÜäŃü¬Ķ¬▓ķĪīŃü½ńø┤ķØóŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéńÆ░ÕóāNPOŃü¦ŃüéŃéŗClientEarthŃüīŃĆüń¤│µ▓╣ŃāĪŃéĖŃāŻŃā╝ShellŃü«ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝ÜŃéÆńøĖµēŗÕÅ¢ŃéŖŃĆüµ░ŚÕĆÖÕżēÕŗĢŃā¬Ńé╣Ńé»ŃüĖŃü«Õ»ŠÕ┐£ŃüīõĖŹÕŹüÕłåŃü©ŃüŚŃü”ń¼¼172µØĪŃüŖŃéłŃü│ń¼¼174µØĪķüĢÕÅŹŃü¦µ┤Šńö¤Ķ©┤Ķ©¤ŃéƵÅÉĶĄĘŃüŚŃü¤õ║ŗµĪłŃü»ŃĆüŃüōŃü«ńŠ®ÕŗÖŃü«ńÅŠõ╗ŻńÜäŃü¬Ķ¬▓ķĪīŃéÆĶ▒ĪÕŠ┤ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéĶŻüÕłżµēĆŃü»ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«µäŵĆص▒║Õ«ÜŃü«Õ”źÕĮōµĆ¦Ńü½ŃüżŃüäŃü”Õłżµ¢ŁŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü»ŃĆīńĄīÕ¢ČÕłżµ¢ŁŃĆŹŃü«ķĀśÕ¤¤Ńü¦ŃüéŃéŗŃü©ŃüŚŃü”Ķ©┤ŃüłŃéÆÕŹ┤õĖŗŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüŃüōŃü«Õłżµ▒║Ńü»ŃĆüńÅŠÕ£©Ńü«ĶŻüÕłżµēĆŃüīńÆ░ÕóāÕĢÅķĪīŃü«ŃéłŃüåŃü¬ĶżćķøæŃü¬µł”ńĢźńÜäÕłżµ¢ŁŃü½õ╗ŗÕģźŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü½µČłµźĄńÜäŃü¦ŃüéŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńż║ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüŃüōŃéīŃü»ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ŃüīŃüōŃéīŃéēŃü«Ńā¬Ńé╣Ńé»ŃéÆÕ«īÕģ©Ńü½ńäĪĶ”¢ŃüŚŃü”ŃéłŃüäŃüōŃü©ŃéƵäÅÕæ│ŃüŚŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃéĆŃüŚŃéŹŃĆüķü®ÕłćŃü¬µāģÕĀ▒ÕÅÄķøå’╝łń¼¼174µØĪ’╝ēŃü©µäŵĆص▒║Õ«ÜŃāŚŃāŁŃé╗Ńé╣ŃéƵ¦ŗń»ēŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü«ķćŹĶ”üµĆ¦ŃéÆÕ╝ĘĶ¬┐ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ńŖȵ│üŃü»ŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣ÕŁÉõ╝ÜńżŠŃéÆńĄ▒µ▓╗ŃüÖŃéŗķÜøŃü½ŃĆüµ£¼ÕøĮŃü«µģŻĶĪīŃéÆŃüØŃü«ŃüŠŃüŠķü®ńö©ŃüÖŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣Ńü«µ│ĢÕŗÖŃā╗Ķ▓ĪÕŗÖÕ░éķ¢ĆÕ«ČŃü©ķĆŻµÉ║ŃüŚŃü”ŃĆüESGŃā¬Ńé╣Ńé»ŃéÆÕɽŃéĆŃüéŃéēŃéåŃéŗŃā¬Ńé╣Ńé»ŃéÆńČ▓ńŠģńÜäŃü½µż£Ķ©ÄŃüŚŃĆüµäŵĆص▒║Õ«ÜŃü«ķüÄń©ŗŃéÆķü®ÕłćŃü½Ķ©śķī▓ŃüŚŃü”ŃüŖŃüÅŃüōŃü©Ńü«Õ┐ģĶ”üµĆ¦ŃéÆÕ╝ĘŃüÅńż║ÕöåŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ńŗ¼ń½ŗÕłżµ¢ŁńŠ®ÕŗÖ’╝łCompanies Act 2006 Section 173’╝ē
ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü»ŃĆüŃüäŃüŗŃü¬ŃéŗÕż¢ķā©ŃüŗŃéēŃü«ÕĮ▒ķ¤┐Ńü½ŃééÕĘ”ÕÅ│ŃüĢŃéīŃüÜŃĆüĶć¬ŃéēŃü«ńŗ¼ń½ŗŃüŚŃü¤Õłżµ¢ŁŃü½Õ¤║ŃüźŃüäŃü”ĶüĘÕŗÖŃéÆķüéĶĪīŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüńē╣Õ«ÜŃü«µĀ¬õĖ╗Ńéäõ╗¢Ńü«ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«Õł®ńøŖŃéÆõ╗ŻÕ╝üŃüÖŃéŗÕĮ╣Õē▓ŃéƵīüŃüżÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü¦ŃüéŃüŻŃü”ŃééŃĆüµ£ĆńĄéńÜäŃü½Ńü»õ╝ÜńżŠÕģ©õĮōŃü«Õł®ńøŖŃü«Ńü¤ŃéüŃü½ńŗ¼ń½ŗŃüŚŃü¤Õłżµ¢ŁŃéÆõĖŗŃüÖŃü╣ŃüŹŃü¦ŃüéŃéŗŃüōŃü©ŃéƵäÅÕæ│ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ńŠ®ÕŗÖŃü»ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńüīń¼¼õĖēĶĆģŃüŗŃéēŃü«µīćńż║Ńü½ńø▓ńø«ńÜäŃü½ÕŠōŃüåŃüōŃü©ŃéÆń”üŃüśŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝ÜÕģ©õĮōŃü«ÕüźÕģ©Ńü¬µ®¤ĶāĮŃü©ŃĆüõ╝ÜńżŠŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗń£¤Ńü«Õ┐ĀÕ«¤µĆ¦ŃéÆõ┐ØĶ©╝ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńø«ńÜäŃü©ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ńøĖÕĮōŃü¬µ│©µäÅŃā╗µŖĆĶāĮŃā╗ÕŗżÕŗēńŠ®ÕŗÖ’╝łCompanies Act 2006 Section 174’╝ē
ŃüōŃü«ńŠ®ÕŗÖŃü»ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ŃüīĶüĘÕŗÖŃéÆķüéĶĪīŃüÖŃéŗõĖŖŃü¦ŃĆüÕÉłńÉåńÜäŃü¬µ│©µäÅŃĆüµŖĆĶāĮŃĆüŃüŖŃéłŃü│ÕŗżÕŗēŃüĢŃéÆĶĪīõĮ┐ŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéēŃü¬ŃüäŃü©Õ«ÜŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«Õ¤║µ║¢Ńü»ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«õ║īŃüżŃü«Ķ”üń┤ĀŃüŗŃéēµ¦ŗµłÉŃüĢŃéīŃéŗńé╣Ńü¦ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«Õ¢äń«Īµ│©µäÅńŠ®ÕŗÖŃü«µ”éÕ┐ĄŃü©ńĢ░Ńü¬Ńéŗńē╣Ķ│¬ŃéƵīüŃüĪŃüŠŃüÖŃĆé
- Õ«óĶ”│ńÜäÕ¤║µ║¢’╝ÜÕĮōĶ®▓ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«ĶüĘÕŗÖŃéÆķüéĶĪīŃüÖŃéŗĶĆģŃü©ŃüŚŃü”ŃĆüÕÉłńÉåńÜäŃü½µ£¤ÕŠģŃüĢŃéīŃéŗõĖĆĶł¼ńÜäŃü¬ń¤źĶŁśŃĆüµŖĆĶāĮŃĆüŃüŖŃéłŃü│ńĄīķ©ōŃĆé
- õĖ╗Ķ”│ńÜäÕ¤║µ║¢’╝ÜÕĮōĶ®▓ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ŃüīÕ«¤ķÜøŃü½µ£ēŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃĆüŃéłŃéŖķ½śÕ║”Ńü¬ń¤źĶŁśŃĆüµŖĆĶāĮŃĆüŃüŖŃéłŃü│ńĄīķ©ōŃĆé
ŃüżŃüŠŃéŖŃĆüŃüōŃü«ńŠ®ÕŗÖŃü»µ£ĆõĮÄķÖÉŃü«Õ¤║µ║¢ŃéÆĶ©ŁŃüæŃüżŃüżŃĆüńē╣Õ«ÜŃü«Õ░éķ¢ĆÕ«Č’╝łõŠŗ’╝ÜÕģ¼Ķ¬Źõ╝ÜĶ©łÕŻ½Ńü«Ķ│ćµĀ╝ŃéƵīüŃüżCFO’╝ēŃü½Ńü»ŃĆüŃüØŃü«Õ░éķ¢ĆµĆ¦Ńü½ŃüĄŃüĢŃéÅŃüŚŃüäŃéłŃéŖķ½śŃüäµ░┤µ║¢Ńü«µ│©µäÅńŠ®ÕŗÖŃéÆĶ¬▓ŃüÖŃüōŃü©ŃéƵäÅÕæ│ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«ńŠ®ÕŗÖŃü«Õ¤║µ║¢ŃéƵśÄńó║Ńü½ŃüŚŃü¤ķćŹĶ”üŃü¬ÕłżõŠŗŃüīŃĆüRe D’Jan of London LtdŃü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃü«õ║ŗµĪłŃü¦Ńü»ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńüīõ╝ÜńżŠŃü«ńü½ńüĮõ┐ØķÖ║ńö│ĶŠ╝µøĖŃü«ÕåģÕ«╣ŃéÆńó║Ķ¬ŹŃüøŃüÜŃü½ńĮ▓ÕÉŹŃüŚŃü¤ńĄÉµ×£ŃĆüõ┐ØķÖ║Õźæń┤äŃüīńäĪÕŖ╣Ńü©Ńü¬ŃéŖŃĆüõ╝ÜńżŠŃü½µÉŹÕ«│Ńüīńö¤ŃüśŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéĶŻüÕłżµēĆŃü»ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«ĶĪīńé║Ńü»ķüÄÕż▒Ńü¦ŃüéŃéŖŃĆüŃĆīÕÉłńÉåńÜäŃü¬µ│©µäŵĘ▒Ńüäõ║║ŃĆŹŃü©ŃüŚŃü”µ£¤ÕŠģŃüĢŃéīŃéŗÕ¤║µ║¢ŃéƵ║ĆŃü¤ŃüŚŃü”ŃüäŃü¬ŃüŗŃüŻŃü¤Ńü©Õłżµ¢ŁŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«ÕłżõŠŗŃü»ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ÕĆŗõ║║Ńü«ń¤źĶŁśŃéäńĄīķ©ōõĖŹĶČ│ŃüīŃĆüńŠ®ÕŗÖķüĢÕÅŹŃü«ÕģŹĶ▓¼õ║ŗńö▒Ńü½Ńü»Ńü¬ŃéēŃü¬ŃüäŃüōŃü©ŃéƵśÄńó║Ńü½ńż║ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«õ║īķćŹÕ¤║µ║¢Ńü«µ│ĢńÜ䵦ŗķĆĀŃü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«Ķ”¬õ╝ÜńżŠŃüŗŃéēŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣ÕŁÉõ╝ÜńżŠŃü½µ┤ŠķüŻŃüĢŃéīŃéŗŃĆüńē╣Õ«ÜŃü«Õ░éķ¢ĆĶ│ćµĀ╝ŃéƵīüŃü¤Ńü¬ŃüäÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü¦ŃüéŃüŻŃü”ŃééŃĆüŃüØŃü«ĶüĘÕŗÖŃü½Ķ”ŗÕÉłŃüŻŃü¤µ£ĆõĮÄķÖÉŃü«µ│©µäÅńŠ®ÕŗÖŃüīĶ¬▓ŃüĢŃéīŃéŗŃüōŃü©ŃéƵäÅÕæ│ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
õĖƵ¢╣Ńü¦ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«Ķ”¬õ╝ÜńżŠŃüŗŃéēµ┤ŠķüŻŃüĢŃéīŃü¤CFOŃéäCTOŃü«ŃéłŃüåŃü¬Õ░éķ¢ĆÕ«ČÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü»ŃĆüŃüØŃü«Õ░éķ¢ĆµĆ¦ŃéåŃüłŃü½ŃĆüŃéłŃéŖķ½śŃüäµ░┤µ║¢Ńü«ńŠ®ÕŗÖŃéÆĶ▓ĀŃüåŃüōŃü©Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ŃüōŃü©Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«ńĄīÕ¢ČĶĆģŃü½Õ»ŠŃüŚŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«ķüĖõ╗╗Ńü½ķÜøŃüŚŃü”ŃĆüÕŹśŃü¬ŃéŗÕĮ╣ĶüĘŃéäńĄīķ©ōŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣µ│ĢŃü«Ķ”üµ▒éµ░┤µ║¢ŃéƵ║ĆŃü¤ŃüÖń¤źĶŁśŃü©µŖĆĶāĮŃéÆĶĆāµģ«ŃüÖŃéŗÕ┐ģĶ”üµĆ¦ŃéÆń¬üŃüŹŃüżŃüæŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüÕ░éķ¢ĆÕ«Čõ╗źÕż¢ŃüīÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ŃéÆÕŗÖŃéüŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕż¢ķā©Ńü«Õ░éķ¢ĆÕ«Č’╝łµ│ĢÕŠŗÕ«ČŃĆüõ╝ÜĶ©łÕŻ½Ńü¬Ńü®’╝ēŃü«ÕŖ®Ķ©ĆŃéÆķü®ÕłćŃü½µ▒éŃéüŃĆüŃüØŃü«ŃāŚŃāŁŃé╗Ńé╣ŃéÆĶ©śķī▓ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃĆüŃā¬Ńé╣Ńé»ń«ĪńÉåõĖŖµźĄŃéüŃü”ķćŹĶ”üŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
Õł®ńøŖńøĖÕÅŹÕø×ķü┐ńŠ®ÕŗÖ’╝łCompanies Act 2006 Section 175’╝ē
ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü»ŃĆüõ╝ÜńżŠŃü©Ńü«ķ¢ōŃü¦ńø┤µÄźńÜäŃüŠŃü¤Ńü»ķ¢ōµÄźńÜäŃü¬Õł®ńøŖńøĖÕÅŹŃüīńö¤ŃüśŃéŗŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»ńö¤ŃüśŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŗńŖȵ│üŃéÆÕø×ķü┐ŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃüōŃü«ńŠ®ÕŗÖŃü»ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńüīõ╝ÜńżŠŃü«Ķ▓ĪńöŻŃĆüµāģÕĀ▒ŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»õ║ŗµźŁµ®¤õ╝ÜŃéÆń¦üńÜäŃü½Õł®ńö©ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆń”üŃüśŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéõŠŗŃüłŃü░ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ŃüīÕĆŗõ║║ńÜäŃü¬ŃāŚŃāŁŃéĖŃé¦Ńé»ŃāłŃü«Ńü¤ŃéüŃü½õ╝ÜńżŠŃü«µ®¤Õ»åµāģÕĀ▒ŃéÆÕł®ńö©ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéäŃĆüõ╝ÜńżŠŃüīµż£Ķ©ÄŃüŚŃü”ŃüäŃéŗõ║ŗµźŁµ®¤õ╝ÜŃéÆÕĆŗõ║║ńÜäŃü½Õź¬ŃüåŃüōŃü©Ńü¬Ńü®ŃüīŃüōŃéīŃü½Ķ®▓ÕĮōŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ńŠ®ÕŗÖŃü»ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ŃüīÕĖĖŃü½õ╝ÜńżŠŃü«µ£ĆÕ¢äŃü«Õł®ńøŖŃü«Ńü¤ŃéüŃü½ĶĪīÕŗĢŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńó║õ┐ØŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü«ŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆé
ń¼¼õĖēĶĆģŃüŗŃéēŃü«õŠ┐ńøŖÕÅŚķĀśń”üµŁóńŠ®ÕŗÖ’╝łCompanies Act 2006 Section 176’╝ē
ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü»ŃĆüŃüØŃü«ĶüĘÕŗÖŃü«ķüéĶĪīŃü½ķ¢óķĆŻŃüŚŃü”ŃĆüÕł®ńøŖńøĖÕÅŹŃéÆńö¤ŃüśŃüĢŃüøŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦Ńü«ŃüéŃéŗõŠ┐ńøŖŃéÆń¼¼õĖēĶĆģŃüŗŃéēÕÅŚŃüæÕÅ¢ŃüŻŃü”Ńü»Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃüōŃü«ńŠ®ÕŗÖŃü»ŃĆüĶ│äĶ│éŃéäķüÄÕ║”Ńü¬Ķ┤łńŁöÕōüŃĆüµÄźÕŠģŃü¬Ńü®ŃéƵśÄńó║Ńü½ń”üŃüśŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«ńŗ¼ń½ŗµĆ¦Ńü©Õģ¼µŁŻµĆ¦ŃéÆõ┐ØĶŁĘŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃü¤ŃüĀŃüŚŃĆüķĆÜÕĖĖŃü«õ╝üµźŁµ┤╗ÕŗĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗĶ╗ĮÕŠ«Ńü¬µÄźÕŠģŃü¬Ńü®Ńü»Ķ©▒Õ«╣ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃüØŃü«Õłżµ¢ŁŃü½Ńü»µģÄķćŹŃüĢŃüīµ▒éŃéüŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ÕÅ¢Õ╝ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕł®Õ«│ķ¢óõ┐éķ¢ŗńż║ńŠ®ÕŗÖ’╝łCompanies Act 2006 Section 177’╝ē
ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü»ŃĆüõ╝ÜńżŠŃü©Ńü«ķ¢ōŃü¦Ķć¬Ķ║½Ńüīńø┤µÄźńÜäŃüŠŃü¤Ńü»ķ¢ōµÄźńÜäŃü¬Õł®Õ«│ķ¢óõ┐éŃéƵ£ēŃüÖŃéŗÕÅ¢Õ╝ĢŃéÆĶĪīŃüåķÜøŃü½ŃĆüŃüØŃü«Õł®Õ«│ķ¢óõ┐éŃü«µĆ¦Ķ│¬Ńü©ń»äÕø▓ŃéÆõ╗¢Ńü«ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü½ķ¢ŗńż║ŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃüōŃü«ńŠ®ÕŗÖŃü»ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝ÜŃü«µäŵĆص▒║Õ«ÜŃāŚŃāŁŃé╗Ńé╣Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗķĆŵśÄµĆ¦ŃéÆńó║õ┐ØŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü½õĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¦ŃüÖŃĆéķü®ÕłćŃü¬ķ¢ŗńż║ŃüīĶĪīŃéÅŃéīŃéīŃü░ŃĆüÕł®ńøŖńøĖÕÅŹŃü«ÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃüŻŃü”ŃééŃĆüõ╗¢Ńü«ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ŃüīŃüØŃü«ńŖȵ│üŃéÆĶ¬ŹĶŁśŃüŚŃü¤õĖŖŃü¦ÕÅ¢Õ╝ĢŃü«µē┐Ķ¬ŹŃéƵż£Ķ©ÄŃü¦ŃüŹŃéŗŃéłŃüåŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
µŚźĶŗ▒õ╝ÜńżŠµ│ĢŃü«ńøĖķüĢńé╣
ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«ńŠ®ÕŗÖŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗĶĆāŃüłµ¢╣
µŚźµ£¼Ńü©ŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣Ńü«õ╝ÜńżŠµ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«ńŠ®ÕŗÖŃü»ŃĆüŃüØŃü«µ│ĢńÜäµĀ╣µŗĀŃĆüµ¦ŗķĆĀŃĆüŃüŖŃéłŃü│ķüŗńö©Ńü½ŃüŖŃüäŃü”µĀ╣µ£¼ńÜäŃü¬ķüĢŃüäŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéÕż¦ŃüŠŃüŗŃü½Ķ┐░Ńü╣ŃéīŃü░ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«õ╝ÜńżŠµ│ĢŃü»ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«ńŠ®ÕŗÖŃéÆÕīģµŗ¼ńÜäŃü½µŹēŃüłŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüŚŃĆüŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣Ńü«õ╝ÜńżŠµ│ĢŃü»ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«ńŠ®ÕŗÖŃéÆÕģĘõĮōńÜäŃü½Ńā¬Ńé╣ŃāłŃéóŃāāŃāŚŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ÕĆÆńöŻÕŹ▒µ®¤õĖŗŃü«ńŠ®ÕŗÖŃü«Ķ╗óµÅø
õ╝ÜńżŠŃüīÕĆÆńöŻÕŹ▒µ®¤Ńü½ńĆĢŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«ńŠ®ÕŗÖŃüīµĀ¬õĖ╗ŃüŗŃéēÕ饵©®ĶĆģŃüĖŃü©Ķ╗óµÅøŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüåÕĤÕēćŃü»ŃĆüŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣µ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗķćŹĶ”üŃü¬ńē╣Ķ│¬Ńü¦ŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«ÕĤÕēćŃü»ŃĆüWest Mercia v DoddŃü«ŃéłŃüåŃü¬ÕłżõŠŗŃéÆķĆÜŃüśŃü”ŃĆüõ╝ÜńżŠŃü«Ķ▓ĪńöŻŃüīÕ«¤Ķ│¬ńÜäŃü½Õ饵©®ĶĆģŃü«ŃééŃü«Ńü©Ńü¬ŃéŗńŖȵ│üõĖŗŃü¦ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ŃüīŃüØŃü«Õł®ńøŖŃéÆĶĆāµģ«ŃüÖŃü╣ŃüŹŃü¦ŃüéŃéŗŃü©ŃüäŃüåĶĆāŃüłµ¢╣Ńü©ŃüŚŃü”ńÖ║Õ▒ĢŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéBHSõ║ŗõ╗ČŃü©ŃüŚŃü”ń¤źŃéēŃéīŃéŗWright & Ors v ChappellŃü«ÕłżõŠŗŃü»ŃĆüÕĆÆńöŻÕŹ▒µ®¤Ńüīńó║Õ«ÜńÜäŃü¦Ńü¬ŃüÅŃü©ŃééŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ŃüīÕ饵©®ĶĆģÕł®ńøŖŃéÆĶ╗ĮĶ”¢ŃüŚŃü”ĶĪīŃüŻŃü¤ŃĆīõĖŹÕĮōŃü¬ÕÅ¢Õ╝ĢŃĆŹŃü½Õ»ŠŃüŚŃĆüń¼¼172µØĪķüĢÕÅŹŃéäŃĆīmisfeasant tradingŃĆŹŃü©ŃüŚŃü”µÉŹÕ«│Ķ│ĀÕä¤Ķ▓¼õ╗╗ŃüīÕĢÅŃéÅŃéīŃüåŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńż║ÕöåŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«Õłżµ▒║Ńü»ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńüīõ╝ÜńżŠŃü«Ķ▓ĪÕŗÖńŖȵ│üŃéÆÕĖĖŃü½ńøŻĶ”¢ŃüŚŃĆüÕ░æŃüŚŃü¦ŃééÕŹ▒ķÖ║Ńü¬ÕģåÕĆÖŃüīĶ”ŗŃéēŃéīŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕ«ēµśōŃü¬Ńā¬Ńé╣Ńé»ŃāåŃéżŃé»ŃéäĶ”¬õ╝ÜńżŠŃüĖŃü«Õł®ńøŖń¦╗Ķ╗óŃü©ŃüäŃüŻŃü¤ĶĪīńé║ŃéÆÕÄ│Ńü½µģÄŃüŠŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéēŃü¬ŃüäŃü©ŃüäŃüåŃĆüµ¢░Ńü¤Ńü¬µ│ĢńÜäÕ¤║µ║¢ŃéÆńó║ń½ŗŃüŚŃü¤Ńü©Ķ¦ŻķćłŃü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆé
µŚźµ£¼µ│ĢŃü¦Ńü»ŃĆüÕ饵©®ĶĆģŃüīÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«ńŠ®ÕŗÖķüĢÕÅŹŃéÆĶ┐ĮÕÅŖŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüõĖ╗Ńü½õ╝ÜńżŠŃéÆõ╗ŗŃüŚŃü”Ńü«ŃĆīÕ饵©®ĶĆģõ╗ŻõĮŹµ©®ŃĆŹŃü«ĶĪīõĮ┐Ńüīµā│Õ«ÜŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣Ńü¦Ńü»ŃĆüńĀ┤ńöŻń«ĪĶ▓Īõ║║’╝łliquidator’╝ēŃüīõ╝ÜńżŠŃéÆõ╗ŻĶĪ©ŃüŚŃü”ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ÕĆŗõ║║ŃéÆńø┤µÄźĶ©┤Ķ┐ĮŃü¦ŃüŹŃéŗŃü©ŃüäŃüåńé╣Ńü¦ŃĆüĶ▓¼õ╗╗Ķ┐ĮÕÅŖŃü«ŃāĪŃé½ŃāŗŃé║ŃāĀŃüīÕż¦ŃüŹŃüÅńĢ░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆ鵌źµ£¼Ńü«Ķ”¬õ╝ÜńżŠŃüŗŃéēµ┤ŠķüŻŃüĢŃéīŃü¤ńĄīÕ¢ČĶĆģŃü»ŃĆüÕŁÉõ╝ÜńżŠŃüīĶ▓ĪÕŗÖÕø░ķøŻŃü½ķÖźŃüŻŃü¤ķÜøŃü½ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«Ńé░Ńā½Ńā╝ŃāŚńĄīÕ¢ČŃü«Ķ½¢ńÉåŃéÆÕä¬ÕģłŃüŚŃü”Õ«ēµśōŃü½µäŵĆص▒║Õ«ÜŃéÆõĖŗŃüÖŃü©ŃĆüŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣µ│ĢõĖŗŃü¦ÕĆŗõ║║ńÜäŃü¬Ķ▓¼õ╗╗ŃéÆĶ┐ĮÕÅŖŃüĢŃéīŃéŗŃā¬Ńé╣Ńé»Ńü½ńø┤ķØóŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«Ńü¤ŃéüŃĆüŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣Ńü¦Ńü«õ║ŗµźŁŃü½ŃüŖŃüäŃü”Ńü»ŃĆüńĄīÕ¢ČÕŹ▒µ®¤Õ»ŠÕ┐£Ńü«ÕłØµ£¤µ«ĄķÜÄŃüŗŃéēŃĆüÕ饵©®ĶĆģÕł®ńøŖŃéƵ£ĆÕä¬ÕģłŃü½ĶĆāŃüłŃĆüµ│ĢÕŗÖŃā╗Ķ▓ĪÕŗÖŃü«Õ░éķ¢ĆÕ«ČŃü©ńČ┐Õ»åŃü½ķĆŻµÉ║ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīõĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü©Ńéü
µ£¼ń©┐Ńü¦Ķ®│Ķ┐░ŃüŚŃü¤ŃéłŃüåŃü½ŃĆüŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣õ╝ÜńżŠµ│Ģ2006Õ╣┤Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«ńŠ®ÕŗÖŃü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«µ│ĢÕłČÕ║”Ńü©Ńü»ńĢ░Ńü¬ŃéŗÕō▓ÕŁ”Ńü©Õ«¤ÕŗÖŃü½Õ¤║ŃüźŃüäŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé7ŃüżŃü«ńŠ®ÕŗÖŃüīŃé│ŃāóŃā│Ńā╗ŃāŁŃā╝ŃéƵłÉµ¢ćÕī¢ŃüŚŃü¤ŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃéŗŃü©ŃüäŃüåµŁ┤ÕÅ▓ńÜäĶāīµÖ»Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼µ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗŃĆīÕ¢äń«Īµ│©µäÅńŠ®ÕŗÖŃĆŹŃéäŃĆīÕ┐ĀÕ«¤ńŠ®ÕŗÖŃĆŹŃü©Ńü»ńĢ░Ńü¬ŃéŗŃā¬Ńé╣Ńé»Ńü©µ®¤õ╝ÜŃéÆõ╝┤ŃüåŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆé
Ńü¬ŃüŖŃĆüń¼¼172µØĪŃü«ŃĆīÕĢōńÖ║ŃüĢŃéīŃü¤µĀ¬õĖ╗õŠĪÕĆżŃĆŹŃü»ŃĆüµĀ¬õĖ╗Õł®ńøŖŃü«Ķ┐Įµ▒éŃéÆõĖ╗Ķ╗ĖŃü©ŃüŚŃüżŃüżŃééŃĆüŃé╣ŃāåŃā╝Ńé»ŃāøŃā½ŃāĆŃā╝ŃéÆĶĆāµģ«ŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüåŃāÅŃéżŃā¢Ńā¬ŃāāŃāēŃü¬ŃéóŃāŚŃāŁŃā╝ŃāüŃéƵÅÉńż║ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüŃüōŃü«ŃéóŃāŚŃāŁŃā╝ŃāüŃü½Ńü»ķÖÉńĢīŃüīŃüéŃéŗŃü©ŃüäŃüåµīćµæśŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃéÆõ╣ŚŃéŖĶČŖŃüłŃéłŃüåŃü©ŃüÖŃéŗÕŗĢŃüŹŃüīŃĆīBetter Business ActŃĆŹŃéŁŃāŻŃā│ŃāÜŃā╝Ńā│Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃü«ŃéŁŃāŻŃā│ŃāÜŃā╝Ńā│Ńü»ŃĆüń¼¼172µØĪŃéƵö╣µŁŻŃüŚŃĆüµĀ¬õĖ╗ŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüÕŠōµźŁÕōĪŃĆüŃé│Ńā¤ŃāźŃāŗŃāåŃéŻŃĆüńÆ░ÕóāŃü©ŃüäŃüŻŃü¤Ńé╣ŃāåŃā╝Ńé»ŃāøŃā½ŃāĆŃā╝Ńü«Õł®ńøŖŃéÆŃĆüµĀ¬õĖ╗Õł®ńøŖŃü©Õ╣│ńŁēŃü½ĶĆāµģ«ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆÕģ©Ńü”Ńü«õ╝üµźŁŃü½ńŠ®ÕŗÖõ╗śŃüæŃéłŃüåŃü©ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ńē╣Ńü½ŃĆüÕĆÆńöŻµÖéŃü«Õ饵©®ĶĆģÕł®ńøŖŃüĖŃü«ķģŹµģ«ŃéäŃĆüESGŃü©ŃüäŃüŻŃü¤ńÅŠõ╗ŻńÜäĶ¬▓ķĪīŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗńŠ®ÕŗÖŃü«ÕÄ│µĀ╝Õī¢Ńü»ŃĆüÕłżõŠŗŃéÆķĆÜŃüśŃü”ńĄČŃüłŃüÜķĆ▓Õī¢ŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüµŚźµ£¼Ńü«ńĄīÕ¢ČĶĆģŃüīµģŻŃéīĶ”¬ŃüŚŃéōŃüĀµ×ĀńĄäŃü┐ŃéÆÕż¦ŃüŹŃüÅĶČģŃüłŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆéŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣Ńü¦Ńü«õ║ŗµźŁŃéƵłÉÕŖ¤Ńü½Õ░ÄŃüÅŃü¤ŃéüŃü½Ńü»ŃĆüŃüōŃéīŃéēŃü«µ│ĢńÜäńŠ®ÕŗÖŃéƵĘ▒ŃüÅńÉåĶ¦ŻŃüŚŃĆüńÅŠÕ£░Ńü«µ│ĢÕŗÖńÆ░ÕóāŃü½ķü®Õ┐£ŃüŚŃü¤Ńé│Ńā╝ŃāØŃā¼Ńā╝ŃāłŃā╗Ńé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣õĮōÕłČŃéƵ¦ŗń»ēŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīÕ┐ģķĀłŃü«Ķ”üõ╗ČŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
Ńé½ŃāåŃé┤Ńā¬Ńā╝: ITŃā╗ŃāÖŃā│ŃāüŃāŻŃā╝Ńü«õ╝üµźŁµ│ĢÕŗÖ
Ńé┐Ńé░: ŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣µĄĘÕż¢õ║ŗµźŁ