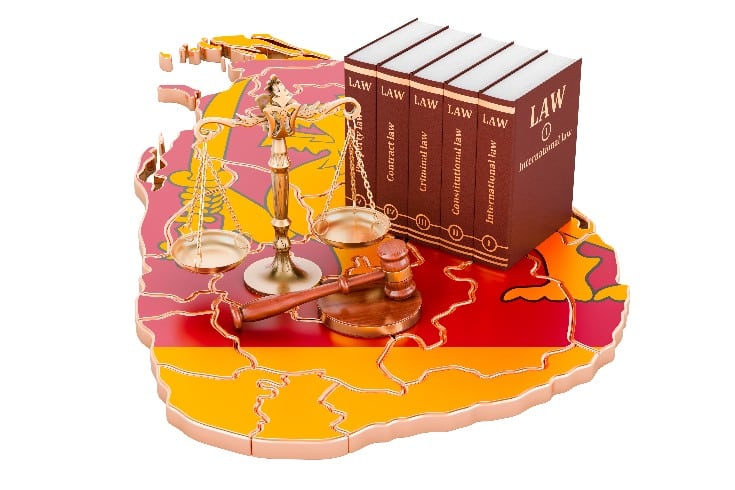ラトビア共和国のNasdaq Rigaと上場基準を弁護士が解説

Nasdaq Rigaは、1993年に設立されたラトビア唯一の証券取引所であり、その最大の特徴は、エストニアのNasdaq Tallinn、リトアニアのNasdaq Vilniusと連携して、共通の取引システムを持つ「Nasdaq Baltic」という単一の統合市場を形成している点にあります。この統合市場は、投資家と上場企業を結びつけるための効率的な電子取引システムを共通して使用しており、米国Nasdaqと同じ「INET」取引システムが採用されています。しかし、Nasdaq Rigaは、名称こそ米国Nasdaqと共通していますが、その監督体制や適用される法制度は根本的に異なります。
本記事では、EUの金融市場における指令(MiFID II)やラトビア商業法に基づく特有のルールに焦点を当て、単なる知識の提供を超えた、実務上の具体的な洞察を提供します。特に、日本の感覚とは異なる「支配権」の定義や、透明性に対する厳しい要件は、現地でのビジネス運営に大きな影響を及ぼす可能性があります。
なお、ラトビアの包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。
この記事の目次
ラトビアのNasdaq Rigaの概要
Nasdaq Rigaも所属する「Nasdaq Baltic」という名称は、単なるブランド名にとどまらず、ラトビア、エストニア、リトアニアというバルト三国が資本市場の機能面で実質的に統合されていることを示しています。これは、日本の主要な証券取引所が国内市場に限定されていることとは対照的です。一つの取引所への上場が、実質的にバルト三国全体の広範な投資家ベースへのアクセスを可能にするという大きな利点があると言えるでしょう。
この市場統合は、各国の限られた市場規模を相互に補完し、全体の流動性を高めることを目的としています。これにより、個別の市場規模が小さいことによる流動性リスクが軽減され、海外からの投資家にとってより魅力的な投資先となる効果を生み出していると考えられます。日本企業がラトビアを拠点として事業を展開する場合、リトアニアやエストニアを含むバルト三国全体をターゲットとした資金調達戦略を立てることが有効であると考えられます。
Nasdaq Rigaは、もともとラトビアの金融・資本市場委員会(FCMC)によって認可・監督されていましたが、現在はラトビア銀行(Bank of Latvia)によって認可され、監督を受けています。同取引所の運営は、欧州連合(EU)の金融市場における指令(MiFID II)や規則(MiFIR)に厳格に準拠しています。これらのEU法は、金融市場の安定性向上と透明性の確保、そして投資家保護を目的としており、ラトビアの国内法体系に深く組み込まれています。監督機関が中央銀行であるラトビア銀行である点は、日本の金融庁が証券取引所の監視を担う構造とは異なります。また、EU法が直接的な法的根拠となることで、上場企業はラトビア国内法に加えて、EU全体に適用される厳格なコンプライアンス要件を遵守する必要があり、これは日本企業が日本の国内法体系のみに準拠する場合とは根本的に異なる点です。
Nasdaq Rigaの株式は、Nasdaq Nordicが92.98%を所有し、残りの7.02%をAS Rietumu Bankaが所有しています。この所有構造からも、同取引所がNasdaqグループの欧州事業戦略における重要な一部であることがうかがえます。
ラトビアNasdaq Rigaと米国Nasdaqとの相違点
管轄と法制度
Nasdaq Rigaと米国Nasdaqは、その名称と「INET」という共通の取引システムによって、同質であると誤解されがちですが、両者の法的・実務的環境は全く異なります。米国Nasdaqが米国証券取引委員会(SEC)の監督下にあるのに対し、Nasdaq Rigaはラトビア銀行の監督下にあります。
この違いは、適用される法制度に由来するものです。米国Nasdaqに上場する企業は、SECへの証券登録と年次報告書の提出が義務付けられていますが、Nasdaq Rigaでは、EUの法規制がその主要な法的枠組みとなります。日本企業がラトビアへの上場を検討する場合、米国の法務要件を遵守する必要は原則としてなく、コンプライアンスの焦点をEUおよびラトビアの法制度に絞ることが求められます。
EUの金融法であるMiFID IIは、金融市場の透明性を高めるための厳格な要件を課しています。その中でも、日本の法務部員にとって特に新しい概念となるのが、LEI(Legal Entity Identifier)コードの義務付けです。これは、金融取引を行う全ての法人に一意の国際的な識別子を付与するもので、ラトビアの金融市場では、このコードなしには銀行が取引注文を受け付けないという事態が生じ得ます。LEIの目的は、監督当局への金融取引報告を通じて、金融市場の透明性を高めることにあります。この要件は、日本の金融商品取引法には存在しない重要な相違点であり、現地での事業展開や金融取引を円滑に行うための実務上の準備が必須となります。
また、両市場は上場市場ティアの構造も大きく異なります。米国Nasdaqには、Nasdaq Global Select Market、Nasdaq Global Market、Nasdaq Capital Marketという3つの主要な市場ティアが存在し、それぞれ異なる財務、流動性、コーポレートガバナンスの基準が設定されています。例えば、Nasdaq Global Select Marketへの上場には、過去3会計年度で合計1,100万米ドル以上の税引前利益や、平均時価総額が5億5,000万米ドル以上といった、非常に厳しい基準が求められます。
一方、Nasdaq Baltic市場には、Main List、Secondary List、First North Growth Marketといったティアが存在します。Nasdaq VilniusのMain Listの基準は、「株式の想定市場価値、または自己資本が400万ユーロ以上」です。これは、米国市場の基準と比較して比較的小規模な企業でも上場できる可能性を示しており、日本のスタートアップや中小企業にとって現実的な選択肢となり得ます。また、First North Growth Marketは、より緩やかな基準で上場できる成長市場であり、メイン市場への「ステップアップ」を意図した位置づけとされています。
共通の技術基盤であるINET取引システム
Nasdaq Rigaと米国Nasdaqは異なる法制度のもとで運営されていますが、両市場が共有する「INET」取引システムは、グローバルな技術基盤としての共通点を提供しています。INETは、もともと電子証券取引プラットフォームとして開発され、2005年にNASDAQによって買収されたものです。この技術は「オーダーペアリングシステム」として、証券会社が電子的に売買注文を追跡し、高速で照合することを可能にします。Nasdaqは、この技術を「X-stream INET」という名称で展開しており、世界最速クラスの取引エンジンであるとされています。
INETの技術的特徴は、その低遅延な取引環境にあります。日本の東京証券取引所(東証)の「arrowhead」システムも、同様に「低遅延、高信頼性、スケーラビリティ」を追求しており、最新の「arrowhead 4.0」では注文応答時間が300マイクロ秒(0.3ミリ秒)にまで高速化しています。一方、INETも株式、債券、ETFなど複数の資産クラスの取引を高速に処理する設計となっており、この技術レベルにおいて両市場の親和性は高いと言えるでしょう。
さらに、情報開示の面でも共通点があります。INETは「ITCH」データフィードを通じて、オーダーブックへの注文の追加・削除・執行など、公開注文や取引の詳細をリアルタイムで提供します。これは、日本の東証が2024年11月に導入した「FLEX Market by Order」という、注文ごとの情報を配信するサービスと概念的に似ています。このような詳細な市場情報は、アルゴリズム取引や高頻度取引を行う投資家にとって不可欠なものであり、高度な技術を要する取引環境がラトビア市場にも整備されていることを示唆しています。
ラトビアNasdaq Rigaの上場基準と日本との相違点

Nasdaq Rigaの上場審査には、形式基準と実質基準があり、この点では日本の東京証券取引所(東証)と同様です。例えば、Nasdaq Vilniusの上場ルールは、Main Listにおいて「発行済株式の少なくとも25%が公に流通していること」を求めており、日本の東証における浮動株比率の概念と類似しています。また、上場申請企業は、監査済みの財務諸表を提出する必要があります。上場準備には、日本の企業が最低3年程度の期間を要すると言われているのと同様に、海外上場も長期的な準備が必要となります。
上場を検討する上で特に留意すべき法的な相違点が、コーポレートガバナンスと情報開示に関連するものです。EUの法律、特にMiFID IIやプロスペクタス規則(Regulation (EU) 2017/1129)は、マネーロンダリング対策(AML)とテロ資金供与対策(CTPF)の強化という目的から、厳格な透明性要件を課しています。ラトビアの金融監督当局であるラトビア銀行は、AML/CTPF関連の違反に対して多額の罰金を科しています。例えば、AS LPB Bankは2023年の検査で、マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止に関する法令違反および内部統制システムの不備を理由に200万ユーロ以上の罰金を科されました。また、AS PrivatBankも、2020年の検査で同様の違反により、75万ユーロ以上の罰金を科されています。これらの事例から、ラトビアの金融機関に対する規制が非常に厳格であることが分かります。
さらに、日本の法感覚と大きく異なる判例が「支配権」の定義にあります。ラトビア行政地方裁判所は2025年8月18日の判決で、制裁対象者リストに含まれていない企業であっても、制裁対象者がその企業の持分を50%間接的に所有している場合、その企業が制裁の適用を受けると判断しました。裁判所は、50%の持分が「取締役会の構成を決定し、会社の決定に影響を与え、資金の使用を管理する能力」を与えるため、ラトビア商業法上の「支配権」の定義を完全に満たすと結論付けています。これは、日本の会社法における「支配株主」の定義が、議決権の過半数(50%超)を占める者とされていることとは異なります。この判例は、日本の投資家や企業がラトビアの企業と合弁事業を設立する際、50対50の持分比率であっても、日本の感覚とは異なる「支配権」のリスクを考慮する必要があることを示唆しています。
また、ラトビアの商事登記簿(Commercial Register)に登録されている株主の個人情報(個人識別番号、住所など)が誰でも閲覧可能であることについても、透明性の高さを示唆しています。この点について、少数株主が個人のプライバシー侵害を主張して訴訟を起こした事例があります。ラトビア憲法裁判所は、株主情報の公開がマネーロンダリングや制裁遵守といった目的のためであるという議会の主張を検討し、この問題の解釈についてEU司法裁判所に予備的な質問を付託しています(Case No. 2024-01-01)。この事例からも、ラトビアでは透明性の確保が極めて重要視されていることが分かります。
ラトビア上場企業の事例
Nasdaq Rigaに上場している主要企業として、金融サービス企業であるDelfinGroupやEleving Groupが挙げられます。DelfinGroupは2009年に設立されたテクノロジーを活用した金融サービス会社で、消費者ローンや質屋ローン、BNPL(Buy Now, Pay Later)などを提供しています。同社は2021年のIPOで約6,000人の新規株主を獲得しており、国内に活発なリテール投資家市場が存在していることが分かります。
また、特筆すべきはEleving Groupの事例です。同社は2012年にラトビアで設立されたフィンテック企業ですが、現在はルクセンブルク籍の会社でありながら、Nasdaq Rigaのメインリストに上場しています。同社は欧州、アフリカ、その他の地域を含む16の市場で事業を展開しており、車両・消費者金融サービスを提供しています。2024年のIPOでは最大2,700万ユーロの資金調達を目標とし、2023年にはNasdaq Balticから最優秀IR賞を受賞するなど、グローバルな資金調達の場としてNasdaq Rigaを活用している好事例と言えます。これは、EUの「パスポート制度」によるもので、目論見書がルクセンブルクの金融セクター監視委員会(CSSF)のような当局によって承認されると、他のEU加盟国でも有効となるため、日本企業もラトビアを足がかりに欧州市場で資本調達を行う戦略が有効であると考えられます。
上場プロセスにおいては、日本の主幹事証券会社と同様に「スポンサー」(First North市場では「公認アドバイザー」)の役割が非常に重要となります。このスポンサーは、上場に向けた準備を支援するだけでなく、取引所との仲介役も担います。取引所のリスティング委員会は、スポンサー候補者が公正・客観的であると確信した場合にのみ、指名されたスポンサーを承認することになっており、客観性に疑義がある場合は却下する権限を有します。法律事務所は、目論見書作成における法的レビューや、関連する契約、コーポレートガバナンス体制の構築において重要な役割を果たします。
まとめ
本稿で解説した通り、ラトビアのNasdaq Rigaは、バルト三国市場の統合された資本市場として、日本の経営者や法務部員にとって新たな資金調達の機会を提供します。しかし、その市場には、米国Nasdaqとは異なる独自の法的・実務的特徴が存在します。EU法に基づく厳格なAML/CTPF要件や、日本の法感覚とは異なる「支配権」の定義は、事業計画の策定において綿密な法務デューデリジェンスを必要とします。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務