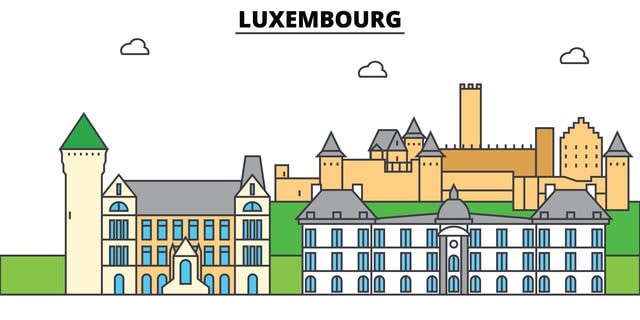„ā§„āŅ„É™„āĘŚÖĪŚíĆŚõĹ„Āę„Āä„ĀĎ„āčśó•śú¨Ť≥áśú¨„Āę„āą„āčÁŹĺŚúįś≥ēšļļŤ≤∑ŚŹé„ÉĽM&A„Āģś≥ēŚĺčŚģüŚčô

„ā§„āŅ„É™„āĘ„Āę„Āä„ĀĎ„āčšľĀś•≠Ť≤∑ŚŹé„ĀģŚ†īťĚĘ„Āß„ĀĮ„ÄĀśó•śú¨„ĀģŚēÜśÖ£ÁŅí„āĄś≥ēŚą∂Śļ¶„Ā®„ĀĮÁēį„Ā™„ā荧áťõĎ„Ā™ś≥ēÁöĄŤ™≤ť°Ć„ĀĆšľī„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāÁČĻ„Āę„ÄĀśó•śú¨ś≥ē„Āę„Āä„ĀĎ„ā蜆™ŚľŹšľöÁ§ĺ„Ā®ŚźąŚźĆšľöÁ§ĺ„ĀęÁõłŚĹď„Āô„āč„ā§„āŅ„É™„āĘ„ĀģšłĽŤ¶Ā„Ā™šľöÁ§ĺŚĹĘśÖč„ĀģÁČĻśÄß„ÄĀ„Éá„É•„Éľ„Éá„É™„āł„āß„É≥„āĻ„Āģťöõ„Āęťú≤Ť¶č„Āó„ĀĆ„Ā°„Ā™ťĚěŚÖ¨ŚľŹ„Ā™ŚēÜśÖ£ÁŅí„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶ŤŅĎŚĻī„ĀĚ„ĀģťĀ©ÁĒ®ÁĮĄŚõ≤„ĀĆŚ§ßŚĻÖ„Āęśč°Ś§ß„Āó„Ā¶„ĀĄ„ā茧ĖŚõĹśäēŤ≥፶ŹŚą∂„ÄĆ„āī„Éľ„Éę„Éá„É≥„ÉĽ„ÉĎ„ÉĮ„Éľ„Ä挹∂Śļ¶„ĀĮ„ÄĀM&A„āíśąźŚäü„Āē„Āõ„āčšłä„ĀßÁźÜŤß£„ĀĆšłćŚŹĮś¨†„Āß„Āô„Äā
śú¨Ť®ėšļč„Āß„ĀĮ„ÄĀ„ā§„āŅ„É™„āĘ„Āß„ĀģM&A„ā휧úŤ®é„Āô„āčśó•śú¨šľĀś•≠ŚźĎ„ĀĎ„Āę„ÄĀšļčś•≠ŚąÜťáé„āíŚēŹ„āŹ„ĀöťĀ©ÁĒ®„Āē„āĆ„āčŚüļśú¨ÁöĄ„Ā™ś≥ēŚą∂Śļ¶„Ā®„ÄĀÁČĻŚģö„ĀģŚąÜťáé„ĀߌēŹť°Ć„Ā®„Ā™„āčÁČĻŚą•„Ā™Ť¶ŹŚą∂„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶Ťß£Ť™¨„Āó„Āĺ„Āô„Äā
„Ā™„Āä„ÄĀ„ā§„āŅ„É™„āĘ„ĀģŚĆÖśč¨ÁöĄ„Ā™ś≥ēŚą∂Śļ¶„Āģś¶āŤ¶Ā„ĀĮšłčŤ®ėŤ®ėšļč„Āę„Ā¶„Āĺ„Ā®„āĀ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„Āď„ĀģŤ®ėšļč„ĀģÁõģś¨°
„ā§„āŅ„É™„āĘ„Āę„Āä„ĀĎ„āčŤ≤∑ŚŹé„ĀģŚüļśú¨„āĻ„ā≠„Éľ„Ɇ„Ā®ŚĮĺŤĪ°„Ā®„Ā™„āčšľöÁ§ĺŚĹĘśÖč
„ā§„āŅ„É™„āĘ„ĀģšłĽŤ¶Ā„Ā™šľöÁ§ĺŚĹĘśÖč
„ā§„āŅ„É™„āĘ„ĀģM&AŚłāŚ†ī„ĀߌĮĺŤĪ°„Ā®„Ā™„āä„ĀÜ„āčšłĽŤ¶Ā„Ā™šľöÁ§ĺŚĹĘśÖč„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆSociet√† per azioniÔľąS.p.A.ԾȄÄć„Ā®„ÄĆSociet√† a responsabilit√† limitataÔľąS.r.l.ԾȄÄć„ĀģšļĆ„Ā§„Āꌧߌą•„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äā
S.p.A.„ĀĮśó•śú¨„Āģś†™ŚľŹšľöÁ§ĺ„ĀęÁõłŚĹď„Āô„āčšľöÁ§ĺŚĹĘśÖč„Āß„Āā„āä„ÄĀŚ§ßŤ¶Źś®°„Ā™šļčś•≠„āĄś†™ŚľŹŚłāŚ†ī„Āł„ĀģšłäŚ†ī„ā퍶Ėťáé„ĀęŚÖ•„āĆ„āčšľĀś•≠„ĀęťĀ©„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāśúÄšĹéŤ≥áśú¨ťáĎ„ĀĮ5šłá„ɶ„Éľ„É≠„Ā®Śģö„āĀ„āČ„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀŤ≥áśú¨„ĀĮ„ÄĆś†™ŚľŹÔľąsharesԾȄÄć„Āꌹ܌Č≤„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„ÄāšłÄśĖĻ„ÄĀS.r.l.„ĀĮśó•śú¨„ĀģŚźąŚźĆšľöÁ§ĺ„Āęšľľ„ĀüśÄߍ≥™„āíśĆĀ„Ā°„ÄĀŤ®≠Áęčśôā„ĀģśúÄšĹéŤ≥áśú¨ťáĎ„ĀĮ„āŹ„Āö„Āč1„ɶ„Éľ„É≠„Āč„āČŚŹĮŤÉĹ„Āß„Āā„āä„ÄĀśüĒŤĽü„Ā™„ā¨„Éź„Éä„É≥„āĻśßčťÄ†„āíśĆĀ„Ā§„Āď„Ā®„Āč„āČ„ÄĀšł≠ŚįŹšľĀś•≠„āĄ„āĻ„āŅ„Éľ„Éą„āĘ„ÉÉ„Éó„ĀߌļÉ„ĀŹśé°ÁĒ®„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
šł°ŤÄÖ„ĀģśúÄ„āāťá捶Ā„Ā™ťĀē„ĀĄ„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„Āģ„ā¨„Éź„Éä„É≥„āĻ„Ā®Áģ°ÁźÜ„ā≥„āĻ„Éą„Āę„Āā„āä„Āĺ„Āô„ÄāS.p.A.„Āß„ĀĮ„ÄĀšľĚÁĶĪÁöĄ„ÄĀšļĆŚĪ§ŚľŹÔľądualisticԾȄÄĀšłÄŚĪ§ŚľŹÔľąmonisticԾȄĀģ„ĀĄ„Āö„āĆ„Āč„ĀģŚé≥ś†ľ„Ā™„ā¨„Éź„Éä„É≥„āĻšĹ∂„ĀĆÁĺ©ŚčôšĽė„ĀĎ„āČ„āĆ„ÄĀÁČĻŚģö„ĀģśĚ°šĽ∂šłč„Āß„ĀĮÁõ£śüĽŚĹĻšľöÔľąstatutory auditorsԾȄĀģŤ®≠ÁĹģ„āāŚŅÖŤ¶Ā„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„ĀĮśó•śú¨„ĀģšľöÁ§ĺś≥ē„ĀĆŚģö„āĀ„āčś©üťĖĘŤ®≠Ť®ą„Ā®śĮĒŤľÉ„Āó„Ā¶„āā„ÄĀ„āą„āäŚé≥ś†ľ„Ā™ŚćįŤĪ°„ā팏ó„ĀĎ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„ĀęŚĮĺ„Āó„ÄĀS.r.l.„Āģ„ā¨„Éź„Éä„É≥„āĻ„ĀĮťĚ쌳ł„ĀęśüĒŤĽü„Āß„Āā„āä„ÄĀŚŹĖÁ∑†ŚĹĻšľö„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹŚćėÁ訄ĀģŚŹĖÁ∑†ŚĹĻ„āíÁĹģ„ĀŹ„Āď„Ā®„ĀĆŚŹĮŤÉĹ„Āß„Āô„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀÁõ£śüĽŚĹĻšľö„ĀĮÁČĻŚģö„ĀģÁĶĆśłąŤ¶Źś®°„āĄŚĺďś•≠Śď°śēį„āíŤ∂Ö„Āą„ā茆īŚźą„Āę„Āģ„ĀŅŤ®≠ÁĹģÁĺ©Śčô„ĀĆÁĒü„Āė„āč„Āü„āĀ„ÄĀÁģ°ÁźÜ„ā≥„āĻ„Éą„ĀĮS.r.l.„ĀģśĖĻ„ĀĆšłÄŤą¨ÁöĄ„ĀęšĹé„ĀĄ„Ā®Ť®Ä„Āą„Āĺ„Āô„Äā
„Āď„ĀģśüĒŤĽüśÄß„ĀĆ„ÄĀŤ≤∑ŚŹéŚģüŚčô„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶ÁČĻśúČ„ĀģŤ™≤ť°Ć„āíÁĒü„ĀŅŚáļ„Āô„Āď„Ā®„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„ā§„āŅ„É™„āĘ„Āģšł≠ŚįŹšľĀś•≠„ÄĀÁČĻ„ĀęS.r.l.„ĀģŚ§ö„ĀŹ„ĀĮ„ÄĀťĚ©śĖįÁöĄ„Āßťęė„ĀĄŚŹéÁõäśÄß„āíśúČ„Āô„ā蚳ĜĖĻ„Āß„ÄĀ„ā≥„Éľ„É̄ɨ„Éľ„Éą„ā¨„Éź„Éä„É≥„āĻ„ĀģŚüļśļĖ„ĀęŚģĆŚÖ®„ĀęśļĖśč†„Āó„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀĄŚ†īŚźą„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
šĺč„Āą„Āį„ÄĀś†™šłĽťĖď„ĀģŚźąśĄŹ„ĀĆśĖáśõłŚĆĖ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Ā™„Āč„Ā£„Āü„āä„ÄĀťĚěŚÖ¨ŚľŹ„Ā™śĄŹśÄĚśĪļŚģö„ĀĆŤ°Ć„āŹ„āĆŤ≠įšļčťĆ≤„ĀĆšĹúśąź„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Ā™„Āč„Ā£„Āü„āä„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüšļčśÖč„ĀĆť†ĽÁĻĀ„Āꍶ茏ó„ĀĎ„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„ĀĮ„ÄĀŚ§ĖŚõĹśäēŤ≥áŚģ∂„ĀĆ„Éá„É•„Éľ„Éá„É™„āł„āß„É≥„āĻ„Āģťöõ„Āę„ÄĀśČÄśúČś®©„ĀģšłćŚģĆŚÖ®„Ā™Ť®ėťĆ≤„āĄŚł≥ÁįŅ„ĀꍮėŤľČ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀĄŚāĶŚčô„Ā®„ĀĄ„Ā£„Āüšļąśúü„Āõ„Ā¨„É™„āĻ„āĮ„āíÁôļŤ¶č„Āô„ā茏ĮŤÉĹśÄß„āíťęė„āĀ„ā荶ĀŚõ†„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āó„Āü„ĀĆ„Ā£„Ā¶„ÄĀS.r.l.„āíŚĮĺŤĪ°„Ā®„Āô„āčM&A„Āß„ĀĮ„ÄĀS.p.A.„āíŚĮĺŤĪ°„Ā®„Āô„ā茆īŚźąšĽ•šłä„Āę„ÄĀ„ā§„āŅ„É™„āĘ„ĀģŚēÜśÖ£ÁŅí„ĀęÁ≤ĺťÄö„Āó„Āüś≥ēŚčô„Éá„É•„Éľ„Éá„É™„āł„āß„É≥„āĻ„ĀģŚįāťĖÄŚģ∂„āíŤĶ∑ÁĒ®„Āó„ÄĀśĹúŚú®ÁöĄ„Ā™„ÄƄɨ„ÉÉ„ÉČ„Éē„É©„ÉÉ„āį„Äć„āíÁČĻŚģö„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆšłćŚŹĮś¨†„Āß„Āô„Äā
ś†™ŚľŹŚŹĖŚĺó„Ā®šļčś•≠Ť≠≤śł°
„ā§„āŅ„É™„āĘ„Āę„Āä„ĀĎ„āčM&AŚŹĖŚľē„ĀĮ„ÄĀ„ĀĽ„Ā®„āď„Ā©„ĀģŚ†īŚźą„ÄĀś†™ŚľŹŚŹĖŚĺóÔľąshare dealԾȄĀĺ„Āü„ĀĮšļčś•≠Ť≠≤śł°Ôľąasset dealԾȄĀģ„ĀĄ„Āö„āĆ„Āč„Āߍ°Ć„āŹ„āĆ„Āĺ„Āô„ÄāŚźąšĹĶÔľąmergerԾȄĀĮ„ÄĀś≥ēÁöĄ„ÉĽŚģüŚčôšłä„ĀģŤ§áťõĎ„Āē„Āč„āČ„ÄĀ„āą„ā䝆ĽŚļ¶„ĀĆšĹé„ĀĄ„Ā®„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
ś†™ŚľŹŚŹĖŚĺó„ĀģŚ†īŚźą„ÄĀŤ≤∑šłĽ„ĀĮŚĮĺŤĪ°šľöÁ§ĺ„Āģś†™ŚľŹ„ā팏ĖŚĺó„Āô„āč„Āď„Ā®„Āę„āą„āä„ÄĀŚĮĺŤĪ°šľöÁ§ĺ„ĀģŤ≥áÁĒ£„ÄĀŤ≤†ŚāĶ„ÄĀ„Āä„āą„Ā≥„Āô„ĀĻ„Ā¶„Āģś≥ēÁöĄťĖĘšŅā„āíťĖďśé•ÁöĄ„ĀęśČŅÁ∂ô„Āó„Āĺ„Āô„Äā„Āď„Āģ„āĻ„ā≠„Éľ„Ɇ„ĀĮšłĽ„ĀęÁ®éŚčôšłä„ĀģÁźÜÁĒĪ„Āč„āČŚ•Ĺ„Āĺ„āĆ„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀ„Éá„É•„Éľ„Éá„É™„āł„āß„É≥„āĻ„ĀßÁôļŤ¶č„Āß„Āć„Ā™„Āč„Ā£„Āüťö†„āĆ„ĀüŤ≤†ŚāĶ„ā팟ę„āÄ„ÄĀťĀéŚéĽ„ĀģÁĶĆŚĖ∂„ĀęŤĶ∑Śõ†„Āô„āč„Āô„ĀĻ„Ā¶„Āģ„É™„āĻ„āĮ„āíŤ≤†„ĀÜ„Āď„Ā®„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
šłÄśĖĻ„ÄĀšļčś•≠Ť≠≤śł°„ĀģŚ†īŚźą„ÄĀŤ≤∑šłĽ„ĀĮšļčś•≠ťĀčŚĖ∂„Āģ„Āü„āĀ„ĀęÁĶĄÁĻĒŚĆĖ„Āē„āĆ„ĀüÁČĻŚģö„ĀģŤ≥áÁĒ£ÔľąšłćŚčēÁĒ£„ÄĀś©üśĘį„ÄĀÁČĻŤ®Ī„ÄĀŚĺďś•≠Śď°„ÄĀŚ•ĎÁīĄ„Ā™„Ā©ÔľČ„āíťĀłśäěÁöĄ„ĀꌏĖŚĺó„Āó„Āĺ„Āô„Äā„Āď„Āģ„āĻ„ā≠„Éľ„Ɇ„ĀģśúÄŚ§ß„ĀģŚą©ÁāĻ„ĀĮ„ÄĀŤ≤∑šłĽ„ĀĆŚľē„ĀćÁ∂ô„ĀźŤ≥áÁĒ£„Ā®Ť≤†ŚāĶ„āíŚé≥ťĀł„Āß„Āć„āč„Āü„āĀ„ÄĀ„É™„āĻ„āĮ„āíťôźŚģö„Āß„Āć„āčÁāĻ„Āę„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
„Āď„ĀģšļĆ„Ā§„Āģ„āĻ„ā≠„Éľ„Ɇ„ĀĮśó•śú¨ś≥ē„Āę„āāŚ≠ėŚú®„Āó„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀ„ā§„āŅ„É™„āĘśįĎś≥ē„Āę„ĀĮšļčś•≠Ť≠≤śł°„Āę„Āä„ĀĎ„āčŚāĶŚčô„āĄŚ•ĎÁīĄ„ĀģśČŅÁ∂ô„ĀęťĖĘ„Āó„Ā¶ÁČĻśúČ„Āģ„Éę„Éľ„Éę„ĀĆŚģö„āĀ„āČ„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀ„Āď„ĀģÁāĻ„ĀĆśó•śú¨ś≥ē„Ā®Ś§ß„Āć„ĀŹÁēį„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
„Āĺ„Āö„ÄĀ„ā§„āŅ„É™„āĘśįĎś≥ēÁ¨¨2558śĚ°„ĀĮ„ÄĀÁČĻśģĶ„ĀģŚźąśĄŹ„ĀĆ„Ā™„ĀĄťôź„āä„ÄĀšļčś•≠ťĀčŚĖ∂„Āģ„Āü„āĀ„ĀęÁ∑†ÁĶź„Āē„āĆ„ĀüťĚěŚÄčšļļÁöĄśÄߍ≥™„ĀģŚ•ĎÁīĄ„ĀĮ„ÄĀŤ≤∑šłĽ„ĀęŤá™ŚčēÁöĄ„ĀęśČŅÁ∂ô„Āē„āĆ„āč„Ā®Ť¶ŹŚģö„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āē„āČ„Āę„ÄĀśįĎś≥ēÁ¨¨2560śĚ°„ĀĮ„ÄĀŚēÜś•≠šľöÁ§ĺ„ĀģŚ†īŚźą„ÄĀŤ≤∑šłĽ„ĀĮŚľ∑Śą∂ÁöĄ„Ā™šľöŤ®ąŚł≥ÁįŅ„ĀꍮėŤľČ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āčŚāĶŚčô„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀŚ£≤šłĽ„Ā®ŚÖĪ„ĀęťÄ£ŚłĮ„Āó„Ā¶Ť≤¨šĽĽ„āíŤ≤†„ĀÜ„Ā®Śģö„āĀ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„ĀĮ„ÄĀšļčś•≠Ť≠≤śł°„Āß„Āā„Ā£„Ā¶„āā„ÄĀšľöŤ®ąŚł≥ÁįŅ„ĀꍮėŤľČ„Āē„āĆ„ĀüŚāĶŚčô„ĀęŚĮĺ„Āô„āčťÄ£ŚłĮŤ≤¨šĽĽ„ĀĮťĀŅ„ĀĎ„āČ„āĆ„Āö„ÄĀŤ≤∑šłĽ„ĀĆ„É™„āĻ„āĮ„āíŚģĆŚÖ®„ĀęťĀģśĖ≠„Āß„Āć„āč„āŹ„ĀĎ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Āď„Ā®„āíÁ§ļ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀśįĎś≥ēÁ¨¨2112śĚ°„ĀĮ„ÄĀšļčś•≠Ť≠≤śł°„ĀģŚ†īŚźą„ÄĀŚĺďś•≠Śď°„Ā®„ĀģťõáÁĒ®ťĖĘšŅā„ĀĮŤ≤∑šłĽ„Āꌾē„ĀćÁ∂ô„ĀĆ„āĆ„ÄĀŚ£≤šłĽ„Ā®Ť≤∑šłĽ„ĀĆŤ≠≤śł°śôāÁāĻ„Āß„ĀģŚĺďś•≠Śď°„Āģś®©Śą©„Āä„āą„Ā≥ŤęčśĪā„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶ťÄ£ŚłĮ„Āó„Ā¶Ť≤¨šĽĽ„āíŤ≤†„ĀÜ„Āď„Ā®„āíŚģö„āĀ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„Āď„āĆ„āČ„ĀģŤ¶ŹŚģö„Āč„āČ„ÄĀšļčś•≠Ť≠≤śł°„ĀĮ„É™„āĻ„āĮ„āíťôźŚģö„Āß„Āć„ā蚳ĜĖĻ„Āß„ÄĀ„Éá„É•„Éľ„Éá„É™„āł„āß„É≥„āĻ„ĀģšłćŚćĀŚąÜ„Āē„ĀĆśĹúŚú®ÁöĄ„Ā™Ť≤†ŚāĶ„ĀģśČŅÁ∂ô„Āę„Ā§„Ā™„ĀĆ„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āó„Āü„ĀĆ„Ā£„Ā¶„ÄĀś†™ŚľŹŚŹĖŚĺó„Āčšļčś•≠Ť≠≤śł°„Āč„ĀģťĀłśäě„ĀĮ„ÄĀŚćė„Ā™„āč„É™„āĻ„āĮŤ®ĪŚģĻŚļ¶„ĀģŚēŹť°Ć„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀÁ®éŚčô„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶„ā§„āŅ„É™„āĘśįĎś≥ēÁČĻśúČ„ĀģśČŅÁ∂ô„Éę„Éľ„Éę„āíÁ∑ŹŚźąÁöĄ„ĀęŤÄÉśÖģ„Āó„Ā¶Śą§śĖ≠„Āô„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āč„Ā®Ť®Ä„Āą„Āĺ„Āô„Äā
„ā§„āŅ„É™„āĘ„Āę„Āä„ĀĎ„āčM&A„Āģś≥ēÁöĄŤ¶ĀšĽ∂„Ā®śČčÁ∂ö„Āć
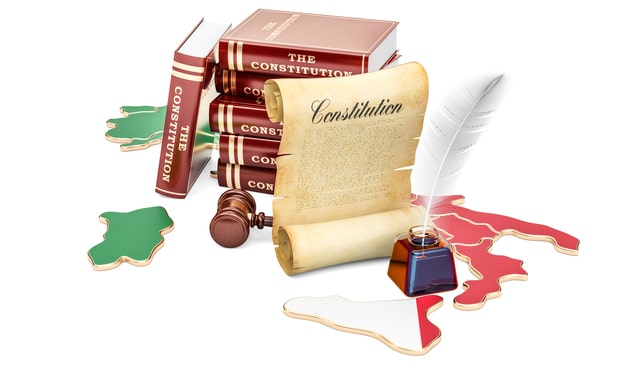
„Éá„É•„Éľ„Éá„É™„āł„āß„É≥„āĻ„ĀģÁõģÁöĄ„Ā®ÁĚÄÁúľÁāĻ
„Ā©„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™ŚąÜťáé„ĀģšľĀś•≠„āíŤ≤∑ŚŹé„Āô„ā茆īŚźą„Āß„āā„ÄĀŚŹĖŚľē„āíśąźŚäü„Āē„Āõ„āč„Āü„āĀ„Āę„ĀĮ„ÄĀŚĺĻŚļē„Āó„Āü„Éá„É•„Éľ„Éá„É™„āł„āß„É≥„āĻ„Ā®„ÄĀ„ā§„āŅ„É™„āĘś≥ēÁČĻśúČ„ĀģŤ≠≤śł°śČčÁ∂ö„Āć„āíś≠£ÁĘļ„ĀęÁźÜŤß£„ĀóŚģüŤ°Ć„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆšłćŚŹĮś¨†„Āß„Āô„Äā
„ā§„āŅ„É™„āĘ„Āę„Āä„ĀĎ„āčM&A„Āß„ĀĮ„ÄĀŚĮĺŤĪ°šľöÁ§ĺ„Āģś≥ēÁöĄ„ÉĽŤ≤°ŚčôÁöĄŚĀ•ŚÖ®śÄß„ā퍙ŅśüĽ„Āó„ÄĀ„É™„āĻ„āĮ„āíšļčŚČć„ĀęÁČĻŚģö„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆM&A„Éó„É≠„āĽ„āĻŚÖ®šĹď„ĀģŚüļÁõ§„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„ÄāÁČĻ„Āęś≥ēŚčô„Éá„É•„Éľ„Éá„É™„āł„āß„É≥„āĻ„ĀĮ„ÄĀŚćė„Ā™„āčšļčŚģüÁĘļŤ™ć„ĀęÁēô„Āĺ„āČ„Āö„ÄĀŤ≤∑ŚŹéšĺ°ś†ľ„Āģśłõť°ćšļ§śłČ„āĄ„ÄĀŤ≤∑šłĽ„āíšŅĚŤ≠∑„Āô„āč„Āü„āĀ„ĀģÁČĻŚģö„ĀģŤ£úŚĄüśĚ°ť†Ö„ā퍮≠Śģö„Āô„āčšłä„Āß„āāťá捶Ā„Ā™ŚĹĻŚČ≤„āíśěú„Āü„Āó„Āĺ„Āô„Äā
ś≥ēŚčô„Éá„É•„Éľ„Éá„É™„āł„āß„É≥„āĻ„ĀģšłĽ„Ā™ÁĚÄÁúľÁāĻ„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĮ„ÄĀšĽ•šłč„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™šļ蝆քĀĆśĆô„Āí„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„Äā
- šľöÁ§ĺ„Āģś≥ēÁöĄšŅĚśúČŤÄÖ„āĄ„ÄĀś†™šłĽ„ÉĽśĆĀŚąÜŤ≠≤śł°„ĀģśúČŚäĻśÄß„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶ťö†„āĆ„Āüś†™šłĽťĖĎÁīĄ„ĀģśúČÁĄ°„āíÁĘļŤ™ć„Āô„āč„Āď„Ā®„Äā
- šłĽŤ¶Ā„Ā™šĺõÁĶ¶„ÄĀśĶĀťÄö„ÄĀ„É™„Éľ„āĻ„ÄĀ„É≠„Éľ„É≥Ś•ĎÁīĄ„ĀģśúČŚäĻśÄß„Ā®Ť≠≤śł°ŚŹĮŤÉĹśÄß„ā팹ܜ쟄Āô„āč„Āď„Ā®„Äā
- šŅāšļČšł≠„ĀģŤ®īŤ®ü„āĄśĹúŚú®ÁöĄ„Ā™ś≥ēÁöĄŤ≤¨šĽĽ„ĀģśúČÁĄ°„ā퍙ŅśüĽ„Āô„āč„Āď„Ā®„Äā
- šļčś•≠„ĀęŚŅÖŤ¶Ā„Ā™Ť®ĪŤ™ćŚŹĮ„āĄ„ÄĀŚäīŚÉćś≥ē„ÉĽÁíįŚĘÉś≥ē„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüŚąÜťáé„Āģ„ā≥„É≥„Éó„É©„ā§„āĘ„É≥„āĻÁä∂ś≥Ā„ā퍩ēšĺ°„Āô„āč„Āď„Ā®„Äā
ŚÖą„ĀęŤŅį„ĀĻ„Āü„āą„ĀÜ„Āę„ÄĀ„ā§„āŅ„É™„āĘ„Āģšł≠ŚįŹšľĀś•≠„Āę„ĀĮ„ÄĀ„ā≥„Éľ„É̄ɨ„Éľ„Éą„ā¨„Éź„Éä„É≥„āĻ„ĀĆťĚěŚÖ¨ŚľŹ„ĀꍰƄāŹ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„āĪ„Éľ„āĻ„ĀĆŚ§ö„ĀŹŤ¶č„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„Äāšĺč„Āą„Āį„ÄĀŤ≠įšļčťĆ≤„ĀĆťĀ©Śąá„ĀęšĹúśąź„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Ā™„Āč„Ā£„Āü„āä„ÄĀŤ≥áśú¨„ĀģŚĘóśłõ„āĄŤ≠≤śł°„ĀĆś≠£„Āó„ĀŹÁôĽŤ®ė„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Ā™„Āč„Ā£„Āü„āä„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āď„ĀÜ„Āó„ĀüśĖáŚĆĖÁöĄ„Ā™ŚĀīťĚĘ„ĀĮ„ÄĀ„Éá„É•„Éľ„Éá„É™„āł„āß„É≥„āĻ„Āę„āą„Ā£„Ā¶ŚąĚ„āĀ„Ā¶śėé„āČ„Āč„Āę„Ā™„āč„Āď„Ā®„ĀĆŚ§ö„ĀŹ„ÄĀśĹúŚú®ÁöĄ„Ā™„É™„āĻ„āĮ„ĀģÁČĻŚģö„Ā®„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„āíťĀ©Śąá„ĀꌕĎÁīĄ„Āꌏćśė†„Āē„Āõ„āč„Āü„āĀ„Āę„ÄĀ„ā§„āŅ„É™„āĘ„ĀģŚēÜśÖ£ÁŅí„ĀęÁ≤ĺťÄö„Āó„ĀüŚľĀŤ≠∑Ś£ę„ĀģÁü•Ť¶č„ĀĆšłćŚŹĮś¨†„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
śĆĀŚąÜ„ÉĽś†™ŚľŹ„ĀģŤ≠≤śł°śČčÁ∂ö„Āć„Ā®ŚÖ¨Ť®ľšļļ„ĀģŚĹĻŚČ≤
śó•śú¨„Āģś†™ŚľŹšľöÁ§ĺ„Āß„ĀĮ„ÄĀŚéüŚČá„Ā®„Āó„Ā¶ś†™ŚľŹ„ĀģŤ≠≤śł°„ĀĮŚĹďšļčŤÄÖťĖď„ĀģŚźąśĄŹ„Āģ„ĀŅ„ĀßśúČŚäĻ„Āß„Āā„āä„ÄĀś†™ŚąłšłćÁôļŤ°ĆšľöÁ§ĺ„Āß„Āā„āĆ„Āįś†™šłĽŚźćÁįŅ„ĀģŚźćÁĺ©śõłśŹõŤęčśĪā„Āę„āą„Ā£„Ā¶Á¨¨šłČŤÄÖ„Āł„ĀģŚĮĺśäóŚäõ„ĀĆÁĒü„Āė„Āĺ„Āô„ÄāšłÄśĖĻ„ÄĀ„ā§„āŅ„É™„āĘ„Āß„ĀĮ„ÄĀS.p.A.„Āģś†™ŚľŹ„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶S.r.l.„ĀģśĆĀŚąÜŤ≠≤śł°„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ÄĀŚÖ¨Ť®ľšļļÔľąnotaryԾȄĀĆťá捶Ā„Ā™ŚĹĻŚČ≤„āíśčÖ„ĀÜÁāĻ„ĀĆ„ÄĀśó•śú¨ś≥ē„Ā®„Āģť°ēŤĎó„Ā™ťĀē„ĀĄ„Āß„Āô„Äā
S.p.A.„Āģś†™ŚľŹŤ≠≤śł°„Āß„ĀĮ„ÄĀś†™ŚľŹ„ĀĆŤ®ľŚąłŚĆĖ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„ā茆īŚźą„ÄĀŤ£ŹśõłÔľągirataԾȄĀę„āą„Ā£„Ā¶Ť≠≤śł°„ĀĆŤ°Ć„āŹ„āĆ„ÄĀŚÖ¨Ť®ľšļļ„ĀģťĚĘŚČć„Āߌ£≤šłĽ„ĀĆŤ£Źśõł„Āó„ÄĀšľöÁ§ĺ„ĀĆś†™šłĽŚźćÁįŅ„ĀꍮėŤľČ„Āó„Āĺ„Āô„ÄāŤ®ľŚąłŚĆĖ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀĄś†™ŚľŹ„ĀĮ„ÄĀŚÖ¨Ť®ľšļļ„Āę„āą„āčŚÖ¨ś≠£Ť®ľśõłÔľąnotarial deedԾȄāíťÄö„Āė„Ā¶Ť≠≤śł°„ĀĆŤ°Ć„āŹ„āĆ„ÄĀŚźĆśßė„Ā꜆™šłĽŚźćÁįŅ„Āł„ĀģŤ®ėŤľČ„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
S.r.l.„ĀģśĆĀŚąÜŤ≠≤śł°„ĀĮ„ÄĀŚÖ¨Ť®ľšļļ„Āę„āą„āčŚÖ¨ś≠£Ť®ľśõł„āíťÄö„Āė„Ā¶Ť°Ć„ĀÜ„Āď„Ā®„ĀĆśÖ£Ť°ĆÁöĄ„ĀęŚŅÖť†ą„Ā®„Āē„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŤ≠≤śł°„ĀĮ„ÄĀÁ¨¨šłČŤÄÖ„ĀęŚĮĺśäó„Āô„āč„Āü„āĀ„Āę„ĀĮšľöÁ§ĺÁôĽŤ®ėÁįŅ„Āł„ĀģÁôĽťĆ≤„ĀĆŚŅÖť†ą„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āď„ĀģŚÖ¨Ť®ľšļļ„ĀģťĖĘšłé„ĀĆŚŅÖť†ą„Ā®„Ā™„āčśÖ£Ť°Ć„ĀĮ„ÄĀM&AśČčÁ∂ö„Āć„Āę„Āä„ĀĎ„āčśó•śú¨ś≥ē„Ā®„ĀģśúÄ„āāť°ēŤĎó„Ā™ťĀē„ĀĄ„ĀģšłÄ„Ā§„Āß„Āā„āä„ÄĀŤ≤∑ŚŹéŚģĆšļÜ„Āĺ„Āß„Āģ„Éó„É≠„āĽ„āĻ„ā퍮ąÁĒĽ„Āô„āčťöõ„Āę„ĀĮ„ÄĀŚÖ¨Ť®ľšļļ„Āģ„āĻ„āĪ„āł„É•„Éľ„ÉęÁĘļšŅĚ„ā팟ę„āĀ„ĀüÁ∂ŅŚĮÜ„Ā™Ť™Ņśēī„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
ÁČĻŚģö„ĀģŚąÜťáé„āĄśĚ°šĽ∂„ĀߌēŹť°Ć„Ā®„Ā™„āč„ā§„āŅ„É™„āĘ„ĀģŤ¶ŹŚą∂
ÁČĻŚģö„Āģšļčś•≠ŚąÜťáé„āĄŚŹĖŚľēŤ¶Źś®°„Āę„āą„Ā£„Ā¶„ĀĮ„ÄĀšłÄŤą¨ÁöĄ„Ā™šľöÁ§ĺś≥ē„ĀęŚä†„Āą„ÄĀÁę∂šļČś≥ē„āĄŚ§ĖŚõĹśäēŤ≥፶ŹŚą∂„ĀĆŚēŹť°Ć„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„ÄāÁČĻ„Āę„ÄĀŤŅĎŚĻī„ĀģŚúįśĒŅŚ≠¶ÁöĄ„Ā™Ś§ČŚĆĖ„Āęšľī„ĀĄ„ÄĀ„Āď„āĆ„āČ„ĀģŤ¶ŹŚą∂„ĀģťĀ©ÁĒ®ÁĮĄŚõ≤„ĀĮŚ§ß„Āć„ĀŹśč°Ś§ß„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
Ś§ĖŚõĹśäēŤ≥፶ŹŚą∂Ôľą„āī„Éľ„Éę„Éá„É≥„ÉĽ„ÉĎ„ÉĮ„ÉľŚą∂Śļ¶ÔľČ
„āī„Éľ„Éę„Éá„É≥„ÉĽ„ÉĎ„ÉĮ„ÉľŚą∂Śļ¶„Ā®„ĀĮ„ÄĀ„ā§„āŅ„É™„āĘśĒŅŚļú„ĀĆ„ÄĀŚõĹťė≤„ÉĽŚõĹŚģ∂ŚģČŚÖ®šŅĚťöú„Āä„āą„Ā≥śą¶Áē•ÁöĄŤ≥áÁĒ£„ĀęťĖĘ„āŹ„āčM&AŚŹĖŚľē„ĀꚼčŚÖ•„Āó„ÄĀśĚ°šĽ∂„ā퍙≤„Āó„Āü„āä„ÄĀŚŹĖŚľē„āíťėĽś≠Ę„Āó„Āü„āä„Āô„āčÁČĻŚą•ś®©ťôź„Āß„Āô„Äā
„Āď„ĀģŚą∂Śļ¶„ĀĮ„ÄĀ„āā„Ā®„āā„Ā®ŚõĹťė≤„āĄŚõĹŚģ∂ŚģČŚÖ®šŅĚťöú„ÄĀ„ā®„Éć„Éę„āģ„Éľ„ÄĀťĀ荾ł„ÄĀťÄöšŅ°„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüÁČĻŚģö„Āģ„ā§„É≥„Éē„É©ŚąÜťáé„ĀęťôźŚģö„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀŤŅĎŚĻī„ĀĚ„ĀģťĀ©ÁĒ®ÁĮĄŚõ≤„ĀĆŚ§ßŚĻÖ„Āęśč°Ś§ß„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāŚÖ∑šĹďÁöĄ„Āę„ĀĮ„ÄĀEUŤ¶ŹŚČá2019/452„Āęś≤Ņ„Ā£„Ā¶„ÄĀ„ÉŹ„ā§„ÉÜ„āĮ„ÄĀ„Éē„ā£„É≥„ÉÜ„ÉÉ„āĮ„ÄĀ„ā§„É≥„ā∑„É•„āĘ„ÉÜ„ÉÉ„āĮ„ÄĀŚĆĽÁôā„ÄĀŤĺ≤ś•≠„ÉĽť£üŚďĀÔľąagri-foodԾȄĀ®„ĀĄ„Ā£„ĀüŚąÜťáé„ĀĆŤŅŌ䆄Āē„āĆ„Āĺ„Āó„Āü„Äā
„Āē„āČ„Āęťá捶Ā„Ā™„Āģ„ĀĮ„ÄĀ„Āď„ĀģŚą∂Śļ¶„ĀĆťĚěEUśäēŤ≥áŚģ∂„Ā†„ĀĎ„Āß„Ā™„ĀŹ„ÄĀEUŚüüŚÜÖśäēŤ≥áŚģ∂„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶ŚõĹŚÜÖśäēŤ≥áŚģ∂„Āę„āāťĀ©ÁĒ®„Āē„āĆ„āč„āą„ĀÜ„Āę„Ā™„Ā£„ĀüÁāĻ„Āß„Āô„ÄāCOVID-19„ÉĎ„É≥„Éá„Éü„ÉÉ„āĮ„āĄŚúįśĒŅŚ≠¶ÁöĄ„Ā™šłćŚģČŚģöŚĆĖ„ā팕Ϝ©ü„Āę„ÄĀ„Āď„ĀģŚą∂Śļ¶„ĀĮŚćė„Ā™„āč„ÄĆŚ§ĖŚõĹśäēŤ≥áŚĮ©śüĽ„ÉĄ„Éľ„Éę„Äć„Āč„āČ„ÄĀŤá™ŚõĹ„Āģ„ÄĆśą¶Áē•ÁöĄŤ≥áÁĒ£„ĀęŚĮĺ„Āô„āčŚļÉÁĮĄ„Ā™śą¶Áē•ÁöĄÁõ£Ť¶Ė„É°„āę„Éč„āļ„Ɇ„Äć„Āł„Ā®ťÄ≤ŚĆĖ„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Ā®Ť®Ä„Āą„Āĺ„Āô„Äā
„āī„Éľ„Éę„Éá„É≥„ÉĽ„ÉĎ„ÉĮ„Éľ„ĀģťÄöÁü•Áĺ©Śčô„ĀĮ„ÄĀśäēŤ≥áŚģ∂„ĀģŚõĹÁĪć„āĄŤ≤∑ŚŹéśĆĀŚąÜŚČ≤Śźą„Āę„āą„Ā£„Ā¶Áēį„Ā™„āä„Āĺ„Āô„ÄāťĚěEUśäēŤ≥áŚģ∂„ĀģŚ†īŚźą„ÄĀŚĮĺŤĪ°šľöÁ§ĺ„Āł„ĀģŤ≠įśĪļś®©„āĄŤ≥áśú¨śĆĀŚąÜ„ĀĆ5%ÔľąšłäŚ†īšľĀś•≠„ĀģŚ†īŚźą„ĀĮ3%ԾȄāíŤ∂Ö„Āą„ĀüŚ†īŚźą„ÄĀ„Āĺ„Āü„ĀĚ„ĀģŚĺĆ10%„ÄĀ15%„ÄĀ20%„ÄĀ25%„ÄĀ50%„ĀęťĀĒ„Āó„ĀüŚ†īŚźą„Āę„ÄĀśĒŅŚļú„Āł„ĀģšļčŚČćťÄöÁü•Áĺ©Śčô„ĀĆÁôļÁĒü„Āó„Āĺ„Āô„ÄāEU„āĄŚõĹŚÜÖśäēŤ≥áŚģ∂„ĀģŚ†īŚźą„ÄĀťÄöŚłł„ĀĮ„ÄĆśĒĮťÖćś®©„ĀģŚŹĖŚĺó„Äć„ĀĆŤ¶ĀšĽ∂„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀšłÄťÉ®„Āģśą¶Áē•ÁöĄŚąÜťáé„Āß„ĀĮś†™ŚľŹŚŹĖŚĺó„Āß„āāťÄöÁü•Áĺ©Śčô„ĀĆÁôļÁĒü„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
ťÄöÁü•ŚĺĆ„ÄĀśĒŅŚļú„ĀĮťÄöŚłł45śó•šĽ•ŚÜÖ„ĀęśĪļŚģö„āíšłč„Āô„Āď„Ā®„Āę„Ā™„Ā£„Ā¶„Āä„āä„ÄĀŤŅŌ䆜ÉÖŚ†Ī„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Ā™Ś†īŚźą„ĀĮŚĽ∂ťē∑„Āē„āĆ„āč„Āď„Ā®„āā„Āā„āä„Āĺ„Āô„ÄāśĒŅŚļú„ĀĮ„ÄĀŚŹĖŚľē„āíÁĄ°śĚ°šĽ∂„ĀßśČŅŤ™ć„Āô„āč„Āč„ÄĀÁČĻŚģö„ĀģśĚ°šĽ∂„ā퍙≤„Āô„Āč„ÄĀ„Āā„āč„ĀĄ„ĀĮśč팟¶„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„Āĺ„Āô„Äā
„Āď„ĀģŚą∂Śļ¶„ĀģťĀ©ÁĒ®ÁĮĄŚõ≤„Āģśč°Ś§ß„ĀĮ„ÄĀŚõĹŚÜÖ„ĀģŤĎóŚźć„Ā™Śą§šĺč„Āę„āą„Ā£„Ā¶„āāŤ£ŹšĽė„ĀĎ„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„ĀĚ„ĀģšĽ£Ť°®ÁöĄ„Ā™šļčšĺč„ĀĆ„ÄĀUniCredit vs. Banco BPMšļ蚼∂„Āß„Āô„Äā„Āď„Āģś°ąšĽ∂„ĀĮ„ÄĀ„ā§„āŅ„É™„āĘ„ĀģŚ§ßśČčťäÄŤ°ĆUniCredit„ĀĆŚźĆ„Āė„ĀŹŚõĹŚÜÖťäÄŤ°Ć„Āß„Āā„āčBanco BPM„ĀęŤ≤∑ŚŹéśŹźś°ą„ā퍰ƄĀ£„Āü„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„ÄĀÁīĒÁ≤č„Ā™ŚõĹŚÜÖŚŹĖŚľē„Āß„Āó„Āü„Äā„Āó„Āč„Āó„ÄĀ„ā§„āŅ„É™„āĘśĒŅŚļú„ĀĮ„ÄĆŚõĹŚģ∂ŚģČŚÖ®šŅĚťöúšłä„ĀģśáłŚŅĶ„Äć„āíÁźÜÁĒĪ„ĀꚼčŚÖ•„Āó„ÄĀÁČĻŚģö„ĀģŤěćŤ≥áśĮĒÁéá„ĀģÁ∂≠śĆĀ„Ā™„Ā©„ÄĀŤ§áśēį„ĀģśĚ°šĽ∂„ā퍙≤„Āó„Āĺ„Āó„Āü„Äā„Āď„ĀģŚą§śĖ≠„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶Ť£ĀŚą§śČÄ„ĀĮ„ÄĀÁĶĆśłąŚģČŚÖ®šŅĚťöú„ĀĆŚõĹŚģ∂ŚģČŚÖ®šŅĚťöú„ĀģÁĮĄŚõ≤ŚÜÖ„Āę„Āā„āč„Āď„Ā®„ā퍙ć„āĀ„Ā§„Ā§„āā„ÄĀšłÄťÉ®„ĀģśĚ°šĽ∂„ĀĆťĀéŚČį„Āß„Āā„āč„Ā®Śą§śĖ≠„Āó„Āĺ„Āó„Āü„Äā
„Āď„ĀģŚą§šĺč„Āč„āČ„ÄĀ„ā§„āŅ„É™„āĘśĒŅŚļú„ĀĆ„āī„Éľ„Éę„Éá„É≥„ÉĽ„ÉĎ„ÉĮ„ÉľŚą∂Śļ¶„āí„ÄĆÁĶĆśłąŚģČŚÖ®šŅĚťöú„Äć„āíśóóŚćį„Āę„ÄĀŤá™ŚõĹ„ĀģÁĶĆśłąśßčťÄ†„āĄÁĒ£ś•≠śĒŅÁ≠Ė„ĀęŚĹĪťüŅ„āíšłé„Āą„āč„Āü„āĀ„ĀģśČčśģĶ„Ā®„Āó„Ā¶ÁĒ®„ĀĄ„Ā¶„ĀĄ„āč„Āď„Ā®„ĀĆŤ®Ä„Āą„āč„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā„Āó„Āü„ĀĆ„Ā£„Ā¶„ÄĀśó•śú¨šľĀś•≠„ĀĮ„ÄĀŚĮĺŤĪ°šľöÁ§ĺ„ĀĆśą¶Áē•ÁöĄŚąÜťáé„ĀęśĆáŚģö„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀŹ„Ā¶„āā„ÄĀÁĶĆśłąŚÖ®šĹď„Āł„ĀģŚĹĪťüŅ„ĀĆŚ§ß„Āć„ĀĄ„Ā®Śą§śĖ≠„Āē„āĆ„ā茆īŚźą„Āę„ĀĮ„ÄĀ„āī„Éľ„Éę„Éá„É≥„ÉĽ„ÉĎ„ÉĮ„ÉľŚą∂Śļ¶„ĀģťĀ©ÁĒ®„ā팏ó„ĀĎ„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āč„Āď„Ā®„āíÁźÜŤß£„Āó„Ā¶„Āä„ĀŹŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
Áę∂šļČś≥ēÔľąM&A„ĀģŚĪäŚáļÁĺ©ŚčôÔľČ
„ā§„āŅ„É™„āĘÁę∂šļČś≥ēÔľąś≥ēŚĺčÁ¨¨287ŚŹ∑/1990ԾȄĀęŚüļ„Ā•„Āć„ÄĀÁČĻŚģö„ĀģŚ£≤šłäťęė„ĀģťĖĺŚÄ§„āíŤ∂Ö„Āą„āčM&A„ĀĮ„ÄĀAGCMÔľąAutorit√† Garante della Concorrenza e del Mercato„ÄĀÁę∂šļČ„ÉĽŚłāŚ†īšŅĚŤ®ľŚļĀԾȄĀł„ĀģšļčŚČćŚĪäŚáļ„ĀĆÁĺ©ŚčôšĽė„ĀĎ„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
AGCM„ĀęŚĪäŚáļ„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Ā®„Ā™„āčM&A„ĀģŚ£≤šłäťęėťĖĺŚÄ§„ĀĮśĮéŚĻīśõīśĖį„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀ2025ŚĻī3śúą18śó•śôāÁāĻ„Āß„ÄĀšĽ•šłč„Āģšł°śĖĻ„ĀģśĚ°šĽ∂„āíśļÄ„Āü„ĀôŚ†īŚźą„ĀęŚĪäŚáļ„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
- ťĖĘšłé„Āô„āč„Āô„ĀĻ„Ā¶„ĀģšľĀś•≠šĹď„Āģ„ā§„āŅ„É™„āĘŚõĹŚÜÖ„Āß„ĀģŚźąŤ®ąŚĻīťĖďŚ£≤šłäťęė„ĀĆ5ŚĄĄ8,200šłá„ɶ„Éľ„É≠„āíŤ∂Ö„Āą„āč„Āď„Ā®„Äā
- ťĖĘšłé„Āô„āčšľĀś•≠šĹď„Āģ„ĀÜ„Ā°ŚįĎ„Ā™„ĀŹ„Ā®„āā2Á§ĺ„ĀĆ„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„Āě„āĆ„ā§„āŅ„É™„āĘŚõĹŚÜÖ„Āß„ĀģŚĻīťĖďŚ£≤šłäťęė„ĀĆ3,500šłá„ɶ„Éľ„É≠„āíŤ∂Ö„Āą„āč„Āď„Ā®„Äā
ŚĪäŚáļŚĺĆ„ÄĀAGCM„ĀĮŚźąšĹĶ„ĀĆÁę∂šļČ„āíŚģüŤ≥™ÁöĄ„ĀęťėĽŚģ≥„Āô„āč„Āč„Ā©„ĀÜ„Āč„āíŚĮ©śüĽ„Āó„Āĺ„Āô„ÄāAGCM„ĀģŚĮ©śüĽ„Éó„É≠„āĽ„āĻ„ĀĮEU„ĀģŚźąšĹĶŤ¶ŹŚą∂„Ā®Ś§ß„Āć„ĀŹśēīŚźą„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Āü„āĀ„ÄĀś¨ßŚ∑ě„ĀģÁę∂šļČś≥ē„Āꝶīśüď„ĀŅ„Āģ„Āā„ā荙≠ŤÄÖ„Āę„ĀĮť°ěšľľśÄß„ā휥ü„Āė„āČ„āĆ„āč„Āß„Āó„āá„ĀÜ„ÄāAGCM„ĀĮ„ÄĀŤŅÖťÄü„Āč„Ā§ÁĘļŚģü„Ā™śĄŹśÄĚśĪļŚģö„āíśĒĮśŹī„Āô„āč„Āü„āĀ„ÄĀś≠£ŚľŹ„Ā™ŚĪäŚáļŚČć„ĀęŚĹďšļčŤÄÖ„Ā®„ĀģťĖď„ĀßšļąŚāôÁöĄ„Ā™ŚćĒŤ≠į„ā퍰ƄĀÜś©üšľö„ā휏źšĺõ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„ĀģšļąŚāôŚćĒŤ≠į„āíÁ©ćś•ĶÁöĄ„ĀęśīĽÁĒ®„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĮ„ÄĀśĹúŚú®ÁöĄ„Ā™Áę∂šļČś≥ēšłä„ĀģŚēŹť°Ć„āíśó©śúü„ĀęÁČĻŚģö„Āó„ÄĀŚŹĖŚľē„ĀģťĀÖŚĽ∂„āĄśĒŅŚļú„Āę„āą„ā蚼čŚÖ•„Āģ„É™„āĻ„āĮ„āíśúÄŚįŹťôź„ĀęśäĎ„Āą„āčšłä„ĀߌģüŚčôÁöĄ„Ā™Śą©ÁāĻ„ĀĆ„Āā„āč„Ā®Ť®Ä„Āą„Āĺ„Āô„Äā
„Āĺ„Ā®„āĀ
„ā§„āŅ„É™„āĘ„Āę„Āä„ĀĎ„āčM&A„ĀĮ„ÄĀśó•śú¨šľĀś•≠„Āę„Ā®„Ā£„Ā¶Ś§ß„Āć„Ā™„Éď„āł„Éć„āĻś©üšľö„āíÁßė„āĀ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀśó•śú¨„Ā®„ĀĮÁēį„Ā™„āčÁ訍ᙄĀģś≥ēÁöĄ„ÉĽśĖáŚĆĖÁöĄ„Ā™Ť™≤ť°Ć„ĀĆšľī„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāÁČĻ„Āę„ÄĀšł≠ŚįŹšľĀś•≠„Āꌧö„ĀĄS.r.l.„ĀģťĚěŚÖ¨ŚľŹ„Ā™„ā¨„Éź„Éä„É≥„āĻ„ĀęŤĶ∑Śõ†„Āô„āč„Éá„É•„Éľ„Éá„É™„āł„āß„É≥„āĻšłä„Āģ„É™„āĻ„āĮ„ÄĀšļčś•≠Ť≠≤śł°„Āę„Āä„ĀĎ„āč„ā§„āŅ„É™„āĘśįĎś≥ēÁČĻśúČ„ĀģŚāĶŚčôśČŅÁ∂ô„Éę„Éľ„Éę„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶ŚúįśĒŅŚ≠¶ÁöĄ„Ā™ŚčēŚźĎ„āíŤÉĆśôĮ„ĀęťĀ©ÁĒ®ÁĮĄŚõ≤„ĀĆśč°Ś§ß„Āó„Āü„ÄĆ„āī„Éľ„Éę„Éá„É≥„ÉĽ„ÉĎ„ÉĮ„Éľ„Ä挹∂Śļ¶„ĀĮ„ÄĀM&AŚŹĖŚľē„ā휧úŤ®é„Āô„āčšłä„ĀßśúÄ„āāťá捶Ā„Ā™ÁēôśĄŹÁāĻ„Ā®Ť®Ä„Āą„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„āČ„ĀģŤ§áťõĎ„Ā™ś≥ēŚčôŤ™≤ť°Ć„āíšĻó„āäŤ∂ä„Āą„āč„Āü„āĀ„Āę„ĀĮ„ÄĀÁŹĺŚúį„Āģś≥ēŚĺč„āĄŚēÜśÖ£ÁŅí„ĀęÁ≤ĺťÄö„Āó„ĀüŚįāťĖÄŚģ∂„Āę„āą„āčÁöĄÁĘļ„Ā™„āĶ„ÉĚ„Éľ„Éą„ĀĆšłćŚŹĮś¨†„Āß„Āô„Äā
„āę„ÉÜ„āī„É™„Éľ: IT„ÉĽ„Éô„É≥„ÉĀ„É£„Éľ„ĀģšľĀś•≠ś≥ēŚčô