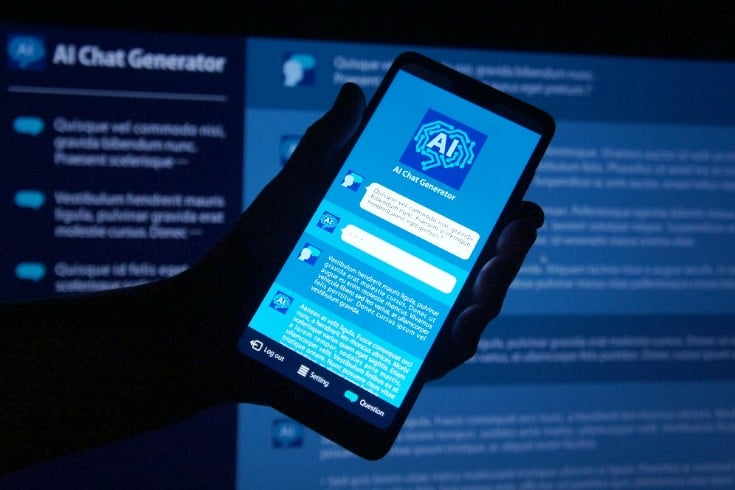еК©жИРйЗСдЄНж≠£еПЧ絶гБЛгВЙз§ЊеКіе£ЂгБЃеИСдЇЛи≤ђдїїгБМеХПгВПгВМгБЯеЃЃеіОеЬ∞еИ§еє≥жИР28еєі3жЬИ23жЧ•еИ§ж±ЇгБЃиІ£и™ђ

еК©жИРйЗСзФ≥иЂЛгВТе§ЦйГ®гБЃе∞ВйЦАеЃґгБІгБВгВЛз§ЊдЉЪдњЭйЩЇеКіеЛЩе£ЂпЉИз§ЊеКіе£ЂпЉЙгВДгВ≥гГ≥гВµгГЂгВњгГ≥гГИгБЂдЊЭй†ЉгБЩгВЛйЪЫгАБдЉБж•≠зµМеЦґиАЕгБѓгАБгБЭгБЃе∞ВйЦАзЯ•и≠ШгБ®еАЂзРЖи¶≥гВТдњ°зФ®гБЧгБЊгБЩгАВгБЧгБЛгБЧгАБгВВгБЧз§ЊеКіе£ЂгВДгВ≥гГ≥гВµгГЂгВњгГ≥гГИгБМдЄНж≠£гВєгВ≠гГЉгГ†гБЃгАМжМЗеНЧељєгАНгБ®гБ™гБ£гБЯе†іеРИгАБдЇЛж•≠дЄїгБѓзЯ•гВЙгБЪзЯ•гВЙгБЪгБЃгБЖгБ°гБЂеИСж≥ХдЄКгБЃи©РжђЇзљ™пЉИ10еєідї•дЄЛгБЃжЗ≤ељє пЉЙгБЃеЕ±зКѓиАЕгБ®гБ™гБ£гБ¶гБЧгБЊгБДгБЊгБЩгАВ
гБЭгБЧгБ¶гАБдЄНж≠£еПЧ絶гБМеЕђзЪДж©ЯйЦҐпЉИеКіеГНе±АгБ™гБ©пЉЙгБЃи™њжЯїгБІзЩЇи¶ЪгБЧгБЯзЮђйЦУгАБз§ЊеКіе£ЂгВДгВ≥гГ≥гВµгГЂгВњгГ≥гГИгБМгАБгАМй°ІеЃҐгБЃеИСдЇЛи≤ђдїїеЫЮйБњгАНгБІгБѓгБ™гБПгАБгАМиЗ™гВЙгБЃе∞ВйЦАи≥Зж†ЉеЙ•е•™гБЃйШ≤ж≠ҐгБ®зµДзєФгБЃе≠ШзґЪгАНгВТжЬАеД™еЕИгБ®гБЧгАБй°ІеЃҐгБЃеИ©зЫКгБ®гБѓжШО祯гБЂзЫЄеПНгБЩгВЛи°МеЛХгВТеПЦгВКеІЛгВБгВЛгВ±гГЉгВєгВВгАБжЃЛењµгБ™гБМгВЙгАБе≠ШеЬ®гБЧгБЊгБЩгАВгБЭгБЖгБЧгБЯз§ЊеКіе£ЂгВДгВ≥гГ≥гВµгГЂгВњгГ≥гГИгБМеПЦгВЛеЕЄеЮЛзЪДгБ™и°МеЛХгБѓгАБй°ІеЃҐгБЄгБЃгАМзФШи®АгБЂгВИгВЛи™ђеЊЧгАНгБІгБЩгАВгАМгБУгВМгБѓеНШгБ™гВЛжЫЄй°ЮдЄКгБЃгГЯгВєгБ†гАНгАМгБУгБЃгБЊгБЊиЗ™дЄїзФ≥еСКгВТгБЫгБЪгБЂдєЧгВКеИЗгВЛгБЃгБМжЬАеЦДгБ†гАНгБ™гБ©гБ®дЄїеЉµгБЧгАБеКіеГНе±АгБЂеѓЊгБЧиЩЪеБљгБЃдЄїеЉµгВТзґЪгБСгВЛгВИгБЖдїХеРСгБСгБЊгБЩгАВ
жЬђи®ШдЇЛгБІиІ£и™ђгБЩгВЛеЃЃеіОеЬ∞жЦєи£БеИ§жЙАеє≥жИР28еєі3жЬИ23жЧ•гБЃеИ§ж±ЇгБѓгАБеК©жИРйЗСгБЃдЄНж≠£еПЧ絶гБЃзЩЇи¶ЪеЊМгАБз§ЊеКіе£ЂгБЃгАМи£ПеИЗгВКгАНгБМгАБеНШгБ™гВЛи™ђеЊЧгБІгБѓгБ™гБПгАБжБРеЦЭгБ™гБ©гБЃзКѓзљ™и°МзВЇгБЂгВ®гВєгВЂгГђгГЉгГИгБЧгБЯгАБйЭЮеЄЄгБЂжВ™и≥™гБ™дЇЛдїґгБІгБЩгАВгБЩгБ™гВПгБ°гАБжЬђдїґгБЃз§ЊеКіе£ЂгБѓгАБи™ђеЊЧгБЂе§±жХЧгБЧгБЯгБ®гБНгАБй°ІеЃҐгВТиДЕгБЧгАБиЩЪеБљгБЃдЊЫињ∞гВТеЉЈи¶БгБЩгВЛгБ®гБДгБЖгАБй°ІеЃҐгБЄгБЃеЉЈи¶Бзљ™гВТзКѓгБЧгБЯгБЃгБІгБЩгАВ
гБУгБЃи®ШдЇЛгБЃзЫЃжђ°
еЬ∞еЯЯеЖНзФЯдЄ≠е∞ПдЉБж•≠еЙµж•≠еК©жИРйЗСеИґеЇ¶гБ®дЄНж≠£еПЧ絶гВєгВ≠гГЉгГ†
гАМеЬ∞еЯЯеЖНзФЯдЄ≠е∞ПдЉБж•≠еЙµж•≠еК©жИРйЗСеИґеЇ¶гАНгБЃж¶Ви¶БгБ®и¶Бдїґ
жЬђдїґгБІз§ЊеКіе£ЂгБМи©РеПЦгВТдЉБгБ¶гБЯгБЃгБѓгАБгАМеЬ∞еЯЯеЖНзФЯдЄ≠е∞ПдЉБж•≠еЙµж•≠еК©жИРйЗСеИґеЇ¶гАНгБІгБЩгАВгБУгВМгБѓгАБйЫЗзФ®жГЕеЛҐгБМеО≥гБЧгБДеЬ∞еЯЯгБІжЦ∞гБЯгБЂеЙµж•≠гБЧгАБеКіеГНиАЕгВТйЫЗгБДеЕ•гВМгВЛдЄ≠е∞ПдЉБж•≠дЇЛж•≠дЄїгБЂеѓЊгБЧгАБеЙµж•≠гБЛгВЙ6гГґжЬИдї•еЖЕгБЃйБЛеЦґи≤їзФ®гВДдЇЇдїґи≤їгВТеК©жИРгБЩгВЛгВВгБЃгБІгБЧгБЯгАВ
гБУгБЃеИґеЇ¶гБЂгБѓгАБдЄНж≠£гБЃгВњгГЉгВ≤гГГгГИгБ®гБ™гБ£гБЯйЗНи¶БгБ™жԃ絶и¶БдїґгБМгБВгВКгБЊгБЧгБЯгАВгБЭгВМгБѓгАБгАМи®≠зЂЛгБХгВМгВЛж≥ХдЇЇз≠ЙгБЃдї£и°®иАЕгБМгАБељУи©≤ж≥ХдЇЇз≠ЙгБ®дЇЛж•≠еЖЕеЃєгБЂйЦҐгБЧгБ¶еРМдЄАжАІгБМи™НгВБгВЙгВМгВЛдЇЛж•≠гВТеЦґгБњгАБеПИгБѓеЦґгВУгБІгБДгБЯе†іеРИгБЂгБѓгАБжԃ絶гБХгВМгБ™гБДгАНгБ®гБДгБЖзВєгБІгБЩгАВгБЩгБ™гВПгБ°гАБжЧҐгБЂеРМгБШдЇЛж•≠гВТгБЧгБ¶гБДгВЛиАЕгБМеРНзЊ©гВТе§ЙгБИгБ¶зФ≥иЂЛгБЩгВЛгБУгБ®гБѓи™НгВБгВЙгВМгБЊгБЫгВУгАВ
жЬђдїґгБЂгБКгБСгВЛеЕЈдљУзЪДгБ™дЄНж≠£гБЃжЙЛеП£
з§ЊеКіе£ЂдЇЛеЛЩжЙАгБЃдї£и°®иАЕгВДз™УеП£жЛЕељУгБЃеЕГз§ЊеКіе£ЂгВЙгБѓгАБй°ІеЃҐжХ∞з§ЊпЉИй£≤й£ЯеЇЧзµМеЦґиАЕгВЙпЉЙгБ®еЕ±иђАгБЧгАБгБУгБЃжԃ絶и¶БдїґгБЃж†єеєєгВТеі©гБЩиЩЪеБљзФ≥иЂЛгВТдљУз≥їзЪДгБЂеЃЯи°МгБЧгБЊгБЧгБЯгАВжЧҐйБВзЈПй°НгБѓзіД2,400дЄЗеЖЖгБЂдЄКгВКгБЊгБЩгАВ
| дЄНж≠£гБЃз®Ѓй°Ю | еЕЈдљУзЪДгБ™жЙЛеП£ | и£БеИ§жЙАгБІи™НеЃЪгБХгВМгБЯдЇЛеЃЯ |
|---|---|---|
| дЇЛж•≠дЄїгБЃеБљи£ЕпЉИеРНзЊ©и≤ЄгБЧпЉЙ | еК©жИРйЗСгБЃжԃ絶и¶БдїґгБІгБВгВЛгАМеРМдЄАдЇЛж•≠гВТеЦґгВУгБІгБДгБ™гБДгБУгБ®гАНгВТеЫЮйБњгБЩгВЛгБЯгВБгАБеЃЯйЪЫгБЃзµМеЦґиАЕгБІгБѓгБ™гБДзђђдЄЙиАЕгБЃеРНзЊ©гВТеАЯгВКгАБжЦ∞и¶ПйЦЛж•≠гБЧгБЯдЇЛж•≠дЄїгБІгБВгВЛгБ®иЩЪеБљзФ≥иЂЛ | еЇЧиИЧ1гБІгБЃдЇЛдїґпЉЪ еЃЯйЪЫгБЃзµМеЦґиАЕгБ®гБѓеИ•гБЂгАБеИ•гБЃдЉЪз§ЊгБЃеЊУж•≠еУ°гВТеРНзЫЃдЄКгБЃдЇЛж•≠дЄїгБ®гБЧгБ¶зФ≥иЂЛ |
| жЮґз©ЇгБЃзµМи≤їи®ИдЄК | еЙµж•≠жФѓжПійЗСгВТеПЧ絶гБЩгВЛгБЯгВБгАБеЃЯйЪЫгБЂгБѓжФѓеЗЇгБЧгБ¶гБДгБ™гБДзµМи≤їгВТи®ИдЄК | еЇЧиИЧ2гБІгБЃдЇЛдїґпЉЪ еЙµж•≠гБЃгБЯгВБгБЃе§ІзРЖзЯ≥зЬЛжЭњи®≠зљЃеЈ•дЇЛгБЃдЇЛеЃЯгБМгБ™гБДгБЂгВВгБЛгБЛгВПгВЙгБЪгАБгБЭгБЃи≤їзФ®262дЄЗ5000еЖЖгВТжЮґз©Їи®ИдЄК |
| зµМи≤їгБЃйБОеЙ∞гБ™ж∞іеҐЧгБЧ | еЃЯйЪЫгБЂгБЛгБЛгБ£гБЯзµМи≤їгБЃй°НгВТе§ІеєЕгБЂж∞іеҐЧгБЧгБЧгБ¶зФ≥иЂЛ | еЇЧиИЧ1гБІгБЃдЇЛдїґпЉЪ еЇЧиИЧжФєи£ЕеЈ•дЇЛи≤їзФ®з≠ЙгБ®гБЧгБ¶гАБе§ЪгБПгБ®гВВ157дЄЗ4000еЖЖгБЧгБЛжФѓеЗЇгБЧгБ¶гБДгБ™гБДгБЂгВВгБЛгБЛгВПгВЙгБЪгАБ644дЄЗ5420еЖЖгВТжФѓеЗЇгБЧгБЯжЧ®гВТиЩЪеБљзФ≥иЂЛпЉИзіД487дЄЗеЖЖгБЃж∞іеҐЧгБЧпЉЙ |
| жЮґз©ЇеКіеГНиАЕгБЃйЫЗзФ® | йЫЗзФ®е•®еК±йЗСгВТеПЧ絶гБЩгВЛгБЯгВБгАБжԃ絶еЯЇжЇЦгБЂеРИиЗігБЩгВЛеКіеГНиАЕгБЃйЫЗзФ®дЇЛеЃЯгБМгБ™гБДгБЂгВВгБЛгБЛгВПгВЙгБЪгАБе§ЪжХ∞гБЃжЮґз©ЇеКіеГНиАЕгВТйЫЗзФ®гБЧгБЯжЧ®гВТзФ≥иЂЛ | еЇЧиИЧ1,2гБІгБЃдЇЛдїґпЉЪ е§ЪжХ∞гБЃжЮґз©ЇеКіеГНиАЕгВТи®ИдЄКгБЧгАБиЩЪеБљгБЃгАМеѓЊи±°еКіеГНиАЕз≠ЙдЄАи¶Іи°®гАНгБ™гБ©гВТжПРеЗЇ |
з™УеП£жЛЕељУгБЃеЕГз§ЊеКіе£ЂгБѓгАБй°ІеЃҐгБЂеѓЊгБЧгАМи¶БгБѓжЫЄй°ЮгБМиВЭењГгБІгБВгВКгАБжЫЄй°ЮгБХгБИжХігБ£гБ¶гБДгВМгБ∞гБДгБДгАНгБ®гАБйЦЛж•≠жЧ•гБЃйБ°еПКжМЗз§ЇгВДгАБйЫЗзФ®гБЃеЃЯжЕЛгБМгБ™гБДиАЕгВТи®ИдЄКгБЩгВЛжЦєж≥ХгВТеЕЈдљУзЪДгБЂжМЗеНЧгБЧгБ¶гБДгБЊгБЧгБЯгАВи£БеИ§жЙАгБѓгАБе∞ВйЦАзЪДгБ™зЯ•и≠ШгБЃгБ™гБДй°ІеЃҐгБМгАБиЗ™еКЫгБІиЩЪеБљгБЃгВњгВ§гГ†гВЂгГЉгГЙгАБеЗЇеЛ§з∞њгАБиЩЪеБљгБЃй†ШеПОжЫЄгБ®гБДгБ£гБЯи§ЗйЫСгБ™жЫЄй°ЮгВТе§ЪжХ∞дљЬжИРгБЩгВЛгБУгБ®гБѓгАМгБЂгВПгБЛгБЂгБѓиАГгБИйЫ£гБДгАНгБ®и™НеЃЪгБЧгАБе∞ВйЦАеЃґгБЂгВИгВЛдЄНж≠£жМЗеНЧи°МзВЇгБМи©РжђЇеЃЯи°МгБЂдЄНеПѓжђ†гБ†гБ£гБЯгБ®гБЧгБ¶гАБгБЭгБЃи≤ђдїїгВТй°ІеЃҐгБ®еРМз®ЛеЇ¶гБЂйЗНгБДгБ®и©ХдЊ°гБЧгБЊгБЧгБЯгАВ
еХПй°МзЩЇи¶ЪеЊМгБЃз§ЊеКіе£ЂгБЂгВИгВЛи™ђеЊЧгБ®еЉЈи¶Б

зµДзєФгБЃдњЭиЇЂгБЃгБЯгВБгБЃгАМзФШи®АгАНгБ®гАМеЉЈи¶БгАН
гБУгБЃдЇЛдїґгБІдЄНж≠£еПЧ絶гБМзЩЇи¶ЪгБЧгБЯгБЃгБѓгАБеКіеГНе±АгБЃи™њжЯїгБЂгВИгВЛгВВгБЃгБІгБЧгБЯгАВгБЭгБЧгБ¶гАБй°ІеЃҐгБѓеКіеГНе±АгБЂеѓЊгБЧгБ¶гАБж≠£зЫігБЂдЇЛеЃЯгВТдЊЫињ∞гБЧгАБдЄНж≠£иЂЛж±ВгБМз§ЊеКіе£ЂдЇЛеЛЩжЙАгБЃиБЈеУ°гБЃжМЗе∞ОгБЂгВИгВЛгВВгБЃгБ†гБ£гБЯгБ®ињ∞гБєгБЊгБЧгБЯгАВ
гБУгВМгБЂеѓЊгБЧгБ¶гАБз§ЊеКіе£ЂдЇЛеЛЩжЙАгБЃдї£и°®иАЕгБ®гАБгБЭгБЃдЉБж•≠гВ∞гГЂгГЉгГЧгБЃжЬАйЂШи≤ђдїїиАЕгВЙпЉИеИ§ж±ЇжЦЗгБЃгБњгБЛгВЙгБѓи©≥зі∞гБМдЄНжШОгБІгБЩгБМгАБгБУгБЃз§ЊеКіе£ЂдЇЛеЛЩжЙАгБѓгАМдЉБж•≠гВ∞гГЂгГЉгГЧгАНгБЂе±ЮгБЩгВЛгВИгБЖгБ™жІЛйА†гБЂгБВгБ£гБЯгВИгБЖгБІгБЩгАВгБУгБЃжІЛйА†иЗ™дљУгБЂгВВе§ІгБНгБ™еХПй°МгБМгБВгБ£гБЯеПѓиГљжАІгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВпЉЙгБѓгАБй°ІеЃҐгВТеСЉгБ≥еЗЇгБЧгАБеКіеГНе±АгБЄгБЃдЊЫињ∞еЖЕеЃєгВТжТ§еЫЮгБХгБЫгВЛгБЯгВБгБЃеЈ•дљЬгВТйЦЛеІЛгБЧгБЊгБЧгБЯгАВељЉгВЙгБѓгАБз§ЊеКіе£ЂдЇЛеЛЩжЙАгБЃйЦҐдЄОгВТеР¶еЃЪгБЩгВЛеЖЕеЃєгБЂдЊЫињ∞гВТи®Вж≠£гБЩгВЛгВИгБЖи¶Бж±ВгБЧгБЊгБЧгБЯгАВ
гБУгБЃи¶Бж±ВгБМйАЪгВЙгБ™гБЛгБ£гБЯйЪЫгАБдЉБж•≠гВ∞гГЂгГЉгГЧгБЃжЬАйЂШи≤ђдїїиАЕгВЙгБѓй°ІеЃҐгБЂеѓЊгБЧгАБж•µгВБгБ¶е®БеЬІзЪДгБ™и®АиСЙгВТжµігБ≥гБЫгБЊгБЧгБЯгАВи£БеИ§жЙАгБМи™НеЃЪгБЧгБЯиДЕињЂгБЃжЦЗи®АгБЂгБѓгАБдї•дЄЛгБЃгВИгБЖгБ™гВВгБЃгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ
- гАМж≠£зЫігБЂи®АгВПгВУгБЛгБ£гБЯгВЙе§Іе§ЙгБ™гБУгБ®гБЂгБ™гВЛгБІгАВгАН
- гАМдЄАзФЯеХЖе£≤гБІгБНгВУгБ™гВЛгБІгАВгАН
- гАМгБЖгБ°гБЂзБЂгБЃз≤ЙгБМйЩНгВКгБЛгБЛгВЛгВИгБЖгБ™гБУгБ®гВТгБЧгБЯгВЙгАБдњЇгБѓзБЂгБЃз≤ЙгВТйЩНгВКгБЛгБґгБЫгВЛгБЮгАВгАН
и£БеИ§жЙАгБѓгАБгБУгВМгВЙгБЃзЩЇи®АгБѓгАБжЬАйЂШи≤ђдїїиАЕгВЙгБМйБХж≥ХгБ™и°МзВЇгВТеРЂгВАжЦєж≥ХгБІй°ІеЃҐгБЃиЇЂдљУгВДеЦґж•≠жіїеЛХгВТеРЂгВАи≤°зФ£гБЂеН±еЃ≥гВТеК†гБИгВЛгБЃгБІгБѓгБ™гБДгБЛгБ®гАМзХПжАЦгБХгБЫгВЛгБЂиґ≥гВКгВЛз®ЛеЇ¶гБЃгВВгБЃгБ®и™НгВБгВЙгВМгВЛгАНгБ®и™НеЃЪгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
иЩЪеБљгБЃжЫЄйЭҐдљЬжИРгБЃеЉЈи¶Б
гБУгБЃиДЕињЂгБЂгВИгВКгАБй°ІеЃҐгБѓгАБиЗ™еЈ±гБЃжДПжАЭгБЂеПНгБЧгБ¶гАБз§ЊеКіе£ЂдЇЛеЛЩжЙАгБЃиБЈеУ°гБЃжМЗе∞ОгБЂгВИгБ£гБ¶дЄНж≠£иЂЛж±ВгВТи°МгБ£гБЯжЧ®гВТгАМеЕ®гБ¶гБѓдЇЛеЃЯгБІгБѓгБВгВКгБЊгБЫгВУгАВгАНгБ®жТ§еЫЮгБЩгВЛжЧ®гБЃиЩЪеБљгБЃжЫЄйЭҐгВТдљЬжИРгБХгБЫгВЙгВМгБЊгБЧгБЯгАВгБУгВМгБѓгАБз§ЊеКіе£ЂдЇЛеЛЩжЙАеБігБМгАБзµДзєФзЪДгБ™и≤ђдїїеЫЮйБњгБЃгБЯгВБгБЂй°ІеЃҐгБЂиЩЪеБљгБЃдЊЫињ∞гВТеЉЈи¶БгБЧгБЯгАБеЉЈи¶Бзљ™гБ®гБДгБЖеИСдЇЛзКѓзљ™гБЂи©≤ељУгБЩгВЛи°МзВЇгБІгБЩгАВ
и£Ьиґ≥пЉЪдЇЛеЛЩжЙАеЖЕгБІгБЃжБРеЦЭи°МзВЇ
гБ™гБКгАБдЄНж≠£еПЧ絶гБЭгВМиЗ™дљУгБ®зЫіжО•гБЃйЦҐдњВгБѓдЄНжШОгБІгБЩгБМгАБгБХгВЙгБЂгБУгБЃзµДзєФгБѓгАБз§ЊеЖЕгГИгГ©гГЦгГЂпЉИеЕГиБЈеУ°гБЃдЄНйБ©еИЗгБ™е•≥жАІйЦҐдњВгВДдЇЛеЛЩгГЯгВєпЉЙгВТеИ©зФ®гБЧгАБеЕГиБЈеУ°гБЂеѓЊгБЧгБ¶гВВгАМгБКеЙНгАБжЃЇгБЩгБЮгАВжЃЇгБЩгБЮгАБгБКеЙНгАВгБКеЙНгБЃи¶™гВВеЕ®йГ®и°МгБПгБЮгАНгБ®иДЕињЂгБЧгАБеРИи®И36дЄЗеЖЖгВТжБРеЦЭгБЩгВЛдЇЛдїґгВВиµЈгБУгБЧгБЊгБЧгБЯгАВеЕГиБЈеУ°пЉИ襀еЃ≥иАЕпЉЙгБѓгАБгБУгБЃиДЕињЂгБЂгВИгВКгАМиЗ™жЃЇгБЩгВЛгБУгБ®гВВдЄАеЃЪз®ЛеЇ¶иАГгБИгБ¶гГ™гВєгГИгВЂгГГгГИгВТи°МгБЖгБЊгБІгБЂиЗ≥гБ£гБ¶гБДгВЛгАНгБїгБ©гБЃгАМж•µеЇ¶гБЃз≤Њз•ЮзЪДгВєгГИгГђгВєгВДзХПжАЦгБЃењµгАНгВТжДЯгБШгБ¶гБДгБЯгБ®и™НеЃЪгБХгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
жЬђдїґеИ§ж±ЇгБЂгБКгБСгВЛеИСдЇЛи≤ђдїї

гБУгБЃз§ЊеКіе£ЂдЇЛеЛЩжЙАгБЃз§ЊеКіе£ЂгБЂгБѓгАБе§Ъй°НгБЃи©РжђЇзљ™гБЂеК†гБИгАБй°ІеЃҐгБЄгБЃеЉЈи¶Бзљ™гАБеЕГиБЈеУ°гБЄгБЃжБРеЦЭзљ™гБ®гБДгБЖи§ЗеРИзЪДгБ™зКѓзљ™гБЃи≤ђдїїгБМеХПгВПгВМгБЊгБЧгБЯгАВгБЭгБЧгБ¶гАБдї•дЄЛгБЃгВИгБЖгБ™еИ§ж±ЇгБМдЄЛгБХгВМгБЊгБЧгБЯгАВ
| з™УеП£жЛЕељУгБЃеЕГз§ЊеКіе£Ђ | з§ЊеКіе£ЂдЇЛеЛЩжЙАгБЃдї£и°®иАЕ | |
|---|---|---|
| и™НеЃЪзљ™зКґ | и©РжђЇгАБи©РжђЇжЬ™йБВгАБеЉЈи¶БгАБжБРеЦЭ | и©РжђЇгАБеЉЈи¶БгАБжБРеЦЭ |
| еИСзљ∞пЉИжЬАзµВпЉЙ | жЗ≤ељє3еєі8жЬИпЉИеЃЯеИСпЉЙ | жЗ≤ељє2еєі4жЬИпЉИеЯЈи°МзМґдЇИ3еєіпЉЙ |
| йЗПеИСеИ§жЦ≠гБЃи¶БеЫ† | и©РжђЇгБЃжМЗеНЧељєгБ®гБЧгБ¶дЄНеПѓжђ†гБ™ељєеЙ≤гВТжЛЕгБДгАБзКѓи°МгБМеЯЈи°МзМґдЇИжЬЯйЦУдЄ≠гБЃеЖНзКѓгБІгБВгБ£гБЯгБЯгВБеЃЯеИС | и©РжђЇгБѓ1дїґгБЃгБњи™НеЃЪгБЂзХЩгБЊгВКгАБдЄНж≠£ж±ЇжЦ≠гБЃи≤ђдїїгБѓи≤†гБЖгВВгБЃгБЃгАБеЙНзІСгБМгБ™гБПгАБ襀еЃ≥еЫЮеЊ©гБМгБ™гБХгВМгБ¶гБДгБЯгБЯгВБеЯЈи°МзМґдЇИ |
гБЊгБ®гВБпЉЪеК©жИРйЗСдЄНж≠£еПЧ絶гБЂйЦҐгБЩгВЛзЫЄиЂЗгБѓеЉБи≠Је£ЂгБЄ
жЬђдїґгБЃжЬАгВВйЗНи¶БгБ™жХЩи®УгБѓгАБзФ≥иЂЛгВТдї£и°МгБЧгБЯз§ЊеКіе£ЂгВДгВ≥гГ≥гВµгГЂгВњгГ≥гГИгБЃдЄ≠гБЂгБѓгАБдЄНж≠£гБМзЩЇи¶ЪгБЧгБЯйЪЫгАБиЗ™иЇЂгБЃеИСдЇЛи≤ђдїїгВДи≥Зж†ЉеЙ•е•™гБ™гБ©гБЃеЗ¶еИЖгБЃеЫЮйБњгВТжЬАеД™еЕИгБЩгВЛиАЕгВВгАБжЃЛењµгБ™гБМгВЙе≠ШеЬ®гБЩгВЛгАБгБ®гБДгБЖгБУгБ®гБІгБЩгАВељЉгВЙгБМгАМжЫЄй°ЮдЄКгБЃгГЯгВєгБ†гБЛгВЙиЗ™дЄїзФ≥еСКгБѓгБЩгВЛгБ™гАНгАМгБУгБ°гВЙгБІгБ™гВУгБ®гБЛгБЩгВЛгАНгБ®и™ђеЊЧгБЧгБ¶гБПгВЛе†іеРИгАБгБЭгВМгБѓгБВгБ™гБЯгБЃеИ©зЫКгБІгБѓгБ™гБПгАБељЉгВЙгБЃдњЭиЇЂгБЃгБЯгВБгБЃзФШи®АгБІгБВгВЛеПѓиГљжАІгБМйЂШгБДгБЃгБІгБЩгАВ
з§ЊеКіе£ЂгВДгВ≥гГ≥гВµгГЂгВњгГ≥гГИгБЃзФШи®АгБЂдєЧгБ£гБ¶дЄНж≠£йЦҐдЄОгВТеР¶еЃЪгБЧгБЯгВКгАБиЩЪеБљгБЃдЊЫињ∞гВТзґЪгБСгБЯе†іеРИгАБгБВгБ™гБЯгБѓељЉгВЙгБЃдЄНж≠£гБЂжЬАеЊМгБЊгБІзµДгБњиЊЉгБЊгВМгАБжЬАзµВзЪДгБЂи©РжђЇзљ™гБЃеЕ±зКѓиАЕгБ®гБЧгБ¶гБЃи≤ђдїїгВТеХПгВПгВМгБЊгБЩгАВгБХгВЙгБЂгАБжЬђдїґгБЃгВИгБЖгБЂгАБзµДзєФзЪДйЪ†иФљеЈ•дљЬгБЃйБОз®ЛгБІгАБиДЕињЂгВДеЉЈи¶БгБ®гБДгБ£гБЯжЦ∞гБЯгБ™зКѓзљ™гБЃиҐЂеЃ≥иАЕгВДеЕ±зКѓиАЕгБЂгБХгВМгВЛгГ™гВєгВѓгБЩгВЙи≤†гБЖгБУгБ®гБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ
дЉБж•≠гБ®гБЧгБ¶гАБеК©жИРйЗСдЄНж≠£гБЃзЦСжГСгБМзФЯгБШгБЯйЪЫгБЂеН±ж©ЯгВТжЬАе∞ПйЩРгБЂжКСгБИгВЛгБЯгВБгБЃеОЯеЙЗгБѓдї•дЄЛгБЃйАЪгВКгБІгБЩгАВ
- зФШи®АгВТжЛТеР¶гБЩгВЛпЉЪз§ЊеКіе£ЂгВДгВ≥гГ≥гВµгГЂгВњгГ≥гГИгБЛгВЙгАБдЄНж≠£гВТеР¶еЃЪгБЩгВЛгВИгБЖи™ђеЊЧгБХгВМгБ¶гВВгАБжЦ≠еЫЇгБ®гБЧгБ¶жЛТеР¶гБЧгБ¶гБПгБ†гБХгБД
- зЛђиЗ™гБЃеЉБи≠Је£ЂгВТзЂЛгБ¶гВЛпЉЪгБЭгБЃз§ЊеКіе£ЂдЇЛеЛЩжЙАгВДгВ≥гГ≥гВµгГЂгВњгГ≥гГИгБ®еИ©еЃ≥йЦҐдњВгБЃгБ™гБДгАБеИСдЇЛгГ™гВєгВѓгБ®и°МжФњгГ™гВєгВѓеПМжЦєгБЂз≤ЊйАЪгБЧгБЯеЉБи≠Је£ЂгБЄгАБињЕйАЯгБЛгБ§ж≠£зЫігБЂзЫЄиЂЗгБЧгБ¶гБПгБ†гБХгБД
- ж≠£зЫігБ™еѓЊењЬгВТеПЦгВЛпЉЪзµДзєФзЪДгБ™йЪ†иФљгВДдЊЫињ∞гБЃжНПйА†гБѓзµґеѓЊгБЂйБњгБСгАБеЉБи≠Је£ЂгБЃжМЗе∞ОгБЃгВВгБ®гАБељУе±АпЉИеКіеГНе±АгВДи≠¶еѓЯпЉЙгБЂеѓЊгБЧгБ¶дЇЛеЃЯгБЂеЯЇгБ•гБДгБЯж≠£зЫігБ™еѓЊењЬгВТгБ®гВЛгБєгБНгБІгБЩ
еК©жИРйЗСдЄНж≠£гБЃжМЗеНЧгБЂгАМеЈїгБНиЊЉгБЊгВМгБЯгАНгБ®жДЯгБШгБЯе†іеРИгАБгБВгВЛгБДгБѓзПЊеЬ®гАБз§ЊеКіе£ЂгВДгВ≥гГ≥гВµгГЂгВњгГ≥гГИгБЛгВЙгБЃеЉЈеЉХгБ™еѓЊењЬгВДељУе±АгБЛгВЙгБЃи™њжЯїгБЂзЫійЭҐгБЧгБ¶гБДгВЛе†іеРИгБѓгАБгБУгВМдї•дЄКеХПй°МгВТжВ™еМЦгБХгБЫгВЛеЙНгБЂгАБељУдЇЛеЛЩжЙАгБЂгБФзЫЄиЂЗгБПгБ†гБХгБДгАВ
ељУдЇЛеЛЩжЙАгБЂгВИгВЛеѓЊз≠ЦгБЃгБФж°ИеЖЕ
гГҐгГОгГ™гВєж≥ХеЊЛдЇЛеЛЩжЙАгБѓгАБITгАБзЙєгБЂгВ§гГ≥гВњгГЉгГНгГГгГИгБ®ж≥ХеЊЛгБЃдЄ°йЭҐгБЂйЂШгБДе∞ВйЦАжАІгВТжЬЙгБЩгВЛж≥ХеЊЛдЇЛеЛЩжЙАгБІгБЩгАВељУдЇЛеЛЩжЙАгБІгБѓгАБжЭ±и®ЉгГЧгГ©гВ§гГ†дЄКе†ідЉБж•≠гБЛгВЙгГЩгГ≥гГБгГ£гГЉдЉБж•≠гБЊгБІгАБгГУгВЄгГНгВєгГҐгГЗгГЂгВДдЇЛж•≠еЖЕеЃєгВТжЈ±гБПзРЖиІ£гБЧгБЯдЄКгБІжљЬеЬ®зЪДгБ™ж≥ХзЪДгГ™гВєгВѓгВТжіЧгБДеЗЇгБЧгАБгГ™гГЉгВђгГЂгВµгГЭгГЉгГИгВТи°МгБ£гБ¶гБКгВКгБЊгБЩгАВдЄЛи®Ши®ШдЇЛгБЂгБ¶и©≥зі∞гВТи®ШиЉЙгБЧгБ¶гБКгВКгБЊгБЩгАВ
гВЂгГЖгВігГ™гГЉ: ITгГїгГЩгГ≥гГБгГ£гГЉгБЃдЉБж•≠ж≥ХеЛЩ