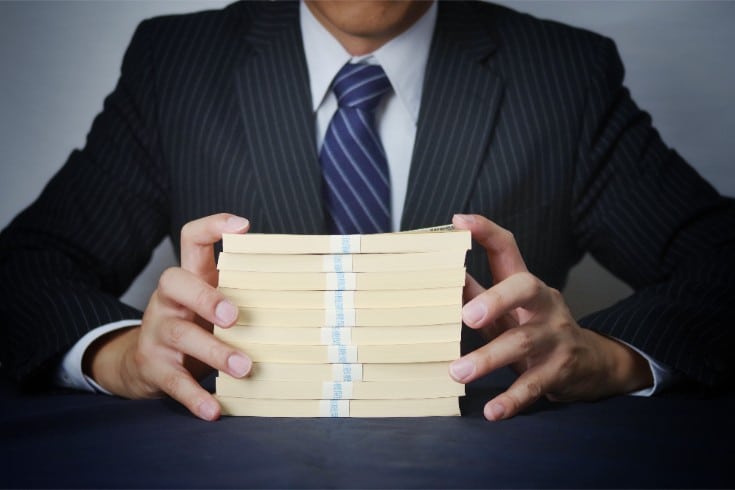иЈңеҠ©йҮ‘дёҚжӯЈеҸ—зөҰгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹзөҢе–¶йҷЈгҒ®ж°‘дәӢжҗҚе®іиі е„ҹиІ¬д»»гҒҢе•ҸгӮҸгӮҢгҒҹз”Іеәңең°иЈҒе№іжҲҗ18е№ҙ10жңҲ3ж—ҘеҲӨжұә

дјҒжҘӯгӮ„жі•дәәгӮ’ж–°гҒҹгҒ«еј•гҒҚз¶ҷгҒ„гҒ зөҢе–¶иҖ…гҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜжҠ•иіҮе…ҲдјҒжҘӯгҒ®дёҚзҘҘдәӢгӮ’зҷәиҰӢгҒ—гҒҹж Әдё»гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒйҮҚиҰҒгҒӘиӘІйЎҢгҒ®дёҖгҒӨгҒҜгҖҒйҒҺеҺ»гҒ®дёҚжӯЈиЎҢзӮәгӮ’жі•зҡ„гҒ«жё…з®—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
ж—§зөҢе–¶йҷЈгӮ„еҪ№е“ЎгҒ«гӮҲгӮӢиЈңеҠ©йҮ‘гғ»еҠ©жҲҗйҮ‘гҒ®дёҚжӯЈеҸ—зөҰгӮ„з§Ғзҡ„жөҒз”ЁгҒҜгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢзө„з№”гҒ®дҝЎз”Ёе•ҸйЎҢгҒ§зөӮгӮҸгӮүгҒҡгҖҒжі•дәәпјҲдјҡзӨҫпјүгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжҗҚе®іиі е„ҹиІ¬д»»гӮ’зҷәз”ҹгҒ•гҒӣгӮӢдёҚжі•иЎҢзӮәгҒ§гҒҷгҖӮгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҒж–°зөҢе–¶йҷЈгӮ„ж Әдё»гҒҜгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹиЎҢзӮәгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹж—§зөҢе–¶йҷЈгӮ„еҪ№е“ЎгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒдјҡзӨҫгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжҗҚе®іиі е„ҹгҒ®и«ӢжұӮгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮж–°гҒҹгҒӘдҪ“еҲ¶гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒдёҚжӯЈгҒ®жё…з®—гҒҜгҖҒзө„з№”гҒ®иІЎеӢҷеҒҘе…ЁжҖ§гӮ’еӣһеҫ©гҒ—гҖҒгӮігғјгғқгғ¬гғјгғҲгғ»гӮ¬гғҗгғҠгғігӮ№гӮ’зўәз«ӢгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гӮӮеҝ…иҰҒгҒӘгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
жң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒзӨҫдјҡзҰҸзҘүжі•дәәгӮ’иҲһеҸ°гҒ«гҖҒж—§дҪ“еҲ¶гҒҢж–ҪиЁӯгҒ®е»әиЁӯиІ»з”ЁгӮ’ж°ҙеў—гҒ—гҒ—гҒҰиЈңеҠ©йҮ‘гӮ’дёҚжӯЈгҒ«еҸ–еҫ—гҒ—гҖҒгҒқгҒ®иіҮйҮ‘гӮ’е…ғзҗҶдәӢгҒ®еҖӢдәәеӮөеӢҷгҒ®иҝ”жёҲгҒ«жөҒз”ЁгҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰж–°дҪ“еҲ¶гҒ«гӮҲгӮӢжҗҚе®іиі е„ҹи«ӢжұӮгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҖҒз”Іеәңең°иЈҒе№іжҲҗ18е№ҙ10жңҲ3ж—ҘеҲӨжұәгӮ’еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иЈҒеҲӨдҫӢгҒҜгҖҒж–°гҒ—гҒҸд»ЈиЎЁжЁ©гӮ’жҸЎгҒЈгҒҹиҖ…гҖҒM&AгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰдјҒжҘӯдҫЎеҖӨгҒ®жҜҖжҗҚгҒ«зӣҙйқўгҒ—гҒҹж–°ж Әдё»е…јзөҢе–¶иҖ…гҖҒгҒқгҒ—гҒҰж Әдё»д»ЈиЎЁиЁҙиЁҹгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢжҠ•иіҮ家гҒӘгҒ©гҖҒгҖҢдёҚжӯЈгӮ’иҝҪеҸҠгҒҷгӮӢз«Ӣе ҙгҖҚгҒ®еҒҙгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒдёҚжӯЈжё…з®—гҒ®е®ҹзҸҫеҸҜиғҪжҖ§гӮ„гҖҒгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘжі•зҡ„иҰҒ件гӮ’зӨәгҒҷгӮӮгҒ®гҒ гҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®зӣ®ж¬Ў
жң¬д»¶жҗҚе®іиі е„ҹи«ӢжұӮдәӢ件гҒ®жҰӮиҰҒ
дәӢ件гҒ®иҲһеҸ°гҒЁдёҚжӯЈе®ҹиЎҢиҖ…гҒ®з«Ӣе ҙ
жң¬д»¶гҒ®еҺҹе‘ҠгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹжі•дәәгҒҜгҖҒи»ҪиІ»иҖҒдәәгғӣгғјгғ зӯүгҒ®зӨҫдјҡзҰҸзҘүдәӢжҘӯгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰиЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹзӨҫдјҡзҰҸзҘүжі•дәәгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жі•дәәгҒ®иЁӯз«ӢгҒЁгҖҒж–ҪиЁӯгҒ®е»әиЁӯгҒ«й–ўдёҺгҒ—гҒҹд»ҘдёӢгҒ®3еҗҚгҒҢгҖҒдёҚжӯЈеҸ—зөҰгӮ’дјҒгҒҰгҒҹе®ҹиЎҢзҠҜпјҲйҖЈеёҜиІ¬д»»иӘҚе®ҡиҖ…пјүгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
- е…ғзҗҶдәӢпјҲиў«е‘Ҡ1пјүпјҡжі•дәәиЁӯз«ӢеҪ“еҲқгҒ®зҗҶдәӢгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжі•дәәгҒ®жҘӯеӢҷе…ЁиҲ¬гӮ’зөұжӢ¬гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹдәәзү©гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®дәәзү©гҒ®еӨҡйЎҚгҒ®еҖӢдәәеӮөеӢҷгҒ®иҝ”жёҲгҒҢгҖҒдёҚжӯЈгӮ№гӮӯгғјгғ гҒ®жңҖеӨ§гҒ®еӢ•ж©ҹгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
- дјҒз”»дјҡзӨҫд»ЈиЎЁпјҲиў«е‘Ҡ2пјүпјҡжі•дәәиЁӯз«ӢгҒ®и©•иӯ°е“ЎгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҖҒдәӢжҘӯиЁҲз”»з«ӢжЎҲзӯүгҒ®жҘӯеӢҷгӮ’委託гҒ•гӮҢгҒҹдјҡзӨҫгҒ®д»ЈиЎЁиҖ…гҒ§гҒҷгҖӮдёҚжӯЈгӮ№гӮӯгғјгғ гҒ®з«ӢжЎҲиҖ…гҒ®дёҖдәәгҒЁгҒ—гҒҰж©ҹиғҪгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
- е»әиЁӯдјҡзӨҫеёёеӢҷеҸ–з· еҪ№пјҲиў«е‘Ҡ3пјүпјҡж–ҪиЁӯгҒ®иЁӯзҪ®дәӢеӢҷзӯүгҒ«й–ўдёҺгҒ—гҒҹдәәзү©гҒ§гҖҒе»әиЁӯдјҡзӨҫгҒ®еёёеӢҷеҸ–з· еҪ№гҒЁгҒ„гҒҶз«Ӣе ҙгҒ«гҒӮгӮҠгҒӘгҒҢгӮүгҖҒдёҚжӯЈеҸ—зөҰгҒ®е®ҹиЎҢеҪ№гҒ®дёҖдәәгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
иЈңеҠ©йҮ‘дёҚжӯЈеҸ—зөҰгҒ®жүӢеҸЈ
дёҚжӯЈгҒ®жүӢеҸЈгҒҜгҖҒе…¬зҡ„иіҮйҮ‘гҒ§гҒӮгӮӢиЈңеҠ©йҮ‘гӮ’жңҖеӨ§йҷҗгҒ«йЁҷгҒ—еҸ–гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒж–ҪиЁӯгҒ®е»әиЁӯиІ»з”ЁгӮ’ж°ҙеў—гҒ—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒдёҚжӯЈеҸ—зөҰгҒ•гӮҢгҒҹиЈңеҠ©йҮ‘гҒҢгҖҒдёҠиЁҳгҒ®е…ғзҗҶдәӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз§Ғзҡ„жөҒз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
- дёҚжӯЈгҒӘиЁҲз”»гҒ®е…ұи¬Җпјҡжі•дәәиЁӯз«Ӣд»ҘеүҚгҒӢгӮүгҖҒе…ғзҗҶдәӢпјҲиў«е‘Ҡ1пјүгҖҒдјҒз”»дјҡзӨҫд»ЈиЎЁпјҲиў«е‘Ҡ2пјүгҖҒе»әиЁӯдјҡзӨҫеёёеӢҷеҸ–з· еҪ№пјҲиў«е‘Ҡ3пјүгҒ®3еҗҚгҒҜгҖҒжі•дәәиЁӯз«ӢеҫҢгҒ«дәӨд»ҳгҒ•гӮҢгӮӢиЈңеҠ©йҮ‘гӮ„еҖҹе…ҘйҮ‘гҒ®дёҖйғЁгӮ’гҖҒе…ғзҗҶдәӢгҒ®жҠұгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹеҖӢдәәеӮөеӢҷпјҲеҗҲиЁҲ1е„„2000дёҮеҶҶпјүгҒ®иҝ”жёҲгҒ«е……гҒҰгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’дјҒгҒҰгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
- ж°ҙеў—гҒ—и«ӢжұӮгҒ®е®ҹиЎҢпјҡе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜ6е„„7980дёҮеҶҶгҒ—гҒӢиҰҒгҒ—гҒӘгҒ„е»әиЁӯдәӢжҘӯиІ»гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒ8е„„2030дёҮеҶҶгӮ’иҰҒгҒ—гҒҹгҒЁгҒҷгӮӢиҷҡеҒҪгҒ®з”іи«ӢгӮ’еұұжўЁзңҢгҒ«иЎҢгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒиЁӯеӮҷж•ҙеӮҷиІ»гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒе®ҹйҡӣгӮҲгӮҠй«ҳйЎҚгҒӘз”іи«ӢгӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
- е·®йЎҚгҒ®жҚ»еҮәгҒЁжөҒз”Ёпјҡе·ҘдәӢи«ӢиІ д»ЈйҮ‘гӮ’8е„„2030дёҮеҶҶгҒЁгҒҷгӮӢгҖҢиЎЁгҒ®еҘ‘зҙ„гҖҚгҒЁгҖҒд»ЈйҮ‘гӮ’6е„„7980дёҮеҶҶгҒ«жёӣйЎҚгҒҷгӮӢгҖҢиЈҸгҒ®еҘ‘зҙ„гҖҚгӮ’зөҗгҒігҖҒгҒқгҒ®е·®йЎҚзҙ„1е„„4050дёҮеҶҶгӮ’дёҚжӯЈгҒ«жҚ»еҮәгҖӮгҒ“гҒ®зөҗжһңгҖҒеҗҲиЁҲ1е„„9691дёҮ2479еҶҶгӮ’дёҚжӯЈгҒ«еҸ—зөҰгҒ—гҒҹгҒЁиӘҚе®ҡгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®дёҚжӯЈеҸ—зөҰгҒ«й–ўдёҺгҒ—гҒҹе…ғзҗҶдәӢгӮү3еҗҚгҒҜгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҖҒиЈңеҠ©йҮ‘йҒ©жӯЈеҢ–жі•йҒ•еҸҚеҸҠгҒіи©җж¬әзҪӘгҒ§иө·иЁҙгҒ•гӮҢгҖҒеҹ·иЎҢзҢ¶дәҲд»ҳгҒҚгҒ®жңүзҪӘеҲӨжұәгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒгҒ“гӮҢгҒҢзўәе®ҡгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
ж—§дҪ“еҲ¶гҒӢгӮүгҒ®жЁ©йҷҗеҘӘйӮ„гҒЁиЁҙиЁҹжҸҗиө·

дёҚжӯЈиЎҢзӮәгҒ®е®ҹиЎҢеҪ“жҷӮгҖҒдёҚжӯЈгҒ«й–ўдёҺгҒ—гҒҹе…ғзҗҶдәӢпјҲиў«е‘Ҡ1пјүгҒҜжі•дәәгҒ®жҘӯеӢҷе…ЁиҲ¬гӮ’зөұжӢ¬гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮжі•дәәеҗҚзҫ©гҒ§гҒ®иҷҡеҒҪгҒ®з”іи«ӢгӮ„иіҮйҮ‘гҒ®еҸЈеә§з§»еӢ•гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®ж—§дҪ“еҲ¶дёӢгҒ§иЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж–°дҪ“еҲ¶гҒЁгҒ—гҒҰйҒҺеҺ»гҒ®дёҚжӯЈгӮ’иҝҪеҸҠгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒгҒҫгҒҡдёҚжӯЈиЎҢзӮәиҖ…гӮ’жі•дәәгҒ®д»ЈиЎЁжЁ©гӮ„жҘӯеӢҷеҹ·иЎҢгҒӢгӮүе®Ңе…ЁгҒ«жҺ’йҷӨгҒ—гҖҒиҝҪеҸҠгҒ®ж„ҸжҖқгӮ’жҢҒгҒЈгҒҹиҖ…гҒҢжі•дәәгҒ®д»ЈиЎЁжЁ©гӮ’жҺҢжҸЎгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…й ҲгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮжң¬д»¶гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒд»ҘдёӢгҒ®зөҢз·ҜгҒ§ж–°дҪ“еҲ¶гҒҢд»ЈиЎЁжЁ©гӮ’зўәдҝқгҒ—гҖҒиЁҙиЁҹжҸҗиө·гӮ’е®ҹзҸҫгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
дёҚжӯЈе®ҹиЎҢжҷӮгҒ®д»ЈиЎЁжЁ©гҒ®зҠ¶жіҒгҒЁжЁ©йҷҗгҒ®ж··д№ұ
е…ғзҗҶдәӢпјҲиў«е‘Ҡ1пјүгҒҜгҖҒжі•дәәиЁӯз«ӢеҪ“еҲқгҒӢгӮүгҒ®зҗҶдәӢгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжҘӯеӢҷе…ЁиҲ¬гӮ’зөұжӢ¬гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒеӨҡйЎҚгҒ®еҖӢдәәеӮөеӢҷгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒеҲҘгҒ®дәәзү©гҒҢеҪўејҸзҡ„гҒ«зҗҶдәӢй•·гҒ«е°ұд»»гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒдёҚжӯЈе®ҹиЎҢжҷӮгҒ«гҒҜиў«е‘Ҡ1гӮүгҒҢжҘӯеӢҷгӮ’дё»е°ҺгҒ—гҖҒжі•дәәгҒ®иіҮйҮ‘гӮ’з§Ғзҡ„гҒ«жөҒз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮдёҚжӯЈгҒҢзҷәиҰҡгҒ—гҒҹеҫҢгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®зҗҶдәӢдјҡгҒҜиў«е‘Ҡ1гӮүгҒ®иҫһд»»гӮ’гӮҒгҒҗгҒЈгҒҰж··д№ұгҒ—гҖҒжӯЈеёёгҒ«йҒӢе–¶гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„зҠ¶ж…ӢгҒ«йҷҘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
жүҖиҪ„еәҒгҒ®д»Ӣе…ҘгҒЁж–°дҪ“еҲ¶гҒ®зўәз«Ӣ
зҗҶдәӢдјҡгҒҢж©ҹиғҪдёҚе…ЁгҒ«йҷҘгҒЈгҒҹзөҗжһңгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®зҗҶдәӢе…Ёе“ЎгҒҢд»»жңҹжәҖдәҶгҒ§йҖҖд»»гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒжүҖиҪ„еәҒгҒ§гҒӮгӮӢеұұжўЁзңҢзҹҘдәӢгҒҢгҖҒзӨҫдјҡзҰҸзҘүжі•гҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒ3еҗҚгҒ®д»®зҗҶдәӢгӮ’йҒёд»»гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶжҺӘзҪ®гӮ’еҸ–гӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®иЎҢж”ҝгҒ«гӮҲгӮӢд»Ӣе…ҘгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒиҝҪеҸҠгҒ®ж„ҸжҖқгӮ’жҢҒгҒЈгҒҹдәәзү©гҒҢжі•дәәгҒ®жӯЈејҸгҒӘд»ЈиЎЁиҖ…гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮд»®зҗҶдәӢгҒ«йҒёд»»гҒ•гӮҢгҒҹ3дәәгҒҜгҖҒжӯЈејҸгҒӘзҗҶдәӢгӮ’йҒёд»»гҒ—гҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҖҒгҒқгҒ®гҒҶгҒЎгҒ®1еҗҚгҒҢзҗҶдәӢй•·гҒ«йҒёд»»гҒ•гӮҢгҖҒжі•дәәгҒ®д»ЈиЎЁжЁ©гӮ’зўәдҝқгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҜгҖҒж ӘејҸдјҡзӨҫгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒж Әдё»гҒҢж—§зөҢе–¶йҷЈгӮ’и§Јд»»гҒ—гҖҒж Әдё»еҒҙгҒ®ж–°зөҢе–¶йҷЈгӮ’д»»е‘ҪгҒҷгӮӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҖҒж Әдё»гҒ«гӮҲгӮӢд»Ӣе…ҘгҒ«зӣёеҪ“гҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ гҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
ж–°дҪ“еҲ¶гҒ«гӮҲгӮӢиЁҙиЁҹжұәиӯ°гҒ®е®ҹиЎҢ
е№іжҲҗ14е№ҙ6жңҲ20ж—ҘгҖҒж–°зҗҶдәӢй•·гҒҢе°ұд»»гҒ—гҒҹж–°зҗҶдәӢдјҡгҒҢй–ӢеӮ¬гҒ•гӮҢгҖҒдёҚжӯЈгҒ«й–ўдёҺгҒ—гҒҹе…ғзҗҶдәӢгӮү3еҗҚгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгҖҢиІёд»ҳйҮ‘иҝ”йӮ„и«ӢжұӮиЁҙиЁҹгӮ’иЎҢгҒҶж—ЁгҒ®жұәиӯ°гҖҚгӮ’жҺЎжҠһгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒдёҚжӯЈиЎҢзӮәиҖ…гҒҢжЁ©йҷҗгӮ’жҸЎгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒ§гӮӮгҖҒжүҖиҪ„еәҒгҒ®жҢҮе°ҺгӮ„гҖҒж ӘејҸдјҡзӨҫгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҪ№е“ЎдәӨд»ЈгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒжі•дәәгҒ®д»ЈиЎЁжЁ©гӮ’зўәдҝқгҒ§гҒҚгӮҢгҒ°гҖҒйҒҺеҺ»гҒ®дёҚжӯЈиЎҢзӮәиҖ…гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжҗҚе®іиі е„ҹи«ӢжұӮиЁҙиЁҹгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒж ӘејҸдјҡзӨҫгҒ®е ҙеҗҲгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒж Әдё»д»ЈиЎЁиЁҙиЁҹгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҗҢж§ҳгҒ®иЁҙиЁҹгӮ’жҸҗиө·гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶйҒёжҠһиӮўгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
е…ұеҗҢдёҚжі•иЎҢзӮәгҒ®з«ӢиЁј
ж–°дҪ“еҲ¶гҒҢиЁҙиЁҹгӮ’жҸҗиө·гҒ—гҒҹеҫҢгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҢе…ғзҗҶдәӢпјҲиў«е‘Ҡ1пјүгҖҒдјҒз”»дјҡзӨҫд»ЈиЎЁпјҲиў«е‘Ҡ2пјүгҖҒе»әиЁӯдјҡзӨҫеёёеӢҷеҸ–з· еҪ№пјҲиў«е‘Ҡ3пјүгҒ®3еҗҚгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒ7604дёҮеҶҶгӮ’и¶…гҒҲгӮӢйҖЈеёҜиІ¬д»»гӮ’иӘҚе®ҡгҒ—гҒҹж №жӢ гҒҜгҖҒеҪјгӮүгҒ«гӮҲгӮӢе…ұеҗҢдёҚжі•иЎҢзӮәпјҲж°‘жі•719жқЎ1й …пјүгҒ®жҲҗз«ӢгҒ§гҒҷгҖӮ
зӣёдә’гҒ®ж„ҸжҖқгӮ’йҖҡгҒҳгҒҹгҖҢе…ұи¬ҖгҖҚгҒ®иӘҚе®ҡ
ж°‘дәӢиІ¬д»»иҝҪеҸҠгҒ®жңҖеӨ§гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒҜгҖҢдёҚжӯЈе®ҹиЎҢиҖ…гҒҹгҒЎгҒҢе…ұи¬ҖгҒ—гҒҰдёҚжі•иЎҢзӮәгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгҖҚгҒ“гҒЁгҒ®з«ӢиЁјгҒ§гҒҷгҖӮиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®3еҗҚгҒҢгҖҒдёҚжӯЈеҸ—зөҰгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҫ—гӮүгӮҢгҒҹйҮ‘е“ЎгӮ’е…ғзҗҶдәӢпјҲиў«е‘Ҡ1пјүгҒ®еҖӢдәәеӮөеӢҷиҝ”жёҲгҒ«е……гҒҰгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҖҒжі•дәәиЁӯз«Ӣд»ҘеүҚгҒӢгӮүгҖҢзӣёдә’гҒ«ж„ҸжҖқгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒдјҒгҒҰгҖҒзҸҫгҒ«е®ҹиЎҢгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиӘҚе®ҡгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
еҲ‘дәӢзўәе®ҡеҲӨжұәгҒ®жҙ»з”Ё
гҒ“гҒ®иӘҚе®ҡгӮ’жұәе®ҡгҒҘгҒ‘гҒҹеј·еҠӣгҒӘиЁјжӢ гҒҜгҖҒ3еҗҚгҒҢж—ўгҒ«иЈңеҠ©йҮ‘йҒ©жӯЈеҢ–жі•йҒ•еҸҚеҸҠгҒіи©җж¬әзҪӘгҒ§жңүзҪӘеҲӨжұәгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰзўәе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶдәӢе®ҹгҒ§гҒҷгҖӮ
еҲ‘дәӢзҪ°гҒҢзўәе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶдәӢе®ҹгҒҜгҖҒж°‘дәӢиЈҒеҲӨгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒиў«е‘ҠгӮүгҒҢгҖҢж•…ж„ҸгҖҚгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰдёҚжӯЈиЎҢзӮәгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҖҒгҒқгҒ—гҒҰдёҚжӯЈгҒ®гҖҢе…ұи¬ҖгҖҚгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’з«ӢиЁјгҒҷгӮӢдёҠгҒ§гҖҒиЁјжҳҺеҠӣгҒ®й«ҳгҒ„иЁјжӢ гҒЁгҒ—гҒҰеј·еҠӣгҒ«дҪңз”ЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮиҝҪеҸҠеҒҙгҒҜгҖҒеҲ‘дәӢдәӢ件гҒ®йҒҺзЁӢгҒ§жҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹдәӢе®ҹгӮ’жңҖеӨ§йҷҗжҙ»з”ЁгҒҷгҒ№гҒҚгҒ§гҒҷгҖӮ
е…¬зҡ„иіҮйҮ‘гҒ®зӣ®зҡ„еӨ–еҲ©з”Ё
иў«е‘ҠеҒҙгҒҜгҖҒжөҒз”ЁгҒ—гҒҹиіҮйҮ‘гҒҢжі•дәәгҒ®иЁӯз«Ӣжә–еӮҷгҒ«й–ўйҖЈгҒҷгӮӢеҖӢдәәеӮөеӢҷгҒ®иҝ”жёҲгҒ«е……гҒҰгӮүгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒз§Ғзҡ„жөҒз”ЁгҒ«гҒҜеҪ“гҒҹгӮүгҒӘгҒ„гҒЁдё»ејөгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҒ“гӮҢгӮ’е…Ёйқўзҡ„гҒ«жҺ’ж–ҘгҒ—гҖҒе…¬зҡ„иіҮйҮ‘гҒ®дёҚжӯЈжөҒз”ЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰжҘөгӮҒгҒҰеҺіж јгҒӘеҲӨж–ӯгӮ’дёӢгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
иЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒиЈңеҠ©йҮ‘зӯүгҒ®зӣ®зҡ„гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҖҢеҺҹе‘ҠгҒ«дәӨд»ҳгҒ•гӮҢгҒҹиЈңеҠ©йҮ‘гӮ„дәӢжҘӯеӣЈгҒӢгӮүгҒ®еҖҹе…ҘйҮ‘гҒҜгҖҒиЁӯз«ӢеҫҢгҒ®жі•дәәгҒ®еҝ…иҰҒиІ»з”ЁгӮ’ж”ҜжҸҙгҒҷгӮӢзӣ®зҡ„гҒ§дәӨд»ҳгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜиІёгҒ—д»ҳгҒ‘гҒ•гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиЁӯз«ӢгҒ®жә–еӮҷиіҮйҮ‘гӮ„еҜ„йҷ„иҖ…гҒ®иІ еӮөгӮ’иҝ”жёҲгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰж”ҜзөҰгҒ•гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҜжҳҺгӮүгҒӢгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁеҲӨзӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®еҲӨзӨәгҒҜгҖҒиЈңеҠ©йҮ‘гғ»еҠ©жҲҗйҮ‘гҒ®дҪҝйҖ”гҒҜеҺіж јгҒ«йҷҗе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲжі•дәәгҒ®иЁӯз«Ӣжә–еӮҷгҒ«й–“жҺҘзҡ„гҒ«й–ўгӮҸгӮӢиІ»з”ЁгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒеҖӢдәәгҒ®иІ еӮөиҝ”жёҲгҒ«е……гҒҰгӮӢиЎҢзӮәгҒҜгҖҒжі•дәәгҒ®еҲ©зӣҠгҒ«еҸҚгҒҷгӮӢгҖҢз§Ғзҡ„жөҒз”ЁгҖҚгҒ«и©ІеҪ“гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеҲӨж–ӯгҒ гҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
дёҚжӯЈеҸ—зөҰгҒ«гӮҲгӮӢжҗҚе®ійЎҚгҒ®з®—е®ҡгҒЁз«ӢиЁј

еҺҹе‘Ҡжі•дәәгҒҜгҖҒж°ҙеў—гҒ—гҒ•гӮҢгҒҹиЈңеҠ©йҮ‘гҒ®е·®йЎҚе…ЁдҪ“гӮ„延ж»һйҮ‘гӮ’еҗ«гӮҖзҙ„2е„„еҶҶгҒ®иі е„ҹгӮ’жұӮгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҢжңҖзөӮзҡ„гҒ«иӘҚе®ҡгҒ—йҖЈеёҜж”Ҝжү•гҒ„гӮ’е‘ҪгҒҳгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒйҮ‘7604дёҮ9446еҶҶгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
иӘҚе®ҡжҗҚе®ійЎҚгҒ®ж №жӢ
иЈҒеҲӨжүҖгҒҢз§Ғзҡ„жөҒз”ЁгҒ«гӮҲгӮӢжҗҚе®ігҒЁгҒ—гҒҰиӘҚе®ҡгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒеҗҲиЁҲ7255дёҮеҶҶгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®йҮ‘йЎҚгҒҜгҖҒиў«е‘Ҡ1гҒ®еҖӢдәәеҸЈеә§гҒ«гҖҢзөҰдёҺгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰжүұгӮҸгӮҢгӮӢеҪўгҒ§жҢҜгӮҠиҫјгҒҫгӮҢгҒҹйҮ‘йЎҚгҒ§гҒҷгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒеҺҹе‘Ҡжі•дәәгҒ®й җйҮ‘еҸЈеә§гҒӢгӮүе…ғзҗҶдәӢпјҲиў«е‘Ҡ1пјүгҒ®еҖӢдәәеҸЈеә§гҒ«ж”Ҝжү•гӮҸгӮҢгҒҹеҗҲиЁҲ7327дёҮеҶҶдҪҷгӮҠгҒ®гҒҶгҒЎгҖҒ7255дёҮеҶҶгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒзЁҺеӢҷжүӢз¶ҡгҒ®дёӯгҒ§е…ғзҗҶдәӢгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢгҖҢзөҰдёҺгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰжүұгӮҸгӮҢгҖҒйҮҚеҠ з®—зЁҺгҒҢиӘІгҒӣгӮүгӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶзөҢз·ҜгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒзЁҺеӢҷеҪ“еұҖгҒҢжі•дәәгҒ®дәӢжҘӯйҒӢе–¶гҒЁгҒҜз„Ўй–ўдҝӮгҒӘгҖҢзөҰдёҺгҖҚгҒЁиӘҚе®ҡгҒ—иӘІзЁҺгҒ—гҒҹдәӢе®ҹгӮ’йҮҚиҰ–гҒ—гҖҒгҖҢгӮӮгҒЈгҒұгӮүгҖҚиў«е‘Ҡ1гҒ®гҖҢеҖӢдәәгҒ®еҲ©зӣҠгӮ’еӣігӮӢгҒҹгӮҒгҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒЁиӘҚгӮҒгӮӢгҒ®гҒҢзӣёеҪ“гҖҚгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹгҖҒдёҚжӯЈеҸ—зөҰгҒЁз§Ғзҡ„жөҒз”ЁгҒ®дәӢжЎҲгҒ§гҒҜгҖҒдјҡзӨҫгҒҢи«ӢжұӮеҸҜиғҪгҒӘжҗҚе®іиі е„ҹгҒҜгҖҒгҒқгҒ®жөҒз”ЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰдјҡзӨҫгҒ«з”ҹгҒҳгҒҹжҗҚе®ігҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒҜеҺҹеүҮзҡ„гҒ«гҒҜгҖҒпјҲдјҡзӨҫгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸпјүеҖӢдәәгҒ®еҲ©зӣҠгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«е…·дҪ“зҡ„гҒ«жөҒз”ЁгҒ•гӮҢгҒҹйҮ‘йЎҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®иЁјжӢ гҒҜгҖҒзЁҺеӢҷгғ»дјҡиЁҲдёҠгҒ®еҮҰзҗҶиЁҳйҢІзӯүгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дёҖйғЁиў«е‘ҠгҒёгҒ®и«ӢжұӮгҒ®жЈ„еҚҙ
жң¬д»¶гҒ§гҒҜгҖҒдёҚжӯЈгҒ«й–ўдёҺгҒ—гҒҹгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢ6еҗҚгҒ®иў«е‘ҠгҒ®гҒҶгҒЎгҖҒдјҡиЁҲдәӢеӢҷжүҖиҒ·е“ЎгӮ„е»әиЁӯдјҡзӨҫгҒӘгҒ©гҒёгҒ®и«ӢжұӮгҒҜжЈ„еҚҙгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еўғз•Ңз·ҡгҒҜгҖҒиҝҪеҸҠиҖ…гҒҢиІ¬д»»гӮ’иІ гҒҶгҒ№гҒҚеҜҫиұЎгӮ’зөһгӮҠиҫјгӮҖдёҠгҒ§йҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҡгҖҒдјҡиЁҲдәӢеӢҷжүҖиҒ·е“ЎгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиІ¬д»»гҒҜеҗҰе®ҡгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®иҒ·е“ЎгҒҜгҖҒдёҠеҸёгӮ„е®ҹиЎҢеҪ№гҒ®жҢҮзӨәгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒй җйҮ‘еҸЈеә§гҒ®еҮәе…ҘйҮ‘гҒЁгҒ„гҒҶгҖҢж©ҹжў°зҡ„гҒӘдәӢеӢҷгҖҚгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгҒ«йҒҺгҒҺгҒӘгҒ„гҒЁиӘҚе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒеҪ“и©ІиҒ·е“ЎгҒҢгҖҒдёҚжӯЈгҒӘз§Ғзҡ„жөҒз”ЁгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҢиҮӘгӮүиӘҚиӯҳгҒ—гҒҰгҖҒиў«е‘ҠгҖҚгҖҢгӮүгҒ®з§Ғзҡ„дёҚжӯЈжөҒз”ЁгҒ«еҠ жӢ…гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’иӘҚгӮҒгӮӢгҒ«и¶ігӮҠгӮӢзҡ„зўәгҒӘиЁјжӢ гҒҜгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒе…ұеҗҢдёҚжі•иЎҢзӮәгҒ®жҲҗз«ӢгӮ’еҗҰе®ҡгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
ж¬ЎгҒ«гҖҒе»әиЁӯдјҡзӨҫпјҲгҒЁгҒ„гҒҶжі•дәәпјүгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢдҪҝз”ЁиҖ…иІ¬д»»и«ӢжұӮгӮӮжЈ„еҚҙгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒдёҚжӯЈе®ҹиЎҢеҪ№гҒ®дёҖдәәгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹе»әиЁӯдјҡзӨҫеёёеӢҷеҸ–з· еҪ№пјҲиў«е‘Ҡ3пјүгҒҜеҖӢдәәгҒЁгҒ—гҒҰйҖЈеёҜиІ¬д»»гӮ’иІ гҒҶдёҖж–№гҒ§гҖҒгҒқгҒ®дҪҝз”ЁиҖ…гҒ§гҒӮгӮӢе»әиЁӯдјҡзӨҫгҒёгҒ®дҪҝз”ЁиҖ…иІ¬д»»пјҲж°‘жі•715жқЎпјүгҒ«еҹәгҒҘгҒҸи«ӢжұӮгҒҜеҗҰе®ҡгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒиў«е‘Ҡ3гҒ®иЎҢзӮәгҒҜгҖҒе»әиЁӯдјҡзӨҫпјҲгҒЁгҒ„гҒҶжі•дәәпјүгҖҢгҒ®еҲ©зӣҠгӮ’еәҰеӨ–иҰ–гҒ—гҖҒгӮӮгҒЈгҒұгӮүиЁӯз«ӢеүҚгҒ®еҺҹе‘ҠгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜиў«е‘ҠгҖҚгҖҢ1гӮүгҒ®еҲ©зӣҠгӮ’еӣігӮҚгҒҶгҒЁгҒ®зӣ®зҡ„гҒ®гӮӮгҒЁиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҖҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒдјҡзӨҫгҒ®дәӢжҘӯжҙ»еӢ•гҒЁгҒҜеҲҮгӮҠйӣўгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢеҖӢдәәзҡ„гҒӘиЎҢзӮәгҖҚгҒЁгҒҝгҒӘгҒ—гҖҒе»әиЁӯдјҡзӨҫгҖҢгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиҒ·еӢҷеҹ·иЎҢгҒ®зҜ„еӣІеҶ…гҒ®гӮӮгҒ®гҒЁгҒҜиӘҚгӮҒйӣЈгҒ„гҖҚгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒгҒӮгӮӢеҪ№е“ЎгҒӘгҒ©гҒ®дёҚжӯЈгҒҢдјҡзӨҫгҒ«гҒҜеҲ©зӣҠгӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒ•гҒҡгҖҒе°ӮгӮүеҖӢдәәгҒ®з§ҒзӣҠгӮ’еӣігӮӢзӣ®зҡ„гҒ§иЎҢгӮҸгӮҢгҒҹе ҙеҗҲгҒҜгҖҒдјҡзӨҫгӮ’зӣёжүӢгҒЁгҒ—гҒҹдҪҝз”ЁиҖ…иІ¬д»»гҒ®иҝҪеҸҠгҒҜеӣ°йӣЈгҒЁгҒӘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®е ҙеҗҲгҒҜдёҚжӯЈиЎҢзӮәиҖ…еҖӢдәәгҒёгҒ®иҝҪеҸҠгӮ’дё»и»ёгҒЁгҒҷгҒ№гҒҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒпјҡдёҚжӯЈеҸ—зөҰгҒ«й–ўгҒҷгӮӢзӣёи«ҮгҒҜејҒиӯ·еЈ«гҒё
з”Іеәңең°иЈҒе№іжҲҗ18е№ҙ10жңҲ3ж—ҘеҲӨжұәгҒҜгҖҒж–°дҪ“еҲ¶гҒ«гӮҲгӮӢйҒҺеҺ»гҒ®дёҚжӯЈгҒ®жё…з®—гҒҢгҖҒжі•зҡ„гҒ«еҸҜиғҪгҒӘгӮұгғјгӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒҷгӮӮгҒ®гҒ гҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮзү№гҒ«жң¬д»¶гҒ§гҒҜгҖҒж°‘дәӢгӮҲгӮҠе…ҲиЎҢгҒ—гҒҰиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹеҲ‘дәӢдәӢ件гҖҒжі•дәәгҒ®д»ЈиЎЁжЁ©гҒ®жҺҢжҸЎгҖҒгҒқгҒ—гҒҰиіҮйҮ‘дҪҝйҖ”гҒ«й–ўгҒҷгӮӢзЁҺеӢҷеҮҰзҗҶгҒҢгҖҒйҮҚиҰҒгҒӘиҰҒзҙ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
M&AеҫҢгҒ®ж–°зөҢе–¶йҷЈгҖҒдјҒжҘӯдҫЎеҖӨгҒ®еӣһеҫ©гӮ’зӣ®жҢҮгҒҷж–°ж Әдё»гҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгӮ¬гғҗгғҠгғігӮ№гҒ®жӯЈеёёеҢ–гӮ’зӣ®жҢҮгҒҷзҗҶдәӢй•·пјҲжң¬д»¶гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢж–°зҗҶдәӢй•·гҒ®з«Ӣе ҙпјүгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиЎҢеӢ•гӮ’иҝ…йҖҹгҒ«еҸ–гӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
- д»ЈиЎЁжЁ©гҒ®зўәдҝқгҒЁжЁ©йҷҗгҒ®иЎҢдҪҝпјҡгҒҫгҒҡгҖҒдёҚжӯЈиЎҢзӮәиҖ…гҒӢгӮүд»ЈиЎЁжЁ©гӮ’е®Ңе…ЁгҒ«еҲҮгӮҠйӣўгҒ—гҖҒжі•дәәгҒҢдё»дҪ“гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰиЁҙиЁҹгӮ’жҸҗиө·гҒ§гҒҚгӮӢдҪ“еҲ¶гӮ’зўәз«ӢгҒҷгӮӢгҒ№гҒҚгҒ§гҒҷгҖӮж ӘејҸдјҡзӨҫгҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒж–°еҸ–з· еҪ№гҒ«гӮҲгӮӢиЁҙиЁҹгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜж Әдё»гҒ«гӮҲгӮӢж Әдё»д»ЈиЎЁиЁҙиЁҹгҒ®жҸҗиө·гҒҢжӨңиЁҺеҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
- иЁјжӢ гҒ®еҸҺйӣҶпјҡеҲ‘дәӢиЈҒеҲӨгҒ®иЁҳйҢІгҖҒиЎҢж”ҝгҒ®иӘҝжҹ»е ұе‘ҠжӣёгҖҒгҒқгҒ—гҒҰжңҖгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘж—§зөҢе–¶йҷЈжҷӮд»ЈгҒ®дјҡиЁҲеёіз°ҝгҒЁзЁҺеӢҷз”іе‘ҠиЁҳйҢІгӮ’йҖҹгӮ„гҒӢгҒ«дҝқе…ЁгҒ—гҖҒгҒ©гҒ®йҮ‘е“ЎгҒҢз§Ғзҡ„жөҒз”ЁгҒ•гӮҢгҒҹгҒӢгӮ’зү№е®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
- е°Ӯй–Җ家гҒёгҒ®зӣёи«ҮпјҡиЈңеҠ©йҮ‘дёҚжӯЈеҸ—зөҰгҒҜгҖҒиЎҢж”ҝжі•гҖҒеҲ‘жі•гҖҒж°‘жі•гҒ®еўғз•ҢгӮ’гҒҫгҒҹгҒҗиӨҮйӣ‘гҒӘеҲҶйҮҺгҒ§гҒҷгҖӮдёҚжӯЈиҝҪеҸҠгӮ’жҲҗеҠҹгҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒеҲ‘дәӢејҒиӯ·гҒЁж°‘дәӢзҙӣдәүгҒ®еҸҢж–№гҒ«зІҫйҖҡгҒ—гҖҒиЈңеҠ©йҮ‘гӮ„еҠ©жҲҗйҮ‘гҒ®дёҚжӯЈеҸ—зөҰгҒ«й–ўгӮҸгӮӢжҘӯеӢҷгҒ®зөҢйЁ“гҒҢиұҠеҜҢгҒӘжі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒ«гҖҒиЁјжӢ дҝқе…ЁгҒ®ж®өйҡҺгҒӢгӮүзӣёи«ҮгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ гҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
еҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ«гӮҲгӮӢеҜҫзӯ–гҒ®гҒ”жЎҲеҶ…
гғўгғҺгғӘгӮ№жі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒҜгҖҒITгҖҒзү№гҒ«гӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲгҒЁжі•еҫӢгҒ®дёЎйқўгҒ«й«ҳгҒ„е°Ӯй–ҖжҖ§гӮ’жңүгҒҷгӮӢжі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒ§гҒҷгҖӮеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§гҒҜгҖҒжқұиЁјгғ—гғ©гӮӨгғ дёҠе ҙдјҒжҘӯгҒӢгӮүгғҷгғігғҒгғЈгғјдјҒжҘӯгҒҫгҒ§гҖҒгғ“гӮёгғҚгӮ№гғўгғҮгғ«гӮ„дәӢжҘӯеҶ…е®№гӮ’ж·ұгҒҸзҗҶи§ЈгҒ—гҒҹдёҠгҒ§жҪңеңЁзҡ„гҒӘжі•зҡ„гғӘгӮ№гӮҜгӮ’жҙ—гҒ„еҮәгҒ—гҖҒгғӘгғјгӮ¬гғ«гӮөгғқгғјгғҲгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдёӢиЁҳиЁҳдәӢгҒ«гҒҰи©ізҙ°гӮ’иЁҳијүгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ«гғҶгӮҙгғӘгғј: ITгғ»гғҷгғігғҒгғЈгғјгҒ®дјҒжҘӯжі•еӢҷ