ŃāóŃāŁŃāāŃé│ńÄŗÕøĮŃü¦Ńü«Õźæń┤äµøĖõĮ£µłÉŃā╗õ║żµĖēµÖéŃü½ÕĢÅķĪīŃü©Ńü¬Ńéŗµ░æµ│ĢŃā╗Õźæń┤äµ│Ģ
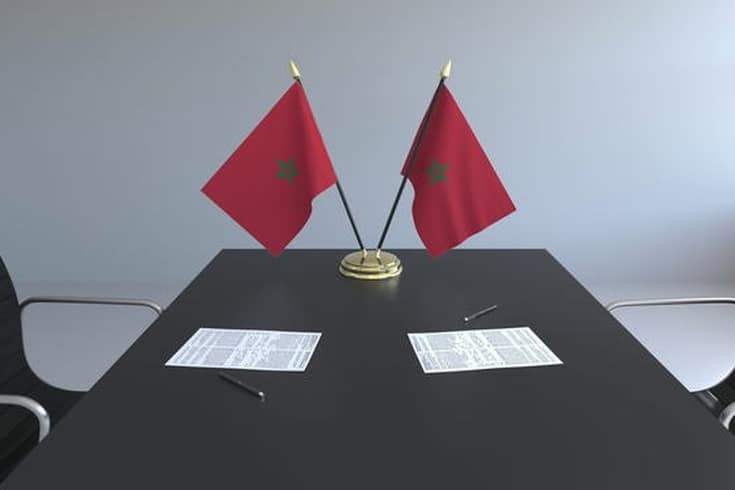
ŃāóŃāŁŃāāŃé│’╝łµŁŻÕ╝ÅÕÉŹń¦░ŃĆüŃāóŃāŁŃāāŃé│ńÄŗÕøĮ’╝ēŃü»ŃĆüÕ£░õĖŁµĄĘŃü©Õż¦Ķź┐µ┤ŗŃéÆńĄÉŃüČÕ£░ńÉåńÜäÕä¬õĮŹµĆ¦ŃĆüŃüØŃüŚŃü”Ķ┐æÕ╣┤Ńü«ńĄīµĖłķ¢ŗµöŠµö┐ńŁ¢Ńü½ŃéłŃéŖŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü½Ńü©ŃüŻŃü”ķŁģÕŖøńÜäŃü¬ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣Õ▒Ģķ¢ŗÕģłŃü«õĖĆŃüżŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüńĢ░µ¢ćÕī¢Õ£ÅŃü¦Ńü«õ║ŗµźŁµłÉÕŖ¤Ńü½Ńü»ŃĆüńÅŠÕ£░Ńü«µ│ĢÕłČÕ║”ŃĆüńē╣Ńü½Õźæń┤äµ│ĢŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗµĘ▒ŃüäńÉåĶ¦ŻŃüīõĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¦ŃüÖŃĆé
µ£¼Ķ©śõ║ŗŃü¦Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü©ÕÉīŃüśÕż¦ķÖĖµ│ĢŃü«ÕĤÕēćŃü½µĀ╣Ńü¢ŃüŚŃü¬ŃüīŃéēŃééŃĆüńŗ¼Ķć¬Ńü«Ķ”üõ╗ČŃéäĶ¦ŻķćłŃéƵīüŃüżŃāóŃāŁŃāāŃé│Ńü«Õźæń┤äµ│ĢŃü«µĀĖÕ┐āŃéÆŃĆüµŚźµ£¼Ńü«µ│ĢÕŗÖµŗģÕĮōĶĆģŃéäńĄīÕ¢ČĶĆģŃü«ńÜ嵦śŃü½ÕÉæŃüæŃü”ŃĆüÕ«¤ÕŗÖńÜäŃü¬Ķ”│ńé╣ŃüŗŃéēĶ®│ń┤░Ńü½Ķ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéÕźæń┤äŃü«µ£ēÕŖ╣Ķ”üõ╗ČŃüŗŃéēŃĆüńē╣Ńü½µ│©µäÅŃüÖŃü╣ŃüŹķøćńö©Õźæń┤äŃü«Õ«¤ÕŗÖŃĆüŃüĢŃéēŃü½Ńü»ÕłżõŠŗŃüīńż║ŃüÖµ│ĢńÜäŃā¬Ńé╣Ńé»Ńü«ÕéŠÕÉæŃüŠŃü¦ŃĆüŃāóŃāŁŃāāŃé│ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣Ńü«ń¼¼õĖƵŁ®ŃéÆĶĖÅŃü┐Õć║ŃüÖŃü¤ŃéüŃü«ķćŹĶ”üŃü¬µ│ĢńÜäń¤źĶ”ŗŃéÆŃüŖÕ▒ŖŃüæŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé┬Ā
Ńü¬ŃüŖŃĆüŃāóŃāŁŃāāŃé│Ńü«Õīģµŗ¼ńÜäŃü¬µ│ĢÕłČÕ║”Ńü«µ”éĶ”üŃü»õĖŗĶ©śĶ©śõ║ŗŃü½Ńü”ŃüŠŃü©ŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«Ķ©śõ║ŗŃü«ńø«µ¼Ī
ŃāóŃāŁŃāāŃé│Õźæń┤äµ│ĢŃü«Õ¤║ńżÄ
µäŵĆØĶ欵▓╗Ńü«ÕĤÕēćŃü©Õż¦ķÖĖµ│ĢŃü«ń│╗ĶŁ£
ŃāóŃāŁŃāāŃé│Ńü»ŃĆüŃüØŃü«µ│ĢÕłČÕ║”Ńü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüµŚźµ£¼Ńü©ÕÉīŃüśŃüÅÕż¦ķÖĖµ│Ģń│╗Ńü«ÕĤÕēćŃéƵÄĪńö©ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«µ│ĢõĮōń│╗Ńü«µĀ╣Õ╣╣Ńü½ŃüéŃéŗŃü«Ńü»ŃĆüŃĆīµäŵĆØĶ欵▓╗Ńü«ÕĤÕēć’╝łprincipe de l’autonomie des volont├®s’╝ēŃĆŹŃü©ŃüäŃüåĶĆāŃüłµ¢╣Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüÕźæń┤äŃüīÕĮōõ║ŗĶĆģķ¢ōŃü«Ķć¬ńö▒Ńü¬µäŵĆØŃü«ÕÉłĶć┤Ńü½ŃéłŃüŻŃü”µłÉń½ŗŃüŚŃĆüŃüØŃü«ÕåģÕ«╣ŃééÕĮōõ║ŗĶĆģŃü«ÕÉłµäÅŃü½ŃéłŃüŻŃü”Ķć¬ńö▒Ńü½ÕĮóµłÉŃüĢŃéīŃéŗŃü©ŃüäŃüåÕ¤║µ£¼ńÜäŃü¬µ│ĢńÜäµĆصā│ŃéÆńż║ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
Õźæń┤äµ│ĢŃü«õĖŁµĀĖŃéÆŃü¬ŃüÖŃĆÄńŠ®ÕŗÖÕÅŖŃü│Õźæń┤äµ│ĢÕģĖŃĆÅ
ŃāóŃāŁŃāāŃé│Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗÕźæń┤äµ│ĢŃü«µĀ╣Õ╣╣ŃéÆŃü¬ŃüÖŃü«Ńü»ŃĆü1913Õ╣┤Ńü½ÕłČÕ«ÜŃüĢŃéīŃü¤ŃĆÄńŠ®ÕŗÖÕÅŖŃü│Õźæń┤äµ│ĢÕģĖ’╝łDahir formant Code des obligations et des contrats’╝ēŃĆÅŃĆüķĆÜń¦░DOCŃü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃü«µ│ĢÕģĖŃü»ŃĆüµ░æõ║ŗÕźæń┤äÕģ©Ķł¼ŃüŗŃéēõĖŹµ│ĢĶĪīńé║’╝łd├®lit’╝ēŃéäµ║¢õĖŹµ│ĢĶĪīńé║’╝łquasi-d├®lit’╝ēŃüŠŃü¦ŃĆüÕ║āń»äŃü¬ķĀśÕ¤¤ŃéÆĶ”ÅÕ«ÜŃüÖŃéŗÕīģµŗ¼ńÜäŃü¬ŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃü«µ│ĢÕģĖŃüī1õĖ¢ń┤Ćõ╗źõĖŖÕēŹŃü½ÕłČÕ«ÜŃüĢŃéīŃü¤ŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃéŗŃüōŃü©Ńü»õ║ŗÕ«¤Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃāóŃāŁŃāāŃé│Ńü»ŃüōŃéīŃéÆķüÄÕÄ╗Ńü«ķü║ńöŻŃü©ŃüŚŃü”µöŠńĮ«ŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü¬ŃüÅŃĆüńÅŠõ╗ŻŃü«ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣ńÆ░ÕóāŃü½ķü®Õ┐£ŃüĢŃüøŃéŗŃü¤ŃéüŃü«ńČÖńČÜńÜäŃü¬µö╣µŁŻŃéÆÕŖĀŃüłŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃü¤Ńü©ŃüłŃü░ŃĆü2007Õ╣┤Ńü«µ│ĢÕŠŗń¼¼53.05ÕÅĘŃü½ŃéłŃéŖŃĆüķø╗ÕŁÉÕĢåÕÅ¢Õ╝ĢŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗĶ”ÅÕ«ÜŃüīµ│ĢÕģĖŃü½ńĄ▒ÕÉłŃüĢŃéīŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüķø╗ÕŁÉńÜäŃü¬µēŗµ«ĄŃü¦õĮ£µłÉŃā╗õ┐ØÕŁśŃüĢŃéīŃü¤µ│ĢńÜäĶĪīńé║ŃüīĶ¬ŹŃéüŃéēŃéīŃéŗŃéłŃüåŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃāóŃāŁŃāāŃé│Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗÕźæń┤äŃü«µ£ēÕŖ╣Ķ”üõ╗Č

µŚźµ£¼µ│ĢŃü©ÕÉīµ¦śŃĆüŃāóŃāŁŃāāŃé│µ│ĢŃü½ŃüŖŃüäŃü”Ńééµ£ēÕŖ╣Ńü¬Õźæń┤äŃéƵłÉń½ŗŃüĢŃüøŃéŗŃü¤ŃéüŃü½Ńü»ŃĆüńē╣Õ«ÜŃü«Ķ”üõ╗ČŃéƵ║ĆŃü¤ŃüÖÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃéēŃü«Ķ”üõ╗ČŃü½Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼µ│ĢŃü½Ńü»Ńü¬ŃüäŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»Ķ¦ŻķćłŃüīńĢ░Ńü¬ŃéŗķćŹĶ”üŃü¬Ķ”üń┤ĀŃüīÕŁśÕ£©ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüŃüØŃü«ķüĢŃüäŃéƵŁŻńó║Ńü½ńÉåĶ¦ŻŃüŚŃü”ŃüŖŃüÅŃüōŃü©ŃüīõĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¦ŃüÖŃĆé
ÕÉłµäÅ’╝łConsentement’╝ēŃü©µäŵĆØĶĪ©ńż║Ńü«ńæĢń¢Ą
Õźæń┤äŃü»ŃĆüÕĮōõ║ŗĶĆģķ¢ōŃü«µ£ēÕŖ╣Ńü¬µäŵĆØĶĪ©ńż║Ńü«ÕÉłĶć┤’╝łÕÉłµäÅ’╝ēŃü½ŃéłŃüŻŃü”µłÉń½ŗŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ÕĤÕēćŃü»µŚźµ£¼µ│ĢŃü©Õģ▒ķĆÜŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃüŚŃü”ŃĆüÕÉłµäÅŃü«µ£ēÕŖ╣µĆ¦ŃüīµÉŹŃü¬ŃéÅŃéīŃéŗŃĆīńæĢń¢ĄŃĆŹŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüŃĆÄńŠ®ÕŗÖÕÅŖŃü│Õźæń┤äµ│ĢÕģĖŃĆÅń¼¼39µØĪŃüīŃĆīķī»Ķ¬ż’╝łerreur’╝ēŃĆüĶ®Éµ¼║’╝łdol’╝ēŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»Õ╝ĘĶ┐½’╝łviolence’╝ēŃü½ŃéłŃüŻŃü”õĖÄŃüłŃéēŃéīŃü¤ÕÉīµäÅŃü»ńäĪÕŖ╣Ńü¦ŃüéŃéŗŃĆŹŃü©Ķ”ÅÕ«ÜŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»µŚźµ£¼Ńü«µ░æµ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗµäŵĆØĶĪ©ńż║Ńü«ńæĢń¢ĄŃü«Ķ”ÅÕ«ÜŃü©ķØ×ÕĖĖŃü½ķĪ×õ╝╝ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéÕ«¤ÕŗÖõĖŖŃü»ŃĆüµäŵĆØĶĪ©ńż║Ńü«ÕÉłĶć┤ŃéÆĶ©╝µśÄŃüÖŃéŗµēŗµ«ĄŃü©ŃüŚŃü”ŃĆüµøĖķØóŃü¦Ńü«Õźæń┤äńĘĀńĄÉŃüīÕ╝ĘŃüÅµÄ©Õź©ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüĢŃéēŃü½ŃĆüŃāóŃāŁŃāāŃé│Ńü¦Ńü»ŃĆüÕźæń┤äµøĖŃü½µ│ĢńÜäŃü¬ÕŖ╣ÕŖøŃéƵīüŃü¤ŃüøŃéŗŃü¤ŃéüŃü½ŃĆüńĮ▓ÕÉŹŃéÆÕģ¼Ķ©╝ÕĮ╣ÕĀ┤Ńéäńē╣Õ«ÜŃü«µ®¤ķ¢óŃü¦Ķ¬ŹĶ©╝ŃüŚŃü”ŃééŃéēŃüåŃĆīµŁŻÕĮōŃü¬Ķ¬ŹĶ©╝’╝łl├®galisation de la signature’╝ēŃĆŹŃüīÕ┐ģĶ”üŃü©Ńü¬ŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»µŚźµ£¼µ│ĢŃü½Ńü»Ńü¬ŃüäŃĆüÕźæń┤äńĘĀńĄÉµÖéŃü«ķćŹĶ”üŃü¬µēŗńČÜŃüŹŃü¦ŃüÖŃĆé┬Ā
ĶāĮÕŖø’╝łCapacit├®’╝ēŃü©Õźæń┤äÕĮōõ║ŗĶĆģŃü«ķü®µĀ╝µĆ¦
Õźæń┤äÕĮōõ║ŗĶĆģŃü»ŃĆüÕźæń┤äŃéÆńĘĀńĄÉŃüÖŃéŗµ│ĢńÜäĶāĮÕŖøŃéƵ£ēŃüŚŃü”ŃüäŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃüōŃü«ÕĤÕēćŃé鵌źµ£¼µ│ĢŃü©Õģ▒ķĆÜŃü«ŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆéŃĆÄńŠ®ÕŗÖÕÅŖŃü│Õźæń┤äµ│ĢÕģĖŃĆÅń¼¼3µØĪŃü»ŃĆüŃĆīµ│ĢÕŠŗŃü½ŃéłŃéŖÕ«ÜŃéüŃéēŃéīŃü¤ńäĪĶāĮÕŖøĶĆģŃéÆķÖżŃüŹŃĆüĶ¬░Ńü¦ŃééÕźæń┤äŃéÆńĄÉŃüČŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃéŗŃĆŹŃü©Õ«ÜŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüµ£¬µłÉÕ╣┤ĶĆģŃéäĶó½õ┐ØõĮÉõ║║Ńü©ŃüäŃüŻŃü¤ŃĆīńäĪĶāĮÕŖøĶĆģŃĆŹŃü«ĶĪīńé║Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüń¼¼5µØĪŃéäń¼¼9µØĪŃü¦ŃüØŃü«ÕŖ╣ÕŖøŃüīĶ®│ń┤░Ńü½Ķ”ÅÕ«ÜŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéń¼¼9µØĪŃü½Ńü»ŃĆīõ╗¢µ¢╣Ńü«ÕĮōõ║ŗĶĆģŃüīńŠ®ÕŗÖŃéÆÕ▒źĶĪīŃüŚŃü¤ŃüōŃü©Ńü½ŃéłŃéŖŃĆüµ£¬µłÉÕ╣┤ĶĆģŃüŠŃü¤Ńü»ńäĪĶāĮÕŖøĶĆģŃüīÕł®ńøŖŃéÆÕŠŚŃü¤ķÖÉÕ║”Ńü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüÕĖĖŃü½ŃüØŃü«ńŠ®ÕŗÖŃéÆĶ▓ĀŃüåŃĆŹŃü©ŃüäŃüåĶ”ÅÕ«ÜŃüīŃüéŃéŖŃĆüŃüōŃéīŃü»µŚźµ£¼Ńü«µ░æµ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕłČķÖÉĶĪīńé║ĶāĮÕŖøĶĆģÕłČÕ║”Ńü©õ╝╝Ńü¤µ¦ŗķĆĀŃü¦ŃüÖŃĆé┬Ā
ńø«ńÜä’╝łObjet’╝ēŃü«ńē╣Õ«ÜµĆ¦Ńü©ÕÉłµ│ĢµĆ¦
Õźæń┤äŃü«ńø«ńÜä’╝łobjet’╝ēŃü»ŃĆüÕÉłµ│ĢŃüŗŃüżńē╣Õ«ÜÕÅ»ĶāĮŃü¦Ńü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃĆÄńŠ®ÕŗÖÕÅŖŃü│Õźæń┤äµ│ĢÕģĖŃĆÅń¼¼58µØĪŃü»ŃĆüŃĆīńŠ®ÕŗÖŃü«Õ»ŠĶ▒ĪŃü©Ńü¬Ńéŗńē®Ńü»ŃĆüŃüØŃü«ń©«ķĪ×Ńü½ŃüŖŃüäŃü”Õ░æŃü¬ŃüÅŃü©Ńééńē╣Õ«ÜŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéēŃü¬ŃüäŃĆŹŃü©Õ«ÜŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüń¼¼59µØĪŃü»ŃĆīńē®ńÉåńÜäŃüŠŃü¤Ńü»µ│ĢńÜäŃü½õĖŹÕÅ»ĶāĮŃü¬ńē®ŃéÆńø«ńÜäŃü©ŃüÖŃéŗńŠ®ÕŗÖŃü»ńäĪÕŖ╣Ńü¦ŃüéŃéŗŃĆŹŃü©Ķ”ÅÕ«ÜŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéÕ░åµØźŃü«ńē®ŃéäĶĪīńé║ŃéÆńø«ńÜäŃü©ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃééÕĤÕēćŃü©ŃüŚŃü”ÕÅ»ĶāĮŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüµ│ĢÕŠŗŃü¦ń”üµŁóŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃéÆķÖżŃüŹŃüŠŃüÖ’╝łń¼¼61µØĪ’╝ēŃĆé┬Ā
µŚźµ£¼Ńü«µ░æµ│ĢŃü½Ńü»Ńü¬ŃüäÕĤÕøĀ’╝łCause’╝ē
ŃāóŃāŁŃāāŃé│Õźæń┤äµ│ĢŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīµ£ĆŃééµ│©µäÅŃéƵēĢŃüåŃü╣ŃüŹŃü»ŃĆīÕĤÕøĀ’╝łCause’╝ēŃĆŹŃü«µ”éÕ┐ĄŃü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»Õźæń┤äŃüīńĘĀńĄÉŃüĢŃéīŃü¤ŃĆīµŁŻÕĮōŃü¬ńÉåńö▒Ńéäńø«ńÜäŃĆŹŃéƵīćŃüŚŃĆüµŚźµ£¼µ│ĢŃü½Ńü»ńø┤µÄźńÜäŃü¬ÕÉīńŁēŃü«µ”éÕ┐ĄŃüīÕŁśÕ£©ŃüŚŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃĆÄńŠ®ÕŗÖÕÅŖŃü│Õźæń┤äµ│ĢÕģĖŃĆÅń¼¼62µØĪŃü»ŃĆīÕĤÕøĀŃü«Ńü¬ŃüäŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»ķüĢµ│ĢŃü¬ÕĤÕøĀŃü½Õ¤║ŃüźŃüÅńŠ®ÕŗÖŃü»ńäĪÕŖ╣Ńü¦ŃüéŃéŗŃĆŹŃü©µśÄĶ©śŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ŃĆīÕĤÕøĀŃĆŹŃü½Ńü»ŃĆüõ║īŃüżŃü«Õü┤ķØóŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé┬Ā
õĖĆŃüżŃü»ŃĆüÕ«óĶ”│ńÜäÕĤÕøĀ’╝łCause objective’╝ēŃü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»Õźæń┤äõĖŖŃü«ńŠ®ÕŗÖŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗńø┤µÄźńÜäŃü¬ŃĆīÕ»ŠõŠĪ’╝łcontrepartie’╝ēŃĆŹŃéƵīćŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéõŠŗŃüłŃü░ŃĆüÕŻ▓Ķ▓ĘÕźæń┤äŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕŻ▓õĖ╗Ńü«ŃĆīĶ▓ĪńöŻµ©®ń¦╗Ķ╗óńŠ®ÕŗÖŃĆŹŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗŃĆīõ╗ŻķćæÕÅŚķĀśŃü«µ©®Õł®ŃĆŹŃüīŃüōŃéīŃü½Ķ®▓ÕĮōŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«Õ«óĶ”│ńÜäÕĤÕøĀŃü»ŃĆüÕźæń┤äŃü«ń©«ķĪ×Ńü½ŃéłŃüŻŃü”õĖĆÕŠŗŃü½Õ«ÜŃüŠŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆé
ŃééŃüåõĖĆŃüżŃü»ŃĆüõĖ╗Ķ”│ńÜäÕĤÕøĀ’╝łCause subjective’╝ēŃü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ÕĮōõ║ŗĶĆģŃüīÕźæń┤äŃéÆńĘĀńĄÉŃüÖŃéŗŃü½Ķć│ŃüŻŃü¤ŃĆīÕĆŗõ║║ńÜäŃü¬ÕŗĢµ®¤’╝łmotif’╝ēŃĆŹŃéƵīćŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ÕŗĢµ®¤Ńü»Õźæń┤äŃüöŃü©Ńü½ńĢ░Ńü¬ŃéŖŃĆüÕżÜµ¦śŃü¦ŃüÖŃĆéŃāóŃāŁŃāāŃé│µ│ĢŃü¦Ńü»ŃĆüŃüōŃü«õĖ╗Ķ”│ńÜäÕĤÕøĀŃüīÕģ¼Õ║ÅĶē»õ┐Ś’╝łbonnes m┼ōurs’╝ēŃéäµ│Ģ’╝łloi’╝ēŃü½ÕÅŹŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüØŃü«Õźæń┤äŃéÆńäĪÕŖ╣Ńü©Õłżµ¢ŁŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
µŚźµ£¼µ│ĢŃü¦Ńü»ŃĆüÕźæń┤äŃü«ÕŗĢµ®¤ŃüīõĖŹµ│ĢŃü¬ÕĀ┤ÕÉłŃĆüµ░æµ│Ģ90µØĪŃü«Õģ¼Õ║ÅĶē»õ┐ŚķüĢÕÅŹŃü©ŃüŚŃü”ńäĪÕŖ╣Ńü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃüōŃéīŃü»ŃĆīÕĤÕøĀŃĆŹŃü©ŃüäŃüåńŗ¼ń½ŗŃüŚŃü¤µ£ēÕŖ╣Ķ”üõ╗ČŃü©ŃüŚŃü”Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüŃéłŃéŖõĖĆĶł¼ńÜäŃü¬µ”éÕ┐ĄŃü©ŃüŚŃü”Õć”ńÉåŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃāóŃāŁŃāāŃé│µ│ĢŃü½ŃüŖŃüäŃü”Ńü»ŃüōŃü«ŃĆīÕĤÕøĀŃĆŹŃüīµśÄńó║Ńü¬ńäĪÕŖ╣õ║ŗńö▒Ńü©ŃüŚŃü”µ®¤ĶāĮŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüŃüōŃü«ķüĢŃüäŃü»Õ«¤ÕŗÖõĖŖŃü«µ│ĢńÜäŃā¬Ńé╣Ńé»Ńü½Õż¦ŃüŹŃü¬ķØ×Õ»Šń¦░µĆ¦ŃéÆŃééŃü¤ŃéēŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
õŠŗŃüłŃü░ŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīńÅŠÕ£░õ╝üµźŁŃü©Õģ▒ÕÉīõ║ŗµźŁÕźæń┤äŃéÆńĘĀńĄÉŃüÖŃéŗķÜøŃĆüÕźæń┤äµøĖõĖŖŃü»ÕÉłµ│ĢńÜäŃü¬õ║ŗµźŁńø«ńÜäŃüīµśÄĶ©śŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃü”ŃééŃĆüŃééŃüŚńøĖµēŗµ¢╣ŃüīŃüØŃü«õ║ŗµźŁŃéÆŃā×ŃāŹŃā╝ŃāŁŃā│ŃāĆŃā¬Ńā│Ńé░ŃéäķüĢµ│ĢĶ¢¼ńē®ÕÅ¢Õ╝ĢŃü«ķÜĀŃéīĶōæŃü©ŃüŚŃü”Õł®ńö©ŃüÖŃéŗµäÅÕø│ŃéƵīüŃüŻŃü”ŃüäŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüØŃü«Õźæń┤äŃü»ŃāóŃāŁŃāāŃé│µ│ĢõĖŖŃĆüńäĪÕŖ╣Ńü©Õłżµ¢ŁŃüĢŃéīŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüÕŹśń┤öŃü¬Õźæń┤äµøĖŃā¼ŃāōŃāźŃā╝ŃüĀŃüæŃü¦Ńü»Ķ”ŗµŖ£ŃüæŃü¬ŃüäŃĆüŃéłŃéŖķ½śµ¼ĪÕģāŃü«µ│ĢńÜäŃā¬Ńé╣Ńé»Ńü¦ŃüÖŃĆé
| ŃāóŃāŁŃāāŃé│µ│Ģ | µŚźµ£¼µ│Ģ | |
|---|---|---|
| ÕÉłµäÅ’╝łConsentement’╝ē | µäŵĆØĶĪ©ńż║Ńü«ÕÉłĶć┤ŃĆéńĮ▓ÕÉŹŃü«µŁŻÕĮōŃü¬Ķ¬ŹĶ©╝ŃüīÕ«¤ÕŗÖõĖŖķćŹĶ”ü | µäŵĆØĶĪ©ńż║Ńü«ÕÉłĶć┤ |
| ĶāĮÕŖø’╝łCapacit├®’╝ē | µ│ĢÕŠŗŃü¦Õ«ÜŃéüŃéēŃéīŃü¤ńäĪĶāĮÕŖøĶĆģŃéÆķÖżŃüŹŃĆüµ£¬µłÉÕ╣┤ĶĆģŃéäĶó½õ┐ØõĮÉõ║║Ńü«õ┐ØĶŁĘĶ”ÅÕ«ÜŃüīÕŁśÕ£© | ÕłČķÖÉĶĪīńé║ĶāĮÕŖøĶĆģÕłČÕ║”Ńü½ŃéłŃéŗ |
| ńø«ńÜä’╝łObjet’╝ē | ÕÉłµ│ĢŃüŗŃüżńē╣Õ«ÜÕÅ»ĶāĮŃü¦ŃüéŃéŗŃüōŃü©Ńü¦ŃĆüńē®ńÉåńÜäŃüŠŃü¤Ńü»µ│ĢńÜäŃü½õĖŹÕÅ»ĶāĮŃü¬ńē®Ńü»ńäĪÕŖ╣ | ńó║Õ«ÜŃā╗Õ«¤ńÅŠÕÅ»ĶāĮŃā╗ķü®µ│ĢŃü¦ŃüéŃéŗŃüōŃü© |
| ÕĤÕøĀ’╝łCause’╝ē | ńŗ¼ń½ŗŃüŚŃü¤Ķ”üõ╗ČŃü©ŃüŚŃü”ÕŁśÕ£©ŃüŚŃĆüÕ«óĶ”│ńÜäŃā╗õĖ╗Ķ”│ńÜäńÉåńö▒Ńü«õĖĪµ¢╣ŃüīÕÉłµ│ĢŃü¦ŃüéŃéŗŃüōŃü©ŃüīÕ┐ģĶ”ü | ńŗ¼ń½ŗŃüŚŃü¤Ķ”üõ╗ČŃü©ŃüŚŃü”Ńü»ÕŁśÕ£©ŃüøŃüÜŃĆüÕŗĢµ®¤Ńü«ķüĢµ│ĢµĆ¦Ńü»Õģ¼Õ║ÅĶē»õ┐ŚķüĢÕÅŹŃü©ŃüŚŃü”Õć”ńÉåŃüĢŃéīŃéŗ |
ŃāóŃāŁŃāāŃé│Ńü«ń┤øõ║ēĶ¦Żµ▒║ŃāĪŃé½ŃāŗŃé║ŃāĀŃü©ĶŻüÕłżõŠŗŃü«ÕŗĢÕÉæ
õĖćõĖĆŃĆüÕźæń┤äń┤øõ║ēŃüīńÖ║ńö¤ŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃāóŃāŁŃāāŃé│Ńü¦Ńü»ÕĢåõ║ŗĶŻüÕłżµēĆ’╝łTribunal de commerce’╝ēŃüīŃüØŃü«ń¼¼õĖĆÕ»®ń«ĪĶĮ䵩®ŃéƵ£ēŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéĶ┐æÕ╣┤ŃĆüÕłżõŠŗŃü«ńĄ▒õĖĆÕī¢ŃüīķĆ▓ŃéōŃü¦ŃüŖŃéŖŃĆüŃüōŃéīŃü»µ│ĢńÜäõ║łĶ”ŗµĆ¦ŃéÆķ½śŃéüŃĆüÕøĮķÜøńÜäŃü¬ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣ķ¢óõ┐éŃü½ŃüŖŃüæŃéŗõ┐ĪķĀ╝ŃéÆÕ╝ĘÕī¢ŃüÖŃéŗÕŗĢŃüŹŃü¦ŃüéŃéŗŃü©Ķ®ĢõŠĪŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ÕłżõŠŗńĄ▒õĖĆÕī¢Ńü«ÕŗĢŃüŹŃü»ŃĆüŃāóŃāŁŃāāŃé│ŃüīÕż¢ÕøĮŃüŗŃéēŃü«µŖĢĶ│ćŃéÆĶ¬śĶć┤ŃüÖŃéŗõĖŖŃü¦ŃĆüµ│ĢńÜäŃü¬Õ«ēÕ«ÜµĆ¦ŃéÆķćŹĶ”üĶ”¢ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃüōŃü©Ńü«ĶĪ©ŃéīŃü©Ķ¦ŻķćłŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīÕÅ»ĶāĮŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃāóŃāŁŃāāŃé│Ńü«ĶŻüÕłżõŠŗŃü»ŃĆüÕźæń┤äõĖŖŃü«ńŠ®ÕŗÖŃü«Ķ¦ŻķćłŃéäŃĆüõĖŹÕ▒źĶĪīµÖéŃü«Ķ▓¼õ╗╗Ķ┐ĮÕÅŖŃü½ŃüŖŃüäŃü”ķćŹĶ”üŃü¬ÕĮ╣Õē▓ŃéƵףŃü¤ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéńē╣Ńü½ÕŖ┤ÕāŹÕłåķćÄŃü½ŃüŖŃüäŃü”Ńü»ŃĆüÕŖ┤ÕāŹĶĆģõ┐ØĶŁĘŃü«Ķ”│ńé╣ŃüŗŃéēÕłżõŠŗŃüīÕĮóµłÉŃüĢŃéīŃéŗÕéŠÕÉæŃüīĶ”ŗŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü¤ŃĆüŃé½ŃéĄŃā¢Ńā®Ńā│Ń齵ĦĶ©┤ĶŻüÕłżµēĆŃüī2021Õ╣┤Ńü½õĖŗŃüŚŃü¤Õłżµ▒║Ńü¦Ńü»ŃĆüõ╗▓ĶŻüÕÉłµäŵøĖŃü«ńĮ▓ÕÉŹõĖŹÕéÖŃüīõ╗▓ĶŻüÕłżµ¢ŁŃü«µ£ēÕŖ╣µĆ¦Ńü½ÕĮ▒ķ¤┐ŃüŚŃü¬ŃüäŃü©Õłżµ¢ŁŃüĢŃéīŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüÕźæń┤äµøĖŃü½ŃüŖŃüæŃéŗõ╗▓ĶŻüµØĪķĀģŃü«ķüŗńö©Ńüīµ┤╗ńÖ║Ńü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃüåŃüŗŃüīŃüłŃüŠŃüÖ’╝łCA. soc. Casablanca 2021’╝ēŃĆéŃüōŃü«ÕłżõŠŗŃüŗŃéēŃĆüĶŻüÕłżÕż¢ń┤øõ║ēĶ¦Żµ▒║’╝łADR’╝ēŃü©ŃüŚŃü”Ńü«õ╗▓ĶŻüŃüīÕ«¤ÕŗÖõĖŖµ£ēÕŖ╣Ńü¬ķüĖµŖ×ĶéóŃü¦ŃüéŃéŗŃüōŃü©ŃüīÕłåŃüŗŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü©Ńéü
µ£¼ń©┐Ńü¦Ķ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃü¤ŃéłŃüåŃü½ŃĆüŃāóŃāŁŃāāŃé│Õźæń┤äµ│ĢŃü»µŚźµ£¼µ│ĢŃü©Õģ▒ķĆÜŃü«Õ¤║ńøżŃéƵīüŃüżŃééŃü«Ńü«ŃĆüńē╣Ńü½ŃĆīÕĤÕøĀŃĆŹŃü«µ”éÕ┐ĄŃéäŃĆüÕźæń┤äµøĖķØóŃü«Ķ¬ŹĶ©╝Ńü¬Ńü®ŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīõ║ŗÕēŹŃü½µŖŖµÅĪŃüŚŃü”ŃüŖŃüÅŃü╣ŃüŹķćŹĶ”üŃü¬ńøĖķüĢńé╣ŃüīÕŁśÕ£©ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃéēŃü«ķüĢŃüäŃéÆĶ╗ĮĶ”¢ŃüŚŃĆüÕ«ēµśōŃü¬Õźæń┤äńĘĀńĄÉŃéÆĶĪīŃüåŃüōŃü©Ńü»ŃĆüÕ░åµØźńÜäŃü¬µ│ĢńÜäŃā¬Ńé╣Ńé»Ńéäõ║łµ£¤ŃüøŃü¼ń┤øõ║ēŃü½ŃüżŃü¬ŃüīŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüŃāóŃāŁŃāāŃé│Ńü»Õż¢ÕøĮµŖĢĶ│ćŃü«Ķ¬śĶć┤Ńü½ń®ŹµźĄńÜäŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüµ│ĢńÜäÕ«ēÕ«ÜµĆ¦ŃéÆķ½śŃéüŃéŗŃü¤ŃéüŃü«ÕŖ¬ÕŖøŃéÆńČÜŃüæŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéńÅŠÕ£░Ńü«µ│ĢÕłČÕ║”ŃéƵŁŻŃüŚŃüÅńÉåĶ¦ŻŃüŚŃĆüķü®ÕłćŃü¬Õźæń┤äµøĖŃéÆõĮ£µłÉŃā╗ń«ĪńÉåŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü¦ŃĆüŃüōŃéīŃéēŃü«Ńā¬Ńé╣Ńé»Ńü»ÕŹüÕłåŃü½Õø×ķü┐ÕÅ»ĶāĮŃüĀŃü©Ķ©ĆŃüłŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆé
Ńé½ŃāåŃé┤Ńā¬Ńā╝: ITŃā╗ŃāÖŃā│ŃāüŃāŻŃā╝Ńü«õ╝üµźŁµ│ĢÕŗÖ
Ńé┐Ńé░: ŃāóŃāŁŃāāŃé│ńÄŗÕøĮµĄĘÕż¢õ║ŗµźŁ


































