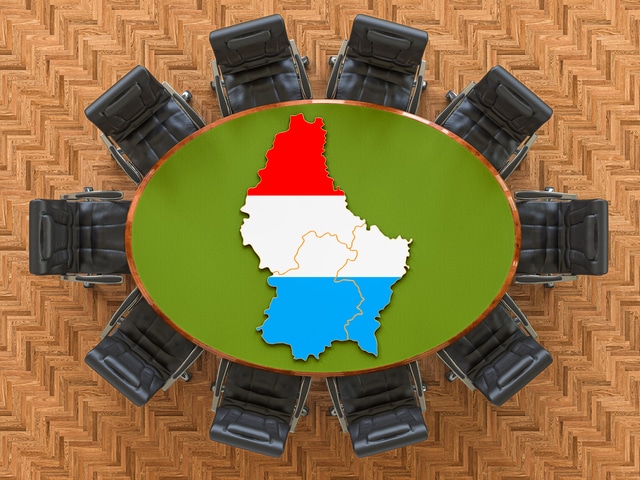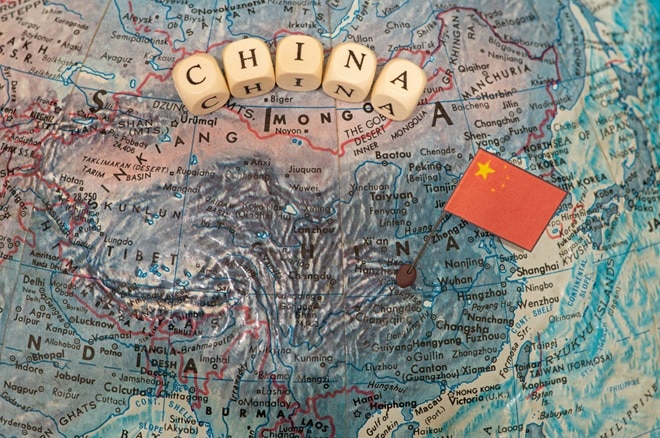гғүгӮӨгғ„жі•дҪ“зі»гҒ®жӯҙеҸІзҡ„ж§ӢйҖ гҒЁBGBгҒ®дё–з•Ңзҡ„еҪұйҹҝ

гғүгӮӨгғ„пјҲжӯЈејҸеҗҚз§°гҖҒгғүгӮӨгғ„йҖЈйӮҰе…ұе’ҢеӣҪпјүгҒ®жі•дҪ“зі»гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒ®гғ«гғјгғ„гӮ’жҺўгӮӢдёҠгҒ§ж¬ гҒӢгҒӣгҒӘгҒ„гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒзҸҫд»ЈгҒ®еӣҪйҡӣгғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжі•зҡ„дәҲиҰӢжҖ§гҒ®еҹәзӣӨгӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢдёҠгҒ§гӮӮжҘөгӮҒгҒҰйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
гғүгӮӨгғ„жі•гҒ®дҪ“зі»гҒҜгҖҒжӯҙеҸІзҡ„гҒ«гҖҒж”ҝжІ»зҡ„гҒӘзөұдёҖгҒ«е…ҲгӮ“гҒҳгҒҰгҖҒеӯҰиЎ“зҡ„гҒӘеҫ№еә•жҖ§гҒЁзҹҘзҡ„гҒӘи«–дәүгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒдё–з•ҢгҒ«йЎһгӮ’иҰӢгҒӘгҒ„еҺіж јгҒӘеҗҲзҗҶжҖ§гӮ’зўәз«ӢгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶзү№з•°гҒӘзөҢз·ҜгӮ’гҒҹгҒ©гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдёӯдё–гҒ®гғӯгғјгғһжі•з¶ҷеҸ—гҒӢгӮүе§ӢгҒҫгӮҠгҖҒ19дё–зҙҖгҒ®жӯҙеҸІжі•еӯҰжҙҫгҒЁжҰӮеҝөжі•еӯҰгҒ®еҸ°й ӯгӮ’зөҢгҒҰгҖҒBGBгҒҜеҚҳгҒӘгӮӢеӣҪ家гҒ®жі•е…ёгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҖҢ法科еӯҰгҒ®зөҗжҷ¶гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰе®ҢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®зҹҘзҡ„иғҢжҷҜгӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгғүгӮӨгғ„гҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒ®й«ҳеәҰгҒӘдәҲиҰӢжҖ§гҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒҢеӣҪйҡӣзҡ„гҒ«гҒ„гҒӢгҒ«гҒ—гҒҰжі•гҒ®гғўгғҮгғ«гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒӢгӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢйҚөгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®жі•е…ёеҢ–гҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§гҒ®жӯҙеҸІзҡ„йҒ…延гҒҢгҖҒгғ‘гғігғҮгӮҜгғҶгғіеӯҰжҙҫгҒ«гӮҲгӮӢгҖҢз·ҸеүҮгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжҰӮеҝөзҡ„гғ»дҪ“зі»зҡ„гҒӘйқ©ж–°гӮ’з”ҹгҒҝеҮәгҒ—гҖҒгҒқгҒ®ж§ӢйҖ гҒҢжҳҺжІ»жңҹгҒ®ж—Ҙжң¬гӮ’еҗ«гӮҖдё–з•Ңеҗ„еӣҪгҒ«ијёеҮәгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®ж°‘жі•е…ёгӮӮгҖҒгғүгӮӨгғ„гҒ®BГјrgerliches Gesetzbuch (BGB)гӮ’дё»иҰҒгҒӘгғўгғҮгғ«гҒЁгҒ—гҒҰжҺЎз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жң¬зЁҝгҒ§гҒҜгҖҒгғүгӮӨгғ„жі•дҪ“зі»гҒҢгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰжӯҙеҸІзҡ„гҒ«еҪўжҲҗгҒ•гӮҢгҖҒгҒқгҒ®ж ёеҝғгҒ§гҒӮгӮӢBGBгҒҢгҒ„гҒӢгҒ«гҒ—гҒҰдҪ“зі»зҡ„гҒӘе„ӘдҪҚжҖ§гӮ’зўәз«ӢгҒ—гҖҒзү№гҒ«ж—Ҙжң¬гҒ®иҝ‘д»ЈеҢ–гҒ«жұәе®ҡзҡ„гҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҹгҒ®гҒӢгӮ’и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®зӣ®ж¬Ў
гғүгӮӨгғ„з§Ғжі•гҒ®еҸӨд»ЈгҒҠгӮҲгҒіиҝ‘дё–гҒ®иө·жәҗпјҲ19дё–зҙҖд»ҘеүҚпјү
з§Ғжі•гҒ®ж–ӯзүҮеҢ–гҒЁдҪ“зі»еҢ–гҒ®еҝ…иҰҒжҖ§
дёӯдё–гҒӢгӮүиҝ‘дё–гҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҖҒгғүгӮӨгғ„гҒ®жі•дҪ“зі»гҒҜж”ҝжІ»зҡ„гҒӘеҲҶж–ӯзҠ¶ж…ӢгӮ’еҸҚжҳ гҒ—гҖҒжҘөеәҰгҒ®ж–ӯзүҮеҢ–гӮ’зү№еҫҙгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҗ„ең°гҒ®й ҳйӮҰгӮ„йғҪеёӮгҒ§гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®ең°еҹҹж…Јзҝ’жі•гӮ„дёӯдё–гҒ®еҲ¶е®ҡжі•гҒҢдё»иҰҒгҒӘжі•жәҗгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®еӨҡж§ҳгҒ§иӨҮйӣ‘гҒӘжі•зҠ¶жіҒгҒҢгҖҒеҫҢгҒ®жі•е…ёеҢ–йҒӢеӢ•гҒ®дё»иҰҒгҒӘе®ҹеӢҷдёҠгҒ®еӢ•ж©ҹгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®иӨҮйӣ‘жҖ§гҒҢгҖҒе…ЁгғүгӮӨгғ„гӮ’зөұдёҖгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еј·еҠӣгҒ§жҷ®йҒҚзҡ„гҒӘжі•жҰӮеҝөгҒ®еҝ…иҰҒжҖ§гӮ’з”ҹгҒҳгҒ•гҒӣгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гғӯгғјгғһжі•гҒ®з¶ҷеҸ—пјҲRezeptionпјүгҒЁгӮІгғһгӮӨгғҚгӮ№гғ»гғ¬гғ’гғҲгҒ®зўәз«Ӣ
гғүгӮӨгғ„гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгғӯгғјгғһжі•гҒҢжі•дҪ“зі»гҒ«е°Һе…ҘгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢз¶ҷеҸ—гҖҚгҒҜгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢеӯҰе•Ҹзҡ„гҒӘзҸҫиұЎгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒе®ҹеӢҷзҡ„гҒӘеҝ…иҰҒжҖ§гҒӢгӮүз”ҹгҒҳгҒҹеҮәжқҘдәӢгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮзү№гҒ«15дё–зҙҖд»ҘйҷҚгҖҒең°еҹҹж…Јзҝ’жі•гӮ„е°Ғе»әжі•гҒҢиӨҮйӣ‘еҢ–гҒҷгӮӢдёӯгҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®еҲ¶еәҰгӮ’дҪ“зі»еҢ–гҒ—гҖҒдёҚи¶ігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢжі•еҺҹеүҮгӮ’иЈңгҒҶзӣ®зҡ„гҒ§гҖҒй«ҳеәҰгҒ«зҷәйҒ”гҒ—гҒҹгғӯгғјгғһжі•гҒҢе°Һе…ҘгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®з¶ҷеҸ—гӮ’еҲ¶еәҰзҡ„гҒ«жҺЁйҖІгҒ—гҒҹйҮҚиҰҒгҒӘиҰҒеӣ гҒ®дёҖгҒӨгҒҢгҖҒ1495е№ҙгҒ«иЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹReichskammergerichtпјҲеёқеӣҪжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖпјүгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒй ҳйӮҰиЈҒеҲӨжүҖгҒӢгӮүгҒ®дёҠиЁҙгӮ’еҸ—гҒ‘д»ҳгҒ‘гӮӢеҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒ„гҖҒзү№гҒ«дёҠиЁҙжЁ©гҒ®зү№жЁ©гӮ’жҢҒгҒҹгҒӘгҒ„й ҳйӮҰгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒе®ҹиіӘзҡ„гҒӘжңҖдёҠзҙҡиЈҒеҲӨжүҖгҒЁгҒ—гҒҰж©ҹиғҪгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеёқеӣҪжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҢгҖҒй«ҳеәҰгҒӘе°Ӯй–ҖжҖ§гӮ’иҰҒгҒҷгӮӢгғӯгғјгғһжі•гӮ’жә–жӢ жі•гҒЁгҒ—гҒҰдҪҝз”ЁгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгғӯгғјгғһжі•гҒ®жҰӮеҝөгҒҢгғүгӮӨгғ„гҒ®жі•е®ҹеӢҷгҒ«ж·ұгҒҸжөёйҖҸгҒ—гҖҒдәӢе®ҹдёҠгҒ®е…ұйҖҡжі•пјҲjus communeпјүгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®ең°дҪҚгӮ’зўәз«ӢгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гӮІгғһгӮӨгғҚгӮ№гғ»гғ¬гғ’гғҲпјҲGemeines Rechtпјҡжҷ®йҖҡжі•пјүгҒ®жҰӮеҝө
еҫҢгҒ®гғүгӮӨгғ„ж°‘жі•е…ёпјҲBГјrgerliches Gesetzbuch, BGBпјүгҒ®еҹәзӨҺгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹжі•жҰӮеҝөгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®Gemeines RechtпјҲжҷ®йҖҡжі•пјүгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒ6дё–зҙҖгҒ®гғҰгӮ№гғҶгӮЈгғӢгӮўгғҢгӮ№еёқгҒ«гӮҲгӮӢгғӯгғјгғһжі•еӨ§е…ЁпјҲзү№гҒ«еӯҰиӘ¬еҪҷзәӮ[Pandectae]пјүгӮ’еҹәжң¬гҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢеҸӨд»Јгғӯгғјгғһжі•гҒ®еҫ©е…ғгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
Gemeines RechtгҒҜгҖҒдёӯдё–гҒ®жі•еӯҰиҖ…гҒҹгҒЎпјҲиЁ»йҮҲеӯҰжҙҫгӮ„гғқгӮ№гғҲиЁ»йҮҲеӯҰжҙҫпјүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз ”з©¶гғ»и§ЈйҮҲгғ»йҒ©еҗҲеҢ–гҒ•гӮҢгҒҹгғӯгғјгғһжі•гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°е°Ғе»әжі•гӮ„гҖҒ家ж—Ҹжі•гӮ„иІЎз”Јжі•гҒ®дёҖйғЁгҒ«иҰӢгӮүгӮҢгӮӢгӮІгғ«гғһгғійғЁж—Ҹжі•гҒ®иҰҒзҙ гҒЁиһҚеҗҲгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒGemeines RechtгҒҜгҖҒгғүгӮӨгғ„гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰ400е№ҙд»ҘдёҠгҒ«гӮҸгҒҹгӮҠжҙ—з·ҙгҒ•гӮҢгҖҒе°Ӯй–ҖеҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒҚгҒҹгҖҒй«ҳеәҰгҒӘеӯҰиЎ“зҡ„гғ»е®ҹи·өзҡ„еҹәзӣӨгӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жӯҙеҸІзҡ„иғҢжҷҜгҒ“гҒқгҒҢгҖҒеҫҢгҒ®19дё–зҙҖгҒ®жі•еӯҰиҖ…гҒҹгҒЎгҒ«гҖҒдҪ“зі»зҡ„гҒӢгҒӨеҗҲзҗҶзҡ„гҒӘжі•е…ёеҢ–гӮ’е®ҹзҸҫгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®иЁҖиӘһгҒЁжҰӮеҝөзҡ„жһ зө„гҒҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®з¶ҷеҸ—гҒ®йҒҺзЁӢгҒҜгҖҒгғүгӮӨгғ„жі•гҒҢгҖҒж—©гҒҸгҒӢгӮүеӯҰиЎ“зҡ„гҒӘ秩еәҸгҒЁеҗҲзҗҶзҡ„гҒӘж§ӢйҖ гӮ’йҮҚиҰ–гҒҷгӮӢеӮҫеҗ‘гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҲқжңҹжі•е…ёеҢ–гҒ®и©ҰгҒҝгҒЁиҮӘ然法гҒ®еҪұйҹҝ
BGBгҒ®зҷ»е ҙгҒ«е…Ҳз«ӢгҒЎгҖҒгғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ§гҒҜе•“и’ҷдё»зҫ©гҒЁиҮӘ然法жҖқжғігҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹеӨ§иҰҸжЁЎгҒӘжі•е…ёеҢ–гҒҢйҖІгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮд»ЈиЎЁзҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгғ—гғӯгӮӨгӮ»гғігҒ®Allgemeines Landrecht (ALR, 1794е№ҙ)гӮ„гҖҒгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ®Allgemeines BГјrgerliches Gesetzbuch (ABGB, 1812е№ҙ)гҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
зү№гҒ«гӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ®ABGBгҒҜгҖҒзҙ„40е№ҙгҒ®жә–еӮҷжңҹй–“гӮ’зөҢгҒҰе…¬еёғгҒ•гӮҢгҖҒжі•гҒ®еүҚгҒ®иҮӘз”ұгҒЁе№ізӯүгҒ®зҗҶеҝөгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒгғӯгғјгғһжі•гҒ®еҢәеҲҶжі•гҒ«еҖЈгҒЈгҒҰдёүйғЁгҒ«ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®еҲқжңҹгҒ®жі•е…ёеҢ–гҒҜгҖҒжі•е…ёдҪңжҲҗгҒ®е®ҹзҸҫеҸҜиғҪжҖ§гӮ’зӨәгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ®е“ІеӯҰзҡ„еҹәзӣӨпјҲжҠҪиұЎзҡ„гҒӘзҗҶжҖ§гҒӢгӮүгҒ®жј”з№№гӮ’ж—ЁгҒЁгҒҷгӮӢиҮӘ然法пјүгҒҜгҖҒеҫҢгҒ«зҷ»е ҙгҒҷгӮӢжӯҙеҸІжі•еӯҰжҙҫгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰж №жң¬зҡ„гҒ«жҢ‘жҲҰгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҲқжңҹгҒ®жі•е…ёгҒҢгҖҒеҫҢгҒ®BGBгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒи¶…гҒҲгӮӢгҒ№гҒҚе…ҲдҫӢгҖҒгҒқгҒ—гҒҰеҸҚйқўж•ҷеё«гҒ®дёЎж–№гҒЁгҒ—гҒҰж©ҹиғҪгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гғүгӮӨгғ„гҒ®жі•е…ёеҢ–гӮ’гӮҒгҒҗгӮӢзҹҘзҡ„гҒӘжҲҰе ҙпјҲ1800е№ҙгҖң1848е№ҙпјү
жі•зөұдёҖгҒ®иҰҒжұӮгҒЁгғҶгӮЈгғңгғјгҒ®жҸҗжЎҲ
19дё–зҙҖеҲқй ӯгҖҒгғҠгғқгғ¬гӮӘгғіжҲҰдәүеҫҢгҒ®гғүгӮӨгғ„ең°еҹҹгҒ§гҒҜгҖҒгғҠгӮ·гғ§гғҠгғӘгӮәгғ гҒ®еҸ°й ӯгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«ж”ҝжІ»зҡ„зөұдёҖгҒёгҒ®ж©ҹйҒӢгҒҢй«ҳгҒҫгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жҷӮд»ЈгҖҒгғҸгӮӨгғҮгғ«гғҷгғ«гӮҜеӨ§еӯҰгҒ®жі•еӯҰиҖ…гӮўгғігғҲгғігғ»гғҶгӮЈгғңгғјпјҲAnton ThibautпјүгҒҜгҖҒз§Ғжі•гҒ®еҚіжҷӮжі•е…ёеҢ–гӮ’еј·гҒҸдё»ејөгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгғҶгӮЈгғңгғјгҒҜгҖҒжі•е…ёеҢ–гҒ®йҒҺзЁӢгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒеҲҶж–ӯгҒ•гӮҢгҒҹгғүгӮӨгғ„гҒ®гҖҢж”ҝжІ»зҡ„зөұдёҖгӮ’дҝғйҖІгҒҷгӮӢгҖҚгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҪјгҒҜгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®зӮ№гҒ§е®Ңз’§гҒӢгҒӨе®Ңе…ЁгҒӘжі•е…ёгӮ’жңӣгӮ“гҒ§гҒҠгӮҠгҖҒгҒқгҒ®жҖқжғігҒҜиҮӘ然法зҡ„гҒӘжҖқиҖғгҒ«еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгғҶгӮЈгғңгғјгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒжі•е…ёгҒҜеӣҪ家е»әиЁӯгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®ж”ҝжІ»е·ҘеӯҰзҡ„гҒӘйҒ“е…·гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжі•гҒҢзөұдёҖгӮ’е°ҺгҒҸгҒ№гҒҚгҒ гҒЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮВ
гӮөгғҙгӮЈгғӢгғјгҒЁжӯҙеҸІжі•еӯҰжҙҫгҒ®иӘ•з”ҹ
гғҶгӮЈгғңгғјгҒ®жҸҗжЎҲгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгғҷгғ«гғӘгғіеӨ§еӯҰгҒ®жі•еӯҰиҖ…гғ•гғӘгғјгғүгғӘгғ’гғ»гӮ«гғјгғ«гғ»гғ•гӮ©гғігғ»гӮөгғҙгӮЈгғӢгғјпјҲFriedrich Carl von SavignyпјүгҒҜгҖҒ1814е№ҙгҒ«гҖҺз«Ӣжі•гҒҠгӮҲгҒіжі•еӯҰгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢзҸҫд»ЈгҒ®дҪҝе‘ҪгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҸ(Vom Beruf unserer Zeit fГјr Gesetzgebung und Rechtswissenschaft)гӮ’еҮәзүҲгҒ—гҖҒжі•е…ёеҢ–иҰҒжұӮгҒёгҒ®еҸҚи«–гӮ’еұ•й–ӢгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®и‘—дҪңгҒҜгҖҒгҒқгҒ®еҫҢ80е№ҙй–“гҒ«гӮҸгҒҹгӮӢгғүгӮӨгғ„гҒ®жі•е…ёеҢ–дҪңжҘӯгӮ’дәӢе®ҹдёҠеҒңжӯўгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«жҲҗеҠҹгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮВ
гӮөгғҙгӮЈгғӢгғјгҒҜгҖҒжі•гҒҢгҒқгҒ®зөұжІ»гҒҷгӮӢгҖҢеӣҪж°‘зІҫзҘһпјҲVolksgeistпјүгҖҚгҒЁдёҖиҮҙгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶжӯҙеҸІжі•еӯҰгҒ®зҗҶи«–гӮ’ж§ӢзҜүгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҪјгҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒжі•гҒҜз«Ӣжі•иҖ…гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжҒЈж„Ҹзҡ„гҒ«дҪңгӮүгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒдәәгҖ…гҒ®е…ұйҖҡгҒ®ж„ҸиӯҳгҒ®дёӯгҒ§жңүж©ҹзҡ„гҒ«зҷәеұ•гҒ—гҖҒжҲҗй•·гҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гӮөгғҙгӮЈгғӢгғјгҒ®жҷӮжңҹе°ҡж—©гҒӘз«Ӣжі•гҒёгҒ®еҸҚеҜҫи«–
гӮөгғҙгӮЈгғӢгғјгҒҜгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®гғүгӮӨгғ„гҒ®жі•еӯҰгҒҢжңӘзҶҹгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжҷӮжңҹе°ҡж—©гҒӘжі•е…ёеҢ–гҒҜжңүе®ігҒӘеҪұйҹҝгӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒҷгҒЁдё»ејөгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҪјгҒҜгҖҒд»ҘеүҚгҒ®дё–д»ЈгҒ®жі•еӯҰиҖ…гҒ®жҖ ж…ўгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз”ҹгҒҳгҒҹжҗҚе®ігҒҜгҖҒгҒҷгҒҗгҒ«дҝ®еҫ©гҒ§гҒҚгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒжі•еҫӢ家гҒҢгҖҢ家гӮ’ж•ҙгҒҲгӮӢгҖҚгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҒ•гӮүгҒӘгӮӢжҷӮй–“гҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
зү№гҒ«еҪјгҒҜгҖҒжҠҪиұЎзҡ„гҒӘзҗҶжҖ§гҒӢгӮүжі•гӮ’е°ҺеҮәгҒҷгӮӢиҮӘ然法гҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹжі•е…ёгӮ’еҚұйҷәиҰ–гҒ—гҖҒгҒқгҒ®гҖҢз„ЎйҷҗгҒ®еӮІж…ўгҒ•гҖҚгӮ„гҖҢжө…и–„гҒӘе“ІеӯҰгҖҚгҒӢгӮү法科еӯҰгӮ’ж•‘гҒҶгҒ№гҒҚгҒ гҒЁи«–гҒҳгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгӮөгғҙгӮЈгғӢгғјгҒ®иҰ–зӮ№гҒ§гҒҜгҖҒжі•гҒ®еҹәжң¬еҺҹеүҮгҒҜгҖҢдәәгҖ…гҒ®е…ұйҖҡгҒ®ж„ҸиӯҳгҒ®дёӯгҒ«з”ҹгҒҚз¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҖҚгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒгҒқгҒ®и©ізҙ°гҒӢгҒӨжӯЈзўәгҒӘйҒ©з”ЁгҒҜгҖҒе°Ӯй–Җ家гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®жі•еӯҰиҖ…пјҲjuristconsultsпјүгҒ®зү№еҲҘгҒӘдҪҝе‘ҪгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®дё»ејөгҒҜгҖҒжі•гҒ®зҷәеұ•гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжЁ©еЁҒгӮ’гҖҒз«Ӣжі•иҖ…пјҲгғҶгӮЈгғңгғјгҒ®з«Ӣе ҙпјүгҒӢгӮүгҖҒжӯҙеҸІзҡ„иіҮж–ҷгӮ’и§ЈйҮҲгҒ—дҪ“зі»еҢ–гҒҷгӮӢеӯҰиӯҳгҒӮгӮӢжі•еӯҰиҖ…гҒёгҒЁж №жң¬зҡ„гҒ«з§»иЎҢгҒ•гҒӣгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮВ
зҹҘзҡ„еҜҫз«ӢгҒҢз”ҹгӮ“гҒ ж§ӢйҖ зҡ„е„ӘдҪҚжҖ§
гӮөгғҙгӮЈгғӢгғјгҒҜжі•е…ёеҢ–гӮ’йҒ…гӮүгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«жҲҗеҠҹгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ®еӢқеҲ©гҒҜзҡ®иӮүгҒӘгҒ“гҒЁгҒ«гҖҒжі•еӯҰгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒжі•е…ёеҢ–гҒ«иҖҗгҒҲгҒҶгӮӢгҒ»гҒ©з§‘еӯҰзҡ„гҒ«гҖҢе®Ңз’§еҢ–гҖҚгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®1814е№ҙгҒӢгӮү1900е№ҙгҒҫгҒ§гҒ®зҙ„80е№ҙй–“гҒ®йҒ…延гҒҜгҖҒгғ‘гғігғҮгӮҜгғҶгғіеӯҰжҙҫпјҲPandectismпјүгҒҢдҝЎгҒҳгҒҢгҒҹгҒ„гҒ»гҒ©гҒ«иӨҮйӣ‘гҒ§дҪ“зі»зҡ„гҒӘж§ӢйҖ гӮ’й–ӢзҷәгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гҖҒжҷӮй–“зҡ„гҒҠгӮҲгҒізҹҘзҡ„ең§еҠӣгӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮВ
гғҶгӮЈгғңгғјгҒ®еӢ•ж©ҹгҒҢдё»гҒ«гҖҢж”ҝжІ»зҡ„гҖҚгҒӘзөұдёҖдҝғйҖІгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ«еҜҫгҒ— гҖҒгӮөгғҙгӮЈгғӢгғјгҒ®еӢқеҲ©гҒҜгҖҢеӯҰиЎ“зҡ„гғ»е“ІеӯҰзҡ„гҖҚгҒӘеҫ№еә•жҖ§гӮ’е„Әе…ҲгҒ•гҒӣгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®зөҗжһңгҖҒгғүгӮӨгғ„гҒ®жі•зөұдёҖпјҲ1900е№ҙпјүгҒҜж”ҝжІ»зҡ„зөұдёҖпјҲ1871е№ҙпјүгҒ«йҒ…гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒжі•й ҳеҹҹгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҚіеә§гҒ®е®ҹз”Ёзҡ„гҒӘж”ҝжІ»зҡ„дҫҝе®ңгӮҲгӮҠгӮӮгҖҒеӯҰе•Ҹзҡ„гҒӘеҫ№еә•жҖ§гҒҢе„Әе…ҲгҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжңҖзөӮзҡ„гҒ«гҖҒBGBгҒҢеҲ¶е®ҡгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁгҒҚгҖҒгҒқгӮҢгҒҜеҚҳгҒӘгӮӢзөұдёҖеӣҪ家гҒ®жі•еҫӢгҒЁгҒ—гҒҰгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеӯҰиЎ“зҡ„гҒӘеҗҲзҗҶжҖ§гҒ®жңҖй«ҳеі°гҒЁгҒ—гҒҰеӣҪйҡӣзҡ„гҒ«и©•дҫЎгҒ•гӮҢгҖҒж”ҝжІ»зҡ„гҒ«жҖҘгҒҢгӮҢгҒҹжі•е…ёгӮҲгӮҠгӮӮйҒҘгҒӢгҒ«еӨ§гҒҚгҒӘе°Ҡ敬гӮ’йӣҶгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮВ
гғүгӮӨгғ„гҒ®гғ‘гғігғҮгӮҜгғҶгғіеӯҰжҙҫгҒЁжҰӮеҝөзҡ„еҺіж јжҖ§пјҲ19дё–зҙҖеҲқй ӯгҖң1871е№ҙпјү

гғ‘гғігғҮгӮҜгғҶгғіеӯҰжҙҫпјҲPandektenwissenschaftпјүгҒ®еҸ°й ӯ
жӯҙеҸІжі•еӯҰжҙҫгҒҢжі•е…ёеҢ–гӮ’йҳ»жӯўгҒ—гҒҹеҫҢгҖҒгӮөгғҙгӮЈгғӢгғјгҒҢжі•еӯҰиҖ…гҒҹгҒЎгҒ«иӘІгҒ—гҒҹгҖҢ家гӮ’ж•ҙгҒҲгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶдҪҝе‘ҪгӮ’жһңгҒҹгҒҷеҪўгҒ§гҖҒ19дё–зҙҖеҲқй ӯгҒ®гғүгӮӨгғ„гҒ®еӨ§еӯҰгҒ§гғ‘гғігғҮгӮҜгғҶгғіеӯҰжҙҫгҒҢеҸ°й ӯгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еӯҰжҙҫгҒ®дё»иҰҒдәәзү©гҒ«гҒҜгҖҒгӮөгғҙгӮЈгғӢгғјиҮӘиә«гҒ«еҠ гҒҲгҖҒгӮІгӮӘгғ«гӮ°гғ»гғ•гғӘгғјгғүгғӘгғ’гғ»гғ—гғ•гӮҝгӮ„гғҷгғ«гғігғҸгғ«гғҲгғ»гғҙгӮЈгғігғҲгӮ·гғЈгӮӨгғҲгҒӘгҒ©гҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гғ‘гғігғҮгӮҜгғҶгғіеӯҰжҙҫгҒҜгҖҒгғӯгғјгғһжі•гҒ®жі•жәҗгҖҒзү№гҒ«гғҰгӮ№гғҶгӮЈгғӢгӮўгғҢгӮ№гҒ®еӯҰиӘ¬еҪҷзәӮпјҲгғ‘гғігғҮгӮҜгғҶгғіпјүгӮ’з ”з©¶гҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгӮ’KonstruktionsjurisprudenzпјҲжҰӮеҝөжі•еӯҰпјүгҒ®гғўгғҮгғ«гҒЁгҒ—гҒҰж•ҷгҒҲгҖҒзЈЁгҒҚдёҠгҒ’гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®йҒӢеӢ•гҒҜгҖҒжӯҙеҸІзҡ„гҒӘгғӯгғјгғһжі•гҒ®з ”究гӮ’гҖҒеҫҢгҒ®з«Ӣжі•гҒ«гӮҲгӮӢжі•е…ёеҢ–гҒ«йҒ©гҒ—гҒҹгҖҒеҺіеҜҶгҒ§жҠҪиұЎзҡ„гҒӢгҒӨдҪ“зі»еҢ–гҒ•гӮҢгҒҹжі•ж•ҷзҫ©гҒёгҒЁеӨүиІҢгҒ•гҒӣгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
жҰӮеҝөжі•еӯҰгҒ®дҪ“зі»зҡ„ж§ӢзҜү
жҰӮеҝөжі•еӯҰгҒҜгҖҒжі•зҡ„гҒӘзўәе®ҹжҖ§гҒЁдҪ“зі»еҢ–гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢй«ҳгҒҫгӮҠгӮҶгҒҸгғӢгғјгӮәгҒ«еҜҫеҝңгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«з”ҹгҒҫгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®жүӢжі•гҒҜгҖҒгғӯгғјгғһжі•гҒ®е…·дҪ“зҡ„гҒӘиҰҸеүҮгҒӢгӮүжҠҪиұЎзҡ„гҒӘжі•зҡ„жҰӮеҝөгӮ„гҒқгҒ®йҡҺеұӨж§ӢйҖ гӮ’е°ҺгҒҚеҮәгҒҷгҒ“гҒЁгҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮВ
гҒ“гҒ®зҹҘзҡ„гӮўгғ—гғӯгғјгғҒгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®зү№е®ҡгҒ®иҰҸеүҮгҒҢгҖҒгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®еҹәжң¬зҡ„гҒӘгҖҒй«ҳеәҰгҒ«жҠҪиұЎеҢ–гҒ•гӮҢгҒҹе®ҡзҫ©пјҲдҫӢпјҡжі•еҫӢиЎҢзӮәгҖҒжЁ©еҲ©иғҪеҠӣгҖҒж„ҸжҖқиЎЁзӨәпјүгҒӢгӮүи«–зҗҶзҡ„гҒ«жј”з№№гҒ•гӮҢгӮӢгҖҢжҰӮеҝөгҒ®гғ”гғ©гғҹгғғгғүгҖҚгҒҢж§ӢзҜүгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®ж–№жі•и«–гҒҜгҖҒBGBгҒҢз¶Ізҫ…зҡ„гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҶ…йғЁзҡ„гҒ«зҹӣзӣҫгҒҢгҒӘгҒҸгҖҒдёҖиІ«жҖ§гӮ’жҢҒгҒӨгҒ“гҒЁгӮ’дҝқиЁјгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еҺіеҜҶгҒӘжҠҖиЎ“гҒҜгҖҒеҸӨгҒ„жі•е…ёпјҲдҫӢгҒҲгҒ°гғҠгғқгғ¬гӮӘгғіжі•е…ёпјүгҒЁгҒ®жұәе®ҡзҡ„гҒӘйҒ•гҒ„гӮ’з”ҹгҒҝеҮәгҒҷгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгғ‘гғігғҮгӮҜгғҶгғіеӯҰжҙҫгҒ®и‘—дҪңгҒҜгҖҒжі•е…ёз·ЁзәӮ委員дјҡгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰдәӢе®ҹдёҠгҒ®йқ’еҶҷзңҹгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
з·ҸеүҮпјҲAllgemeiner TeilпјүгҒ®е°Һе…Ҙ
жҰӮеҝөжі•еӯҰгҒҜгҖҒзү№гҒ«BGBгҒ®жі•е…ёеҢ–гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгғүгӮӨгғ„ж°‘жі•гҒ®дҪ“зі»еҢ–гҒЁжҰӮеҝөзҡ„гғүгӮ°гғһгғҶгӮЈгӮҜгҒ«ж°ёз¶ҡзҡ„гҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®дҪ“зі»еҢ–гҒ®жңҖгӮӮзӢ¬еүөзҡ„гҒ§еҪұйҹҝеҠӣгҒ®еӨ§гҒҚгҒ„йқ©ж–°гҒҢгҖҒBGBгҒ®еҶ’й ӯгҒ«зҪ®гҒӢгӮҢгҒҹгҖҢз·ҸеүҮпјҲAllgemeiner TeilпјүгҖҚгҒ§гҒҷгҖӮ
BGBгҒҜгҖҒз·ҸеүҮпјҲ第дёҖз·ЁпјүгҒ«з¶ҡгҒҚгҖҒеӮөжЁ©жі•гҖҒзү©жЁ©жі•гҖҒ家ж—Ҹжі•гҖҒзӣёз¶ҡжі•гҒ®дә”йғЁж§ӢжҲҗгӮ’гҒЁгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮз·ҸеүҮгҒ«гҒҜгҖҒз§Ғжі•гҒ®е…ЁгҒҰгҒ®й ҳеҹҹпјҲиІЎз”Јжі•гҖҒеӮөжЁ©жі•гҖҒ家ж—Ҹжі•гҖҒзӣёз¶ҡжі•пјүгҒ«е…ұйҖҡгҒ—гҒҰйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢе®ҡзҫ©гҒЁеҺҹеүҮгҒҢеҢ…жӢ¬зҡ„гҒ«еҸҺгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеҗ„жі•еҹҹгҒ§е…ұйҖҡгҒ®жҰӮеҝөпјҲдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒжҷӮеҠ№гҖҒз„ЎеҠ№гҖҒиЎҢзӮәиғҪеҠӣпјүгӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒ—е®ҡзҫ©гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒжі•е…ёе…ЁдҪ“гҒ®жҰӮеҝөзҡ„дёҖиІ«жҖ§гҒҢдҝқиЁјгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮз·ҸеүҮгҒҜгҖҒгғ‘гғігғҮгӮҜгғҶгғіеӯҰжҙҫгҒ®дҪ“зі»еҢ–гҒ®й ӮзӮ№гӮ’иЎЁгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒBGBгҒ®жңҖгӮӮйҡӣз«ӢгҒЈгҒҹзү№еҫҙгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҫҢгҒ«ж—Ҙжң¬гҒ®ж°‘жі•е…ёгӮ’еҗ«гӮҖеӨҡгҒҸгҒ®еӨ–еӣҪгҒ®жі•е…ёгҒ«еҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®еӯҰиЎ“зҡ„гҒӘеҚ“и¶ҠжҖ§гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢгғүгӮӨгғ„гҒ®еҹ·зқҖгҒҜгҖҒ1871е№ҙгҒ«гғүгӮӨгғ„еёқеӣҪгҒҢзөұдёҖгҒ•гӮҢгҒҹжҷӮгҖҒж—ўеӯҳгҒ®еӯҰиЎ“зҡ„гҒӘеҹәзӣӨгҒҢйқһеёёгҒ«е®ҢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒҹгӮҒгҖҒиө·иҚү委員дјҡгҒҜеҹәжң¬зҡ„гҒ«ж—ўеӯҳгҒ®гғ‘гғігғҮгӮҜгғҶгғіеӯҰжҙҫгҒ®ж•ҷ科жӣёгӮ’жі•е…ёгҒ®жқЎж–ҮгҒёгҒЁгҖҢзҝ»иЁігҖҚгҒҷгӮӢеҪўгҒ§дҪңжҘӯгӮ’йҖІгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж§ӢйҖ зҡ„гҒӘе„ӘдҪҚжҖ§гҒҢгҖҒBGBгӮ’гғ•гғ©гғігӮ№гғўгғҮгғ«гҒЁе·®еҲҘеҢ–гҒҷгӮӢгҖҒгғүгӮӨгғ„гҒ®гҖҢжі•зҡ„гҒӘијёеҮәиЈҪе“ҒгҖҚгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гғүгӮӨгғ„ж°‘жі•е…ёпјҲBGBпјүгҒ®иӘ•з”ҹпјҲ1871е№ҙгҖң1900е№ҙпјү
зөұдёҖеҫҢгҒ®ж”ҝжІ»зҡ„жҺЁйҖІеҠӣ
1871е№ҙгҒ«гғүгӮӨгғ„еёқеӣҪгҒҢжҲҗз«ӢгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒ®е“ІеӯҰзҡ„гғ»еӯҰиЎ“зҡ„гҒӘи«–дәүгҒ®ж–Үи„ҲгҒҜдёҖеӨүгҒ—гҖҒжі•зҡ„зөұдёҖгҒ®йҒ”жҲҗгҒҢеӣҪ家гҒ®жңҖе„Әе…ҲдәӢй …гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®ж”ҝжІ»зҡ„иҰҒи«ӢгҒҜгҖҒгӮөгғҙгӮЈгғӢгғјгҒ®еҸҚеҜҫи«–гҒҢдҫқжӢ гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖҒдёӯеӨ®йӣҶжЁ©зҡ„гҒӘз«Ӣжі•жЁ©гҒ®ж¬ еҰӮгҒЁгҒ„гҒҶе•ҸйЎҢгӮ’еҸ–гӮҠйҷӨгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮе…ЁеӣҪзҡ„гҒӘжі•еҫӢгҒ®зөұдёҖгҒҜгҖҒж–°иҲҲеӣҪ家гҒ®дёҚеҸҜж¬ гҒӘеҹәзӣӨгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
иө·иҚүйҒҺзЁӢгҒЁеҲқжңҹгҒ®жү№еҲӨ
BGBгҒ®иө·иҚүгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«е§”е“ЎдјҡгҒҢиЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒ1888е№ҙгҒ«зҷәиЎЁгҒ•гӮҢгҒҹ第дёҖиҚүжЎҲгҒҜгҖҒгҒқгҒ®еҶ…е®№гҒ®гҖҢгҒӮгҒҫгӮҠгҒ«гғӯгғјгғһзҡ„гҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶжү№еҲӨгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒеҚҙдёӢгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еҚҙдёӢгҒҜгҖҒжі•е…ёгҒҢеҚҳгҒӘгӮӢгғ‘гғігғҮгӮҜгғҶгғіеӯҰжҙҫгҒ®еҺіеҜҶгҒӘгғӯгғјгғһжі•гҒ«еҹәгҒҘгҒҸеӯҰиЎ“зҡ„жј”зҝ’гҒ«з•ҷгҒҫгӮүгҒҡгҖҒзӨҫдјҡзҡ„гҒӘеӨүеҢ–гӮ„гӮІгғ«гғһгғізҡ„гҒӘжі•зҡ„дјқзөұгҒ«гӮӮй…Қж…®гҒ—гҒҹгҖҒе®ҹз”Ёзҡ„гҒӘеӣҪж°‘жі•гҒЁгҒ—гҒҰж©ҹиғҪгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеӯҰиЎ“зҡ„гҒӘзҙ”зІӢжҖ§гҒЁж”ҝжІ»зҡ„гғ»ж–ҮеҢ–зҡ„гҒӘеҸ—е®№жҖ§гҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮВ
гҒ“гҒ®жү№еҲӨгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒ第дәҢ委員дјҡгҒҢгӮҲгӮҠзҸҫе®ҹзҡ„гҒӘгӮўгғ—гғӯгғјгғҒгҒ§еҶҚиө·иҚүгӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
е…¬еёғгҒЁж–ҪиЎҢ
жңҖзөӮзҡ„гҒӘ第дәҢиҚүжЎҲгҒҜ1896е№ҙгҒ«е…¬еёғгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒиұЎеҫҙзҡ„гҒӘж„Ҹе‘іеҗҲгҒ„гҒӢгӮүгҖҒ1900е№ҙ1жңҲ1ж—ҘгҒ«ж–ҪиЎҢгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®ж–ҪиЎҢж—ҘгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҖҒгғүгӮӨгғ„гҒҜж”ҝжІ»зҡ„гҒӘзөұдёҖгҒ«еҠ гҒҲгҒҰгҖҒеҢ…жӢ¬зҡ„гҒӘз§Ғжі•гҒ®зөұдёҖгӮ’йҒ”жҲҗгҒ—гҖҒеӣҪж°‘еӣҪ家гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®е®ҢжҲҗгӮ’иұЎеҫҙгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
жҺ’д»–жҖ§гҒ®еҺҹеүҮгҒЁжі•зҡ„зөұдёҖгҒ®йҒ”жҲҗ
BGBгҒҢеӣҪеҶ…гҒ§жһңгҒҹгҒҷгҒ№гҒҚжңҖеӨ§гҒ®дҪҝе‘ҪгҒҜгҖҒй•·е№ҙгҒ®Gemeines RechtжҷӮд»ЈгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжі•гҒ®ж–ӯзүҮеҢ–гӮ’е®Ңе…ЁгҒ«е…ӢжңҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ®дё»иҰҒгҒӘжі•е…ёгҖҒгҒқгҒ—гҒҰBGBгӮӮгҖҒгҒ“гҒ®зӣ®зҡ„гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҖҢеҺіж јгҒӘжҺ’д»–жҖ§жқЎй …гҖҚгӮ’еӮҷгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
BGBгҒ®ж–ҪиЎҢжі•пјҲEinfГјhrungsgesetz zum BGB, EGBGBпјүгҒ®з¬¬55жқЎгҒҜгҖҒй ҳйӮҰгҒ®з§Ғжі•иҰҸеүҮгҖҒгҒ“гӮҢгҒ«гҒҜж…Јзҝ’жі•гӮӮеҗ«гҒҫгӮҢгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®жңүеҠ№жҖ§гӮ’е–ӘеӨұгҒ•гҒӣгӮӢгҒЁе®ҡгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒBGBгҒҢе”ҜдёҖгҒӢгҒӨжЁ©еЁҒгҒӮгӮӢз§Ғжі•гҒ®жәҗжіүгҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҖҒең°еҹҹзҡ„гҒӘж…Јзҝ’жі•гҒҢиҮӘеҫӢзҡ„гҒӘжі•жәҗгҒЁгҒ—гҒҰе®Ңе…ЁгҒ«е»ғжӯўгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гғүгӮӨгғ„жі•гғўгғҮгғ«гҒ®дё–з•Ңзҡ„гҒӘеәғгҒҢгӮҠ
BGBгҒ®дҪ“зі»зҡ„гҒӘијёеҮә
гғүгӮӨгғ„ж°‘жі•е…ёгҒҜгҖҒгҒқгҒ®ж–ҪиЎҢеҫҢгҖҒд»–гҒ®еӣҪгҖ…гҒ®з§Ғжі•гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰйқһеёёгҒ«йҮҚиҰҒгҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮBGBгҒҢеӣҪйҡӣзҡ„гҒ«жҲҗеҠҹгӮ’еҸҺгӮҒгҒҹиҰҒеӣ гҒҜгҖҒгҒқгҒ®ж”ҝжІ»зҡ„гҒӘиғҢжҷҜгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒзҙ”зІӢгҒ«гҖҢж§ӢйҖ зҡ„е„ӘдҪҚжҖ§гҖҚгҒЁгҖҢжҰӮеҝөзҡ„жҳҺжҷ°гҒ•гҖҚгҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮBGBгҒҜгҖҒеҸӨгҒ„гғҠгғқгғ¬гӮӘгғіжі•е…ёгғўгғҮгғ«гҒҢж¬ гҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҖҒз§Ғжі•гҒ®зө„з№”еҢ–гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®з§‘еӯҰзҡ„гҒ«иЁјжҳҺгҒ•гӮҢгҒҹж–№жі•пјҲгғ‘гғігғҮгӮҜгғҶгғідҪ“зі»гҒЁз·ҸеүҮпјүгӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒҠгӮҲгҒігҒқгҒ®д»–гҒ®ең°еҹҹгҒ§гҒ®еҸ—е®№
BGBгҒҜгҖҒгӮ№гӮӨгӮ№гӮ„гӮ®гғӘгӮ·гғЈгҒ®з§Ғжі•гҒ«зӣҙжҺҘзҡ„гҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгӮ№гӮӨгӮ№ж°‘жі•е…ёгҒЁйҖЈжҗәгҒ—гҒҰгҖҒгғӯгӮ·гӮўгӮ„гӮ№гӮ«гғігӮёгғҠгғ“гӮўи«ёеӣҪгҒ®жі•гҒ«гӮӮеҪұйҹҝгӮ’еҸҠгҒјгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ®ABGBпјҲ1812е№ҙпјүгҒҜе…ҲиЎҢгҒҷгӮӢжі•е…ёгҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒBGBгҒҜгҒ•гӮүгҒ«гӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўжі•гҒ«гӮӮеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
йқһгғЁгғјгғӯгғғгғ‘еңҸгҖҒзү№гҒ«гӮўгӮёгӮўең°еҹҹгӮ„гғ©гғҶгғігӮўгғЎгғӘгӮ«гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢBGBгҒ®жҷ®еҸҠгҒҜгҖҒгҒқгҒ®еӯҰиЎ“зҡ„гҒӘеЁҒдҝЎгҒ«ж”ҜгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮBGBгҒҜгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®жңҖгӮӮеҗҲзҗҶзҡ„гҒӢгҒӨжҠҖиЎ“зҡ„гҒ«е®Ңз’§гҒӘж°‘жі•е…ёгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®и©•дҫЎгӮ’еҫ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒжҳҺжІ»ж—Ҙжң¬гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жҖҘйҖҹгҒӘиҝ‘д»ЈеҢ–гӮ’зӣ®жҢҮгҒҷеӣҪ家гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒдјқзөұзҡ„гҒӘжі•дҪ“зі»гҒ«еҸ–гҒЈгҒҰд»ЈгӮҸгӮӢзҗҶжғізҡ„гҒӘгғўгғҮгғ«гҒЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®дәӢе®ҹгҒҜгҖҒжі•дҪ“зі»гҒҢеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮж”ҝжІ»зҡ„гғ»и»ҚдәӢзҡ„еҫҒжңҚгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҒ®гҒҝијёеҮәгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒзҹҘиӯҳдәәгӮ„еӯҰиЎ“з•ҢгҒ®гғҲгғ¬гғјгғӢгғігӮ°гҖҒгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҢзҹҘзҡ„гғ»ж§ӢйҖ зҡ„е„ӘдҪҚжҖ§гҖҚгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰијёеҮәгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иЁјжҳҺгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮBGBгҒ®дҪ“зі»гҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢгҖҒеӣҪйҡӣзҡ„гҒӘе•Ҷе“ҒгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гғүгӮӨгғ„BGBгҒЁж—Ҙжң¬гҒ®з§Ғжі•иҝ‘д»ЈеҢ–

жҳҺжІ»жҷӮд»ЈгҒ®ж”ҝжІ»зҡ„гӮӨгғігӮ»гғігғҶгӮЈгғ–
ж—Ҙжң¬гҒ®ж°‘жі•е…ёпјҲ1898е№ҙ7жңҲ16ж—Ҙж–ҪиЎҢпјүгҒҜгҖҒгғүгӮӨгғ„гҒ®BGBпјҲ1900е№ҙ1жңҲ1ж—Ҙж–ҪиЎҢпјүгӮ’дё»иҰҒгҒӘгғўгғҮгғ«гҒЁгҒ—гҒҰжҺЎз”ЁгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®жі•е…ёеҢ–гҒ®дё»гҒӘеӢ•ж©ҹгҒҜгҖҒгғЁгғјгғӯгғғгғ‘и«ёеӣҪгҒ®гҒқгӮҢгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢж”ҝжІ»зҡ„гҒӘзү№еҫҙгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮжңҖеӨ§гҒ®зӣ®жЁҷгҒҜгҖҒгҖҢдёҚе№ізӯүжқЎзҙ„гӮ’ж”№жӯЈгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҚгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒҢиҝ‘д»ЈеҢ–гҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’иҘҝ欧еҲ—еј·гҒ«зҙҚеҫ—гҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®жңҖгӮӮжЁ©еЁҒгҒӮгӮӢзҸҫд»Јзҡ„гҒӘжі•е…ёгғўгғҮгғ«гҒ§гҒӮгӮӢBGBгҒ®жҺЎз”ЁгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒҢиҘҝжҙӢгҒЁеҗҢзӯүгҒ®жі•зҡ„еҹәзӣӨгҒ§йҒӢе–¶гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒҷгҖҒжҲҰз•Ҙзҡ„гҒӘеӨ–дәӨж”ҝзӯ–гҒ®жүӢж®өгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒй–ўзЁҺиҮӘдё»жЁ©гҒЁжІ»еӨ–жі•жЁ©гҒ®еӣһеҫ©гҒЁгҒ„гҒҶеӣҪ家主権гҒ®еӣһеҫ©гӮ’жӯЈеҪ“еҢ–гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®жүӢж®өгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
ж§ӢйҖ зҡ„жҺЎз”ЁгҒЁгғ‘гғігғҮгӮҜгғҶгғідҪ“зі»гҒ®еҸ—е®№
ж—Ҙжң¬гҒҜгҖҒBGBгҒӢгӮүгҒқгҒ®дҪ“зі»зҡ„гҒӘж§ӢйҖ гӮ’жң¬иіӘзҡ„гҒ«з¶ҷеҸ—гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮзү№гҒ«гҖҒжЁ©еҲ©иғҪеҠӣгӮ„жі•еҫӢиЎҢзӮәгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжҠҪиұЎзҡ„гҒӘжҰӮеҝөгӮ’гҖҒзү©жЁ©гӮ„еӮөжЁ©гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҖӢеҲҘгҒ®жі•еҹҹгҒ«е…Ҳз«ӢгҒЈгҒҰжүұгҒҶгҖҢз·ҸеүҮгҖҚпјҲAllgemeiner TeilпјүгҒ®жҰӮеҝөзҡ„дҫЎеҖӨгӮ’иӘҚиӯҳгҒ—гҖҒгҒқгҒ®дә”йғЁж§ӢжҲҗгҒ®дҪ“зі»гӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒж–ӯзүҮзҡ„гҒӘжұҹжҲёжҷӮд»ЈгҒ®жі•гҒӢгӮүгҖҒзөұдёҖзҡ„гҒ§жҰӮеҝөзҡ„гҒӘжі•зҡ„гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒёгҒ®и»ўжҸӣгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
ж…Јзҝ’жі•гӮ’гӮҒгҒҗгӮӢеӣҪеҶ…дәӢжғ…
гғүгӮӨгғ„гҒ®BGBгҒҢеӣҪеҶ…гҒ®е®Ңе…ЁгҒӘжі•зҡ„зөұдёҖгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҖҒж…Јзҝ’жі•гӮ’иҮӘеҫӢзҡ„гҒӘжі•жәҗгҒЁгҒ—гҒҰеҺіж јгҒ«е»ғжӯўгҒ—гҒҹгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жі•е…ёгҒҜж…Јзҝ’жі•гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгӮҲгӮҠеҘҪж„Ҹзҡ„гҒӘе§ҝеӢўгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
ж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜжқЎзҙ„ж”№жӯЈгҒҢжңҖе„Әе…ҲдәӢй …гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеӣҪеҶ…гҒ®жі•зҡ„зөұдёҖгҒҜеүҜж¬Ўзҡ„гҒӘйҮҚиҰҒжҖ§гҒ—гҒӢжҢҒгҒҹгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒж…Јзҝ’жі•гӮ’е®Ңе…ЁгҒ«е»ғжӯўгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгӮҖгҒ—гӮҚгҖҒд»ҘеүҚгҒ®гҖҢж—§ж°‘жі•гҖҚгҒ®йҒӢе‘ҪгҒҢзӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒиҘҝжҙӢжі•е°Һе…ҘгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеӣҪеҶ…гҒ®еәғзҜ„гҒӘж•өж„ҸгҒ«еҜҫжҠ—гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгҖҢе°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮдёҖйғЁгҒ®ж—Ҙжң¬гҒ®жі•зҡ„дјқзөұгӮ’ж•‘жёҲгҒҷгӮӢгҖҚгҒҹгӮҒгҒ®е„ӘгӮҢгҒҹжҲҰз•ҘгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒж…Јзҝ’жі•гҒ®з¶ӯжҢҒгҒҢж©ҹиғҪгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
ж—Ҙжң¬гҒ®жі•д»ӨйҒ©з”ЁгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжі•пјҲжі•дҫӢпјү第2жқЎгҒҜгҖҒе…¬гҒ®з§©еәҸгҒ«еҸҚгҒ—гҒӘгҒ„ж…Јзҝ’гҒҜгҖҒгҖҢжі•еҫӢгҒЁеҗҢдёҖгҒ®еҠ№еҠӣгӮ’жңүгҒҷгӮӢгҖҚгҒЁжҳҺиЁҳгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒе…ҘдјҡжЁ©пјҲе…ұеҗҢеҲ©з”Ёең°гҒ«й–ўгҒҷгӮӢжі•зҡ„иҰҸеүҮпјүгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҖҒж—Ҙжң¬гҒ§йқһеёёгҒ«йҮҚиҰ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹең°е…ғгҒ®ж…Јзҝ’жі•гӮ’йҒ©з”ЁеҸҜиғҪгҒЁгҒҷгӮӢиҰҸе®ҡгҒҢж°‘жі•е…ёгҒ«жҳҺзӨәзҡ„гҒ«еҗ«гҒҫгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®зӣёйҒ•зӮ№гҒҜгҖҒBGBгҒ®еӣҪйҡӣзҡ„гҒӘйҒәз”ЈгӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢдёҠгҒ§йқһеёёгҒ«йҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®жі•е…ёгҒҜж§ӢйҖ зҡ„гҒ«гҒҜгғүгӮӨгғ„зҡ„гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒгҒқгҒ®гҖҢе“ІеӯҰзҡ„еҹәзӣӨгҖҚгҒҜгҖҒзӢ¬иҮӘгҒ®ж”ҝжІ»зҡ„гғ»ж–ҮеҢ–зҡ„иӘІйЎҢгҒ«еҜҫеҮҰгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«дҝ®жӯЈгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮж—Ҙжң¬гҒҜгҖҒBGBгҒ®й«ҳеәҰгҒ«еҗҲзҗҶзҡ„гҒӘгҖҢж§ӢйҖ гҖҚгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰжі•гӮ’зө„з№”еҢ–гҒ—гҒӨгҒӨгҖҒгғүгӮӨгғ„жі•иҮӘиә«гҒҢеӣҪеҶ…гҒ§еҺіж јгҒ«зҰҒжӯўгҒ—гҒҹгҖҒгғҚгӮӨгғҶгӮЈгғ–гҒӘVolksgeistгҒ®дёҚеҸҜж¬ гҒӘгҖҢиҰҒзҙ гҖҚгӮ’дҝқжҢҒгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«жҲҗеҠҹгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒ
гғүгӮӨгғ„гҒ®жі•дҪ“зі»гҒ®жӯҙеҸІгҒҜгҖҒдёӯдё–гҒӢгӮүгҒ®гғӯгғјгғһжі•з¶ҷеҸ—гҒЁгҖҒ19дё–зҙҖгҒ®жӯҙеҸІжі•еӯҰжҙҫпјҲгӮөгғҙгӮЈгғӢгғјпјүгҒЁжҰӮеҝөжі•еӯҰжҙҫпјҲгғ‘гғігғҮгӮҜгғҶгғіеӯҰжҙҫпјүгҒ®зҹҘзҡ„гҒӘеҠӘеҠӣгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҪўжҲҗгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®й•·жңҹй–“гҒ«гӮҸгҒҹгӮӢеӯҰиЎ“зҡ„гҒӘжҙ—з·ҙгҒ“гҒқгҒҢгҖҒBGBгҒ«й«ҳеәҰгҒӘдҪ“зі»зҡ„е„ӘдҪҚжҖ§гӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮзү№гҒ«гҖҒз·ҸеүҮгҒЁгҒ„гҒҶжҰӮеҝөзҡ„ж§ӢйҖ гҒҜгҖҒз§Ғжі•гҒ®е…Ёй ҳеҹҹгӮ’и«–зҗҶзҡ„гҒ«ж•ҙзҗҶгҒ—гҖҒBGBгӮ’еҚҳгҒӘгӮӢжі•еҫӢйӣҶгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒ法科еӯҰгҒ®йӣҶеӨ§жҲҗгҒЁгҒ—гҒҰдё–з•ҢгҒ«иӘҚгӮҒгҒ•гҒӣгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жӯҙеҸІзҡ„гҒӘе„ӘдҪҚжҖ§гҒ«зқҖзӣ®гҒ—гҒҹж—Ҙжң¬гҒҜгҖҒжҳҺжІ»жҷӮд»ЈгҒ®гҖҢдёҚе№ізӯүжқЎзҙ„гҒ®ж”№жӯЈгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж”ҝжІ»зҡ„иҰҒи«ӢгҒ«еҝңгҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒBGBгҒ®ж§ӢйҖ гӮ’гғўгғҮгғ«гҒЁгҒ—гҒҰжҺЎз”ЁгҒ—гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®иҝ‘д»ЈеҢ–гҒ®зӨҺгӮ’зҜүгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
зҸҫеңЁгҖҒгғүгӮӨгғ„гҒ§гҒ®дәӢжҘӯеұ•й–ӢгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒгҒ“гҒ®жӯҙеҸІзҡ„гғ»жҰӮеҝөзҡ„иғҢжҷҜгӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒжі•еҲ¶еәҰгҒ®еҺіж јгҒӘдәҲиҰӢжҖ§гӮ’жҠҠжҸЎгҒ—гҖҒйҒ©еҲҮгҒӘжҲҰз•ҘгӮ’ж§ӢзҜүгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҹәзӣӨгҒЁгҒӘгӮӢгҒҜгҒҡгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮ«гғҶгӮҙгғӘгғј: ITгғ»гғҷгғігғҒгғЈгғјгҒ®дјҒжҘӯжі•еӢҷ