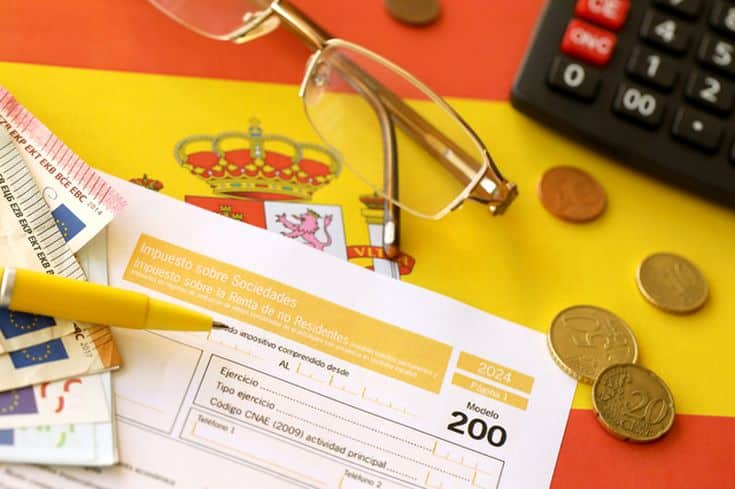ドイツ等の欧州企業ガバナンスにおける二層型経営構造とは

ドイツ、オランダ、オーストリア及びフィンランドといったEU圏の国々は、その会社法における企業ガバナンスとして、「二層型経営構造」や「二層型ガバナンス」と呼ばれる仕組みを採用しています。この二層型の構造は、単なる組織上の違いに留まらず、企業の意思決定プロセスやガバナンスの根本的な理念に大きな違いをもたらすものです。
本記事では、これらの国に共通して見られる二層型経営構造の理念を解説し、その上で、ドイツの厳格な共同決定制度、オーストリアの独特な任免要件、オランダの「大会社」を対象とした強制適用、そしてフィンランドにおける選択制の現状など、各国の独自性、特に日本の会社法と比較した相違点を解説します。
この記事の目次
二層型経営構造の共通理念:経営と監督の明確な分離
「一層型」と「二層型」
企業統治のモデルは、経営の「意思決定」と「監督」の役割をどのように組織に組み込むかという観点から、大きく「一層型(one-tier)」と「二層型(two-tier)」の二つに分類することができます。
このうち、一層型経営構造は、業務執行を担う執行役員(executive director)と、その監督を担う非執行役員(non-executive director)が一つのボード(取締役会)を構成するモデルです。このモデルは、欧米の多くの国で採用されており、日本の指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社も、この一層型と類似した仕組みであると言えます。一層型では、経営と監督が同一の組織内に存在するため、ボードメンバー間の情報共有がより迅速かつ詳細に行われ、監督がより実践的になるという利点があると言えるでしょう。
これに対し、二層型経営構造(dual boardまたはtwo-tier system)は、企業の意思決定機能を「経営を担う機関」と「その経営を監督する機関」という、完全に独立した二つの組織に分離する企業統治モデルです。このモデルでは、ドイツの株式法(AktG)が規定する、執行役会(Vorstand)と監査役会(Aufsichtsrat)という二つの機関からなる構造が典型的です。
役割分担の原則
二層型構造の本質は、役割分担の明確化です。執行役会は、会社の日常的な業務執行と運営の全責任を負い、その活動は法的、倫理的基準、そして会社の最善の利益に従って行われることが求められます。一方で、監査役会は、執行役会の業務執行が適切かつ法令に準拠して行われているかを監視し、助言を与える役割を担います。この二つの機関は、メンバーの兼務が法的に禁止されるなど、その独立性が厳格に保たれています。例えば、ドイツの監査役会は、経営戦略の長期的な方向性について執行役会に助言を行い、同時にその進捗を監督します。
経営陣の選任・解任権
日本の会社法では、取締役の選任・解任権は株主総会に帰属しており、監査役や監査等委員会は経営陣の職務執行を監査・監督しますが、経営者の直接的な任免権は持っていません。これに対し、「二層型経営構造」を採用する国の多くでは、監査役会が執行役会メンバーを任命し、また、正当な理由がある場合には解任する権限を持つという、日本とは根本的に異なる権限構造が確立されています。この「間接的な統治モデル」は、株主が選任した監査役会が、より専門的かつ客観的な視点から経営陣を評価し、長期的な視点での経営を促すことを目的としています。
この権限構造の違いは、ガバナンスの仕組みに大きな変化をもたらします。ドイツやオーストリアでは、監査役会が経営陣と株主総会の間に位置する「専門家による緩衝材」として機能します。株主総会は、監査役会メンバーを選任・解任することで、間接的に経営に影響力を及ぼしますが、経営陣の直接的な任免権を株主から切り離すことで、短期的な利益追求に偏りがちな株主の意向が、企業の長期戦略に直接的な影響を与えることを防ぐことができます。この構造は、短期的な効率性よりも、経営の安定性と長期的な視点での企業価値向上を重視するというガバナンス理念の表れとも言えます。
ドイツ:厳格な二層型構造と「共同決定」制度

ドイツでは、株式会社(Aktiengesellschaft; AG)が二層型経営構造であることを、株式法(AktG)によって原則として義務付けられています。日本の会社法が多様な機関設計を許容しているのとは対照的な制度設計です。この制度は、単なる形式的なものではなく、執行役会と監査役会のメンバーが相互に兼任することを禁止するなど、両機関の独立性を確保するものです。
監査役会の監督権限
ドイツの監査役会は、執行役会に対する広範な監督権限を有しています。その最も重要な権限の一つが、執行役会のメンバーを任命し、解任することです。また、ドイツ株式法第111条第4項は、定款で定められた重要な業務執行行為について、執行役会が監査役会の承認を得ることを義務付けています。この承認権を持つ監査役会は、単に事後報告を受ける立場ではなく、経営の方向性を共同で決定する強力な機関として機能します。
ドイツ独自の「共同決定(Mitbestimmung)」制度
ドイツの会社統治を理解する上で、日本の制度との比較において特に重要な論点が「共同決定(Mitbestimmung)」制度です。共同決定は、一定規模以上の企業について、監査役会(Aufsichtsrat)に株主代表だけでなく従業員代表も参加させることを求めるもので、適用対象は株式会社(AG)に限られず、有限会社(GmbH)等の会社形態にも及びます。ドイツ共同決定法(MitbestG)等に基づき、通常、従業員数が2,000人を超える企業(単体又はグループ会社を含めた規模で判断される場合があります)では、監査役会は株主代表と従業員代表が同数で構成されます(もっとも、可否同数の場合には議長の第二票により結論が決する仕組みがあります)。また、従業員数が500人を超える企業では、三分の一参加法(Drittelbeteiligungsgesetz(DrittelbG))により、監査役会の3分の1を従業員代表が占めます。
ドイツの共同決定制度は、「ステークホルダー資本主義」を法制度として具現化したものと評価することができます。これは、企業統治の目的が株主利益の最大化に留まらず、従業員という重要なステークホルダーの利益も考慮に入れるべきであるという価値観を強く反映しているものです。従業員代表がガバナンス機関に参加することで、経営判断はより多角的な視点から検討され、短期的な利益追求や財務的な効率性(financial market perspective)を抑制し、長期的な雇用安定や安定性といった目標を重視する傾向を生み出す可能性があります。
オーストリア:ドイツとの類似点と「二重多数」要件

オーストリアの株式法も、ドイツと同様に、経営を担う執行役会(Management Board)と、その監督を担う監査役会(Supervisory Board)から成る二層型構造を採用しています。このモデルでは、経営陣の任免権を株主総会ではなく、監査役会が有するという基本的な仕組みも共通しています。
オーストリアの二層型構造には、経営陣の任免において独自の要件があります。従業員代表が監査役会に参加する場合、執行役会メンバーの任命・解任決議には、監査役会全体の過半数に加え、株主総会で選出された監査役会メンバーの過半数という、二つの多数要件(「二重多数」、double majority)を満たす必要があります。
この二重多数要件は、ドイツの共同決定制度と同様に、企業の最も重要な意思決定において、「株主の意向」と「従業員の意向」のバランスを取ることを目的としています。この仕組みにより、一方の勢力(例えば、従業員代表)が全体の過半数を占めない場合でも、任免決議に拒否権を行使するのと同等の効果を持つことができます。この制度は、株主の利益と従業員の利益が対立する場面において、経営陣の選任・解任が一方的な決定とならないよう、より広範な合意形成を促すための制度的保障であると言えるでしょう。ドイツとオーストリアは、いずれも従業員代表をガバナンスに取り込むことで、企業統治におけるステークホルダーの役割を重視していますが、その実現方法において細かな違いが存在する訳です。
オランダ:「大会社」制度と選択肢

オランダでは、すべての株式会社に二層型構造が義務付けられているわけではありません。オランダ国内で100人以上の従業員を有し、払込資本が1,600万ユーロ以上などの基準を一定期間継続して満たしていると、法律が定める「大会社(large company)」として扱われ、「構造規制(structuurregime)」が適用されます。
この構造規制が適用されると、企業は「一層型ボード(one-tier board)」または「二層型ボード(two-tier board)」のいずれかを採用することが義務付けられます。
一層型ボードは、業務執行を担う業務執行取締役(executive directors)と、監督を担う非業務執行取締役(non-executive directors)が一つの法人組織(one corporate body)を構成するモデルです。この構造の主な利点は、経営と監督が同じボード内に存在するため、ボードメンバー間の情報共有がより迅速かつ詳細に行われ、監督がより実践的になる点にあります。また、非業務執行取締役がボードの一員となることで、モチベーションと責任感が高まる可能性があると言えます。
一方、二層型ボードは、執行役会(executive board)と、独立した監査役会(supervisory board)という二つの法人組織から成ります。このモデルの利点は、経営陣と監督者が完全に分離されることにより、監査役会がより独立した客観的な視点を持つことができる点にあります。
そして、オランダでは、ほとんどの公開有限会社(nv)や非公開有限会社(bv)が、二層型ボードを採用しています。なお、どちらの構造を選択する場合でも、非業務執行取締役または監査役会メンバーは自然人である必要があります。
オランダの法制度は、経営の柔軟性と独立性のバランスを慎重に考慮しており、企業がその規模や特性に応じて最適なガバナンスモデルを選択することを可能にしていると言えるでしょう。
フィンランド:法制度上の選択肢

フィンランドの有限責任会社法(FCA)では、取締役会(Board of Directors)の設置が義務付けられている一方、監査役会(Supervisory Board)の設置は任意です。したがって、企業は二層型構造を採用することも可能です。しかし、法制度上は二層型も可能であるにもかかわらず、実際には大半の公開会社が「一層型ボード(one-tier board)」を選択しています。
一層型ボードでは、経営を担う執行役員(executive director)と、監督を担う非執行役員(non-executive director)が同一の取締役会に所属します。非執行役員は日々の業務執行には関与せず、経営陣を監督する役割を担います。この構造の利点は、情報共有がより迅速に行われ、監督がより実践的になることであると指摘されています。
フィンランドのモデルは、取締役会全体が監督機能を持ち、必要に応じてCEO(執行役)に権限を委譲するという、日本の指名委員会等設置会社に近い理念を持っており、これは、ドイツのような厳格な分離モデルとは異なる、別のコーポレートガバナンスの形と言えるでしょう。
イタリア:選択肢となったが普及が進まず
2003年改革により、イタリアの株式会社(S.p.a.)は、定款の定めによって、以下の3つの経営・監査モデルを選択することができるようになりました。
- 経営機関である取締役会(Consiglio di Amministrazione)または単独取締役(Amministratore Unico)と、監査機関である法定監査役会(Collegio Sindacale)から構成される伝統モデル(Sistema tradizionale)
- ドイツ法に由来し、経営と監督の機能を、経営評議会(Consiglio di Gestione)と監査役会(Consiglio di Sorveglianza)と、明確に分離する二元モデル(Sistema dualistico)
- 米国法に由来するモデルで、単一の取締役会(Consiglio di Amministrazione)が経営と監督の両方を担う一元モデル(Sistema monistico)
ただ、イタリアの立法者は、ドイツの二元モデルを参考にしつつも、労働者参加(cogestione)の要素を排除しました。この結果、イタリアの二元モデルは、純粋な企業ガバナンスの効率性向上に焦点を当てた、いわば「骨抜きにされたモデル」とも評価されています。
そして、2003年改革によって新しい経営モデルが導入されてから2017年末までの時点で、イタリアの上場企業のうち二元モデルを採用していたのは、わずか2社に過ぎません。
まとめ
本記事で解説したように、ドイツ、オランダ、オーストリア、フィンランドの二層型経営構造は、一見類似しているようで、その背後には法制度、文化、歴史に基づいた重要な相違点が存在します。ドイツの厳格な「経営と監督の分離」と「共同決定」、オーストリアの「二重多数」要件、オランダの「大会社」を対象としたプラグマティックな規制、そしてフィンランドの「一層型ボード」を主流とする柔軟性。これらの違いは、単なる組織図の差ではなく、企業が社会においてどのような役割を果たすべきか、という哲学の違いに根ざしているとも言えるでしょう。
| ドイツ | オーストリア | オランダ | フィンランド | |
|---|---|---|---|---|
| 二層型構造の法的強制力 | 原則義務(AG) | 原則義務 | 「大会社」に義務 | 任意 |
| 経営陣の任免権限 | 監査役会 | 監査役会 | 監査役会 | 株主総会 |
| 従業員代表の関与 | 共同決定(人数に応じ同数または1/3) | 任免決議に「二重多数」要件 | 監査役候補の推薦権 | 監督機能を持つ監査役会の設置は任意 |
| 主流のボード構造 | 二層型 | 二層型 | 選択肢あり(大会社は強制) | 一層型 |
日本の経営者にとって、これらの複雑な制度を理解することは、M&Aや新規事業設立、合弁事業の運営において、予期せぬリスクを回避し、ステークホルダーとの円滑な関係を築く上で不可欠です。ガバナンスの仕組みは、その国のビジネス文化や意思決定プロセスそのものに直結しているからです。
例えば、ドイツでは、経営陣の任免権を監査役会に委ねることで、短期的な株主の圧力から経営陣を守り、長期的な視点での企業価値向上を促そうという理念が働いています。これは、日本の会社法が取締役の任免権を株主総会に留保している点と大きく異なります。さらに、ドイツやオーストリアでは従業員代表が経営の監督に関与することで、企業統治の目的を株主利益の最大化だけでなく、従業員を含めたより広範なステークホルダーの利益を考慮に入れるべきだという思想が制度に組み込まれています。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務