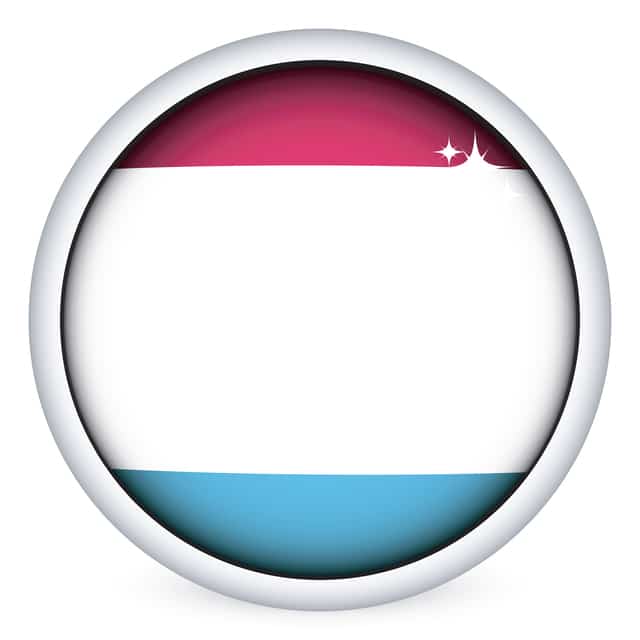ウズベキスタンの法律の全体像とその概要を弁護士が解説

ウズベキスタン共和国(以下、ウズベキスタン)は、日本企業にとって非常に魅力的な投資先として急速に存在感を高めています。2016年のミルジヨエフ大統領就任以降、政府は「新ウズベキスタン」戦略を掲げ、強力なトップダウンによる市場開放と経済の自由化を推進してきました。その結果、国際通貨基金(IMF)やアジア開発銀行(ADB)は、同国の実質GDP成長率が2025年以降も6%台後半という、世界でも稀に見る高い水準で推移すると予測しています。
この力強い経済成長は、外国直接投資(FDI)の積極的な誘致政策と、世界貿易機関(WTO)への加盟を最大の目標とした矢継ぎ早の法制度の近代化によって支えられています。法務省の分析によれば、ウズベキスタンの法体系は、日本と同じく大陸法(シビル・ロー)を基盤とし、そこに旧ソ連法の強い影響が残るという構造を持っています。このため、民法、労働法、税法といった主要な法律が「法典(Code)」として整備されており、法体系の「構造」自体は、日本の法務担当者にとって比較的理解しやすいものと言えるでしょう。
しかし、個別の法規制、特に会社設立、労働者の解雇、個人データの取り扱い、不動産の所有といった、ビジネスの根幹に関わる具体的なルールにおいて、日本法とは大きく異なるウズベキスタン特有の規制が数多く存在します。むしろ、法制度が「安定」しているのではなく、「国家戦略として意図的に、かつ急速に変更され続けている」こと自体が、同国でビジネスを行う上での最大の特徴であり、同時に法務リスクの源泉ともなっています。
本記事では、ウズベキスタン進出を検討する日本企業が直面する会社設立・ガバナンス、労働法、個人情報保護法、およびM&Aなどの主要法分野における日本法との「差異」と「実務上のリスク」について網羅的に解説します。
この記事の目次
ウズベキスタンにおける会社設立とガバナンス
進出形態の選択肢
外国投資家がウズベキスタンで事業活動を行うための主要な進出形態は、有限責任会社(LLC:Limited Liability Company)と株式会社(JSC:Joint Stock Company)の二つです。実務上、JSCの設立・運営は「非常に時間がかかり、規制が厳しい」プロセスであると認識されており、多くの外国投資家はLLCを選択する傾向にあります。
日本企業が海外進出の初期段階で検討する「駐在員事務所」や「支店」といった形態については、ウズベキスタン法は極めて厳格な制限を設けており、日本法との違いに特に注意が必要です。
第一に、駐在員事務所(RO:Representative Office)は、法的に現地法人格を持たない組織として認定(Accreditation)を受けることが可能ですが、その活動は「マーケティング及び非取引的なサポート」に厳格に限定されています。法律は、ROが「商業活動を行ってはならない」と明記しており、これに違反した場合、当局によって認定が取り消される可能性があります。これは、営業活動の準備行為が比較的広範に認められる日本の実務とは大きく異なる点です。
第二に、支店(Branch)の形態は、法制度上、さらに困難です。ウズベキスタンの法律は、外国企業の支店設置を明確に禁止してはいませんが、その登録手続きを規律する具体的な法規制が存在しません。このため実務上は、当局が外国法人の支店登録を通常拒否する状況にある模様です。
この二つの制約より、ウズベキスタンの法制度は、外国投資家に対し、「駐在員事務所」や「支店」といった簡素な形態での「お試しの」事業展開を事実上許さず、最初から現地法人(LLCまたはJSC)の設立、すなわちウズベキスタン法に基づく完全な法務・税務コンプライアンスのコミットメントを求める構造になっている、と言えるでしょう。日本企業が他国でしばしば採用する「まず支店で市場の感触を掴み、軌道に乗ったら現地法人化する」という段階的な進出戦略は、ウズベキスタンでは法的に採用できない可能性が高いと言えます。
なお、現地法人の設立登記プロセス自体は「ワンストップショップ」原則が採用されており、理論上は2営業日以内に完了するとされています。ただし、すべての提出書類はウズベク語で作成する必要があります。
LLCとJSCの機関設計と最低資本金
ウズベキスタンで現地法人を設立する際、そのガバナンスと資本に関するルールにも注意が必要です。
機関設計については、LLCは「有限責任・追加責任会社法」(Law No. 310-II)に基づき、最高意思決定機関は「社員総会」です。監査役会(Supervisory Board)の設置は任意とされています。一方、JSCは「株式会社法」(Law No. ZRU-370)に基づき、「株主総会」と、業務執行を監督する「監査役会」の設置が求められます。
日本企業が特に注目すべきは、最低資本金に関する規定です。原則として、LLCおよびJSCともに、最低資本金の定めはありません。しかし、この原則には重大な例外があります。それは、「外国企業」がLLCを設立する場合に限り、約31,000米ドル相当の最低資本金が要求されるという点です。日本企業は、この初期費用を事業計画に予め織り込む必要があります。
ウズベキスタンと日本法との差異が大きい主要法分野

労働法における解雇規制
2023年4月30日に施行された新労働法は、日本企業がウズベキスタンで事業運営を行う上で、最も実務上の困難に直面する可能性のある分野の一つです。ウズベキスタンでは、解雇の要件と手続きが労働法典に極めて詳細かつ明確に「成文化」されています。労働契約の終了には「正当な理由」が必要であり、その理由は法律で定められたものに限られます。特に、会社側の都合(経営判断)による解雇について、その理由ごとに厳格な「事前通知期間」が定められています。
- 整理解雇(組織変更、人員削減、業務量の減少など):少なくとも2ヶ月前の通知が必要。
- 能力不足(従業員の資格不足や業務不適合):少なくとも2週間前の通知が必要。
- 懲戒解雇(従業員の重大な規律違反):少なくとも3日前の通知が必要。
さらに、従業員の規律違反(guilty actions)を理由とする場合を除き、解雇に際しては、勤続年数に応じた法定の退職金(Severance payment)の支払いが義務付けられています。この金額も、以下のように労働法典で詳細に規定されています。
- 勤続3年未満:平均月給の50%
- 勤続3~5年:平均月給の75%
- 勤続5~10年:平均月給の100%
- 勤続10~15年:平均月給の150%
- 勤続15年以上:平均月給の200%
これらの規定より、整理解雇は「2ヶ月前の通知」と「高額な法定退職金」という二重のコストを伴う経営判断となります。
個人情報保護法におけるデータローカライゼーション義務
2019年7月に採択された「個人データ法」(Law No. ZRU-547)には、日本企業を含むグローバル企業のIT戦略の根幹を揺るがす、極めて厳格な規制が含まれています。
日本の個人情報保護法は、データを外国にある第三者に移転する場合、本人の同意や、個人情報保護委員会による十分性認定(adequate decision)などを要件としていますが、サーバーの物理的な設置場所を国内に限定する「データローカライゼーション」は原則として要求していません。
しかし、ウズベキスタン法は、この点で根本的に異なります。「個人データ法」の改正(第27条の1)により、ウズベキスタン国民の個人データを(インターネットを含め)情報技術を用いて処理する「事業者(owner or operator)」は、「ウズベキスタンの領土内に物理的に設置された技術的手段(サーバー)において、その収集、体系化、保管」を行うことが義務付けられました。政府はこの義務の執行に強い姿勢を見せており、違反した外国のインターネットサービスに対しては、国内からのアクセスを「ブロックする」権限を有しています。
この厳格なデータローカライゼーション義務は、グローバル共通のクラウドインフラ(Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platformなど)や、本社(日本)で一元管理されるSaaS(Salesforce等のCRMシステムや、Workday等のHRシステム)を利用する現代のビジネスモデルと真っ向から対立します。
日本企業はウズベキスタン市場に参入するために、(1) グローバル標準のITインフラの利用を諦め、ウズベキスタン国内に高コストなローカルサーバーを構築・運用する、(2) そもそもウズベキスタン市場への参入を断念する、という二者択一を迫られる可能性があります。これは、特にIT・デジタル関連企業にとって、進出の可否を決定づける「ビジネス・ブレーカー(事業の障害)」となり得る、最重要の法規制です。
広告法における言語規制
2022年9月に施行された新「広告法」(Law No. ZRU-776)は、日本の景表法(不当景品類及び不当表示防止法)や薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)、医療広告ガイドラインに相当する規制を含みますが、日本法には見られない独自の規定が設けられています。
最大の特徴は、国家の言語政策に基づく厳格な「言語規制」です。広告は原則としてウズベク語(国家語)でなければなりません。外国語(ロシア語や英語など)による翻訳を併記することは可能ですが、その翻訳テキストは「ウズベク語のテキストよりも小さいフォント」でなければならず、かつ「広告スペース全体の40%を超えてはならない」と定められています。これは、表示内容の「真実性」や「優良誤認」を規律する日本の景表法とは全く異なる、ナショナル・アイデンティティに基づく規制であり、広告デザインの根本的な変更を要求するものです。
外国法人・外国人による所有を制限する不動産法
ウズベキスタンでは、民法および財産法上、土地は原則として国有(非私有)とされています。外国法人は、土地の「所有権」を持つことはできず、原則としてリース(賃借権)のみが認められます(最長25年)。ただし、その土地の上に建設された建物や構造物(工場、オフィスビルなど)の「所有権」を取得することは可能です。このように「土地(リース)と建物(所有)の権利が分離する」という点は、日本の不動産実務とは異なるため、投資家は十分な注意を払う必要があります。
さらに厳格なのが、外国人が「個人」として居住用不動産(特に首都タシケント)を購入する場合の条件です。2020年の閣僚会議決定などに基づき、外国人がタシケントで居住用不動産を購入するには、以下の複数の条件をすべて満たす必要があります。
- ウズベキスタンの居住許可(IDカード)を保有していること
- タシケントにおける永続的な登録(propiska)を有すること
- タシケントにおいて3年以上の永続的な居住または就労実績があること
- 対象物件が新築であること
- 最低購入価格(3,300 BCV、約89,000米ドル相当)以上であること
この「3年間の居住実績」という要件は、日本から派遣される駐在員(経営者、技術者など)が、赴任後すぐに個人として住宅を購入することを事実上不可能にしています。ただし、同規定は、この要件が「IT Visa」保有者には免除されるとしています。
ウズベキスタンにおけるM&Aと事業拡大に関する法務
2023年に施行された新・競争法(独占禁止法)
日本企業がウズベキスタンの既存企業を買収(M&A)または合弁事業(JV)を設立する際、競争法(日本の独占禁止法に相当)に基づく規制を検討する必要があります。2023年10月、新「競争法」(Law No. ZRU-850)が施行され、企業結合審査に関するルールが明確化されました。
企業結合(M&A)は、一定の基準を満たす場合、「競争促進・消費者保護委員会」への「事前届出」が義務付けられています。
日本法と特に異なるのは、届出が必要となる株式取得のトリガー(閾値)です。ウズベキスタン法では、以下の取得が審査対象となります。
- JSC(株式会社):議決権株式の25%超の取得
- LLC(有限責任会社):持分の3分の1超の取得
上記の取得に該当し、かつ、当事者の総資産または総売上高が一定の財務的基準(例:当事者の合計資産額が500,000 BCV(基本計算値)を超える、等)を満たす場合に、事前届出が必要となります。
司法制度と「経済裁判所」
ウズベキスタンでのビジネスが紛争に至った場合の解決手段について、司法制度の構造とリスクを理解しておくことは重要です。ウズベキスタンの裁判所制度は、最高裁判所を頂点とする三審制(原則)を採用しています。
特徴的なのは、専門裁判所の存在です。企業間・投資家間の商事紛争、および「投資家と行政機関との間の紛争」(許認可の取り消しや税務処分など)については、専門の「経済裁判所(Economic Courts)」が管轄権を有しています。また、最高裁判所が投資紛争を直接審理する新たな手続きも導入されています。
ウズベキスタンの「投資法」などの法律は、外国投資家が国際仲裁(ICSIDなど)によって紛争を解決することを認めています。ウズベキスタンは、外国仲裁判断の承認・執行を義務付けるニューヨーク条約にも加盟しています。
しかし、これらの法律上の保護と、実際の司法実務との間には、投資家にとって予測不可能な「ギャップ」が存在するリスクが指摘されています。近時の裁判例(非公開のA vs B事件)において、ウズベキスタンの裁判所(第一審から最高裁判所まで)が、LCIA(ロンドン国際仲裁裁判所)による外国仲裁判断の承認・執行の申立てを、「管轄権がない」というニューヨーク条約の解釈を逸脱したと見られる理由で、申立ての「受理自体」を拒否するという事態が発生したと報告されています。
これは、投資家がシンガポールやロンドンでの国際仲裁に勝訴しても、ウズベキスタン国内にある相手方の「資産の差し押さえ」が実行できず、権利が実現できないリスクがあることを示しています。したがって、日本企業は、契約書上の紛争解決条項を設計する際、「国際仲裁」を定めるだけでなく、その判断がウズベキスタン国内で実際に執行可能かというリスクを考慮し、場合によっては国内の経済裁判所での解決も検討する必要があります。
ウズベキスタンの主要な許認可や新領域等の法規制
主要な許認可ビジネス
ウズベキスタンでは、多くの事業分野で政府による許認可(ライセンス)が要求されます。これらの規制は、日本の資金決済法、金融商品取引法、あるいは各種業法に相当するものです。
2024年現在、許認可が必要な活動リストには、以下のような分野が含まれています。
- 金融セクター:銀行、信用供与(マイクロクレジット)、保険、証券市場の専門的活動、決済システム事業者、決済処理事業者
- 専門サービス:弁護士、公証人、観光活動、出版活動
- テクノロジー関連:暗号保護製品(cryptographic protection)の設計、開発、製造、販売、修理、使用
- その他:宝くじの開催、アルコール飲料の卸売
進出を検討する日本企業は、自社の事業がこれらの許認可対象に該当しないか、事前に綿密な調査が不可欠です。特に「暗号保護製品の設計・開発」といった規定は、一般的なITセキュリティソフトウェアの販売や、暗号化技術を用いたサービスの提供など、一見すると直ちに該当しないように見える事業も対象となる可能性があり、その解釈の範囲について専門的な確認が求められます。
人工知能(AI)を巡る動向
人工知能(AI)について、ウズベキスタン政府は、新技術分野、特にAIの導入を国家戦略として強力に推進しています。「デジタル・ウズベキスタン2030」戦略の一環として、2024年10月14日には大統領決議(No. PQ-358)が採択され、「2030年までのAI技術発展戦略」が承認されました。この戦略は、2030年までにAI製品・サービス市場を15億ドル規模に拡大し、「政府AI準備度インデックス」で世界トップ50入りを目指すという野心的なものです。現時点では、EUのAI法のような厳格な「規制法(ハードロー)」ではなく、AIの導入を銀行、税務、医療、農業などの分野で促進し、同時に「規制枠組みを構築する」ことを目指す「産業育成」フェーズにあります。
物流法務
ウズベキスタンは、国土が海に面していない「内陸国」であると同時に、その隣国もすべて内陸国であるという、世界に二つしかない「二重内陸国(Double Landlocked Country)」です。この地理的制約は、日本企業に対して、法務上も実務上も影響を及ぼします。
日本の商社やメーカーにとっての「物流法務」が、通常は海事法や海上保険を中心とするのに対し、ウズベキスタンにおける物流法務は、もっぱら「通関法(Customs Law)」と「陸上輸送法(Transit Law)」となります。この地理的制約は、極めて高い輸送コストと、不安定なリードタイムをもたらします。
実務上の最大のリスクは、法規制そのものよりも、その運用の不統一性にあると指摘されています。調査によれば、「税関法規の解釈が、国境の税関ポストごとに異なる」ことが常態化しており、担当官によって異なる判断が下されるケースが報告されています。このため、貿易業者は「まず(税関の要求通りに)支払い、後で裁判所に(その決定の)訴訟を起こす」という対応を迫られることがあるとされます。
政府もこの問題を深く認識しており、「陸路(TIR)輸送のデジタル化」や、アフガニスタンを経由してパキスタンの港(アラビア海)に至る新鉄道回廊の建設など、「二重内陸国」から「陸路で繋がる国(Land-linked)」への転換を国家戦略として模索しています。
まとめ
ウズベキスタンは、6%を超える高い経済成長と、WTO加盟を目指す強力な法制度の近代化が両立するダイナミックな市場です。しかし、日本法の常識で事業を進めることには重大なリスクが伴います。特に、以下の分野は日本法と根本的に異なる規制や実務上の課題が存在するため、進出前に綿密な法務分析が不可欠です。
- 労働法:2023年新労働法の下、解雇事由と手続き、退職金が法典で厳格に定められており、日本のような柔軟な雇用調整は極めて困難です。
- 個人情報保護法:「個人データ法」(ZRU-547)は、ウズベク国民の個人データを国内サーバーに物理的に保管することを義務付けており、グローバルなクラウド・SaaS戦略の根本的な見直しを迫ります。
- 不動産法:土地が原則非私有であることに加え、外国人が個人で不動産(住宅)を所有するには「3年以上の居住実績」が必要とされるなど、厳格な制限が存在します。
- 広告規制:「広告法」(ZRU-776)は、ウズベク語を優先する言語規制など、独自の規制を設けています。
ウズベキスタンの法制度は、現時点において発展途上かつ急速な変動の最中にあります。新法(2023年競争法、2024年AI戦略など)が次々と導入されており、公式の法令データベース(lex.uzなど)で最新の情報を常に追跡することが重要です。
ウズベキスタンを含む新興国特有の法務リスクの分析、日本法との比較を踏まえた契約書の作成や現地法規制への対応、コンプライアンス体制の構築など、企業の国際展開における複雑な法的課題について、モノリス法律事務所は幅広くサポートいたします。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務
タグ: ウズベキスタン共和国海外事業