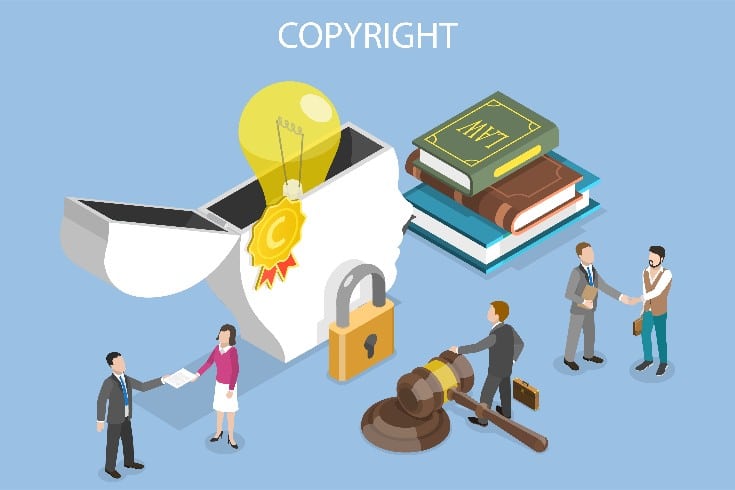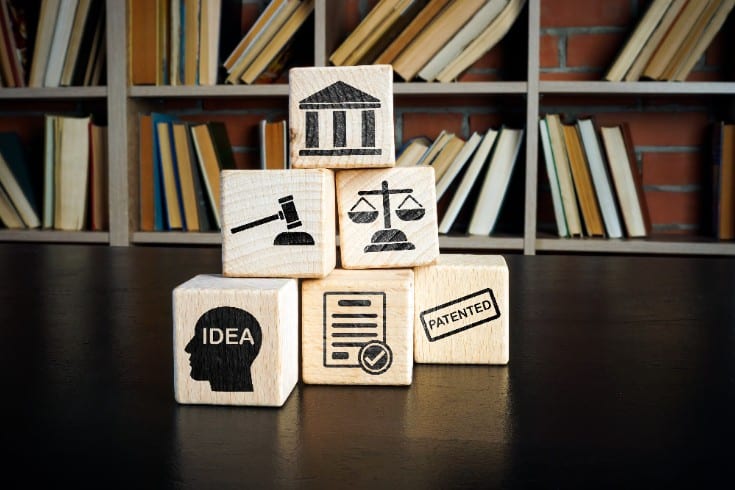ńäĪµ¢ŁµŖĢń©┐ŃüĢŃéīŃü¤ńö╗ÕāÅŃéÆŃā¬ŃāØŃé╣Ńāł’╝łŃā¬ŃāäŃéżŃā╝Ńāł’╝ēŃüÖŃéŗĶĪīńé║Ńü»ĶæŚõĮ£µ©®õŠĄÕ«│Ńü½Ńü¬ŃéŗŃü«Ńüŗ’╝¤

SNSŃü»ŃĆüÕĆŗõ║║Ńü«Ńü┐Ńü¬ŃéēŃüÜõ╝üµźŁŃü½Ńü©ŃüŻŃü”ŃééµāģÕĀ▒ńÖ║õ┐ĪŃü«ķćŹĶ”üŃü¬ŃāäŃā╝Ńā½Ńü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéķŁģÕŖøńÜäŃü¬ńö╗ÕāÅŃéƵ┤╗ńö©ŃüŚŃü¤µāģÕĀ▒ńÖ║õ┐ĪŃü»Õ║āÕĀ▒ŃéäĶ▓®õ┐āµ┤╗ÕŗĢŃü½ÕŖ╣µ×£ńÜäŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃüØŃü«ńö╗ÕāÅŃüīń¼¼õĖēĶĆģŃü«ĶæŚõĮ£ńē®ŃéÆńäĪµ¢ŁŃü¦Õł®ńö©ŃüŚŃü¤ŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃüŻŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüµäÅÕø│ŃüøŃüÜĶæŚõĮ£µ©®õŠĄÕ«│Ńü«Ńā¬Ńé╣Ńé»ŃéÆĶ▓ĀŃüåÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéńē╣Ńü½ŃĆüÕŠōµźŁÕōĪŃü½ŃéłŃéŗÕ«ēµśōŃü¬Ńā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃéäŃéĘŃé¦ŃéóŃüīŃĆüõ╝üµźŁÕģ©õĮōŃü«õ┐ĪķĀ╝ŃéÆµÉŹŃü¬Ńüåõ║ŗµģŗŃü½ńÖ║Õ▒ĢŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃééĶĆāŃüłŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
µ£¼Ķ©śõ║ŗŃü¦Ńü»ŃĆüŃĆīńäĪµ¢ŁµŖĢń©┐ŃüĢŃéīŃü¤ńö╗ÕāÅŃéƵŗĪµĢŻŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüõ╝üµźŁŃü©ŃüŚŃü”ĶæŚõĮ£µ©®õŠĄÕ«│Ńü½ÕĢÅŃéÅŃéīŃéŗŃü«Ńüŗ’╝¤ŃĆŹŃü©ŃüäŃüåķćŹĶ”üŃü¬ń¢æÕĢÅŃü½Õ»ŠŃüŚŃĆüÕ«¤ķÜøŃü«õ║ŗõŠŗŃü©ŃüØŃü«ĶŻüÕłżõŠŗŃéÆõ║żŃüłŃü¬ŃüīŃéēĶ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«Ķ©śõ║ŗŃü«ńø«µ¼Ī
SNSŃü½ŃüŖŃüæŃéŗµŗĪµĢŻŃü©ĶæŚõĮ£µ©®Ńü©Ńü«ķ¢óõ┐é
SNSŃü»ŃĆüµāģÕĀ▒Ńüīń×¼ŃüÅķ¢ōŃü½Õ║āŃüīŃéŗńÅŠõ╗ŻŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüÕĆŗõ║║Ńā╗õ╝üµźŁŃéÆÕĢÅŃéÅŃüÜķćŹĶ”üŃü¬Ńé│Ńā¤ŃāźŃāŗŃé▒Ńā╝ŃéĘŃā¦Ńā│ŃāäŃā╝Ńā½Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüŃüØŃü«µŗĪµĢŻµĆ¦Ńü«ķ½śŃüĢŃéåŃüłŃü½ŃĆüĶæŚõĮ£µ©®Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗÕĢÅķĪīŃééńö¤ŃüśŃéäŃüÖŃüÅŃü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéńē╣Ńü½ŃĆüńö╗ÕāÅŃéäÕŗĢńö╗Ńü¬Ńü®Ńü«ĶæŚõĮ£ńē®Ńü»ŃĆüÕ«╣µśōŃü½Ńé│ŃāöŃā╝ŃéäĶ╗óĶ╝ēŃüīĶĪīŃéÅŃéīŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüµ©®Õł®ĶĆģŃü«µäÅÕø│ŃüŚŃü¬ŃüäÕĮóŃü¦Õ║āŃüŠŃüŻŃü”ŃüŚŃüŠŃüåŃé▒Ńā╝Ńé╣ŃüīÕŠīŃéÆńĄČŃüĪŃüŠŃüøŃéōŃĆé
ĶæŚõĮ£µ©®µ│ĢŃü»ŃĆüĶæŚõĮ£ńē®ŃéÆÕēĄõĮ£ŃüŚŃü¤ĶæŚõĮ£ĶĆģŃü½ŃüĢŃüŠŃü¢ŃüŠŃü¬µ©®Õł®ŃéÆĶ¬ŹŃéüŃĆüŃüØŃü«µ©®Õł®ŃéÆõŠĄÕ«│ŃüÖŃéŗĶĪīńé║ŃéÆń”üŃüśŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃüōŃü¦ķćŹĶ”üŃü¬Ńü«Ńü»ŃĆüĶæŚõĮ£µ©®õŠĄÕ«│Ńü»µĢģµäÅŃü½ĶĪīŃüŻŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü½ķÖÉŃéēŃüÜŃĆüķüÄÕż▒Ńéäń¤źŃéēŃü¬ŃüŗŃüŻŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü¦Ńé鵳Éń½ŗŃüÖŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŗŃü©ŃüäŃüåŃüōŃü©Ńü¦ŃüÖŃĆé
SNSŃü½ŃüŖŃüæŃéŗŃĆīµŗĪµĢŻŃĆŹŃü©ŃüäŃüåĶĪīńé║Ńü»ŃĆüÕģĘõĮōńÜäŃü½Ńü®Ńü«ŃéłŃüåŃü¬µ│ĢńÜäÕü┤ķØóŃéƵīüŃüżŃü«Ńü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆéõ╗ŻĶĪ©ńÜäŃü¬ŃééŃü«Ńü©ŃüŚŃü”ŃĆüŃĆīĶżćĶŻĮµ©®ŃĆŹŃü©ŃĆīÕģ¼ĶĪåķĆüõ┐Īµ©®ŃĆŹŃüīµīÖŃüÆŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ĶżćĶŻĮµ©®Ńü©Ńü»ŃĆüĶæŚõĮ£ńē®ŃéÆŃé│ŃāöŃā╝ŃüŚŃü¤ŃéŖŃĆüŃāŚŃā¬Ńā│ŃāłŃéóŃé”ŃāłŃüŚŃü¤ŃéŖŃüÖŃéŗµ©®Õł®Ńü¦ŃüÖŃĆéŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃéäŃéĘŃé¦ŃéóŃü«µ®¤ĶāĮŃéÆÕł®ńö©ŃüŚŃü”ńö╗ÕāÅŃéÆĶć¬ÕłåŃü«ŃéóŃé½Ńé”Ńā│ŃāłŃü½ĶĪ©ńż║ŃüĢŃüøŃéŗĶĪīńé║Ńü»ŃĆüµāģÕĀ▒Õć”ńÉåń½»µ£½Ńü«ńö╗ķØóõĖŖŃü½ĶĪ©ńż║ŃüĢŃüøŃéŗŃü¤ŃéüŃü½ŃĆüõĖƵÖéńÜäŃü½ŃéŁŃāŻŃāāŃéĘŃāźŃāćŃā╝Ńé┐Ńü©ŃüŚŃü”ĶżćĶŻĮŃüĢŃéīŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüŃüōŃü«ĶżćĶŻĮµ©®Ńü½µŖĄĶ¦”ŃüÖŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃĆé
Õģ¼ĶĪåķĆüõ┐Īµ©®Ńü»ŃĆüĶæŚõĮ£ńē®ŃéÆŃéżŃā│Ńé┐Ńā╝ŃāŹŃāāŃāłŃü¬Ńü®Ńü«ķĆÜõ┐ĪÕø×ńĘÜŃéÆķĆÜŃüśŃü”Õģ¼ĶĪåŃü½ķĆüõ┐ĪŃüŚŃü¤ŃéŖŃĆüÕÅŚõ┐ĪŃü¦ŃüŹŃéŗŃéłŃüåŃü½ŃüŚŃü¤ŃéŖŃüÖŃéŗµ©®Õł®Ńü¦ŃüÖŃĆéŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃéäŃéĘŃé¦ŃéóŃü½ŃéłŃüŻŃü”ŃĆüĶć¬ÕłåŃü«ŃāĢŃé®ŃāŁŃā»Ńā╝Ńü¬Ńü®õĖŹńē╣Õ«ÜÕżÜµĢ░Ńü«õ║║Ńüīńö╗ÕāÅŃéÆĶ”ŗŃéēŃéīŃéŗńŖȵģŗŃü½ŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü»ŃĆüŃüōŃü«Õģ¼ĶĪåķĆüõ┐Īµ©®Ńü½ķ¢óŃéÅŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ķ¢óķĆŻĶ©śõ║ŗ’╝ܵē┐Ķ½ŠŃü¬ŃüŚŃü¦Ńü«ÕåÖń£¤ńŁēŃü«Õģ¼ĶĪ©Ńü©ĶæŚõĮ£µ©®Ńü«ķ¢óõ┐é
Twitter’╝łńÅŠX’╝ēŃü«ŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃü©ŃüØŃü«Ńā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃü«õ║ŗµĪł

ŃāŹŃāāŃāłŃéäSNSõĖŖŃü¦ŃĆüĶæŚõĮ£ńē®ŃéÆńäĪµ¢ŁŃü¦ŃéóŃāāŃāŚŃāŁŃā╝ŃāēŃüÖŃéŗĶĪīńé║Ńü»ĶæŚõĮ£µ©®µ│ĢŃü½ķüĢÕÅŹŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃü¦Ńü»ŃĆüńäĪµ¢ŁŃü¦ŃéóŃāāŃāŚŃāŁŃā╝ŃāēŃüĢŃéīŃü¤ńö╗ÕāÅõ╗śŃüŹŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃéÆŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃüÖŃéŗĶĪīńé║Ńü»Ńü®ŃüåŃü¬ŃéŗŃü«Ńü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆé
Twitter’╝łńÅŠX’╝ēŃü«õ╗Ģµ¦śŃü½ÕŠōŃüŻŃü”õ╗¢ĶĆģŃü«ńö╗ÕāÅõ╗śŃüŹŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃéÆŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃüŚŃü¤Ńü©ŃüŹŃü½ŃééŃĆüĶæŚõĮ£µ©®ŃéÆõŠĄÕ«│ŃüÖŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŗŃü©ŃüäŃüåÕłżµ¢ŁŃéÆŃĆüµ£Ćķ½śĶŻüÕłżµēĆŃüīõĖŗŃüŚŃü”ŃüäŃéŗĶŻüÕłżõŠŗŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
µ£¼õ║ŗµĪłŃü¦ÕĤÕæŖŃü©Ńü¬ŃüŻŃü¤Ńü«Ńü»ĶüʵźŁÕåÖń£¤Õ«ČŃü¦ŃüÖŃĆéÕĤÕæŖŃü»Ńé╣Ńé║Ńā®Ńā│Ńü«ÕåÖń£¤Ńü«ķÜģŃü½ŃĆīŌÆĖ’╝łĶæŚõĮ£ĶĆģÕÉŹ’╝ēŃĆŹńŁēŃü«µ¢ćÕŁŚŃéÆÕŖĀŃüłŃĆüŃüōŃü«ńö╗ÕāÅŃéÆĶć¬ÕĘ▒Ńü«ķüŗÕ¢ČŃüÖŃéŗŃé”Ńé¦Ńā¢ŃéĄŃéżŃāłŃü½µÄ▓Ķ╝ēŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«Ńé╣Ńé║Ńā®Ńā│Ńü«ÕåÖń£¤ŃéÆķüĢµ│ĢŃü½ŃéóŃāāŃāŚŃāŁŃā╝ŃāēŃüĢŃéīŃü¤Ńü©ŃüŚŃü”ŃĆüÕĮōµÖéŃü«TwitterŃéÆķüŗÕ¢ČŃüÖŃéŗTwitterńżŠ’╝łµŚźµ£¼µö»ńżŠŃü¦ŃüéŃéŗTwitter JapanµĀ¬Õ╝Åõ╝ÜńżŠŃü©µ£¼ńżŠŃü¦ŃüéŃéŗŃāäŃéżŃāāŃé┐Ńā╝Ńā╗ŃéżŃā│Ńé»’╝ēŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”ńÖ║õ┐ĪĶĆģµāģÕĀ▒ķ¢ŗńż║Ķ½ŗµ▒éŃéÆĶĪīŃüäŃüŠŃüŚŃü¤’╝łõ╗źõĖŗŃĆüńżŠÕÉŹńŁēŃü»ÕĮōµÖéŃü«ŃééŃü«ŃéÆĶ©śĶ╝ēŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖ’╝ēŃĆé
µ░ÅÕÉŹõĖŹĶ®│ĶĆģAŃü»ŃĆüÕĤÕæŖŃü½ńäĪµ¢ŁŃü¦Ķć¬ÕłåŃü«ŃāŚŃāŁŃāĢŃéŻŃā╝Ńā½ńö╗ÕāÅŃü©ŃüŚŃü”µ£¼õ╗ČÕåÖń£¤Ńü«ńö╗ÕāÅŃāĢŃéĪŃéżŃā½ŃéÆŃéóŃāāŃāŚŃāŁŃā╝ŃāēŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃéīŃü½ŃéłŃüŻŃü”TwitterŃü«ŃāŚŃāŁŃāĢŃéŻŃā╝Ńā½ńö╗ÕāÅŃāĢŃéĪŃéżŃā½õ┐ØÕŁśURLõĖŖŃü½ÕÉīńö╗ÕāÅŃāĢŃéĪŃéżŃā½ŃüīĶć¬ÕŗĢńÜäŃü½õ┐ØÕŁśŃā╗ĶĪ©ńż║ŃüĢŃéīŃĆüAŃü«Ńé┐ŃéżŃāĀŃā®ŃéżŃā│Ńü½µ£¼õ╗ČÕåÖń£¤ŃüīĶĪ©ńż║ŃüĢŃéīŃéŗŃéłŃüåŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
µ░ÅÕÉŹõĖŹĶ®│ĶĆģBŃü»ŃĆüĶć¬ÕĘ▒Ńü«ŃéóŃé½Ńé”Ńā│ŃāłŃü¦ŃĆüÕĤÕæŖŃü½ńäĪµ¢ŁŃü¦µ£¼õ╗ČÕåÖń£¤Ńü«ńö╗ÕāÅŃāĢŃéĪŃéżŃā½ŃéÆÕɽŃéĆŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃéÆĶĪīŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖTwitterŃü«ŃāäŃéżŃā╝Ńāłńö╗ÕāÅŃāĢŃéĪŃéżŃā½õ┐ØÕŁśURLŃü½µ£¼õ╗ČÕåÖń£¤Ńü«ńö╗ÕāÅŃāĢŃéĪŃéżŃā½ŃüīĶć¬ÕŗĢńÜäŃü½õ┐ØÕŁśŃā╗ĶĪ©ńż║ŃüĢŃéīŃĆüµ£¼õ╗ČŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃéÆĶĪ©ńż║ŃüÖŃéŗURLÕÅŖŃü│BŃü«ŃéóŃé½Ńé”Ńā│ŃāłŃü«Ńé┐ŃéżŃāĀŃā®ŃéżŃā│Ńü½µ£¼õ╗ČÕåÖń£¤ŃüīĶĪ©ńż║ŃüĢŃéīŃéŗŃéłŃüåŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
µ░ÅÕÉŹõĖŹĶ®│ĶĆģCDEŃü»ŃüØŃéīŃü×ŃéīŃĆüBŃü«ŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃü«Ńā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃéÆŃüŚŃü¤ŃüōŃü©Ńü¦ŃĆüCDEŃü«ÕÉäŃé┐ŃéżŃāĀŃā®ŃéżŃā│Ńü½µ£¼õ╗ČÕåÖń£¤ŃüīĶĪ©ńż║ŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ÕĤÕæŖŃü»ŃĆüŃéóŃé½Ńé”Ńā│ŃāłAÕÅŖŃü│BŃü½ŃüżŃüŹŃĆüµ£¼õ╗ČÕåÖń£¤Ńü«ĶĪ©ńż║Ńü½ŃéłŃéŖÕģ¼ĶĪåķĆüõ┐Īµ©®’╝łĶæŚõĮ£µ©®µ│Ģń¼¼23µØĪń¼¼1ķĀģ’╝ēŃüīõŠĄÕ«│ŃüĢŃéīŃü¤Ńü©õĖ╗Õ╝ĄŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃāŚŃāŁŃāĢŃéŻŃā╝Ńā½ńö╗ÕāÅŃü½Ķ©ŁÕ«ÜŃüÖŃéŗĶĪīńé║ŃĆüńäĪµ¢ŁŃü¦ńö╗ÕāÅŃüØŃü«ŃééŃü«Ńü«ŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃüÖŃéŗĶĪīńé║ŃüīÕģ¼ĶĪåķĆüõ┐Īµ©®õŠĄÕ«│Ńü©Ńü¬ŃéŗŃüōŃü©Ńü»ŃāäŃéżŃāāŃé┐Ńā╝ńżŠÕü┤Ńééõ║ēŃüäŃüŠŃüøŃéōŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéµ£¼õ╗ČŃü¦õ║ēńé╣Ńü©Ńü¬ŃüŻŃü¤Ńü«Ńü»ŃĆüCDEŃü½ŃéłŃéŗŃĆüŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłĶĪīńé║Ńü¦ŃüÖŃĆéŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃü½ŃéłŃüŻŃü”ŃĆüµ£¼õ╗ČÕåÖń£¤ŃüīĶĪ©ńż║ŃüĢŃéīŃĆüÕĤÕæŖŃü«ĶæŚõĮ£µ©®ńŁēŃüīõŠĄÕ«│ŃüĢŃéīŃü¤ŃüŗÕÉ”ŃüŗŃüīõ║ēŃéÅŃéīŃéŗŃüōŃü©Ńü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ķ¢óķĆŻĶ©śõ║ŗ’╝ÜÕåÖń£¤µŖĢń©┐Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗĶæŚõĮ£ńē®µĆ¦Ńü©ĶæŚõĮ£ĶĆģ
ÕĤÕæŖŃü©Ķó½ÕæŖŃü«õĖ╗Õ╝Ą
ÕĤÕæŖŃü»
- Õģ¼ĶĪåķĆüõ┐Īµ©®
- ÕÉīõĖƵƦõ┐صīüµ©®
- µ░ÅÕÉŹĶĪ©ńż║µ©®
- ÕÉŹĶ¬ēÕŻ░µ£øõ┐صīüµ©®
Ńü«õŠĄÕ«│ŃéÆõĖ╗Õ╝ĄŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüØŃéīŃü×ŃéīÕĆŗÕłźŃü½Ķ”ŗŃü”ŃüäŃüŹŃüŠŃüŚŃéćŃüåŃĆé
ÕĤÕæŖŃü»ŃĆüńö╗ÕāÅõ╗śŃüŹŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃéƵŖĢń©┐ŃüŚŃü¤ĶĆģŃüĀŃüæŃü¬ŃüÅŃĆüŃüØŃü«ŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃéÆŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃüŚŃü¤ĶĆģŃü½ŃüżŃüäŃü”ŃééŃĆüŃĆīŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃü½ŃéłŃéŖńäĪµ¢ŁĶ╗óĶ╝ēŃü«ńö╗ÕāÅõ╗śŃüŹŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃéÆŃé┐ŃéżŃāĀŃā®ŃéżŃā│Ńü½ĶĪ©ńż║ŃüÖŃéŗĶĪīńé║ŃüīÕģ¼ĶĪåķĆüõ┐Īµ©®Ńü¬Ńü®ŃéÆõŠĄÕ«│ŃĆŹŃüÖŃéŗĶæŚõĮ£µ©®õŠĄÕ«│Ńü½ŃüéŃü¤ŃéŗŃĆüŃü©õĖ╗Õ╝ĄŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüĢŃéēŃü½ŃĆüÕĤÕæŖŃü»ŃĆüTwitterŃü«õ╗Ģµ¦śõĖŖŃĆüńö╗ÕāÅõ╗śŃüŹŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃéÆŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃü½ŃéłŃéŖŃé┐ŃéżŃāĀŃā®ŃéżŃā│Ńü½ĶĪ©ńż║ŃüÖŃéŗķÜøŃü½Ńü»Ķć¬ÕŗĢŃü¦ŃāłŃā¬Ńā¤Ńā│Ńé░ŃüīĶĪīŃéÅŃéīŃéŗ’╝łŃüäŃéÅŃéåŃéŗŃĆīŃéżŃā│Ńā®ŃéżŃā│Ńā¬Ńā│Ńé»ŃĆŹ’╝ēŃü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃüōŃü«ŃāłŃā¬Ńā¤Ńā│Ńé░ĶĪīńé║ŃüīÕÉīõĖƵƦõ┐صīüµ©®’╝łĶæŚõĮ£µ©®µ│Ģń¼¼20µØĪń¼¼1ķĀģ’╝ēŃéÆõŠĄÕ«│ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃü©õĖ╗Õ╝ĄŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃü¬ŃüŖŃĆüÕÉīõĖƵƦõ┐صīüµ©®Ńü©Ńü»Ķć¬ÕłåŃü«ĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ÕåģÕ«╣ÕÅłŃü»ķĪīÕÅĘŃéÆĶć¬ÕłåŃü«µäÅŃü½ÕÅŹŃüŚŃü”ÕŗصēŗŃü½µö╣ÕżēŃüĢŃéīŃü¬Ńü䵩®Õł®Ńü«ŃüōŃü©ŃéƵīćŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüĢŃéēŃü½ŃāłŃā¬Ńā¤Ńā│Ńé░Ńü½ŃéłŃüŻŃü”ŃĆüĶć¬ÕĘ▒Ńü«µ░ÅÕÉŹŃüīŃéÅŃüŗŃéēŃü¬ŃüÅŃü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗŃüōŃü©ŃüŗŃéēµ░ÅÕÉŹĶĪ©ńż║µ©®Ńü«õŠĄÕ«│ŃééõĖ╗Õ╝ĄŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüŠŃü¤ŃĆüÕĤÕæŖŃü»ŃĆüŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłĶĪīńé║Ńü½ŃéłŃüŻŃü”ŃĆüķ¢▓Ķ”¦ĶĆģŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”ÕĤÕæŖŃü«ÕåÖń£¤ŃüīŃĆīńäĪµ¢ŁÕł®ńö©ŃüŚŃü”Ńé鵦ŗŃéÅŃü¬ŃüäõŠĪÕĆżŃü«õĮÄŃüäĶæŚõĮ£ńē®ŃĆŹŃü¦ŃüéŃéŗŃüŗŃü«ŃéłŃüåŃü¬Ķ¬żŃüŻŃü¤ÕŹ░Ķ▒ĪŃéÆõĖÄŃüłŃü”ŃüäŃéŗŃüōŃü©ŃüīÕÉŹĶ¬ēÕŻ░µ£øõ┐صīüµ©®’╝łĶæŚõĮ£µ©®µ│Ģń¼¼113µØĪń¼¼6ķĀģ’╝ēŃéÆõŠĄÕ«│ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃĆüŃü©ŃééõĖ╗Õ╝ĄŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüōŃéīŃü½Õ»ŠŃüŚŃĆüTwitterńżŠÕü┤Ńü»ŃĆīŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłĶĆģŃü»Ķć¬Ńéēńö╗ÕāÅ’╝łÕåÖń£¤’╝ēŃāćŃā╝Ńé┐ŃéÆķĆüõ┐ĪŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃéÅŃüæŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüÕåÖń£¤Ńü©Ńü»ńäĪķ¢óõ┐éŃü«ŃāćŃā╝Ńé┐ŃéÆķĆüõ┐ĪŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃü½ķüÄŃüÄŃü¬ŃüäŃü«Ńü¦ŃĆüÕģ¼ĶĪåķĆüõ┐Īµ©®Ńü«õŠĄÕ«│Ńü½Ńü»Ķ®▓ÕĮōŃüŚŃü¬ŃüäŃĆŹŃü©õĖ╗Õ╝ĄŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüŠŃü¤ŃĆüĶć¬ÕŗĢŃü¦ŃāłŃā¬Ńā¤Ńā│Ńé░ŃüīĶĪīŃéÅŃéīŃéŗŃüōŃü©ŃüīĶæŚõĮ£ĶĆģõ║║µĀ╝µ©®Ńü«õŠĄÕ«│Ńü½ŃüéŃü¤ŃéŗŃĆüŃü©ŃüäŃüåÕĤÕæŖŃü«õĖ╗Õ╝ĄŃü½ŃüżŃüäŃü”ŃééŃĆüõĖŗĶ©śŃü«ŃéłŃüåŃü½ÕÅŹĶ½¢ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
- TwitterŃü«õ╗Ģµ¦śõĖŖŃĆüŃāłŃā¬Ńā¤Ńā│Ńé░ĶĪīńé║Ńü»ŃĆüķ¢▓Ķ”¦ĶĆģŃü¦ŃüéŃéŗŃéżŃā│Ńé┐Ńā╝ŃāŹŃāāŃāłŃā”Ńā╝ŃéČŃā╝Ńü«Ńé│Ńā│ŃāöŃāźŃā╝Ńé┐õĖŖŃü¦ĶĪīŃéÅŃéīŃéŗŃü«Ńü¦ŃĆüŃāłŃā¬Ńā¤Ńā│Ńé░ĶĪīńé║Ńü«ĶĪīńé║õĖ╗õĮōŃü»Ńā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłĶĆģŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃéżŃā│Ńé┐Ńā╝ŃāŹŃāāŃāłŃā”Ńā╝ŃéČŃā╝Ńü©Ńü¬ŃéŖŃĆüŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłĶĆģŃü½ÕÉīõĖƵƦõ┐صīüµ©®ŃüŖŃéłŃü│µ░ÅÕÉŹĶĪ©ńż║µ©®Ńü«õŠĄÕ«│Ńü»µłÉń½ŗŃüŚŃü¬ŃüäŃĆé
- ŃāłŃā¬Ńā¤Ńā│Ńé░Ńü»ŃĆüTwitterŃü«ŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀõĖŖŃĆüĶżćµĢ░Ńü«ÕåÖń£¤ŃéÆķÖÉŃéēŃéīŃü¤ńö╗ķØóÕåģŃü½ńäĪńÉåŃü¬ŃüÅĶć¬ńäČŃü½ĶĪ©ńż║ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü½Ķć¬ÕŗĢńÜäŃüŗŃüżµ®¤µó░ńÜäŃü½ĶĪīŃéÅŃéīŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃéŗŃü«Ńü¦ŃĆüŃĆīŃéäŃéĆŃéÆÕŠŚŃü¬ŃüäŃĆŹ’╝łĶæŚõĮ£µ©®ń¼¼20µØĪń¼¼2ķĀģń¼¼4ÕÅĘ’╝ēµö╣ÕżēŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüÕÉīõĖƵƦõ┐صīüµ©®Ńü«õŠĄÕ«│Ńü»µłÉń½ŗŃüŚŃü¬ŃüäŃĆé
- µŖĢń©┐Ńü«Ńā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃü½ŃéłŃéŖŃĆüÕĤÕæŖŃü«Õ«óĶ”│ńÜäŃü¬ÕÉŹĶ¬ēŃĆüÕŻ░µ£øŃüīõĮÄõĖŗŃüÖŃéŗŃééŃü«Ńü©Ńü»ĶĆāŃüłŃéēŃéīŃü¬ŃüäŃü«Ńü¦ŃĆüÕÉŹĶ¬ēÕŻ░µ£øõ┐صīüµ©®Ńü»µłÉń½ŗŃüŚŃü¬ŃüäŃĆé
ķ¢óķĆŻĶ©śõ║ŗ’╝ÜĶæŚõĮ£ĶĆģõ║║µĀ╝µ©®Ńü©ÕÉŹĶ¬ēÕÅłŃü»ÕŻ░µ£øŃü«õ┐ØĶŁĘŃü©Ńü»’╝¤
µØ▒õ║¼Õ£░µ¢╣ĶŻüÕłżµēĆŃü«Õłżµ¢Ł’╝ÜÕĤÕæŖŃü«Ķ½ŗµ▒éŃéÆĶ¬ŹŃéüŃüÜ
1Õ»®Ńü«µØ▒õ║¼Õ£░µ¢╣ĶŻüÕłżµēĆŃü»ŃĆüCDEŃü«ĶĪīŃüŻŃü¤Ńā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«ŃéłŃüåŃü½Ķ®ĢõŠĪŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤
- Ńā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłĶĪīńé║Ńü½ŃéłŃéŖÕÉīŃé┐ŃéżŃāĀŃā®ŃéżŃā│Ńü«URLŃü½Ńā¬Ńā│Ńé»ÕģłŃü¦ŃüéŃéŗURLŃüĖŃü«ŃéżŃā│Ńā®ŃéżŃā│Ńā¬Ńā│Ńé»ŃüīĶć¬ÕŗĢńÜäŃü½Ķ©ŁÕ«ÜŃüĢŃéīŃĆüÕÉīURLŃüŗŃéēŃā”Ńā╝ŃéČŃā╝Ńü«ŃāæŃéĮŃé│Ńā│ńŁēŃü«ń½»µ£½Ńü½ńø┤µÄźńö╗ÕāÅŃāĢŃéĪŃéżŃā½Ńü«ŃāćŃā╝Ńé┐ŃüīķĆüõ┐ĪŃüĢŃéīŃéŗ
- ÕÉäURLŃü½µĄüķĆܵāģÕĀ▒Ńü«ŃāćŃā╝Ńé┐Ńü»õĖĆÕłćķĆüõ┐ĪŃüĢŃéīŃüÜŃĆüÕÉīURLŃüŗŃéēŃā”Ńā╝ŃéČŃā╝Ńü«ń½»µ£½ŃüĖŃü«ÕÉīŃāćŃā╝Ńé┐Ńü«ķĆüõ┐ĪŃééĶĪīŃéÅŃéīŃü¬ŃüäŃüŗŃéēŃĆüµ£¼õ╗ČŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłĶĪīńé║Ńü»ŃüØŃéīĶć¬õĮōŃü©ŃüŚŃü”õĖŖĶ©śŃāćŃā╝Ńé┐ŃéÆķĆüõ┐ĪŃüŚŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»ŃüōŃéīŃéÆķĆüõ┐ĪÕÅ»ĶāĮÕī¢ŃüÖŃéŗŃééŃü«Ńü¦Ńü¬Ńüä
õ╗źõĖŖŃü«ńé╣ŃüŗŃéēŃĆüÕģ¼ĶĪåķĆüõ┐ĪŃü½Ńü»ÕĮōŃü¤ŃéēŃü¬ŃüäŃü©Õłżµ¢ŁŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüÕÉīŃüśŃüÅŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃü«õ╗ĢńĄäŃü┐õĖŖŃĆüńö╗ÕāÅŃāĢŃéĪŃéżŃā½Ńü«µö╣ÕżēŃééĶĪīŃéÅŃéīŃü¬ŃüäŃüŗŃéēÕÉīõĖƵƦõ┐صīüµ©®õŠĄÕ«│Ńü»µłÉń½ŗŃüŚŃü¬ŃüäŃüŚŃĆüµ£¼õ╗ČŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłĶĆģŃéēŃüŗŃéēÕģ¼ĶĪåŃüĖŃü«µ£¼õ╗ČÕåÖń£¤Ńü«µÅÉõŠøÕÅłŃü»µÅÉńż║ŃüīŃüéŃéŗŃü©Ńü»ŃüäŃüłŃü¬ŃüäŃüŗŃéēµ░ÅÕÉŹĶĪ©ńż║µ©®õŠĄÕ«│Ńé鵳Éń½ŗŃüŚŃü¬ŃüäŃü©ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüØŃüŚŃü”ŃĆüÕĤÕæŖŃü»µ£¼õ╗ČŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłĶĪīńé║Ńü½ŃéłŃéŗµĄüķĆܵāģÕĀ▒Ńü«URLŃüŗŃéēŃé»Ńā®ŃéżŃéóŃā│ŃāłŃé│Ńā│ŃāöŃāźŃā╝Ńé┐Ńā╝ŃüĖŃü«µ£¼õ╗ČÕåÖń£¤Ńü«ńö╗ÕāÅŃāĢŃéĪŃéżŃā½Ńü«ķĆüõ┐ĪŃü»Ķć¬ÕŗĢÕģ¼ĶĪåķĆüõ┐ĪŃü½ÕĮōŃü¤ŃéŖŃĆüµ£¼õ╗ČŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłĶĆģŃéēŃéÆŃüØŃü«õĖ╗õĮōŃü©Ńü┐ŃéŗŃü╣ŃüŹŃüĀŃüŗŃéēŃĆüµ£¼õ╗ČŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłĶĪīńé║Ńü»Õģ¼ĶĪåķĆüõ┐Īµ©®õŠĄÕ«│Ńü©Ńü¬ŃéŗŃü©õĖ╗Õ╝ĄŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüµ£¼õ╗ČÕåÖń£¤Ńü«ńö╗ÕāÅŃāĢŃéĪŃéżŃā½ŃéÆTwitterŃü«ŃéĄŃā╝ŃāÉŃā╝Ńü½ŃéóŃāāŃāŚŃāŁŃā╝ŃāēŃüŚŃĆüŃüōŃéīŃéÆÕģ¼ĶĪåķĆüõ┐ĪŃüŚÕŠŚŃéŗńŖȵģŗŃéÆõĮ£Õć║ŃüŚŃü¤Ńü«Ńü»BŃü¦ŃüéŃéŗŃüŗŃéēŃĆüõĖŖĶ©śķĆüõ┐ĪŃü«õĖ╗õĮōŃü»ÕÉīõ║║Ńü¦ŃüéŃéŗŃü©Ńü┐ŃéŗŃü╣ŃüŹŃüĀŃü©ŃüŚŃü”ŃĆüA,BŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ńÖ║õ┐ĪĶĆģµāģÕĀ▒Ńü«ķ¢ŗńż║ŃéÆÕæĮŃüśŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüCDEŃü½Õ»ŠÕ┐£ŃüÖŃéŗķø╗ÕŁÉŃāĪŃā╝Ńā½ŃéóŃāēŃā¼Ńé╣Ńü«ķ¢ŗńż║Ńü»Ķ¬ŹŃéüŃüŠŃüøŃéōŃü¦ŃüŚŃü¤’╝łµØ▒õ║¼Õ£░µ¢╣ĶŻüÕłżµēĆÕ╣│µłÉ28Õ╣┤9µ£ł15µŚźÕłżµ▒║’╝ēŃĆé
ÕĤÕæŖŃü»ŃĆüŃüōŃéīŃéÆõĖŹµ£ŹŃü©ŃüŚŃü”µÄ¦Ķ©┤ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ń¤źĶ▓Īķ½śńŁēĶŻüÕłżµēĆŃü«Õłżµ¢Ł’╝ÜÕĤÕæŖŃü«Ķ½ŗµ▒éŃéÆõĖĆķā©Ķ¬ŹŃéüŃéŗ

2Õ»®Ńü©Ńü¬ŃüŻŃü¤ń¤źĶ▓Īķ½śńŁēĶŻüÕłżµēĆŃü»CDEŃü½ŃéłŃéŗÕģ¼ĶĪåķĆüõ┐Īµ©®õŠĄÕ«│Ńü½ŃüżŃüŹŃĆüĶć¬ÕŗĢÕģ¼ĶĪåķĆüõ┐ĪŃü«õĖ╗õĮōŃüīµ£¼õ╗ČŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłĶĆģŃéēŃü¦ŃüéŃéŗŃü©ŃüäŃüåŃüōŃü©Ńü»Ńü¦ŃüŹŃü¬ŃüäŃüŚŃĆüµ£¼õ╗ČŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłĶĪīńé║ŃüīĶć¬ÕŗĢÕģ¼ĶĪåķĆüõ┐ĪĶĪīńé║Ķć¬õĮōŃéÆÕ«╣µśōŃü½ŃüŚŃü¤Ńü©Ńü»ŃüäŃüäķøŻŃüäŃüŗŃéēŃĆüµ£¼õ╗ČŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłĶĆģŃéēŃéÆÕ╣ćÕŖ®ĶĆģŃü©Ķ¬ŹŃéüŃéŗŃüōŃü©ŃééŃü¦ŃüŹŃü¬ŃüäŃü©ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüŠŃü¤ŃĆüĶæŚõĮ£ńē®Ńü¦ŃüéŃéŗµ£¼õ╗ČÕåÖń£¤Ńü»ŃāćŃā╝Ńé┐Ńü«Ńü┐ŃüīķĆüõ┐ĪŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃüŗŃéēŃĆüŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃü½ŃéłŃéŖĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ŃāćŃā╝Ńé┐ŃüīĶżćĶŻĮŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃü©ŃüäŃüåŃüōŃü©Ńü»Ńü¦ŃüŹŃü¬ŃüäŃü©ŃüŚŃü”ĶżćĶŻĮµ©®õŠĄÕ«│ŃééĶ¬ŹŃéüŃüŠŃüøŃéōŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüÕģ¼ĶĪåõ╝Øķüöµ©®Ńü«õŠĄÕ«│ĶĪīńé║Ķć¬õĮōŃüīĶ¬ŹŃéüŃéēŃéīŃü¬ŃüäŃüŗŃéēŃüØŃü«Õ╣ćÕŖ®ŃüīĶ¬ŹŃéüŃéēŃéīŃéŗõĮÖÕ£░ŃééŃü¬ŃüäŃü©ŃüŚŃü”ŃĆü1Õ»®Ńü©ÕÉīµ¦śŃü«Õłżµ¢ŁŃéÆŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
õĖƵ¢╣ŃĆüĶæŚõĮ£ĶĆģõ║║µĀ╝µ©®Ńü«õŠĄÕ«│Ńü½ŃüżŃüäŃü”µż£Ķ©ÄŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕÉīõĖƵƦõ┐صīüµ©®Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüµ£¼õ╗Čńö╗ÕāÅŃü»ŃĆüµĆصā│ŃüŠŃü¤Ńü»µä¤µāģŃéÆÕēĄõĮ£ńÜäŃü½ĶĪ©ńÅŠŃüŚŃü¤ŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃéŖŃĆüµ¢ćĶŖĖŃĆüÕŁ”ĶĪōŃĆüńŠÄĶĪōÕÅłŃü»ķ¤│µźĮŃü«ń»äÕø▓Ńü½Õ▒×ŃüÖŃéŗŃééŃü«Ńü©ŃüŚŃü”ĶæŚõĮ£µ©®µ│ĢŃü½ŃüäŃüåĶæŚõĮ£ńē®Ńü©ŃüäŃüåŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃéŗŃü©ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüCDEŃü«ŃéóŃé½Ńé”Ńā│ŃāłŃü½ĶĪ©ńż║ŃüÖŃéŗŃü½ķÜøŃüŚŃĆüµ£¼õ╗ČŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłĶĪīńé║Ńü«ńĄÉµ×£Ńü©ŃüŚŃü”õĮŹńĮ«ŃéäÕż¦ŃüŹŃüĢŃü¬Ńü®ŃüīµīćÕ«ÜŃüĢŃéīŃü¤Ńü¤ŃéüŃü½ńĢ░Ńü¬ŃüŻŃü¤ńö╗ÕāÅŃü©Ńü¬ŃüŻŃü¤ŃééŃü«Ńü©Ķ¬ŹŃéüŃéēŃéīŃéŗŃüŗŃéēŃĆüµ£¼õ╗ČŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłĶĆģŃéēŃü½ŃéłŃüŻŃü”µö╣ÕżēŃüĢŃéīŃü¤ŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃéŖŃĆüÕÉīõĖƵƦõ┐صīüµ©®Ńü«õŠĄÕ«│Ńü¦ŃüéŃéŗŃü©Ķ¬ŹŃéüŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüĶĪ©ńż║Ńü½ķÜøŃüŚŃü”ŃĆüĶüʵźŁÕåÖń£¤Õ«ČŃü¦ŃüéŃéŗµÄ¦Ķ©┤õ║║Ńü«µ░ÅÕÉŹŃüīĶĪ©ńż║ŃüĢŃéīŃü¬ŃüÅŃü¬ŃüŻŃü¤ŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃéŗŃüŗŃéēŃĆüµÄ¦Ķ©┤õ║║Ńü»ŃĆüµ£¼õ╗ČŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłĶĆģŃéēŃü½ŃéłŃüŻŃü”ŃĆüµ£¼õ╗ČŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłĶĪīńé║Ńü½ŃéłŃéŖŃĆüĶæŚõĮ£ńē®Ńü«Õģ¼ĶĪåŃüĖŃü«µÅÉõŠøŃüŠŃü¤Ńü»µÅÉńż║Ńü½ķÜøŃüŚŃĆüĶæŚõĮ£ĶĆģÕÉŹŃéÆĶĪ©ńż║ŃüÖŃéŗµ©®Õł®ŃéÆõŠĄÕ«│ŃüĢŃéīŃü¤Ńü©ŃüäŃüåŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃéŗŃü©ŃüŚŃü”ŃĆüµ░ÅÕÉŹĶĪ©ńż║µ©®õŠĄÕ«│ŃééĶ¬ŹŃéüŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüŠŃü¤ń¤źĶ▓Īķ½śńŁēĶŻüÕłżµēĆŃü»ŃĆüĶó½µÄ¦Ķ©┤õ║║ŃéēŃü»ĶæŚõĮ£µ©®µ│Ģ20µØĪ4ķĀģŃü«ŃĆīŃéäŃéĆŃéÆÕŠŚŃü¬ŃüäŃĆŹµö╣ÕżēŃü½ÕĮōŃü¤ŃéŗŃü©õĖ╗Õ╝ĄŃüŚŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüī’╝īµ£¼õ╗ČŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłĶĪīńé║Ńü»µ£¼õ╗ČŃéóŃé½Ńé”Ńā│Ńāł2Ńü½ŃüŖŃüäŃü”µÄ¦Ķ©┤õ║║Ńü½ńäĪµ¢ŁŃü¦µ£¼õ╗ČÕåÖń£¤Ńü«ńö╗ÕāÅŃāĢŃéĪŃéżŃā½ŃéÆÕɽŃéĆŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃüīĶĪīŃéÅŃéīŃü¤ŃééŃü«ŃéÆŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃüŚŃü¤ĶĪīńé║Ńü¬Ńü«Ńü¦ŃüéŃéŗŃüŗŃéēŃĆüŃüØŃü«ŃéłŃüåŃü¬ĶĪīńé║Ńü½õ╝┤Ńüåµö╣ÕżēŃüīŃĆīŃéäŃéĆŃéÆÕŠŚŃü¬ŃüäŃĆŹµö╣ÕżēŃü½ÕĮōŃü¤ŃéŗŃü©Ķ¬ŹŃéüŃéŗŃüōŃü©Ńü»Ńü¦ŃüŹŃü¬ŃüäŃĆüŃü©ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
Ńü¬ŃüŖÕÉŹĶ¬ēÕŻ░µ£øõ┐صīüµ©®Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»õŠĄÕ«│ŃéÆĶ¬ŹŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃüØŃü«ńÉåńö▒Ńü©ŃüŚŃü”ŃĆüŃéĄŃā│Ńā¬Ńé¬ŃéäŃāćŃéŻŃé║ŃāŗŃā╝Ńü«ŃéŁŃāŻŃā®Ńé»Ńé┐Ńā╝Ńü©Ńü©ŃééŃü½µ£¼õ╗ČÕåÖń£¤ŃüīĶĪ©ńż║ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃüŗŃéēŃü©ŃüäŃüŻŃü”ŃĆüŃüØŃü«ŃüōŃü©ŃüŗŃéēńø┤ŃüĪŃü½ŃĆüŃĆīńäĪµ¢ŁÕł®ńö©ŃüŚŃü”ŃééŃüŗŃüŠŃéÅŃü¬ŃüäõŠĪÕĆżŃü«õĮÄŃüäĶæŚõĮ£ńē®ŃĆŹŃĆüŃĆīÕ«ēŃüŻŃüĮŃüäĶæŚõĮ£ńē®ŃĆŹŃü¦ŃüéŃéŗŃüŗŃü«ŃéłŃüåŃü¬Ķ¬żŃüŻŃü¤ÕŹ░Ķ▒ĪŃéÆõĖÄŃüłŃéŗŃü©ŃüäŃüåŃüōŃü©Ńü»Ńü¦ŃüŹŃü¬ŃüäŃü©ŃüäŃüåŃü«ŃüīńÉåńö▒Ńü¦ŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«ńĄÉµ×£ŃĆüTwitterńżŠÕü┤Ńü½Ńü»ŃĆüŃéóŃé½Ńé”Ńā│ŃāłAŃĆüBŃü«õ┐ص£ēĶĆģŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüŃéóŃé½Ńé”Ńā│ŃāłCDEŃü«ÕÉäõ┐ص£ēĶĆģŃü«ķø╗ÕŁÉŃāĪŃā╝Ńā½ŃéóŃāēŃā¼Ńé╣Ńü«ķ¢ŗńż║ŃééÕæĮŃüśŃéēŃéīŃüŠŃüŚŃü¤’╝łń¤źĶ▓Īķ½śńŁēĶŻüÕłżµēĆÕ╣│µłÉ30Õ╣┤4µ£ł25µŚź’╝ēŃĆé
ŃüōŃéīŃéÆõĖŹµ£ŹŃü©ŃüŚŃü”TwitterńżŠÕü┤Ńü»õĖŖÕæŖŃüŚŃĆüõĖŖÕæŖÕÅŚńÉåńö│ŃüŚń½ŗŃü”ŃüīÕÅŚńÉåŃüĢŃéīŃü¤Ńü¤ŃéüŃĆüµ£Ćķ½śĶŻüÕłżµēĆŃü«Õłżµ¢ŁŃéÆõ╗░ŃüÉŃüōŃü©Ńü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
µ£Ćķ½śĶŻüÕłżµēĆŃü«Õłżµ¢Ł’╝ܵ░ÅÕÉŹĶĪ©ńż║µ©®Ńü«õŠĄÕ«│ŃéÆĶ¬ŹŃéüŃéŗ
µ£Ćķ½śĶŻüÕłżµēĆŃü»ŃĆüÕÉīõĖƵƦõ┐صīüµ©®Ńü«õŠĄÕ«│Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüõĖŖÕæŖÕÅŚńÉåµ▒║Õ«ÜŃü«ķÜøŃü½õĖŖÕæŖńÉåńö▒ŃüŗŃéēµÄÆķÖżŃüŚŃĆüµ░ÅÕÉŹĶĪ©ńż║µ©®Ńü«õŠĄÕ«│Ńü«Ńü┐Ńü½ŃüżŃüäŃü”Õłżµ¢ŁŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
TwitterńżŠÕü┤Ńü»ńö│ŃüŚń½ŗŃü”ńÉåńö▒Ńü©ŃüŚŃü”ŃĆüµ£¼õ╗ČÕÉäŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłĶĆģŃü»ÕÉäŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃü½ŃéłŃüŻŃü”ĶæŚõĮ£µ©®õŠĄÕ«│Ńü©Ńü¬ŃéŗĶæŚõĮ£ńē®Ńü«Õł®ńö©ŃéÆŃüŚŃü”ŃüäŃü¬ŃüäŃüŗŃéēŃĆüĶæŚõĮ£µ©®µ│Ģ19µØĪ1ķĀģŃü«ŃĆīĶæŚõĮ£ńē®Ńü«Õģ¼ĶĪåŃüĖŃü«µÅÉõŠøĶŗźŃüŚŃüÅŃü»µÅÉńż║ŃĆŹŃéÆŃüŚŃü”ŃüäŃü¬Ńüäńé╣ŃéÆŃüéŃüÆŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüĢŃéēŃü½ŃĆüµ£¼õ╗ČÕÉäŃé”Ńé¦Ńā¢ŃāÜŃā╝ŃéĖŃéÆķ¢▓Ķ”¦ŃüÖŃéŗŃā”Ńā╝ŃéČŃā╝Ńü»ŃĆüÕÉäŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłĶ©śõ║ŗõĖŁŃü«ÕÉäĶĪ©ńż║ńö╗ÕāÅŃéÆŃé»Ńā¬ŃāāŃé»ŃüÖŃéīŃü░ŃĆüµ░ÅÕÉŹĶĪ©ńż║ķā©ÕłåŃüīŃüéŃéŗÕģāńö╗ÕāÅŃéÆĶ”ŗŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃéŗŃü«ŃüĀŃüŗŃéēŃĆüÕÉäŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłĶĆģŃü»µ£¼õ╗ČÕåÖń£¤Ńü½ŃüżŃüŹŃĆīŃüÖŃü¦Ńü½ĶæŚõĮ£ĶĆģŃüīĶĪ©ńż║ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃü©ŃüōŃéŹŃü½ÕŠōŃüŻŃü”ĶæŚõĮ£ĶĆģÕÉŹŃéÆĶĪ©ńż║ŃĆŹ’╝łÕÉīµØĪ2ķĀģ’╝ēŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃü©ŃüäŃüłŃéŗŃü©ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃéłŃüŻŃü”ŃĆüÕÉäŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃü½ŃéłŃéŗµ░ÅÕÉŹĶĪ©ńż║µ©®Ńü«õŠĄÕ«│ŃéÆĶ¬ŹŃéüŃü¤ÕĤջ®Ńü«Õłżµ¢ŁŃü½Ńü»ĶæŚõĮ£µ©®µ│ĢŃü«Ķ¦Żķćłķü®ńö©Ńü«Ķ¬żŃéŖŃüīŃüéŃéŗŃĆüŃü©õĖ╗Õ╝ĄŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüōŃéīŃü½Õ»ŠŃüŚŃĆüµ£Ćķ½śĶŻüŃü»ŃĆüµ░ÅÕÉŹĶĪ©ńż║µ©®Ńü«õŠĄÕ«│ŃéÆĶ¬ŹŃéüŃĆüõĖŖÕæŖŃéƵŻäÕŹ┤ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüØŃü«ńÉåńö▒Ńü©ŃüŚŃü”Ńü»ŃĆüõĖŗĶ©ś2ńé╣ŃéƵīÖŃüÆŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
- ĶĪ©ńż║ńö╗ÕāÅŃéÆŃé»Ńā¬ŃāāŃé»ŃüÖŃéīŃü░ŃĆüµ░ÅÕÉŹĶĪ©ńż║ķā©ÕłåŃüīŃüéŃéŗÕģāńö╗ÕāÅŃéÆĶ”ŗŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃéŗŃü©ŃüŚŃü”ŃééŃĆüÕÉäĶĪ©ńż║ńö╗ÕāÅŃüīĶĪ©ńż║ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃé”Ńé¦Ńā¢ŃāÜŃā╝ŃéĖŃü©Ńü»ÕłźÕĆŗŃü«Ńé”Ńé¦Ńā¢ŃāÜŃā╝ŃéĖŃü½µ░ÅÕÉŹĶĪ©ńż║ķā©ÕłåŃüīŃüéŃéŗŃü©ŃüäŃüåŃü½Ńü©Ńü®ŃüŠŃüŻŃü”ŃüäŃéŗńé╣
- ÕÉäŃé”Ńé¦Ńā¢ŃāÜŃā╝ŃéĖŃéÆķ¢▓Ķ”¦ŃüÖŃéŗŃā”Ńā╝ŃéČŃā╝Ńü»ŃĆüÕÉäĶĪ©ńż║ńö╗ÕāÅŃéÆŃé»Ńā¬ŃāāŃé»ŃüŚŃü¬ŃüäķÖÉŃéŖŃĆüĶæŚõĮ£ĶĆģÕÉŹŃü«ĶĪ©ńż║ŃéÆńø«Ńü½ŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü»Ńü¬ŃüäŃü«Ńü¦ŃüéŃéŗŃüŚŃĆüķ¢▓Ķ”¦ŃüÖŃéŗŃā”Ńā╝ŃéČŃā╝ŃüīĶĪ©ńż║ńö╗ÕāÅŃéÆķĆÜÕĖĖŃé»Ńā¬ŃāāŃé»ŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüłŃéŗŃéłŃüåŃü¬õ║ŗµāģŃééŃüåŃüŗŃüīŃéÅŃéīŃü¬Ńüäńé╣
ŃéłŃüŻŃü”ŃĆüÕÉäŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłĶ©śõ║ŗõĖŁŃü«ĶĪ©ńż║ńö╗ÕāÅŃéÆŃé»Ńā¬ŃāāŃé»ŃüÖŃéīŃü░ŃĆüµ░ÅÕÉŹĶĪ©ńż║ķā©ÕłåŃüīŃüéŃéŗÕģāńö╗ÕāÅŃéÆĶ”ŗŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃéŗŃü©ŃüäŃüåŃüōŃü©ŃéÆŃééŃüŻŃü”ŃĆüÕÉäŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłĶĆģŃüīĶæŚõĮ£ĶĆģÕÉŹŃéÆĶĪ©ńż║ŃüŚŃü¤ŃüōŃü©Ńü½Ńü¬ŃéŗŃééŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüäŃü©ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüōŃüåŃüŚŃü”ŃĆüÕĤջ®Ńü¦ŃüéŃéŗń¤źĶ▓Īķ½śĶŻüŃü«Õłżµ¢ŁŃüīńó║Õ«ÜŃüŚŃĆüŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃü»ĶæŚõĮ£ĶĆģõ║║µĀ╝µ©®õŠĄÕ«│Ńü½Ńü¬ŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃüīŃüéŃéŖŃĆüTwitterŃü«õ╗Ģµ¦śŃü½ÕŠōŃüŻŃü”õ╗¢ĶĆģŃü«ńö╗ÕāÅõ╗śŃüŹŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃéÆŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłŃüŚŃü¤Ńü©ŃüŹŃü½ŃééŃĆüńÖ║õ┐ĪĶĆģµāģÕĀ▒ķ¢ŗńż║Ńü¦µāģÕĀ▒Ńüīķ¢ŗńż║ŃüĢŃéīŃéŗŃüōŃü©ŃééŃüéŃéŗŃü©ŃüäŃüåŃüōŃü©Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤’╝łµ£Ćķ½śĶŻüÕłżµēĆõ╗żÕÆī2Õ╣┤7µ£ł21µŚźÕłżµ▒║’╝ēŃĆé
Ńü¬ŃüŖŃĆüµ£Ćķ½śĶŻüŃü»ŃĆüÕÉīõĖƵƦõ┐صīüµ©®Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»õĖŖÕæŖńÉåńö▒ŃüŗŃéēµÄÆķÖżŃüŚŃĆüµ░ÅÕÉŹĶĪ©ńż║µ©®Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü«Ńü┐Õłżµ¢ŁŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüµ░ÅÕÉŹĶĪ©ńż║µ©®õŠĄÕ«│ŃüĢŃüłĶé»Õ«ÜŃüĢŃéīŃéīŃü░µ©®Õł®õŠĄÕ«│ŃüīĶ¬ŹŃéüŃéēŃéīŃéŗŃü©ŃüäŃüåŃüōŃü©ŃééŃüéŃéŖŃĆüÕÉīõĖƵƦõ┐صīüµ©®Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗÕłżµ¢ŁŃü»ķćŹĶ”üŃü¦Ńü¬ŃüäŃü©Õłżµ¢ŁŃüŚŃü¤Ńü«ŃüŗŃééŃüŚŃéīŃüŠŃüøŃéōŃĆé
ŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüń¤źĶ▓Īķ½śĶŻüŃü¦Ńü»ŃĆüŃĆīŃāłŃā¬Ńā¤Ńā│Ńé░ĶĪīńé║ŃüīÕÉīõĖƵƦõ┐صīüµ©®õŠĄÕ«│Ńü½Ńü¬ŃéŗŃĆŹŃü©Õłżµ¢ŁŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüµ£Ćķ½śĶŻüŃééŃüōŃü«Õłżµ¢ŁŃéÆÕɔիÜŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃéÅŃüæŃü¦Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéµ£Ćķ½śĶŻüŃüīĶ┐░Ńü╣Ńü¤µ░ÅÕÉŹĶĪ©ńż║µ©®Ńü«ĶČŻµŚ©Ńü»ŃĆüÕÉīõĖƵƦõ┐صīüµ©®Ńü½ŃüżŃüäŃü”ŃééĶ®▓ÕĮōŃüÖŃéŗŃü©ĶĆāŃüłŃéŗŃüōŃü©ŃééŃü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü©Ńéü’╝ÜSNSŃü¦Ńü«ĶæŚõĮ£µ©®õŠĄÕ«│Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»Õ╝üĶŁĘÕŻ½Ńü½ńøĖĶ½ćŃéÆ
µ£¼Ķ©śõ║ŗŃü¦Ńü»ŃĆüSNSŃü½ŃüŖŃüæŃéŗńö╗ÕāÅŃü«ńäĪµ¢ŁµŗĪµĢŻŃü©ĶæŚõĮ£µ©®õŠĄÕ«│Ńü«Ńā¬Ńé╣Ńé»Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ķ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéńē╣Ńü½ŃĆüµ£Ćķ½śĶŻüÕłżµēĆõ╗żÕÆī2Õ╣┤7µ£ł21µŚźÕłżµ▒║Ńü»ŃĆüŃā¬ŃāäŃéżŃā╝ŃāłĶĪīńé║ŃüīĶæŚõĮ£µ©®õŠĄÕ«│Ńü©Ńü¬ŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃüīŃüéŃéŗŃüōŃü©ŃéƵśÄńó║Ńü½ńż║ŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüÕ«ēµśōŃü¬µāģÕĀ▒µŗĪµĢŻŃü½Ńü»µ│©µäÅŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆé
ĶæŚõĮ£µ©®µ│ĢŃü»ĶżćķøæŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüÕĆŗÕłźŃü«Ńé▒Ńā╝Ńé╣Ńü½ŃéłŃüŻŃü”Õłżµ¢ŁŃüīńĢ░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃĆīń¤źŃéēŃü¬ŃüŗŃüŻŃü¤ŃĆŹŃü©ŃüŚŃü”ŃééĶ▓¼õ╗╗ŃéÆÕģŹŃéīŃéŗŃü©Ńü»ķÖÉŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃééŃüŚŃĆüĶć¬ńżŠŃü«SNSÕł®ńö©Ńü½ŃüŖŃüäŃü”ĶæŚõĮ£µ©®õŠĄÕ«│Ńü½ÕĮōŃü¤ŃéŗŃüŗŃü®ŃüåŃüŗõĖŹÕ«ēŃéƵä¤ŃüśŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃéäŃĆüĶæŚõĮ£µ©®õŠĄÕ«│Ńü¦ŃāłŃā®Ńā¢Ńā½Ńü½ÕĘ╗ŃüŹĶŠ╝ŃüŠŃéīŃü”ŃüŚŃüŠŃüŻŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü»ŃĆüķƤŃéäŃüŗŃü½Õ╝üĶŁĘÕŻ½Ńü½ńøĖĶ½ćŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆŃüŖŃüÖŃüÖŃéüŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ķ¢óķĆŻĶ©śõ║ŗ’╝ÜTwitterŃü«Ńé╣Ńé»ŃéĘŃā¦Õ╝Ģńö©Ńü»ĶæŚõĮ£µ©®õŠĄÕ«│Ńü½Ńü¬Ńéŗ’╝¤õ╗żÕÆī5Õ╣┤Õłżµ▒║ŃéÆĶ¦ŻĶ¬¼
ÕĮōõ║ŗÕŗÖµēĆŃü½ŃéłŃéŗÕ»ŠńŁ¢Ńü«ŃüöµĪłÕåģ
ŃāóŃāÄŃā¬Ńé╣µ│ĢÕŠŗõ║ŗÕŗÖµēĆŃü»ŃĆüITŃĆüńē╣Ńü½ŃéżŃā│Ńé┐Ńā╝ŃāŹŃāāŃāłŃü©µ│ĢÕŠŗŃü«õĖĪķØóŃü½Ķ▒ŖÕ»īŃü¬ńĄīķ©ōŃéƵ£ēŃüÖŃéŗµ│ĢÕŠŗõ║ŗÕŗÖµēĆŃü¦ŃüÖŃĆéĶ┐æÕ╣┤ŃĆüŃāŹŃāāŃāłõĖŖŃü½ŃüŖŃüæŃéŗĶæŚõĮ£µ©®õŠĄÕ«│Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ÕżÜŃüÅŃü«µ│©ńø«ŃüīķøåŃüŠŃüŻŃü”ŃüŖŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéÕĮōõ║ŗÕŗÖµēĆŃü¦Ńü»ńĄīķ©ōĶ▒ŖÕ»īŃü¬Õ╝üĶŁĘÕŻ½Ńü½ŃéłŃéŗÕ░éķ¢ĆŃāüŃā╝ŃāĀŃü½Ńü”Õ»ŠńŁ¢Ńü½ŃüéŃü¤ŃüŻŃü”ŃüŖŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéõĖŗĶ©śĶ©śõ║ŗŃü½Ńü”Ķ®│ń┤░ŃéÆĶ©śĶ╝ēŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃüŠŃüÖŃü«Ńü¦ŃüöÕÅéńģ¦ŃüÅŃüĀŃüĢŃüäŃĆé
ŃāóŃāÄŃā¬Ńé╣µ│ĢÕŠŗõ║ŗÕŗÖµēĆŃü«ÕÅ¢µē▒ÕłåķćÄ’╝ÜÕÉäń©«õ╝üµźŁŃü«ITŃā╗ń¤źĶ▓Īµ│ĢÕŗÖ
Ńé½ŃāåŃé┤Ńā¬Ńā╝: ITŃā╗ŃāÖŃā│ŃāüŃāŻŃā╝Ńü«õ╝üµźŁµ│ĢÕŗÖ