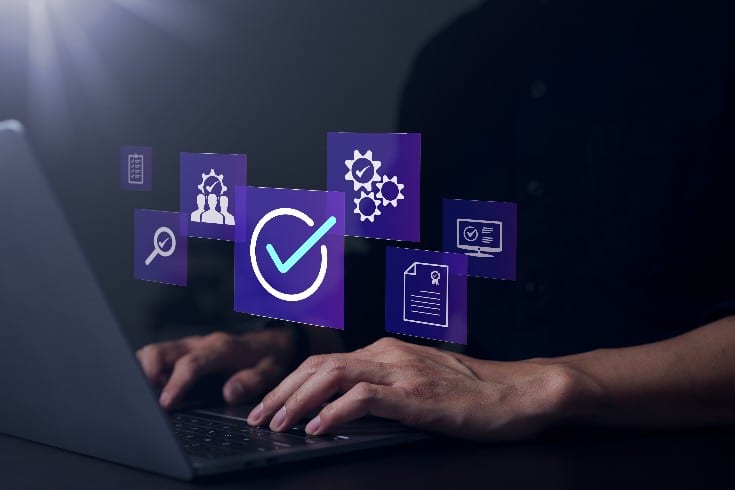アルメニア共和国の法律の全体像とその概要を弁護士が解説

アルメニア共和国(以下、アルメニア)は、近年、日本企業を含む外国からの投資先として注目を集めています。特にIT分野の急速な発展は目覚ましく、堅調な経済成長を牽引しています。
アルメニアの法制度は、ソビエト連邦からの独立後に継承した法体系を基礎としつつ、欧州評議会(Council of Europe)との関係強化の中で、ドイツ法やフランス法の要素を積極的に取り入れ、独自の発展を遂げてきました。その結果、憲法を最高規範として、民法典や会社法などが体系的に整備され、法の支配と三権分立が憲法上の原則として確立されています。
しかし、この「ソ連法の土台」と「欧州法の枠組み」というハイブリッドな構造より、アルメニア法務には二面性があると言えます。一方では、日本企業にとって非常に魅力的なインセンティブ、例えば世界でも類を見ない手厚い「IT分野への税制優遇」や、法改正リスクから投資家を保護する「グランドファザー条項」が存在します。他方で、日本法とは根本的に異なる、あるいは日本よりも遥かに厳格な義務、例えば会社設立時に課される「実質的支配者(UBO)の迅速な電子開示義務」や、2026年から完全義務化される「雇用契約の完全デジタル化」、公開会社に法律で強制される厳格な「コーポレートガバナンス」などが、「ハードロー(遵守必須の法律)」として存在します。
アルメニアへの進出やM&Aを検討している日本企業が、現地での法務戦略を構築する上で不可欠となる、各法分野の概要と、それがビジネス実務に具体的にどのような影響を及ぼすのか、現地の法令について解説します。
この記事の目次
アルメニアの司法制度と法体系

アルメニアの法体系は、憲法を最高規範とし、その下に民法典、刑法典、税法典などの主要な法典が整備された、典型的な大陸法(シビル・ロー)国家です。この点は日本と共通しており、法典の構造や用語には既視感を覚えることも多いでしょう。
しかし、司法制度の構造は日本と大きく異なります。日本の司法制度が、地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所という単一のピラミッド構造を持ち、最高裁判所が最終的な法令解釈権と違憲審査権の双方を担うのに対し、アルメニアの司法制度は、最高位の裁判権が目的別に二分化されている点が最大の特徴です。
具体的には、通常の民事事件、刑事事件、行政事件は、三審制の構造をとります。第一審裁判所として、一般管轄裁判所(民事・刑事)のほかに、専門裁判所としての行政裁判所が存在します。第二審は、民事控訴裁判所、刑事控訴裁判所、行政控訴裁判所に分かれています。
そして、これらの通常の事件における最高裁判所の役割を担うのが、「破毀院(Court of Cassation)」です。ただし、その役割は日本や米国型の「終審」とは異なり、主に「法令の統一的な適用を確保する」ことや、「司法判断の見直し」に重点が置かれています。
一方で、破毀院とは完全に別系統の最高裁判所として、「憲法裁判所(Constitutional Court)」が存在します。憲法裁判所の唯一の役割は、「憲法の優位性を確保する」こと、すなわち、法律、大統領令、政府決定その他の規範が憲法に違反していないかを審査する「違憲審査」です。
アルメニアでの会社設立とコーポレートガバナンスの重要相違点
アルメニアの主要な会社形態と設立
アルメニアでのビジネス展開における最初のステップは、現地法人の設立です。日本の合同会社(LLC)や株式会社(KK)と同様に、アルメニアでも主な会社形態として「有限責任会社(Limited Liability Company, LLC)」と「株式会社(Joint Stock Company, JSC)」が定められています。実務上、非公開の子会社設立や小規模ビジネスにはLLCが、将来的な株式の公募を想定する場合にはJSCが選択されます。
アルメニアの会社設立手続きは、日本の法務局での登記手続きと比較して、驚くほど迅速です。「法人の国家登録に関する法律」に基づき、登記当局(State Register of Legal Entities)へのオンライン申請が完備されており、書類に不備がなければ通常1〜2営業日で登記が完了します。設立時の国庫手数料も原則不要であり、ビジネスの立ち上げ(セットアップ)は非常に容易であると言えます。
しかし、この設立過程には、日本企業が直面する最初のコンプライアンス上の「罠」が潜んでいます。
「実質的支配者(UBO)」の電子届出義務
日本では、株式会社の設立時に公証役場で実質的支配者(UBO)の申告を行いますが、登記後の継続的な電子届出義務は限定的です。
これに対し、アルメニアはマネーロンダリング対策(AML)および採掘産業透明性イニシアティブ(EITI)への国際的なコミットメントを背景に、非常に厳格かつ透明性の高いUBO(Ultimate Beneficial Owner:実質的支配者)開示制度を導入しています。
「法人の国家登録に関する法律」の改正に基づき、アルメニア国内の全ての法人は、その法人を最終的に支配している「個人」の情報を特定し、法務省の国家登記簿(中央登録簿)に電子的に届け出ることが法律で義務付けられています。
特に注意すべきは、その期限です。新規に設立された法人は、設立登記の日からわずか40日以内に、このUBO情報を専用の電子ポータル(english.hartak.am)を通じて提出しなければなりません。UBO情報(例えば、支配構造の変更や個人の住所変更)があった場合も、同様に変更から40日以内の更新が義務付けられています。
アルメニアの会社設立は、「1〜2日での迅速な設立」と、「40日以内の厳格なUBO開示」がセットになっています。この「スピードのミスマッチ」は、複雑な資本構成を持つ日本企業にとって深刻なコンプライアンス・リスクとなり得ます。例えば、日本の親会社がシンガポールやオランダの持株会社を経由してアルメニア子会社を設立する場合、法務部がその複雑な資本の連鎖を遡り、「最終的な個人」を特定するUBOの調査には、数週間を要することも珍しくありません。
しかし、アルメニアの登記プロセスは非常に速いため、法務部がUBOの調査を完了する前に、現地の担当者が登記を完了させてしまうリスクがあります。その瞬間から40日間のカウントダウンが開始され、法務部のUBO特定作業が間に合わなければ、新会社は設立後わずか1ヶ月強で法律違反(届出義務違反)の状態に陥ってしまいます。したがって、M&Aや子会社設立時のプロジェクト管理においては、UBOの特定作業を「設立後」のタスクではなく、「設立申請前」に完了させておくべき最優先のタスクとして組み込むべきです。
日本の「コーポレートガバナンス・コード」との違い
アルメニアは、コーポレートガバナンスの分野でも急速な法整備を進めています。この点も、日本法とのアプローチの違いが顕著です。
日本のコーポレートガバナンス・コードは、金融庁と東京証券取引所が策定した「ソフトロー」であり、基本的には「コンプライ・オア・エクスプレイン(Comply or Explain)」の原則に基づいています。例えば、プライム市場の上場企業には「独立社外取締役を3分の1以上」選任することが求められますが、これはあくまで努力目標であり、選任しない場合はその「理由を説明」すれば足ります。
これに対し、アルメニアは2019年以降、特に公開株式会社(Open JSC)のガバナンスを強化する法改正を行っており、その主要なルールの多くが、説明責任で回避することのできない「ハードロー(法律上の強制義務)」として定められています。
「株式会社法(Law on Joint Stock Companies)」は、公開株式会社(Open JSC)に対し、特に以下の2点を法律で義務付けています。
- 独立取締役1/3義務: 取締役会の構成員の少なくとも3分の1は、「独立取締役」でなければならない。この規定は、同法第85条第5項に明記されています。
- 会長とCEOの兼任禁止: 取締役会の会長(Board Chair)とCEO(または総監督, General Director)の役職を同一人物が兼任することは、法律で禁止されています。
アルメニアは、資本市場の信頼性を国際水準(特にEU基準)まで引き上げるため、日本が数十年間かけてソフトローで進めてきたガバナンス改革のプロセスを飛び越し、直接的に「ハードロー」による厳格なガバナンス体制を採用したと言えます。日本企業がアルメニア企業を買収し、将来的に現地での上場(Open JSC化)を目指す場合、日本の「(説明すれば許容される)会長兼社長」や「(3分の1未満の)独立取締役」といったガバナンス体制は、アルメニアでは法律違反(株式会社法第85条違反)となります。買収後のPMI(経営統合)の初期段階から、この厳格なハードロー要件を満たすための役員構成を設計する必要があります。
アルメニアのビジネス基盤となる不動産・労働・税務
契約法の原則と不動産法
アルメニア民法典は、日本法と同様に「契約の自由」を基本原則としています。当事者は、法令に反しない限り、契約条件を自由に決定することができます。また、国際的な契約(例えば、日本の親会社とアルメニア子会社の間の契約)においては、当事者が(アルメニア法以外の)「外国法を準拠法として選択する自由」も明確に認められています。
不動産所有権についても、アルメニアは外国企業に対し非常に開放的です。外国人(日本国民および日本法人)は、原則としてアルメニア国民・法人と同様に不動産の所有権を持つことができ、アパート、コンドミニアム、商業ビル、オフィス、工場、住宅、庭園用の土地などは、外国人が自由に所有権を取得し、登記することが可能です。
ただし、日本法と根本的に異なる重大な例外が「土地」に関する規制です。アルメニア憲法および土地法典は、外国人(外国籍の個人および外国法人)が「農業用地」の所有権を持つことを原則として禁止しています。
この厳格な規制は、一見すると農業ビジネスへの外国投資を阻害するように見えますが、実務上は広く認められた2つの回避策(ワークアラウンド)が存在します。
- アルメニア法人を通じた所有: 外国人(日本企業)が100%出資してアルメニア現地法人(LLCなど)を設立し、そのアルメニア法人が農業用地の所有権者となることは適法です。
- 長期リース: 土地の所有権者にリース料を支払い、長期リース契約を結ぶことで、実質的な土地利用権を確保する方法です。
このことから、アルメニアの「外国人による農地所有禁止」規制は、外国「資本」の排除を目的としたものではなく、外国「籍」の主体が直接登記簿に載ることを制限する「形式的」な規制であると解釈できます。日本企業が農業分野(例えば、ワイナリーや農産物加工)に進出する場合、この規制を「投資障壁」と捉える必要はなく、法務戦略としては、単に「現地法人設立」というステップが一つ追加されるものと理解しておけばよいでしょう。
労働法と「雇用契約のデジタルシステム」
雇用関係は、アルメニア労働法典(Labour Code)によって規律されます。日本法と同様に、労働時間、安全衛生、雇用契約の期間(原則として期間の定めなし)など、労働者保護の諸原則が定められています。
近年、アルメニアの労務管理において最も劇的な変化であり、日本企業が必ず対応しなければならないのが、雇用契約の完全デジタル化です。2024年12月4日に採択された改正法(HO-525-N)により、労働法典に「第13.1章 デジタル雇用契約システム」が新設されました。
これは、雇用契約の締結、変更、終了のすべてを、政府が管理する統一電子プラットフォーム上で、デジタル署名を用いて行うことを義務付ける、非常に先進的かつ強制力のある制度です。
この制度の導入スケジュールは以下の通りです。
- 2025年7月1日: システム稼働。この時点では任意での利用(従来の紙の契約も可)が可能です。
- 2026年1月1日: すべての「新規」雇用契約は、このデジタルシステムを通じて締結することが法律上の義務となります。
- 2027年1月1日(または2026年12月31日): この期限までに、既存の(紙で締結された)すべての有効な雇用契約を、デジタルシステムに登録(デジタル化)することが義務付けられます。
このデジタル雇用契約システムは、日本で進められているような単なる「電子化(ペーパーレス化)」とは、その本質が異なります。注目すべきは、このプラットフォームの管理・運営主体が、労働省ではなく「国家歳入委員会(State Revenue Committee, SRC)」、すなわち日本の国税庁に相当する「税務当局」である点です。さらに、このシステムには移民局や労働監査局もアクセス権を持ちます。
日本企業がアルメニアで現地スタッフを雇用する場合、2026年以降、「税務署に知られずに人を雇う」ことは物理的に不可能になります。雇用契約書がシステムに登録された瞬間に、当局は雇用関係の発生と納税義務(源泉徴収)を即座に把握します。これにより、サービス残業、給与の過少申告、不法就労といったグレーゾーンの労務管理は完全に排除されることになります。アルメニアに進出する企業は、100%クリーンな労務・税務コンプライアンス体制を構築・維持することが、法的に強制されることになるのです。
アルメニア労働法典の改正に関する公式情報は、アルメニアの公式法律情報システム(ARLIS)で確認できます。
IT分野への大型税制優遇を特徴とする税法
アルメニアの標準的な法人所得税(CIT)率は18%です。これは、日本の実効税率(約30%)と比較して大幅に低い水準です。この18%という税率は、アルメニア税法典(TAX CODE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA)第118条第1項に規定されています。
そして、現在のアルメニア進出における最大の魅力が、特にIT・ハイテク分野の企業に対して導入された、時限的な(2025年1月1日〜2031年12月31日まで)大型税制優遇措置です。
政府が認定した「ハイテク活動」(ソフトウェア開発、R&Dなど)を行う企業は、以下の(選択可能な)破格の優遇措置を享受できます。
- 売上税1%の選択: 標準の「18%法人所得税」に代わり、「1%の売上税(Turnover Tax)」を選択することが可能になります。これは、利益率の高いIT企業にとって、税負担を劇的に軽減するものです。
- R&D人材の個人所得税10%: 従業員の個人所得税(PIT)は通常20%ですが、認定されたR&D(研究開発)業務に従事する従業員に支払われる給与については、10%に軽減されます。
- R&D給与の200%損金算入: 法人所得税(18%)を選択した場合、R&D専門スタッフの給与コストの200%(つまり2倍の金額)を、課税所得の計算上、費用(損金)として控除できます。
アルメニアは、これらの「1%売上税」や「200%損金算入」といった極めてアグレッシブな税制を導入することで、自国を単なるタックスヘイブン(租税回避地)ではなく、高度人材とR&D投資が実態をもって集積する「タックス・ヘブン(税制上の聖域、Tax HavenではなくTax Heaven)」として国家的にブランディングしようとしています。日本のIT企業にとって、この税制優遇は単なるコスト削減に留まらず、アルメニアを「オフショア開発拠点」として活用する上で、世界で最も魅力的な法制度の一つとして検討に値するものと言えるでしょう。
アルメニアのM&A・外国投資と「グランドファザー条項」
アルメニアは「外国投資法(Law on Foreign Investments)」に基づき、外国投資家(日本企業を含む)に対して、原則としてアルメニア国民・法人と同一の待遇(ナショナル・トリートメント)を保障しており、非常に開放的な投資環境を提供しています。
M&Aや投資に対する規制も限定的です。前述の「農業用地」のほか、「視聴覚メディア(放送局)」(外国資本は50%未満)など、ごく一部の戦略分野に限られます。金融分野(銀行、投資会社など)の株式の20%、50%、75%以上を取得する場合は、アルメニア中央銀行(CBA)の事前承認が必要です。
外国投資家が最も懸念するリスクの一つに、「投資後の不利な法改正(例:突然の増税、新たな規制の導入)」があります。アルメニアは、この「カントリーリスク」に対し、法律によって強力な保護規定を設けています。
「外国投資法」の第7条は、以下のように規定しています。「アルメニア共和国の外国投資関連法規が改正された場合、外国投資家の要求に基づき、投資の実行時点において有効であった法規が、その時点から5年間適用されるものとする。」
これは「グランドファザー条項」と呼ばれるもので、その実務上の意味は絶大です。例えば、日本企業がアルメニアに工場を建設した後、仮にアルメニア政府が法人税を18%から30%に引き上げる法改正を行ったとしても、その日本企業は「改正前の18%」の法律を、自ら要求することによって5年間適用し続けることができる、ということを意味します。
この「5年間のグランドファザー条項」は、アルメニア政府が自国の「法的不安定性」のリスク(旧ソ連からの移行国であるという歴史的背景)を自ら認識し、そのリスクを「5年間の法的安定性の保証」という形でヘッジする(投資家に保証を提供する)という、極めて合理的かつ投資家フレンドリーな政策の表れです。日本企業がM&A(特に大規模な初期投資が必要なインフラや製造業)を行う際、この条項は、カントリーリスクを大幅に低減させるポジティブな評価要因として、法務・財務の両面で考慮されるべき重要な規定です。
アルメニアにおけるその他のビジネス関連法分野

医療機器(Medical Device)の規制
日本では、医薬品も医療機器も「薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」という単一の法律で一体的に規制されています。
これに対し、アルメニアの「医薬品法(Law on Medicinal Products)」は医薬品を対象としており、製造・卸売にはライセンスが必要ですが、この法律は医療機器を対象外としています。そしてこの結果、アルメニアの国内法上、医療機器の製造、輸入、販売、保管には、ライセンスが不要であるとされています。
ただし、この「医療機器ライセンス不要」という極めて特殊な状況は、間もなく終了します。アルメニアは「ユーラシア経済連合(EAEU)」の加盟国であり、EAEUは域内で共通の医療機器規制を導入しています。アルメニア国内法に基づく簡易的な運用(=登録不要)が認められる移行(猶予)期間は、2025年12月31日をもって終了するとされています。
2026年1月1日以降、アルメニアで医療機器を販売するには、EAEUの統一登録制度に基づく、より複雑で厳格な承認が必須となる見込みです。アルメニアの医療機器市場は、2025年末を境に「規制ゼロ」から「複雑な国際規制(EAEU)」へと一気に移行する「レギュラトリー・クリフ(規制の崖)」の淵に立っています。
個人情報保護法
個人情報保護法 アルメニアは2015年に「個人データ保護法(Law on Protection of Personal Data)」を施行しており、日本の個人情報保護法やEUのGDPRと類似した原則(適法性、目的の限定、安全管理など)を採用しています。監督当局は個人データ保護庁(PDPA)です。
日本企業にとって重要な「国境を越えたデータ移転」については、GDPRと同様の枠組みが採用されています。データ移転は、移転先(日本など)が「十分な保護レベル(adequate level of protection)」を確保している場合にのみ適法となります。アルメニアはEU/EEA諸国を十分な保護レベルがあると認めていますが、日本は現時点で含まれていません。したがって、アルメニア子会社から日本の親会社へ個人データ(従業員情報、顧客情報など)を移転する場合、データ主体(本人)の同意や、標準契約条項(SCC)に類似する契約上の保護措置といった、適法な移転根拠を確保する必要があります。
決済関連の法律
決済サービス、電子マネー(E-money)の発行、資金移動は、中央銀行(CBA)の厳格な監督下にあり、事業者は「決済機関(PO)」や「電子マネー機関(EMI)」などのライセンスを取得する必要があります。
また、日本との実務上の大きな違いとして、「非現金取引法(Law on Non-Cash Transactions)」の存在が挙げられます。この法律により、法人・個人事業主が関与する取引や、個人間の取引であっても、一定額(30万ドラム、約12万円)を超える支払いは、現金で行うことが禁止され、銀行振込などの非現金手段が強制されます。
まとめ
アルメニアの法制度は、旧ソ連からの独立後、欧州の基準(大陸法)を取り入れながら、急速に独自の発展を遂げています。その結果、日本企業のビジネス展開において、「強力な追い風」となる制度と、「厳格な義務」となる制度が混在する、非常に特徴的な法環境が形成されています。
アルメニア法務のリスクとして、日本法との違いが大きい以下の4点には、特に注意が必要です。
- 労務管理の完全デジタル化: 2026年1月1日から、すべての新規雇用契約は、税務当局が管理するデジタルシステムで締結することが「義務」となります。紙の契約書による従来の人事管理は、もはや許容されません。
- 厳格なガバナンス(ハードロー): 日本の「コンプライ・オア・エクスプレイン」とは異なり、公開株式会社(Open JSC)は、法律により「独立取締役1/3以上」の選任と「CEO/会長の兼任禁止」が強制されます。
- 即時のUBO開示義務: 設立後わずか40日以内に、最終的な「実質的支配者(UBO)」の情報を当局に電子的に届け出る厳格な義務があります。
- 規制の移行期: 医療機器の「ライセンス不要」という現在の特例は2025年末で終了し、EAEUの厳格な規制に移行します。また、AIの「利用」については、2025年からプライバシー上重大な懸念のある監視法案が施行される予定です。
アルメニアは、特にIT・ハイテク分野において、法制度をテコに(Tax Heavenとして)国家的な変革を進めている、ダイナミックな国です。しかし、その急速な変化は、労働法やコンプライアンス分野で、日本企業がこれまで経験したことのない、透明で厳格な「デジタル義務」も同時に生み出しています。「追い風」を最大限に活用し、「義務」の罠に陥らないためには、日本法との違いを正確に把握し、最新の法改正を踏まえた法務戦略を策定することが不可欠です。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務