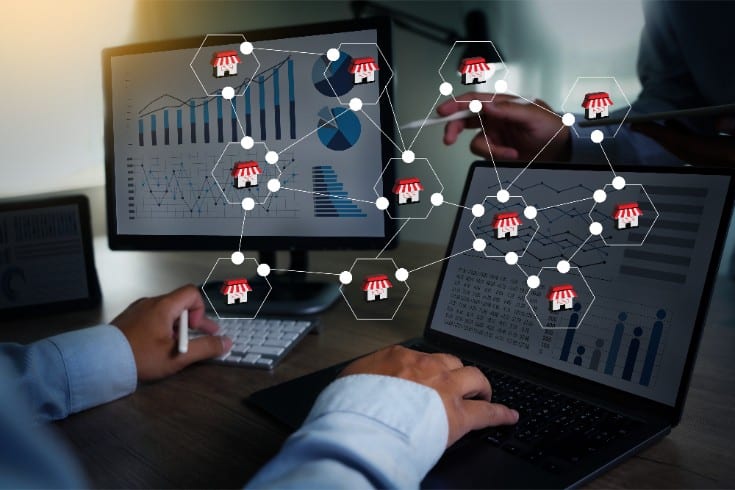гғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ®жі•еҫӢгҒ®е…ЁдҪ“еғҸгҒЁжҰӮиҰҒгӮ’ејҒиӯ·еЈ«гҒҢи§ЈиӘ¬

гғ•гӮЈгғӘгғ”гғізөҢжёҲгҒҜиҝ‘е№ҙгҖҒгӮўгӮёгӮўгҒ®дёӯгҒ§гӮӮзү№гҒ«й«ҳгҒ„жҲҗй•·зҺҮгӮ’з¶ӯжҢҒгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒиӢҘгҒ„еҠҙеғҚеҠӣгҒЁж—әзӣӣгҒӘеҶ…йңҖгӮ’иғҢжҷҜгҒ«гҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№жҘӯгӮ’дёӯеҝғгҒ«зҷәеұ•гӮ’йҒӮгҒ’гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеӣҪйҡӣйҖҡиІЁеҹәйҮ‘пјҲIMFпјүгҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒ2025е№ҙгҒ«гҒҜеҗҚзӣ®GDPгҒ§дё–з•Ң第32дҪҚгҒ«йҒ”гҒҷгӮӢгҒЁдәҲжё¬гҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒITгҒҠгӮҲгҒігғ“гӮёгғҚгӮ№гғ—гғӯгӮ»гӮ№гӮўгӮҰгғҲгӮҪгғјгӮ·гғігӮ°пјҲBPOпјүгҖҒйӣ»еӯҗж©ҹеҷЁиЈҪйҖ гҖҒиҰіе…үжҘӯгҒҢдё»иҰҒгҒӘзүҪеј•еҪ№гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ®жі•дҪ“зі»гҒҜгҖҒжӨҚж°‘ең°жҷӮд»ЈгҒ®жӯҙеҸІзҡ„иғҢжҷҜгҒӢгӮүгҖҒгӮ№гғҡгӮӨгғігҒ®ж°‘жі•пјҲCivil LawпјүгҒЁгӮўгғЎгғӘгӮ«гҒ®гӮігғўгғігғӯгғјпјҲCommon LawпјүгҒҢж··еңЁгҒҷгӮӢгғҰгғӢгғјгӮҜгҒӘзү№еҫҙгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒгғ•гӮЈгғӘгғ”гғіжі•гҒ®жі•дҪ“зі»гҒӢгӮүгҖҒзү№гҒ«ж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҢй–ўеҝғгӮ’жҢҒгҒӨгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶжі•еҲҶйҮҺгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒж—Ҙжң¬жі•гҒЁгҒ®жҜ”ијғгӮ’дәӨгҒҲгҒӘгҒҢгӮүи©ізҙ°гҒ«и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®зӣ®ж¬Ў
гғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ®жі•дҪ“зі»гҒЁеҸёжі•еҲ¶еәҰгҒ®е…ЁдҪ“еғҸ
гӮ·гғ“гғ«гғӯгғјгҒЁгӮігғўгғігғӯгғјгҒ®иһҚеҗҲ
гғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ®жі•дҪ“зі»гҒҜгҖҒгӮ№гғҡгӮӨгғіжӨҚж°‘ең°жҷӮд»ЈгҒ«е°Һе…ҘгҒ•гӮҢгҒҹгӮ·гғ“гғ«гғӯгғјпјҲеӨ§йҷёжі•пјүгҒЁгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ®зұіеӣҪзөұжІ»жҷӮд»ЈгҒ«зўәз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹгӮігғўгғігғӯгғјпјҲиӢұзұіжі•пјүгҒ®иҰҒзҙ гҒҢиһҚеҗҲгҒ—гҒҹгҖҢгғҸгӮӨгғ–гғӘгғғгғүгҖҚгҒӘж§ӢйҖ гӮ’жңүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®жі•дҪ“зі»гҒҢгҖҒж°‘жі•гӮ„е•Ҷжі•гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжҲҗж–Үжі•гӮ’дё»иҰҒгҒӘжі•жәҗгҒЁгҒҷгӮӢгӮ·гғ“гғ«гғӯгғјгӮ’еҹәзӣӨгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ§гҒҜжҲҗж–Үжі•гҒ«еҠ гҒҲгҖҒй«ҳдҪҚгҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҖҒзү№гҒ«жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨдҫӢгҒҢдёӢзҙҡиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨжұәгӮ’жӢҳжқҹгҒҷгӮӢгӮігғўгғігғӯгғјгҒ®еҺҹеүҮпјҲеҲӨдҫӢжі•дё»зҫ©пјүгҒҢеј·гҒҸеҪұйҹҝгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
иЈҒеҲӨжүҖгҒ®зЁ®йЎһгҒЁж§ӢйҖ
гғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ®еҸёжі•еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖпјҲSupreme CourtпјүгӮ’й ӮзӮ№гҒЁгҒҷгӮӢеӣӣж®өйҡҺгҒ®йҡҺеұӨж§ӢйҖ гӮ’жңүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжңҖдёҠдҪҚгҒ«дҪҚзҪ®гҒҷгӮӢжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒйҰ–еёӯеҲӨдәӢгҒЁ14дәәгҒ®йҷӘеёӯеҲӨдәӢгҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҖҒжҶІжі•и§ЈйҮҲгӮ„дёӢзҙҡиЈҒеҲӨжүҖгҒӢгӮүгҒ®дёҠиЁҙгӮ’жүұгҒҶгҒ»гҒӢгҖҒеҸёжі•иЎҢж”ҝгҒ®зӣЈзқЈгӮ„иЈҒеҲӨжүӢз¶ҡиҰҸеүҮгҒ®еҲ¶е®ҡжЁ©йҷҗгҒӘгҒ©гҖҒеәғзҜ„гҒӘжЁ©йҷҗгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®дёӢгҒ«гҒҜгҖҒең°ж–№иЈҒеҲӨжүҖпјҲRegional Trial CourtsпјүгӮ„гҖҒжңҖгӮӮиә«иҝ‘гҒӘдәӢ件гӮ’жүұгҒҶ第дёҖеҜ©иЈҒеҲӨжүҖпјҲFirst-Level CourtsпјүгҒҢй…ҚзҪ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮи»Ҫеҫ®гҒӘзҠҜзҪӘгӮ„е°‘йЎҚгҒ®ж°‘дәӢдәӢ件гӮ’жүұгҒҶ第дёҖеҜ©иЈҒеҲӨжүҖгҒӢгӮүгҒ®жҺ§иЁҙгҒҜгҖҒең°ж–№иЈҒеҲӨжүҖгҒҢжӢ…еҪ“гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮең°ж–№иЈҒеҲӨжүҖгҒӢгӮүгҒ®дёҠиЁҙгҒҜгҖҒжҺ§иЁҙиЈҒеҲӨжүҖпјҲCourt of AppealsпјүгҒҢжүұгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжҺ§иЁҙиЈҒеҲӨжүҖгӮ„гҖҒе…¬еӢҷе“ЎгҒ®жұҡиҒ·дәӢ件гӮ’жүұгҒҶгӮөгғігғҮгӮЈгӮ¬гғігғҗгғӨгғіпјҲSandiganbayanпјүгҖҒзЁҺеӢҷдәӢ件гӮ’жүұгҒҶзЁҺеӢҷжҺ§иЁҙиЈҒеҲӨжүҖпјҲCourt of Tax AppealsпјүгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹзү№еҲҘиЈҒеҲӨжүҖгҒӢгӮүгҒ®жұәе®ҡгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢдёҠиЁҙгҒҜгҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒ«гҒ®гҒҝиЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ®иЈҒеҲӨжүҖйҡҺеұӨж§ӢйҖ гӮ’гҒҫгҒЁгӮҒгӮӢгҒЁгҖҒд»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
| иЈҒеҲӨжүҖеҗҚпјҲж—Ҙжң¬иӘһ/иӢұиӘһпјү | дё»гҒӘеҪ№еүІгҒЁз®ЎиҪ„ | |
|---|---|---|
| 第еӣӣйҡҺеұӨ | жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖпјҲSupreme Courtпјү | жҶІжі•и§ЈйҮҲгҖҒеҸёжі•иЎҢж”ҝгҒ®зӣЈзқЈгҖҒдёӢзҙҡиЈҒеҲӨжүҖгҒӢгӮүгҒ®дёҠиЁҙеҜ© |
| 第дёүйҡҺеұӨ | жҺ§иЁҙиЈҒеҲӨжүҖпјҲCourt of Appealsпјү | ең°ж–№иЈҒеҲӨжүҖгҒӢгӮүгҒ®дёҠиЁҙеҜ©гҖҒзү№е®ҡгҒ®жә–еҸёжі•ж©ҹй–ўгҒ®жұәе®ҡгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжҺ§иЁҙеҜ© |
| зү№еҲҘиЈҒеҲӨжүҖпјҲSandiganbayanгҖҒCourt of Tax AppealsгҒӘгҒ©пјү | е…¬еӢҷе“ЎгҒ®жұҡиҒ·дәӢ件гҖҒзЁҺеӢҷй–ўйҖЈгҒ®иЁҙиЁҹгҒӘгҒ©гӮ’е°Ӯй–Җзҡ„гҒ«жүұгҒҶ | |
| 第дәҢйҡҺеұӨ | ең°ж–№иЈҒеҲӨжүҖпјҲRegional Trial Courtsпјү | йҮҚеӨ§гҒӘж°‘дәӢгғ»еҲ‘дәӢдәӢ件гҒ®з¬¬дёҖеҜ©гҖҒ第дёҖеҜ©иЈҒеҲӨжүҖгҒӢгӮүгҒ®дёҠиЁҙеҜ© |
| 第дёҖйҡҺеұӨ | 第дёҖеҜ©иЈҒеҲӨжүҖпјҲFirst-Level Courtsпјү | и»Ҫеҫ®гҒӘж°‘дәӢгғ»еҲ‘дәӢдәӢ件гҖҒең°ж–№жқЎдҫӢйҒ•еҸҚгҒӘгҒ©гҒ®з¬¬дёҖеҜ© |
гғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ®дјҡзӨҫиЁӯз«ӢгҒЁгӮігғјгғқгғ¬гғјгғҲгӮ¬гғҗгғҠгғігӮ№

дјҡзӨҫиЁӯз«ӢжүӢз¶ҡгҒҚгҒ®жҹ”и»ҹжҖ§
2019е№ҙгҒ«еҲ¶е®ҡгҒ•гӮҢгҒҹгғ•гӮЈгғӘгғ”гғіж”№жӯЈдјҡзӨҫжі•пјҲRepublic Act No. 11232пјүгҒҜгҖҒгғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ®дјҡзӨҫиЁӯз«ӢжүӢз¶ҡгҒҚгҒ«жҠңжң¬зҡ„гҒӘеӨүеҢ–гӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮжңҖгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘеӨүжӣҙзӮ№гҒ®дёҖгҒӨгҒҜгҖҒж ӘејҸдјҡзӨҫиЁӯз«ӢгҒ«еҝ…иҰҒгҒ гҒЈгҒҹжңҖдҪҺиіҮжң¬йҮ‘еҲ¶еәҰгҒҢж’Өе»ғгҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒе°ҸиҰҸжЁЎгҒӘиө·жҘӯ家гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒ®еҸӮе…ҘйҡңеЈҒгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸдёӢгҒҢгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒжңҖдҪҺ5дәәгҒ гҒЈгҒҹзҷәиө·дәәиҰҒ件гҒҢж’Өе»ғгҒ•гӮҢгҖҒеҚҳдёҖгҒ®иҮӘ然дәәгҖҒдҝЎиЁ—гҖҒгҒҫгҒҹгҒҜжі•еҫӢдёҠгҒ®е®ҹдҪ“гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиЁӯз«ӢгҒ§гҒҚгӮӢгҖҢдёҖдәәдјҡзӨҫпјҲOne Person Corporation, OPCпјүгҖҚгҒҢжі•зҡ„гҒ«иӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гӮҢгӮүгҒ®ж”№жӯЈгҒҜгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢжүӢз¶ҡгҒҚгҒ®з°Ўзҙ еҢ–гҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгӮүгҒҡгҖҒгғ•гӮЈгғӘгғ”гғіж”ҝеәңгҒҢж„Ҹеӣізҡ„гҒ«гҖҒзү№гҒ«гӮ№гӮҝгғјгғҲгӮўгғғгғ—гӮ’еҗ«гӮҖе°ҸиҰҸжЁЎгҒӘиө·жҘӯ家гҒҢгғ“гӮёгғҚгӮ№гӮ’з«ӢгҒЎдёҠгҒ’гӮ„гҒҷгҒ„з’°еўғгӮ’ж•ҙеӮҷгҒ—гҖҒзөҢжёҲгӮ’жҙ»жҖ§еҢ–гҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®ж”ҝзӯ–зҡ„жҺӘзҪ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжҚүгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®дјҡзӨҫжі•гҒҢжңҖдҪҺ1еҗҚгҒ®зҷәиө·дәәгӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгҒ“гҒ®дёҖдәәдјҡзӨҫеҲ¶еәҰгҒҜйқһеёёгҒ«жҹ”и»ҹжҖ§гҒҢй«ҳгҒҸгҖҒеҚҳзӢ¬гҒ§дәӢжҘӯгӮ’еұ•й–ӢгҒ—гҒҹгҒ„ж—Ҙжң¬гҒ®зөҢе–¶иҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰйӯ…еҠӣзҡ„гҒӘйҒёжҠһиӮўгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
| ж—§жі•пјҲж”№жӯЈеүҚпјү | ж”№жӯЈдјҡзӨҫжі•пјҲ2019е№ҙпјү | ж—Ҙжң¬жі•гҒЁгҒ®жҜ”ијғ | |
|---|---|---|---|
| жңҖдҪҺзҷәиө·дәәж•° | 5дәәд»ҘдёҠгҖҒ15дәәд»ҘдёӢ | 1дәәд»ҘдёҠгҖҒ15дәәд»ҘдёӢгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒ1дәәдјҡзӨҫпјҲOPCпјүгҒ®иЁӯз«ӢгҒҢеҸҜиғҪгҖӮ | ж—Ҙжң¬жі•гҒҜзҷәиө·дәә1дәәд»ҘдёҠгҖӮгғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ®дёҖдәәдјҡзӨҫеҲ¶еәҰгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®зҷәиө·дәәиҰҒ件гӮҲгӮҠгӮӮжҹ”и»ҹжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ |
| жңҖдҪҺиіҮжң¬йҮ‘ | жҺҲжЁ©иіҮжң¬гҒ®25%д»ҘдёҠгӮ’жү•иҫјгҒҝгҖҒгҒӢгҒӨзҷәиЎҢжёҲж ӘејҸз·ҸйЎҚгҒ®25%д»ҘдёҠгӮ’жү•иҫјгӮҖеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹ | зү№еҲҘжі•гҒ§еҲҘйҖ”иҰҸе®ҡгҒҢгҒӘгҒ„йҷҗгӮҠгҖҒжңҖдҪҺиіҮжң¬йҮ‘гҒҜдёҚиҰҒгҖӮ | ж—Ҙжң¬жі•гӮӮжңҖдҪҺиіҮжң¬йҮ‘гҒ®иҰҸе®ҡгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒгғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ§гҒҜгҒ“гҒ®ж’Өе»ғгҒҢиҝ‘е№ҙе®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ |
| еӯҳз¶ҡжңҹй–“ | 50е№ҙпјҲжӣҙж–°еҸҜиғҪпјү | ж°ёд№…еӯҳз¶ҡгҒҢеҸҜиғҪгҖӮ | ж—Ҙжң¬жі•гҒЁеҗҢж§ҳгҖҒе®ҡж¬ҫгҒ§еҲҘйҖ”е®ҡгӮҒгҒӘгҒ„йҷҗгӮҠгҖҒж°ёд№…еӯҳз¶ҡгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ |
гӮігғјгғқгғ¬гғјгғҲгӮ¬гғҗгғҠгғігӮ№гҒЁеҸ–з· еҪ№гҒ®жЁ©йҷҗ
гғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ®ж ӘејҸдјҡзӨҫгҒ§гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®дјҡзӨҫжі•гҒЁеҗҢж§ҳгҒ«гҖҒеҸ–з· еҪ№дјҡпјҲBoard of DirectorsпјүгҒҢдјҡзӨҫгҒ®жҘӯеӢҷеҹ·иЎҢгӮ’жӢ…гҒҶжңҖй«ҳж„ҸжҖқжұәе®ҡж©ҹй–ўгҒЁгҒ—гҒҰдҪҚзҪ®гҒҘгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҸ–з· еҪ№дјҡгҒҜгҖҒжі•еҫӢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒдјҡзӨҫгҒ®гҒҷгҒ№гҒҰгҒ®дјҒжҘӯжЁ©йҷҗгӮ’иЎҢдҪҝгҒ—гҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®дәӢжҘӯгӮ’йҒӮиЎҢгҒ—гҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®дјҒжҘӯиІЎз”ЈгӮ’з®ЎзҗҶгҒҷгӮӢгҒЁе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ®дјҡзӨҫжі•гҒҜгҖҒеҸ–з· еҪ№гҒ®еҝ е®ҹзҫ©еӢҷпјҲDuty of LoyaltyпјүгҒЁжіЁж„Ҹзҫ©еӢҷпјҲDuty of CareпјүгӮ’жҳҺзўәгҒ«иҰҸе®ҡгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®зҫ©еӢҷгҒ«йҒ•еҸҚгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒҜгҖҒдјҡзӨҫгӮ„ж Әдё»гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжҗҚе®іиі е„ҹиІ¬д»»гӮ’иІ гҒҶеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒж Әдё»гҒ®жЁ©еҲ©гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒзҙҜз©ҚжҠ•зҘЁпјҲCumulative VotingпјүеҲ¶еәҰгҒҢзҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гӮӮзү№еҫҙзҡ„гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒж Әдё»гҒҢдҝқжңүгҒҷгӮӢж ӘејҸж•°гҒ«еҝңгҒҳгҒҰиӨҮж•°гҒ®иӯ°жұәжЁ©гӮ’жҢҒгҒЎгҖҒгҒқгӮҢгӮ’зү№е®ҡгҒ®еҖҷиЈңиҖ…гҒ«йӣҶдёӯгҒ—гҒҰжҠ•зҘЁгҒ§гҒҚгӮӢеҲ¶еәҰгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҚҳиЁҳйқһжӢҳжқҹжҠ•зҘЁеҲ¶еәҰгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰгҖҒе°‘ж•°ж Әдё»гӮӮеҸ–з· еҪ№гӮ’йҒёд»»гҒҷгӮӢж©ҹдјҡгҒҢдҝқйҡңгҒ•гӮҢгҖҒе°‘ж•°ж„ҸиҰӢгҒҢеҸ–з· еҪ№дјҡгҒ«еҸҚжҳ гҒ•гӮҢгӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢM&AгҒЁеӨ–еӣҪдәәжҠ•иіҮиҰҸеҲ¶
жі•дәәиІ·еҸҺгҒ«й–ўгҒҷгӮӢдё»иҰҒгҒӘжі•еҫӢ
гғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢM&AпјҲеҗҲдҪөгғ»иІ·еҸҺпјүеҸ–еј•гҒҜгҖҒиӨҮж•°гҒ®дё»иҰҒгҒӘжі•еҫӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиҰҸеҲ¶гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдёӯеҝғгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒҜж”№жӯЈдјҡзӨҫжі•пјҲRepublic Act No. 11232пјүгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҗҲдҪөгӮ„дәӢжҘӯзөұеҗҲгҒ®жүӢз¶ҡгҒҚгӮ’е®ҡгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«еҠ гҒҲгҒҰгҖҒеӨ§иҰҸжЁЎгҒӘM&AеҸ–еј•гҒҜгғ•гӮЈгғӘгғ”гғіз«¶дәүжі•пјҲPhilippine Competition Act, R.A. No. 10667пјүгҒ®иҰҸеҲ¶еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҗҢжі•гҒҜгҖҒеҸ–еј•иҰҸжЁЎгҒҢдёҖе®ҡгҒ®еҹәжә–пјҲдҫӢпјҡ2025е№ҙ3жңҲ1ж—ҘжҷӮзӮ№гҒ§гҖҢSize of PersonгҖҚгҒҢ85е„„гғҡгӮҪгҖҒгҒӢгҒӨгҖҢSize of TransactionгҖҚгҒҢ35е„„гғҡгӮҪпјүгӮ’и¶…гҒҲгӮӢе ҙеҗҲгҖҒгғ•гӮЈгғӘгғ”гғіз«¶дәү委員дјҡпјҲPCCпјүгҒёгҒ®дәӢеүҚеұҠеҮәгҒЁжүҝиӘҚгӮ’зҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒйҒ•еҸҚгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒҜеҸ–еј•гҒҢз„ЎеҠ№гҒЁгҒӘгӮҠгҖҒеҸ–еј•йЎҚгҒ®жңҖеӨ§5%гҒ®зҪ°йҮ‘гҒҢ科гҒӣгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒдёҠе ҙдјҒжҘӯгҒ®M&AгҒ§гҒҜгҖҒиЁјеҲёиҰҸеҲ¶жі•пјҲSecurities Regulation Code, R.A. No. 8799пјүгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒе…¬й–ӢиІ·д»ҳгҒ‘пјҲTender OfferпјүгҒ®зҫ©еӢҷгҒҢз”ҹгҒҳгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еӨ–еӣҪдәәжҠ•иіҮгғҚгӮ¬гғҶгӮЈгғ–гғӘгӮ№гғҲ
гғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ®жі•еҫӢгҒҜгҖҒзү№е®ҡгҒ®з”ЈжҘӯгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеӨ–еӣҪдәәгҒ«гӮҲгӮӢжҠ•иіҮгӮ„еҮәиіҮжҜ”зҺҮгӮ’еҲ¶йҷҗгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®иҰҸеҲ¶гҒҜгҖҢеӨ–еӣҪдәәжҠ•иіҮгғҚгӮ¬гғҶгӮЈгғ–гғӘгӮ№гғҲпјҲForeign Investment Negative List, FINLпјүгҖҚгҒ«йӣҶзҙ„гҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жҠ•иіҮ家гҒҢM&AгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢдёҠгҒ§жңҖгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘжі•зҡ„еҲ¶зҙ„гҒ®дёҖгҒӨгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гғӘгӮ№гғҲгҒҜгҖҒеӨ–еӣҪдәәжҠ•иіҮгӮ’еҲ¶йҷҗгҒҷгӮӢдёҖж–№гҒ§гҖҒгҖҢдҪ•гҒҢиЁұгҒ•гӮҢгӮӢгҒӢгҖҚгҒ®жҳҺзўәгҒӘжҢҮйҮқгӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒжӣ–жҳ§гҒӘиҰҸеҲ¶гҒ®дёӢгҒ§жҠ•иіҮеҲӨж–ӯгӮ’иҝ«гӮүгӮҢгӮӢгӮҲгӮҠгӮӮгҖҒжҠ•иіҮ家гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰжі•зҡ„е®үе®ҡжҖ§гҒЁдәҲжё¬еҸҜиғҪжҖ§гӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒҷгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгғӘгӮ№гғҲгҒҜгҖҒжҶІжі•гӮ„зү№е®ҡгҒ®жі•еҫӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгғ•гӮЈгғӘгғ”гғіеӣҪж°‘гҒ«йҷҗе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢжҙ»еӢ•гӮ’еҲ—жҢҷгҒ—гҒҹгҖҢгғӘгӮ№гғҲAгҖҚгҒЁгҖҒеӣҪйҳІгӮ„е…¬иЎҶиЎӣз”ҹгғ»йҒ“еҫігҒ«й–ўйҖЈгҒҷгӮӢжҙ»еӢ•гӮ’еҲ—жҢҷгҒ—гҒҹгҖҢгғӘгӮ№гғҲBгҖҚгҒ®2гҒӨгҒ«еҲҶгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒеәғе‘ҠжҘӯгҒҜеӨ–еӣҪдәәгҒ®еҮәиіҮжҜ”зҺҮгҒҢ30%гҒ«гҖҒе…¬е…ұдәӢжҘӯгҒҜ40%гҒ«еҲ¶йҷҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®дјҒжҘӯгҒҢгҒ“гӮҢгӮүгҒ®еҲҶйҮҺгҒ®гғ•гӮЈгғӘгғ”гғіжі•дәәгӮ’иІ·еҸҺгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒиІ·еҸҺеҫҢгҒ®жҢҒгҒЎеҲҶжҜ”зҺҮгҒҢгҒ“гӮҢгӮүгҒ®дёҠйҷҗгӮ’и¶…гҒҲгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«жіЁж„Ҹж·ұгҒҸеҸ–еј•гӮ’иЁӯиЁҲгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒе…¬е…ұдәӢжҘӯгҒҜжҶІжі•дёҠгҒ®еҲ¶зҙ„гҒҢиӘІгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒиІ·еҸҺеҜҫиұЎгҒ®дәӢжҘӯеҶ…е®№гӮ’зІҫжҹ»гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮ
гғ•гӮЈгғӘгғ”гғідёҚеӢ•з”ЈжүҖжңүжЁ©гҒ®жі•зҡ„еҲ¶зҙ„
еӨ–еӣҪдәәгҒ®еңҹең°жүҖжңүгӮ’еҲ¶йҷҗгҒҷгӮӢжҶІжі•иҰҸе®ҡ
гғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ®дёҚеӢ•з”Јжі•гҒ§жңҖгӮӮзү№еҫҙзҡ„гҒӢгҒӨйҮҚиҰҒгҒӘзӮ№гҒҜгҖҒеӨ–еӣҪдәәгҒ«гӮҲгӮӢеңҹең°жүҖжңүгҒҢеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰзҰҒжӯўгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮгғ•гӮЈгғӘгғ”гғіжҶІжі•з¬¬12жқЎз¬¬7й …гҒҜгҖҒеңҹең°гҒ®жүҖжңүжЁ©гӮ’гғ•гӮЈгғӘгғ”гғіеӣҪж°‘гҖҒгҒҫгҒҹгҒҜж ӘејҸгҒ®60%д»ҘдёҠгӮ’гғ•гӮЈгғӘгғ”гғіеӣҪж°‘гҒҢжүҖжңүгҒҷгӮӢжі•дәәгҒ«йҷҗе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҺҹеүҮгҒҜгҖҒеӨ–еӣҪдәәгӮӮиҮӘз”ұгҒ«еңҹең°гӮ’иіје…ҘгҒ§гҒҚгӮӢж—Ҙжң¬гҒ®жі•еҫӢгҒЁж №жң¬зҡ„гҒ«з•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®жҶІжі•дёҠгҒ®еҲ¶зҙ„гҒҢгҖҒгғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеӨ–еӣҪдәәгҒ«гӮҲгӮӢдёҚеӢ•з”ЈжҠ•иіҮгҒ®ж…ЈиЎҢгӮ’еҪўжҲҗгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзӣҙжҺҘзҡ„гҒӘеңҹең°жүҖжңүгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒеӨ–еӣҪдәәгҒҜд»–гҒ®жі•зҡ„жүӢж®өгӮ’жЁЎзҙўгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҲ¶зҙ„гӮ’иҝӮеӣһгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеҗҲжі•зҡ„гҒ«дёҚеӢ•з”ЈгӮ’еҲ©з”Ёгғ»жҠ•иіҮгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®д»ЈжӣҝжүӢж®өгҒҢзҷәеұ•гҒ—гҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®зөҢе–¶иҖ…гҒҢеңҹең°гӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒҷгӮӢдәӢжҘӯпјҲе·Ҙе ҙе»әиЁӯгҒӘгҒ©пјүгӮ’иЎҢгҒҶе ҙеҗҲгҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®д»ЈжӣҝжүӢж®өгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еӨ–еӣҪдәәгҒ§гӮӮеҸҜиғҪгҒӘдёҚеӢ•з”ЈжҠ•иіҮж–№жі•
жҶІжі•дёҠгҒ®еҲ¶йҷҗгҒҢгҒӮгӮӢдёҖж–№гҒ§гҖҒеӨ–еӣҪдәәгҒҢеҗҲжі•зҡ„гҒ«гғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ®дёҚеӢ•з”ЈгҒ«жҠ•иіҮгҒҷгӮӢж–№жі•гҒҜиӨҮж•°еӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
- гӮігғігғүгғҹгғӢгӮўгғ гҒ®еҢәеҲҶжүҖжңүжЁ©пјҡеӨ–еӣҪдәәгҒҜгӮігғігғүгғҹгғӢгӮўгғ гҒ®еҢәеҲҶжүҖжңүжЁ©гӮ’100%жүҖжңүгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®гӮігғігғүгғҹгғӢгӮўгғ е…ЁдҪ“гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеӨ–еӣҪдәәжүҖжңүзҺҮгҒҢ40%д»ҘдёӢгҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶеҲ¶йҷҗгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
- й•·жңҹгғӘгғјгӮ№еҘ‘зҙ„пјҡеңҹең°гҒ®жүҖжңүжЁ©гҒҜеҫ—гӮүгӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒеӨ–еӣҪдәәгҒҜеңҹең°гӮ’жңҖй•·50е№ҙй–“гҖҒгҒ•гӮүгҒ«25е№ҙй–“гҒ®жӣҙж–°гҒҢеҸҜиғҪгҒЁгҒ„гҒҶй•·жңҹгҒ§гғӘгғјгӮ№гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж–№жі•гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеӨ–еӣҪдәәгҒҜеңҹең°гҒ®дёҠгҒ«е»әзү©гӮ’е»әгҒҰгҒҰжүҖжңүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
- жі•дәәиЁӯз«ӢгҒ«гӮҲгӮӢжүҖжңүпјҡеӨ–еӣҪиіҮжң¬гҒҢ40%д»ҘдёӢпјҲгғ•гӮЈгғӘгғ”гғіиіҮжң¬гҒҢ60%д»ҘдёҠпјүгҒ®ж ӘејҸдјҡзӨҫгӮ’иЁӯз«ӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®жі•дәәеҗҚзҫ©гҒ§еңҹең°гӮ’жүҖжңүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж–№жі•гҒҜгҖҒзҸҫең°гҒ®гғ‘гғјгғҲгғҠгғјгҒЁеҗҲејҒдәӢжҘӯгӮ’зө„гӮҖе ҙеҗҲгҒ«зү№гҒ«жңүеҠ№гҒ§гҒҷгҖӮ
гғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ®еҠҙеғҚжі•

гҖҢйӣҮз”Ёе®үе®ҡдҝқйҡңгҖҚгҒ®еҺҹеүҮ
гғ•гӮЈгғӘгғ”гғіеҠҙеғҚжі•пјҲLabor Code of the PhilippinesпјүгҒҜгҖҒеҠҙеғҚиҖ…гҒ®гҖҢйӣҮз”Ёе®үе®ҡдҝқйҡңпјҲSecurity of TenureпјүгҖҚгӮ’еј·гҒҸдҝқиӯ·гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜжҶІжі•дёҠгҒ®еҺҹеүҮгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҠҙеғҚжі•д»ҘдёҠгҒ«гҖҒе®үжҳ“гҒӘи§ЈйӣҮгӮ’иӘҚгӮҒгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶеј·гҒ„гӮ№гӮҝгғігӮ№гӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ§гҒҜгҖҢд»»ж„ҸйӣҮз”ЁпјҲAt-Will EmploymentпјүгҖҚгҒ®жҰӮеҝөгҒҢеӯҳеңЁгҒӣгҒҡгҖҒи§ЈйӣҮгҒҜеҺіж јгҒӘжі•зҡ„иҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒҷе ҙеҗҲгҒ«гҒ®гҒҝиЁұгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬гҒ®йӣҮз”Ёж…ЈиЎҢгҒ§гӮӮи§ЈйӣҮгҒҜж…ҺйҮҚгҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжі•зҡ„гҒ«гҒҜгҖҢи§ЈйӣҮжЁ©жҝ«з”Ёжі•зҗҶгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҲӨдҫӢжі•зҗҶгҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ§гҒҜгҖҢжӯЈеҪ“гҒӘзҗҶз”ұгҖҚпјҲJust CauseпјүгҒҫгҒҹгҒҜгҖҢжі•зҡ„жЁ©йҷҗгҒ®гҒӮгӮӢзҗҶз”ұгҖҚпјҲAuthorized CauseпјүгҒЁгҒ„гҒҶжҲҗж–Үжі•дёҠгҒ®еҺіж јгҒӘиҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒҷеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®зөҢе–¶иҖ…гҒҢжңҖгӮӮжіЁж„ҸгҒҷгҒ№гҒҚгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®и§ЈйӣҮиҰҒ件гҒ®еҺігҒ—гҒ•гҒ§гҒҷгҖӮе®үжҳ“гҒӘи§ЈйӣҮгҒҜгҖҢдёҚеҪ“и§ЈйӣҮпјҲIllegal DismissalпјүгҖҚгҒЁгҒҝгҒӘгҒ•гӮҢгҖҒжі•зҡ„гҒ«з„ЎеҠ№гҒЁгҒӘгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒи§ЈйӣҮгҒ•гӮҢгҒҹеҫ“жҘӯе“ЎгҒҜеҺҹиҒ·гҒёгҒ®еҫ©её°гҒЁгҖҒи§ЈйӣҮжҷӮгҒӢгӮүеҫ©её°жҷӮгҒҫгҒ§гҒ®жәҖйЎҚгҒ®иіғйҮ‘гғ»жүӢеҪ“гҒ®ж”Ҝжү•гҒ„гӮ’и«ӢжұӮгҒҷгӮӢжЁ©еҲ©гӮ’еҫ—гҒҫгҒҷгҖӮ
и§ЈйӣҮгҒ®гҖҢжӯЈеҪ“гҒӘзҗҶз”ұгҖҚгҒЁгҖҢжі•зҡ„жЁ©йҷҗгҒ®гҒӮгӮӢзҗҶз”ұгҖҚ
гғ•гӮЈгғӘгғ”гғіеҠҙеғҚжі•гҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®дәӢз”ұгӮ’и§ЈйӣҮгҒ®жӯЈеҪ“гҒӘзҗҶз”ұгҒЁгҒ—гҒҰе®ҡгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
- жӯЈеҪ“гҒӘзҗҶз”ұпјҲJust Causeпјүпјҡеҫ“жҘӯе“ЎгҒ®йҒҺеӨұгӮ„жӮӘж„ҸгҒ®гҒӮгӮӢиЎҢзӮәгҒ«гӮҲгӮӢи§ЈйӣҮгҒ§гҒҷгҖӮдҫӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒйҮҚеӨ§гҒӘдёҚжӯЈиЎҢзӮәгҖҒиҒ·еӢҷгҒ®йҮҚеӨ§гҒӘжҖ ж…ўгғ»еёёзҝ’зҡ„гҒӘжҖ ж…ўгҖҒйӣҮз”Ёдё»гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢи©җж¬әиЎҢзӮәгҒӘгҒ©гҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
- жі•зҡ„жЁ©йҷҗгҒ®гҒӮгӮӢзҗҶз”ұпјҲAuthorized Causeпјүпјҡеҫ“жҘӯе“ЎгҒ«йҒҺеӨұгҒҜгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒ®гҖҒзөҢе–¶дёҠгҒ®зҗҶз”ұгӮ„дёҚеҸҜжҠ—еҠӣгҒ«гӮҲгӮӢи§ЈйӣҮгҒ§гҒҷгҖӮдҫӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒзңҒеҠӣеҢ–иЈ…зҪ®гҒ®е°Һе…ҘгҖҒдәәе“ЎеүҠжёӣпјҲRedundancyпјүгҖҒдәӢжҘӯдёҚжҢҜгҒ«дјҙгҒҶдәәе“Ўж•ҙзҗҶпјҲRetrenchmentпјүгҖҒдәӢжҘӯгҒ®й–үйҺ–гҒӘгҒ©гҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®зҗҶз”ұгҒ§и§ЈйӣҮгӮ’иЎҢгҒҶе ҙеҗҲгҖҒйӣҮз”Ёдё»гҒҜгҖҒи§ЈйӣҮгҒ®еҝ…иҰҒжҖ§гӮ’иЁјжҳҺгҒҷгӮӢеҚҒеҲҶгҒӘиЁјжӢ пјҲиІЎеӢҷжӣёйЎһгҒӘгҒ©пјүгӮ’жҸҗзӨәгҒ—гҖҒиӘ е®ҹгҒӘжүӢз¶ҡгҒҚгӮ’иёҸгӮҖгҒ“гҒЁгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
жі•е®ҡеҠҙеғҚжҷӮй–“гҒЁзҰҸеҲ©еҺҡз”ҹ
гғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ®жі•е®ҡеҠҙеғҚжҷӮй–“гҒҜгҖҒ1ж—Ҙ8жҷӮй–“гҖҒйҖұ40жҷӮй–“гҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒж—Ҙжң¬гҒ«гҒҜгҒӘгҒ„зӢ¬иҮӘгҒ®зҰҸеҲ©еҺҡз”ҹеҲ¶еәҰгҒҢзҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжңҖгӮӮд»ЈиЎЁзҡ„гҒӘгҒ®гҒҢгҖҢ13гғ¶жңҲжүӢеҪ“пјҲ13th Month PayпјүгҖҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒйӣҮз”Ёдё»гҒҜеҫ“жҘӯе“ЎгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒ1е№ҙй–“гҒ®еҹәжң¬зөҰгҒ®12еҲҶгҒ®1д»ҘдёҠгҒ®йҮ‘йЎҚгӮ’е№ҙжң«гҒҫгҒ§гҒ«ж”Ҝжү•гӮҸгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ“гҒ®еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒе№ҙжң«гғңгғјгғҠгӮ№гҒЁгҒҜеҲҘгҒ«жі•еҫӢгҒ§зҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ§дәӢжҘӯгӮ’иЎҢгҒҶдёҠгҒ§еҝ…й ҲгҒ®гӮігӮ№гғҲгҒЁгҒ—гҒҰиӘҚиӯҳгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ®еәғе‘ҠиҰҸеҲ¶гҒЁж¶ҲиІ»иҖ…дҝқиӯ·жі•еҲ¶
ж¶ҲиІ»иҖ…дҝқиӯ·жі•гҒЁиҮӘдё»иҰҸеҲ¶
гғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ«гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жҷҜе“ҒиЎЁзӨәжі•гҒ«зӣёеҪ“гҒҷгӮӢж¶ҲиІ»иҖ…дҝқиӯ·жі•пјҲConsumer Act of the Philippines, R.A. No. 7394пјүгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮеҗҢжі•гҒҜгҖҒе•Ҷе“ҒгҒ®жҖ§иіӘгҖҒзү№еҫҙгҖҒе“ҒиіӘгҖҒдҫЎж јгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰж¶ҲиІ»иҖ…гӮ’иӘӨи§ЈгҒ•гҒӣгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘиҷҡеҒҪгҒҫгҒҹгҒҜж¬әзһһзҡ„гҒӘеәғе‘ҠгӮ’зҰҒжӯўгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж”ҝеәңж©ҹй–ўгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒиІҝжҳ“з”ЈжҘӯзңҒпјҲDTIпјүгҒҢж¶ҲиІ»иҖ…гҒӢгӮүгҒ®иӢҰжғ…гӮ’еҸ—гҒ‘д»ҳгҒ‘гҖҒиӘҝжҹ»гғ»иӘҝеҒңгғ»иЈҒе®ҡгӮ’иЎҢгҒҶжЁ©йҷҗгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒжҘӯз•ҢгҒ®иҮӘдё»иҰҸеҲ¶ж©ҹй–ўгҒ§гҒӮгӮӢеәғе‘Ҡеҹәжә–и©•иӯ°дјҡпјҲAd Standards Council, ASCпјүгҒҢзӢ¬иҮӘгҒ®гӮ¬гӮӨгғүгғ©гӮӨгғігӮ’зӯ–е®ҡгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒдјҡе“ЎдјҒжҘӯгҒҜгҒ“гӮҢгҒ«еҫ“гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ§гҒҜгҖҒж”ҝеәңж©ҹй–ўгҒ«гӮҲгӮӢеј·еҲ¶еҠӣгҒ®гҒӮгӮӢжі•иҰҸеҲ¶гҒЁгҖҒжҘӯз•ҢгҒ®иҮӘдё»иҰҸеҲ¶ж©ҹй–ўгҒ«гӮҲгӮӢгӮ¬гӮӨгғүгғ©гӮӨгғігҒҢдҪөеӯҳгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®жҘӯз•ҢеӣЈдҪ“гҒ«гӮҲгӮӢиҮӘдё»иҰҸеҲ¶гҒҢжі•зҡ„гҒӘеј·еҲ¶еҠӣгӮ’жҢҒгҒҹгҒӘгҒ„гҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ§гҒҜASCгҒёгҒ®иӢҰжғ…гҒҢж”ҝеәңж©ҹй–ўгҒ®иӘҝжҹ»гҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒеәғе‘ҠгӮ’еҮәгҒҷдјҒжҘӯгҒҜгҖҒжі•зҡ„гҒӘиҰҸеҲ¶гҒ«еҠ гҒҲгҒҰгҖҒASCгҒ®гӮ¬гӮӨгғүгғ©гӮӨгғігҒ«гӮӮйҒ•еҸҚгҒҢгҒӘгҒ„гҒӢгӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
и–¬ж©ҹжі•гғ»еҢ»зҷӮеәғе‘ҠгӮ¬гӮӨгғүгғ©гӮӨгғі
еҢ»и–¬е“ҒгҖҒеҢ»зҷӮж©ҹеҷЁгҖҒеҢ–зІ§е“ҒгҒӘгҒ©гҒ®еәғе‘ҠгҒҜгҖҒйЈҹе“ҒеҢ»и–¬е“ҒеұҖпјҲFood and Drug Administration, FDAпјүгҒ®еҺіж јгҒӘиҰҸеҲ¶гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҫгҒҷгҖӮжңӘзҷ»йҢІгғ»жңӘиӘҚеҸҜгҒ®иЈҪе“ҒгҒ®еәғе‘ҠгҒҜзҰҒжӯўгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеәғе‘ҠеҶ…гҒ®еҠ№жһңеҠ№иғҪгҒ«й–ўгҒҷгӮӢдё»ејөгҒҜгҖҒFDAгҒҢжүҝиӘҚгҒ—гҒҹеҶ…е®№гҒ«йҷҗгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеҮҰж–№и–¬гҒҜгҖҒеҢ»зҷӮеҫ“дәӢиҖ…еҗ‘гҒ‘гҒ®е°Ӯй–ҖиӘҢгҒӘгҒ©гҒ®зү№е®ҡгҒ®еӘ’дҪ“д»ҘеӨ–гҒ§дёҖиҲ¬еҗ‘гҒ‘гҒ«еәғе‘ҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜзҰҒгҒҳгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»и–¬е“Ғеәғе‘ҠгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиҰҸеҲ¶гҒ§жңҖгӮӮйЎ•и‘—гҒӘзү№еҫҙгҒҜгҖҒеҫҢзҷәеҢ»и–¬е“ҒпјҲгӮёгӮ§гғҚгғӘгғғгӮҜпјүгҒ®еҗҚз§°гӮ’гғ–гғ©гғігғүеҗҚгӮҲгӮҠзӣ®з«ӢгҒҹгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒеҚҳгҒ«иҷҡеҒҪеәғе‘ҠгӮ’йҳІгҒҗгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒеӣҪж°‘гҒҢе®үдҫЎгҒӘеҫҢзҷәеҢ»и–¬е“ҒгӮ’йҒёжҠһгҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҢ»зҷӮиІ»гҒ®иІ жӢ…гӮ’и»ҪжёӣгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж”ҝеәңгҒ®жҳҺзўәгҒӘж”ҝзӯ–зҡ„ж„ҸеӣігҒҢеҸҚжҳ гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜгҖҒеҢ»и–¬е“ҒгҒ®гғ–гғ©гғігғүеҗҚгҒҢеүҚйқўгҒ«еҮәгӮӢеәғе‘ҠгҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ§гҒҜгҒ“гҒ®зӮ№гҒҢеҺіж јгҒ«иҰҸеҲ¶гҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеәғе‘ҠгҒ®гӮҜгғӘгӮЁгӮӨгғҶгӮЈгғ–гӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢдёҠгҒ§йҮҚиҰҒгҒӘз•ҷж„ҸзӮ№гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ§иЁұиӘҚеҸҜгӮ’иҰҒгҒҷгӮӢдәӢжҘӯгҒЁжі•еӢҷдёҠгҒ®з•ҷж„ҸзӮ№
дәӢжҘӯзҷ»йҢІжүӢз¶ҡгҒҚгҒЁдё»иҰҒгҒӘиЁұиӘҚеҸҜж©ҹй–ў
гғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ§дәӢжҘӯгӮ’е§ӢгӮҒгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒиӨҮж•°гҒ®ж”ҝеәңж©ҹй–ўгҒ§гҒ®зҷ»йҢІгғ»иЁұиӘҚеҸҜгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҡгҖҒж ӘејҸдјҡзӨҫгҒҜиЁјеҲёеҸ–引委員дјҡпјҲSECпјүгҒ«гҖҒеҖӢдәәдәӢжҘӯдё»гҒҜиІҝжҳ“з”ЈжҘӯзңҒпјҲDTIпјүгҒ«гҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢдәӢжҘӯеҗҚгҒЁжі•дәәеҗҚгӮ’зҷ»йҢІгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮиҝ‘е№ҙгҖҒSECгҒҜеӨ–еӣҪдјҒжҘӯгӮ’еҗ«гӮҖжі•дәәгҒ®зҷ»йҢІгӮ’1ж—ҘгҒ§е®ҢдәҶгҒ•гҒӣгӮӢгӮӘгғігғ©гӮӨгғігӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҢOneSECгҖҚгӮ’е°Һе…ҘгҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒжүӢз¶ҡгҒҚгҒ®еҠ№зҺҮеҢ–гӮ’йҖІгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж¬ЎгҒ«гҖҒдәӢжҘӯжүҖгӮ’зҪ®гҒҸеҗ„ең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“пјҲLGUпјүгҒӢгӮүгҖҒгғҗгғ©гӮ¬гғігғ»гӮҜгғӘгӮўгғ©гғігӮ№пјҲBarangay ClearanceпјүгҒЁеёӮй•·иЁұеҸҜиЁјпјҲMayor’s Permit / Business PermitпјүгӮ’еҸ–еҫ—гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
зү№е®ҡгҒ®дәӢжҘӯгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгҒ•гӮүгҒ«еҖӢеҲҘгҒ®иЁұиӘҚеҸҜгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
- иіҮйҮ‘жұәжёҲгӮөгғјгғ“гӮ№пјҡгғ•гӮЈгғігғҶгғғгӮҜдјҒжҘӯгҒӘгҒ©гҖҒиіҮйҮ‘жұәжёҲгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢдәӢжҘӯгҒҜгҖҒгғ•гӮЈгғӘгғ”гғідёӯеӨ®йҠҖиЎҢпјҲBangko Sentral ng Pilipinas, BSPпјүгҒҢзӣЈзқЈгҒҷгӮӢиіҮйҮ‘жұәжёҲгӮ·гӮ№гғҶгғ жі•пјҲNational Payment Systems Act, R.A. No. 11127пјүгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒдәӢеүҚгҒ®иЁұиӘҚеҸҜгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
- жө·дәӢз”ЈжҘӯпјҡжө·дәӢз”ЈжҘӯгҒҜгҖҒжө·дәӢз”ЈжҘӯеәҒпјҲMaritime Industry Authority, MARINAпјүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиҰҸеҲ¶гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҗҢеәҒгҒҜгҖҒиҲ№иҲ¶гҒ®зҷ»йҢІгҖҒдәӢжҘӯиҖ…гҒ®е…ҚиЁұд»ҳдёҺгҖҒжө·дәӢе®үе…Ёеҹәжә–гҒ®ж–ҪиЎҢгҒӘгҒ©гӮ’жӢ…гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
е„ӘйҒҮжҺӘзҪ®гҒЁгӮӨгғігӮ»гғігғҶгӮЈгғ–
гғ•гӮЈгғӘгғ”гғізөҢжёҲеҢәеәҒпјҲPEZAпјүгӮ„жҠ•иіҮ委員дјҡпјҲBOIпјүгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж”ҝеәңж©ҹй–ўгҒ«дәӢжҘӯгӮ’зҷ»йҢІгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеӨ–еӣҪдјҒжҘӯгҒҜеӨ§е№…гҒӘзЁҺеҲ¶е„ӘйҒҮжҺӘзҪ®пјҲгӮҝгғғгӮҜгӮ№гғ»гғӣгғӘгғҮгғјгӮ„зү№еҲҘжі•дәәжүҖеҫ—зЁҺгҒӘгҒ©пјүгӮ„йқһзЁҺеҲ¶дёҠгҒ®гӮӨгғігӮ»гғігғҶгӮЈгғ–пјҲеӨ–еӣҪдәәгҒ®йӣҮз”ЁиЁұеҸҜгҖҒгғ“гӮ¶еҸ–еҫ—ж”ҜжҸҙгҒӘгҒ©пјүгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
PEZAгҒЁBOIгҒ®гӮӨгғігӮ»гғігғҶгӮЈгғ–гҒҜдјјгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«иҰӢгҒҲгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®зӣ®зҡ„гҒЁйҒ©з”ЁиҰҒ件гҒҢеӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮPEZAгҒҜгҖҒијёеҮәеҝ—еҗ‘еһӢгҒ®дјҒжҘӯгӮ„ITгғ»BPOдјҒжҘӯгҒӘгҒ©гҖҒзү№е®ҡгҒ®з”ЈжҘӯгҒ«зү№еҢ–гҒ—гҖҒзөҢжёҲзү№еҢәпјҲгӮЁгӮігӮҫгғјгғіпјүеҶ…гҒ§гҒ®дәӢжҘӯеұ•й–ӢгӮ’еүҚжҸҗгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдёҖж–№гҖҒBOIгҒҜгҖҒеӣҪеҶ…еёӮе ҙеҝ—еҗ‘гҒ®жҲҰз•Ҙзҡ„гҒӘз”ЈжҘӯгӮ’еҗ«гӮҖгҖҒгӮҲгӮҠе№…еәғгҒ„дәӢжҘӯгӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҖҒе ҙжүҖгҒ®еҲ¶зҙ„гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ©гҒЎгӮүгҒ®ж©ҹй–ўгҒ«зҷ»йҢІгҒҷгӮӢгҒӢгҒҜгҖҒеҚҳгҒ«зЁҺйҮ‘гҒ®е•ҸйЎҢгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒдәӢжҘӯгҒ®жҖ§иіӘгҖҒеҜҫиұЎеёӮе ҙгҖҒз«Ӣең°жҲҰз•ҘгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгғ“гӮёгғҚгӮ№гғўгғҮгғ«е…ЁдҪ“гҒ«й–ўгӮҸгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘж„ҸжҖқжұәе®ҡгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒијёеҮәиЈҪйҖ жҘӯгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°PEZAгҖҒгғ•гӮЈгғӘгғ”гғіеӣҪеҶ…еёӮе ҙеҗ‘гҒ‘гҒ«иЈҪе“ҒгӮ’иІ©еЈІгҒҷгӮӢдәӢжҘӯгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°BOIгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒдәӢжҘӯиЁҲз”»гҒ«еҝңгҒҳгҒҰжңҖйҒ©гҒӘйҒёжҠһгӮ’иЎҢгҒҶеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒ
жң¬зЁҝгҒ§и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒгҒқгҒ®жӯҙеҸІзҡ„иғҢжҷҜгҒӢгӮүж—Ҙжң¬гҒ®гҒқгӮҢгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢзӢ¬иҮӘгҒ®иҰҒзҙ гӮ’еӨҡгҒҸеҗ«гӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒеӨ–еӣҪдәәгҒ®еңҹең°жүҖжңүеҲ¶йҷҗгҖҒеҠҙеғҚиҖ…гҒ®и§ЈйӣҮиҰҒ件гҒ®еҺіж јгҒ•гҖҒеҢ»и–¬е“Ғеәғе‘ҠгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮёгӮ§гғҚгғӘгғғгӮҜеҗҚз§°гҒ®иҰҸеҲ¶гҖҒгҒқгҒ—гҒҰеӨҡеұӨзҡ„гҒӘдәӢжҘӯиЁұиӘҚеҸҜгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒӘгҒ©гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®е•Ҷзҝ’ж…ЈгӮ„жі•еӢҷж„ҹиҰҡгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘзӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®йҒ•гҒ„гӮ’дәӢеүҚгҒ«жҠҠжҸЎгҒ—гҖҒе°Ӯй–Җзҡ„гҒӘжі•еӢҷиӘҝжҹ»гҒЁйҒ©еҲҮгҒӘжүӢз¶ҡгҒҚгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒгғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ§гҒ®гғ“гӮёгғҚгӮ№гӮ’жҲҗеҠҹгҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®йҚөгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ«гғҶгӮҙгғӘгғј: ITгғ»гғҷгғігғҒгғЈгғјгҒ®дјҒжҘӯжі•еӢҷ