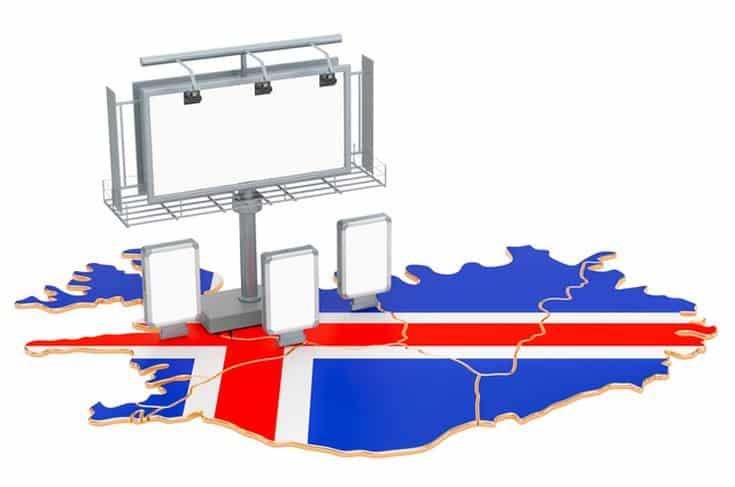ブラジルの海事法・海商法の解説
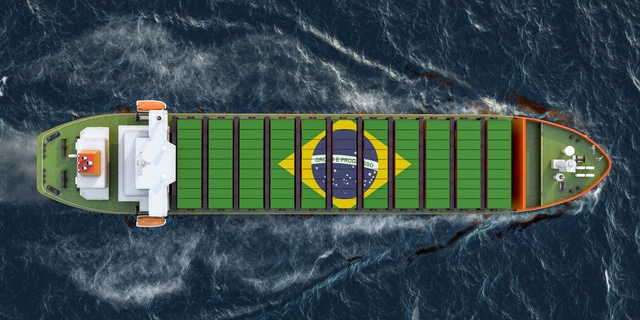
ブラジル(正式名称、ブラジル連邦共和国)は、広大な海岸線と豊かな天然資源を背景に、海事・海運分野において極めて重要な市場です。しかし、この巨大な市場でのビジネス展開を検討する日本企業にとって、同国の海事法・海商法は、日本法とは異なる独特の法的構造を有しており、その理解は事業リスクを管理する上で不可欠です。
本記事では、ブラジルの海事法・海商法がどのような法源から成り立っているのかを概観しつつ、特に日本法とは異なる「内航海運の規制緩和」「船主責任制限」「船舶登録制度」「海事先取特権」「海事裁判所の役割」といった五つの主要な論点に焦点を当てて、その法的特徴と実務上の注意点を包括的に解説します。近年、同国で成立した画期的な法改正「BR do Mar」プログラムなど、最新の動向も踏まえ、ブラジル進出に際しての戦略立案の一助となることを目指します。
なお、ブラジルの包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。
この記事の目次
ブラジル海事法・海商法の法源と全体像
ブラジル海事法の法体系は、複数の異なる時代と性質の法源が複雑に絡み合う、極めて特異な構造を有しています。その主要な根拠は、驚くべきことに、1850年に制定された旧ブラジル商法典(Brazilian Commercial Code of 1850)の海事関連規定に由来しており、この規定は、2002年の民法典(Civil Code of 2002)によって一部が廃止されたものの、海事分野では現在も効力を維持しています。この旧商法典に加えて、ブラジルが批准したごく少数の国際条約や、個別法、政令が法体系を構成しています。
ブラジル法の特徴として、国際的な海事条約の多くを批准していない点が挙げられます。例えば、海事債権の責任制限に関する分野では、日本を含む多くの国が採用している1976年LLMC条約(Convention on the Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976)ではなく、1924年のブリュッセル条約(International Convention for the Unification of Certain Rules relating to the Limitation of the Liability of Owners of Sea-going Vessels, 1924)に依拠しています。こうした国際的な枠組みへの非加盟は、国際的なプレイヤーや投資家にとっての不確実性を生み出し、ブラジルの海事分野がその潜在能力を十分に発揮することを阻害する一因となっているという指摘もなされています。
しかし、近年、この旧来の法体系を刷新し、市場を活性化させるための動きが活発化しています。新たな商法典の制定に向けた議論が進められる中で、2022年1月には、Law No. 14,301、通称「BR do Mar」と呼ばれる画期的な法律が制定されました。これは、ブラジル国内の内航海運(カボタージュ)を刺激し、規制を大幅に緩和することを目的としています。このような個別法の登場は、古い国内法と現代の国際ルールが混在する静的な法体系から、市場のニーズに応じた動的な法改正が行われる、ブラジル海事法における新たなトレンドを示しています。
日本法が、統一された商法典や国際条約に基づいて比較的整合性の高い体系を構築しているのに対し、ブラジルの法体系は、時代も性質も異なる複数の法源が「パッチワーク」のように組み合わさっている点が根本的に異なります。この非統一性が、国際的なビジネスを行う上で予測不可能性と法的リスクを増大させている主要な要因であると言えます。したがって、ブラジルでの海事ビジネスを検討する際には、単一の法体系を前提とせず、個別の事案ごとに適用される可能性のあるすべての法源を網羅的に検討し、専門家による助言を得ることが不可欠となります。
ブラジル内航海運(カボタージュ)の規制緩和

ブラジル国内の港間を結ぶ海上輸送、すなわち内航海運(カボタージュ)は、長らく旧法Law No. 9,432/1997によって厳格に規制されてきました。この旧法下では、裸用船(Bareboat Charter)はブラジル籍の船舶を保有する企業に限定されており、外国籍船舶の市場への参入は極めて困難な状況でした。これは、内航海運への参入には、ブラジル籍の船舶を所有・建造する必要があることを意味し、莫大な初期投資と、外国籍船舶の定期用船(Time Charter)に比べて最大で70%も高い運航コストを要するため、新規参入の大きな障壁となっていました。
この状況を打開するため、2022年1月に制定されたのが「BR do Mar」プログラム(Law No. 14,301/2022)です。この新法は、内航海運市場への参入障壁を意図的に取り除くことを目的としており、外国籍船舶の用船に関する規制を大幅に緩和しました。その最大の変更点は、段階的な移行措置を経て、ブラジル籍の船舶を所有していなくとも、外国籍船舶を裸用船契約でチャーターすることが可能になったことです。さらに、ブラジル籍の船会社(EBN)は、自社の完全子会社である外国法人の所有する船舶を定期用船することも認められました。
この法改正は、ブラジル内航海運市場への参入を検討している日本企業にとって、極めて重要な戦略的機会をもたらします。自社で高価な船舶を所有することなく、既存の外国籍船舶を柔軟に用船して事業を開始できるようになったからです。これにより、資本的リスクを抑えつつ、ブラジル市場の巨大な潜在力にアクセスすることが可能となります。一方で、外国籍船舶を内航海運に参入させる場合、その船舶がブラジル海事当局が定める安全基準を満たしている必要があります。そのため、事業計画の段階から、規制当局との連携や、現地の専門知識を持つパートナーの確保が重要であると言えるでしょう。
ブラジル船舶の登録制度
ブラジルにおける船舶の登録制度は、日本とは異なり、「Inscrição(登録)」と「Registro(登記)」という二つの異なる概念で運用されている点が特徴的です。
- Inscrição(登録):すべてのブラジル籍のレクリエーション用・スポーツ用船舶は、海軍港務局(Capitanias, Delegacias, Agências da Marinha do Brasil)への登録が義務付けられています。この手続きが完了すると、「Título de Inscrição de Embarcação (TIE)」という文書が発行されます。
- Registro(登記):一方で、大型船舶(レクリエーション用でも全長24メートル以上、総トン数(AB)100トン超のヨットなど)は、海事裁判所(Tribunal Marítimo)での登記が義務付けられます。この手続きにより、「Provisão de Registro de Propriedade Marítima (PRPM)」が発行されます。海事裁判所は、船舶の所有権、抵当権、その他の先取特権に関する公的な記録を維持管理する役割を担っています。
日本法においては、船舶の所有権や抵当権は、法務局が管理する登記簿によって一元的に公示されます。しかし、ブラジルではInscriçãoとRegistroという異なる機関による二重の制度が存在し、特に大型船舶の所有権や担保権は海事裁判所が管理している点が大きな違いです。この二重構造は、船舶取引や担保設定を行う際に、より複雑な手続きを要求します。単に「登録」が完了したと認識するだけでなく、所有権や担保権の保護を確保するため、海事裁判所での「登記」手続きを正確に実施することが、法的リスクを回避する上で不可欠であると言えるでしょう。
ブラジル海事先取特権と船舶の差押え(アレスト)
ブラジルにおける海事先取特権(Maritime Lien)は、主に1850年旧商法典(Articles 470 and 471)と、ブラジルが批准している1926年ブリュッセル条約(International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to Maritime Liens and Mortgages of 1926)に基づいて規定されています。これらの法令は、船舶の差押え(Arrest)を可能にする「特権的債権」を列挙しています。具体的には、国への租税、船員の給与、船舶の維持費、貨物の滅失・損害に関する債務、サルベージ費用、海難救助に関する債権などが含まれます。これらの債権は物権的効力(in rem effects)を有するため、債務者が誰であるかに関わらず、船舶そのものに対して差押えが可能です。
日本法にも船舶先取特権が存在しますが、その対象となる債権の範囲に違いがあります。日本の商法では、人命や身体の侵害による損害賠償請求権が筆頭に挙げられている一方で、ブラジル法では「貨物の滅失・損害」「サルベージ費用」「海難事故による債権」などが明示されている点が特徴的です。このように両国で特権が認められる債権の範囲が異なるため、貨物輸送や船舶運航でトラブルが発生した際、どちらの法が適用されるかによって、債権回収の優先順位や差押えの可否が大きく変わってきます。ブラジルでの債権保全を考える際には、自社の債権がブラジル法上の「特権的債権」に該当するかどうかを事前に精査することが極めて重要となります。
ブラジル商法典第482条は、外国籍船舶の差押えを制限しており、原則として、差押えはブラジル国内で発生した海事先取特権に基づくもの、または海外で発生したものであってもブラジル国内で強制執行可能な権利に基づくものに限定されます。
ブラジルの船主責任制限
船主責任制限(Limitation of Liability)は、海難事故による船主の賠償責任額を、船舶のトン数に応じて一定額に制限する国際的に広く採用されている制度です。しかし、ブラジルは国際海事機関(IMO)が主導する主要な責任制限条約を批准しておらず、同国が依拠しているのは、1924年のブリュッセル船主責任制限条約と、タンカーによる油濁損害に関する1969年CLC条約のみです。
一方、日本が依拠しているのは、より現代的で、責任限度額が大幅に引き上げられている1976年海事債権についての責任の制限に関する条約(LLMC)とその1996年議定書です。
この制度的な違いは、日本企業にとって極めて重要です。1924年ブリュッセル条約では、責任限度額は「トン当たり8ポンドスターリング」で計算されるのに対し、1976年LLMC条約は「特別引出権(SDR)」という国際的な通貨単位で計算され、その限度額は定期的に引き上げられています。日本の法制度は、世界の主流に沿って、被害者保護の観点から責任限度額を大幅に引き上げる方向で進化してきたことがわかります。
| ブラジル | 日本 | |
|---|---|---|
| 適用法源 | 1924年ブリュッセル条約(トン当たり8ポンドスターリング) | 1976年LLMC条約・1996年議定書(特別引出権SDR) |
| 責任限度額の考え方 | 賠償責任総額は、船舶のトン数に応じて算出 | 責任限度額は、船舶のトン数に応じて段階的に計算される |
| 賠償額(参考)(貨物損害等) | トン当たり8ポンドスターリング | 2,000トン以下の船舶:約4.53百万SDR |
この表から、ブラジルで海難事故が発生した場合、適用される責任限度額が日本の基準よりもはるかに低くなる可能性があることが理解できます。これは、一見、船主にとって有利に見えますが、同時に、訴訟において被害者が責任制限を突き崩そうとするリスクを高めることにもつながります。したがって、ブラジルでのオペレーションを計画する際には、現地の法的枠組みに合わせた適切な保険(P&I保険など)の付保や、リスクマネジメント戦略を再構築することが不可欠となります。
ブラジル海事裁判所の役割

ブラジル海事裁判所(Tribunal Marítimo)は、司法機関ではなく、国防省傘下の海軍司令部に属する行政機関です。しかし、その有機法(Law No. 2,180/1954)によれば、海難事故や海事関連事案の審理を行う際に「判断的な性格」を帯び、当事者主義と弁論主義が尊重されます。このため、その判決は「準司法的」な性質を持つと解釈されています。
海事裁判所の判決は、技術的事項に関する限り、「証拠的価値(probative value)」を有し、その内容が正確であると推定されます。さらに、ブラジル民事訴訟法第313条第7項は、海難事故に関連する民事訴訟が提起された場合、海事裁判所の判断を待つために訴訟手続きを一時停止することができると定めています。
日本法における海難審判所は、海難の原因を究明し、その結果を懲戒処分に結びつける純粋な行政機関であり、損害賠償などの民事紛争はすべて一般の裁判所が管轄します。ブラジルの海事裁判所は、行政機関でありながら、民事裁判に影響力を持つという点で、日本には存在しない特異な地位にあります。このハイブリッドな性質は、複雑な訴訟構造を生み出します。したがって、ブラジルで海難事故に遭遇した場合、日本企業は、刑事・民事の裁判所手続きと並行して、この海事裁判所での調査手続きにも対応する必要があるということになります。海事裁判所の判断は、その後の民事訴訟における賠償責任の有無や範囲に大きな影響を及ぼす可能性があるため、初期段階から専門家を介して慎重に対応することが、全体的なリスクを低減する上で不可欠です。
まとめ
ブラジルの海事法・海商法は、1850年の旧商法典と国際条約、そして近年の市場活性化を目的とした新法が複雑に絡み合う、独自の法体系を形成しています。特に、国際的なスタンダードとは異なる船主責任制限制度や、行政機関でありながら準司法的機能を持つ海事裁判所の存在は、日本の実務経験者にとって大きな違いとして認識しておくべき点です。
近年成立した「BR do Mar」プログラムは、内航海運市場への参入障壁を劇的に引き下げ、日本企業に新たなビジネスチャンスをもたらす一方で、その法務戦略の立案には現地の法的・実務的課題に対する深い理解が求められます。
ブラジルでの海事関連ビジネスを検討する際には、こうした複雑な法的構造を正確に理解し、予期せぬリスクを回避するための適切な法的支援が不可欠です。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務