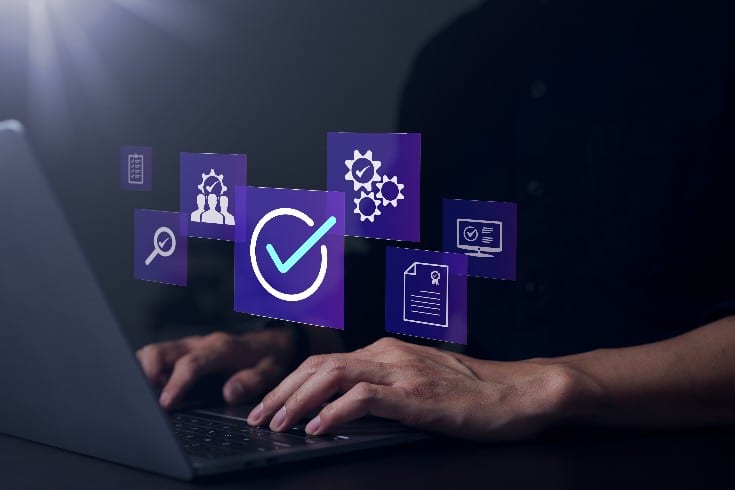デンマークの契約法解説:日本法との違いとビジネス上の留意点

北欧のデンマーク王国(以下、デンマーク)は、自由で効率的な市場として知られていますが、その契約法体系は、日本とは異なる独特なバランスの上に成り立っています。基盤となるのは、契約締結、期限、権利、終了など、財産法分野における法的取引の基本的な側面を規定する「契約法」(Aftaleloven)です。この法律は、当事者の自由な意思決定を尊重する「契約自由の原則」を中核に据えながらも、「不合理な契約条項を修正・無効化できる広範な司法介入の仕組み」や、「労働者の権利を強力に保護する強制法規」という、日本法に比して遥かに厳格なガードレールを設けています。
特に、契約が無効となる可能性がある場合の要件や、従業員に競業避止義務を課す際の高額な強制補償義務は、デンマークでのビジネス展開を検討される日本の経営者や法務部員の方々にとって、決定的な違いとして理解しておく必要があります。本稿では、デンマーク契約法の中核であるAftalelovenと、特に強制法規が適用される労働契約に焦点を当て、日本法との異同を交えながらその特徴を解説します。
この記事の目次
デンマーク契約法の法源と基盤原則
契約自由の原則と「誠実義務」の役割
デンマークは、統一された民法典を持たない大陸法とコモンローのハイブリッド的な法域であり、その契約法は個別の制定法と判例法によって形成されています。その中でも、Aftaleloven(契約法)が一般原則を定める主要な制定法です。契約法における最上位の原則は「契約の自由」であり、「合意は拘束する」(Pacta sunt servanda)という大原則がこれを裏付けています。商事契約においては特にこの自由主義的なアプローチが顕著であり、契約審査の出発点となるのは、当事者の当初の意図、すなわち「意思の合致」(meeting of the wills)を確認することです。
一方で、この契約自由の原則は、ノルディック法に特有の「誠実義務」、または「忠実義務」(Lojalitet)の原則によって調整されています。これは、契約当事者が相手方の利益を考慮に入れる一般的な義務を指し、契約の形成段階から履行段階まで広く適用されると解されています。このLojalitetの原則は、後に解説するAftaleloven第36条の一般条項において最も明確に表現されており、契約形式上の欠陥だけでなく、公平性や関係性への配慮に基づいて、裁判所が契約に介入するための重要な法的根拠となっています。
デンマークの契約成立における日本の法理との相違点
Aftaleloven第1部(Conclusion of Contracts)は、契約成立に関する基本的なルールを定めていますが、日本の民法が定めるルールとは、特に「申し込みの拘束力」の点で重要な違いがあります。
申し込みの不可撤回性と「契約拘束力」
Aftaleloven第1条は、「申し込み及び承諾の返答は、それらを行った者を拘束する」と規定しています。これは、申込者が承諾のための期間を定めた場合、承諾期間中はその申し込みが撤回不可能となる、大陸法的な「申し込みの不可撤回性」を意味します。
これは、日本の民法が定める「隔地者に対する申込みは、撤回の意思表示をしても、その効力を生じない」(民法521条第1項、承諾期間を定めた場合)という規定と類似しているようにも見えますが、デンマーク法は、申し込みがなされた時点で、その意思表示自体が相手方を拘束する力を持つという点で、日本の法理よりも申込者に厳格な姿勢を要求します。これにより、承諾期間中のリスクは基本的に全面的に申込者に割り当てられ、相手方(被承諾者)の信頼利益が強く保護されることになります。
遅延した承諾に対する申込者の「通知義務」
承諾期間を徒過して遅延した承諾は、原則として新たな「対抗申し込み」(カウンター・オファー)と見なされ、契約は成立しません(Aftaleloven第4条第1項)。これは日本法と変わらない原則です。
しかし、Aftalelovenには、「誠実義務」に基づく非常に重要な例外規定が設けられています(第4条第2項)。
「承諾の送付者が、それが適時に受領されたと信じる場合であり、かつ、申込者がその事実を認識していなければならない場合ではないときは、この限りではない。このような場合において、申込者がその返答を受諾する意図がないときは、申込者は遅滞なく承諾の送付者に対しその旨を通知しなければならない。申込者がこれに反したときは、契約は成立したものと見なされる。」(Aftaleloven第4条第2項、意訳)
これは、承諾者が「間に合った」と善意で誤解していることを申込者が知っている、または知るべき場合、申込者は、契約を拒否したいのであれば、自ら積極的に通知しなければならないという義務(通知義務:Reklamationspligt)を課すものです。申込者がこの通知を怠った場合(沈黙した場合)、契約が成立したものと見なされます。
日本の法制度では、通常、遅延した承諾に対して申込者が積極的に拒否する義務を負うことはありません。このデンマーク法の規定は、契約成立の過程においても誠実な取引を強制するLojalitet原則の直接的な現れであり、日本の経営者や法務部員の方々がデンマークでの取引において特に注意すべき、法理上の重要な違いです。
デンマーク司法による介入と契約の修正・無効化(Aftaleloven第36条)

Aftaleloven第36条は、契約の自由原則に対する最も強力で広範な制限を提供する、司法審査のツールであり、日本法との最も決定的な違いの一つです。
§ 36が定める「不合理性」の広範な審査権限
「契約は、その履行が不合理であるか、または誠実義務の原則と矛盾する場合、全体または一部が修正または無効とされることがある。その他の法律行為についても同様とする。」(Aftaleloven第36条第1項、意訳)
第36条は、日本の民法における公序良俗(90条)や信義則(1条2項)に相当する一般条項ですが、その適用範囲は遥かに広範です。
特に重要なのは、裁判所が裁定を下す際、以下の3つの主要な事情を考慮に入れなければならないと規定している点です。
- 契約が締結された時点で存在していた事情(ex ante要因)。
- 契約の条項自体。
- その後に発生した事情(ex post要因)。(Aftaleloven第36条第2項)
日本の契約法においては、契約締結後に予期せぬ困難が生じた場合の「事情変更の原則」は、一般法に明文規定がなく、判例によって適用が極めて限定されています。これに対し、デンマークの§ 36は、契約締結後の事情変化(ex post要因)を修正・無効化の正当な根拠として、法律行為全般にわたって包括的に考慮することを、制定法自体が定めているのです。
これにより、デンマークの裁判所は、契約を「不合理」(unreasonable)と判断する際に、単なる道徳的な意見ではなく、契約が当事者双方の共同価値を最大化する「経済的効率性」をベンチマークとして判断する傾向にあることが指摘されています。契約締結後に予期せぬ事情が発生し、契約が非効率的になってしまった場合、リスクの再配分が当事者の共同契約価値を著しく増加させる場合に限り、介入が許容されるという実務的な視点から判断されます。
商事契約における責任制限条項の有効性
国際的な商取引においては、責任制限条項はリスク管理の要ですが、デンマーク法の下でも§ 36の審査対象となります。
特に、責任制限条項が「特に負担が大きい」(particularly burdensome)と見なされる場合、裁判所は、その条項が交渉過程や契約文書において、いかに明確に言及され、合意に至ったかについて、より厳格な要件を課します。日本の裁判所でも同様の傾向は見られますが、デンマークではこの広範な§ 36の適用リスクを常に念頭に置く必要があります。
一方で、事前に業界内で交渉され、広く受け入れられている標準的な契約書(「合意文書」Agreed Documents)から派生した責任制限条項に対しては、より緩やかな受容要件が適用される傾向があります。例えば、最高裁判所の判決(U.1995.856/2H)では、ノルディック貨物運送業者協会の一般条件(NSAB)に含まれる責任制限が、注文書で特定の条項への直接的な言及がなくとも、NSAB全体への言及だけで有効であると認められました。この判例は、定型化された商事取引においては、効率性を優先し、個々の標準条項の明確な確認の必要性を緩和する、文脈依存的な司法アプローチを示しています 9。
デンマークの労働契約における強制法規:日本とは異なる高コストな規制
デンマークでのビジネス展開を検討する日本の経営者にとって、特に厳格な対応が求められるのが雇用契約です。労働法は契約自由の一般原則に対する最も強力な強制的な制限を課しており、特に雇用条項法(Employment Clauses Act)による競業避止義務等に対する規制は、日本法とは大きく異なる点です。
競業避止・顧客勧誘禁止条項の強制的な補償義務
デンマークの雇用条項法(2016年1月1日発効)は、競業避止条項および顧客勧誘禁止条項を使用する能力を大幅に制限し、その有効性の要件と強制的な補償を課しています。
厳しい有効性要件
これらの条項が有効とされるためには、従業員が最低6ヶ月以上の継続雇用を完了していることが必須です0。また、競業避止義務は特に信頼された地位にある従業員にのみ有効とされ、雇用主は、その条項が必要である理由を書面で具体的に説明しなければなりません。
強制的な高額補償と一括払いの義務
最も注目すべきは、強制される補償の水準と支払い方法です。補償額は、給与だけでなく、社用車や携帯電話などの手当を含む従業員の総給与パッケージに基づいて計算されます。
特に、拘束期間の最初の2ヶ月分の補償額は、雇用終了時の最終月給とともに一括で支払われなければならず、いかなる場合も相殺(減額)することはできません。
さらに、拘束期間中に従業員が他の適切な仕事を見つけた場合、その新しい雇用主からの給与は補償額に対して相殺される可能性がありますが、それでもなお強制的な最低補償率が維持されなければなりません。
| 条項の期間 | 最初の2ヶ月の一括払い率(相殺不可) | 適切な仕事を見つけた場合の最低補償率(3ヶ月目以降) |
| 最大6ヶ月 | 報酬の40% | 報酬の16% |
| 最大12ヶ月 | 報酬の60% | 報酬の24% |
日本の労働法においても、競業避止条項の有効性を判断する上で、その代償措置(補償)の有無は重要な要素とされますが、デンマークのように具体的な補償の最低額と、その一部の一括払いを法律で強制する規定は存在しません。これは、デンマーク法が労働者の職業選択の自由の制限に対し、極めて高い財政的なコストを課し、その利用を抑制していることを示しています。
従業員勧誘禁止条項の原則的禁止
さらに、デンマークの雇用条項法は、自社の従業員の勧誘を禁止する条項(従業員勧誘禁止条項や、引き抜き禁止条項、no-poaching/no-hire clauses)を、会社買収の場合を除き、完全に禁止しています 2。日本の商慣行では、M&Aやプロジェクト契約において従業員の引き抜きを禁止する条項がしばしば用いられますが、デンマークではこの規定が原則として無効であることを意味します。
まとめ
デンマーク王国の契約法は、「契約の自由」というリベラルな原則を基盤としながらも、Aftaleloven第36条による広範な司法介入の可能性、そして労働法分野における極めて厳格かつ強制的な保護規定という、二重の法的アイデンティティを持っています。特に、遅延した承諾に対する申込者の通知義務、広範な事情変更の考慮を可能にする§ 36の適用、そして競業避止義務に付随する高額な強制補償義務は、日本の法理との決定的な違いとして、現地でのリスク管理と契約戦略の策定において最優先で考慮されるべき事項です。国際的な取引や現地法人の設立、人材戦略を進めるにあたっては、このデンマーク特有の法的緊張関係を理解することが不可欠となります。当事務所では、こうした複雑な国際法務環境下での契約戦略の策定や、現地法規への対応について、専門的な知見をもってサポートいたします。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務
タグ: 海外事業