гӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўе…ұе’ҢеӣҪгҒ®жі•дҪ“зі»гҒЁеҸёжі•еҲ¶еәҰгӮ’ејҒиӯ·еЈ«гҒҢи§ЈиӘ¬

гӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўпјҲжӯЈејҸеҗҚз§°гҖҒгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўе…ұе’ҢеӣҪпјүгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒЁеҗҢж§ҳгҒ«еҸӨд»Јгғӯгғјгғһжі•гҒ«иө·жәҗгӮ’жҢҒгҒӨеӨ§йҷёжі•зі»гҒ«еұһгҒ—гҖҒжҲҗж–Үжі•гҒҢдё»иҰҒгҒӘжі•жәҗгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ§еӨҡгҒҸгҒ®йЎһдјјжҖ§гҒҢиҰӢгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жі•дҪ“зі»гҒ®е…ұйҖҡжҖ§гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬дәәгҒҢгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ®жі•еҲ¶еәҰгӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢдёҠгҒ§еӨ§гҒҚгҒӘеҠ©гҒ‘гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒжі•гҒ®йҒӢз”ЁгӮ„еҸёжі•гҒ®ж§ӢйҖ гҒ«гҒҜгҖҒгғ“гӮёгғҚгӮ№жҲҰз•ҘгҒ«зӣҙжҺҘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҶгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘзӣёйҒ•зӮ№гӮӮеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
жң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒгҒҫгҒҡдёЎеӣҪгҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒ®йЎһдјјжҖ§гӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒӨгҒӨгҖҒзү№гҒ«йҮҚиҰҒгҒӘзӣёйҒ•зӮ№гҒ§гҒӮгӮӢгҖҢеҲӨдҫӢгҒ®еҪ№еүІгҒЁе®ҹеӢҷдёҠгҒ®ж„Ҹе‘іеҗҲгҒ„гҖҚгҖҢеҸёжі•гҒ®е°Ӯй–ҖеҢ–гҒЁеҲҶйӣўгҖҚгҖҢж°‘дәӢиЁҙиЁҹгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиЈҒеҲӨе®ҳгҒ®иғҪеӢ•зҡ„гҒӘеҪ№еүІгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶдёүгҒӨгҒ®и«–зӮ№гҒ«з„ҰзӮ№гӮ’еҪ“гҒҰгҒҰгҖҒи©ізҙ°гҒ«и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®иЁҳдәӢгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒзү№гҒ«еҲӨдҫӢгҒ®еҪ№еүІгҖҒзӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еӯҳеңЁгҖҒгҒқгҒ—гҒҰе°Ӯй–ҖиЈҒеҲӨжүҖгҒ®з®ЎиҪ„жЁ©гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҖҒж—Ҙжң¬гҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘеҒҙйқўгҒёгҒ®зҗҶи§ЈгӮ’ж·ұгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮҢгҒ°е№ёгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ®еҢ…жӢ¬зҡ„гҒӘжі•еҲ¶еәҰгҒ®жҰӮиҰҒгҒҜдёӢиЁҳиЁҳдәӢгҒ«гҒҰгҒҫгҒЁгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®зӣ®ж¬Ў
гӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ®жі•дҪ“зі»
жі•гҒ®йҡҺеұӨж§ӢйҖ пјҲStufenbauпјүгҒЁEUжі•гҒ®ең°дҪҚ
гӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ®жі•дҪ“зі»гҒҜгҖҒжі•еӯҰиҖ…гғҸгғігӮ№гғ»гӮұгғ«гӮјгғігҒҢжҸҗе”ұгҒ—гҒҹжі•ж®өйҡҺиӘ¬пјҲStufenbauпјүгӮ’е…·дҪ“еҢ–гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ®жңҖдёҠдҪҚгҒ«гҒҜгҖҒгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўйҖЈйӮҰжҶІжі•пјҲBundes-Verfassungsgesetz, B-VGпјүгӮ„еҖӢгҖ…гҒ®жҶІжі•еҫӢгҖҒгҒқгҒ—гҒҰEUеҠ зӣҹжқЎзҙ„пјҲEU-BeitrittsakteпјүгҒҢдҪҚзҪ®д»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®дёӢгҒ«гҒҜгҖҒйҖЈйӮҰжі•гӮ„е·һжі•пјҲLandesgesetzeпјүгҒҢз¶ҡгҒҚгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒқгҒ®дёӢгҒ«ж”ҝд»ӨгӮ„иЎҢж”ҝе‘Ҫд»ӨгҒҢдҪҚзҪ®гҒҷгӮӢгҖҒеҺіж јгҒӘйҡҺеұӨж§ӢйҖ гӮ’еҪўжҲҗгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮВ гҒ“гҒ®йҡҺеұӨж§ӢйҖ гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жҶІжі•гӮ’жңҖй«ҳжі•иҰҸгҒЁгҒҷгӮӢжі•йҡҺеұӨгҒЁеҪўејҸзҡ„гҒ«йЎһдјјгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒҢ1995е№ҙ1жңҲ1ж—ҘгҒ«EUгҒ«еҠ зӣҹгҒ—гҒҹзөҗжһңгҖҒEUжі•гҒҢеӣҪеҶ…жі•гҒ®жңҖдёҠдҪҚгҒ«дҪҚзҪ®д»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹзӮ№гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ«гҒҜгҒӘгҒ„жұәе®ҡзҡ„гҒӘзү№еҫҙгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®EUеҠ зӣҹгҒҜгҖҒеҚҳгҒ«еӣҪйҡӣжқЎзҙ„гӮ’жү№еҮҶгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶдәӢе®ҹгҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгӮүгҒҡгҖҒгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ®еӣҪеҶ…法秩еәҸгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ«ж°ёз¶ҡзҡ„гҒӘж§ӢйҖ еӨүеҢ–гӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬гҒ®жі•дҪ“зі»гҒ§гҒҜгҖҒеӣҪйҡӣжқЎзҙ„гҒ®еӣҪеҶ…жі•дёҠгҒ®ең°дҪҚгҒҜиӯ°и«–гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ§гҒҜEUжі•гҒҢеӣҪеҶ…жі•гҒ«е„Әи¶ҠгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеҺҹеүҮгҒҢжҳҺзўәгҒ«зўәз«ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒEUгҒҢеҲ¶е®ҡгҒҷгӮӢзү№е®ҡгҒ®жҢҮд»ӨгӮ„иҰҸеүҮпјҲдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒдёҖиҲ¬гғҮгғјгӮҝдҝқиӯ·иҰҸеүҮгҖҢGDPRгҖҚпјүгҒҜгҖҒгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўеӣҪеҶ…гҒ§зӣҙжҺҘзҡ„гҒ«жі•зҡ„жӢҳжқҹеҠӣгӮ’жҢҒгҒӨгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ§гғ“гӮёгғҚгӮ№гӮ’еұ•й–ӢгҒҷгӮӢдјҒжҘӯгҒ«гҒҜгҖҒгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўеӣҪеҶ…гҒ®жі•д»ӨйҒөе®ҲгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒEUе…ЁдҪ“гҒ®жі•иҰҸеҲ¶еӢ•еҗ‘гӮ’еёёгҒ«жҠҠжҸЎгҒ—гҖҒиҮӘзӨҫгҒ®дәӢжҘӯгҒ«дёҺгҒҲгӮӢеҪұйҹҝгӮ’и©•дҫЎгҒҷгӮӢиғҪеҠӣгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮВ гӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўдёҖиҲ¬ж°‘жі•е…ёпјҲABGBпјүгҒ®жӯҙеҸІзҡ„ж„Ҹзҫ©
1811е№ҙ6жңҲ1ж—ҘгҒ«е…¬еёғгҒ•гӮҢгҖҒ1812е№ҙ1жңҲ1ж—ҘгҒ«ж–ҪиЎҢгҒ•гӮҢгҒҹгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўдёҖиҲ¬ж°‘жі•е…ёпјҲAllgemeines bГјrgerliches Gesetzbuch вҖ“ ABGBпјүгҒҜгҖҒгғ•гғ©гғігӮ№ж°‘жі•е…ёпјҲCode civilпјүгҒЁдёҰгҒ¶гҖҒеӨ§йҷёжі•зі»гӮ’д»ЈиЎЁгҒҷгӮӢдё–з•ҢжңҖеҸӨгҒ®ж°‘жі•е…ёгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒҷгҖӮ200е№ҙд»ҘдёҠгӮ’зөҢгҒҹзҸҫеңЁгӮӮеҠ№еҠӣгӮ’жңүгҒ—гҖҒгҒқгҒ®ж №жң¬еҺҹеүҮгҒҜгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ®з§Ғжі•гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдё»иҰҒгҒӘжі•жәҗгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ABGBгҒҜгҖҒе•“и’ҷдё»зҫ©зҡ„гҒӘиҮӘ然法жҖқжғігҒ®еҪұйҹҝгӮ’еј·гҒҸеҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§зҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒ第16жқЎгҒ§гҒҜгҖҢгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®дәәгҒҜгҖҒз”ҹеҫ—гҒ®иҮӘ然法дёҠгҒ®жЁ©еҲ©гӮ’жңүгҒ—гҖҒеҖӢдәәгҒЁгҒ—гҒҰе°ҠйҮҚгҒ•гӮҢгӮӢгҖҚгҒЁиҰҸе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҖӢдәәгҒ®е°ҠеҺігӮ„иҮӘз”ұгҒҢжі•дҪ“зі»гҒ®ж №е№№гҒ«жҚ®гҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҲҶгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®жҖқжғізҡ„иғҢжҷҜгҒҜгҖҒгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўжі•гҒ®зҗҶи§ЈгӮ’ж·ұгӮҒгӮӢдёҠгҒ§ж¬ гҒӢгҒӣгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
ABGBгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬ж°‘жі•е…ёгҒ®иө·иҚүгҒ«гӮӮеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҹгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒеҘ‘зҙ„гҒ®и§ЈйҮҲгҒ«й–ўгҒҷгӮӢ第914жқЎгӮ„гҖҒдёҚжҳҺзўәгҒӘжқЎй …гӮ’еӮөеӢҷиҖ…гҒ«жңүеҲ©гҒ«и§ЈйҮҲгҒҷгӮӢ第915жқЎгҒӘгҒ©гҖҒзҸҫд»ЈгҒ®ж—Ҙжң¬жі•гҒ«гӮӮйҖҡгҒҳгӮӢжі•зҡ„иҰҸзҜ„гҒҢABGBгҒ«иҰӢгҒҰеҸ–гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҖҒгӮҲгӮҠжӯЈзўәгҒ«иҝ°гҒ№гӮҢгҒ°гҖҒд»ҘдёӢгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҡгҖҒжҳҺжІ»жҷӮд»ЈгҒ«ж—Ҙжң¬гҒ®ж°‘жі•е…ёгҒҢеҲ¶е®ҡгҒ•гӮҢгӮӢйҒҺзЁӢгҒ§гҒҜгҖҒеҪ“еҲқгҖҒгғ•гғ©гғігӮ№гҒ®жі•еӯҰиҖ…гҒ§гҒӮгӮӢгӮ®гғҘгӮ№гӮҝгғјгғҙгғ»гӮЁгғҹгғјгғ«гғ»гғңгӮўгӮҪгғҠгғјгғүгғ»гғүгғ»гғ•гӮ©гғігӮҝгғ©гғ“гғјпјҲGustave Emile Boissonade de FontarabieпјүгҒҢжӢӣиҒҳгҒ•гӮҢгҖҒгғ•гғ©гғігӮ№жі•зі»гҒ®ж—§ж°‘жі•е…ёиҚүжЎҲгҒҢдҪңжҲҗгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ®дҝ®жӯЈгӮ’зөҢгҒҰгҖҒжңҖзөӮзҡ„гҒ«гҒҜгғүгӮӨгғ„ж°‘жі•е…ёпјҲBГјrgerliches Gesetzbuch, BGBпјүгҒ®дҪ“зі»гӮ’иүІжҝғгҒҸеҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгҒҹзҸҫиЎҢж°‘жі•е…ёгҒҢе®ҢжҲҗгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ—гҒҰгҖҒABGBгҒҜгҖҒBGBгӮ„гҒқгҒ®д»–еӨҡгҒҸгҒ®еӨ§йҷёжі•зі»ж°‘жі•е…ёгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘжәҗжөҒгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒй–“жҺҘзҡ„гҒ«ж—Ҙжң¬гҒ®жі•дҪ“зі»гҒ®жҖқжғіеҪўжҲҗгҒ«еҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҹеәғеӨ§гҒӘзҹҘзҡ„жҪ®жөҒгҒ®дёҖйғЁгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜй–“йҒ•гҒ„гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҖҢж—Ҙжң¬гҒ®ж°‘жі•гҒҢзӣҙжҺҘзҡ„гҒ«ABGBгӮ’еҸӮз…§гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢиЁігҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒABGBгҒҜж—Ҙжң¬гҒ®ж°‘жі•гҒ®жәҗжөҒгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒҜгҒӮгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢжӯЈзўәгҒӘиЎЁзҸҫгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ®еҸёжі•еҲ¶еәҰ
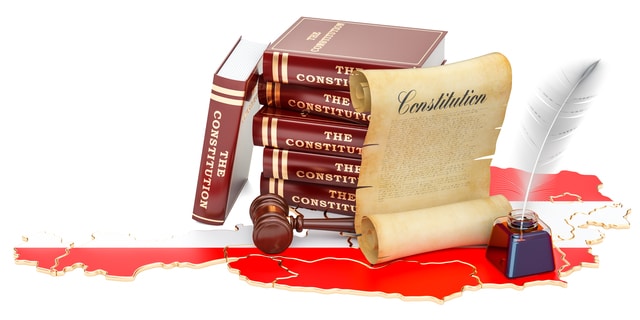
дёүгҒӨгҒ®зӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖ
ж—Ҙжң¬гҒ®еҸёжі•еҲ¶еәҰгҒҢжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖдёҖе…ғзҡ„гҒ«ж°‘дәӢгҖҒеҲ‘дәӢгҖҒиЎҢж”ҝгҖҒжҶІжі•еҲӨж–ӯгӮ’жӢ…гҒҶгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ®еҸёжі•еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒйҖҡеёёиЈҒеҲӨжүҖпјҲOrdinary CourtsпјүгҖҒжҶІжі•иЈҒеҲӨжүҖпјҲVerfassungsgerichtshof – VfGHпјүгҖҒиЎҢж”ҝиЈҒеҲӨжүҖпјҲVerwaltungsgerichtshof – VwGHпјүгҒЁгҒ„гҒҶдёүгҒӨгҒ®зӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢзӢ¬иҮӘгҒ®з®ЎиҪ„жЁ©гӮ’жҢҒгҒӨгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ§еӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®дёүгҒӨгҒ®жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮгғ’гӮЁгғ©гғ«гӮӯгғјгҒ®й ӮзӮ№гҒ«дҪҚзҪ®гҒ—гҖҒдә’гҒ„гҒ«е„ӘеҠЈй–ўдҝӮгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®еҪ№еүІгҒҜжҳҺзўәгҒ«еҲҶгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖпјҲOGHпјүгҒҜж°‘дәӢгҒҠгӮҲгҒіеҲ‘дәӢдәӢ件гҒ®жңҖзөӮеҜ©гӮ’жүұгҒ„гҖҒжҶІжі•иЈҒеҲӨжүҖпјҲVfGHпјүгҒҜжі•еҫӢгҒ®еҗҲжҶІжҖ§гӮ„ж”ҝд»ӨгҒ®йҒ©жі•жҖ§гҒӘгҒ©гӮ’еҲӨж–ӯгҒҷгӮӢгҖҢжҶІжі•гҒ®е®Ҳиӯ·иҖ…гҖҚгҒ§гҒҷгҖӮзӣҙиҝ‘гҒ®йҮҚиҰҒгҒӘеҲӨдҫӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒж°—еҖҷдҝқиӯ·жі•гӮ’гӮҒгҒҗгӮӢгҖҢгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ®еӯҗдҫӣгҒҹгҒЎеҜҫгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўж”ҝеәңгҖҚиЁҙиЁҹпјҲVfGH 2023е№ҙ6жңҲ27ж—ҘпјүгӮ„гҖҒе®үжҘҪжӯ»гҒ®зҰҒжӯўгҒҢйҒ•жҶІгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ—гҒҹеҲӨжұәпјҲVfGH 2020е№ҙ12жңҲ11ж—ҘгҖҒG 139/2019пјүгҒӘгҒ©гҖҒзӨҫдјҡзҡ„гҒ«еӨ§гҒҚгҒӘй–ўеҝғгӮ’йӣҶгӮҒгӮӢдәӢжЎҲгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰе°Ӯй–Җзҡ„гҒӘеҲӨж–ӯгӮ’дёӢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдёҖж–№гҖҒиЎҢж”ҝиЈҒеҲӨжүҖпјҲVwGHпјүгҒҜгҖҒзЁҺеӢҷгҖҒз”ЈжҘӯе…ҚиЁұгҖҒйӣЈж°‘е•ҸйЎҢгҒӘгҒ©гҖҒиЎҢж”ҝиЎҢзӮәгҒ®йҒ©жі•жҖ§гӮ’еҜ©жҹ»гҒҷгӮӢжңҖзөӮеҜ©гӮ’жӢ…гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®дёүе…ғж§ӢйҖ гҒҜгҖҒеҸёжі•гҒ®е°Ӯй–ҖжҖ§гӮ’жҘөйҷҗгҒҫгҒ§й«ҳгӮҒгҖҒеҗ„еҲҶйҮҺгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжЁ©еҠӣеҲҶз«ӢгӮ’еҫ№еә•гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҢгҖҢжңҖеҫҢгҒ®з ҰгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰе№…еәғгҒ„жЎҲ件гӮ’жүұгҒҶгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ§гҒҜгҖҢзү№е®ҡгҒ®еҲҶйҮҺгҒ®гӮ№гғҡгӮ·гғЈгғӘгӮ№гғҲгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еҪ№еүІгҒҢжҳҺзўәгҒ«еҲҶгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
еҲӨдҫӢгҒ®жі•зҡ„жӢҳжқҹеҠӣ
еӨ§йҷёжі•зі»гҒ«еұһгҒҷгӮӢгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ§гҒҜгҖҒеҲӨдҫӢгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ«ж—Ҙжң¬гҒ®еҲӨдҫӢжі•гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҢжі•зҡ„жӢҳжқҹеҠӣгҖҚгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮиЈҒеҲӨе®ҳгҒҜжҲҗж–Үжі•гҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰеҖӢгҖ…гҒ®дәӢжЎҲгӮ’еҲӨж–ӯгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҺҹеүҮгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒйҒҺеҺ»гҒ®еҲӨдҫӢгҒҜгҒӮгҒҸгҒҫгҒ§и«–жӢ гҒЁгҒ—гҒҰеҸӮиҖғгҒ«гҒ•гӮҢгӮӢгҒ«йҒҺгҒҺгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ“гҒ®еҹәжң¬ж§ӢйҖ гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®йҒӢз”Ёе®ҹж…ӢгҒЁдјјгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®иЈҒеҲӨжүҖ法第10жқЎгҒҜгҖҢиЈҒеҲӨе®ҳгҒҜгҖҒгҒқгҒ®иүҜеҝғгҒ«еҫ“гҒ„зӢ¬з«ӢгҒ—гҒҰгҒқгҒ®иҒ·жЁ©гӮ’иЎҢгҒ„гҖҒгҒ“гҒ®жҶІжі•еҸҠгҒіжі•еҫӢгҒ«гҒ®гҒҝжӢҳжқҹгҒ•гӮҢгӮӢгҖҚгҒЁе®ҡгӮҒгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®иҰҸе®ҡгҒҜеҲӨдҫӢгҒҢжі•зҡ„гҒӘжӢҳжқҹеҠӣгӮ’жҢҒгҒҹгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ®ж №жӢ гҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®еҪўејҸзҡ„гҒӘе»әеүҚгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҸёжі•е®ҹеӢҷгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒзү№гҒ«жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨдҫӢгҒҜжҘөгӮҒгҒҰеј·гҒ„еҪұйҹҝеҠӣгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒеҲӨдҫӢгҒҢиЈҒеҲӨе®ҳгҒ®жҒЈж„Ҹзҡ„гҒӘгҖҢиЈҒйҮҸгҖҚгӮ’зөұеҲ¶гҒ—гҖҒжі•гҒ®е®үе®ҡжҖ§гӮ„дәҲжё¬еҸҜиғҪжҖ§гӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж©ҹиғҪзҡ„гҒӘеҝ…иҰҒжҖ§гҒӢгӮүз”ҹгҒҳгӮӢгҖҢдәӢе®ҹдёҠгҒ®жӢҳжқҹеҠӣгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮжңҖй«ҳиЈҒгҒ®еҲӨдҫӢгҒҜгҖҢеҲӨдҫӢжі•зҗҶгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰе®ҹеӢҷгҒ«е®ҡзқҖгҒ—гҖҒдјҒжҘӯгҒ®иЎҢеӢ•иҰҸзҜ„гҒ«зӣҙжҺҘзҡ„гҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ®еҲӨдҫӢжі•гӮӮгҒҫгҒҹгҖҒж—Ҙжң¬гҒЁеҗҢж§ҳгҖҒеҪўејҸгҒЁе®ҹж…ӢгҒҢд№–йӣўгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖпјҲOGHпјүгҒ®еҲӨжұәгҒҜгҖҒеҪўејҸзҡ„гҒ«гҒҜдёӢзҙҡеҜ©гӮ’жі•зҡ„гҒ«жӢҳжқҹгҒҷгӮӢе…ҲдҫӢгҒЁгҒҜгҒҝгҒӘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®жЁ©еЁҒгҒҜгҖҢжі•йҒ©з”ЁгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжҳҺзўәжҖ§гӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҖҚпјҲprovides clarity on the application of the lawпјүгҒЁгҒ„гҒҶйҮҚиҰҒгҒӘж©ҹиғҪгӮ’жҢҒгҒӨгҒЁгҒ•гӮҢгҖҒе®ҹеӢҷдёҠгҒҜдёӢзҙҡеҜ©гҒҢгҒқгҒ®еҲӨж–ӯгҒ«иҝҪеҫ“гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®йҒӢз”Ёе®ҹж…ӢгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢдәӢе®ҹдёҠгҒ®жӢҳжқҹеҠӣгҖҚгҒЁдјјгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ®еҸёжі•еҲ¶еәҰгҒ«гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒЁжұәе®ҡзҡ„гҒ«з•°гҒӘгӮӢзӮ№гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒҜгҖҒжңҖй«ҳиЎҢж”ҝиЈҒеҲӨжүҖпјҲVwGHпјүгҒҢгҖҒзү№е®ҡгҒ®жқЎд»¶дёӢгҒ§дёӢзҙҡеҜ©гҒ®еҲӨж–ӯгӮ’жі•зҡ„гҒ«жӢҳжқҹгҒҷгӮӢд»•зө„гҒҝгҒ§гҒҷгҖӮVwGHгҒҢгҖҒдёӢзҙҡиЎҢж”ҝиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨжұәгӮ’з ҙжЈ„гҒ—гҒҰе·®гҒ—жҲ»гҒҷе ҙеҗҲгҖҒдёӢзҙҡеҜ©гҒҜVwGHгҒҢзӨәгҒ—гҒҹжі•и§ЈйҮҲгҒ«гҖҢжӢҳжқҹгҒ•гӮҢгӮӢгҖҚпјҲbound to apply the interpretationпјүгҒ“гҒЁгҒҢжҳҺж–ҮгҒ§е®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®иЈҒеҲӨжүҖжі•гҒ«гҒҜгҒӘгҒ„гҖҒгӮҲгӮҠеј·гҒ„еҲ¶еәҰзҡ„гҒӘжӢҳжқҹеҠӣгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиЎҢж”ҝжі•гҒ®й ҳеҹҹгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжі•гҒ®зөұдёҖжҖ§гӮ’гӮҲгӮҠеј·еҠӣгҒ«жӢ…дҝқгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўйҖҡеёёиЈҒеҲӨжүҖгҒ®ж§ӢйҖ гҒЁе•ҶдәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҪ№еүІ
第дёҖеҜ©иЈҒеҲӨжүҖгҒ®з®ЎиҪ„жЁ©
гӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ®ж°‘дәӢиЁҙиЁҹгҒ§гҒҜгҖҒ第дёҖеҜ©гҒ®з®ЎиҪ„жЁ©гҒҜзҙӣдәүгҒ®жҖ§иіӘгӮ„йҮ‘йЎҚгҒ«еҝңгҒҳгҒҰжұәе®ҡгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«йҮ‘йЎҚгҒҢйҮҚиҰҒгҒӘеҲӨж–ӯеҹәжә–гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзҙӣдәүйҮ‘йЎҚгҒҢ1дёҮ5,000гғҰгғјгғӯд»ҘдёӢгҒ®ж°‘дәӢдәӢ件гҒҜең°ж–№иЈҒеҲӨжүҖпјҲBezirksgerichtпјүгҒҢз®ЎиҪ„жЁ©гӮ’жңүгҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгӮ’и¶…гҒҲгӮӢе ҙеҗҲгҒҜе·һиЈҒеҲӨжүҖпјҲLandesgerichtпјүгҒҢ第дёҖеҜ©гҒ®з®ЎиҪ„жЁ©гӮ’жңүгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒең°ж–№иЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒйҮ‘йЎҚгҒ«гҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒиіғиІёеҖҹгҖҒ家ж—Ҹжі•гҖҒдёҚеӢ•з”Јй–ўйҖЈгҒӘгҒ©зү№е®ҡгҒ®дәӢ件гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮз®ЎиҪ„жЁ©гӮ’жҢҒгҒЎгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®зҙӣдәүйҮ‘йЎҚгҒ«еҹәгҒҘгҒҸз®ЎиҪ„жЁ©гҒ®еҲҶеүІгҒҜгҖҒиЁҙиЁҹжүӢз¶ҡгҒ®еҠ№зҺҮеҢ–гҒЁгҖҒеҗ„иЈҒеҲӨжүҖгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдәӢ件гҒ®е°Ӯй–ҖеҢ–гӮ’еҗҢжҷӮгҒ«йҒ”жҲҗгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®е®ҹз”Ёзҡ„гҒӘд»•зө„гҒҝгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮҰгӮЈгғјгғіе•ҶдәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ®е°Ӯй–ҖжҖ§
гӮҰгӮЈгғјгғігҒ«гҒҜгҖҒзү№еҲҘгҒӘе•ҶдәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ§гҒӮгӮӢгӮҰгӮЈгғјгғіе•ҶдәӢиЈҒеҲӨжүҖпјҲHandelsgericht WienпјүгҒҢиЁӯзҪ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒе•ҶжҘӯзҷ»иЁҳз°ҝгҒ«зҷ»иЁҳгҒ•гӮҢгҒҹдәӢжҘӯиҖ…й–“гҒ®зҙӣдәүгҖҒзҹҘзҡ„иІЎз”ЈжЁ©пјҲзү№иЁұгҖҒе•ҶжЁҷгҖҒж„ҸеҢ гҖҒе®ҹз”Ёж–°жЎҲгҒӘгҒ©пјүгҖҒдјҡзӨҫжі•пјҲAktiengesetz, GmbH-GesetzпјүгҒ«еҹәгҒҘгҒҸзҙӣдәүгҖҒдёҚе…¬жӯЈз«¶дәүгҒ«й–ўгҒҷгӮӢзҙӣдәүгҒӘгҒ©гҖҒзү№е®ҡгҒ®е•ҶжҘӯй–ўйҖЈдәӢ件гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ第дёҖеҜ©з®ЎиҪ„жЁ©гӮ’е°Ӯеұһзҡ„гҒ«жңүгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒзҹҘзҡ„иІЎз”ЈжЁ©гҒҢзөЎгӮҖзҙӣдәүгӮ„гҖҒдјҡзӨҫжі•дёҠгҒ®е•ҸйЎҢгҒ«зӣҙйқўгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒйҮҚзӮ№зҡ„гҒ«иӘҝжҹ»гҒҷгӮӢгҒ№гҒҚеҜҫиұЎгҒҜгҖҒгӮҰгӮЈгғјгғіе•ҶдәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨдҫӢгӮ„йҒӢз”Ёе®ҹеӢҷгҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢиғҪеӢ•зҡ„гҖҚгҒӘиЈҒеҲӨе®ҳ
гӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ®ж°‘дәӢиЁҙиЁҹе®ҹеӢҷгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҪ“дәӢиҖ…дё»зҫ©зҡ„гҒӘиЁҙиЁҹе®ҹеӢҷгҒЁгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘйҒ•гҒ„гҒҜгҖҒиЈҒеҲӨе®ҳгҒ®еҪ№еүІгҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ®иЈҒеҲӨе®ҳгҒҜгҖҒзҙӣдәүи§ЈжұәгҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҰйқһеёёгҒ«иғҪеӢ•зҡ„пјҲinquisitorialпјүгҒӘеҪ№еүІгӮ’гҒ«жӢ…гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҪ“дәӢиҖ…гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«зҙӣдәүгҒ®еҶ…е®№гӮ’иӘҝжҹ»гҒ—гҖҒжі•зҡ„и«–зӮ№гӮ’зөһгӮҠиҫјгҒҝгҖҒеҝ…иҰҒгҒ«еҝңгҒҳгҒҰе°Ӯй–Җ家гӮ’жӢӣиҮҙгҒҷгӮӢжЁ©йҷҗгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒеҪ“дәӢиҖ…гҒҢдё»ејөгҒЁиЁјжӢ гӮ’жҸҗеҮәгҒ—гҖҒиЈҒеҲӨе®ҳгҒҜжҸҗеҮәгҒ•гӮҢгҒҹеҶ…е®№гҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰеҲӨж–ӯгӮ’дёӢгҒҷж—Ҙжң¬гҒ®иЁҙиЁҹе®ҹеӢҷгҒЁгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬гҒ®жі•еӢҷжӢ…еҪ“иҖ…гҒҜгҖҒиҮӘзӨҫгҒ«жңүеҲ©гҒӘиЁјжӢ гӮ’з¶Ізҫ…зҡ„гҒ«еҸҺйӣҶгғ»жҸҗеҮәгҒҷгӮӢж—Ҙжң¬гҒ®иЁҙиЁҹжҲҰз•ҘгҒ«ж…ЈгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮўгғ—гғӯгғјгғҒгҒҜеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮжӯ“иҝҺгҒ•гӮҢгҒҡгҖҒгӮҖгҒ—гӮҚиЈҒеҲӨе®ҳгҒҢжұӮгӮҒгӮӢзү№е®ҡгҒ®жғ…е ұгҒ«з„ҰзӮ№гӮ’еҪ“гҒҰгҖҒиғҪеӢ•зҡ„гҒӘиӘҝжҹ»гҒ«еҚ”еҠӣгҒҷгӮӢж–№гҒҢгҖҒгӮҲгӮҠеҠ№зҺҮзҡ„гҒӘиЁҙиЁҹйҖІиЎҢгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®йҒ•гҒ„гӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ§иЁҙиЁҹгҒ«зӣҙйқўгҒ—гҒҹйҡӣгҒ«гҖҒзҸҫең°гҒ®ејҒиӯ·еЈ«гҒЁеҜҶгҒ«йҖЈжҗәгҒ—гҖҒзҸҫең°гҒ®иЁҙиЁҹж–ҮеҢ–гҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹжҲҰз•ҘгӮ’ж§ӢзҜүгҒҷгӮӢдёҠгҒ§дёҚеҸҜж¬ гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒ
гӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ®жі•дҪ“зі»гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒЁиө·жәҗгӮ’еҗҢгҒҳгҒҸгҒҷгӮӢеӨ§йҷёжі•зі»гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®йЎһдјјзӮ№гӮ’жңүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеҸёжі•еҲ¶еәҰгҒ®дёүе…ғж§ӢйҖ гӮ„гҖҒеҪўејҸзҡ„гҒ«гҒҜжӢҳжқҹеҠӣгӮ’жҢҒгҒҹгҒӘгҒ„гҒЁгҒ•гӮҢгӮӢеҲӨдҫӢгҒ®е®ҹиіӘзҡ„гҒӘеҪ№еүІгҖҒгҒқгҒ—гҒҰй«ҳеәҰгҒ«е°Ӯй–ҖеҢ–гҒ•гӮҢгҒҹе•ҶдәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еӯҳеңЁгҖҒж°‘дәӢиЁҙиЁҹгҒ®е®ҹеӢҷгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиЈҒеҲӨе®ҳгҒ®иғҪеӢ•зҡ„гҒӘеҪ№еүІгҒӘгҒ©гҖҒгғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ«зӣҙжҺҘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘзӣёйҒ•зӮ№гӮӮеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгӮүгҒ®йҒ•гҒ„гӮ’жӯЈзўәгҒ«зҗҶи§ЈгҒ—гҖҒзҸҫең°гҒ®жі•еӢҷз’°еўғгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹжҲҰз•ҘгӮ’ж§ӢзҜүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ§гҒ®дәӢжҘӯеұ•й–ӢгӮ’жҲҗеҠҹгҒ«е°ҺгҒҸйҚөгҒЁгҒӘгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гӮ«гғҶгӮҙгғӘгғј: ITгғ»гғҷгғігғҒгғЈгғјгҒ®дјҒжҘӯжі•еӢҷ


































