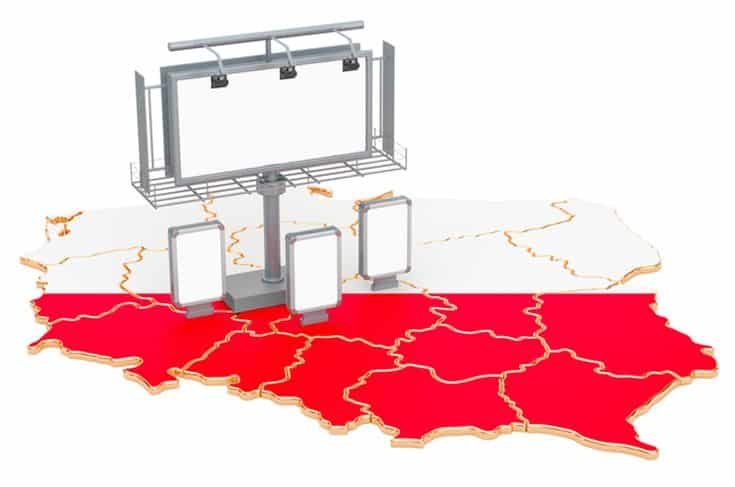гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүе…ұе’ҢеӣҪгҒ®жі•еҫӢгҒ®е…ЁдҪ“еғҸгҒЁгҒқгҒ®жҰӮиҰҒгӮ’ејҒиӯ·еЈ«гҒҢи§ЈиӘ¬

гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒҜгҖҒгҒқгҒ®е®үе®ҡгҒ—гҒҹж”ҝжІ»зөҢжёҲгҖҒй«ҳгҒ„ж•ҷиӮІж°ҙжә–гҖҒгҒқгҒ—гҒҰгғҮгӮёгӮҝгғ«еҢ–гҒҢйҖІгӮ“гҒ зӨҫдјҡгӮӨгғігғ•гғ©гҒӢгӮүжіЁзӣ®гӮ’йӣҶгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒгӮ№гӮҝгғјгғҲгӮўгғғгғ—гӮЁгӮігӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®жҙ»зҷәгҒ•гӮ„гҖҒз’°еўғжҠҖиЎ“гҖҒжғ…е ұйҖҡдҝЎжҠҖиЎ“пјҲICTпјүеҲҶйҮҺгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮӨгғҺгғҷгғјгӮ·гғ§гғігҒҜгҖҒж–°гҒҹгҒӘеёӮе ҙж©ҹдјҡгӮ’жұӮгӮҒгӮӢдјҒжҘӯгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰеӨ§гҒҚгҒӘеҸҜиғҪжҖ§гӮ’з§ҳгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
жң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒгғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒ®е…ЁдҪ“еғҸгӮ’жҰӮиҰігҒ—гҖҒзү№гҒ«ж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҢй–ўеҝғгӮ’жҢҒгҒӨгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶдјҡзӨҫиЁӯз«ӢгҖҒеӨ–еӣҪжҠ•иіҮгҖҒеҘ‘зҙ„жі•гҖҒеәғе‘ҠиҰҸеҲ¶гҖҒеҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·гҖҒеҠҙеғҚжі•гҖҒгҒқгҒ—гҒҰзү№е®ҡгҒ®з”ЈжҘӯеҲҶйҮҺгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиҰҸеҲ¶гҒ«з„ҰзӮ№гӮ’еҪ“гҒҰгҖҒе®ҹеӢҷдёҠгҒ®з•ҷж„ҸзӮ№гӮ’и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®зӣ®ж¬Ў
гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүжі•еҲ¶еәҰгҒ®е…ЁдҪ“еғҸ
гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒеҢ—欧諸еӣҪгҒ«е…ұйҖҡгҒҷгӮӢеӨ§йҷёжі•зі»гҒ«еұһгҒ—гҖҒзү№гҒ«гӮ№гӮҰгӮ§гғјгғҮгғіжі•гҒ®еҪұйҹҝгӮ’еј·гҒҸеҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒйҖҸжҳҺжҖ§гҒҢй«ҳгҒҸгҖҒгғҮгӮёгӮҝгғ«еҢ–гҒҢжҺЁйҖІгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеӣҪйҡӣзҡ„гҒӘгғ“гӮёгғҚгӮ№з’°еўғгҒ«йҒ©еҝңгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶеҒҙйқўгҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒҜжҲҗж–Үжі•дё»зҫ©гӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒдё»иҰҒгҒӘжі•еҲҶйҮҺгҒҜжі•е…ёеҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҸёжі•еҲ¶еәҰгҒҜдёүеҜ©еҲ¶гӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҖҒдёҖиҲ¬иЈҒеҲӨжүҖгҒЁиЎҢж”ҝиЈҒеҲӨжүҖгҖҒгҒ•гӮүгҒ«еҠҙеғҚиЈҒеҲӨжүҖзӯүгҒ®зү№еҲҘиЈҒеҲӨжүҖгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒгҒқгҒ®й«ҳгҒ„йҖҸжҳҺжҖ§гҒЁгғҮгӮёгӮҝгғ«еҢ–гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзү№еҫҙгҒҘгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒжі•д»ӨгӮ„еҲӨдҫӢгҖҒиЎҢж”ҝжүӢз¶ҡгҒҚгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжғ…е ұгҒҢгӮӘгғігғ©гӮӨгғігҒ§е®№жҳ“гҒ«е…ҘжүӢгҖҒжі•зҡ„гҒӘжғ…е ұгҒёгҒ®гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒҢжҜ”ијғзҡ„е®№жҳ“гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒжі•зҡ„зўәе®ҹжҖ§гҒЁдәҲжё¬еҸҜиғҪжҖ§гҒҢйҮҚиҰ–гҒ•гӮҢгӮӢеӮҫеҗ‘гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдјҡзӨҫиЁӯз«ӢгҒЁеӨ–еӣҪиіҮжң¬гҒ®жҠ•иіҮгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжі•иҰҸеҲ¶
гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ§гҒ®дјҡзӨҫиЁӯз«ӢгҒҜжҜ”ијғзҡ„з°Ўзҙ еҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеӨ–еӣҪиіҮжң¬гҒ«гӮҲгӮӢжҠ•иіҮгӮӮз©ҚжҘөзҡ„гҒ«еҘЁеҠұгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҢгғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ«йҖІеҮәгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«жңҖгӮӮдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘеҪўж…ӢгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®ж ӘејҸдјҡзӨҫгҒ«зӣёеҪ“гҒҷгӮӢгҖҢOsakeyhtiГ¶ (Oy)гҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢжңүйҷҗдјҡзӨҫгҒ§гҒҷгҖӮ
дјҡзӨҫеҪўж…ӢгҒ®зЁ®йЎһгҒЁзү№еҫҙ
гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүдјҡзӨҫжі•пјҲOsakeyhtiГ¶laki, 624/2006пјүгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒжңүйҷҗиІ¬д»»дјҡзӨҫпјҲOsakeyhtiГ¶, OyпјүгҒҢжңҖгӮӮдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘдәӢжҘӯеҪўж…ӢгҒЁгҒ—гҒҰеҲ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҪўж…ӢгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®ж ӘејҸдјҡзӨҫгҒ«йЎһдјјгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒж Әдё»гҒ®иІ¬д»»гҒҢжңүйҷҗгҒ§гҒӮгӮӢзӮ№гҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒҷгҖӮжңүйҷҗиІ¬д»»дјҡзӨҫпјҲOyпјүгҒ®иЁӯз«ӢгҒ«гҒҜгҖҒе°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮ1еҗҚгҒ®ж Әдё»гҒЁ1еҗҚгҒ®еҸ–з· еҪ№гҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒӘгҒҠгҖҒ3еҗҚжңӘжәҖгҒ®е ҙеҗҲгҒҜиЈңж¬ еҸ–з· еҪ№гӮ’е°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮ1еҗҚзҪ®гҒҸеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒ»гҒӢгҖҒеҪ№е“Ўгғ»д»ЈиЎЁиҖ…зӯүгҒ«гҒҜEEAеұ…дҪҸиҰҒ件пјҲе…ҚйҷӨеҲ¶еәҰгҒӮгӮҠпјүгҒҢиӘІгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮзү№зӯҶгҒҷгҒ№гҒҚгҒҜгҖҒ2019е№ҙд»ҘйҷҚгҖҒжңҖдҪҺиіҮжң¬йҮ‘иҰҒ件гҒҢж’Өе»ғгҒ•гӮҢгҒҹзӮ№гҒ§гҒҷгҖӮ
дјҡзӨҫиЁӯз«ӢжүӢз¶ҡ
дјҡзӨҫиЁӯз«ӢгҒҜгҖҒгғ•гӮЈгғігғ©гғігғүзү№иЁұзҷ»йҢІеәҒпјҲPRHпјүеӮҳдёӢгҒ®гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүиІҝжҳ“зҷ»йҢІпјҲSuomen kaupparekisteriпјүгҒёгҒ®зҷ»йҢІгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰиЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮеҝ…иҰҒгҒӘжӣёйЎһгӮ’жҸҗеҮәгҒ—гҖҒзҷ»йҢІж–ҷгӮ’ж”Ҝжү•гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§жүӢз¶ҡгҒҚгҒҢе®ҢдәҶгҒ—гҖҒгӮӘгғігғ©гӮӨгғігҒ§гҒ®жүӢз¶ҡгҒҚгӮӮеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ®дјҡзӨҫиЁӯз«ӢжүӢз¶ҡгҒҚгҒҢиІҝжҳ“зҷ»йҢІгҒёгҒ®гҖҢзҷ»йҢІгҖҚгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰиЎҢгӮҸгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жі•еӢҷеұҖгҒ§гҒ®гҖҢзҷ»иЁҳгҖҚгҒЁжҰӮеҝөзҡ„гҒ«гҒҜйЎһдјјгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ§гҒҜжі•еҲ¶еәҰгҒ®гғҮгӮёгӮҝгғ«еҢ–гҒҢйҖІгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒзү©зҗҶзҡ„гҒӘжӣёйЎһгҒ®гӮ„гӮҠеҸ–гӮҠгҒҢжёӣгӮҠгҖҒеҮҰзҗҶжҷӮй–“гҒҢзҹӯзё®гҒ•гӮҢгҖҒйҖІжҚ—зҠ¶жіҒгҒ®иҝҪи·ЎгҒҢе®№жҳ“гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еӨ–еӣҪиіҮжң¬гҒӢгӮүгҒ®жҠ•иіҮиҰҸеҲ¶
гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒҜеҹәжң¬зҡ„гҒ«еӨ–еӣҪжҠ•иіҮгҒ«й–Ӣж”ҫзҡ„гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒзү№е®ҡгҒ®жҲҰз•Ҙзҡ„з”ЈжҘӯгӮ’йҷӨгҒҚгҖҒзү№еҲҘгҒӘдәӢеүҚжүҝиӘҚгӮ„еҲ¶йҷҗгҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒйҳІиЎӣгӮ„йҮҚиҰҒгӮӨгғігғ•гғ©гҒӘгҒ©гҒ®зү№е®ҡгҒ®еҲҶйҮҺгҒ§гҒҜгҖҒеӣҪ家е®үе…ЁдҝқйҡңдёҠгҒ®иҰізӮ№гҒӢгӮүжҠ•иіҮеҜ©жҹ»гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮжҠ•иіҮиЁҲз”»гӮ’з«ӢгҒҰгӮӢдёҠгҒ§гҒҜгҖҒеҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢдәӢжҘӯгҒҢгҖҢеӣҪ家е®үе…ЁдҝқйҡңгҖҚгҒ®зҜ„з–ҮгҒ«е…ҘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгӮ’ж—©жңҹгҒ«и©•дҫЎгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ®еҘ‘зҙ„жі•
гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ®еҘ‘зҙ„жі•гҒҜгҖҒеҘ‘зҙ„гҒ®иҮӘз”ұгҒ®еҺҹеүҮгӮ’еҹәзӣӨгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒж¶ҲиІ»иҖ…дҝқиӯ·гӮ„еҠҙеғҚеҘ‘зҙ„гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҪ“дәӢиҖ…гҒ®дҝқиӯ·гӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҹеј·иЎҢиҰҸе®ҡгҒҢеӨҡгҒҸеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ®еҘ‘зҙ„жі•гҒҜгҖҒеҘ‘зҙ„жі•пјҲLaki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista, 228/1929пјүгӮ’дё»гҒҹгӮӢж №жӢ гҒЁгҒ—гҖҒеҘ‘зҙ„гҒ®иҮӘз”ұгҒ®еҺҹеүҮгӮ’йҮҚиҰ–гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҸЈй ӯгҒ§гҒ®еҗҲж„ҸгӮӮеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰжңүеҠ№гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒдёҚеӢ•з”ЈгҒ®еЈІиІ·гҒӘгҒ©гҖҒзү№е®ҡгҒ®еҘ‘зҙ„гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜжӣёйқўгҒ«гӮҲгӮӢеҗҲж„ҸгҒҢзҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҘ‘зҙ„гҒ®и§ЈйҮҲгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҪ“дәӢиҖ…гҒ®зңҹгҒ®ж„ҸжҖқгҒҢйҮҚиҰ–гҒ•гӮҢгҖҒдҝЎзҫ©иӘ е®ҹгҒ®еҺҹеүҮгҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜж—Ҙжң¬гҒ®ж°‘жі•гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҺҹеүҮгҒЁйЎһдјјгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеәғе‘ҠиҰҸеҲ¶гҒЁж¶ҲиІ»иҖ…дҝқиӯ·

гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ®еәғе‘ҠиҰҸеҲ¶гҒЁж¶ҲиІ»иҖ…дҝқиӯ·гҒҜгҖҒEUжі•пјҲзү№гҒ«дёҚе…¬жӯЈеҸ–еј•ж…ЈиЎҢжҢҮд»ӨпјүгҒ«жә–жӢ гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жҷҜе“ҒиЎЁзӨәжі•гӮ„й–ўйҖЈгӮ¬гӮӨгғүгғ©гӮӨгғігӮҲгӮҠгӮӮеәғзҜ„гҒӢгҒӨеҺіж јгҒӘеҒҙйқўгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒеәғе‘ҠгҒ®зңҹе®ҹжҖ§гҖҒиӘӨи§ЈгӮ’жӢӣгҒҸиЎЁзӨәгҒ®зҰҒжӯўгҖҒж¶ҲиІ»иҖ…гҒ®жЁ©еҲ©дҝқиӯ·гҒҢйҮҚиҰ–гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
еәғе‘ҠиҰҸеҲ¶гҒ®жҰӮиҰҒ
гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ®ж¶ҲиІ»иҖ…дҝқиӯ·жі•пјҲKuluttajansuojalaki, 38/1978пјүгҒҜгҖҒеәғе‘ҠгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдёҚе…¬жӯЈгҒӘе•Ҷж…ЈиЎҢгӮ’зҰҒжӯўгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒзү№гҒ«иӘӨи§ЈгӮ’жӢӣгҒҸиЎЁзӨәгӮ„дёҚеҪ“гҒӘе„ӘдҪҚжҖ§гӮ’дёҺгҒҲгӮӢиЎҢзӮәгҒҢеҺігҒ—гҒҸиҰҸеҲ¶гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®жҷҜе“ҒиЎЁзӨәжі•пјҲдёҚеҪ“жҷҜе“ҒйЎһеҸҠгҒідёҚеҪ“иЎЁзӨәйҳІжӯўжі•пјүгҒЁеҗҢж§ҳгҒ«гҖҒж¶ҲиІ»иҖ…гӮ’ж¬әгҒҸгӮҲгҒҶгҒӘиЎЁзӨәгҒҜзҰҒжӯўгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒEUжҢҮд»ӨгҒ«еҹәгҒҘгҒҸиҰҸеҲ¶гҒҜгӮҲгӮҠеҢ…жӢ¬зҡ„гҒ§гҖҒгғҮгӮёгӮҝгғ«еәғе‘ҠгӮ„гӮӨгғігғ•гғ«гӮЁгғігӮөгғјгғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°гҒ«гӮӮйҒ©з”ЁзҜ„еӣІгҒҢеәғгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеәғе‘ҠгҒҜзңҹе®ҹгҒ§иӘӨи§ЈгӮ’жӢӣгҒӢгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒҡгҖҒж¶ҲиІ»иҖ…гҒёгҒ®йҖҸжҳҺжҖ§гҒҢеј·гҒҸжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
ж¶ҲиІ»иҖ…дҝқиӯ·гҒ®еј·еҢ–
гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ§гҒҜгҖҒж¶ҲиІ»иҖ…еҘ‘зҙ„гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдёҚе…¬жӯЈжқЎй …гҒ®зҰҒжӯўгҖҒиҝ”е“ҒжЁ©гҖҒдҝқиЁјиІ¬д»»гҒӘгҒ©гҖҒж¶ҲиІ»иҖ…гҒ®жЁ©еҲ©гҒҢжүӢеҺҡгҒҸдҝқиӯ·гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®ж¶ҲиІ»иҖ…гҒ®жЁ©еҲ©гҒҜгҖҒгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°еҘ‘зҙ„дёҠгҒ®еҗҲж„ҸгӮ’дёҠеӣһгӮӢеҠ№еҠӣгӮ’жҢҒгҒӨгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·гҒЁгғҮгғјгӮҝгғ—гғ©гӮӨгғҗгӮ·гғј
гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒҜEUеҠ зӣҹеӣҪгҒ§гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·гҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒдё–з•ҢгҒ§жңҖгӮӮеҺіж јгҒӘгғҮгғјгӮҝдҝқиӯ·жі•гҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒӮгӮӢдёҖиҲ¬гғҮгғјгӮҝдҝқиӯ·иҰҸеүҮпјҲGDPR: General Data Protection Regulation, Regulation (EU) 2016/679пјүгҒҢзӣҙжҺҘйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·жі•гҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰгҖҒйҒ©з”ЁзҜ„еӣІгҖҒгғҮгғјгӮҝдё»дҪ“гҒ®жЁ©еҲ©гҖҒдјҒжҘӯгҒ®зҫ©еӢҷгҖҒзҪ°еүҮгҒ®зӮ№гҒ§еӨ§гҒҚгҒӘйҒ•гҒ„гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
GDPRгҒҜгҖҒEUеҹҹеҶ…гҒ®гғҮгғјгӮҝдё»дҪ“гҒ®еҖӢдәәгғҮгғјгӮҝгӮ’еҮҰзҗҶгҒҷгӮӢдјҒжҘӯгҒ«йҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҖҒгҒқгҒ®еҮҰзҗҶгҒҢEUеҹҹеӨ–гҒ§иЎҢгӮҸгӮҢгӮӢе ҙеҗҲгҒ§гӮӮйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҖҢеҹҹеӨ–йҒ©з”ЁгҖҚгҒ®еҺҹеүҮгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒгғ•гӮЈгғігғ©гғігғүеёӮе ҙгӮ’гӮҝгғјгӮІгғғгғҲгҒЁгҒҷгӮӢж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰзү№гҒ«йҮҚиҰҒгҒӘиҖғж…®дәӢй …гҒ§гҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®еҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·жі•гӮӮеҹҹеӨ–йҒ©з”ЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒGDPRгҒҜгҖҒеҗҢж„ҸгҒ®еҸ–еҫ—гҖҒгғҮгғјгӮҝдё»дҪ“гҒ®жЁ©еҲ©пјҲеҝҳгӮҢгӮүгӮҢгӮӢжЁ©еҲ©гҖҒгғҮгғјгӮҝгғқгғјгӮҝгғ“гғӘгғҶгӮЈгҒ®жЁ©еҲ©гҒӘгҒ©пјүгҖҒгғҮгғјгӮҝдҝқиӯ·еҪұйҹҝи©•дҫЎпјҲDPIAпјүгҖҒгғҮгғјгӮҝдҫөе®ійҖҡзҹҘгҖҒгғҮгғјгӮҝдҝқиӯ·иІ¬д»»иҖ…пјҲDPOпјүгҒ®иЁӯзҪ®зҫ©еӢҷгҒӘгҒ©гҖҒгӮҲгӮҠеҺіж јгҒӘиҰҒ件гӮ’иӘІгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒЁж—Ҙжң¬гҒ®еҠҙеғҚжі•еҲ¶гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдё»иҰҒгҒӘзӣёйҒ•зӮ№
гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ®еҠҙеғҚжі•гҒҜгҖҒеҫ“жҘӯе“ЎгҒ®жЁ©еҲ©дҝқиӯ·гҒ«йҮҚзӮ№гӮ’зҪ®гҒ„гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҠҙеғҚзө„еҗҲгҒ®еҪұйҹҝеҠӣгҒҢеј·гҒ„гҒ“гҒЁгҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®еҠҙеғҚеҹәжә–жі•гӮ„еҠҙеғҚеҘ‘зҙ„жі•гҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰгҖҒеҠҙеғҚжҷӮй–“гҖҒи§ЈйӣҮиҰҸеҲ¶гҖҒеӣЈдҪ“дәӨжёүгҒ®еҪ№еүІгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰйЎ•и‘—гҒӘйҒ•гҒ„гҒҢиҰӢгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
еҠҙеғҚеҘ‘зҙ„гҒЁеҠҙеғҚжқЎд»¶
гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ®еҠҙеғҚеҘ‘зҙ„жі•пјҲTyГ¶sopimuslaki, 55/2001пјүгҒҜгҖҒеҖӢеҲҘгҒ®йӣҮз”Ёй–ўдҝӮгӮ’иҰҸе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ§гҒҜгҖҒеҠҙеғҚзө„еҗҲгҒЁдҪҝз”ЁиҖ…еӣЈдҪ“гҒҢз· зөҗгҒҷгӮӢеӣЈдҪ“еҠҙеғҚеҚ”зҙ„пјҲCollective Bargaining Agreements, CBAпјүгҒҢжҘөгӮҒгҒҰйҮҚиҰҒгҒӘеҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒжі•е®ҡеҹәжә–гӮҲгӮҠгӮӮжңүеҲ©гҒӘеҠҙеғҚжқЎд»¶гӮ’е®ҡгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҖҒеҠҙеғҚиҖ…гҒ®еӨ§йғЁеҲҶгӮ’гӮ«гғҗгғјгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҢгғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ§еҫ“жҘӯе“ЎгӮ’йӣҮз”ЁгҒҷгӮӢйҡӣгҒҜгҖҒеҚҳгҒ«еҠҙеғҚеҘ‘зҙ„жі•гӮ„еҠҙеғҚжҷӮй–“жі•гҒӘгҒ©гҒ®еҖӢеҲҘжі•иҰҸгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒи©ІеҪ“гҒҷгӮӢз”ЈжҘӯеҲҶйҮҺгҒ®CBAгҒ®еҶ…е®№гӮ’и©ізҙ°гҒ«зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®еҠҙеғҚжі•гҒҢдё»гҒ«еҖӢеҲҘжі•иҰҸгҒЁе°ұжҘӯиҰҸеүҮгҒ«йҮҚзӮ№гӮ’зҪ®гҒҸгҒ®гҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮҠгҖҒгғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ§гҒҜCBAгҒҢе®ҹиіӘзҡ„гҒӘжңҖдҪҺеҹәжә–гҒЁгҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒдәҲжңҹгҒӣгҒ¬дәә件費増еҠ гӮ„еҠҙеғҚжқЎд»¶гҒ®еҺіж јеҢ–гҒ«зӣҙйқўгҒҷгӮӢгғӘгӮ№гӮҜгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҜгғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ§гҒ®йӣҮз”ЁиЁҲз”»гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒCBAгҒ®иӘҝжҹ»гҒЁе°Ӯй–Җ家гҒ«гӮҲгӮӢгӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№гӮ’гҖҒж—Ҙжң¬д»ҘдёҠгҒ«йҮҚиҰ–гҒҷгҒ№гҒҚгҒ§гҒҷгҖӮ
и§ЈйӣҮиҰҸеҲ¶
гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢйӣҮз”ЁеҘ‘зҙ„гҒ®зөӮдәҶгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢжӯЈеҪ“гҒӢгҒӨеҗҲзҗҶзҡ„гҒӘзҗҶз”ұгҖҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜж—Ҙжң¬гҒ®и§ЈйӣҮжЁ©жҝ«з”Ёжі•зҗҶгҒ«йЎһдјјгҒ—гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ§гҒҜеҠҙеғҚзө„еҗҲгҒ®еҪұйҹҝеҠӣгҒҢеј·гҒҸгҖҒCBAгҒ«гӮҲгӮӢдҝқиӯ·гӮӮеҠ гӮҸгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒе®ҹеӢҷдёҠгҒҜж—Ҙжң¬гӮҲгӮҠгӮӮи§ЈйӣҮгҒ®гғҸгғјгғүгғ«гҒҢй«ҳгҒҸгҖҒдјҒжҘӯгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰдәәе“ЎеүҠжёӣгӮ„зө„з№”еҶҚз·ЁгҒ®жҹ”и»ҹжҖ§гҒҢеҲ¶йҷҗгҒ•гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ§гҒҜгҖҒеҠҙеғҚзө„еҗҲгҒ®еҠӣгҒҢеј·гҒҸгҖҒCBAгҒҢеәғзҜ„гҒ«йҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒи§ЈйӣҮгҒ®жӯЈеҪ“жҖ§гҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҲӨж–ӯеҹәжә–гҒҢгӮҲгӮҠеҺіж јгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒдјҒжҘӯгҒҢдёҖж–№зҡ„гҒ«и§ЈйӣҮгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеӣ°йӣЈгҒ«гҒӘгӮӢеӮҫеҗ‘гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ®еҢ»и–¬е“Ғгғ»еҢ»зҷӮж©ҹеҷЁгҒ®иҰҸеҲ¶гҒЁеҢ»зҷӮеәғе‘ҠгӮ¬гӮӨгғүгғ©гӮӨгғі

гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ§гҒҜгҖҒеҢ»и–¬е“Ғжі•пјҲLГӨГӨkelaki, 395/1987пјүгҒҢеҢ»и–¬е“ҒгҒ®иЈҪйҖ гҖҒиІ©еЈІгҖҒијёе…ҘгҖҒжөҒйҖҡгӮ’иҰҸеҲ¶гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒEUгҒ®еҢ»и–¬е“ҒиҰҸеҲ¶жһ зө„гҒҝгҒ«жә–жӢ гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҢ»зҷӮеәғе‘ҠгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒеҺіж јгҒӘиҰҸеҲ¶гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҢ»зҷӮеәғе‘ҠгӮ¬гӮӨгғүгғ©гӮӨгғігҒЁеҗҢж§ҳгҒ«гҖҒиҷҡеҒҪгғ»иӘҮеӨ§еәғе‘ҠгҖҒиӘӨи§ЈгӮ’жӢӣгҒҸиЎЁзӨәгҒҢзҰҒжӯўгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒеҮҰж–№и–¬гҒ®дёҖиҲ¬еҗ‘гҒ‘еәғе‘ҠгҒҜеҺігҒ—гҒҸеҲ¶йҷҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиіҮйҮ‘жұәжёҲгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®иҰҸеҲ¶
гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ®иіҮйҮ‘жұәжёҲгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜгҖҒEUгҒ®жұәжёҲгӮөгғјгғ“гӮ№жҢҮд»ӨпјҲPSD2пјүгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒиіҮйҮ‘жұәжёҲгӮөгғјгғ“гӮ№жі•пјҲMaksupalvelulaki, 297/2010пјүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиҰҸеҲ¶гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®иіҮйҮ‘жұәжёҲжі•гҒЁеҗҢж§ҳгҒ«гҖҒжұәжёҲгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®жҸҗдҫӣиҖ…гҒ«гғ©гӮӨгӮ»гғігӮ№еҸ–еҫ—гӮ’зҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гҖҒеҲ©з”ЁиҖ…дҝқиӯ·гӮ’еј·еҢ–гҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒгӮӘгғјгғ—гғігғҗгғігӮӯгғігӮ°гҒ®жҺЁйҖІгӮ„гҖҒ第дёүиҖ…жұәжёҲгӮөгғјгғ“гӮ№гғ—гғӯгғҗгӮӨгғҖгғјпјҲTPPпјүгҒёгҒ®йҠҖиЎҢеҸЈеә§жғ…е ұгӮўгӮҜгӮ»гӮ№иЁұеҸҜгҒӘгҒ©гҖҒж—Ҙжң¬гӮҲгӮҠгӮӮйҖІгӮ“гҒ иҰҸеҲ¶з’°еўғгҒҢиҰӢгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ®йҮ‘иһҚзӣЈзқЈеәҒпјҲFIN-FSAпјүгҒҢжұәжёҲгӮөгғјгғ“гӮ№гғ—гғӯгғҗгӮӨгғҖгғјгҒ®гғ©гӮӨгӮ»гғігӮ№гӮ’зӣЈзқЈгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒ
гғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒёгҒ®дәӢжҘӯеұ•й–ӢгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒзҸҫең°гҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒёгҒ®ж·ұгҒ„зҗҶи§ЈгҒЁйҒ©еҲҮгҒӘеҜҫеҝңгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮжң¬зЁҝгҒ§и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒҜж—Ҙжң¬жі•гҒЁе…ұйҖҡгҒ®еҹәзӣӨгӮ’жҢҒгҒӨдёҖж–№гҒ§гҖҒдјҡзӨҫиЁӯз«ӢгҖҒеҘ‘зҙ„гҖҒеәғе‘ҠиҰҸеҲ¶гҖҒеҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·гҖҒеҠҙеғҚжі•гҖҒзү№е®ҡгҒ®з”ЈжҘӯеҲҶйҮҺгҒ®иҰҸеҲ¶гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒе®ҹеӢҷдёҠйҮҚиҰҒгҒӘзӣёйҒ•зӮ№гҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒGDPRгҒ®еҹҹеӨ–йҒ©з”ЁгҖҒеӣЈдҪ“еҠҙеғҚеҚ”зҙ„гҒ®еәғзҜ„гҒӘеҪұйҹҝгҖҒгҒқгҒ—гҒҰеҺіж јгҒӘж¶ҲиІ»иҖ…дҝқиӯ·гғ»еәғе‘ҠиҰҸеҲ¶гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҢдәӢеүҚгҒ«еҚҒеҲҶгҒ«жӨңиЁҺгҒ—гҖҒеҜҫзӯ–гӮ’и¬ӣгҒҳгӮӢгҒ№гҒҚдё»иҰҒгҒӘгғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒҷгҖӮ
гғўгғҺгғӘгӮ№жі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒ®жө·еӨ–йҖІеҮәж”ҜжҸҙгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰиұҠеҜҢгҒӘзөҢйЁ“гҒЁе®ҹзёҫгӮ’жңүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзҸҫең°гҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒ«й–ўгҒҷгӮӢи©ізҙ°гҒӘиӘҝжҹ»гҖҒдјҡзӨҫиЁӯз«ӢжүӢз¶ҡгҖҒеҗ„зЁ®еҘ‘зҙ„жӣёгҒ®дҪңжҲҗгғ»гғ¬гғ“гғҘгғјгҖҒGDPRгӮ’еҗ«гӮҖеҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·дҪ“еҲ¶гҒ®ж§ӢзҜүгҖҒеҠҙеғҚжі•еӢҷгӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№гҖҒеәғе‘ҠиҰҸеҲ¶гҒ«й–ўгҒҷгӮӢгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№ж”ҜжҸҙгҒӘгҒ©гҖҒеӨҡеІҗгҒ«гӮҸгҒҹгӮӢгғӘгғјгӮ¬гғ«гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮгғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ®жі•еҫӢе°Ӯй–Җ家гҒЁгҒ®гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮӮжҙ»з”ЁгҒ—гҖҒиІҙзӨҫгҒ®гғ“гӮёгғҚгӮ№гҒҢзҸҫең°гҒ§еҶҶж»‘гҒӢгҒӨжі•зҡ„гҒ«е®үе…ЁгҒ«еұ•й–ӢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҖҒжңҖйҒ©гҒӘгӮҪгғӘгғҘгғјгӮ·гғ§гғігӮ’гҒ”жҸҗжЎҲгҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
й–ўйҖЈеҸ–жүұеҲҶйҮҺпјҡеӣҪйҡӣжі•еӢҷгғ»жө·еӨ–дәӢжҘӯ
гӮ«гғҶгӮҙгғӘгғј: ITгғ»гғҷгғігғҒгғЈгғјгҒ®дјҒжҘӯжі•еӢҷ