フランス民法典の「予見可能性のない状況変化」と契約の再交渉(ハードシップ条項)

フランスでのビジネスを行う上で、注意しなければいけないテーマの一つが、「予見可能性のない状況変化」と契約の再交渉を定める、いわゆる「ハードシップ条項」です。これは、フランス民法典第1195条に明文化された制度であり、契約締結時には予見できなかった状況変化によって、一方の当事者の契約履行が「過度な負担」となった場合に、再交渉や裁判所による契約の改訂・解除を認めるものです。
予見できなかった状況変化が生じた場合について、日本でも、「事情変更の原則」と呼ばれる法理は存在します。ただ、フランス民法典のハードシップ条項は、日本の事情変更の原則とは根本的に異なる特徴を持っています。
なお、フランス法は、2016年の契約法大改正により、このハードシップ条項を明文化しました。この歴史的背景を紐解くと、従前、判例法理は「契約は守られなければならない」(Pacta sunt servanda)という原則を守り、予見不可能な状況変化による契約の改訂を否定してきました。しかし、こうした判例法理は、戦争、パンデミック、金融危機など、現代の経済環境における大規模な混乱に対応できないという問題を生じさせました。立法者は、この問題を解決し、契約関係に柔軟性を持たせるため、明文規定を導入した、とされています。
本記事では、フランス民法典のハードシップ条項の要件や、これに関連する裁判例について、解説します。
なお、フランスの包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。
この記事の目次
フランス民法典が定めるハードシップ条項の法的根拠と要件
フランス民法典第1195条は、ハードシップ条項の適用要件と手続きを定めています。この条文は、予見不可能な状況変化が契約履行を著しく困難にした場合の当事者の権利として、以下の条項を置いています。
契約締結時に予見不可能であった状況変化が、そのリスクを引き受けていなかった当事者にとって、履行を過度な負担とする場合、当該当事者は、相手方に対し、契約の再交渉を求めることができる。相手方は、再交渉期間中も、その義務を履行し続けなければならない。再交渉が拒絶された、または失敗した場合、当事者は、自らが定める日および条件で契約を終了させることに合意するか、または共同で裁判官に契約の改訂を求めることができる。合理的な期間内に合意がない場合、裁判官は、当事者の一方の請求により、契約を改訂し、または自らが定める日および条件で契約を終了させることができる。
フランス民法典第1195条
この条文から読み取れるハードシップ条項の適用要件は、以下の三つです。
契約締結時に予見不可能であった状況変化であること
ハードシップを主張する出来事は、契約を締結した時点において、当事者が合理的に予見できなかったものでなければなりません。裁判所は、当事者の専門性や契約締結時の状況を考慮して、予見可能性の有無を個別に判断します。
履行が一方にとって「過度な負担」となったこと
単に履行が困難になったり、当初の利益が見込めなくなったりしただけでは足りません。経済的に「過度に」負担が重くなったことが必要です。これは、事業の採算性を著しく損なうほどの、甚大な経済的不均衡が生じたことを指します。
そのリスクを負わない合意がなされていること
影響を受けた当事者が、契約上、その状況変化によるリスクを自ら引き受けていないことが要件となります。
なお、この要件に関連する重要なポイントとして、ハードシップ条項は任意規定であるため、当事者間の合意による排除が可能です。つまり、当事者が契約に「ハードシップ条項を適用しない」旨を明記したり、リスクを一方的に引き受ける条項を設けていたりした場合は、ハードシップ条項は適用されず、「予見不可能であった状況変化」などが生じた場合でも契約を有効に存続させることができます。
フランスのハードシップ条項と日本法の「事情変更の原則」との相違点
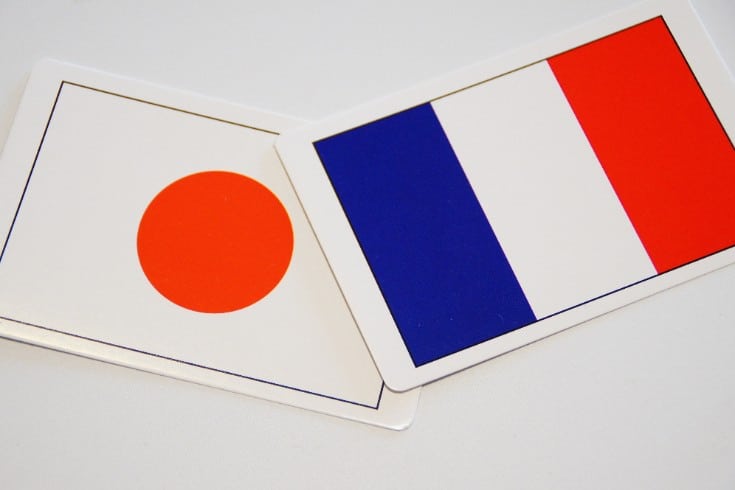
日本法における「事情変更の原則」は、民法第1条2項の信義誠実の原則を根拠とする判例法理で、一定の条件が満たされた場合に契約の解除や契約の改定を認める法原理です。日本の最高裁は、こうした法理があり得ること自体は認めていますが、この原則の適用を極めて限定的に解釈しており、適用を否定した事例が多数存在します。また、あくまで判例法理であり、法律上明文で認められている制度ではありません。
フランス法では、ハードシップの要件を満たした場合、当事者は相手方に対し、「再交渉要請」という具体的な手続を、法文上で認められています。また、再交渉が拒否されたり、合理的な期間内に合意に至らなかった場合、一方の当事者の請求に基づき、裁判官が契約を「改訂」または「解除」する権限を持ちます。この裁判官の能動的な介入権は、日本法には見られない大きな特徴です。
この違いより、フランス法では、再交渉の請求権が法的に保障されているため、契約相手が交渉に応じない場合でも、法的手段を通じて解決を図ることができますし、交渉拒否が事後的に法的に問題になりやすいという構造があります。これに対し、日本法では、日本の法務省の検討資料でも言及されているように、再交渉義務が確立されていないため、契約交渉での再交渉の拒否が法的に問題となりにくいという実務上の違いが生じます。
| 項目 | フランス法(ハードシップ条項) | 日本法(事情変更の原則) |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 民法典第1195条(明文規定) | 信義誠実の原則(判例法理) |
| 再交渉義務 | 履行が過度な負担となった場合、相手方に対し再交渉を求めることができる(法的権利) | 明示的な義務はない |
| 裁判所の役割 | 契約の改訂または解除 | 主に契約の解除の可否を判断 |
| 適用要件の厳格性 | 比較的柔軟な適用が可能(条文に定められた要件を満たせば適用されうる) | 極めて厳格な適用(適用否定例が多数存在) |
現代のビジネスにおけるハードシップ条項の適用と裁判例
近年の新型コロナウイルス感染症のパンデミックやウクライナ紛争といった国際的な出来事は、ハードシップ条項がどのように実務で機能するかを示す具体的なケーススタディとなりました。これらの出来事によるサプライチェーンの混乱や原材料価格の急騰により、多くの企業にとって、契約履行が「過度な負担」となる状況が生じたからです。
このような状況下で、フランスの裁判所が下した一つの重要な判断が、2022年12月14日のパリ商事裁判所の判決です。この判決は、ハードシップ条項の適用を認め、契約の解除を命じた具体例として、実務上大きな指針となり得ます。
この事案では、新型コロナウイルス感染症のパンデミックとウクライナ紛争によるインフレで、ある企業の生産コストが300%も上昇し、採算割れの状態に陥ったと主張されました。裁判所は、この「300%のコスト上昇」が、契約履行が「過度な負担」であるという要件を満たすと判断しました。そして、再交渉を経ても合意に至らなかったため、契約の解除を命じたのです。
一方、この制度の適用に慎重な姿勢を示した判決も出ています。2022年6月30日、破棄院(Cour de cassation)は、新型コロナウイルス対策の営業停止措置によって商業用テナントが賃料を支払えない状況が、ハードシップ条項の適用要件を満たすかについて検討しました。破棄院は、賃料支払いが「金銭債務」であることを理由に、この状況が直ちに「過度な負担」に当たるとは判断しませんでした。この判決は、ハードシップ条項が、経済的な均衡が著しく崩れた場合に適用されるという考え方を改めて強調し、特に販管費の金銭債務についてはその適用が限定的である旨を述べていると言えるでしょう。
これらの裁判例から、条文上の「過度な負担」(excessively onerous)という抽象的な概念に対し、具体的な判断基準が示されたということができます。単に採算性が悪化しただけではハードシップは認められず、事業の存続に影響を与えるほどの甚大な経済的負担が求められるという姿勢を読み取ることができます。ただ、300%という数値は、今後のハードシップ条項の適用を検討する上で、一つの重要なベンチマークとして参照される可能性があります。
フランスでの契約実務とハードシップ条項

フランスでのビジネスを検討する日本企業は、フランス民法典第1195条の存在を前提として、契約交渉を行う必要があります。重要なポイントは、以下の2点だと思われます。
まず、ハードシップ条項とフォース・マジュール(不可抗力)条項との違いを理解し、それぞれに対応した条項を規定することです。フォース・マジュールは、例えば輸出入禁止や法的制裁などにより、契約履行が物理的または法的に「不可能」になった場合に適用される制度です。一方、ハードシップは、履行は可能であることを前提に、それが経済的に「過度な負担」となる場合に適用されます。契約書では、これらの条項を明確に区別し、それぞれの適用範囲と効果を具体的に定める必要があります。
また、フランス民法典第1195条は任意規定であるため、当事者の合意によりその適用を排除または修正することができます。このことは、長期契約や、価格変動リスクの高い契約において、契約交渉における重要なポイントとなります。
日本法の下では、ハードシップに関する合意は、「原則として契約による拘束力が強く、事情変更の原則は例外的にしか使えない」という前提の下で、例えば、原価変動リスクを負わない側は、「ハードシップに関する合意を契約書に記載しない方が良い」という判断を行い、契約交渉を行っているはずです。しかしフランスでは、「契約書に何も記載しないと、民法典の定めるハードシップ条項が有効になる」ため、日本での契約交渉とは、ゲームルールが異なります。ハードシップ条項の発動を求めない側も、明示的にその適用を排除する条項を、契約書に追加する必要があります。デフォルトでハードシップ条項が適用されるため、明示的な価格調整条項や再交渉の条件、リスク分担に関する条項を設けることが、将来的なリスクを管理する上で不可欠だと言えます。
まとめ
フランス法は、2016年の民法典改正により、予見不能な状況変化による過度な負担に対し、再交渉を求める法定の権利と1104条を根拠とする再交渉義務、さらに裁判所による能動的な契約改訂・解除の道を開きました。これは、明文規定がなく、適用が極めて厳格な日本の事情変更の原則とは異なるものです。特に、再交渉義務の有無と、裁判所の契約改訂権限が決定的な違いを生み出しています。近年の裁判例は、「過度な負担」の具体的な基準を示唆しており、実務上の指針となり得ることがわかります。
フランスでのビジネス展開を検討する日本企業にとって、この制度を深く理解し、契約締結前に、ハードシップ条項の適用関係を慎重に確認することが不可欠です。フォース・マジュール条項などと組み合わせて、自社に有利な契約条件を交渉することが、将来的なリスクを効果的に管理する上で不可欠となります。単に契約書を締結するだけでなく、将来的なリスクを予見し、それを契約に織り込むという「予防法務」の観点が、フランスでの取引のためには重要だと言えるでしょう。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務


































