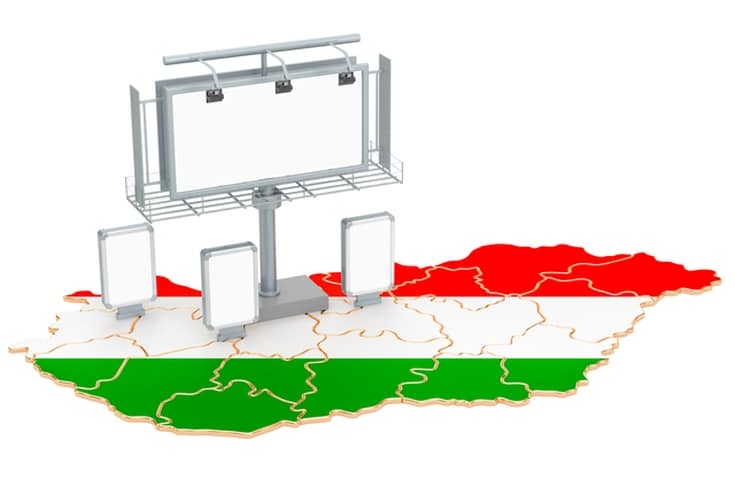гӮӨгғігғүе…ұе’ҢеӣҪгҒ®жі•дҪ“зі»гҒЁеҸёжі•еҲ¶еәҰгӮ’ејҒиӯ·еЈ«гҒҢи§ЈиӘ¬

жҖҘйҖҹгҒӘзөҢжёҲжҲҗй•·гӮ’йҒӮгҒ’гӮӢгӮӨгғігғүпјҲжӯЈејҸеҗҚз§°пјҡгӮӨгғігғүе…ұе’ҢеӣҪпјүгҒҜгҖҒе·ЁеӨ§гҒӘеёӮе ҙгғқгғҶгғігӮ·гғЈгғ«гҒЁиұҠеҜҢгҒӘдәәжқҗгӮ’иғҢжҷҜгҒ«гҖҒж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰдёҚеҸҜж¬ гҒӘгғ“гӮёгғҚгӮ№гғ‘гғјгғҲгғҠгғјгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®ең°дҪҚгӮ’зўәз«ӢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®еёӮе ҙгҒёгҒ®еҸӮе…ҘгӮ„дәӢжҘӯжӢЎеӨ§гӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢдјҒжҘӯгҒҢзӣҙйқўгҒҷгӮӢжңҖеӨ§гҒ®йҡңеЈҒгҒ®дёҖгҒӨгҒҢгҖҒжҘөгӮҒгҒҰиӨҮйӣ‘гҒӢгҒӨзӢ¬зү№гҒӘи«–зҗҶгҒ§еӢ•гҒҸгҖҢжі•еҲ¶еәҰгҖҚгҒ§гҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬гҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒҜжҳҺжІ»жңҹгҒ«гғүгӮӨгғ„гӮ„гғ•гғ©гғігӮ№гҒ®еӨ§йҷёжі•пјҲгӮ·гғ“гғ«гғ»гғӯгғјпјүгӮ’зҜ„гҒЁгҒ—гҒҰж•ҙеӮҷгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒе…ӯжі•е…ЁжӣёгҒ«д»ЈиЎЁгҒ•гӮҢгӮӢжҲҗж–Үжі•пјҲгӮігғјгғүпјүгҒҢжі•гҒ®дё»иҰҒгҒӘжәҗжіүгҒ§гҒҷгҖӮеҜҫгҒ—гҒҰгҖҒгӮӨгғігғүгҒҜиӢұеӣҪжӨҚж°‘ең°жҷӮд»ЈгҒ«е°Һе…ҘгҒ•гӮҢгҒҹиӢұзұіжі•пјҲгӮігғўгғігғ»гғӯгғјпјүгҒ®дјқзөұгӮ’иүІжҝғгҒҸеҸ—гҒ‘з¶ҷгҒ„гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж №жң¬зҡ„гҒӘжі•дҪ“зі»гҒ®зӣёйҒ•гҒҜгҖҒеҘ‘зҙ„жӣёгҒ®и§ЈйҮҲгҒӢгӮүеҠҙеӢҷз®ЎзҗҶгҖҒзҙӣдәүи§ЈжұәгҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§гҖҒгҒӮгӮүгӮҶгӮӢгғ“гӮёгғҚгӮ№еұҖйқўгҒ«еҪұйҹҝгӮ’еҸҠгҒјгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгӮӨгғігғүжі•еӢҷгӮ’йӣЈи§ЈгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢгҖҒжҶІжі•гҒ«еҹәгҒҘгҒҸеҺіж јгҒӘгҖҢйҖЈйӮҰеҲ¶гҖҚгҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒ«дјҙгҒҶжі•гҒ®йҮҚеұӨж§ӢйҖ гҒ§гҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜе…ЁеӣҪдёҖеҫӢгҒ®иҰҸеҲ¶гҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢдәӢй …гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгӮӨгғігғүгҒ§гҒҜе·һгҒ”гҒЁгҒ«е…ЁгҒҸз•°гҒӘгӮӢиҰҸеҲ¶гҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢзҸҚгҒ—гҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮеҠ гҒҲгҒҰгҖҒиҝ‘е№ҙгҒ®гӮӨгғігғүеҸёжі•гҒҜгҖҒгғ“гӮёгғҚгӮ№з’°еўғгҒ®ж”№е–„гӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҹгҖҢе•ҶжҘӯиЈҒеҲӨжүҖжі•пјҲCommercial Courts ActпјүгҖҚгҒ®еҲ¶е®ҡгӮ„гҖҒгҖҢеӣҪз«ӢдјҡзӨҫжі•еҜ©еҲӨжүҖпјҲNCLTпјүгҖҚгҒ®жЁ©йҷҗеј·еҢ–гҒӘгҒ©гҖҒзҹўз¶ҷгҒҺж—©гҒ«ж”№йқ©гӮ’йҖІгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒгӮӨгғігғүжі•еӢҷгҒ®ж №е№№гӮ’жҲҗгҒҷгҖҢгӮігғўгғігғ»гғӯгғјгҒЁеҲӨдҫӢжі•гҒ®жӢҳжқҹеҠӣгҖҚгҖҒиӨҮйӣ‘жҖӘеҘҮгҒӘгҖҢйҖЈйӮҰеҲ¶дёӢгҒ®з«Ӣжі•жЁ©йҷҗгҖҚгҖҒгҒқгҒ—гҒҰж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҢжңҖгӮӮиӯҰжҲ’гҒҷгҒ№гҒҚгҖҢзҙӣдәүи§ЈжұәгҒЁеҸёжі•еҲ¶еәҰгҒ®жңҖж–°еӢ•еҗ‘гҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒӘжқЎж–ҮгҒЁйҮҚиҰҒеҲӨдҫӢгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒи©ізҙ°гҒӢгҒӨз¶Ізҫ…зҡ„гҒ«и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢжҰӮиӘ¬гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгӮӨгғігғүгҒ§дәӢжҘӯгӮ’еұ•й–ӢгҒҷгӮӢзөҢе–¶иҖ…гҒҠгӮҲгҒіжі•еӢҷжӢ…еҪ“иҖ…гҒҢгҖҒжі•зҡ„гғӘгӮ№гӮҜгӮ’жӯЈзўәгҒ«дәҲжё¬гҒ—гҖҒжҲҰз•Ҙзҡ„гҒӘж„ҸжҖқжұәе®ҡгӮ’иЎҢгҒҶгҒҹгӮҒгҒ®зҫ…йҮқзӣӨгҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒгӮӨгғігғүгҒ®еҢ…жӢ¬зҡ„гҒӘжі•еҲ¶еәҰгҒ®жҰӮиҰҒгҒҜдёӢиЁҳиЁҳдәӢгҒ«гҒҰгҒҫгҒЁгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®зӣ®ж¬Ў
гӮігғўгғігғ»гғӯгғјдҪ“зі»гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮӨгғігғүгҖҢжі•гҖҚпјҡеҲӨдҫӢжі•дё»зҫ©гҒЁе…ҲдҫӢжӢҳжқҹжҖ§
ж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒ®жі•еӢҷжӢ…еҪ“иҖ…гҒҢгӮӨгғігғүжі•гҒ«и§ҰгӮҢгҒҹйҡӣгҖҒжңҖеҲқгҒ«жҲёжғ‘гҒҶгҒ®гҒҢгҖҢжқЎж–ҮгҒҢиҰӢеҪ“гҒҹгӮүгҒӘгҒ„гҖҚгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҢжқЎж–ҮгҒ®ж–ҮиЁҖгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜзөҗи«–гҒҢеҮәгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶдәӢж…ӢгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒгӮӨгғігғүгҒҢгӮігғўгғігғ»гғӯгғјпјҲCommon LawпјүгҒ®еӣҪгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҲӨдҫӢжі•пјҲCase LawпјүгҒҢжҲҗж–Үжі•гҒЁеҗҢзӯүгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҒқгӮҢд»ҘдёҠгҒ®йҮҚгҒҝгӮ’жҢҒгҒӨгҒ“гҒЁгҒ«иө·еӣ гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®жі•еҲ¶еәҰгҖҒгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгӮ·гғ“гғ«гғ»гғӯгғјпјҲеӨ§йҷёжі•пјүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒжі•е…ёпјҲгӮігғјгғүпјүгҒҢ第дёҖж¬Ўзҡ„гҒӘжі•жәҗгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҪ№еүІгҒҜжқЎж–ҮгҒ®и§ЈйҮҲйҒ©з”ЁгҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“ж—Ҙжң¬гҒ§гӮӮеҲӨдҫӢгҒҜе®ҹеӢҷдёҠйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжі•еҪўејҸзҡ„гҒ«гҒҜгҖҒеҲӨжұәгҒҜгҒқгҒ®дәӢ件йҷҗгӮҠгҒ®и§ЈжұәгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒе°ҶжқҘгҒ®дәӢ件гӮ’жі•зҡ„гҒ«жӢҳжқҹгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгӮӨгғігғүгҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒйҒҺеҺ»гҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨжұәпјҲе…ҲдҫӢпјүгҒҢгҖҒе°ҶжқҘзҷәз”ҹгҒҷгӮӢйЎһдјјгҒ®дәӢ件гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰжі•зҡ„жӢҳжқҹеҠӣгӮ’жҢҒгҒӨгҒЁгҒ„гҒҶгҖҢе…ҲдҫӢжӢҳжқҹжҖ§гҒ®еҺҹзҗҶпјҲStare DecisisпјүгҖҚгҒҢжҺЎз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҺҹзҗҶгҒҜгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢж…Јзҝ’гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгӮӨгғігғүжҶІжі•гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжҳҺзўәгҒ«иЈҸд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹжҶІжі•дёҠгҒ®еҺҹеүҮгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӨгғігғүжҶІжі•з¬¬141жқЎгҒЁжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжұәгҒ®зө¶еҜҫжҖ§
гӮӨгғігғүгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҲӨдҫӢжі•гҒ®жӢҳжқҹеҠӣгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒжңҖгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘжі•зҡ„ж №жӢ гҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒҢгӮӨгғігғүжҶІжі•з¬¬141жқЎгҒ§гҒҷгҖӮеҗҢжқЎгҒҜд»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҰҸе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
The Constitution of India, Article 141пјҡ
“The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India.”
пјҲгӮӨгғігғүжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе®ЈиЁҖгҒ•гӮҢгҒҹжі•гҒҜгҖҒгӮӨгғігғүй ҳеңҹеҶ…гҒ®гҒҷгҒ№гҒҰгҒ®иЈҒеҲӨжүҖгӮ’жӢҳжқҹгҒҷгӮӢгҖӮпјү
еҸӮиҖғпјҡгӮӨгғігғүжҶІжі•з¬¬141жқЎпјҲжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨжұәгҒ®жӢҳжқҹеҠӣпјү
гҒ“гҒ®жқЎж–ҮгҒҢжҢҒгҒӨж„Ҹе‘ігҒҜжҘөгӮҒгҒҰйҮҚгҒ„гҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨжұәгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгҒқгӮҢгҒҜгҖҢеҲӨдҫӢгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰе°ҠйҮҚгҒ•гӮҢгӮӢгҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгӮӨгғігғүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҢеҲӨжұәгҒ®дёӯгҒ§зӨәгҒ—гҒҹжі•и§ЈйҮҲгӮ„еҺҹеүҮгҒҜгҖҒгҖҢLawпјҲжі•пјүгҖҚгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒЁгҒ—гҒҰжүұгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒеӣҪдјҡгҒҢеҲ¶е®ҡгҒ—гҒҹжі•еҫӢпјҲActпјүгҒЁеҗҢзӯүгҒ®еҠ№еҠӣгӮ’жҢҒгҒЎгҖҒгӮӨгғігғүе…ЁеңҹгҒ®й«ҳзӯүиЈҒеҲӨжүҖпјҲHigh CourtпјүгӮ„дёӢзҙҡиЈҒеҲӨжүҖгӮ’жі•зҡ„гҒ«жӢҳжқҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҢгӮӨгғігғүжі•гҒ®гғӘгӮ№гӮҜеҲҶжһҗгӮ’иЎҢгҒҶйҡӣгҒҜгҖҒеҲ¶е®ҡжі•гӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜдёҚеҚҒеҲҶгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҢгҒқгҒ®жқЎж–ҮгӮ’гҒ©гҒҶи§ЈйҮҲгҒ—гҒҹгҒӢгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜжқЎж–ҮгҒ®з©әзҷҪгӮ’еҹӢгӮҒгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҺҹеүҮгӮ’е®ЈиЁҖгҒ—гҒҹгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒжңҖж–°гҒ®еҲӨдҫӢпјҲPrecedentпјүгӮ’иӘҝжҹ»гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮжқЎж–ҮдёҠгҒҜеҗҲжі•гҒ«иҰӢгҒҲгӮӢиЎҢзӮәгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒжңҖй«ҳиЈҒгҒ®еҲӨжұәгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰйҒ•жі•гҒЁеҲӨж–ӯгҒ•гӮҢгӮӢгғӘгӮ№гӮҜгҒҢеёёгҒ«еӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҢеҲӨжұәзҗҶз”ұпјҲRatio DecidendiпјүгҖҚгҒЁгҖҢеӮҚи«–пјҲObiter DictaпјүгҖҚгҒ®еі»еҲҘ
е…ҲдҫӢжӢҳжқҹжҖ§гҒ®еҺҹзҗҶгӮ’е®ҹеӢҷгҒ§йҒ©з”ЁгҒҷгӮӢйҡӣгҖҒжҘөгӮҒгҒҰйҮҚиҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒҢгҖҒеҲӨжұәж–ҮгҒ®гҒ©гҒ®йғЁеҲҶгҒҢжӢҳжқҹеҠӣгӮ’жҢҒгҒӨгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ§гҒҷгҖӮгӮӨгғігғүгҒ®жі•зҡ„е®ҹеӢҷгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒжӢҳжқҹеҠӣгӮ’жҢҒгҒӨгҒ®гҒҜеҲӨжұәгҒ®зөҗи«–гӮ’е°ҺгҒҚеҮәгҒҷгҒҹгӮҒгҒ«дёҚеҸҜж¬ гҒӘи«–зҗҶзҡ„ж ёгҒЁгҒӘгӮӢгҖҢеҲӨжұәзҗҶз”ұпјҲRatio DecidendiпјүгҖҚгҒ®гҒҝгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиЈҒеҲӨе®ҳгҒҢиЈңи¶ізҡ„гҒ«иҝ°гҒ№гҒҹж„ҸиҰӢгӮ„ж„ҹжғігҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜд»®е®ҡгҒ®и©ұгҒ§гҒӮгӮӢгҖҢеӮҚи«–пјҲObiter DictaпјүгҖҚгҒ«гҒҜжі•зҡ„жӢҳжқҹеҠӣгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгҒӮгӮӢеҘ‘зҙ„зҙӣдәүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰжңҖй«ҳиЈҒгҒҢгҖҢжң¬д»¶еҘ‘зҙ„гҒ®и§ЈйҷӨгҒҜз„ЎеҠ№гҒ§гҒӮгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶзөҗи«–гӮ’еҮәгҒ—гҒҹгҒЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®зөҗи«–гҒ«иҮігӮӢйҒҺзЁӢгҒ§гҖҢеҘ‘зҙ„жӣёз¬¬XжқЎгҒ«еҹәгҒҘгҒҸйҖҡзҹҘгҒҜгҖҒжӣёз•ҷйғөдҫҝгҒ§иЎҢгӮҸгӮҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶи«–зҗҶгҒҢеұ•й–ӢгҒ•гӮҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҢзөҗи«–гҒ®еҹәзӨҺгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮҢгҒ°гҖҒгҒ“гӮҢгҒҜRatio DecidendiгҒЁгҒ—гҒҰеҫҢгҒ®дәӢ件гӮ’жӢҳжқҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеҗҢгҒҳеҲӨжұәж–ҮгҒ®дёӯгҒ§иЈҒеҲӨе®ҳгҒҢгҖҢгӮӮгҒЈгҒЁгӮӮгҖҒгӮӮгҒ—еҪ“дәӢиҖ…гҒҢйӣ»еӯҗгғЎгғјгғ«гҒ§гҒ®йҖҡзҹҘгҒ«дәӢеүҚгҒ«еҗҲж„ҸгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒӘгӮүгҒ°гҖҒзөҗи«–гҒҜз•°гҒӘгҒЈгҒҹгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹд»®е®ҡгҒ®и©ұгӮ’иҝ°гҒ№гҒҹе ҙеҗҲгҖҒгҒқгӮҢгҒҜObiter DictaгҒ«йҒҺгҒҺгҒҡгҖҒе°ҶжқҘгҒ®дәӢ件гҒ§иЈҒеҲӨжүҖгӮ’жӢҳжқҹгҒ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
ж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҢзҸҫең°гҒ®ејҒиӯ·еЈ«пјҲAdvocateпјүгҒӢгӮүж„ҸиҰӢжӣёпјҲLegal OpinionпјүгӮ’еҸ–еҫ—гҒҷгӮӢйҡӣгҖҒгҒқгҒ®ж №жӢ гҒЁгҒ—гҒҰжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢеҲӨдҫӢгҒҢгҖҒдәӢжЎҲгҒ®ж ёеҝғйғЁеҲҶпјҲRatioпјүгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢеӮҚи«–пјҲObiterпјүгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгӮ’иҰӢжҘөгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒжі•зҡ„е®үе®ҡжҖ§гӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢдёҠгҒ§жҘөгӮҒгҒҰйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮзҸҫең°гҒ®ејҒиӯ·еЈ«гҒҢжңүеҲ©гҒӘзөҗи«–гӮ’е°ҺгҒҸгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒгҒӮгҒҲгҒҰObiter DictaгӮ’еј•з”ЁгҒ—гҒҰгҒҸгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гӮӮгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгҒқгҒ®еҲӨдҫӢгҒ®е°„зЁӢзҜ„еӣІгӮ’ж…ҺйҮҚгҒ«жӨңиЁҺгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҸёжі•иҰҸеҫӢгҒЁеҲӨдҫӢеӨүжӣҙгҒ®еҺіж јгҒ•
е…ҲдҫӢжӢҳжқҹжҖ§гҒҜгҖҒжі•зҡ„е®үе®ҡжҖ§гҒЁдәҲжё¬еҸҜиғҪжҖ§гӮ’жӢ…дҝқгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®иЈ…зҪ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒдёӢзҙҡиЈҒеҲӨжүҖгӮ„гҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒ®е°‘дәәж•°гҒ®ж§ӢжҲҗпјҲBenchпјүгҒҢгҖҒйҒҺеҺ»гҒ®зўәз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹеҲӨдҫӢгӮ’и»ҪиҰ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҢеҸёжі•иҰҸеҫӢпјҲJudicial DisciplineпјүгҖҚгҒ®иҰізӮ№гҒӢгӮүеҺігҒ—гҒҸжҲ’гӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
2025е№ҙгҖҒгӮӨгғігғүжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҜ Gayatri Balasamy v. M/s ISG Novasoft Technologies Limited (2025 INSC 605) гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒд»ІиЈҒиЈҒе®ҡгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ®д»Ӣе…ҘжЁ©йҷҗгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰйҮҚиҰҒгҒӘеҲӨж–ӯгӮ’дёӢгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®дәӢжЎҲгҒ§гҒҜгҖҒйҒҺеҺ»гҒ®еҲӨдҫӢпјҲMcDermot International Inc. case зӯүпјүгҒҢд»ІиЈҒиЈҒе®ҡгҒ®дҝ®жӯЈгӮ’иӘҚгӮҒгҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒж–°гҒҹгҒӘи§ЈйҮҲгҒҢеҝ…иҰҒгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒҢе•ҸгӮҸгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮжңҖй«ҳиЈҒгҒҜеӨҡж•°ж„ҸиҰӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒзү№е®ҡгҒ®жқЎд»¶дёӢгҒ§иЈҒеҲӨжүҖгҒ«гӮҲгӮӢдҝ®жӯЈжЁ©йҷҗгӮ’иӘҚгӮҒгӮӢеҲӨж–ӯгӮ’дёӢгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜйҒҺеҺ»гҒ®еҲӨдҫӢгҒЁгҒ®ж•ҙеҗҲжҖ§гӮ’ж…ҺйҮҚгҒ«жӨңиЁҺгҒ—гҖҒи©ізҙ°гҒӘи«–зҗҶж§ӢжҲҗгӮ’зөҢгҒҹдёҠгҒ§гҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
еҸӮиҖғпјҡгӮӨгғігғүжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖпјҡдё»иҰҒеҲӨжұәгҒ®иҰҒзҙ„пјҲLandmark Judgment Summariesпјү
гҒҫгҒҹгҖҒ2025е№ҙгҒ«жіЁзӣ®гҒ•гӮҢгҒҹеҲҘгҒ®дәӢдҫӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгғңгғігғҷгӮӨй«ҳзӯүиЈҒеҲӨжүҖгҒҢжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒ®йҒҺеҺ»гҒ®еҲӨдҫӢпјҲGodrej & Boyce Mfg. Co. Ltd. caseпјүгҒ«еҫ“гӮҸгҒҡгҒ«еҲӨжұәгӮ’дёӢгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҢгҖҢеҸёжі•иҰҸеҫӢгҒ®ж¬ еҰӮгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰеј·гҒҸеҸұиІ¬гҒ—гҖҒй«ҳзӯүиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨжұәгӮ’з ҙжЈ„гҒ—гҒҹдәӢжЎҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮжңҖй«ҳиЈҒгҒҜгҒ“гҒ®дёӯгҒ§гҖҒгҖҢStare decisis et non quieta movereпјҲжұәе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«еҫ“гҒ„гҖҒе№із©ҸгҒӘгӮӮгҒ®гӮ’еӢ•гҒӢгҒ•гҒӘгҒ„пјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгғ©гғҶгғіиӘһгҒ®ж јиЁҖгӮ’еј•з”ЁгҒ—гҖҒе…ҲдҫӢжӢҳжқҹжҖ§гҒҜжі•гҒ®дёӢгҒ®е№ізӯүгӮ’е®ҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®йҳІжіўе ӨгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁеј·иӘҝгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®дәӢдҫӢгҒҜгҖҒгӮӨгғігғүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰжңҖй«ҳиЈҒеҲӨдҫӢгҒҢгҒ„гҒӢгҒ«зө¶еҜҫзҡ„гҒӘеҠ№еҠӣгӮ’жҢҒгҒӨгҒӢгӮ’еҰӮе®ҹгҒ«зӨәгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒжңҖж–°гҒ®жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжұәгӮ’еёёгҒ«гғ•гӮ©гғӯгғјгӮўгғғгғ—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®йҮҚиҰҒжҖ§гӮ’зӨәе”ҶгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӨгғігғүйҖЈйӮҰеҲ¶гҒ®ж ёеҝғпјҡз«Ӣжі•жЁ©йҷҗгҒ®дёүеұӨж§ӢйҖ гҒЁгҖҢгӮігғігӮ«гғ¬гғігғҲгғ»гғӘгӮ№гғҲгҖҚгҒ®зҪ

ж—Ҙжң¬гҒҜеҚҳдёҖеӣҪ家гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеӣҪдјҡгҒҢеҲ¶е®ҡгҒ—гҒҹжі•еҫӢгҒҜеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰе…ЁеӣҪдёҖеҫӢгҒ«йҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮеҢ—жө·йҒ“гҒӢгӮүжІ–зё„гҒҫгҒ§гҖҒеҠҙеғҚеҹәжә–жі•гӮ„дјҡзӨҫжі•гҒ®еҶ…е®№гҒҢеӨүгӮҸгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгӮӨгғігғүгҒҜгҖҢйҖЈйӮҰеҲ¶пјҲFederal SystemпјүгҖҚгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒз«Ӣжі•жЁ©йҷҗгҒҢйҖЈйӮҰж”ҝеәңпјҲUnionпјүгҒЁе·һж”ҝеәңпјҲStateпјүгҒ«еҺіж јгҒ«еҲҶй…ҚгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жЁ©йҷҗеҲҶй…ҚгҒ®гғ«гғјгғ«гҒҜгҖҒгӮӨгғігғүжҶІжі•з¬¬246жқЎгҒҠгӮҲгҒіз¬¬7д»ҳеүҮпјҲSeventh ScheduleпјүгҒ«иҰҸе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒд»ҘдёӢгҒ®3гҒӨгҒ®гғӘгӮ№гғҲпјҲListпјүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз®ЎзҗҶгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жҶІжі•з¬¬7д»ҳеүҮгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢ3гҒӨгҒ®гғӘгӮ№гғҲ
- йҖЈйӮҰгғӘгӮ№гғҲпјҲList I – Union Listпјү
йҖЈйӮҰиӯ°дјҡпјҲParliamentпјүгҒ®гҒҝгҒҢжҺ’д»–зҡ„гҒӘз«Ӣжі•жЁ©йҷҗгӮ’жҢҒгҒӨдәӢй …гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гҒҜгҖҒеӣҪйҳІгҖҒеӨ–дәӨгҖҒйү„йҒ“гҖҒйҠҖиЎҢгҖҒйҖҡиІЁгҖҒиҲӘз©әгҖҒеҺҹеӯҗеҠӣгҖҒзү№иЁұгғ»е•ҶжЁҷзӯүгҒ®зҹҘзҡ„иІЎз”ЈжЁ©гҖҒжүҖеҫ—зЁҺпјҲиҫІжҘӯжүҖеҫ—гӮ’йҷӨгҒҸпјүгҖҒдјҡзӨҫжі•гҒӘгҒ©гҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮе…Ё100й …зӣ®иҝ‘гҒҸгҒ«еҸҠгҒ¶гҒ“гӮҢгӮүгҒ®еҲҶйҮҺгҒҜгҖҒгӮӨгғігғүе…ЁеңҹгҒ§зөұдёҖзҡ„гҒӘжі•иҰҸеҲ¶гҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮжҜ”ијғзҡ„жҠҠжҸЎгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„й ҳеҹҹгҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгғҮгғӘгғјгҒ§иЁӯз«ӢгҒ—гҒҹзҸҫең°жі•дәәгҒ®дјҡзӨҫжі•дёҠгҒ®зҫ©еӢҷгҒҜгҖҒгғ гғігғҗгӮӨгӮ„гғҗгғігӮ¬гғӯгғјгғ«гҒ§гӮӮеҹәжң¬зҡ„гҒ«гҒҜеҗҢдёҖгҒ§гҒҷгҖӮ - е·һгғӘгӮ№гғҲпјҲList II – State Listпјү
е·һиӯ°дјҡпјҲState LegislatureпјүгҒ®гҒҝгҒҢжҺ’д»–зҡ„гҒӘз«Ӣжі•жЁ©йҷҗгӮ’жҢҒгҒӨдәӢй …гҒ§гҒҷгҖӮиӯҰеҜҹгҖҒе…¬иЎҶиЎӣз”ҹгҖҒиҫІжҘӯгҖҒеңҹең°пјҲLandпјүгҖҒең°ж–№иҮӘжІ»гҖҒе·һеҶ…гҒ®е•ҶжҘӯгҖҒй…’йЎһиҰҸеҲ¶гҒӘгҒ©гҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«ж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰжіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒ®гҒҜгҖҢеңҹең°гҖҚгҒҢе·һгғӘгӮ№гғҲгҒ«еҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҒ§гҒҷгҖӮе·Ҙе ҙгҒ®е»әиЁӯз”Ёең°еҸ–еҫ—гӮ„дёҚеӢ•з”Јй–ӢзҷәгӮ’иЎҢгҒҶйҡӣгҖҒеңҹең°гҒ®з”ЁйҖ”еӨүжӣҙпјҲConversion of Land UseпјүгӮ„еҸ–еҫ—жүӢз¶ҡгҒҚгҖҒеҚ°зҙҷзЁҺпјҲStamp DutyпјүгҒӘгҒ©гҒҜе·һгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе…ЁгҒҸз•°гҒӘгӮӢиҰҸеҲ¶гҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгӮҝгғҹгғ«гғ»гғҠгғјгғүгӮҘе·һгҒ§гҒ®еңҹең°еҸ–еҫ—гғҺгӮҰгғҸгӮҰгҒҢгҖҒгӮ°гӮёгғЈгғ©гғјгғҲе·һгӮ„гғһгғҸгғјгғ©гғјгӮ·гғҘгғҲгғ©е·һгҒ§гҒҜе…ЁгҒҸйҖҡз”ЁгҒ—гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶдәӢж…ӢгҒҢй »зҷәгҒҷгӮӢгҒ®гҒҜгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҒ§гҒҷгҖӮ - гӮігғігӮ«гғ¬гғігғҲгғ»гғӘгӮ№гғҲпјҲList III – Concurrent Listпјү
йҖЈйӮҰгҒЁе·һгҒ®еҸҢж–№гҒҢз«Ӣжі•жЁ©йҷҗгӮ’жҢҒгҒӨдәӢй …гҒ§гҒҷгҖӮеҘ‘зҙ„жі•гҖҒеҲ‘дәӢжі•гҖҒеҠҙеғҚжі•гҖҒеҖ’з”Јжі•гҖҒж°‘дәӢиЁҙиЁҹжүӢз¶ҡгҖҒйӣ»ж°—гҖҒжЈ®жһ—дҝқиӯ·гҖҒж•ҷиӮІгҒӘгҒ©гҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гғӘгӮ№гғҲгҒ“гҒқгҒҢгҖҒгӮӨгғігғүжі•еӢҷгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжңҖеӨ§гҒ®гҖҢзҪ гҖҚгҒЁгҒӘгӮҠеҫ—гӮӢй ҳеҹҹгҒ§гҒҷгҖӮгҒӘгҒңгҒӘгӮүгҖҒеҗҢгҒҳдәӢй …гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰйҖЈйӮҰжі•гҒЁе·һжі•гҒҢдҪөеӯҳгҒ—гҖҒе ҙеҗҲгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜеҶ…е®№гҒҢзҹӣзӣҫгҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮігғігӮ«гғ¬гғігғҲгғ»гғӘгӮ№гғҲгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢзҹӣзӣҫпјҲRepugnancyпјүгҖҚгҒЁеӨ§зөұй ҳгҒ®еҗҢж„Ҹ
гӮігғігӮ«гғ¬гғігғҲгғ»гғӘгӮ№гғҲгҒ«еҗ«гҒҫгӮҢгӮӢдәӢй …пјҲдҫӢгҒҲгҒ°еҠҙеғҚжі•пјүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒйҖЈйӮҰжі•гҒЁе·һжі•гҒ®еҶ…е®№гҒҢзҹӣзӣҫгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒгҒ©гҒЎгӮүгҒҢе„Әе…ҲгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮгӮӨгғігғүжҶІжі•з¬¬254жқЎгҒҜгҖҒеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰйҖЈйӮҰжі•гҒҢе„Әе…ҲгҒҷгӮӢпјҲDoctrine of RepugnancyпјүгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’гҖҢйҖЈйӮҰжі•е„ӘдҪҚгҒ®еҺҹеүҮгҖҚгҒЁе‘јгҒігҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ“гҒ«гҒҜе®ҹеӢҷдёҠжҘөгӮҒгҒҰйҮҚиҰҒгҒӘдҫӢеӨ–иҰҸе®ҡпјҲArticle 254(2)пјүгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгӮӮгҒ—гҖҒгҒӮгӮӢе·һгҒҢеҲ¶е®ҡгҒ—гҒҹжі•еҫӢгҒҢгҖҒж—ўеӯҳгҒ®йҖЈйӮҰжі•гҒЁзҹӣзӣҫгғ»жҠөи§ҰгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгҒқгҒ®е·һжі•гҒҢгҖҢеӨ§зөұй ҳгҒ®еҗҢж„ҸпјҲPresidential AssentпјүгҖҚгӮ’еҫ—гҒҰгҒ„гӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒ®е·һеҶ…гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜе·һжі•гҒҢйҖЈйӮҰжі•гҒ«е„Әе…ҲгҒ—гҒҰйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®д»•зө„гҒҝгҒҜгҖҒгғ“гӮёгғҚгӮ№е®ҹеӢҷгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰжҘөгӮҒгҒҰж·ұеҲ»гҒӘеҪұйҹҝгӮ’еҸҠгҒјгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҢгҖҢгӮӨгғігғүгҒ«гҒҜгҖҮгҖҮгҒЁгҒ„гҒҶйҖЈйӮҰжі•гҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгӮүе®үеҝғгҒ гҖҚгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒйҖІеҮәе…ҲгҒ®е·һгҒҢзӢ¬иҮӘгҒ®дҝ®жӯЈжі•пјҲState AmendmentпјүгӮ’еҲ¶е®ҡгҒ—гҖҒеӨ§зөұй ҳгҒ®еҗҢж„ҸгӮ’еҫ—гҒҰгҒ„гӮҢгҒ°гҖҒйҖЈйӮҰжі•гҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢгғ«гғјгғ«гҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮзү№гҒ«еҠҙеғҚжі•гӮ„еҘ‘зҙ„жі•гҒ®еҲҶйҮҺгҒ§гҒҜгҖҒе·һгҒ”гҒЁгҒ®дҝ®жӯЈгҒҢй »з№ҒгҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒдәӢеүҚгҒ®гғӯгғјгӮ«гғ«гғ»гғ«гғјгғ«зўәиӘҚгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮ
гӮұгғјгӮ№гӮ№гӮҝгғҮгӮЈпјҡгғ©гӮёгғЈгӮ№гӮҝгғіе·һгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҠҙеғҚжі•ж”№йқ©
гҒ“гҒ®йҖЈйӮҰеҲ¶гҒ®иӨҮйӣ‘гҒ•гҒЁгҖҒе·һгҒ«гӮҲгӮӢзӢ¬иҮӘж”№жӯЈгҒ®еҪұйҹҝеҠӣгӮ’иұЎеҫҙгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢгҖҒгғ©гӮёгғЈгӮ№гӮҝгғіе·һгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҠҙеғҚжі•ж”№жӯЈгҒ®дәӢдҫӢгҒ§гҒҷгҖӮ
йҖЈйӮҰжі•гҒ§гҒӮгӮӢеҠҙеғҚдәүиӯ°жі•пјҲIndustrial Disputes ActпјүгҒ®з¬¬5Bз« гҒ§гҒҜгҖҒеҠҙеғҚиҖ…гҒҢ100дәәд»ҘдёҠгҒ®е·Ҙе ҙгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒи§ЈйӣҮпјҲRetrenchmentпјүгӮ„дёҖжҷӮеё°дј‘пјҲLay-offпјүгҖҒдәӢжҘӯжүҖй–үйҺ–пјҲClosureпјүгӮ’иЎҢгҒҶйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒдәӢеүҚгҒ«гҖҢйҒ©жӯЈгҒӘж”ҝеәңпјҲAppropriate GovernmentпјүгҖҚгҒ®иЁұеҸҜгӮ’еҫ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁиҰҸе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гҖҢдәӢеүҚиЁұеҸҜеҲ¶гҖҚгҒҜгҖҒдәӢе®ҹдёҠгҒ®и§ЈйӣҮзҰҒжӯўиҰҸе®ҡгҒЁгҒ—гҒҰж©ҹиғҪгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгӮӨгғігғүгҒ®иЈҪйҖ жҘӯгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰйӣҮз”ЁиӘҝж•ҙгӮ’жҘөгӮҒгҒҰеӣ°йӣЈгҒ«гҒ—гҖҒжө·еӨ–жҠ•иіҮгҒ®йҳ»е®іиҰҒеӣ гҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮдјҒжҘӯгҒҜйңҖиҰҒгҒ®еӨүеӢ•гҒ«еҝңгҒҳгҒҰдәәе“ЎгӮ’иӘҝж•ҙгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҡгҖҒзөҗжһңгҒЁгҒ—гҒҰжӯЈиҰҸйӣҮз”ЁгӮ’йҒҝгҒ‘гҖҒеҘ‘зҙ„еҠҙеғҚиҖ…пјҲContract LaborпјүгҒёгҒ®дҫқеӯҳгӮ’еј·гӮҒгӮӢеӮҫеҗ‘гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒ2014е№ҙгҖҒгғ©гӮёгғЈгӮ№гӮҝгғіе·һж”ҝеәңгҒҜгҒ“гҒ®зҠ¶жіҒгӮ’жү“з ҙгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҠҙеғҚдәүиӯ°жі•гҒ®е·һеҶ…йҒ©з”ЁгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеӨ§иғҶгҒӘж”№жӯЈгӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒдәӢеүҚиЁұеҸҜгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮӢе·Ҙе ҙгҒ®иҰҸжЁЎпјҲThresholdпјүгӮ’гҖҢ100дәәд»ҘдёҠгҖҚгҒӢгӮүгҖҢ300дәәд»ҘдёҠгҖҚгҒ«еј•гҒҚдёҠгҒ’гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒгҖҢ100дәәд»ҘдёҠгҖҚгҒЁе®ҡгӮҒгӮӢйҖЈйӮҰжі•гҒ®иҰҸе®ҡгҒЁжҳҺгӮүгҒӢгҒ«зҹӣзӣҫгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮйҖҡеёёгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒжҶІжі•з¬¬254жқЎгҒ®еҺҹеүҮгҒ«гӮҲгӮҠз„ЎеҠ№гҒЁгҒӘгӮӢгҒҜгҒҡгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгғ©гӮёгғЈгӮ№гӮҝгғіе·һж”ҝеәңгҒҜгҒ“гҒ®ж”№жӯЈжі•жЎҲгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒжҶІжі•з¬¬254жқЎз¬¬2й …гҒ®жүӢз¶ҡгҒҚгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҢеӨ§зөұй ҳгҒ®еҗҢж„ҸгҖҚгӮ’еҸ–еҫ—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«жҲҗеҠҹгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
еҸӮиҖғпјҡTimes of Indiaпјҡгғ©гӮёгғЈгӮ№гӮҝгғіе·һгҒ®еҠҙеғҚжі•ж”№жӯЈгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеӨ§зөұй ҳгҒ®жүҝиӘҚ
гҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒгғ©гӮёгғЈгӮ№гӮҝгғіе·һеҶ…гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҠҙеғҚиҖ…гҒҢ300дәәжңӘжәҖгҒ®е·Ҙе ҙгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒж”ҝеәңгҒ®иЁұеҸҜгҒӘгҒҸи§ЈйӣҮгӮ„дәӢжҘӯй–үйҺ–гҒҢеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒдјҒжҘӯгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒ®еҠҙеғҚеёӮе ҙгҒ®жҹ”и»ҹжҖ§гӮ’йЈӣиәҚзҡ„гҒ«й«ҳгӮҒгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҖҒгғһгғҮгӮЈгғӨгғ»гғ—гғ©гғҮгғјгӮ·гғҘе·һгҒӘгҒ©д»–гҒ®гҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®е·һгӮӮеҗҢж§ҳгҒ®ж”№жӯЈиҝҪйҡҸгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®дәӢдҫӢгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҢйҖІеҮәе…ҲгӮ’йҒёе®ҡгҒҷгӮӢйҡӣгҖҒеҚҳгҒ«гӮӨгғігғ•гғ©гӮ„зү©жөҒгӮігӮ№гғҲгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгҖҢгҒқгҒ®е·һгҒҢгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзӢ¬иҮӘгҒ®жі•ж”№жӯЈгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҖҚгӮ’и©ізҙ°гҒ«иӘҝжҹ»гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®йҮҚиҰҒжҖ§гӮ’зӨәе”ҶгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҗҢгҒҳгҖҢеҠҙеғҚдәүиӯ°жі•гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶйҖЈйӮҰжі•гҒ®дёӢгҒ«гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒе·һгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҢи§ЈйӣҮгҒ®гҒ—гӮ„гҒҷгҒ•гҖҚгӮ„гҖҢгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№гғ»гӮігӮ№гғҲгҖҚгҒҢеҠҮзҡ„гҒ«з•°гҒӘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гҖҢгӮігғігӮ«гғ¬гғігғҲгғ»гғӘгӮ№гғҲгҖҚгҒҢз”ҹгҒҝеҮәгҒҷжі•зҡ„гҒӘгғўгӮ¶гӮӨгӮҜжЁЎж§ҳгҒ“гҒқгҒҢгҖҒгӮӨгғігғүжі•еӢҷгҒ®зңҹй«„гҒЁгӮӮиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӨгғігғүеҸёжі•еҲ¶еәҰгҒ®ж§ӢйҖ ж”№йқ©пјҡе•ҶжҘӯиЈҒеҲӨжүҖжі•гҒ«гӮҲгӮӢиҝ…йҖҹеҢ–гҒёгҒ®жҢ‘жҲҰ
гӮӨгғігғүгҒ®еҸёжі•еҲ¶еәҰгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжңҖеӨ§гҒ®иӘІйЎҢгҒҜгҖҒж…ўжҖ§зҡ„гҒӘгҖҢиЈҒеҲӨгҒ®йҒ…延гҖҚгҒ§гҒҷгҖӮж°‘дәӢиЁҙиЁҹгҒ®и§ЈжұәгҒ«10е№ҙд»ҘдёҠгӮ’иҰҒгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮзҸҚгҒ—гҒҸгҒӘгҒҸгҖҒеҘ‘зҙ„еұҘиЎҢгҒ®еј·еҲ¶гӮ„еӮөжЁ©еӣһеҸҺгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдәҲжё¬еҸҜиғҪжҖ§гҒ®ж¬ еҰӮгҒҢгҖҒдё–з•ҢйҠҖиЎҢгҒ®гҖҢEase of Doing BusinessпјҲгғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ®гҒ—гӮ„гҒҷгҒ•пјүгҖҚгғ©гғігӮӯгғігӮ°гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮй•·гӮүгҒҸгӮӨгғігғүгҒ®и©•дҫЎгӮ’дёӢгҒ’гӮӢиҰҒеӣ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®зҠ¶жіҒгӮ’жү“з ҙгҒ—гҖҒжө·еӨ–гҒӢгӮүгҒ®жҠ•иіҮгӮ’е‘јгҒіиҫјгӮҖгҒҹгӮҒгҒ«е°Һе…ҘгҒ•гӮҢгҒҹеҲҮгӮҠжңӯгҒҢгҖҒ2015е№ҙе•ҶжҘӯиЈҒеҲӨжүҖжі•пјҲCommercial Courts ActпјүгҒ§гҒҷгҖӮ
е•ҶжҘӯиЈҒеҲӨжүҖпјҲCommercial CourtsпјүгҒ®иЁӯзҪ®гҒЁз®ЎиҪ„
е•ҶжҘӯиЈҒеҲӨжүҖжі•гҒҜгҖҒйҖҡеёёгҒ®ж°‘дәӢдәӢ件гҒЁгҒҜеҲҘгҒ«гҖҒдёҖе®ҡйЎҚд»ҘдёҠгҒ®гҖҢе•ҶжҘӯзҙӣдәүпјҲCommercial DisputeпјүгҖҚгӮ’е°Ӯй–Җзҡ„гҒ«жүұгҒҶиЈҒеҲӨжүҖгӮ’иЁӯзҪ®гҒ—гҖҒиҝ…йҖҹгҒӘеҜ©зҗҶгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§иЁҖгҒҶгҖҢе•ҶжҘӯзҙӣдәүгҖҚгҒ®е®ҡзҫ©гҒҜйқһеёёгҒ«еәғгҒҸгҖҒзү©е“ҒгҒ®еЈІиІ·гҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®жҸҗдҫӣгҖҒе»әиЁӯе·ҘдәӢгҖҒгғ•гғ©гғігғҒгғЈгӮӨгӮәгҖҒеҗҲејҒдәӢжҘӯгҖҒзҹҘзҡ„иІЎз”ЈжЁ©гҖҒдҝқйҷәгҖҒйҮ‘иһҚеҸ–еј•гҒӘгҒ©гҖҒгғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ«й–ўйҖЈгҒҷгӮӢгҒ»гҒјгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®зҙӣдәүгҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
зү№зӯҶгҒҷгҒ№гҒҚгҒҜгҖҒгҒқгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢзҙӣдәүдҫЎйЎҚпјҲSpecified ValueпјүгҒ®еӨүйҒ·гҒ§гҒҷгҖӮеҪ“еҲқгҖҒгҒ“гҒ®жі•еҫӢгҒҜ1,000дёҮгғ«гғ”гғјпјҲзҙ„1,700дёҮеҶҶпјүд»ҘдёҠгҒ®еӨ§иҰҸжЁЎзҙӣдәүгҒ®гҒҝгӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒдёӯе°ҸдјҒжҘӯгӮ’еҗ«гӮҖгӮҲгӮҠеәғзҜ„гҒӘгғ“гӮёгғҚгӮ№зҙӣдәүгӮ’иҝ…йҖҹеҢ–гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒ2018е№ҙгҒ®ж”№жӯЈгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеҹәжә–йЎҚгҒҢдёҖж°—гҒ«гҖҢ30дёҮгғ«гғ”гғјпјҲзҙ„50дёҮеҶҶпјүд»ҘдёҠгҖҚгҒ«гҒҫгҒ§еј•гҒҚдёӢгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒзҸҫеңЁгҒ§гҒҜеӨ§дјҒжҘӯй–“гҒ®зҙӣдәүгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®дёӯе°ҸиҰҸжЁЎгҒ®еҸ–еј•гӮ„гӮөгғ—гғ©гӮӨгғӨгғјгҒЁгҒ®гғҲгғ©гғ–гғ«гҒӘгҒ©гҖҒB2BзҙӣдәүгҒ®еӨ§йғЁеҲҶгҒҢе•ҶжҘӯиЈҒеҲӨжүҖгҒ®з®ЎиҪ„дёӢгҒ«е…ҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе•ҶжҘӯиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒйҖҡеёёгҒ®ж°‘дәӢиЈҒеҲӨжүҖпјҲCivil CourtпјүгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢгҖҒеҺіж јгҒӘгӮҝгӮӨгғ гғ©гӮӨгғігҒЁеҗҲзҗҶеҢ–гҒ•гӮҢгҒҹжүӢз¶ҡгҒҚгҒ§йҒӢе–¶гҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгӮӮгҒ“гҒ®ж–°гҒ—гҒ„гғ«гғјгғ«гҒ®дёӢгҒ§зҙӣдәүи§ЈжұәгӮ’еӣігӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҺіж јгҒӘгӮҝгӮӨгғ гғ©гӮӨгғіз®ЎзҗҶпјҡзӯ”ејҒжӣёжҸҗеҮәгҒ®гҖҢ120ж—Ҙгғ«гғјгғ«гҖҚ
е•ҶжҘӯиЈҒеҲӨжүҖжі•гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒ®жі•еӢҷжӢ…еҪ“иҖ…гҒҢжңҖгӮӮиӯҰжҲ’гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒҢгҖҒжүӢз¶ҡгҒҚгҒ®еҺіж јгҒӘжңҹйҷҗз®ЎзҗҶгҒ§гҒҷгҖӮдёӯгҒ§гӮӮгҖҒиў«е‘ҠгҒҢиЁҙзҠ¶гӮ’еҸ—гҒ‘еҸ–гҒЈгҒҰгҒӢгӮүгҖҢзӯ”ејҒжӣёпјҲWritten StatementпјүгҖҚгӮ’жҸҗеҮәгҒҷгӮӢжңҹйҷҗгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҢжҘөгӮҒгҒҰеҺігҒ—гҒ„и§ЈйҮҲгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’зҹҘгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҜиҮҙе‘Ҫзҡ„гҒӘгғӘгӮ№гӮҜгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
йҖҡеёёгҒ®ж°‘дәӢиЁҙиЁҹжі•пјҲCode of Civil Procedure, 1908пјҡCPCпјүгҒ®дёӢгҒ§гҒҜгҖҒзӯ”ејҒжӣёгҒ®жҸҗеҮәжңҹйҷҗгҒҜиЁҙзҠ¶йҖҒйҒ”гҒӢгӮү30ж—Ҙд»ҘеҶ…гҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҢиЁұеҸҜгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒ§гӮӮжңҖеӨ§90ж—Ҙд»ҘеҶ…гҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒе®ҹеӢҷдёҠгҒҜгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еәғзҜ„гҒӘиЈҒйҮҸгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒ90ж—ҘгӮ’и¶…гҒҲгҒҰжҸҗеҮәгҒ•гӮҢгҒҹзӯ”ејҒжӣёгӮӮгҖҢжӯЈеҪ“гҒӘзҗҶз”ұгҖҚгӮ„гҖҢжӯЈзҫ©гҒ®е®ҹзҸҫгҖҚгӮ’еҗҚзӣ®гҒ«еҸ—зҗҶгҒ•гӮҢгӮӢгӮұгғјгӮ№гҒҢеӨҡгҖ…гҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гғ«гғјгӮәгҒӘйҒӢз”ЁгҒҢиЈҒеҲӨйҒ…延гҒ®дёҖеӣ гҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒе•ҶжҘӯиЈҒеҲӨжүҖжі•гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®ж…ЈиЎҢгӮ’е®Ңе…ЁгҒ«еҗҰе®ҡгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҗҢжі•гҒ«еҹәгҒҘгҒҸжүӢз¶ҡгҒҚгҒ§гҒҜгҖҒиЁҙзҠ¶йҖҒйҒ”гҒӢгӮү30ж—Ҙд»ҘеҶ…гҒ«зӯ”ејҒжӣёгӮ’жҸҗеҮәгҒҷгӮӢзҫ©еӢҷгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒжӯЈеҪ“гҒӘзҗҶз”ұгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰиЈҒеҲӨжүҖгҒҢ延長гӮ’иӘҚгӮҒгҒҹе ҙеҗҲгҒ§гӮӮгҖҒгҒқгҒ®дёҠйҷҗгҒҜгҖҢ120ж—ҘгҖҚгҒЁжі•е®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ—гҒҰжңҖгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘзӮ№гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®120ж—ҘгҒЁгҒ„гҒҶжңҹйҷҗгҒҢгҖҢеј·иЎҢиҰҸе®ҡгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒSCG Contracts India Pvt. Ltd. v. K.S. Chamankar Infrastructure Pvt. Ltd. (2019) гҒӘгҒ©гҒ®еҲӨжұәгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҖҢе•ҶжҘӯиЈҒеҲӨжүҖжі•гҒ®дёӢгҒ§гҒҜгҖҒ120ж—ҘгӮ’и¶…гҒҲгҒҰзӯ”ејҒжӣёгӮ’еҸ—гҒ‘еҸ–гӮӢжЁ©йҷҗгҒҜиЈҒеҲӨжүҖгҒ«гҒҜдёҖеҲҮгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁеҲӨзӨәгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдәӢжғ…гҒҢгҒӮгӮҚгҒҶгҒЁгӮӮгҖҒ120ж—ҘгӮ’1ж—ҘгҒ§гӮӮйҒҺгҒҺгӮҢгҒ°гҖҒиў«е‘ҠгҒҜзӯ”ејҒжӣёгӮ’жҸҗеҮәгҒҷгӮӢжЁ©еҲ©гӮ’е®Ңе…ЁгҒ«еӨұгҒ„пјҲForfeiture of RightпјүгҖҒиҮӘгӮүгҒ®иЁҖгҒ„еҲҶгӮ’жі•е»·гҒ§дё»ејөгҒҷгӮӢж©ҹдјҡгӮ’еҘӘгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜдәӢе®ҹдёҠгҒ®ж•—иЁҙгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®иЈҒеҲӨе®ҹеӢҷгҒ®ж„ҹиҰҡгҒ§гҖҢеӨҡе°‘йҒ…гӮҢгҒҰгӮӮиЈҒеҲӨжүҖгҒҢдҪ•гҒЁгҒӢгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖҚгҒЁз”ҳгҒҸиҰӢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒеҸ–гӮҠиҝ”гҒ—гҒ®гҒӨгҒӢгҒӘгҒ„дәӢж…ӢгӮ’жӢӣгҒҸгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮұгғјгӮ№гғ»гғһгғҚгӮёгғЎгғігғҲгғ»гғ’гӮўгғӘгғігӮ°пјҲCase Management Hearingпјү
иҝ…йҖҹеҢ–гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®гӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘд»•зө„гҒҝгҒҢгҖҒгӮӘгғјгғҖгғјXV-AпјҲOrder XV-AпјүгҒЁгҒ—гҒҰе°Һе…ҘгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢгӮұгғјгӮ№гғ»гғһгғҚгӮёгғЎгғігғҲгғ»гғ’гӮўгғӘгғігӮ°гҖҚгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒжң¬ж јзҡ„гҒӘеҜ©зҗҶпјҲTrialпјүгҒ«е…ҘгӮӢеүҚгҒ«гҖҒиЈҒеҲӨе®ҳгҒЁеҪ“дәӢиҖ…гҒҢдёҖе ӮгҒ«дјҡгҒ—гҖҒдәүзӮ№гҒ®ж•ҙзҗҶгҖҒиЁјжӢ иӘҝгҒ№гҒ®гӮ№гӮұгӮёгғҘгғјгғ«гҖҒиЁјдәәгҒ®ж•°гҖҒејҒи«–гҒ®жңҹж—ҘгҒӘгҒ©гӮ’гҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒжұәе®ҡгҒҷгӮӢжүӢз¶ҡгҒҚгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гғ’гӮўгғӘгғігӮ°гҒҜгҖҒжңҖеҲқгҒ®гӮұгғјгӮ№гғ»гғһгғҚгӮёгғЎгғігғҲгғ»гғ’гӮўгғӘгғігӮ°гӮ’гҖҒеҪ“дәӢиҖ…гҒ«гӮҲгӮӢгҖҢиҮӘзҷҪгғ»еҗҰиӘҚгҒ®з”іиҝ°жӣёпјҲAffidavit of Admission or DenialпјүгҖҚгҒ®жҸҗеҮәгҒӢгӮү4йҖұй–“д»ҘеҶ…гҒ«й–ӢеӮ¬гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§жұәе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹгӮ№гӮұгӮёгғҘгғјгғ«гҒҜеҪ“дәӢиҖ…гӮ’жӢҳжқҹгҒ—гҖҒгӮӮгҒ—еҪ“дәӢиҖ…гҒҢжӯЈеҪ“гҒӘзҗҶз”ұгҒӘгҒҸжңҹж—ҘгӮ’йҒөе®ҲгҒ—гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгӮігӮ№гғҲпјҲзҪ°йҮ‘зҡ„гҒӘиІ»з”ЁиІ жӢ…пјүгӮ’е‘ҪгҒҳгҒҹгӮҠгҖҒз”із«ӢгӮ’еҚҙдёӢгҒ—гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢжЁ©йҷҗгӮ’жҢҒгҒЎгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜж—Ҙжң¬гҒ®гҖҢејҒи«–жә–еӮҷжүӢз¶ҡгҖҚгҒ«йЎһдјјгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҢгӮҲгӮҠдё»е°ҺжЁ©гӮ’жҸЎгӮҠгҖҒгӮҝгӮӨгғ гғ©гӮӨгғігҒ®йҒөе®ҲгӮ’еҺіж јгҒ«жұӮгӮҒгӮӢзӮ№гҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒҷгҖӮиЈҒеҲӨе®ҳгҒҜгҖҢеҜ©зҗҶгҒ®йҖІиЎҢз®ЎзҗҶиҖ…гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еҪ№еүІгӮ’еј·гҒҸжңҹеҫ…гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жҸҗиЁҙеүҚиӘҝеҒңпјҲPre-Institution MediationпјүгҒ®зҫ©еӢҷеҢ–
2018е№ҙгҒ®ж”№жӯЈгҒ«гӮҲгӮҠе°Һе…ҘгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒ®з”»жңҹзҡ„гҒӘеҲ¶еәҰгҒҢгҖҒ第12AжқЎгҒ«еҹәгҒҘгҒҸгҖҢжҸҗиЁҙеүҚиӘҝеҒңгҖҚгҒ®зҫ©еӢҷеҢ–гҒ§гҒҷгҖӮз·ҠжҖҘгҒ®жҡ«е®ҡзҡ„ж•‘жёҲпјҲUrgent Interim ReliefгҖҒд»®еҮҰеҲҶгҒӘгҒ©пјүгӮ’жұӮгӮҒгӮӢе ҙеҗҲгӮ’йҷӨгҒҚгҖҒеҺҹе‘ҠгҒҜе•ҶжҘӯиЈҒеҲӨжүҖгҒ«иЁҙиЁҹгӮ’жҸҗиө·гҒҷгӮӢеүҚгҒ«гҖҒж”ҝеәңжҢҮе®ҡгҒ®ж©ҹй–ўпјҲдё»гҒ«жі•зҡ„гӮөгғјгғ“гӮ№еҪ“еұҖпјүгҒ«гӮҲгӮӢгҖҢиӘҝеҒңпјҲMediationпјүгҖҚгӮ’зөҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ“гҒ®иӘҝеҒңгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҜгҖҒжңҹй–“гҒҢ3гғ¶жңҲпјҲеҪ“дәӢиҖ…гҒ®еҗҲж„ҸгҒ§гҒ•гӮүгҒ«2гғ¶жңҲ延長еҸҜпјүгҒ«йҷҗе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ„гҒҹгҒҡгӮүгҒ«жҷӮй–“гӮ’жөӘиІ»гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’йҳІгҒ„гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮӮгҒ—гҒ“гҒ“гҒ§е’Ңи§ЈгҒҢжҲҗз«ӢгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒ®е’Ңи§ЈеҗҲж„ҸгҒҜиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨжұәгӮ„д»ІиЈҒеҲӨж–ӯпјҲArbitral AwardпјүгҒЁеҗҢзӯүгҒ®еҹ·иЎҢеҠӣгӮ’жҢҒгҒЎгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеҲҘйҖ”иЁҙиЁҹгӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҰе’Ңи§ЈеҶ…е®№гӮ’зўәе®ҡгҒ•гҒӣгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒй«ҳйЎҚгҒӘиЁҙиЁҹиІ»з”ЁгҒЁж•°е№ҙгҒ®жҷӮй–“гӮ’иІ»гӮ„гҒҷеүҚгҒ«гҖҒе…¬зҡ„гҒӘжһ зө„гҒҝгҒ®дёӯгҒ§иҝ…йҖҹгҒӘи§ЈжұәгӮ’еӣігӮӢйҮҚиҰҒгҒӘж©ҹдјҡгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдёҖж–№гҒ§гҖҒгҖҢгҒЁгӮҠгҒӮгҒҲгҒҡиЁҙиЁҹгӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҰзӣёжүӢгҒ«гғ—гғ¬гғғгӮ·гғЈгғјгӮ’гҒӢгҒ‘гӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжҲҰиЎ“гӮ’гҒЁгӮӢе ҙеҗҲгҒ§гӮӮгҖҒз·ҠжҖҘжҖ§гҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒгҒҫгҒҡгҒҜиӘҝеҒңгӮ’зөҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгғҸгғјгғүгғ«гҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӨгғігғүдјҒжҘӯжі•еӢҷгҒ®жңҖеүҚз·ҡпјҡNCLTгҒЁдјҡзӨҫжі•й–ўйҖЈзҙӣдәү

гӮӨгғігғүгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдјҡзӨҫжі•еӢҷгҒ®еӨ§гҒҚгҒӘи»ўжҸӣзӮ№гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒҢгҖҒ2013е№ҙдјҡзӨҫжі•пјҲCompanies ActпјүгҒ®еҲ¶е®ҡгҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒ«з¶ҡгҒҸгҖҢеӣҪз«ӢдјҡзӨҫжі•еҜ©еҲӨжүҖпјҲNational Company Law TribunalпјҡNCLTпјүгҖҚгҒҠгӮҲгҒігҒқгҒ®дёҠзҙҡеҜ©гҒ§гҒӮгӮӢгҖҢеӣҪз«ӢдјҡзӨҫжі•жҺ§иЁҙеҜ©еҲӨжүҖпјҲNCLATпјүгҖҚгҒ®иЁӯз«ӢгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒҜгҖҒеҫ“жқҘгҒ®й«ҳзӯүиЈҒеҲӨжүҖгҒӘгҒ©гҒҢжӢ…гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹдјҡзӨҫжі•й–ўйҖЈгҒ®жЁ©йҷҗгӮ’йӣҶзҙ„гҒ—гҒҹе°Ӯй–Җж©ҹй–ўгҒ§гҒҷгҖӮ
NCLTгҒ®е°Ӯеұһз®ЎиҪ„гҒЁж°‘дәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ®жҺ’йҷӨ
2013е№ҙдјҡзӨҫ法第430жқЎгҒҜгҖҒNCLTгҒҢжЁ©йҷҗгӮ’жҢҒгҒӨдәӢй …гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒйҖҡеёёгҒ®ж°‘дәӢиЈҒеҲӨжүҖпјҲCivil CourtпјүгҒҢиЁҙиЁҹгӮ’еҸ—зҗҶгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жҳҺзўәгҒ«зҰҒжӯўгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жқЎж–ҮгҒҜгҖҒдјҒжҘӯжі•еӢҷгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢзҙӣдәүи§ЈжұәгҒ®еңЁгӮҠж–№гӮ’ж №жң¬гҒӢгӮүеӨүгҒҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
Companies Act, 2013, Section 430пјҡ
“No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which the Tribunal or the Appellate Tribunal is empowered to determine…”
пјҲж°‘дәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒеҜ©еҲӨжүҖгҒҫгҒҹгҒҜжҺ§иЁҙеҜ©еҲӨжүҖгҒҢжұәе®ҡгҒҷгӮӢжЁ©йҷҗгӮ’жңүгҒҷгӮӢдәӢй …гҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҖҒгҒ„гҒӢгҒӘгӮӢиЁҙиЁҹгҒҫгҒҹгҒҜжүӢз¶ҡгҒҚгӮӮеҸ—зҗҶгҒҷгӮӢз®ЎиҪ„жЁ©гӮ’жңүгҒ—гҒӘгҒ„…пјү
еҸӮиҖғпјҡ2013е№ҙдјҡзӨҫ法第430жқЎпјҲж°‘дәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ®з®ЎиҪ„жЁ©гҒ®жҺ’йҷӨпјү
гҒӢгҒӨгҒҰгҒҜгҖҒж ӘејҸгҒ®иӯІжёЎгҒ«й–ўгҒҷгӮӢзҙӣдәүгҖҒж Әдё»еҗҚз°ҝгҒ®жӣёгҒҚжҸӣгҒҲгҖҒеҸ–з· еҪ№гҒ®йҒёд»»гҒ«й–ўгҒҷгӮӢдәүгҒ„гҖҒдјҡзӨҫгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжҠ‘ең§гғ»дёҚеҪ“з®ЎзҗҶпјҲOppression and MismanagementпјүгҒӘгҒ©гҒҢж°‘дәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ«жҢҒгҒЎиҫјгҒҫгӮҢгҖҒдёҖиҲ¬гҒ®ж°‘дәӢдәӢ件гҒЁгҒ—гҒҰжүұгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—зҸҫеңЁгҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®дјҒжҘӯзөұжІ»пјҲCorporate GovernanceпјүгҒ«й–ўгӮҸгӮӢзҙӣдәүгҒҜгҖҒдјҡзӨҫжі•гҒ®е°Ӯй–Җж©ҹй–ўгҒ§гҒӮгӮӢNCLTгҒ®е°Ӯеұһз®ЎиҪ„гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮNCLTгҒҜгҖҢжә–еҸёжі•зҡ„ж©ҹй–ўпјҲQuasi-Judicial BodyпјүгҖҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒйҖҡеёёгҒ®иЈҒеҲӨжүҖгӮҲгӮҠгӮӮз°Ўжҳ“гҒӢгҒӨиҝ…йҖҹгҒӘжүӢз¶ҡгҒҚгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
Shashi Prakash KhemkaеҲӨжұәгҒ®иЎқж’ғ
гҒ“гҒ®з®ЎиҪ„гҒ®еҲҶж°ҙе¶әгӮ’жұәе®ҡгҒҘгҒ‘гҖҒж°‘дәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ®д»Ӣе…ҘгӮ’е®Ңе…ЁгҒ«йҒ®ж–ӯгҒ—гҒҹгҒ®гҒҢгҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒ«гӮҲгӮӢ Shashi Prakash Khemka v. NEPC Micon (2019) гҒ®еҲӨжұәгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®дәӢжЎҲгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҺҹе‘ҠгҒҜж ӘејҸгҒ®з§»и»ўгҒ«й–ўгҒҷгӮӢдёҚжӯЈгӮ’дё»ејөгҒ—гҖҒдјҡзӨҫжі•гҒ«еҹәгҒҘгҒҸж Әдё»еҗҚз°ҝгҒ®иЁӮжӯЈпјҲRectification of RegisterпјүгӮ’жұӮгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮе•ҸйЎҢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®зҙӣдәүгӮ’еҜ©зҗҶгҒҷгҒ№гҒҚгҒҜж°‘дәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒӢгҖҒгҒқгӮҢгҒЁгӮӮNCLTгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ§гҒҷгҖӮжңҖй«ҳиЈҒгҒҜгҖҒ2013е№ҙдјҡзӨҫ法第59жқЎгҒҢNCLTгҒ«ж Әдё»еҗҚз°ҝгҒ®иЁӮжӯЈгӮ’е‘ҪгҒҳгӮӢжЁ©йҷҗгӮ’дёҺгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жҢҮж‘ҳгҒ—гҖҒ第430жқЎгҒ®иҰҸе®ҡгҒЁеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰи§ЈйҮҲгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒгҒ“гҒ®зЁ®гҒ®зҙӣдәүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰж°‘дәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ®з®ЎиҪ„жЁ©гҒҜе®Ңе…ЁгҒ«жҺ’йҷӨгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁж–ӯгҒҳгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®еҲӨжұәгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҢзҸҫең°гҒ®еҗҲејҒгғ‘гғјгғҲгғҠгғјпјҲJoint Venture PartnerпјүгҒЁгҒ®й–“гҒ§ж ӘејҸгҒ®жүҖжңүжЁ©гӮ„зөҢе–¶жЁ©гӮ’е·ЎгӮӢдәүгҒ„гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҖҒгҒқгҒ®жҲҰе ҙгҒҜдёҖиҲ¬гҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒNCLTгҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢзўәе®ҡгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒNCLTгҒҜгҖҒ2016е№ҙеҖ’з”Јгғ»з ҙз”Јжі•пјҲInsolvency and Bankruptcy Code, 2016пјҡIBCпјүгҒ«еҹәгҒҘгҒҸеҖ’з”ЈжүӢз¶ҡгҒ®жүұгҒ„гӮ„гҖҒеҗҲдҪөгғ»иІ·еҸҺпјҲM&AпјүгҒ®жүҝиӘҚж©ҹй–ўгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еҪ№еүІгӮӮжӢ…гҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгӮӨгғігғүгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдјҒжҘӯжі•еӢҷгҒ®гҖҢеҝғиҮ“йғЁгҖҚгҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«IBCгҒ«еҹәгҒҘгҒҸеҖ’з”Јз”із«ӢгҒҜгҖҒеӮөжЁ©еӣһеҸҺгҒ®еј·еҠӣгҒӘгғ„гғјгғ«гҒЁгҒ—гҒҰж©ҹиғҪгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒNCLTгҒ®е®ҹеӢҷеӢ•еҗ‘гӮ’жҠҠжҸЎгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜеӮөжЁ©з®ЎзҗҶгҒ®иҰізӮ№гҒӢгӮүгӮӮдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮ
иЁјжӢ жі•гҒЁжүӢз¶ҡжі•гҒ®зҸҫд»ЈеҢ–пјҡгӮӨгғігғүжі•гҒЁж—Ҙжң¬жі•гҒ®еҜҫжҜ”
жңҖеҫҢгҒ«гҖҒе®ҹеӢҷгғ¬гғҷгғ«гҒ§жҘөгӮҒгҒҰйҮҚиҰҒгҒӘгҖҢиЁјжӢ гҖҚгҒ®жүұгҒ„гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгӮӨгғігғүгҒ®жі•еҲ¶еәҰж”№йқ©гҒҜе®ҹдҪ“жі•гҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгӮүгҒҡгҖҒжүӢз¶ҡжі•гӮ„иЁјжӢ жі•гҒ®еҲҶйҮҺгҒ§гӮӮжҖҘйҖҹгҒ«йҖІгӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ2023е№ҙгҖҒгӮӨгғігғүгҒҜиӢұеӣҪжӨҚж°‘ең°жҷӮд»ЈгҒ®1872е№ҙгҒ«еҲ¶е®ҡгҒ•гӮҢгҒҹгӮӨгғігғүиЁјжӢ жі•пјҲIndian Evidence ActпјүгӮ’е»ғжӯўгҒ—гҖҒж–°гҒҹгҒ«гҖҢгӮӨгғігғүиЁјжӢ жі•пјҲBharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023пјҡBSAпјүгҖҚгӮ’еҲ¶е®ҡгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®ж–°жі•гҒҜгҖҒгғҮгӮёгӮҝгғ«жҷӮд»ЈгҒ®зҸҫе®ҹгҒ«еҚігҒ—гҒҹиЁјжӢ гғ«гғјгғ«гӮ’е°Һе…ҘгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
иЁјжӢ й–ӢзӨәпјҲDiscoveryпјүгҒ®зҜ„еӣІгҒЁзҫ©еӢҷ
ж—Ҙжң¬гҒ®ж°‘дәӢиЁҙиЁҹгҒ§гҒҜгҖҒжҸҗиЁҙеүҚгҒ«зӣёжүӢж–№гҒ®иЁјжӢ гӮ’еј·еҲ¶зҡ„гҒ«е…ҘжүӢгҒҷгӮӢжүӢж®өгҒҜжҘөгӮҒгҒҰйҷҗе®ҡзҡ„гҒ§гҒҷгҖӮеҪ“дәӢиҖ…гҒҜиҮӘеҲҶгҒ«жңүеҲ©гҒӘиЁјжӢ гӮ’жҸҗеҮәгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢеҺҹеүҮгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒзӣёжүӢж–№гҒ®жүӢе…ғгҒ«гҒӮгӮӢдёҚеҲ©гҒӘиЁјжӢ гӮ’жҸҗеҮәгҒ•гҒӣгӮӢгҒ«гҒҜй«ҳгҒ„гғҸгғјгғүгғ«гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдёҖж–№гҖҒгӮӨгғігғүгҒ®ж°‘дәӢиЁҙиЁҹжі•пјҲCode of Civil ProcedureпјүгҒҜгҖҒгӮігғўгғігғ»гғӯгғјгҒ®дјқзөұгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒгӮҲгӮҠеј·еҠӣгҒӘиЁјжӢ й–ӢзӨәпјҲDiscoveryпјүгҒ®жүӢз¶ҡгҒҚгӮ’иӘҚгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
зү№гҒ«е•ҶжҘӯиЈҒеҲӨжүҖгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҪ“дәӢиҖ…гҒҜиЁҙгҒҲгҒ®жҸҗиө·жҷӮпјҲиў«е‘ҠгҒҜзӯ”ејҒжӣёгҒ®жҸҗеҮәжҷӮпјүгҒ«гҖҒиҮӘиә«гҒҢдҫқжӢ гҒҷгӮӢгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®ж–ҮжӣёгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгҒқгҒ®жҷӮзӮ№гҒ§жүҖжҢҒгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖҢиҮӘиә«гҒ«дёҚеҲ©гҒӘж–ҮжӣёгҖҚгӮӮеҗ«гӮҒгҒҰй–ӢзӨәгғ»гғӘгӮ№гғҲеҢ–гҒҷгӮӢзҫ©еӢҷгӮ’иІ гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’гҖҢзңҹе®ҹгҒ®й–ӢзӨәпјҲDisclosure of TruthпјүгҖҚгҒЁе‘јгҒігҒҫгҒҷгҖӮгӮӮгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®ж®өйҡҺгҒ§ж–ҮжӣёгӮ’йҡ еҢҝгҒ—гҖҒеҫҢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒӢгӮүиЁјжӢ гҒЁгҒ—гҒҰжҸҗеҮәгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҜеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰгҒ“гӮҢгӮ’иӘҚгӮҒгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҜгҖҒгҖҢжүӢжҢҒгҒЎгҒ®гӮ«гғјгғүгӮ’йҡ гҒ—гҒҰгҒҠгҒ„гҒҰгҖҒжі•е»·гҒ®е°Ӣе•ҸгҒ§еҲҮгӮҠеҮәгҒ—гҒҰзӣёжүӢгӮ’й©ҡгҒӢгҒӣгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒгғүгғ©гғһгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжҲҰиЎ“гҒҢйҖҡз”ЁгҒ—гҒ«гҒҸгҒ„гҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҜгҖҒзҙӣдәүгҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҹеҲқжңҹж®өйҡҺгҒ§гҖҒзӨҫеҶ…гҒ®й–ўйҖЈж–ҮжӣёпјҲйӣ»еӯҗгғЎгғјгғ«гӮ’еҗ«гӮҖпјүгӮ’гҒҷгҒ№гҒҰжҙ—гҒ„еҮәгҒ—гҖҒжңүеҲ©гғ»дёҚеҲ©гӮ’е•ҸгӮҸгҒҡи©•дҫЎгҒ—гҒҹдёҠгҒ§гҖҒй–ӢзӨәгҒҷгҒ№гҒҚзҜ„еӣІгӮ’ејҒиӯ·еЈ«гҒЁеҚ”иӯ°гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жә–еӮҷдёҚи¶ігҒҜгҖҒиЁҙиЁҹгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰиҮҙе‘Ҫзҡ„гҒӘгғҖгғЎгғјгӮёгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
йӣ»еӯҗиЁјжӢ гҒ®йҮҚиҰҒжҖ§гҒ®еў—еӨ§гҒЁBSA 2023
ж–°гҒ—гҒ„BSA 2023гҒ§гҒҜгҖҒйӣ»еӯҗиЁҳйҢІпјҲElectronic RecordsпјүгҒҢзҙҷгҒ®ж–ҮжӣёгҒЁеҗҢзӯүгҒ®жі•зҡ„ең°дҪҚгӮ’жҢҒгҒӨгҒ“гҒЁгҒҢгӮҲгӮҠжҳҺзўәгҒ«иҰҸе®ҡгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮе®ҡзҫ©гҒ«гҒҜгҖҒеҚҠе°ҺдҪ“гғЎгғўгғӘгӮ„гӮ№гғһгғјгғҲгғ•гӮ©гғігҖҒгғ©гғғгғ—гғҲгғғгғ—гҒ«дҝқеӯҳгҒ•гӮҢгҒҹгғҮгғјгӮҝгӮӮжҳҺзӨәзҡ„гҒ«еҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҢгӮӨгғігғүеӯҗдјҡзӨҫгӮ„еҸ–еј•е…ҲгҒЁгӮ„гӮҠеҸ–гӮҠгҒҷгӮӢйӣ»еӯҗгғЎгғјгғ«гҖҒгғҒгғЈгғғгғҲгӮўгғ—гғӘпјҲWhatsAppзӯүпјүгҒ®еұҘжӯҙгҖҒгӮөгғјгғҗгғјгғӯгӮ°гҒӘгҒ©гҒҜгҖҒзҙӣдәүжҷӮгҒ«жұәе®ҡзҡ„гҒӘиЁјжӢ гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®йӣ»еӯҗиЁјжӢ гҒҢжі•е»·гҒ§иӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒгғҮгғјгӮҝгҒ®зңҹжӯЈжҖ§гӮ’иЁјжҳҺгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®иЁјжҳҺжӣёпјҲCertificateпјүгҒ®жҸҗеҮәгҒӘгҒ©гҖҒеҺіж јгҒӘиҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒҷеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙеёёзҡ„гҒӘгғҮгғјгӮҝгӮ¬гғҗгғҠгғігӮ№пјҲгғҮгғјгӮҝгҒ®дҝқеӯҳгҖҒж”№гҒ–гӮ“йҳІжӯўжҺӘзҪ®пјүгҒЁгҖҒзҙӣдәүзҷәз”ҹжҷӮгҒ®дҝқе…ЁжҺӘзҪ®пјҲDigital ForensicsпјүгҒ®жә–еӮҷгҒҢгҖҒгӮӨгғігғүжі•еӢҷгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҫгҒҷгҒҫгҒҷйҮҚиҰҒгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒ
жң¬иЁҳдәӢгҒ§и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҰгҒҚгҒҹйҖҡгӮҠгҖҒгӮӨгғігғүгҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒҜгҖҢгӮігғўгғігғ»гғӯгғјгҒ®дёҚж–ҮеҫӢгҖҚгҒЁгҖҢйҖЈйӮҰеҲ¶гҒ®иӨҮйӣ‘гҒ•гҖҚгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҖҢжҖҘйҖҹгҒӘеҸёжі•ж”№йқ©гҖҚгҒҢзөЎгҒҝеҗҲгҒҶгҖҒжҘөгӮҒгҒҰеӢ•зҡ„гҒӘгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ®зү№еҫҙгҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®3зӮ№гҒ«йӣҶзҙ„гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
- жі•гҒ®жәҗжіүгҒ®иӨҮеұӨжҖ§пјҡ жқЎж–ҮпјҲActпјүгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒ®жңҖж–°еҲӨдҫӢпјҲзү№гҒ«Ratio DecidendiпјүгӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒжӯЈзўәгҒӘжі•зҡ„гғӘгӮ№гӮҜгҒҜжҠҠжҸЎгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮеҲӨдҫӢгҒҜдәӢе®ҹдёҠгҒ®еҸӮз…§еҹәжә–гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҖҢжі•гҖҚгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
- ең°еҹҹгҒ®зү№ж®ҠжҖ§гҒЁйҖЈйӮҰеҲ¶гҒ®зҪ пјҡ еҠҙеғҚжі•гӮ„еңҹең°жі•гҒӘгҒ©гҖҒгӮігғігӮ«гғ¬гғігғҲгғ»гғӘгӮ№гғҲгӮ„е·һгғӘгӮ№гғҲгҒ«еҗ«гҒҫгӮҢгӮӢдәӢй …гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒе·һгҒ”гҒЁгҒ«жі•иҰҸеҲ¶гҒҢз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгғ©гӮёгғЈгӮ№гӮҝгғіе·һгҒ®еҠҙеғҚжі•ж”№жӯЈгҒ«иҰӢгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒйҖЈйӮҰжі•гҒЁз•°гҒӘгӮӢгғ«гғјгғ«гҒҢеӨ§зөұй ҳгҒ®еҗҢж„ҸгӮ’еҫ—гҒҰйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮұгғјгӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒйҖІеҮәе…Ҳе·һгҒ«зү№еҢ–гҒ—гҒҹгғҮгғҘгғјгғҮгғӘгӮёгӮ§гғігӮ№гҒҢеҝ…й ҲгҒ§гҒҷгҖӮ
- зҙӣдәүи§ЈжұәжүӢз¶ҡгҒҚгҒ®еҺіж јеҢ–пјҡ е•ҶжҘӯиЈҒеҲӨжүҖгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢзӯ”ејҒжӣёжҸҗеҮәгҒ®120ж—Ҙгғ«гғјгғ«гӮ„гҖҒNCLTгҒ®е°Ӯеұһз®ЎиҪ„гҒӘгҒ©гҖҒжүӢз¶ҡгҒҚгҒ®дёҚеӮҷгҒҢиҮҙе‘Ҫзҡ„гҒӘзөҗжһңгӮ’жӢӣгҒҸд»•зө„гҒҝгҒҢеј·еҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®ж„ҹиҰҡгҒ§жңҹйҷҗгӮ’з”ҳгҒҸиҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгӮ„гҖҒз®ЎиҪ„гӮ’иӘӨгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜиЁұгҒ•гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гӮӨгғігғүеёӮе ҙгҒҜгҒқгҒ®е·ЁеӨ§гҒӘйӯ…еҠӣгҒЁеј•гҒҚжҸӣгҒҲгҒ«гҖҒй«ҳеәҰгҒӘжі•зҡ„гғӘгғҶгғ©гӮ·гғјгҒЁгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№гҒёгҒ®жҠ•иіҮгӮ’иҰҒжұӮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬жі•гҒ®еёёиӯҳгӮ’дёҖж—Ұи„ҮгҒ«зҪ®гҒҚгҖҒгӮӨгғігғүеӣәжңүгҒ®жі•гғӯгӮёгғғгӮҜгҒ«йҒ©еҝңгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒгғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ®жҲҗеҠҹгӮ’е®ҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®з¬¬дёҖжӯ©гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ«гғҶгӮҙгғӘгғј: ITгғ»гғҷгғігғҒгғЈгғјгҒ®дјҒжҘӯжі•еӢҷ
гӮҝгӮ°: гӮӨгғігғүе…ұе’ҢеӣҪжө·еӨ–дәӢжҘӯ