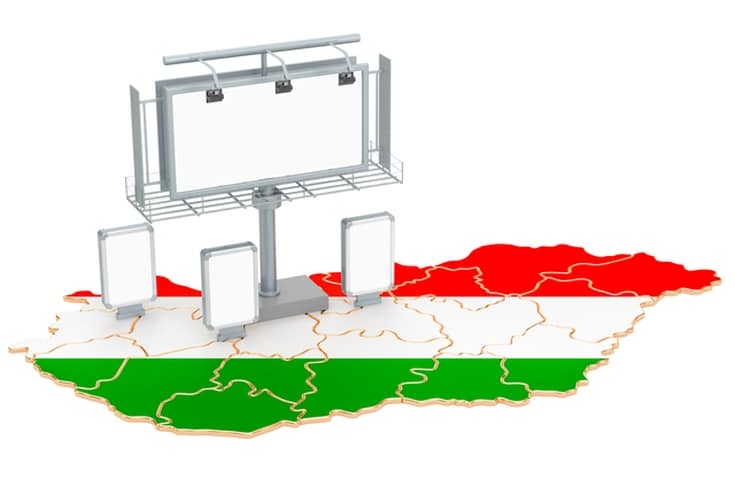ŃéżŃé┐Ńā¬ŃéóÕģ▒ÕÆīÕøĮŃü¦Ńü«Õźæń┤äµøĖõĮ£µłÉŃā╗õ║żµĖēµÖéŃü½ÕĢÅķĪīŃü©Ńü¬Ńéŗµ░æµ│ĢŃü©Õźæń┤äµ│Ģ

ŃéżŃé┐Ńā¬Ńéó’╝łµŁŻÕ╝ÅÕÉŹń¦░ŃĆüŃéżŃé┐Ńā¬ŃéóÕģ▒ÕÆīÕøĮ’╝ēŃü¦Ńü«ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣Õ▒Ģķ¢ŗŃéƵż£Ķ©ÄŃüÖŃéŗµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü½Ńü©ŃüŻŃü”ŃĆüńÅŠÕ£░Ńü«Õźæń┤äµ│ĢõĮōń│╗ŃéƵĘ▒ŃüÅńÉåĶ¦ŻŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü»ŃĆüõ║łµ£¤ŃüøŃü¼µ│ĢńÜäŃā¬Ńé╣Ńé»ŃéÆÕø×ķü┐ŃüŚŃĆüÕååµ╗æŃü¬õ║ŗµźŁķüŗÕ¢ČŃéÆÕ«¤ńÅŠŃüÖŃéŗõĖŖŃü¦õĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¦ŃüÖŃĆéŃéżŃé┐Ńā¬ŃéóŃü«µ│ĢÕłČÕ║”Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü©ÕÉīµ¦śŃü½µ░æµ│ĢŃéÆÕ¤║ńøżŃü©ŃüÖŃéŗÕż¦ķÖĖµ│Ģń│╗Ńü½Õ▒×ŃüŚŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃüØŃü«õĖŁµĀĖŃü½Ńü»µŚźµ£¼µ│ĢŃü½Ńü»Ńü¬Ńüäńŗ¼Ķć¬Ńü«µ”éÕ┐ĄŃéäŃĆüÕ«¤ÕŗÖõĖŖŃü«ķüŗńö©Ńü½ŃüŖŃüäŃü”ķćŹĶ”üŃü¬ńøĖķüĢńé╣ŃüīÕŁśÕ£©ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
µ£¼Ķ©śõ║ŗŃü¦Ńü»ŃĆüŃéżŃé┐Ńā¬Ńéóµ░æµ│ĢÕģĖ’╝łCodice Civile’╝ēŃü½Õ«ÜŃéüŃéēŃéīŃü¤Õźæń┤äŃü«Õ¤║µ£¼ÕĤÕēćŃéÆĶ¦ŻĶ¬¼ŃüÖŃéŗŃü©Ńü©ŃééŃü½ŃĆüńē╣Ńü½µ│©µäÅŃüÖŃü╣ŃüŹķćŹĶ”üŃü¬µ│ĢńÜäµ”éÕ┐ĄŃü½ńä”ńé╣ŃéÆÕĮōŃü”ŃüŠŃüÖŃĆéÕģĘõĮōńÜäŃü½Ńü»ŃĆüÕźæń┤äŃü«ńø«ńÜäŃéÆÕÄ│µĀ╝Ńü½Õ»®µ¤╗ŃüÖŃéŗŃĆīCausaŃĆŹŃü«µ”éÕ┐ĄŃü©ķØ×ÕģĖÕ×ŗÕźæń┤äŃü«µ£ēÕŖ╣µĆ¦ŃĆüÕźæń┤äõĖŹÕ▒źĶĪīµÖéŃü«ń½ŗĶ©╝Ķ▓¼õ╗╗Ńü«ÕĤÕēćŃĆüŃüØŃüŚŃü”µÖéÕŖ╣µ£¤ķ¢ōŃü«ĶżćķøæŃü¬ķüŗńö©Ńü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆüµŚźµ£¼µ│ĢŃü©Ńü«µ»öĶ╝āŃéÆõ║żŃüłŃü”Ķ®│ń┤░Ńü½Ķ½¢ŃüśŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃéēŃü«ń¤źĶ”ŗŃü»ŃĆüŃéżŃé┐Ńā¬ŃéóŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕźæń┤äõ║żµĖēŃéäŃā¬Ńé╣Ńé»Ńā×ŃāŹŃéĖŃāĪŃā│ŃāłŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüńÜ嵦śŃü«ńŠģķćØńøżŃü©Ńü¬ŃéŗŃü»ŃüÜŃü¦ŃüÖŃĆé
Ńü¬ŃüŖŃĆüŃéżŃé┐Ńā¬ŃéóŃü«Õīģµŗ¼ńÜäŃü¬µ│ĢÕłČÕ║”Ńü«µ”éĶ”üŃü»õĖŗĶ©śĶ©śõ║ŗŃü½Ńü”ŃüŠŃü©ŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«Ķ©śõ║ŗŃü«ńø«µ¼Ī
ŃéżŃé┐Ńā¬ŃéóÕźæń┤äµ│ĢŃü«Õ¤║ńøżŃü©Õźæń┤äĶć¬ńö▒Ńü«ÕĤÕēć
µ░æµ│ĢÕģĖ’╝łCodice Civile’╝ēŃü«ÕĮ╣Õē▓Ńü©ŃĆīÕźæń┤äŃĆŹŃü«Õ«ÜńŠ®
ŃéżŃé┐Ńā¬ŃéóÕźæń┤äµ│ĢŃü«õĖ╗Ķ”üŃü¬µ│Ģµ║ÉŃü»ŃĆü1942Õ╣┤ÕłČÕ«ÜŃü«µ░æµ│ĢÕģĖ’╝łCodice Civile’╝ēŃü¦ŃüÖŃĆéÕÉīµ│ĢÕģĖŃü»ŃĆüÕźæń┤äŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗõĖĆĶł¼ńÜäŃü¬Ķ”ÅÕ«ÜŃéÆń¼¼1321µØĪŃüŗŃéēń¼¼1469µØĪŃü½ŃéÅŃü¤ŃüŻŃü”Õīģµŗ¼ńÜäŃü½Õ«ÜŃéüŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüÕĢåÕÅ¢Õ╝ĢŃéÆÕɽŃéĆÕģ©Ńü”Ńü«Õźæń┤äŃü½ķü®ńö©ŃüĢŃéīŃéŗŃĆüŃéżŃé┐Ńā¬Ńéóµ░æõ║ŗµ│ĢŃü«õĖŁÕ┐āńÜäŃü¬µ│Ģµ║ÉŃü©ŃüŚŃü”Ńü«Õ£░õĮŹŃéÆńó║ń½ŗŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
µ░æµ│ĢÕģĖń¼¼1321µØĪŃü»ŃĆüÕźæń┤äŃéÆŃĆī2õ║║ŃüŠŃü¤Ńü»ŃüØŃéīõ╗źõĖŖŃü«ÕĮōõ║ŗĶĆģķ¢ōŃü¦ŃĆüńøĖõ║ÆŃü«Ķ▓ĪńöŻńÜäµ│ĢÕŠŗķ¢óõ┐éŃéÆÕēĄĶ©ŁŃĆüĶ”ÅÕŠŗŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»µČłµ╗ģŃüĢŃüøŃéŗŃü¤ŃéüŃü«ÕÉłµäÅŃĆŹŃü©Õ«ÜńŠ®ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«Õ«ÜńŠ®Ńü»ŃĆüÕÉłµäÅŃü«µäŵĆØĶĪ©ńż║’╝łAccordo’╝ēŃĆüµ│ĢÕŠŗõĖŖŃü«ķ¢óķĆŻµĆ¦’╝łRapporto Giuridico’╝ēŃĆüŃüØŃüŚŃü”Ķ▓ĪńöŻńÜäµĆ¦Ķ│¬’╝łCarattere Patrimoniale’╝ēŃü©ŃüäŃüå3ŃüżŃü«Ķ”üń┤ĀŃéÆÕ╝ĘĶ¬┐ŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüµŚźµ£¼Ńü«µ░æµ│ĢŃüīÕ«ÜŃéüŃéŗŃĆīÕźæń┤äŃü»ŃĆüµ│ĢÕŠŗĶĪīńé║Ńü¦ŃüéŃéŖŃĆüÕĮōõ║ŗĶĆģŃü«ÕÉłµäÅŃü½ŃéłŃüŻŃü”µłÉń½ŗŃüÖŃéŗŃĆŹŃü©ŃüäŃüåńÉåĶ¦ŻŃü©µ£¼Ķ│¬ńÜäŃü½ÕÉīŃüśŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃĆīÕźæń┤äĶć¬ńö▒Ńü«ÕĤÕēćŃĆŹŃü©ķØ×ÕģĖÕ×ŗÕźæń┤äŃü«ÕÄ│µĀ╝Ńü¬Õ»®µ¤╗
ŃéżŃé┐Ńā¬Ńéóµ░æµ│ĢŃü»ŃĆüÕĮōõ║ŗĶĆģŃüīĶć¬ÕĘ▒Ķ▓¼õ╗╗Ńü«õĖŗŃü¦Õźæń┤äÕåģÕ«╣ŃéÆĶć¬ńö▒Ńü½ÕĮóµłÉŃü¦ŃüŹŃéŗŃĆīÕźæń┤äĶć¬ńö▒Ńü«ÕĤÕēć’╝łprincipio di libert├Ā contrattuale’╝ēŃĆŹŃéÆÕ¤║µ£¼ÕĤÕēćŃü©ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéµ░æµ│ĢÕģĖń¼¼1322µØĪń¼¼1ķĀģŃü»ŃĆüŃĆīÕĮōõ║ŗĶĆģŃü»ŃĆüµ│ĢÕŠŗŃüīĶ¬▓ŃüÖÕłČķÖÉŃü«ń»äÕø▓ÕåģŃü¦ŃĆüÕźæń┤äŃü«ÕåģÕ«╣ŃéÆĶć¬ńö▒Ńü½µ▒║Õ«ÜŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃéŗŃĆŹŃü©Õ«ÜŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«Ķ”ÅÕ«ÜŃü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«µ░æµ│ĢŃüīÕ«ÜŃéüŃéŗÕźæń┤äĶć¬ńö▒Ńü«ÕĤÕēćŃü©ÕÉīĶČŻµŚ©Ńü¦ŃüéŃéŗŃü©Ķ©ĆŃüłŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüµ│©ńø«ŃüÖŃü╣ŃüŹŃü»ÕÉīµØĪń¼¼2ķĀģŃü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃü«Ķ”ÅÕ«ÜŃü»ŃĆüÕĮōõ║ŗĶĆģŃüīµ│ĢÕŠŗŃü½µśÄĶ©śŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃü¬ŃüäķĪ×Õ×ŗŃü«Õźæń┤ä’╝łķØ×ÕģĖÕ×ŗÕźæń┤ä’╝ēŃéÆńĘĀńĄÉŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃééĶ¬ŹŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃĆīµ│Ģń¦®Õ║ÅŃü½ÕŠōŃüŻŃü”õ┐ØĶŁĘŃü½ÕĆżŃüÖŃéŗÕł®ńøŖ’╝łinteressi meritevole di tutela’╝ēŃéÆÕ«¤ńÅŠŃüÖŃéŗķÖÉŃéŖŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆŹŃü©ŃüäŃüåÕÄ│µĀ╝Ńü¬Ķ”üõ╗ČŃéÆÕŖĀŃüłŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«µØĪµ¢ćŃü»ŃĆüµ│ĢÕģĖŃü½µśÄĶ©śŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃü¬ŃüäŃā¬Ńā╝Ńé╣’╝łLeasing’╝ēŃéäŃāĢŃā®Ńā│ŃāüŃāŻŃéżŃé║’╝łFranchising’╝ēŃü©ŃüäŃüŻŃü¤Õźæń┤äķĪ×Õ×ŗŃéƵ│ĢńÜäŃü½µ£ēÕŖ╣Ńü©ŃüÖŃéŗµĀ╣µŗĀŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
µŚźµ£¼µ│ĢŃééÕÉīµ¦śŃü½ŃĆüµ░æµ│ĢŃü«Ķ”ÅÕ«ÜŃü½Ńü¬ŃüäÕźæń┤äķĪ×Õ×ŗ’╝łķØ×ÕģĖÕ×ŗÕźæń┤ä’╝ēŃéÆÕĮōõ║ŗĶĆģŃü«ÕÉłµäÅŃü½ŃéłŃüŻŃü”Ķć¬ńö▒Ńü½õĮ£µłÉŃü¦ŃüŹŃéŗŃü©Ķ¦ŻķćłŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃüØŃü«µ£ēÕŖ╣µĆ¦Ńü»õĖ╗Ńü½ŃĆīÕģ¼Õ║ÅĶē»õ┐ŚŃĆŹŃü½ÕÅŹŃüŚŃü¬ŃüäŃüŗŃü©ŃüäŃüåµČłµźĄńÜäŃü¬Õ»®µ¤╗Ńü½ńĢÖŃüŠŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéõĖƵ¢╣ŃĆüŃéżŃé┐Ńā¬Ńéóµ│ĢŃü«ŃĆīõ┐ØĶŁĘŃü½ÕĆżŃüÖŃéŗÕł®ńøŖŃĆŹŃü©ŃüäŃüåĶ”üõ╗ČŃü»ŃĆüÕŹśŃü½Õźæń┤äÕåģÕ«╣Ńüīµ│ĢÕŠŗŃü½µŖĄĶ¦”ŃüŚŃü¬ŃüäŃüŗŃü©ŃüäŃüåÕĮóÕ╝ÅńÜäŃü¬ŃāüŃé¦ŃāāŃé»ŃéÆĶČģŃüłŃĆüĶŻüÕłżµēĆŃüīŃĆüÕĮōõ║ŗĶĆģŃüīÕźæń┤äŃéÆķĆÜŃüśŃü”Ķ┐Įµ▒éŃüÖŃéŗŃĆīńø«ńÜäŃĆŹŃüīńżŠõ╝ÜńÜäŃü½µŁŻÕĮōŃü¦ŃĆüŃüŗŃüżµ│ĢńÜäŃü½õ┐ØĶŁĘŃüÖŃéŗõŠĪÕĆżŃüīŃüéŃéŗŃüŗŃéÆń®ŹµźĄńÜäŃü½Õ«¤Ķ│¬Õ»®µ¤╗ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńż║ÕöåŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«ÕÄ│µĀ╝Ńü¬Õ»®µ¤╗Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«µ│ĢÕŗÖµŗģÕĮōĶĆģŃüīµģŻŃéīŃü”ŃüäŃü¬ŃüäŃā¬Ńé╣Ńé»ŃéÆńö¤Ńü┐Õć║ŃüÖÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüķØ×ÕģĖÕ×ŗÕźæń┤äŃü«ńĘĀńĄÉŃü½ķÜøŃüŚŃü”Ńü»ŃĆüŃüØŃü«Õźæń┤äŃü«ÕģĘõĮōńÜäŃü¬ŃĆīńø«ńÜäŃĆŹŃüīŃĆüŃéżŃé┐Ńā¬ŃéóŃü«µ│Ģń¦®Õ║ÅŃüŗŃéēĶ”ŗŃü”ŃĆīõ┐ØĶŁĘŃü½ÕĆżŃüÖŃéŗŃĆŹŃü©Õłżµ¢ŁŃüĢŃéīŃéŗŃüŗŃü©ŃüäŃüåĶ”│ńé╣ŃüŗŃéēŃü«õ║ŗÕēŹµż£Ķ©ÄŃüīõĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃéżŃé┐Ńā¬ŃéóķØ×ÕģĖÕ×ŗÕźæń┤äŃü½ŃüŖŃüæŃéŗŃĆīCausaŃĆŹŃü«µ”éÕ┐ĄŃü©µ£Ćķ½śĶŻüÕłżõŠŗ

ŃéżŃé┐Ńā¬ŃéóŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕźæń┤äŃü«µłÉń½ŗĶ”üõ╗ČŃü©ŃĆīCausaŃĆŹ
ŃéżŃé┐Ńā¬Ńéóµ░æµ│ĢÕģĖń¼¼1325µØĪŃü»ŃĆüÕźæń┤äŃü«Õ┐ģķĀłĶ”üõ╗ČŃü©ŃüŚŃü”ŃĆīÕĮōõ║ŗĶĆģŃü«ÕÉłµäÅ’╝łaccordo’╝ēŃĆŹŃĆīCausaŃĆŹŃĆīńø«ńÜä’╝łoggetto’╝ēŃĆŹŃĆīÕĮóÕ╝Å’╝łforma’╝ēŃĆŹŃü«4ŃüżŃéƵīÖŃüÆŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ŃüåŃüĪŃĆīCausaŃĆŹŃü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«µ│ĢÕŠŗŃü½Ńü»Ķ”ŗŃéēŃéīŃü¬Ńüäńŗ¼ńē╣Ńü¬µ”éÕ┐ĄŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüÕźæń┤äŃü«µ£ēÕŖ╣µĆ¦ŃéÆÕłżµ¢ŁŃüÖŃéŗõĖŖŃü¦µźĄŃéüŃü”ķćŹĶ”üŃü¬ÕĮ╣Õē▓ŃéƵףŃü¤ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ŃĆīÕģĘõĮōńÜäŃü¬Causa’╝łcausa in concreto’╝ēŃĆŹŃü«Õ»®µ¤╗
Ķ┐æÕ╣┤ŃĆüŃéżŃé┐Ńā¬ŃéóŃü«ÕłżõŠŗŃü»ŃĆüŃüōŃü«õ╝ØńĄ▒ńÜäŃü¬Ķ¦ŻķćłŃüŗŃéēŃĆüÕĮōõ║ŗĶĆģŃüīÕĆŗŃĆģŃü«Õźæń┤äŃü¦Ķ┐Įµ▒éŃüÖŃéŗÕģĘõĮōńÜäŃü¬ńø«ńÜäŃéäÕł®ńøŖŃéÆķćŹĶ”¢ŃüÖŃéŗŃĆīÕģĘõĮōńÜäŃü¬Causa’╝łcausa in concreto’╝ēŃĆŹŃüĖŃü©Ķ¦ŻķćłŃüīń¦╗ĶĪīŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ŃĆīÕģĘõĮōńÜäŃü¬CausaŃĆŹŃü»ŃĆüŃĆīÕźæń┤äŃüīÕģĘõĮōńÜäŃü½Õ«¤ńÅŠŃüŚŃéłŃüåŃü©ŃüÖŃéŗÕĮōõ║ŗĶĆģŃü«Õł®ńøŖŃü«ÕÉłµłÉŃĆŹŃü¦ŃüéŃéŗŃü©Õ«ÜńŠ®ŃüĢŃéīŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüÕŹśŃü¬ŃéŗÕĮōõ║ŗĶĆģŃü«ÕĆŗõ║║ńÜäŃü¬ÕŗĢµ®¤’╝łmotivi’╝ēŃü©Ńü»µśÄńó║Ńü½Õī║ÕłźŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«µ”éÕ┐ĄŃü«ńó║ń½ŗŃü»ŃĆüķØ×ÕģĖÕ×ŗÕźæń┤äŃü«ŃĆīõ┐ØĶŁĘŃü½ÕĆżŃüÖŃéŗÕł®ńøŖŃĆŹÕ»®µ¤╗Ńü«µ│ĢńÜäµĀ╣µŗĀŃéÆÕ╝ĘÕī¢ŃüŚŃĆüĶŻüÕłżµēĆŃü«õ╗ŗÕģźń»äÕø▓ŃéƵŗĪÕż¦ŃüÖŃéŗńĄÉµ×£ŃéÆŃééŃü¤ŃéēŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃü©Ķ©ĆŃüłŃüŠŃüÖŃĆéŃééŃüŚÕźæń┤äŃü«ńø«ńÜäŃüīķüĢµ│ĢŃü¦ŃüéŃüŻŃü¤ŃéŖŃĆüŃüéŃéŗŃüäŃü»ÕŹśŃü½ŃĆīõ┐ØĶŁĘŃü½ÕĆżŃüŚŃü¬ŃüäŃĆŹŃü©Õłżµ¢ŁŃüĢŃéīŃéīŃü░ŃĆüÕźæń┤äÕģ©õĮōŃüīńäĪÕŖ╣Ńü©Ńü¬ŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŗŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆé
ķØ×ÕģĖÕ×ŗÕźæń┤äŃü«µ£ēÕŖ╣µĆ¦Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗµ£Ćķ½śĶŻüÕłżõŠŗ
ķØ×ÕģĖÕ×ŗÕźæń┤äŃü«µ£ēÕŖ╣µĆ¦Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗĶŁ░Ķ½¢Ńü½ńĄéµŁóń¼”ŃéƵēōŃüżõĖŖŃü¦ķćŹĶ”üŃü¬µīćķćØŃéÆńż║ŃüŚŃü¤Ńü«ŃüīŃĆüŃéżŃé┐Ńā¬Ńéóµ£Ćķ½śĶŻüÕłżµēĆŃĆüńĄ▒õĖƵ│ĢÕ╗ĘŃüī2023Õ╣┤2µ£ł23µŚźŃü½õĖŗŃüŚŃü¤Õłżµ▒║’╝łÕłżµ▒║ńĢ¬ÕÅĘ5657ÕÅĘ’╝ēŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«õ║ŗµĪłŃü¦Ńü»ŃĆüÕż¢Ķ▓©Õ╗║Ńü”Ńü«ŃĆīńé║µø┐Ńā¬Ńé╣Ń黵ØĪķĀģŃĆŹŃéÆÕɽŃéĆõĖŹÕŗĢńöŻŃā¬Ńā╝Ńé╣Õźæń┤äŃüīŃĆüķØ×ÕģĖÕ×ŗńÜäŃü¬ŃĆīķćæĶ׏µ┤Šńö¤ÕĢåÕōüŃĆŹŃü©ŃüŚŃü”ŃĆīõ┐ØĶŁĘŃü½ÕĆżŃüÖŃéŗÕł®ńøŖŃĆŹŃéƵ¼ĀŃüŹŃĆüńäĪÕŖ╣Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüäŃüŗŃü©ŃüäŃüåńé╣Ńüīõ║ēŃéÅŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
µ£Ćķ½śĶŻüÕłżµēĆŃü»ŃĆüŃüōŃü«Õźæń┤äŃü«ŃĆīńé║µø┐Ńā¬Ńé╣Ń黵ØĪķĀģŃĆŹŃüīŃĆīõ┐ØĶŁĘŃü½ÕĆżŃüŚŃü¬Ńüä’╝łimmeritevole di tutela’╝ēŃĆŹŃü©Ńü»Õłżµ¢ŁŃüøŃüÜŃĆüÕźæń┤äÕģ©õĮōŃéƵ£ēÕŖ╣Ńü©Ķ¬ŹŃéüŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüØŃü«ńÉåńö▒Ńü©ŃüŚŃü”ŃĆüµ£Ćķ½śĶŻüŃü»õ╗źõĖŗŃü«ķćŹĶ”üŃü¬ÕĤÕēćŃéÆĶ┐░Ńü╣ŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéń¼¼õĖĆŃü½ŃĆümeritevolezza’╝łõ┐ØĶŁĘŃü½ÕĆżŃüÖŃéŗŃüōŃü©’╝ēŃü«Õ»®µ¤╗Ńü»ŃĆüÕźæń┤äŃüØŃü«ŃééŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüÕĮōõ║ŗĶĆģŃüīÕźæń┤äŃéÆķĆÜŃüśŃü”ķüöµłÉŃüŚŃéłŃüåŃü©ŃüŚŃü¤ŃĆīńø«ńÜäŃĆŹŃĆüŃüÖŃü¬ŃéÅŃüĪŃĆīÕģĘõĮōńÜäŃü¬Causa’╝łscopo pratico, la causa concreta’╝ēŃĆŹŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”ĶĪīŃéÅŃéīŃéŗŃü╣ŃüŹŃü¦ŃüéŃéŗŃü©ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéń¼¼õ║īŃü½ŃĆüÕźæń┤äÕĮōõ║ŗĶĆģķ¢ōŃü«ŃāæŃāĢŃé®Ńā╝Ńā×Ńā│Ńé╣Ńü½ÕŹśń┤öŃü¬õĖŹÕØćĶĪĪŃüīŃüéŃüŻŃü¤Ńü©ŃüŚŃü”ŃééŃĆüÕĮōõ║ŗĶĆģŃüīĶć¬ŃéēŃü«µäŵĆØŃü©Ķć¬ńö▒Ńü¬Õłżµ¢ŁŃü¦ŃüØŃü«Ńā¬Ńé╣Ńé»ŃéäõĖŹÕł®ńøŖŃéÆńÉåĶ¦ŻŃüŚŃĆüÕÅŚŃüæÕģźŃéīŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüéŃéīŃü░ŃĆüŃüØŃü«õ║ŗÕ«¤ŃüĀŃüæŃü¦ŃĆīÕźæń┤äŃéÆõ┐ØĶŁĘŃü½ÕĆżŃüŚŃü¬ŃüäŃééŃü«ŃĆŹŃü½ŃüÖŃéŗńÉåńö▒Ńü½Ńü»Ńü¬ŃéēŃü¬ŃüäŃü©Õłżµ¢ŁŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéµ£ĆÕŠīŃü½ŃĆüÕłżµ▒║Ńü»ŃĆüÕźæń┤äĶć¬ńö▒Ńü«ÕĤÕēć’╝łlibert├Ā negoziale’╝ēŃüīŃĆüĶŻüÕłżµēĆŃü«õ╗ŗÕģźŃéÆķÖÉÕ«ÜŃüÖŃéŗķćŹĶ”üŃü¬ÕĤÕēćŃü¦ŃüéŃéŗŃüōŃü©ŃéÆÕåŹńó║Ķ¬ŹŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüōŃü«ÕłżõŠŗŃü»ŃĆüķüÄÕÄ╗Ńü«ŃĆīÕŹśń┤öŃü¬õĖŹÕØćĶĪĪŃü«µś»µŁŻŃĆŹŃéÆķćŹĶ”¢ŃüÖŃéŗÕéŠÕÉæŃü½µŁ»µŁóŃéüŃéÆŃüŗŃüæŃĆüķØ×ÕģĖÕ×ŗÕźæń┤äŃü«Õ»®µ¤╗ŃüīŃĆīÕźæń┤äŃü«µĀ╣µ£¼ńø«ńÜäŃü«µŁŻÕĮōµĆ¦ŃĆŹŃü½ńĄ×ŃéēŃéīŃéŗŃü©ŃüäŃüåµśÄńó║Ńü¬µīćķćØŃéÆńż║ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«ŃüōŃü©ŃüŗŃéēŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīŃéżŃé┐Ńā¬ŃéóŃü¦Ńü«Õźæń┤äõ║żµĖēŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüõĖŹÕł®ńøŖŃü½Ķ”ŗŃüłŃéŗµØĪķĀģŃéÆÕŹśń┤öŃü½µÄÆķÖżŃüÖŃéŗŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüŃüØŃü«µØĪķĀģŃüīÕźæń┤äÕģ©õĮōŃü«õĖŁŃü¦Ńü®Ńü«ŃéłŃüåŃü¬ŃĆīµŁŻÕĮōŃü¬ńø«ńÜäŃĆŹŃéƵףŃü¤ŃüÖŃü«ŃüŗŃéƵśÄńó║Ńü½Ķ½¢ńÉåń½ŗŃü”Ńü”Ķ¬¼µśÄŃü¦ŃüŹŃéŗŃéłŃüåŃĆüÕźæń┤äµøĖõĮ£µłÉŃü«µ«ĄķÜÄŃüŗŃéēµł”ńĢźńÜäŃü½ÕÅ¢ŃéŖńĄäŃéĆÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŗŃü©Ķ©ĆŃüłŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆé
ŃéżŃé┐Ńā¬ŃéóŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕźæń┤äõĖŹÕ▒źĶĪīµÖéŃü«µĢæµĖłŃü©Õ«¤ÕŗÖõĖŖŃü«ńĢÖµäÅńé╣
ŃĆīÕźæń┤äŃü»ÕĮōõ║ŗĶĆģķ¢ōŃü½µ│ĢÕŠŗŃü«ÕŖ╣ÕŖøŃéÆńÖ║ńö¤ŃüĢŃüøŃéŗŃĆŹÕĤÕēć
ŃéżŃé┐Ńā¬Ńéóµ░æµ│ĢÕģĖń¼¼1372µØĪŃü»ŃĆüŃĆīÕźæń┤äŃü»ŃĆüÕĮōõ║ŗĶĆģķ¢ōŃü½µ│ĢÕŠŗŃü«ÕŖ╣ÕŖøŃéÆńÖ║ńö¤ŃüĢŃüøŃéŗŃĆŹŃü©Õ«ÜŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«µ░æµ│ĢŃüīÕ«ÜŃéüŃéŗÕźæń┤äŃü«µ│ĢńÜäµŗśµØ¤ÕŖøŃü©ÕÉīõĖĆŃü«ĶČŻµŚ©Ńü¦ŃüéŃéŖŃĆüõĖĆÕ║”µ£ēÕŖ╣Ńü½µłÉń½ŗŃüŚŃü¤Õźæń┤äŃü»ŃĆüÕĮōõ║ŗĶĆģķ¢ōŃü«ÕÉłµäÅŃü½ŃéłŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃéäµ│ĢÕŠŗŃüīĶ¬ŹŃéüŃéŗÕĀ┤ÕÉł’╝łõŠŗ’╝ÜõĖŹÕ▒źĶĪīŃü½ŃéłŃéŗĶ¦ŻķÖż’╝ēŃéÆķÖżŃüŹŃĆüõĖƵ¢╣ńÜäŃü½Ķ¦ŻķÖżŃü¦ŃüŹŃü¬ŃüäŃüōŃü©ŃéƵäÅÕæ│ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
Õ▒źĶĪīĶ½ŗµ▒éŃā╗Õźæń┤äĶ¦ŻķÖżŃā╗µÉŹÕ«│Ķ│ĀÕä¤
Õźæń┤äõĖŹÕ▒źĶĪī’╝łinadempimento’╝ēŃü©Ńü»ŃĆüÕéĄÕŗÖĶĆģŃüīÕźæń┤äõĖŖŃü«ńŠ®ÕŗÖŃéÆÕ▒źĶĪīŃüŚŃü¬ŃüäŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»õĖŹÕ«īÕģ©Ńü¬ÕĮóŃü¦Õ▒źĶĪīŃüÖŃéŗńŖȵģŗŃéƵīćŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéõĖŹÕ▒źĶĪīŃüīńÖ║ńö¤ŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕ饵©®ĶĆģŃü»ŃĆüńøĖµēŗµ¢╣Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”ŃĆīÕźæń┤äŃü«Õ▒źĶĪīŃéÆĶ½ŗµ▒éŃüÖŃéŗ’╝łazione di adempimento’╝ēŃĆŹŃüŗŃĆüŃüéŃéŗŃüäŃü»ŃĆīÕźæń┤äŃéÆĶ¦ŻķÖżŃüÖŃéŗ’╝łrisoluzione per inadempimento’╝ēŃĆŹŃüŗŃéÆķüĖµŖ×ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆéŃüäŃüÜŃéīŃü«ÕĀ┤ÕÉłŃééŃĆüµÉŹÕ«│Ķ│ĀÕä¤ŃéÆĶ½ŗµ▒éŃüÖŃéŗµ©®Õł®Ńü»Õż▒ŃéÅŃéīŃüŠŃüøŃéōŃĆé
Õźæń┤äĶ¦ŻķÖżŃü»ŃĆüõĖŹÕ▒źĶĪīŃüīŃĆīķćŹÕż¦’╝łgrave’╝ēŃĆŹŃü¦ŃüéŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü½ķÖÉŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆéĶŻüÕłżµēĆŃü»ŃĆüõĖŹÕ▒źĶĪīŃüīÕźæń┤äķ¢óõ┐éŃü«ÕØćĶĪĪŃéÆÕ┤®ŃüÖŃü╗Ńü®Ńü½ķćŹÕż¦Ńü¦ŃüéŃéŗŃüŗŃéÆŃĆüÕ«óĶ”│ńÜäŃā╗õĖ╗Ķ”│ńÜäŃü¬ŃüÖŃü╣Ńü”Ńü«õ║ŗµāģŃéÆĶĆāµģ«ŃüŚŃü”Õłżµ¢ŁŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéÕ╗║Ķ©ŁĶ½ŗĶ▓ĀÕźæń┤ä’╝łcontratto di appalto’╝ēŃü½ŃüŖŃüæŃéŗõĖŹÕ▒źĶĪīŃéÆŃéüŃüÉŃéŖŃĆüµ£Ćķ½śĶŻüŃü»ŃĆüńÖ║µ│©ĶĆģÕü┤Ńü«õĖŹÕ▒źĶĪīŃü½ŃéłŃéŖÕźæń┤äŃüīĶ¦ŻķÖżŃüĢŃéīŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüĶ½ŗĶ▓ĀµźŁĶĆģŃü»ŃĆüµ£¬Õ▒źĶĪīķā©ÕłåŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗķĆĖÕż▒Õł®ńøŖ’╝łlucro cessante’╝ēŃéÆµÉŹÕ«│Ķ│ĀÕä¤Ńü©ŃüŚŃü”Ķ½ŗµ▒éŃü¦ŃüŹŃéŗŃü©Ńü«Õłżµ¢ŁŃéÆńż║ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ķÜøŃü«ķĆĖÕż▒Õł®ńøŖŃü»ŃĆüķĆÜÕĖĖŃĆüÕźæń┤äķĪŹŃü«10’╝ģŃü©ŃüŚŃü”ń«ŚÕ«ÜŃüĢŃéīŃéŗŃāæŃā®ŃāĪŃāłŃā¬ŃāāŃé»Ńü¬Õ¤║µ║¢Ńüīńö©ŃüäŃéēŃéīŃéŗŃüōŃü©ŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüÖ’╝łŃé½ŃāāŃéĄŃā╝ŃāäŃéŻŃé¬Ńā╝ŃāŹŃĆüń¼¼õĖƵ│ĢÕ╗ĘŃĆü2023Õ╣┤10µ£ł2µŚźÕłżµ▒║ŃĆüÕłżµ▒║ńĢ¬ÕÅĘ27690ÕÅĘ’╝ēŃĆé
õĖŹÕ▒źĶĪīŃü½ŃüŖŃüæŃéŗń½ŗĶ©╝Ķ▓¼õ╗╗Ńü«µēĆÕ£©
Õźæń┤äõĖŹÕ▒źĶĪīµÖéŃü«ń½ŗĶ©╝Ķ▓¼õ╗╗Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«µ│ĢÕ«¤ÕŗÖÕ«ČŃüīµ£ĆŃééµ│©µäÅŃüÖŃü╣ŃüŹŃéżŃé┐Ńā¬Ńéóµ│ĢŃü«ķćŹĶ”üŃü¬ńē╣ÕŠ┤Ńü¦ŃüÖŃĆéŃéżŃé┐Ńā¬Ńéóµ░æµ│ĢÕģĖń¼¼1218µØĪŃü»ŃĆüŃĆīÕéĄÕŗÖĶĆģŃüīŃĆüÕéĄÕŗÖõĖŹÕ▒źĶĪīŃüŠŃü¤Ńü»Õ▒źĶĪīķüģµ╗×ŃüīŃĆüĶć¬ÕĘ▒Ńü½ÕĖ░Ķ▓¼µĆ¦Ńü«Ńü¬Ńüäõ║ŗńö▒Ńü½ŃéłŃéŗÕ▒źĶĪīõĖŹĶāĮŃü½ŃéłŃüŻŃü”ńö¤ŃüśŃü¤ŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃéŗŃüōŃü©ŃéÆĶ©╝µśÄŃüŚŃü¬ŃüäķÖÉŃéŖŃĆüÕéĄÕŗÖõĖŹÕ▒źĶĪīŃü½ŃéłŃüŻŃü”ńö¤ŃüśŃü¤µÉŹÕ«│ŃéÆĶ│ĀÕä¤ŃüÖŃéŗĶ▓¼õ╗╗ŃéÆĶ▓ĀŃüåŃĆŹŃü©Õ«ÜŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ÕłżõŠŗµ│ĢõĖŖŃĆüŃüōŃü«ÕĤÕēćŃü½ŃéłŃéŖŃĆüÕ饵©®ĶĆģŃü»Ķ©┤Ķ©¤Ńü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆīÕźæń┤äŃü«ÕŁśÕ£©ŃĆŹŃü©ŃĆīÕéĄÕŗÖõĖŹÕ▒źĶĪīŃü«õ║ŗÕ«¤ŃĆŹŃéÆõĖ╗Õ╝ĄŃā╗ń½ŗĶ©╝ŃüÖŃéīŃü░ÕŹüÕłåŃü©ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéõĖƵ¢╣Ńü¦ŃĆüÕéĄÕŗÖĶĆģŃü»ŃĆüµÉŹÕ«│Ķ│ĀÕä¤Ķ▓¼õ╗╗ŃéÆÕģŹŃéīŃéŗŃü¤ŃéüŃü½ŃĆüĶć¬ŃéēŃü½Ķ▓¼õ╗╗ŃüīŃü¬ŃüäŃüōŃü©’╝łõĖŹÕÅ»µŖŚÕŖøŃü¬Ńü®’╝ēŃéÆĶ©╝µśÄŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆé
ŃüōŃü«ń½ŗĶ©╝Ķ▓¼õ╗╗Ńü«µ¦ŗķĆĀŃü»ŃĆüõĖĆĶ”ŗŃüÖŃéŗŃü©µŚźµ£¼Ńü«µ░æµ│Ģń¼¼415µØĪŃü«ÕéĄÕŗÖõĖŹÕ▒źĶĪīĶ▓¼õ╗╗Ńü©õ╝╝Ńü”ŃüäŃéŗŃéłŃüåŃü½µĆØŃüłŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃéżŃé┐Ńā¬Ńéóµ│ĢŃü»ŃĆüŃéłŃéŖÕÄ│µĀ╝Ńü½ŃĆīÕ▒źĶĪīŃüīõĖŹÕÅ»ĶāĮŃü¦ŃüéŃéŗŃüōŃü©’╝łimpossibilit├Ā’╝ēŃĆŹŃü©ŃĆīŃüØŃéīŃüīĶć¬ÕĘ▒Ńü½ÕĖ░Ķ▓¼µĆ¦Ńü«Ńü¬ŃüäÕĤÕøĀŃü½ŃéłŃéŗŃüōŃü©’╝łcausa non imputabile’╝ēŃĆŹŃü«õ║īŃüżŃéÆÕÉīµÖéŃü½Ķ©╝µśÄŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéƵ▒éŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«µ│ĢÕ«¤ÕŗÖÕ«ČŃüīµģŻŃéīĶ”¬ŃüŚŃéōŃüĀŃĆīÕŹśŃü¬ŃéŗķüÄÕż▒Ńü«µ£ēńäĪŃĆŹŃü«ĶŁ░Ķ½¢ŃéłŃéŖŃééŃü»ŃéŗŃüŗŃü½ÕÄ│ŃüŚŃüäÕ¤║µ║¢Ńü¦ŃüéŃéŖŃĆüÕźæń┤äõĖŖŃü«Ńā¬Ńé╣Ńé»ŃéÆÕéĄÕŗÖĶĆģÕü┤Ńü½Õż¦ŃüŹŃüÅÕüÅŃéēŃüøŃéŗÕ«¤õĮōµ│ĢõĖŖŃü«Õż¦ŃüŹŃü¬ńē╣ÕŠ┤Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüŚŃü¤ŃüīŃüŻŃü”ŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīŃéżŃé┐Ńā¬ŃéóŃü¦ÕéĄÕŗÖĶĆģŃü©Ńü¬ŃéŗÕźæń┤äŃéÆńĘĀńĄÉŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕźæń┤äÕ▒źĶĪīŃüīõĖŹÕÅ»ĶāĮŃü©Ńü¬Ńéŗõ║ŗµģŗŃéƵā│Õ«ÜŃüŚŃĆüŃüØŃéīŃüīŃĆīĶć¬ÕĘ▒Ńü½ÕĖ░Ķ▓¼µĆ¦Ńü«Ńü¬Ńüäõ║ŗńö▒ŃĆŹŃü¦ŃüéŃéŗŃü©Ķ©╝µśÄŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü«Ķ©śķī▓’╝łõŠŗ’╝ÜõĖŹÕÅ»µŖŚÕŖøõ║ŗńö▒Ńü«ńÖ║ńö¤ŃĆüÕģ¼ńÜäµ®¤ķ¢óŃü«ÕæĮõ╗żŃü¬Ńü®’╝ēŃéÆĶ®│ń┤░Ńü½µ«ŗŃüÖŃüōŃü©ŃüīµźĄŃéüŃü”ķćŹĶ”üŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃéżŃé┐Ńā¬ŃéóŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕ饵©®Ńü«µÖéÕŖ╣µ£¤ķ¢ōŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗń¤Łµ£¤µÖéÕŖ╣

ŃéżŃé┐Ńā¬Ńéóµ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗµÖéÕŖ╣’╝łprescrizione’╝ēŃü«õĖĆĶł¼ÕĤÕēćŃü»ŃĆüµ░æµ│ĢÕģĖń¼¼2946µØĪŃü½Õ«ÜŃéüŃéēŃéīŃü¤10Õ╣┤ķ¢ōŃü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüµŚźµ£¼µ░æµ│ĢŃü«Õ饵©®Ńü«µČłµ╗ģµÖéÕŖ╣’╝łÕĤÕēć5Õ╣┤ŃĆüÕĢåõ║ŗÕ饵©®Ńü»5Õ╣┤’╝ēŃü©õ╝╝Ńü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüŃéżŃé┐Ńā¬Ńéóµ│ĢŃü¦Ńü»ŃĆüńē╣Õ«ÜŃü«Õźæń┤äŃéäÕ饵©®Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”ŃĆü10Õ╣┤ŃéłŃéŖń¤ŁŃüäµÖéÕŖ╣µ£¤ķ¢ōŃüīÕżÜµĢ░Õ«ÜŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüÕ«¤ÕŗÖõĖŖŃü«µ│©µäÅŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆéõŠŗŃüłŃü░ŃĆüĶ│āĶ▓ĖÕƤŃü«Õ«ČĶ│āŃéäŃĆüµÉŹÕ«│Ķ│ĀÕä¤Ķ½ŗµ▒鵩®’╝łõĖŹµ│ĢĶĪīńé║Ńü½Õ¤║ŃüźŃüÅÕĀ┤ÕÉł’╝ēŃü»5Õ╣┤ŃĆüĶć¬ńö▒ĶüʵźŁõ║║’╝łÕ╝üĶŁĘÕŻ½ŃĆüÕģ¼Ķ¬Źõ╝ÜĶ©łÕŻ½Ńü¬Ńü®’╝ēŃü«ÕĀ▒ķģ¼Ķ½ŗµ▒鵩®Ńü»3Õ╣┤ŃĆüķüŗķĆüÕźæń┤äŃéäõ┐ØķÖ║Õźæń┤äŃü«µ©®Õł®Ńü»1Õ╣┤ŃĆüÕ«┐µ│Ŗµ¢ĮĶ©ŁŃü«Õ饵©®Ńü»6Ńāȵ£łŃü©ŃüäŃüŻŃü¤ń¤Łµ£¤µÖéÕŖ╣Ńüīķü®ńö©ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«ÕżÜµ¦śŃü¬ń¤Łµ£¤µÖéÕŖ╣Ńü«ÕŁśÕ£©Ńü»ŃĆüÕ饵©®ń«ĪńÉåŃü«Õ«¤ÕŗÖŃü½Õż¦ŃüŹŃü¬ÕĮ▒ķ¤┐ŃéÆõĖÄŃüłŃüŠŃüÖŃĆ鵌źµ£¼õ╝üµźŁŃü»ŃĆüÕÅ¢Õ╝ĢŃü«ńøĖµēŗµ¢╣ŃüīŃéżŃé┐Ńā¬ŃéóŃü«õ║ŗµźŁĶĆģŃü¦ŃüéŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüØŃü«ÕÅ¢Õ╝ĢŃüīŃü®Ńü«ń¤Łµ£¤µÖéÕŖ╣Ńü«Õ»ŠĶ▒ĪŃü©Ńü¬ŃéŗŃüŗŃéƵŁŻńó║Ńü½µŖŖµÅĪŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéµÖéÕŖ╣Ńü»ŃĆüÕéĄÕŗÖĶĆģŃüĖŃü«µøĖķØóŃü½ŃéłŃéŗĶ½ŗµ▒é’╝łintimazione di pagamento’╝ēŃéäĶ©┤Ķ©¤Ńü«µÅÉĶĄĘŃĆüŃüéŃéŗŃüäŃü»ÕéĄÕŗÖĶĆģŃü½ŃéłŃéŗÕéĄÕŗÖŃü«µē┐Ķ¬ŹŃü½ŃéłŃüŻŃü”õĖŁµ¢ŁŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéõĖŁµ¢ŁŃüīńÖ║ńö¤ŃüÖŃéŗŃü©ŃĆüµÖéÕŖ╣µ£¤ķ¢ōŃü»µ£ĆÕłØŃüŗŃéēÕåŹĶ©łń«ŚŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«µēŗńČÜŃüŹŃéƵĆĀŃéŗŃü©ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«Õ¤║µ║¢Ńü¦Ńü»ŃüŠŃüĀµÖéÕŖ╣ŃüīµłÉń½ŗŃüŚŃü¬ŃüäŃü©ĶĆāŃüłŃü”ŃüäŃü¤Õ饵©®ŃüīŃĆüŃéżŃé┐Ńā¬Ńéóµ│ĢõĖŗŃü¦Ńü»ŃüÖŃü¦Ńü½µČłµ╗ģŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃĆüŃü©ŃüäŃüåõ║ŗµģŗŃüīńÖ║ńö¤ŃüŚŃüåŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüիܵ£¤ńÜäŃü¬Õ饵©®ń«ĪńÉåŃü©µÖéÕŖ╣õĖŁµ¢ŁµÄ¬ńĮ«ŃéÆĶ¼øŃüśŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃĆüõĖŹµĖ¼Ńü«µÉŹÕż▒ŃéÆķś▓ŃüÉõĖŖŃü¦õĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü©Ńéü
µ£¼Ķ©śõ║ŗŃü¦Ńü»ŃĆüŃéżŃé┐Ńā¬ŃéóÕźæń┤äµ│ĢŃü«µĀĖÕ┐āńÜäŃü¬µ”éÕ┐ĄŃü©ŃĆüµŚźµ£¼µ│ĢŃü©Ńü«ķćŹĶ”üŃü¬ńøĖķüĢńé╣Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ķ¦ŻĶ¬¼ŃüäŃü¤ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéńē╣Ńü½ŃĆüķØ×ÕģĖÕ×ŗÕźæń┤äŃü«µ£ēÕŖ╣µĆ¦Ńü½Õ»ŠŃüÖŃéŗÕÄ│µĀ╝Ńü¬Õ»®µ¤╗ŃéÆÕÅ»ĶāĮŃü½ŃüÖŃéŗŃĆīCausaŃĆŹŃü«µ”éÕ┐ĄŃü©ŃĆüÕźæń┤äõĖŹÕ▒źĶĪīµÖéŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕéĄÕŗÖĶĆģÕü┤Ńü«ķćŹŃüäń½ŗĶ©╝Ķ▓¼õ╗╗Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣Õ«¤ÕŗÖŃü¦Ńü»ķ”┤µ¤ōŃü┐ŃüīĶ¢äŃüÅŃĆüµ│©µäÅŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüÕżÜÕ▓ÉŃü½ŃéÅŃü¤Ńéŗń¤Łµ£¤µÖéÕŖ╣Ńü«ÕŁśÕ£©Ńü»ŃĆüÕ饵©®ń«ĪńÉåŃü«ŃüéŃéŖµ¢╣ŃüØŃü«ŃééŃü«Ńü½ÕĮ▒ķ¤┐ŃéÆÕÅŖŃü╝ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
| ŃéżŃé┐Ńā¬Ńéóµ│Ģ | µŚźµ£¼µ│Ģ | ńĢÖµäÅńé╣ | |
|---|---|---|---|
| ķØ×ÕģĖÕ×ŗÕźæń┤äŃü«µ£ēÕŖ╣µĆ¦ | µ░æµ│ĢÕģĖń¼¼1322µØĪŃĆīõ┐ØĶŁĘŃü½ÕĆżŃüÖŃéŗÕł®ńøŖ’╝łmeritevole di tutela’╝ēŃĆŹŃéÆĶ”üõ╗ČŃü©ŃüÖŃéŗń®ŹµźĄńÜäŃü¬ÕÅĖµ│ĢÕ»®µ¤╗ | µ░æµ│Ģń¼¼90µØĪŃĆīÕģ¼Õ║ÅĶē»õ┐ŚŃĆŹŃü½ÕÅŹŃüŚŃü¬ŃüäŃüŗŃü©ŃüäŃüåµČłµźĄńÜäŃü¬Õ»®µ¤╗ŃüīõĖŁÕ┐ā | Õźæń┤äŃü«ŃĆīÕģĘõĮōńÜäŃü¬ńø«ńÜäŃĆŹŃüīµŁŻÕĮōŃü¦ŃüéŃéŗŃüŗŃĆüõ║ŗÕēŹŃü½ń▓Šµ¤╗ŃüÖŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŗ |
| Õźæń┤äõĖŹÕ▒źĶĪīµÖéŃü«ń½ŗĶ©╝Ķ▓¼õ╗╗ | µ░æµ│ĢÕģĖń¼¼1218µØĪ Õ饵©®ĶĆģŃü»õĖŹÕ▒źĶĪīŃéÆĶ©╝µśÄŃüÖŃéīŃü░ĶČ│ŃéŖŃĆüÕéĄÕŗÖĶĆģÕü┤ŃüīÕĖ░Ķ▓¼µĆ¦Ńü«Ńü¬ŃüäÕ▒źĶĪīõĖŹĶāĮŃéÆĶ©╝µśÄŃüÖŃéŗńŠ®ÕŗÖŃéÆĶ▓ĀŃüå | µ░æµ│Ģń¼¼415µØĪ Õ饵©®ĶĆģŃü»ÕéĄÕŗÖõĖŹÕ▒źĶĪīŃü«õ║ŗÕ«¤ŃéÆń½ŗĶ©╝ŃüŚŃĆüÕéĄÕŗÖĶĆģŃü»Ķć¬ÕĘ▒Ńü½ÕĖ░Ķ▓¼õ║ŗńö▒ŃüīŃü¬ŃüäŃüōŃü©ŃéÆÕÅŹĶ©╝ŃüÖŃéŗ | ÕéĄÕŗÖĶĆģÕü┤Ńü½µźĄŃéüŃü”ķćŹŃüäĶ▓¼õ╗╗ŃüīĶ¬▓ŃüĢŃéīŃéŗŃüōŃü©ŃéÆĶ¬ŹĶŁśŃüŚŃĆüŃā¬Ńé╣Ńé»ń«ĪńÉåŃéÆÕŠ╣Õ║ĢŃüÖŃéŗ |
| Õ饵©®Ńü«µÖéÕŖ╣µ£¤ķ¢ō | µ░æµ│ĢÕģĖń¼¼2946µØĪ ÕĤÕēć10Õ╣┤ŃüĀŃüīŃĆüńē╣Õ«ÜŃü«ķĪ×Õ×ŗŃü¦1Õ╣┤ŃĆü3Õ╣┤ŃĆü5Õ╣┤Ńü¬Ńü®Ńü«ń¤Łµ£¤µÖéÕŖ╣ŃüīÕżÜµĢ░ÕŁśÕ£© | µ░æµ│Ģń¼¼166µØĪŃĆüÕĢåµ│Ģń¼¼522µØĪ ÕĤÕēć5Õ╣┤’╝łÕĢåõ║ŗÕ饵©®’╝ēŃüŠŃü¤Ńü»10Õ╣┤’╝łµ░æõ║ŗÕ饵©®’╝ē | Õźæń┤äŃü«µĆ¦Ķ│¬Ńü½Õ┐£ŃüśŃü”µÖéÕŖ╣µ£¤ķ¢ōŃéƵŁŻńó║Ńü½µŖŖµÅĪŃüŚŃĆüµÖéÕŖ╣õĖŁµ¢ŁµÄ¬ńĮ«ŃéƵĆĀŃéēŃü¬Ńüä |
| Õźæń┤äŃü«ńø«ńÜä | µ░æµ│ĢÕģĖń¼¼1325µØĪ ŃĆīCausa in concretoŃĆŹŃü«µ”éÕ┐ĄŃü½ŃéłŃéŖŃĆüÕĮōõ║ŗĶĆģŃüīÕĆŗŃĆģŃü«Õźæń┤äŃü¦Ķ┐Įµ▒éŃüÖŃéŗÕģĘõĮōńÜäŃü¬ńø«ńÜäŃüīķćŹĶ”¢ŃüĢŃéīŃéŗ | ŃĆīńø«ńÜäŃĆŹ ķĆÜÕĖĖŃü»µ│ĢÕŠŗĶĪīńé║Ńüīńø«µīćŃüÖµ│ĢńÜäÕŖ╣µ×£ŃéƵīćŃüŚŃĆüŃéżŃé┐Ńā¬ŃéóŃü«ŃéłŃüåŃü¬ÕÅĖµ│ĢÕ»®µ¤╗Ńü«Õ»ŠĶ▒ĪŃü©Ńü»Ńü¬ŃéēŃü¬Ńüä | Õźæń┤äŃü«ŃĆīń£¤Ńü«ńø«ńÜäŃĆŹŃéƵśÄńó║Ńü½Ķ©ĆĶ¬×Õī¢ŃüŚŃĆüµŁŻÕĮōµĆ¦ŃéÆĶ½¢ńÉåńÜäŃü½Ķ¬¼µśÄŃü¦ŃüŹŃéŗŃéłŃüåµ║¢ÕéÖŃüÖŃéŗ |
ŃüōŃéīŃéēŃü«ĶżćķøæŃü¬µ│ĢÕłČÕ║”ŃéÆńÉåĶ¦ŻŃüŚŃĆüŃéżŃé┐Ńā¬ŃéóŃü¦Ńü«õ║ŗµźŁŃéÆÕååµ╗æŃü½ķĆ▓ŃéüŃéŗŃü¤ŃéüŃü½Ńü»ŃĆüńÅŠÕ£░Ńü«µ│ĢńÜäÕ░éķ¢Ćń¤źĶŁśŃü½Õ¤║ŃüźŃüäŃü¤Õźæń┤䵦ŗń»ēŃü©Ńā¬Ńé╣Ńé»ń«ĪńÉåŃüīõĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¦ŃüÖŃĆé
Ńé½ŃāåŃé┤Ńā¬Ńā╝: ITŃā╗ŃāÖŃā│ŃāüŃāŻŃā╝Ńü«õ╝üµźŁµ│ĢÕŗÖ