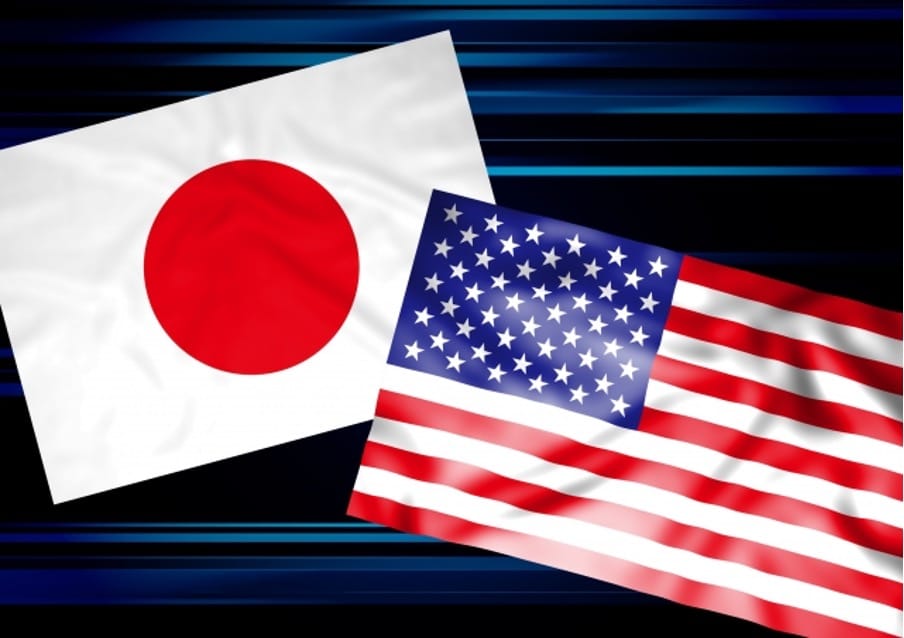アメリカにおけるNASDAQへのSPAC上場の仕組みを弁護士が解説

米国NASDAQ市場におけるSPAC(特別買収目的会社)を通じた上場は、従来のIPO(新規株式公開)とは一線を画す革新的な手法として、近年急速な広がりを見せていました。未公開企業が短期間で公開企業となる道を開いたこの手法は、特に成長著しいテクノロジー企業や、既存の産業構造にとらわれない革新的なビジネスモデルを持つ企業にとって、魅力的な選択肢であったからです。
しかし、2024年に米国証券取引委員会(SEC)が導入した新規則により、このプロセスは「簡易な上場手段」から、厳格な審査と綿密な準備を要するルートへと変わりました。この環境の変化は、日本企業が米国市場での上場を検討する上でも、深く理解すべき重要な要素です。
この記事では、NASDAQ上場を検討している日本企業向けに、SPAC上場の仕組みや詳細なプロセス、特に、De-SPAC取引と償還、そして2024年以降の新規則に焦点を当て、上場実務を実際に手がけている弁護士が解説します。
この記事の目次
SPAC上場の仕組みと通常のIPOとの違い
SPAC上場の基本的な仕組み
SPAC(Special Purpose Acquisition Company)は、特定の事業を持たず、未公開企業との合併や買収を目的に、「スポンサー」と呼ばれるプロの経営陣や投資家チームによって設立される「ブランク・チェック・カンパニー(Blank Check Company)」です。まず、SPAC自体がIPOを行い、公衆から資金を調達します。この資金は、買収対象企業が見つかるまでの間、投資家保護のため信託口座(Trust Account)に預託される点が最大の特徴です。そして、このプロセスにおいて、SPACは通常18〜24ヶ月以内にターゲットとなる企業を探し、合併を完了させる必要があります。もしこの期間内に合併が成立しない場合、SPACは清算され、信託口座に預託された資金は、利子を付けて投資家に返還されます。これにより、投資家は元本を保全できるという仕組みが備わっています。
つまり、上場を検討している会社(ターゲット企業)の目線から見ると、上記のような形で設立され、ターゲット企業を探しているSPACを探し、そのSPACと合併を行って、NASDAQ上場を実現する、ということになります。
このSPAC上場は、従来のIPOとはいくつかの点で根本的に異なります。従来のIPOが、企業が直接株式を公衆に売り出して資金調達を行うプロセスであるのに対し、SPAC上場は、未公開企業が既に公開企業であるSPACと合併することで、間接的に上場を果たす手法です。この合併取引は、一般に「De-SPAC取引」と呼ばれます。
SPAC上場の利点
従来のIPOと比較すると、SPACは上場までのプロセス期間が短いという利点がしばしば言及されてきました。ただ、この「速さ」は、SPACとターゲット企業との交渉が開始されてから合併を完了するまでの期間(3〜6ヶ月)を指しており、ターゲット企業の目線で、SPAC上場の準備を開始してから上場までの全体像を考慮すると、必ずしも従来のIPOより著しく短期間であるとまでは言えません。
SPACの重要な利点は、期間の短縮だけではありませんでした。通常のIPOでは、企業の将来の業績見通し(プロジェクション)に関する開示は、事実上厳しく制限されています。しかし、SPAC取引では、買収合意に至る過程で、スポンサーが対象企業の成長ストーリーと将来の業績見通しを投資家に提示し、企業価値の評価を説得することが可能でした。この柔軟性、つまり、将来性に基づく企業評価を市場に提示できる点が、まだ収益が安定していない・通常のIPOでは上場が困難なアーリーステージの企業や、将来性に基づいて高い企業価値評価を求める企業にとって、魅力的なポイントになっていました。
De-SPAC取引によるNASDAQ上場のプロセス

NASDAQへのSPAC上場は、以下のようなステップを経て進行します。
フェーズ1:交渉と合併契約の締結
まず、買収対象となる企業はSPACと交渉し、合併条件を合意します。米国では、SPACはIPOで調達した資金の80%以上の公正価値を持つ事業との合併を追求することが規制上求められています。この交渉では、合併後の企業価値評価、SPACの経営陣や創設者が保有する株式(プロモート株)の取り扱い、そして潜在的な株主からの償還請求(Redemption)に備えたPIPE(Private Investment in Public Equity)などの追加資金調達についても検討されます。
フェーズ2:SECへの登録と株主総会による承認
合併契約が締結されると、SPACは合併の詳細を記載した登録届出書(Form S-4)をSECに提出します。この書類は、合併の背景、リスク要因、両社の財務情報、合併後の新会社の経営陣構成など、投資家が合併の是非を判断するために不可欠な情報を提供するためのものです。また、Form S-4には、合併対象企業(ターゲット企業)の過去3年分の監査済み財務諸表や、経営陣による事業内容の分析と議論(MD&A)といった詳細な財務情報が含まれます。
SECの審査を経て、SPACは株主総会を開催し、合併案の承認を求めます。この段階で、SPACの公募株主には、合併案に反対した場合に、自身の株式を信託口座の資金と引き換えに換金(償還)する権利が付与されます。この点に関しては詳細を後述します。
フェーズ3:De-SPAC完了とNASDAQ上場
株主の承認と全ての規制上の要件がクリアされると、合併が完了し、新会社はNASDAQで取引を開始します。合併完了から4営業日以内に、新会社はSuper Form 8-KをSECに提出する義務があります。この書類は、上場企業としての継続的な情報開示義務を果たすためのもので、Form 10登録届出書に要求される情報と同等の詳細な内容(事業内容、リスク要因、財務情報、経営陣の情報など)が含まれます。
SPACにおける合併承認と償還権(Redemption Right)
株主総会における合併承認の要件
日本の会社法では、合併等の会社の根幹に関わる重要な事項については、議決権の過半数を持つ株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成をもって決議する「特別決議」が原則として必要とされます(会社法第309条第2項)。
一方、米国において多くのSPACが法人格を持つデラウェア州の会社法(Delaware General Corporation Law)では、合併承認の要件は通常、発行済株式の過半数(a majority of the outstanding stock)の賛成と定められています(DGCL§251(c))。
この要件の違いは、単なる数字の差ではなく、株主間のパワーバランスと投資家保護の仕組みにおける思想の違いによるものです。日本の制度は、厳格な議決権のハードルを設けることで、少数派の株主の意見を保護し、会社経営に重大な影響を及ぼす決定を安易に行わせないようにしています。これに対し、米国のSPAC取引における投資家保護は、議決権のハードルを低くする一方で、反対する株主に対して、投資元本を上場時の価格で換金できる「償還権(Redemption Right)」という別の手段を提供しています。
米国では、議決権のハードルが低い代わりに、反対株主はキャピタルゲインを放棄してでも投資元本を保全するという形で自己の利益を守る仕組みになっていると言えます。
償還権(Redemption Right)
SPACの株主が持つ償還権は、ターゲット企業にとって、De-SPAC取引における最大の不確実性であり、潜在的なリスクとなり得ます。ターゲット企業は、SPACの信託口座に預託されている潤沢な資金を、合併後の運転資金や将来の成長のための資金源として期待することが一般的です。しかし、もし多くのSPAC株主がこの償還権を行使した場合、信託口座の現金が大幅に減少する「ファンディングギャップ(資金不足)」が生じることになります。
近年の市場動向を見ると、このリスクは現実のものとなっています。2021年のDe-SPAC取引における平均償還率は7%〜43%の範囲でしたが、2022年には平均80%以上、2023年第1四半期には平均95%にも達する案件があったというデータがあります。この高割合な償還は、特にDe-SPAC取引の完了に必要な最低限の現金を確保する「ミニマムキャッシュコンディション(Minimum Cash Condition)」を達成できなくなるという重大な問題を引き起こします。
ミニマムキャッシュコンディション(Minimum Cash Condition)
ここで、「ミニマムキャッシュコンディション(Minimum Cash Condition)」とは、De-SPAC取引の合併契約に通常含まれる条項のことです。この条項は、取引完了後にSPACの信託口座に、買収に必要な最低限の現金が残っていることを条件とするものです。ターゲット企業がこの条件を交渉で設定するのは、合併後の事業運営や成長戦略に必要な資金を確実に確保するためです。
SPAC株主の償還権の行使率が高くなると、このミニマムキャッシュコンディションを満たせなくなるリスクが高まります。この場合、De-SPAC取引自体が失敗に終わるか、ターゲット企業が取引を成立させるために、合併契約の条件を修正し、この現金の最低条件を撤廃または引き下げる必要に迫られる可能性があります。また、もう一つの重要な対応策は、PIPE(Private Investment in Public Equity)と呼ばれる手法で、機関投資家などから追加の資金調達を行うことです。これらの追加資金調達は、高割合な償還によって生じた資金の穴埋めを目的として行われます。高割合な償還は、合併後の新会社の流動性低下にもつながり、事業運営に支障をきたす可能性もあります。
したがって、ターゲット企業がSPAC上場を検討する際には、SPACの保有する資金をそのまま自社の資金と見なすのではなく、株主の償還によって大幅に目減りする可能性があることを事前に認識し、資金調達計画を綿密に立てておくことが不可欠となります。
PIPE(Private Investment in Public Equity)
なお、PIPE(Private Investment in Public Equity)とは、前述のように、高割合な償還によってSPACの信託口座の現金が大幅に目減りし、ミニマムキャッシュコンディションが達成できなくなることを回避するために用いられる手段で、公募とは異なり、一部の機関投資家などから非公開で資金を調達することを指します。追加の株式を発行することで行われ、従来の公募と比較して迅速に資金を調達できるという利点があります。また、合併契約の署名前に、買収価格の一部を賄うためにPIPEによる資金調達が事前に手配されることも少なくありません。
近年の市場動向では、高割合な償還が常態化しているため、PIPEのような追加資金調達が取引を成立させるための不可欠な要素となりつつあります。ただ、PIPEは新たな株式を発行するため、既存の株主の持分比率がその分希薄化される点には注意が必要です。
2024年SEC新規則の導入と厳格化された審査基準

2020年から2021年にかけてのSPACブーム期、一部のSPACは従来のIPOよりも緩やかな開示や法的責任の枠組みを濫用しているといった懸念が、投資家や市場関係者から提起されました。これに対し、SECは投資家保護を強化するため、2024年1月24日にSPACに関する最終規則を採択しました。この規則は、SPAC取引を従来のIPOにより近い規制の対象とすることで、市場の健全化を目指すものです。
主要な新規則とその影響は以下の通りです。
共同登録者としての責任
新規則は、De-SPAC取引におけるターゲット企業をSPACと「共同登録者(Co-registrant)」と定義することを明確化しました。これにより、ターゲット企業の取締役および役員は、合併に関する登録届出書(Form S-4)の内容について、SPAC側と同じ法的責任を負うことになります。
開示義務の強化
SPACのスポンサー報酬、利益相反、潜在的な株式の希薄化に関する詳細な開示が義務付けられました。これには、スポンサーがわずかな費用で取得した株式(プロモート株)やワラントの量と価格に関する情報が含まれます。スポンサーが他のエンティティにも関与している場合など、投資家の利益と相反する可能性のある状況についても開示が求められます。
プロジェクション(将来見通し)に関する保護の排除
最も重要な変更点の一つは、De-SPAC取引におけるプロジェクションが、米国証券訴訟改革法(Private Securities Litigation Reform Act of 1995:PSLRA)のセーフハーバー(免責規定)の対象外とされたことです。SPACブーム期には、将来の収益見通しを積極的に活用し、高い企業価値を正当化することが一般的でした。しかし、これらの予測が非現実的なものであった場合、投資家は大きな損失を被るリスクがありました。
PSLRAのセーフハーバーを排除することで、プロジェクションの作成者(ターゲット企業とスポンサー)は、その内容について訴訟リスクを負うことになります。これにより、無責任な楽観的予測が抑制され、より現実的で根拠のあるプロジェクションのみが開示されることが期待されます。この結果、SPAC上場は、「夢物語」で投資家を惹きつける手法から、確固たる事業計画と安定した収益基盤を持つ企業に限定されることになると言えるでしょう。
この最終規則に関する詳細は下記記事で解説しています。
まとめ:NASDAQへのSPAC上場は弁護士に相談を
2024年以降、米国NASDAQへのSPAC上場は、通常のIPOと同じような水準の、厳格な審査と綿密な準備を要する選択肢へと変わりました。SPAC上場のプロセスは、米国証券法と日本の法務双方に精通した専門家による多角的なサポートなしには、円滑に進めることが困難になっています。また、安定した収益基盤と明確な成長戦略を持つ企業でなければ、もはや承認を得ることは困難になっていると言えます。
金利引き下げ後の市場回復に伴い、SPAC市場は再び活気を取り戻しつつあります。しかし、復活の兆しを見せているのは、厳選された質の高い案件に限られます。つまり、単に財務要件を満たすだけでなく、明確な成長戦略と、厳しい開示要件に耐えうる強固な内部統制・ガバナンス体制を持つ企業でなければ、実際問題としてSPACによる上場を成功させることは困難です。
当事務所による対策のご案内
モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。ベンチャー法務に経験と実績を有し、国際ネットワークと連携する法律事務所として、モノリス法律事務所は日本企業によるNASDAQ上場を全面的にサポートいたします。NASDAQ上場支援については、下記記事をご参照ください。
モノリス法律事務所の取扱分野:NASDAQ上場支援
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務
タグ: NASDAQ上場支援アメリカ