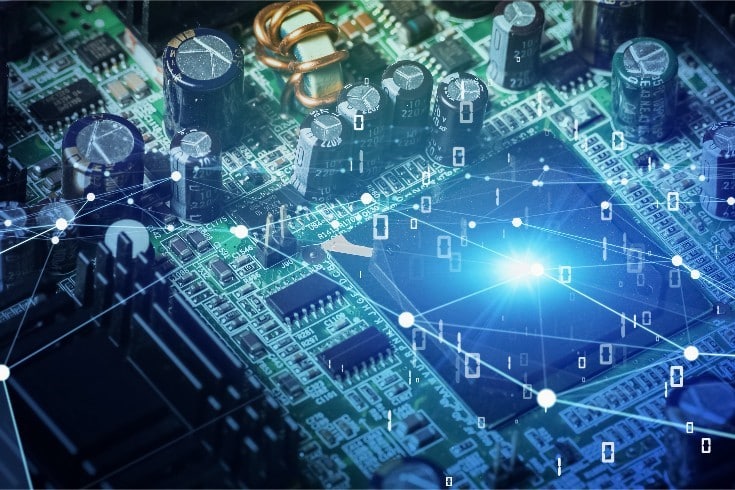ÂÖçË®±„Å™„Åó„ÅƉ∫∫ÊùêÁ¥π‰ªã„ÅØÈÅïÊ≥ïÔºüÊúâÊñôËÅ∑Ê•≠Á¥π‰ªã„ÅÆË®±ÂèØ„ÅåÂøÖ˶ńřÂÝ¥Âêà„Å®„ÅØ

採用活動の手法が多様化するなかで、リファラル採用やマッチングサイトなど、従来の人材紹介会社を介さない採用スタイルが広がっています。これらの仕組みを設計する際には、どこからが「有料職業紹介事業」に該当するのかを正しく理解しておかなければなりません。
職業安定法では、求人者と求職者の間に立ち、雇用関係の成立をあっせんする行為を「職業紹介」と定義しています。無許可で職業紹介を行えば、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という重い罰則の対象となる恐れがあり、注意が必要です。
本記事では、許可が必要な行為と不要な行為の違いを整理し、リファラル採用やマッチングサービスを運営する際に注意すべき法的リスクについて解説します。
この記事の目次
有料職業紹介事業とは
ÊúâÊñôËÅ∑Ê•≠Á¥π‰ªã‰∫ãÊ•≠„Å®„ÅØ„ÄÅʱlj∫∫ËÄքŴʱÇËÅ∑ËÄÖ„ÇíÁ¥π‰ªã„Åó„ÄÅʱlj∫∫ËÄÖ„Åã„ÇâÁ¥π‰ªãÊâãÊï∞Êñô„ÇíÂèó„ÅëÂèñ„Çã‰∫ãÊ•≠„ÅÆ„Åì„Å®„Çí„ÅÑ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇÁ¥π‰ªãÊâãÊï∞Êñô„ÅØ„ÄåÁ¥π‰ªãÊñô„Äç„Å®Â뺄Å∞„Çå„ÄÅÂéöÁîüÂä¥ÂÉçÁúÅ„ÅåÂÆö„ÇÅ„Çã„É´„ɺ„É´„ÅÆ„ÇÇ„Å®„Å߉∏äÈôê„Ååʱ∫„ÇÅ„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„Älj∏ÄËà¨ÁöÑ„Å´„ÅØ„ÄÅÁ¥π‰ªã„Åï„Çå„Åü‰∫∫Êùê„ÅÆÊÉ≥ÂÆöÂπ¥Âèé„ÅÆ30„Äú40ÔºÖÁ®ãÂ∫¶„ÅåÁõ∏ÂÝ¥„Åß„Åô„ÄÇ
重要なのは、法律上の「職業紹介」の定義です。職業安定法第4条では「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間に雇用関係の成立をあっせんすること」とされています。
ÊúâÊñôËÅ∑Ê•≠Á¥π‰ªã‰∫ãÊ•≠„ÅØ„Ä剪≤‰ªã„Åó„ŶÈõáÁî®Èñ¢‰øÇ„ÇíÊàêÁ´ã„Åï„Åõ„ÇãË°åÁÇ∫„Äç„Å®„ÄåÂݱÈÖ¨„ÇíÂæó„Ç㉪ïÁµÑ„Åø„Äç„Åå„Ǫ„ÉÉ„Éà„Å´„Å™„Å£„Åü‰∫ãÊ•≠ÂΩ¢ÊÖã„Åß„ÅÇ„Çä„ÄÅÂéöÁîüÂä¥ÂÉçÁúÅ„ÅÆË®±ÂèØ„ÇíÂæó„ŶÂàù„ÇńŶÂêàÊ≥ïÁöÑ„Å´ÈÅãÂñ∂„Åß„Åç„ÇãÁÇπ„Åå§߄Åç„Å™ÁâπÂ楄Åß„Åô„ÄÇ
ÊúâÊñôËÅ∑Ê•≠Á¥π‰ªã‰∫ãÊ•≠Ë®±ÂèØ„ÅåÂøÖ˶ńřÂÝ¥Âêà

ÂâçËø∞„ÅÆÈÄö„Çä„ÄÅÊúâÊñôËÅ∑Ê•≠Á¥π‰ªã‰∫ãÊ•≠„ÅÆË®±ÂèØ„ÅåÂøÖ˶ńŴ„Å™„Çã„ÅÆ„ÅØ„ÄÅʱlj∫∫ËÄքŮʱÇËÅ∑ËÄÖ„ÅÆÈñì„Å´ÈõáÁî®Èñ¢‰øÇ„ÇíÊàêÁ´ã„Åï„Åõ„Çã„Çà„Å܉ª≤‰ªã„Åó„ÄÅ„Åù„ÅÆÂØæ‰æ°„Å®„Åó„ŶÂݱÈÖ¨„ÇíÂèó„ÅëÂèñ„ÇãÂÝ¥Âêà„Åß„Åô„ÄÇ
‰æã„Åà„Å∞„Äʼn∫∫ÊùêÁ¥π‰ªã‰ºöÁ§æ„ÅÆ„Ç®„ɺ„Ç∏„Çß„É≥„Éà„Ååʱlj∫∫Á•®„ÇíÊèêÁ§∫„Åó„ŶÂøúÂãü„ÇíÂãß„ÇÅ„Åü„Çä„ÄÅÈù¢Êé•Êó•Á®ã„ÇíË™øÊ籠Åó„Åü„Çä„Åô„ÇãË°åÁÇ∫„ÅØ„Äå„ÅÇ„Å£„Åõ„Çì„Äç„Åß„Åô„ÄÇ„Åì„ÅÆÂÝ¥Âêà„ÅØÂéöÁîüÂä¥ÂÉçÁúÅ„ÅÆË®±ÂèØ„ÅåÂøÖ˶ńÅß„Åô„ÄÇ
ÈÄÜ„Å´„ÄÅÂçò„Ŵʱlj∫∫ÊÉÖÂݱ„ÇÑʱÇËÅ∑ËÄÖÊÉÖÂݱ„ÇíÂÖ¨Èñã„Åô„Çã„ÅÝ„Åë„Åß„ÄÅÂÄãÂà•„ÅÆ„Éû„ÉÉ„ÉÅ„É≥„Ç∞„ÇÑÊù°‰ª∂Ë™øÊ籠ŴÈñ¢‰∏é„Åó„Å™„ÅÑÂÝ¥Âêà„ÅØ„ÄåËÅ∑Ê•≠Á¥π‰ªã„Äç„Å´ÂΩì„Åü„Çâ„Åö„ÄÅË®±ÂèØ„Å؉∏ç˶ńŮ„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
なお、無許可で有料の職業紹介を行うと、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という重い罰則が科されます。そのため、事業を始める前に自らのサービス内容が「職業紹介」に該当するかどうかを確認することが重要です。
„Å™„Åä„ÄÅÂá∫Âêë„ɪʥæÈÅ£„ɪÊ∫ñÂßª„ɪ˴ãË≤Ý„Å™„Å©ËÅ∑Ê•≠Á¥π‰ªã‰ª•Â§ñ„ÅƉ∫∫ÊùêÊ¥ªÁŴÈñ¢„Åó„Ŷ„ÅØ„Äʼn∏ãË®ò„ÅÆË®ò‰∫ã„Å´„ŶËߣ˙¨„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
ÊúâÊñôËÅ∑Ê•≠Á¥π‰ªã‰∫ãÊ•≠Ë®±ÂèØ„ÅåÂøÖ˶ńř„ÅÑÂÝ¥Âêà

ÊúâÊñôËÅ∑Ê•≠Á¥π‰ªã‰∫ãÊ•≠„ÅÆË®±ÂèØ„Åå‰∏ç˶ńŮ„Å™„Çã„ÅÆ„ÅØ„ÄÅʱlj∫∫ËÄÖ„ÇÑʱÇËÅ∑ËÄÖ„Åã„ÇâÊèê‰æõ„Åï„Çå„ÅüÊÉÖÂݱ„Çí„ÄÅ„Åù„ÅÆ„Åæ„Åæ„ÅÆ„Åã„Åü„Å°„ÅßÊé≤˺â„Åó„ÄÅÈÅãÂñ∂ËÄÖ„Å剪≤‰ªãË°åÁÇ∫„Çí„Åó„Å™„ÅÑÂÝ¥Âêà„Åß„Åô„ÄÇ
‰æã„Åà„Å∞„ÄÅWantedly„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å™„ǵ„ɺ„Éì„Çπ„Åß„ÅØ„ÄÅʱÇËÅ∑ËÄÖ„ÅåʧúÁ¥¢Êù°‰ª∂„ÇíÂÖ•Âäõ„Åô„Çã„Å®„ÄÅ„Åù„Çå„Å´ÂΩì„Ŷ„ÅØ„Åæ„Çãʱlj∫∫„Çí„Åô„Åπ„Ŷ˰®Á§∫„Åô„Ç㉪ïÁµÑ„Åø„ÇíÊé°ÁÅó„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇÈÅãÂñ∂ËÄÖ„ÅåÂÄãÂà•„ÅÆʱÇËÅ∑ËÄÖ„Å´Âêà„Çè„Åõ„Ŷʱlj∫∫„ÇíÈÅ∏„Çì„ÅÝ„Çä„ÄÅÈù¢Êé•Êó•Á®ã„ÇíË™øÊ籠Åó„Åü„Çä„Åô„Çã„Åì„Å®„ÅØ„Å™„Åè„ÄÅ„ÅÇ„Åè„Åæ„ÅßÊÉÖÂݱÊèê‰æõ„Å´Âæπ„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã„Åü„ÇÅ„ÄÅ„Åì„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å™„DZ„ɺ„Çπ„Åß„ÅØË®±ÂèØ„Å؉∏ç˶ńÅß„Åô„ÄÇ
逆に、次のような行為をすると「職業紹介」に当たる可能性が高まります。
- ʱlj∫∫„ÇÑʱÇËÅ∑ËÄÖ„ÅÆÊÉÖÂݱ„Å´„Ç≥„É°„É≥„Éà„ÇÑÂÆ£‰ºùÊñáÂè•„Ç퉪ò„ÅëÂäÝ„Åà„Çã
- 面接の日程調整や連絡の代行を行う
- ÂøúÂãüÊñáÈù¢„Çí‰øÆÊ≠£„Åô„Çã„Å™„Å©„ÄÅÈÄö‰ø°ÂÜÖÂÆπ„Å´Êâã„ÇíÂäÝ„Åà„Çã
- ÈÅãÂñ∂ËÄÖ„ÅåÊÉÖÂݱ„ÇíÂèñÊç®ÈÅ∏Êäû„Åó„ÄÅÁâπÂÆö„ÅƄɶ„ɺ„Ç∂„ɺ„Å´Êèê‰æõ„Åô„Çã
ÂèÇËÄÉÔºàÂéöÁîüÂä¥ÂÉçÁúÅ„ÅÆÂ֨˰®ÔºâÔºö„Ç∞„ɨ„ɺ„Çæ„ɺ„É≥ËߣÊ∂àÂà∂Â∫¶„ÅÆÊ¥ªÁî®ÂÆüÁ∏æÔΩúÂéöÁîüÂä¥ÂÉçÁúÅÔºàÂãüÈõÜÊÉÖÂݱÁ≠âÊèê‰æõ„Å´„Åä„ÅфŶÂêÑʱÇËÅ∑ËÄÖÊØé„Å´ÂãüÈõÜË®ò‰∫ã„ÅÆË°®Á§∫ÈÝÜÂ∫è„Çí„Éë„ɺ„ÇΩ„Éä„É©„ǧ„Ç∫„Åô„Çã„ǵ„ɺ„Éì„ÇπÔºâ
„Åì„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å´„ÄÅÊé≤˺â„Åï„Çå„ÅüÊÉÖÂݱ„Å´ÈÅãÂñ∂ËÄÖ„ÅÆÊÑèÂõ≥„ÇÑÂà§Êñ≠„ÅåËøΩË®ò„Åï„Çå„Çã„ÅãÂ궄Åã„Åå„ÄÅËÅ∑Ê•≠Á¥π‰ªã„Å´„Åä„Åë„ÇãË®±ÂèØ„ÅÆÂøÖ˶ÅÊÄß„Å´ÂΩ±Èüø„ÇíÂèä„ź„Åó„Åæ„Åô„ÄÇ
業務委託のあっせんに伴う有料職業紹介事業許可
上記のとおり、雇用関係の成立のあっせんでなければ、職業安定法上の職業紹介には該当しません。
„Åó„Åü„Åå„Å£„Ŷ„ÄÅÈõáÁî®Èñ¢‰øÇ„Åß„ÅØ„Å™„Åè„ÄÅÊ•≠ÂãôÂßîË®óÈñ¢‰øÇ„ÅÆÊàêÁ´ã„Çí„ÅÇ„Å£„Åõ„Çì„Åô„ÇãÂÝ¥Âêà„Å´„ÅØ„ÄÅÊúâÊñôËÅ∑Ê•≠Á¥π‰ªã‰∫ãÊ•≠Ë®±ÂèØ„ÇíÂèñÂæó„Åô„ÇãÂøÖ˶ńÅå„Å™„ÅÑ„Åì„Å®„Å´„Å™„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
„Åó„Åã„Åó„ÄÅÈõáÁî®Èñ¢‰øÇ„ÅÆÊàêÁ´ã„ÅÆ„ÅÇ„Å£„Åõ„Çì„Å´Ë©≤ÂΩì„Åô„Çã„ÅãÂ궄Åã„ÅØ„Äʼn∫ãÊ•≠„ÅÆÂÆüÊÖã„Åã„ÇâÂÆüË≥™ÁöÑ„Å´Âà§Êñ≠„Åï„Çå„Çã„Åü„ÇÅ„ÄÅÊ•≠ÂãôÂßîË®ó„Å®Áß∞„Åó„Ŷ„ÅфŶ„ÇÇÂÆüË≥™ÁöÑ„Å´„ÅØÈõáÁÅß„ÅÇ„Çã„Å®Âà§Êñ≠„Åï„Çå„Çã„Çà„ÅÜ„Å™ÂÝ¥Âêà„ÅØ„ÄÅÊúâÊñôËÅ∑Ê•≠Á¥π‰ªã‰∫ãÊ•≠„ÅÆË®±ÂèØ„ÅåÂøÖ˶ńŮ„Å™„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
ÊúâÊñôËÅ∑Ê•≠Á¥π‰ªã‰∫ãÊ•≠Ë®±ÂèØ„ÇíÂèñÂæó„Åó„Å™„ÅÑÂÝ¥Âêà„ÅÆÊ≥®ÊÑèÁÇπ

Wantedly„Å™„Å©„Å®ÂêåÊßò„Å´„ÄÅÊúâÊñôËÅ∑Ê•≠Á¥π‰ªã‰∫ãÊ•≠Ë®±ÂèØ„ÇíÂèñÂæó„Åõ„Åö„Å´„ÄÅʱlj∫∫ËÄքɪʱÇËÅ∑ËÄÖ„ÅÆ„Éû„ÉÉ„ÉÅ„É≥„Ç∞„ǵ„ɺ„Éì„Çπ„Çí„É°„ǧ„É≥„Å®„Åó„Åü‰∫ãÊ•≠„ÇíÂßã„ÇÅ„Åü„ÅÑ„Å®„ÅÑ„ÅÜÂÝ¥Âêà„Å´„ÅØ„ÄÅÁâπÂÆö„ÅÆÊñáˮĄÅÆË®ò˺â„ÇÑÁâπÂÆö„ÅƄǵ„ɺ„Éì„Çπ„Å™„Å©„Å´„Çà„Çä„ÄÅÊúâÊñôËÅ∑Ê•≠Á¥π‰ªã‰∫ãÊ•≠Ë®±ÂèØ„ÇíÂèñ„ÇãÂøÖ˶ńÅåÁîü„Åò„Çã„ÅÆ„ÅßÊ∞ó„Çí„ŧ„Åë„ÇãÂøÖ˶ńÅå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„Äljª•‰∏ã„Åß„ÅØ„ÄÅ„Éù„ǧ„É≥„Éà„Å®„Å™„ÇãÁÇπ„ÇíÂÖ∑‰ΩìÁöÑ„Å´Ë™¨Êòé„Åó„Åæ„Åô„ÄÇ
ÊúâÊñôËÅ∑Ê•≠Á¥π‰ªã‰∫ãÊ•≠Ë®±ÂèØ„ÇíÂèñÂæó„Åó„Å™„ÅÑÂÝ¥Âêà„Å´„ÇÑ„Å£„Ŷ„ÅØ„ÅÑ„Åë„Å™„ÅÑ„Åì„Å®
運営するサービスのウェブサイト等に以下の記載をしたり、以下のサービスを提供したりすると、「職業紹介」にあたると判断される可能性があります。
„Åó„Åü„Åå„Å£„Ŷ„ÄÅÊúâÊñôËÅ∑Ê•≠Á¥π‰ªã‰∫ãÊ•≠Ë®±ÂèØ„ÇíÂèñÂæó„Åó„Å™„ÅÑÂÝ¥Âêà„Å´„ÅØ„Äʼnª•‰∏ã„ÅÆ„Åì„Å®„ÇíË°å„Çè„Å™„ÅÑ„Çà„ÅÜ„Å´Ê∞ó„Ç퉪ò„Åë„Åæ„Åó„Çá„ÅÜ„ÄÇ
- ʱlj∫∫ÊÉÖÂݱ„ɪʱÇËÅ∑ËÄÖÊÉÖÂݱ„Å´„ÄÅÈÅãÂñ∂ËÄÖ„ÅåÁ¥π‰ªãÊñáÂè•„ÇÑÂÆ£‰ºùÊñáÂè•„Ç퉪ò„Åó„Åü„Çä„ÄÅÈÅãÂñ∂ËÄÖ„ÅÆÂà§Êñ≠„Å´„Çà„Çäʱlj∫∫ÊÉÖÂݱ„ɪʱÇËÅ∑ËÄÖÊÉÖÂݱ„Çí„Ç´„ÉÜ„Ç¥„É©„ǧ„Ç∫„Åó„Åü„Çä„Åô„Çã„Åì„Å®
- 求人者・求職者間の面談の日程調整を行う等の便宜を図ること
- ÈÅãÂñ∂„Åô„Çã„Ƕ„Çß„Éñ„ǵ„ǧ„Éà‰∏ä„Åßʱlj∫∫ËÄքɪʱÇËÅ∑ËÄÖ„ÅåÊÑèÊÄùÁñéÈÄö„Åô„Çã„Å®„Åç„ÄÅÈÄö‰ø°ÂÜÖÂÆπ„ÇíÂäÝÂ∑•„Åô„Çã„Åì„Å®
- ÈÅãÂñ∂ËÄÖ„Åå„ÄÅʱlj∫∫ÊÉÖÂݱ„ɪʱÇËÅ∑ËÄÖÊÉÖÂݱ„ÇíÈÅ∏Âà•„Åó„Ŷ„ÄÅÂÄãÂà•„ÅÆʱlj∫∫ËÄքɪʱÇËÅ∑ËÄÖ„Å´Âêë„Åë„ŶÊèê‰æõ„Åô„Çã„Åì„Å®
ʱlj∫∫ÊÉÖÂݱ„ɪʱÇËÅ∑ËÄÖÊÉÖÂݱ„ÅƉΩúÊàê
‰∏äË®ò1„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÄÅ„Éû„ÉÉ„ÉÅ„É≥„Ç∞„ǵ„ɺ„Éì„Çπ„Å®„Åó„ŶÈÅãÂñ∂„Åô„Çã„Ƕ„Çß„Éñ„ǵ„ǧ„Éà‰∏ä„Ŵʱlj∫∫ÊÉÖÂݱ„ÇÑʱÇËÅ∑ËÄÖÊÉÖÂݱ„ÇíÊé≤˺â„Åô„ÇãÂÝ¥Âêà„Å´„ÄÅʱlj∫∫ËÄքɪʱÇËÅ∑ËÄÖ„Å´‰ª£„Çè„Å£„Ŷ„ÄÅÈÅãÂñ∂ËÄÖ„Ååʱlj∫∫ÊÉÖÂݱ„ɪʱÇËÅ∑ËÄÖÊÉÖÂݱ„Çí‰ΩúÊàê„Åô„Çã„Å®„ÄåËÅ∑Ê•≠Á¥π‰ªã„Äç„Å´Ë©≤ÂΩì„Åô„Çã„Å®„Åó„Ŷ„ÄÅÊúâÊñôËÅ∑Ê•≠Á¥π‰ªã‰∫ãÊ•≠Ë®±ÂèØ„ÇíÂèñÂæó„Åô„ÇãÂøÖ˶ńÅåÂá∫„Ŷ„Åç„Åæ„Åô„ÄÇ
„Åó„Åü„Åå„Å£„Ŷ„ÄÅʱlj∫∫ÊÉÖÂݱ„ÅØʱlj∫∫‰ºÅÊ•≠Ëá™Ë∫´„Å´ËᙄÇâ„ÅÆË≤¨‰ªª„Å´„Åä„ÅфŶÁôªÈå≤„Åó„Ŷ„ÇÇ„Çâ„Å܉ªïÁµÑ„Åø„Å®„Åô„ÇãÂøÖ˶ńÅå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇʱÇËÅ∑ËÄÖ„ÅÆÊÉÖÂݱ„ÇÇÂêåÊßò„Å´„ÄÅʱÇËÅ∑ËÄÖËá™Ë∫´„ÅåÁôªÈå≤„Åó„Å™„Åë„Çå„Å∞„Å™„Çä„Åæ„Åõ„Çì„ÄÇ
„Åæ„Åü„ÄÅʱlj∫∫ÊÉÖÂݱ„ÇÑʱÇËÅ∑ËÄÖÊÉÖÂݱ„Çíʱlj∫∫‰ºÅÊ•≠Âèà„ÅØʱÇËÅ∑ËÄÖËá™Ë∫´„Å´ÁôªÈå≤„Åó„Ŷ„ÇÇ„Çâ„ÅÜÂÝ¥Âêà„Åß„ÇÇ„ÄÅ„Éû„ÉÉ„ÉÅ„É≥„Ç∞„ǵ„ɺ„Éì„ÇπÈÅãÂñ∂ËÄÖ„ÅåÂÆ£‰ºùÊñáÂè•„ÇÑ„Ç¢„Éî„ɺ„É´„Éù„ǧ„É≥„ÉàÁ≠â„ÅÆ„Ç≥„É°„É≥„Éà„ÇíËøΩÂäÝ„Åô„Çã„Åì„Å®„Åå„ÄåËÅ∑Ê•≠Á¥π‰ªã„Äç„Å´Ë©≤ÂΩì„Åô„Çã„Å®Âà§Êñ≠„Åï„Çå„Çã„Åä„Åù„Çå„Åå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
„Åó„Åü„Åå„Å£„Ŷ„ÄÅÊúâÊñôËÅ∑Ê•≠Á¥π‰ªã‰∫ãÊ•≠Ë®±ÂèØ„ÇíÂèñÂæó„Åó„Å™„ÅÑ„ÅÆ„Åß„ÅÇ„Çå„Å∞„ÄÅÁôªÈå≤„Åï„Çå„Åüʱlj∫∫ÊÉÖÂݱ„ɪʱÇËÅ∑ËÄÖÊÉÖÂݱ„Å∏„ÅÆÂäÝÁ≠Ü„ÅØ„Åô„Åπ„Åç„Åß„ÅØ„ÅÇ„Çä„Åæ„Åõ„Çì„ÄÇ
„Åæ„Å®„ÇÅ„Çã„Å®„ÄÅʱlj∫∫ËÄքŮʱÇËÅ∑ËÄÖ„ÅÆÈñì„Å´„ÄÅ„Éû„ÉÉ„ÉÅ„É≥„Ç∞„ǵ„ɺ„Éì„ÇπÈÅãÂñ∂ËÄÖ„ÅÆÊÑèÂõ≥„ÇÑÂà§Êñ≠„Ç퉺¥„ÅÜË°åÁÇ∫„ÅƉªãÂú®„Åå„ÅÇ„Çã„ÅãÂ궄Åã„Åå„Éù„ǧ„É≥„Éà„Å®„Å™„Çä„Åæ„Åô„ÄÇʱlj∫∫ËÄքɪʱÇËÅ∑ËÄÖ„Å´„Çà„Å£„ŶÁôªÈå≤„Åï„Çå„ÅüÊÉÖÂݱ„Çí„Åù„ÅÆ„Åæ„Åæ„Ƕ„Çß„Éñ„ǵ„ǧ„Éà‰∏ä„ÅßÂÖ¨Èñã„Åô„Çã„Å®„ÅÑ„Å£„Åü„ÄÅÂçòÁ¥î„Å™ÊÉÖÂݱÊèê‰æõ„Å´Âæπ„Åô„Çã„Åì„Å®„ÅåÈáç˶ńŮ„ÅÑ„Åà„Åæ„Åô„ÄÇ
求人者と求職者の意思疎通

‰∏äË®ò3„Å´Ë®ò˺â„ÅÆ„Å®„Åä„Çä„ÄÅʱlj∫∫‰ºÅÊ•≠„Å´ÂØæ„Åó„ŶʱÇËÅ∑ËÄÖ„ÅåÂïèÂêà„Åõ„ÇÑÂøúÂãü„Çí„Åô„ÇãÂÝ¥Âêà„Å™„Å©„ÄÅʱlj∫∫ËÄքɪʱÇËÅ∑ËÄÖ„ÅåÊÑèÊÄùÁñéÈÄö„ÇíË°å„ÅÜÈöõ„Å´„ÄÅÈÄö‰ø°ÂÜÖÂÆπ„Çí„Éû„ÉÉ„ÉÅ„É≥„Ç∞„ǵ„ɺ„Éì„ÇπÈÅãÂñ∂ËÄÖ„ÅåÂäÝÂ∑•„Åô„Çã„Å®„ÄåËÅ∑Ê•≠Á¥π‰ªã„Äç„Å´„ÅÇ„Åü„Çä„ÄÅÊúâÊñôËÅ∑Ê•≠Á¥π‰ªã‰∫ãÊ•≠Ë®±ÂèØ„ÅÆÂèñÂæó„ÅåÂøÖ˶ńŮ„Å™„Å£„Ŷ„Åó„Åæ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
例えば、
- 求人企業に向けたサービスとして、求職者に対する連絡用のテンプレートを作成すること
- 求職者が求人企業に応募する際に、応募の文面を求人企業の受けがいいように修正するようなサービスを行うこと
などは、「職業紹介」にあたると判断されることがあります。
したがって、有料職業紹介事業許可を取得しないのであれば、このようなサービスを行うことはできません。 
‰ª•‰∏ä„Åã„Çâ„ÄńǶ„Çß„Éñ„ǵ„ǧ„Éà„ÇíÈÄö„Åò„Ŷʱlj∫∫‰ºÅÊ•≠„ŮʱÇËÅ∑ËÄÖ„ÅåÈÄ£Áµ°„ÇíÂèñ„ÇäÂêà„Åà„Çã„Çà„ÅÜ„Å™„Ç∑„Çπ„ÉÜ„ÉÝ„ÇíË®≠„Åë„Åü„Å®„Åó„Ŷ„ÇÇ„Äʼn∏°ËÄÖ„ÅÆÈÄ£Áµ°ÂÜÖÂÆπ„Å´„ÅØÈñ¢‰∏é„Åõ„Åö„ÄÅ„Åü„ÅÝÈÄ£Áµ°ÁÉфɺ„É´„ÇíÊèê‰æõ„Åô„Çã„ÅÆ„Åø„Åß„ÅÇ„Çå„Å∞„ÄÅ„Éû„ÉÉ„ÉÅ„É≥„Ç∞„ǵ„ɺ„Éì„ÇπÈÅãÂñ∂ËÄÖ„ÅÆÊÑèÂõ≥„ÇÑÂà§Êñ≠„Å剪ãÂú®„Åô„Çã„Åì„Å®„Å´„ÅØ„Å™„Çâ„Å™„ÅÑ„Åü„ÇÅ„ÄÅËÅ∑Ê•≠ÂÆâÂÆöÊ≥ï‰∏ä„ÅÆÂïèÈ°å„ÅØÁîü„Åò„Å™„ÅÑ„Å®ËÄÉ„Åà„Çâ„Çå„Åæ„Åô„ÄÇ
近年増えている「リファラル採用」の違法性
リファラル採用は、社員が知人や友人を会社に紹介する制度で、採用コストの削減やミスマッチ防止につながる手法として注目を集めています。しかし、紹介に対してインセンティブを支払う仕組みを誤ると、職業安定法違反となるリスクがあります。
ÂÖ∑‰ΩìÁöÑ„Å´„ÅØ„ÄÅËÅ∑Ê•≠ÂÆâÂÆöÊ≥ïÁ¨¨30Êù°„ÅØ„ÄåÊúâÊñôËÅ∑Ê•≠Á¥π‰ªã„Äç„ÇíÂéöÁîüÂä¥ÂÉçÁúÅ„ÅÆË®±ÂèØÂà∂„Å®ÂÆö„ÇńŶ„Åä„Çä„ÄÅÁ¥π‰ªãË°åÁÇ∫„Å´ÂݱÈÖ¨„Ç퉺¥„ÅÜÂÝ¥Âêà„ÅØË®±ÂèØ„ÅåÂøÖ˶ńÅß„Åô„ÄÇ„Åæ„Åü„ÄÅÁ¨¨40Êù°„Åß„ÅØ„ÄÅÂä¥ÂÉçËÄÖ„ÅÆÂãüÈõÜ„Å´Âæì‰∫ã„Åô„ÇãËÄÖ„Å´ÂØæ„Åó„ÄʼnºÅÊ•≠„ÅåÂݱÈÖ¨„Çí‰∏é„Åà„Çã„Åì„Å®„ÇíÁ¶ÅÊ≠¢„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇÈÅïÂèç„Åô„Çã„Å®6„ÅãÊúà‰ª•‰∏ã„ÅÆÊãòÁ¶ÅÂàë„Åæ„Åü„ÅØ30‰∏áÂÜ܉ª•‰∏ã„ÅÆÁΩ∞Èáë„ÅåÁßë„Åï„Çå„ÇãÂèØËÉΩÊÄß„Åå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
„ŧ„Åæ„Çä„ÄÅ„É™„Éï„Ç°„É©„É´Êé°ÁÇíË°å„ÅÜÈöõ„Å´„ÄÅÂݱÈÖ¨„Çí„ÄåÁ¥π‰ªãÊñô„Äç„Å®„Åó„ŶÁ§æÂì°„Å´ÊîØÊâï„ÅÜ„Å®ÈÅïÊ≥ï„Å´Ë©≤ÂΩì„Åô„ÇãÊÅê„Çå„Åå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇÈÅ©Ê≥ï„Å´Âà∂Â∫¶„ÇíË®≠Ë®à„Åô„Çã„Åü„ÇÅ„Å´„ÅØ„Äńǧ„É≥„Ǫ„É≥„ÉÜ„Ç£„Éñ„Çí„ÄåÁµ¶‰∏é„Äç„Å®„Åó„ŶÂ∞±Ê•≠˶èÂâá„Å´ÊòéË®ò„Åó„ÄÅÂä¥ÂÉçÂü∫Ê∫ñÁõ£Áù£ÁΩ≤„Å∏„ÅƱäÂá∫„ÇíÊ∏à„Åæ„Åõ„Ŷ„Åä„Åè„Åì„Å®„ÅåÈáç˶ńÅß„Åô„ÄÇ
まとめ:人材紹介トラブルでお悩みなら弁護士へご相談を
もともと、Wantedlyのような求人企業と求職者のマッチングサービスは、IT業界を中心に利用されるようになりましたが、最近では他の業界へも拡大しています。働き方の多様化に伴い、今後は同種のサービスの需要の高まりが期待されます。
„ÇÇ„Å£„Å®„ÇÇ„Äʼn∫∫ÊùêÁ¥π‰ªã„Å´Èñ¢„Åó„Ŷ„ÅØÂä¥ÂÉçËÄÖ‰øùË≠∑„ÅÆ˶ÅË´ã„Ååº∑„ÅÑ„Åü„ÇÅ„ÄÅËÅ∑Ê•≠ÂÆâÂÆöÊ≥ï„Å´„Çà„ÇäÂé≥„Åó„ÅÑ„É´„ɺ„É´„ÅåÂÆö„ÇÅ„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ„Åì„ÅÆ„Åü„ÇÅ„ÄÅÂêåÁ®Æ„ÅƄǵ„ɺ„Éì„Çπ„ÅƱïÈñã„ÇíʧúË®é„Åó„Ŷ„ÅÑ„ÇãÂÝ¥Âêà„Å´„ÅØ„Äʼn∫ãÂâç„Å´Ê≥ïÁöÑ„Å™ÂïèÈ°å„Åå„Å™„ÅÑ„ÅãÂøÖ„ÅöʧúË®é„Åô„ÇãÂøÖ˶ńÅå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
„Å™„Åä„ÄÅITÊ•≠Áïå„Åß„ÅƉ∫∫Êùê„Éì„Ç∏„Éç„Çπ„Åß„ÅØÂÅΩË£ÖË´ãË≤Ý„ÇÇÂïèÈ°å„Å´„Å™„Çä„ÇÑ„Åô„ÅÑ„ÅÆ„Åß„ÄÅ‰Ωµ„Åõ„ŶÁ¢∫Ë™ç„Åó„Ŷ„Åä„Åè„Å®ËâØ„ÅÑ„Åß„Åó„Çá„ÅÜ„ÄÇITÊ•≠Áïå„ÅÆÂÅΩË£ÖË´ãË≤Ý„Å´Èñ¢„Åó„Ŷ„ÅØ„Äʼn∏ãË®òË®ò‰∫ã„ÅßËߣ˙¨„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
当事務所による対策のご案内
„É¢„Éé„É™„ÇπÊ≥ïÂæã‰∫ãÂãôÊâÄ„ÅØ„ÄÅIT„ÄÅÁâπ„Å´„ǧ„É≥„Çø„ɺ„Éç„ÉÉ„Éà„Å®Ê≥ïÂæã„ÅƉ∏°Èù¢„Å´È´ò„ÅÑÂ∞ÇÈñÄÊÄß„ÇíÊúâ„Åô„ÇãÊ≥ïÂæã‰∫ãÂãôÊâÄ„Åß„Åô„ÄÇÂΩì‰∫ãÂãôÊâÄ„Åß„ÅØ„ÄÅÊù±Ë®º‰∏äÂÝ¥‰ºÅÊ•≠„Åã„Çâ„Éô„É≥„ÉÅ„É£„ɺ‰ºÅÊ•≠„Åæ„Åß„ÄÅ„Åï„Åæ„Åñ„Åæ„Å™Ê°à‰ª∂„Å´ÂØæ„Åô„Çã•ëÁ¥ÑÊõ∏„ÅƉΩúÊàê„ɪ„ɨ„Éì„É•„ɺ„ÇíË°å„Å£„Ŷ„Åä„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ„ÇÇ„Åó•ëÁ¥ÑÊõ∏Á≠â„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÅäÂõ∞„Çä„Åß„ÅÇ„Çå„Å∞„Äʼn∏ãË®òË®ò‰∫ã„Çí„ÅîÂèÇÁÖß„Åè„ÅÝ„Åï„ÅÑ„ÄÇ