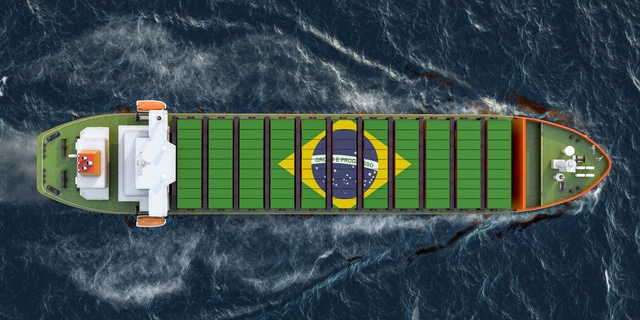ポーランドでの契約書作成・交渉時に問題となる民法・契約法

中東欧における経済の中心地として、また欧州連合(EU)の重要な一員として、ポーランドは日本企業にとってますます魅力的なビジネス拠点となっています。しかし、同国で事業を展開し、現地企業との取引を成功させるためには、その法的基盤、特に民法および契約法に関する深い理解が不可欠です。ポーランドは、日本と同様に大陸法(シビル・ロー)の法体系に属しており、法典を中心とした構造など、一見すると親しみやすい側面も多く存在します。現行のポーランド民法典(Kodeks cywilny)は1964年に制定されたもので、ドイツ民法学の影響を受けたパンデクテン方式を採用している点も、日本の法務担当者にとっては理解の助けとなるでしょう。
しかし、この表面的な類似性の下に、ポーランド独自の歴史的経緯から生まれた、日本法とは大きく異なる重要な法的概念や制度が数多く存在します。これらの違いを看過することは、予期せぬ契約上のリスクや紛争を招く原因となりかねません。例えば、契約の有効性を判断する上で極めて重要な役割を果たす「社会共存の原則」という包括的な概念は、日本の公序良俗や信義則とは異なる射程と機能を持っています。また、契約違反が生じた際の債務不履行責任においては、債務者の過失が「推定」されるという、日本の一般的な考え方とは逆の構造が採用されており、これは紛争時の立証責任に大きな影響を与えます。
さらに、実務上頻繁に利用される「違約罰(Kara Umowna)」は、損害の発生を証明せずとも請求できる強力な権利である一方、裁判所がその額を減額できるという独自の制度が設けられています。商品の欠陥に関する「瑕疵担保責任(Rękojmia)」についても、買主が行使できる権利の順序に特有のルールが存在し、特に事業者間取引においては、この法定責任を契約によってどのように修正するかが交渉の重要な焦点となります。
本記事では、これらのポーランド民法・契約法に特有の重要論点に焦点を当て、日本の法律との比較を交えながら、ポーランドでのビジネス展開を検討されている日本企業が実務上注意すべきポイントを、具体的な法令や判例を基に詳説します。
この記事の目次
ポーランド民法・契約法の法体系
大陸法体系に属する共通点と歴史的背景の違い
ポーランドと日本の民法は、いずれもローマ法を淵源とする大陸法体系に属するという大きな共通点を持っています。特に、ポーランド民法典がドイツ法学に由来するパンデクテン方式(総則、物権、債権、親族、相続という構成)を採用している点は、同じくドイツ民法の影響を強く受けた日本の民法典の構造と類似しており、日本の法律専門家にとって、その全体像を把握しやすいものとなっています。この共通の構造は、法律の基本的な考え方や用語において一定の理解の土台を提供します。
しかし、この構造的な類似性は、両国の法制度が同一であることを意味するものではありません。むしろ、ポーランド法の真の姿は、その複雑で重層的な歴史的背景から理解する必要があります。日本の民法が主にドイツ法とフランス法を選択的に継受して成立したのに対し、ポーランドは18世紀末の国家分割以降、オーストリア、プロイセン、ロシアという三国の支配下に置かれ、それぞれの地域の法制度が個別に適用される時代が長く続きました。1918年の独立回復後、これらの異なる法制度を統一する試みがなされましたが、第二次世界大戦後の社会主義時代にはソビエト連邦の影響を色濃く受けた法改正が行われました。そして1989年の体制転換以降は、市場経済への移行と2004年のEU加盟に伴い、急速に西欧的な法制度、特にEU法との整合性を図るための変革を遂げてきました。
このような歴史的経緯から、ポーランドの民法・契約法は、一見すると日本の法体系と似た骨格を持ちながらも、その細部においては異なる法概念や解釈論が埋め込まれているという特徴があります。例えば、社会主義時代に導入された概念が、体制転換後に市場経済における公正さを担保するためのツールとして再解釈されるなど、独自の発展を遂げた分野も少なくありません。したがって、日本の法律専門家がポーランド法を扱う際には、この「似て非なる」構造を常に意識し、安易に日本法の知識を当てはめることなく、ポーランド法固有の解釈や判例の動向を慎重に確認することが極めて重要です。
日本法と異なる「社会共存の原則」の概念
ポーランドの契約法を理解する上で避けて通れないのが、「社会共存の原則」(zasady współżycia społecznego)という独特の概念です。これは、ポーランド民法典第353¹条に明記されている契約自由の原則の根幹をなす制限原理の一つです。同条は、「契約当事者は、その内容または目的が、当該法律関係の性質、法律または社会共存の原則に反しない限り、自らの裁量によって法律関係を形成することができる」と定めています。
この「社会共存の原則」は、成文法には定義されていない、社会における公正さや誠実さ、道徳といった不文の規範を指す「包括条項(general clause)」として機能します。これにより、裁判所は、形式的には合法であっても、実質的に一方の当事者にとって著しく不公正であったり、社会的に許容されないような契約内容を無効と判断する広範な裁量を持つことになります。
この点は、日本の民法における「公の秩序又は善良の風俗」(公序良俗)や「信義誠実の原則」(信義則)と機能的に類似していますが、その適用範囲と射程において重要な違いがあります。日本の公序良俗違反による無効は、反社会的な内容の契約など、比較的限定的な場面で適用される傾向にあります。一方、ポーランドの「社会共存の原則」は、より積極的に個別の契約における当事者間の実質的な公平性を確保するために用いられます。例えば、当事者間の力関係の不均衡を利用した一方的に有利な条項は、たとえ強行法規に直接違反していなくても、この原則に反するとして無効とされる可能性があります。
「社会共存の原則」に関する重要判例
この原則の重要性を示す判例として、ポーランド最高裁判所が2012年12月30日に下した判決(事件番号 III CzP 84/12)が挙げられます。この判決において最高裁は、商事会社法における「良き慣行」(dobre obyczaje)違反と、民法典における「社会共存の原則」違反は、実質的に同じ概念であるとの判断を示しました。「社会共存の原則」という言葉は社会主義時代からの名残でイデオロギー的な響きを持つため、新しい法律では「良き慣行」という言葉が使われる傾向にありますが、最高裁は両者を同一視することで、この原則が現代の市場経済においても取引の公正さを担保する重要な規範であることを明確にしたのです。この判例から、ポーランドの司法が、社会主義時代の法概念を現代の市場経済における公正さを実現するための柔軟なツールとして積極的に再利用していることが見て取れます。
そして、この原則の具体的な適用について、契約終了後の競業避止義務に関する判例が非常に参考になります。ポーランド最高裁判所が2003年9月11日に下した判決(事件番号 III CKN 579/01)では、業務委託契約(zlecenia)において、契約終了後3年間にわたり競業を禁止し、違反した場合には高額な違約罰を課す一方で、競業を控えることに対するいかなる金銭的対価(補償)も定めていない条項が問題となりました。最高裁判所は、この契約終了後の競業避止義務条項を「社会共存の原則」に反し無効であると判断しました。その理由として、何らの対価もなしに、長期間にわたって契約当事者の一方の経済活動の自由を著しく制限することは、公正さの原則に反するとしたのです。
日本においても、特に雇用契約における退職後の競業避止義務の有効性は、公序良俗(民法90条)に反するか否かという観点から、制限の期間、範囲、必要性、そして代償措置の有無などを総合的に考慮して判断されます。しかし、対等な当事者間とされる事業者間の契約(業務委託契約など)においては、契約自由の原則がより広く尊重される傾向にあり、代償措置がないことのみを理由に直ちに無効と判断される可能性は、雇用契約の場合に比べて低いと言えるでしょう 。ポーランドのこの判例は、「社会共存の原則」が、事業者間の契約であっても、一方に不利益な義務を課す場合には相応の対価を要求するという、より実質的な公平性を強く求める規範として機能していることを示しています。
ポーランドにおける契約締結実務の重要ポイント
契約自由の原則とその重要な制約
ポーランドの契約法は、民法典第353条に定められる「契約自由の原則」を基本としています。これは、当事者が誰と、どのような内容の契約を、どのような方式で締結するかを原則として自由に決定できるという、近代私法の根幹をなす理念です。しかし、この自由は無制限ではなく、同条が明記する通り、三つの重要な制約に服します。
第一の制約は「法律関係の性質」(natura stosunku)です。これは、契約内容が、その契約類型が本来持つべき本質的な特徴を損なうものであってはならないという原則です。例えば、医師の治療契約のような、専門的な知識をもって最善の努力を尽くすことを目的とする「準委任契約」において、特定の結果(例えば「完治」)を保証する条項を設けることは、契約の性質に反するとして無効と判断される可能性があります。
第二の制約は「法律」(ustawa)です。これは、契約内容が、当事者の意思によって変更することが許されない強行法規(ius cogens)に違反してはならないという原則です。これは日本の民法にも共通する考え方であり、消費者保護法規や労働法規など、当事者間の合意によっても排除できないルールがこれに該当します。
第三の制約が、前述した「社会共存の原則」です。これは、契約内容が法的には許容されていても、著しく不公正であったり、一方の当事者を不当に搾取するものであったりする場合に、その効力を否定するものです。民法典第58条は、法律または社会共存の原則に反する法律行為を「絶対的に無効」と定めており、この原則が強力な法的効果を持つことを示しています。
これらの制約は、単なる理論上の存在ではなく、ポーランドの裁判所で実際に契約の有効性を判断する際の重要な基準として機能しています。このことから、ポーランドで契約書を作成する際には、日本以上に「形式」だけでなく「実質」が問われるということが言えるでしょう。つまり、単に法律の条文に違反していないかを確認するだけでなく、その契約が取引の目的に照らして合理的か、当事者間の利益のバランスが著しく損なわれていないか、といった実質的な観点からの検討が不可欠です。特に、力関係に差がある当事者間の契約においては、一方的に有利な条項を設けることは、後に「社会共存の原則」違反を理由に無効とされるリスクを内包している点を十分に認識しておく必要があります。
契約の方式と書面・ドキュメント形式
ポーランドの契約法では、契約自由の原則の一環として、原則として「方式の自由」が認められています。法律が特定の方式を要求しない限り、契約は口頭、電子メール、あるいは当事者の行動によっても有効に成立します。しかし、取引の安定性と証明の確実性を確保するため、法律は特定の法律行為について厳格な方式を要求しており、これを遵守しない場合、その法律行為は無効となることがあります。
ポーランド法が定める主要な契約方式には、以下のものがあります。
まず、「書面形式」(forma pisemna)です。これは、契約内容を記載した文書に当事者が自筆で署名することによって成立します。この自筆署名は、適格電子署名(kwalifikowany podpis elektroniczny)によって代替することも可能です。多くの重要なビジネス契約において、最低限要求される形式です。
次に、「ドキュメント形式」(forma dokumentowa)があります。これは比較的新しい形式で、書面形式よりも柔軟です。署名は不要で、電子メールやSMS、音声録音など、内容を記録でき、かつ意思表示をした人物を特定できるデータ媒体であれば、この形式の要件を満たします。迅速性が求められる日常的な取引で有用な形式です。
そして最も厳格な形式が、「公正証書形式」(akt notarialny)です。これは、公証人(notariusz)が契約書全体を作成し、当事者の面前でその内容を読み聞かせた上で、当事者および公証人が署名することによって作成される公文書です。法律がこの形式を要求しているにもかかわらず、他の形式で契約を締結した場合、その契約は絶対的に無効となります。
公正証書形式が法的に義務付けられている代表的な例としては、不動産の所有権移転契約、有限会社(sp. z o.o.)の持分譲渡契約、会社の定款作成などが挙げられます。
ここで特筆すべきは、ポーランドにおける公証人の役割です。日本の公証人が主に署名の認証や文書の確定日付付与といった形式的な役割を担うのに対し、ポーランドの公証人は「公的な信頼を託された者」(person of public trust)と位置づけられる法律家であり、取引の適法性と当事者双方の利益保護を確保する実質的な責任を負います。公証人は、単に当事者が持参した文書を認証するのではなく、自ら契約書を起草し、その内容が法規や社会共存の原則に反していないかを確認する義務があります。このため、公正証書を要求される取引においては、公証人が取引の合法性を担保する「法の番人」としての役割を果たすことになります。これは、取引の安全性に大きく寄与する一方で、契約内容が公証人による実質的な審査を受けることを意味し、日本企業にとっては留意すべき重要な手続き上の特徴と言えるでしょう。
ポーランドにおける契約違反時の救済措置と責任

債務不履行責任の構造と過失の推定
契約が履行されなかった、あるいは不完全にしか履行されなかった場合の債務不履行責任は、ポーランド民法典第471条にその基本が定められています。同条は、「債務者は、債務の不履行または不適切な履行から生じた損害を賠償する義務を負う。ただし、その不履行または不適切な履行が、債務者の責めに帰すことのできない事由によるものである場合は、この限りでない」と規定しています。
この条文の構造が、日本法との比較において極めて重要な違いを含んでいます。それは、「過失の推定」という点です。日本の民法では、債権者が債務不履行責任を追及する場合、原則として債務者の故意・過失といった帰責事由の存在を債権者側が主張・立証する必要があります。これに対し、ポーランド民法典第471条は、債務の不履行または不適切な履行という事実があれば、債務者の過失が法的に「推定」される構造になっています。したがって、債務者が責任を免れるためには、債務者自らが「その不履行が自己の責めに帰すことのできない事由によるものであった」ことを積極的に証明しなければなりません。
この立証責任の転換は、契約違反を巡る紛争において、債権者(損害を受けた側)に著しく有利な状況をもたらします。債権者は、契約の存在、債務不履行の事実、損害の発生、そして不履行と損害との間の因果関係を証明すれば足り、債務者の内的な心理状態である過失の有無まで立証する必要はありません。立証の負担は、全面的に債務者側に移ります。
この法制度から、ポーランドにおけるビジネス実務上の重要な示唆が得られます。ポーランドで事業を行う日本企業が契約上の義務を負う側(例えば、製品の納入やサービスの提供を行う側)になる場合、自社の義務履行を妨げる可能性のあるあらゆる事象について、極めて詳細かつ正確に記録を保持しておく必要があります。万が一、債務不履行が発生した場合、「相手方がこちらの過失を証明できないから大丈夫だろう」という日本的な感覚は通用しません。むしろ、自らが不可抗力や第三者の行為など、自己の管理の及ばない事由によって履行が妨げられたことを、客観的な証拠をもって証明できなければ、法的に責任を負うことになります。この点は、契約管理およびリスク管理体制を構築する上で、特に注意を払うべきポイントです。
違約罰(Kara Umowna)の特異性
ポーランドの契約実務において広く用いられている特徴的な制度が、「違約罰」(kara umowna)です。これは、民法典第483条および第484条に規定されており、日本の違約金や損害賠償額の予定に類似しつつも、独自の機能とルールを持っています。
違約罰の最も重要な特徴は、以下の通りです。
第一に、違約罰は「非金銭債務」の不履行または不適切な履行に対してのみ設定できます。例えば、納期の遅延、品質基準の未達、秘密保持義務違反といった義務の履行を担保するために用いられます。金銭の支払遅延に対して違約罰を設定することはできません。
第二に、債権者は、実際に損害が発生したかどうか、またその損害額がいくらであったかを証明することなく、契約で定められた違約罰の支払いを請求できます。契約違反の事実さえあれば請求権が発生するため、債権者にとっては損害額の立証という困難なプロセスを回避できる、極めて強力な権利となります。
第三に、原則として、債権者は違約罰として定められた金額を超える損害賠償を請求することはできません。ただし、契約書に「違約罰の請求は、それを超える損害賠償の請求を妨げない」といった趣旨の条項を設けることで、実際の損害額が違約罰の額を上回る場合に、その差額を請求することが可能になります。
しかし、この強力な違約罰制度には、債務者を保護するための重要な仕組みが備わっています。それが、民法典第484条第2項に定められた「裁判所による減額」(miarkowanie)です。債務者は、裁判所に対し、(1) 債務が相当な程度履行された場合、または (2) 違約罰が「著しく過大」(rażąco wygórowana)である場合に、その減額を求めることができます。
何が「著しく過大」にあたるかについては、長年議論がありましたが、近時のポーランド最高裁判所の判決(2024年1月19日)は、その判断基準を具体化する上で重要な指針を示しました。同判決によれば、裁判所は単に違約罰の額と実際の損害額を比較するだけでなく、契約全体の価額に対する違約罰の比率、契約違反の性質や悪質性の程度、違反によって債務者が得た利益の有無など、複数の要素を総合的に考慮して判断すべきであるとされています。また、契約違反を理由に契約が解除された場合に違約罰を定めることの有効性については、ポーランド最高裁判所の判決(2008年12月17日、事件番号 I CSK 240/08)などにより肯定されています。
これらのことから、違約罰は、債権者にとっては債務履行を確保するための有効な手段である一方、債務者にとっては過大な負担となりうる両刃の剣であると言えます。契約交渉においては、違約罰の条項を設けること自体が重要な交渉事項となります。違約罰を設定する際には、それが抑止力として機能しつつも、後に裁判所で「著しく過大」と判断されて減額されるリスクを回避できるような、合理的でバランスの取れた金額を設定することが肝要です。
瑕疵担保責任(Rękojmia)における買主の権利
ポーランド民法における「瑕疵担保責任」(rękojmia za wady)は、売買された目的物に物理的または法的な瑕疵(欠陥)があった場合に、売主が買主に対して負う法定の厳格責任です。これは当事者間の特約がない限り法律上当然に発生する責任であり、日本の契約不適合責任に相当しますが、買主の権利行使の順序に特徴があります。
瑕疵があった場合、買主は原則として以下の4つの権利を有します。
- 瑕疵の修補請求
- 瑕疵のない物との交換請求
- 代金減額の意思表示
- 契約の解除(ただし、瑕疵が軽微でない場合に限る)
これらの権利の関係性、特に消費者(B2C)取引においては、特有の階層構造が設けられています。買主は、代金減額や契約解除を直ちに選択できるわけではありません。まず、買主が代金減額または契約解除の意思表示をした場合でも、売主が遅滞なく、かつ買主に過度の不便をかけずに、目的物を修補または交換することを申し出た場合、買主はこれを受け入れなければならないとされています。つまり、売主には最初に瑕疵を是正する機会(追完の機会)が与えられています。
ただし、売主のこの権利は一度きりです。一度修補または交換された目的物になお瑕疵が存する場合、売主はもはや修補や交換を申し出ることはできず、買主は自由に代金減額や契約解除を選択できるようになります。この仕組みは、日本の契約不適合責任において、買主が追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除を状況に応じて選択できるのとは異なり、より明確に売主の追完権を優先させる構造となっています。
この瑕疵担保責任の規定は、事業者間(B2B)取引と消費者(B2C)取引でその性質が大きく異なります。B2C取引においては、これらの規定は消費者を保護するための強行法規であり、契約によって消費者に不利に変更することは原則として許されません。一方、B2B取引においては、契約自由の原則が広く適用され、当事者間の合意によって瑕疵担保責任の内容を拡張、制限、あるいは完全に免除することが可能です。
したがって、B2B取引における契約交渉では、この法定の瑕疵担保責任をどのように扱うかが極めて重要な論点となります。売主としては責任範囲を限定または免除する条項を盛り込むことを目指し、買主としては法定の強力な権利を維持、あるいはさらに有利な条件を確保することを目指すことになります。この交渉の結果が、取引のリスク配分を直接的に決定づけるため、日本企業がポーランド企業と契約を締結する際には、瑕疵担保責任に関する条項の文言を細心の注意を払って検討する必要があります。なお、この法定の瑕疵担保責任(rękojmia)とは別に、通常は製造業者などが任意で提供する「保証」(gwarancja)制度も存在し、買主はどちらの権利を行使するかを選択できます。
ポーランドの契約に関連するその他の重要規定
消滅時効制度
契約に基づく権利も、一定期間行使しないと消滅時効にかかり、相手方が時効の完成を主張すれば、裁判所を通じてその権利を実現することができなくなります。ポーランドの消滅時効制度は、日本法と期間設定においていくつかの違いがあり、注意が必要です。
ポーランド民法における一般的な消滅時効期間は6年です。しかし、ビジネスに関連する請求権、すなわち「事業活動に関連する請求権」については、より短い3年という期間が適用されます。賃料のような定期的な給付を目的とする債権の時効期間も3年です。したがって、企業間の商取引から生じる債権の多くは、原則として3年で時効にかかると理解しておくのが実務的です。
さらに、特定の契約類型については、個別の法律でこれらとは異なる特別な時効期間が定められています。例えば、売買契約における瑕疵に関する請求権は、買主が瑕疵を発見してから1年以内に行使する必要がありますが、この期間は目的物の引渡しから2年を超えることはできません。また、請負契約(契約で特定された仕事の完成を目的とする契約)から生じる請求権の時効期間は、仕事の目的物が引き渡された日から2年と、非常に短く設定されています。
これらの期間を日本の制度と比較すると、特に商事債権の考え方に違いが見られます。日本では2020年の民法改正により商事時効(5年)の規定は廃止され、債権の消滅時効は原則として「権利を行使することができることを知った時から5年間」または「権利を行使することができる時から10年間」に統一されました。これに対し、ポーランドでは「事業活動に関連する請求権」というカテゴリーで3年という統一的な短期時効が維持されています。以下に、主要な請求権に関する両国の時効期間を比較します。
| ポーランドの消滅時効期間 | 日本の消滅時効期間 | |
|---|---|---|
| 一般的な債権 | 6年 | 権利行使可能を知った時から5年、または権利行使可能な時から10年 |
| 事業活動に関連する債権 | 3年 | 権利行使可能を知った時から5年、または権利行使可能な時から10年 |
| 売買契約の瑕疵に関する請求権 | 瑕疵発見から1年(引渡しから2年以内) | 契約不適合を知った時から1年以内に通知 |
不可抗力(Force Majeure)と事情変更の原則(Rebus Sic Stantibus)
契約締結時には予見できなかった重大な事態が発生し、契約の履行が困難または不可能になった場合に備えるための法的救済制度として、ポーランド法は二つの重要な仕組みを提供しています。
一つは「不可抗力」(Force Majeure)です。興味深いことに、ポーランドの民法典には「不可抗力」を直接定義する条文が存在しません。この概念は、判例や学説を通じて形成されてきたもので、一般に「外部から発生し、予測不可能で、回避不可能な出来事」と解釈されています。成文法上の明確な定義がないため、契約当事者がどのような事態を不可抗力とみなし、その場合にどのような効果(例えば、履行義務の免除や期間の延長)が生じるのかを、契約書の中で具体的に定義しておくことが極めて重要となります。戦争、天災、パンデミック、政府の命令などを不可抗力事由として具体的に列挙した条項(不可抗力条項)を設けることが、一般的な実務となっています。
もう一つは、民法典第357¹条に規定されている「事情変更の原則」(rebus sic stantibus)です。これは、契約締結後に「例外的」かつ「予見不可能」な事情の変更が生じ、その結果、当初の契約通りに履行することが一方の当事者にとって著しく困難となったり、甚大な損失をもたらす恐れがあったりする場合に、裁判所が介入して契約内容を修正または解除することを認める制度です。裁判所は、当事者双方の利益を考慮し、履行の方法や対価の額を変更したり、最終的には契約そのものを解消する判決を下すことができます。
この二つの制度は、相互に補完的な関係にあります。契約上の不可抗力条項は、当事者間の合意に基づき、特定の予見可能なリスク(例えば、特定のストライキやサプライチェーンの混乱など)を管理するための私的な取り決めです。これに対し、事情変更の原則は、不可抗力条項ではカバーしきれないような、まさに「想定外」の根本的な状況変化に対応するための、司法による最終的な救済措置(セーフティネット)と位置づけられます。したがって、ポーランドでビジネスを行う際には、契約書に詳細な不可抗力条項を盛り込んでリスク管理を図ると同時に、万が一の事態には事情変更の原則に基づく司法的救済の可能性があることを理解しておくという、二段構えのアプローチが有効です。
まとめ
本記事では、ポーランドの民法および契約法について、特に日本企業が現地でビジネスを展開する上で重要となる論点を、日本法との比較を交えながら解説しました。ポーランド法は、日本と同じ大陸法体系に属し、一見すると親しみやすい構造を持っていますが、その内実には独自の歴史的背景から生まれた、看過できない重要な違いが存在します。
特に、契約の有効性を実質的な公平性の観点から判断する「社会共存の原則」の存在、債務不履行責任における「債務者の過失推定」という立証責任の転換、損害の証明を不要とする一方で裁判所による減額が可能な「違約罰(Kara Umowna)」制度、そして売主に最初の追完の機会を与える「瑕疵担保責任(Rękojmia)」の階層的構造は、日本の法務実務家の感覚とは大きく異なるため、十分な注意が必要です。
これらのポーランド法に特有の制度は、契約交渉、リスク管理、そして紛争解決の各段階において、日本企業に直接的な影響を及ぼします。ポーランドでのビジネスを成功に導くためには、日本法の常識を一旦脇に置き、これらの法制度の趣旨と機能を正確に理解した上で、現地の法務環境に適合した契約戦略を策定することが不可欠です。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務