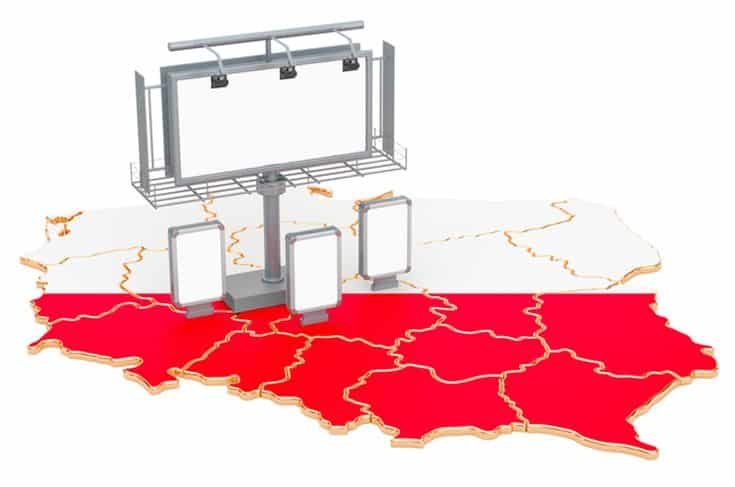уГЮуГлуВ┐хЕ▒хТМхЫ╜уБлуБКуБСуВЛши┤шиЯуГ╗ф╗▓шгБуГ╗шк┐хБЬуБлуВИуВЛч┤Ыф║Йшзгц▒║уГбуВлуГЛуВ║уГа

уГЮуГлуВ┐уБоц│ХхИ╢х║жуБпуАБхдзщЩ╕ц│Хя╝ИCivil Lawя╝ЙуБишЛ▒ч▒│ц│Хя╝ИCommon Lawя╝ЙуБошжБч┤ауВТшЮНхРИуБХуБЫуБЯчЛмшЗкуБоуГПуВдуГЦуГкуГГуГЙуВ╖уВ╣уГЖуГауВТчЙ╣х╛┤уБиуБЧуАБуБХуВЙуБлцмзх╖ЮщАгхРИя╝ИEUя╝Йц│ХуБох╜▒щЯ┐уВТх╝╖уБПхПЧуБСуБжуБДуБ╛уБЩуАВ
цЬмшиШф║ЛуБзуБпуАБцЧецЬмф╝БценуБМуГЮуГлуВ┐хЫ╜хЖЕуБоф╝БценуБихеСч┤ДуВТч╖ач╡РуБЧуАБуБ╛уБЯуБпф║ЛценуВТх▒ХщЦЛуБЩуВЛщЪЫуБлчЫ┤щЭвуБЧуБЖуВЛч┤Ыф║ЙуБлуБдуБДуБжуАБши┤шиЯуГ╗ф╗▓шгБуГ╗шк┐хБЬуБлуВИуВЛшзгц▒║уГбуВлуГЛуВ║уГауВТшзгшкмуБЧуБ╛уБЩуАВ
уБ╛уБЯуАБцЧецЬмхЫ╜хЖЕуБзуБоши┤шиЯхИдц▒║уВДф╗▓шгБхИдцЦнуБМуГЮуГлуВ┐хЫ╜хЖЕуБзуБДуБЛуБлхЯ╖шбМхПпшГ╜уБзуБВуВЛуБЛуБиуБДуБЖчВ╣уВВщЗНшжБуБзуБЩуАВуГЮуГлуВ┐уБпEUхКачЫЯхЫ╜уБзуБВуВКуАБщЭЮEUхКачЫЯхЫ╜уБзуБВуВЛцЧецЬмуБЛуВЙуБохИдц▒║уБлуБпуАБEUхЯЯхЖЕуБЛуВЙуБохИдц▒║уБиуБпчХ░уБкуВЛхПЦуВКцЙ▒уБДуБМщБйчФиуБХуВМуБ╛уБЩуАВ
уГЮуГлуВ┐хЕ▒хТМхЫ╜уБлуБКуБСуВЛши┤шиЯуГ╗ф╗▓шгБуГ╗шк┐хБЬуБлуВИуВЛч┤Ыф║Йшзгц▒║уГбуВлуГЛуВ║уГауБлуБдуБДуБжуАБшзгшкмуБЧуБ╛уБЩуАВ
уБкуБКуАБуГЮуГлуВ┐хЕ▒хТМхЫ╜уБохМЕцЛмчЪДуБкц│ХхИ╢х║жуБоцжВшжБуБпф╕ЛшиШшиШф║ЛуБлуБжуБ╛уБиуВБуБжуБДуБ╛уБЩуАВ
уБУуБошиШф║ЛуБочЫоцмб
уГЮуГлуВ┐уБошгБхИдцЙАуБоцзЛцИРуБичобш╜Дций
уГЮуГлуВ┐уБохП╕ц│Хх║ЬуБпуАБцЖ▓ц│ХшгБхИдцЙАя╝ИConstitutional Courtя╝ЙуАБцОзши┤щЩвя╝ИCourt of Appealя╝ЙуАБхИСф║ЛцОзши┤щЩвя╝ИCourt of Criminal Appealя╝ЙуАБхИСф║ЛшгБхИдцЙАя╝ИCriminal Courtя╝ЙуАБц░Сф║ЛшгБхИдцЙАя╝ИCivil Courtя╝ЙуБиуБДуБгуБЯф╕Кч┤ЪшгБхИдцЙАя╝ИSuperior Courtsя╝ЙуБиуАБц▓╗хоЙхИдф║ЛшгБхИдцЙАя╝ИCourt of Magistratesя╝ЙуБиуБДуБгуБЯф╕Лч┤ЪшгБхИдцЙАя╝ИInferior Courtsя╝ЙуБЛуВЙуБкуВЛщЪОх▒дцзЛщАауВТцЬЙуБЧуБжуБДуБ╛уБЩ уАВхХЖф║Лч┤Ыф║ЙуБпф╕АшИмчЪДуБлуГЮуГлуВ┐уБоц░Сф║ЛшгБхИдцЙАя╝ИCivil Courtsя╝ЙуБМчобш╜ДуБЧуБ╛уБЩуАВ
ц░Сф║ЛшгБхИдцЙАчммф╕Ахпйя╝ИFirst Hall of the Civil Courtя╝ЙуБпуАБхо╢цЧПщГия╝ИFamily Sectionя╝ЙуАБф╗╗цДПчобш╜ДщГия╝ИVoluntary Jurisdiction Sectionя╝ЙуАБхХЖф║ЛщГия╝ИCommercial Sectionя╝ЙуАБуБКуВИуБ│ф╕АшИмчобш╜ДщГия╝ИGeneral Jurisdiction Sectionя╝ЙуБо4уБдуБоуВ╗уВпуВ╖уГзуГ│уБлхИЖуБЛуВМуБжуБКуВКуАБц░Сф║ЛуБКуВИуБ│хХЖф║ЛуБошлЛц▒ВуВТцЙ▒уБЖф╕АшИмчЪДуБкчобш╜ДцийуВТцЬЙуБЧуБ╛уБЩуАВшлЛц▒ВщбНуБМтВм11,646.87уВТш╢ЕуБИуВЛхХЖф║ЛцбИф╗╢уБпуАБц░Сф║ЛшгБхИдцЙАчммф╕АхпйуБМчобш╜ДуБЧуБ╛уБЩуАВуБУуВМуБлхп╛уБЧуАБтВм11,646.87ф╗еф╕ЛуБошлЛц▒ВуБпф╕Лч┤ЪшгБхИдцЙАуБзуБВуВЛц▓╗хоЙхИдф║ЛшгБхИдцЙАуБМцЛЕх╜УуБЧуБ╛уБЩуАВуБХуВЙуБлуАБтВм3,494.06цЬкц║АуБох░СщбНшлЛц▒ВуБлуБдуБДуБжуБпуАБх░СщбНшлЛц▒ВхпйхИдцЙАя╝ИSmall Claims Tribunalя╝ЙуБиуБДуБЖчЙ╣хоЪуБохпйхИдцЙАуБМхИдцЦнуВТф╕ЛуБЧуБ╛уБЩуАВцЧецЬмуБлуБКуБСуВЛуАБхЬ░цЦ╣шгБхИдцЙАуГ╗ч░бцШУшгБхИдцЙАуГ╗х░СщбНши┤шиЯуАБуБлш┐СуБДцжВх┐╡уБзуБЩуАВ
уБкуБКуАБф╛ЛуБИуБ░уАБщЫЗчФищЦвф┐ВуБохХПщбМуВДф╕Нх╜УшзгщЫЗуБоф║ЛцбИуВТцЙ▒уБЖчФгценхпйхИдцЙАя╝ИIndustrial Tribunalя╝ЙуБкуБйуАБчЙ╣хоЪуБохХЖценчЪДцАзш│куБоч┤Ыф║ЙуВТшзгц▒║уБЩуВЛуБЯуВБуБлшинчлЛуБХуВМуБЯх░ВщЦАхпйхИдцЙАя╝Иspecialised tribunalsя╝ЙуВВхнШхЬиуБЧуБ╛уБЩуАВ
ши┤шиЯцЙЛч╢ЪуБохЯ║цЬм
уГЮуГлуВ┐уБоф╕Кч┤ЪшгБхИдцЙАуБлуБКуБСуВЛц░Сф║Лши┤шиЯуБпуАБщАЪх╕╕уАБчФ│шлЛшАЕуБлуВИуВЛхогшкУф╗ШчФ│члЛцЫ╕я╝Иsworn applicationя╝ЙуВТшгБхИдцЙАцЫ╕шиШх▒АуБлцПРхЗ║уБЩуВЛуБУуБиуБлуВИуБгуБжщЦЛхзЛуБХуВМуБ╛уБЩуАВф╕Лч┤ЪшгБхИдцЙАуБзуБпуАБхогшкУуБох┐ЕшжБуБМуБкуБДчФ│члЛцЫ╕уБзцЙЛч╢ЪуБНуВТщЦЛхзЛуБзуБНуБ╛уБЩуАВчФ│члЛцЫ╕уБпщБЕц╗ЮуБкуБПшвлхСКуБлщАБщБФуБХуВМуАБшгБхИдцЙАуБпщАБщБФцЧеуБЛуВЙ15цЧеф╗ещЩН30цЧеф╗ехЖЕуБохпйчРЖцЬЯцЧеуВТцМЗхоЪуБЧуБ╛уБЩуАВшвлхСКуБМхогшкУф╗ШчнФх╝БцЫ╕уВТцПРхЗ║уБЧуБкуБДха┤хРИуБпуАМcontumaciousя╝Иф╕НцЬНх╛Уя╝ЙуАНуБиуБ┐уБкуБХуВМуБ╛уБЩуАВ
цЫ╕щЭвуБлуВИуВЛф║ИхВЩцЙЛч╢ЪуБНуБох╛МуАБшгБхИдцЙАуБохпйчРЖуБМщА▓шбМуБЧуАБх╜Уф║ЛшАЕуБпши╝цЛауВТцПРхЗ║уБЧуАБши╝ф║║уБох░ЛхХПуБКуВИуБ│хПНхп╛х░ЛхХПуБМшбМуВПуВМуБ╛уБЩуАВуБУуВМуБпшгБхИдцЙАшЗкф╜УуБ╛уБЯуБпшгБхИдцЙАуБМф╗╗хС╜уБЧуБЯхП╕ц│ХшгЬхКйхоШуБохЙНуБзшбМуВПуВМуБ╛уБЩуАВуГЮуГлуВ┐уБошгБхИдцЙАуБКуВИуБ│хЙНш┐░уБохпйхИдцЙАуБлуБКуБСуВЛуБЩуБ╣уБжуБохХЖф║ЛцЙЛч╢ЪуБпхЕмщЦЛуБзхпйчРЖуБХуВМуАБф╕АшИмуБошк░уВВуБМхВНшБ┤уБЩуВЛуБУуБиуБМуБзуБНуБ╛уБЩ
уГЮуГлуВ┐уБошгБхИдцЙАуБпуАБф╕АшИмчЪДуБлщЭЮхК╣чОЗуБзуБВуВКуАБцЙЛч╢ЪуБНуБлщХ╖цЬЯщЦУуБощБЕх╗╢уБМф╕АшИмчЪДуБзуБВуВЛуБицМЗцСШуБХуВМуБжуБДуБ╛уБЩуАВуБУуБочК╢ц│БуБпуАБч┤Ыф║Йшзгц▒║уБощХ╖цЬЯхМЦуБиуБЭуВМуБлф╝┤уБЖш▓╗чФихвЧхКауБоуГкуВ╣уВпуВТф╝┤уБДуБ╛уБЩуАВуБЧуБЛуБЧуАБшлЛц▒ВщбНуБлх┐ЬуБШуБжчобш╜ДшгБхИдцЙАуБМч┤░хИЖхМЦуБХуВМуАБх░СщбНшлЛц▒ВхпйхИдцЙАуВДчФгценхпйхИдцЙАуБоуВИуБЖуБкх░ВщЦАхпйхИдцЙАуБМшинуБСуВЙуВМуБжуБДуВЛуБиуБДуБЖхБ┤щЭвуВВуБВуВКуБ╛уБЩуАВ
ф╗гцЫ┐чЪДч┤Ыф║Йшзгц▒║я╝ИADRя╝ЙуБощБ╕цКЮшВв
уГЮуГлуВ┐уБзуБпуАБши┤шиЯф╗ехдЦуБоч┤Ыф║Йшзгц▒║цЙЛцо╡уБиуБЧуБжуАБф╗▓шгБя╝ИArbitrationя╝ЙуБишк┐хБЬя╝ИMediationя╝ЙуБМц│ХчЪДуБлчв║члЛуБХуВМуБжуБКуВКуАБуБЭуБохИйчФиуБМцОихеиуБХуВМуБжуБДуБ╛уБЩуАВуБУуВМуВЙуБпуАБшгБхИдцЙАуБзуБоши┤шиЯуБицпФш╝ГуБЧуБжуАБуВИуВКш┐ЕщАЯуАБф╜ОуВ│уВ╣уГИуАБщЭЮхЕмх╝ПуАБуБЛуБдцйЯхпЖцАзуБощлШуБДшзгц▒║уВТхПпшГ╜уБлуБЩуВЛуБиуБДуБЖхИйчВ╣уБМуБВуВКуБ╛уБЩ уАВ
ф╗▓шгБя╝ИArbitrationя╝Й
уГЮуГлуВ┐уБлуБКуБСуВЛф╗▓шгБуБпуАБуГЮуГлуВ┐ф╗▓шгБц│Хя╝ИArbitration Act, Chapter 387 of the Laws of Maltaя╝ЙуБлуВИуБгуБжшжПхоЪуБХуВМуБжуБДуБ╛уБЩуАВуБУуБоц│Хх╛ЛуБлхЯ║уБеуБНуАБуГЮуГлуВ┐ф╗▓шгБуВ╗уГ│уВ┐уГ╝я╝ИMalta Arbitration Centre, MACя╝ЙуБМшинчлЛуБХуВМуАБхЫ╜хЖЕф╗▓шгБуБКуВИуБ│хЫ╜щЪЫхХЖф║Лф╗▓шгБуБоф┐ГщА▓уБищБЛхЦ╢уВТцЛЕуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВуГЮуГлуВ┐ф╗▓шгБц│ХуБпуАБхЫ╜щЪЫчЪДуБкф╗▓шгБуБоф╕╗шжБуБкцЮач╡ДуБ┐уБзуБВуВЛUNCITRALуГвуГЗуГлц│ХуВТчммф╕Аф╗Шх▒ЮцЫ╕уБиуБЧуБжч╡ДуБ┐ш╛╝уВУуБзуБКуВК уАБхдЦхЫ╜ф╗▓шгБхИдцЦнуБоцЙ┐шкНуБКуВИуБ│хЯ╖шбМуБлщЦвуБЩуВЛуГЛуГеуГ╝уГиуГ╝уВпцЭбч┤Дя╝И1958х╣┤я╝ЙуБоч╜▓хРНхЫ╜уБзуБЩуАВуБУуВМуБлуВИуВКуАБхЫ╜щЪЫчЪДуБкф╗▓шгБхИдцЦнуБоуГЮуГлуВ┐уБлуБКуБСуВЛхЯ╖шбМхПпшГ╜цАзуБМф┐Эши╝уБХуВМуБжуБДуБ╛уБЩуАВ
ф╗▓шгБхРИцДПуБпуАБуАМх╜Уф║ЛшАЕуБМуАБчЙ╣хоЪуБоц│ХчЪДщЦвф┐ВуБлщЦвуБЧуБжчФЯуБШуБЯуАБуБ╛уБЯуБпх░ЖцЭечФЯуБШуБЖуВЛуБЩуБ╣уБжуБоч┤Ыф║ЙуБ╛уБЯуБпчЙ╣хоЪуБоч┤Ыф║ЙуВТф╗▓шгБуБлф╗ШшиЧуБЩуВЛуБУуБиуБлхРИцДПуБЧуБЯуВВуБоуАНуБихоЪч╛йуБХуВМуБ╛уБЩуАВуБУуВМуБпуАБхеСч┤Дф╕нуБоф╗▓шгБцЭбщаЕуБох╜вх╝ПуВТуБиуВЛуБУуБиуВВуАБхИещАФуБохРИцДПуБох╜вх╝ПуВТуБиуВЛуБУуБиуВВхПпшГ╜уБзуБЩуАВф╗▓шгБцЙЛч╢ЪуБНуБощЦЛхзЛуБлуБпуАБщАЪх╕╕уАБх╜Уф║ЛшАЕхПМцЦ╣уБохРМцДПуБМх┐ЕшжБуБзуБЩуБМуАБуГЮуГлуВ┐ф╗▓шгБц│ХуБпуАБш╗╜х╛оуБкф║дщАЪф║ЛцХЕуВДуГЮуГ│уВ╖уГзуГ│уБоч┤Ыф║ЙуБкуБйуАБчЙ╣хоЪуБочК╢ц│Бф╕ЛуБзф╗▓шгБуБМч╛йхЛЩф╗ШуБСуВЙуВМуВЛха┤хРИуВВшжПхоЪуБЧуБжуБДуБ╛уБЩуАВ
уГЮуГлуВ┐ф╗▓шгБуВ╗уГ│уВ┐уГ╝уБлуВИуБгуБжчЩ╗щМ▓уБХуВМуБЯф╗▓шгБхИдцЦнуБпуАБхЯ╖шбМцийхОЯя╝Иexecutive titleя╝ЙуВТцзЛцИРуБЧуБ╛уБЩ уАВуБУуВМуБлуВИуВКуАБхЫ╜хЖЕхИдц▒║уБихРМцзШуБлхЯ╖шбМуБМхПпшГ╜уБиуБкуВКуБ╛уБЩуАВуБ╛уБЯуАБчЙ╣хоЪуБоцЭбч┤ДуБМщБйчФиуБХуВМуВЛхдЦхЫ╜ф╗▓шгБхИдцЦнуБпуАБуГЮуГлуВ┐ф╗▓шгБуВ╗уГ│уВ┐уГ╝уБлуВИуВЛчЩ╗щМ▓х╛МуАБуГЮуГлуВ┐уБошгБхИдцЙАуБлуВИуБгуБжхЫ╜хЖЕхИдцЦнуБихРМцзШуБлхЯ╖шбМуБХуВМуБ╛уБЩуАВф╗▓шгБхИдцЦнуБлхп╛уБЩуВЛф╕НцЬНчФ│члЛуБжуБоца╣цЛауБпуАБф╗▓шгБц│Хчмм70цЭбуБлшй│ч┤░уБлшжПхоЪуБХуВМуБжуБДуБ╛уБЩуАВуБУуВМуБлуБпуАБх╜Уф║ЛшАЕуБошбМчВ║шГ╜хКЫуБоцмахжВуАБф╕НщБйхИЗуБкщАЪчЯеуАБф╗▓шгБуБочпДхЫ▓уВТш╢ЕуБИуВЛф║ЛщаЕуБохИдцЦнуАБхРИцДПуБХуВМуБЯцЙЛч╢ЪуБНуБ╛уБЯуБпц│ХуБоф╕НщБ╡хоИуБкуБйуБМхРлуБ╛уВМуБ╛уБЩуАВуБ╛уБЯуАБхп╛ш▒бф║ЛщаЕуБМуГЮуГлуВ┐ц│ХуБоф╕ЛуБзф╗▓шгБхПпшГ╜уБзуБкуБДха┤хРИуВДуАБхИдцЦнуБМхЕмх║ПшЙпф┐ЧуБлхПНуБЩуВЛха┤хРИуВВуАБхИдцЦнуБохПЦуВКц╢ИуБЧуБМхПпшГ╜уБзуБЩуАВцЬАч╡ВчЪДуБкф╗▓шгБхИдцЦнуБлхп╛уБЧуБжуБпуАБц│Хх╛Лф╕КуБоф║ЙчВ╣я╝Иpoint of lawя╝ЙуБлуБдуБДуБжцОзши┤щЩвуБ╕уБоцОзши┤уБМшкНуВБуВЙуВМуВЛха┤хРИуБМуБВуВКуБ╛уБЩуАВ
шк┐хБЬя╝ИMediationя╝Й
уГЮуГлуВ┐уБлуБКуБСуВЛшк┐хБЬуБпуАБшк┐хБЬц│Хя╝ИMediation Act, Chapter 474 of the Laws of Maltaя╝ЙуБлуВИуБгуБжшжПхИ╢уБХуВМуБжуБДуБ╛уБЩуАВуГЮуГлуВ┐шк┐хБЬуВ╗уГ│уВ┐уГ╝я╝ИMalta Mediation Centreя╝ЙуБпуАБч┤Ыф║Йх╜Уф║ЛшАЕуБМшЗкчЩ║чЪДуБлуАБуБ╛уБЯуБпшгБхИдцЙАуВДф╗ЦуБошгБхоЪцйЯщЦвуБЛуВЙуБоф╗ШшиЧуБлуВИуБгуБжуАБшк┐хБЬуВТщАЪуБШуБжч┤Ыф║ЙуВТшзгц▒║уБЩуВЛуБЯуВБуБоуГХуВйуГ╝уГйуГауВТцПРф╛ЫуБЧуБжуБДуБ╛уБЩуАВ
шк┐хБЬуБпуАБф╕нчлЛчЪДуБзш│Зца╝уБоуБВуВЛхЕмх╣│уБкшк┐хБЬф║║я╝Иmediatorя╝ЙуБМуАБч┤Ыф║Йх╜Уф║ЛшАЕщЦУуБоф║дц╕ЙуВТф┐ГщА▓уБЧуАБшЗкчЩ║чЪДуБкшзгц▒║уВТцФпцП┤уБЩуВЛуГЧуГнуВ╗уВ╣уБзуБЩуАВшк┐хБЬф║║уБпшзгц▒║чнЦуВТх╝╖хИ╢уБЩуВЛцийщЩРуВТцМБуБЯуБЪуАБшгБхИдхоШуВДф╗▓шгБф║║уБиуБЧуБжшбМхЛХуБЩуВЛуБУуБиуБпуБВуВКуБ╛уБЫуВУуАВшзгц▒║уБпх╜Уф║ЛшАЕщЦУуБохРИцДПуБлуВИуБгуБжуБоуБ┐щБФцИРуБХуВМуБ╛уБЩуАВшк┐хБЬуБпуАБши┤шиЯуБлцпФуБ╣уБжш▓╗чФиуБМуБпуВЛуБЛуБлхоЙуБПуАБш┐ЕщАЯуБкуГЧуГнуВ╗уВ╣уБзуБЩуАВуБ╛уБЯуАБщЭЮхЕмх╝ПуБЛуБдцйЯхпЖцАзуБМщлШуБДуБиуБДуБЖчЙ╣х╛┤уБМуБВуВКуБ╛уБЩуАВшк┐хБЬф╕нуБлш┐░уБ╣уВЙуВМуБЯуБУуБиуВДцПРхЗ║уБХуВМуБЯцЦЗцЫ╕уБпуБЩуБ╣уБжцйЯхпЖцГЕха▒уБзуБВуВКуАБуБДуБЛуБкуВЛши┤шиЯцЙЛч╢ЪуБНуБлуБКуБДуБжуВВши╝цЛауБиуБЧуБжшкНуВБуВЙуВМуБ╛уБЫуВУуАВуБУуВМуБлуВИуВКуАБх╜Уф║ЛшАЕщЦУуБощЦвф┐ВцАзуБМч╢нцМБуБХуВМуВДуБЩуБПуАБчЙ╣уБлуГУуВ╕уГНуВ╣щЦвф┐ВуБоч╢Щч╢ЪуВТцЬЫуВАха┤хРИуБлцЬЙхК╣уБкцЙЛцо╡уБиуБкуВКуБ╛уБЩуАВшк┐хБЬуБоч╡РцЮЬуБиуБЧуБжч╖ач╡РуБХуВМуБЯхРИцДПуБпуАБхЯ╖шбМхПпшГ╜уБиуБкуВКуБ╛уБЩуАВ
хеСч┤ДцЫ╕уБлуБКуБСуВЛф╗▓шгБцЭбщаЕуБох┐ЕшжБцАз
уБУуБЖуБЧуБЯуВ╖уВ╣уГЖуГауБочФицДПуБХуВМуБжуБДуВЛуГЮуГлуВ┐уБлуБКуБДуБжуБпуАБхеСч┤ДуВТч╖ач╡РуБЩуВЛщЪЫуАБхеСч┤ДцЫ╕уБлуАМф╗▓шгБцЭбщаЕуАНуВТцШОчд║чЪДуБлхРлуВБуВЛуБУуБиуБпуАБч┤Ыф║ЙчЩ║чФЯцЩВуБоуГкуВ╣уВпуВТхдзх╣ЕуБлш╗╜ц╕ЫуБЩуВЛцИжчХечЪДцОкч╜оуБиуБкуВКх╛ЧуБ╛уБЩуАВуГЮуГлуВ┐уБошгБхИдцЙАуБощЭЮхК╣чОЗцАзуВТхЫЮщБ┐уБЧуАБуГЛуГеуГ╝уГиуГ╝уВпцЭбч┤ДуБлхЯ║уБеуБПхЫ╜щЪЫчЪДуБкхЯ╖шбМхПпшГ╜цАзуВТчв║ф┐ЭуБЩуВЛуБЯуВБуБзуБЩуАВшк┐хБЬуВВщЦвф┐ВцАзч╢нцМБуБошж│чВ╣уБЛуВЙцЬЙчФиуБзуБЩуБМуАБуБЭуБохРИцДПуБохЯ╖шбМхКЫуБлуБдуБДуБжуБпуАБцЬАч╡ВчЪДуБкхРИцДПхЖЕхо╣уВТц│ХчЪДцЛШцЭЯхКЫуБоуБВуВЛх╜вуБзцЦЗцЫ╕хМЦуБЩуВЛуБкуБйуАБх░ВщЦАхо╢уБоуВвуГЙуГРуВдуВ╣уВТх╛ЧуБжцЕОщЗНуБлщА▓уВБуВЛх┐ЕшжБуБМуБВуВКуБ╛уБЩуАВ
цЧецЬмф╝БценуБМуГЮуГлуВ┐ф╝БценуБихеСч┤ДуБЩуВЛщЪЫуБочХЩцДПчВ╣
уГЮуГлуВ┐ф╝БценуБиуБохЫ╜щЪЫхеСч┤ДуБлуБКуБДуБжуБпуАБч┤Ыф║ЙчЩ║чФЯцЩВуБоуГкуВ╣уВпуВТцЬАх░ПщЩРуБлцКСуБИуВЛуБЯуВБуАБф║ЛхЙНуБоц║ЦхВЩуБихеСч┤ДхЖЕхо╣уБоцЕОщЗНуБкцдЬшиОуБМф╕НхПпцмауБзуБЩуАВчЙ╣уБлуАБцЧецЬмуБиуГЮуГлуВ┐уБоц│ХхИ╢х║жуБощБХуБДуВТчРЖшзгуБЧуАБщБйхИЗуБкцЭбщаЕуВТхеСч┤ДуБлчЫЫуВКш╛╝уВАуБУуБиуБМщЗНшжБуБиуБкуВКуБ╛уБЩуАВ
ц║ЦцЛац│ХуБишгБхИдчобш╜ДуБощБ╕цКЮ
хЫ╜щЪЫхеСч┤ДуБлуБКуБСуВЛф╕АшИмшлЦуБзуБпуБВуВКуБ╛уБЩуБМуАБх╜Уф║ЛшАЕуБпхеСч┤ДуБоц║ЦцЛац│Хя╝Иgoverning lawя╝ЙуБКуВИуБ│ч┤Ыф║Йшзгц▒║уБошгБхИдчобш╜Дя╝Иjurisdictionя╝ЙуБ╛уБЯуБпф╗▓шгБхЬ░я╝Иarbitral seatя╝ЙуВТшЗкчФ▒уБлщБ╕цКЮуБЩуВЛуБУуБиуБМф╕АшИмчЪДуБлшкНуВБуВЙуВМуБжуБДуБ╛уБЩуАВуБУуБоцШОчд║чЪДуБкхРИцДПя╝Иexpress choice of court agreement or express jurisdiction clauseя╝ЙуБпуАБч┤Ыф║ЙчЩ║чФЯцЩВуБоц│ХчЪДф║Иц╕мхПпшГ╜цАзуВТхдзх╣ЕуБлщлШуВБуВЛуБЯуВБуАБце╡уВБуБжщЗНшжБуБзуБЩуАВ
шгБхИдчобш╜ДцЭбщаЕуБлуБпуАБчЙ╣хоЪуБоц│ХхЯЯуБошгБхИдцЙАуБоуБ┐уБМч┤Ыф║ЙуВТцЙ▒уБЖуАМх░Вх▒ЮчЪДя╝Иexclusiveя╝ЙуАНуАБчЙ╣хоЪуБошгБхИдцЙАуБМчобш╜ДцийуВТцМБуБдуБУуБиуВТшкНуВБуБдуБдф╗ЦуБошгБхИдцЙАуВВчобш╜ДцийуВТцМБуБдхПпшГ╜цАзуВТшкНуВБуВЛуАМщЭЮх░Вх▒ЮчЪДя╝Иnon-exclusiveя╝ЙуАНуАБуБЭуБЧуБжф╕АцЦ╣уБох╜Уф║ЛшАЕуБоуБ┐уБМчЙ╣хоЪуБоц│ХхЯЯуБзцПРши┤уВТхИ╢щЩРуБХуВМуВЛуАМщЭЮхп╛чз░чЪДя╝Иasymmetricя╝ЙуАНуБ╛уБЯуБпуАМчЙЗхЛЩчЪДя╝Иone-sided/unilateralя╝ЙуАНуБкуВВуБоуБМуБВуВКуБ╛уБЩ уАВц║ЦцЛац│ХуБишгБхИдчобш╜ДуБМчХ░уБкуВЛха┤хРИуАБчобш╜ДшгБхИдцЙАуБМхдЦхЫ╜ц│ХуВТщБйчФиуБЩуВЛуБЯуВБуБлх░ВщЦАхо╢уБоши╝цЛауВТх┐ЕшжБуБиуБЧуАБши┤шиЯш▓╗чФиуБМхвЧхКауБЩуВЛхПпшГ╜цАзуБМуБВуВЛуБЯуВБуАБщАЪх╕╕уБпф╕бшАЕуВТф╕АшЗ┤уБХуБЫуВЛуБоуБМцЬЫуБ╛уБЧуБДуБиуБХуВМуБ╛уБЩуАВ
хеСч┤Дч╖ач╡РхЙНуБоуГЗуГеуГ╝уГЗуГкуВ╕уВзуГ│уВ╣
уГЮуГлуВ┐ф╝БценуБиуБохПЦх╝ХуВТшбМуБЖщЪЫуБлуБпуАБчЫ╕цЙЛцЦ╣уБоф╝БценчЩ╗щМ▓цГЕха▒я╝Иcorporate registration detailsя╝ЙуВТцдЬши╝уБЩуВЛуБУуБиуБМце╡уВБуБжщЗНшжБуБзуБЩ уАВуБУуВМуБлуБпуАБф╝Ъчд╛уБоцнгх╝ПхРНчз░уАБцЬмх║ЧцЙАхЬихЬ░уАБф╗гшбишАЕуБоц░ПхРНуБиф╜ПцЙАуБкуБйуБощЗНшжБуБкцГЕха▒уБМхРлуБ╛уВМуБ╛уБЩ уАВф╝БценчЩ╗щМ▓ч░┐уБпф╕АшИмуБлхЕмщЦЛуБХуВМуБжуБКуВКуАБц│ХхЛЩх▒Ая╝ИLegal Affairs Bureauя╝ЙуВТщАЪуБШуБжши╝цШОцЫ╕уВТхПЦх╛ЧуБзуБНуБ╛уБЩ уАВуБУуБочв║шкНуБпуАБхПЦх╝ХчЫ╕цЙЛуБМцнгх╜УуБкц│Хф║║уБзуБВуВЛуБУуБиуВТф┐Эши╝уБЧуАБцЮ╢чй║уБочЫ╕цЙЛцЦ╣уБиуБохПЦх╝ХуГкуВ╣уВпуВТцОТщЩдуБЩуВЛуБЯуВБуБлф╕НхПпцмауБзуБЩуАВ
цЧецЬмхЫ╜хЖЕуБзуБохИдц▒║уБоуГЮуГлуВ┐уБлуБКуБСуВЛхЯ╖шбМхПпшГ╜цАз
цЧецЬмф╝БценуБлуБиуБгуБжуАБуГЮуГлуВ┐хЫ╜хЖЕуБоф╝БценуБиуБощЦУуБзч┤Ыф║ЙуБМчЩ║чФЯуБЧуАБцЧецЬмхЫ╜хЖЕуБзхИдц▒║уВДф╗▓шгБхИдцЦнуВТх╛ЧуБЯха┤хРИуАБуБЭуВМуБМуГЮуГлуВ┐хЫ╜хЖЕуБзхЯ╖шбМхПпшГ╜уБзуБВуВЛуБЛхРжуБЛуБпце╡уВБуБжщЗНшжБуБкхХПщбМуБзуБЩуАВуБУуБохЯ╖шбМхПпшГ╜цАзуБпуАБхЫ╜щЪЫчЪДуБкцЭбч┤ДуБоцЬЙчДбуАБуБКуВИуБ│хРДхЫ╜уБохЫ╜хЖЕц│ХуБлуВИуБгуБжхоЪуБ╛уВКуБ╛уБЩуАВ
хдЦхЫ╜хИдц▒║уБоцЙ┐шкНуБихЯ╖шбМуБоц│ХчЪДцЮач╡ДуБ┐
уГЮуГлуВ┐уБлуБКуБСуВЛхдЦхЫ╜хИдц▒║уБоцЙ┐шкНуБКуВИуБ│хЯ╖шбМуБпуАБф╕╗уБлч╡Дч╣ФуГ╗ц░Сф║Лши┤шиЯц│Хя╝ИCode of Organisation and Civil Procedure, Chapter 12 of the Laws of Malta, ф╗еф╕ЛуАМCOCPуАНя╝ЙуБоArt. 825Aф╗ещЩНуБлуВИуБгуБжшжПхоЪуБХуВМуБжуБДуБ╛уБЩ уАВуБУуВМуВЙуБошжПхоЪуБпуАБEUшжПхЙЗуБочпДхЫ▓хдЦуБоф║ЛщаЕуАБуБ╛уБЯуБпEUшжПхЙЗуБичЯЫчЫ╛уБЧуБкуБДха┤хРИуБлщБйчФиуБХуВМуБ╛уБЩуАВ
уГЮуГлуВ┐уБпEUхКачЫЯхЫ╜уБзуБВуВЛуБЯуВБуАБф╗ЦуБоEUхКачЫЯхЫ╜уБошгБхИдцЙАуБлуВИуБгуБжф╕ЛуБХуВМуБЯхИдц▒║уБпуАБEUшжПхЙЗя╝ИчЙ╣уБлц░Сф║ЛхПКуБ│хХЖф║ЛуБлщЦвуБЩуВЛшгБхИдчобш╜ДцийуБоцЙ┐шкНхПКуБ│хЯ╖шбМуБлщЦвуБЩуВЛшжПхЙЗя╝ИEUя╝ЙNo 1215/2012уАБщАЪчз░уАМуГЦуГкуГеуГГуВ╗уГлIшжПхЙЗя╝ИцФ╣цнгя╝ЙуАНя╝ЙуБлхЯ║уБеуБНуАБхЯ╖шбМхогшиАя╝Иexequaturя╝ЙуБох┐ЕшжБуБкуБПуГЮуГлуВ┐уБзцЙ┐шкНуГ╗хЯ╖шбМуБХуВМуБ╛уБЩ уАВуБЧуБЛуБЧуАБцЧецЬмуБпEUхКачЫЯхЫ╜уБзуБпуБкуБДуБЯуВБуАБцЧецЬмхЫ╜хЖЕуБошгБхИдцЙАуБлуВИуБгуБжф╕ЛуБХуВМуБЯхИдц▒║уБоуГЮуГлуВ┐уБлуБКуБСуВЛхЯ╖шбМуБпуАБCOCPуБоф╕АшИмшжПхоЪуБлцЬНуБЧуБ╛уБЩуАВCOCP Art. 826уБлхЯ║уБеуБНуАБхдЦхЫ╜хИдц▒║уБМуГЮуГлуВ┐уБзхЯ╖шбМуБХуВМуВЛуБЯуВБуБлуБпуАБф╗еф╕ЛуБошжБф╗╢уВТц║АуБЯуБЩх┐ЕшжБуБМуБВуВКуБ╛уБЩуАВ
- х╜Ушй▓хИдц▒║уБМхОЯхИдц▒║хЫ╜уБоц│Хх╛ЛуБлх╛УуБгуБжцЧвхИдхКЫя╝Иres judicataя╝ЙуВТцЬЙуБЧуАБцОзши┤уБохп╛ш▒буБиуБкуВЙуБкуБДуБУуБи
- х╜Ушй▓хИдц▒║уБМуГЮуГлуВ┐хЫ╜хдЦуБочобш╜ДцийуВТцЬЙуБЩуВЛшгБхИдцЙАуБлуВИуБгуБжф╕ЛуБХуВМуБЯуВВуБоуБзуБВуВЛуБУуБи
уБУуВМуВЙуБошжБф╗╢уВТц║АуБЯуБЧуБЯф╕КуБзуАБх╜Ушй▓хИдц▒║уБоцЙ┐шкНуБихЯ╖шбМуВТц▒ВуВБуВЛчФ│члЛуБжуВТуГЮуГлуВ┐уБошгБхИдцЙАуБлцПРхЗ║уБЩуВЛх┐ЕшжБуБМуБВуВКуБ╛уБЩ уАВчФ│члЛуБжуБлуБпуАБхИдц▒║уБошкНши╝шмДцЬмуБиуАБшЛ▒шкЮуБ╛уБЯуБпуГЮуГлуВ┐шкЮуБ╕уБошкНши╝ч┐╗ши│уБМц╖╗ф╗ШуБХуВМуБкуБСуВМуБ░уБкуВКуБ╛уБЫуВУуАВ
COCP Art. 811уБКуВИуБ│Art. 827уБпуАБхдЦхЫ╜хИдц▒║уБоцЙ┐шкНуБ╛уБЯуБпхЯ╖шбМуБМцЛТхРжуБХуВМуВЛхПпшГ╜цАзуБоуБВуВЛшдЗцХ░уБоф║ЛчФ▒уВТхоЪуВБуБжуБДуБ╛уБЩуАВф╕╗уБкцЛТхРжф║ЛчФ▒уБлуБпф╗еф╕ЛуБМхРлуБ╛уВМуБ╛уБЩуАВ
- уБДуБЪуВМуБЛуБох╜Уф║ЛшАЕуБлуВИуВЛшйРцм║уБлуВИуБгуБжхИдц▒║уБМхПЦх╛ЧуБХуВМуБЯха┤хРИ
- цХЧши┤уБЧуБЯшвлхСКуБлхп╛уБЧуБжх┐ЕшжБуБкхПмхЦЪчК╢уБ╛уБЯуБпши┤шиЯщЦЛхзЛхС╜ф╗дуБМщБйхИЗуБлщАБщБФуБХуВМуБкуБЛуБгуБЯха┤хРИя╝ИуБЯуБауБЧуАБшвлхСКуБМшгБхИдуБлхЗ║х╗╖уБЧуБкуБЛуБгуБЯха┤хРИуБлщЩРуВЛя╝Й
- хИдц▒║уВТф╕ЛуБЧуБЯшгБхИдцЙАуБМчобш╜ДцийуВТцЬЙуБЧуБжуБДуБкуБЛуБгуБЯха┤хРИя╝ИуБЯуБауБЧуАБх╜Ушй▓чХ░шн░уБМцПРш╡╖уБХуВМуАБхИдцЦнуБХуВМуБжуБДуБкуБДха┤хРИуБлщЩРуВЛя╝Й
- хИдц▒║уБМшкдуБгуБЯц│ХуБощБйчФиуВТхРлуВУуБзуБДуВЛха┤хРИ
- хИдц▒║уБМуАМextra petitaуАНя╝ИшлЛц▒ВуБочпДхЫ▓уВТш╢ЕуБИуВЛя╝ЙуБ╛уБЯуБпуАМultra petitaуАНя╝ИцийщЩРуВТш╢ЕуБИуВЛя╝ЙуБзуБВуВЛха┤хРИ
- хИдц▒║уБМуГЮуГлуВ┐уБохЕмх║ПшЙпф┐Чя╝Иpublic policyя╝ЙуБ╛уБЯуБпхЫ╜хЖЕхЕмц│ХуБлхПНуБЩуВЛшжПхоЪуВТхРлуВУуБзуБДуВЛха┤хРИ
уБУуБУуБзчЙ╣уБлхХПщбМуБкуБоуБМуАБуАМцХЧши┤уБЧуБЯшвлхСКуБлхп╛уБЧуБжх┐ЕшжБуБкхПмхЦЪчК╢уБ╛уБЯуБпши┤шиЯщЦЛхзЛхС╜ф╗дуБМщБйхИЗуБлщАБщБФуБХуВМуБкуБЛуБгуБЯха┤хРИуАНуБиуБДуБЖцЭбф╗╢уБзуБЩуАВцЧецЬмуБоф╝Ъчд╛уБМуГЮуГлуВ┐уБоф╝Ъчд╛уБлхп╛уБЧуАБцЧецЬмхЫ╜хЖЕуБошгБхИдцЙАуБзши┤шиЯуВТцПРш╡╖уБЩуВЛха┤хРИуАБуБЭуБоши┤чК╢чнЙуВТуАБуБйуБоуВИуБЖуБлуГЮуГлуВ┐хЫ╜хЖЕуБоф╝БценуБлщАБщБФуБЩуВМуБ░шЙпуБДуБЛуАБуБиуБДуБЖчВ╣уБМхХПщбМуБиуБкуВЛуБЛуВЙуБзуБЩуАВ
уГПуГ╝уВ░щАБщБФцЭбч┤ДуБлхЯ║уБеуБПхЫ╜щЪЫщАБщБФуБоф╗Хч╡ДуБ┐
цЧецЬмуБиуГЮуГлуВ┐хЕ▒хТМхЫ╜уБпуАБуБДуБЪуВМуВВуАМц░Сф║ЛхПИуБпхХЖф║ЛуБлщЦвуБЩуВЛшгБхИдф╕КхПКуБ│шгБхИдхдЦуБоцЦЗцЫ╕уБохдЦхЫ╜уБлуБКуБСуВЛщАБщБФуБлщЦвуБЩуВЛцЭбч┤ДуАНя╝ИуГПуГ╝уВ░щАБщБФцЭбч┤Дя╝ЙуБоч╖ач┤ДхЫ╜уБзуБЩуАВцЧецЬмуБп1970х╣┤7цЬИ27цЧеуБлуАБуГЮуГлуВ┐уБп2011х╣┤10цЬИ1цЧеуБлуБУуБоцЭбч┤ДуБМчЩ║хК╣уБЧуБжуБДуБ╛уБЩуАВцЧецЬмуБоф╝Ъчд╛уБМцЧецЬмуБошгБхИдцЙАуБзуГЮуГлуВ┐уБоф╝Ъчд╛уБлхп╛уБЧуБжши┤шиЯуВТш╡╖уБУуБЧуБЯха┤хРИуАБцЧецЬмуБошгБхИдцЙАуБЛуВЙуГЮуГлуВ┐уБоф╝Ъчд╛уБ╕уБощАБщБФуБпуАБуБУуБоуГПуГ╝уВ░щАБщБФцЭбч┤ДуБошжПхоЪуБлх╛УуБгуБжшбМуВПуВМуВЛуБУуБиуБлуБкуВКуБ╛уБЩуАВ
уГПуГ╝уВ░щАБщБФцЭбч┤ДуБлхЯ║уБеуБПщАБщБФуБпуАБф╗еф╕ЛуБоцЙЛщаЖуБзщА▓уВБуВЙуВМуВЛуБоуБМф╕АшИмчЪДуБзуБЩуАВ
- ф╕нхдох╜Ух▒АуБ╕уБощАБф╗Ш: цЧецЬмуБошгБхИдцЙАя╝ИуБ╛уБЯуБпщАБщБФуВТшбМуБЖцийщЩРуБоуБВуВЛхП╕ц│ХхоШя╝ЙуБпуАБщАБщБФуВТц▒ВуВБуВЛцЦЗцЫ╕я╝Иши┤чК╢уАБхПмхЦЪчК╢уБкуБйя╝ЙуБиуАБщАБщБФшлЛц▒ВцЫ╕уАБши┤шиЯуБоцжВшжБцЫ╕уБиуБДуБгуБЯциЩц║ЦхМЦуБХуВМуБЯцЫ╕х╝ПуВТуАБуГЮуГлуВ┐уБоф╕нхдох╜Ух▒Ая╝ИCentral Authorityя╝ЙуБлчЫ┤цОещАБф╗ШуБЧуБ╛уБЩуАВуБкуБКуАБщАБщБФуБХуВМуВЛуБЩуБ╣уБжуБоцЦЗцЫ╕уБпуАБцЧецЬмшкЮуБЛуВЙуГЮуГлуВ┐шкЮуБ╛уБЯуБпшЛ▒шкЮуБ╕уБохоМхЕиуБкч┐╗ши│уБМц▒ВуВБуВЙуВМуБ╛уБЩуАВ
- уГЮуГлуВ┐хЫ╜хЖЕуБзуБощАБщБФ: уГЮуГлуВ┐уБоф╕нхдох╜Ух▒АуБпуАБуБЭуБоцЦЗцЫ╕уВТхПЧщаШуБЧуБЯх╛МуАБуГЮуГлуВ┐хЫ╜хЖЕуБоц│ХуБзши▒хо╣уБХуВМуВЛцЦ╣ц│ХуБзщАБщБФуВТцЙЛщЕНуБЧуБ╛уБЩуАВщАЪх╕╕уАБуБУуВМуБпчП╛хЬ░уБошгБхИдцЙАуБохЯ╖шбМхоШя╝Иbailiffя╝ЙуВТщАЪуБШуБжшбМуВПуВМуБ╛уБЩуАВ
- щАБщБФши╝цШОцЫ╕уБош┐ФщАБ: щАБщБФуБМхоМф║ЖуБЩуВЛуБиуАБуГЮуГлуВ┐уБоф╕нхдох╜Ух▒АуБпщАБщБФши╝цШОцЫ╕уВТф╜ЬцИРуБЧуАБщАБщБФуВТшлЛц▒ВуБЧуБЯцЧецЬмуБохП╕ц│ХхоШуБлш┐ФщАБуБЧуБ╛уБЩуАВ
уАМщБйхИЗуБлщАБщБФуБХуВМуБЯуБУуБиуАНуБиуБДуБЖшжБф╗╢уБпуАБшвлхСКуБМши┤шиЯуБохнШхЬиуВТчв║хоЯуБлчЯеуВКуАБщШ▓х╛буБоцйЯф╝ЪуВТф╕ОуБИуВЙуВМуБЯуБУуБиуВТф┐Эши╝уБЩуВЛуБЯуВБуБоуВВуБоуБзуБЩуАВхЫ╜щЪЫчЪДуБкхИдц▒║уБоцЙ┐шкНуГ╗хЯ╖шбМуБлуБКуБДуБжуАБшвлхСКуБоуАМуГЗуГеуГ╝уГ╗уГЧуГнуВ╗уВ╣я╝ИщБйцнгцЙЛч╢Ъя╝ЙуБоцийхИйуАНуВДуАМхЕмцнгуБкшгБхИдуВТхПЧуБСуВЛцийхИйуАНуБМх░КщЗНуБХуВМуБЯуБЛуБйуБЖуБЛуБМхО│уБЧуБПхпйцЯ╗уБХуВМуБ╛уБЩуАВ
уБЧуБЯуБМуБгуБжуАБшвлхСКуБоцЙАхЬиуБМф╕НцШОуБкха┤хРИуБкуБйуБлчФиуБДуВЙуВМуВЛхЕмчд║щАБщБФя╝Иservice by publicationя╝ЙуБоуВИуБЖуБкуАБхоЯщЪЫуБлшвлхСКуБлцЦЗцЫ╕уБМцЙЛц╕буБХуВМуБкуБДщАБщБФцЦ╣ц│ХуБзуБпуАБуГЮуГлуВ┐уБзуБохИдц▒║цЙ┐шкНуБМцЛТхРжуБХуВМуВЛхПпшГ╜цАзуБпуАБщлШуБДуВВуБоуБишиАуБИуБ╛уБЩуАВуБУуБоуВИуБЖуБкщАБщБФцЦ╣ц│ХуБпуАБшвлхСКуБМхоЯщЪЫуБлши┤шиЯуБохнШхЬиуВТчЯеуВЛцйЯф╝ЪуБМце╡уВБуБжщЩРхоЪчЪДуБзуБВуВЛуБЯуВБуАБхЫ╜щЪЫчЪДуБкцЦЗшДИуБзуБпуАМщБйхИЗуБкщАБщБФуАНуБиуБпуБ┐уБкуБХуВМуБЪуАБшвлхСКуБощШ▓х╛буБоцийхИйуБМф╛╡хо│уБХуВМуБЯуБихИдцЦнуБХуВМуВЛуГкуВ╣уВпуБМуБВуВЛуБЯуВБуБзуБЩуАВ
уГЮуГлуВ┐хЫ╜хЖЕуБохИдц▒║уБоцЧецЬмуБлуБКуБСуВЛхЯ╖шбМхПпшГ╜цАз
уБкуБКуАБх┐╡уБоуБЯуВБуАБщАЖуБоуГСуВ┐уГ╝уГ│уБлуБдуБДуБжшзгшкмуБЩуВЛуБиуАБцЧецЬмуБлуБКуБДуБжуБпуАБхдЦхЫ╜хИдц▒║уБоцЙ┐шкНуБпц░Сф║Лши┤шиЯц│Хя╝Их╣│цИР8х╣┤ц│Хх╛Лчмм109хП╖я╝Йчмм118цЭбуАБхЯ╖шбМуБпц░Сф║ЛхЯ╖шбМц│Хя╝ИцШнхТМ54х╣┤ц│Хх╛Лчмм4хП╖я╝Йчмм24цЭбуБлуВИуБгуБжшжПхоЪуБХуВМуБжуБДуБ╛уБЩуАВхдЦхЫ╜хИдц▒║уБМцЬАч╡ВчЪДуБЛуБдчв║хоЪчЪДуБкуВВуБоуБзуБВуВЛха┤хРИуАБф╗еф╕ЛуБоцЭбф╗╢уВТц║АуБЯуБЫуБ░хК╣хКЫуВТцЬЙуБЧуБ╛уБЩуАВ
- хдЦхЫ╜шгБхИдцЙАуБочобш╜ДцийуБМуАБцЧецЬмуБоц│Хф╗дуАБцЭбч┤ДуБ╛уБЯуБпцЕгч┐ТуБлуВИуВКхРжхоЪуБХуВМуБкуБДуБУуБи
- цХЧши┤уБЧуБЯшвлхСКуБМуАБши┤шиЯуБощЦЛхзЛуБлх┐ЕшжБуБкхПмхЦЪчК╢уБ╛уБЯуБпхС╜ф╗дуВТщБйхИЗуБлщАБщБФуБХуВМуБЯуБУуБия╝ИхЕмчд║щАБщБФуБ╛уБЯуБпуБУуВМуБлщбЮуБЩуВЛщАБщБФуВТщЩдуБПя╝ЙуАБуБ╛уБЯуБпщАБщБФуВТхПЧуБСуБЪуБлх┐Ьши┤уБЧуБЯуБУуБи
- хИдц▒║уБохЖЕхо╣уБКуВИуБ│ши┤шиЯцЙЛч╢ЪуБНуБМуАБцЧецЬмуБохЕмуБочзйх║ПуБ╛уБЯуБпхЦДшЙпуБощвиф┐ЧуБлхПНуБЧуБкуБДуБУуБи
- чЫ╕ф║Тф┐Эши╝уБМуБВуВЛуБУуБи
цЧецЬмуБпуАБуГЮуГлуВ┐уБиуБощЦУуБзхИдц▒║уБочЫ╕ф║ТцЙ┐шкНуГ╗хЯ╖шбМуБлщЦвуБЩуВЛф║МхЫ╜щЦУцЭбч┤ДуВТч╖ач╡РуБЧуБжуБДуБ╛уБЫуВУуАВуБЧуБЯуБМуБгуБжуАБцЧецЬмуБзуГЮуГлуВ┐уБохИдц▒║уВТхЯ╖шбМуБЧуВИуБЖуБиуБЩуВЛха┤хРИуАБф╕КшиШц░Сф║Лши┤шиЯц│Хчмм118цЭбчмм4хП╖уБоуАМчЫ╕ф║Тф┐Эши╝уАНуБошжБф╗╢уБМуАБхдзуБНуБкхХПщбМуБиуБкуВКуБ╛уБЩуАВ
цЧецЬмуГ╗уГЮуГлуВ┐щЦУуБлуБКуБСуВЛхИдц▒║хЯ╖шбМуБошдЗщЫСцАзуБиф╗▓шгБуБохДкф╜НцАз
цЧецЬмуБиуГЮуГлуВ┐уБощЦУуБлуБпуАБшгБхИдцЙАхИдц▒║уБочЫ╕ф║ТхЯ╖шбМуВТчЫ┤цОешжПхоЪуБЩуВЛф║МхЫ╜щЦУцЭбч┤ДуБМхнШхЬиуБЧуБкуБДуБЯуВБуАБхИдц▒║уБохЯ╖шбМуБпхПМцЦ╣уБохЫ╜хЖЕц│ХуБлхЯ║уБеуБПшдЗщЫСуБкуГЧуГнуВ╗уВ╣уБиуБкуВКуБ╛уБЩуАВчЙ╣уБлуАБцЧецЬмхБ┤уБМуГЮуГлуВ┐хИдц▒║уВТхЯ╖шбМуБЩуВЛщЪЫуБлуАМчЫ╕ф║Тф┐Эши╝уАНуБочлЛши╝уБМх┐ЕшжБуБиуБкуВЛчВ╣уБпуАБхдзуБНуБкуГПуГ╝уГЙуГлуБзуБЩуАВуГЮуГлуВ┐хБ┤уБМцЧецЬмхИдц▒║уВТхЯ╖шбМуБЩуВЛщЪЫуВВуАБCOCPуБоцзШуАЕуБкцЛТхРжф║ЛчФ▒уБлчЫ┤щЭвуБЩуВЛхПпшГ╜цАзуБМуБВуВКуБ╛уБЩуАВуБУуБошдЗщЫСуБХуБиф╕Нчв║хоЯцАзуБпуАБши┤шиЯуВТщБ╕цКЮуБЩуВЛщЪЫуБохдзуБНуБкуГкуВ╣уВпуБиуБкуВКуБ╛уБЩуАВ
уБУуВМуБлхп╛уБЧуАБф╗▓шгБхИдцЦнуБпуАБуГЮуГлуВ┐уБМуГЛуГеуГ╝уГиуГ╝уВпцЭбч┤ДуБоч╜▓хРНхЫ╜уБзуБВуВЛуБЯуВБуАБцЧецЬмуБзх╛ЧуВЙуВМуБЯф╗▓шгБхИдцЦнуВВуГЮуГлуВ┐уБзцпФш╝ГчЪДхо╣цШУуБлхЯ╖шбМхПпшГ╜уБзуБВуВЛуБиуБДуБЖцШОчв║уБкхДкф╜НцАзуВТцМБуБдуБУуБиуБлуБкуВКуБ╛уБЩуАВуБЧуБЯуБМуБгуБжуАБцЧецЬмф╝БценуБМуГЮуГлуВ┐ф╝БценуБиуБохЫ╜щЪЫхеСч┤ДуВТч╖ач╡РуБЩуВЛщЪЫуБлуБпуАБч┤Ыф║Йшзгц▒║цЭбщаЕуБиуБЧуБжуАМф╗▓шгБхРИцДПуАНуВТхДкхЕИчЪДуБлщБ╕цКЮуБЩуВЛуБУуБиуБМуАБх░ЖцЭечЪДуБкхЯ╖шбМуГкуВ╣уВпуВТхдзх╣ЕуБлш╗╜ц╕ЫуБЩуВЛцЬАуВВш│вцШОуБкцИжчХеуБзуБВуВЛуБишиАуБИуБ╛уБЩуАВ
уБ╛уБиуВБ
уГЮуГлуВ┐хЕ▒хТМхЫ╜уБиуБоуГУуВ╕уГНуВ╣уБпуАБуБЭуБохЬ░чРЖчЪДхДкф╜НцАзуБиEUхКачЫЯхЫ╜уБиуБЧуБжуБохоЙхоЪцАзуБЛуВЙуАБцЧецЬмф╝БценуБлуБиуБгуБжхдзуБНуБкцйЯф╝ЪуВТцПРф╛ЫуБЧуБ╛уБЩуАВуБЧуБЛуБЧуАБхЫ╜щЪЫхПЦх╝ХуБлф╝┤уБЖч┤Ыф║ЙуГкуВ╣уВпуВТхК╣цЮЬчЪДуБлчобчРЖуБЩуВЛуБЯуВБуБлуБпуАБуГЮуГлуВ┐уБоц│ХчЪДцЮач╡ДуБ┐чРЖшзгуБЩуВЛуБУуБиуБМф╕НхПпцмауБзуБЩуАВуГЮуГлуВ┐уБохП╕ц│ХхИ╢х║жуБпуАБши┤шиЯуБощХ╖цЬЯхМЦуБиуБДуБЖшк▓щбМуВТцК▒уБИуВЛф╕АцЦ╣уБзуАБшлЛц▒ВщбНуБлх┐ЬуБШуБЯх░ВщЦАчЪДуБкшгБхИдцЙАуВДуАБф╗▓шгБуГ╗шк┐хБЬуБиуБДуБгуБЯф╗гцЫ┐чЪДч┤Ыф║Йшзгц▒║я╝ИADRя╝ЙцЙЛцо╡уБМхЕЕхоЯуБЧуБжуБДуБ╛уБЩуАВчЙ╣уБлф╗▓шгБуБпуАБуГЛуГеуГ╝уГиуГ╝уВпцЭбч┤ДуБлхЯ║уБеуБПхЫ╜щЪЫчЪДуБкхЯ╖шбМхПпшГ╜цАзуБМчв║ф┐ЭуБХуВМуБжуБДуВЛчВ╣уБзуАБши┤шиЯуВИуВКуВВцЬЙхИйуБкщБ╕цКЮшВвуБиуБкуВКуБ╛уБЩуАВ
щЦвщАгхПЦцЙ▒хИЖщЗОя╝ЪхЫ╜щЪЫц│ХхЛЩуГ╗уГЮуГлуВ┐хЕ▒хТМхЫ╜
уВлуГЖуВ┤уГкуГ╝: ITуГ╗уГЩуГ│уГБуГгуГ╝уБоф╝Бценц│ХхЛЩ
уВ┐уВ░: уГЮуГлуВ┐хЕ▒хТМхЫ╜ц╡╖хдЦф║Лцен