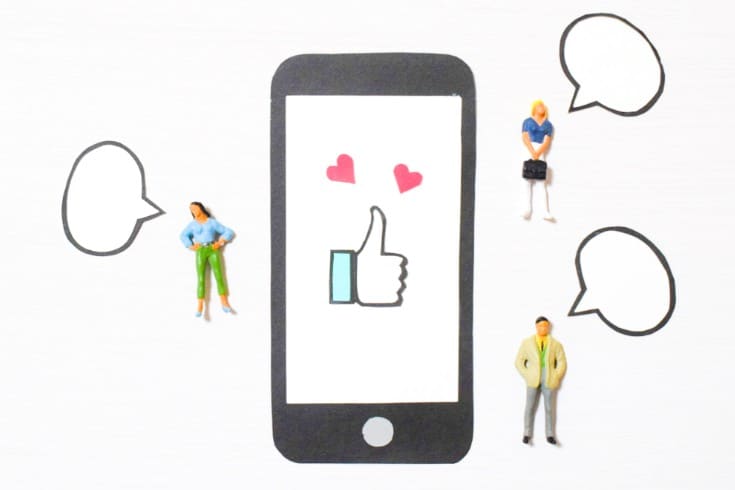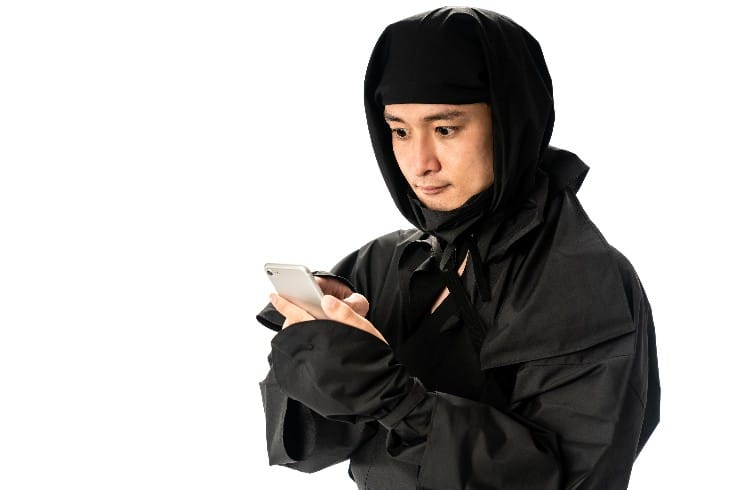令和7年(2025年)5月薬機法改正を解説、コンビニ等で医薬品販売や創薬スタートアップ支援等

令和7年(2025年)5月14日に国会で「医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下:薬機法とします)」の改正法が成立し、同月21日に公布されました。本改正は私たちの暮らしとの関わりでは、コンビニ等で医薬品販売が可能となるほか、ビジネスの分野で創薬スタートアップを支援する内容等が含まれており、重要な改正といえます。
そこで本記事では、令和7年(2025年)5月の薬機法の改正について解説します。
この記事の目次
薬機法改正の背景と概要
薬機法(旧:薬事法)は、医薬品や医療機器等の品質、有効性、安全性を確保するための基本法です。今回の令和7年(2025年)年5月改正では、医薬品の供給や薬局の在り方、創薬支援など広範な分野にわたって制度が見直されました。
- 公布日:令和7年(2025年)5月21日
- 施行日:公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日以降に段階的に施行
参考:令和7年の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)等の一部改正について|厚生労働省
薬機法改正の背景
令和7年の薬機法改正の背景には、医薬品メーカーによる不正事案が頻発したことがあります。製造記録の改ざんや必要な試験を怠っていたことが相次ぎ発覚、製品の出荷停止や回収が発生し、医薬品の供給不足が発生しました。そこで、品質の確保された医薬品等を国民に迅速かつ適正に提供していくために、医薬品等の品質及び安全性の確保の強化、医療用医薬品等の安定供給体制の強化、国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能の強化がされています。
また、創薬環境の変化等の状況に対応するために、より活発な創薬が行われる環境を整備するための措置が取られています。
薬機法改正の概要
令和7年の薬機法の改正は大きく分けると次の4つに分かれます。
- 医薬品等の品質及び安全性の確保の強化
- 医療用医薬品等の安定供給体制の強化等
- より活発な創薬が行われる環境の整備
- 国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能の強化等
上記の改正は、改正薬機法公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されることになっています。以下、詳しく内容を見てみましょう。
医薬品等の品質及び安全性の確保の強化

令和7年薬機法改正として、医薬品等の品質及び安全性の確保の強化のための改正が行われています。
- 医薬品品質保証責任者及び医薬品安全管理責任者の設置を法定
- 副作用に係る情報収集等に関する計画の作成・実施の義務化
- 法令違反等があった場合の責任役員の変更命令
医薬品品質保証責任者及び医薬品安全管理責任者の設置を法定
今回の改正で、すべての製造販売業者に対して「医薬品品質保証責任者」および「医薬品安全管理責任者」の設置が法定化されました(薬機法第17条第6項)。
これにより、組織内に品質や安全性に関する明確な責任者が存在し、リスク発生時の対応や情報伝達が迅速かつ確実になることが期待されます。責任体制を制度化したことで、品質不良や回収対応の初動遅れなど、過去の問題に対する具体的な対策を取ることができます。
副作用に係る情報収集等に関する計画の作成・実施の義務化
医薬品の製造販売業者は、厚生労働大臣が指定する医薬品の製造販売をする場合で当該医薬品の安全性及び有効性を確保するため必要があると認められるときなどに、医薬品を使用することに伴う副作用の発生等の最小化するための計画を作成しなければならないとしました(薬機法第68条の2)。
法令違反等があった場合の責任役員の変更命令
法令違反など一定の場合に、その薬事に関する業務に責任を有する役員を変更しなければ、保健衛生上の危害の発生または拡大を防止するために必要な業務の運営の改善が見込まれないと認めるときは、厚生労働大臣が薬事に関する業務に責任を有する役員の変更を命じることができるとしました(薬機法第72条の8)。
なお、前述の医薬品品質保証責任者および医薬品安全管理責任者についても変更を命じることができます(薬機法第73条)。
医療用医薬品等の安定供給体制の強化等
医療用医薬品等の安定供給体制の強化のために次のような改正が行われています。(なお、いずれも政令で定める日に施行予定)
- 医療用医薬品の供給体制管理責任者の設置
- 出荷停止時の届出を義務化
- 供給不足時の増産等の必要な協力の要請
- 製造販売承認を一部変更する場合の手続
- 後発医薬品製造基盤整備基金の創設
医療用医薬品の供給体制管理責任者の設置
特定医薬品の製造販売業者は、特定医薬品供給体制管理責任者を置かなければなりません(薬機法第18条の2の2)。特定医薬品供給体制管理責任者は、製造販売をする特定医薬品に関する製造販売の計画の策定、当該特定医薬品の供給状況の調査並びに製造業者・卸売販売業者その他の当該特定医薬品の供給に係る関係者との連絡体制の整備その他の当該特定医薬品の供給体制の管理の統括を行います。
出荷停止時の届出を義務化
特定医薬品の製造販売業者は、特定医薬品について、6か月以内にその出荷の停止や制限、またはそのおそれがある場合には、厚生労働大臣に届出をすることが義務化されました(薬機法第18条の3)。
これにより、医薬品の供給不安を迅速に把握できるようになります。特に、がん治療薬や感染症治療薬など、代替がきかない医薬品が突然供給停止となる事態を未然に防ぐことが期待されています。
国が早期に情報を把握することで、他社への増産要請や代替薬の調整など、必要な対応を速やかに講じられる体制が整備されました。これにより、患者への影響を最小限に抑え、医療現場の混乱回避につなげることが目的とされています。
供給不足時の増産等の必要な協力の要請
特定医薬品について、供給不足の場合やその蓋然性があり国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある場合には、厚生労働大臣は、製造販売業者・製造業者・卸売販売業者その他の関係者に対して、当該特定医薬品または代替薬の増産、販売の調整などの必要な協力を求めることができると規定しました(医療法36条第1項)。
製造販売承認を一部変更する場合の手続
医薬品などの製造販売承認を一部変更する場合の手続きについて、中程度の変更に該当する場合の類型が設けられました。
特に適切な製造管理または品質管理を要するものとして厚生労働省令で定める医薬品などについて、製造方法などの承認事項の一部を変更する場合は、厚生労働大臣が3カ月以内に承認の可否を判断するものとされています(薬機法第14条第15項、23条の25第14項)。
また、医薬品などの品質に与える影響が小さい軽微な変更を行う場合、個別の届出に代えて、年度ごとにまとめた報告を行い確認を受けることができます。特定軽微変更である旨の確認(薬機法14条20項、23条の25第19項)。
後発医薬品製造基盤整備基金の創設
医療用医薬品の供給不足の原因の一つである後発医薬品産業における生産効率の低下に対応するために、「後発医薬品製造基盤整備基金」が設置されることになりました(改正国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則27条)。
活発な創薬が行われる環境の整備
今回の薬機法改正では、革新的医薬品の実用化や創薬スタートアップの支援に向けた新たな仕組みが整備され、より活発な創薬が行われる環境の整備のための法改正が行われました。(なお、いずれも政令で定める日に施行予定)
- 医薬品・医療機器等の条件付き承認制度の見直し
- 医薬品の製造販売業者に対する小児用医薬品開発の計画策定を努力義務化
- 革新的医薬品等実用化支援基金の設置
医薬品・医療機器等の条件付き承認制度の見直し
希少で患者数が少ない疾患や重篤かつ代替の治療法がない疾患を対象に、探索的臨床試験等で、一定程度の有効性・安全性が確認され、臨床的有用性が合理的に予測可能な場合に、承認後に検証的臨床試験等を行うことを条件に承認する条件付き承認制度の見直しがされました(薬機法第14条の2の2以下)。
医薬品の製造販売業者に対する小児用医薬品開発の計画策定を努力義務化
小児用の薬局医薬品の開発を促進するために必要な小児の疾病の診断、治療または予防に使用する医薬品の品質、有効性及び安全性に関する資料の収集に関する計画を作成と、当該計画に基づき、遅滞なく、必要な資料の収集を行う努力義務が課せられました(薬機法第14条の8の2)。
革新的医薬品等実用化支援基金の設置
官民連携して継続的に創薬基盤を強化するため、国庫と民間からの出えん金(寄附金)で「革新的医薬品等実用化支援基金」を設置します(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則20条)。基金事業では、創薬クラスターキャンパス整備事業者の取組等を支援し、より活発な創薬が行われる環境を整備します。
国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能の強化等

国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能の強化のために薬機法の改正が行われています。
調剤業務の一部の外部委託が可能に
薬局開設者は、特定調剤業務について厚生労働省令で定める要件を備えている薬局に外部委託することが可能となります(改正薬機法第9条の5)。
濫用のおそれのある医薬品の販売について
医薬品の販売に関する規制について、若年者を中心に一般用医薬品の濫用が社会問題化している状況を踏まえて、販売に規制を加える措置が取られました。具体的には、中枢神経系の興奮・抑制・幻覚を生ずるおそれがある一定の医薬品(=指定濫用防止医薬品)を販売・授与・配置する場合には、書面を用いた情報の提供や一定の事項の確認が必要となります(薬機法第36条の11第1項・第2項)。
薬剤師等が常駐しない店舗における一般用医薬品の販売が可能に
薬剤師が常駐していないコンビニなどの店舗(=登録受渡店舗)でも、あらかじめ登録された薬剤師が遠隔で管理する仕組みを導入することで、一般用医薬品を販売できるようになりました(薬機法第29条の5~9)。販売に関する責任は、リモートで管理を行う薬剤師が所属する薬局や販売業者が負うことになります。
まとめ:薬機法改正点については弁護士に相談を
令和7年5月の薬機法改正は、医薬品の品質・安全性の強化、安定供給体制の整備、創薬支援、薬局機能の拡張といった多角的な視点から実施されました。とくに注目されるのは、薬剤師の遠隔管理による一般用医薬品販売の容認や、創薬スタートアップ向け基金の新設であり、医薬品業界だけでなく、小売業や調剤業務、創薬スタートアップにも影響を及ぼします。新たなビジネス創出の可能性が期待されます。
当事務所による対策のご案内
モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に豊富な経験を有する法律事務所です。当事務所では、メディア運営事業者・レビューサイト運営事業者・広告代理店・サプリメントといったD2Cや化粧品メーカー・クリニック・ASP事業者などに対し、記事やLPのリーガルチェック、ガイドライン作成やサンプリングチェックなどのサービスを提供しています。下記記事にて詳細を記載しております。
モノリス法律事務所の取扱分野:記事・LPの薬機法等チェック
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務