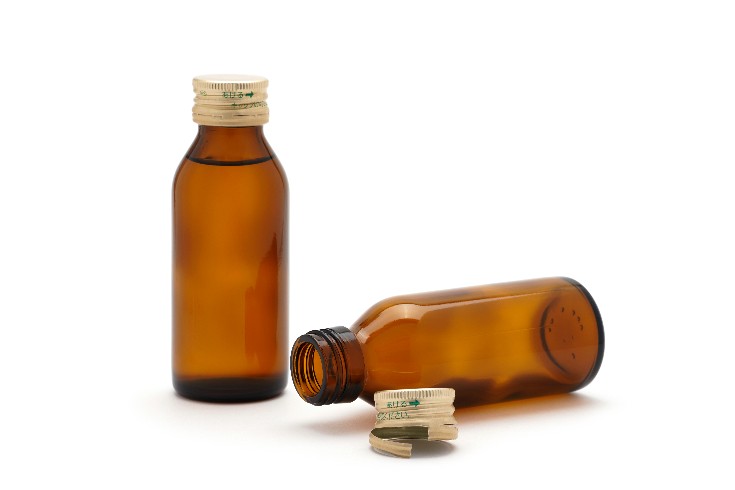Ķ¢¼µ®¤µ│ĢŃü½ķ¢óķĆŻŃüÖŃéŗŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃü«Õ«ÜńŠ®Ńü©Õ║āÕæŖĶĪ©ńÅŠŃü«µ│©µäÅńé╣

µŚźÕĖĖńö¤µ┤╗Ńü¦õĖŹĶČ│ŃüŚŃüīŃüĪŃü¬µĀäķżŖŃéÆĶŻ£ŃüåŃü¤ŃéüŃü½ŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃéÆÕł®ńö©ŃüÖŃéŗõ║║ŃééÕżÜŃüäŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆéŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃü»ŃĆüŃāēŃā®ŃāāŃé░Ńé╣ŃāłŃéóŃü¬Ńü®Ńü¦Ķ”ŗŃüŗŃüæŃéŗŃü╗ŃüŗŃĆüķĆÜĶ▓®ńĢ¬ńĄäŃéäķøæĶ¬īÕ║āÕæŖŃü¬Ńü®Ńü¦ŃééÕÅ¢ŃéŖµē▒ŃéÅŃéīŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüµŚźÕĖĖńö¤µ┤╗Ńü¦ńø«Ńü½ŃüÖŃéŗµ®¤õ╝ÜŃééÕóŚŃüłŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃéÆĶ▓®ÕŻ▓ŃüÖŃéŗķÜøŃü«Õ║āÕæŖŃü½ŃüŖŃüäŃü”Ńü»ŃĆüµ│ĢĶ”ÅÕłČŃü«Ķ”│ńé╣ŃüŗŃéēŃĆüŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃüīÕī╗Ķ¢¼ÕōüŃü¬Ńü«ŃüŗķŻ¤ÕōüŃü¬Ńü«ŃüŗŃü©ŃüäŃüåńé╣ŃüīŃü©Ńü”ŃééķćŹĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆéń¤źŃéēŃü¬ŃüäŃüŠŃüŠÕ║āÕæŖŃéÆÕć║ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃü©ŃĆüµ░ŚŃüźŃüŗŃü¬ŃüäŃüåŃüĪŃü½ķüĢµ│ĢĶĪīńé║Ńü©Ńü¬ŃéŖŃĆüĶ¬▓ÕŠ┤ķćæŃüīĶ¬▓ŃüĢŃéīŃéŗńŁēŃĆüõ║ŗµźŁŃü½Õż¦ŃüŹŃü¬µÉŹÕż▒ŃüīńÖ║ńö¤ŃüŚŃü”ŃüŚŃüŠŃüåÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«Ķ©śõ║ŗŃü¦Ńü»ŃĆüŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃü«µĆ¦Ķ│¬ŃéäÕ║āÕæŖŃü¦µ░ŚŃéÆõ╗śŃüæŃéŗŃü╣ŃüŹĶĪ©ńÅŠŃü«ŃāØŃéżŃā│ŃāłŃü¬Ńü®ŃéÆĶ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«Ķ©śõ║ŗŃü«ńø«µ¼Ī
Ķ¢¼µ®¤µ│ĢŃü©Ńü»
Ķ¢¼µ®¤µ│ĢŃü»ŃĆüÕī╗Ķ¢¼ÕōüŃā╗Õī╗ńÖéµ®¤ÕÖ©Ńā╗Õī╗Ķ¢¼ķā©Õż¢ÕōüŃā╗Õī¢ń▓¦ÕōüŃü¬Ńü®ŃéÆÕ»ŠĶ▒ĪŃü©ŃüŚŃü¤µ│ĢÕŠŗŃü¦ŃĆüŃüØŃü«ÕōüĶ│¬Ńā╗µ£ēÕŖ╣µĆ¦Ńā╗Õ«ēÕģ©µĆ¦Ńü«ńó║õ┐ØŃéäŃĆüõ┐ØÕüźĶĪøńö¤õĖŖŃü«ÕŹ▒Õ«│Ńü«ńÖ║ńö¤Ńā╗µŗĪÕż¦Ńü«ķś▓µŁóŃü«Ńü¤ŃéüŃü«Ķ”ÅÕłČŃéÆĶĪīŃüåŃü¬Ńü®Ńü«Õ┐ģĶ”üŃü¬µÄ¬ńĮ«ŃéÆĶ¼øŃüÜŃéŗŃüōŃü©Ńü¦ŃĆüõ┐ØÕüźĶĪøńö¤Ńü«ÕÉæõĖŖŃéÆÕø│ŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńø«ńÜäŃü©ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖ’╝łĶ¢¼µ®¤µ│Ģń¼¼1µØĪ’╝ēŃĆé
Õī╗Ķ¢¼ÕōüŃü»Õł®ńö©ĶĆģŃü«Ķ║½õĮōŃü½ÕĮ▒ķ¤┐ŃéÆÕÅŖŃü╝ŃüÖÕÅ»ĶāĮµĆ¦Ńüīķ½śŃüäŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃéŗŃüōŃü©ŃüŗŃéēŃĆüĶŻĮķĆĀŃéäĶ▓®ÕŻ▓ŃĆüÕ║āÕæŖŃü©ŃüäŃüŻŃü¤ŃüĢŃüŠŃü¢ŃüŠŃü¬ĶĪīńé║Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ķ¢¼µ®¤µ│ĢõĖŖŃü¦Ķ”ÅÕłČŃüīÕ«ÜŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃü«Õ«ÜńŠ®
ŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃü½Ńü»ŃĆüÕ«¤Ńü»ĶĪīµö┐ńÜäŃü¬Õ«ÜńŠ®Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüõĖĆĶł¼ńÜäŃü½ŃĆīńē╣իܵłÉÕłåŃüīµ┐āńĖ«ŃüĢŃéīŃü¤ķīĀÕēżŃéäŃé½ŃāŚŃé╗Ńā½ÕĮóµģŗŃü«ĶŻĮÕōüŃĆŹŃü©ĶĆāŃüłŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüõ║║ŃüīńĄīÕÅŻńÜäŃü½µ£Źńö©ŃüÖŃéŗķŻ▓ķŻ¤ńē®Ńü»ŃĆüŃĆīķŻ¤ÕōüŃĆŹŃü©ŃĆīÕī╗Ķ¢¼ÕōüńŁēŃĆŹŃü½ÕłåŃüæŃéēŃéīŃéŗŃü©ŃüĢŃéīŃü”ŃüŖŃéŖ’╝łķŻ¤ÕōüÕ«ēÕģ©Õ¤║µ£¼µ│Ģń¼¼2µØĪń¼¼1ķĀģŃĆüķŻ¤ÕōüĶĪøńö¤µ│Ģń¼¼4µØĪń¼¼1ķĀģÕÅéńģ¦’╝ēŃĆüŃĆīÕī╗Ķ¢¼ÕōüńŁēŃĆŹŃü½Ķ®▓ÕĮōŃüÖŃéŗŃüŗŃü®ŃüåŃüŗŃü»Ķ¢¼µ®¤µ│Ģń¼¼2µØĪń¼¼1ķĀģŃéÆÕ¤║µ║¢Ńü½Õłżµ¢ŁŃüĢŃéīŃéŗŃü©ŃüōŃéŹŃĆüŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃü»Õī╗Ķ¢¼ÕōüńŁēŃü«Õ«ÜńŠ®Ńü½Ńü»Ķ®▓ÕĮōŃüŚŃü¬ŃüäŃü¤ŃéüŃĆüŃüéŃüÅŃüŠŃü¦ķŻ¤ÕōüŃü©ŃüŚŃü”µē▒ŃéÅŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŚŃü¤ŃüīŃüŻŃü”ŃĆüŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃü«Ķ▓®ÕŻ▓ŃéäÕ║āÕæŖŃü¬Ńü®Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüÕĤÕēćŃü©ŃüŚŃü”Ķ¢¼µ®¤µ│ĢŃü«Ķ”ÅÕłČŃü»ÕÅŖŃü░ŃüÜŃĆüµÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│ĢŃéäÕüźÕ║ĘÕóŚķĆ▓µ│ĢŃü¬Ńü®Ńü«µ│ĢÕŠŗŃü½ŃéłŃéŗĶ”ÅÕłČŃéÆÕÅŚŃüæŃéŗŃüōŃü©Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃééŃüŻŃü©ŃééŃĆüŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃü»ŃĆüŃüØŃü«ÕĮóńŖČŃüīķīĀÕēżŃéäŃé½ŃāŚŃé╗Ńā½Ńü«ŃéłŃüåŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüÕī╗Ķ¢¼ÕōüŃü«ŃéłŃüåŃü¬Õż¢Ķ”│ŃéƵ£ēŃüÖŃéŗŃééŃü«ŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃü«ŃéłŃüåŃü¬ÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»ŃĆüÕŠīĶ┐░ŃüÖŃéŗŃéłŃüåŃü½Õī╗Ķ¢¼ÕōüŃü©Ńü┐Ńü¬ŃüĢŃéīŃü”Ķ¢¼µ®¤µ│ĢŃü«Ķ”ÅÕłČÕ»ŠĶ▒ĪŃü©Ńü¬ŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃü©ÕüźÕ║ĘķŻ¤ÕōüŃü«ķüĢŃüä
ŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃü©ÕÉīµ¦śŃü½ŃĆüÕüźÕ║ĘķŻ¤ÕōüŃü½ŃééĶĪīµö┐ńÜäŃü¬Õ«ÜńŠ®Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüõĖĆĶł¼ńÜäŃü½Ńü»ŃĆüÕüźÕ║ĘķŻ¤ÕōüŃü©Ńü»ŃĆīÕüźÕ║ĘŃü«õ┐صīüÕóŚķĆ▓Ńü½Ķ│ćŃüÖŃéŗķŻ¤ÕōüÕģ©Ķł¼ŃĆŹŃü©ĶĆāŃüłŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüÕłåķĪ×õĖŖŃü»ŃĆīķŻ¤ÕōüŃĆŹŃü½Ķ®▓ÕĮōŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüåńé╣ŃééŃĆüŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃü©ÕÉīµ¦śŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃééŃüŻŃü©ŃééŃĆüÕüźÕ║ĘķŻ¤ÕōüŃü«õĖŁŃü½Ńü»ŃĆüÕ║āÕæŖńŁēŃü½µłÉÕłåŃü«µ®¤ĶāĮŃü«ĶĪ©ńż║ŃüīÕÅ»ĶāĮŃü©Ńü¬ŃéŗŃĆīõ┐ØÕüźµ®¤ĶāĮķŻ¤ÕōüÕłČÕ║”ŃĆŹŃüīÕł®ńö©ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃééŃü«ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃü»ŃĆüŃĆīõ┐ØÕüźµ®¤ĶāĮķŻ¤ÕōüÕłČÕ║”ŃĆŹŃüīÕł®ńö©ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃü¬ŃüäŃĆüŃüäŃéÅŃéåŃéŗŃĆīÕüźÕ║ĘķŻ¤ÕōüŃĆŹŃü©Õæ╝Ńü░ŃéīŃéŗŃééŃü«Ńü½ÕłåķĪ×ŃüĢŃéīŃéŗŃüōŃü©Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ÕüźÕ║ĘķŻ¤ÕōüŃü«µĆ¦Ķ│¬ŃéäŃĆüÕüźÕ║ĘķŻ¤ÕōüŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕ║āÕæŖĶĪ©ńż║Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüÕłźŃü«Ķ©śõ║ŗŃü¦Ķ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃüŠŃüÖŃü«Ńü¦ŃĆüŃüöÕÅéńģ¦ŃüÅŃüĀŃüĢŃüäŃĆé
ķ¢óķĆŻĶ©śõ║ŗ’╝ÜĶ¢¼µ®¤µ│ĢŃü«Õ║āÕæŖĶ”ÅÕłČŃü©Ńü»’╝¤ķü®µ│ĢŃü¬ĶĪ©ńÅŠŃü¦Õ║āÕæŖŃéÆõĮ£µłÉŃüÖŃéŗŃāØŃéżŃā│ŃāłŃéÆĶ¦ŻĶ¬¼
ŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃü©Õī╗Ķ¢¼ÕōüŃü«ķüĢŃüä
ÕēŹĶ┐░Ńü«Ńü©ŃüŖŃéŖŃĆüŃĆīÕī╗Ķ¢¼ÕōüŃĆŹŃü½Ķ®▓ÕĮōŃüÖŃéŗŃüŗŃü®ŃüåŃüŗŃü»ŃĆüĶ¢¼µ®¤µ│Ģń¼¼2µØĪń¼¼1ķĀģŃéÆÕ¤║µ║¢Ńü½Õłżµ¢ŁŃüĢŃéīŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃü©Õī╗Ķ¢¼ÕōüŃü»µśÄńó║Ńü¬Õī║ÕłźŃüīŃü¬ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃü©ŃüäŃüłŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüÕĢåÕōüŃü«ÕĮóńŖČŃéäÕ║āÕæŖŃü«ĶĪ©ńż║Ńü½ŃéłŃüŻŃü”Ńü»ŃĆüķŻ¤ÕōüŃü¦ŃüéŃüŻŃü”ŃééÕī╗Ķ¢¼ÕōüŃü©Ńü┐Ńü¬ŃüĢŃéīŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃĆüŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃééÕī╗Ķ¢¼ÕōüŃü©Ńü┐Ńü¬ŃüĢŃéīŃéŗŃüŖŃüØŃéīŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
Õī╗Ķ¢¼ÕōüŃü¦ŃüéŃéīŃü░ĶŻĮķĆĀŃéäĶ▓®ÕŻ▓Ńü½ķÜøŃüŚŃü”ÕÄÜńö¤ÕŖ┤ÕāŹÕż¦ĶćŻńŁēŃü«µē┐Ķ¬ŹŃéäĶ©▒ÕÅ»ŃüīÕ┐ģĶ”üŃü©Ńü¬ŃéŗŃü½ŃééŃüŗŃüŗŃéÅŃéēŃüÜŃĆüÕī╗Ķ¢¼ÕōüŃü©Ńü┐Ńü¬ŃüĢŃéīŃü¤ķŻ¤ÕōüŃü»ŃüōŃéīŃéēŃü«µē┐Ķ¬ŹŃéÆÕŠŚŃüÜŃü½ĶŻĮķĆĀŃéäĶ▓®ÕŻ▓ŃüīŃü¬ŃüĢŃéīŃü”ŃüŚŃüŠŃüåŃüōŃü©ŃüŗŃéēŃĆü’ĮóńäĪµē┐Ķ¬ŹńäĪĶ©▒ÕÅ»Õī╗Ķ¢¼ÕōüŃĆŹŃü©Õæ╝Ńü░ŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ķü®ÕłćŃü¬µē┐Ķ¬ŹŃéäĶ©▒ÕÅ»ŃéÆÕÅŚŃüæŃüÜŃü½Õī╗Ķ¢¼ÕōüŃéÆĶŻĮķĆĀŃā╗Ķ▓®ÕŻ▓ŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»ŃĆü’╝ōÕ╣┤õ╗źõĖŗŃü«µć▓ÕĮ╣ŃééŃüŚŃüÅŃü»300õĖćÕååõ╗źõĖŗŃü«ńĮ░ķćæŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»ŃüØŃü«õĖĪµ¢╣Ńüīń¦æŃüøŃéēŃéīŃéŗŃüŖŃüØŃéīŃüīŃüéŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃü«ĶŻĮķĆĀŃā╗Ķ▓®ÕŻ▓ŃéÆĶĪīŃüåķÜøŃü½Ńü»ŃĆüÕī╗Ķ¢¼ÕōüŃü©Ńü┐Ńü¬ŃüĢŃéīŃéŗŃüōŃü©Ńü«Ńü¬ŃüäŃéłŃüåŃü½ń┤░Õ┐āŃü«µ│©µäÅŃéƵēĢŃéÅŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆé
Ķ¢¼µ®¤µ│ĢŃü¦ŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃéÆÕÅ¢ŃéŖńĘĀŃüŠŃéŗńÉåńö▒
ŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃüīÕī╗Ķ¢¼ÕōüŃü©ÕÉīµ¦śŃü«µłÉÕłåŃéÆÕɽŃéĆŃüōŃü©ŃéäŃĆüÕī╗Ķ¢¼ÕōüŃü©Ķ¬żĶ¦ŻŃüĢŃéīŃéŗŃéłŃüåŃü¬ÕŖ╣ĶāĮÕŖ╣µ×£ŃéÆÕ║āÕæŖŃü¦Ķ©śĶ╝ēŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīĶ©▒ŃüĢŃéīŃéŗŃü©ŃĆüÕī╗Ķ¢¼ÕōüŃü«µē┐Ķ¬ŹŃéäĶ©▒ÕÅ»ÕłČÕ║”ŃéƵĮ£Ķä▒ŃüŚŃü”ńäĪµē┐Ķ¬ŹŃā╗ńäĪĶ©▒ÕÅ»Ńü¦Õī╗Ķ¢¼ÕōüŃü©ÕÉīńŁēŃü«ÕĢåÕōüŃéÆĶ▓®ÕŻ▓ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīÕÅ»ĶāĮŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüŚŃüŠŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüØŃüåŃü¬ŃéŗŃü©ŃĆüõ║║Ńü«Ķ║½õĮōŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”ŃüĢŃüŠŃü¢ŃüŠŃü¬µé¬ÕĮ▒ķ¤┐ŃéÆÕÅŖŃü╝ŃüŚŃĆüÕüźÕ║ĘĶó½Õ«│ŃéÆńö¤ŃüśŃüĢŃüøŃéŗŃüŖŃüØŃéīŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéÕī╗Ķ¢¼ÕōüŃü©ÕÉīµ¦śŃü«µłÉÕłåŃéÆÕɽŃéĆÕĢåÕōüŃéäŃĆüÕī╗Ķ¢¼ÕōüŃü©Ķ¬żĶ¦ŻŃüĢŃéīŃéŗŃéłŃüåŃü¬ÕŖ╣ĶāĮÕŖ╣µ×£ŃéÆÕ║āÕæŖŃü¦Ķ©śĶ╝ēŃüŚŃü¤ÕĢåÕōüŃü¬Ńü®Ńü»ŃĆüŃĆīÕī╗Ķ¢¼ÕōüŃĆŹŃü©Ńü┐Ńü¬ŃüĢŃéīŃĆüµē┐Ķ¬ŹŃéäĶ©▒ÕÅ»Ńü¬ŃüÅĶŻĮķĆĀŃā╗Ķ▓®ÕŻ▓ńŁēŃéÆĶĪīŃüåŃüōŃü©Ńü»ÕēŹĶ┐░Ńü«ŃéłŃüåŃü¬ÕÄ│ńĮ░Ńü½Õć”ŃüĢŃéīŃéŗŃü©ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ÕÄÜńö¤ÕŖ┤ÕāŹń£üŃü«ŃāøŃā╝ŃāĀŃāÜŃā╝ŃéĖŃü¦Ńü»ŃĆüńäĪµē┐Ķ¬ŹńäĪĶ©▒ÕÅ»Õī╗Ķ¢¼ÕōüµāģÕĀ▒ŃéƵÄ▓Ķ╝ēŃüŚŃü”ŃüäŃéŗń«ćµēĆŃü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«ŃéłŃüåŃü¬µ│©µäÅŃéÆĶ©śĶ╝ēŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ńäĪµē┐Ķ¬ŹńäĪĶ©▒ÕÅ»Õī╗Ķ¢¼ÕōüŃü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«Õī╗Ķ¢¼ÕōüŃĆüÕī╗ńÖéµ®¤ÕÖ©ńŁēŃü«ÕōüĶ│¬ŃĆüµ£ēÕŖ╣µĆ¦ÕÅŖŃü│Õ«ēÕģ©µĆ¦Ńü«ńó║õ┐ØńŁēŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗµ│ĢÕŠŗŃü½Õ¤║ŃüźŃüÅÕōüĶ│¬Ńā╗µ£ēÕŖ╣µĆ¦Ńā╗Õ«ēÕģ©µĆ¦Ńü«ńó║Ķ¬ŹŃüīŃü¬ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüøŃéōŃĆé
µż£Õć║ŃüĢŃéīŃü¤Õī╗Ķ¢¼ÕōüµłÉÕłåŃü«Õɽµ£ēķćÅŃü»ŃĆüÕ┐ģŃüÜŃüŚŃééÕØćõĖĆŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüŃüäŃüĪŃü®Ńü½µæéÕÅ¢ŃüÖŃéŗŃü©ÕüźÕ║ĘĶó½Õ«│ŃéÆńö¤ŃüśŃéŗŃüŖŃüØŃéīŃüīŃüéŃéŗķćÅŃüīÕɽŃüŠŃéīŃü”ŃüäŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü¤ŃĆüõĖŹĶĪøńö¤Ńü¬ÕĀ┤µēĆŃéäµ¢╣µ│ĢŃü¦ĶŻĮķĆĀŃüĢŃéīŃü¤ŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃéŗŃüŖŃüØŃéīŃüīŃüéŃéŖŃĆüµ£ēÕ«│Ńü¬õĖŹń┤öńē®ńŁēŃüīÕɽŃüŠŃéīŃü”ŃüäŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīÕɔիÜŃü¦ŃüŹŃüŠŃüøŃéōŃĆéÕĀ▒ÕæŖŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗÕüźÕ║ĘĶó½Õ«│Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüµż£Õć║ŃüĢŃéīŃü¤Õī╗Ķ¢¼ÕōüµłÉÕłåŃü«Ńü┐Ńü½ŃéłŃéŗŃééŃü«Ńü©Ńü»ķÖÉŃéēŃüÜŃĆüŃüØŃüåŃüŚŃü¤õĖŹń┤öńē®ńŁēŃüīķ¢óõ┐éŃüŚŃü”ŃüäŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
’╝łÕć║ÕģĖ’╝ÜńäĪµē┐Ķ¬ŹńäĪĶ©▒ÕÅ»Õī╗Ķ¢¼ÕōüµāģÕĀ▒’Į£ÕÄÜńö¤ÕŖ┤ÕāŹń£ü’╝ē
ŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃü«Ķ¢¼µ®¤µ│ĢŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗÕ║āÕæŖĶ”ÅÕłČŃü«Õ»ŠĶ▒Ī
ŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃéÆÕ║āÕæŖŃā╗ń┤╣õ╗ŗŃüÖŃéŗķÜøŃü»ŃĆüÕ¬ÆõĮōŃéäń½ŗÕĀ┤Ńü½ŃüŗŃüŗŃéÅŃéēŃüÜĶ¢¼µ®¤µ│ĢŃü«Ķ”ÅÕłČÕ»ŠĶ▒ĪŃü©Ńü¬ŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéĶ¢¼µ®¤µ│ĢŃü¦Ńü»ŃĆīõĖĆĶł¼µČłĶ▓╗ĶĆģÕÉæŃüæŃü«ŃüÖŃü╣Ńü”Ńü«Õ║āÕæŖÕ¬ÆõĮōŃĆŹŃüīÕ»ŠĶ▒ĪŃü©ŃüĢŃéīŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüSNSŃĆüŃā¢ŃāŁŃé░ŃĆüŃāĆŃéżŃā¼Ńé»ŃāłŃāĪŃā╝Ńā½Ńü¬Ńü®µÄ▓Ķ╝ēÕĀ┤µēĆŃéäµēŗµ«ĄŃü½ÕłČķÖÉŃü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆé
ńÖ║õ┐ĪĶĆģŃüīõ╝üµźŁŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃéżŃā│ŃāĢŃā½Ńé©Ńā│ŃéĄŃā╝ŃéäŃéóŃāĢŃéŻŃā¬Ńé©ŃéżŃé┐Ńā╝Ńü¦ŃüéŃüŻŃü”ŃééŃĆüÕåģÕ«╣Ńü½ŃéłŃüŻŃü”Ńü»Ķ”ÅÕłČŃü«Õ»ŠĶ▒ĪŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü¤ŃĆüĶ¢¼µ®¤µ│ĢõĖŖŃü«Õ║āÕæŖŃü©Õłżµ¢ŁŃüĢŃéīŃéŗŃüŗŃü»ŃĆüÕÄÜńö¤ÕŖ┤ÕāŹń£üŃü«ķĆÜń¤źŃü½Õ¤║ŃüźŃüÅ3Ķ”üõ╗ČŃü«ŃüÖŃü╣Ńü”ŃéƵ║ĆŃü¤ŃüÖŃüŗŃü®ŃüåŃüŗŃü¦µ▒║ŃüŠŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
Ńā╗ķĪ¦Õ«óŃéÆĶ¬śÕ╝ĢŃüÖŃéŗ’╝łķĪ¦Õ«óŃü«Ķ│╝Õģźµäŵ¼▓ŃéƵśéķĆ▓ŃüĢŃüøŃéŗ’╝ēµäÅÕø│ŃüīµśÄńó║Ńü¦ŃüéŃéŗŃüōŃü©
Ńā╗ńē╣Õ«ÜÕī╗Ķ¢¼ÕōüńŁēŃü«ÕĢåÕōüÕÉŹŃüīµśÄŃéēŃüŗŃü½ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃüōŃü©
Ńā╗õĖĆĶł¼õ║║ŃüīĶ¬Źń¤źŃü¦ŃüŹŃéŗńŖȵģŗŃü¦ŃüéŃéŗŃüōŃü©
’╝łÕć║ÕģĖ’╝ÜĶ¢¼õ║ŗµ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕī╗Ķ¢¼ÕōüńŁēŃü«Õ║āÕæŖŃü«Ķ®▓ÕĮōµĆ¦Ńü½ŃüżŃüäŃü”’Į£ÕÄÜńö¤ÕŖ┤ÕāŹń£ü’╝ē
ŃüōŃü«3Ķ”üõ╗ČŃü»õĖĆĶ”ŗŃéĘŃā│ŃāŚŃā½Ńü½Ķ”ŗŃüłŃéŗŃééŃü«Ńü«ŃĆüÕ«¤ķÜøŃü«ķüŗńö©Ńü¦Ńü»µģÄķćŹŃü¬Õłżµ¢ŁŃüīµ▒éŃéüŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ÕĢåÕōüŃü«ń┤╣õ╗ŗŃüīńø«ńÜäŃü¦Ńü¬ŃüÅŃü”ŃééŃĆüĶ│╝ÕģźŃéÆõ┐āŃüÖŃéłŃüåŃü¬ĶĪ©ńÅŠŃüīÕɽŃüŠŃéīŃü”ŃüäŃéīŃü░ŃĆīķĪ¦Õ«óĶ¬śÕ╝ĢŃü«µäÅÕø│ŃüéŃéŖŃĆŹŃü©Õłżµ¢ŁŃüĢŃéīŃéŗŃüŖŃüØŃéīŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü¤ŃĆüÕĢåÕōüÕÉŹŃéÆńø┤µÄźĶ©śĶ╝ēŃüŚŃü”ŃüäŃü¬ŃüäÕĀ┤ÕÉłŃü¦ŃüéŃüŻŃü”ŃééŃĆüÕŠīŃüŗŃéēŃāüŃā®ŃéĘŃéäĶ│ćµ¢ÖŃüīµÅÉõŠøŃüĢŃéīŃéŗŃéłŃüåŃü¬ÕĀ┤ÕÉłŃü»ŃĆīÕĢåÕōüÕÉŹŃü«µśÄńż║ŃĆŹŃü©ŃüĢŃéīŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦Ńü»ķ½śŃüäŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃüĢŃéēŃü½ŃĆüIDŃéäŃāæŃé╣Ńā»Ńā╝ŃāēŃü«ÕģźÕŖøŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¬WebŃéĄŃéżŃāłŃü¦ŃééŃĆüĶ¬░Ńü¦ŃééńÖ╗ķī▓Ńü¦ŃüŹŃéŗÕĮóÕ╝ÅŃü¦ŃüéŃéīŃü░ŃĆīõĖĆĶł¼õ║║ŃüīĶ¬Źń¤źŃü¦ŃüŹŃéŗńŖȵģŗŃĆŹŃü½Ķ®▓ÕĮōŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüÕ║āÕæŖŃü©Õłżµ¢ŁŃüĢŃéīŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃü«Ķ¢¼µ®¤µ│ĢŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗÕ║āÕæŖĶĪ©ńÅŠŃü«µ│©µäÅńé╣
ŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłńŁēŃü«ÕĢåÕōüŃüīÕī╗Ķ¢¼ÕōüŃü©Ńü┐Ńü¬ŃüĢŃéīŃéŗŃüŗÕÉ”ŃüŗŃü«Ķ¦ŻķćłŃü«ŃāØŃéżŃā│ŃāłŃü©ŃüŚŃü”Ńü»ŃĆü
- ÕŖ╣ĶāĮÕŖ╣µ×£ŃĆüÕĮóńŖČÕÅŖŃü│ńö©µ│Ģńö©ķćÅŃü«Õ”éõĮĢŃü½ŃüŗŃüŗŃéÅŃéēŃüÜŃĆüÕłżµ¢ŁÕ¤║µ║¢Ńü«’╝æ’╝Ä’╝łŌĆ╗ńē®Ńü«µłÉÕłåµ£¼Ķ│¬’╝łÕĤµØɵ¢Ö’╝ēŃüīŃĆüÕ░éŃéēÕī╗Ķ¢¼ÕōüŃü©ŃüŚŃü”õĮ┐ńö©ŃüĢŃéīŃéŗµłÉÕłåµ£¼Ķ│¬’╝łÕĤµØɵ¢Ö’╝ēŃü¦ŃüéŃéŗŃü©Õłżµ¢ŁŃüĢŃéīŃü¤ÕĀ┤ÕÉł’╝ēŃü½Ķ®▓ÕĮōŃüÖŃéŗµłÉÕłåµ£¼Ķ│¬’╝łÕĤµØɵ¢Ö’╝ē’╝łÕ░éŃéēÕī╗Ķ¢¼ÕōüŃü©ŃüŚŃü”õĮ┐ńö©ŃüĢŃéīŃéŗµłÉÕłåµ£¼Ķ│¬’╝łÕĤµØɵ¢Ö’╝ēŃā¬Ńé╣ŃāłŃü½Ķ©śĶ╝ēŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃééŃü«’╝ēŃüīķģŹÕÉłÕÅłŃü»Õɽµ£ēŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü»ŃĆüÕĤÕēćŃü©ŃüŚŃü”Õī╗Ķ¢¼ÕōüŃü«ń»äÕø▓Ńü©ŃüÖŃéŗŃĆé
- Õłżµ¢ŁÕ¤║µ║¢Ńü«’╝æ’╝ÄŃü½Ķ®▓ÕĮōŃüŚŃü¬Ńü䵳ÉÕłåµ£¼Ķ│¬’╝łÕĤµØɵ¢Ö’╝ēŃüīķģŹÕÉłÕÅłŃü»Õɽµ£ēŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü¦ŃüéŃüŻŃü”ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«ŌæĀŃüŗŃéēŌæóŃü½ńż║ŃüÖŃüäŃüÜŃéīŃüŗŃü½Ķ®▓ÕĮōŃüÖŃéŗŃééŃü«Ńü½ŃüéŃüŻŃü”Ńü»ŃĆüÕĤÕēćŃü©ŃüŚŃü”Õī╗Ķ¢¼ÕōüŃü©Ńü┐Ńü¬ŃüÖŃééŃü«Ńü©ŃüÖŃéŗŃĆé
ŌæĀ Õī╗Ķ¢¼ÕōüńÜäŃü¬ÕŖ╣ĶāĮÕŖ╣µ×£ŃéƵ©ÖŃü╝ŃüåŃüÖŃéŗŃééŃü«
ŌæĪ ŃéóŃā│ŃāŚŃā½ÕĮóńŖČŃü¬Ńü®Õ░éŃéēÕī╗Ķ¢¼ÕōüńÜäÕĮóńŖČŃü¦ŃüéŃéŗŃééŃü«
Ōæó ńö©µ│Ģńö©ķćÅŃüīÕī╗Ķ¢¼ÕōüńÜäŃü¦ŃüéŃéŗŃééŃü«
’╝łÕć║ÕģĖ’╝ÜŃĆīńäĪµē┐Ķ¬ŹńäĪĶ©▒ÕÅ»Õī╗Ķ¢¼ÕōüŃü«µīćÕ░ÄÕÅ¢ńĘĀŃéŖŃü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆŹ’Į£ÕÄÜńö¤ÕŖ┤ÕāŹń£ü’╝ē
ŃüīµīÖŃüÆŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆéÕŹśŃü½Õī╗Ķ¢¼ÕōüŃü½õĮ┐ńö©ŃüĢŃéīŃéŗŃéłŃüåŃü¬µłÉÕłåŃüīÕɽŃüŠŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃüŗŃü®ŃüåŃüŗŃüĀŃüæŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüÕĢåÕōüŃü«ÕĮóńŖČŃéäńö©µ│Ģńö©ķćÅŃü«ĶĪ©Ķ©śŃü¬Ńü®ŃüŗŃéēŃééÕī╗Ķ¢¼ÕōüŃü©Ńü┐Ńü¬ŃüĢŃéīŃéŗŃüŖŃüØŃéīŃüīŃüéŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüµ│©µäÅŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆé
ÕŖĀŃüłŃü”ŃĆüõĖŖĶ©śÕÄÜńö¤ÕŖ┤ÕāŹń£üŃüīńż║ŃüÖĶ│ćµ¢ÖŃü¦Ńü»ŃĆüÕī╗Ķ¢¼ÕōüńÜäŃü©Õłżµ¢ŁŃüĢŃéīŃéŗÕ║āÕæŖĶĪ©ńÅŠŃü«ÕģĘõĮōõŠŗŃééµīÖŃüÆŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃĆÉÕī╗Ķ¢¼ÕōüńÜäŃü¬ÕŖ╣ĶāĮÕŖ╣µ×£Ńü©Õłżµ¢ŁŃüĢŃéīŃéŗÕ║āÕæŖĶĪ©ńÅŠŃü«õŠŗŃĆæ
| ÕłåķĪ× | Ķ¬¼µśÄ | ĶĪ©ńÅŠõŠŗ |
| ń¢ŠńŚģŃü«µ▓╗ńÖéŃā╗õ║łķś▓ | ńŚģµ░ŚŃü«µ▓╗ńÖéŃüŠŃü¤Ńü»õ║łķś▓ŃéÆńø«ńÜäŃü©ŃüÖŃéŗÕŖ╣ĶāĮÕŖ╣µ×£ | Ńā╗ń│¢Õ░┐ńŚģŃĆüķ½śĶĪĆÕ£¦Ńü«õ║║Ńü½ Ńā╗ĶāāµĮ░ńśŹŃü«õ║łķś▓ Ńā╗Ńé¼Ńā│ŃüīŃéłŃüÅŃü¬Ńéŗ Ńā╗ĶéØĶćōķÜ£Õ«│ŃéƵ▓╗ŃüÖ |
| Ķ║½õĮōµ®¤ĶāĮŃü«ÕóŚÕ╝ĘŃā╗ÕóŚķĆ▓ | ÕŹśŃü¬ŃéŗµĀäķżŖĶŻ£ńĄ”Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüĶ║½õĮōµ®¤ĶāĮŃéÆÕ╝ĘÕī¢ŃüÖŃéŗÕåģÕ«╣ | Ńā╗ń¢▓ÕŖ┤Õø×ÕŠ® Ńā╗Õ╝Ęń▓ŠŃā╗Õ╝ĘÕŻ« Ńā╗ķŻ¤µ¼▓ÕóŚķĆ▓ Ńā╗ĶŗźĶ┐öŃéŖ Ńā╗ńŚģµ░ŚŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗĶć¬ńäȵ▓╗ńÖÆÕŖøŃéÆķ½śŃéüŃéŗ |
| ÕŖ╣ĶāĮÕŖ╣µ×£Ńü«µÜŚńż║ | ńø┤µÄźńÜäŃü¬Ķ©śĶ┐░ŃüīŃü¬ŃüÅŃü”ŃééŃĆüķĆŻµā│ŃüĢŃüøŃéŗĶĪ©ńÅŠ | Ńā╗ŃĆīÕ╗ČÕæĮŌŚ»ŌŚ»ŃĆŹŃĆīŌŚ»ŌŚ»Ńü«ń▓ŠŃĆŹŃü¬Ńü®Ńü«ÕÉŹń¦░ Ńā╗ĶŻĮµ│ĢŃā╗µłÉÕłåĶ¬¼µśÄŃü¦ÕŖ╣µ×£ŃéÆŃü╗Ńü«ŃéüŃüŗŃüÖ Ńā╗ÕŁ”ĶĆģŃā╗Õī╗ÕĖ½Ńü«Ķ½ćĶ®▒ŃéÆÕ╝Ģńö©ŃüŚÕŖ╣µ×£ŃéÆńż║Õöå |
ŃüŠŃü¤ŃĆüńäĪµē┐Ķ¬ŹńäĪĶ©▒ÕÅ»Õī╗Ķ¢¼ÕōüŃü»Õī╗Ķ¢¼ÕōüŃü©Ńü┐Ńü¬ŃüĢŃéīŃéŗõ╗źõĖŖŃĆüĶ¢¼µ®¤µ│ĢõĖŖŃü«Õ║āÕæŖĶ”ÅÕłČŃéÆÕÅŚŃüæŃéŗŃüōŃü©Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéĶ¢¼µ®¤µ│Ģń¼¼68µØĪŃü¦Ńü»ŃĆüµē┐Ķ¬ŹÕēŹŃü«Õī╗Ķ¢¼ÕōüŃü«ÕÉŹń¦░ŃéäĶŻĮķĆĀµ¢╣µ│ĢŃĆüÕŖ╣ĶāĮÕŖ╣µ×£ŃĆüµĆ¦ĶāĮŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗÕ║āÕæŖŃüīń”üµŁóŃüĢŃéīŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüŃüōŃéīŃü½ķüĢÕÅŹŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»2Õ╣┤õ╗źõĖŗŃü«µć▓ÕĮ╣ŃééŃüŚŃüÅŃü»200õĖćÕååõ╗źõĖŗŃü«ńĮ░ķćæŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»ŃüØŃü«õĖĪµ¢╣Ńüīń¦æŃüøŃéēŃéīŃéŗŃüŖŃüØŃéīŃéäŃĆüÕ║āÕæŖŃü«õĖŁµŁóÕæĮõ╗żŃéäÕåŹńÖ║ķś▓µŁóÕæĮõ╗żŃü¬Ńü®Ńü«µÄ¬ńĮ«ÕæĮõ╗żŃéÆÕÅŚŃüæŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
µÄ¬ńĮ«ÕæĮõ╗żŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüÕłźĶ©śõ║ŗŃü¦Ķ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃüŠŃüÖŃü«Ńü¦ŃĆüŃüöÕÅéńģ¦ŃüÅŃüĀŃüĢŃüäŃĆé
ķ¢óķĆŻĶ©śõ║ŗ’╝ÜĶ¢¼µ®¤µ│ĢŃü«Ķ¬▓ÕŠ┤ķćæÕłČÕ║”Ńü©Ńü»’╝¤Õ»ŠĶ▒ĪŃü©Ńü¬ŃéŗĶĪīńé║ŃéäµĖøÕģŹŃüĢŃéīŃéŗŃé▒Ńā╝Ńé╣ŃéÆĶ¦ŻĶ¬¼
Ķ¢¼µ®¤µ│ĢŃü½ķüĢÕÅŹŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü«µ│ĢńÜäŃā¬Ńé╣Ńé»
Ķ¢¼µ®¤µ│ĢŃü½ķüĢÕÅŹŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»ŃĆüõ╗źõĖŗ3ŃüżŃü«Õć”ÕłåŃü½ńø┤ķØóŃüÖŃéŗŃā¬Ńé╣Ńé»ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
- ĶĪīµö┐Õć”Õłå
- Ķ¬▓ÕŠ┤ķćæń┤Źõ╗śÕæĮõ╗ż
- Õłæõ║ŗńĮ░
ĶĪīµö┐Õć”ÕłåŃü»ŃĆüĶ¢¼µ®¤µ│ĢķüĢÕÅŹŃü«ń¢æŃüäŃüīńö¤ŃüśŃĆüĶĪīµö┐ŃüŗŃéēŃü«µīćµæśŃéƵöŠńĮ«ŃüÖŃéŗŃü¬Ńü®ÕłØÕŗĢÕ»ŠÕ┐£ŃüīķüģŃéīŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃéłŃéŖķćŹŃüäÕć”ÕłåŃü½ŃüżŃü¬ŃüīŃéŗŃü¤ŃéüķƤŃéäŃüŗŃü¬Õ»ŠÕ┐£ŃüīõĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¦ŃüÖŃĆé
ÕÄÜńö¤ÕŖ┤ÕāŹń£üŃéäķāĮķüōÕ║£ń£īŃü½ŃéłŃéŗĶ¬┐µ¤╗ŃüīÕģźŃéŖŃĆüÕ┐ģĶ”üŃü©Õłżµ¢ŁŃüĢŃéīŃéīŃü░ĶĪīµö┐µīćÕ░ÄŃüīĶĪīŃéÅŃéīŃĆüµö╣Õ¢äŃüīŃü¬ŃüäÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»µÄ¬ńĮ«ÕæĮõ╗żŃü¬Ńü®Ńü«Õć”ÕłåŃüīõĖŗŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
µÄ¬ńĮ«ÕæĮõ╗żŃü¦Ńü»ŃĆüķüĢÕÅŹÕ║āÕæŖŃü«õĖŁµŁóŃéäÕåŹńÖ║ķś▓µŁóńŁ¢Ńü«Õ«¤µ¢ĮŃĆüķüĢÕÅŹõ║ŗÕ«¤Ńü«Õģ¼ĶĪ©Ńü¬Ńü®ŃüīÕæĮŃüśŃéēŃéīŃĆüķüĢÕÅŹÕåģÕ«╣ŃüīÕ║āŃüÅń¤źŃéēŃéīŃéŗŃüōŃü©Ńü¦õ╝üµźŁŃü«õ┐ĪķĀ╝ŃüīĶæŚŃüŚŃüÅµÉŹŃü¬ŃéÅŃéīŃéŗŃüŖŃüØŃéīŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
Ķ¬▓ÕŠ┤ķćæń┤Źõ╗śÕæĮõ╗żŃü»ŃĆüĶÖÜÕüĮŃéäĶ¬ćÕż¦Ńü¬Õ║āÕæŖŃéÆĶĪīŃüŻŃü¤õ║ŗµźŁĶĆģŃü½Õ»ŠŃüŚŃĆüÕÄÜńö¤ÕŖ┤ÕāŹÕż¦ĶćŻŃüīÕĮōĶ®▓ķüĢÕÅŹÕ║āÕæŖŃü½ŃéłŃéŗÕŻ▓õĖŖķĪŹŃü«4.5’╝ģŃü½ńøĖÕĮōŃüÖŃéŗĶ¬▓ÕŠ┤ķćæŃü«ń┤Źõ╗śŃéÆÕæĮŃüśŃéŗµÄ¬ńĮ«Ńü¦ŃüÖ’╝łĶ¢¼µ®¤µ│Ģń¼¼75µØĪŃü«5Ńü«2’╝ēŃĆé
Ńü¬ŃüŖŃĆüÕÉīŃüśÕ║āÕæŖŃüīµÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│ĢŃü½ŃééķüĢÕÅŹŃüŚŃü”ŃüäŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü»ŃĆüķćŹĶżćĶ¬▓ÕŠ┤ŃéÆķü┐ŃüæŃéŗŃü¤ŃéüŃü½Ķ¬┐µĢ┤ŃüīĶĪīŃéÅŃéīŃĆüµÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│ĢŃü«Ķ¬▓ÕŠ┤ķćæÕæĮõ╗żŃüīÕģłĶĪīŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü»Ķ¢¼µ®¤µ│ĢŃü«Ķ¬▓ÕŠ┤ķćæŃüī1.5’╝ģÕłåŃü½µĖøķĪŹŃüĢŃéīŃüŠŃüÖ’╝łĶ¢¼µ®¤µ│Ģń¼¼75µØĪŃü«5Ńü«3’╝ēŃĆé
ŃüŠŃü¤ŃĆüķüĢÕÅŹŃéÆÕÄÜńö¤ÕŖ┤ÕāŹÕż¦ĶćŻŃü½Ķć¬õĖ╗ńÜäŃü½ÕĀ▒ÕæŖŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»ŃĆüĶ¬▓ÕŠ┤ķćæŃüī50’╝ģµĖøķĪŹŃüĢŃéīŃéŗĶ”ÅÕ«ÜŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüÖ’╝łÕÉīµ│Ģń¼¼75µØĪŃü«5Ńü«4’╝ēŃĆé
Ķ¢¼µ®¤µ│ĢŃü½ķüĢÕÅŹŃüÖŃéŗÕ║āÕæŖĶĪīńé║Ńü½Ńü»ŃĆüÕåģÕ«╣Ńü½Õ┐£ŃüśŃü”µć▓ÕĮ╣ŃéäńĮ░ķćæŃü¬Ńü®Ńü«Õłæõ║ŗńĮ░Ńüīń¦æŃüĢŃéīŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃĆīĶ¬ćÕż¦Õ║āÕæŖńŁēŃĆŹŃü½Ķ®▓ÕĮōŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü»ŃĆü2Õ╣┤õ╗źõĖŗŃü«µŗśń”üÕłæŃüŠŃü¤Ńü»200õĖćÕååõ╗źõĖŗŃü«ńĮ░ķćæŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»ŃüØŃü«õĖĪµ¢╣Ńüīń¦æŃüĢŃéīŃüŠŃüÖ’╝łĶ¢¼µ®¤µ│Ģń¼¼85µØĪń¼¼4ÕÅĘ’╝ēŃĆéŃĆīµ£¬µē┐Ķ¬ŹÕī╗Ķ¢¼ÕōüńŁēŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗÕ║āÕæŖŃĆŹŃü½ŃüżŃüäŃü”ŃééŃĆüÕÉīµ¦śŃü«ńĮ░ÕēćŃüīķü®ńö©ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖ’╝łĶ¢¼µ®¤µ│Ģń¼¼85µØĪń¼¼5ÕÅĘ’╝ēŃĆé
õĖƵ¢╣ŃĆüŃĆīńē╣Õ«Üń¢ŠńŚģńö©Ńü«Õī╗Ķ¢¼ÕōüńŁēŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗÕ║āÕæŖÕłČķÖÉķüĢÕÅŹŃĆŹŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü»ŃĆü1Õ╣┤õ╗źõĖŗŃü«µŗśń”üÕłæŃééŃüŚŃüÅŃü»100õĖćÕååõ╗źõĖŗŃü«ńĮ░ķćæŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»ŃüØŃü«õĮĄń¦æŃüīÕ«ÜŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖ’╝łĶ¢¼µ®¤µ│Ģń¼¼86µØĪń¼¼1ķĀģń¼¼17ÕÅĘ’╝ēŃĆé
Ķ¢¼µ®¤µ│ĢķüĢÕÅŹŃüīń¢æŃéÅŃéīŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü»ŃĆüĶ¢¼µ®¤µ│ĢŃü½Ķ®│ŃüŚŃüäÕ╝üĶŁĘÕŻ½Ńü¬Ńü®Ńü«Õ░éķ¢ĆÕ«ČŃü©ķĆŻµÉ║ŃüŚŃĆüõ║ŗÕ«¤ķ¢óõ┐éŃéƵĢ┤ńÉåŃüŚŃü¤ŃüåŃüłŃü¦ķü®ÕłćŃü¬Õ»ŠÕ┐£µ¢╣ķćØŃéƵż£Ķ©ÄŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīķćŹĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü©Ńéü’╝ÜŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃü«Õ║āÕæŖŃü½Ńü»Õ╝üĶŁĘÕŻ½Ńü«Ńā¬Ńā╝Ńé¼Ńā½ŃāüŃé¦ŃāāŃé»ŃéÆ
ŃüōŃü«ŃéłŃüåŃü½ŃĆüŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃü«ŃüżŃééŃéŖŃü¦ĶŻĮķĆĀŃā╗Ķ▓®ÕŻ▓ŃüŚŃü¤Ńü©ŃüŚŃü”ŃééŃĆüõĮ┐ńö©ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗµłÉÕłåŃéäÕĢåÕōüŃü«ÕĮóńŖČŃĆüÕ║āÕæŖŃü«ĶĪ©ńż║Ńü¬Ńü®ŃéÆńÉåńö▒Ńü½ŃĆīÕī╗Ķ¢¼ÕōüŃĆŹŃü©Ńü┐Ńü¬ŃüĢŃéīŃü”ŃüŚŃüŠŃüåÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃüåŃü¬ŃéīŃü░ŃĆüĶŻĮķĆĀŃü«õĖŁµŁóŃéäÕ║āÕæŖĶ”ÅÕłČķüĢÕÅŹŃü½ŃéłŃéŗĶ¬▓ÕŠ┤ķćæŃü«ÕŠ┤ÕÅÄŃü¬Ńü®ŃĆüõ║ŗµźŁŃü½ÕżÜÕż¦Ńü¬µÉŹÕż▒ŃéÆńö¤Ńü┐Õć║ŃüÖŃüōŃü©Ńü½ŃééŃüżŃü¬ŃüīŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃü«ĶŻĮķĆĀŃā╗Ķ▓®ÕŻ▓ŃéäŃĆüÕ║āÕæŖŃéÆõĮ£µłÉŃüÖŃéŗķÜøŃü½Õ░æŃüŚŃü¦ŃééõĖŹÕ«ēŃü¬ŃüōŃü©ŃüīŃüéŃéīŃü░ŃĆüĶ¢¼µ®¤µ│ĢŃü½Ķ®│ŃüŚŃüäÕ╝üĶŁĘÕŻ½Ńü½ńøĖĶ½ćŃüŚŃü”Ńü┐ŃüŠŃüŚŃéćŃüåŃĆé
ŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃü¬Ńü®Ńü«Õ║āÕæŖŃü«Ńā¬Ńā╝Ńé¼Ńā½ŃāüŃé¦ŃāāŃé»ŃéäµøĖŃüŹµÅøŃüłĶĪ©ńÅŠŃü«µÅɵĪłŃü»ŃĆüķØ×ÕĖĖŃü½Õ░éķ¢ĆµĆ¦Ńü«ķ½śŃüäķĀśÕ¤¤Ńü¦ŃüÖŃĆéŃāóŃāÄŃā¬Ńé╣µ│ĢÕŠŗõ║ŗÕŗÖµēĆŃü»ŃĆüĶ¢¼µ®¤µ│Ģµ│ĢÕŗÖŃāüŃā╝ŃāĀŃéÆńĄäµłÉŃüŚŃĆüŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃüŗŃéēÕī╗Ķ¢¼ÕōüŃüŠŃü¦ŃĆüŃüĢŃüŠŃü¢ŃüŠŃü¬ÕĢåµØÉŃü«Ķ©śõ║ŗŃāüŃé¦ŃāāŃé»ńŁēŃü½Õ»ŠÕ┐£ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ÕĮōõ║ŗÕŗÖµēĆŃü½ŃéłŃéŗÕ»ŠńŁ¢Ńü«ŃüöµĪłÕåģ
ŃāóŃāÄŃā¬Ńé╣µ│ĢÕŠŗõ║ŗÕŗÖµēĆŃü»ŃĆüITŃĆüńē╣Ńü½ŃéżŃā│Ńé┐Ńā╝ŃāŹŃāāŃāłŃü©µ│ĢÕŠŗŃü«õĖĪķØóŃü½Ķ▒ŖÕ»īŃü¬ńĄīķ©ōŃéƵ£ēŃüÖŃéŗµ│ĢÕŠŗõ║ŗÕŗÖµēĆŃü¦ŃüÖŃĆéÕĮōõ║ŗÕŗÖµēĆŃü¦Ńü»ŃĆüŃāĪŃāćŃéŻŃéóķüŗÕ¢Čõ║ŗµźŁĶĆģŃā╗Ńā¼ŃāōŃāźŃā╝ŃéĄŃéżŃāłķüŗÕ¢Čõ║ŗµźŁĶĆģŃā╗Õ║āÕæŖõ╗ŻńÉåÕ║ŚŃā╗ŃéĄŃāŚŃā¬ŃāĪŃā│ŃāłŃü©ŃüäŃüŻŃü¤D2CŃéäÕī¢ń▓¦ÕōüŃāĪŃā╝Ńé½Ńā╝Ńā╗Ńé»Ńā¬ŃāŗŃāāŃé»Ńā╗ASPõ║ŗµźŁĶĆģŃü¬Ńü®Ńü½Õ»ŠŃüŚŃĆüĶ©śõ║ŗŃéäLPŃü«Ńā¬Ńā╝Ńé¼Ńā½ŃāüŃé¦ŃāāŃé»ŃĆüŃé¼ŃéżŃāēŃā®ŃéżŃā│õĮ£µłÉŃéäŃéĄŃā│ŃāŚŃā¬Ńā│Ńé░ŃāüŃé¦ŃāāŃé»Ńü¬Ńü®Ńü«ŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣ŃéƵÅÉõŠøŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéõĖŗĶ©śĶ©śõ║ŗŃü½Ńü”Ķ®│ń┤░ŃéÆĶ©śĶ╝ēŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃāóŃāÄŃā¬Ńé╣µ│ĢÕŠŗõ║ŗÕŗÖµēĆŃü«ÕÅ¢ŃéŖµē▒ŃüäÕłåķćÄ’╝ÜĶ©śõ║ŗŃā╗LPŃü«Ķ¢¼µ®¤µ│ĢńŁēŃāüŃé¦ŃāāŃé»
Ńé½ŃāåŃé┤Ńā¬Ńā╝: ITŃā╗ŃāÖŃā│ŃāüŃāŻŃā╝Ńü«õ╝üµźŁµ│ĢÕŗÖ
Ńé┐Ńé░: Õī╗õ║ŗµ│Ģķ¢óķĆŻĶ¢¼µ®¤µ│Ģ