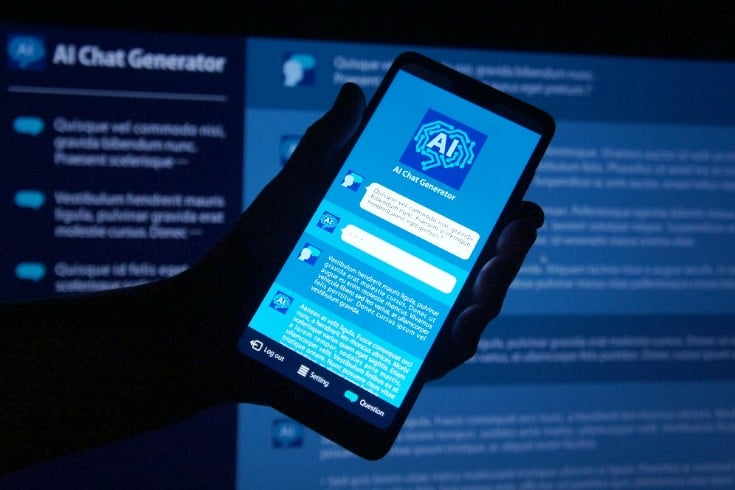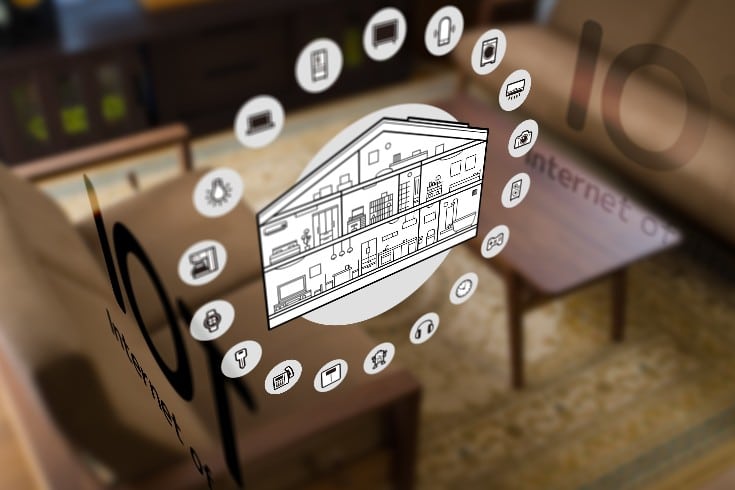AI推進法とは?企業が知っておくべきポイントを分かりやすく解説

令和7年(2025年)5月に成立し6月公布・施行された日本のAI技術開発に大きな転換点となる新法があります。「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(通称:AI推進法)です。
この法律は、日本のAI戦略を国家レベルで推進するための「基本ルール」を定めたもので、企業にとっても無視できない内容が盛り込まれています。罰則規定こそありませんが、今後のAI関連規制の方向性を示すものとして重要な法律といえるでしょう。
本記事では、AI推進法の背景から具体的な企業対応まで、法律に馴染みのない方にも分かりやすく解説していきます。
この記事の目次
AI推進法の成立の背景
AI推進法が制定される背景には、技術面・政策面・社会面での複数の要因が重なっています。まずは、この法律がなぜこのタイミングで必要とされたのか、その背景を詳しく見ていきましょう。
国際競争の激化とAI政策の立案が急務に
令和7年(2025年)5月に成立したAI推進法は、日本におけるAIの研究開発・社会実装の推進を国家戦略として位置付け、今後の経済社会におけるイノベーションの中核としてAIの果たす役割を明確に示した初の包括的な法制度です。
この法律が必要になった最大の理由は、AI技術の急速な進展と、それに伴う国際的な競争激化にあります。特に、ChatGPTをはじめとする生成AIの登場以降、アメリカやヨーロッパを中心にAIに関する政策や規制の枠組みが次々と整備され、日本も同様の政策対応を迫られる状況となっていました。
こうした状況を受けて、政府はAIを国家成長戦略の重要な柱と位置付け、内閣府を中心にさまざまな体制整備を進めてきました。具体的には「AI戦略会議」「内閣府AI戦略チーム」「AI制度研究会」などの組織を立ち上げ、2025年には包括的な「中間とりまとめ」を発表するに至りました。
AIが抱えるリスクへの対応
また、AI活用の拡大により、従来では考えられなかった様々なリスクが顕在化してきたことも立法の大きな契機となりました。
例えば、生成AIが既存の著作物を無断で学習データとして使用する著作権の問題、個人情報の取り扱いに関する課題、アルゴリズムが「ブラックボックス」となることで生じる透明性の問題、さらには差別的・虚偽的な出力を生み出すといった倫理的課題など、多岐にわたる問題が指摘されるようになりました。
法的基盤整備の必要性
こうした複雑な課題に対応するためには、AIの研究・活用に関する基本理念や国の責務、事業者・研究者の努力義務を明文化し、関係省庁が連携して一貫した施策を講じる体制の法的根拠を整備する必要性に迫られました。
本法律は、AIに関する施策の方向性を示し、国民・企業・研究機関が一体となってAIの健全な発展を促進するための「旗印」としての役割を担うこととなります。言い換えれば、今後のAI関連法制度の「憲法」のような存在として機能することが期待されています。
AI推進法の概要

それでは、AI推進法の具体的な内容を詳しく見ていきましょう。この法律は複数の章にわたって構成されており、AIに関する国の基本的な考え方から具体的な施策、推進体制まで幅広くカバーしています。
法律の目的と「人工知能関連技術」の定義
AI推進法は、AI関連技術の研究開発および活用の促進を通じて、国民生活の向上と経済社会の持続的発展、さらには国際競争力の強化を図ることを目的としています。
同法では「人工知能関連技術」について、「人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用して処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術」と定義しています。
簡単に言えば、ChatGPTのような生成AIから自動運転システムまで、人間の知的作業を代替したり支援したりする技術全般を幅広く対象としている、ということです。
基本理念と各主体の責務
次に注目すべきは、基本理念および関係主体の責務です。本法は、AIが今後の経済社会および安全保障において基幹的な役割を果たすことを明確に示しつつ、以下のような原則を掲げています。
- 研究開発力の維持・強化
- 国際的な規範との整合性の確保
- 倫理性(権利利益保護、透明性、適正性)ある技術の推進
そして、これらを実現するため、国や地方公共団体、研究機関、活用事業者、さらには一般国民に至るまで、各主体の連携とそれぞれの立場に応じた努力が求められています。
特に企業を含む「活用事業者」については、国及び地方自治体の施策への協力が努力義務として明示されており、単なる受益者ではなく施策推進の一翼を担うことが期待されています。
具体的な施策の方向性
こうした理念に基づき、本法第2章では、具体的な施策の方向性が定められています。主なポイントは以下の通りです。
研究開発の一貫した支援
基礎研究から実装段階に至るまで一貫した支援の必要性が示され、研究成果の円滑な移転や研究環境の整備が国の責務とされました。これまでのように研究と実用化が分断されるのではなく、シームレスな支援体制の構築が目指されています。
データインフラの整備
AI開発に必要不可欠な大規模データセット等の整備と共用化が掲げられており、産学官を横断するインフラの構築が今後進められることになります。これは、個々の企業や研究機関では準備が困難な大規模なデータ基盤を、国が主導して整備することを意味しています。
国際規範に即したルール整備
さらに、AIの適正な研究開発・活用を促すため、国が国際規範に即した指針整備を進めることを定めています。また、国は、リスク事例の分析を含む調査研究を通じ、事業者への助言や指導を行うこととされています。
人材育成と教育の拡充
人材育成を定める第14条と、教育・普及啓発を定める第15条は、本法の大きな特徴です。第14条では、研究開発や産業現場を担う高度専門人材の養成が国の責務として掲げられています。一方、第15条では、AIに関する国民全体の理解・リテラシー向上を目的とした教育・普及施策が定められ、初等中等教育を含む幅広い学習段階での取り組みが期待されています。
調査研究と国際協力
実態調査や国際的動向に関する調査研究も規定され、これにより柔軟な政策の立案・見直しが可能となる体制が整備されます。そして第17条では、国際協力の重要性が強調され、国際的な枠組み形成への積極的な参画が国の責務と位置付けられています。
人工知能基本計画の策定
第3章では、本法の核心ともいえる「人工知能基本計画」の策定について定められています(第18条)。この基本計画は、政府が本法の理念と方針に基づき、今後のAI政策全体を包括的・計画的に推進するための中核文書です。第3章および第4章の規定は、公布の日から3カ月以内に施行されることとされています。
基本計画については、閣議決定後に「遅滞なく」公表することが求められており、AI技術の急速な進展を踏まえ、定期的な見直しや柔軟な運用が可能な設計となっている点も特徴的です。定期的な見直しや柔軟な運用が可能な設計とされている点も特徴的です。
人工知能戦略本部の設置
続く第4章では、政策推進の実行力を担保するための組織として「人工知能戦略本部」の設置が規定されています。この戦略本部は、内閣総理大臣を本部長とし、内閣官房長官およびAI戦略担当大臣を副本部長、さらに全ての国務大臣を構成員とするもので、政府全体の司令塔として機能することが予定されています。
将来への対応力を持つ法制度設計
なお、附則では、施行期日や経過措置、将来の制度改正に向けた検討条項などが定められており、本法が固定的な枠組みにとどまらず、柔軟に進化することを想定した構造となっている点も重要です。国際情勢等の変化に応じて必要な法制上の措置を講じる旨が盛り込まれており、今後のガイドライン整備や新たな個別立法への展開が視野に入れられています。
以上のように、本法はAI技術の研究開発と社会実装を国家的課題と位置付け、その推進のために必要な理念、体制、施策を広範に整備するものであり、今後のAI政策の「憲法」とも呼べる性格を有しています。企業の法務担当者としては、こうした基本法の内容とそこに込められた政策的意図を的確に把握し、今後の規制動向や業界ガイドラインの形成に対する備えを講じておくことが、中長期的なリスク対応の鍵となるでしょう。
AI推進法において企業に求められる対応

法律の内容を理解したうえで、実際に企業はどう対応すればよいのでしょうか。AI推進法は基本法という性格上、直接的な義務や罰則は定めていませんが、企業として押さえておくべきポイントがいくつかあります。
基本法としての性格と企業への影響
AI推進法が「基本法」であることから、現時点で直ちに罰則や義務規定が科されるわけではありません。しかし、国の方針が明文化されたことにより、企業としては将来的な規制導入や行政的な評価に備えた体制整備が求められることになります。
特に重要な3つの条文
企業との関係で特に重要となるのは、第7条、第13条、第16条です。それぞれの内容を確認してみましょう。
人工知能関連技術を活用した製品又はサービスの開発又は提供をしようとする者その他の人工知能関連技術を事業に利用しようとする者(以下「活用事業者」という。)は、自ら積極的に当該人工知能関連技術を活用してその事業活動の効率化及び高度化並びに新産業の創出に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。
第7条:行政施策への協力義務
第7条では、企業を含む関係者に対し、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力することが求められています。これは法的な強制力はないものの、行政との信頼関係を構築する観点からも、自主的な対応が重要になってきます。
国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正な実施を図るため、国際的な規範の趣旨に即した指針の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
第13条:国際規範に即した指針の整備
第13条では、国際的な規範の趣旨に即した指針を整備することが規定されており、中間取りまとめにおいて、広島プロセス国際指針等がその例として挙げられています。企業にとっては、この指針が今後のAI活用における行動基準として参考になるものです。
国は、国内外の人工知能関連技術の研究開発及び活用の動向に関する情報の収集、不正な目的又は不適切な方法による人工知能関連技術の研究開発又は活用に伴って国民の権利利益の侵害が生じた事案の分析及びそれに基づく対策の検討その他の人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に資する調査及び研究を行い、その結果に基づいて、研究開発機関、活用事業者その他の者に対する指導、助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
第16条:国による指導助言
第16条では、国が調査研究等を行い、それに基づいて研究開発機関や活用事業者に指導助言を行うことができることが定められています。
調査研究等の具体的な内容としては、以下の3点が挙げられています:
- AIの研究開発及び活用の動向に関する情報の収集
- 不正な目的又は不適切な使用により国民の権利利益が侵害された事案の分析及び対策の検討
- その他のAIの研究開発及び活用の推進に資する調査及び研究
なお、指導助言の具体的な内容については、附帯決議9において、「当該事業者等の営業秘密や知的財産権の保護に配慮しつつ、過度に重い負担や情報開示を求めないように留意すること」とされており、事業者に一定の配慮がなされています。
企業に求められる具体的な対応策
では、具体的にどのような対応を進めていけばよいのでしょうか。法律で直接求められているもの以外にも、企業として検討すべき重要な対応策がいくつかあります。以下、主要なポイントを整理して紹介します
AIポリシー・倫理ガイドラインの整備
直接条文上求められるもの以外で企業が検討すべき対応として、AI開発・利用に携わる企業は、倫理的・法的リスクへの対応方針を明文化し、社内外に発信することが望まれます。これは、いわゆる「AIポリシー」や「AI倫理ガイドライン」の整備に相当し、すでに一部の大手企業では策定が進んでいます。
技術的対応の強化
次に、アルゴリズムの透明性や説明可能性を確保する技術的対応が不可欠です。これは特に、採用・与信・価格設定など、人の評価に関与する分野においては強く求められる傾向があります。また、訓練データの出所や品質管理に関する内部統制も重要な課題となるでしょう。
外部連携の積極的活用
加えて、外部との連携も重要な要素です。研究機関・大学との共同開発や、官民連携プロジェクトへの参画は、国の支援を受けつつ技術力の向上を図る好機となります。これに加え、企業間での情報共有や業界団体による自主的ガイドラインの策定も、今後の実務対応において有効な選択肢となります。
AI非開発企業も対象となる対応事項
また、AIの開発を行わない企業の法務部門としても、以下のような対応が求められます:
- AI活用に関する契約書類(開発契約、利用規約、データ提供契約等)の見直し
- 生成AIに関連する知的財産・個人情報に関する社内研修の実施
- 今後のガイドライン整備に伴う新たな義務への対応準備
特に、今後のガイドライン整備に伴い、新たな義務が課される可能性もあるため、継続的な情報収集と迅速な対応体制の構築が重要になってきます。
まとめ:AI推進法ついては専門家に相談を
AI推進法は、いわゆる「実効性ある法規制」ではなく、国家としての基本方針を示す理念法としての性格が強いものです。しかし、そこに掲げられた理念は、今後の立法・行政運用・民間実務の方向性を決定付けるものとして、極めて重要な意義を持ちます。
企業にとっては、この法律を単なる指針として捉えるのではなく、むしろAIをめぐる社会的期待とリスクへの対応力を高めるための出発点と位置付けることが求められます。
AI推進法の趣旨を深く理解し、自社にとっての実務的影響を正確に把握することが、今後の企業価値の向上に資する第一歩となるでしょう。AIの利活用を推進しながらも、法的リスクを最小限に抑えるために、改めて、法律の内容の確認と専門家との連携を怠らないようにしましょう。
当事務所による対策のご案内
モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。当事務所では、東証上場企業からベンチャー企業まで、さまざまなリーガルサポートの提供や、契約書の作成・レビュー等を行っております。詳細については、下記記事をご参照ください。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務