イタリア共和国の法体系と司法制度を弁護士が解説

イタリア(正式名称、イタリア共和国)の法体系は、その根幹を大陸法系の成文法主義に置きつつも、近年、欧州連合(EU)の法令との密接な連携によって常に動的な変革を遂げています。イタリアでの事業展開を成功させるためには、その法制度の特性を深く理解し、日本法との重要な相違点を認識しておくことが不可欠となります。
本記事では、イタリア法の根幹をなす法源、EU法がもたらす最新の潮流、そして裁判官の役割や判例の扱い方といった、日本企業が特に留意すべき司法制度の特性を、具体的な法令や実務慣行に基づきながら、日本法との比較を通じて解説します。
なお、イタリアの包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。
この記事の目次
イタリア法の歴史的ルーツと成文法主義
イタリアの法制度の歴史的ルーツは、紀元前までさかのぼる古代ローマ帝国に深く根ざしています。ローマ法は、その法体系と、法の支配、公正、不偏といった原則を確立し、中世以降のヨーロッパ大陸における法制度の形成に決定的な影響を与え、現代イタリア法の礎を築きました。こうした歴史的背景から、イタリアは、包括的な法典に法律を体系的に編纂する成文法主義(Civil Law)を堅固に採用しています。この法体系では、法律は包括的な法典に体系的に編纂され、裁判官は個々の紛争に際して、これらの法典を解釈し適用することで解決を図ります。この特徴は、個別の判例を主要な法源と見なす英米法系(Common Law)とは対照的であり、日本の法制度とも共通するものです。
また、イタリアの法制度は、中央集権的な日本とは異なり、多層的な地方分権という側面も持っています。行政区画は、中央政府、20の州(Regione)、そして県(Provincia)やコムーネ(Comune)という3つの階層で構成されています。この地方分権は、単に行政サービスの分担にとどまらず、税法や観光業の許認可など、ビジネスに直接影響を与える法律の制定・適用にも及んでいます。そのため、イタリアで事業を展開する際には、中央政府の法律だけでなく、事業を行う地域の州やコムーネの規制も詳細に確認する必要があります。この多層的な構造により、法律は複雑になりますが、地域ごとの特性に応じた柔軟な対応が可能になっています。
イタリア法の法源とその階層構造
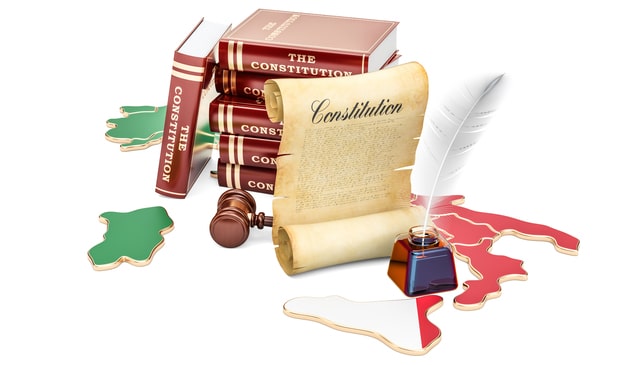
イタリアの法体系は、厳格な階層構造を持つ成文法に基づいています。すべての法規範の最上位に位置するのは、1948年に制定されたイタリア共和国憲法です。憲法は、個人の自由と基本的権利を保障するとともに、三権分立を規定しており、他のすべての法規範の最終的な根拠となります。
憲法の下には、民法典、刑法典、商法典といった主要な法典が整備されており、これらがイタリアの成文法主義の根幹を形成しています。これらの法典は、特定の法律分野における包括的な規範を体系的に定めており、日本と同様に、個々の法律に優先する上位の包括的法源として機能します。
法律の制定は、下院である代議院(Camera dei Deputati)と上院である元老院(Senato della Repubblica)からなる両院制の国会が担います。しかし、中央政府の権限に加えて、地方自治体、特に州(Regione)が独自の立法権限を有していることは、イタリアの法体系の大きな特徴です。州は、地域開発や保健衛生など、特定の州内事項に関する法律を制定することができます。この地方分権的な立法構造は、日本のより中央集権的な法制度とは異なる重要な点であり、特定の地域で事業を展開する際には、国の法律だけでなく州法も確認する必要があります。
イタリアの法体系を理解する上で、とりわけ重要なのが、欧州連合(EU)法の存在です。イタリアはEU加盟国として、EUの法源を国内法体系に取り入れる義務を負っています。EU規則(Regulation)は加盟国で直接適用され、指令(Directive)は国内法への転換が義務付けられます。この原則は、加盟国が条約を通じて主権の一部をEUに委譲していることによるものです。したがって、特定の分野においては、国内法典よりもEU法が事実上優先されることになります。
欧州連合(EU)法の潮流とイタリア国内法への転換
EU法がイタリア国内法に統合されるプロセスは、単一の静的な事象ではなく、常に改正・更新され続ける動的なものです。
例えば、イタリア国内法である資金決済法(Decreto Legislativo n. 11/2010)は、EUの旧PSD(2007年指令)を国内法化したもので、その後に制定されたPSD2(2015年指令)は、この既存の国内法令を改正する形で施行されたものです。イタリアの法規制は、EUの要請に応じて既存の枠組みを継続的に見直されていくことになります。PSD2の主な目的は、オープンバンキングを推進し、新たな市場参入者であるサードパーティ・プロバイダー(TPP)を市場に受け入れること、そして顧客認証の厳格化(SCA)を通じて決済のセキュリティを向上させることでした。
また、AI(人工知能)の利用を規制する Regulation (EU) 2024/1689(通称:EU AI Act)に関しても、同様の動きが見られます。イタリアでは、政府が2024年5月20日に提出した法案(当初 Bill No. 1146/2024 と報じられた)が、2025年9月17日に議会で最終可決され、法律となりました( Law No. 1146‑B/2025 )。この法律は、EU AI Actの原則を遵守しつつ、国内でのAI利用に関する詳細な規律を定めており、医療、労働、知的専門職、司法、公共行政などの特定セクターに焦点を当てた規定を含んでいます。特に、労働法分野では、雇用主が従業員に対してAIシステムの利用を通知する義務を定めています。また、著作権法にも改正が盛り込まれ、AIの支援を受けて生成された著作物であっても、それが著作者の知的努力の結果である限り著作権による保護が受けられることが明文で規定されています。
イタリア司法制度の構造と裁判所の役割

イタリアの司法制度は、三審制を基本としています。通常裁判所は、第一審、第二審(控訴)、第三審(最終審)から構成されています。
- 第一審裁判所:軽微な民事・刑事事件を扱う名誉職の平和判事(Giudice di Pace)と、より重大な事案を扱う地方裁判所(Tribunale)があります。地方裁判所は、通常の民事・刑事事件に加えて、企業、破産、労働、未成年者に関する専門的な事件を扱うための専門部門を内部に設けており、複雑な事案に対する専門的な知見に基づいた迅速な解決を目指しています。
- 第二審裁判所:第一審の判決に対する不服を審査する控訴裁判所(Corte d’Appello)が担当します。ここでは、第一審の事実認定や法律解釈の適否が再審査されます。
- 第三審裁判所(最終審):法律の解釈を統一し、司法判断の一貫性を保つための最終審として、ローマに拠点を置く最高裁判所(Corte di Cassazione)が存在します。最高裁判所は、原則として事実関係の審理は行わず、法律解釈の誤りや手続違反のみを審査します。
通常裁判所とは別に、特定の分野を専門的に扱う専門裁判所も存在します。
- 地域行政裁判所(Tribunali Amministrativi Regionali – TAR):公的機関の行為に関する行政紛争を扱います。TARの判決に対する第二審は、国務院(Consiglio di Stato)への控訴となります。
- 会計検査院(Corte dei conti):公的資金の監査と管理を担い、公会計に関する訴訟管轄を有しています。これは、日本においては通常裁判所が扱う公会計に関する事案を、独立した憲法上の機関が担っている点で大きく異なります。
この司法制度の構造は、一般法理を扱う「通常司法」と、特定の公法領域を扱う「専門司法」を明確に分けるものです。日本の裁判所が行政事件も一元的に扱うのに対し、イタリアでは行政紛争はTARの管轄となります。
| 種類 | 日本語名称 | イタリア語名称 | 主な役割と管轄 |
|---|---|---|---|
| 通常裁判所 | 平和判事 | Giudice di Pace | 軽微な民事・刑事事件の第一審。名誉職の判事。 |
| 通常裁判所 | 地方裁判所 | Tribunale | 重大な民事・刑事事件の第一審。専門部門も有する。 |
| 通常裁判所 | 控訴裁判所 | Corte d’Appello | 第一審判決に対する控訴審(事実・法律審)。 |
| 通常裁判所 | 最高裁判所 | Corte di Cassazione | 最終審。法律解釈の統一。 |
| 専門裁判所 | 地域行政裁判所 | Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) | 行政機関との紛争に関する第一審。 |
| 専門裁判所 | 会計検査院 | Corte dei conti | 公的資金の監査、公会計に関する訴訟。 |
日本法との比較に見るイタリア司法の特徴
イタリアの司法制度は、日本と同様に大陸法系に属するものの、裁判官の役割や判例の扱い方において、日本とは異なる独特な側面を持っています。
裁判官の積極的な役割と手続原則のニュアンス
日本の民事・刑事訴訟は、原則として当事者が主張・立証活動を主導する「当事者主義」を基本としています。これに対し、イタリアでは裁判官が事実認定や証拠収集に積極的に関与する「職権探知主義的」な側面が強い傾向にあるとされています。
しかし、この違いは単純な二元論ではなく、複雑な歴史と最新の動向によって形成されています。例えば、刑事手続においては、1989年の法改正により、かつての職権主義的な手続から、検察官、被告人、弁護人が主導的な役割を担う当事者主義へと移行した歴史があります。また、民事訴訟においても、近年、手続きの迅速化を目的とした法改正が進められており、裁判官は当事者間の「協力」を促し、不当な訴訟行為に対して制裁を課す権限を与えられています。
このように、イタリアの司法制度は、日本の当事者主導の訴訟進行とは異なり、裁判官がより積極的に事件の進行や証拠の評価に関与する側面が色濃く残っていると言えます。このような裁判官の積極的な関与は、裁判の進行や結果の予測可能性に影響を及ぼす可能性があります。
判例の法的拘束力と実務上の影響
イタリアは成文法主義の国であるため、個々の判決(判例)には、英米法におけるstare decisis(先例拘束性の原則)のような直接的な法的拘束力はありません。あくまで助言的な目的で用いられるに留まるとされています。しかし、この原則は、実務上の運用において、日本の法慣行とは異なる形で修正されています。
最高裁判所(Corte di Cassazione)の主要な役割は「法解釈の統一」であり、下級審の裁判官は、最高裁判所が示した法解釈に「強い参照点」(robust reference point)として従う傾向があります。この状態は、jurisprudence constante(継続的な判例)と呼ばれ、最高裁の判例が下級審を事実上強く拘束する日本の法慣行とは、その根拠とメカニズムが異なります。
この「法的拘束力なき実務上の権威」が形成される背景には、最高裁判所内に存在する特別な組織「Ufficio del Massimario」の役割があります。この組織は、最高裁判決の中から「massime」(最も重要な法的原則)と呼ばれる要点を抽出し、体系化して公表する役割を担っています。これにより、下級審の裁判官は、自らの判断が最高裁の統一見解と矛盾しないか容易に確認でき、不必要に控訴や上告のリスクを冒すことを避けるインセンティブが働きます。これは、判例が実務上の権威を持つことについて、組織的なプロセスを通じてその影響力が形成される、イタリア法特有のメカニズムであると言えるでしょう。
| 項目 | イタリア法 | 日本法 |
|---|---|---|
| 法源の階層 | 憲法を頂点とする成文法主義。州法など地方自治体による立法も重要。 | 憲法を頂点とする成文法主義。地方自治体には条例制定権がある。 |
| EU法の位置づけ | EU規則は直接適用され、指令は国内法に転換される。EU法は国内法に事実上優越する。 | 国際条約は国内法と同様の効力を持つ。EU法のような動的な統合はない。 |
| 裁判官の役割 | 裁判官は、手続の迅速化や適正化のために、当事者と協力し、より積極的に訴訟を管理する側面が強い。 | 裁判の進行は原則として当事者が主導し、裁判官は中立的な立場を保つ当事者主義が基本。 |
| 判例の法的拘束力 | 直接的な法的拘束力はない。しかし、最高裁の判例は「法解釈の統一」のために強い実務的影響力を持つ(jurisprudence constante)。 | 直接的な法的拘束力はないが、最高裁の判例は下級審を事実上強く拘束する慣行がある。 |
| 裁判制度の構造 | 通常裁判所とは別に、行政紛争を扱う地域行政裁判所(TAR)や公会計を扱う会計検査院(Corte dei conti)など、特定の分野に特化した専門裁判所が存在する。 | 通常裁判所が行政事件も一元的に管轄する。専門部(知的財産部、倒産部など)は存在するが、専門裁判所は限定的。 |
まとめ
イタリアの法体系は、伝統的な成文法主義の堅固な基盤と、欧州連合の潮流に柔軟に対応する動的な性質が融合することで、独自の複雑な構造を形成しています。特に、裁判官の積極的な役割や、判例に法的拘束力はないものの実務上強い影響力を持つという特性は、日本の法慣行とは大きく異なります。これらの点を深く理解することは、イタリアでの事業を展開する上で不可欠な法的判断を下す上での基盤となります。
イタリアでのビジネスは、単に法律を遵守するだけでなく、法規制が常に変化しうるという前提で、継続的な法的監視を行う必要があります。そして、訴訟や紛争に直面した際には、日本企業が慣れ親しんだ手続きとは異なる、より個別具体的な法的分析と、裁判官の積極的な関与を念頭に置いた戦略的な対応が求められます。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務


































